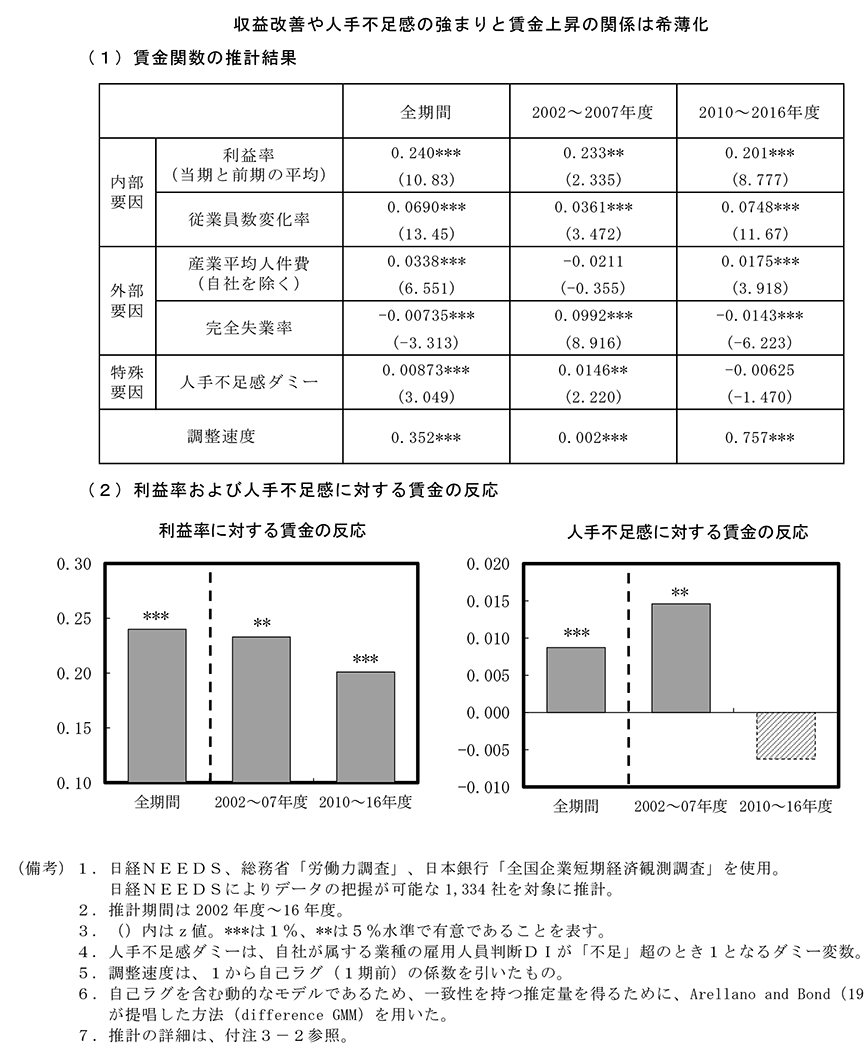第3章 企業部門の成長に向けた取組と好循環の確立(第1節)
第1節 企業部門の投資・支出行動の特徴とその背景
1 企業収益の改善と投資・支出行動
本項では、今回の景気回復局面における企業収益の改善には、交易条件の改善による売上高の増加の下で、企業の抑制的な投資・支出行動による固定費負担の低下が相応に影響している事実を確認する。また、こうした企業行動を受けて、労働分配率が低下していること、配当性向も横ばいで推移し、企業部門が貯蓄超過になっていることを確認する。さらに、我が国企業の収益率は上昇しているものの、収益率の水準は諸外国と比べてなお低いことを確認する。
(企業収益は、交易条件の改善と固定費の抑制により改善)
我が国の企業収益は、今回の景気回復局面において、過去最高水準で推移している。収益が大きく改善した背景を分析するために、企業の経常利益(全規模・全産業)の変動を、①「売上高要因」(売上の変動によるもの)、②「変動費率要因」(原材料費などの変動費の変動によるもの)、③「固定費要因」(人件費や減価償却費などの営業内の固定費の変動によるもの)、④「営業外収益要因」(海外子会社からの配当金の増加などによるもの)、⑤「営業外費用要因」(借入金等の支払利息の変動などによるもの)、の5つの要因に分解する(第3-1-1図(1))。
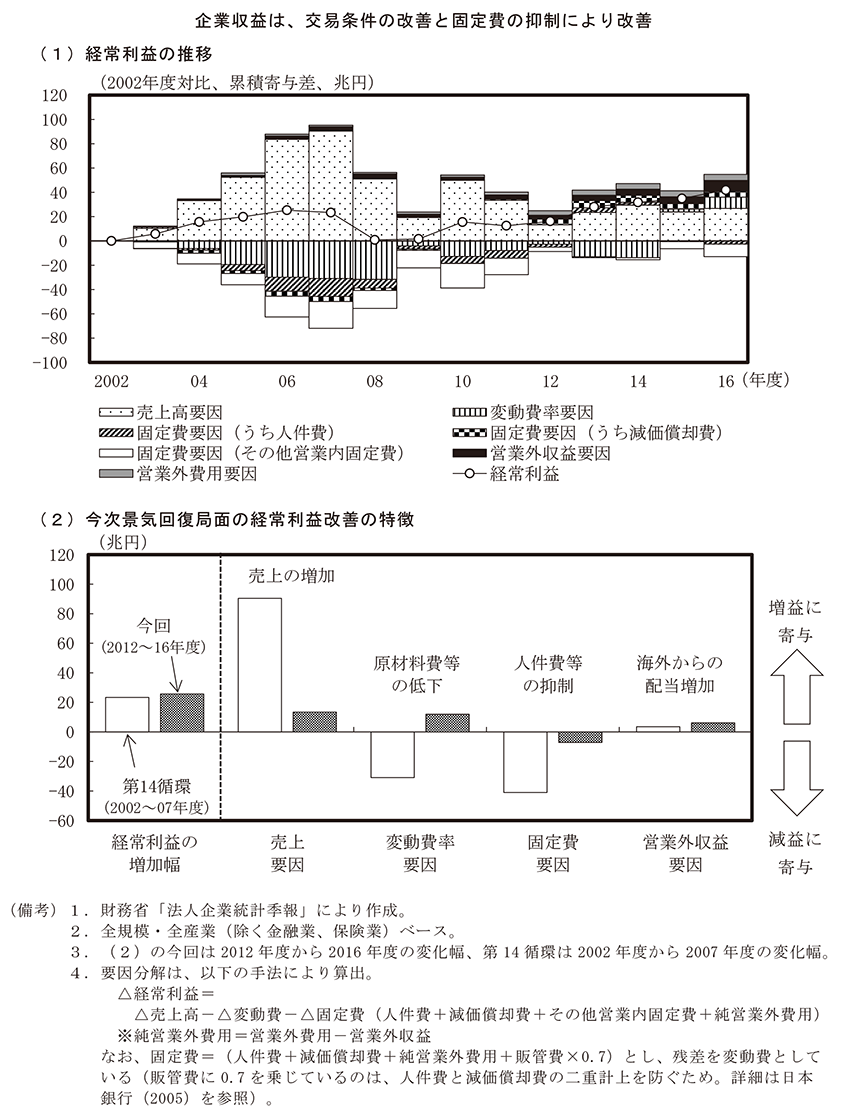
まず、今回の景気回復局面における最も大きな特徴は、売上高が増加する中、過去の景気回復局面では収益の下押しとなることの多かった「変動費率要因」が、押し上げ要因として寄与している点である。すなわち、直近の景気の谷を含む2012年度から足下の2016年度までをみると、2013年度~14年度にかけては交易条件の悪化(主として、原油価格の上昇等による投入価格の上昇)によって「変動費率要因」が下押しに寄与していたが、2015年度以降は、原油価格の低下もあって、これらの交易条件が改善し、「変動費率要因」が収益の押し上げに寄与している。これに対し、戦後最長の景気回復局面を含む2002年度~07年度の間では、「変動費率要因」は交易条件の悪化(当時の原油価格の上昇)を反映して、一貫して下押し方向に寄与していたことがわかる(前掲第3-1-1図(2))。
次に、減価償却費や人件費といった固定費が抑制気味である点も特徴的である。減価償却費は、国内で行った設備投資(有形固定資産等の取得)に応じて計上される費用であるが、好調な企業収益と比べると設備投資の伸びが鈍めの動きを続けていることから、2012年度~16年度における収益への影響は小さい。また、人件費も、2012年度~16年度においては、小幅に増加しているものの、人件費の抑制スタンスが同様に指摘されていた2002年度~07年度と比べてもほとんど増加しておらず、収益に与える影響は小さい。以上を踏まえると、今回の景気回復局面における固定費は総じて抑制的であり、結果として、「固定費要因」による収益下押しは限定的であることがわかる(前掲第3-1-1図(2))。
さらに、企業の資金運用や資金調達の方法が変化していることが、収益の押し上げに貢献している。資金運用面では、グローバル化の進展を受けて、海外子会社などからの配当が増加している(「営業外収益要因」が押し上げに寄与)。また、資金調達面では、企業の過剰債務の解消や自己資本の強化から、有利子負債の残高が減少しているほか、低金利環境もあいまって、支払利息が減少している(「営業外費用要因」が押し上げに寄与)。
(労働分配率は、生産性向上と比べ賃金上昇が弱いことから、低下傾向)
企業が生み出した付加価値の使途は、大別すると、①賃金支払いによる従業員への還元、②配当による株主への還元、③国内外の実物投資や金融投資、④企業の内部資金として蓄積、の4つの選択肢が考えられる。以下では、これらの動向を確認する。
まず、賃金支払いについては、前述のとおり、全規模・全産業ベースの人件費をみると、このところほとんど変化していない。賃金(正確には実質賃金)の水準は、長い目でみれば、労働生産性との見合いで決まると考えられることから、ここでは労働分配率の動向を規模・業種別に確認する(第3-1-2図(1))。労働分配率は、いずれの規模・業種においても、2010年代入り後、低下傾向にある。水準を比較すると、製造業より非製造業が低い傾向にあるほか、中堅・中小企業より大企業が低い傾向にあることがみてとれる。
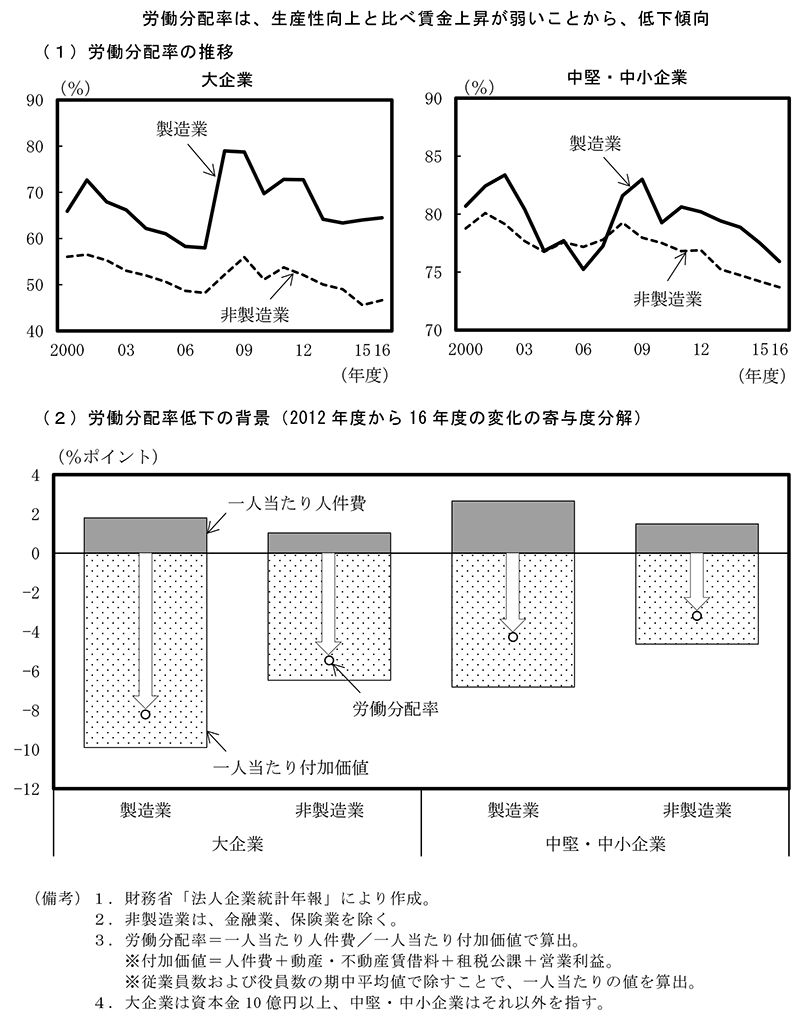
労働分配率の低下の背景を確認するために、直近の景気の谷を含む2012年度から足下の2016年度までの労働分配率の変化について、分子の「一人当たり人件費」と、分母の「一人当たり付加価値」の寄与をみると、全ての規模・業種において、「一人当たり付加価値」の向上ほどには、「一人当たり人件費」の伸び率が高まっていないことがわかる(前掲第3-1-2図(2))。景気回復期においては、一般に生産性の伸びが賃金上昇率を上回り、労働分配率は低下する傾向にある点には留意する必要があるが、製造業と非製造業の状況を比較すると、非製造業では、生産性の向上度合いが製造業と比べて鈍く、その結果、賃金も上昇させづらい状況となっている可能性が示唆される。
(配当金は当期純利益と並行して増加しており、内部留保も増加)
次に、当期純利益の分配先である、配当、役員賞与1、フローの内部留保2の状況を確認する(第3-1-3図)。2012年度以降の動向をみると、大企業では、当期純利益が増加する中、配当金と内部留保がともに増加しているが、増加幅でみると内部留保が配当金の伸びを上回っている。また、中堅・中小企業でも、配当金の増加ペースは相対的に低く、その結果、内部留保が増加していることがわかる。
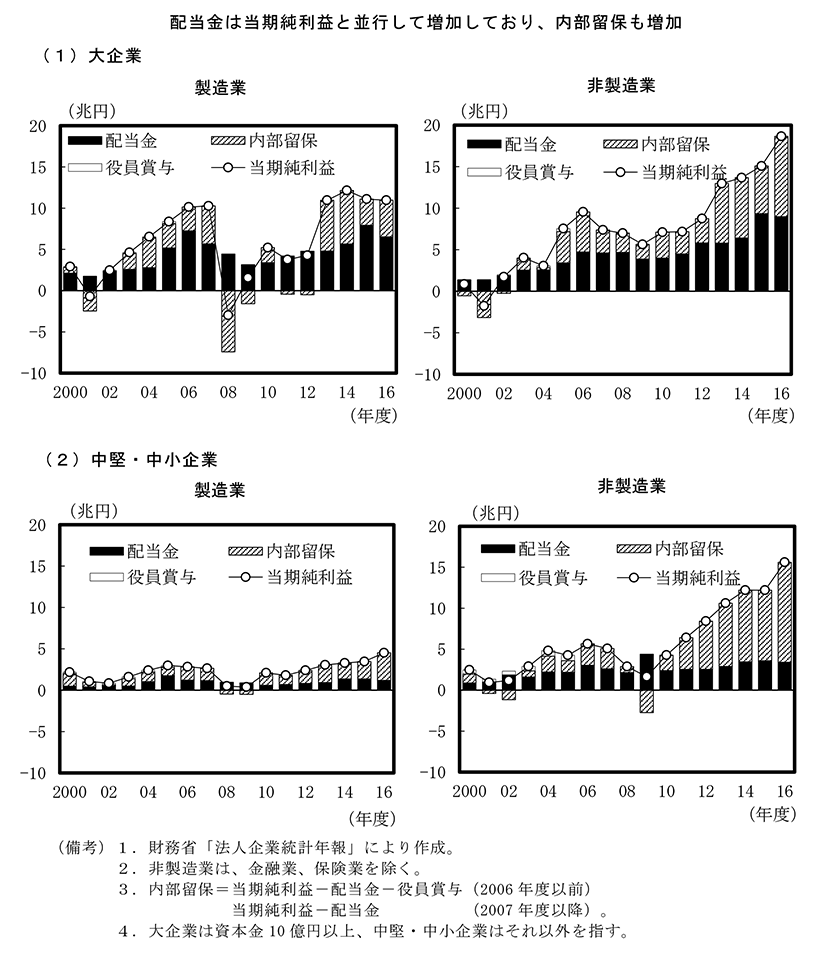
(企業部門は貯蓄超過)
企業部門は、一般に、借入れを行うことで投資の資金手当てを行うため、貯蓄・投資バランスは投資超過となる傾向がある。実際に、1961年以降の企業部門の貯蓄・投資バランスの動向をみると、1990年代末頃までは企業部門は投資超過の状態であったが、2000年代以降についてはほぼ一貫して貯蓄超過の状態になっている3(第3-1-4図)。この背景としては、1990年代初までのバブル期において、過剰な資本ストックが蓄積されたことにより、2000年代を通じて投資を抑制し、不採算部門のリストラ等を行い、資本ストックの過剰を解消してきたことがある。他方、2012年以降については、企業収益の改善によって企業貯蓄が大きく増加する一方で、国内の設備投資は、緩やかな増加基調にあるとはいえ、好調な企業収益と比べて鈍めの動きを続けており、その結果として、企業の貯蓄超過幅は対付加価値比率でみて過去最大となっている。
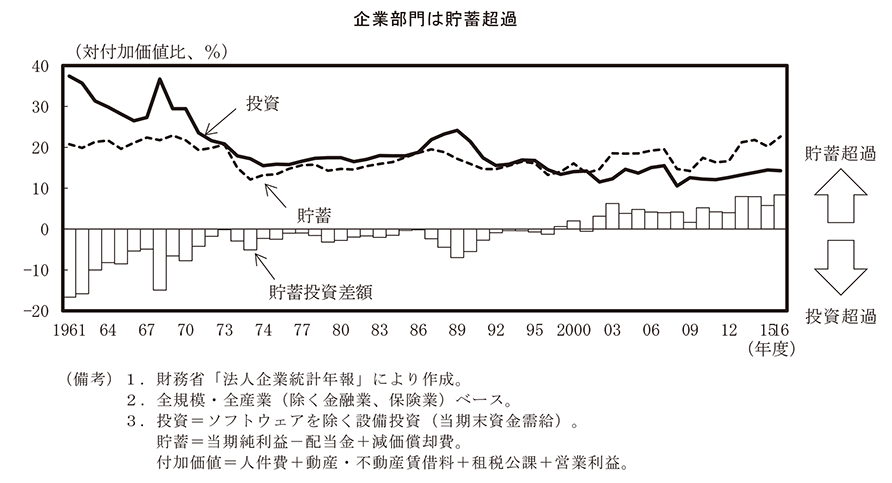
(資金運用は国内投資から海外M&Aに、資金調達は借入から自己資本にシフト)
これまでの分析結果によると、企業部門では、交易条件の改善を主因とする売上高の増加や、人件費などの固定費の抑制により、収益が着実に改善する一方で、配当や国内設備投資の動きは相対的に鈍く、貯蓄超過(資金余剰)の状態となっていることが確認される。以下では、企業部門の資金運用や調達の構造など、ストック面での変化を確認する。
まず、全規模ベースでみると(第3-1-5図(1)左)、資金運用面では、「現金・預金」がバランスシート全体に占める割合は、過去数十年の間、あまり大きく変化していない。こうした中、国内設備投資のストックを示す「償却資産」をみると、2000年代半ば以降、低下傾向を辿っている。一方、主に海外企業に対するM&Aの状況を示す「投資有価証券」4は、「償却資産」が減少傾向となり始めた2000年代半ばから、逆に上昇傾向を辿っている。こうした傾向は、とりわけ大企業においてはっきりと確認される一方(第3-1-5図(2)左)、中堅・中小企業では緩やかなものとなっている(第3-1-5図(3)左)。
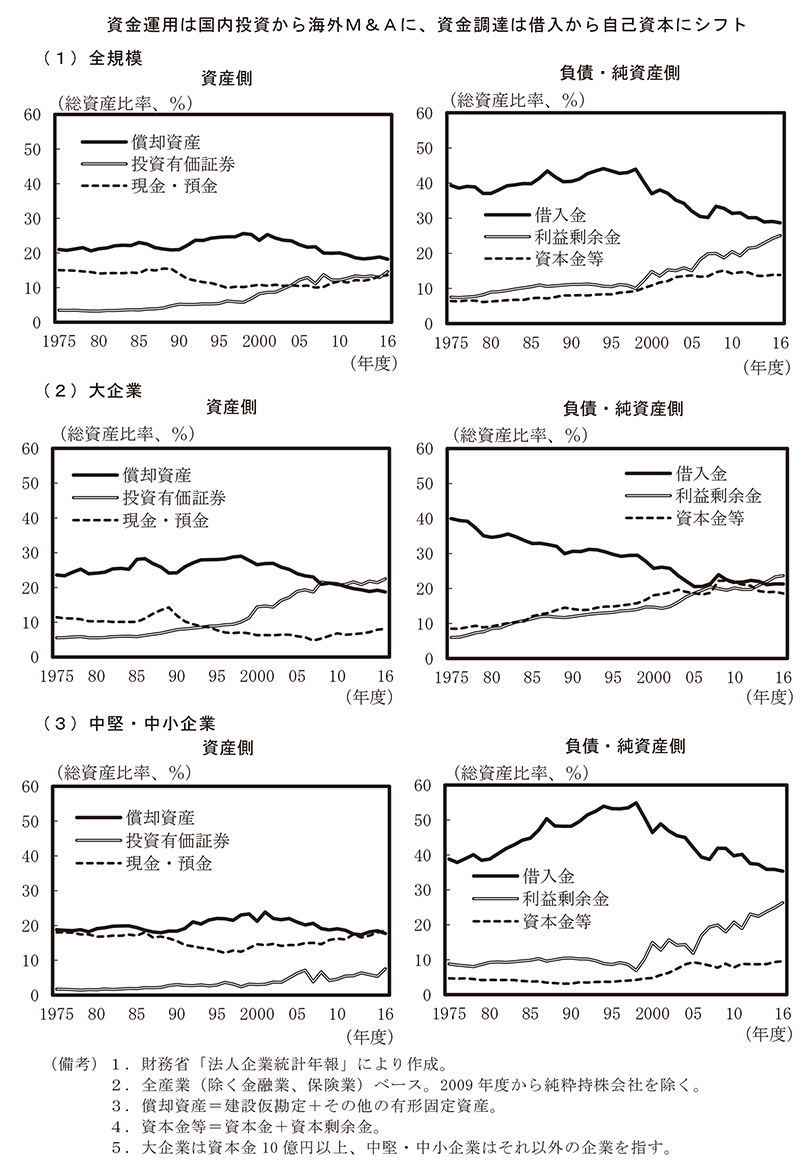
次に、資金調達面をみると、全規模では(前掲第3-1-5図(1)右)、1990年代後半以降、過剰債務の解消を背景に「借入金」が減少する一方、「資本金等」の自己資本が増加しており、財務体質が強化されていることが確認できる。特に「借入金」の動向については、大企業が一貫して削減を図ってきた一方(前掲第3-1-5図(2)右)、中堅・中小企業では、企業の過剰債務問題が顕在化した1990年代後半までの期間では増加傾向にあったものが、それ以降は減少傾向に転じている点が特徴的である(前掲第3-1-5図(3)右)。こうした中、「利益剰余金」は、いずれの企業規模でも増加している。
以上をまとめると、資金調達面では、ストックの内部留保を示す利益剰余金が増加している一方、それに対応した資金運用面では、現金保有は大きく変動していないものの、生産・営業設備を含む償却資産が減少し、M&Aなどによる投資有価証券が大きく増加していることが確認できる。
(我が国のROAは上昇しているものの、欧米対比ではなお低い)
最後に、我が国企業のROA(総資産利益率)の動向を確認する。法人企業統計の集計データを用いて、企業の平均的なROAの動向をみると、総資産の伸びが緩やかな中、経常利益が大きく改善していることを主因に、堅調に上昇している5(第3-1-6図(1)、(2))。
なお、我が国のROAを、欧米と比較すると、現状では相対的に低い水準で推移しており、いまだ改善の余地があることがわかる6(第3-1-6図(3))。
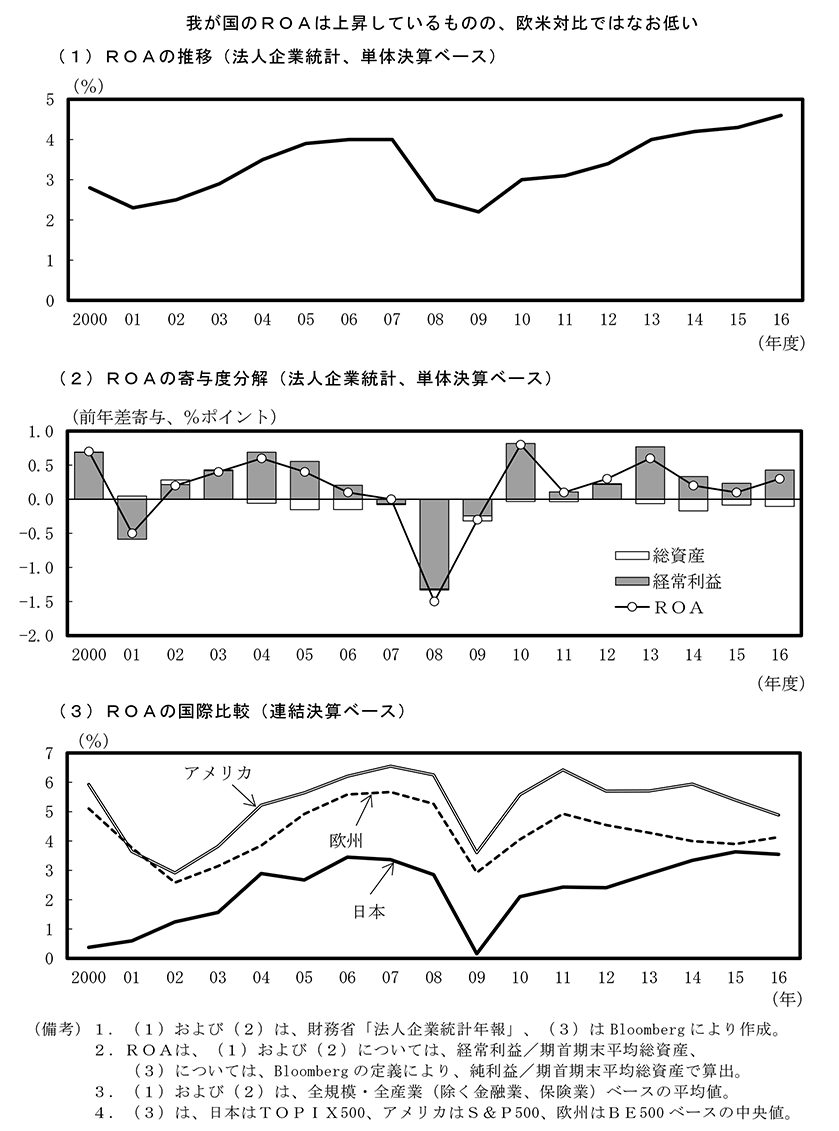
2 企業の内部資金と投資行動
前項で確認した抑制的な国内設備投資の背景については、様々な見方が指摘されているが、最近の先行研究などを概観すると、主に以下の2つの仮説が挙げられることが多い。
第一の仮説は、バブル崩壊や世界金融危機などの経験を踏まえ、我が国企業の過度な安全性志向が投資を抑制している、というものである7。
第二の仮説は、国内設備投資は抑制的であるとしても、M&Aをはじめとする別の投資的支出は増加しており、これらを合算した「広義の投資」は、必ずしも抑制されていない、というものである。この仮説によれば、企業は投資収益率などに基づき、合理的に広義の投資水準を判断し実行しているということとなる。
本項では、主に後者の仮説を検証するために、上場企業(製造業)の財務データを用いた実証的な分析を行う8。分析にあたっては、標準的な設備投資関数の推計において、被説明変数を国内設備投資とするモデルと、国内設備投資とM&Aを合算した「広義の投資」とするモデルをそれぞれ推計し、その結果を比較することで、両者に影響を及ぼす諸要因がどのように異なるかあるいは類似しているのかを考察する9。推計期間は2002年度~16年度とし、全期間における推計と、世界金融危機の前後(2002年度~07年度、2010年度~16年度)の期間にデータを分割した推計を行い、各期間の特徴についても考察する。
(企業の内部資金の使途は、国内投資からM&Aを含む広義の投資にシフト)
まず、推計期間全体の結果を全般的に確認すると、以下の3つのことがわかる(第3-1-7図)。第一に、トービンのqの構成要素について、資本収益率の係数は、国内設備投資、広義の投資とも、理論どおり有意にプラスとなっている。一方、資本コストの係数は、国内設備投資では理論どおり有意にマイナスとなっているが、広義の投資では有意となっていない10。第二に、キャッシュフロー比率および現預金比率の係数は、国内設備投資、広義の投資とも、有意にプラスとなっており、内部資金の制約に影響を受けることがわかる。第三に、負債比率の係数は、国内設備投資、広義の投資とも、有意にマイナスとなっており、高い負債比率は信用リスクや債務の過剰さなどを反映し、外部資金調達が困難になるために投資が制約されるという理論に整合的な結果となっていることがわかる。
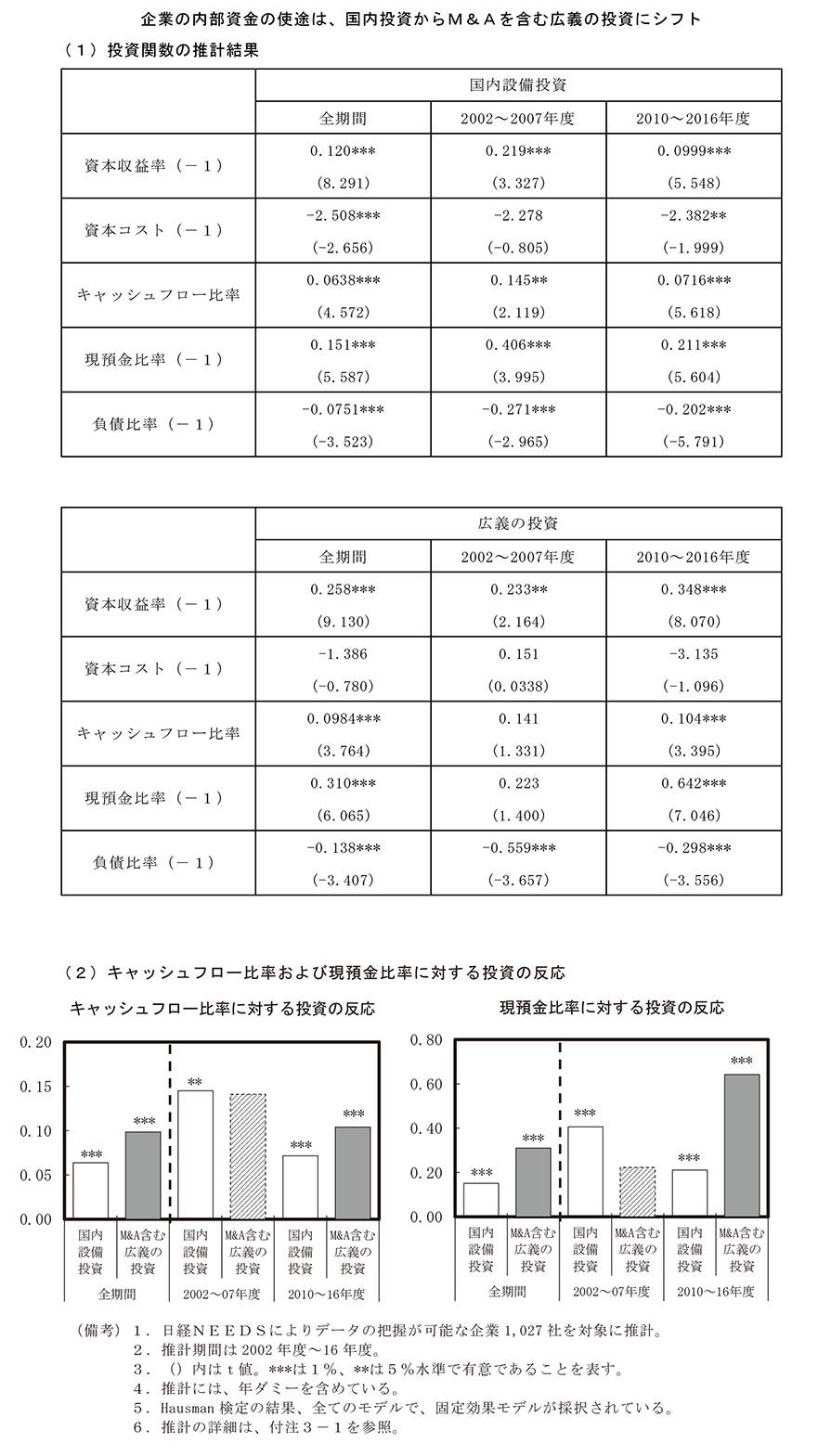
次に、国内設備投資関数と広義の投資関数の推計結果を推計期間全体で比較すると、①投資関数の最も基本的な構成要素である資本収益率、②内部資金に対する感応度を表すキャッシュフロー比率および現預金比率、③財務リスクを表す負債比率、のいずれについても、広義の投資における係数が国内設備投資における係数を、絶対値でみて大きく上回っていることがわかる。この結果から、企業の収益性や財務状況は、国内設備投資と比べて、M&Aを加えた広義の投資の決定に際して、より大きな影響を持っていることが示唆される。こうした背景には、技術革新等に伴う事業環境の変化やグローバル化が進む中で、企業が新たな事業分野の開拓や世界展開を視野に入れてM&A等を含む広義の投資を活発化させる中で、そうしたリスクの高い投資に係る不確実性の増加に対応するために内部資金を重視している可能性が考えられる11。
さらに、期間別の推計結果からは、主に以下の2つの結果を読み取ることができる。第一に、国内設備投資については、資本収益率、キャッシュフロー比率および現預金比率、負債比率のいずれについても、世界金融危機を境に、係数の絶対値が小さくなっている。第二に、広義の投資については、これらの係数は、世界金融危機の前には、一部の係数について有意なものが得られていない一方で、世界金融危機の後では、全ての係数が有意となっている。このことから、世界金融危機以降、企業の収益性や財務状況が国内設備投資に与える影響がやや低下する中で、M&Aを含む広義の投資については、不確実性への対応ということもあり、内部資金への感応度が高い傾向にあることが示唆される12。
(中長期的な成長のためには、設備投資や研究開発がなお重要)
以上の推計結果からは、企業は、投資収益率などに基づき、合理的に投資水準を判断し、その結果、国内設備投資のみではなく、M&Aを含む広義の投資を実行しているということとなる。実際、企業の成長性を確保するための投資行動として、すでに実績のある良質な企業をM&Aの対象とすることで、設備投資と比べ相対的に短期間のうちに成果をあげられる可能性があることが考えられる。また、自企業で保有していない生産・営業用の設備や新たな経営資源を取り込むことによって、企業価値の向上を実現できる可能性もある13。
もっとも、企業が収益力や競争力を高め、中長期的な成長を持続・促進させるためには、将来の財やサービスの供給能力の向上につながる設備投資はなお重要であると考えられる。また、新製品やサービスを市場に投入する前段階である各種の研究開発(基礎・応用研究や開発・実用化のための研究など)も重要である。こうした観点を踏まえると、生産性を高めるために必要な設備投資や研究開発を実施することの重要性は引き続き高いと考えられる。
3 企業の賃金決定行動の背景
第1項で確認したように、企業収益の改善と比べて、賃金上昇は緩やかなものにとどまっており、労働分配率も低下傾向にある。本項では、企業の賃金決定行動に焦点を当て、上場企業の財務データを用いた実証的な分析を行う。分析にあたっては、一人当たり賃金を被説明変数とする賃金交渉モデルに基づく推計を行い、①企業収益の状況や従業員の交渉力(内部要因)、②労働市場全体の需給を表す産業平均の賃金動向や失業率(外部要因)、③人手不足感の高まり(特殊要因)、の3つの視点から考察を行う14。推計期間は2002年度~16年度とし、全期間における推計と、世界金融危機の前後(2002年度~07年度、2010年度~16年度)の期間にデータを分割した推計を行い、各期間の特徴についても考察する。
(収益改善と賃金上昇の関係性が薄れている)
まず、推計期間全体の結果をみると、内部要因、外部要因とも、おおむね理論と整合的な符号が有意に得られている(第3-1-8図)。第一に、内部要因については、利益率15、従業員数変化率(従業員の交渉力の代理変数)とも、係数が有意にプラスとなっており、企業の収益性が高いほど、また従業員数が増えるほど、既存の労働者の影響力によって賃金に対して上昇圧力がかかるという理論と整合的な結果となっている。第二に、外部要因の影響について、産業平均人件費の係数が有意にプラスとなっており、外部賃金が高いほど各企業の賃金も高くなること、また、失業率の係数は有意にマイナスとなっており、労働需給全体の悪化を示す失業率の上昇は賃金にはマイナスの影響を及ぼすこと、が確認できる。
もっとも、金融危機の前後の推計結果を比較すると、これらの要因による影響が異なっていることがわかる。まず、利益率の係数は、金融危機の前後で有意にプラスとなっており、絶対値が低下している。このことから、近年、収益改善と賃金上昇の関係が薄れている可能性が示唆される。一方、産業平均人件費と完全失業率の係数をみると、金融危機前では、前者は有意となっておらず、後者は期待される符号条件には合わない結果となっている。これは、金融危機前の局面では、デフレの状態が続く中で、賃金上昇が非常に緩やかであったことが影響しているとみられる16。
(近年、人手不足に直面する企業では、賃金が上昇していない可能性)
それでは、近年の人手不足感の高まりとの関係はどうであろうか。第3-1-8図の特殊要因(人手不足感ダミー)の係数をみると、推計期間全体および金融危機前の期間では有意にプラスとなっているが、金融危機後の期間では有意となっていないことがわかる。このことから、近年、企業が人手不足に直面していても、賃金上昇につながっていない可能性が示唆される。特に、人手不足感が推計期間を通じて一貫してみられる非製造業において賃金上昇が弱い傾向がみられることから、こうした業種で人手不足に対して賃金の相対的に低いパート労働者を活用してきたことが影響している可能性が考えられる。