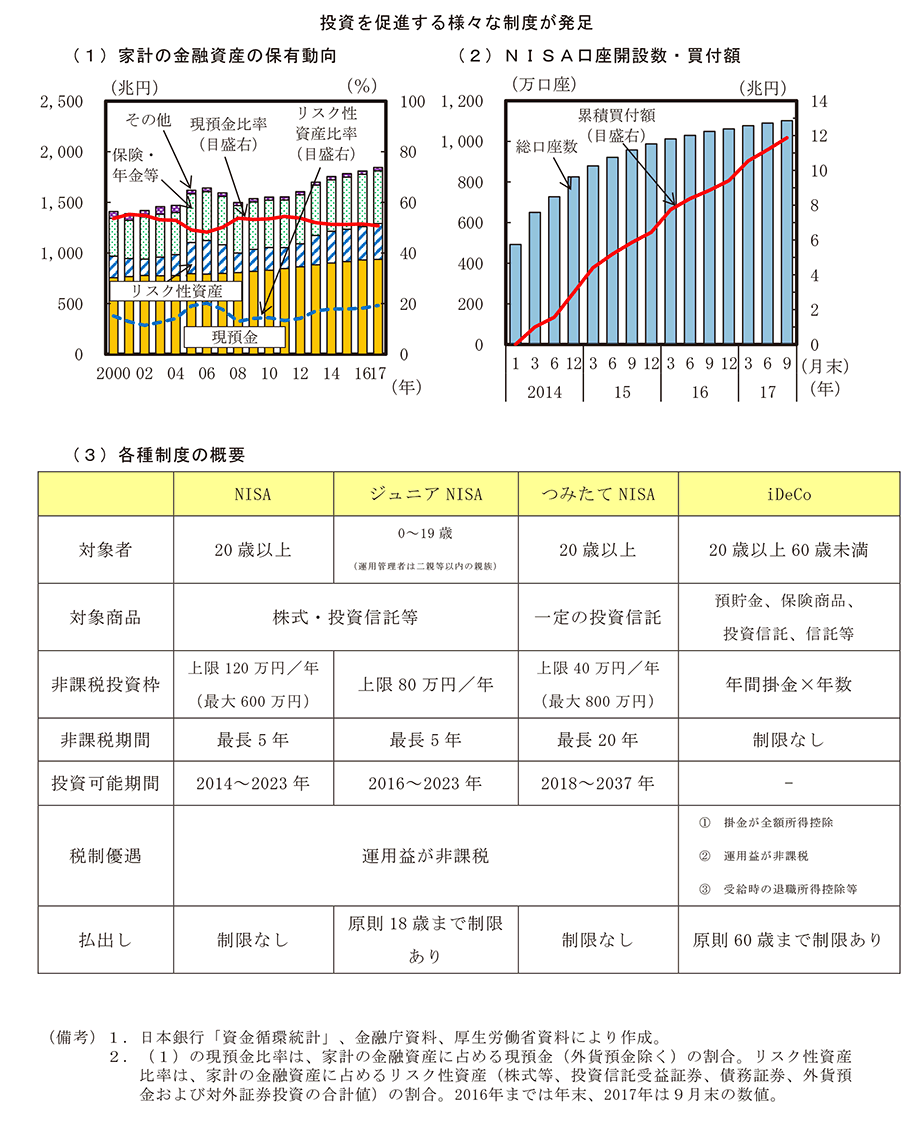第1章 日本経済の現状とデフレ脱却に向けた課題(第3節)
第3節 デフレ脱却に向けた動き
本節では、物価の現状について概観し、長期にわたる景気回復によりデフレ脱却に向け局面変化が着実に見られていることを確認する。またその局面変化を確実にデフレ脱却に結び付けるためにはどのような課題があるかについても考察する。最後に、最近の金融市場の動向についても触れる。
1 デフレ脱却に向けた局面変化
(物価動向について)
消費者物価の動向を、生鮮食品を除く総合(コア)でみると、2016年に入り、円高方向への動きやエネルギー価格の低下等により、前年比で低下していたが、2016年後半からのエネルギー価格の上昇などにより、2017年に入ってからプラスに転じ、2017年11月時点において0%台後半で推移している(第1-3-1図)。
他方、物価の基調について、「生鮮食品及びエネルギーを除く総合(いわゆる「コアコア」)」でみると、2016年後半以降は前年比、前月比とも0%近傍の動きとなっている。これは、原材料費の上昇などにより一般食料工業製品などが上昇し、またインバウンドが好調であることなどを背景に宿泊料が上昇しているほか、単身世帯の増加もあって外食が上昇している一方、携帯電話機や携帯電話通信料などが下落していることが主な要因である。
また、民間エコノミストによる予想物価上昇率は、2012年以降徐々に上昇し、2015年は1%程度で安定的に推移した後2016年に入って低下した。その後、原油価格の影響等により再び上昇したが、足下では1%弱程度となっている。一方で、家計の予想物価上昇率については、食料品の値上がり等の影響を受けやすいことから民間エコノミストによる予想物価上昇率に比べれば高い水準で推移しているものの、2%程度で落ちついている。
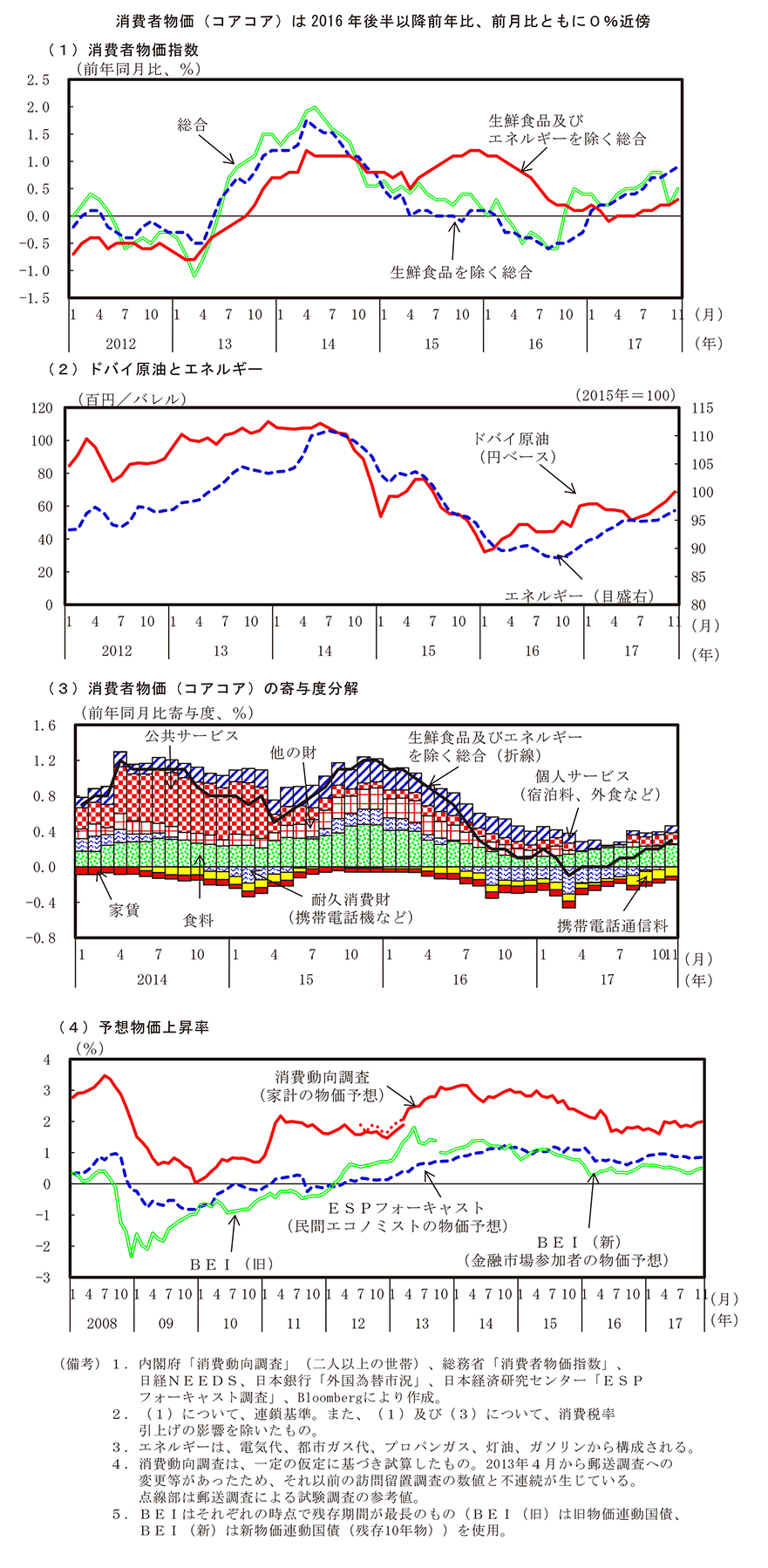
(景気回復の長期化もありGDPギャップはプラスに転じる)
景気循環を均した平均的な供給力を示す潜在GDPと実際に需要されたGDP水準とのかい離率であるGDPギャップは、これまでマイナスの期間が多かったが、長期にわたる景気回復もあり、プラスに転じている(第1-3-2図)。GDPギャップがプラスになるということは経済全体で需給が引き締まっている状態である。これまでの消費者物価(コア)とGDPギャップのデータを用い、両者の相関を見ると、GDPギャップの上昇から半年程度のラグを伴って消費者物価も上昇する傾向が見られること(付図1-3
)から、今後は、GDPギャップの引き締まりが消費者物価の押上げに寄与することが見込まれる。ただし、過去のデータから推計される関係式からは、GDPギャップの変化が消費者物価(コア)を押し上げる効果は限定的1である点には留意が必要である。これは、デフレが長期化したことにより、賃金や価格設定の行動様式が慎重化したこと等が反映されている可能性がある。
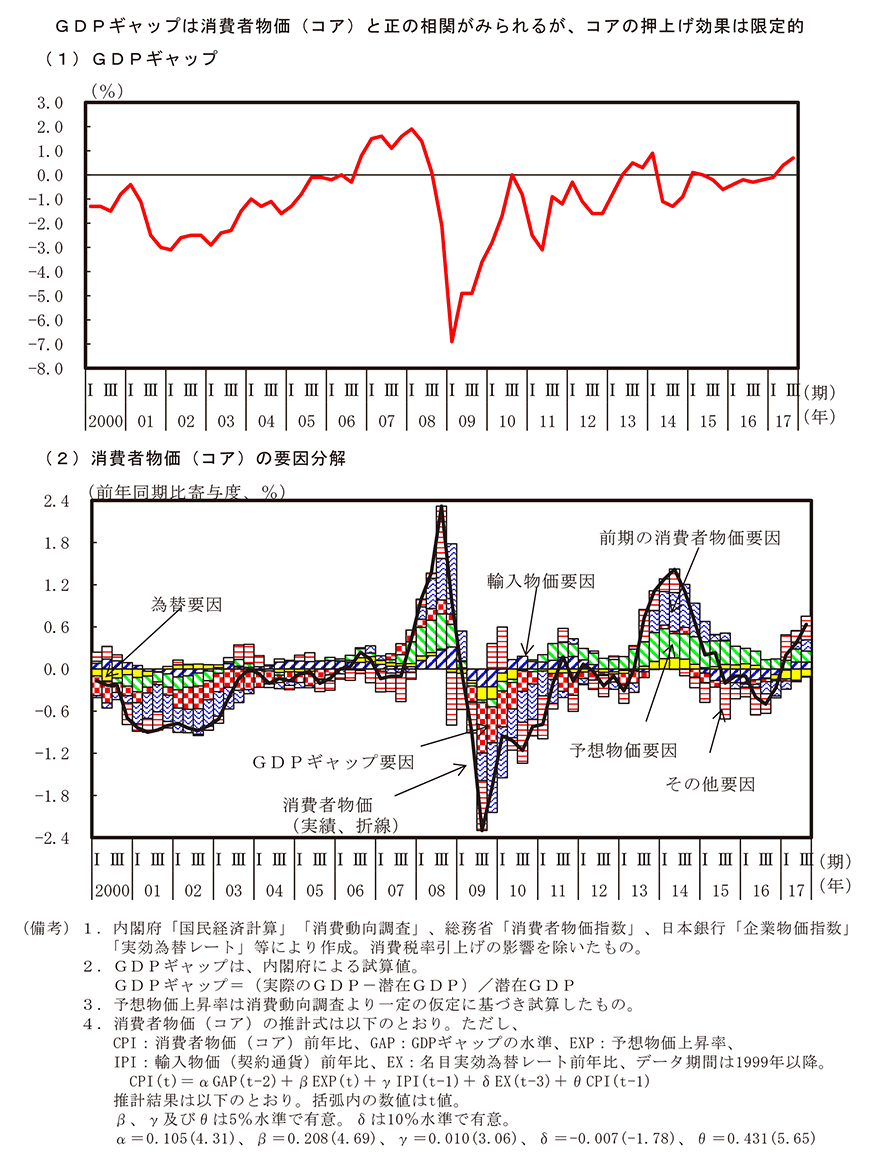
(人手不足感が四半世紀ぶりの高水準となり、パートを中心に賃上げが続く)
前節で見たように、景気回復の長期化により雇用・所得環境は改善を続け、人手不足感は四半世紀ぶりの高水準となっている(第1-3-3図)。また、雇用環境のひっ迫によりパートを中心に賃金が上昇している。
賃金の伸びをマクロ的にみるために、生産一単位当たりの労働コスト(ユニットレーバーコスト、以下、「ULC」という。)の変化を生産性要因と賃金要因に分解すると、賃金要因が生産性要因を上回っているため2014年半ば以降前年比でプラスが続いている。ULCの上昇は、生産性の上昇以上に賃金が上がっていることを意味するため、企業にとってはコストプッシュ要因2となる。消費者物価のコアコアとULCの関係を見ると緩やかな正の相関が長期的に確認できるため、今後はプラスで推移しているULCとともにコアコアも緩やかに上昇することが期待される。

(企業物価は最終財価格も上昇し始め、一部の消費者向けでの価格転嫁の動き)
企業物価の動向を需要段階別で見ると、資源価格の回復により素原材料価格が2017年に入り前年比で大きく上昇し、その動きが中間財、さらには最終財にも波及しつつある(第1-3-4図)。
企業物価の最終財のうち、消費財と消費者物価(財)との時差相関をみると、企業物価の消費財の上昇から半年程度のラグを伴って消費者物価(財)が押し上がると見込まれる(付図1-4
)。また、人件費の上昇による運送料の上昇やインバウンド需要の高まりによる宿泊料の上昇などにより企業向けサービスも緩やかに増加を続けており、価格転嫁の動きが企業物価では着実に進行していることがうかがえる。景気回復局面においても企業向けのみで上昇を続けていた配送料については、2017年10月からは消費者向け価格でも上昇の動きがみられる。また、外食でも価格が上昇している。ただし、小売全体でみると、仕入れ価格が上昇しているものの、販売価格の上昇はわずかであり、今後は価格転嫁がスムーズに行われるか否かが注目される。
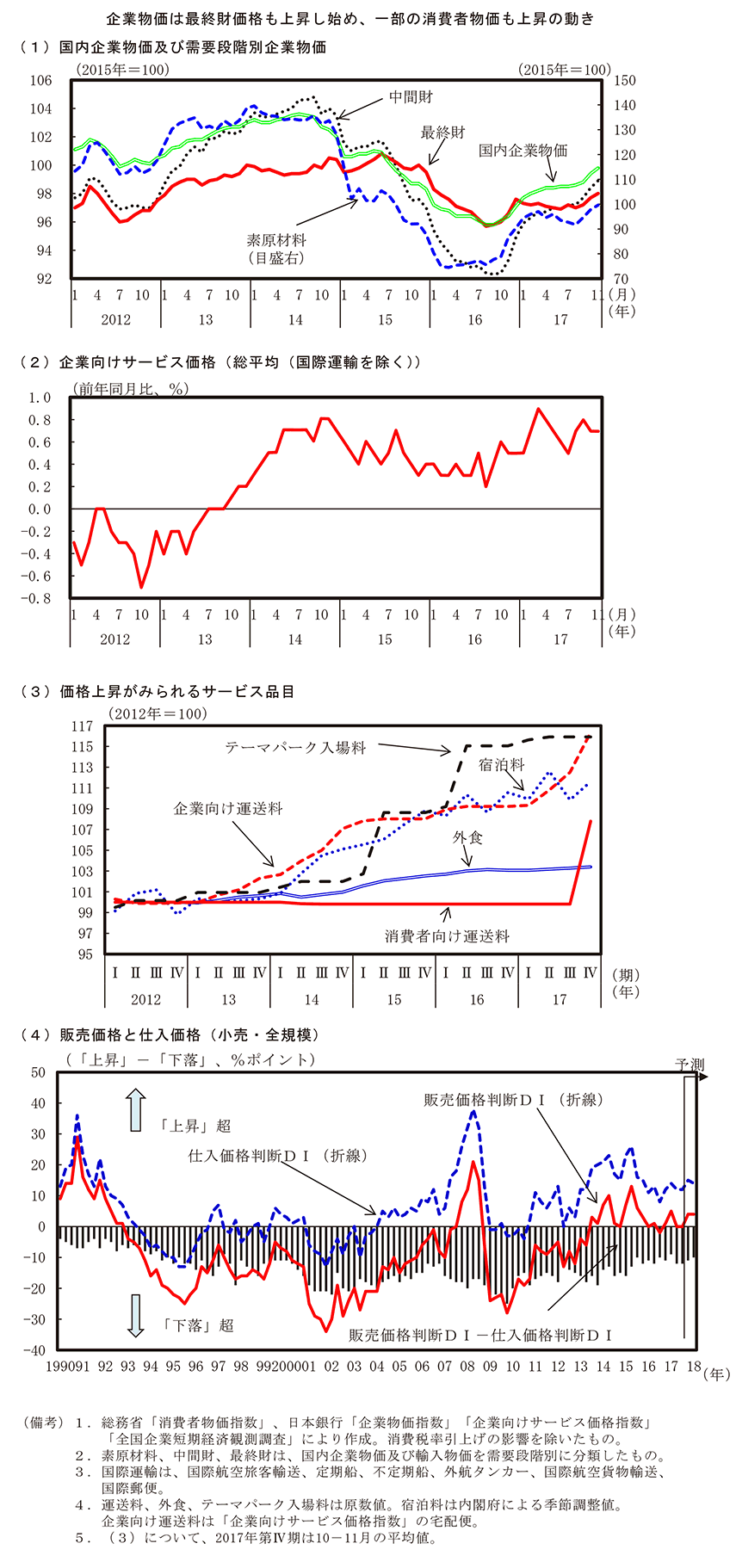
(物価を取り巻く環境の局面変化)
以上で確認したように、物価を取り巻く環境については、GDPギャップがプラスに転じるとともに、人手不足感が四半世紀ぶりの高水準になっている。こうした需給のひっ迫に加え、第1節でみたように企業収益が過去最高を更新する中で、春闘では過去4年間にベアを含む賃上げが実現し、緩やかではあるが賃金も上昇し、ULCも僅かながらプラスとなっている。加えて価格転嫁が企業物価では着実に進行し、配送料など一部ではその波が消費者物価に及びつつある。このように、物価を取り巻く環境には局面変化がみられるが、消費者物価の基調が現状では横ばい圏内にとどまっていることを踏まえると、物価の持続的な上昇につながるためには、まだ課題も残っている。次項ではこうした局面変化をデフレ脱却に確実につなげるための課題を確認する。
2 デフレ脱却に向けた今後の課題
(国際的にみても賃金の上昇が物価の押し上げに重要)
我が国のみならず、アメリカやEUなど他の先進国においても、景気回復の割には賃金や物価上昇率が過去と比べて低い水準にとどまっているとの指摘がなされている。こうした背景には、相対的に賃金水準の低い非正規労働者の比率が高まっていること3や、ネットを通じた電子商取引が拡大する中で価格競争が激化していること等が指摘されている。こうした要因の影響があるとしても、我が国の物価上昇率は他の先進国と比べても低い水準にとどまっており、これら以外の要因も我が国の物価上昇率を抑制していることが考えられる。そこで、日本、アメリカ、ユーロ圏の物価上昇率について、財とサービス価格に分けて動向をみてみると、経済のグローバル化に伴い安い財を輸入できることもあり、これら先進国・地域の財の価格は横ばい圏内で推移している(第1-3-5図)。他方、サービス価格の動向について、日米欧を比較すると、アメリカ及びユーロ圏のサービス価格は一貫して日本のサービス価格の伸びを上回って推移しており、こうしたサービス価格の動向の相違が、物価全体の動向の違いを生み出していることが示唆される。サービス業においては、財と比べて人件費比率が高いことから、サービス価格の動向はそれぞれの国・地域の雇用・賃金動向を大きく反映していると考えられる。実際に、時間当たり賃金の伸びを、日米欧で比較すると、我が国の賃金上昇率は、一貫してアメリカやドイツの賃金上昇率を下回っている。
こうしたことを踏まえると、デフレ脱却に向け持続的な物価上昇を実現するためには、賃金上昇率を高めていくことが重要な課題であると考えられる。
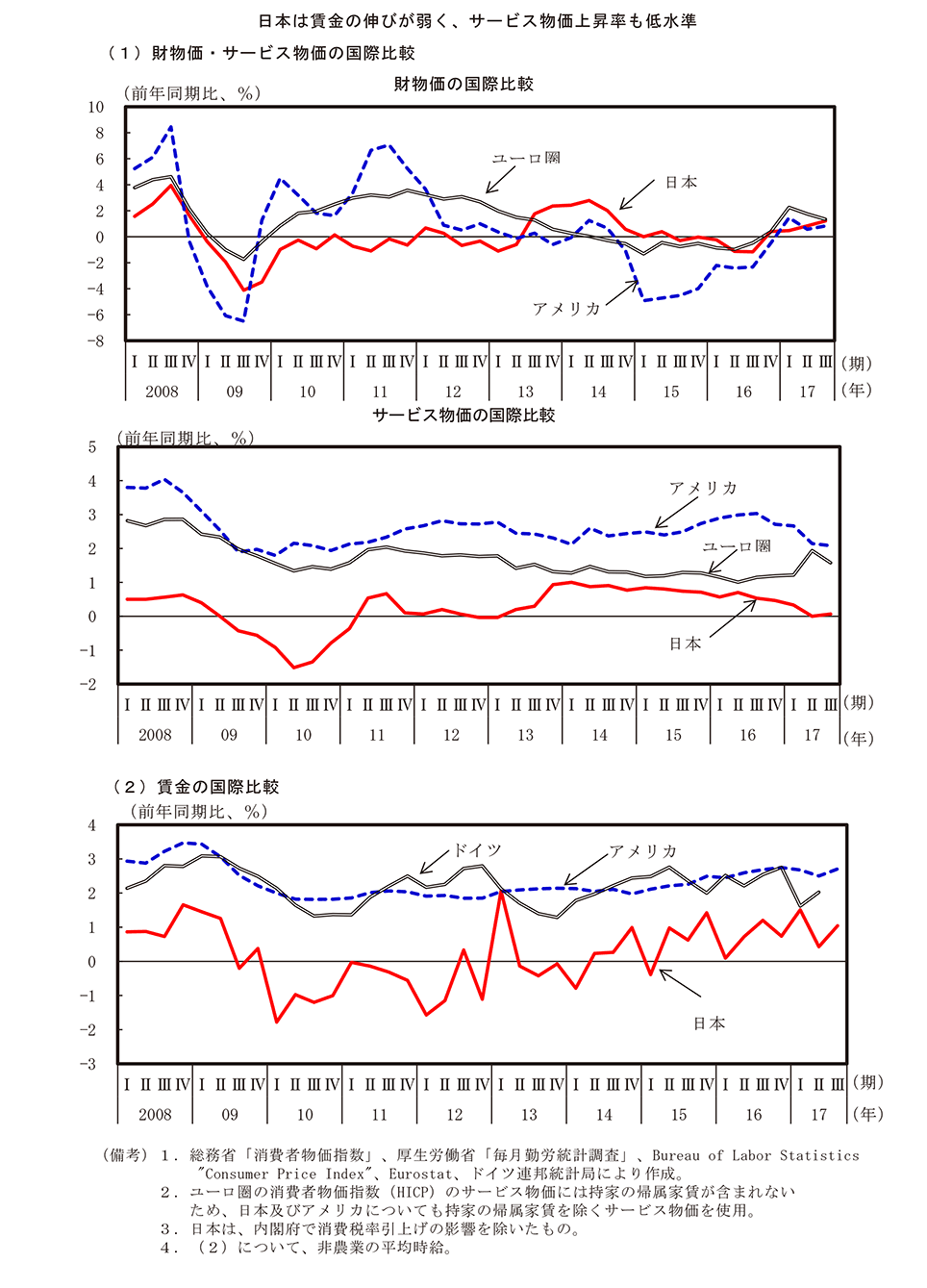
(人手不足感が高まっても、一般労働者の賃金の上昇は緩やか)
我が国の労働市場においては、労働需給が引き締まり方向で推移している中で、既にみたように、パートの時給は上昇しているものの、一般労働者の定期給与の伸びは緩やかとなっている。主な産業別に労働者の過不足感と一般労働者の所定内給与及びパートタイム労働者の時給の上昇率の相関をみると、パートでは労働者不足の産業ほどパート時給の増加が高いという関係が見い出せるが、一般労働者ではその関係を見出すことができず、所定内給与の増加幅も小さいことから、人手不足感が高まっても一般労働者の賃上げにはあまり結びついていないことが確認できる(第1-3-6図)。
こうした背景には、人手不足への対応として、一般労働者の賃上げで対応すると企業にとって中長期的にコスト増につながるので、比較的調整のしやすいパートでの賃上げでこれまで対応してきたと考えられる。ただし、労働需給のひっ迫もあり、雇用形態としては、パートタイム等の増加より正社員の採用や登用の増加で対応する意向がみられる。具体的には、企業が労働者不足にどのように対応しているかを厚生労働省「労働経済動向調査」でみると、「臨時・パートの増加」で対応する企業よりも「正社員採用・登用の増加」で対応する企業の割合が高い。なお、人手不足への対処方法は、外部からの人員確保だけではなく、労働条件の改善や省力化投資による対応など様々な手法となっており、今後はさらなる賃上げの実現や省力化投資の増加が期待される。
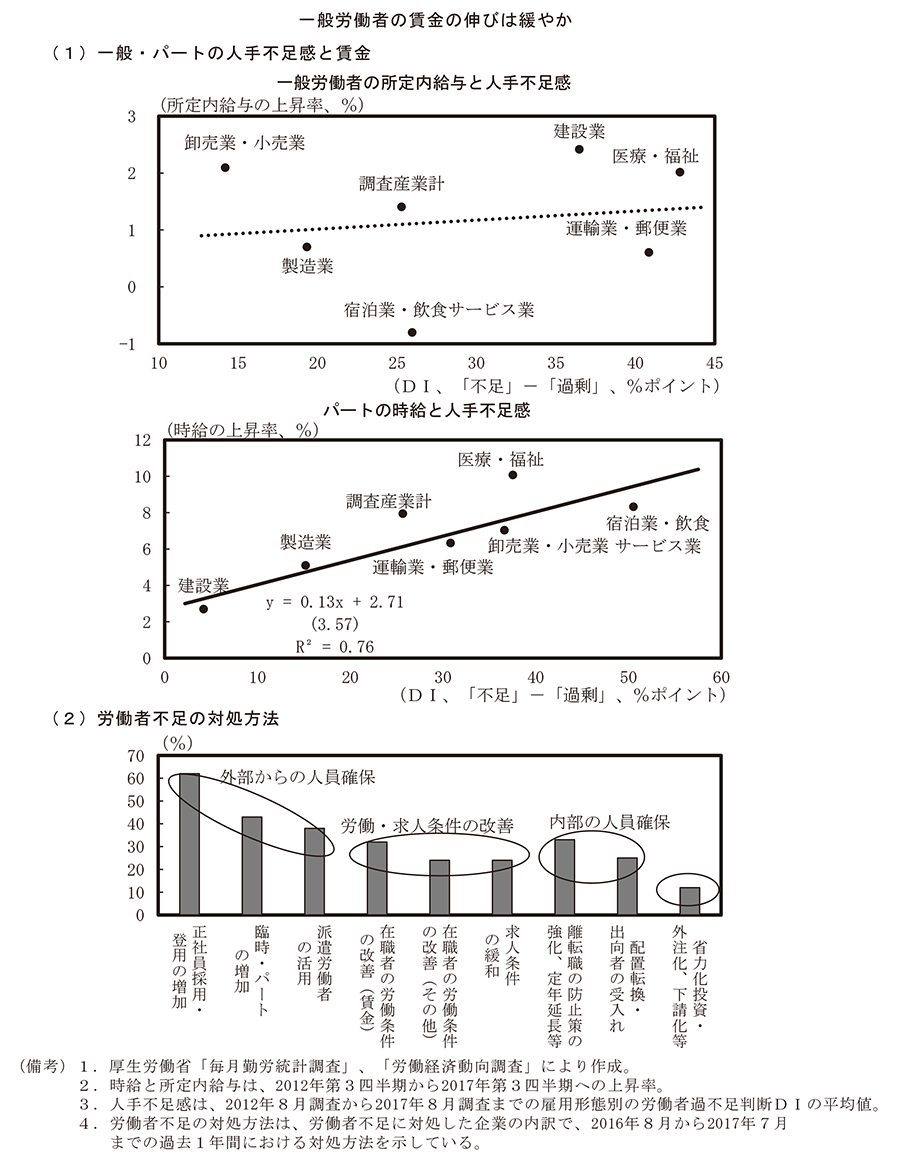
(ベア実現のためには生産性上昇、成長見込みの上昇が重要)
春闘においては、これまでと比べると、過去4年間で2%程度の高い賃上げ率が達成されている。賃上げは定期昇給とベースアップ(ベア)に分けられるが、定期昇給がマクロでみた賃金上昇に与える影響については、労働者全体の年齢構成が変化しない場合、全体でみると相殺4されることになる。このため、マクロでみた賃金を上昇させるためには、ベアをどの程度確保できるかが重要となる。ただし、これまでみたように、人手不足にもかかわらず企業は中長期的なコスト増になる一般労働者の定期給与増には慎重であり、ベアは過去4年間、0%台半ばの上昇率にとどまっている。
ベアを企業の成長率見込み、労働生産性、CPI(総合)(いずれも1期前)で要因分解すると、これまでのベアの動きを、相当程度、この3要因で説明できる(第1-3-7図)。労働生産性は企業の収益に直結するのでベアにも影響されることに加え、ベアは将来的な企業のコスト増につながるため企業の将来の成長見込みにも影響されること、また労働側としては足下の物価上昇を踏まえて来年度の賃上げ交渉をすることから1期前のCPIが重要な要素になると考えられる。
このことからベアを確実に実現するためには労働生産性を高めるとともに、企業が将来にわたり高成長が続くという見込みを持てる環境を整備することが重要であるといえよう。ただし、今回の景気回復局面の動きを見ると、特に2014年度から2016年度においては実際のベアがこれら3要因で説明できる推計値より大幅に下回っている。企業が過去最高の企業収益を更新していることも踏まえると、今後はこれまで以上の高いベアの実現が期待される。
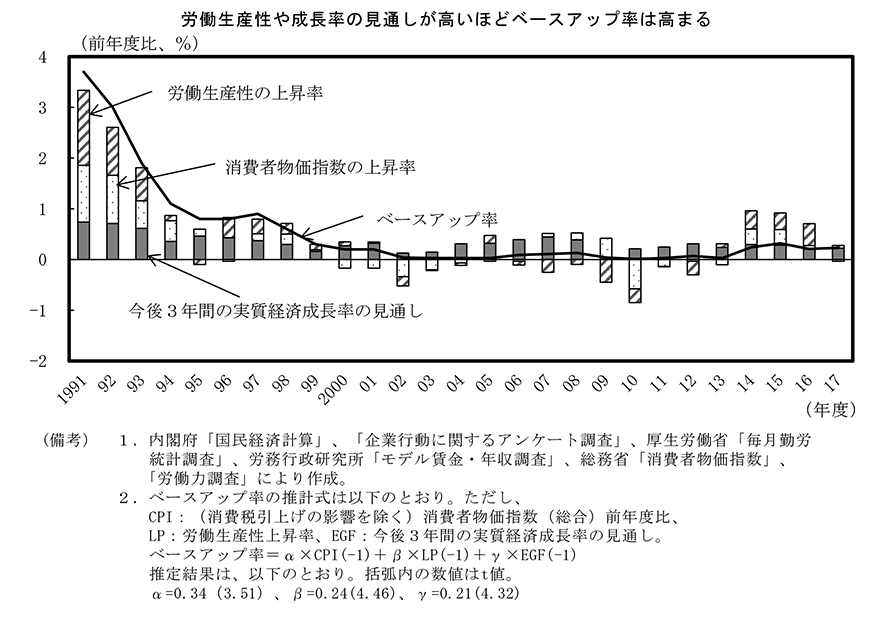
コラム1-4 労働者の年齢構成の変化が賃金に与える影響
賃金カーブはおおむね50歳代前半をピークとしていることから、賃金水準の高い中高年の労働者が増加することにより、全年齢を平均した一人当たりの賃金が押し上げられるが、逆に賃金水準の高い高年齢の労働者の退職や賃金水準の低い若年の労働者の増加により、一人当たりの平均賃金が押し下げられることになる。そのため、団塊世代(1947年~1949年生まれ)の退職に伴い、構造的に一人当たりの平均賃金が上がりにくくなっているとの指摘がされることがある。
そこで、一般労働者の定期給与の変化を、年齢構成が変化することによる要因と各年齢の賃金水準の変化による要因とに分解し、過去10年の動きを分析すると、年齢構成による効果は、2002年以降もプラスに寄与しているものの、賃金を決める要因としては、各年齢の賃金水準の変化による効果が大半を占めていることがわかる(コラム1-4図)。
2007年~2011年頃は、団塊世代の賃金水準が大幅に落ち込む60歳代に差し掛かることで年齢構成効果のプラスの寄与が減少していたが、団塊の世代の退職が進み賃金水準も低くなった2012年以降は、主に団塊ジュニア世代(1971~1974年生まれ)が賃金水準の高い50歳代前半に近づきつつあることで、プラスの寄与が再び増加している。また、若年の労働者の割合は少子化の影響等により長期的に減少傾向5にあるため、年齢構成効果に対するマイナスの寄与はしていない。
さらに、一般労働者の賃金カーブの2002年から2016年への変化を見ると、20歳代の若年層の賃金が上昇し、30歳代後半から40歳代の中年層の賃金が減少している。こうした中年層は、団塊ジュニア世代とも重なることから、賃金水準の低下している中年層の割合が増加していることは、一人当たりの平均賃金の伸び悩みの要因の一つとして考えられる6。
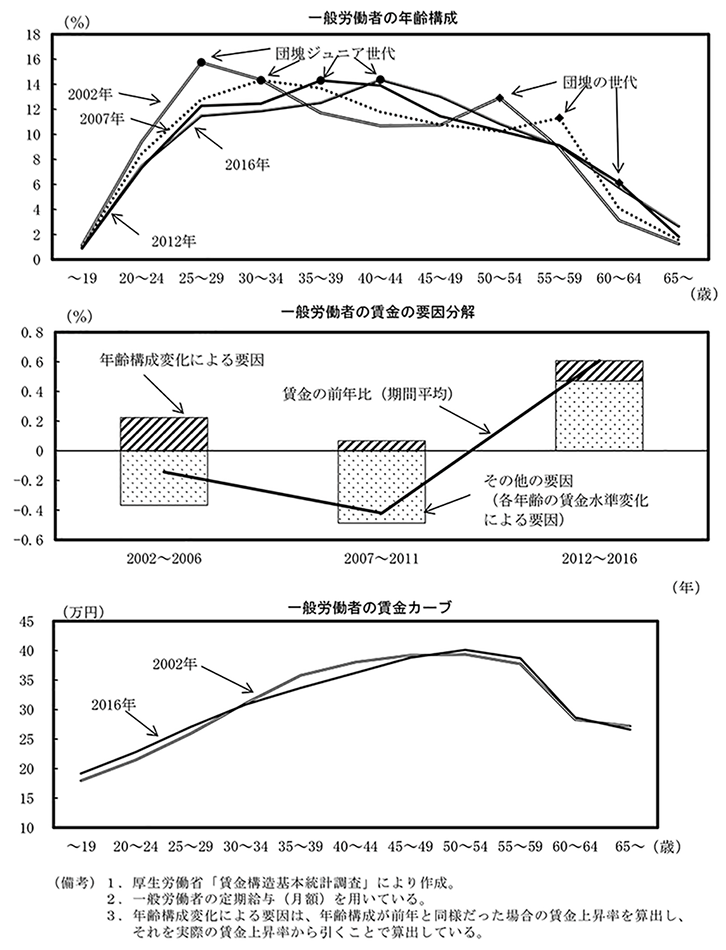
(生産性向上とともに、大幅な賃上げが重要)
企業は労働生産性を高めることで収益向上を実現し、労働者への賃上げも可能となる。我が国の労働生産性と賃金の動向を製造業、非製造業に分けてみると、製造業は労働生産性が向上しているもののそれに見合った賃上げができておらず、そのためULCも低下が続いている(第1-3-8図)。90年代半ばについては急激に円高が進んだため、労働生産性が向上しても賃上げではなく円ベースで見た販売価格の引き下げを選択していた可能性がある。ただし、現在はかつてのような円高局面ではなく、第1節で確認したように交易条件も改善しているため今後は労働生産性上昇に見合った賃上げが期待される。
非製造業はICT資本の利活用の遅れなどにより労働生産性が上がっていないため賃上げが難しく、ULCも横ばいの動きとなっている。我が国は少子化もあり生産年齢人口が減少しており、潜在成長率を高めるためにも生産性の向上は急務である。特に労働生産性の伸びが緩慢な非製造業は、産業構造の変化もあり、GDP、雇用面で見ても我が国経済の多くの部分を占めるため、今後は非製造業を中心に、労働生産性を大きく向上させることが重要であるとともに、製造業も含め大幅な賃上げが期待される。
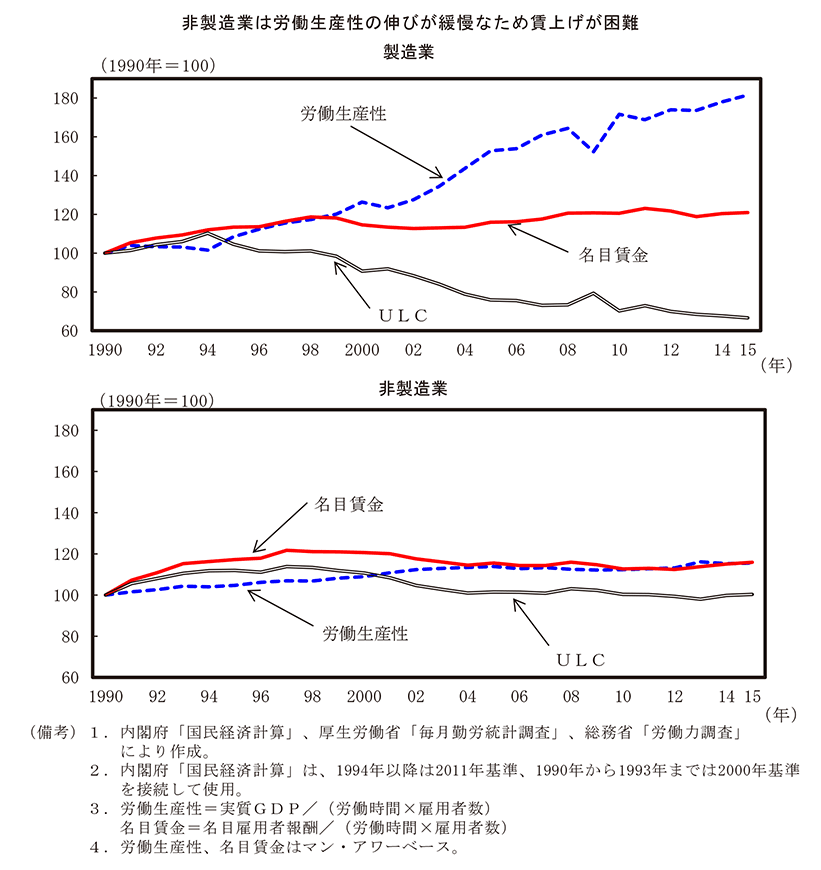
(消費者への価格転嫁のためには需要面の強さも重要)
消費者物価において、価格が最近上昇している一部のサービス価格の動向の背景をみると、当該サービスに対する需要増加により価格転嫁が可能となっている面がみられる。日銀短観の各産業の販売価格判断DIと仕入れ価格判断DIの差を価格転嫁の程度とみなし、当該産業の需給判断DIを需要の強さを示すものとみなして、両者の相関をみると、総じて需要の強い産業において価格転嫁が進んでいる傾向がみられる(第1-3-9図)。
既にみたように、企業は消費者物価への価格転嫁に慎重な姿勢がみられるが、こうした背景を確認するために、ある財の価格が上昇した際に、当該財の需要がどの程度変化するかを示す、財別の需要の価格弾力性を推計した。この結果をみると、耐久財の価格弾力性が1.4程度と最も高く、食品等を含む非耐久財の価格弾力性が0.5程度とその次に高くなっている。特に、食品等を含む非耐久財の価格弾力性については、その多くが必需品であり、本来は価格弾力性がほとんどないと考えられるが、時系列で価格弾力性の変化をみると、近年上昇傾向がみられており、消費者が食品や日用品などの価格変化に敏感になっている可能性が示唆される。
こうした点を踏まえると、今後、消費者物価レベルでの価格上昇が広くみられるようになるためには、コスト面の押し上げだけでなく、需要面の強さも重要であることが示唆される。こうした観点からは、賃金の上昇によって、家計の勤労所得が増加し、それに見合って消費需要も強くなることが期待される。
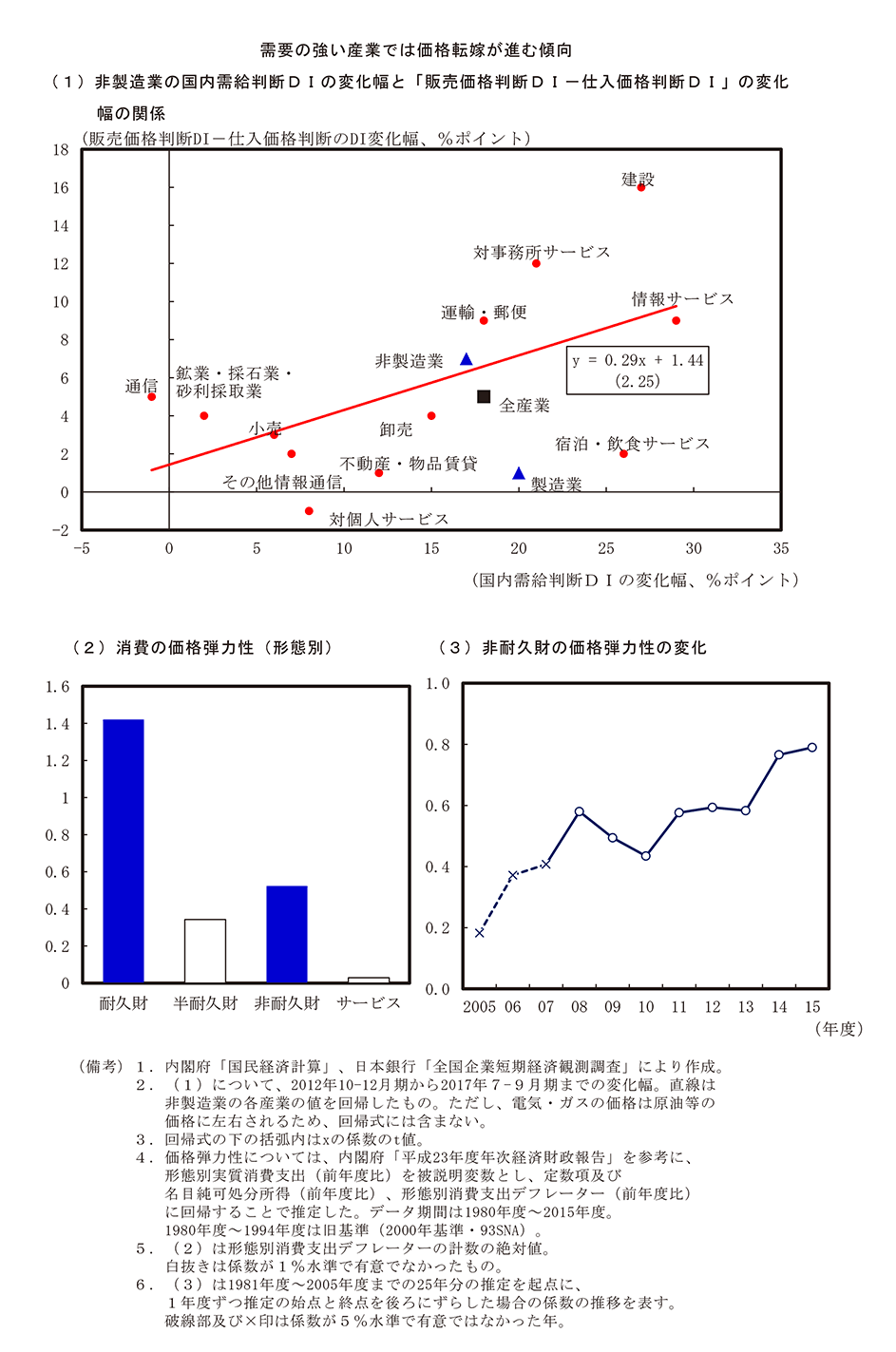
コラム1-5 運送料が上昇した場合の物価全体への影響
人手不足感の高まりに伴う人件費の上昇等により、企業向け運送料が上昇している点については既に述べたとおりだが、ここでは、企業向け運送料の上昇が、消費者が直面する物価7にどの程度の影響を及ぼすかについて見てみよう。
各産業が財・サービスを生産・販売する際には、別の産業から原材料やサービス等を購入している。この連鎖的なつながりを表したものが産業連関表である。この産業連関表(54部門)に基づき、54部門の価格がそれぞれ1%上昇し、これが投入される産業において全て価格転嫁されたと仮定した場合における物価全体の上昇率を試算した。その結果、54部門の平均は0.03%となったのに対し、運送業の定義に近い道路貨物輸送が含まれる運輸・郵便部門が1%上昇した場合の物価全体の上昇率は0.09%となり、平均を大きく上回った。この背景としては、運輸・郵便部門は様々な産業に利用されており、価格上昇が物価全体の押上げにつながりやすいことが挙げられる。
次に、具体的にどの産業への影響が大きいかを確認するため、産業連関表において道路貨物輸送の価格が上昇した場合の影響について同様の手法を用いて試算すると、特に飲食品部門や対個人サービス部門等の価格押上げに寄与するとみられる。これは飲食品部門や対個人サービスにおいて、特に運送業が利用される割合が高いことが要因である。
実際に価格上昇に伴うコスト増加を販売価格にどの程度転嫁するかは各企業の判断になるため、ある程度の幅を持って見る必要があるものの、他部門との関連の強い品目の価格上昇は、広い範囲の財・サービス価格を押し上げる可能性があることが示唆される。
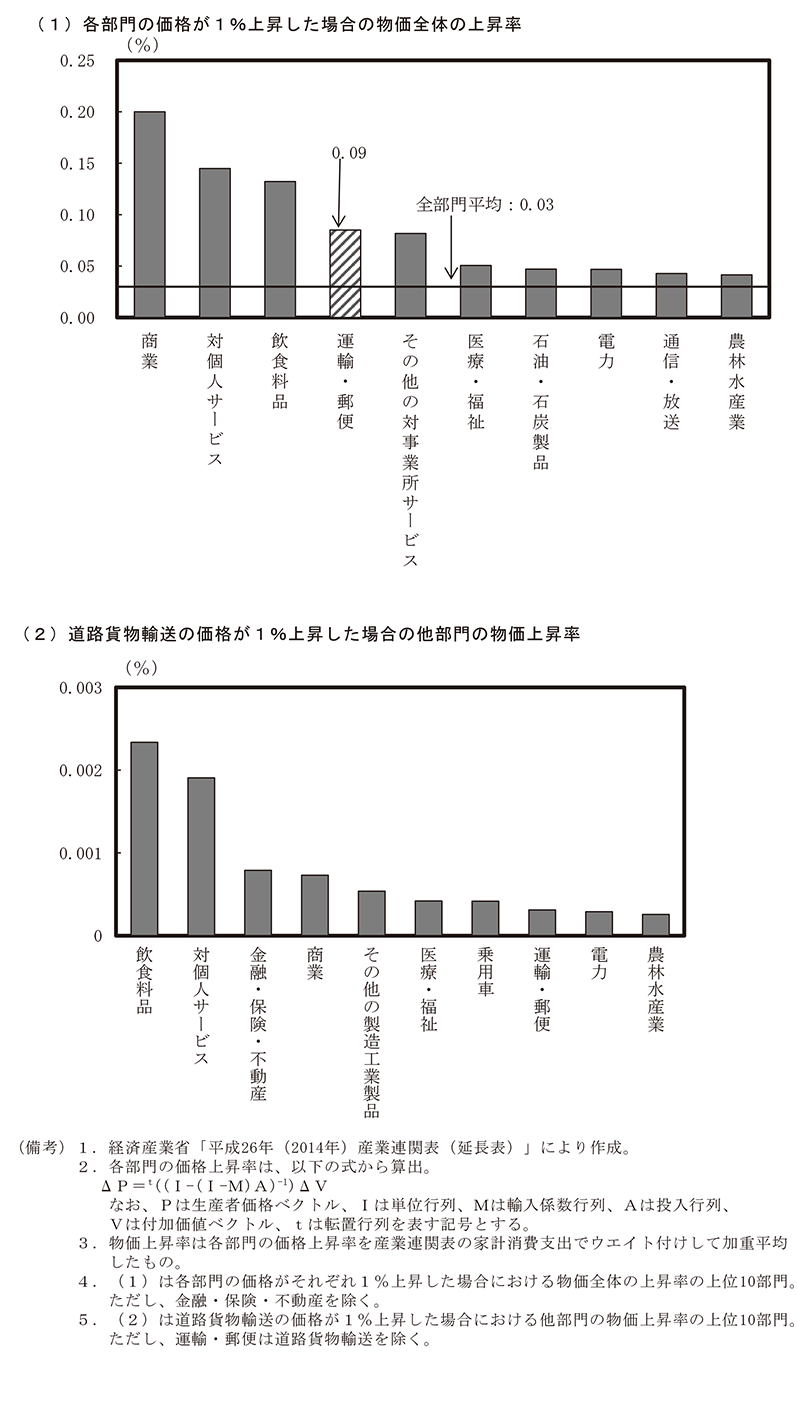
3 金融市場の動向と家計の資産運用
(金融市場の動向)
この1年の金融市場の動向を見ると、日本銀行の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の効果もあり、10年債利回りはおおむね0%程度のプラス圏で安定的に推移した(第1-3-10図)。また、アメリカのFED(連邦準備制度)が利上げを行う中、インフレ率の低位安定等を背景にアメリカの長期金利も大きな変動がなかったため、日米の金利差は安定的に推移、ドル円の為替レートも変動が少なく推移した。
なお、2016年以降の日本銀行の金融政策の変遷と、その間の国債利回りの動向を振り返ると、金融政策については、2016年1月には、「量」・「質」・「金利」の3つの次元で金融緩和を進めていく「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定した。また同年9月の金融政策決定会合においては、「量的・質的金融緩和」及び「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の下での経済・物価動向と政策効果について「総括的な検証」を行い、イールドカーブ・コントロール等を盛り込んだ「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入した。この間の国債利回りの動向をイールドカーブの変化を通じて概観すると、従来からの長期国債買入れと組み合わせたマイナス金利政策の導入によって、金利にさらなる下押し圧力が加わったことで、イールドカーブ全体が低下したほか、特に長い年限の金利水準が大きく低下したことによって、イールドカーブはフラット化した状態となった。その後は、2016年9月に導入された「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の下で、短い年限の金利水準は小幅のマイナス圏で推移し、10年債利回りはおおむねゼロ%程度のプラス圏で安定的に推移するなかで、長い年限の金利水準は上昇した。その結果イールドカーブは、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」導入時を上回って推移している。
一方、企業収益が過去最高を更新していることなどもあり、日経平均株価は年後半に上げ幅を拡大し、バブル崩壊後の戻り高値であった1996年の水準を超える水準にまで回復した。
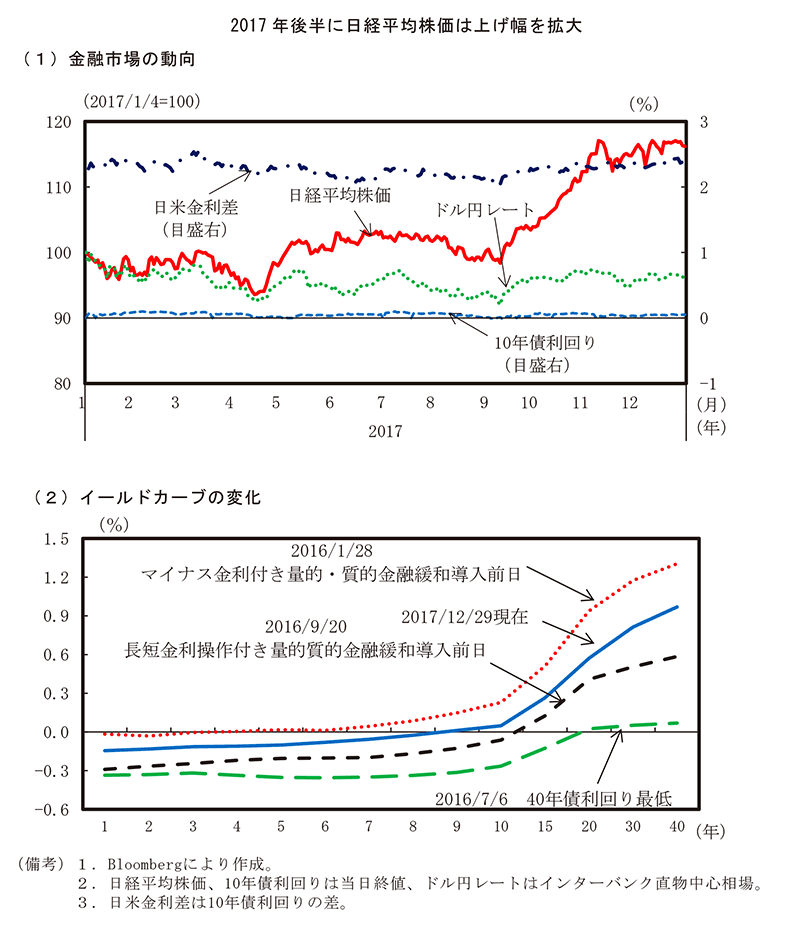
(家計の金融資産の動向)
前項で確認したように株価の上昇などによる資産効果も消費を押し上げているが、人生百年時代を迎える中、将来への備えとなる家計の安定的な資産形成という観点からも金融資産の動向は重要である。家計の金融資産残高の動きを見ると、緩やかに増加を続けているが、現預金の比率が一貫して高水準で推移し、株式などのリスク性資産の割合は低位にとどまっている(第1-3-11図)。
2014年1月にスタートしたNISAは、個人投資家のための税制優遇制度であり、総口座数は増加しており、累積買付額は11兆円超となっている。NISA以外にもジュニアNISA、つみたてNISA、iDeCOなど投資を促進する制度が次々とできており、今後は、将来への備えとなる安定的な資産形成の実現に向けた動きが促進されること、また「貯蓄から投資へ」の流れが促進されることで家計から企業への資金供給が拡大し、経済が成長するとともに、家計も潤い、さらなる投資につながるという好循環が生みだされることも期待される。