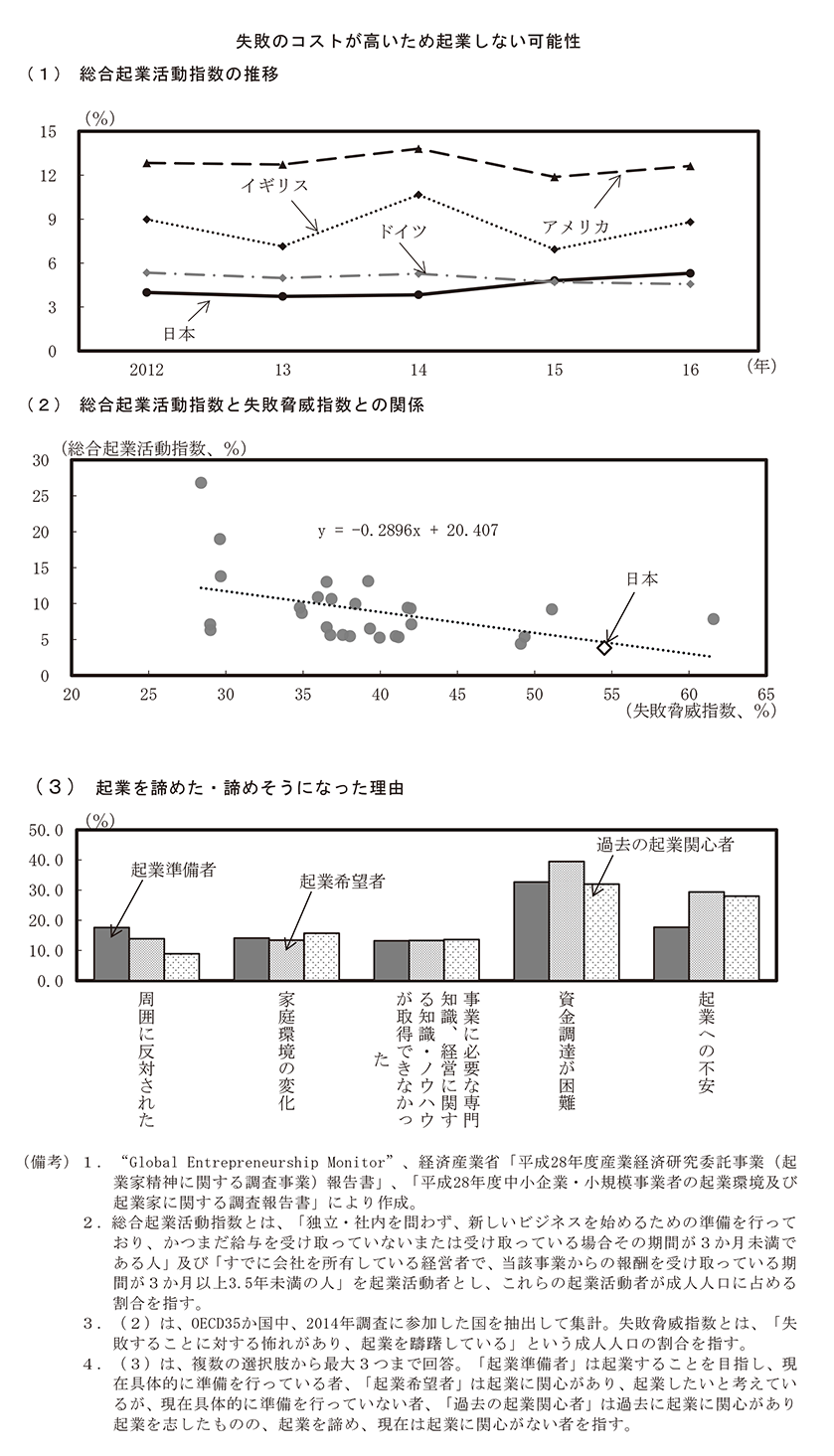第2章 多様化する職業キャリアの現状と課題(第1節)
第1節 職業キャリア形成の変化
本節では、まず、なぜ職業キャリアを多様化させることが今後重要になってくるのかについて考察する。次に、そのような複線型のキャリア形成には市場の流動性が必要であるが、現在の労働市場はどの程度その要望に応えているのかについて、転職市場の現状を分析する。最後に、キャリア形成の選択肢としての副業・起業について現状と課題を整理する。
1 職業キャリアの多様化はなぜ必要か
(世界有数の長寿国、日本)
今後、人生における就業期間が長期化することが見込まれているが、その一番の理由は平均寿命の伸長である。第2-1-1図(1)は戦後の平均寿命の推移をみたものであるが、1950年の平均寿命は男性58歳、女性62歳であったが、65年後の2015年時点では、男性81歳、女性87歳と、男性で23年、女性で25年の長寿化が進んでいる。この傾向は今後も続いていき、2050年までに女性の平均寿命は90歳を超えることが予想されている。
このような長寿化に伴い、Gratton and Scott(2016)が指摘するように、引退期間において必要な資金を確保するためにも、就業期間の長期化が進むと考えられる。例えば、仮に60歳で引退すると、平均寿命が75歳であれば予想される引退期間は15年だが、平均寿命が85歳であれば予想される引退期間は25年となる。今後その期間がさらに長期化すれば、仮に賃金水準が同じでも、現在の世代の貯蓄行動が前の世代と同じでは引退後に貯金が足りなくなる可能性がある。
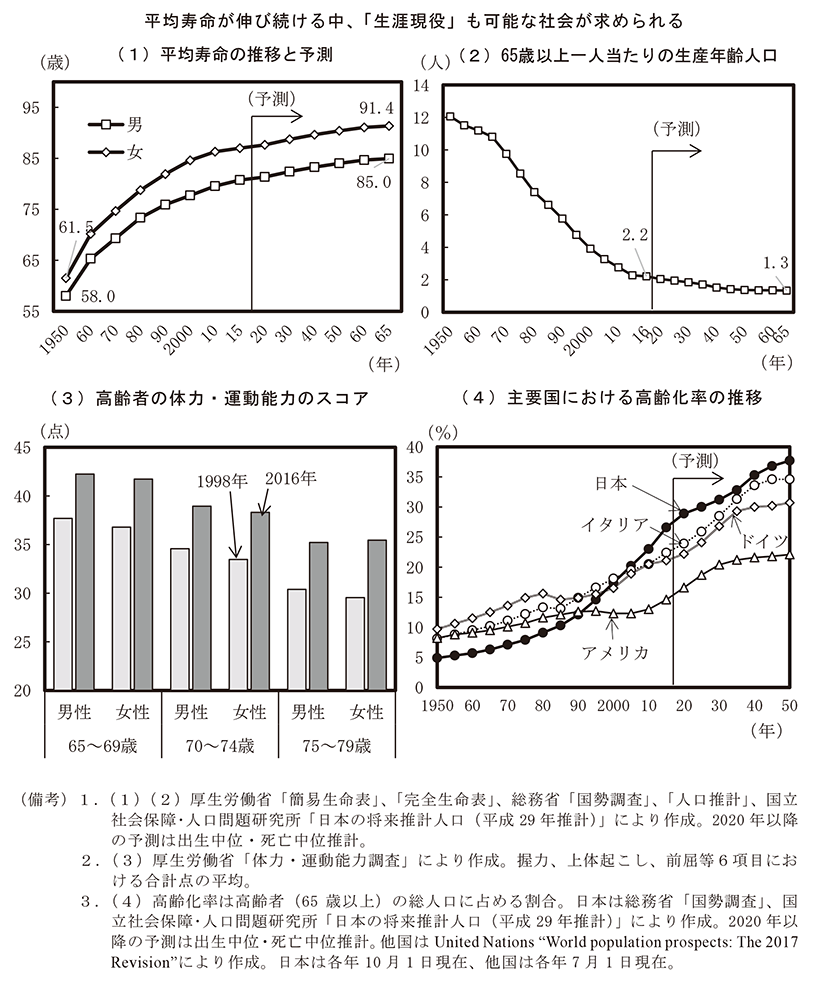
また、高齢者(65歳以上)一人当たりの生産年齢人口(15~64歳)の推移をみると、1950年で12.1人、1980年で7.4人、2016年で2.2人と急激に減少している(第2-1-1図(2))。このように世代間扶助の観点からは、より少ない現役世代で高齢者への給付を負担することとなっているが、今後就業期間が長期化すれば、若年世代の負担軽減に寄与するものと考えられる。
現在の高齢者は、昔の高齢者と比較して体力・運動能力も高く、例えば、2016年の75~79歳の体力・運動能力のスコアは、1998年における65~69歳のスコアとおおむね同じである(第2-1-1図(3))。労働市場が人手不足となるなか、日本の高齢化率は世界で最も高くなっており(第2-1-1図(4))、就業を希望すれば生涯現役で働くこともできるなど、年齢にとらわれずに自由に職業人生を設計できるようなシステムが求められる。
(技術革新と中スキル就業者の減少)
最近の技術進歩はこれまで以上に変化のスピードが早い。就業期間が長期化するにもかかわらず、外部環境の変化が激しければスキルが陳腐化しやすいため、年齢にかかわらず定期的にスキルをアップデートすることが必要となる。また、次節で詳しく述べるが、事務的な仕事はAI等に代替されやすくなってきており、技能のアップデート以外にも、学び直しを行っていかないと労働市場で失業する確率が高くなる可能性もある。
第2-1-2図(1)はG7諸国で、スキル別の就業者シェアの変化をみたものだが、程度にばらつきはあるものの、各国とも中スキルの就業者シェアが低下し、高・低スキルの就業者のシェアが増加している。こうした先進国における中スキル就業者のシェアの低下は、グローバル化よりも技術進歩の影響が大きいことが指摘されている(IMF、2017)。現時点では、日本の中スキルのシェアの低下幅は他国と比較して少ないが、今後この傾向が加速化する可能性も考えられる。
先進国の中スキルの職業シェア低下の背景には、製造業における中スキル労働者の減少が大きく寄与している(OECD、2017)。仮に、こうした製造業における中スキル労働者の減少が、機械の導入による生産性向上の結果であれば、雇用が減少しても付加価値が減少するとは限らない。この点を確認するために、日本、アメリカを比較すると、程度の差はあるが、両国の製造業とも雇用者数は減少トレンドである一方、付加価値は上昇トレンドにある(第2-1-2図(2))。製造業における労働者数の減少は、労働集約的な生産工程を海外に移転する等のグローバル化が影響している可能性はあるが、ロボット等の新技術の導入により、より少ない労働者で高付加価値を生み出せるようになったことが主な要因であると考えられる1。
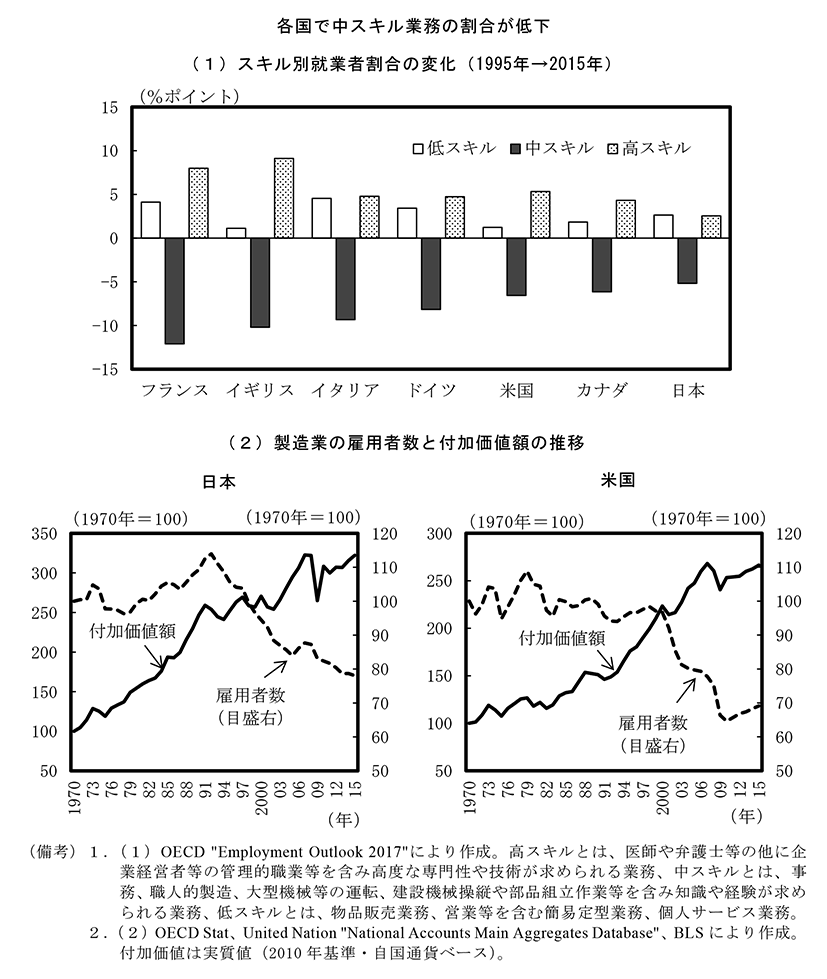
(女性の正規雇用としての職場復帰が課題)
職業キャリアの多様化が必要な理由として、より多くの女性が労働参加するようになったことも挙げられる。人口減少と人手不足が深刻な日本経済においては、性別にかかわらず活躍できる環境の整備が必要である。
近年その傾向は弱まっているものの、女性が出産・育児により離職し、その後労働市場に正社員として復帰していないケースは依然として多い。第2-1-3図は2010年に出産した母親の就業状況の変化を追跡調査したものであるが、出産前(妊娠判明時)には62%の女性が有職であったが、第1子出産後(出産半年後)には有職の割合が36%にまで減少しており、有職者の約4割の女性が出産を契機に無職になっている。その後、有職者の割合は増え、出産5年後の有業割合だけをみれば、出産1年前とほぼ同じになるが、実際増えているのはパートやアルバイトであり、常勤の割合は出産後減少したままである。
女性社員の能力が発揮できるような特質をもつ企業では、生産性や競争力が高いとの分析は多い2。出産等で一時的に労働市場から離れることはあっても、その後、休職前と同じキャリアパスに戻ってこられるような労働システムにすることで、女性人材の活躍を推進していくことは日本経済にとって非常に重要である。
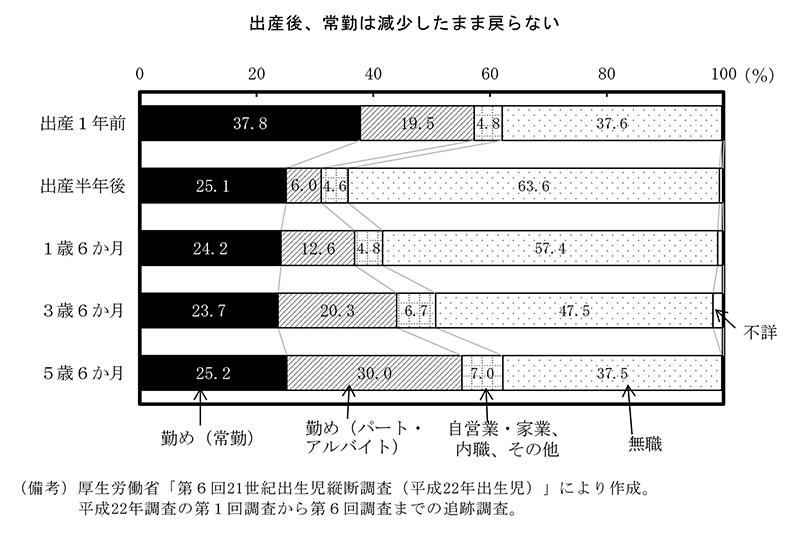
2 転職市場は流動的か
長期化する就業生活をより充実したものにするためには、より柔軟に働き方を調整できること、言い換えれば、望んだ時に転職がしやすいように、労働市場が流動的であることが必須だろう。以下では、転職市場の現状について整理し、雇用の流動性について考察する。
(近年の転職者数は緩やかに増加。入職経路は多様)
転職者数3・転職率の推移をみたのが第2-1-4図(1)・(2)である。転職者数の推移をみると、男女間に大きな水準の差はないが、男性の就業者の方が多いため、転職率でみると女性の水準が高くなる。1990年代前半の転職者数は250万人程度で推移していたが、2000年代にかけて増加し、2006~07年に346万人とピークに達した。その後、経済情勢の悪化を背景に転職者数・転職率は減少したが、足下では女性の転職者数が緩やかに増加する一方、男性の転職者数はおおむね横ばいで推移しているため、全体の転職者数・転職率は緩やかに増加している。ただし、2016年の水準は90年代前半よりは高いものの、リーマンショック以前よりは低くなっている。
次に、年齢階級別に転職率の動向を確認する(第2-1-4図(3))。15~34歳の年齢層では、金融危機前までは上昇トレンドであったが、この背景には新卒時に希望する職業に就職できなかった若年層が、景気回復を背景に転職を行った可能性が考えられる。大卒・高卒の求人倍率と入社3年後の在職率の関係をみると、両者の動きはおおむね一致している(付図2-1
)。2000年代前半頃は、新卒の求人倍率が低く、この時期に入社した者の3年後の在職率も低くなっている。
金融危機後、15~34歳の転職率は低下し、その後はおおむね横ばいで推移している。この背景には、景気低迷が長引く中で、終身雇用を希望する若者の割合が高くなっていることが影響している可能性がある4。金融危機後、新卒の求人倍率が低下しても、以前ほど在職率が低下しなくなった傾向があることも、若年層のこうした意識を反映していると考えられる(付図2-1
)。
35~44歳、45~54歳の転職率をみると、大まかな動きは15~34歳の転職率と同じであるが、足下では35~44歳の転職率が若干の低下傾向にある一方、45~54歳の転職率は上昇しており、2016年の水準は2007年と並び最高水準にある。55歳以上の年齢層では上昇トレンドが続いており、2016年の水準は金融危機前を超えて最も高くなっている。平均余命が伸びていることなどを背景に、就業意欲のある高齢者が定年後、再就職などに積極的になっていることが背景にあると考えられる。
こうしてみると、近年の転職者数・転職率は、高齢層や女性を中心に増加しているものの、全体的な増加のペースは非常に緩やかである。若年層が一企業での継続雇用を志向している可能性や、2016年の水準が依然として金融危機前より低いことを踏まえると、足下の雇用の流動性の高まりは限定的と言えるだろう。
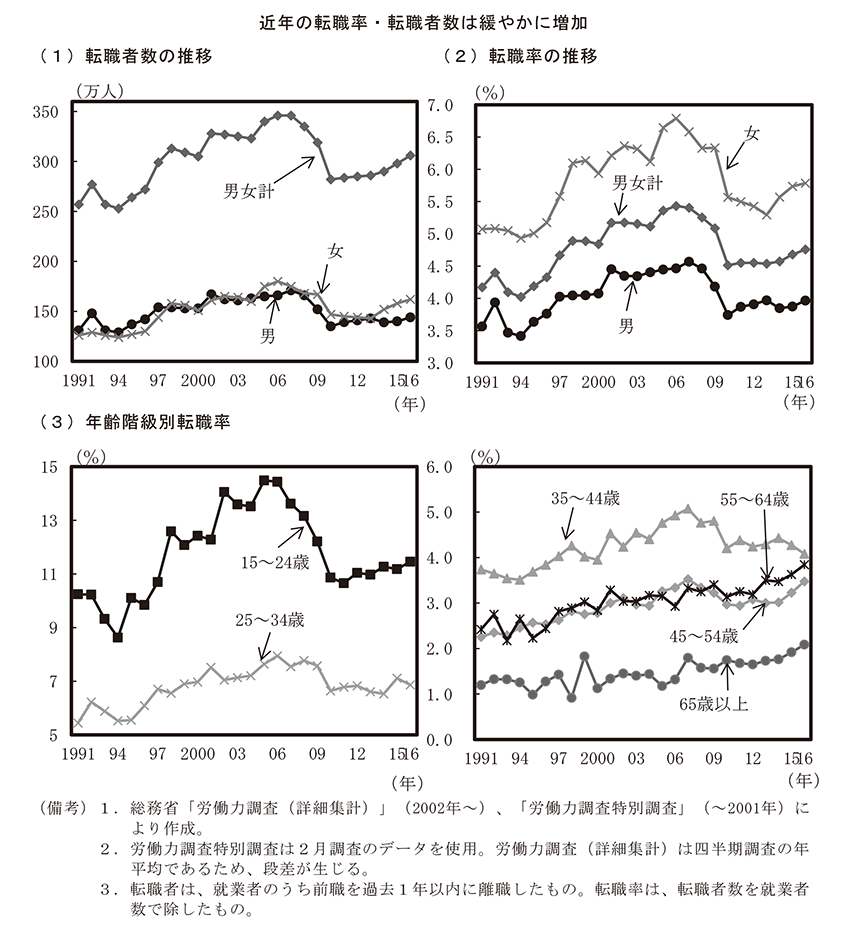
ここで、転職者がどのような経路で入職しているのかについても確認するために、直近2年以内に退職経験者であり、2016年末に就業者である者を対象に、現在の勤務先をみつけた経路を整理した(第2-1-5図)。最も多い経路は職業紹介安定所(ハローワーク)であり、全体の21%はこの経路で入職している。次に、正規・非正規ともに、家族や知人の紹介や、インターネットの転職情報サイトによる入職が多い。非正規については、求人情報誌・広告等の割合が16%と高いが、これはパートやアルバイトへの就職に際し広く利用されているためと考えられる。
入職経路は業種による差異も大きいため(コラム2-1)、ハローワークの統計だけでなく、民間の転職サービス会社が出す倍率等、利用可能なデータを包括的にみることが重要である。
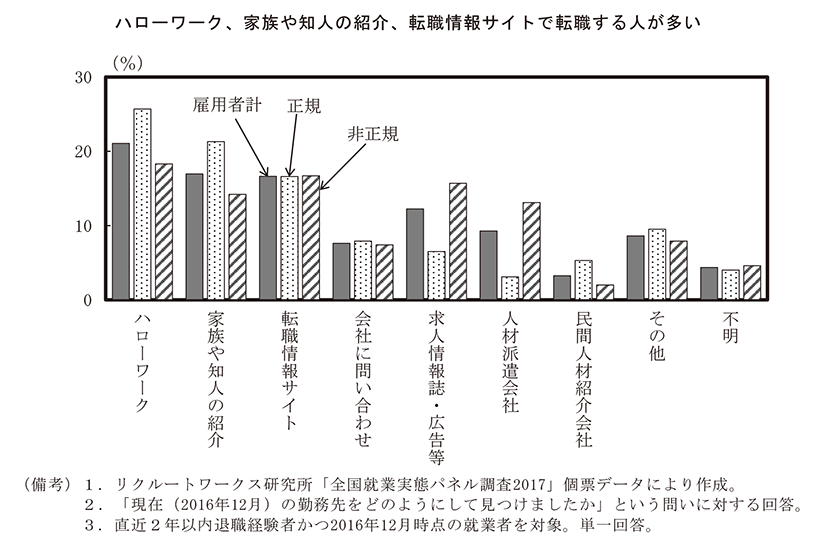
コラム2-1 業種別の転職経路
第2-1-5図では転職経路の全体像を概観したが、転職経路は業種間による差異が非常に大きいことが指摘できる。コラム2-1図は、現在の勤め先をどのようにしてみつけたかについて、回答者を転職後の業種別に集計したうえで、各業種の中におけるハローワーク、インターネットの転職情報サイト、求人情報・広告等、人材派遣会社の4種類の入職経路の割合をみたものである。
第2-1-5図でみたように、最も代表的な入職経路は、ハローワークであるが、特に社会保険・福祉が高いのが特徴であり、同業種に入職した人のうち32%がハローワークを経由している。事実、ハローワークにおける求人・求職の統計である厚生労働省「職業安定業務統計」では、介護サービス関係の職業の求人・求職が多くなっている。また、建設業、医療業、製造業においても割合は高く、これらの業種に入職した4分の1以上の者はハローワークを通して就職している。
一方、情報通信業、金融業・保険業においては、ハローワークを通した転職は非常に少なく、特に情報通信業では7%と1割をきる。ハローワークの統計からこれらの業種の転職者動向を把握するのは困難であると言える。情報通信業では転職情報サイト(25%)や人材派遣会社(23%)を通しての転職割合が高く、金融業・保険業では人材派遣会社(27%)経由の転職割合が高い。これらの業種では、受付業務や付帯業務が比較的多く、こうした産業では派遣会社を利用する傾向がある5。また、個票情報をより詳しくみると、情報通信業ではIT系のエンジニア派遣が一定数存在しているほか、金融業・保険業では派遣会社が契約社員・正社員の人材紹介を行っていると思われる例もみられる。
また、その他の特徴的な業種としては、転職情報サイトにおける不動産業(29%)や、求人情報誌・広告における卸売・小売業(16%)の割合が高い。
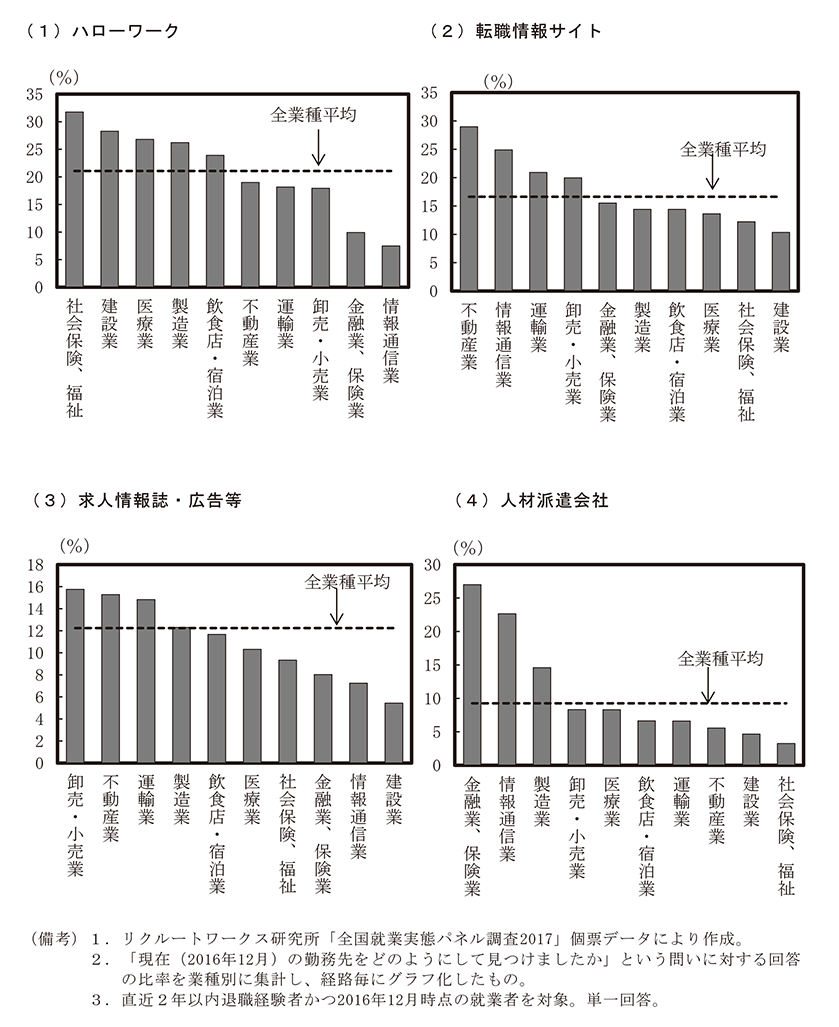
(初職により異なる雇用の流動性)
上記では転職者数や転職率などのフローの動向に着目したが、ストックである転職経験者の動向についても確認しておこう。日本の代表的な職業キャリアのイメージは、学校卒業後に就職した会社に定年まで勤める「一企業キャリア」であるが、現状でそのキャリアパスを歩んでいる人は、どの程度いるのだろうか。
第2-1-6図は、初職が雇用者(正規・非正規)である者のうち、2016年12月時点での退職回数と現在の就業状態を性別・年齢階級別にみたものである。就業経験のある男性の79%は初職が正規であるが、そのうち一度も退職することなく「終身雇用」パスを歩んでいる男性(退職回数0回)は、30代で48%、40代で38%、50代で34%である。これに転職回数1回(退職1回・現在有業)を含めると、30~59歳で6割弱となり、過半数以上の男性の転職回数は多くても1回である。なお、転職2回以上の人の割合は30代で上昇した後、40~65歳ではおおむね4割程度で一定となっている。一方、就業経験のある男性の11%は初職が非正規であるが、退職回数が非常に多く退職回数2回以上と回答した割合が最も多い。新卒時に非正規として採用されると、正規に転換しづらいため、その後のキャリアパスに大きく影響される姿となっている6。
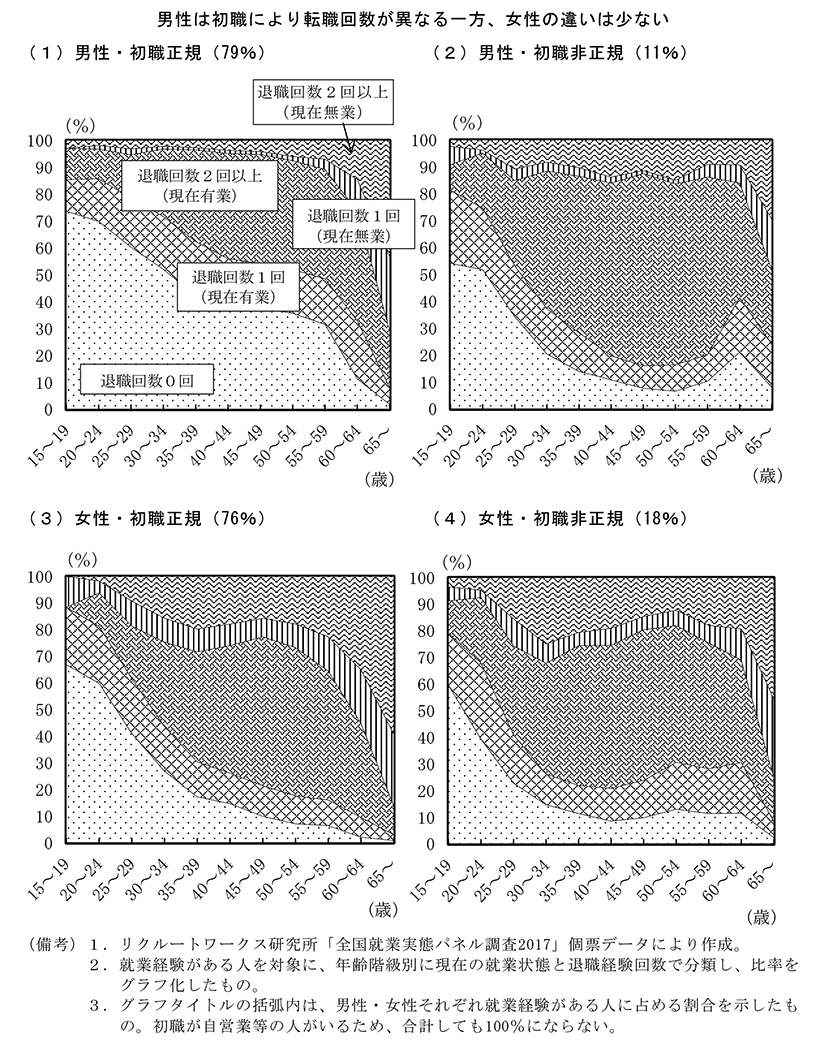
就業経験のある女性では、初職が正規であるのは76%、非正規であるのは18%であり、初職の正規・非正規の割合は、男性と大きな差はないが、その後退職回数は男性と大きく異なる。初職が正規・非正規にかかわらず、グラフの形状が似通っているのが特徴的である。正規で入職した女性のうち、「終身雇用」パスを歩んでいるのは50代で7%程度でしかなく、労働市場から退出した割合も高い。この背景には、前掲の第2-1-3図のように、出産等により所謂「正社員コース」から一度外れてしまうと元に戻れないことが背景にあると考えられる。
初職が正規である男性は、労働市場の中で割合も高いが、雇用の流動性は限定的である。一方、女性や初職が非正規である男性は、転職回数が2回以上の割合も多いが、この背景には正社員に転換できず、非正規の職を転々としていることが考えられるため、転職が希望する職業キャリアの形成に結びついていない傾向があると考えられる。
(転職により賃金が上がる人の特徴は何か)
多様な働き方が浸透し、雇用の流動性が高まるための重要な要素の一つは、転職が不利にならないことである。その点では、転職により賃金が減少しないことが重要な要素の一つであると考えられる。ここでは、厚生労働省「雇用動向調査」のデータを用いて、転職者の性質と転職前後の賃金変化率の関係について、時系列変化を含めてみていくこととしたい7。
まず、転職前後の賃金変化と関係の深い変数を調べるため、機械学習の手法を用いて、転職後に賃金が変化する人の特徴について整理する。ここでは機械学習の分野でよく使われている「ランダム・フォレスト」という手法を用いた8。同手法は、説明変数の数が多くても対応でき、それぞれの説明変数の「重要度」を算出できることから、転職者が持つ多数の特徴のうち、どこに注目するのが適切かを把握するのに有用であると考えられる。なお、この「重要度」とは各変数の賃金変化に対する予測力(推計誤差)の大きさで評価したものである。
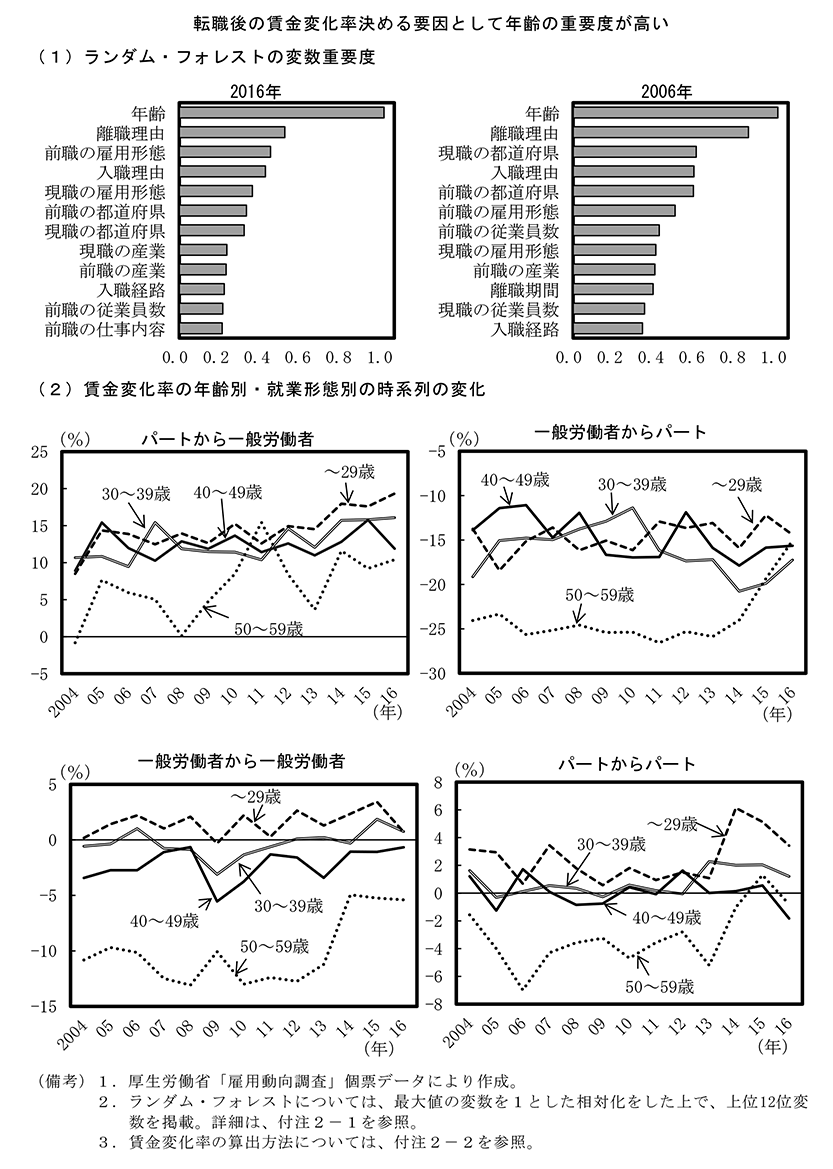
直近の2016年と10年前の2006年の2年を対象とした分析結果をみると(第2-1-7図(1))、両年とも「年齢」の重要度が最も高くなっており、特に2016年では他の変数に対する相対的な年齢の重要度が高くなっているのが特徴である。この背景には、10年前に比べて、定年後の再就職が活発化していることがあると考えられる。また、その次に高い要素としては、前職をやめた理由・現職を選んだ理由、前職・現職の従業上の地位、都道府県、産業、企業規模などが続いている。
では、前述の重要度が高い項目について、より詳細にその内容を確認していきたい。第2-1-7図(2)は、転職前後の従業上の地位の変化別及び年齢階級別に賃金変化率の推移をみたものである9。おおまかな傾向として、年齢階級層が若いほど、変化率が高い傾向にあることがわかる。特に、一般労働者から一般労働者への転職においてその傾向が強く、29歳以下では、グラフ中のほぼすべての時期でプラスだが、30~39歳では0%前後、40歳以上では常にマイナス圏となっている10。また、一般労働者間での転職による賃金変化率は、パート間での転職による賃金変化率と比較して、低い傾向もみてとれる。
パートから一般労働者の転職による賃金変化率をみると、全般的に上昇傾向にある。ただし、50歳未満では近年年齢による差がみられるようになり、20代と40代を比較すると、2011年では両者の差は1%程度であったが、2016年では20代が19%程度の賃金上昇となる一方、40代では12%程度の上昇となっている。一方、逆の一般労働者からパートの賃金変化率に関しては、おおむね横ばいで推移している。
こうしてみると、ランダム・フォレストの結果が示すように、年齢は転職後の賃金上昇率を大きく左右する要素であることがわかる。これは、個々人の観測される属性をコントロールしても、年齢が若いほど、期待される賃金変化率も高いという関係は変わらないためである(付注2-2
)。年齢が高くなると、短期的には転職が不利に働く(賃金が減少する)確率が高くなることが、転職による流動性が限定的となる要因の一つだと考えられる。
年齢・雇用形態以外の要素が、賃金変化率に与える影響についてもみるために、個々人の属性をコントロールした回帰分析を、2014~16年の直近3年間と2004~06年の10年前とで行い、ランダム・フォレストの結果も参考にしつつ、賃金変化率に対して影響力の高い属性をプロットした11(第2-1-8図)。
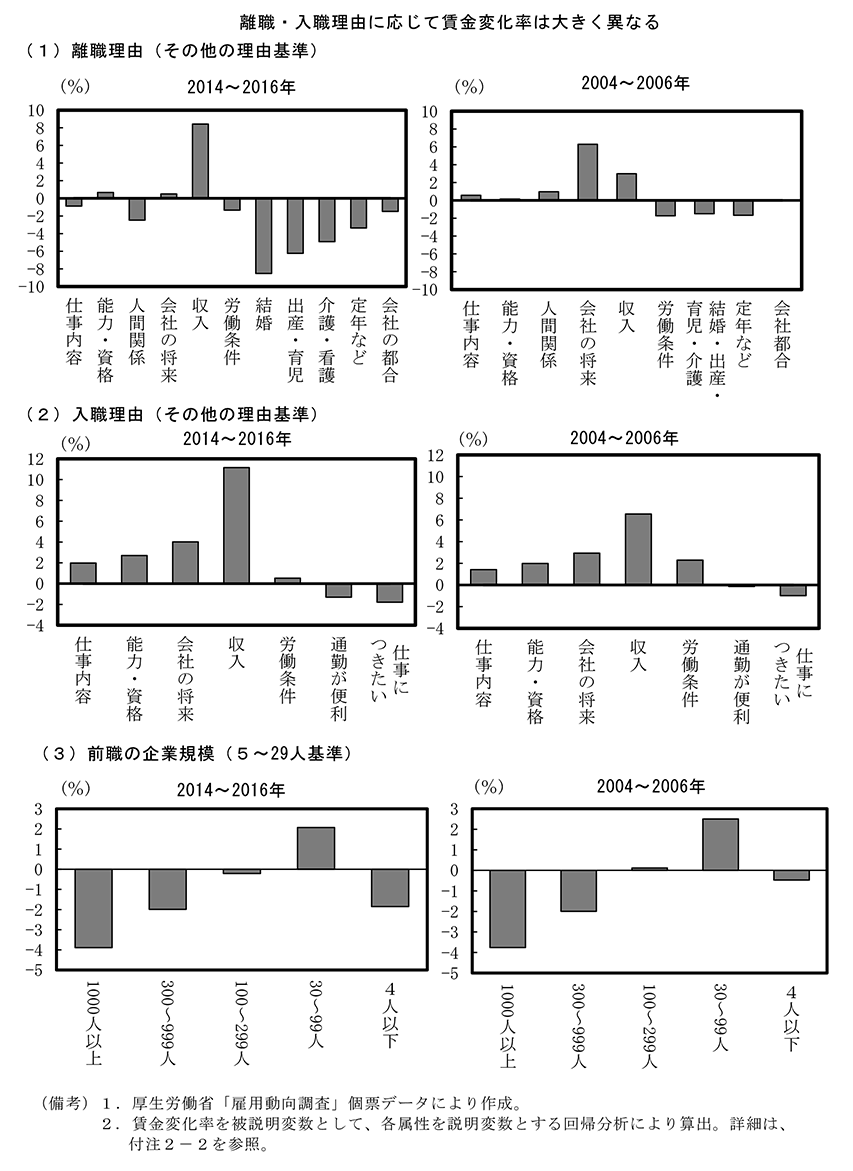
まず、離職理由について、「その他の理由」と答えた人を基準に賃金変化率を比較すると、直近では、収入が少ないことを理由に前職をやめた場合、賃金上昇率が非常に高くなっており、10年前の係数の約2.8倍もの値となっている。また、2014~16年では、結婚、出産・育児、介護・看護などの理由の押し下げ幅が10年前と比較して大きくなっているが、これは出産・育児等が理由で離職した後、パートタイム労働者として復帰する人の割合が増えた結果であると考えられる12。
次に、入職理由について、「その他の理由」と答えた人を基準に賃金変化率を比較すると、離職理由同様、近年では収入を理由に入職した人の係数が非常に高くなっている。10年前と比較して、収入を目的とした転入職は、人手不足を反映して、より賃金上昇率が高くなっている可能性がある。一方、とにかく仕事に就きたいと答えた人は、両期間ともに賃金上昇率が低下する傾向がある。
このように離職・入職理由に応じて、転職成果である賃金変化率が大きく異なっているため、ランダム・フォレストにおいても重要度の高い変数として上位にでてきたものと考えられる。
最後に、企業規模について確認する。前職の従業員規模が「5~29人」であった人を基準に賃金変化率を比較すると、前職の従業員規模が大きい大企業であれば、転職後に賃金上昇率は下がる傾向にある。一方、前職が30~99人規模の企業であった場合、賃金上昇率は上がる傾向にある。10年前と比較しても、係数にほぼ変化がみられないことから、大企業からの転職は転職後不利になる傾向には変化がないと言える。
3 副業・起業はどこまで進んでいるか
雇用者として転職を行うことだけなく、副業や起業を行うことも多様なキャリア形成に向けた選択肢の一つである。ここでは現状の副業・起業にどのような特徴がみられるのかについて整理を行う。
(全体的に副業内容は補助的な性質が強い)
まず、副業をしている人の仕事の内容や特徴について確認する。調査によって「副業」の定義が異なる点には注意する必要があるが、リクルートワークス研究所の調査によると、2016年中に副業・兼業を実施した雇用者の割合は12.9%(正規:10.8%、非正規:16.1%)であり13、ある程度副業に対する敷居が下がっている可能性も指摘できる。
2016年における週当たりの副業時間の調査結果をみると、一定の時間を回答した割合と不規則と回答した割合がそれぞれ半分ずつとなっている。うち一定の時間を回答した者を対象に副業時間を整理すると(第2-1-9図(1))、5時間以下が約40%、10時間以下が約65%となっており、定期的に副業を行っている者の多くは、土日を除き多くても1日2時間以下の副業時間となっている。
また、2016年に副業を行った者の収入をみると、年収20万円未満の回答が多く、全体的な傾向としては、副業の時間や収入は限定的であり、補助的な役割が強いと言える(第2-1-9図(2))。さらに、収入が多い副業の仕事内容についてみると(第2-1-9図(3))、主な仕事と同じ内容と回答する人が2割程度あり、主な仕事に対するスキルアップ等を目的の一つとして副業行っている可能性もある。ただ、その他多くの人々は、アンケートの回答、軽作業、飲食・小売、事務等の簡単な仕事を副業としており、現状の副業は追加的な収入が目的という側面が強いと思われる。
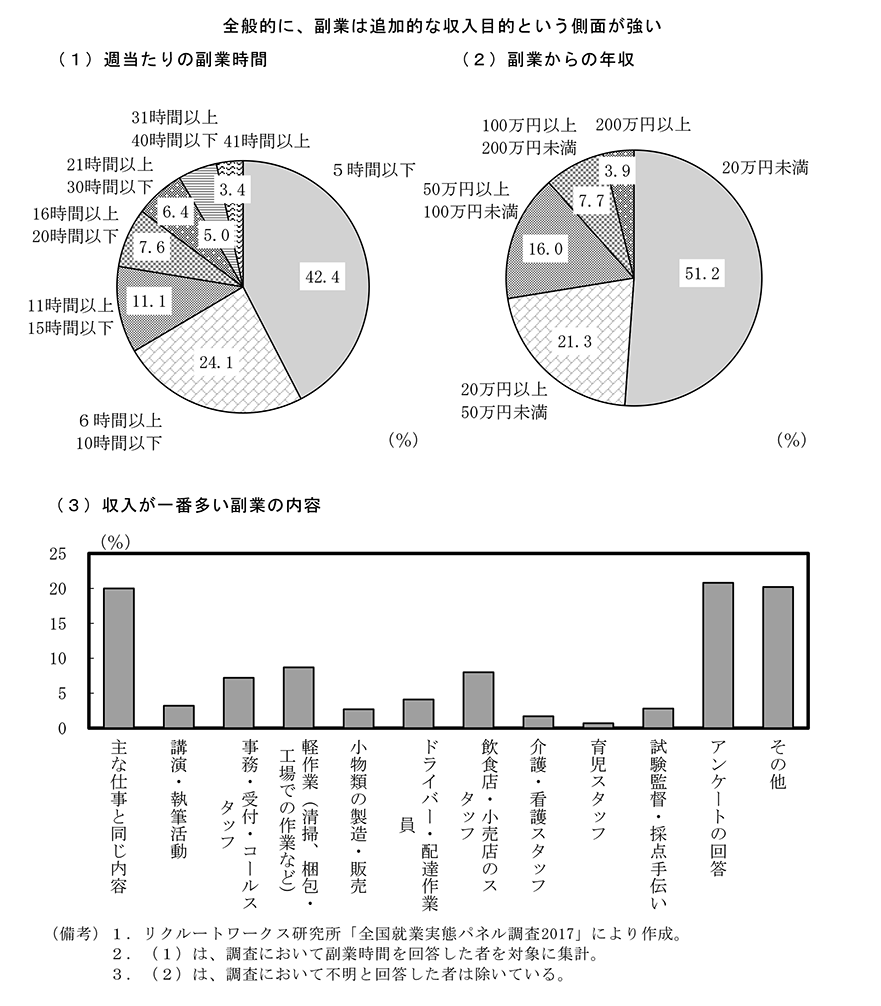
(自己啓発や転職意向の人は副業確率が高い)
次に、副業をしている人の特徴について整理しておきたい。第2-1-10図は、前出のリクルートワークス研究所調査における副業の有無と回答者の属性の関係を調べることにより、どのような特徴を持っている人が副業を行う確率が高くなるのかを、男女別にプロビットモデルを用いて分析したものである14。
これによると、転職意向がある人や、実際に転職活動している人は、副業を行う確率が高くなっている。例えば、転職意向あり・活動ありの者は、転職意向がない人と比較して男性で12%、女性で10%副業する確率が高くなる。また、自主的に能力のレベルアップを行っている(自己啓発活動をしている)人についても副業の確率が高くなることから、キャリアのステップアップを図りたい目的で副業を行っている可能性が指摘できる。
フレックス制、テレワーク制が適用され、ある程度仕事のコントロールが自分でしやすい労働者は副業確率が高くなる傾向がある。また、男女共に非正規雇用者であることは副業確率を有意に上昇させる。女性では有意ではないが、男性では週当たりの労働時間が短い人や、年収の少ない人(400万円未満)が副業の確率が高いとの結果になっている。こうした推計結果は、本業の時間が短く、収入が少ない労働者が生活費の足しにしようと副業を行っている可能性が高いことを示唆している15。
副業に対するネガティブな見方の一つに、副業を許可すれば、離職につながるとの考えがある。確かに、上記の推計でも、自己啓発を行っている人や転職意欲の高い人の副業確率が高いという結果になっている。だが、副業を許可している企業の事例をみると、仮に従業員が離職したとしても、業務委託契約を締結する等、離職後も関係性を保持することで、双方の利益になるため、そもそも従業員の離職はリスクではないと回答している企業もある(萩原・戸田(2016)、リクルートワークス(2015))。第2-1-9図でみたように、副業の内容についても、主な仕事と同じという回答が2割程度あることを踏まえれば、副業がきっかけで転職したとしても、同じ業界・業種に留まる可能性が高く、離職後も情報交換でき、また、従業員がレベルアップして同じ企業に戻ってくることも考えられる。
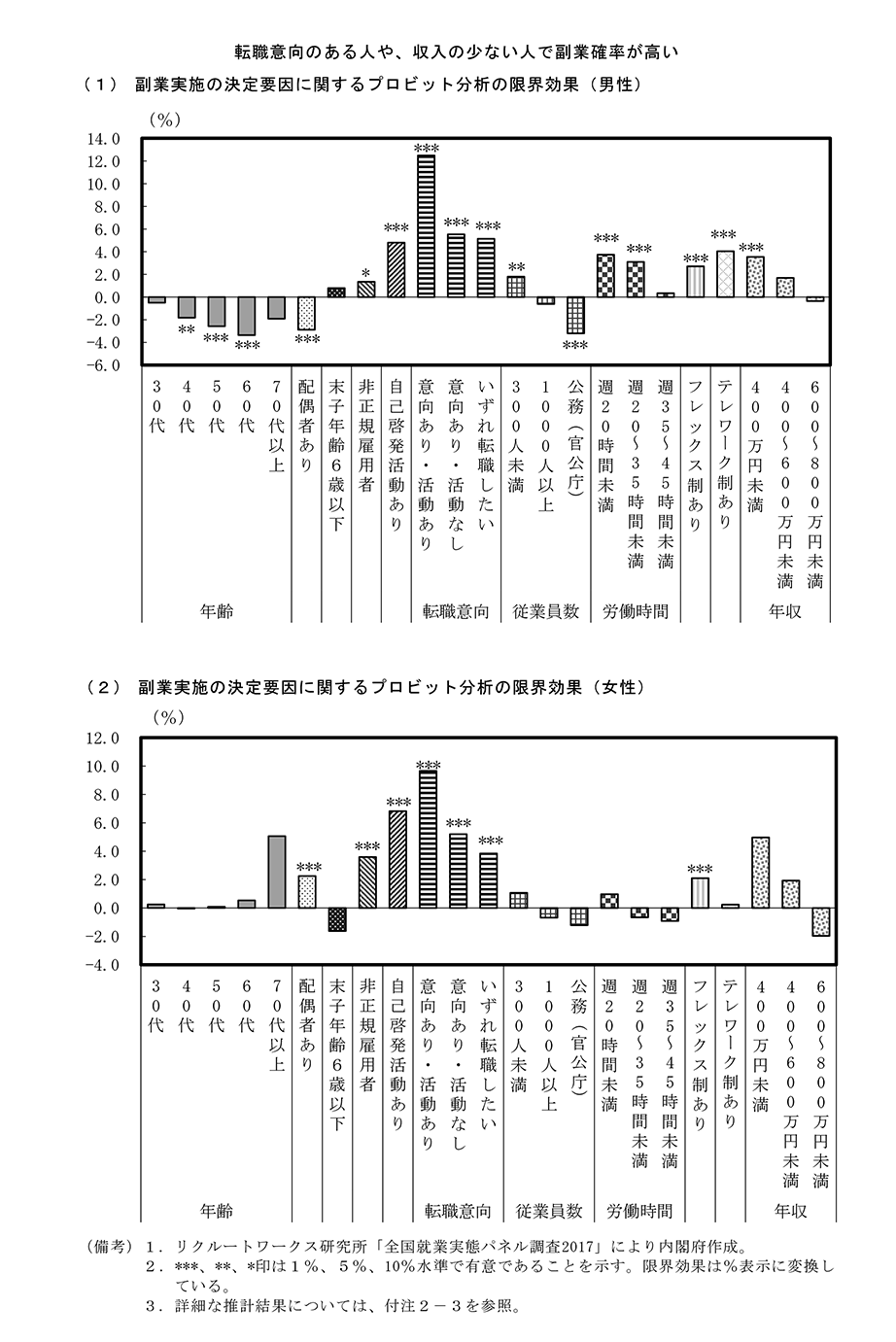
(失敗のコストが高いため起業しない可能性)
本節の最後に、起業の動向とその課題について整理する。第2-1-11図(1)はGEM(Global Entrepreneurship Monitor)が公表する起業活動の水準(総合起業活動指数、TEA16)の推移をみたものであるが、日本は他国より低い水準であるが、2014年以降は緩やかに増加している。2016年にはドイツを超える水準になったものの、OECD諸国でデータが利用可能な29か国中では25位と、依然としてその水準は国際的にみて高いわけではない。
日本の総合起業活動指数と相関の高い要素の一つとして、起業が失敗した時のコストが大きいことが指摘できる。第2-1-11図(2)は、OECD諸国において起業活動の水準(TEA)と失敗脅威指数17の相関関係を、国際比較が利用可能な2014年でみたものであるが、両者は負の相関関係があり、日本の失敗脅威指数は国際的にみても高い水準にあることがわかる。
第2-1-11図(3)では、起業準備者、起業希望者、起業を断念した者に対して、起業を諦めそうになった(諦めた)理由を聞いたものであるが、その理由としては、資金調達の困難さに加え、起業への不安、周囲の反対等が多いことがわかる。転職市場の動向をみた際に、雇用の流動性は限定的であると指摘したが、起業で失敗した際に、再び雇用者として転職市場に参入しようとしても、希望する仕事に就きにくいなど、セカンドチャンスが少ないことが、起業への不安や周囲の反対につながっている可能性がある18。