第2節 様々なリスクへの対応
前節では、今回の震災がいかに被災地の生産、雇用・所得に影響を与えたか、また被災地の企業の被災によりサプライチェーンが寸断することで、いかに我が国の生産全体に大きな影響を与えたかを確認した。今回の震災に限らず、リーマンショックなど大きな経済的なショックが次々と日本経済を襲っている。こうした経済における極端な変動のリスクにどう対応するかは重要な課題である。本節では、様々なリスクと効率性との関係、またリスクに対する備えについて考察する。
1 サプライチェーンの再編成
部品供給などのサプライチェーンを一極集中することや在庫を圧縮することは、コスト面での優位性をもたらし効率性の向上に結び付く。しかし今回のサプライチェーンの寸断は、部品供給を特定の地域や企業に強く依存しすぎることや在庫を極限まで減らすことのもろさを露呈させることとなった。現在、サプライチェーンの再構築が進んでいるが、本項ではサプライチェーン再構築にあたって重要と思われる論点を整理する。
(主要企業におけるサプライチェーン構築の動向)
前節で確認したように、東日本大震災により東北地方や関東地方の工場が被災したため、そこで生産されていた部品を利用して生産を行っていた被災地以外の工場においても生産をストップせざるを得ないというサプライチェーンの寸断が発生し、我が国全体の生産活動に大きな影響を及ぼした。これまで我が国は、自動車産業などにおいて、相対的に費用が安く整備されている交通インフラを活用し、各工程がそれぞれ比較優位のある地域で生産を担うサプライチェーンの網を形成してきた。これにより効率性を高めたり、規模の経済の効果32を享受することができた。また徹底した生産管理により在庫を極限まで圧縮することで、生産の効率性を高めてきた。今般の震災では、この効率性を重視した生産活動の仕組みが、結果として大きなマイナス効果を生み出すこととなった。サプライチェーンの再考については各社で検討が進んでいるが、ここでは、先行研究も参照した上で、主要産業におけるサプライチェーン再構築方針を確認しよう(第2-2-1表)。
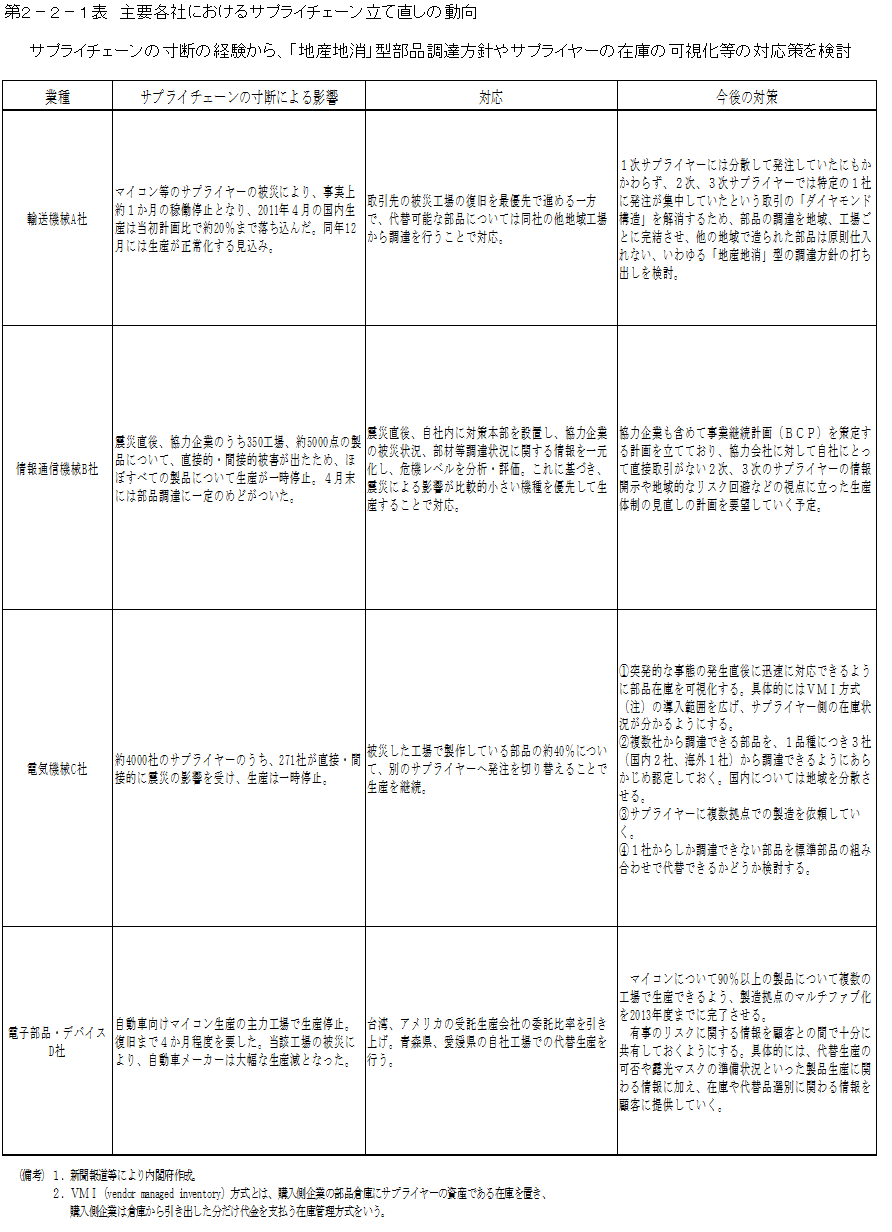
まず、サプライチェーンに関する先行研究であるKleindorferandSaad(2005)をみると、自然災害などによるサプライチェーン寸断リスクへの対応として、リスク要因の特定、リスク評価、リスク軽減が重要と指摘している。リスク評価や軽減の原則として、調達先を多様化・分散化すること、サプライチェーンの頑健性と効率性はトレードオフであること、各工程をモジュール化33することを挙げている。特にそれまでの 20年間(80年代半ばから 2000年代半ば)は、サプライチェーンの頑健性と効率性はトレードオフであることをあまり考慮せずに、効率性のみが追及されすぎたと主張している。こうしたことを踏まえると、サプライチェーンの効率性追求は我が国に限ったことではなく、世界的な潮流であった可能性が高い。
以上を踏まえて、今後の主要産業におけるサプライチェーン再構築方針の論点を考えてみると、おおむね次の2つのポイントに集約される。
第一に、サプライチェーンにおける1次下請けだけではなく、2次、3次の下請け業者も含めて特定業者に偏らずに分散化していることの重要性である。サプライチェーンの構築にあたっては、多くの会社が多様化・分散化の重要性に気づき、その対応策として1次下請け会社の分散は進めていたが、再委託先である2次、3次のサプライヤーが1社もしくは数社に集中していたため、結果的にはリスク分散になっていなかったという反省がある(いわゆるサプライチェーンのダイヤモンド構造)。今後は、多くの会社において、1次の下請けだけでなく、2次、3次の下請けの状況についても適切に把握をし、必要に応じて分散が図られることになると考えられる。
第二に、カスタム生産などの高度部品の代替先確保である。今回のサプライチェーン寸断の影響が甚大になった理由の一つとして、自動車の部品であるマイコンが自動車メーカーの各社ごとにスペックが異なるカスタム生産となっていたため、マイコン製造工場が被災すると他工場での代替生産が難しく、影響が甚大かつ長期化したという経緯がある。先の先行研究でも指摘しているように、工程のモジュール化は災害発生時の影響を軽減するうえで重要であり、当然、企業機密との関係もあるが、可能な範囲で生産のモジュール化を進めるというのも論点となるだろう。
また、これとは別に一部の企業では、部品生産から最終組立までを同じ地域で完結させる、いわゆる生産工程における「地産地消」の実施を検討している。現在は整備された交通網や相対的に安い輸送費を利用して、異なる地域にサプライチェーンの網をめぐらせているが、生産工程の地域間分散はリスク増加につながるとも考えられる。地域をまたがって工程間分業を行った場合、複数地域における自然災害リスクを抱え込むことになる。もちろん、一つの地域で生産工程を完結させることはコスト面などから非効率な場合もあるが、できるだけ部品生産と最終組立工程を近づけるということは考慮すべき論点と考えられる。
(在外法人における日本国内からの部品調達割合は既に減少傾向)
先ほど確認したように、一部の企業では、部品生産と最終組立までの工程を地理的に近づけることで、他地域における災害で必要な部品供給が滞るリスクを避ける方法をとる可能性がある。これは、我が国企業の海外現地法人からみると、これまで日本から高度な部品など仕入れ(日本から見ると輸出)ていたものを、できる限り現地での部品調達に変える、つまりは在外法人の日本国内からの部品調達比率を下げる可能性が生じるということになる。これは、輸出の減少に伴う国内生産の減少を引き起こすおそれがあるが、ここでは在外法人の日本国内からの部品調達割合の状況を経済産業省の「海外事業活動基本調査」を活用して確認してみよう(第2-2-2図)。
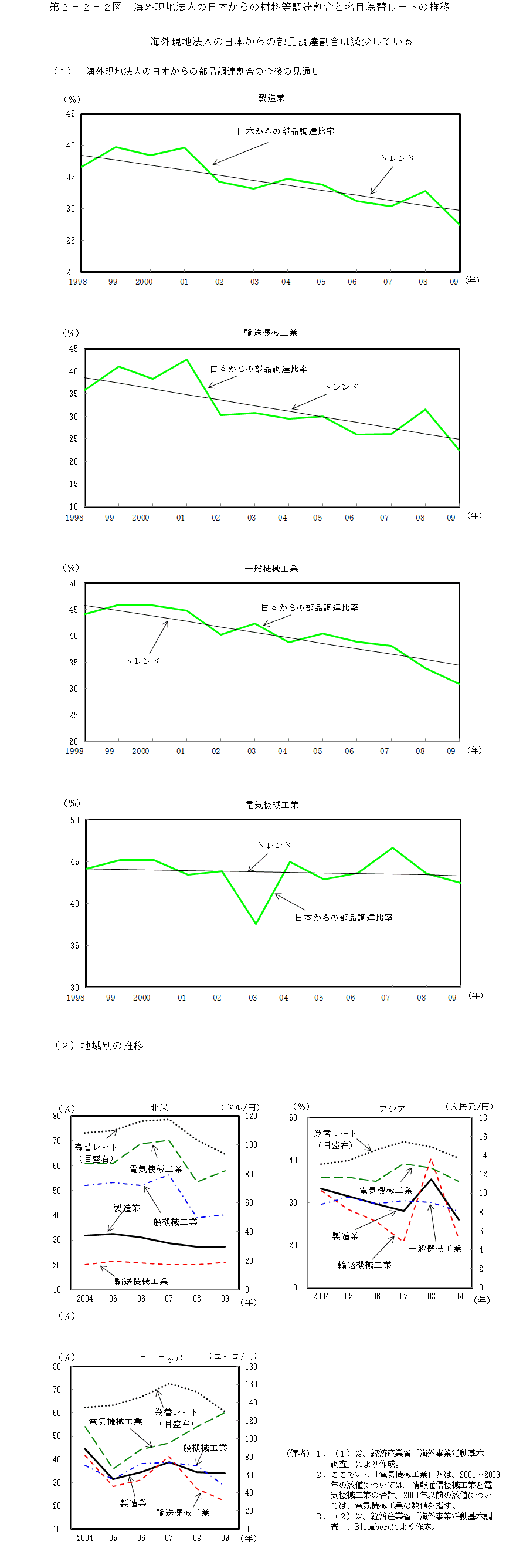
まず業種ごとに日本からの部品調達割合の推移をみると、2000年代初頭には30%台の半ばであった部品調達割合は、その後は電気機械工業以外において大きな減少傾向にあることが分かる。製造業全体でみても 2009年には 98年に比べて 10%ポイント程度落ち込んでおり、とりわけ輸送機械工業においてその減少傾向が著しい。データが存在する98年以降のトレンドを描いて見ると、特に輸送機械工業と一般機械工業で明確な下落トレンドが観察でき、今から10年後の2020年には輸送機械工業で10%程度、一般機械工業で25%程度、製造業全体でも20%程度になると考えられる。
この要因としては、為替要因(円高になると、日本国内から部品調達をするよりも現地企業から部品調達をする方が有利となる)が考えられる。しかし、各地域における部品調達割合と為替レートとの関係を見ると、北米における電気機械工業や一般機械工業などにおいては相関が高いが、それぞれの地域の製造業全体と為替レートについては、少なくとも同時点での相関は確認できず、過去の為替レートのトレンドに影響を受けている可能性はあるものの、それ以外の要因、例えば在外法人の設立期間の長期化による地元企業との関係強化などにより規定されている可能性がある。
産業ごとの特徴をより仔細に見ると、北米やヨーロッパにある在外法人においては、電気機械工業の部品の半分以上を日本国内からの供給に頼っていることが分かる。これは、電気機械工業の材料として、高度な技術を要しカスタム生産が多い電子部品などのウエイトが高いためと考えられる。電気機械工業に関しては、どの地域でも高い水準で推移しており、日本企業の技術優位性が高いことを示唆している。
このように在外法人の日本からの部品調達割合を見ると、電気機械工業においては高い水準を維持しているものの、製造業全体としては減少傾向にあることが分かる。この傾向に加え、今回の東日本大震災を契機として部品供給の現地化がより一層進むと、在外法人の日本からの部品調達割合のさらなる減少を招き、我が国国内の生産や輸出に悪影響を及ぼすことが懸念される。
(原材料在庫率の増加は経常利益にマイナスの影響をもたらす)
先述の通り、生産工程の合理化や輸送手段の効率化などにより余分な原材料在庫を極限まで圧縮し、原材料在庫率(原材料在庫を売上高で除した値)を低くすることは、経常利益にとってプラスになると考えられる。しかし東日本大震災後に原材料在庫が少なかったことにより生産がすぐにストップしてしまった経験を踏まえ、今後、ある程度の在庫の積み増しに各社が動くことが予想される。そうした傾向が広範にみられるようになると経常利益にどのような影響を与えるだろうか。「法人企業統計季報」を活用し、経常利益に原材料貯蔵品在庫34率の変動が与える影響を確認しよう(第2-2-3図)。
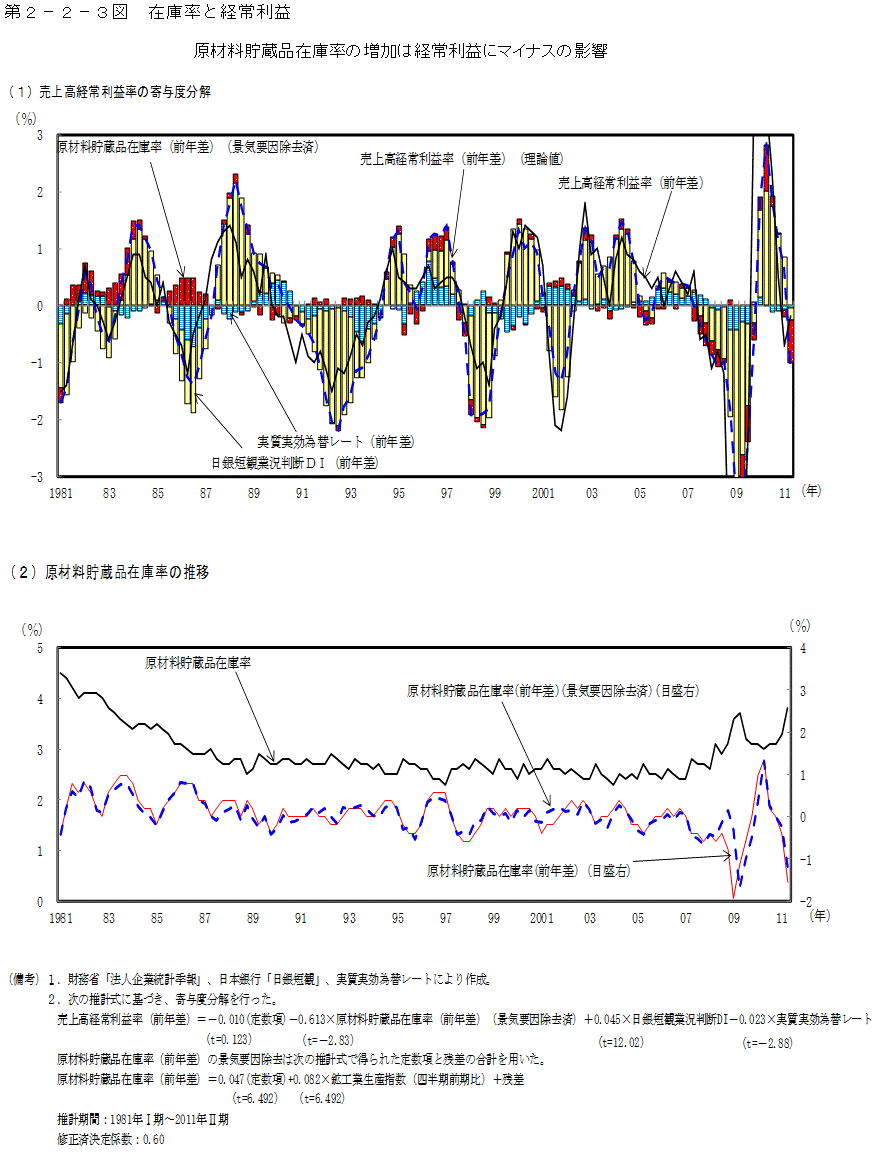
全規模製造業のデータを使い、売上高経常利益率(経常利益を売上高で除したもの)の前年比を、景気要因として日本銀行短観業況判断DI、為替要因として実質実効為替レート、さらに景気要因を除いた原材料貯蔵品在庫率35の前年比で回帰分析をしてみると、原材料貯蔵品在庫率の上昇は経常利益にマイナスの影響を及ぼすことが確認できる。それとともに経常利益の変化を寄与度分解してみると、以下のことが分かる。我が国の企業が生産工程の合理化などに取り組んだおかげで、原材料貯蔵品在庫率は80年代前半には4%程度であったものが、90年代以降はおおむね2%台の半ばに低下している。そのため、原材料貯蔵品在庫率の変動は80年代から90年代初頭にかけては経常利益の変動にプラスに寄与することが多かった。しかし、その寄与度が景気要因や為替要因に比べると限定的であることを考慮すると、仮に80年代の原材料貯蔵品在庫率の水準に戻したとしても、その経常利益への影響は限定的であると考えられる。ただし、景気が悪化し在庫率要因もマイナスに寄与することになると、結果として企業に大きな影響が及ぶため、原材料貯蔵品在庫の積み増しを行う際は、効率性ひいては企業業績への影響を十分に注視しながら行う必要があるだろう。
今後、サプライチェーンの見直しが各企業において本格的に進む可能性がある。今回の大震災が震災の直接的な影響が小さかった地域や海外にまで大きな影響を及ぼしたことで、部品供給を他地域や他社に大きく依存することのリスクが再認識された。ただし、先述のとおり、我が国においては、交通インフラが整い輸送費が相対的に低いために、各部品を1社が1か所で量産し、日本全国もしくは海外に輸送するというサプライチェーン構造によって比較優位や規模の経済の効果を徹底的に高め、産業競争力を高めてきたという歴史もある。サプライチェーンの再構築にあたっては、震災前のサプライチェーン構築の背景を十分に理解し、さらに今回の分析で示した論点も考慮した上で、適切に頑健性と効率性のバランスをとることが望まれる。
2 経済における極端な変動のリスク
自然災害に限らず、2008年に発生したリーマンショックも、世界中の企業や投資家にとって、これまで経験したことのない大きな出来事であったと言える。経済的なショックに適切に対応するため、金融市場や企業では将来起こり得るリスクを想定し、そのための準備を整えていると考えられている。しかし、実際どの程度のリスクを織り込み、その想定は十分かつ正確なのであろうか。ここでは金融市場や企業の将来見通しについて確認する。
(経済指標の変動分布は正規分布とは異なる)
まず我が国における主要経済指標(GDP(実質)、株価(日経平均)、為替(円ドルレート)、債券先物(10年物))の変動率の推移や、その確率密度分布を確認してみよう。各指標ともに、40年から 60年程度と長期のデータを使用しており、正規分布に近い形で分布が形成されると予想されるが実際はどうであろうか(第2-2-4図)。
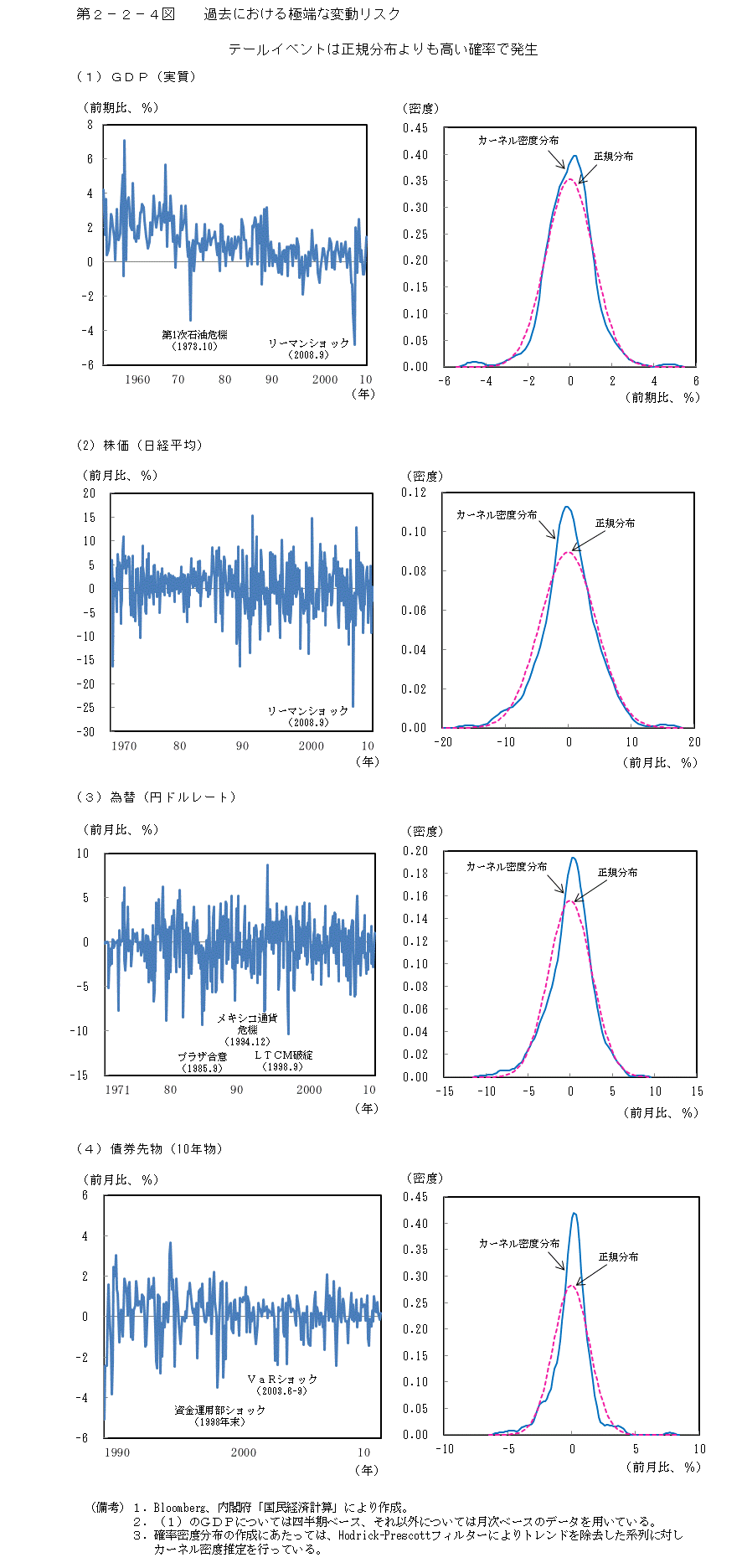
まず、各指標の変動率の推移をみると、いずれの指標においても非常に大きなショックが複数回起こっていることが分かる。例えば、GDP成長率(四半期別、前期比)で見ると、プラスの方では高度経済成長時代の5%強の成長が3回発生しており、逆にマイナスの方では第一次石油ショックやリーマンショック時に3%から4%程度の大きなマイナス成長を経験している。また、リーマンショック時の株価やプラザ合意時の為替、さらには2003年のVaR(Value at Risk)ショック36時の債券先物価格などにおいても、非常に大きな変動が発生していることが分かる。
こういった変動は何らかのトレンドを持っていると考えられるため、そういったトレンドを除去したうえでカーネル密度推定37を行い確率密度分布をプロットすると、いずれの指標も、中心では正規分布より確率密度が高いが、その周りの中央部では正規分布より確率密度は低く、逆に、正規分布ではほとんど起きることが想定されない両端部分において正規分布を超える確率密度となっていることが分かる。このように、発生確率は低いものの、起こると非常に大きな影響をもたらす事象をテール・イベントと呼び、そのテール・イベントから発生するリスクをテール・リスク38と呼ぶが、このときに仮に正規分布を活用してリスクを考慮・推計したとすると、リスクを過小評価するおそれがあることがこの結果からも分かる。例えば、多くの金融機関でリスク管理手法として採用されているVaR39であるが、その前提として正規分布を仮定しているとしたらリスクを過小評価してしまうことになるし、そもそも信頼区間を超えて発生するテール・リスクの規模を評価することはできない。
また、主要経済指標の変動率の推移をみると、変動が大きい時期もあれば、小さい時期もあり、常に一定の変動率となっていないことが分かる。例えば株価をみると1980年付近は非常に変動幅が小さかったものの、1990年以降は変動幅が拡大している。このことは、リスク管理を行う上で、どの期間を参照するかによって、見込むリスク量が変わってしまう可能性を示唆している。他方、稀な自然災害の確率を資産価格決定モデルに織り込むことにより、通常のモデルでは説明できない資産価格の特異な動きを説明しようとする研究も行われている40。
このようにこれまでの主要な経済指標の分布を見ると、テール・イベントは通常の手法で想定される頻度に比べて発生頻度が高く、テール・イベントへの備えが非常に重要であることが分かる。
(大きな経済ショックが発生すると市場の予想確率分布は変化)
我が国の経済指標は、正規分布で予想される以上にテール・イベントが発生しやすいことを確認したが、実際に市場において極端な変動リスクはどの程度評価されており、どういった予想がなされているのであろうか。ここでは、金融市場で取引されているデリバティブの一種であるオプションの価格を用いて、市場参加者が予想している株価・債券先物といった金融資産の予想確率分布を推計する。また、過去のショック発生前後で予想確率分布の形状がどのように変化したのかを確認してみよう(第2-2-5図)。
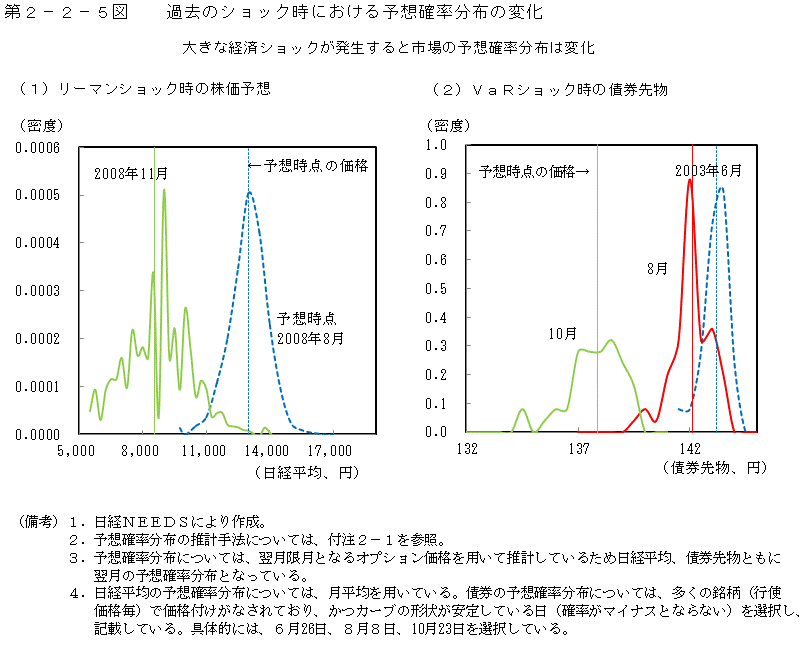
まず、2008年9月に発生したリーマンショック前後における株価の予想確率分布を比較すると、ショックの発生前(2008年8月)と発生後(2008年11月)では、株価の急落を受けて分布の中心が大きく左側にシフトしたことが分かる。また、分布の広がりが拡大(標準偏差が上昇)しており、つまり市場参加者が価格変動のリスクをより多く見込むようになり、テール・リスクを意識するようになったと考えられる。
次に、2003年6月から9月にかけて発生した金利急上昇局面(VaRショック)の前後における債券先物価格の予想確率分布を比較してみよう。金利が本格的に上昇(債券価格が下落)する前の6月の分布と、金利上昇中の8月の分布を比較すると、債券先物価格の下落に伴い、分布の中心が左方シフトするとともに、分布の形状が左に歪んでおり、債券価格の急落といった下方リスクがより強く意識されるようになったといえよう。また、8月の分布を、金利上昇が一服した10月の分布と比較すると、分布の広がりは大きく変わっていないものの、尖り度合いが減少しており、相場の水準に対する確信度が低下したと考えられる。
以上を踏まえると、市場予想の分布は常に一定の形状をとるわけではなく、経済変動ショックの前後で大きく変化するものであり、非常に不安定なものであるといえよう。
(企業の短期予測は足下の動きに影響されやすい)
前項では金融市場の参加者がどういった形で価格変動リスクを見込んでいるのかについて分析したが、経済活動の主たるプレイヤーである企業は経済の予測に際して適切にリスクを織り込んでいるだろうか。ここでは、内閣府の「企業行動に関するアンケート調査」における予想実質経済成長率を活用して、経済危機(ここでは2008年9月に発生したリーマンショック)後にどのように予想を変化させているかを確認してみよう(第2-2-6図)。
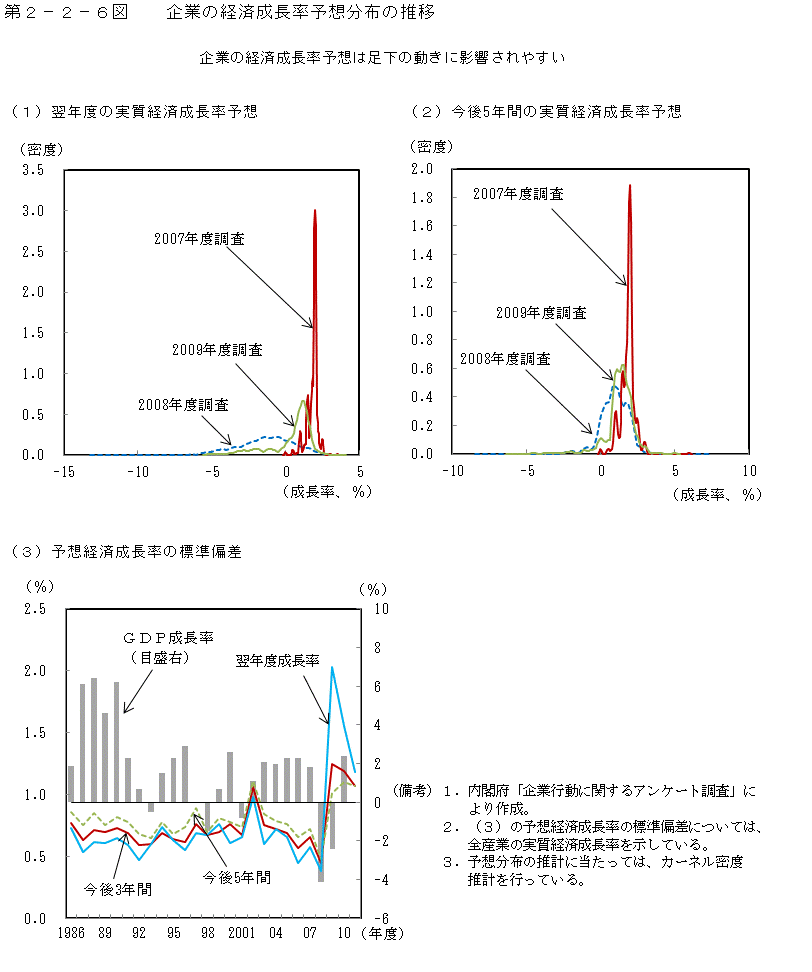
まず翌年度の経済成長率の予想であるが、リーマンショック発生前の2007年度調査(調査時期は2008年1月)においては、多くの企業が2%程度を予想し、プラス1~2%の範囲にほぼ全ての企業の予測が集中し、分散は極めて低いことが分かる。リーマンショック後の2008年度調査(調査時期は 2009年2月)の動きを見ると、予想成長率の山がマイナス領域にシフトするだけでなく、予想の分布がマイナス方向に急激に広がったことが分かる。リーマンショックのような負の出来事があったことから期待成長率がマイナス方向にシフトすることは容易に理解できるが、その分布が大幅に広がるということは、いかに企業が平時においてテール・イベントを予想していないかを示唆している。さらに翌年の2009年度調査(調査時期は2010年1月)の分布を見ると、成長率の落ち込みが和らいだこともあり山がプラス方向にシフトしているが、それに加えてその分布が急激に小さくなっている。以上のことから、多くの企業においては、大きなショック後に、テール・イベントを考慮した上で経済成長の見通しをたてるためにその分布が広がるが、経済変動が落ち着いてくるとテール・イベントへの関心が弱くなるため、ショックを織り込む企業が少なくなると考えられる。
一方、今後5年間の経済成長率の予想においては、先ほどの翌年度の予想の動きと似ているが、リーマンショック後における分布のばらつきは1年後の経済成長率の予想に比べて小さいことが分かる。仮に、企業がテール・イベントの発生リスクを毎年度、独立的に考えるのであれば1年後の経済成長率の予想でも、今後5年間の経済成長率の予想でも変わらないはずであるが、今後5年間の経済成長率予想の分散の方が小さいということは、多くの企業が、テール・イベントは最初の1年間に起こる確率は高いが、その後の4年間ではもう起きないと想定していると考えられる。以上のことを確認するため、企業の翌年度、今後3年間、今後5年間の予想成長率の標準偏差の動向を時系列でみると、大きな経済の落ち込みがあった翌年ほど、標準偏差が拡大しており、足下の状況が先行きの予想に大きく影響していることが分かる。また、リーマンショック前までは、予想期間が長い方がリスクも発生しやすいと考えるためか標準偏差が大きくなる傾向が見られたが、リーマンショック後は、長期の予想期間の方が標準偏差が小さくなっており、先行きの経済成長率の変動は収束していくと企業が予想していることが分かる。
この結果を踏まえると、企業においては、普段からリスクを適切に予想しながら経営計画を立てているとは言い難く、足下の状況に影響を受けやすいといえよう。経済活動のグローバル化が進み、地球上のいずれかの地域で顕在化したショックが他地域に波及しやすくなっていることを考慮すれば、大きなショックがない平時から、適切なリスク管理が望まれるといえよう。
3 リスクへの対応
私たちは、ここ数年の間に東日本大震災の発生やリーマンショックなど、発生する可能性が極めて低いものの、いったん起きればその影響が極めて甚大なテール・イベントを経験してきた。その中で、今回の大震災を契機として、前述したサプライチェーンの寸断に加え、交通機関の混乱などによってその脆弱性が顕在化した東京一極集中のリスクなど、リスクに対応するための様々な論点が浮かび上がってきた。リーマンショックのような経済的なリスクや震災のような自然災害のリスクが顕在化することは今後も想定されるため、リスクに強い社会、制度の構築は急務である。ここでは、震災後にでてきたリスクへの備えに関する論点を検討するとともに、リスクへの対応として有力な手段である保険について確認する。
(非常時に備え、バックアップ体制の構築は官民問わず不可欠)
今回の東日本大震災は、東日本を中心に大きな損害をもたらし、また我々に多くの教訓をもたらした。時間の経過とともに、震災で得た教訓について風化するおそれもあるが、自然災害が多く、バブル経済崩壊やリーマンショックなど経済的な大変動も決して少なくない我が国においては、リスクへの対応をより強固にするために、今回でてきた問題点を整理し、共有することは非常に重要である。ここでは、今回の東日本大震災を機にでてきた論点を確認しよう(第2-2-7表)。
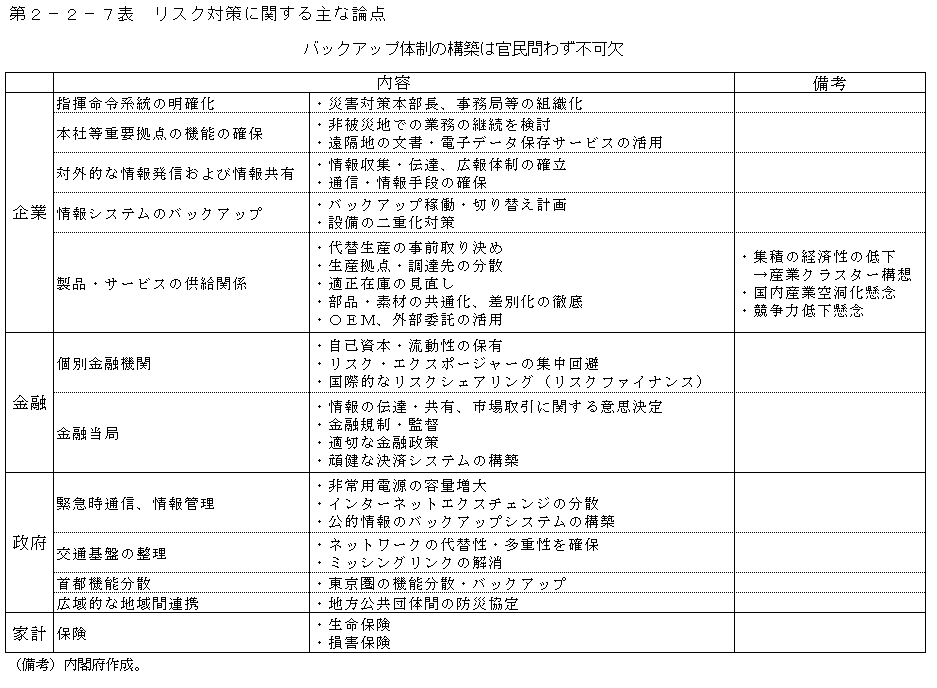
まず企業部門においては、これまで確認してきたように効率性を追求したサプライチェーンの脆弱性が確認された。これまでは効率性と頑健性のトレードオフの認識が薄く、効率性のみに重点が置かれてきたという指摘もある。今後は、効率性を大きく損なわない範囲でのサプライチェーンの再構築41が不可欠である。また、事業継続計画(BCP)の策定の重要性があげられる。内閣府の「企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」(2010)によれば、2009年度におけるBCPの策定状況(策定済みと策定中の合計)は、大企業において6割程度、中堅企業では3割程度と事業継続計画への取組は十分とは言い難い。大規模災害後に、必要な業務に対して優先度をつけて効率的に対応するためにもBCPの策定は急務である。さらに、情報システムが事業を支える重要なインフラになっていることにかんがみ、重要な業務を支える情報を中心にバックアップシステムを整備することや、自家発電装置、電源や回線など各種設備の二重化対策を実施することで、自然災害などにより情報システムが被災した場合や電力の供給がストップした際に備えることが求められる。
次に、金融は、電力や水道などと並ぶライフラインの一つであり、経済活動を支える重要なインフラであることから、非常時における金融市場や金融システムの安定確保が不可欠である。リスク管理については、先ほど確認した、例えばVaR手法にも限界がある42ことを考慮すると、ショックが発生した際の耐久力、つまりそれぞれの金融機関が十分な自己資本や流動性を保有しておくことが望まれる。またリスクの一部集中を避ける、つまりリスク・エクスポージャー43の集中を回避することが重要である。サブプライム・ローン問題では、一見すると証券化により分散は図られていたが、アメリカの住宅価格に依存するという形でリスクが集中していたために問題が深刻化した。このような事態を防ぐためにリスク・エクスポージャーの分散が必要である。また、国際決済銀行(BIS) (2010)は、経済の負のショックなどへの金融機関の頑強性を強化することや、金融リスクの蓄積を主体的に回避し、金融破たんのリスクを減らすためには、マクロプルーデンス44政策が重要であることを指摘している。
最後に、震災当日の交通機関の混乱などを踏まえ、東京一極集中の危険性が指摘されている。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を東京圏とした場合、これら1都3県という限られた土地に日本の人口や名目GDPの3割程度、また大企業本社・本店数45の6割強が集中しており、極めて大きな経済的ウエイトを占めていることが分かる。首都直下地震の可能性も指摘されているなか、このような過度の集積は、必要以上の混乱を招く危険性があるだけでなく、これだけの経済規模の地域が一時的にせよその活動をストップすることで、経済、行政など日本全体のあらゆる活動がストップしてしまう可能性を秘めており、例えば関西圏や、太平洋側にある東京圏とは逆の日本海側などに、有事の際に経済や行政機能の一部を分担できる態勢を構築しておくことも、リスクに備えるという意味では有効であると考えられる。ただし、組織の分散は非効率を招きやすいので、効率性とリスク分散のバランスをとった上で、適切な対応を考える必要がある。
(地震保険の加入は所得要因よりも地理的なリスクに依存)
先ほど確認したように企業であればBCPの策定、情報システムのバックアップの確保などが対応策として考えられ、また、企業、家計ともに非常時の食料や燃料を備蓄しておくという手段も自然災害などのリスクに備えるという意味では有効である。これらの対策以外にも、通常時の所得を災害時に効果的に移転するという意味では、大規模リスクに対して保険の果たす役割が非常に大きいと考えられる。ここでは、東日本大震災でも注目を集めた地震保険についてその現状を確認しよう(第2-2-8図)。
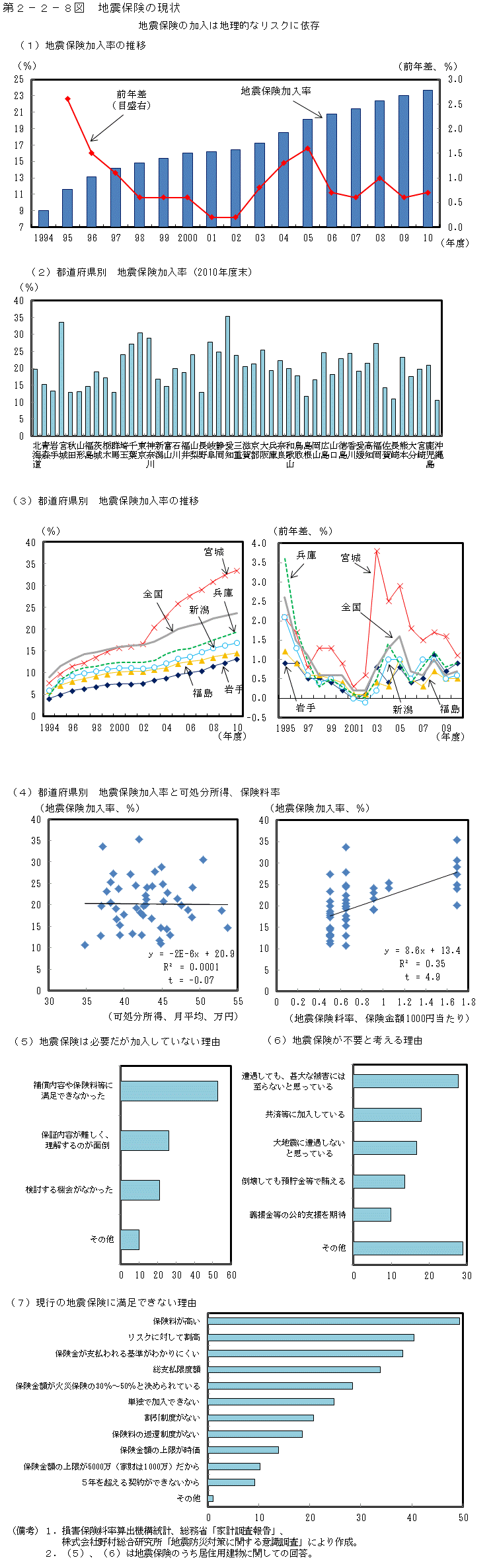
まず、我が国における地震保険加入率46の動向を見ると、年々増加している。特に1995年や2005年前後において増加幅が大きいが、95年には阪神・淡路大震災が、2003年には宮城県中部地震が、そして2005年には宮城県沖地震や新潟中越地震が起きたため地震保険加入者が急増したと考えられる。2010年度末の都道府県別の地震保険加入率の水準をみると、2003年、2005年に大きな地震が発生した宮城県や、首都直下地震や東海大地震の可能性が指摘されている首都圏や愛知県で加入率が高くなっていることが分かる。都道府県別の地震保険加入率の年次推移をみると、例えば兵庫県では95年に増加率が大幅に上昇し、宮城県でも2003年以降に上昇率が大きくなっており、地震のあった後に地震に関係ある地域で急激に加入率が高まり、その後時間とともに加入率の上昇率は鈍化している47。加入行動は、地震という出来事に左右され、また、その効果は時間とともに薄れていくといえよう。
次に地震保険の加入要因について考えてみよう。Kunreuther (2006)によれば、人々が地震保険に入らない要因として、①大規模災害の発生確率を過小評価している、②災害の影響を考慮する際に短期間(1、2年)しか考慮していない、③家計の予算的に厳しい、④大規模災害後は公的機関が助けてくれるので自ら地震保険に加入する必要がないと考えがちである、といったことが指摘されている48が、我が国ではどうであろうか。まず県別のデータを用いて所得要因をあらわす可処分所得と地震保険加入率の関係を見ると、両者には相関が確認できず、所得が多い県ほど地震保険加入率が高いという関係は見出せなかった49。一方、地震発生のリスクを示す地震保険料率と地震保険加入率の関係を県別でみると、両者には正の相関、つまり地震発生確率が高い県ほど、地震保険加入率が高まるという関係が確認された。
地震保険に関するアンケート調査50を活用し、地震保険が必要だと思うが加入していない理由や地震保険を不要だと思う理由、さらには現行の地震保険に満足できない理由をみると、「検討したが、補償内容や保険料等に満足できなかったから」や「保険料が高い」、「リスクに対して割高」という回答が上位にきており、Kunreutherが指摘したように、人々が大規模災害の発生確率を過小評価していたり、短期間でしか災害の影響を考慮していない可能性51がある。また、不要の理由として、「義援金等の公的な支援を期待しているから」も1割近くの回答があり、震災が起きても公的部門からの支援があるので地震保険に入らないという要因が我が国でも存在していることを示している。
地震保険は災害前後の所得移転を適切に実現するという効果を持つため、大震災のようなリスクへの備えとして有効活用が望まれる。地震保険をより一層活用するためには、人々が考えている地震の発生リスクが過小なのか、それとも保険料率が過大(保険側が地震発生リスクを過大に評価している)なのかを今後、さらに詳細に分析する必要があるといえよう。また、これまで見てきたように地震保険の加入行動をみると、地震が発生したかどうかに強く影響されていたり、大規模災害発生の確率を過小評価している可能性があるなど、人々のリスクの認知や対応の仕方の特性を考慮した上で対応することが望まれる。

