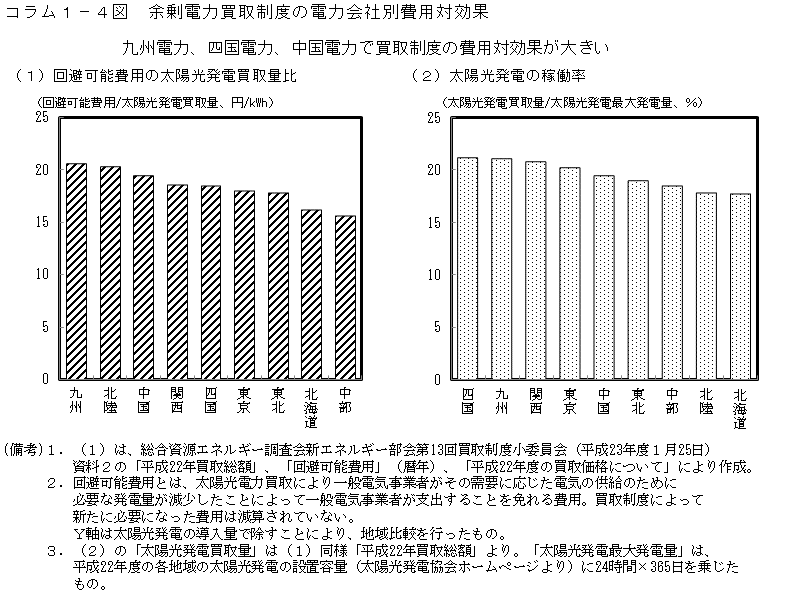第3節 電力供給不足と日本経済
2011年の東日本大震災によって生じた東京電力福島第一原子力発電所の損壊と放射性物質拡散事故は、安全性に対する社会的な懸念の高まりを惹起し、全国にある原子力発電所の稼働に影響を与えることとなった。現在、こうした状況を受けて、原子力発電を含む電力供給の在り方が政府において検討されている21。一般的に、望ましい電源の組合せや供給体制の姿は発送電技術と需要の変化により変わるが、ここでは、こうした議論の前提となる電力と経済活動全般の課題や現状について概観し、最後に、電力供給が我が国の経済活動に与える影響を検討する。
1 電力と経済活動
(経済成長とともに増加する電力需要)
長期的な電力と経済活動の関係について概観すると、70年度から2009年度までの39年間に実質GDPは約2.8倍になったが、電力需要量は約3.1倍になっており、電力需要の所得弾性値は1を超えている(第1-3-1図(1))。また、同期間の部門別変化をみると、家庭部門(世帯用)の需要量は約5.5倍に、業務部門(事務所や小売店舗等)の需要量は約5.2倍となる一方、産業部門(工場等)は約1.9倍に止まっている。この結果、家庭部門のシェアは 13%ポイント程度上昇して 28.5%のシェアを、業務部門も 13%ポイント程度上昇して33.0%のシェアを占めることになった。他方、産業部門は、63.8%から38.5%へと25%ポイント強のシェア減少となった(第1-3-1図(2))。
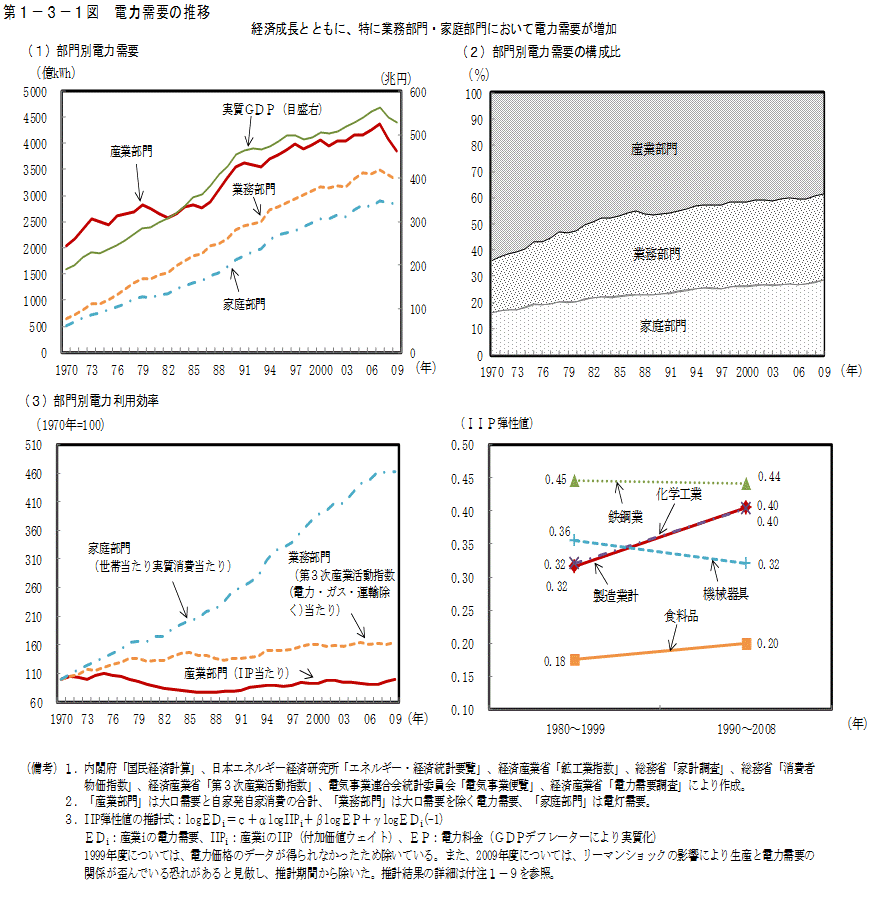
(部門により異なる利用効率)
家庭部門や業務部門が伸びる一方で産業部門の伸びが相対的に抑制されていることから、部門間で電力利用効率に大きな違いがあることが分かる。家庭部門やサービス業を含む業務部門の伸びが高い点には、世帯所得の上昇に伴う需要シフトや電力利用度の高いサービス財への支出と供給の増加という要因がある。ただし、2008年度以降の動きをみると、何れの部門においても、単位当たり電力需要量が減少している。これは、2008年のリーマンショックとそれによる景気後退を原因とする電力需要の落ち込みが大きかったことを示唆している。
各部門の電力利用効率について、家庭部門は実質消費当たり、業務部門は第3次産業活動指数当たり、そして産業部門は鉱工業生産指数当たりという単位電力使用量を定義した上で算出した。この結果からは、第一に、家庭部門においては、家電製品の普及とともに世帯当たり電力需要が増加したが、普及度が既に高くなった90年代中頃からは伸びが鈍化したことがみてとれる22。2008年度以降は景気要因もあるため減少しているが、近年の省エネ機器の普及なども、一定の効果を果たしていると考えられる23。第二に、業務部門では、70年以降、空調機器の普及やOA化とともに電力需要が上昇している24。第三に、産業部門では、70年代初頭に生産当たりの電力需要が増加したものの、73年の第一次石油危機を機に減少へと転じ、それ以来、70年を下回るかそれと同水準の単位当たり電力需要量で推移した。産業部門は電力利用の効率改善を伴いつつ、生産が拡大したことがうかがえるが、90年代に入ると若干の増加基調をみせている(第1-3-1図(3))。
(産業部門内の弾性値にもばらつき)
産業部門については、部門計の電力需要の伸びは生産の伸びに対して低いが、業種別の動きをみるために電力需要の生産弾性値を計測した。推計期間は 80年度~99年度(I期)と90年度~2008年度(II期)に分けたが、結果から以下の点を読み取ることができる(第1-3-1図(4))。まず、製造業全体の生産弾性値は、I期が 0.32、II期は 0.40と若干上昇している。なお、同期間の価格弾性値は▲0.26から▲0.24へとわずかに低下している。第二に、機械器具製造業の弾性値は、I期が 0.36、II期は 0.32と低下気味である。第三に、化学工業の弾性値は、I期が 0.32、II期は 0.40と若干上昇している。最後に、食料品製造業の弾性値は、I期が 0.18、II期は 0.20とわずかに上昇し、また弾性値は他の産業に比べて小さい。これは、生産の変化が電力需要の変化につながりにくい、すなわち、生産数量の多寡にかかわらず、一定の電力を必要とする事業特性を反映したものと考えられる。
(近年、電気料金はおおむね安定的な動き)
電気料金(総合単価(販売額/販売数量))の推移についてみると、特別高圧電力(産業向け)及び電灯(家庭等向け)単価は、共に73年の第一次石油危機と79年の第二次石油危機の際に大幅に上昇したものの、90年代以降は緩やかな下落傾向にある(第1-3-2図(1))。特に、2004年以降の電気料金は、資源価格の高騰にも関わらず下落傾向で推移している。この背景には、1)電力発電に占める(相対的に発電コストの高い)火力発電の割合の低下(75年の75%から2005年には57%)、2)(火力発電の中では相対的に発電コストの低い)石炭火力発電の割合の増加(75年の 4.0%から 2005年には 18.2%)25、3)2000年以降の大口電力の小売自由化による競争圧力の高まり26、等があるとみられる(第1-3-2図(2))。
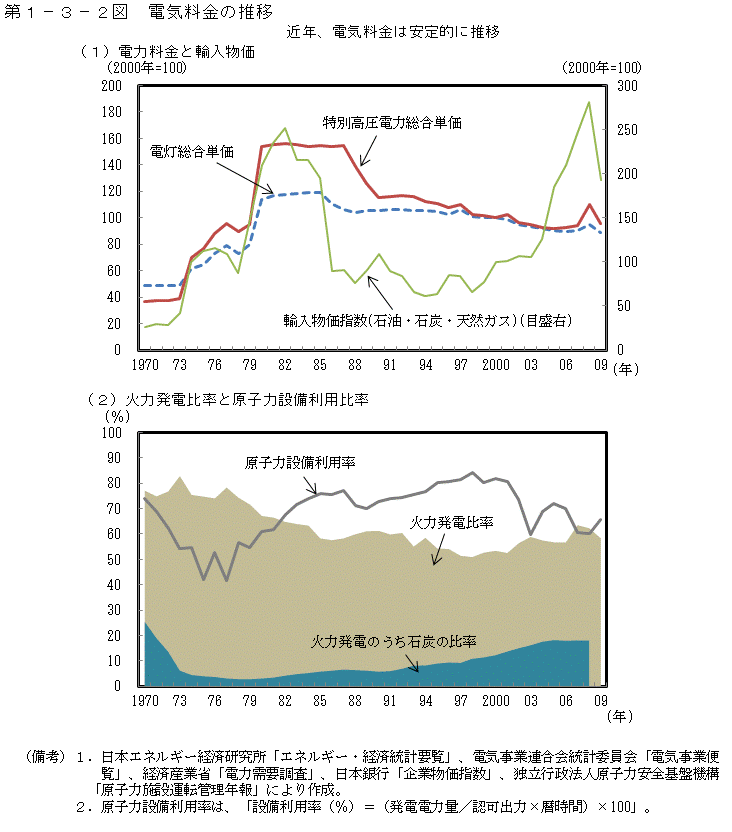
特別高圧電力と電灯の料金比較では、前者は既に小売段階まで自由化されている一方、後者は引き続き規制料金であるが、両者の動きには2000年の自由化以降も大差がみられない。
この点については、自由化部門の価格低下圧力が規制部門の料金引き下げにも一定の効果をもたらしているとの指摘もある27。
(震災による電力供給制約の発生)
東日本大震災の発生により、電力事業が、電気事業法の求める供給義務を果たせないという未曾有の事態に陥ったことは記憶に新しく、いまだ問題解決には至っていない。以下では、震災後に採られた電力の需給対策を振り返った後に、節電の動きについて確認する。
2011年3月11日の震災発生を受け、東京電力は3月14日に「計画停電」の実施を発表した。「計画停電」とは、管区内の一定地域に対する電力供給を停止し、総供給に合わせて需要の調整を行うものであるが、需要家は、節電も併せて求められた。「計画停電」は4月8日に解除されたが、夏季の需要拡大局面に向け、政府の電力需給対策本部が取りまとめた「夏季の電力需給対策」に則り、東京電力及び東北電力管区内の全需要家に対して一律15%の節電目標が設定された。また、大口需要家(契約電力500kW以上の事業者)に対しては、電気事業法第 27条に基づく使用制限が実施された。この措置は7月1日から9月9日まで続いた(第1-3-3表)。
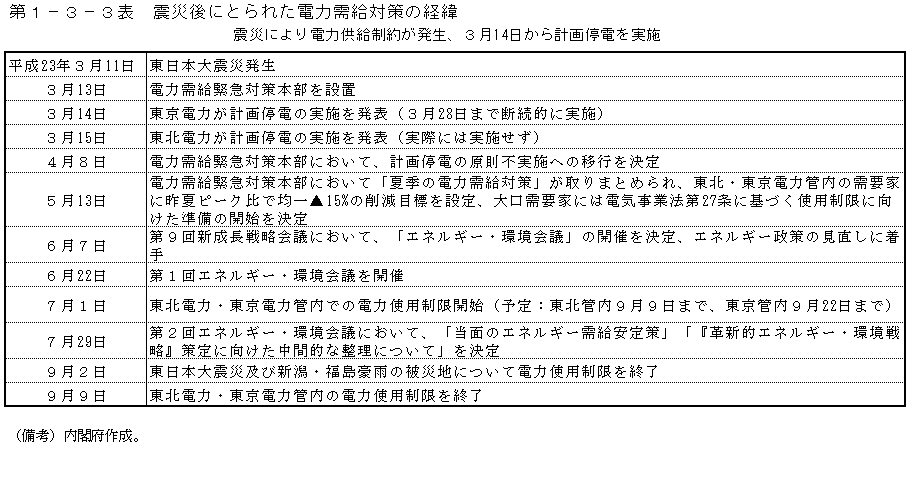
(大幅に減少した電力需要)
こうした需要制限による供給制約への対処により、電力需要は大幅に減少した。①計画停電原則実施期間(3月 14日~4月7日)、②計画停電原則不実施期間(4月8日~6月 30日)、③電力使用制限期間(7月1日~9月9日)のいずれの期間においても、東京電力及び東北電力管内において、一日の最大電力使用量は、前年同期を常に大きく下回った。
東京電力管内を例に電力需要の動きを詳しくみると、計画停電期間(3月)は月内最大使用量が▲23%と大幅に抑制され、計画停電の原則不実施期間(5、6月)は需要抑制がやや緩んで▲11~▲16%となった。夏季の電力使用制限が実施された期間(7、8月)は再び減少幅が▲16~▲23%と拡大し、最終的に制限目標の▲15%は達成された。上記のように一日の最大使用量は前年を大きく下回ったが、最少使用量は前年とほぼ同水準であったことから、電力需要が全体的に下方シフトしたのではなく、需要のピークが抑えられて全体の需要が平準化されたことが分かる(第1-3-4図(1))28。
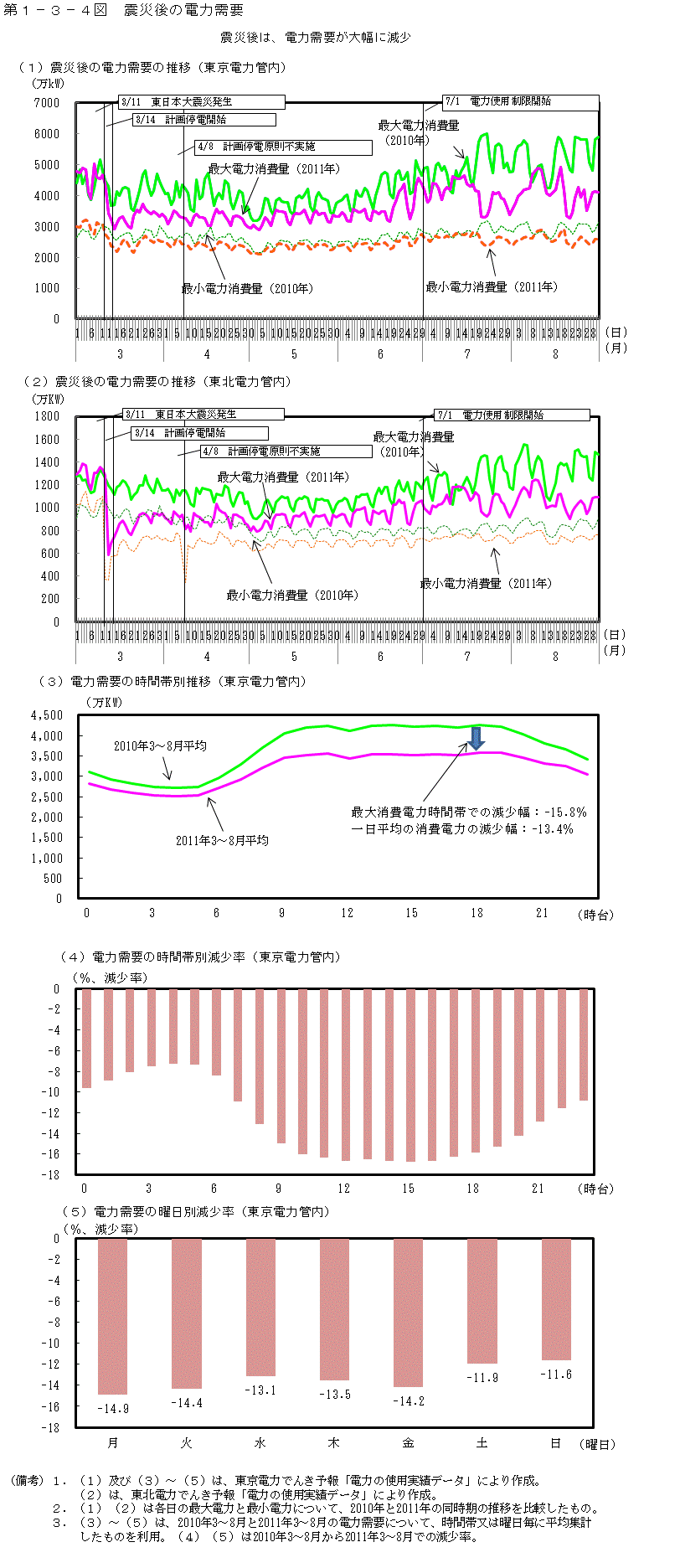
(電力需要の時間シフト)
ピークが抑えられて平準化という点を詳しくみるため、東京電力管内の平均的な一日の時間別の推移(3~8月平均)を描くと、少し異なった傾向がみられる。時間帯別に期間中の平均的な需要量をみると、ピーク時間帯の減少率は約▲16%、一日平均の削減率は約▲13%となった。時間帯別削減率をみると、削減は専ら9時から19時に集中している。ただし、ピークを削るという意味では平準化しているが、他の時間帯への代替はあまり働いていない。実際、現行の生活習慣を前提にした経済活動を想えば、深夜早朝に電力需要を生じる生産活動を行うことにも限度がある。また、曜日間の代替についてみると、例えば自動車産業による土日操業(木金休業)の実施等もあり、平日の削減率が大きく休日である土日の削減率は若干小さくなっていることが分かる。曜日間の代替は若干行われたものの、時間帯の代替はあまりなかったようにみられる(第1-3-4図(3)~(5))。
(節電の維持・拡大は可能か)
今回は政府の制限目標が一応達成されたが、東京電力管内の場合、節電の主体別動向をみると、削減率が最も大きかったのは、法令による制限の課せられた大口需要家の▲29%、次いで小口需要家の▲19%となっており、一般家庭は▲6%に止まった29。
大口需要家の貢献は、勤務時間のシフト、輪番休業など休日・休暇の活用、自家発電の活用など、事業者の努力により実現したが、これは、空調や照明を制限したことによる労働環境の悪化や蓄電池購入や自家発電の利用等による追加的費用の増大等、企業と雇用者の経済活動や日常生活に追加負担を伴うものであった。アンケート調査30によると、「自家発電、蓄電池の導入・活用」については32社が効果ありとしながらも、今後も実施可能としたのは6社に止まっている。また、「休日・休暇の活用」については、27社が効果ありとしたものの、今後も実施可能とした企業は0社であった。こうした回答の理由として、前者については「燃料費の増大」、後者については「従業員の家庭生活への影響」といった理由が挙げられている。したがって、こうした点への追加的な配慮なしに量的な抑制・削減を継続することは、国内での生産活動や国民生活にとって大きな負担となる。
我が国の産業部門は製品の高度化を図りつつ、生産当たりの電力需要量を抑制しており、電力利用効率は高い。商工業部門のGDP当たり電力需要量を主要先進国間で比較しても、為替の影響を勘案する必要もあるが、我が国は一貫して低水準にある(第1-3-5図(1))。他方、家庭部門については、ここ数年は減少の動きがみられるものの、世帯当たり電力需要量は所得水準の上昇とともに増大しており、また、人口当たりの家庭部門電力需要量を主要先進国間で比較しても、世帯数の増加という要因に留意は必要であるが、我が国は相対的に伸び率が高い(第1-3-5図(2))。今後、需要の抑制・削減を行うとすれば、家庭部門が対象となり得るが、多数かつ多様な一般家庭の電力需要を法令で規制することは、費用対効果の点からも有効性の点からも適当とは思われない。
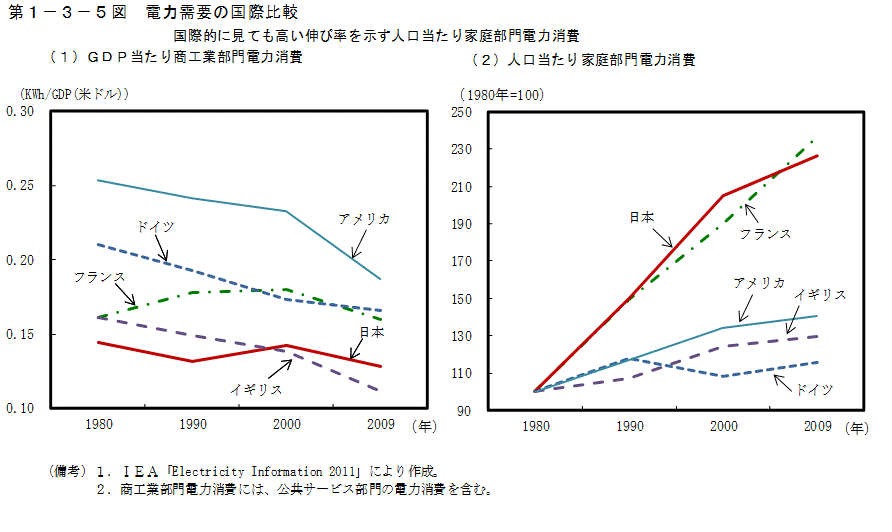
以上のように、量的な制限を課す手法は負担が大きいものとなるおそれが強い。電力需要量が価格に対して十分弾力的であれば、料金による調整が有効であり、かつ、資源配分の観点からも好ましい31。つまり、一定の基礎的な需要量は確保した上で、それ上回る部分については、需要量が大きい時間帯を勘案した価格付け(ピークロードプライシング)といった、節電へのインセンティブを与える料金制度を導入することも一案であろう。
2 電力需給の現状と新たな電源
これまで需要側の現状と震災後に生じた節電の概要を振り返ってきたが、次に供給側である電気事業者の現状と新たな電源を巡る議論に触れたい。
(電源シフトによる対応と電力事業の生産性)
電力会社の費用構造を事業部門別にみると、総費用の 47%程度が発電部門で生じており、他社等からの電力購入による費用は 15%程度となっている(第1-3-6図(1))。2005年度から2010年度の5年間でみると、いずれの電力会社においても発電費用と電力購入費用が増加している。これは原燃料価格の上昇により燃料費が増加したことが主因だが、一部には原子力発電の設備利用率が低下したことも影響している(第1-3-6図(3))。また、発電に要する費用をOECD諸国の平均と比較すると、2001年からは全体としての差は縮まっているものの、水準は高止まりしている(第1-3-6図(4))。なお、発電費用や電力購入費用を除いた送電、変電、配電等の費用は、管内の人口密度や地理的事情により会社ごとに違いが生じている。次に、費用構造を支出項目別にみると、先ほどの事業部門別の発電部門の一部となる燃料費と電力購入費が合わせて40%程度となる。減価償却と修繕費は合わせて26%程度であり、人件費は10%程度といった構造である。会社別にみると、東北電力や四国電力では人件費が高く、北海道電力、東北電力、四国電力では修繕費が高い。また、北海道電力、四国電力では委託費が高くなっている(第1-3-6図(2)32。
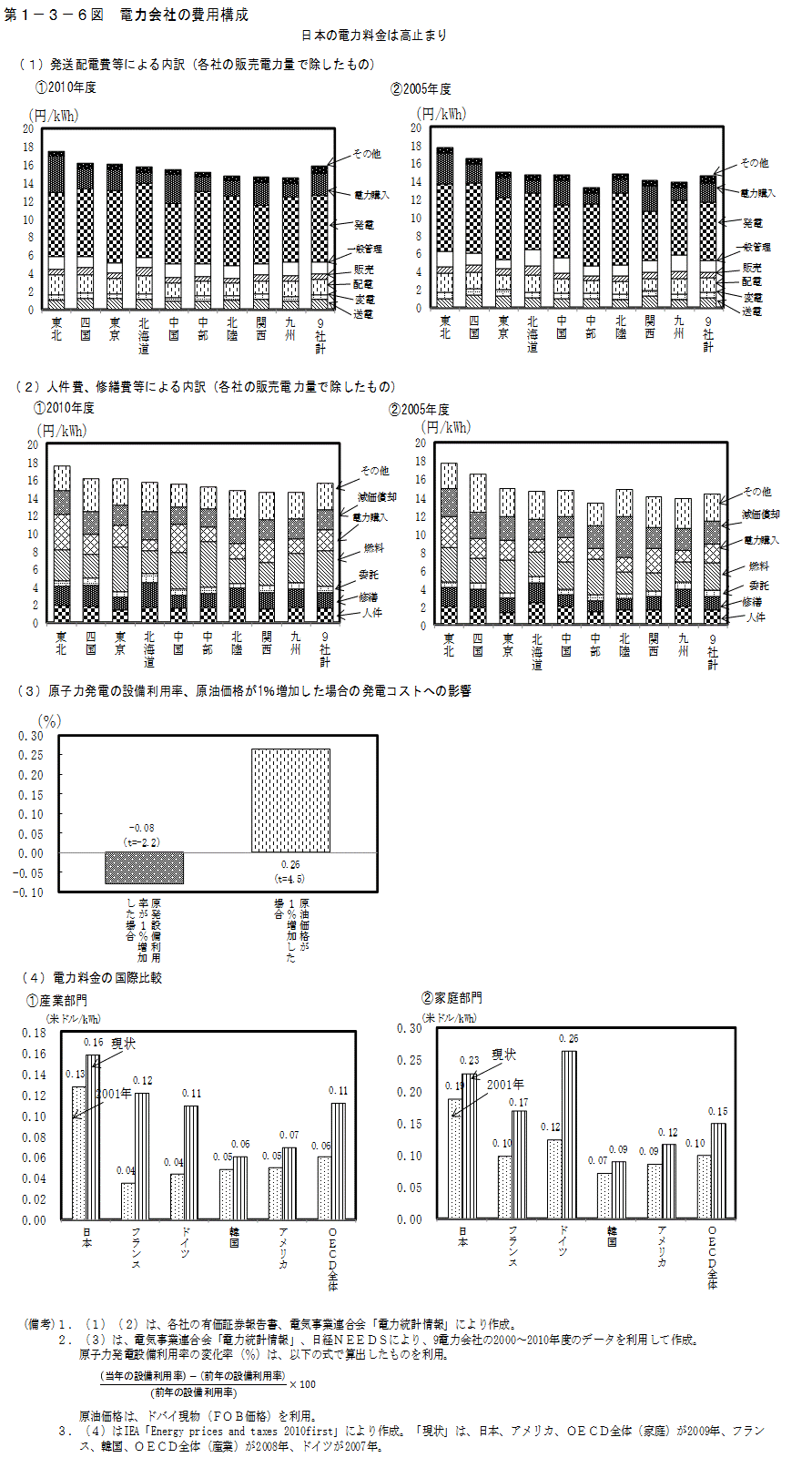
(再生可能エネルギーに依存できるか)
費用の40%程度を原燃料費に費やし、かつ、それは輸入に充てざるを得ないという背景から、我が国では、より安価な発電コストということで70年代より原子力発電を導入し、その比率を高めてきたが、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、今後の供給体制については現在検討されているところである。こうした中、地球温暖化ガス削減という目的に加え、電力の供給制約回避という切迫した事情が生じたこともあり、新たな電源として再生可能エネルギーに注目が集まっている。
再生可能エネルギーの主要なものを比較すると、有力候補としては、先ず太陽光発電があげられる。太陽光発電は、2009年11月から開始されている「余剰電力買取制度」等により、急速に普及が進んできている(第1-3-7図(1))33。風力や地熱といった発電方法も有力候補であるが、風力発電の場合、発電可能な立地に偏りがみられることや、用地規制(自然公園法や建築基準法等)に伴う審査が課題との指摘がある(第1-3-7図(2))34。地熱発電の場合、従前から熱源を利用している事業者等との調整等が課題との指摘がある35。これらの規制や事業者間調整の問題を克服する必要はあるが、「再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度」(コラム1-4)により、普及の速度が高まることが期待されている。
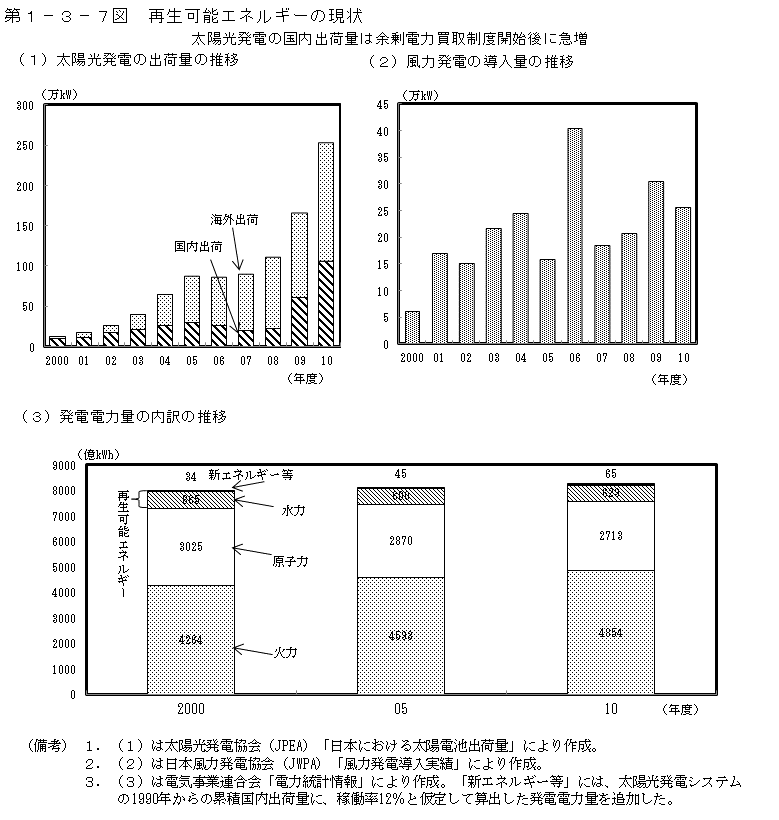
しかしながら、水力発電を除くこうした再生可能エネルギーが電力供給に占める割合は、2010年度末で1%にも満たない(第1-3-7図(3))。原子力発電所の稼働が全て停止した場合、失われる発電量は約30%であり、将来はこうしたエネルギー源に依存する程度を引き上げるにせよ、再生可能エネルギーで直ちに代替することができると考えることは現実的ではない。
(太陽光発電の普及目標と蓋然性)
太陽光発電は比較的普及しているものの、石炭やLNG火力発電と比較すれば、3~5倍の高い発電費用を要する技術である(第1-3-8図(1))36。太陽光発電の費用は基本的に装置であるパネルの価格であるが、その価格は量産化につれて低下しており、97年から2010年の間に半減している(第1-3-8図(2))。そこで、97年以降の太陽光パネルの価格と累積出荷量から得られる関係(習熟曲線)を用いて今後の価格を予測すると、仮に2020年頃の年間出荷量が2005年比で10~20倍程度に増加する場合、価格は更に3割程度低下すると見込まれる(第1-3-8図(3))37。
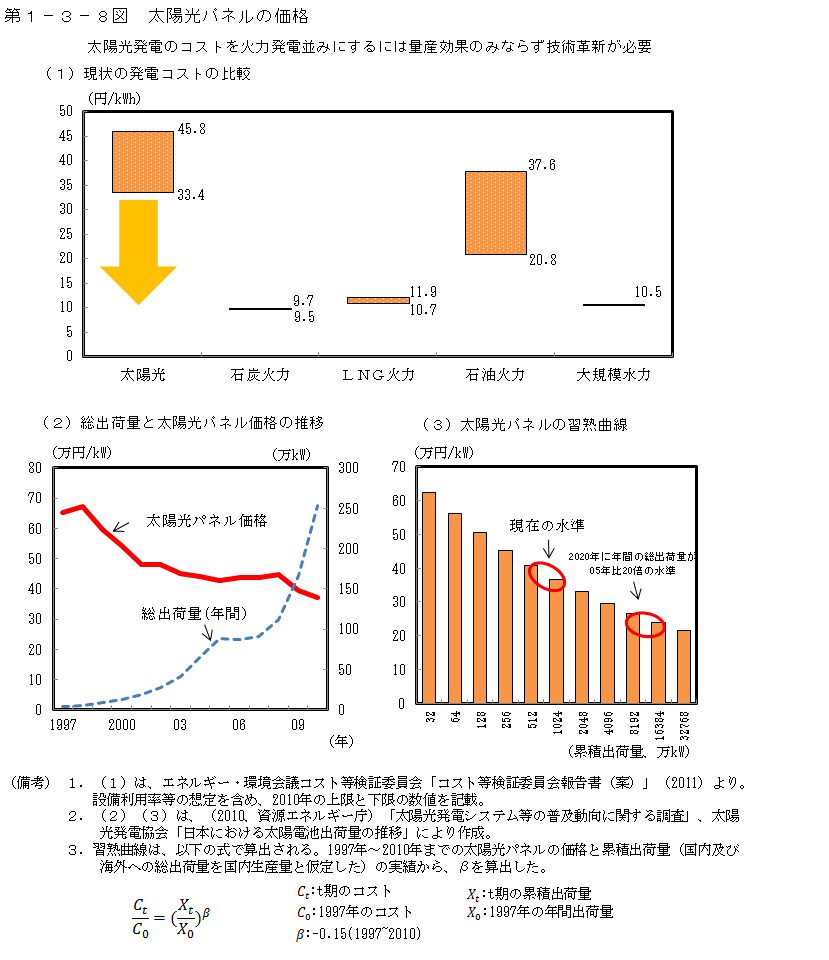
したがって、太陽光発電の費用を火力発電並みに低下させるには、こうした量産効果に加え、さらなる技術革新による発電量増大・発電単価の低下が必要となる。具体的に指摘されている技術的課題としては、現在主流である「結晶系シリコン太陽電池」に対し、加工用途が広いものの現状では発電効率が劣る「薄膜系シリコン太陽電池」38の高効率化や「有機系太陽電池」39の開発等がある40。
(供給体制の改革とこれまでの経緯)
当面の供給制約を回避することや代替的な再生可能エネルギーの普及を目指す動きとともに、東京電力福島第一原子力発電所の事故は、電力供給体制の在り方に対する議論を活発化し、未解決の課題に改めて焦点を当てることになった。
第一は発送電の分離問題である。これは、大規模なネットワーク設備を必要とする送電部門については地域ごとに独占的な送電会社を設置し、担当させるものの、発電部門は原則参入自由化を目指すものである。これにより発電の地域独占が消滅し、発電における新規参入を促すとともに、料金の合理化をもたらす効果があるとの指摘がある41。実際、発電部門における新規参入者の販売電力量に占める市場シェアは3.5%程度に止まっている42。一方、この点については、発電と一体的な送電網の整備によって、質の高い電力供給が維持されており、引き続き一体的な整備・運用が求められるとの見解もある43。
こうした電力自由化については、その効果について様々な分析・評価が行われた。例えば内閣府(2010)は、電力事業の規制改革がもたらした消費者余剰の増分について2005年度から 2008年度の3年間で約1兆円と試算している。また、戒能(2007)は、89年度の電力供給費用を基準とすると、2003年度に同費用は16%低減しており、このうち制度変更44の影響による低減分は5%と分析している。また、当該供給費用と電気料金の低減幅はほぼ同水準であるため、制度変更の影響は電気料金引き下げの原資の一部となっていたと理解されるとも指摘している。
第二の点は、料金算定方式の改善である。
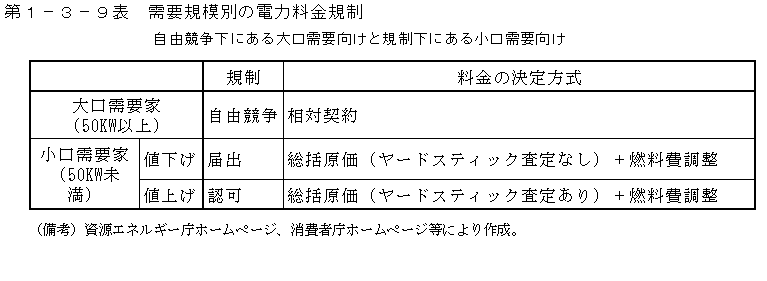
現行の総括原価方式には効率化インセンティブが欠落しており、規制料金分野(小口料金)における料金の高止まりにつながっているとの指摘がある。過去には、費用項目を積み上げる方法ではなく、料金に上限を定めた上で、一定の生産性上昇率を仮定して削減していくというプライスキャップ方式(価格の上限を決めるもの)が提案されていた。ただし、費用削減のインセンティブは働く一方、収益を増加させるために設備投資やその他必要な経費が削られ、電力の質と安全性が低下するというデメリットも指摘されている。
最後は、原子力発電施設の取り扱いである。東京電力福島第一原子力発電所の事故による損害賠償額は、一過性の損害分として2兆6,184億円、年度ごとに発生し得る損害分として初年度 1兆 246億円、2年度以降毎年 8,972億円に上る45。こうした巨額の損害が発生し得る施設の管理・運用について、私企業が担うことが適切なのかどうか、また、私企業が担う場合に国はどのように関与すべきなのかについて、議論を深めていくことが望まれる。
3 当面の電源シフトが及ぼす影響:シミュレーション
(電源シフトの生産性効果)
原子力発電所の停止件数が増加する中、再生可能エネルギーが直ちに代替することは現実的ではないことから、火力発電施設の稼働率引き上げや再稼働が進められている。電力の供給制約が一層厳しくなれば、広範な生産と雇用の調整が始まるおそれが高まる。また、火力発電への依存度が高まれば、石油・石炭・LNGといった原燃料輸入は増加する。こうした動きが月々の貿易や景気動向のみならず、中長期の成長力に与える影響も無視できない。
そこで、発電コストの上昇が及ぼす影響について、応用一般均衡モデルを用いて試算する。試算には、GTAP(Global Trade Analysis Project)事務局が提供している第7版のデータセット(2010年5月公表、基準年は2004年)を世界12カ国・地域、15産業・商品に集計して利用した(付注第1-10-1表)。
今回の試算では、原子力発電施設の停止が電力業の生産フロンティアの内側へのシフト、つまり、生産性低下であると捉え、その生産性低下が経済に与える影響を描いている。生産性低下の程度については、2010年度の発電実績、稼働率、発電方法別シェア、各発電方法の単価(の逆数)を用いて生産性の(対称)変化率を求め、▲10.2%と見込んだ(第1-3-10表)。
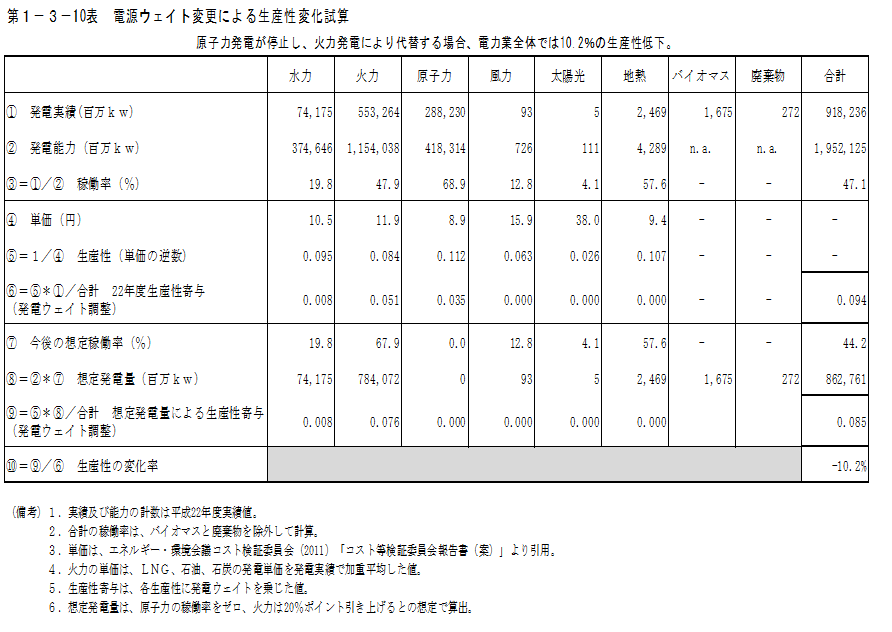
具体的には、稼働を停止する原子力発電を火力発電により代替すると考えると、火力発電設備の稼働率を 2010年度対比で 20%ポイント上昇させることで 2010年度比の総発電量で約94%程度まではカバーできるという想定を置いた。この場合、原子力発電と火力(平均)発電の発電単価差から計算される生産性低下は10%程度となる。
(二つのシナリオ)
こうした生産性低下を外生的に与えつつ、新たな供給体制に対応した経済の姿を求めたが、その際、経済の動きについて、二つの異なる仮定を置いた。ある経済的なショックによって生じる変化がもたらす資源配分上の影響をみるのであれば、資本は一定という静学的な処理でも十分であるが、投資の変化による資本ストックの変化の効果を仮定し、それが生産の変化へと更につながった場合の姿、つまり、動態的な変化を描くことも試みた。利用した経済モデルでは貯蓄率は一定であるが、これを原資とする投資は、生産や収益率によって影響を受けることになる。そこで、ケース1では、貯蓄投資差額が対外収支によって調整される場合を、ケース2では、投資が資本ストックを動かし、さらに資本ストックが生産を動かすことで貯蓄投資差額がバランスする場合を描いた。前者の対外収支が調整する程度は、投資収益率が国内外で均衡するまで動くように、また、後者の資本ストックが調整する程度は、対外収支のGDP比率が一定の中、貯蓄率と投資率が一致するまで動くようにそれぞれ計算している。
(マクロ経済への影響)
試算結果の概要は以下の通りである。我が国の電力業に生じる生産性低下は、実質GDPを▲0.39(ケース1)~▲0.60(ケース2)%程度減少させる。こうした影響は、貿易を通じて諸外国にも多少影響するが、大半は日本経済の変化により、世界全体のGDPが、 ▲0.04(ケース1)~▲0.08(ケース2)%程度減少する。
生産性の低下による実質GDPの減少に対し、投資と貯蓄は異なった変化をみせる。貿易により調整するケース1では、各国の投資は世界平均の期待収益率に一致する水準に決まる一方、貯蓄は各国の所得の一定率と仮定している。したがって、両者は必ずしも一致せず、今回は貯蓄が超過する結果となっている。モデル上、貯蓄超過は純対外資本流出や貿易収支と一致し、その幅は所得比で0.15%程度である。また、モデル上は均衡から均衡への移行を計算しており、その調整過程は捨象されている。このため、失業は明示的に存在せず、賃金や資本コストを含めた価格が需給を調整するように変化(今回は下落)している。その結果、輸出価格が下落、輸入価格は上昇することから、我が国の交易条件は▲0.15%程度悪化する。逆に、諸外国では、産油国を含む地域を中心に交易条件の改善がみられ、輸入が増加する。
ケース2では、世界平均の期待収益率に一致する水準に投資が決まるのではなく、変化する期待収益率により投資が変化し、それに併せて資本ストックも変化する。ケース1のような対外収支の変化を通じた生産性ショックの調整はほとんど生じず、生産性のショックによる所得減少は必要とする資本量の減少へとつながり、実質GDPの下落幅はより大きくなる。
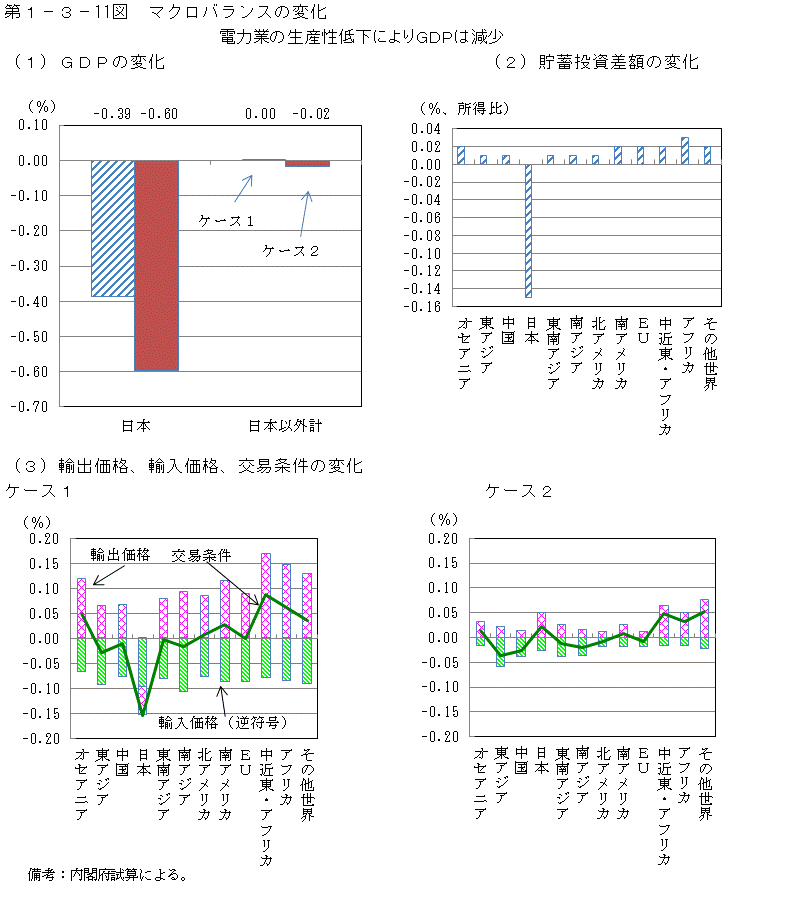
(部門間の変化)
次に、産業部門レベルで生じる変化をみる。電力業への影響は直接であるが、その供給は約▲2%の減少となり、需給を均衡させる電力価格は10%以上上昇する。電力価格の変化を受けて、各産業は供給価格を引き上げることになるが、それは同時に需要を減退させることで、最終的な均衡へと至る。財別生産面では、所得の低下により非製造業を中心に減少がみられるが、ケース1では、輸送機械、電気機械、一般機械、繊維・アパレルが、輸出の増加により生産量を増やしている。これは、賃金や資本コストの下落により生産コスト・生産価格が全体として低下し、国内需要は低迷するものの、他国との間での価格競争力が改善して輸出が増加するためである。なお、輸送機械については、電力価格が高まることで中間投入財としての電力を代替することによる需要も増加に寄与している。他方、資本ストックが減少し、対外的な調整がほとんどないケース2の場合、電力価格の上昇は、輸送機械の微増を例外として、全部門の生産量を低下させる。特に、非鉄金属に悪影響が出るのは、この部門に対する電力価格の波及が大きいためである。
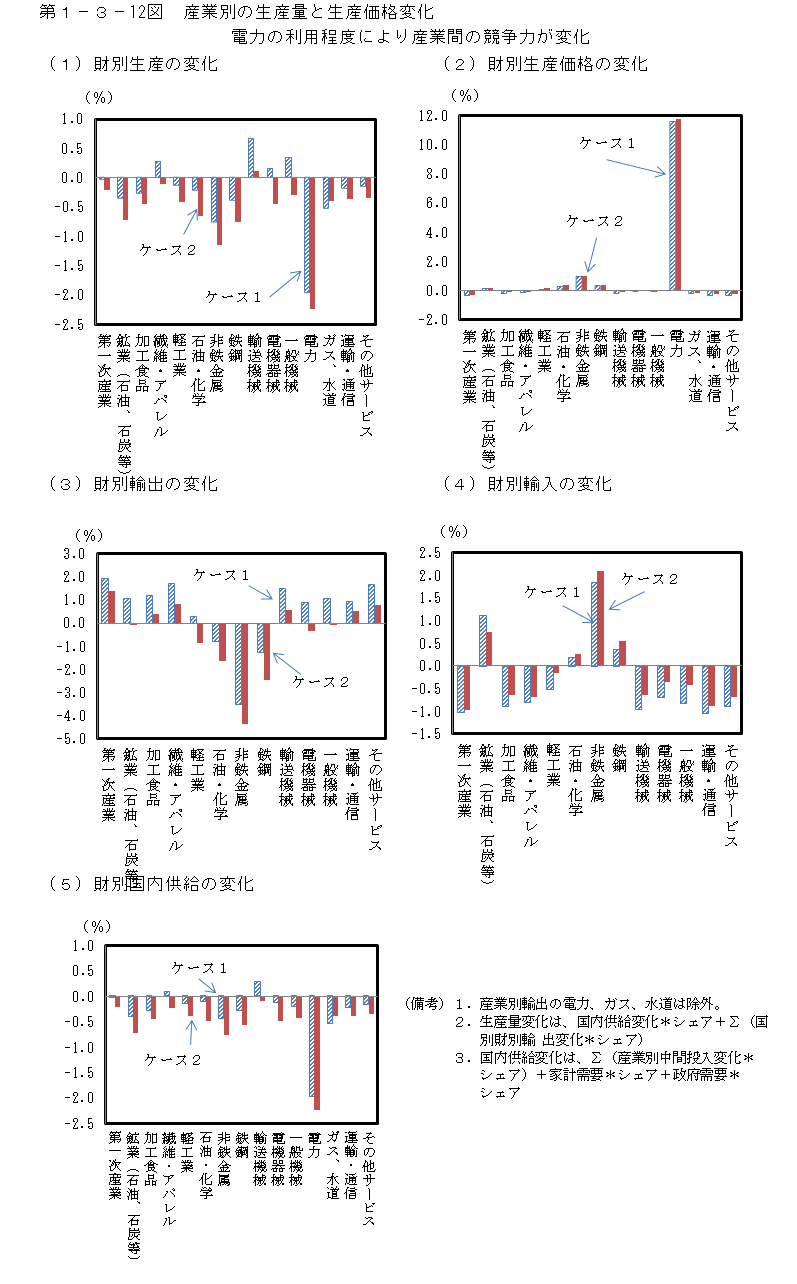
コラム1-4 再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度について
再生可能エネルギーの「全量固定価格買取制度」は、2011年8月26日に法案が可決され、2012年7月から施行される見込みである。予定買取対象は、五つ(太陽光、風力、中小水力(3万 kW未満)、地熱、バイオマス)の発電方法のいずれかで発電された電力であり、買取価格は経済産業大臣(告示)が定める。これに先立つ現行制度は、「余剰電力買取制度(エネルギー供給構造高度化法(平成21年7月1日成立、平成21年8月28日施行))」と呼ばれ、電力事業者に住宅太陽光発電の買取義務を課している。2011年度の買取価格は40円/kWh(経済産業大臣告示)であった。下図(1)は、各電力事業者の回避可能費用を買取量で除した値であり、節約効率(既存発電費用の高さ)を意味する。また、(2)は(1)の買取量を需要者が設置した施設の最大発電可能量で除した値であり、稼働率(太陽光発電に対する環境適性)を意味する。地域別にみると、節約率上位は、九州電力、北陸電力、中国電力の順であり、稼働率上位は、四国電力、九州電力、関西電力の順である。九州電力は全体の効果が大きい。相対的に、中部電力や北海道電力は、節約率でも稼働率でも劣っており、他の再生可能エネルギーを対象にする方が望ましいかもしれない。