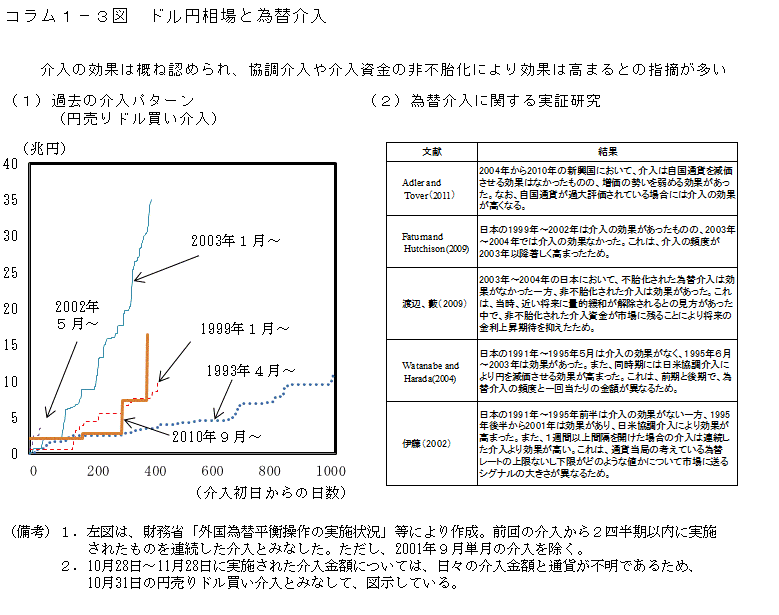第2節 円高と日本経済
2008年のリーマンショック後、我が国の通貨円は主要な通貨に対して増価基調にある。以下では、為替レートの変化を確認し、その背景を探る。そして、こうした為替変化が企業の行動に与える影響を概観する。最後に、円高に関連して指摘される産業空洞化のリスクについて検証する。
1 為替レートの決定メカニズム
(高止まりする名目レート)
名目実効為替レートの増価基調は、2000年代に入っていったん弱まったものの、2008年のリーマンショックや 2010年以降のギリシャに端を発する欧州の政府債務問題といった世界的な危機が繰り返される中で、再びその傾向が現れてきた。年間の変動を均して2008年9月を基準としてみた場合、1年後の2009年9月では21.5%、2年後の2010年9月では24.7%と高止まり、3年後の 2011年9月では 31.7%と円高が進んだ水準で高止まっている(第1-2-1図(1))。
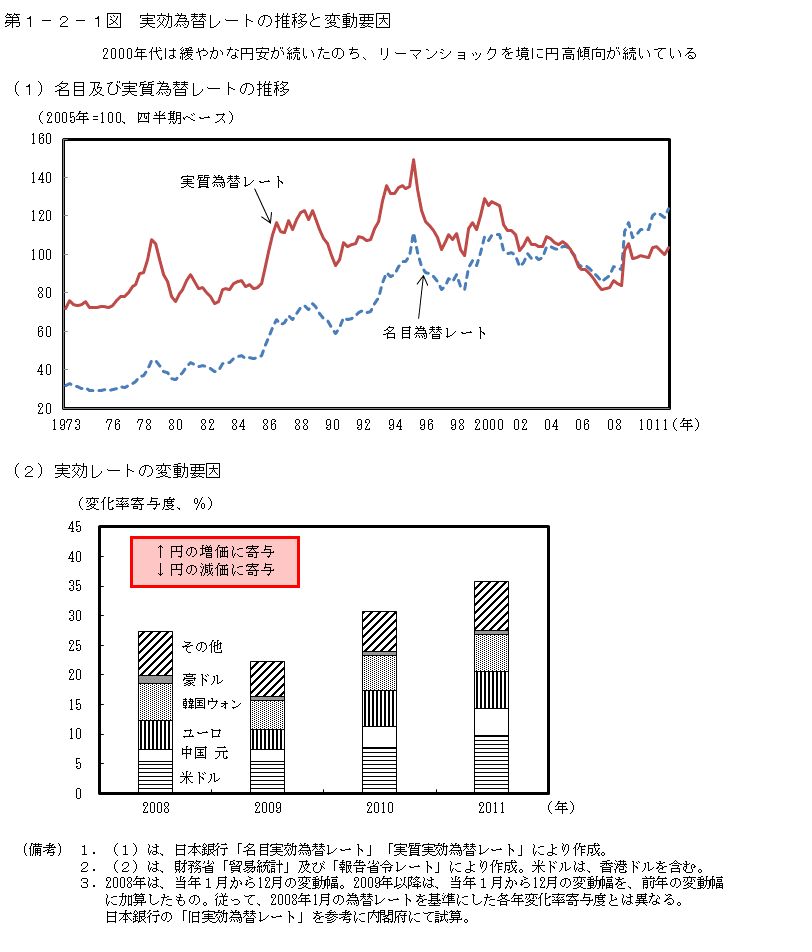
こうした名目実効為替レートの変化を構成する通貨別の寄与に分解し、リーマンショックにより為替水準が大幅シフトした 2008年以降の累積寄与をみると、2011年8月時点では、ドル(米・香港)、韓国ウォン、ユーロの順に増価へ寄与した。(第1-2-1図(2))。
(為替レートは物価に影響し、また、影響される)
世界的な金融危機の中、自国通貨が安全資産とみなされて増価することは、その限りにおいては好ましく、また、輸入される最終需要財の価格低下や、中間投入物価が下がることによる生産者物価の低下というメリットも存在する(第1-2-2図(1))。しかしながら、国内固有の投入コスト(中間投入と付加価値)を一定にする限り、外貨建価格の上昇により輸出の価格競争力は低下する。我が国の場合、経済全体としては、輸出超過/貯蓄超過の構造的な基調もあるため、為替増価のデメリットが上回るのが現状である。
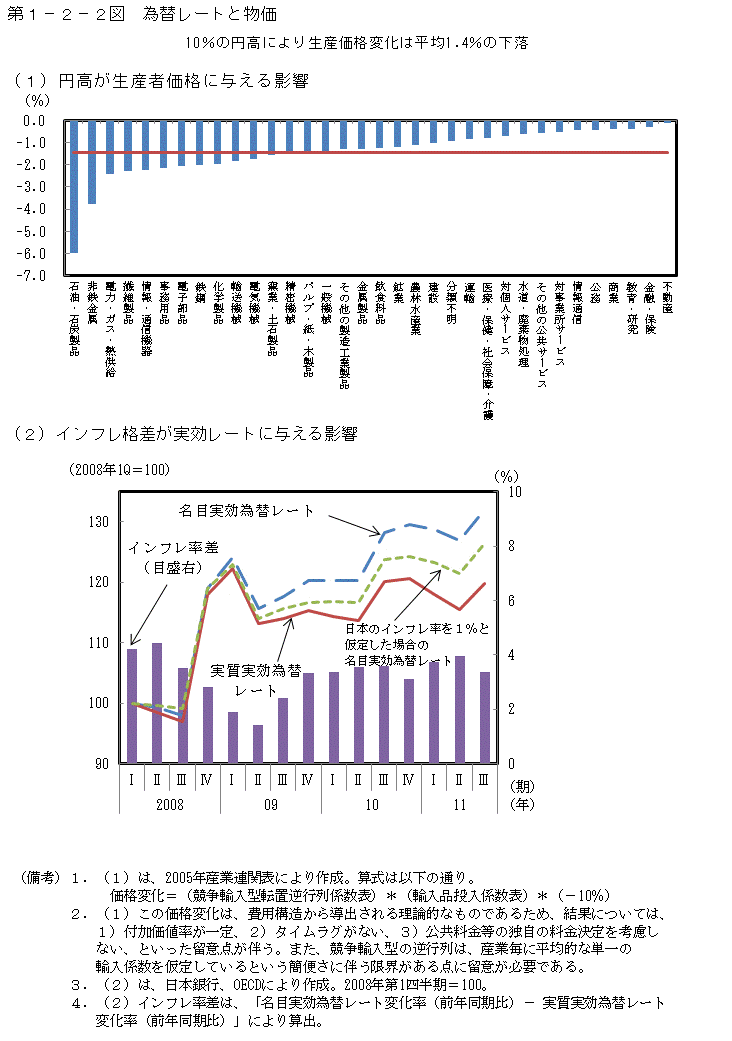
他方、為替レートは物価に影響されて決まるという面もある。我が国と貿易相手国・地域の相対物価で名目実効為替レートを割り戻した値(実質実効為替レート)は、通貨の購買力の比を反映している。この購買力の比が安定的であれば、国によりインフレ率に違いがある場合、中長期的にはその違いを調整する方向に名目為替レートが変化する。例えば、我が国のインフレ率が貿易相手国よりも低い場合には、名目実効為替レートは増価基調を有することになる。我が国は2009年以降もデフレ状態にあるが、仮に、同期間の物価上昇率が、例えば日本銀行の「中長期的な物価安定の理解」の範囲内にある1%で推移していたとするならば、2011年9月の名目実効為替レートは、実績よりも約5%、円ドル換算で4円程度の円安であったということになる(第1-2-2図(2))10。
(円高の中、交易条件は悪化)
また、為替レートと似た概念に交易条件指数(輸出価格と輸入価格の比)がある。同指数の上昇は一単位の輸出で、より多くの輸入を賄うことができることを意味する。また、同指数は物価の比ということから、原油など原材料価格の世界的な動向に大きく左右される(第1-2-3図)。
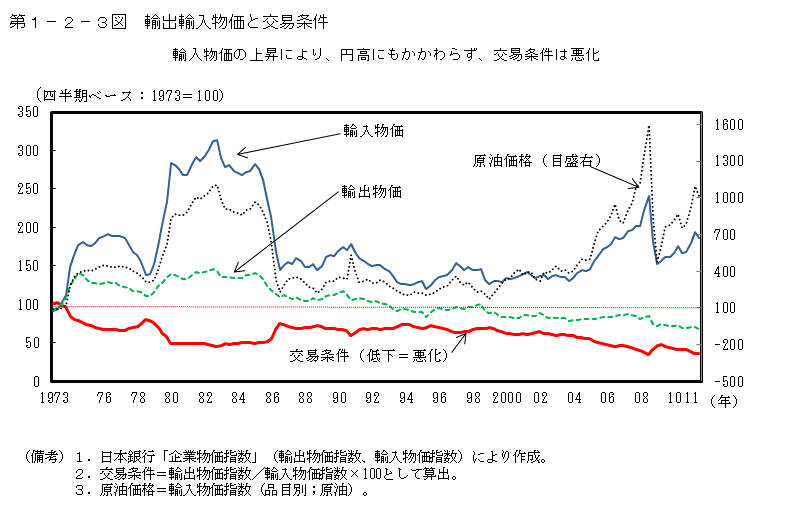
データを確認すると、長期的には輸入価格の変動が大きく、特に、80年代や 2000年代後半に大きな水準変化が生じている。前者には、85年秋のプラザ合意以降に進展した円高や86年に生じた原油価格の5割程度に及ぶ急落が背景にある。また、後者には、2003年からの4年間で3倍以上に急騰した原油価格の影響がある。
他方、輸出価格は、輸入価格ほどの変動はないものの、明らかな下落基調を示している。我が国の場合、主な輸出品は鉱工業製品であることから、その背後には費用項目として中間投入や労働・資本といった付加価値の変動があり、その先には海外における当該商品の需給動向がある。なお、輸出品目別にみると、おおむね全てが低下傾向にあり、例外としては市況の影響が出やすい鉱業品が上昇することがある程度である。
こうした動きを合成した交易条件指数は、86年の第3四半期以来、四半世紀も継続的に低下を続けており、2011年第3四半期の水準は当時の50%である。同じ期間、名目実効為替レートは約87%増価し、実質実効為替レートは約11%減価している。
(為替を決定する物価と金利)
為替レートの決定メカニズムについては、諸説あるが、ここでは、長期的には一物一価を成立させる水準で決まるという購買力平価に着目したものと、基本的には資産収益率の格差を相殺するように決まるという金利裁定に着目したものに基づいて、円ドルレートの変動要因を分析してみる。
まず日米両国の消費者物価と貿易財物価(輸出入物価をそれぞれの国の輸出入比率で加重した値)のそれぞれを用いてレートの予測値を計算した結果からは、消費者物価の場合には、長期的には為替レートと同方向に動いている傾向は見いだせるものの、短期的な円ドルレートの追跡力は認められない(第1-2-4図(1))。これは、消費者物価にはサービス等の非貿易財が含まれており、これらには貿易を通じた裁定がさほど働かないためと考えられる。
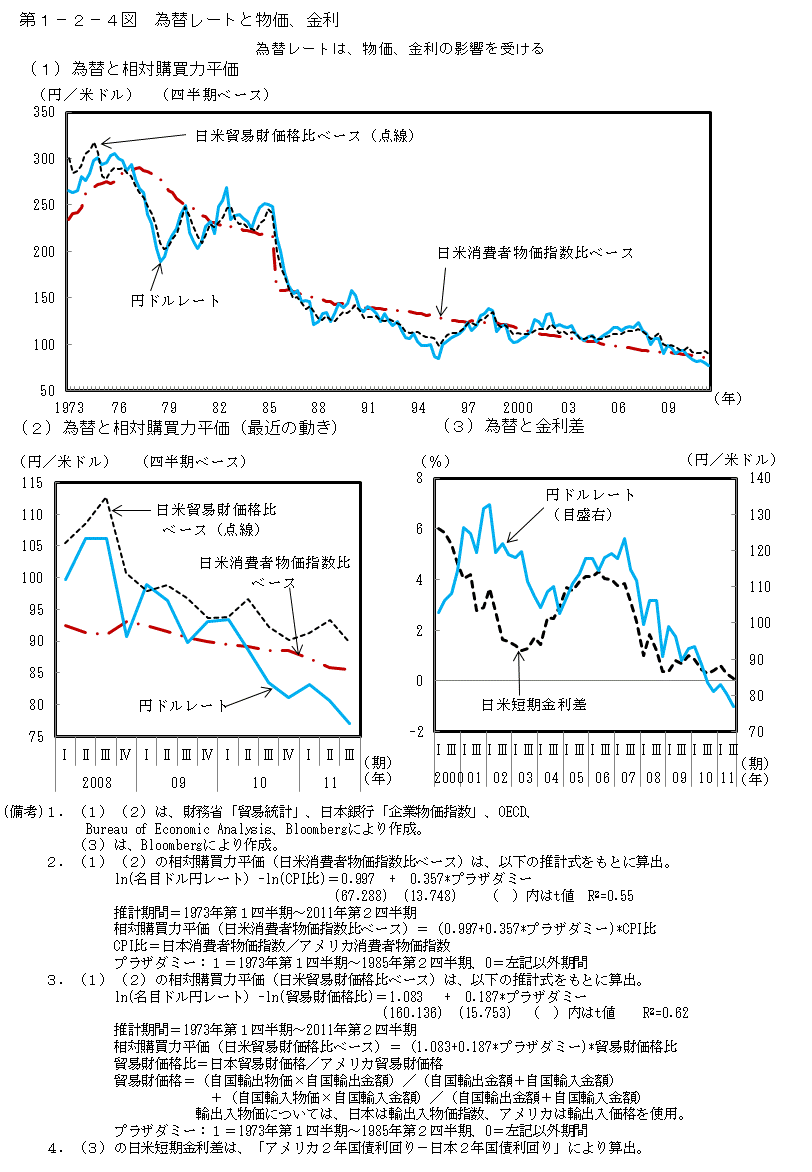
他方、貿易財物価による相対購買力平価はおおむねの動きを追跡できており、為替レートの変化貿易財価格の比に連動していることを示している11。ただし、貿易財物価による相対購買力平価も短期的には、現実の為替レートとかい離する場合がある。例えば、リーマンショック後の 2008年第4四半期には、為替レートが相対購買力平価から 10%程度かい離したことになる。さらに、2010年第2四半期以降にも、相対購買力平価を10%前後上回る円高が続いていることが示されている(第1-2-4図(2))。
また、物価差と同様に金利差についても通貨間で裁定が働くとの考え方を確認すると、両者の関係は2000年代後半になると、明らかな相関がみられるようになっている(第1-2-4図(3))。
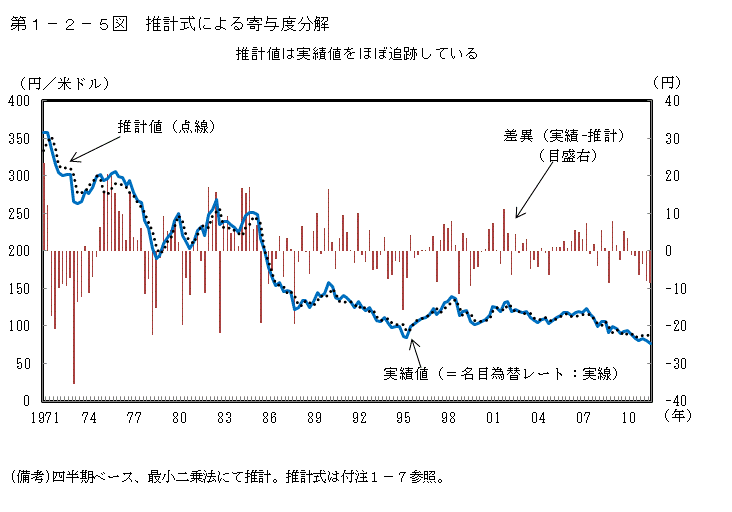
そこで、相対購買力平価や金利差を含んだ為替レート関数を推計した。こうした要因に加え、推計式には、累積経常収支、GDP成長率格差といった要因、また、日米において量的な金融緩和策がとられた期間を1とするダミー変数も含めた。推計結果からは、1)貿易財価格ベースの相対購買力平価は、こうした他の要因を織り込んでもおおむね成立すること、2)アメリカと我が国の実質金利差の縮小は円高に寄与すること、3)我が国の累積経常収支(GDP比)で測った対外資産の増加は円高に寄与する符号は得られたが統計的に有意ではないこと、4)アメリカと我が国の実質成長率格差の縮小は円高に寄与する符号は得られたが統計的に有意ではないこと、5)アメリカの量的緩和ダミーはドル円レートと有意な関係にないが、我が国の量的緩和ダミーは円安に寄与していること、が推察される。
コラム1-2 円高=交易条件の改善ではない
円高になると単位当たりに多くの輸入ができることから、交易条件の改善と同義で用いられることも多い。交易条件が輸出価格と輸入価格の比であることから、円高で輸入価格が下がるのだから当然という理屈である。しかし、為替と交易条件の決まり方をみると、両者は必ずしも同じでないことが分かる。岡田・浜田(2009)は、こうした違いを整理しているが、交易条件の動き方と為替レートの動き方は、2国2貿易財に非貿易財の世界で考える場合、以下のような定義式で表すことができる(価格は変化率である)。
実質為替レート=名目為替レート-購買力平価
=(A国の貿易財1ウェイト-B国の貿易財1ウェイト)・交易条件
+[A国非貿易財ウェイト*(A国非貿易財価格-A国貿易財価格)
-B国非貿易財ウェイト*(B国非貿易財価格-B国貿易財価格)]
ただし、
一般物価=貿易財価格*貿易財ウェイト+非貿易財価格*非貿易財ウェイト
貿易財価格=1財価格*1財ウェイト+2財価格*2財ウェイト
交易条件=1財価格(A国輸出、B国輸入)-2財価格(A国輸入、B国輸出)
こうした定義関係から明らかなことは、交易条件はA国及びB国の輸出財価格の比であるから、生産性格差で変化していくということ、また、実質為替レートは、非貿易財価格と貿易財の相対価格に影響されるということである。
例えば、一般的に製造業の生産性上昇率は高いものの、非製造業の生産性上昇率は低いと指摘されるが、我が国は、この差が大きいといわれる。そこで、我が国をA国として式をみれば、第2項の部分にある非貿易財と貿易財の国内比率が上昇しやすく、実質レートが円高になりやすいということになる。日米間の比較を通じ、80年代後半にみられた「内外価格差」論でもしばしばみられた「我が国の貿易財と非貿易財の価格差はアメリカよりも大きい」といった指摘は、このことを指しており、非製造業の生産性上昇が、実質レートの安定化には不可欠との含意が導ける。
また、80年代はアメリカ及びヨーロッパが 50%程度を占める貿易相手であったが、2000年代になると、そのウェイトは25%を下回る状況にある。他方、アジア諸国の貿易ウェイトは同期間に 30%程度から 50%を超えるところまで上昇している。こうした貿易相手の変化は、貿易財の中身が変わることで交易条件の動き方が変わるだけでなく、相手国における貿易財と非貿易財の価格比も変わることから、実質為替レートの変化に影響を与える。
2 為替レートと企業の対応
ここでは、先にみた為替レートの変化が企業の行動に与える影響を概観する。
(我が国の輸出企業にみられる特徴)
為替レートがマクロ要因で変動する中、企業はこれを与件として最適な事業展開を行っている。こうした為替レートの変動や水準が企業行動に与える影響については、これまでも継続的に分析されてきたが、ここでは、我が国輸出企業の契約通貨の動向を確認し、為替変化と価格付け戦略の特徴に着目する。
最初の契約通貨については、我が国の輸出企業は、邦貨建てではなくドル建てで輸出をする割合が高く、所得水準の似ている諸外国では自国通貨建ての割合が高いという傾向と異なっている、との指摘がある12。契約通貨比率の動きをみると、輸出面では、円のシェアが40%前後、米ドルが50%前後で推移している。地域別にみると、対アジアでは円とドルのシェアが拮抗しており、対EUでは50%弱のユーロにドルが次ぐ形となっている。輸入面では、対EUを除いてドルのシェアが高いことが確認され、対アジアでもドル建てが70%を超えている(第1-2-6図(1))。
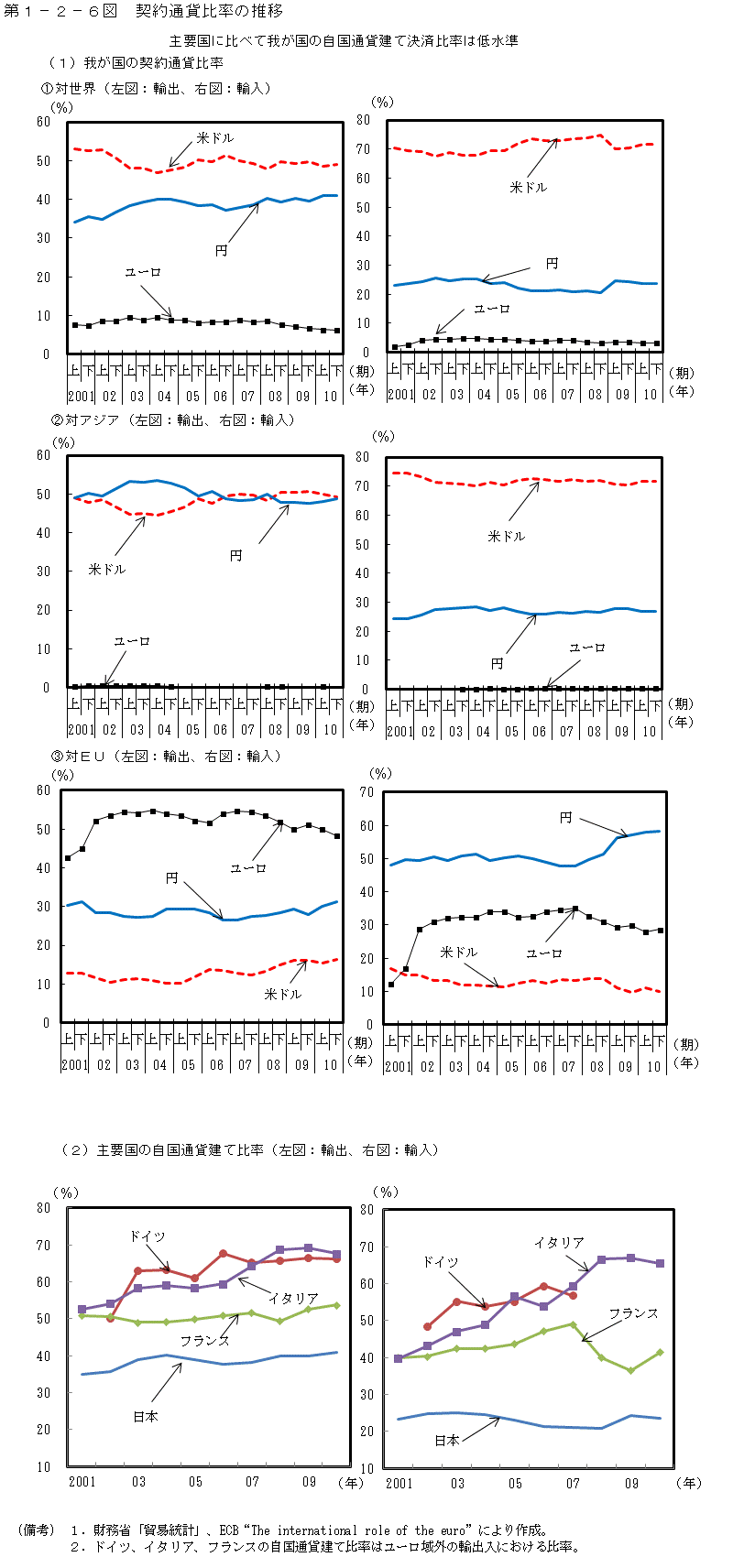
次に、契約通貨の比率を欧州諸国と比較すると、自国通貨による輸出(ユーロ域外)はおおむね50%を超えており、我が国では自国通貨建て輸出は40%程度に止まり、輸入(ユーロ域外)面でも自国通貨建てが少なくとも 40%は超える一方、我が国の自国通貨建て輸入は30%を超えない。(第1-2-6図(2))こうした契約通貨の比率については、先行研究によると、輸出する財の製品差別化の程度や競争力の程度が高ければ、価格弾性値が小さくなるので自国通貨建て輸出が選択されやすいとされている13。また、貿易が企業内取引であれば、現地に設置した販売会社に生じ得る為替リスクを企業グループ全体でプールするという戦略がとられるとの指摘もある14。
(業種ごとに異なる価格転嫁率)
外貨建て輸出が多いと、現地の販売価格が為替変動に沿って改定されない限り、円建てで割引か割増をする必要が生じる。円高に対応して円建ての輸出価格を切り下げる(ドル建て価格を維持する)という我が国輸出企業に特徴的な点は、理論的には仕向け別価格形成(pricing-to-market)という合理的な行動で説明される。具体的には、輸出先市場における価格競争が激しく、価格上昇以上に販売量が減少し、売上額が減少するといった状態であれば、現地通貨建て価格を固定し、円建て輸出価格は引き下げるということである。これは、当該財の需要の価格弾力性が大きいということであり、例えば、多くの競争企業も類似品を生産している製品差別化の進んでいない財が該当する。
そこで、我が国の輸出物価指数がどの程度為替レートに弾力的かという点を測ると、80年代から2000年頃までは、おおむね0.4程度(例えば、10%の円高に対して円建て価格を6%程度引き下げて、結果として、ドル建て(現地)価格は4%上昇)で推移していた。2000年代には、若干低下するが、ドル建て(現地)価格の弾力性はあまり変わっていない。ただし、82年を100として累積した価格転嫁指数で表現すると、我が国の輸出企業は現地価格の転嫁割合を低下させてきている(第1-2-7図)15。
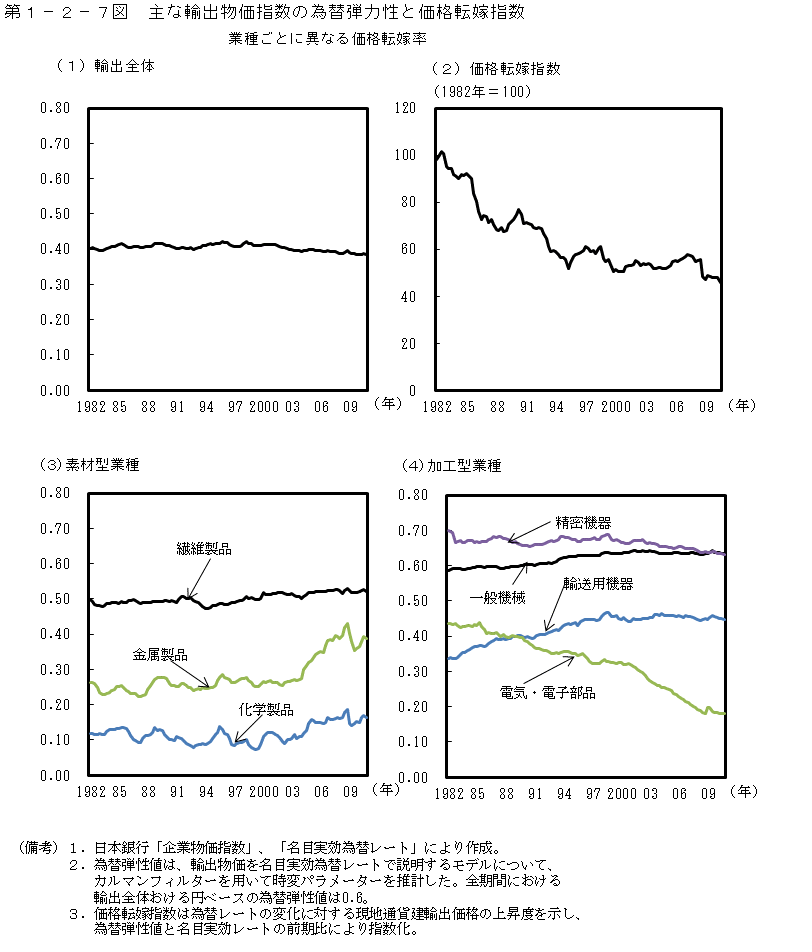
こうした動きを主な財別輸出価格指数について比較すると、輸出価格の為替弾性値の水準と変化のそれぞれに違いがみられる。第一に、ドル建て(現地)価格の為替弾性値が継続的に低下している(円建て輸出価格の為替弾性値が高い)のは、電気・電子部品、精密機器といった分野である。ただし、精密機器については、低下傾向にあるものの水準は高く、為替変化を現地の販売価格に反映させやすい商品である。他方、電気・電子部品は、低下傾向に加えて水準も低く、為替変化に合わせて円建て輸出価格を調整し、ドル建て(現地)価格を維持する傾向がみられる。これは、販売先市場における価格競争が厳しいことを示唆している。第二に、繊維製品、一般機械、輸送用機械については、おおむね水準が安定的しており、ドル建て(現地)価格の改定と円建て輸出価格の改定を4~6割の間で組合せている。また、精密機器ほどではないものの、ある程度の価格交渉力、市場支配力があると思われる。最後に、化学製品と金属製品は、円建て輸出価格の調整に依存しやすい水準だが、2000年代に入ってから大幅にドル建て(現地)価格の弾性値を押し上げる傾向がみられる。これは、製品差別化に成功したためなのか、資源価格高に伴う価格交渉力の高まりなのか判然としないが、以前は10%の円高に対して円建て輸出価格を7.5~9%程度は切り下げて、ドル建て(現地)価格の上昇を1~2.5%程度に抑制していたのが、2000年代後半では、円建て輸出価格は6~8.5%程度引き下げ、ドル建て(現地)価格を1.5~4%程度引き上げるようになっている。
(円高対応は、海外生産、効率化、製品差別化)
現地での価格交渉力、市場支配力のない企業、業種が為替増価に対して取り得る戦略は、①海外生産の拡大、②国内生産の効率化、③製品差別化の三つであろう。このうち、①の海外生産の拡大については、これまでの海外生産比率の推移でみることができるが、90年以降の動きを概観すると、製造業の加工型(電気機械、輸送用機械)と素材型(化学、鉄鋼等)の何れにおいても、海外における事業展開を拡大している。特に、5年後の海外現地生産比率見込みと実績を比較すると、多少の変動はあるもののおおむね達成され続けてきており、企業は計画的に海外現地生産を高めているとみられる(第1-2-8図(1)及び(2))。
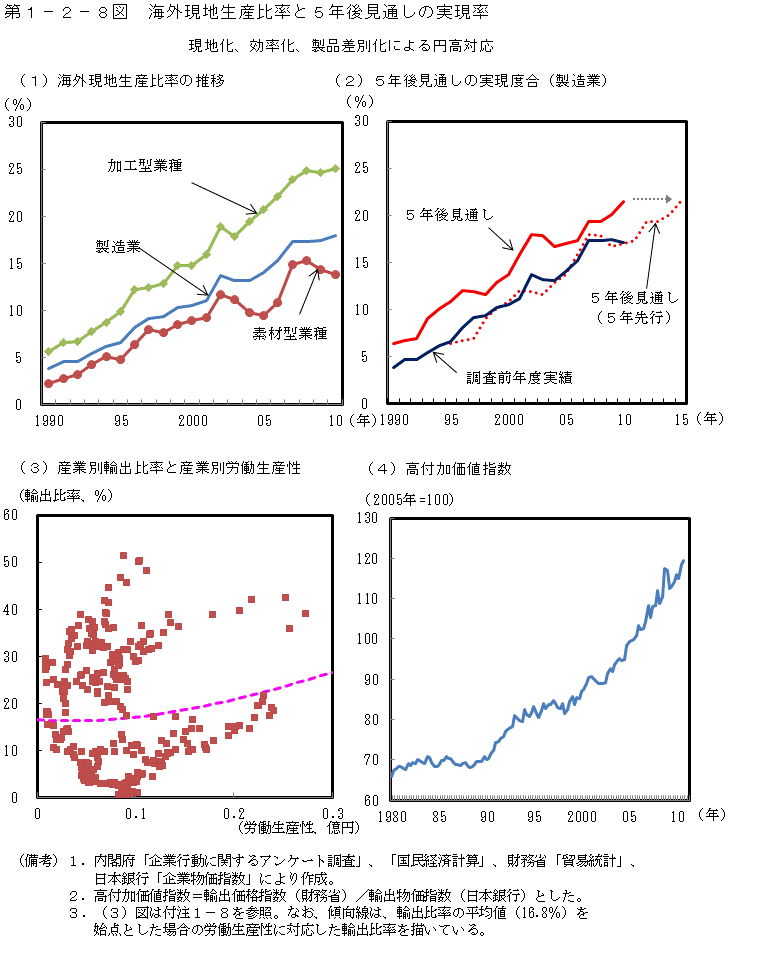
また、②の国内生産の効率化については、これを労働生産性とみると、労働生産性が高いと輸出比率は高いという傾向がみられる(第1-2-8図(3))。最後に③の製品差別化については、輸出品の品質を計る指数をみると、品目間及び品目内での高付加価値商品へのシフトが進展していると推察される(第1-2-8図(4))。
3 産業空洞化論と雇用調整
これまでみたとおり、円高に対して我が国企業は、海外生産の拡大、国内生産の効率化、製品差別化という三つの手段を用いて競争力を維持している。一方、リーマンショック後も含め、為替が増価する局面においては、しばしば「産業空洞化」のリスクが指摘され、政策対応を含めた声が上がってきたことも事実である16。その際、「産業空洞化」の懸念としては、輸入品との価格競争力を失う業種が生産拠点を海外に移転することで、国内雇用が脅かされるという場合と、輸出品の生産拠点を海外に移転することで、国内雇用が脅かされるという場合がある。
(輸入浸透度は継続的に上昇)
最近までの輸入浸透度の推移をみると、おおむねほとんどの業種において上昇傾向にある。ただし、産業間での水準差も大きく、例えば、精密機械や繊維の輸入浸透度は50%を超えているが、食料品や電気機械では増加傾向にあるものの、10%程度に止まっている。輸送機械については5%程度での横ばいとなっている。次に輸入浸透度と雇用者数や生産量の関係をみると、絶対的縮小(輸入浸透度も国内生産指標もマイナス)をみせる産業は見当たらないが、繊維業では、輸入浸透度の高まりと雇用者数や生産の減少が確認され、いわゆる空洞化とみられる傾向を示している17。ただし、繊維業においても、労働生産性はおおむね不変である。我が国の雇用構造全体がサービス部門へシフトしていることを勘案すれば、製造業の各産業の動静について考えるには、雇用者数や生産量といった規模ではなく、労働生産性といった効率性や質を示す指標で評価することが適当であろう18。他の産業についてみると、輸入浸透度が高まる中、精密機械の労働生産性はおおむね不変、電気機械は大幅上昇している(第1-2-9図)。
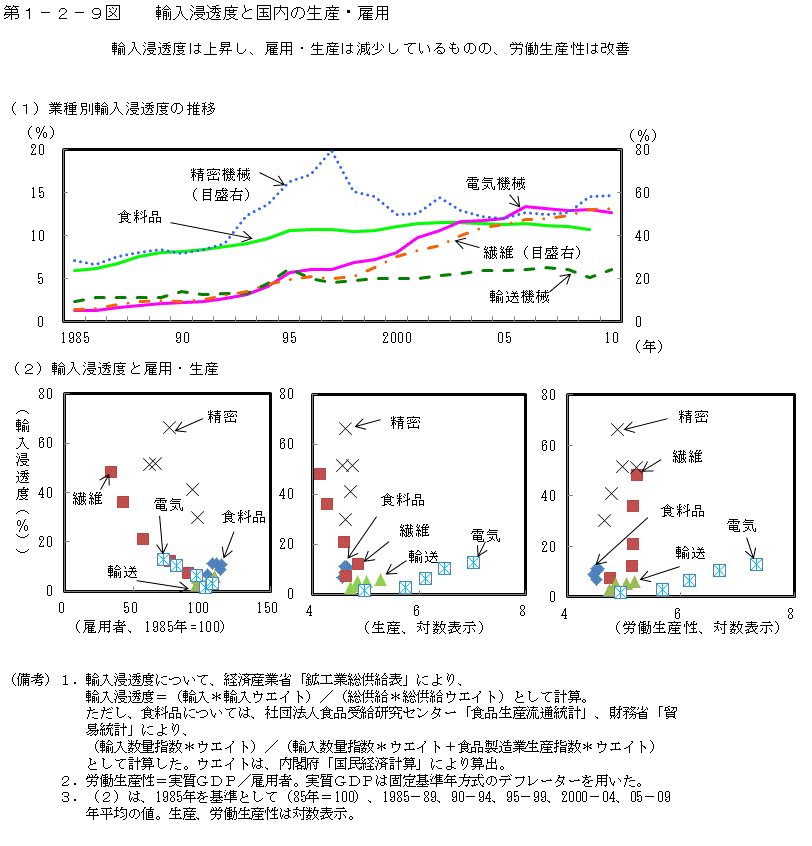
(海外現地生産比率も継続的に上昇)
次に、国内生産が海外生産へと代替されているかという点について、産業別海外現地生産比率と雇用者数や生産の動きの関係から確認する。雇用者数との関係からは、海外現地生産比率が高まる中で雇用者数が増加する産業もあれば、減少する産業もあり、明確な因果関係を読み取ることはできないが、生産については、繊維を除く業種で横ばいもしくは拡大が確認できる。労働生産性でみると、海外現地生産比率が高まる中、労働生産性も高まっていることが分かる(第1-2-10図(1))。
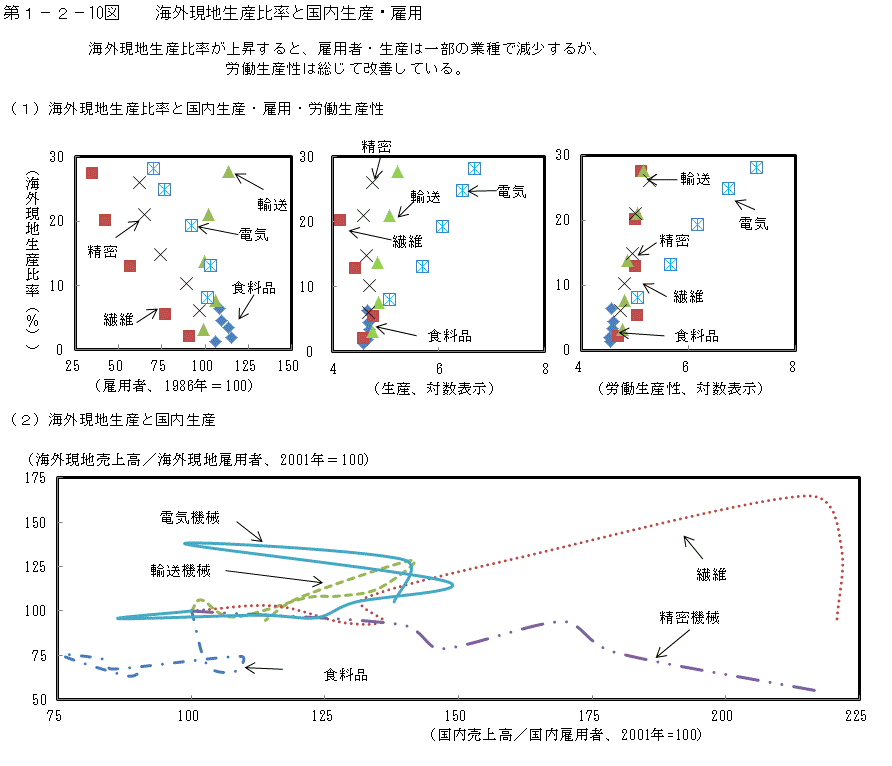
また、海外現地法人と国内法人の一人当たり売上高の推移をみると、国内法人の一人当たり売上高が減少する一方、海外現地法人の一人当たり売上高が増加する傾向にある産業はなく、海外シフトによる国内の生産性低下はみられない(第1-2-10図(2))。
(円高、産業空洞化対策は産業高度化対策)
長期的な動向としては、輸入浸透度の上昇や海外現地生産比率の高まりがみられるものの、それが国内製造業の労働生産性低下を伴った縮小にはつながってはいない。製品輸入の拡大が国内生産を代替する面はあるものの、各産業では、より付加価値の高い商品の生産へとシフトしていることを意味する。また、海外現地生産の拡大についても、円高の影響は当然あると考えられるが、いわゆる貿易・投資のグローバル化と呼ばれる動きの一環として、積極的に海外市場への参入を果たし、産業立地の最適化を行っている結果とみられる。
しかしながら、リーマンショック後の円高は、先の為替レート関数が示すように、ゼロ金利制約による実質金利の高止まりや経常収支黒字の累積などの理由から19、貿易財の相対価格からみた水準を超える円高になっている。
為替変動におけるグローバルに生じているリスク回避的な要因については、我が国が世界経済の安定化に寄与することにより間接的に是正することは可能であるが、より直接的に実施可能な措置としては、本来であれば持続可能な事業や雇用を維持するための企業支援策や雇用対策等ということになる(第1-2-11表)。
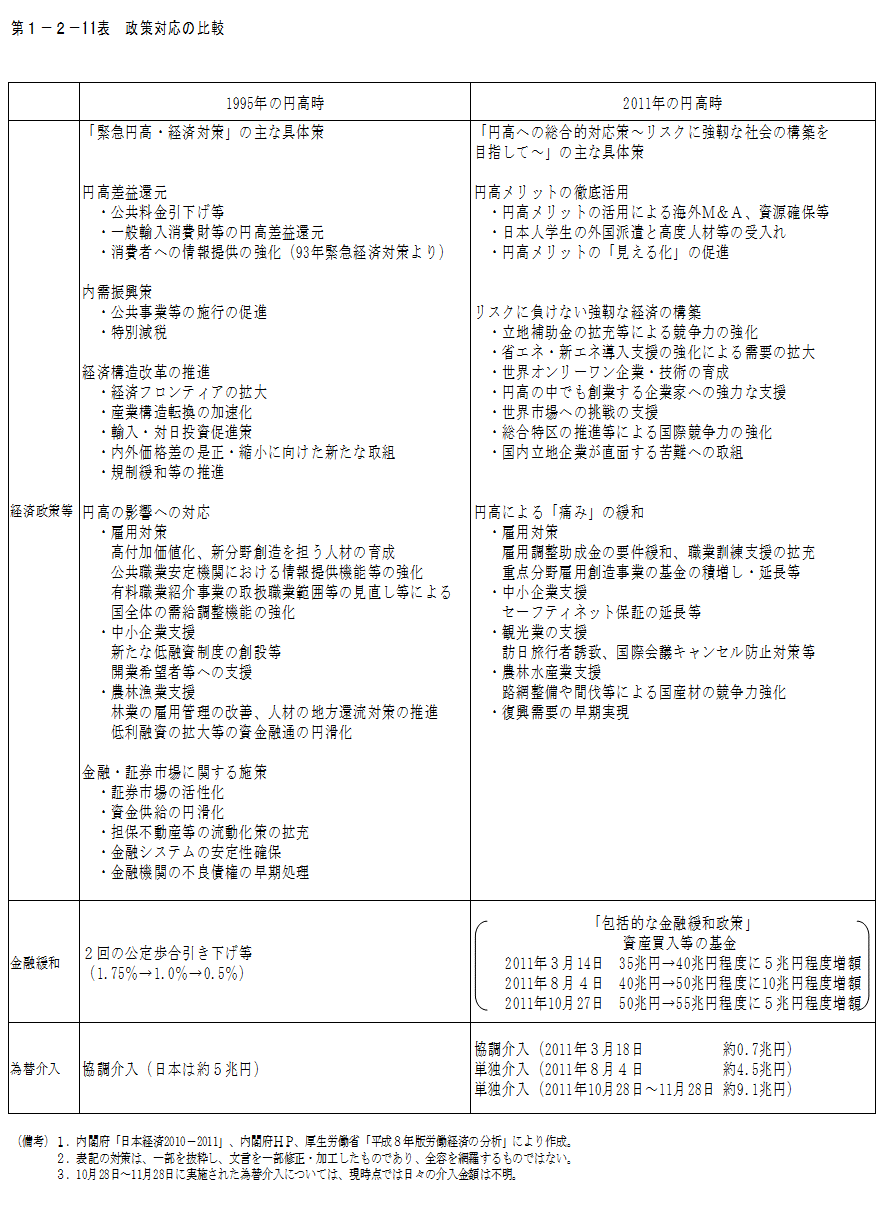
本節で明らかになったように、為替レートを長期的に決定するのは貿易財の価格比であり、貿易財生産者の相対的な生産性である。ただし、貿易財を作る企業間にも生産性の違いがあり、為替レートはあくまでも平均生産性で決まることから、貿易財を生産する全ての産業が一様に比較優位を持つことはない。比較優位は海外の競争相手との違いだけで決まるのではなく、同じ国内の異なる財の生産者との競争によっても決まる。したがって、円高に対応して事業や雇用を維持するための措置を講じる場合でも、構造的に比較優位を失った産業等を過度に保護することは、長期的に我が国の生産性を高めていく上での制約となるおそれがある。
また、こうした貿易財を作る産業間の相対的な生産性格差に加え、貿易財部門と非貿易財部門の生産性格差も重要となる。我が国の場合、既に製造業よりも非製造業の方が多くの雇用と付加価値を生み出しているが、平均的な労働生産性は低い20。非製造業の生産性が製造業に比較して相対的に低い程度が諸外国よりも大きい場合、交易条件の変化に関わりなく実質為替レートが増価してしまう。為替レートは全体の一部の財によって決定されるに過ぎないようにみえるが、非製造業の生産性を高めることが、為替に影響されにくい経済を作る基礎となる。
コラム1-3 円高と為替介入(2011)
約6年ぶりとなる 2010年9月の外国為替平衡操作(為替介入)の後、2011年に入ると、10月までに三度の為替介入が実施された。これらの介入前後の動きは以下のとおりである。
(1)3月の東日本大震災直後:震災により外貨資産を円に戻すとの思惑等を背景に円高が進んだ。3月17日には、1ドル=76円25銭を記録したが、翌18日に日本銀行他、アメリカ、英国、カナダ当局及び欧州中央銀行との協調介入が実施され、1ドル=85円台まで円安方向に戻した。(2)8月の海外経済の不安定化:アメリカの景気や欧州債務問題に対する市場の懸念が高まり、8月3日には76円台後半まで円高が進行した。各国当局は協調介入に慎重であったが、翌4日、我が国は介入を単独実施した。一時80円台まで円安に振れたが、翌5日にアメリカ国債の格付けが引き下げられたこともあり、円買いは続いた。(3)10月末のドル下落:10月後半に欧州当局が債務問題への包括策に合意したことなどをきっかけに、ドルが主要通貨に対して売られた。ドル円レートは戦後最高値を更新し、一時、75円 32銭をつけた。そこで10月31日、一日の介入金額は不明であるが、過去最大と評されている大規模な円売り・ドル買い介入を単独実施した。この介入を契機として79円台半ばまで円安方向に振れた後は、おおむね78円台前半で推移した。
過去と比べると、2003年1月からの介入ケースを除けば、今回のケースはやや金額が大きい。為替介入の効果については様々な研究がなされているが、為替介入は、おおむね急激な自国通貨の増価ペースを減速させる点では効果があるとしているほか、海外当局との協調介入や、介入資金を市場に残す非不胎化介入を行うことで介入の効果が高まるとの指摘が多い。