第2章 米国の貿易・投資構造(第3節)
第3節 米国のサービス貿易と所得・投資構造
米国経済は、財貿易は赤字である一方、サービス貿易は黒字となっており、とりわけ高付加価値のデジタル・知財サービスの輸出に強みがある。また、米国は世界各国に直接投資を行い、高い収益率で直接投資収益を上げている。
本節では、米国のサービス貿易と所得・投資構造について確認する。その上で、財の貿易収支、サービス収支、所得収支を総じてみた経常収支が赤字の状況が継続していることについて、その背景にある財政赤字と基軸通貨であるドルの役割について考察する。
1.サービス貿易の構造
米国のサービス貿易は、一貫して黒字を続けている(第2-3-1図)。2000年以降、サービス輸出をけん引する主要な項目としては、「コンサルティングサービス、R&D等」80、「知的財産権使用料」、「情報通信サービス」のデジタル・知財サービスや、「金融サービス」が挙げられる。
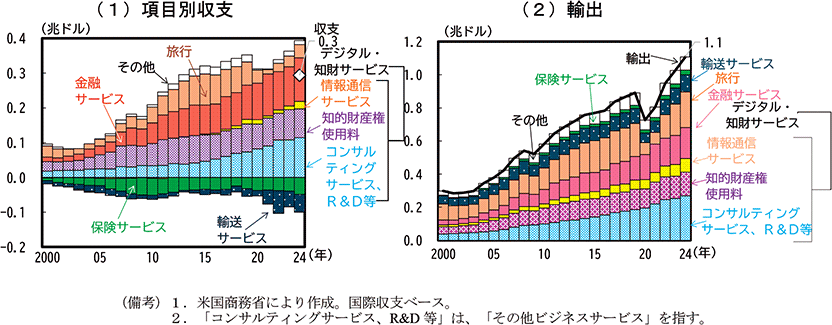
サービス収支を相手国・地域別にみると(第2-3-2図)、アイルランドに対するサービス黒字は大きくかつ拡大傾向にあることが分かる。また、2020年から2021年にかけて、特に中国、カナダに対するサービス収支の黒字幅が縮小しているが、これは、感染症拡大による渡航制限に伴う旅行サービス輸出額の減少に起因している。
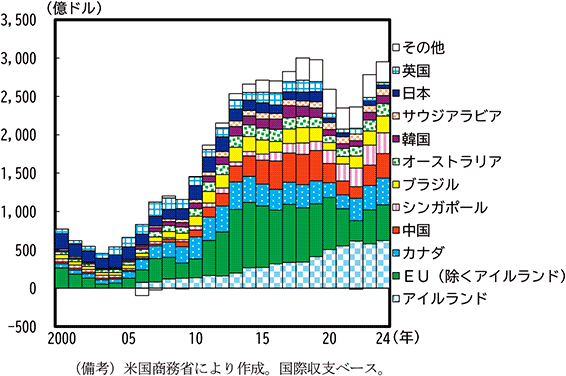
相手国別のサービス輸出の品目別シェアをみると(第2-3-3図)、全世界向けデジタル・知財サービスの輸出シェアが4割以上を占めており、特に、米国からのサービス輸出で3位であるアイルランド向け輸出はデジタル・知財サービスの輸出シェアが9割弱を占めている。アイルランド向けの輸出全体に占めるデジタル・知財サービスの輸出の割合が高い背景としては、アイルランドは、法人税率が低いことに加え、若年人口比率や教育水準が高く英語圏でもあることから、米国企業が、生産、研究・開発拠点としてアイルランドに集積していることが挙げられる81。また、2014年から2024年にかけてのデジタル・知財サービスの輸出は71%増加しており、特に、アイルランド向けは124%増加している。
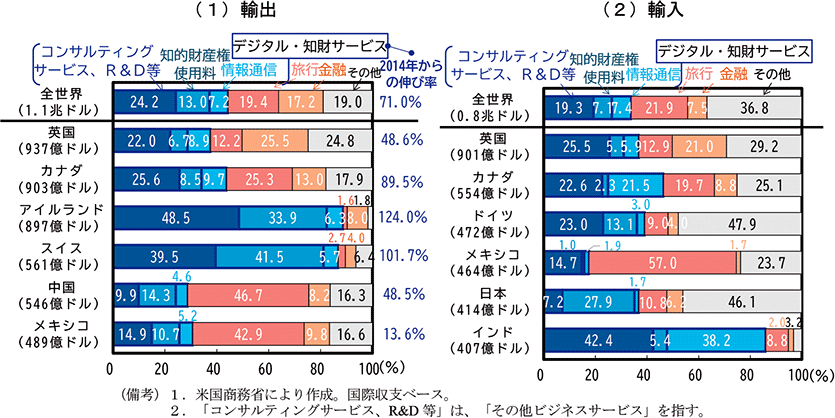
英国は、米国からのサービス輸出相手国としても、サービス輸入相手国としても1位となっている。品目としては、輸出入ともに、デジタル・知財サービスや金融サービスのシェアが高い。米英両国の供給表及び使用表82をみると、金融業や情報通信業において、両国ともビジネスサービス(品目)の中間投入比率が全産業平均と比較して高く、労働生産性も高くなっている。米英では、こうした労働生産性の高い産業において、専門ビジネスサービスの水平分業が進んでいることが確認できる(第2-3-4表)。
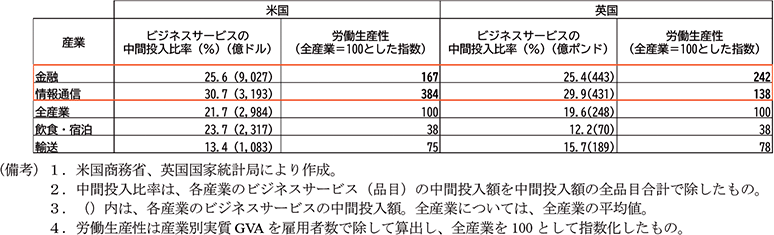
米英間でのビジネスサービス貿易は、一方的な取引ではなく、国内での知識の蓄積・応用を経て、再び国外へとサービスが輸出される相互関係にあると考えられる83(第2-3-5表)。直接投資や国際分業を通じた企業間ネットワークの形成といった水平分業によって高度なサービスの輸出入が可能となり、産業全体の生産性向上と経済全体の成長拡大に寄与していると考えられる。
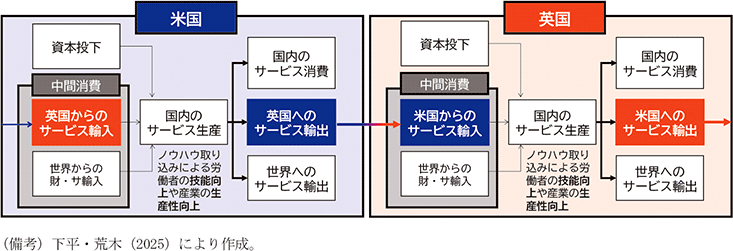
2.所得収支と投資構造
(第一次所得収支は赤字に転じた)
米国の投資構造について理解するため、第一次所得収支について確認する(第2-3-6図)。第一次所得収支は、対外債権・債務から生じる利子・配当金等の収支であり、投資収益と雇用者報酬84で構成される。米国の場合、第一次所得収支の受取り・支払いの両方について、95%以上を投資収益が占めている。
投資収益は、直接投資収益、証券投資収益、その他投資収益、準備資産収益に分けられる85。2000年代後半以降、主に直接投資収益の黒字額が証券投資による赤字額を上回り、第一次所得収支は黒字基調で推移してきた。しかし、2018年以降、直接投資収益が横ばいで推移する一方、証券投資収益とその他投資収益の赤字額が拡大したことにより、第一次所得収支の黒字額は縮小し、2024年には第一次所得収支は1960年の統計開始以降初めて赤字となった。
また、第一次所得収支の投資収益について、受取側と支払側に分けて確認すると、2024年時点において、受取の44.3%が直接投資である一方、支払の50.4%を証券投資が占めている(第2-3-7図)。したがって、対米投資(諸外国から米国への投資)と対外投資(米国から諸外国への投資)とで投資形態が異なることが推察される。
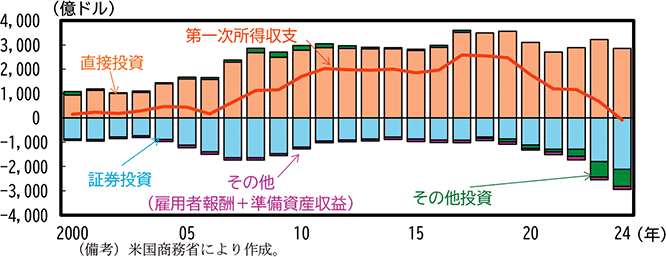
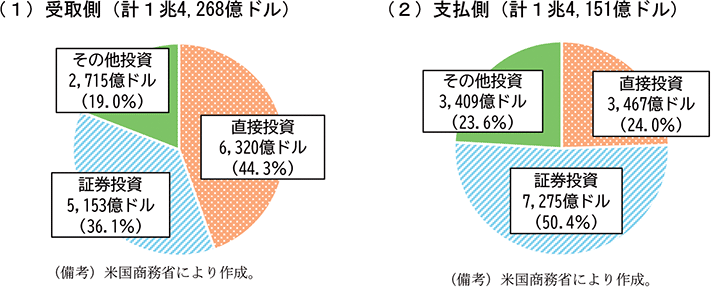
次に、直接投資の内訳を受取・支払別にみると(第2-3-8図)、大きくは出資所得(海外子会社からの配当金(資金還流)収益と再投資収益)と利子所得(海外子会社からの借入・債券利子収益)に分けられるが、受取・支払ともに、出資所得が9割以上を占めていることが分かる。受取側については、2006年から17年まで、現地法人で得られた収益の半分以上が現地で再投資に費やされている。2018年には配当による資金還流が急増し、再投資収益がマイナスへ転じているが、これは第一次トランプ政権で成立した2017年減税・雇用法(TCJA:Tax Cuts and Jobs Act)の影響によるものである86。一方、支払側については、受取側以上に再投資収益の割合が高く、米国内での再投資に資金が振り分けられていると考えられる。2020年以降、収益の米国内への再投資の増加が顕著となっており、2011~20年の平均944億ドルに対し、2021年以降の平均は2,141億ドルと、2倍以上になっている。
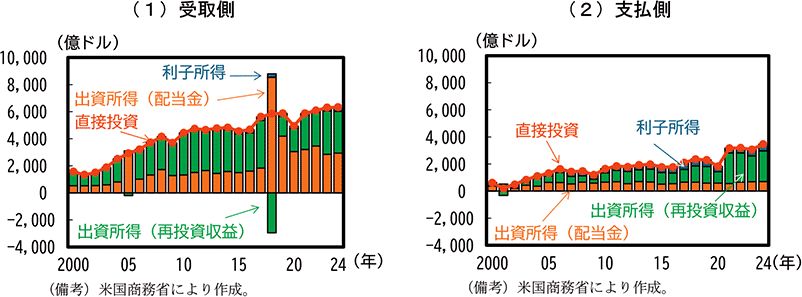
次に、証券投資の内訳を受取・支払別にみると(第2-3-9図)、受取側は株式に係る配当金(非支配会社からの株式配当金による収益)が債券利子(直接投資に分類されない債券利子収益)を上回っている一方、支払側は債券利子による支出が7割近くを占めている。債券利子支払の46.7%(2024年時点)は米国債の利払費であり、その割合は上昇傾向にある。主に諸外国による米国債投資に対する利払いが、米国の証券投資収益の支払側として計上されている。
なお、対米証券投資に関連して、外国政府・外国居住者による米国長期証券の年間の純取得額の推移を第2-3-10図87に示す。2019年以降、米国株式の取得が増加しており、投資先としての需要が高まっている。
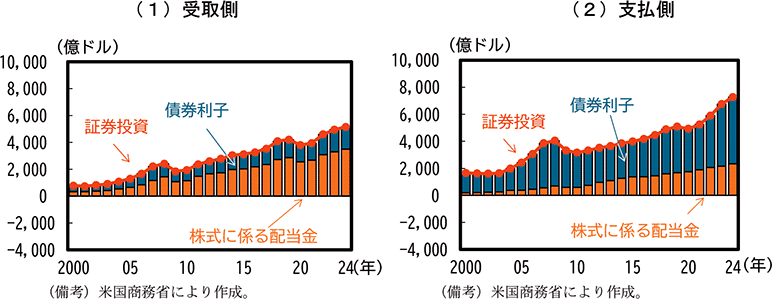
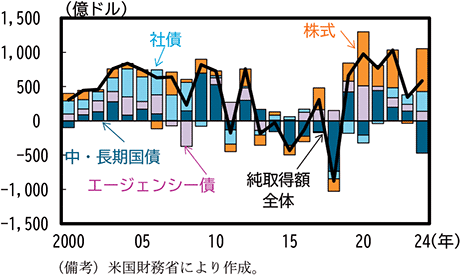
最後に、その他投資の収支をみると(第2-3-11図)、2017年までは黒字で推移してきたが、2018年以降は赤字に転じており、その赤字額は2023年以降、拡大している。部門別では、民間企業(除く商業銀行)と中央銀行・政府は赤字が拡大している一方、商業銀行は2016年以降黒字になっている。
その他投資に係る金融収支をみると(第2-3-12図)、基調的に資本流入が続いており、特に、2020~22年の3年間の純流入額は1.5兆ドルに及んだ。感染症拡大後の低金利の中で、企業の資金需要が回復し(第2-3-13図)、民間企業(除く商業銀行)が海外の投資家や金融機関から資金を調達して投資に振り向けた。これが2023年以降のその他投資収支の赤字額の拡大に寄与していると考えられる。
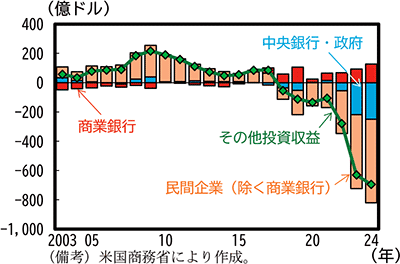
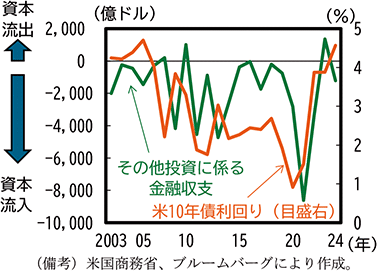
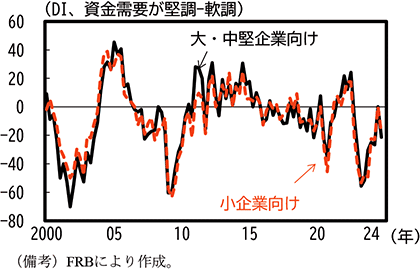
(対外・対米投資収益率の不均衡)
ここまでフロー面での投資所得の内訳及び推移をみてきたが、ストック面での対外純資産残高(Net International Investment Position:NIIP)についても確認する。米国では、対外負債が対外資産を恒常的に上回っているため、負の対外純資産(対外純負債)が続いており(第2-3-14図)、その値は2010年以降、拡大傾向にある。対外純負債は、対GDP比でも、2010年以降上昇しており、2024年には対GDP比▲89.9%となった。IMFによると、2023年以降の対外純負債額の拡大は、米国株価の上昇によるバリュエーション効果の寄与が大きく、2022年(対GDP比▲61.2%)から2023年(同▲70.7%)の拡大のうち、約4分の3を占めるとされている88。
投資項目別にみると、証券投資が対外純負債額の大部分を占めている(2024年の証券投資の構成比は約66%)。証券投資は、負債(海外投資家による米国への証券投資残高)が基調的に増加している(第2-3-15図)。前述のとおり、2023年以降はバリュエーション効果により、上昇幅が拡大している。なお、海外投資家による米国債への投資は、証券投資の約3割を占めている。
一方、近年の傾向に変化がみられるのが直接投資残高89である。直接投資は、2000年に統計開始以降初めて対外負債が対外資産を上回ったものの、2002年以降は2015年に至るまで対外資産が対外負債を上回っていた(第2-3-16図)。しかし、2015年にアイルランドによる医薬品企業の買収が急増したことや、カナダや英国からの直接投資の流入が続いたことで、直接投資の対外負債が対外資産を上回った(時価ベースで対米直接投資が対外直接投資を上回った)。また、2022年以降は、前述のバリュエーション効果や、利益剰余金の増加が主因となり、海外からの直接投資残高が増加している。また、新規の直接投資では、情報業や専門サービス業など非製造業企業への買収が増加している。これらの詳細については後述する。
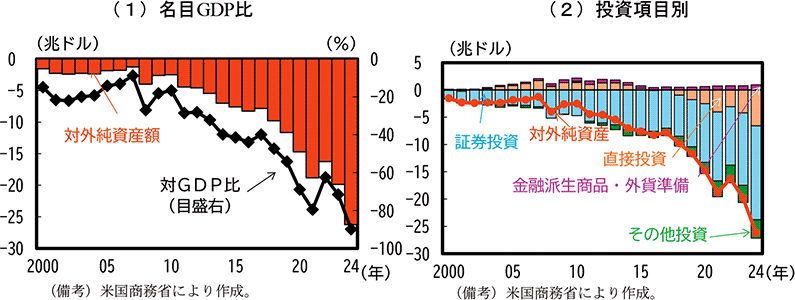
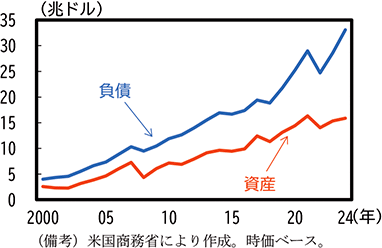
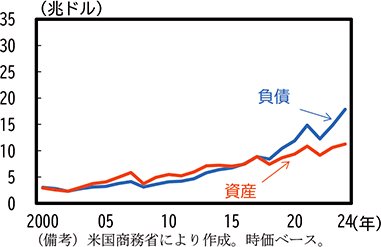
次に、対外資産・負債の収益率を確認する。
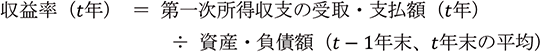
により求めた収益率の推移をみると(第2-3-17図)、対米投資に係る資産(米国からみると負債)がもたらす収益率が2%から4%程度であるのに対し、対外投資に係る資産がもたらす収益率が4%から5%程度と、2000年以降対外投資収益率が対米投資収益率を上回っていることが分かる。このことから、米国全体でみると海外から低コストで資本を調達し、海外へ高い収益率で投資してきたことがうかがえる。
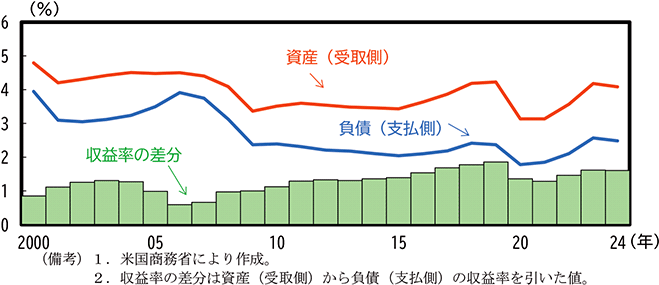
投資項目別に対外資産・負債の収益率の差分をみると、証券投資やその他投資の収益率の差分に比べ、直接投資の収益率の差分は大きく、対米・対外の違いが顕著に表れている(第2-3-18図)。ただし、直接投資の収益率の差分は、2018年の4.9%ポイントで頭打ちとなっており、2024年では3.7%ポイントまで低下している。証券投資については、2007年までは2003年を除いてマイナス、つまり、負債の収益率が資産の収益率を上回っていたが、2008年以降は資産の収益率が上回り、1%ポイント程度で安定して推移している。その他投資については、2000年以降、1%ポイント程度で推移している。
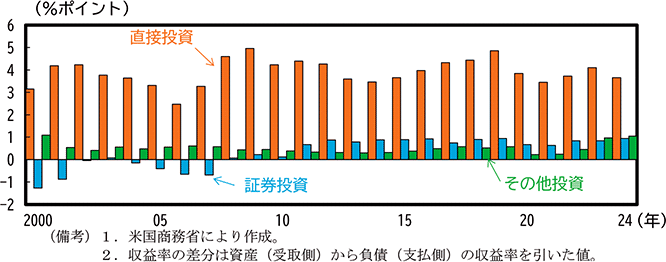
このように、米国は世界最大規模の純債務国であるが、主に証券投資によって低コストで調達した資本を、主に直接投資によって高い収益率で運用することにより、対外資産からの収益が対外負債への支払を上回る構造となってきた。これについては、米ドルが世界の基軸通貨であるために享受してきた米国の「法外な特権(Exorbitant Privilege)90」とも指摘される。
しかし、これまでみてきたとおり、この構造に変化が生じつつある。第2-3-14図のNIIPでは、2018年に初めて直接投資の資産を負債が上回った。さらに、第2-3-18図における対外・対米直接投資の収益率の差分は2022年以降縮小し、2024年には証券投資収益・その他投資収益の赤字を直接投資収益の黒字が下回ったことで、第一次所得収支は統計上初めて赤字となった。
また、保護主義的な通商政策が発表された2025年4月には、通貨・債券の投資先としての米国への懸念が広がり、米金融市場でトリプル安91となった。このような状況は、政策の如何によっては、低いコストで海外から資本を調達し、海外での高い収益率で投資利益を得るという基軸通貨国としての「法外な特権」を米国が享受できなくなるおそれがあることを想起させた。
(直接投資の状況)
次に、対外・対米直接投資の状況について詳細を確認する。
第2-3-19図は、2000年と2023年における直接投資の残高と各国・地域が占める割合(上位5か国・地域+日本)を示している92。ここでは、前述のNIIPの時価ベースでの対外投資残高とは異なり、簿価ベースの評価がなされている93。
(1)図から、2000年に1.32兆ドルであった対外直接投資残高は、2023年に6.68兆ドルに増加したことがわかる。対外直接投資先の順位は、2000年は英国、カナダ、オランダ、バミューダ諸島、日本と続く。一方、2023年においては英国、オランダ、ルクセンブルク、アイルランド、カナダとなっている。なお、日本は2000年時点では4.3%を占め、全世界で5番目の対外投資先であったが、2023年には0.9%となっている。この順位変動には、米国による諸外国の非金融持株会社への投資増加が影響しており、詳細は後述する。
一方、(2)図から、対米直接投資残高は1.26兆ドルから5.39兆ドルに増加していることがわかる。対米直接投資を行っている上位5か国は、2000年時点では、英国、日本、ドイツ、カナダ、フランス、2023年時点では、日本、カナダ、ドイツ、英国、フランスとなっており、日本の順位が上昇して、世界最大の対米直接投資国となっている。日本については、後述するが、新規の直接投資が増えたというよりは、米国現地法人で得られた利益の再投資による直接投資フローの積上げによるところが大きい。
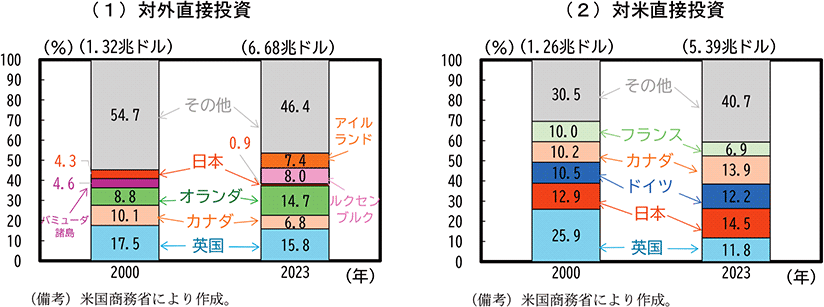
対外直接投資残高の2023年時点での上位5か国及び日本について、投資先企業の業種区分(NAICSベース)の割合をみると94(第2-3-20図)、対外直接投資全体のうち、最大の割合を占めるのは事業活動を行っていない非金融持株会社(48.8%)であり、オランダ、ルクセンブルクは、特にその傾向が顕著である。日本については、非金融持株会社の投資残高がマイナスとなっているが、日本に所在する子会社が損失を出したことによる再投資収益の赤字、日本に所在する子会社から親会社への貸付フローが累積した結果などが要因として考えられる。
非金融持株会社を除くと、最大の対外投資先である英国については、金融業の割合が高く、カナダや日本については製造業の割合が高い。
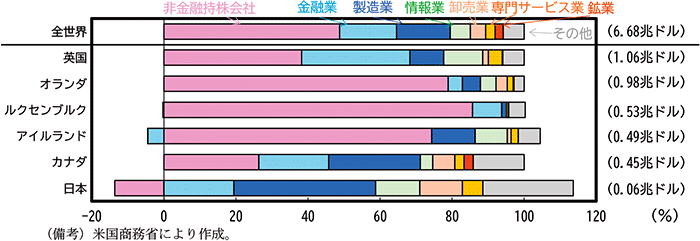
非金融持株会社の割合が高いオランダ、ルクセンブルクについては、優遇税制が充実していることや、広範な租税条約ネットワークを持つため、企業の活動地というよりもグローバル企業におけるタックスプランニング上の中継地点として、持株会社が置かれている。つまり、米国企業が税負担軽減のため、これらの国に知的財産権や利益を集中させている可能性がある。
このように、実質的な雇用や資本形成を伴わず、実態のない対外直接投資はファントムFDI(Phantom Foreign Direct Investment)と呼ばれ、2010年代前半にかけて急増してきた。2019年時点で世界の対外直接投資のうち、約40%がファントムFDIであり95、その大部分が米国の多国籍企業に起因する。特に、ルクセンブルクでは人口約60万人に対し、世界からの直接投資残高は約4兆ドルと推計されており、一人当たり約660万ドル(約9.6億円96)となっている97。
一方、アイルランドも非金融株式会社のシェアが高いものの、第1節で確認したとおり、アイルランドからは医薬品関連の輸入が多くみられており、医薬品産業に関わる実態のある事業会社(製造・販売・研究開発会社など)が多数存在する。それに加えて、アイルランドへの知的財産権使用料のサービス輸出額は、対外直接投資額では上回るオランダ、ルクセンブルクに比べて大きく、2024年では2国合計の3倍以上である(第2-3-21図、第2-3-22図98)。つまり、アイルランドにおける非金融持株会社は、統括会社として置かれた側面がありつつも、域内で稼ぐ知的財産権が集約された、アイルランド国内の製造・販売会社の親会社としての色合いが強い。したがって、非金融持株会社としては、
- 実態をもたせつつ統括会社としての機能を持たせる(特に医薬品):アイルランド
- 中継・利益移転に特化(ファントムFDI):オランダ、ルクセンブルク
といった住みわけがなされていると考えられる。
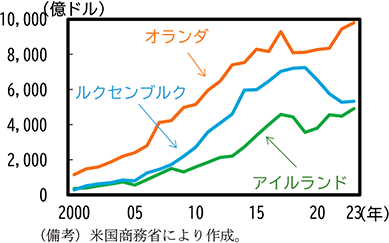
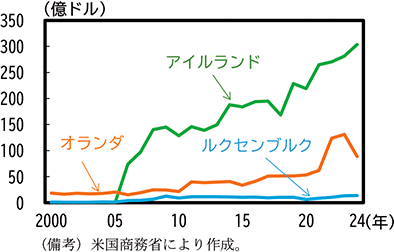
一方、対米直接投資残高の2023年時点での上位5か国について、投資先企業の業種区分(NAICSベース)の割合をみると99(第2-3-23図)、対米直接投資全体のうち、最大の割合を占めるのは製造業(41.2%)であり、金融業、卸売業が続く。上位5か国においても、カナダ以外は製造業が50%前後の割合を占めており、製造業への投資残高は日本が最大となっている。一方、カナダについては、金融業に属する企業への投資が多いことが特徴的である。
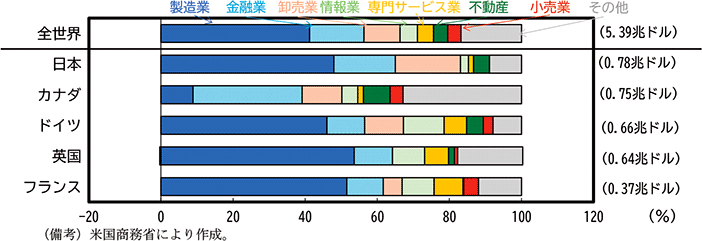
製造業については、第二次トランプ政権がアメリカ・ファースト政策に基づく通商政策や規制緩和、税制優遇措置等を通じて米国内へ回帰させることを目指している。その製造業への対外・対米直接投資残高(ストック)の金額とその業種別の内訳(2023年)を確認すると(第2-3-24図)100、対外・対米ともに製薬含む化学企業への直接投資が最も大きい。また、食料品やコンピュータ・電子機器については、対米直接投資が対外直接投資の半分程度にとどまる。
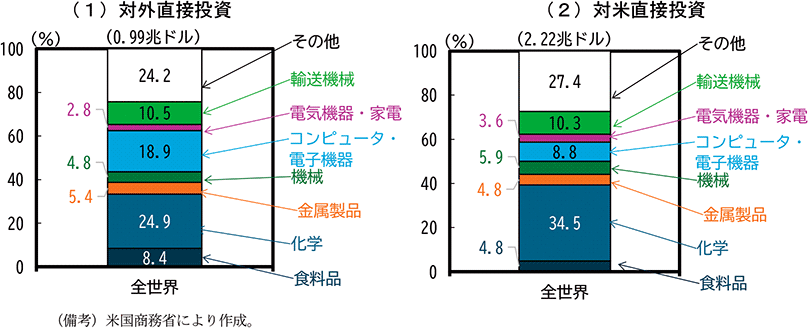
次に、直接投資の主要相手国との製造業に係る投資額とその内訳を確認していく。まず日本について(第2-3-25図)、対外直接投資は化学、コンピュータ・電子機器と続く。対米直接投資は43%を化学が占めており、輸送機械、コンピュータ・電子機器が続いている。輸送機械については、第1節でも触れたとおり自動車の対米輸出が多く、現地生産も進んでいることが示されている。
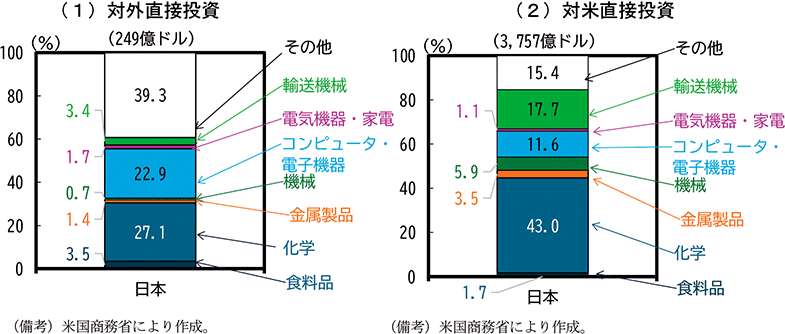
また、カナダについては(第2-3-26図)、対外直接投資は化学、コンピュータ・電子機器、輸送機械の順に多く、対米直接投資は、自動車を含む輸送機械が23.8%と最大で、化学、食料品の順に多い。自動車産業に関する分業体制が主にUSMCA地域内で構築されていることが、輸送機械の割合の高さに反映されている。また、食料品についても第1節で触れたように、カナダ・メキシコからの輸入額が多いことに関連しているとみられる。
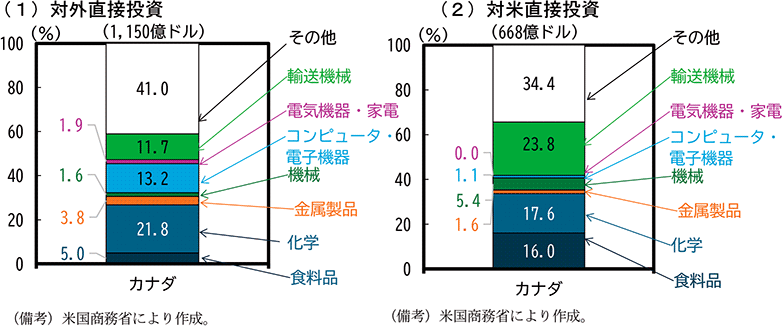
アイルランドについては(第2-3-27図)、対外直接投資は化学が52.8%と半分以上を占める。今までみてきたとおり医薬品関連の企業への投資が多いことが反映されているとみられるものの、前述のとおり大半は非金融持株会社に分類されている。なお、対米直接投資額は欠損値が多く、分析が困難である。
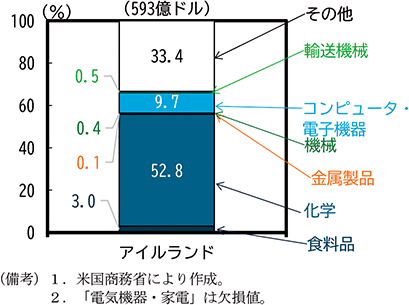
これまで対米直接投資をストック面(対米直接投資残高)から確認してきたが、対米直接投資の構造変化について理解を深めるため、フロー面についても確認する。第2-3-13図の説明でも触れたとおり、フロー面でみた対米直接投資は、
対米直接投資 = 株式資本(除く再投資)+収益の再投資+負債性資本
で構成され、これらの毎年の純流入額の推移を第2-3-28図に示す。収益の再投資については増加基調にある一方で、株式資本の純流入は2015年に頭打ちとなり、2021年から2023年にかけては3年連続で再投資収益が株式資本の純流入を上回った。これらの毎年のフローの年平均額は、2000年代に1,745億ドルであったが、2010年代には在米外資系企業の投資増加と既存の在米企業の収益増加の両方に起因し、2,712億ドルにまで増加した(第2-3-29図)。2020年代に入ってからも、平均で2,722億ドルと、堅調なペースで米国への直接投資の流入が進んでいる。ただし、その内訳については変化が生じており、2000年代には株式資本の純流入が1,745億ドル(80.4%)であったが、2020年代には1,273億ドル(46.8%)にまで低下した一方、収益の再投資は176億ドル(10.1%)から1,617億ドル(59.4%)に上昇した。つまり、既存の在米企業があげる収益が海外へ還流せず米国内で再投資される金額は増加する一方、新規の直接投資の流入は伸び悩んでいる。
また、第2-3-30図は、対米直接投資残高の2023年上位5か国について、2020年代累計の対米直接投資の純流入額を示している。日本やフランス、ドイツについては、2020年代に入り、新規の株式資本の流入は少ないにも関わらず、既存の米国子会社で得た利益の再投資による対米直接フローの積上げが大きく、資本の引上げも少ないため、対米直接投資残高の上位を維持していると考えられる。一方、カナダは、株式資本の純流入のシェアが全世界や他の上位国に比べ高く、新規案件が比較的多いと推察される。また、英国は負債性資本の引上げ(親子ローンの返済や債券の償還など)が他国に比べて多かったとみられ、第2-3-19図で示したとおり、直接投資残高全体に占める割合が低下した。
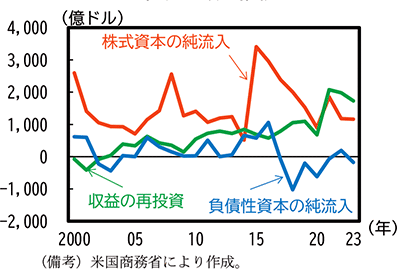
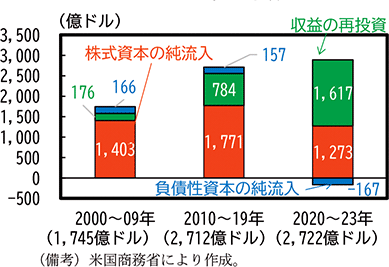
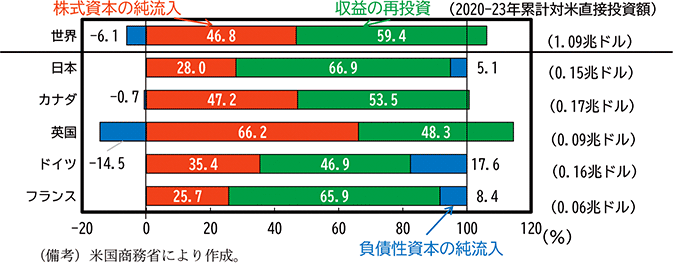
次に、毎年の資本流入額のうち、在米外資系企業が米国企業の買収・新規設立・拡大に費やした支出額の推移を確認する(第2-3-31図)。この統計は、米国商務省が在米外資系企業を対象に実施する調査から、米国企業の買収・新規設立・拡大に費やした支出を示しており、収益の再投資や負債性資本(貸付・借入金、債券投資残高)による直接投資残高の増減は含まれない。
米国への直接投資は、買収による投資がグリーンフィールド投資(事業拠点の新規設立・拡大)を大きく上回り、全体の9割以上を占める。2015年に買収による投資が増加しているが、これは主にアイルランド企業による医薬品企業の買収が急増したことに起因している(アイルランドの2015年投資額は1,759億ドル、前年差+2,326億ドル)。さらに2016~18年にかけても主にカナダや英国などから、3,000億ドル前後の対米直接投資が続いたことが、この時期に対米直接投資残高が増加した要因である。また、感染症拡大後の2021年にも大きく増加しているが、2022年から23年にかけては2年連続で減少しており、新規の直接投資が減速傾向にあることが示されている。
また、新規の対米直接投資全体に占める製造業の割合は、大型案件によってブレが生じるものの、直近では3年連続で減少しており、海外からの直接投資の対象企業に変化がみられる(第2-3-32図)。具体的には、2022年は情報サービス業、2023年は運輸・倉庫業や専門サービス業における直接投資額が多かったと報告されている101。
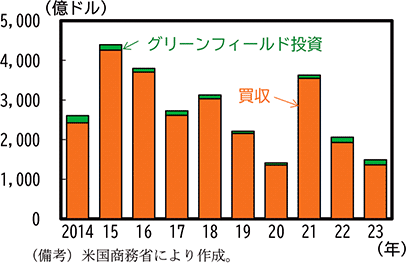
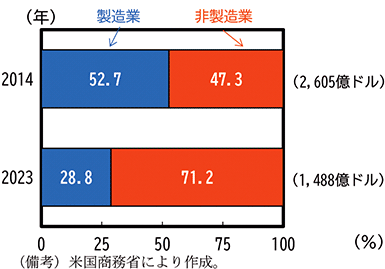
3.経常収支とISバランス、財政の関係
(米国の経常赤字は拡大)
ここまでみてきたとおり、米国では、財貿易の赤字が大きい一方、サービス輸出や直接投資が活発に行われている。財の貿易収支、サービス収支、所得収支を総じてみた経常収支をみると、2000年以降、貿易収支・第二次所得収支102の赤字額がサービス収支・第一次所得収支の黒字額を上回り、経常赤字となっている(第2-3-33図)。経常赤字額は、世界金融危機後の2010年代はおおむね横ばいで推移してきたものの、2020年以降、拡大傾向にある。要因として、感染症拡大後の回復期以降、貿易赤字が拡大したことに加え、第2項でみてきたとおり、第一次所得収支が縮小していることが挙げられる。
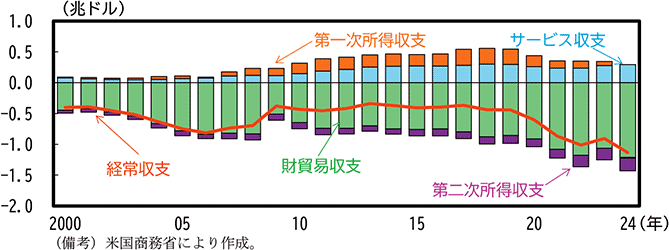
(政府部門が経常赤字と民間部門の貯蓄超過分を吸収)
海外からの資本流入にあたる経常収支は、一国全体の貯蓄超過分(投資・貯蓄バランスまたはISバランス)と概念上、一致する。式にすると以下のとおり。
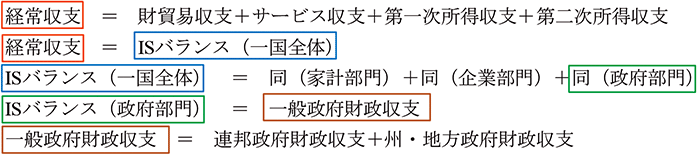
すなわち、財貿易収支、サービス収支、第一次所得収支、第二次所得収支の合計として定まる経常収支は、一国全体のISバランスに一致する。さらに、一国全体のISバランスは、米国の部門(家計部門、企業部門、政府部門)別のISバランスの合計として表すことができる。このうち、政府部門のISバランスは、一般政府の財政収支に相当する概念である。一般政府財政収支は、連邦政府財政収支、州・地方政府財政収支の合計である。
第2-3-34図は、米国の部門(家計部門、企業部門、政府部門)別のISバランスを示している。米国のISバランスは、民間部門の家計・企業部門は黒字、政府部門は赤字であり、その和である経常収支は赤字となっている。政府部門のISバランスは財政収支と同義であるが、歳出が歳入を上回り(財政赤字)、不足分は国債発行により賄っている。言い換えると、民間部門の貯蓄と経常収支の赤字の合計額は、政府部門の赤字と同額になるように同時決定されている。
2020年から21年は、政府による個人向け給付金や企業への支援などの財政出動により、民間部門(特に家計)の貯蓄が急増しISバランスの黒字額が拡大した一方、政府部門の赤字額が拡大した。2022年以降の感染症拡大後の景気回復期には、家計部門が積みあがった超過貯蓄を取り崩し、消費を増加させたことから、家計部門のISバランスの黒字額は縮小した。また、財政出動の終了と景気回復による税収増加によって、政府部門の赤字額も縮小した。2023年以降については、金利上昇による政府部門の利払い負担増加や税収の減少によって赤字額が拡大した一方、民間部門の黒字額は小幅に拡大している。
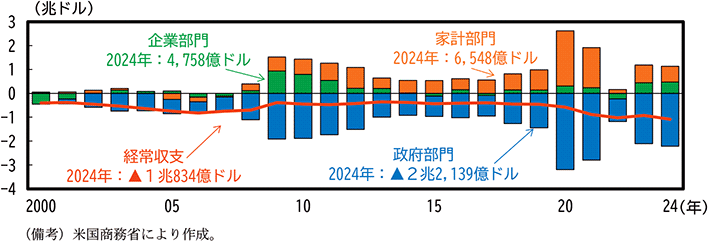
次に、継続的に赤字となっている政府部門のISバランス、つまり財政収支について、収入・支出別に内訳項目の推移を確認する(第2-3-35図、第2-3-36図)103。
まず、一般政府の収入については、個人税(所得税等)が税収の半分以上を占め、最大の収入項目となっている。感染症拡大後の2022年には、個人所得の増加に伴い一時的に急増したものの、2023年には減少に転じた104。また、感染症拡大以降の企業収益の増加によって法人所得税は増加している。
一方、一般政府の支出については、2015年から経常移転(社会保障給付、失業保険等)が消費支出(教育・防衛関連支出、政府職員への給料等)を上回り、最大の支出項目となっている。また、利払費による支出が足下の金利上昇に伴って増加している。これらの支出項目が主因として、政府部門のISバランス(財政収支)は赤字が続いている。他方、補助金については、2020年、2021年に急増しているが、これは給与保護プログラム(Paycheck Protection Program:PPP)105を始めとする感染症拡大期間における経済対策として実施された支出が増加したためである。
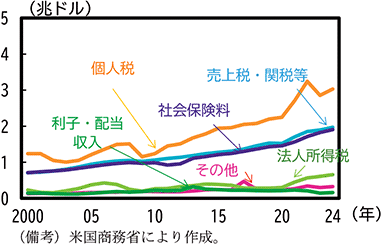
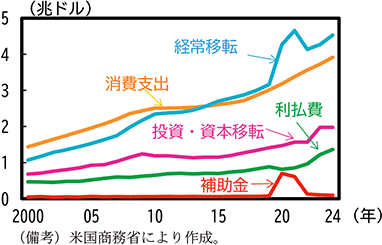
(政府部門の赤字)
次に、一般政府の財政状況の詳細を確認する。
一般政府の財政収支の推移をみると(第2-3-37図)、2001会計年度106以降、連邦政府の財政赤字拡大によって、一般政府の財政赤字は拡大しており、一般政府債務残高は増加している(第2-3-38図)。ただし、経済成長と物価上昇によってGDPは名目値で上昇したため、2022会計年度以降、一般政府債務残高対GDP比は低下している。
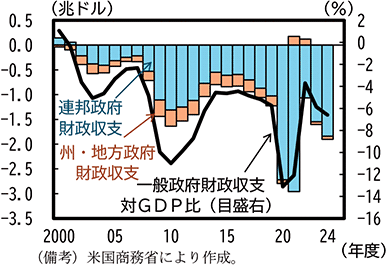
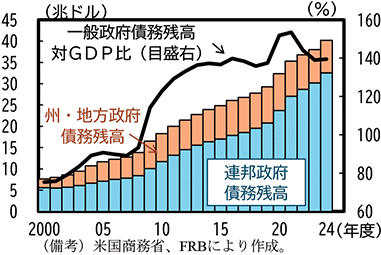
ここで、一般政府の財政赤字の主因となっている連邦政府の財政収支の推移を歳入・歳出の面からみると107(第2-3-39図)、連邦政府の財政収支は、1998会計年度から2001会計年度まで黒字だったが、2002会計年度以降、赤字になっている。それ以降、世界金融危機や感染症拡大期間の大規模な財政支出の拡大によって、赤字が大幅に拡大する局面もあり、財政赤字は継続している。直近の財政赤字額は、2022会計年度:1.4兆ドル、2023会計年度:1.7兆ドル、2024会計年度:1.8兆ドルと2年度連続の増加となっている。結果として、連邦政府の債務残高は増加傾向にある(第2-3-40図)。ただし、一般政府と同様、名目GDPが物価上昇もあり債務残高より大きく増加したため、2022会計年度以降、一般政府同様、連邦政府債務残高対GDP比は低下している。
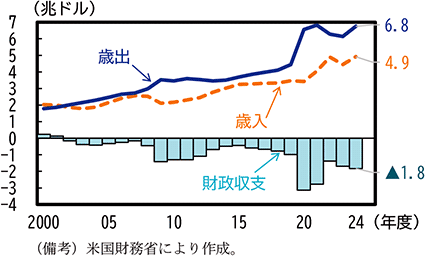
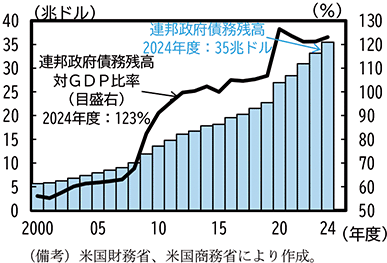
次に、連邦政府の歳入・歳出の内訳項目別に確認する(第2-3-41図)。2024年度における連邦政府の歳入は4.9兆ドル、歳出は6.8兆ドルであり、1.8兆ドルの財政赤字となっている。歳入・歳出の内訳をみると、歳入は大きい順に個人所得税、社会保障税等、法人所得税となる一方、歳出は社会保障年金(連邦老齢・遺族・障害年金など)、保健(メディケイド、オバマケアの税額控除など)、利払費、メディケア、国防費、所得保障(連邦政府職員・退役軍人年金、SNAP108など)と続く。近年は、高齢化に伴う社会保障費の増大や、債務残高拡大・金利上昇による利払費の増加(名目GDP比で3.1%)が、財政赤字の拡大に寄与している。
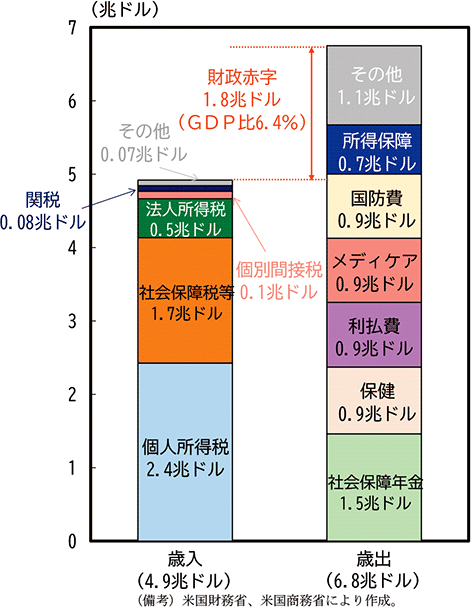
長期金利の動向をみると、FRBによる利上げサイクルが終了した2023年半ば以降、10年債利回りは4.5%前後で推移している(第2-3-42図)。2023年9月に10年債利回りが4.5%に到達したが、これは2007年10月以来であった。利下げが行われた2024年後半にかけては、全ての年限で利回りは一時低下したものの、経済が堅調さを維持していたことで年末にかけて上昇に転じた。2025年にかけては、利下げ期待によって短期金利が低下する一方、長期金利は高止まりを続けており、より長い年限の30年債は上昇した。
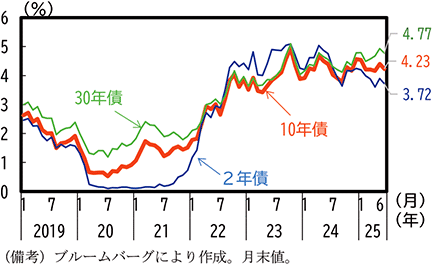
(財政調整法の審議)
2025年7月4日、トランプ大統領が最重要法案と位置づける財政調整法109「一つの大きな美しい法案(One Big Beautiful Bill Act)」が成立した。同法案はまず、下院で作成された法案が5月22日に下院で可決された。その後、上院で修正された法案が7月1日に上院で可決され、7月3日に同内容の修正案が下院でも可決された。そして、7月4日にトランプ大統領が署名したことにより成立した。
財政調整法の主な要素としては、2017年TCJA(いわゆるトランプ減税)の恒久化、チップ・残業代非課税などの新たな減税策、メディケイド及びSNAPにおける給付要件の厳格化(扶養家族のいない健康若年層に対する就労要件復活)、EV・エネルギー関連の税額控除撤廃等が含まれ、トランプ大統領の公約が盛り込まれている(第2-3-43表)。
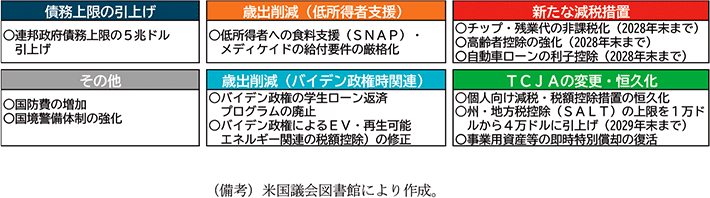
財政調整法による財政への影響について、議会予算局が推計を行っており、2025~34会計年度累計の財政収支に対する影響を第2-3-44図に示す。同法により、10年間で累計3.4兆ドル財政赤字が拡大すると推計されている110。
減税措置のうち、2017年TCJAにおいて2025年末に期限が切れる措置(個人所得税率の引下げ等)の変更・恒久化によって4.6兆ドルの歳入減・歳出増が見込まれる。一方で、新たな減税(チップ・残業代の非課税等)は0.7兆ドル程度と比較的少額であり、これは多くが期限付きの措置であることも特徴の1つである。民間シンクタンクの「責任ある連邦予算委員会」によると、これらの期限付き措置が全て恒久化されると、10年間で財政赤字は累計4.8兆ドルになると推計されている111。
他方、SNAP・メディケイドの低所得者支援に関する厳格化や、バイデン政権時に導入されたEV・再生エネルギー関連の税額控除の廃止等、様々な歳出削減策が盛り込まれている。
また、議会予算局は財政調整法による利払費の増加分について、下院法案時点では10年間で合計5,510億ドルになると推定しており、最終版についても同等の影響が見込まれる。
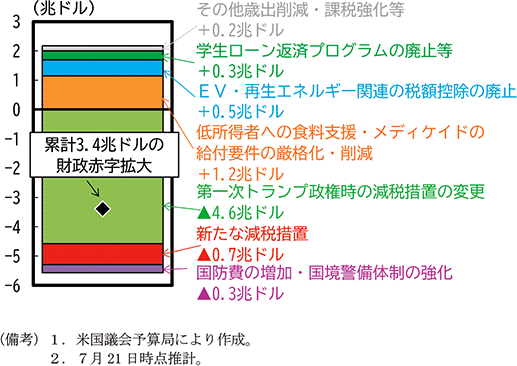
一方、議会予算局はトランプ政権の関税率引上げが財政収支に与える影響についても試算を行っている(第2-3-45表)。これによると、推計で仮定された関税率(対中関税や自動車関税等)が今後引き下げられない場合、10年間の累計で2.8兆ドル関税収入が増加するとされており、財政調整法による財政への影響を一部相殺することとなる。
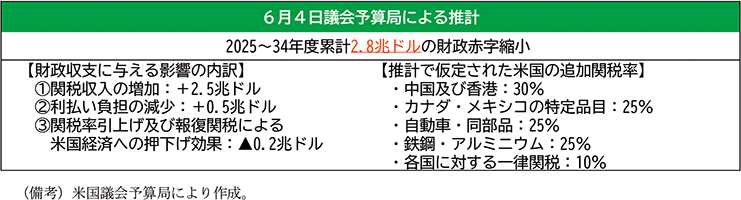
同法による連邦債務残高への影響を第2-3-46図に示す。連邦政府債務上限は36.1兆ドルから5兆ドル引き上げられ、41.1兆ドルとなる。2025年6月末時点で連邦政府債務残高は36.2兆112ドルであり、既に引上げ前の連邦政府債務上限に達しているため、デフォルトを一時的に回避するための特別措置(公務員年金への投資停止など)により資金繰りを維持している。
議会予算局による2025年1月のベースライン推計に財政調整法による毎年の財政収支への影響を加算した場合(7月21日推計、利払い負担増加分は含まれない)、引上げ後の債務上限41.1兆円に債務残高が達するのは2027年前半頃であると見込まれる。
2034会計年度末においては、同法の下で連邦政府債務残高は59.8兆ドルとなり、GDP比では141%になる。
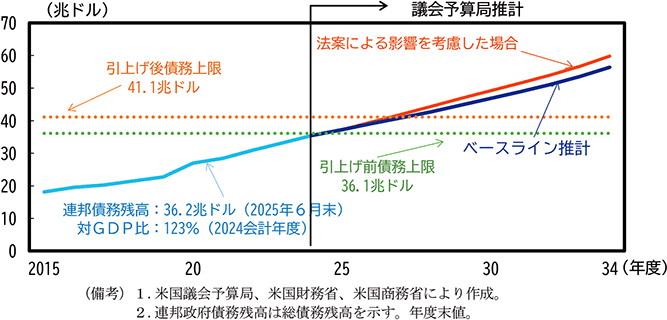
以上のとおり、同法により連邦政府債務残高が更に増加することが見込まれ、これまで以上に国内外の投資家による米国債の購入が必要となることを意味する。一方、現政権による保護主義的な通商政策や諸外国のデジタルサービス税等に対する報復措置などの議論は、内外の投資家による米国債離れを誘発し、それによる金利上昇への懸念も生じさせている。金利上昇による利払費の増加、それに伴う更なる債務の拡大と負のスパイラルに陥る可能性も否定できない。第二次トランプ政権が推進する関税措置による財政赤字・経常赤字への影響とともに、それに対するマーケットの反応も注視していく必要がある。
(米国債をめぐる環境の変化)
これまでみてきたとおり、米国は政府部門の債務によって経常赤字が支えられているが、この構造が持続してきた背景には、海外からの米国債への需要の堅調さがある。米国に対し貿易黒字である諸外国は、米国へ商品を輸出する代わりに米ドルを得る。さらに、米ドルは基軸通貨であり、世界全体での多くの貿易は米ドル建てで決済されるため、米ドルの需要は他通貨に比べて高い。米ドルの余剰資金は投資へと向けられるが、その際、米国は世界最大の債券市場であり流動性が高く市場も厚いことから、デフォルトリスクが小さい安全資産として米国債券が選好されやすい。加えて、各国中央銀行は基軸通貨のドルを外貨準備として保有する必要があるため、米国債をドルの運用手段として大量に保有している。つまり、ドルが基軸通貨である限り、海外からの安全資産としての需要によって、米国債は安定的に消化される状況が続いていると言える。このように、米国は世界の基軸通貨としてのドルの役割を大いに活用し、海外からの直接・証券投資を呼び込むことで国内経済が成長を続けてきた。直接投資残高での議論でも触れたように、これも基軸通貨ドルの法外な特権(exorbitant privilege)の一側面である。
しかし、この構造の持続性には中長期的な潜在リスクがあり、債務の拡大によって米国債への信任が毀損する可能性がある。実際、2011年8月に大手格付け会社であるS&Pグローバル・レーティグスにより、米国債格付けは「AAA」から「AA+」に引き下げられた。次いで2023年8月にはフィッチ・レーティングが「AAA」から「AA+」へ引下げを決定、そして2025年5月にはムーディーズも「Aaa」から「Aa1」に引下げを行い113、米国債は主要格付け機関3社による最高位の格付けを失った(第2-3-47表)。今後、更なる引下げがなされた場合、金利の上昇など金融市場に影響を与える可能性がある。
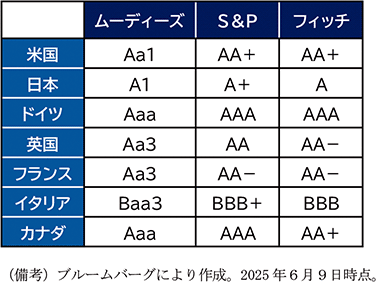
議会予算局の長期予測によると、政府債務の対GDP比は今後も拡大を続け、2055年には169%にまで増加する見込みである(第2-3-48図)。さらに、このような財政拡大局面ではクラウディングアウト114によって民間部門の投資が抑制されてしまう可能性もある。
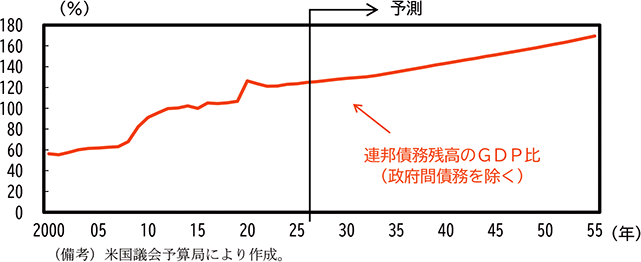
近年では、海外による米国債の保有比率は低下傾向にある。資金循環統計で米国債の保有部門を確認すると(第2-3-49図)、かつては海外部門が最大の保有部門であり、全体の半分程度を占めていたが、2024年末には32.6%まで減少し、米国内の金融機関部門を下回った。なお、金融機関部門の中ではマネー・マーケット・ファンド(MMF)が最大の保有主体となっている。
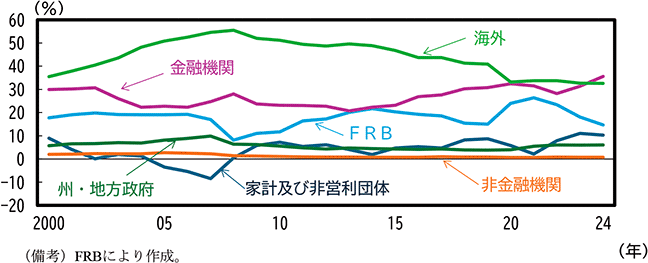
海外部門の国別の保有比率の上位5か国(2024年末時点)の推移をみると(第2-3-50図)115、日本は現在も世界最大の米国債保有国であるが、その比率は、2000年台前半の30%台から低下し、2024年末には12.4%となっている。また、一時最大の保有国であった中国についても2010年頃から低下してきており、2025年3月には2002年6月ぶりに英国の保有比率を下回り3番目となった。日本や中国では外貨準備として米ドルを保有するため、政府当局が安定的に米国債の購入を続けてきたが、この2か国の保有割合が低下傾向にある。一方、英国やルクセンブルクなどの保有割合が緩やかに上昇している。また、新興国が対米貿易黒字を計上していることにより、これら5か国以外の割合も大きく上昇し、米国債はより多くの国に分散して保有されるようになってきていることが分かる。
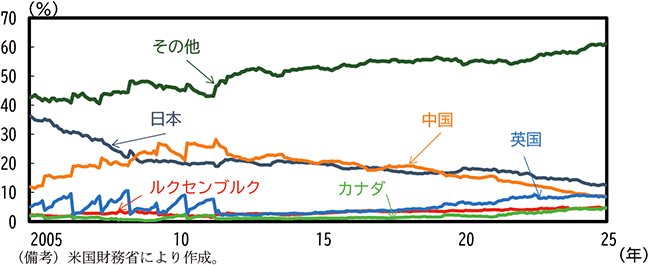
このように、米国債の購入主体には変化が生じつつある。連邦債務残高が今後も拡大を続けるとみられる中、今後、基軸通貨としてのドルの信認が揺らぐようなことが生じることがあれば、米国内の資金不足分を海外から安定的にファイナンスできる構造の継続が困難になる可能性もあることには留意する必要がある。
コラム5 基軸通貨ドルの持続性と1970年代後半~プラザ合意まで
米ドルが世界の基軸通貨であることによって米国が享受してきた「法外な特権(Exorbitant Privilege)」について、以下3点について触れてきた。
- 米ドルの高い購買力による輸入の拡大(経常赤字(特に貿易赤字)の維持)
- 諸外国が財・サービス貿易で得た米ドルの安定投資先として、米国債への投資拡大(財政赤字の維持)
- 諸外国から低コストで調達した資本を使い、諸外国へ高収益率で運用が可能
経常赤字や財政赤字はその国の通貨の信認低下を招き、資本流出や金利高騰を招く可能性があるとされる。一方で米国の場合、世界各国が外貨準備や決済に米ドルを必要とするため、低リスクの投資先として米国債の需要は強い。そのため、経常赤字・財政赤字(「双子の赤字」)を維持しつつ、低金利で資本を調達し続けることが可能であった116。
このように経常赤字・財政赤字を起点に世界へ米ドルが供給されてきたが、米ドルが基軸通貨であるとしても、この「双子の赤字」は無制限に拡大できるものではなく、行き過ぎると信認が毀損する可能性を内包している。これは「トリフィンのジレンマ117」と呼ばれ、「双子の赤字」が政府当局や市場で注目される局面とともに議論されてきた。
過去、これらの赤字拡大がドルの信認低下を引き起こした例として、1970年代後半から1985年のプラザ合意にかけての動きが挙げられる(図1、図2、図3)。1971年に金本位制が終焉を迎え、各国通貨が変動相場へと移行する中、米ドルを始めとする米資産への信認は低下しつつあった。また、1970年代半ばにかけてベトナム戦争に伴う多額の国防費を支出しており、財政赤字拡大・物価上昇の局面にあった。加えて1970年後半に2度のオイルショックを経験し、消費者物価上昇率は一時前年比14.8%(1980年3月)まで上昇した。その結果、第一次オイルショック後の1973~76年頃には、株式市場が軟調な中でも米ドル、米国債は売られ続けた(トリプル安)。
経済がスタグフレーションとなる中、ボルカー議長のFRBは強力な金融引締め政策を取ったことにより金利が急騰、それによって諸外国から米国への資本流入は加速した。それに伴うドル高によって米国の輸出競争力は低下する一方、輸入が増えたことにより、経常赤字は1977年に143億ドル、1978年に151億ドルと2年連続で過去最大を更新した。
1981年に共和党のレーガン大統領が就任すると、大規模減税と国防費の増加により財政赤字は更に拡大し、1983年に2,078億ドル(名目GDP比5.9%)となった。インフレも鎮静化されず、ドル高が維持される中で経常赤字は1983~85年にかけて一層増加することとなった。この頃から米国の「双子の赤字」が米国のみならず世界経済の大きなテーマとして議論を呼び、基軸通貨ドルの持続性などグローバル不均衡がもたらす影響についての懸念も高まっていった。
最終的には1985年、ベーカー財務長官の下でG5c(米国・日本・ドイツ・フランス・英国)においてプラザ合意がなされ、協調介入により為替相場が調整(ドル安)され、基軸通貨ドルがもたらすグローバル不均衡は一時的に是正された。財政収支への影響は限定的だったものの、経常赤字は1987年をピークに縮小し、1991年には経常黒字に転じた。
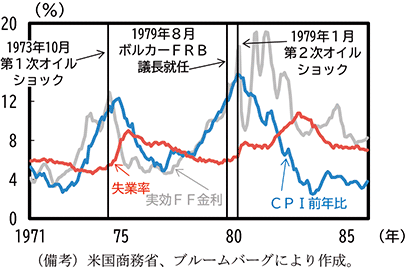
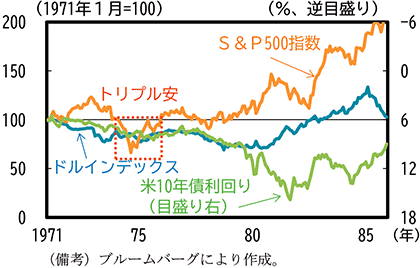
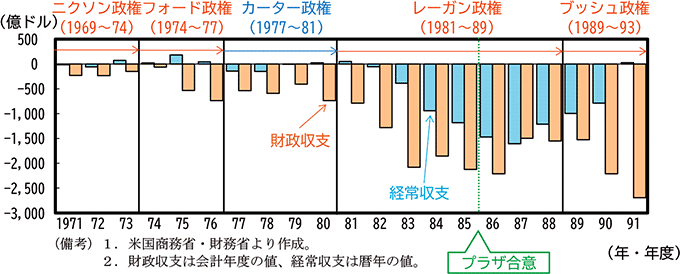
現代に立ち返ると、2017年の第一次トランプ政権におけるTCJAの成立、2020年、2021年の感染症拡大期間の経済支援などによって財政赤字は拡大傾向を強めており、ドル高が維持される中で貿易赤字は拡大が顕著である。こうした中、保護主義的な色彩が強い第二次トランプ政権が誕生して以降、グローバル不均衡への議論が再び活発化しており、更には基軸通貨ドルがもたらす構造の持続性(トリフィンのジレンマ)についても議論が広がっている。足下では、前述のとおり、米国債の購入主体の変化、直接投資収益の伸び悩みなど、基軸通貨ドルがもたらす「法外な特権」について構造変化の可能性があることに留意しておく必要がある。
他方で、ドルに代わる基軸通貨を模索する動きも出ている。BRICSでは新通貨構想が推進されており、また、人民元での国際決済システム(CIPS:Cross-Border Inter-Bank Payment System)が2015年に開始され、日本を含む先進国の銀行も参加している。他にも、各国・地域の中央銀行が発行する中央銀行デジタル通貨(CBDC:Central Bank Digital Currency)の議論が進み、一部の国ではCBDCを相互に取引するシステムが実験段階にある。基軸通貨ドルの持続性をめぐる議論とともに、国際的な決済システムの構造変化が起き始めているといえる。

