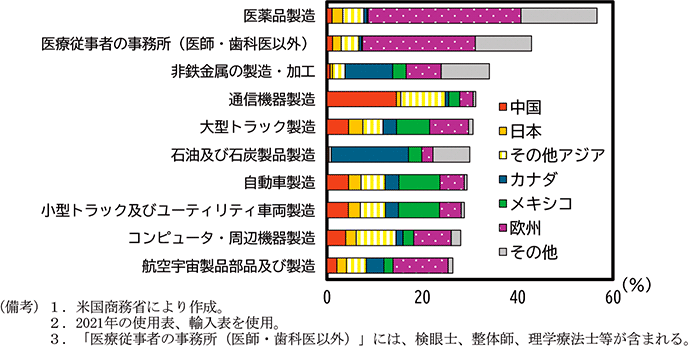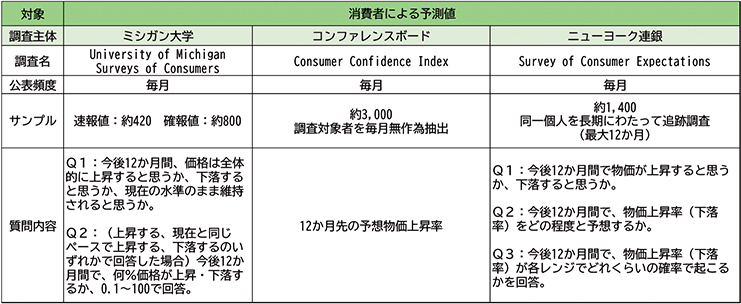第2章 米国の貿易・投資構造(第2節)
第2節 米国の通商政策と通商政策が財貿易・物価に与える影響
トランプ大統領は、2025年1月20日の就任直後から矢継ぎ早に大統領令に署名を行い、第一次トランプ政権と比較してより幅広い国及び品目に対して追加関税を課してきた。本節では、まずトランプ大統領が就任以来行ってきた通商政策42を概観した上で、米国の関税措置及びそれに対する各国の対応が米国の財輸出入に与えた影響、そして、今後の物価動向に与える影響を議論する。
1.米国の通商政策の動向
以下では、第二次トランプ政権の通商政策について第一次政権と比較しつつ概観する。
(法的根拠)
第一次政権と第二次政権のいずれにおいても、特に通商政策について、発足後の1か月間、迅速かつ広範な政策展開を行っているが、第二次政権が第一次政権に比べより迅速に関税措置を実施することができたのは、関税措置の法的根拠の違いにも起因する(第一次、第二次政権における主たる関税措置の法的根拠の比較は第2-2-1表を参照)。第一次政権では、関税発動の根拠として主に以下の法律が用いられた43。
- 1962年通商拡大法232条(安全保障): 特定製品の輸入が米国の安全保障を脅かす場合、商務長官による調査を経た上で、大統領は関税引上げ等、輸入に規制を課す権限が付与される44。
- 1974年通商法301条(不公正貿易慣行): 相手国の不公正な貿易慣行等が米国のビジネスに負担や制限を加える場合、調査を経た上で、米国通商代表部(USTR)は関税引上げ等の措置を取ることができる45。
1.について、第一次政権では、鉄鋼やアルミニウムの輸入に対して追加関税が発動された。また、自動車・同部品についても調査は実施されたが、関税発動には至らなかった。2.について、第一次政権では主に中国に対する関税措置で用いられた。
第二次政権では、関税発動の法的根拠として、第一次政権と同様の法律1.1962年通商拡大法232条(安全保障)(以下「232条」という。)に加えて、国際緊急経済権限法(IEEPA46)が用いられた。IEEPAにおける「国家緊急事態」とは、大統領が「米国の安全保障、外交政策、または経済に対する、その全部または実質的な部分が米国外に起因する、異常かつ重大な脅威」が存在すると判断し、これに関する「国家緊急事態」を宣言した場合に、大統領にその脅威に対処するための権限を付与するものである47。第二次政権では、IEEPAを根拠にして、4月5日から全ての国に対して10%の追加関税を課した48(詳細については後述)。
(関税発動までのプロセス)
第一次トランプ政権における通商政策は、主に特定の国や品目を対象とした関税措置であった。前述のとおり、その多くは、232条や1974年通商法301条(不公正貿易慣行)といった法令に基づいて実施された。これらの条項に基づいた関税の発動には、USTRや商務省による調査、公聴会、関係省庁との協議といった複雑なプロセスが必要であり、最終的な措置の決定及び実行までには一定の期間を要した。
一方、第二次トランプ政権の通商政策は、IEEPAを法的根拠とし、他国との貿易赤字や輸入依存状態などを「国家緊急事態」と位置づけることで、より包括的な品目や国に対し、迅速に関税措置が実施された。なお、232条に基づく鉄鋼・アルミニウムや自動車・同部品への関税措置については、第一次政権時に実施された調査結果やその後の状況変化を根拠とすることで、法に基づく協議プロセスを省略し、前回よりも迅速に関税措置を実施・修正している。
また、第二次政権では議会の承認が不要な大統領を用いて速やかに各省庁へ各種政策の実施を指示している。第一次政権では政権発足後1か月の間に署名した大統領令49の数が13であるのに対し、第二次政権では70であり、発足直後から集中的に大統領令に署名している。第二次政権では、関税発動の法的根拠の変更に加え、大統領令を用いることで、従来に比べ、迅速に関税措置を含む通商政策を実施することが可能となっている。
以下では、トランプ第二次政権の通商政策を大きく(1)品目別の関税、(2)国別の関税、(3)「相互関税」の3つに分けて、内容を概観する。
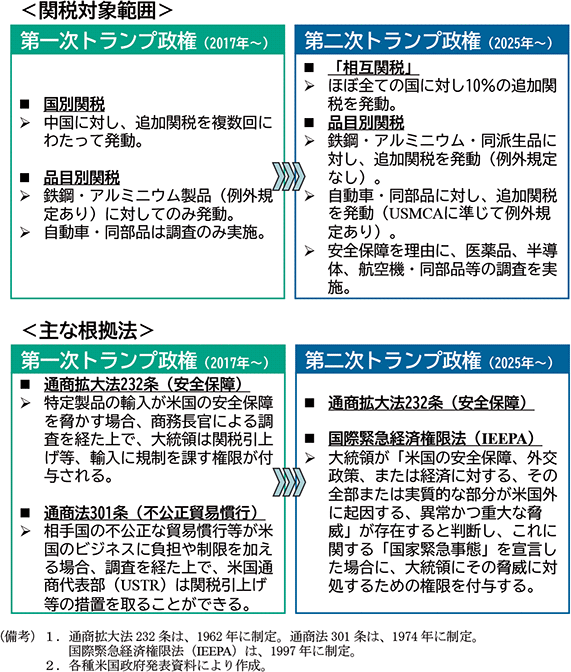
(1)品目別の関税
(鉄鋼、アルミニウムに対する追加関税)
2025年2月10日、トランプ大統領は、鉄鋼及びアルミニウムの輸入が米国の安全保障を脅かしているという理由に加え、米国の鉄鋼及びアルミニウムの国内産業を保護することを目的として、3月12日以降、鉄鋼・アルミニウムの輸入に一律で25%の追加関税を課す大統領令に署名した。当該大統領令では、第一次トランプ政権下で導入されたアルミニウムに対する10%の関税率を25%に引き上げるとともに、鉄鋼・アルミニウムに対する既存の例外措置を全て失効させた。また、鉄鋼・アルミニウムの主要な川下製品を含めるため、第一次政権で導入した措置と比較して追加関税の対象となる鉄鋼・アルミニウムの派生品の範囲を拡大した50(第2-2-2表)。
その後も派生品の範囲は段階的に拡大された。4月2日には、米国商務省産業安全保障局(BIS)が、4月4日以降、アルミニウムの派生品として、ビール及び空のアルミニウム缶51を新たに関税対象に追加すると発表した。さらに、6月16日には、鉄鋼の派生品として、冷蔵庫、冷凍庫、食器洗い機、電気調理器、洗濯機、乾燥機等の白物家電が6月23日以降、新たに関税対象に追加されることが発表された。
また、6月3日にトランプ大統領が署名した大統領令において、6月4日以降、鉄鋼・アルミニウムに対する追加関税率は25%から50%に引き上げられた。
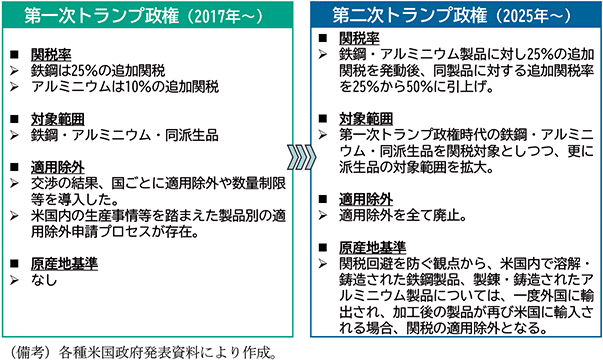
(自動車・同部品に対する追加関税)
2025年3月26日、トランプ大統領は、232条等に基づき、自動車(完成車(乗用車、小型トラック))の輸入については4月3日以降、自動車部品の輸入については5月3日以降、25%の追加関税を課す大統領令に署名した。ただし、USMCAの対象となる自動車(完成車)については、米国外部分(その価値全体から米国内で取得、完全に生産または実質的変更が加えられた価値を除いた部分)のみが追加関税の対象となることとしている。また、USMCAの対象となる自動車部品については、米国外部分のみに課税する手続きが定められるまでは、追加関税の対象とならないこととしている(第2-2-3表)。
また、4月29日に署名した大統領令において、米国で組み立てられた自動車の価値の15%に相当する自動車部品に対する関税を1年間減免し、その後1年間は当該価値の10%に相当する額を減免することを定めた52。
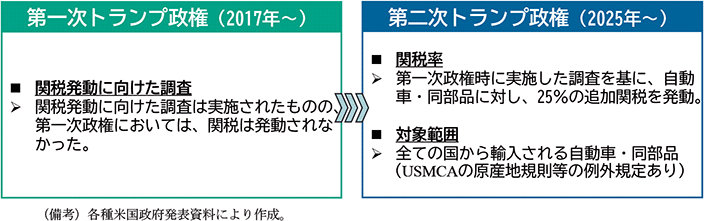
(安全保障を理由とした品目別調査)
なお、上記関税措置のほか、232条に基づき、米国の安全保障に及ぼす影響を判断するための調査として、半導体、医薬品、銅、木材、重要鉱物、民間航空機・同部品、中型・大型トラックの輸入について相次いで調査が行われている。今後、これらの品目に品目別関税が課される可能性がある(詳細は後述)。
(2)国別の関税
ここでは、米国と中国、カナダ、メキシコ、英国とのそれぞれの貿易構造を確認し、中国、カナダ、メキシコに対する国別の関税の内容及び英国との貿易合意の内容を確認する。
(中国との貿易)
米国と中国間の貿易構造を確認すると(第2-2-4図)、中国向け輸出では、「穀物、飼料等」が多い53。また、「医薬品、医療機器」、「原油・天然ガス」、「民間航空機・同部品」、「半導体」などの輸出も多い。
中国からの輸入では、「携帯電話、その他家庭用品」、「コンピュータ・同周辺機器」のほか、「衣料品・履物」、「家具、家電」など消費者にとって身近な製品が多く中国から輸入されている。
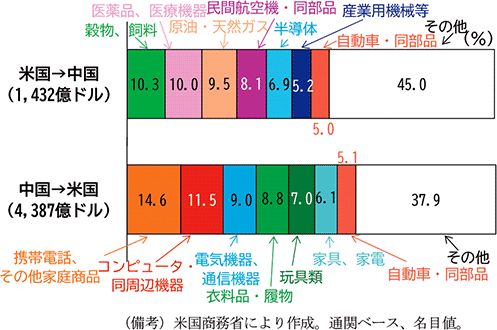
(カナダとの貿易)
米国とカナダ間の貿易構造を確認すると(第2-2-5図)、米国からカナダへの輸出は、「完成車」、「飲食料品」、「自動車部品」が多い。一方、カナダからの輸入では、「原油・天然ガス」、「飲食料品」、「完成車」、「自動車・部品」、「ボーキサイト、アルミニウム」が多い。
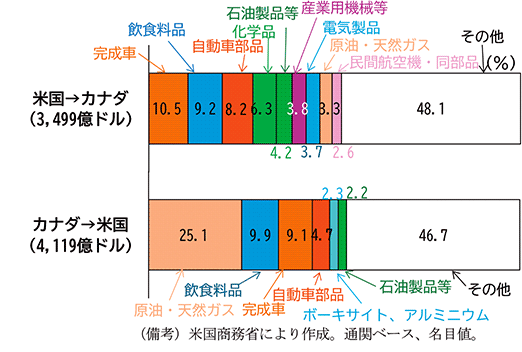
(メキシコとの貿易)
米国とメキシコ間の貿易構造を確認すると(第2-2-6図)、米国からメキシコへの輸出は、「電気機器、通信機器」、「飲食料品」、「金属・鉱物等」が多い。一方、メキシコからの輸入では、「完成車」、「自動車部品」、「コンピュータ・同周辺機器」が多く、この3分類で全体の約5割を占める。
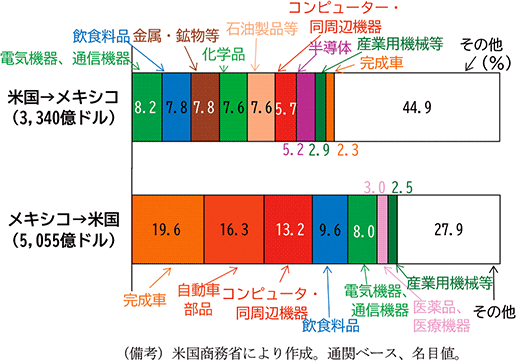
(英国との貿易)
米国と英国間の貿易構造を確認すると(第2-2-7図)、米国から英国への輸出は、「非貨幣用金54」、「原油・天然ガス」、「民間航空機・同部品」の輸出が多い。一方、英国からの輸入では、「完成車」、「自動車部品」、「民間航空機・同部品」、「マテリアル・ハンドリング機器55」などが多い。
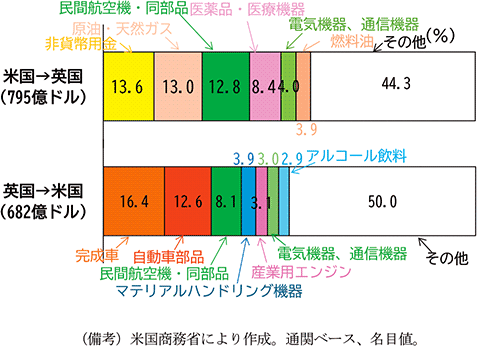
(中国との通商関係)
2025年2月1日にトランプ大統領は、フェンタニルなどの違法薬物がもたらす脅威をIEEPAにおける「国家緊急事態」と認定した上で、中国がこうした違法薬物の米国への流入を阻止するために必要な対応を行っていないとし、2月4日から危機が緩和されるまでの間、中国からの輸入品に10%の追加関税を課すとした大統領令に署名した。
上記の動きを受け、2月4日、中国は、米国から輸入される石炭、天然ガスについて15%、原油、農業機械、大型自動車、ピックアップトラックについて10%の追加関税を課すことを発表し、2月10日に発効した。
その後、トランプ大統領は3月3日、中国が違法薬物の問題の緩和に十分な措置を講じていないとして、2月1日の大統領令(10%の追加関税)を改正し、3月3日から20%の追加関税を課す大統領令に署名した。これを受け、中国は、3月4日、米国の追加関税措置を理由とする米国からの農林水産物輸入に対する追加関税措置56を発表、同措置は3月10日に発効した。
その後、トランプ大統領は後述する「相互関税」の一環として、更に中国からの輸入品に対して34%(3月までの追加関税と合わせて累計54%)の追加関税の導入を発表した。これに対して中国は即座に米国からの全ての輸入品に対して34%の追加関税を課すことを発表し、以降4月上旬に米中間で関税率引上げが繰り返された(第2-2-8表)。4月11日以降は、米国の対中追加関税率が累計145%、中国の対米追加関税率が125%と高率の関税水準が維持されることとなった。
こうした高い水準の関税率が米中間の貿易、ひいては世界経済に大きな影響を与えることが想定される中で、5月12日にスイスのジュネーブで米中の閣僚級協議57が行われ、相互に関税率を引き下げること等に合意した。これに基づき、5月14日以降、米国の対中追加関税率は累計54%に引き下げられた上で、90日間(8月半ばまで)は更に累計30%まで引き下げられることとなった。同様に、中国の対米追加関税率も34%に引き下げられた上で、90日間は更に10%まで引き下げられることとなった。
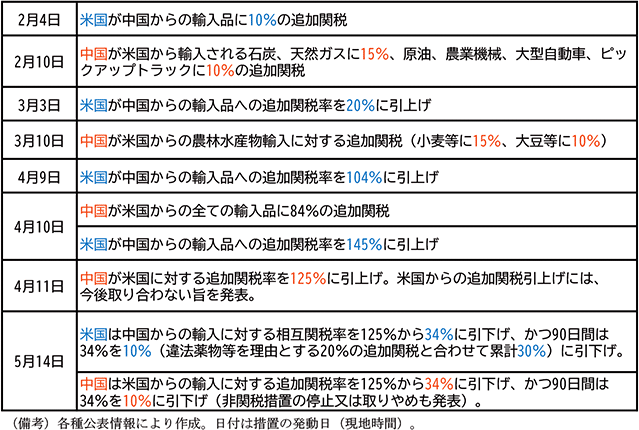
(カナダ、メキシコとの通商関係)
2025年2月1日、トランプ大統領は、不法移民やフェンタニルなどの違法薬物がもたらす脅威をIEEPAにおける「国家緊急事態」と認定し、2月4日から危機が緩和されるまでの間、カナダとメキシコからの輸入品に25%の追加関税(カナダから輸入されるエネルギー資源は10%)を課す大統領令に署名した。
その後、トランプ大統領は、メキシコのシェインバウム大統領、カナダのトルドー首相(当時)との電話会談等を行った結果、2月3日に、2月1日の大統領令を改正し、関税措置を3月4日まで停止する大統領令に署名した。
当該関税措置は、3月4日に発効されたものの、3月6日、トランプ大統領は、USMCAの適用を受ける財(原産地規則等を満たすもの)を追加関税の適用除外とするとともに、肥料等に用いられる塩化カリウムに対する追加関税率は10%に引き下げる新たな例外措置を3月7日に設けるとした大統領令に署名した。
こうした米国の追加関税措置を受け、3月3日、カナダのトルドー首相(当時)は対抗措置として、米国からの輸入品総額1,550億カナダドルに対する25%の報復関税(300億カナダドル分は3月4日から、1,250億カナダドル分は3月25日から発動)を発表した。うち、300億カナダドル分の報復関税は3月4日から実際に発動されたが、米国側の関税措置の見直しを受けて、残りの1,250億カナダドル分については発動が見送られた。
この他、カナダは品目別関税に対しても対抗措置を導入した。3月12日の米国による鉄鋼・アルミニウム関税の引上げを受け、3月13日以降米国から輸入される鉄鋼、アルミニウム製品及びその他の財合計298億カナダドル分に対して、25%の追加関税を導入した。更に、4月3日の米国による自動車関税の引上げを受け、4月9日以降、米国から輸入されるUSMCAの対象とならない自動車(完成車)及びUSMCAの対象となる自動車(完成車)のうちカナダ、メキシコ外の部分に25%の関税を課している。
対照的に、メキシコのシェインバウム大統領は、3月4日の記者会見で、報復関税を含む対抗措置を3月9日に発表すると発言したものの、米国側の関税措置の見直しを受けて、3月6日には対抗措置発表の見送りを表明した。これ以降、メキシコは米国の関税措置に対する報復関税措置は取っていない。
(英国との貿易交渉)
第二次トランプ政権が相次いで導入した品目別、国別の関税措置や後述の「相互関税」を受けて各国が米国との通商協議を行う中、5月8日には英国が米国との貿易合意に至った。合意文書58に記載された主な内容として、英国は米国から輸入される牛肉やエタノールの関税率引下げを行うこととされている。他方、米国は英国から輸入される自動車について年間10万台までの10%の関税割当制度(10万台を超えた部分については上述の自動車に対する25%の追加関税の対象となる)や鉄鋼・アルミニウムについて最恵国税率での関税割当制度を設けることとされている。また、232条に基づく調査が行われている医薬品についても、今後の協議を通じて英国を優遇して取り扱う旨が記載されている。さらに、両国は引き続き通商協議を続けていくこととしている。
(3)「相互関税」
上述の品目別、国別の関税措置に加え、4月2日には、トランプ大統領は「相互関税」(Reciprocal Tariff)と称する全ての国を対象とした広範な関税措置を発表した(第2-2-9表、第2-2-10表)。これは、非対称な関税率や非関税障壁等による各国との非互恵的な通商関係が米国の多額かつ継続的な財貿易赤字として表れ、米国の安全保障と経済に対して異常かつ重大な脅威をもたらしているという状況を、IEEPAに規定される「国家緊急事態」であると認定した上で、全ての国に対する追加関税措置を講ずるというものである。この措置は貿易赤字とその根底にある非互恵的待遇が解決されたと大統領が判断するまで有効とされた。
この措置の発表を受けて金融資本市場が大きく変動する中、75を超える貿易相手国が米国との通商協議のために接触してきているとして、4月9日、トランプ大統領は、中国以外の国別上乗せ関税率の適用を90日間(7月9日まで)停止する大統領令に署名した。
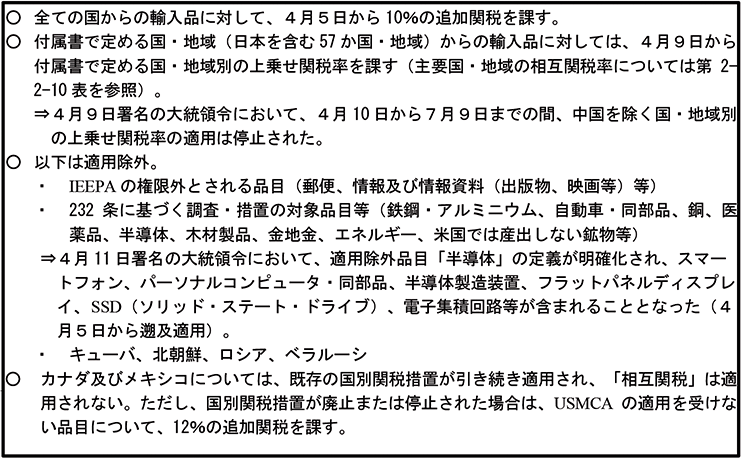
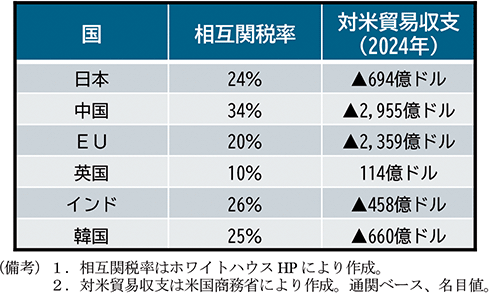
Box.相互関税率の決定方法について
各国・地域に課した相互関税率の決定方法として、USTRの公表資料(Reciprocal Tariff Calculations)では、次のように説明されている。二国間の財貿易収支が0となる追加関税率は、式(8)のとおり計算される。
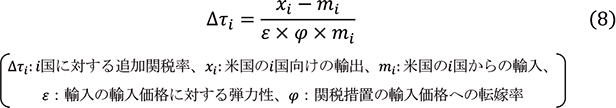
ここで、USTRの公表資料では、ε=4, φ=0.25と設定されていることから、ε× φ=1となるため、式(8)に代入すると、式(9)が得られる。
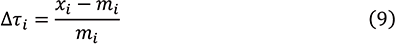
このことから、米国の輸出と米国の輸入の差分(米国の貿易収支)を米国の輸入額で割った値を二国間の財貿易収支が0となる追加関税率とみなしていることとなる。
2025年4月2日にトランプ大統領が発表した「各国が米国に対して課している非関税障壁を含む関税率」(Tariffs Charged to the U.S.A Including Currency Manipulation and Trade Barriers)は、式(9)で計算される追加関税率とおおむね一致しており、その値をおおよそ2で割った値が相互関税率(U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs)と発表されたと考えられる59。
例として、式(9)を用いて日本の相互関税率を算出する。2024年の米国から日本への輸出額(797億ドル)と日本からの輸入額(1,482億ドル)をそれぞれ式(9)に代入することで、日本が米国に対して課している非関税障壁を含む関税率(46%)が求められ、それを2で割ることにより、相互関税率(23%)が求められる60。これは、2025年4月2日にトランプ大統領が発表した日本が米国に対して課している非関税障壁を含む関税率(46%)、日本に対する相互関税率(24%)とおおむね一致する。
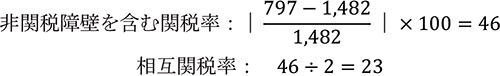
2.通商政策が財貿易に与える影響
これまで概観してきたトランプ大統領の通商政策が米国の財輸入に与えた影響について確認する。2025年1月のトランプ大統領就任後、米国による関税率引上げを見越した駆け込みの影響等から財輸入が増加し、2025年3月には統計上、過去最大の財貿易赤字となった61(第2-2-11図)。
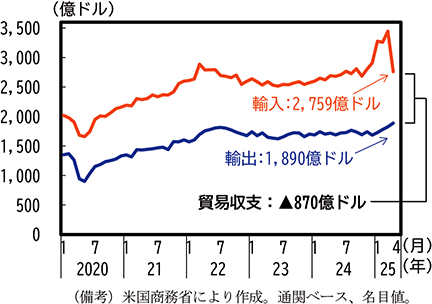
主要品目別輸入の前月比寄与度の動向をみると、2025年1月に工業原材料(特に非貨幣用金)が増加し、3月に消費財(特に医薬品)が増加した一方、4月に消費財、工業原材料、自動車・同部品が減少していることが確認できる(第2-2-12図)。
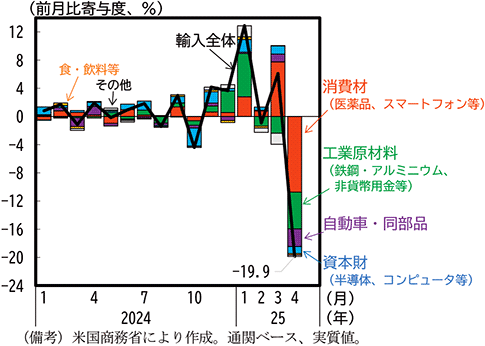
2025年1月、3月、4月の輸入の動向をさらに詳細に確認する(第2-2-13図)。
1月の工業原材料の輸入の増加の主要因は、スイスからの非貨幣用金等の輸入の急増である。非貨幣用金の輸入の急増の背景には、安全資産としての金需要の高まりに加え、金に関税が課されるとの懸念から、ニューヨークの先物市場の金価格が大きく上昇したことが背景にある可能性がある。ただし、米国のGDP統計(NIPA)では、金が用いられた時計や宝飾品等の最終財を生産するための中間投入として輸入する場合を除き、非貨幣用金の輸入はGDPの構成項目とならない扱いとなっており62、米国のGDP成長率には影響しない63。
3月の消費財の輸入の増加の主要因は、アイルランドからの医薬品の輸入の増加である。医薬品に対し今後関税措置が課されるとの懸念から、アイルランドから医薬品を駆け込みで輸入したと考えられる。
4月には、3月の医薬品の輸入急増の反動から消費財のうち医薬品の輸入が減少したことに加え、非貨幣用金が4月2日発表の「相互関税」の対象外となったことによる輸入の減少がみられた。また、鉄鋼・アルミニウムに対する関税、完成車に対する関税の影響を受け、工業原材料と自動車・同部品の輸入の減少もみられる(品目別の輸入動向の詳細は後述)。
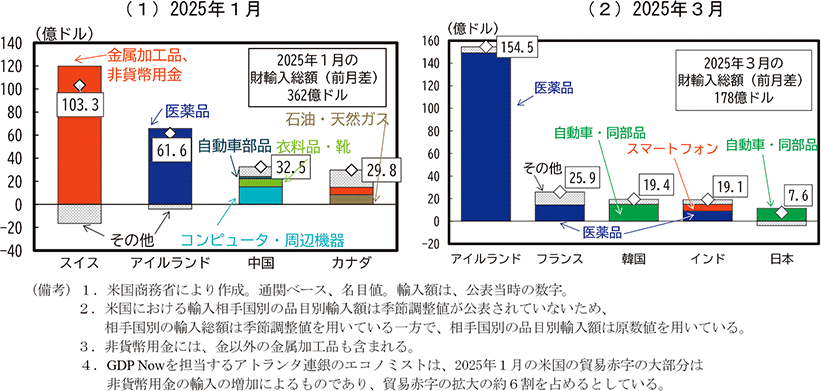
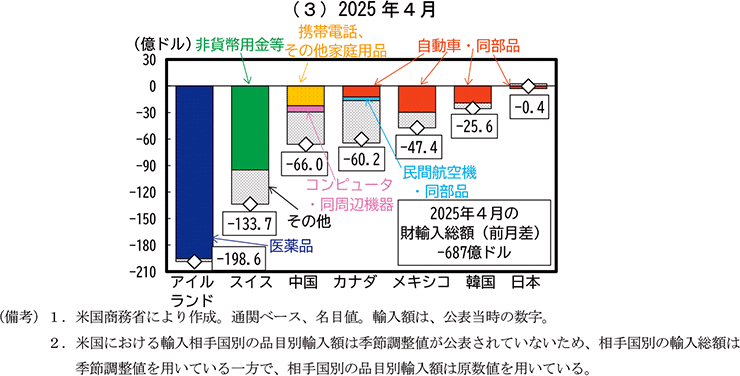
次に、安全保障を理由として関税が発動または調査が実施されている品目について、就任前後で輸入がどのように変化したか確認する。2024年における該当の品目の国別シェアをみると(第2-2-14図)、個別の品目では特定の国からの輸入シェアが大きい。
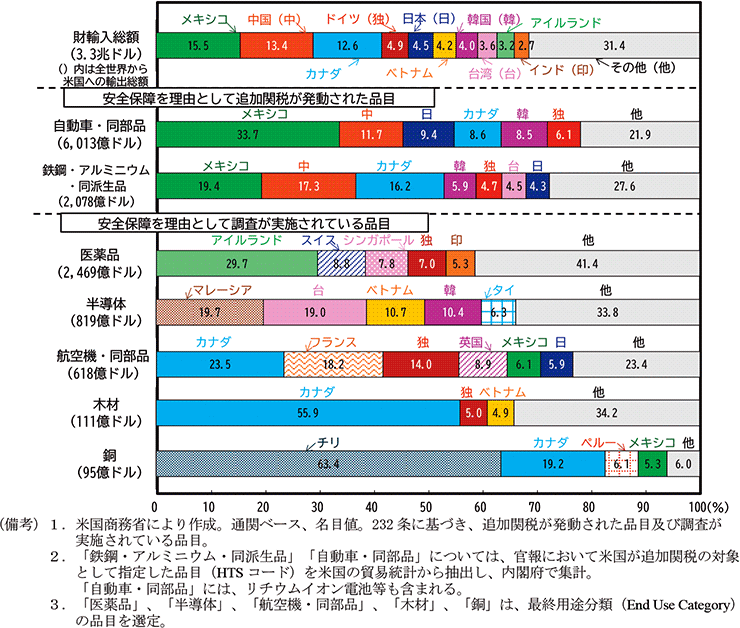
ここでは、個別の品目について、輸入の状況を確認する。まずは、安全保障を理由として 232条による品目別関税が発動された「鉄鋼・アルミニウム・同派生品」、「自動車・同部品」について動向を確認する。
(鉄鋼・アルミニウム・同派生品)
鉄鋼・アルミニウム・同派生品の輸出、輸入の動向をみると(第2-2-15図)、輸入が輸出を上回って推移している。鉄鋼・アルミニウム・同派生品の追加関税は2月にトランプ大統領が大統領令に署名し、3月に追加関税が発動し、4月にはさらに拡大した品目に対し関税が発動された。3月はカナダ、メキシコからの輸入が増加したが、4月にはメキシコ以外の国からの輸入が減少した。なお、中国に対しては別途2月から国別の関税が課されていたこともあり、前年に比べ輸入が減少していることが確認できる。
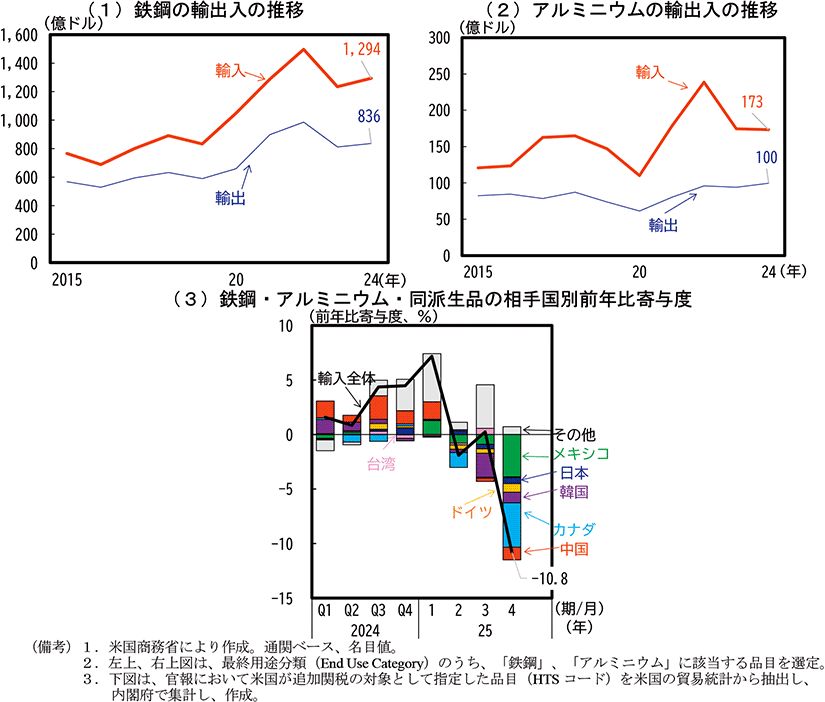
(自動車・同部品)
自動車・同部品の輸出、輸入の推移をみると(第2-2-16図)、輸入は継続的に輸出を上回っている。自動車(完成車)への追加関税は4月に発動され、5月に自動車部品に対しても追加関税が発動された。自動車・同部品の輸入を前年比でみると、3月には主にメキシコからの輸入が駆け込みで増加したのち、4月には減少している。なお、中国に対しては別途2月から国別の関税が課されていたこともあり、前年に比べ輸入が減少していることが確認できる。
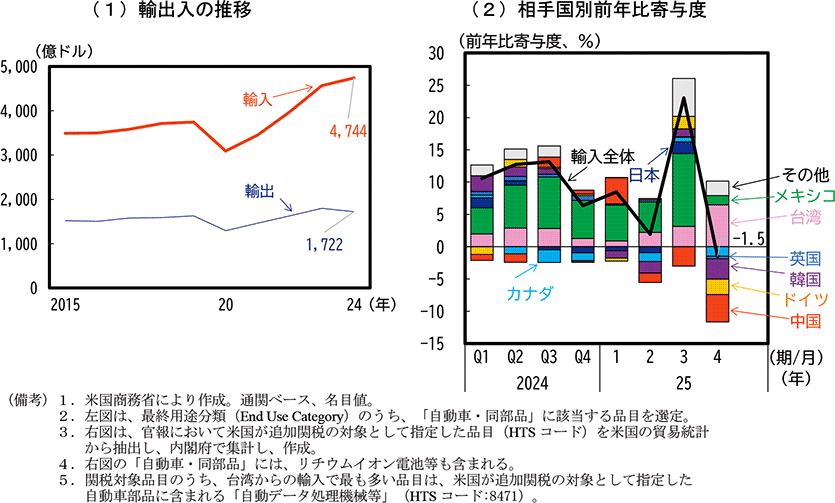
次に、現在、232条による調査が実施されている「医薬品」、「半導体」、「航空機・同部品」、「木材」、「銅」について輸入の動向を確認する。
(医薬品)
医薬品の輸入を確認すると(第2-2-17図)、2017年以降継続して増加し、輸出との差も拡大傾向にある。前節で確認したとおり、医薬品の輸入相手国はアイルランドのシェアが大きい。4月16日、商務省は官報にて、232条に基づき、医薬品の輸入が米国の安全保障に及ぼす影響を判断するための調査を開始したと発表した。発表前に、トランプ大統領は、演説や自身のSNSにおいて医薬品の生産拠点を国内へ移転すること、薬価の引下げを目指すことについて言及していた。また、4月2日に「相互関税」を発表することについても言及していた64。このことから、医薬品に対する関税発動を見据え、2025年3月は医薬品の輸入が前年比で増加した。
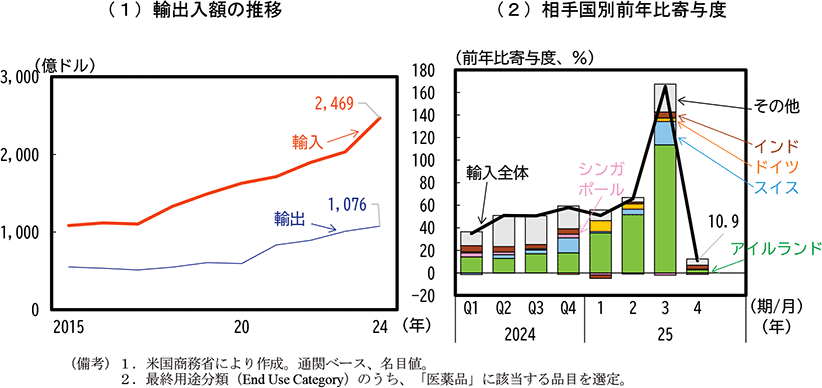
(半導体)
半導体は、2020年から2024年にかけて輸出と輸入の差が拡大傾向にある(第2-2-18図)。2025年4月16日、商務省は、官報にて、232条に基づき、半導体の輸入が米国の安全保障に及ぼす影響を判断するための調査を開始したと発表した。半導体の輸入をみると、2024年後半以降、台湾、マレーシアからの輸入の増加寄与が大きい。
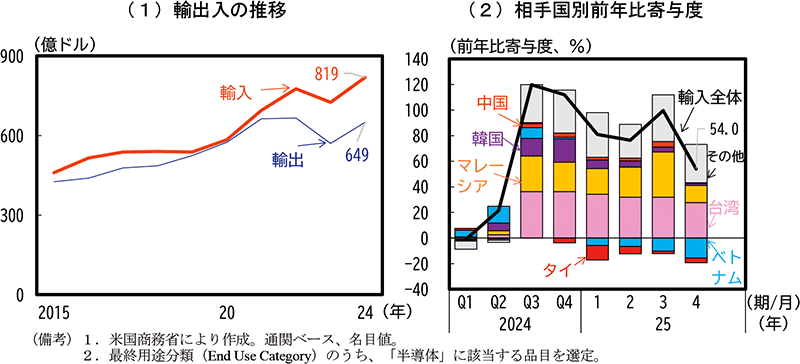
(航空機・同部品)
航空機については、米国航空機産業が比較優位を持つ品目であり、2015年から2024年まで輸出が輸入を上回って推移している(第2-2-19図)。5月13日、商務省は、官報にて、232条に基づき、民間航空機、ジェットエンジン、同部品の輸入が米国の安全保障に及ぼす影響を判断するための調査を開始したと発表した。民間航空機・同部品の輸入をみると、2025年はドイツからの輸入が減少傾向にある。
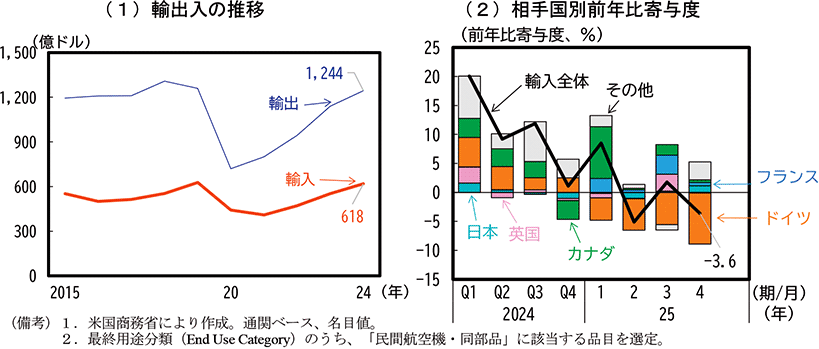
(木材)
木材の輸出、輸入の動向を確認すると(第2-2-20図)、2015年から2024年にかけて継続的に輸出が輸入を上回っているものの、輸入相手国ではカナダが約6割を占めている(第2-2-14図)。2025年3月1日、トランプ大統領は、232条に基づき、商務長官に対し、木材・同派生品の輸入に係る安全保障上の影響の調査を指示した。木材の輸入は、カナダからの輸入が全体の輸入に影響を与えている66。
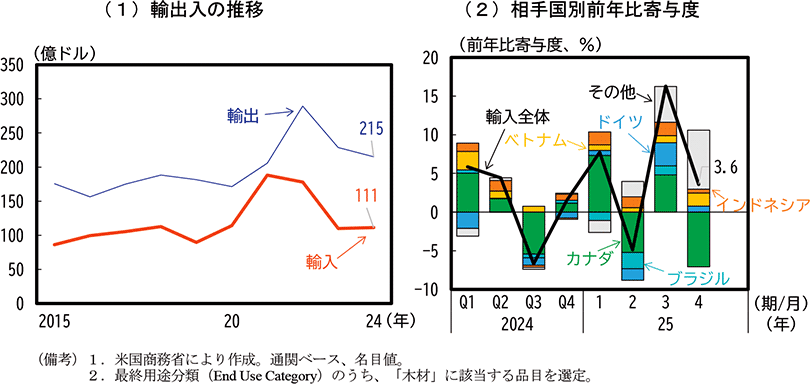
(銅)
銅の輸出、輸入の動向を確認すると(第2-2-21図)、2015年から2024年にかけて継続的に輸出が輸入を上回っているものの、輸入相手国では銅の生産量が多いチリが約6割を占めている(第2-2-14図)。2月25日、トランプ大統領は、232条に基づき、商務長官に対して、銅の輸入に係る安全保障上の影響の調査を指示した。3、4月はチリからの銅の輸入が増加した。
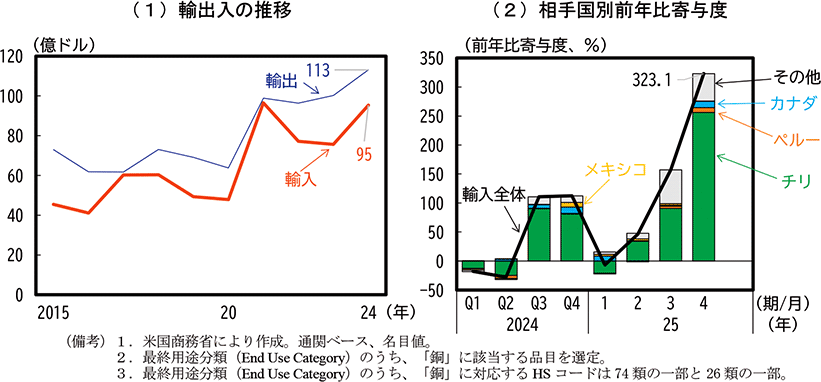
第二次トランプ政権は、これらの品目のほか、トラックや鉱物資源などに関する調査も実施している。232条による調査は、商務長官が調査開始後270日以内に調査結果と取るべき措置の勧告または措置を取らない旨の勧告を大統領に報告することとなっている。大統領は、商務長官の報告を受け取ってから90日以内に、措置を取るか否か、決断する必要がある。大統領が措置を発動すると決めた場合、15日以内にその措置を実施しなくてはならず、その品目の輸入が米国の安全保障を危うくするおそれがなくなるようにするために、同品目及び派生品について関税率引上げを含めた輸入の調整を行うこととなる67。現在実施している232条による調査の結果が関税の発動につながるか注視する必要がある。
Box.デミニミスルール (De Minimis Rule)(少額貨物の輸入における非課税基準額ルール)
米国では、800ドル以下の少額貨物の輸入については関税賦課が免除されてきた(デミニミスルール)。しかしながら、同制度によって薬物等の違法な物品が輸入されている可能性も指摘されてきた。2025年1月20日の就任日にトランプ大統領が署名した大統領令では、財務長官等に対して、現在の米国のデミニミスルールに起因する関税収入の損失と偽造品やフェンタニル等の違法薬物の輸入によるリスクを評価するよう指示した。さらに、トランプ大統領が2月1日に署名した大統領令において、中国からの輸入品に対する10%の追加関税はこうした少額貨物も適用対象となる旨規定された。ただし、少額貨物に対する関税徴収の制度構築に時間を要したことから、中国から輸入される少額貨物への関税賦課の開始は5月2日からとなった。4月上旬には米中間で相互に関税率の引上げが繰り返された中で少額貨物に対する関税の水準も変更が繰り返されたが、5月12日の米中間の合意により、当面は54%の従価税または1件当たり100ドルの従量税のいずれかが各輸入業者の選択に従って課されることとなっている。
税関・国境取締局(CBP)によると、米国に到着するデミニミスルールの対象となる少額貨物の数は増加しており、2024会計年度(2023年10月~2024年9月)には13.6億個、総額646億ドルに達した(図1)。また、中国側統計では、2024暦年の米国への少額貨物の輸出額は229億ドルとなっている(図2)。双方のカバレッジや比較時点に留意する必要があるが、単純に計算すれば、直近では中国からの輸入が米国のデミニミスルール対象の輸入額の約3分の1に相当する規模となっている68。もっとも、少額貨物の輸出額は中国の対米輸出全体の4.4%にとどまっており、今般のデミニミスルールの見直しによる中国の対米輸出へのマクロ的な影響は限定的と考えられる。
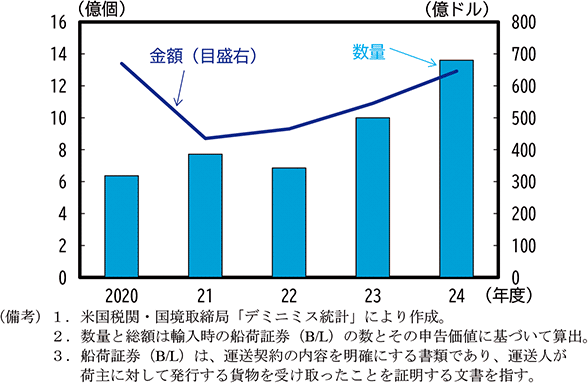
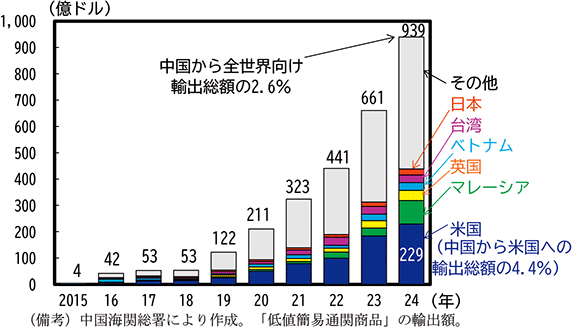
3.通商政策が物価に与える影響
2025年1月のトランプ大統領就任以降、予想物価上昇率の上昇がみられている。ここでは、各地区の連邦準備銀行(以下、「連銀」という。)や各機関等が公表している予想物価上昇率を概観する。予想物価上昇率の算出方法は、大きく分けて5つの種類があり、(1)消費者による予測値、(2)企業の担当者による予測値、(3)エコノミストによる予測値、(4)マーケットデータに基づく予測値、(5)モデルによって計算された予測値がある。(1)の例としてはミシガン大学やコンファレンスボード、ニューヨーク連銀による消費者へのアンケート調査、(2)の例としてはクリーブランド連銀やアトランタ連銀による企業向け調査、(3)の例としてはフィラデルフィア連銀によるエコノミスト予測調査、(4)の例としては国債利回りからインフレ連動国債利回りを引いたブレーク・イーブン・インフレ率、(5)の例としてはフィラデルフィア連銀やクリーブランド連銀によるモデル予測が挙げられる(第2-2-22表)。
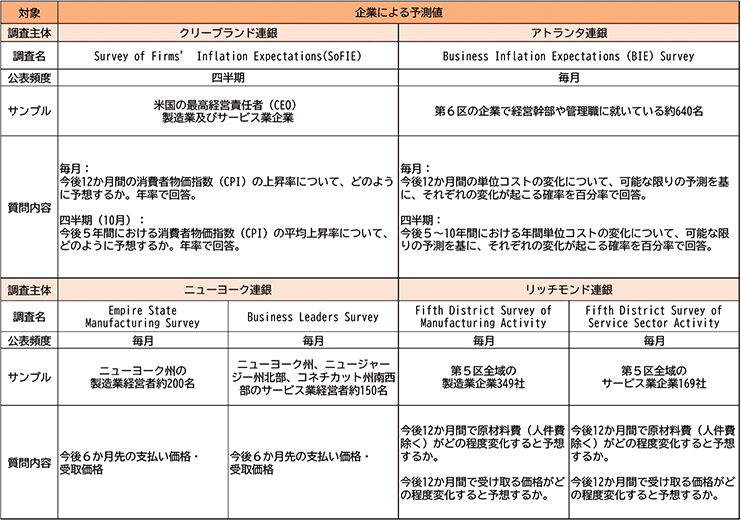
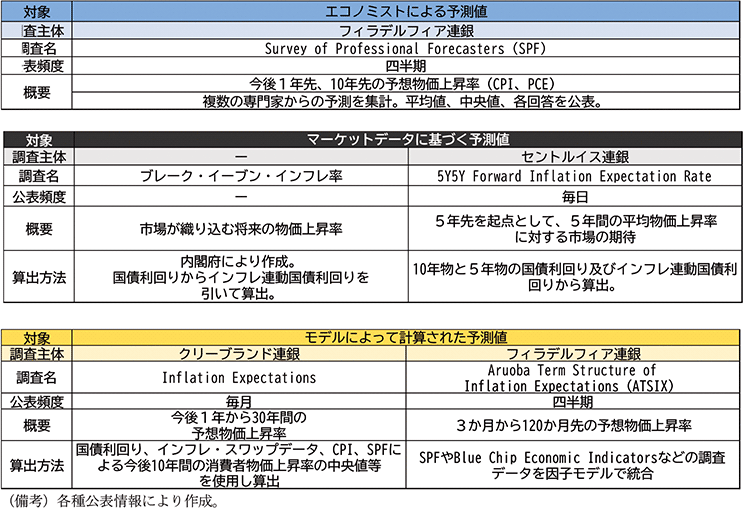
これらの予想物価上昇率を予測期間別にみると(第2-2-23図)、短期的な予想である1年先予想物価上昇率では、特に、消費者による予測であるミシガン大学が5月値6.6%と、1981年11月の7.3%以来の高さとなった。また、企業、エコノミストによる予測や、モデルによる推計では消費者の予測と同様にこのところ予想物価が上昇している一方、市場参加者による予測であるブレーク・イーブン・インフレ率はこのところ低下している。長期的な予想である10年先予想物価上昇率では、消費者による予測であるミシガン大学は5月値4.2%と高い水準にあるものの、エコノミスト、市場参加者、モデルによる予測値・推計値は、FRBの物価安定目標である2%程度でおおむね安定している(第2-2-24図)。FRBのパウエル議長は、2025年5月のFOMC後の記者会見において、「今後1年程度を超える長期的な予想物価上昇率を示すほとんどの指標は、2%の物価安定目標と一致している71」と発言しており、これらのデータと整合的であることが分かる。
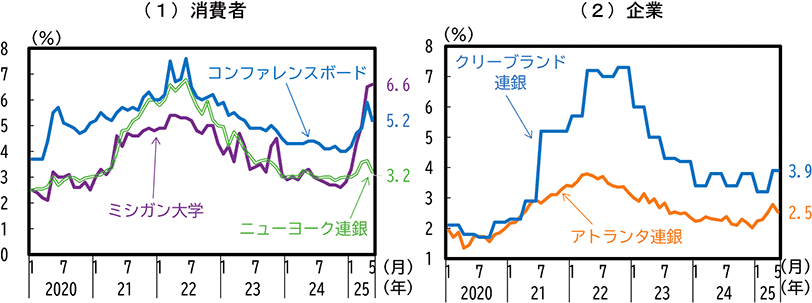
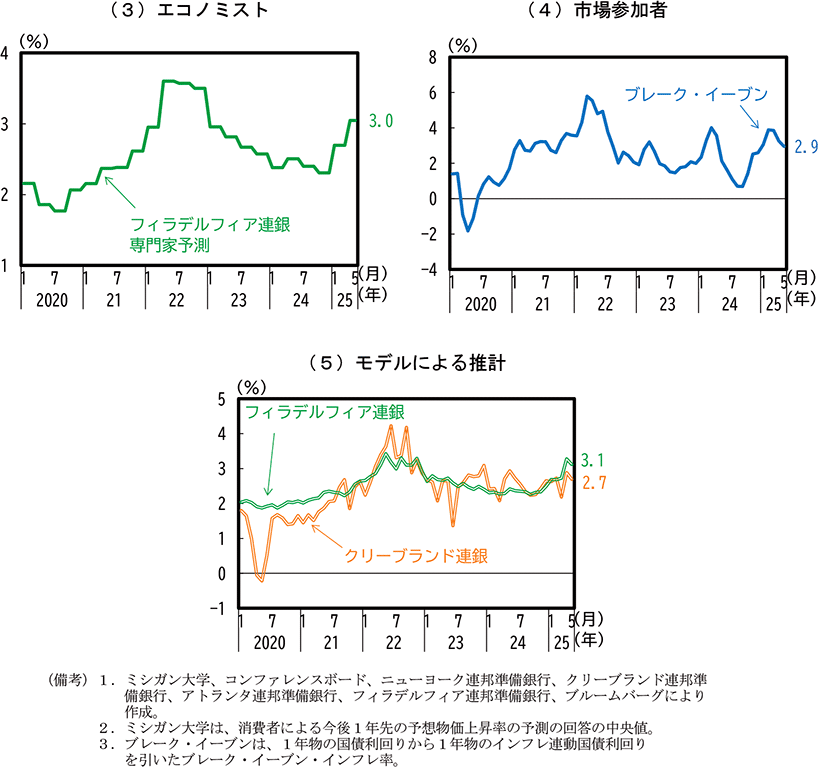
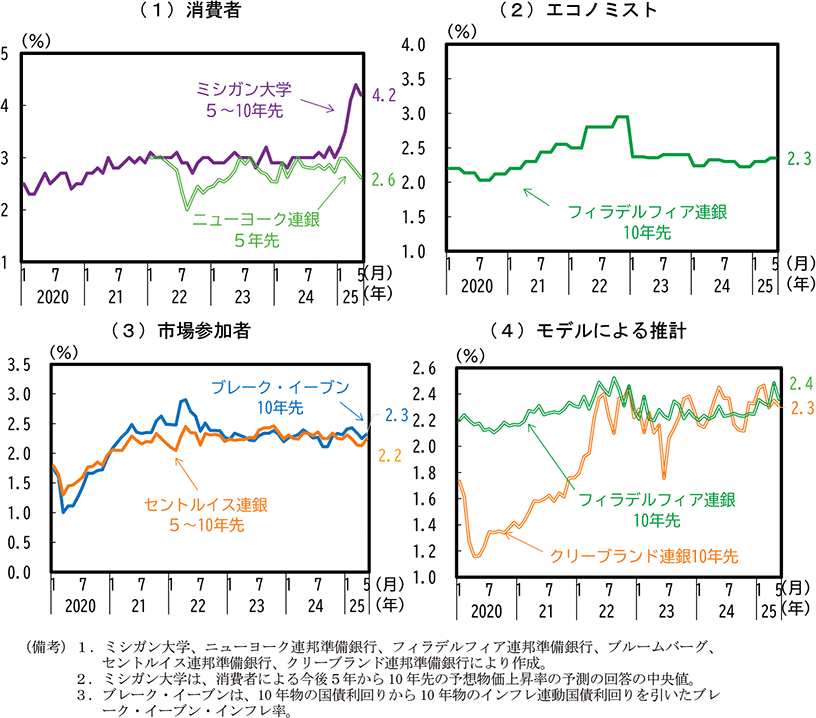
(関税措置による生産者物価への影響)
第二次トランプ政権による各種関税措置によって、企業の財輸入に係るコストが上昇することにより、最終的には消費者物価の上昇につながる可能性がある。輸入コストの上昇が消費者物価の上昇につながるまでの経路としては、川上企業から川下企業に対する価格転嫁、川下企業から消費者に対する価格転嫁が考えられる。ここでは、過去の各種関税措置がどの程度価格転嫁されたのかについて、需要段階別、品目別の生産者物価指数から確認する。
米国の生産者物価指数は、(1)産業分類指数、(2)商品分類指数、(3)最終需要・中間需要(FD-ID)指数の3つに分類される。(3)FD-ID指数は、需要段階別に統合し集計され、素材・原材料に最も近い段階であるステージ1(川上)から最終需要に最も近い段階のステージ4(川下)までの中間需要に投入される財・サービスの価格、最終需要に配分される財・サービスの価格で構成されているため、企業間取引価格の動向をみることができる(FD-ID指数の詳細は、Box参照)。
まず、2025年5月までの生産者物価指数と消費者物価指数の推移を確認する。第2-2-25図をみると、消費者物価指数はおおむね横ばいで推移している一方で、生産者物価指数は上昇している。生産者物価指数のうち、特に中間需要向け財は第二次トランプ政権が発足した2025年1月以降、物価上昇率の伸びが高い。関税による物価の押し上げ効果は川上の中間財に現れ始めている。
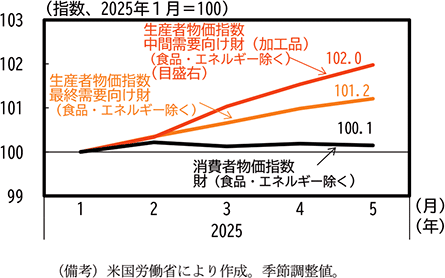
Box.生産者物価指数の最終需要・中間需要(FD-ID)指数について72
米国労働省が公表する生産者物価指数(PPI)は、国内生産者が受け取る販売価格の平均的な変化を測定している73。ここでは、最終需要・中間需要(FD-ID)指数と呼ばれる米国のPPIの特徴を解説する。
FD-ID指数は、商品ベースの生産者物価指数から構築されており、商品ごとに買い手の種類別の使用割合に基づき、最終需要向け、中間需要向けに再グループ化している74。FD-ID指数のうち最終需要向けについては、最終需要(個人消費、設備投資、政府支出、輸出)として使用されることを目的として販売される商品、中間需要向けについては、企業に生産への中間投入物として販売される商品を形態別に財・サービス・建設に分け、その価格変動を生産者視点から測定している。中間需要向けについては、更に二つの種類に大別され、中間需要向け商品を商品の類似性によって整理した商品タイプ処理(by commodity type)と、中間需要向け商品を生産段階別に4段階で整理した生産フロー処理(by production flow)とに分けられる(図1)。
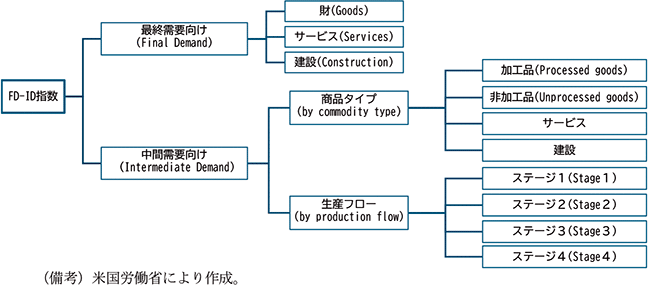
生産フロー処理では、原材料から最終製品に至る生産の流れの中で、各商品が生産のどの段階にあるかを4つのステージ(ステージ1~4)に分けて区分している。区分分けにあたっては、生産過程で材料が加工されていく「順方向」の流れ(フォワード・フロー)を最大限に捉えるように設計している。一方、最終製品が再び原材料に戻るような「逆方向」の流れ(バック・フロー)が可能な限り含まれないように設計している。ステージ4の産業は主に最終需要として使用される生産物を生産し、ステージ3の産業は主にステージ4の産業によって使用される生産物を生産する。各ステージの指数は4つの生産段階それぞれで産業が使用する生産物の価格を追跡している。例えば、ステージ4での中間需要指数は、ステージ4に属する産業では生産しないが中間消費を行う商品の価格変動を追跡する。ステージは図2のとおり定義され、各ステージに属する主な産業、各ステージで使用される財・サービスは以下のとおりとなる(表3)。
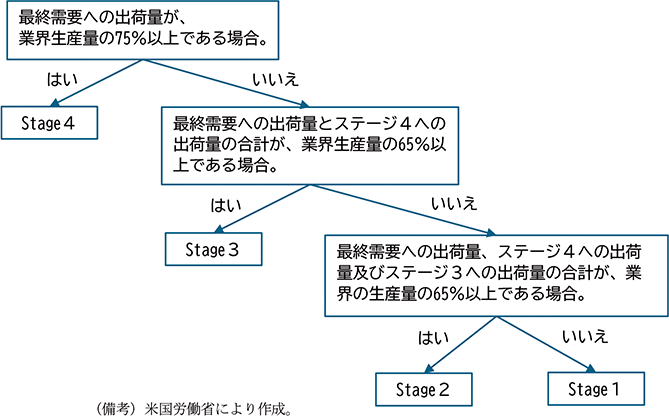
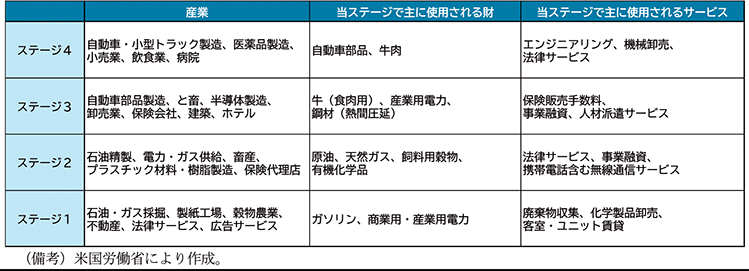
過去、鉄鋼・アルミニウムの生産者物価が関税措置に起因して上昇した例としては、第一次トランプ政権時の鉄鋼・アルミニウム関税の賦課がある。トランプ大統領は、2018年3月23日から、232条に基づき鉄鋼に25%、アルミニウムに10%の関税賦課を実施した75。
当時、鉄鋼・アルミニウムの生産者物価の上昇が米国内の各産業に与えた影響を分析するため、まずは米国の主要産業の内、鉄鋼・アルミニウムを中間財として使用している割合が高い産業を選出し、各産業の需要段階のステージ分類を確認する。続いて、各産業の生産者物価指数の動向や、より川下の産業の生産者物価への波及を確認する。
米国商務省が公表している使用表(The Use Table)76を用いて、米国の主要産業のうち鉄鋼・アルミニウムを中間財として使用している割合が高い産業を確認する(第2-2-26表)。第2-2-26表(1)をみると、「鉄鋼製品」、「板金・構造部材」が中間財としての鉄鋼の使用割合が高い。第2-2-26表(2)をみると、「アルミニウム製品」、「アルミナ及び一次アルミニウム」、「バネ及びワイヤー製品」、「軍用装甲車、戦車、戦車部品」、「非鉄金属鋳物」が中間財としてのアルミニウムの使用割合が高い。
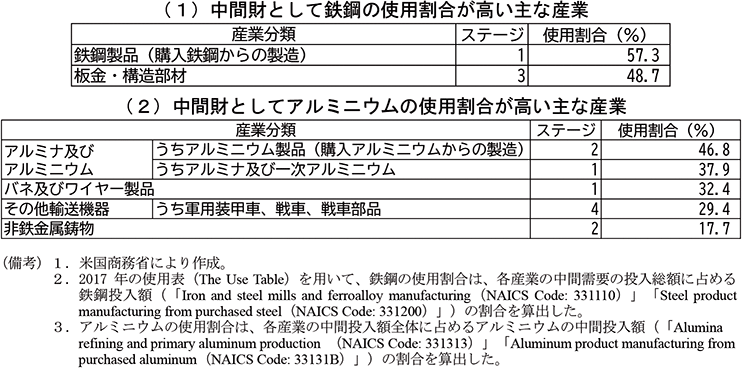
まず、中間財として鉄鋼の使用割合が高い産業の生産者物価を確認する。
第一次トランプ政権時、最も川上の産業であるステージ1に属する「鉄鋼製品」は、ステージ3に属する「板金・構造部材」よりも価格が上昇している(第2-2-27図(1))。また、価格上昇の早さに着目すると、最も川上の産業であるステージ1に属する「鉄鋼製品」は価格上昇が早く進み、2018年9月にピークに達したが、ステージ3に属する「板金・構造部材」は価格上昇が緩やかに進んだ。
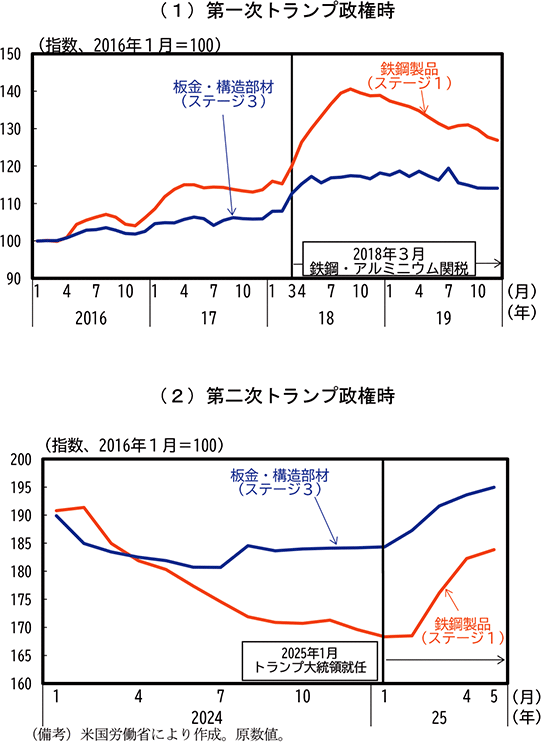
続いて、アルミニウムの使用割合が高い産業について、2020年末以降の生産者物価指数を確認する。第一次トランプ政権時、川上の産業であるステージ1、2に属する「アルミナ及びアルミニウム」、ステージ1に属する「バネ及びワイヤー製品」は、ステージ2に属する「非金属鋳造」やステージ4に属する「その他輸送機器」よりも価格上昇率が大きく、また、価格上昇が早い(第2-2-28図(1))。
以上から、第一次トランプ政権時には、鉄鋼、アルミニウムの使用割合が高い産業においては、より上流にある産業の方が価格の上昇率が大きく、より早く価格上昇が生じていたことが分かる。
第二次トランプ政権時の2025年1月以降の推移を確認すると、鉄鋼については、最も川上の産業であるステージ1に属する「鉄鋼製品」は、ステージ3に属する「板金・構造部材」よりも価格がより大きく上昇している(第2-2-27図(2))。また、アルミニウムについては、川上の産業であるステージ1、2に属する「アルミナ及びアルミニウム」は、ステージ2に属する「非金属鋳造」やステージ4に属する「その他輸送機器」よりも価格上昇率が大きく、また、価格上昇が始まった時期が早い(第2-2-28図(2))。
今後、第二次トランプ政権による関税措置の影響により、より上流にある産業において、より早く価格上昇が生じるとともに、より大きな価格上昇となることが想定される。
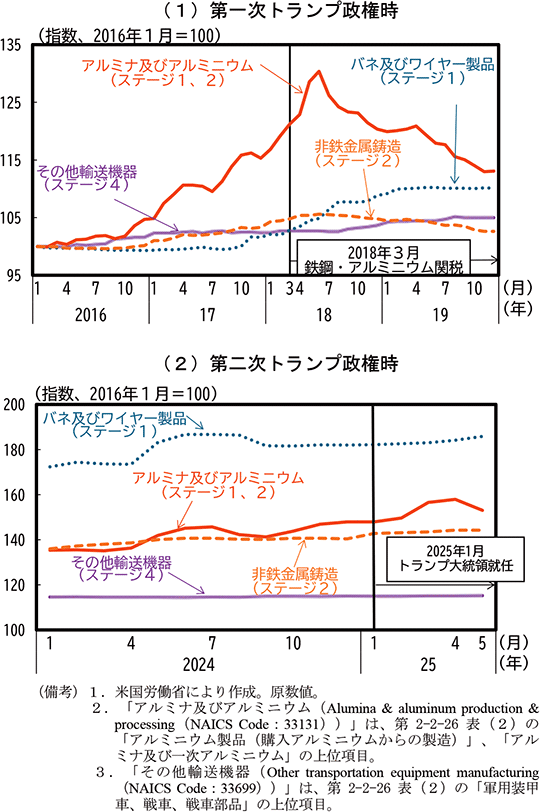
コラム4 実効関税率と生産者物価の関係
第二次トランプ政権による関税措置により、米国が輸入する際の実効関税率は大きく上昇している。本コラムでは、実効関税率の上昇が生産者物価に与える影響を確認するため、第一次トランプ政権時代の鉄鋼・アルミニウム関税における関税率の変化が生産者物価に与えた影響について分析する。
主要相手国別に実効関税率をみると(図1)、第一次トランプ政権時は、2018年から2019年にかけて中国に対する実効関税率が徐々に上昇し、その後も高い水準を維持しているのに対し、カナダ・メキシコに対する実効関税率は一時的に上昇の後低下した。第二次トランプ政権の2025年以降は、中国に対する実効関税率が大きく上昇しているほか、各国に対する実効関税率も第一次トランプ政権時と比較して上昇していることがうかがえる。
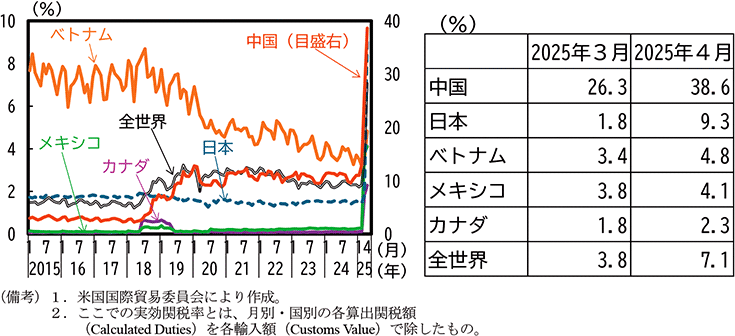
実効関税率の長期推移をみると(図2)、第二次トランプ政権の関税措置により米国が輸入する際の実行関税率は、2025年4月9日時点で、世界経済のブロック化をもたらした1930年のスムート・ホーリー法77による関税率引上げの時期を上回り、1900年頃と同程度の水準となっている。
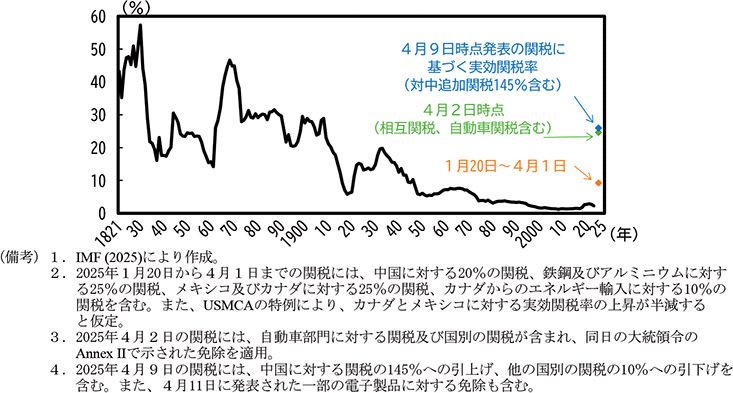
ここで、第一次トランプ政権時の鉄鋼・アルミニウム関税に着目し、関税率の変化が生産者物価に与える影響について分析を行う。当時の課税対象品目について、米国国際貿易委員会(United States International Trade Commission)が提供するデータを用いて、2017年1月から2018年12月までの実効関税率78と、それらに対応する生産者物価を用いてパネルデータ分析を行った。
なお、本分析では、統計上の制約から、これまでみてきたステージ別の生産者物価指数を用いていないことから、生産工程における価格転嫁を考慮していない点には留意が必要である。
第一次トランプ政権時の鉄鋼・アルミニウムに対する関税措置の対象品目に対応する産業分類(12分類)ごとに実効関税率を計算し、生産者物価との関係を推計した。
t月におけるi産業の生産者物価指数をPPIit、t月におけるi産業の実効関税率をTariffit、i産業ごとの固定効果をuiとし、
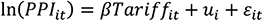
を最小二乗法で推計を行った。推計した結果は以下のとおり79。
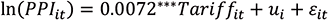
この結果から、ある産業の実効関税率が1%pt上昇すると、その産業の生産者物価指数が0.72%pt上昇する傾向にあることが確認できた。
(関税措置による消費者物価への影響)
次に、第二次トランプ政権の関税措置による消費者物価への影響を確認するために、消費に占める輸入品の割合を品目別に確認する。
米国商務省が公表している直近の2017年の使用表(The Use Table)、輸入表(Import Matrix)等を用いて、米国内の最終需要のうち個人消費支出(PCE)において、品目別の輸入割合を算出した(第2-2-29図)。
(1)では、個人消費支出全体に占める耐久財・非耐久財・サービスの輸入割合をそれぞれ示している。耐久財消費の20%、非耐久財消費の13%、サービス消費の2%を輸入品が占めており、個人消費支出全体に占める輸入割合は6%である。
(2)では、より詳細な品目において、個人消費支出全体に占める輸入割合を計算した。具体的には、個人消費支出(購入者価格)を、①個人消費(生産者価格)のうち輸入分、②個人消費(生産者価格)のうち国内生産分、③運輸マージン、④卸売マージン、⑤小売マージンの5つに分解した上で、輸入割合が高い順に並べたものである。例えば、「テレビ、パソコン等」は、輸入割合が45%、卸売マージンが16%、小売マージンが31%を占め、国内生産の割合は7%である。また、「スマートフォン等通信機器」は、輸入割合が37%、卸売マージンが26%、小売マージンが35%を占め、国内生産の割合は2%である。こうした日々の生活に使う消費財は輸入割合が高く、関税措置の影響を受けやすい構造にあると考えられる。ただし、卸売マージン、小売マージンが大きい財では、関税率引上げに伴うコスト増の大部分がマージンの圧縮によって吸収され、消費者物価を押し上げる効果は限定的となる可能性がある。
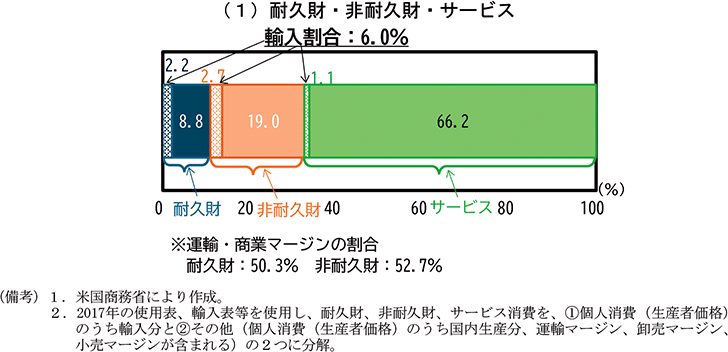
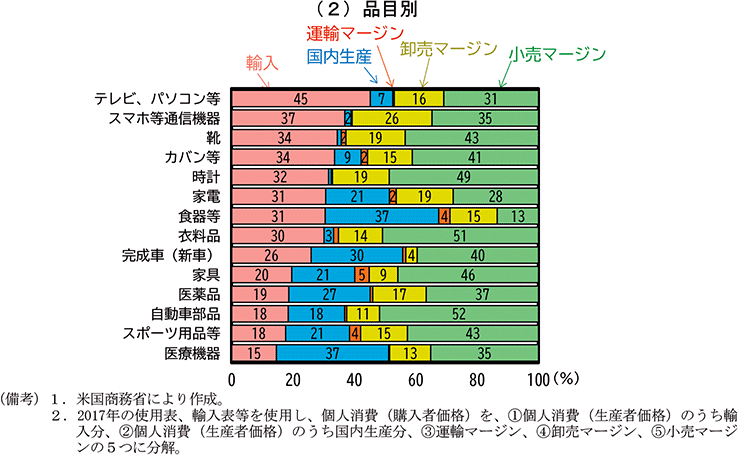
第2-2-30図は、各産業の中間投入に占める輸入品割合を輸入相手国別に示したものである。医薬品は個人消費支出に占める輸入割合は2割弱であるものの(第2-2-29図(2))、医薬品製造業の中間投入のうち6割弱を輸入品が占めており、特に、欧州からの輸入品が3割強を占めている。このことから、米国内で医薬品を製造する際に中間投入として必要となる品目に関税がかかる場合、米国の医薬品製造業に影響を与えると考えられる。また、通信機器については、個人消費支出に占める輸入品の割合が3割強を占める中、通信機器製造業の中間投入も3割強を輸入品が占めており、特に中国からの輸入が約15%を占めている。このため、通信機器については、第二次トランプ政権による対中関税措置の影響が、通信機器を輸入する際に直接与える影響と、米国内で通信機器を製造する際のコスト上昇という両面から影響を与えると考えられる。