第2章 米国の貿易・投資構造(第1節)
第1節 米国の財貿易の構造
本節では、米国の財貿易について、品目別及び相手国別に構造分析を行う。また、米国の財貿易の取引相手国を決定する要因について、国際貿易の重力モデルに基づいた分析を行う。
1.財貿易の基本構造
米国の財貿易の推移を確認すると(第2-1-2図)、輸出、輸入はともに増加傾向にあるが、特に、1990年代後半以降、輸入が輸出を上回って推移しており、財貿易赤字は拡大傾向にある。対照的に、サービス貿易では、輸出は輸入を上回って推移しており、サービス黒字の状況が継続している。2024年の財貿易赤字は1兆2,154億ドルであり、サービス黒字(3,119億ドル)を上回っている。
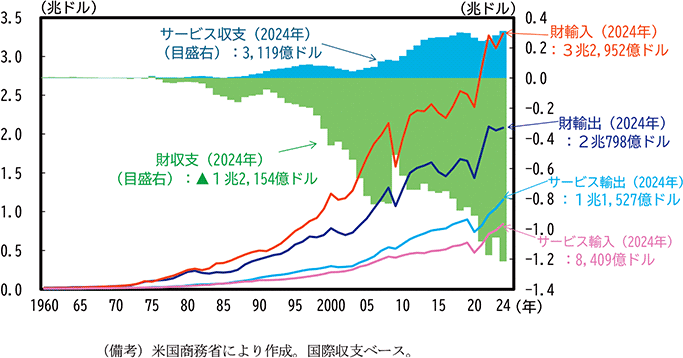
2024年の各国の財・サービス収支の黒字、赤字別の順位をみると(第2-1-3図)、米国は、財貿易収支では▲1兆2,154億ドルと世界最大の赤字国(2位は英国の▲2,887億ドル)である一方、サービス収支では3,119億ドルと世界最大の黒字国(2位は英国の2,475億ドル)である。財・サービスを合わせた収支では、▲9,035億ドルと世界最大の赤字国となる(2位はインドの▲1,010億ドル)。
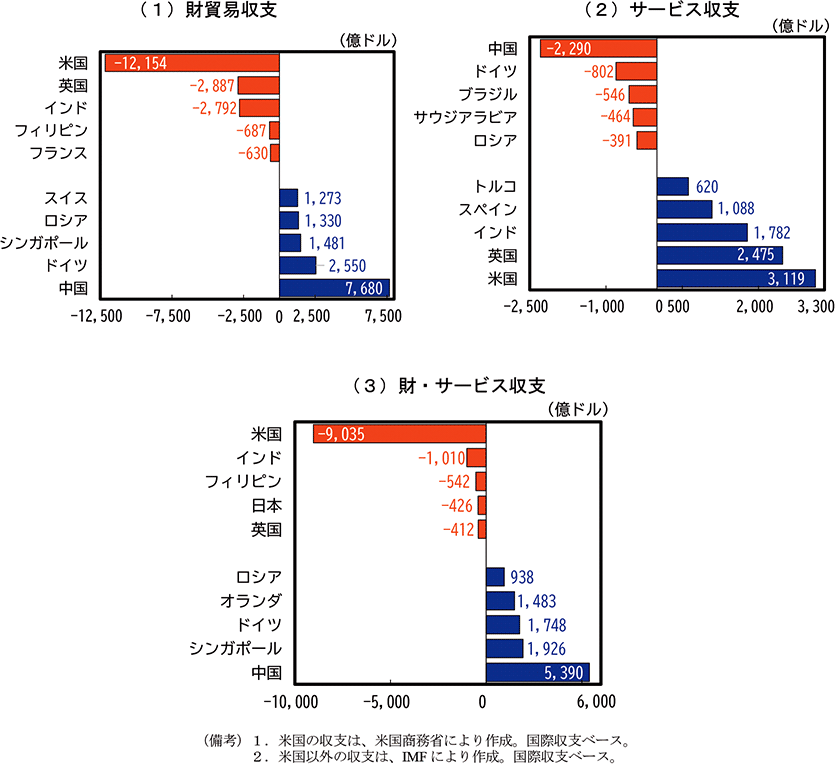
財貿易収支の対GDP比をみると、2010年以降、おおむね▲3%から▲7%の範囲内で横ばいで推移している(第2-1-4図)。また、サービス収支の対GDP比は、2010年以降、おおむね0.8%から1.5%の範囲内で横ばいで推移している(第2-1-5図)。財貿易赤字の拡大は米国の経済成長を阻害する要因とはなっていない。
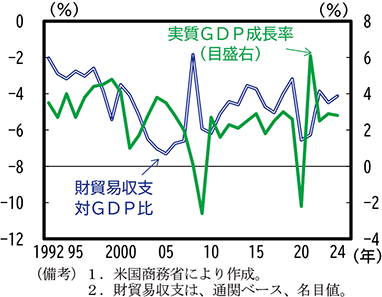
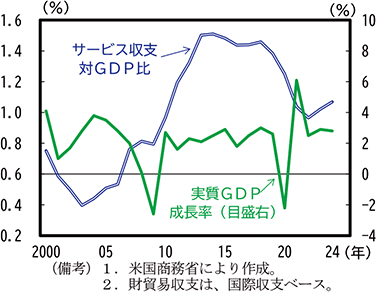
次に、財貿易収支を相手国・地域別に確認する。2010年以降、米国の財貿易赤字の最大の相手国は中国であるが、近年はEUやASEANといった他の地域に対する赤字額のシェアが拡大している(第2-1-6図)。世界金融危機後から第一次トランプ政権3発足前の2012~2016年と、感染症拡大後の2021~2024年における中国、EU、ASEANとの財貿易収支について、両期間の平均をとって確認すると、中国との財貿易赤字は110億ドル縮小した一方、ASEANとの赤字は1,493億ドル拡大し、EUとの赤字は796億ドル拡大した。ASEAN諸国では特にベトナムからの輸入が増加している。背景の一つには、サプライチェーンの強靭化のため、中国以外の代替的な生産拠点の確保(いわゆる「チャイナ・プラスワン」)の狙いが進んでいることが挙げられる4。EU加盟国ではアイルランドに対する赤字が大きい(詳細については後述)。
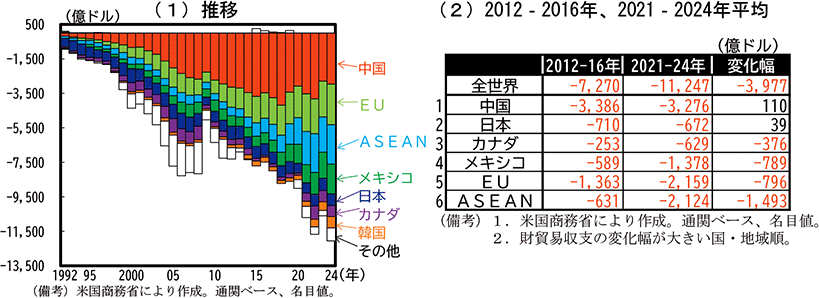
2024年における米国の財貿易収支を国・地域別にみると(第2-1-7図)、EU加盟国のオランダに対する黒字が最も大きいが、これは同国のロッテルダム港、アムステルダム港等が、EU域内への輸出の中継地点となることが多いことに起因する。
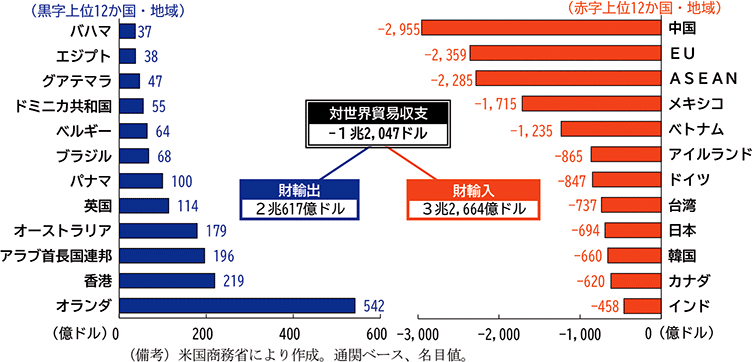
ここまで米国の財貿易収支と2024年における国・地域別の収支の動向と特徴を確認した。次に米国の財の輸出と輸入について、それぞれ主要品目別の動向と特徴を確認する(第2-1-8図)。ここでは、米国商務省が公表している財貿易の「最終用途分類」(End Use Category)に沿って、「飲食料品」(Foods, Feeds, and Beverages)、「工業原材料」(Industrial Supplies and Materials)、「資本財」(Capital Goods, Except Automotive)、「自動車・同部品」(Automotive Vehicles, Parts, and Engines)、「消費財」(Consumer Goods)、「その他」(Other Goods)という6つの分類5に分けて確認する(最終用途分類についてはBox参照)。
Box.「最終用途分類」(End Use Category)について
ここでは、財貿易を把握するために用いている最終用途分類(End Use Category)について、HSコード、HTSコードと比較した位置づけについて説明する。
HS(Harmonized System)コードとは、世界税関機構(WCO)が管理する国際的に統一された商品の名称及び分類のためのコードシステムであり、財貿易におけるあらゆる商品を体系的に分類するために使用される。HSコードは通常、6桁の数字で構成されており、頭の1~2桁で「類」Chapter)、続く3~4桁で「項」(Heading)、5~6桁で「号」(Subheading)を示す。この6桁の数字はWCO加盟国間で共通である。
各国は、HSコードを基に、自国の詳細な分類や特定の関税率を適用するために独自に細分化した国内版のコードシステムを作成している。米国の場合は、HSコード6桁に4桁を追加し合計10桁となるHTS(Harmonized Tariff Schedule)コードが作成されており、米国における輸入関税率の適用に使用されている。
「最終用途分類」(End Use Category)は、米国商務省が毎月公表している貿易統計を公表する際に使用されている、独自の品目分類である。前述のHSコードやHTSコードとは異なり、品目の物理的な性質や機能ではなく、その品目が最終的にどのように使用されるかという観点から分類し直したものである。なお、分類に当たってはHTSコードを基にして、それぞれの品目がどの最終用途カテゴリーに該当するか分類している。分類方法として、基本的には、HTSコードを「飲食料品」(Foods, Feeds, and Beverages)、「工業原材料」(Industrial Supplies and Materials)、「資本財」(Capital Goods, Except Automotive)、「消費財」(Consumer Goods)、「自動車・同部品」(Automotive Vehicles, Parts, and Engines)、「その他」 (Other Goods)のいずれかに分類される。
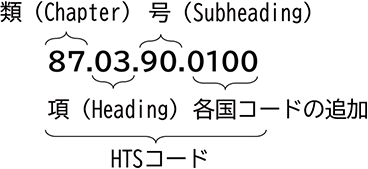
まずは、財輸出入を主要品目別にみると、輸出は、工業原材料(35%)、資本財(31%)、消費財(13%)の順にシェアが大きい。輸入は、資本財(29%)、消費財(25%)、工業原材料(21%)の順にシェアが大きい。
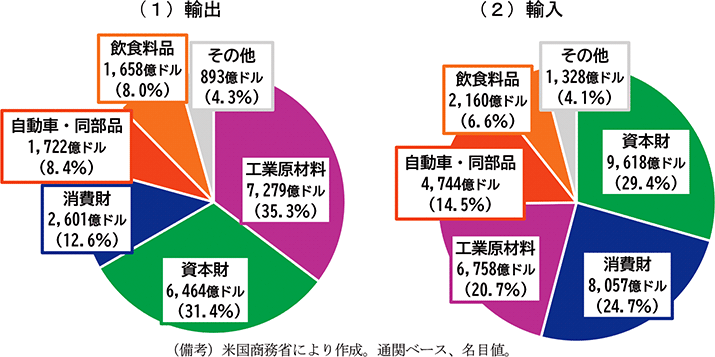
次に、主要品目別の収支をみると、全体として輸入額が輸出額を上回り、収支は赤字となっているものが多い(第2-1-9図)。特に消費財(▲5,456億ドル)、資本財(▲3,154億ドル)、自動車・同部品(▲3,021億ドル)の順に赤字が大きい。一方、工業原材料では輸出超過となっており、主要品目の中では唯一の黒字となっている。
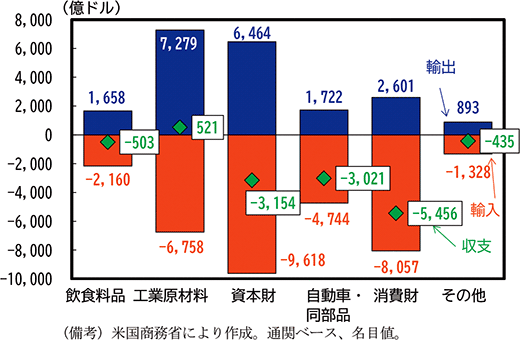
次に、主要品目を構成する詳細な品目は具体的にどのようなものか、2024年のデータを用いて主要品目の詳細品目を輸出、輸入に分けて確認する。
(飲食料品)
まずは、飲食料品の輸出入動向を確認する(第2-1-10図)。輸出については「穀物、飼料」のシェアが39.5%と最も大きい。さらに、「穀物、飼料」の中でも、大豆、トウモロコシが高いシェアを占めている6。飲食料品について、輸出額と輸入額を合わせた米国の貿易総額の上位国をみると(第2-1-11図)、隣国であるメキシコ、カナダが最も大きく、次いで中国となっている。メキシコ、カナダとの飲食料品の輸出、輸入をみると(第2-1-12図)、メキシコからは「野菜、果物、ナッツ」を多く輸入し、カナダからは、「畜産物」を多く輸入していることが分かる。
中国に対しては、米国の輸出超過となっているが、特に「大豆」の輸出が多く、米国の「大豆」輸出の約5割は中国向けである。また、日本、韓国に対しても米国は輸出超過となっており、これは、米国は農産品に関して比較優位を持っていることに起因している。
輸入は、「野菜、果物、ナッツ」(25.1%)のシェアが最も大きく、次いで「畜産物」(22.8%)が大きい。「野菜、果物、ナッツ」、「畜産物」の輸入相手国では、隣国であるメキシコ、カナダからの輸入シェアがそれぞれ大きい7。また、メキシコ、カナダに次いで輸入超過となっているイタリアからは「食用油・油糧種子」、「パン製品」、ブラジルからは「コーヒー豆」の輸入が多い。
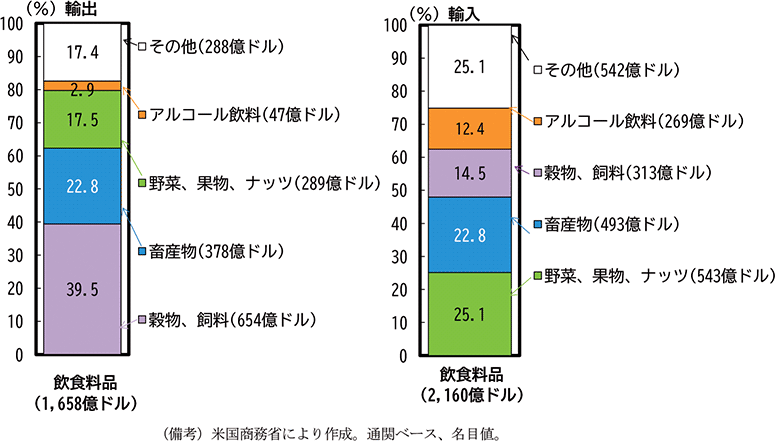
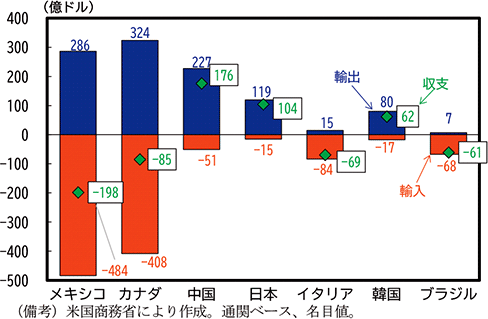
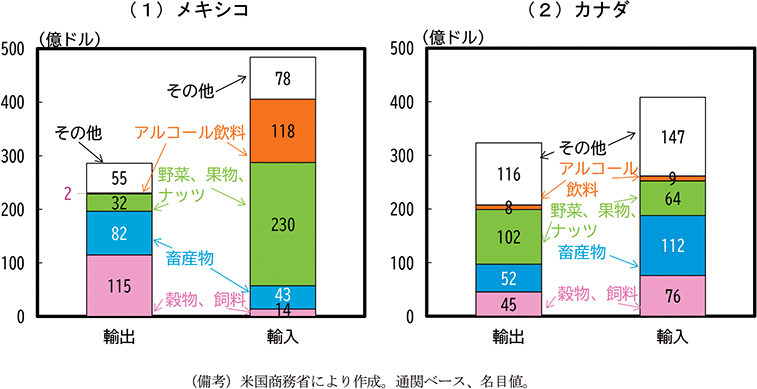
(工業原材料)
次に、工業原材料の輸出入について確認すると(第2-1-13図)、原油・石油等を含む「エネルギー・燃料8」が輸出(46.5%)と輸入(37.8%)のいずれにおいてもシェアが大きい。輸入相手国では、カナダが半分を占めている(詳細は後述)。また、鉄鋼・アルミニウムや鉱物資源を含む「金属・鉱物等」も、輸出(18.2%)と輸入(27.8%)においてシェアが大きい。
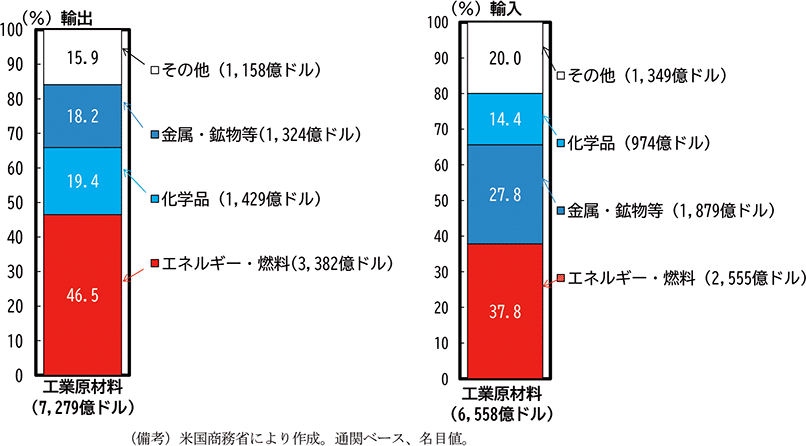
金属と鉱物に分けて輸出入を確認すると(第2-1-14図)、いずれの品目においても主要な相手国はカナダ、メキシコである。また、「アルミニウム9」、「銅」の輸出入をそれぞれみると(第2-1-15図)、アルミニウムはカナダからの輸入が多く、銅はチリからの輸入が多い。これは、カナダはアルミニウムの生産量が世界第4位と多いこと、チリは銅の生産量が世界第1位と多いことに起因する(第2-1-16図)。なお、鉱石は採掘後に不純物を取り出す精錬工程を経てから市場に流通する製品になることから、その過程を見越して、自国以外の国・地域において重要鉱物の埋蔵が確認されたことが分かった段階で、その国・地域に対し、国として積極的な投資を行い、鉱山などの権益を確保することで精錬のシェアを拡大させる動きがみられる。野木森(2023)によると、重要鉱物は世界の様々な国・地域で採掘可能であるが、精錬・加工プロセスは中国に集中していることが指摘されている10。
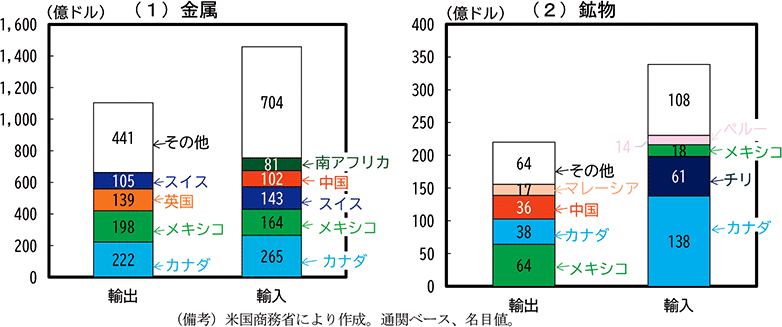
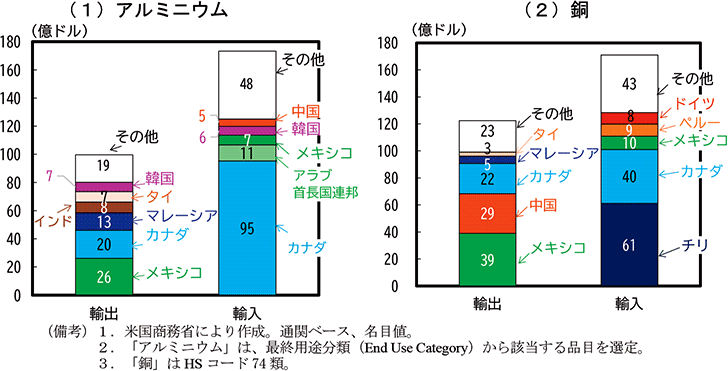
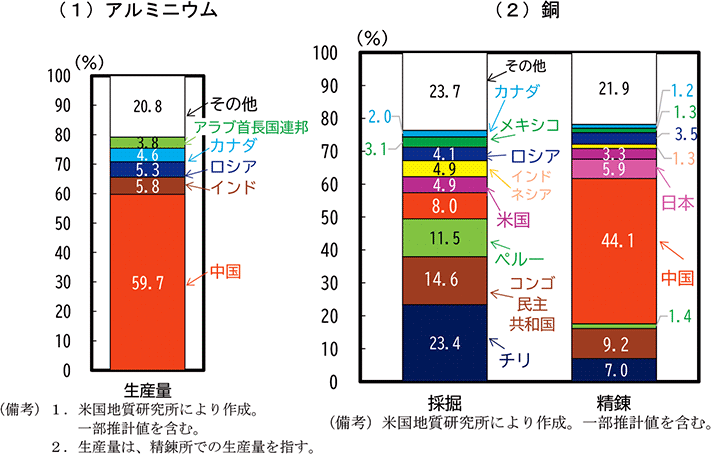
次に、米国の一次エネルギーの生産、輸出入を確認すると(第2-1-17図)、1960年以降、輸入量が輸出量を上回っていたが、シェールガス革命11を受けて一次エネルギーの生産量と輸出量は2010年以降に拡大し、2020年には輸出量が輸入量を上回り、その差は拡大傾向にある。
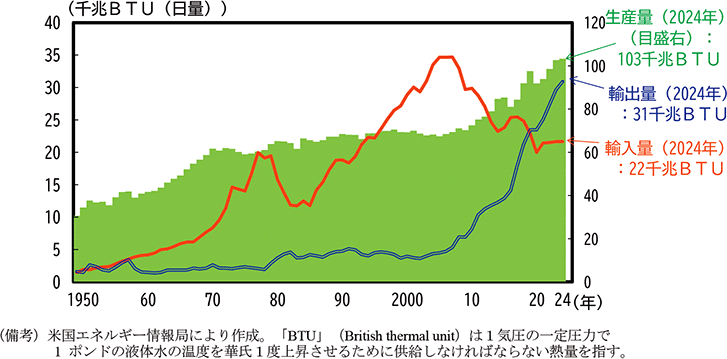
工業原材料の貿易総額の上位国をみると(第2-1-18図)、カナダからの工業原材料の輸入が最も大きく、カナダに対する貿易収支が▲1,148億ドルと最大となっている。カナダの貿易統計から米国向けの「原油・石油等12」の輸出を確認すると、米国向け輸出のシェアは全世界向け輸出の95.6%であり、カナダのエネルギー輸出の最大の相手国は米国である。これは、カナダと米国の間には、「メインライン」等の主要なパイプラインが存在し、カナダから米国への原油・石油等の輸送システムが確立されていることが関係している13。
カナダから米国各州への原油・石油等の輸出額をみると(第2-1-19図)、特に米国の中西部に位置するイリノイ州への輸出額が大きいが、これは前述のパイプライン「メインライン」の主なルート先に含まれる州であり、かつ、米国の中西部が米国内のパイプライン網における結節点となっていることが要因と考えられる。米国の国防石油行政区(Petroleum Administration for Defense District)14の「原油等15」の移出量をみると(第2-1-20図)、イリノイ州のある中部地域から他地域への移出量が最も多い。中部地域に次いで他地域への移出量が多い地域は、米国内で一次エネルギー生産量が最も多いテキサス州のある湾岸地域である。地域間の移出量をみると、
- 中部地域から湾岸地域への13.5億バレル(全地域向け移出のうち66.5%)
- 湾岸地域から大西洋岸地域への12.9億バレル(同上68.9%)
- ロッキー山脈地域から中部地域への6.3億バレル(同上83.4%)
の順に多い。このことから、カナダから輸入した原油・石油等が、米国中部地域から米国内の他地域に移出されていることが示唆される。
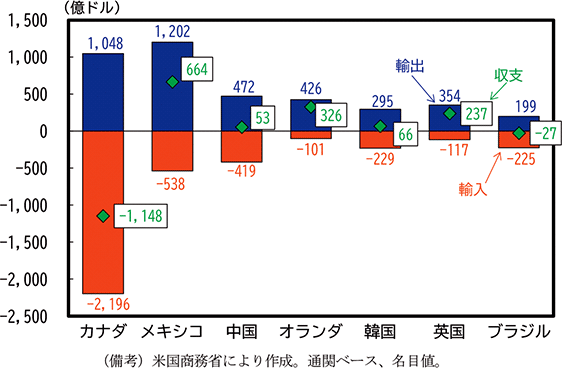
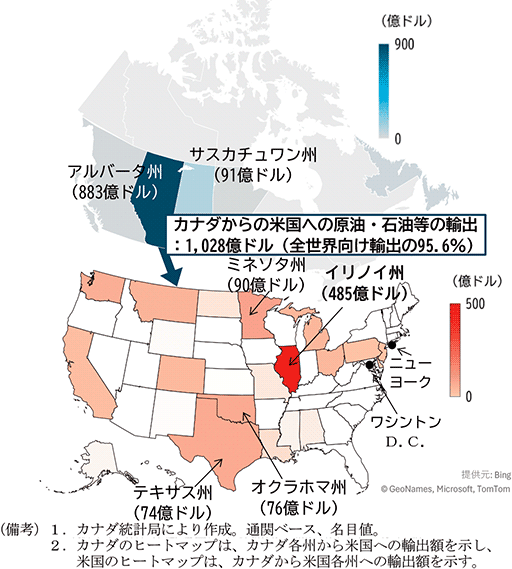
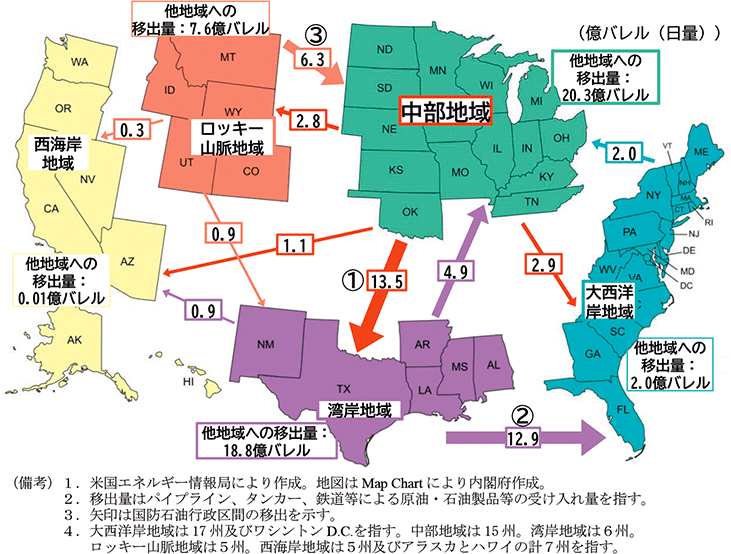
米国の原油・石油等の輸出入の相手国・地域をみると(第2-1-21図)、ロシアのウクライナ侵略を受け、対ロシアの制裁として欧州がロシア産原油の輸入を減らしたことから、欧州向けの米国産の原油・石油等の輸出が増えたと考えられる。米国では、全世界からの原油・石油等の輸入は減少傾向にあるものの、カナダからの輸入量は継続的に増加している16。
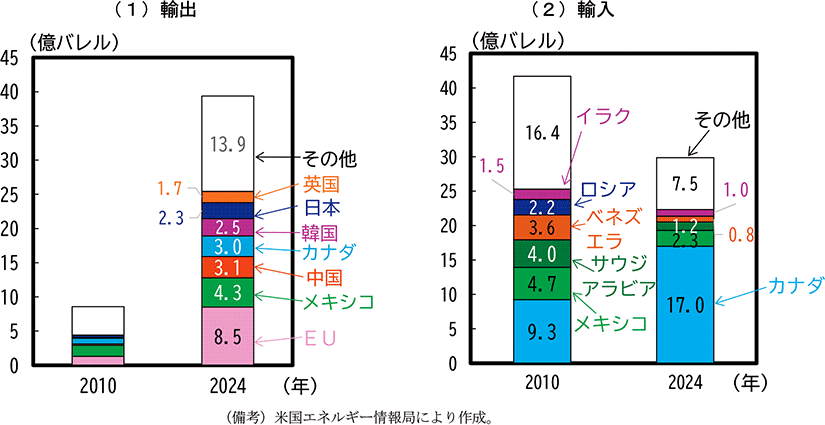
(資本財)
次に、資本財の輸出入動向について確認する(第2-1-22図)。資本財の輸出額(6,464億ドル)と輸入額(9,618億ドル)を合わせた貿易総額は、1.6兆ドルと主要品目の中で最大である。資本財の中では、民間航空機・同部品、コンピュータ・同周辺機器、半導体等、他国との水平分業が多く行われている財を中心に、貿易総額が大きくなっている。
詳細品目をみると、輸出では、「民間航空機・同部品」(19.2%)のシェアが大きい。輸入では、「コンピュータ・同周辺機器」(22.6%)のシェアが大きい。米国の資本財貿易は、輸出、輸入においてシェアの最も大きい品目が異なり、米国の企業が高い国際競争力を持つ「民間航空機・同部品」を輸出している一方で、製品の企画やデザインは米国で行うものの、生産工程は米国以外に設置することの多い「コンピュータ・同周辺機器」といった財を輸入している。
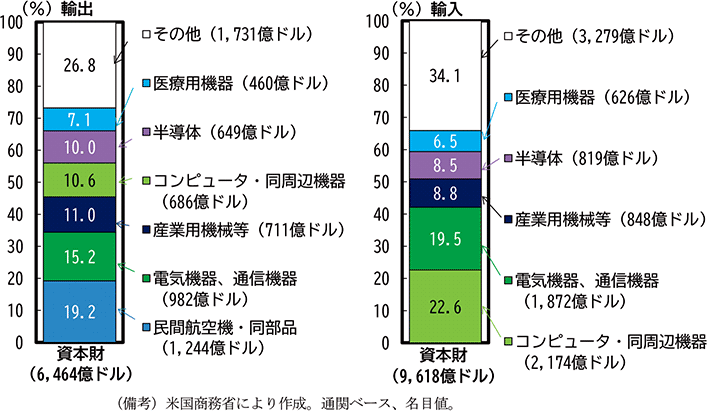
国・地域別に資本財の輸入額のシェアをみると(第2-1-23図)、輸入における中国のシェアは、2015年から2024年にかけて28.9%から15.0%まで低下した。一方、メキシコのシェアは、同期間において、14.0%から17.0%へと上昇し、2024年には中国のシェアを抜いて最大の輸入相手国となった。また、台湾のシェアも3.3%から9.4%へと上昇している。これは、第一次トランプ政権が2018年7月に半導体やその他工業製品を含む340億ドル相当の中国製品に対し25%の追加関税を発動し、その後も複数回にわたって中国から輸入される製品に対し追加関税を発動17したことにより、中国からの資本財の輸入コストが増加したことなどが挙げられる。また、経済安全保障上の懸念もあり、米国企業が調達先を多様化したことも考えられる(先端技術製品の貿易動向についてはBox参照)。
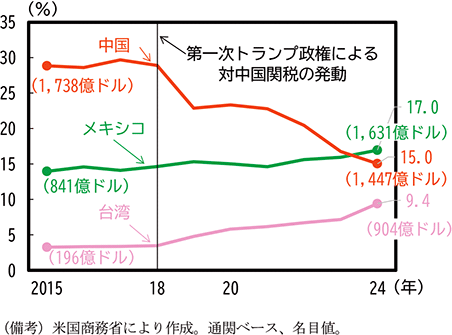
資本財輸入で最もシェアが大きい「コンピュータ・同周辺機器」を国・地域別にみると(第2-1-24図)、中国からの輸入額が2018年以降緩やかに減少する中、台湾、メキシコからの輸入額が増加し、2024年にはそれぞれ中国を上回った18。一方、米国の中国向けのコンピュータ・電子機器部門の対外直接投資残高の推移を確認すると(第2-1-25図)、中国向けについては、2012年以降増加傾向にあり、2023年には172億ドルとなり、台湾、メキシコを上回っている。このことから、米国の企業のコンピュータ等の生産工程の一部は、引き続き中国に設置されていると考えられる19。
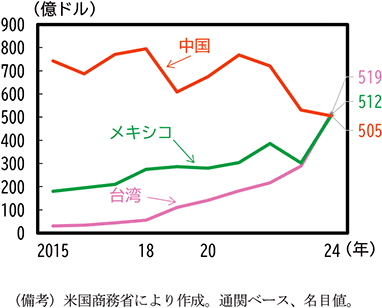
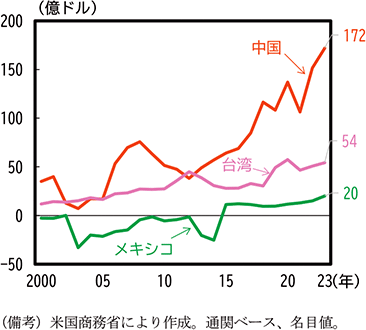
Box.先端技術製品(Advanced Technology Product)の貿易動向について
ここでは、財貿易における先端技術製品の動向を確認する。米国商務省は、「先端技術製品」(Advanced Technology Product)として、化学、情報、電子、自動化装置、航空宇宙、軍事、原子力等の10の分野別の分類を行っており(表1)、それぞれの分野に対応する品目のHTSコードを公表している。2015年から2024年までの貿易動向を確認すると20、先端技術製品の輸出、輸入ともに増加傾向にあるが、輸入が輸出を上回るペースで増加した結果、赤字は拡大している。また、先端技術製品の財貿易全体に占めるシェアは、輸出、輸入、収支のいずれも約2割となっている(図2)。
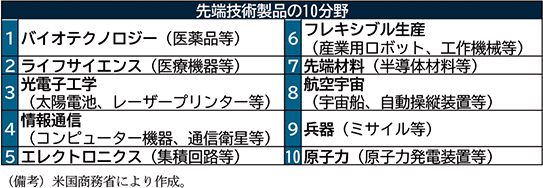
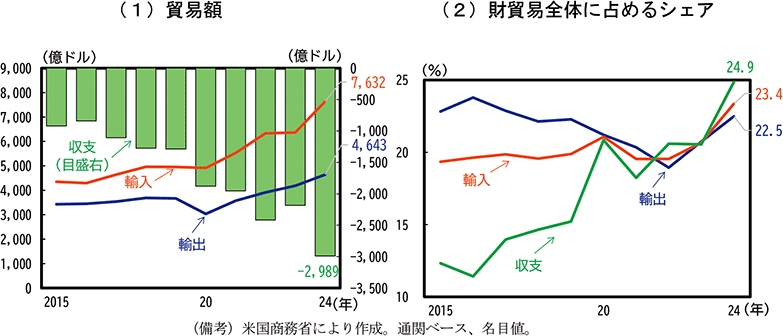
先端技術製品の輸出、輸入を相手国・地域別に確認すると(図3)、2015年から2024年にかけて輸出相手国・地域はほとんど変化がない。一方、輸入相手国・地域は、中国のシェアが35.7%から14.7%に低下している。これは、2018年以降の米中貿易摩擦もありサプライチェーンの見直しが進んだ表れである可能性がある。一方、輸入相手国・地域のうち、アイルランド、台湾のシェアは上昇した。アイルランドからは医薬品、台湾からは半導体等の輸入が増加しており、アイルランドは「バイオテクノロジー」、台湾は「情報通信」、「エレクトロニクス」の輸入が増加に寄与していると考えられる(図4)。
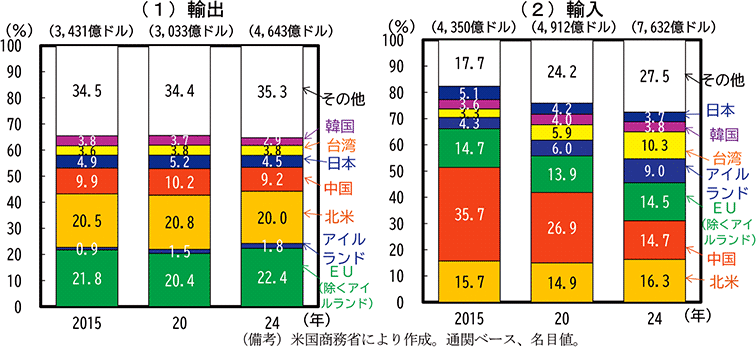
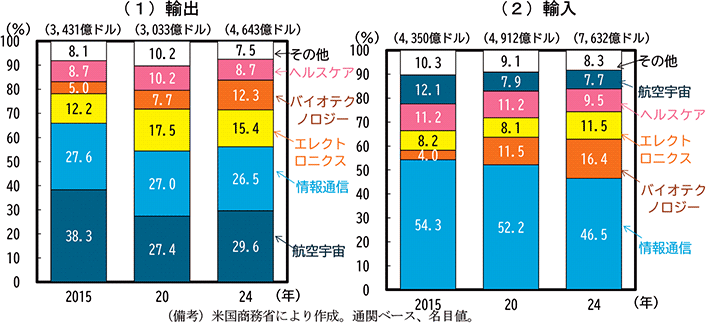
(自動車・同部品)
次に、自動車・同部品の輸出入動向について確認する(第2-1-26図)。自動車・同部品の輸出入に占める詳細品目別シェアを確認すると、輸出入ともに完成車(乗用車、トラック、バス等)が5割以上を占めている。ただし、金額規模でみると、いずれの詳細品目においても輸入が輸出を上回っている。また、貿易総額の上位国をみると(第2-1-27図)、メキシコ、日本、韓国、ドイツといった国とは貿易赤字となっている。
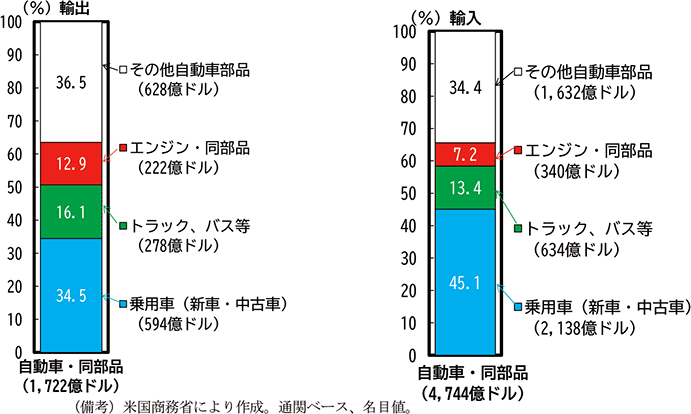
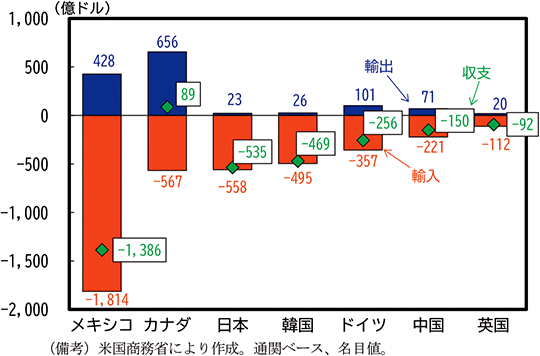
自動車・同部品の品目別の輸入額を国別にみると(第2-1-28図)、自動車・同部品は2010年から2024年にかけてメキシコのシェアが上昇している。特に完成車の輸入シェアが伸びており、その輸入シェアは、カナダと日本を抜いて1位となった。
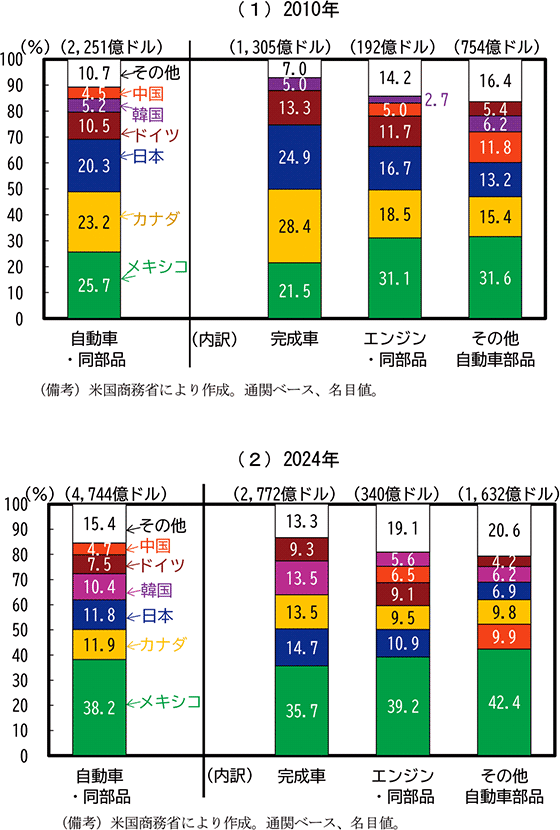
自動車・同部品の生産拠点がメキシコに多く立地されるようになった要因としては、北米自由貿易協定(NAFTA)やそれを基にした米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の発効とともに、両国の賃金格差が一つの要因として考えられる。2004年、2014年、2024年におけるメキシコ、カナダ、米国の製造業の雇用者の平均給与(月額)をみると(第2-1-29図)、3か国とも平均給与は2004年から2024年にかけて増加しているものの、メキシコの製造業の雇用者の平均給与は、カナダ、米国に比べ低い水準で推移している。また、メキシコでは1983年に、自動車産業の製造の振興のため、マキラドーラ21が導入され、外資系企業の誘致が活発になった。その後も政令による国産化義務の緩和などがあり、自動車メーカーを輸出のための新規投資に誘導した。また、1970年代には米国の大手自動車会社(いわゆるビッグスリー22)は北米大陸規模で生産体制を見直し、車種ごとに生産拠点を振り分けた。開発コストと製造コストの節約のため、海外へ生産拠点を移していく中で23、メキシコは中小型車とエンジン、労働集約的な部品の生産拠点を定め、投資を拡大した。加えて、メキシコの教育水準が向上することで労働者の技能や技術水準も上がったことも自動車産業の振興に寄与したと考えられる。
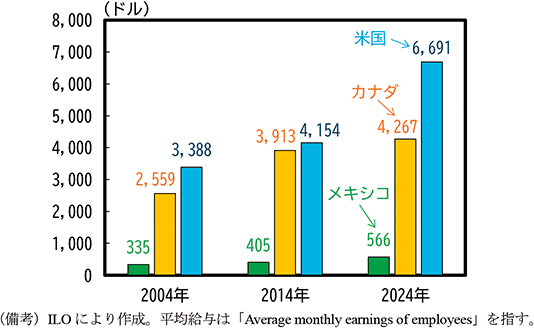
米国とメキシコ、カナダの自動車の生産、販売、輸出入台数をみると(第2-1-30図)、メキシコ、カナダからの輸入が米国国内の自動車販売を補完することで米国における旺盛な自動車需要がまかなわれていることが分かる。メキシコは、自国内での生産台数が販売台数を上回っており、輸出先の大部分は米国向けである。
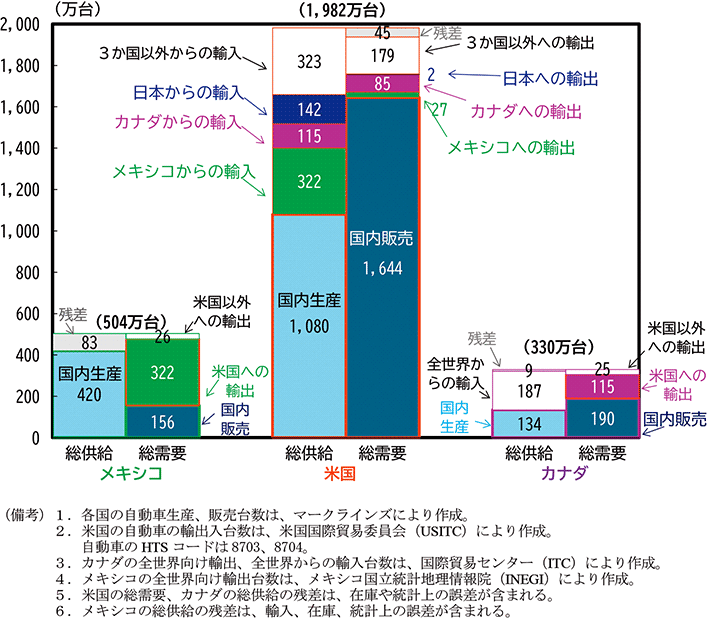
(消費財)
次に、消費財について確認する(第2-1-31図)。消費財の輸入(8,057億ドル)は、輸出(2,601億ドル)の約3倍であり、国別では、中国、アイルランドからの輸入が多い(第2-1-32図)。詳細品目をみると、「医薬品」のシェアは、輸出(41.4%)、輸入(30.6%)のいずれにおいても最大である。特にアイルランドからの医薬品の輸入額シェアは約3割と高い(第2-1-33図)。また、アイルランドは、対内直接投資を呼び込むための税制優遇、英語という共通言語といった面で有利な点が多いことから、米国の多国籍企業によるアイルランドを生産拠点とした医薬品の役割が大きくなっている(詳細については後述)。また、医薬品以外の主要な輸入品目としては「衣料品・履物」、「携帯電話、その他家庭用品」、「玩具類」、「家具、家庭用品等」があり、いずれも国別でみると中国のシェアが最も大きい。また、「携帯電話、その他家庭用品」に含まれる「スマートフォン」は、中国、インドからの輸入が9割を占めている24。
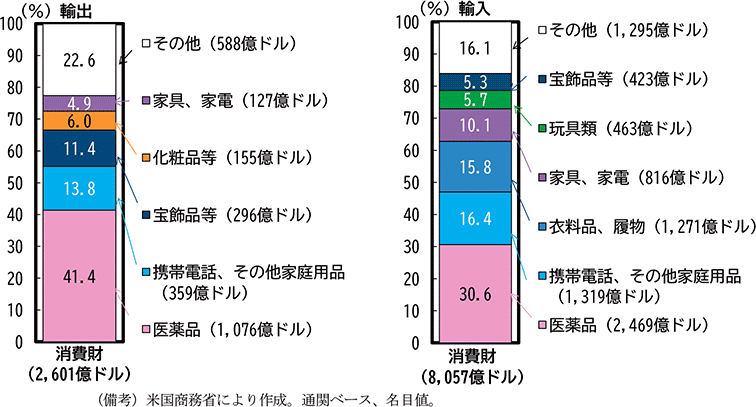
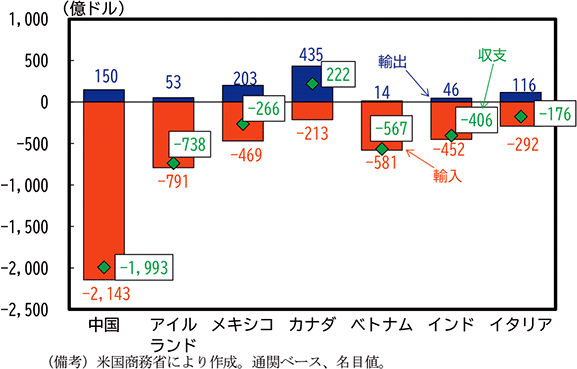
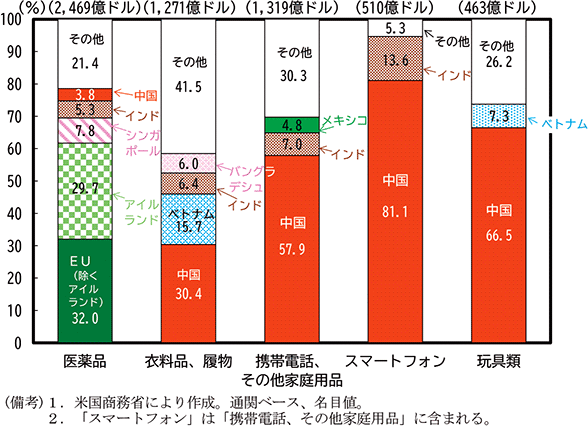
国・地域別に消費財輸入のシェアをみると(第2-1-34図)、2015年の中国のシェアは39.3%、2020年は34.0%、2024年は26.6%と低下しているものの、いずれの年も中国のシェアが最大である。なお、中国のシェアが低下する一方、アイルランド(2015年:4.9%、2024年:9.8%)、ベトナム(2015年:4.3%、2024年:7.2%)のシェアが上昇している。アイルランドのシェアが上昇している要因としては、前述のとおり、医薬品の生産拠点としての取引が多くなっていることによるものである。ベトナムのシェアが上昇している要因としては、2018年以降の米中貿易摩擦や中国における賃金上昇に伴い、企業が生産拠点の多様化を図ったことが挙げられる。
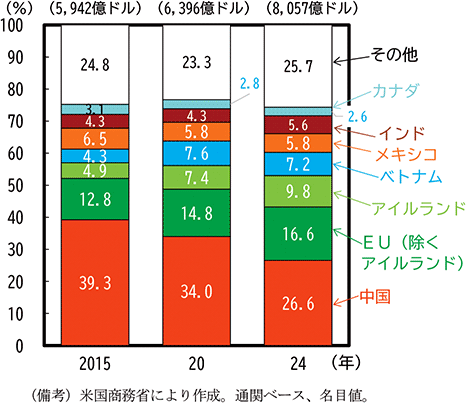
次に、縦軸に財輸出額、横軸に財輸入額、円(バブル)の大きさは財貿易総額(財輸出と財輸入の合計)を示したバブルチャートを確認する。右上に位置する品目は貿易総額が大きく、45度線より上(下)に位置する品目は輸入超過(輸出超過)である。ここでは45度線の下に位置する品目を米国が他国より比較優位のある品目、上に位置する品目を他国が米国より比較優位のある品目とみなして議論を進める。
まずは、主要品目別にみると(第2-1-35図)、資本財、工業原材料、消費財、自動車・同部品、飲食料品の順に貿易総額(円の大きさ)が大きい。この中で、工業原材料は輸出超過である一方、他の品目は輸入超過となっている。
詳細品目別にみると(第2-1-36図)、工業原材料の「エネルギー・燃料」、「化学品」、資本財の「民間航空機・同部品」、飲食料品の「穀物、飼料等」については米国が比較優位のある品目である。一方、「完成車」、消費財の「医薬品」、資本財の「コンピュータ・同周辺機器」、飲食料品の「野菜、果物、ナッツ」は他国が米国より比較優位がある。
このことから、米国が他国より比較優位のある品目の生産に特化して輸出し、他国が比較優位のある品目を輸入することにより、米国は自国内のみで生産するよりも多様な財をより安価に消費することができていると考えられる25。
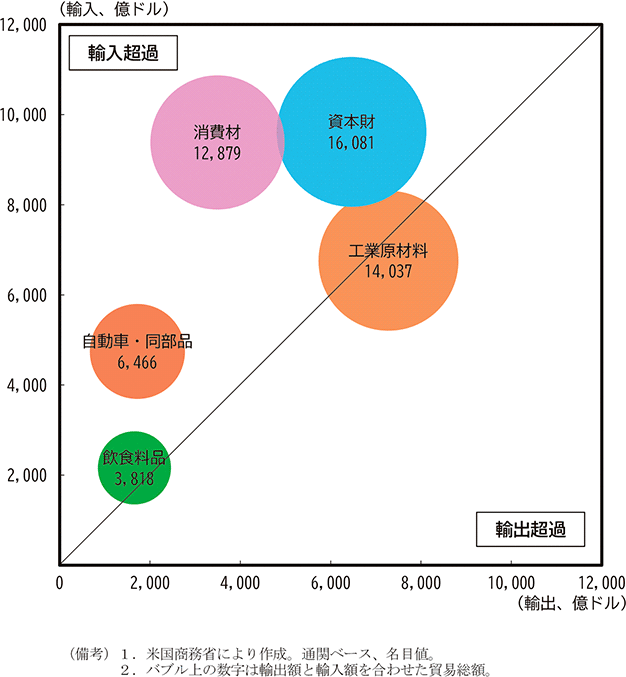
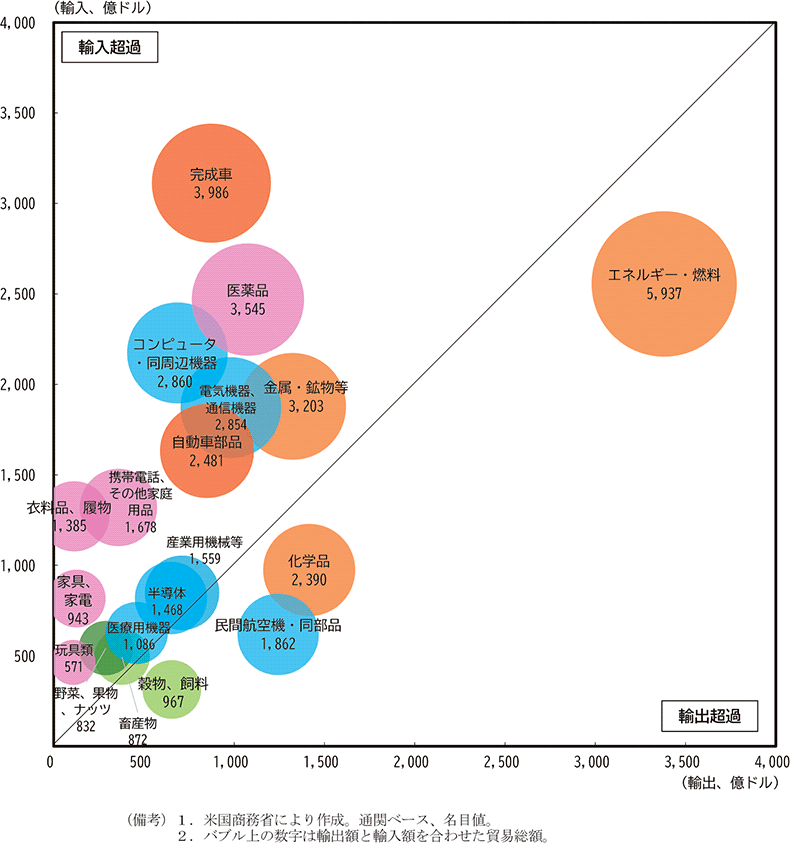
2.重力モデルを用いた財貿易の構造分析
これまで、米国の財貿易の基本構造について概観してきた。ここでは、国際貿易の重力モデル(Gravity Model)を用いて、米国の財貿易の特徴を分析する。具体的には、「①全ての国の財貿易を対象とした分析」「②米国の財貿易額を対象とした分析」「③米国の財輸入を対象とした分析」の3種類の分析を行う。①で各国の財貿易にみられる一般的な傾向を確認したのち、②で米国の財貿易にみられる特徴を確認する。そして、③で米国からの財輸入額が大きい上位10か国・地域に焦点を当て、それらの国・地域が米国との財貿易額が大きくなる要因について分析する。
国際貿易における重力モデルは、物理学の万有引力の法則(二つの物体間に働く力は二つの物体の質量の積に比例し、二つの物体間の距離の二乗に反比例するという法則)を国家間の貿易額に応用したモデルであり、二国間の貿易額は両国の経済規模(GDP等)の積に比例し、二国間の距離に反比例すると仮定する。ただし、その関係は、厳密に成り立つものではなく、多くのサンプルが存在する時に、平均的に成り立つものと理解される。
t年の国iと国jとの間の財貿易額をTradeijt、国iと国jとの間の地理的距離をDistijt、国iと国jのGDPをそれぞれGDPit、GDPjt、誤差項をuijtとすると、
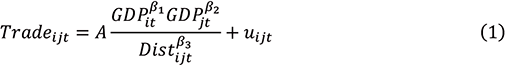
と表すことができる。ここで、
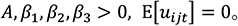
ここでは、フランス国際経済予測研究センター(CEPII)が提供する重力モデルを推計するためのデータベース(CEPII Gravity Database)(以下「CEPIIデータベース」という。)を用いて推計する。
重力モデルの推計に当たっては、ポアソン疑似最尤推定法(Poisson pseudo-maximum-likelihood method, PPML method)を用いる26。ポアソン疑似最尤推定法を用いることにより、最小二乗法で推計するよりも、より精度の高い推定値を得られることが知られている27。
(実証分析①:全ての国の財貿易を対象とした分析)
まずは、CEPIIデータベースに登録されている全ての国・地域28の財貿易のデータを用いて推定を行う。なお、貿易国同士で公用語が共通か否か、貿易国同士でFTAを締結しているか否か、年ごとの各国・地域共通の要因を捉えるために、対応するダミー変数を設定した29。Tradeijtをt年の国iの国jからの財輸入額30とすると、推定式は、式(2)のとおり(各変数の定義、推計結果の詳細は付注2-1参照)。
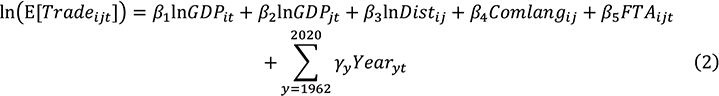
式(2)をポアソン疑似最尤推定法により推計した結果は、式(3)のとおりであり、各係数ともに、統計的に有意な結果が得られた31。
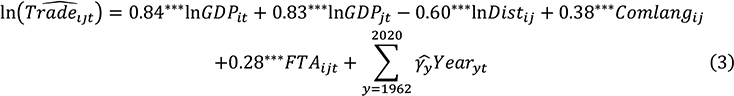
式(3)の各係数は、以下のとおり、解釈ができる。
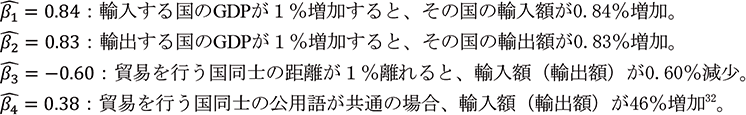
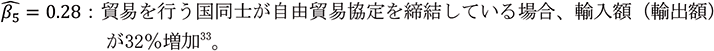
以上から、
- 財貿易額は、輸入国のGDP及び輸出国のGDPとそれぞれ正の相関がある
- 輸入国と輸出国との間で公用語が共通である方が財貿易額が大きくなる
- 輸入国と輸出国との間でFTAが締結されている方が財貿易額が大きくなる
- 輸入国と輸出国との間の距離が近い方が財貿易額が大きくなる
という重力モデルが想定している係数の方向性と一致する結果が確認された。
(実証分析②:米国の財貿易額を対象とした分析)
続いて、米国の財貿易にのみ焦点を当て、米国との財貿易額が大きい国の特徴について、重力モデルを用いて実証分析を行う。
CEPIIデータベースから米国の財貿易のデータのみを取り出し、ポアソン疑似最尤推定法を用いて推定を行った。なお、実証分析①と同様、米国の貿易相手国の公用語が英語か否か、米国と貿易相手国とでFTAを締結しているか否か、年ごとの各国・地域共通の要因を捉えるために、対応するダミー変数を設定した。加えて、米国との財貿易額(輸出額と輸入額の和)が大きい上位10か国・地域34(メキシコ、カナダ、中国、ドイツ、日本、韓国、台湾、ベトナム、英国、インド)により焦点を当てて分析するために、上位10か国・地域それぞれ特有の固定効果をみるためのダミー変数も設定した35。Tradejtをt年の米国の国jとの財貿易額(輸出額と輸入額の和)とすると、推定式は、式(4)のとおり。
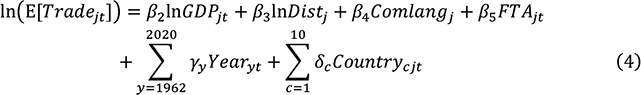
式(4)をポアソン疑似最尤推定法により推計した結果は、式(5)のとおりであり、各係数ともに、統計的に有意な結果が得られた。
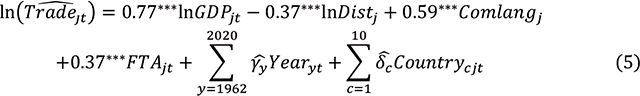
式(5)の各係数は、以下のとおり、解釈ができる。
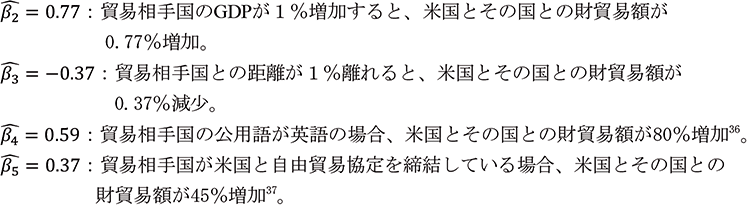
以上の結果から、米国との距離が近いほど、経済規模が大きいほど、米国との財貿易額が大きくなることが確認できた。
ここで、米国の2024年の財貿易額(財輸出と財輸入の総額)の相手国別の順位をみると、上から順に、メキシコ、カナダ、中国、ドイツ、日本となっている(第2-1-37表)。
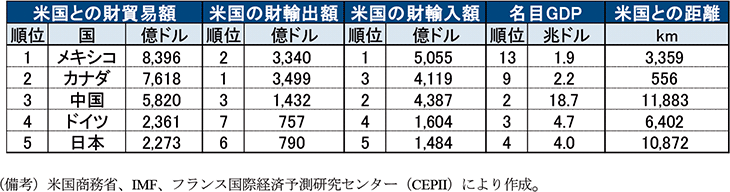
重力モデルによって得られた結果を直感的に理解するために、米国の財貿易額上位5か国を円(各国の円の面積は各国のGDPに比例)として世界地図の配置に沿って描画した図を確認すると(第2-1-38図)、メキシコとカナダは米国との距離が近い一方、中国、ドイツ、日本は世界のGDPの2位、3位、4位と経済規模が大きい(円の面積が大きい)。よって、重力モデルに基づく推計結果が示している①距離が近いほど財貿易額が増える(メキシコ、カナダ)、②貿易相手国のGDPが大きいほど財貿易額が増える(中国、ドイツ、日本)という結果と整合的に説明ができる。
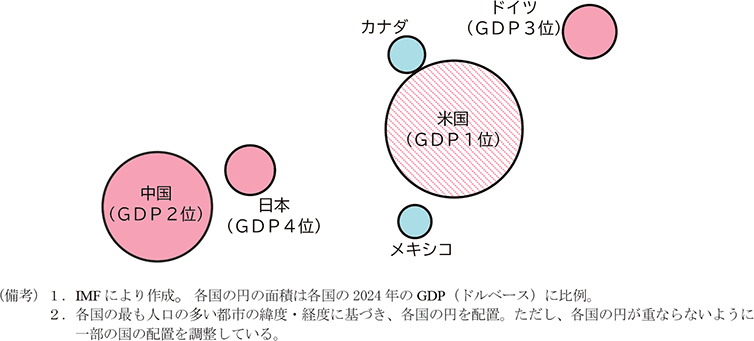
(実証分析③:米国の財輸入を対象とした分析)
さらに、より詳細に米国の貿易相手国の決定要因を整理するために、CEPIIデータベースから米国の財輸入のデータのみを取り出し、ポアソン疑似最尤推定法を用いて推定を行った。なお、実証分析①及び②と同様、米国の貿易相手国の公用語が英語か否か、米国と貿易相手国とでFTAを締結しているか否か、年ごとの各国共通の要因を捉えるために、対応するダミー変数を設定した。加えて、米国との財輸入額が大きい上位10か国・地域38(メキシコ、中国、カナダ、ドイツ、日本、ベトナム、韓国、台湾、アイルランド、インド)により焦点を当てて分析するために、上位10か国・地域それぞれの固定効果をみるためのダミー変数も設定した39。Importjtをt年の米国の国jからの財輸入額とすると、推定式は、式(6)のとおり。
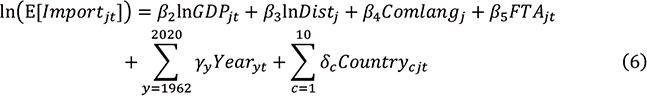
式(6)をポアソン疑似最尤推定法により推計した結果は、式(7)のとおりであり、一部の年ダミーの係数を除き、各係数ともに、統計的に有意な結果が得られた。
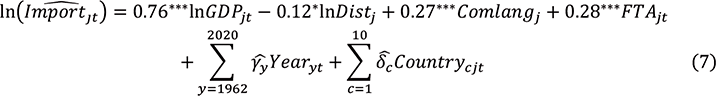
式(7)の各係数は、以下のとおり、解釈ができる。
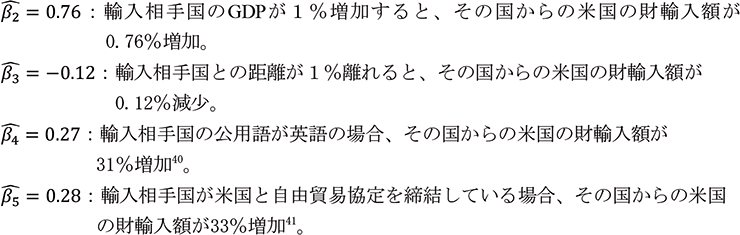
また、国・地域別固定効果の係数 については、ベトナム、台湾、韓国ともに統計的に有意な正の値が得られていることから、GDP、距離、共通言語、FTAの有無以外のその国・地域特有の要因から、米国のその国・地域からの財輸入が増えていることが示唆される。
については、ベトナム、台湾、韓国ともに統計的に有意な正の値が得られていることから、GDP、距離、共通言語、FTAの有無以外のその国・地域特有の要因から、米国のその国・地域からの財輸入が増えていることが示唆される。
以上の結果を踏まえ、米国の財輸入額上位10か国・地域それぞれの輸入額の決定要因を整理する。第2-1-39図では、米国の財輸入額上位10か国・地域を円(各国・地域の円の面積は各国・地域のGDPに比例)として世界地図の配置に沿って描画しており、第2-1-40表では米国の財輸入額上位10か国・地域の基本情報を示している。
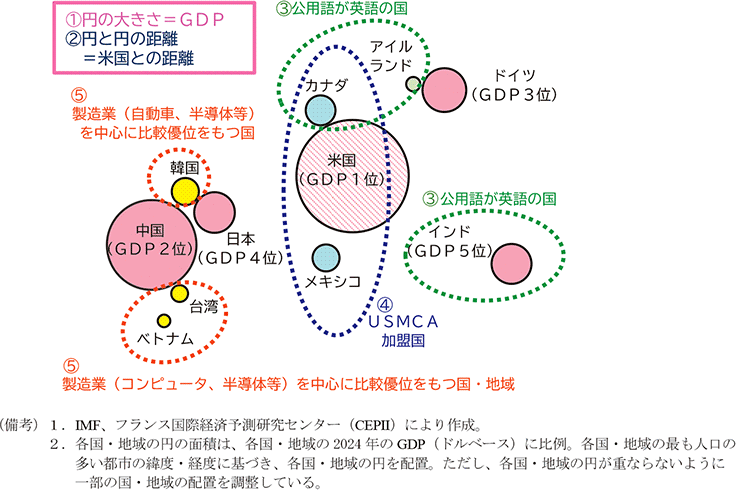
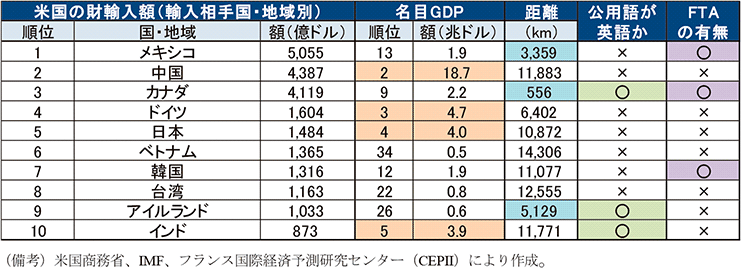
メキシコやカナダについては、米国との距離の近さや米国との自由貿易協定(USMCA)があることから、米国の同国からの財輸入が大きいと考えられる。第1項で確認したとおり、メキシコとカナダは米国向けの自動車・同部品供給網が立地しており、米国の自動車・同部品の輸入の1位はメキシコ、2位はカナダとなっている。また、カナダと米国との間には原油・天然ガスを供給するパイプラインが形成されており、カナダから原油・天然ガスが米国に輸出されている。こうした米国のメキシコ、カナダからの財輸入は、米国との距離の近さやUSMCAの存在が寄与しているといえる。
また、中国、ドイツ、日本、インドについては、それぞれ、世界2位、3位、4位、5位の経済規模をもつ国であり、経済規模の大きさが米国の財輸入の大きさにつながっていると言える。具体的な品目としては、中国からは携帯電話、玩具、衣類等の消費財や、コンピュータ・同周辺機器等の資本財を輸入している。ドイツ、日本からは、自動車・同部品、工業用機械、医薬品等を輸入している。インドからは、携帯電話や医薬品等の消費財を主に輸入している。これらの経済規模の大きい4か国からは、それぞれの国が比較優位をもつ財を米国が輸入しているといえる。
アイルランドについては、米国との距離の近さや公用語が英語であることもあり、米国のアイルランド向けの直接投資額が大きい(詳細は第3節で後述)。特に、製薬会社がアイルランドに多数立地することから、第1項で確認したとおり、米国の医薬品の輸入額の1位はアイルランドとなっている。
ベトナム、台湾、韓国については、他の輸入上位国と比較して経済規模も小さく、米国との距離も遠く、公用語も英語ではないにも関わらず、米国の財輸入額上位6位、7位、8位となっており、重力モデルの説明変数とは別の要因から米国からの財輸入額が大きいと考えられる。ベトナム、台湾、韓国は、製造業を中心に比較優位をもつ国・地域である。特に、ベトナム、台湾からは、コンピュータ・同周辺機器、半導体など、韓国からは、自動車・同部品、半導体等の輸入が多く、これらの品目は、これら3か国・地域にそれぞれ国際競争力の高い企業が存在することに加え、米国にとってもサプライチェーン上必要不可欠な品目でもあることから、経済規模や米国との距離の遠さにも関わらず、これらの国・地域からの輸入が大きいと考えられる。また、サプライチェーンの多様化を進めるため、中国以外の代替的な生産拠点の確保(いわゆる「チャイナ・プラスワン」)の動きが進んでいることも、これらの国・地域の財輸入増加につながっている可能性がある。
以上、重力モデルを用いて、米国の貿易相手国の決定要因の整理を行った。今回行った分析から、米国との距離の近さ(カナダ、メキシコ)、経済規模の大きさ(中国、ドイツ、日本、インド)、距離が近く共通言語(アイルランド)、製造業を中心に比較優位をもつ(ベトナム、台湾、韓国)といった、国・地域ごとのそれぞれ異なる要因から米国の主要輸入相手先となっていることが分かる。また、ここでの分析を踏まえれば、貿易額の決定要因については、長期的にみれば、経済規模、二国間の距離、言語の共通性、各国産業の比較優位等の要因に依存すると考えられることから、米国政府が広範な関税措置を導入したとしても、追加関税措置それだけを受けて各国が柔軟に貿易相手国を変更することは容易でないことも示していると考えられる(米国の第二次トランプ次政権の通商政策については第2節で詳述)。
 と置き換えている。
と置き換えている。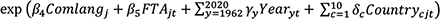 と置き換えている。
と置き換えている。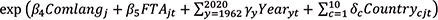 と置き換えている。
と置き換えている。
