第1章 2025年前半の世界経済の動向(第3節)
第3節 欧州の景気動向
本節では、主に2025年前半のユーロ圏及び英国経済を概観するとともに、今後の見通しとリスク要因について整理する。
1.ユーロ圏経済の動向
(ユーロ圏では、景気は持ち直しの動き)
ユーロ圏経済の動向を実質GDPの推移から概観50すると、2022年後半以降、前年比10%を超える消費者物価の上昇率とそれを抑制するための政策金利の引上げの影響もあり、個人消費や設備投資が停滞して、実質GDPは横ばい傾向で推移してきた。その後、物価上昇率の低下に伴う実質賃金の上昇等を受けて2024年11月から消費は持ち直しの動きがみられることに加え、一部に駆け込み輸出がみられることから、2025年1-3月期の実質GDP成長率は前期よりも上昇しており、景気は持ち直しの動きがみられる(第1-3-1図)。
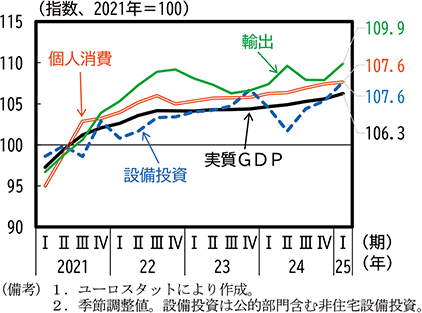
(個人消費は持ち直しの動き)
ユーロ圏の個人消費を、実質GDPの家計消費からみると、サービス消費は堅調に推移する一方、非耐久消費財や半耐久消費財は、2022年10-12月期以降はおおむね横ばいで推移している。2023年後半以降は消費者物価上昇率の鈍化と名目賃金の上昇を受けて実質賃金がプラスで推移していることから、総じてみれば、消費は持ち直しの動きが続いている(第1-3-2図)。
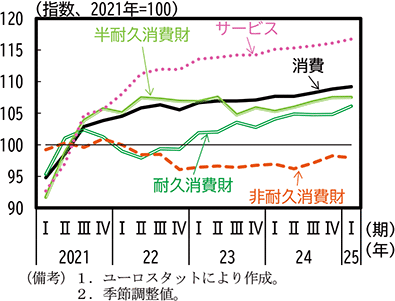
次に、実質小売販売額をみると、実質賃金がプラスで推移したこともあり、2024年後半以降、上向きの動きとなっている(第1-3-3図、第1-3-4図)
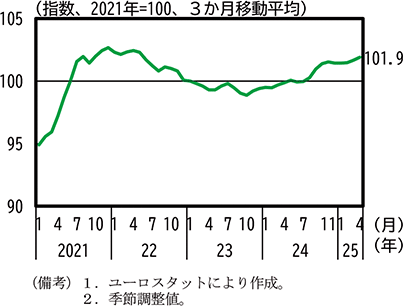
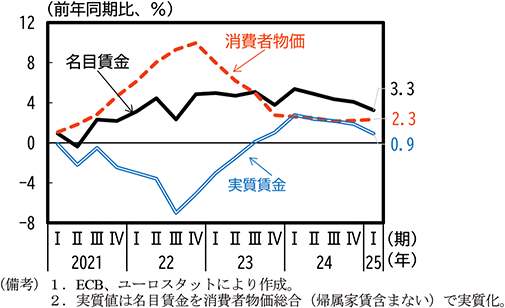
自動車の新規登録台数をみると、感染症拡大に伴う供給制約が解消された2023年9月以降も感染症拡大前の2019年を下回る水準で推移し、2025年4月においてもこの傾向が続いている(第1-3-5図)。
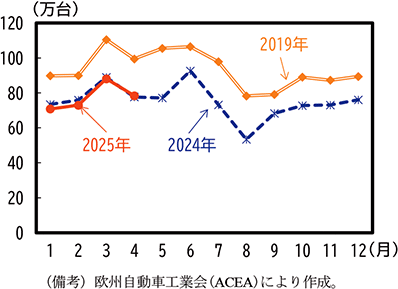
実質賃金がプラスで推移している中でも消費の回復が緩やかなものにとどまる背景には、消費者信頼感(消費者マインド)51の改善ペースの弱さが考えられる。消費者マインドを構成する、家計の現状と先行き、経済見通し及び高額商品購買意欲の推移をみる と、2024年に入って以降、家計の先行きのDI52は、消費者物価上昇率の低下を受けて、ほぼゼロ近傍まで改善しているが、経済見通しや高額商品購買意欲のDIは、雇用不安や物価見通しの悪化を受けた貯蓄志向の高さなどを背景に、停滞していた53。
また、米国の政策動向の影響を受けた不透明感の高まりを背景に、2025年1月以降、経済見通しのDIはマイナス幅を拡大しており、消費者マインド全体で見れば、おおむね横ばい圏内となっている(第1-3-6図)。
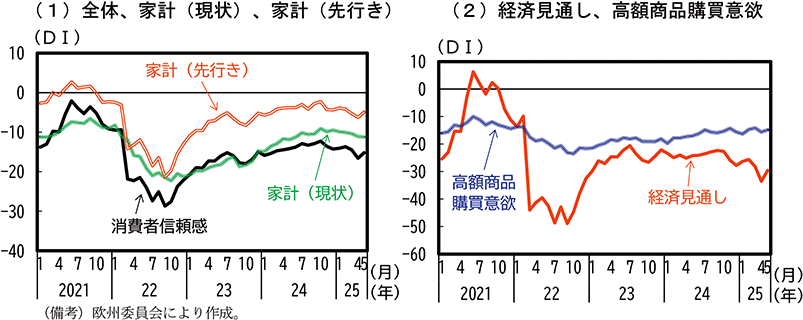
このように消費者マインドの改善ペースが弱いことから、足下では、家計貯蓄率は高止まりしている。家計貯蓄率は、感染症拡大で大きく上昇した後、感染症の収束ともに低下傾向となっていたが、2022年半ば以降は緩やかな上昇傾向に転じた。物価上昇の影響もあり、2023年7-9月期以降の家計貯蓄率は、実質賃金がプラスに転じている中でも、依然として感染症拡大前の平均を上回る水準で推移している(第1-3-7図)。
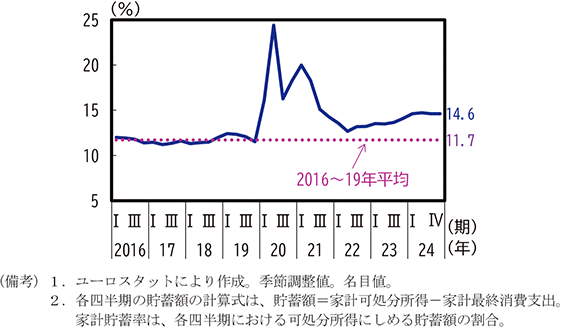
そこで貯蓄志向をみると、2022年5月以降、消費者物価上昇率の高まりを受け貯蓄志向はマイナスに転じたが、消費者物価上昇率の鈍化を受け、2023年2月以降、貯蓄志向はプラスに転じ、2023年末以降はプラス幅が拡大している。
2025年に入って米国の政策動向の影響を受けた不透明感の高まりから貯蓄志向は高止まりしていたが、連邦議会選挙後のドイツにおける政策の先行き不透明感の解消や「相互関税」の上乗せ部分の適用の3か月間停止を受け、貯蓄志向の高まりは鈍化した。ただし、依然として感染症拡大前(2015~19年)の平均を上回って推移するなど、貯蓄志向が高い状況であることに留意が必要である(第1-3-8図)。
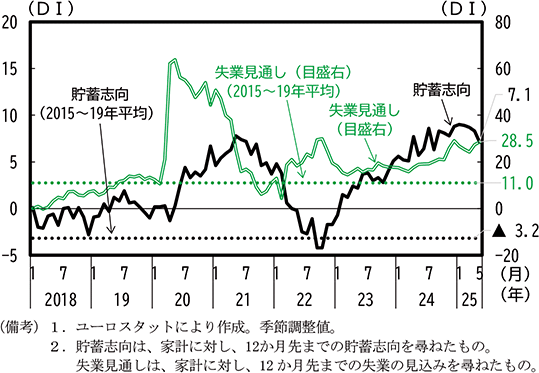
雇用不安について、失業見通しのDIをみると、感染症拡大期の2020年に大きく上昇したものの感染症の収束を受けて2021年夏頃には大きく低下している(第1-3-8図)。さらに、ロシアのウクライナ侵略を契機としたエネルギー価格の上昇、製造業を中心とした生産調整を背景に雇用不安は再び上昇に転じ、引き続き感染症拡大前(2015~19年)の平均を上回って推移している。
以上のように、実質賃金がプラスに推移している中、消費は、総じてみれば持ち直しの動きがみられているものの、政策の先行き不透明感や雇用不安、さらには米国の政策動向の影響による不透明感の高まり等を背景とした貯蓄志向の高さや消費者マインドの弱さなどから、ユーロ圏の消費の持ち直しの動きは緩やかなものにとどまっている。
(設備投資は持ち直している)
続いて、設備投資の動向を確認する。
2021年以降は、政策的な後押し54もあって脱炭素やデジタル化に向けた投資需要を中心に、知的財産生産物投資55、機械・機器投資及び構築物投資のいずれも持ち直しの動きがみられた。しかし2023年以降は、政策の先行き不透明感56に加え、高い金利水準の継続や中国等の輸出先の資本財需要の低下を受けた工場建設等を控える動きがみられ始めたことから、知的財産生産物投資、機械・機器投資及び構築物投資のいずれもおおむね横ばいとなった。その後、2025年1-3月期については、金利水準の低下や同年2月に行われたドイツ連邦議会選挙の結果(第1-3-10表)を受け、第1党となったキリスト教民主同盟(CDU)・キリスト教社会同盟(CSU)と第3党のドイツ社会民主党(SPD)が後述する財政拡張的な経済政策に合意したことで政策の先行き不透明感が薄れたことから、機械・機器投資は持ち直しの動きがみられており、設備投資全体としても持ち直している(第1-3-9図)。
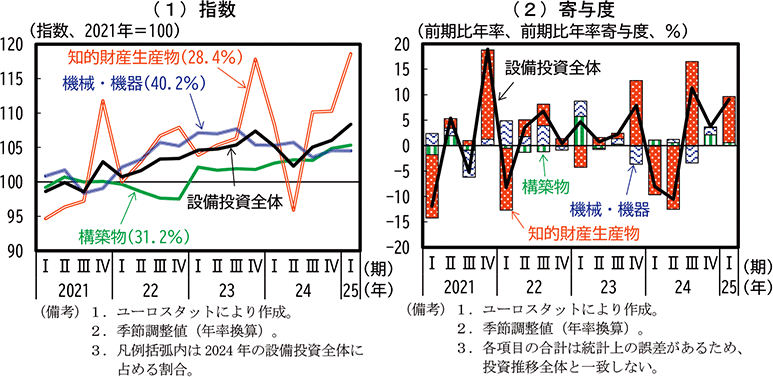
先行きについては、米国の政策動向の影響にも留意が必要である。2025年2月、米国がウクライナへの軍事支援の一時停止を発表するなど米国の欧州における安全保障スタンスが変わりつつあることも背景に、2025年3月、欧州委員会は域内の防衛力を抜本的に強化するための「欧州再軍備計画」(ReArm Europe Plan / Readiness 2030)57を公表した。同計画では、EU加盟国の防衛力強化を支援する最大1,500億ユーロの新たな融資制度を通じて、欧州の防衛能力への投資を迅速かつ大幅に増加させるとともに、「安定・成長協定58」の国別適用除外条項の協調的な発動により、EU加盟国の国防費増加を可能にすることとしている。
また、ドイツでは、2025年2月、連邦議会選挙が実施され、第1党となったCDU・CSUが第3党のSPDと連立政権を樹立し、2025年5月にメルツ政権が発足した。欧州の安全保障環境が大きく変化する中、CDU・CSUとSPDは連立政権樹立に向けた正式交渉に先立ち、2025年3月、インフラ基金の創設と債務ブレーキ59の見直しに合意した(第1-3-10表)。
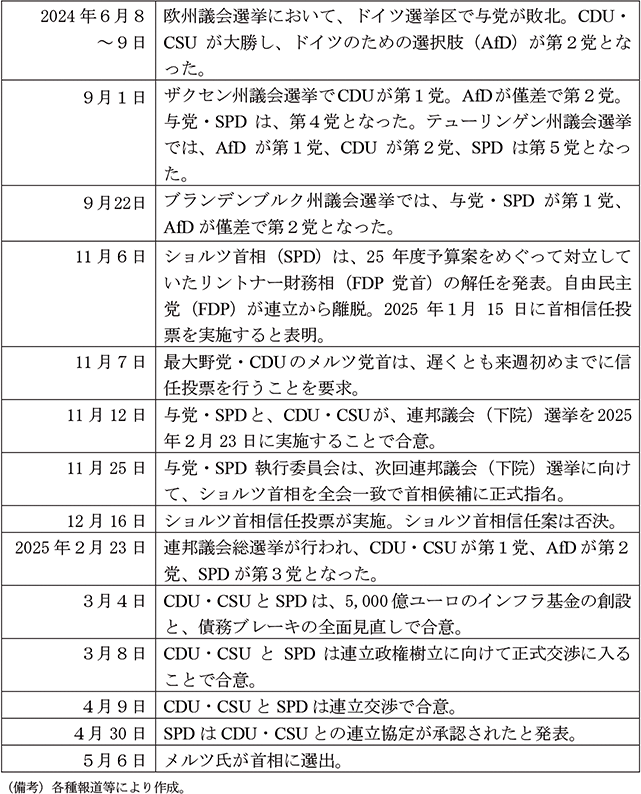
ドイツの設備投資マインドは、政策金利の低下や政策の先行き不透明感の解消が相まって、構築物投資や機械・機器設備投資、知的財産生産物投資の増加が見込まれるとの期待感から、製造業を中心に改善がみられ、DIが2025年初夏にはマイナス幅が3ポイント縮減した(第1-3-11図)。
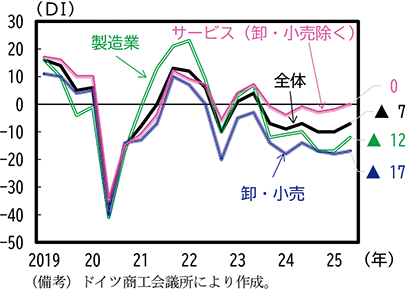
政策金利の引下げによって金融環境が投資を後押しする方向に作用するとともに、防衛支出の拡大は2025年後半以降の欧州各国の設備投資を押し上げる方向に寄与する可能性があることから、今後、ユーロ圏の設備投資は持ち直し基調で推移することが期待される。
(財輸出は一部に米国向け駆け込み輸出がみられ、このところ増加している)
続いて輸出の動向を確認する60。
まず、輸出(財輸出及びサービス輸出)をみると、感染症拡大後の落ち込みから持ち直した後、2022年以降は停滞がみられたものの、このところ持ち直している。輸出のうち、対GDP比(2024年)で32.7%を占める財輸出では、2022年7-9月期以降弱含んでいたものの、このところ増加している。一方、対GDP比(2024年)で16.8%を占めるサービス輸出は2021年以降増加している(第1-3-12図)。
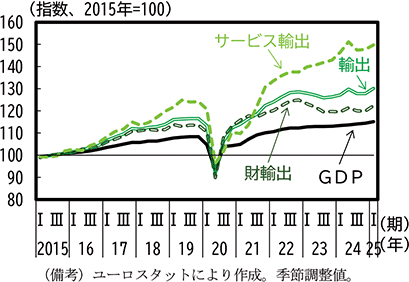
財輸出の動きについて、輸出相手国別の動向とともに分析する。
まず、ユーロ圏外への主要貿易相手国は、米国(構成比16.8%)、英国(同10.1%)、ポーランド(同7.4%)、中国(同6.7%)となっている(第1-3-13図(1))。主要相手国別の財輸出の動向をみると、英国のEU離脱や感染症拡大を受けて2020年1月以降、全体として減少したが、米国向け輸出の回復にけん引されて2020年8月以降は持ち直しの動きに転じた。2023年以降は中国の不動産市場の停滞に伴う需要減退を受け、中国向け輸出は緩やかな減少傾向にある。その後2025年に入り、米国の駆け込み需要を受けた輸出の増加がみられ、財輸出はこのところ増加している(第1-3-13図(2))。
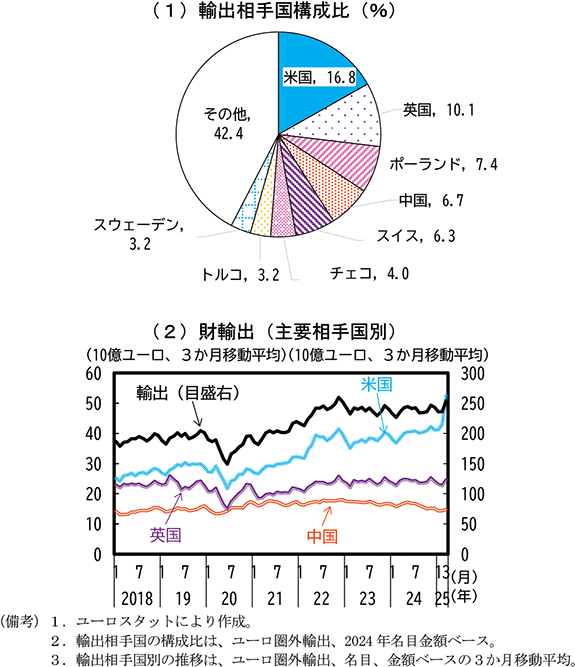
品目別財輸出をみると、化学・基礎薬品(構成比20.6%)、機械・機器(同12.5%)、自動車(同11.1%)が主要品目である。化学・基礎薬品は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン・医薬品の需要増もあって堅調に推移し、2020年以降財輸出をけん引している。特に、アイルランドには大手製薬企業が集積していることから、医薬品の輸出が堅調に推移61しており、米国、英国向けの化学・基礎薬品がユーロ圏の財輸出をけん引していると考えられる。一方、機械・機器や自動車は、2022年秋以降停滞しているが、これは中国の内燃機関車62への需要が低下したためである(第1-3-14図)。
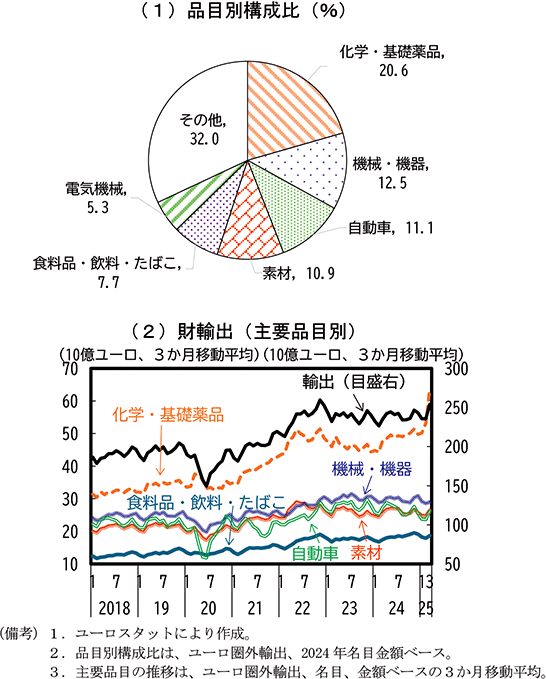
米国向け財輸出の国別構成をみると、ドイツ(構成比33.5%)、アイルランド(同15.1%)、イタリア(同13.5%)となっている。また、主要国の推移をみると、ドイツ及びイタリアは、振れを伴いながら緩やかな増加傾向にあったが、2025年2月以降、増加のペースが加速している。アイルランドも、振れを伴いながら緩やかな増加傾向にあったが、2024年以降増加のペースが加速し、2025年に入って急増している。一方、フランス及びオランダは、おおむね横ばいで推移している(第1-3-15図)。
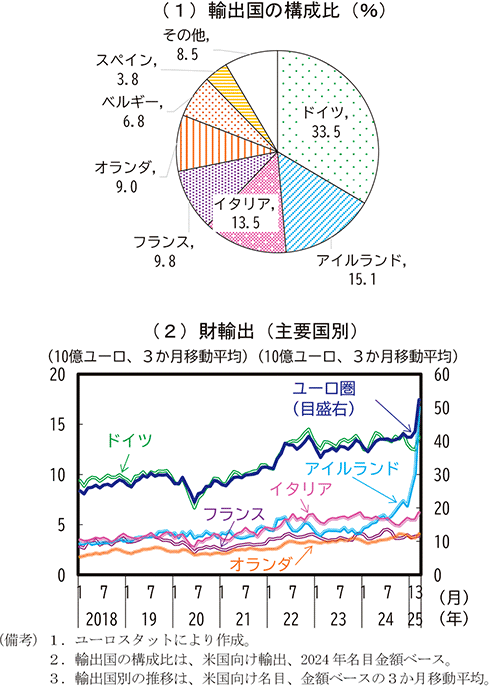
米国向けの財輸出の品目別構成をみると、化学・基礎薬品(構成比33.8%)、機械・機器(同13.4%)、自動車(同10.0%)となっている。また主要品目の推移をみると、機械・機器及び自動車はおおむね横ばいで推移。化学・基礎薬品は2018年以降緩やかな増加傾向にあったが、2025年に入り、米国の通商政策に伴う駆け込み需要を受け急増し、ユーロ圏の米国向け財輸出を押し上げている(第1-3-16図)。
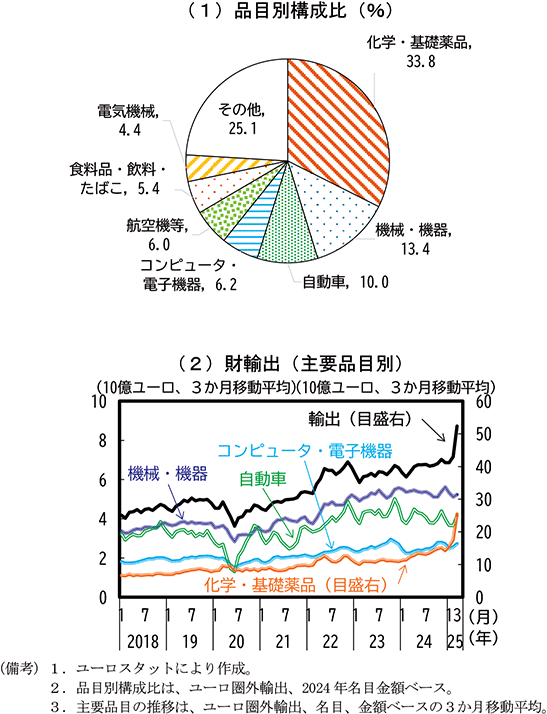
次に、中国向けの財輸出の品目別構成をみると、機械・機器(構成比20.2%)、化学・基礎薬品(同16.6%)、自動車(同12.8%)となっている。主要品目の推移をみると、機械・機器は振れを伴いつつも緩やかな増加基調にあったが、2024年6月以降減少に転じている。化学・基礎薬品は2023年2月から3月にかけて急増したものの反落し、その後はおおむね横ばいで推移している63。自動車については、2022年から2024年にかけて28.2%減少しており、自動車輸出の減少が中国向け輸出を下押ししていたが、2025年に入り下げ止まりの兆しがみえている(第1-3-17図)。
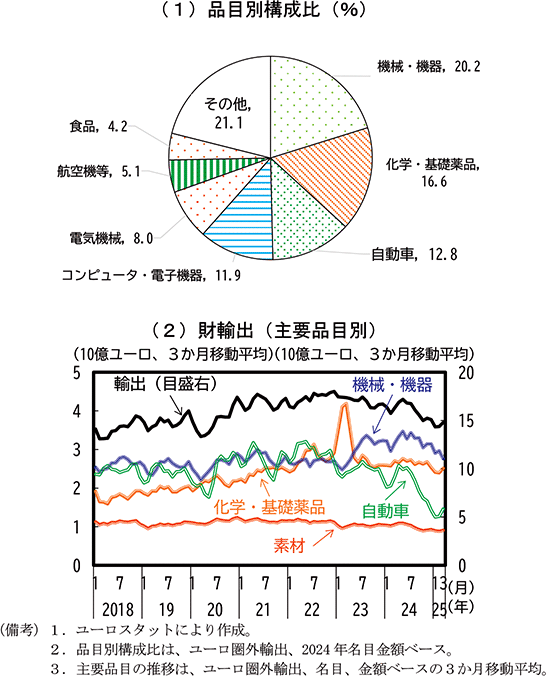
2025年1月以降、米国が関税措置を発表・実施する中、欧州委員会は2025年3月、鉄鋼・アルミニウムに係る関税措置に対し対抗措置を発表したが、その後、米国による「相互関税」の上乗せ部分の実施延期等の対応を受け、2025年7月14日まで対抗措置の発動を延期した(第1-3-18表)。
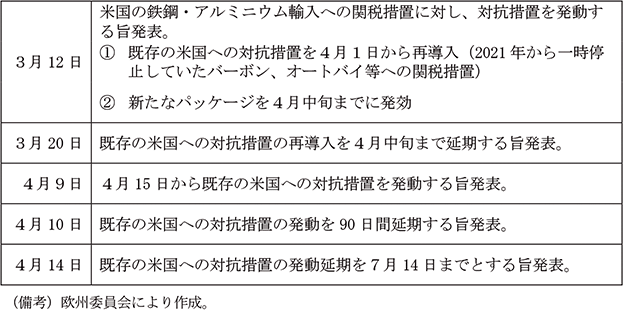
Box.米国の関税措置を受けたユーロ圏の財輸出の動向について
ユーロ圏外輸出について、輸出相手国別の寄与度を確認すると、米国向け輸出が2024年11月以降の輸出金額の増加に影響している(図1)。
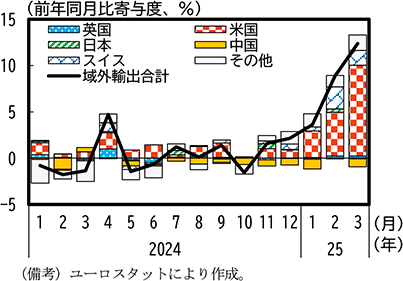
財別にみると、基礎薬品を含む化学製品が2024年11月以降増加し、2025年2月以降はさらに増加している(図2)。
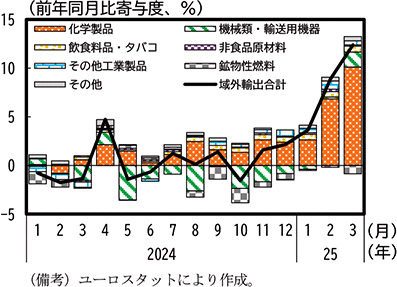
ユーロ圏の化学・基礎薬品は米国が最大の輸出相手国となっており(図3)、2025年2月以降の動向は、米国の関税措置を見越して関税発動前に輸出を前倒しする、いわゆる駆け込み輸出の動きによるものと考えられる。また、4月から5月に関税が発動された自動車・同部品については、機械類・輸送用機器の輸出が3月に増加しており、同様に駆け込み輸出によるものと考えられる(図2)。
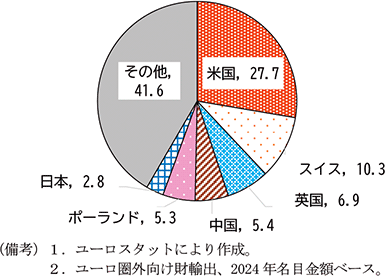
ユーロ圏の主要国別に米国への財輸出をみると、飲食料品が主な輸出品目であるスペインでは駆け込み輸出はみられず、化学・基礎薬品のシェアが大きいアイルランド、ドイツ、イタリアでは輸出金額が大きく増加しており、米国の駆け込み需要による財輸出の増加は国によって度合いが異なることが分かる(図4、5)。
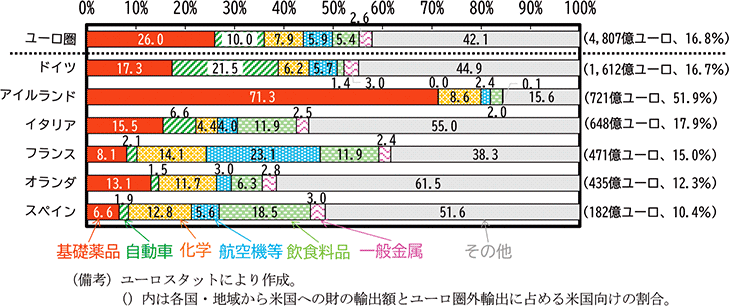
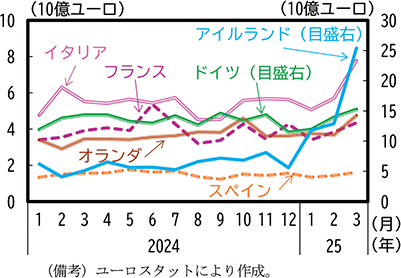
以上のように、ユーロ圏における圏外輸出は自動車を中心に中国向け輸出が押し下げている一方、化学・基礎薬品がけん引する米国向け輸出が押し上げており、国ごとにばらつきはあるものの、総じてみれば、駆け込み輸出の影響から財輸出は増加している。
ただし、先行きについては、駆け込み需要を受けた輸出の増加がはく落するとともに、今後の米国の政策動向の帰すうによっては更に財輸出は弱含むことが見込まれることには留意が必要である。
(労働需給のひっ迫が続く)
続いて、労働市場の動向を確認する。
まず、就業者数は、2021年以降増加傾向で推移しているが、2024年4-6月期以降伸びが緩やかになっている(第1-3-19図)。
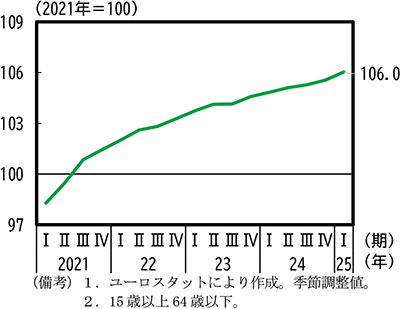
さらに、労働参加率をみると、感染症拡大以前から男女ともに上昇傾向にあり、歴史的に高い水準にある(第1-3-20図)。ただし、水準自体は依然として男女に差がみられ、例えば2024年10-12月期の女性の労働参加率は70.7%と男性に比べ9.1%ポイント低い。欧州委員会等は、こうした労働市場における男女差は労働需給の効率的なマッチングを妨げ、継続的な労働力不足の一因となっていると指摘しており、特定分野の教育課程における男女差の解消や、保育サービスの充実など女性が労働参加しやすい環境整備を行う重要性を指摘している64。
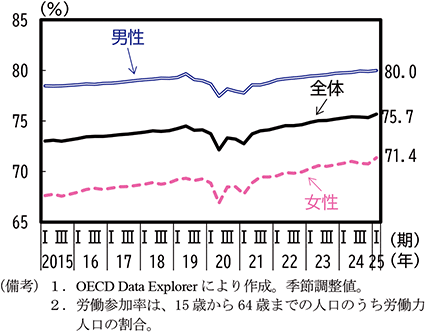
続いて、労働需要の変動を求人率65から確認する。2021年以降、感染症収束を受けた経済活動の再開等を受けて労働需要が増加したことから求人率が上昇し、2022年前半にかけて3.4%となった。その後、物価上昇率の高まりや、それに対応する政策金利の引上げなどから景気の鈍化とともに企業の労働需要が低下し、求人率は低下傾向となったが、2025年1-3月期は2.4%と感染症拡大前の5年間平均と比べて0.5%ポイント高い水準にとどまっている。以上のとおり、就業者数が2021年以降増加傾向にある中においても、求人率は感染症拡大前をなお上回っており、引き続き労働需要は高い水準にある(第1-3-21図)。
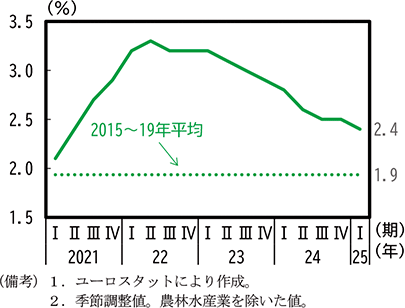
こうした中、失業率についても、継続する労働需給のひっ迫を受け、2025年4月において6.2%と1999年1月のユーロ導入以降で最も低い水準となっている(第1-3-22図)。
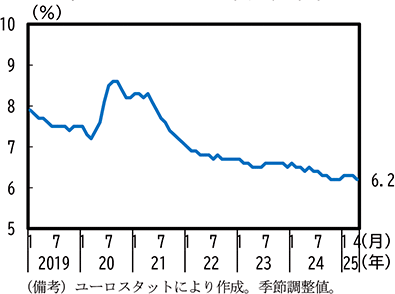
(消費者物価上昇率は2%程度で安定的に推移)
ユーロ圏の消費者物価上昇率(総合、前年比)は、エネルギー価格がピークアウトした2022年半ば以降低下傾向となり、2023年10月以降2%近傍で推移している(第1-3-23図)。こうした中、2023年7-9月期以降実質賃金のプラス幅が拡大していることを受け、2023年後半以降消費者物価に対するサービス価格の押上げ寄与が大きくなっている。
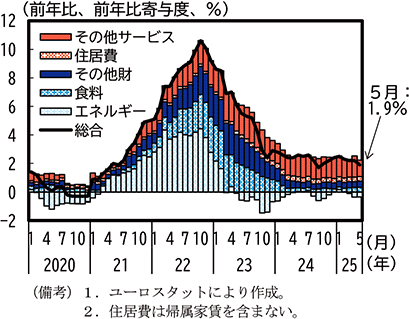
2024年以降、エネルギー、食料及びその他財の価格上昇率が安定的に推移している背景としては、輸入物価の高騰が一服したことによるインフレ圧力の低下が考えられる。財及びサービスの輸入物価66(前年比)をみると(第1-3-24図)、2022年前半から半ばにかけては、ロシアのウクライナ侵略を受けたエネルギー及び食料価格の高騰(コラム3 図1)により、財を中心に輸入物価上昇率は加速した。しかしながら、2022年後半以降は、政策金利の引上げに伴う通貨高に加え(第1-3-25図)、供給量の安定に伴うエネルギー及び食料価格の下落(コラム3 図1)並びに国際物流コストの低下(第1-3-26図)を受け、輸入物価の上昇率は低下傾向となり、2023年以降はマイナスで推移していたことから、輸入インフレ圧力は一旦収束していると考えられる。ただし、2025年初に通貨安等の影響から財輸入物価がプラスに転じ、輸入物価もプラスに転じている。
また、ロシアによるウクライナ侵略開始から3年が経過する中、2025年5月の消費者物価上昇率におけるエネルギー価格寄与度は▲0.3%ポイントとなっており、エネルギー価格上昇に伴う下振れリスクがあるとまでは認められなくなっている。ただし、2025年6月におけるイラン・イスラエルの軍事衝突を始め、中東地域の地政学的リスクは依然として存在しており、情勢が緊迫化すれば国際的なエネルギー価格が急騰する可能性もあり、引き続き中東地域をめぐる情勢を注視する必要がある。
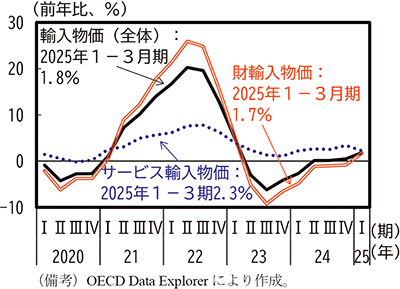
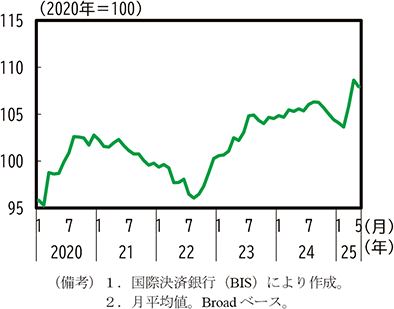
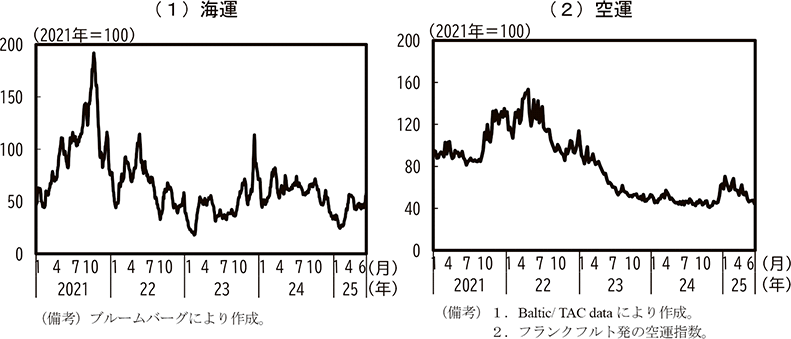
(ECBは物価上昇率の落ち着きとともに政策金利を引下げ)
欧州中央銀行(ECB)は、2023年10月以降、インフレ懸念が減退し、消費者物価上昇率が安定的に2%台に落ち着いてきたことを受け、2024年6月に政策金利を4.00%から0.25%ポイント引き下げ、3.75%とした。以降、9月、10月、12月、2025年1月、3月、4月、6月とそれぞれ0.25%ポイント引き下げ、現在の預金ファシリティ金利は2.00%となっている67 (第1-3-27図、第1-3-28表)。
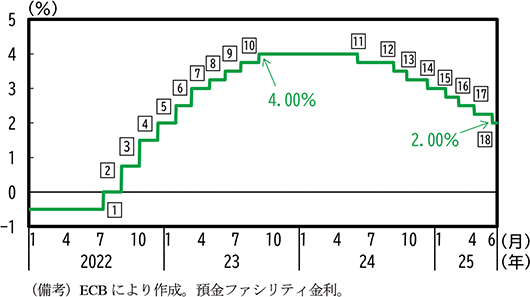
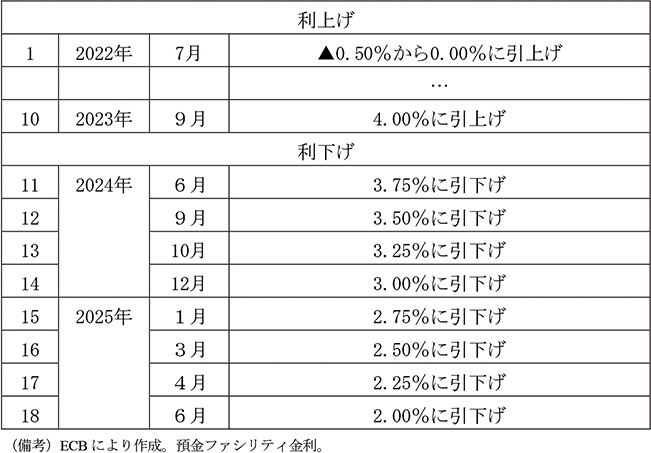
ECBは、金融政策について、2025年4月以降の理事会の声明において「緊縮的」という文言を削除している。その理由として、緊縮的か緩和的かの基準とされる「中立金利は『ショック』がない場合には機能する概念だが、現在、『ショック』がない世界におらず、政策の引き締め度合いの検証はもはや機能していないため」として、不確実性の高い現下の情勢において緊縮的かどうかを判断することは適切ではないとの認識を示している68。
(財政状況に留意が必要)
EUは、財政ルールである「安定・成長協定」において、各加盟国の財政収支対GDP比を▲3%以内とするなどの取り決めがあるが(第1-3-29図)、安全保障環境の変化を受け、2025年3月、欧州委員会は「欧州再軍備計画」を発表し、各国において防衛費の財政支出を「安定・成長協定」に基づく財政収支の算定ルールから適用除外とすることとしている。
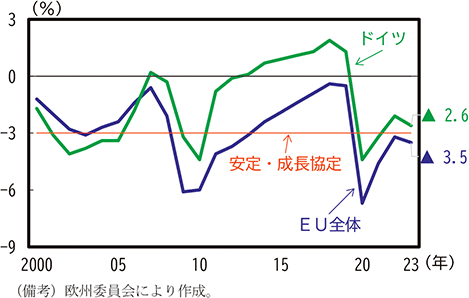
(長期金利は高止まり)
ドイツでは、ECBによる政策金利の引上げや保有資産の縮減を受けて、長期金利は2022年初から上昇基調となった。2023年末にはECBによる政策金利の引下げ観測が高まり、長期金利は一時的に低下したものの、その後は米金利につれて、おおむね横ばいで推移した。2025年3月には、インフラ基金の設置及び防衛支出を債務ブレーキの適用除外とする旨が公表されたことを受け、長期金利は急速に上昇し、2023年11月以来の水準に達した。その後は、ECBによる政策金利の引下げ継続の観測に加え、米国による関税措置を背景としたドル建て資産に対する相対的な魅力度の低下から、ユーロ建て資産への需要が高まり、長期金利は低下に転じた。ただし、依然として高水準での推移が続いている(第1-3-30図)。
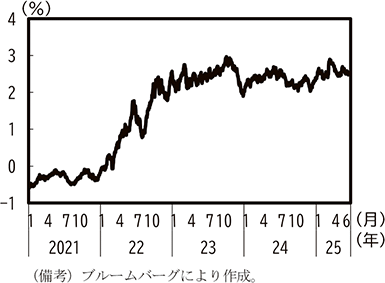
(株価は上昇基調を維持)
ドイツの株価指数(DAX)は、2022年のロシアのウクライナ侵略に伴う天然ガスを始めとするエネルギー69価格の上昇や、ECBによる金融引締め姿勢を背景に下落したが、2022年末以降はインフレ圧力の緩和を背景に持ち直しの動きがみられた。2023年後半には、世界的な金利上昇から下落に転じるも、2023年末以降は、ECBによる政策金利の引下げ期待から堅調な推移となった。2025年は、ECBによる利下げ継続の観測や、インフラ基金の設置及び防衛支出を債務ブレーキの適用除外とする旨が公表されたことを受け、株価は大幅に上昇している。2025年4月には、米国による関税措置の影響から一時的に大きく下落したものの、「相互関税」の国別上乗せ関税率の適用延期や防衛・インフラ関連企業を中心とした今後の企業業績期待の高まりを背景に、株価は再び上昇基調を強め、2025年5月から6月上旬にかけて過去最高値を更新した(第1-3-31図)。
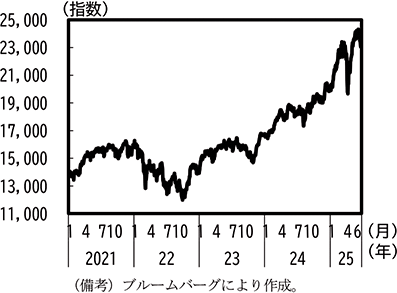
(2025年に入り、ユーロは対ドルで上昇傾向)
2022年はウクライナ侵略の長期化に加え、欧米間の金利差の拡大を背景に、ユーロは対ドルで下落基調となった。2023年は、ECBによる政策金利の引上げが継続されたことにより、欧米間の金利差が縮小し、ユーロは対ドルで上昇に転じた。その後はおおむね横ばいで推移したが、2024年末以降は、ECBによる政策金利の引き下げ継続の観測が強まり、再びユーロは対ドルで下落した。2025年3月には、ドイツでインフラ基金の設置及び防衛支出を債務ブレーキの適用除外とする旨が公表されたことを受けて長期金利が上昇し、ユーロは対ドルで上昇した。4月以降は、米国の政策動向を巡る不透明感の高まりからドルが弱含みとなり、ユーロは対ドルで上昇傾向で推移している(第1-3-32図)。
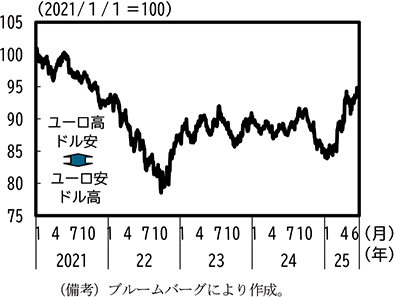
コラム2 ドイツ経済の課題
ドイツでは、2025年2月23日に実施されたドイツ連邦議会選挙の結果、CDU・CSUとSPDによる連立政権が成立した。本コラムでは、その背景にある経済社会の構造問題について概観する。
基礎統計をみると、ドイツの人口は日本の3分の2、就業者数は63%、一人当たり年間労働時間は82%である一方、名目GDPは日本とほぼ同水準にあり、日本よりも一人当たり及び時間当たり労働生産性が高い(1表)。
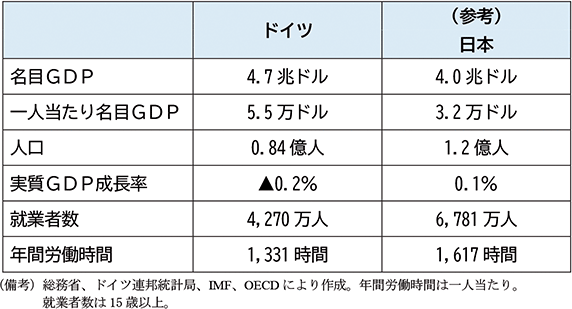
名目GDPの推移をみると、ドイツの名目GDPは、米ドル換算で2023年に日本を上回り、世界第3位となった。ドイツでは、1990年の東西ドイツ統一以降、発展度合いの異なる二つの経済市場を統合する様々な困難に直面する中で、2002年以降、労働市場改革を進めるとともに、1999年のユーロ導入や、累次のEU加盟国の拡大に伴う欧州域内の貿易・投資の活発化にも支えられた結果として、この20年間、実質で年平均1.1%、名目で年平均2.9%の成長率を実現している(図2)。
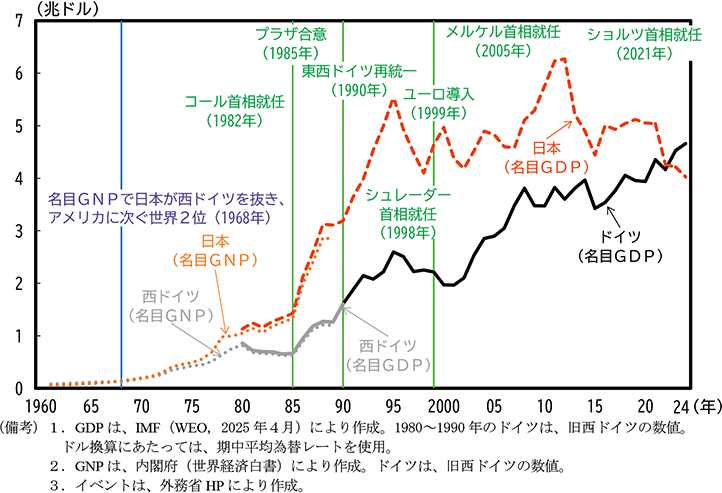
一方で、労働者の高齢化とともに技能労働者(Skilled labor)の不足がドイツの経済成長のボトルネックとなる可能性が指摘されている70。総人口及び生産年齢人口の推移をみると、総人口は2024年の8,470万人をピークに緩やかに減少する見込みである。また、生産年齢人口は、1997年をピークに振れを伴いながら減少し、2024年以降も引き続き減少する見込みであり、生産年齢人口の総人口に対する割合については、1988年をピークに緩やかな低下が続く見込みである(図3)。
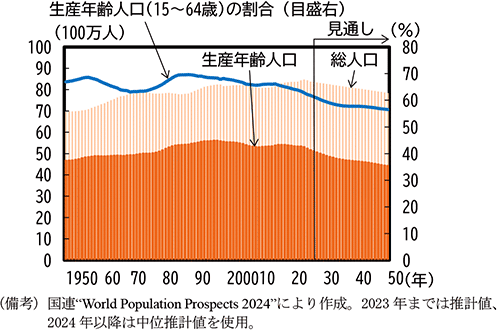
このような状況を踏まえ、女性及び高齢者の就業率を高める政策的な対応に加え、外国人の技術労働者の重要性も指摘されている71。就業者数の動向をみると、感染症拡大の影響が大きかった2020年4-6月期から2021年1-3月期を除き、一貫して増加している。その内訳をみると、ドイツ国籍を有する者については、2020年4-6月期から2021年1-3月期を除き増加に寄与していたものの、2023年1-3月期以降、減少に寄与している。一方、EU加盟国やその他の国の国籍等外国籍を有する者については、一貫して増加に寄与している(図4)。
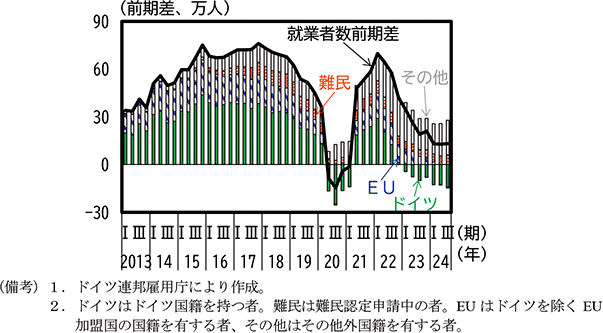
この背景には、共通国境管理の漸進的撤廃に関する協定(シェンゲン協定)により、外国籍を有する労働者はシェンゲン協定加盟国からドイツに入国しやすいということがある。ドイツはシェンゲン協定に1985年に署名しており、シェンゲン協定加盟国間の移動には出入国審査が不要となっている。また、ドイツでは、EU加盟国、欧州経済領域72加盟国及びスイス以外からの外国籍を有する者が就労目的でドイツに滞在するには、原則として、就労先の求人がドイツ人等では満たせないことについて連邦雇用機関の同意を得る必要があるが、医療や介護、ITを始めとする高度技能を要する分野については、技能を有する労働力の不足が深刻化しているため、外国籍の高度技能人材受け入れ促進に向けたビザ発給や滞在許可の優遇制度を設けている73。
以上のとおり、ドイツ経済における外国籍を有する労働者の役割は重要性を増している。一方で、外国籍を持つ者の排斥を訴える政党が台頭している点にも留意が必要である。2025年2月23日に行われたドイツ連邦議会選挙では、メルケル元首相の寛容な難民政策を批判するAfDが152議席を獲得し、改選前の76議席から大幅に議席を伸ばして第二党となった74(図5)。
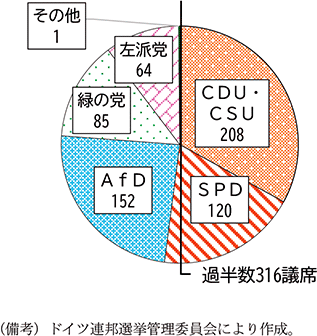
AfDが台頭した背景について、ドイツの州別一人当たりGDPをみると、旧西ドイツ州は5.4万ユーロである一方、AfDが支持を得たとされる旧東ドイツ州では3.9万ユーロと7割程度にとどまっている。依然として旧東西ドイツ間には経済格差があることがわかり、こうした経済格差が外国籍労働者に対する態度の違いに繋がっている可能性がある。また、各州の人口における外国籍を有する者の割合をみると、旧西ドイツ州は15.7%に対して、旧東ドイツ州では7.6%であり、旧東ドイツ圏は旧西ドイツ圏に比べて、外国籍を有する者の人口割合が半分程度となっている。
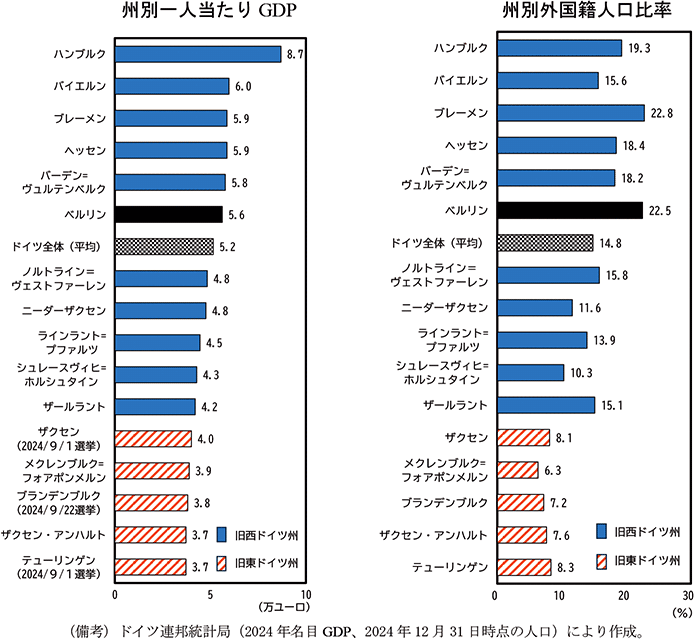
このように、生産年齢人口が減少傾向にあるドイツ経済においては、外国人労働者の受入れは不可欠と考えられていることから、ドイツ政府は、外国人労働者に対するドイツ語教育やドイツ文化の教育等、社会統合政策を進めている。
2.英国経済の動向
(英国では、景気は持ち直している)
英国経済の動向を実質GDPの推移から概観75すると、英国では2022年後半以降、急激な物価上昇と政策金利の引上げを受けて、実質GDPが横ばい傾向で推移してきたが、後述する物価上昇率の低下に伴う実質賃金の上昇などを受けて消費が持ち直し、2023年10-12月期以降実質GDP成長率はプラスで推移しており76、景気は持ち直している(第1-3-33図)。
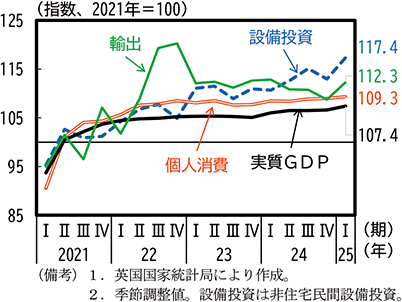
(消費は持ち直している)
英国の個人消費を実質GDPの家計消費からみると、2022年10-12月期以降は弱い動きが継続していたものの、2023年10-12月期以降持ち直しの動きに転じている。2023年後半以降は消費者物価上昇率の鈍化と名目賃金の上昇を受けて実質賃金がプラスで推移していることから、サービス、半耐久消費財、耐久消費財の消費は堅調に推移している。総じてみれば、消費は持ち直している(第1-3-34図)。
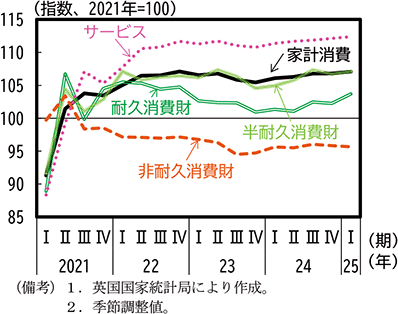
次に、実質小売販売額の動向をみると、2021年秋以降、感染症収束に伴う経済活動の再開やウクライナ侵略に伴うエネルギー価格等の高騰を受けた消費者物価の上昇により、実質小売販売額は、低下傾向が続いていたが、2023年後半以降は消費者物価の上昇の鈍化と名目賃金の上昇を受けて実質賃金の上昇率がプラスで推移する中(後述)、持ち直している(第1-3-35図)。
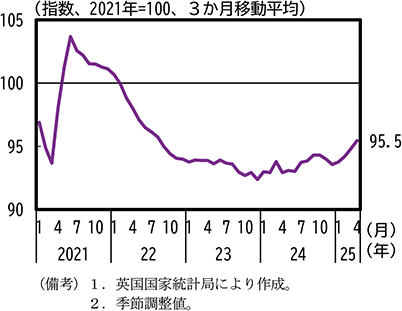
自動車の新規登録台数をみると、供給制約が解消された2023年9月以降も感染症拡大前の2019年を下回る水準が継続しているものの、2025年2月においては約8.4万台と、感染症拡大前の2019年2月の約8.2万台を上回っており、回復の兆しがみられる(第1-3-36図)。
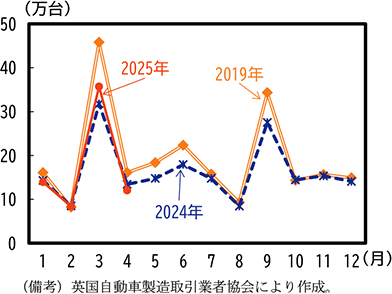
こうした消費動向の説明要因となりうる実質賃金の動向を確認する。前述の要因により、2022年4-6月期以降消費者物価上昇率が名目賃金上昇率を上回り、実質賃金上昇率はマイナス傾向で推移していたが、消費者物価上昇率の低下を受けて、2023年4-6月期以降は実質賃金の上昇率はプラスで推移している(第1-3-37図)。
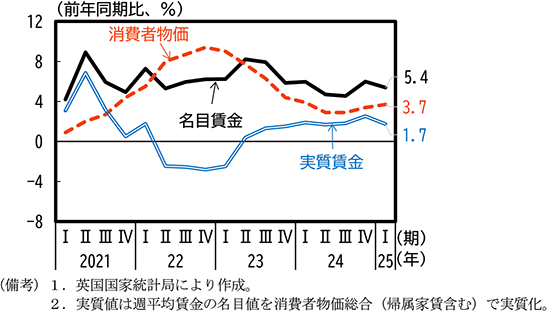
また、消費者信頼感をみると、2024年に入って以降、家計の先行きは、消費者物価上昇率の低下を受けて改善が続き、DIは2024年6月にはプラスとなった(第1-3-38図(1))。しかし、同年10月末に提出された秋季予算において国民保険料の企業負担が増加することが判明すると77、雇用者負担が価格へ転嫁されることへの懸念から経済見通しを中心にマイナス幅が拡大。さらに、米国の政策動向の影響を受けた先行き不透明感も重なり、経済見通しが悪化したことで、消費者信頼感は足下で低下傾向にある。英国の消費者信頼感(消費者マインド)の改善ペースが全体として弱い背景には、依然として高い水準にとどまる政策金利78と、これに伴うローン金利の高止まりも相まって、高額商品購買意欲の改善の動きが鈍いことが考えられる(第1-3-38図(2))。
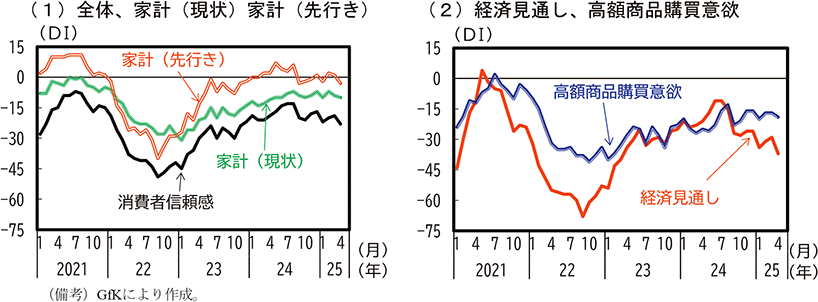
このように消費者マインドの改善ペースが弱いことから、家計貯蓄率は引き続き感染症拡大前(2016~19年平均)を上回って推移している。家計貯蓄率は、感染症収束に伴い低下していたが、2022年半ば以降は緩やかな上昇傾向に転じており、2024年10-12月期には12.0%と高止まりしている(第1-3-39図)。英国予算責任局は足下の家計貯蓄率の高まりの背景について、実質賃金と純金利収入の上昇が家計実質可処分所得を下支えし、金利の上昇と不確実性の高まりが貯蓄を促進していると指摘79しており、経済見通しの悪化(第1-3-38図(2))や金利の高止まり、米国の政策動向による不透明感から貯蓄志向が高まっていると考えられる。
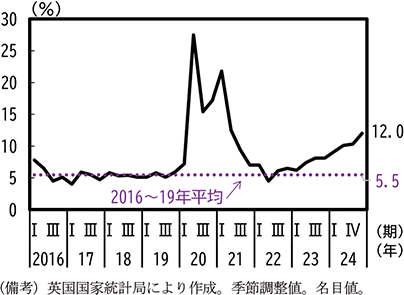
以上のように、実質賃金が持ち直しの動きをみせる中でも、経済見通しの先行き不透明感から消費者マインドの改善ペースの弱さがみられるが、英国の消費は、総じてみれば持ち直している。
(設備投資は、持ち直しの動きがみられる)
英国においても、ユーロ圏と同様に政策対応を受けた80脱炭素やデジタル化に向けた設備投資需要から、2021年以降、知的財産生産物投資、機械・機器投資及び構築物投資のいずれも持ち直してきたが、2022年以降の政策金利引上げの継続やウクライナ侵略等に伴う経済の先行き不透明感から、2023年半ば以降は機械・機器投資及び知的財産生産物投資が減速した。2024年7月にスターマー内閣が発足して以降、設備投資マインドは上向き、さらに政策金利の引下げを受けた借り入れ負担の軽減も相まって、2025年1-3月期には機械・機器投資及び構築物投資に持ち直しの動きがみられ、英国の設備投資は持ち直しの動きがみられている。(第1-3-40図、第1-3-41図)。
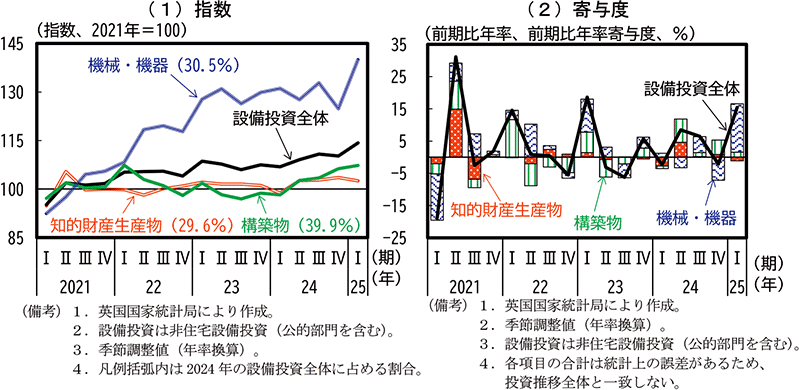
ただし、先行きについて設備投資マインドをみると、2025年1月以降は国民保険料の雇用主負担の増加に伴う企業負担の増加や、米国の政策動向の影響を受けた不透明感の高まり、世界経済の減速懸念から、DIは投資意欲が横ばいであることを意味する0以下で推移しており、設備投資は持ち直しの動きが一服する可能性がある(第1-3-41図)。
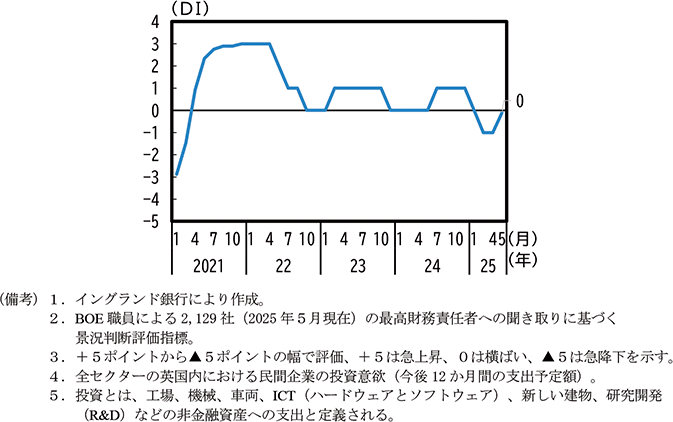
(財輸出、サービス輸出ともに、増加している)
続いて輸出の動向を確認する。
2020年1月のEU離脱と感染症拡大が相まって、2020年4-6月期に財輸出、サービス輸出ともに大きく減少した。その後、対GDP比(2024年)で12.8%を占める財輸出は、一時的な増加を除き81減少傾向にあった。2024年10-12月期を底に、米国向け輸出の増加を背景として増加に転じているものの82、感染症拡大前の水準を回復していない。対GDP比(2024年)で17.8%を占めるサービス輸出は、感染症の収束を受けて緩やかに増加傾向が続き、2024年7-9月期以降一服感がみられたものの、増加に転じている83(第1-3-42図)。
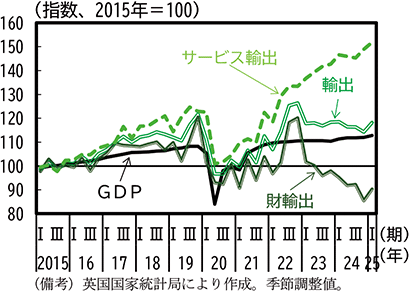
こうした輸出の動きについて相手国別の動向とともに分析する。
まず財輸出の輸出相手国別の動向をみると、2024年の主要輸出相手国は、米国(構成比16.2%)、ドイツ(同8.8%)、オランダ(同7.6%)、アイルランド(同6.5%)、フランス(同6.3%)中国(同4.6%)となっている。輸出相手国別の推移をみると、財輸出が2023年9月以降緩やかな低下傾向にある中で米国向け財輸出は高止まりし、2025年以降、急増している(第1-3-43図)。一方、ドイツやアイルランド等ユーロ圏向けの財輸出は2023年以降減少傾向が続いており84、英国の財輸出を下押ししている。なお、中国向け輸出は大きく変動している時期85もあるが、2023年以降停滞している。
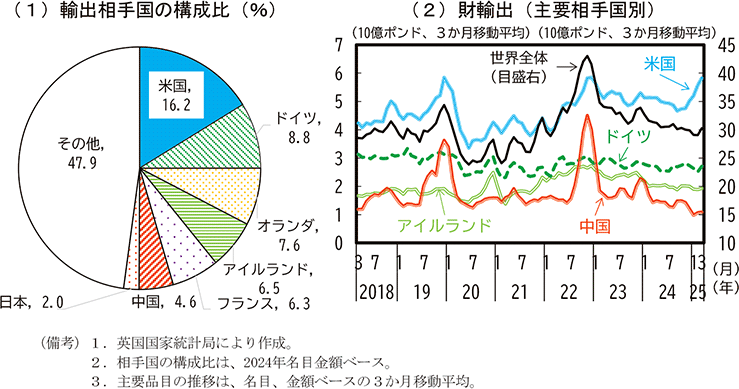
次に、サービス輸出の動向をみると、主要輸出相手国は、米国(構成比27.0%)、ドイツ(同5.7%)、アイルランド(同5.4%)となっており、相手国別の推移をみると、米国向けがけん引する形で増加傾向にある。また、ドイツやアイルランド等ユーロ圏向けのサービス輸出も緩やかな増加傾向にあり、総じてみれば増加傾向にある(第1-3-44図)。
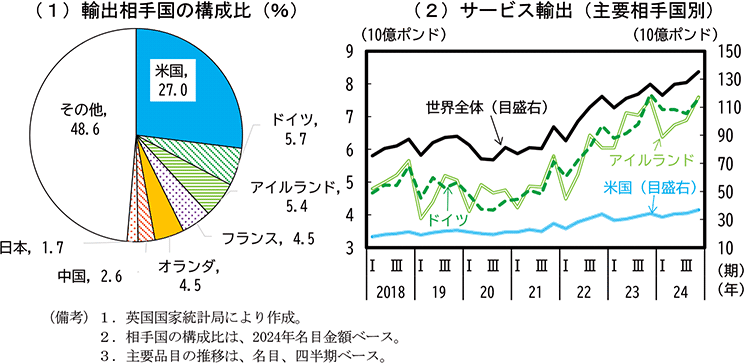
以上のように、英国の財輸出、サービス輸出はともに対米国向け輸出が堅調に推移している。
先行きについては、英国は名目GDPに占めるサービス輸出の割合が財輸出よりも高く86、米国の政策動向の影響はユーロ圏経済等を通じて間接的に受ける程度にとどまると考えられる点に留意する必要がある87。
(労働需給のひっ迫は緩和)
続いて、労働市場の動向を確認する。
まず、就業者数は2023年以降おおむね横ばい傾向で推移していたが、2024年7-9月期以降は増加傾向で推移している(第1-3-45図)。
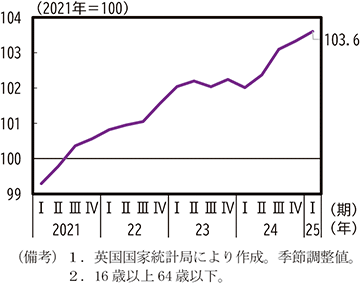
さらに、労働参加率をみると、感染症拡大後、男性の労働参加率が精神疾患等長期疾病に伴う非労働力化などの影響を受け88、2019年10-12月期から2021年1-3月期にかけて2.2%ポイント低下したことなどから、全体としては2019年10-12月期から1.8%ポイント低下しているが、ユーロ圏と比較して高い水準を維持している(第1-3-46図)。
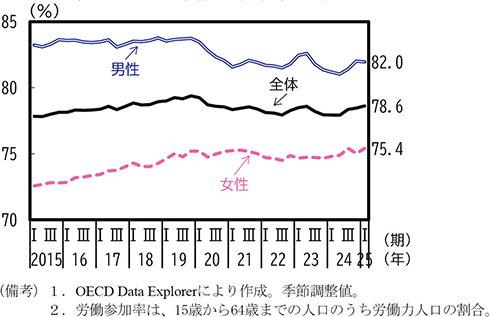
続いて、労働需要の強さを求人率89の動向から確認する。2021年以降経済活動の再開等を受けて労働需要が増加したことから求人率が上昇し、2022年前半にかけて3.8%となった。その後、政策金利の引上げを受けた労働需要の減少により低下傾向となった。さらに2024年10月末に公表された秋季予算において国民保険料の企業負担の増加が決定されると、人件費の高まりから雇用を減少させる動きがみられ、2025年1-3月期には2.3%と感染症拡大前を下回る水準まで低下しており、労働需要はおおむね感染症拡大以前を下回る水準まで減少したものと考えられる(第1-3-47図)。
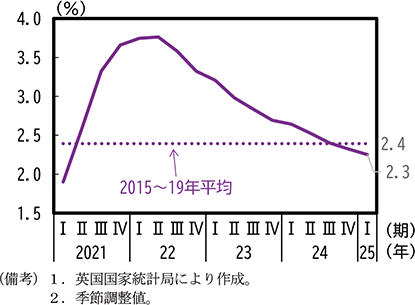
以上のように、就業者数は2023年以降おおむね横ばい傾向で推移していたが、2024年7-9月期以降は増加傾向で推移しており、労働参加率は引き続き高い水準を維持している。求人率は、おおむね感染症拡大前を下回る水準まで低下している。
また、失業率は、低水準にあった2022年に比べ、2023年に入って以降は上昇傾向にあることから、英国の労働市場は緩和傾向にあると考えられる90(第1-3-48図)。
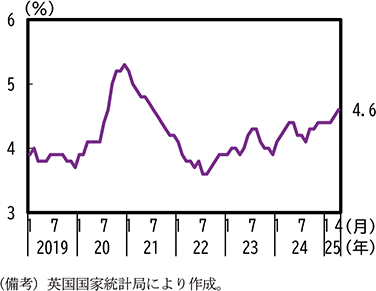
(輸入物価上昇率が上昇に転じ、消費者物価上昇率は上昇)
英国の消費者物価上昇率(総合、前年比)は、2022年半ば以降低下傾向となり、2024年9月には1.7%まで低下していたが、その後上昇に転じ、2025年4月には3.5%となっている(第1-3-49図)。要因として、その他財価格のプラス寄与が高まったことと、エネルギー価格のマイナス寄与がはく落してきたことの2点が挙げられる。2024年10月以降、エネルギー価格のマイナス寄与が徐々に小さくなったことが全体の消費者物価上昇率を1%ポイント程度、その他財価格の寄与増加が0.5%ポイント程度押し上げている。食料品価格及び住居費以外のその他サービス価格上昇率はおおむね横ばいで推移している。
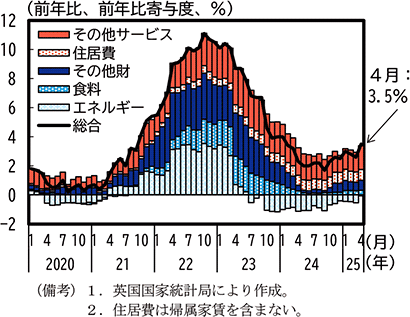
エネルギー価格が上昇していた背景としては、輸入インフレ圧力の高まりが考えられる。財及びサービスの輸入物価91(前年比)の動向をみると(第1-3-50図)、2022年前半から半ばにかけては、ウクライナ侵略を受けたエネルギー及び食料価格の高騰(コラム5 図1)により、財を中心に輸入物価上昇率は加速した。しかしながら、2022年後半以降は、政策金利引上げの進展に伴う通貨高に加え(第1-3-51図)、エネルギー及び食料価格の下落(コラム5 図1)並びに国際物流コストの低下(第1-3-26図)を受け輸入物価の上昇率は低下傾向となり、2023年に入ってからはマイナスで推移していた。2023年10月のパレスチナ武装勢力ハマスによるイスラエルへの大規模襲撃をきっかけに、中東情勢の緊迫化からエネルギー価格に下げ止まりがみられ、2025年に入ってからは通貨安等の影響も相まって財輸入物価はマイナス幅が縮小し、輸入物価は2025年1-3月期0.1%とプラスに転じた。今後の中東情勢によってはエネルギー価格が上昇に転じる可能性もあり、引き続き情勢を注視する必要がある。
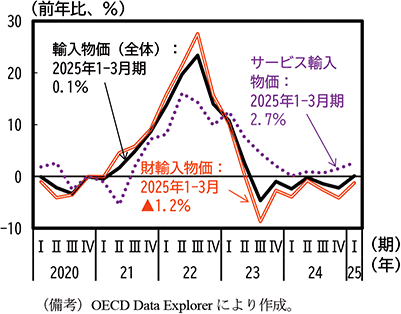
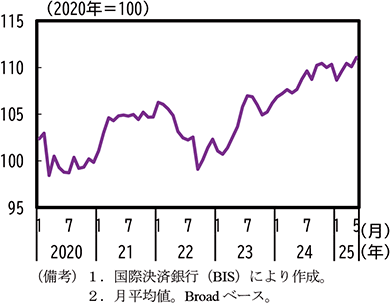
(BOEは政策金利を引下げ)
イングランド銀行(BOE)は、2021年末以降、消費者物価上昇率の加速を受けて政策金利の引上げを継続してきたが、2023年秋以降は政策金利を据え置いてきた。金利引上げの効果もあり消費者物価上昇率は2022年末以降低下傾向となり、2024年5月以降は2%台で推移してきたことを受け(第1-3-49図)、BOEは政策金利のバンク・レートを2024年7月に5.25%から0.25%ポイント引き下げ、5.00%とした。以降、11月、2025年2月、5月とそれぞれ0.25%ポイント引き下げ、4.25%とした(第1-3-52図、第1-3-53表)。
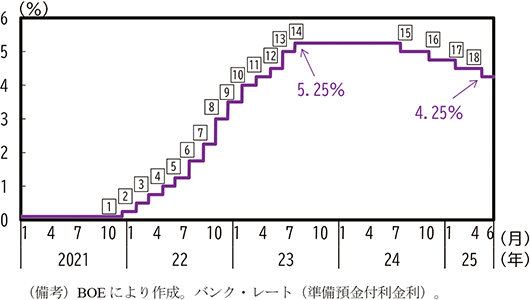
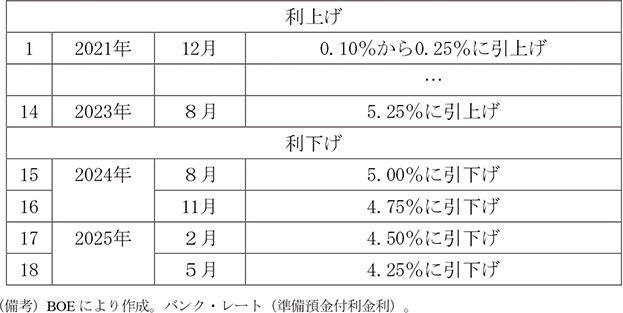
また、BOEは、保有する英国債の削減を進めている。2022年2月に満期を迎えた国債の再投資を中止して以降、金融政策目的で保有する国債を削減しており、2024年9月の金融政策委員会において、2025年9月までに金融政策目的で保有する国債を1,000億ポンド92削減し、5,580億ポンドとすることを公表している。
今後の金融政策については、2025年5月の金融政策委員会において、中期的に物価上昇率を持続可能な形で2%の目標まで戻すためには、委員会の任務に沿って、十分な期間、十分に引締め的な金融政策であり続ける必要があるとの認識を示した。
(利払費の拡大等財政状況に留意が必要)
英国においては、財政規律と競争力の向上に資する財政支出の両立が課題となっている93。英国債の長期金利は、おおむね米国債の長期金利に連動して上昇傾向にあるが、2025年1月には、いわゆるトラスショックが生じた2022年9月当時と同水準まで上昇し、その後おおむね横ばいで推移している(第1-3-54図)。
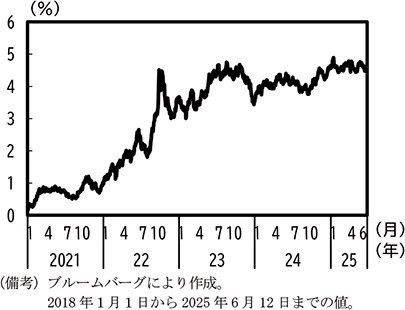
この背景には、財政状況に対する市場参加者の懸念の高まりが考えられることから、公共部門債務残高対GDP比94を確認する。
2025年3月に公表された2025年春季予算における予測値において、公共部門債務残高対GDP比は、2024年度95の95.9%から、2025年度には95.1%に低下するも、2029年度は96.1%となる見通しが示されている(第1-3-55図)。
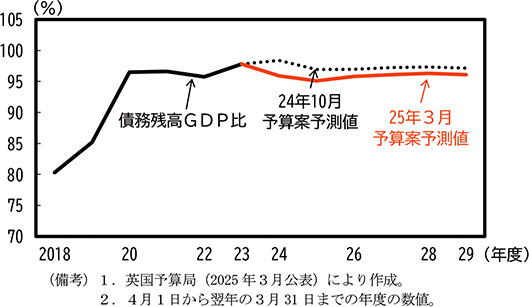
さらに、公共部門支出対GDP比をみると、英国債等の利払費は長期金利の高止まりもあり感染症拡大前である2019年の1.7%から、2023年には3.9%と2.3倍に増加しており、2024年以降も同程度で推移する見通しとなっている(第1-3-56図)。
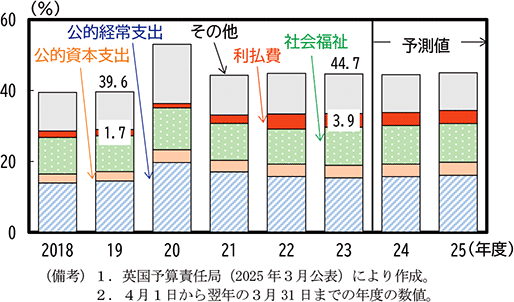
このように、英国債金利の上昇が続いてきた中で、利払費は高止まりする見通しであることから、今後の財政状況とそれに対するマーケットの反応には注意が必要である。
(まとめ:景気の先行きは持ち直しの動きが弱まる可能性がある)
これまでみてきたように、物価上昇率が低下する中で、ユーロ圏、英国ともに実質GDP成長率は2025年1-3月期でプラスとなり、景気は総じて持ち直している。
先行きについては、ユーロ圏では、米国の通商政策による影響から、持ち直しの動きが弱まる可能性があり、米国の政策動向による影響に留意する必要がある。個人消費は、名目賃金の上昇傾向が続く中で、消費者物価上昇率の低下を受けた実質可処分所得の増加とともに、政策金利引下げを受けた消費者マインドの改善を受けて、緩やかに持ち直していくことが考えられる。
英国では、政策金利の高止まりの長期化に伴う下振れリスクと米国の政策動向による影響に留意する必要があるものの、景気は持ち直しが続くことが期待される。個人消費は、実質賃金の上昇を受けた実質可処分所得の増加とともに、政策金利引下げへの期待から消費者マインドが改善し、緩やかに持ち直していくことが考えられる。
設備投資については、ユーロ圏、英国ともに、政策金利の引下げとともに脱炭素やデジタル化に向けた政策効果が発現し、緩やかに持ち直していくこと見込まれるが、米国の政策動向による影響から一服する可能性がある。ただし、ユーロ圏については、安全保障環境の変化を踏まえた防衛支出の増加や、ドイツにおけるインフラ投資の増加により、持ち直し基調が強まることも考えられる。
輸出については、ユーロ圏、英国ともに米国の政策動向による影響を受けた世界経済の変動から、財輸出は影響を受けることが見込まれるが、サービス輸出は堅調に推移することが見込まれる。英国については、2024年12月に発効したCPTPPへの加盟によって上振れすることも考えられる。
また、ユーロ圏、英国ともに財政状況をめぐる動向とそれに対する金融資本市場の反応を注視する必要がある。

