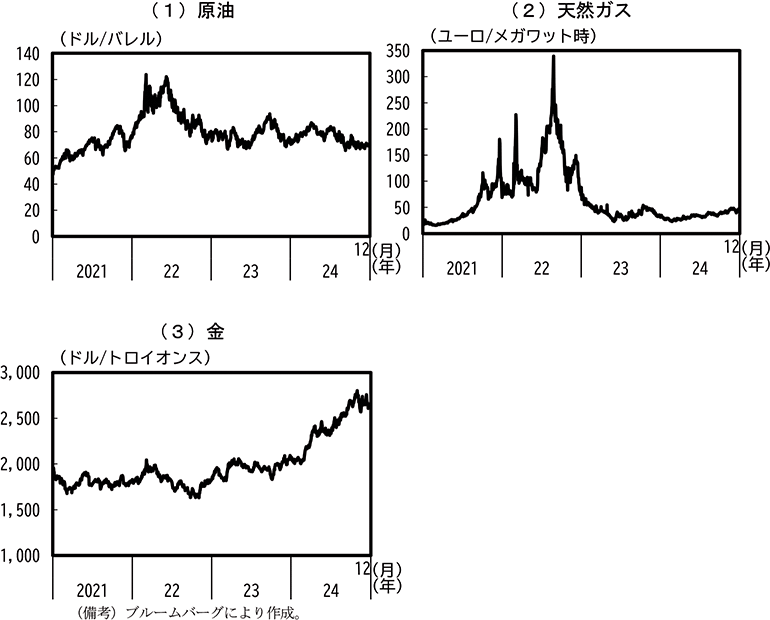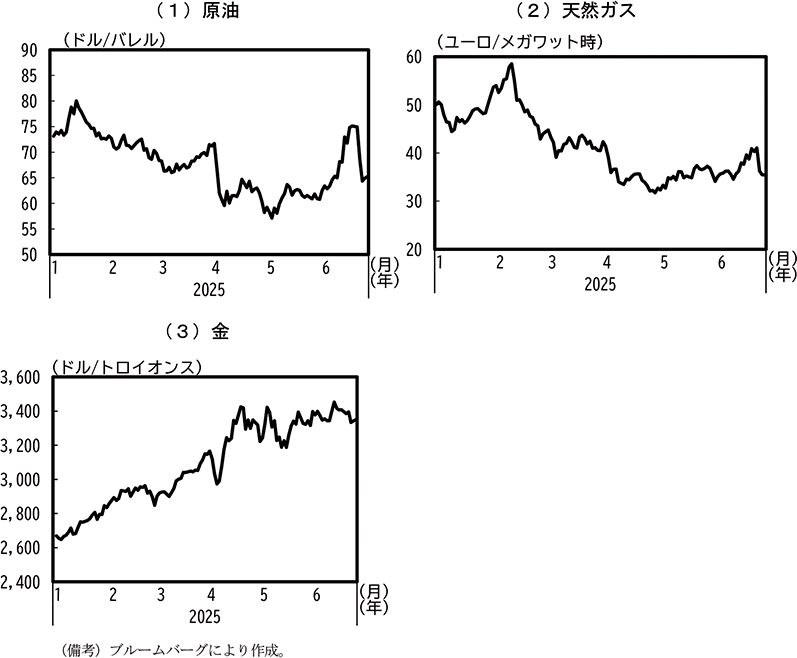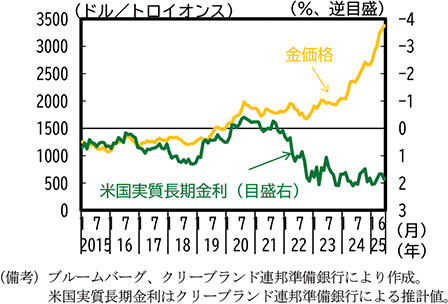第1章 2025年前半の世界経済の動向(第4節)
第4節 世界経済の見通しとリスク
本節では、前節までの各地域の経済動向の分析を踏まえ、世界経済の見通しとリスク要因について議論する。
1.世界経済の見通し
(世界経済の成長率は低下する見通し)
2025年6月に公表されたOECDの世界経済見通しでは、世界の実質GDP成長率は2024年の3.3%から2025年には2.9%に低下し、2026年も2.9%で推移すると予測されている(第1-4-1図)。その背景には、関税率の引上げや政策不確実性の高まりによって設備投資や貿易の伸びが抑制されること、貿易コストの増加による最終財価格の押上げや消費者マインドの悪化によって消費の伸びが低下することなどがある。世界の実質GDP成長率が3%を割り込むのは、世界的な感染症拡大により経済活動が抑制された2020年(▲3.0%)を除くと、第一次トランプ政権下の米中貿易摩擦が激化した2019年(2.9%)以来となる(第1-4-2図)。
主要国・地域別の実質GDP成長率の予測をみると、米国では、大幅な関税率の引上げと貿易相手国の対抗措置、政策不確実性の高まり等から、2024年の2.8%から2025年には1.6%まで低下すると予測されている。中国では、財政拡大が幾分景気押上げに働くものの、米中間相互の大幅な関税率引上げを予測の前提として、実質GDP成長率は2024年の5.0%から2025年には4.7%まで低下、政府目標の「5%前後」を下回ると予測されている。対照的に、ユーロ圏では、2024年の0.8%から2025年には1.0%とわずかに高まる予測となっている。ユーロ圏においても貿易摩擦が下押し圧力となるものの、感染症拡大後の経済立て直しを目指した復興基金(「次世代のEU」)による投資促進政策の継続等が景気を下支えするとしている96。
なお、これらの予測は2025年5月中旬時点の各国間の関税率が2026年にかけて維持されるといった技術的な試算前提に基づいており、それ以降の鉄鋼・アルミニウムに係る追加関税率の50%への引上げ、あるいは各国通商交渉の結果による関税率の見直し等の影響は当然加味されていない。さらに、今後の通商政策を始めとする米国の政策動向やそれに対する他国の反応など種々の不確実性があり、その帰すうによって予測結果が大きく変わり得ることには留意が必要である。
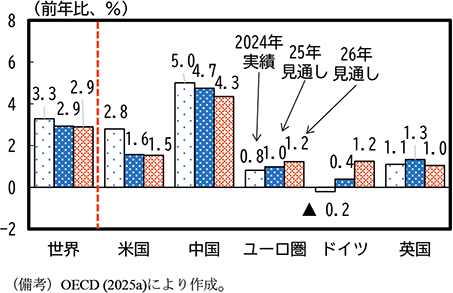
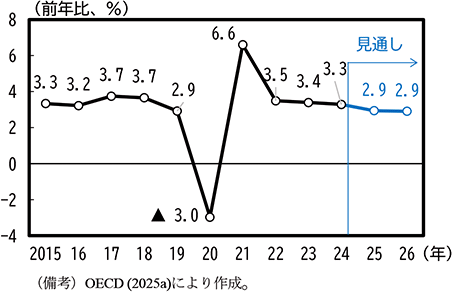
2.先行きのリスク要因
(通商政策等の米国の政策動向)
第2章で詳述するが、2025年1月の米国第二次トランプ政権発足後、トランプ大統領は、中国、カナダ、メキシコからの輸入に対する国別追加関税や、鉄鋼、アルミニウム、自動車・同部品の輸入に対する品目別追加関税、「相互関税」といった関税措置を相次いで導入するとともに、更なる追加関税措置も視野に医薬品や半導体等の調査を実施している。このうち、「相互関税」の国別上乗せ分については、当初7月9日、その後延長され8月1日まで適用が停止された。また、米中間の関税率は当初8月12日、その後延長され11月10日まで相互に一時引下げとなったほか、英国に対しては自動車の輸入に対する追加関税について年間10万台までの関税割当制度を設ける、7月には日本やEU等と新たな関税率に関する合意に至るなど、各国・地域との交渉を通じて米国の関税措置や相手国・地域の対抗措置に変化が生じる動きもみられる(第1-4-3表)。7月31日には、各国・地域との交渉を踏まえた新たな国別関税率(8月7日から適用)を定めた大統領令が署名されたところであり、引き続き米国の通商政策や各国・地域の対応等の関連動向を注視していく必要がある。
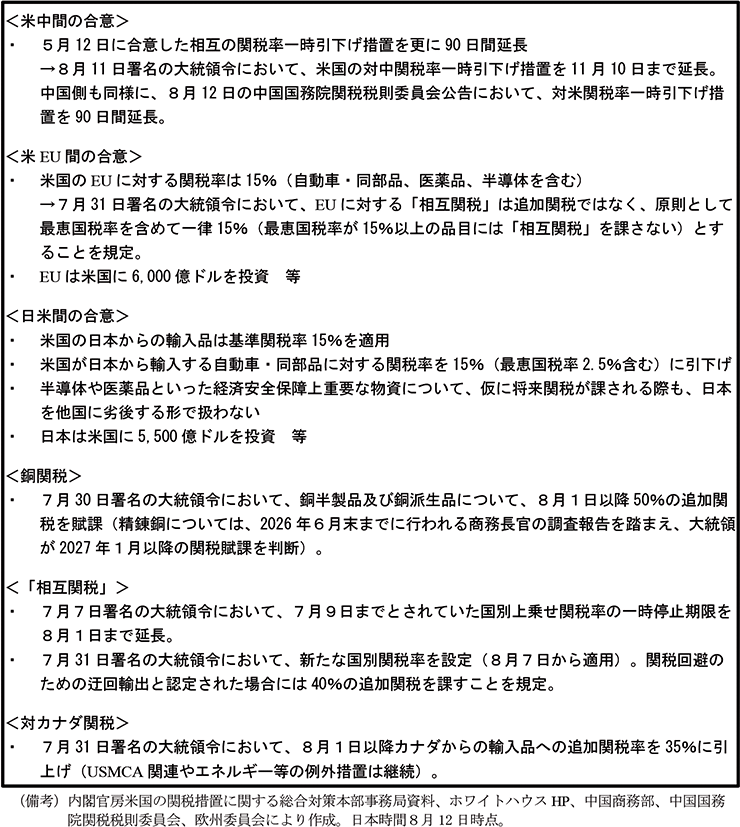
また、第二次トランプ政権は関税措置以外にも、不法移民対策や大型減税、国内投資の促進、エネルギー政策の転換等の様々な政策を進めている。米国は世界のGDPの約4分の1を占めており、米国経済の動向は世界経済に大きな影響をもたらし得るところ、こうした政策が米国の景気を押し上げ、または押し下げる場合、世界経済にも大きな影響を与える。
この他、2025年3月に米国がウクライナへの軍事支援を一時停止するなど、欧州の安全保障環境に関する米国の関与が大きく変化する中、EUでは同月に欧州委員会が「欧州再軍備計画」を策定し、関連する財政規律を緩和しつつウクライナ支援を含めた加盟国の防衛支出を拡大する方向に進んでいる。特にドイツにおいては、2025年3月に基本法(憲法)が改正され、防衛費は債務ブレーキの対象外に位置付けられることとなった。こうした防衛支出の拡大それ自体は公需の増加として欧州各国のGDPを押し上げる方向に寄与すると考えられる。このように、米国の安全保障政策の変化が他の国・地域の防衛支出の拡大を通じて世界経済に影響を与える可能性もある。
(高い金利水準の継続)
前節まででみたように、物価上昇率の落ち着きを受けて、欧米の主要な中央銀行は2024年から相次いで利下げを行っているが、その進展には地域ごとに差が出てきている。ユーロ圏では、利下げ開始前のピーク時には4.00%であった政策金利(預金ファシリティ金利)が2025年6月には2.00%まで引き下げられ、ECBの金融政策声明からも「緊縮的」との文言が削除されるなど、高い金利水準が継続している状況とはいえなくなっている。
米国でも、ピーク時に5.25~5.50%となっていた政策金利(FF金利)の誘導目標は2024年12月のFOMC会合時点で4.25~4.50%まで引き下げられたが、その後は据え置かれ、依然としてFF金利の長期見通しである3.0%より高い水準にある。英国でも、ピーク時に5.25%であった政策金利は2025年5月の会合時点で4.25%まで引き下げられたが、BOEの市場参加者へのアンケートにおける中立金利97の中央値3.25%(2025年5月調査)よりはなお高い水準にある。さらに、両国の長期金利については、政策金利の引上げに伴って2022年に大きく上昇した後、2025年6月に至るまで高い水準(米国:4.2%程度、英国:4.5%程度)でおおむね横ばいで推移している。
こうした米国や英国における高い金利水準の継続は、両国のインフレ圧力の根強さや財政の持続可能性への懸念を背景にしているものの、同時に家計の住宅ローンの利払い負担や企業の資金調達コストの高止まりをもたらすことから、固定資産投資が抑制され、景気を下押しするリスクがあることには留意する必要がある。
(金融資本市場の変動)
米国の通商政策の動向を受けて、特に「相互関税」や対中関税率の引上げが相次いで発表された2025年4月にかけて世界の株価、金利、為替、国際商品価格の変動が高まった(第1-4-4図、第1-4-5図)。5月12日の米中間の合意等、米国と各国との通商交渉の進展もあり、その後はこうした金融資本市場の変動が更に高まっている状況とはいえないものの、引き続き、米国の通商政策等を受けた金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。
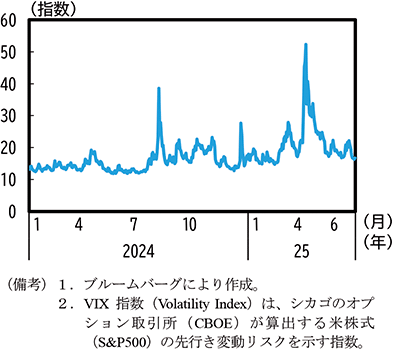
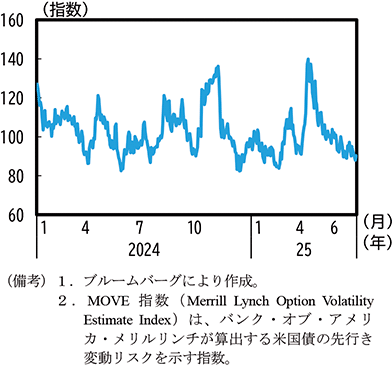
(中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響)
第2節でみたように、中国では、不動産市場の停滞が継続している。2022年前後から下落が継続してきた新築住宅販売価格については、各種政策支援もあって2025年春頃には大都市を中心に下げ止まりの動きがみられたが、依然として不動産開発投資が前年比で大幅な減少を続けているほか、住宅在庫も対前年比で増加を続けているといった状況には変化がみられない(第1-4-6図)。今後進展していく人口減少が住宅需要を下押しすることも考慮すると、短期的に不動産市場の停滞状況が大きく改善することは見通しにくい。不動産市場の停滞が長期化した場合、負の資産効果98等を通じて中国の景気を下押しする可能性があり、その影響が貿易や投資を通じて世界全体の景気を押し下げるリスクがある。
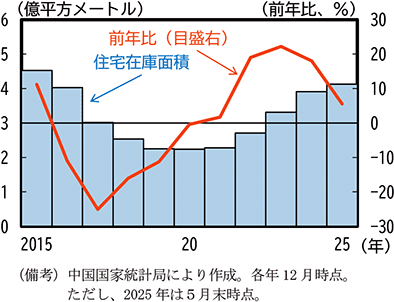
(中東地域やウクライナ侵略をめぐる情勢)
中東では、2023年10月に発生したイスラエル及びパレスチナ武装勢力間の衝突と、翌11月のイエメン国内の武装勢力であるホーシー派による紅海航行船舶への攻撃を受け、欧州とアジア間の海運がスエズ運河を回避して喜望峰回りとなる動きが生じ、2025年に入ってもその傾向は継続している(第1-4-7図)。イスラエルとパレスチナ武装勢力間の衝突は、2025年1月に6週間の停戦合意が成立したものの、3月以降はその延長に向けた交渉が停滞し、イスラエル軍はガザ地区での地上作戦を再開している。また、6月13日、イスラエルはイランの核関連施設等を攻撃し、これに対してイランも報復攻撃を行うなど、双方で報復の応酬となった。さらに、6月22日には米国がイランの核関連施設3か所を攻撃し、一段と緊張が高まったが、同月23日に米国のトランプ大統領がイスラエルとイランの停戦が発効する旨を表明した。こうした中東情勢が、今後一層緊迫化する場合、原油価格や輸送コストの上昇等を通じて世界の物価上昇率を高め、経済を下押しする可能性がある。
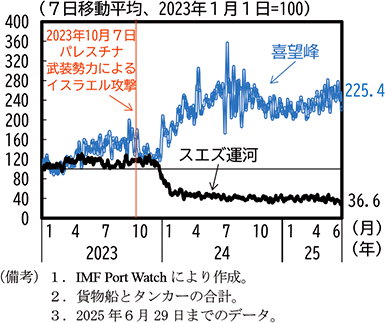
また、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略は3年を経過してもなお継続しており、欧州では安価であったロシアからの天然ガス輸入を米国等へ代替させる動きが続いている。また、ウクライナは小麦の主要生産国であることから、2022年には小麦の国際市況が高騰する事態も生じた。足下では、これらの国際商品価格は2022年の高騰からは落ち着きを取り戻しているが、ウクライナ情勢をめぐる不確実性は依然として高い状態が続いており、国際商品市況の変動に伴う世界的な物価上昇や経済への下押し圧力が再び生じる可能性には留意する必要がある。
コラム3 国際商品市況
本コラムでは、各国の物価や景気動向に影響を与える可能性のある国際商品市況について、2025年前半の動向を中心に概観する。各国のエネルギー物価に影響を与える原油、天然ガスに加え、このところ価格高騰が顕著な金の価格動向を振り返る。
(i)原油
原油価格(WTI)(図1(1))は、2021年初は50ドル/バレル前後であったが、2022年2月に起きたロシアによるウクライナ侵略をきっかけとして一時120ドル/バレルまで上昇した。その後は値下がりに転じたが、2023年10月のパレスチナ武装勢力によるイスラエルへの攻撃を契機とした中東情勢の緊迫化から、100ドル/バレル近くまで上昇した。その後は、価格はやや下落し、2024年末にかけて70ドル/バレル前後で推移した。
足下の動向をみると(図2(1))、2025年初は72ドル/バレルであったが、米英によるロシアの石油生産・輸出に対する制裁強化の発表を受け、1月中旬には78ドル/バレルまで上昇した。1月20日の米トランプ政権発足後は、米国のエネルギー政策の転換や関税措置等を受けた世界的な景気減速懸念による需給緩和予想などから3月半ば頃にかけて67ドル/バレル前後まで緩やかな下落基調が続いたが、米国による「相互関税」の発表にOPECプラスの自主減産縮小決定も重なり、4月4日には前日比▲7.4%、62ドル/バレルまで大幅に下落した。その後も、米国の景気減速懸念等から4月末にかけて58ドル/バレルまで下落したが、5月8日の米英合意や同月12日の米中合意といった米国と各国の通商協議の進展を受けて上昇し、6月上旬にかけて60ドル/バレル台前半で推移した。6月13日のイスラエルによるイラン攻撃とイランによる報復攻撃の応酬により中東地域の緊張が高まると原油価格は一段と上昇し、一時75ドル/バレルを超えたが、6月23日にトランプ米大統領がイスラエルとイランの停戦を発表すると65ドル/バレル前後まで下落した。
(ii)天然ガス
欧州における天然ガスの先物価格(TTF)(図1(2))は、2021年初は20ユーロ/メガワット時前後であったが、2021年冬期の低い気温に起因する需要増によって上昇した後、ロシアによるウクライナへの侵略により、一時210ユーロ/メガワット時まで上昇した。2022年8月には、ロシアのガスプロムによるノルドストリーム・パイプラインの定期修理とその間のガス供給停止の発表により供給不安となり、一時300ユーロ/メガワット時を超えるまで上昇した。その後、欧州諸国によるガス備蓄の確保の進展や記録的な暖冬及び春以降の気温上昇による需要減等もあり、2023年5月頃までに30ユーロ/メガワット時と、ロシアによるウクライナ侵略前の2021年半ば頃の水準まで低下した。2023年10月には、パレスチナ武装勢力によるイスラエルへの攻撃等の中東情勢の悪化を受け、再び50ユーロ/メガワット時まで上昇した。2024年前半には30ユーロ/メガワット時前後で推移したが、夏以降はウクライナ情勢の悪化懸念や12月のプーチン大統領によるウクライナとのガス輸送協定を延長しない旨の発言もあり、年末にかけて50ユーロ/メガワット時まで上昇した。
足下の動向をみると(図2(2))、2025年初は50ユーロ/メガワット時であったが、気温の低下や再生可能エネルギーの出力低下等の要因から2月半ばには58ユーロ/メガワット時まで上昇した。その後はこれらの要因の解消やウクライナにおける緊張緩和期待などから下落傾向で推移し、4月には米トランプ政権の関税措置による景気後退懸念の高まりから30ユーロ/メガワット時前後まで下落した。その後はやや値を戻し、6月前半にかけて35ユーロ/メガワット時前後で推移した。6月13日のイスラエルによるイラン攻撃以降は一時40ユーロ/メガワットを超えるまで上昇したが、6月23日の停戦発表後は6月末にかけて35ユーロ/メガワット前後の水準まで値を戻した。
このように、欧州の天然ガス価格は2022年に高騰した後、2023年以降は徐々に高騰前の水準に戻って安定的に推移していることから、エネルギー価格の上昇を起点とした近年のユーロ圏の物価上昇にも落ち着きがみられ、2023年半ば以降はエネルギー価格の消費者物価上昇率への寄与がマイナス傾向で推移している。
(iii)金
NY市場の金の先物価格(図1(3))は、2021年初は1,950ドル/トロイオンス前後であったが、2022年2月のロシアによるウクライナ侵略を受けて、3月には一時2,000ドル/トロイオンスまで上昇した。その後はFRBによる利上げを受けて米国の長期金利が上昇する中、2022年秋には1,700ドル/トロイオンスを割り込むまで低下した。その後、2022年末頃から金価格は再び上昇し、2023年春頃から年末にかけてはおおむね2,000ドル/トロイオンス前後で推移した。2024年春頃には米国の利下げ観測やイスラエルとイランの間での緊張増大を受けて金価格は再び上昇し、2,400ドル/トロイオンスを超えるまでに至った。その後も中東情勢の緊迫化や米国の利下げ期待等から秋にかけて金価格は上昇し、年末にかけては2,700ドル/トロイオンス前後で推移した。
足下の動向をみると(図2(3))、2025年初は2,600ドル/トロイオンス程度であったが、1月20日の発足以降、米トランプ政権の通商政策等の不透明感から安全資産として金が買われ、連日過去最高値を更新、2月半ばには2,900ドル/トロイオンスを超えるまで値上がりした。2月末は利益確定の売りもあって一時的に値上がりに落ち着きがみられたが、3月にはトランプ政権の関税措置の発表が相次ぐ中で金が買われ、「相互関税」が発表された4月2日には3,160ドル/トロイオンスまで高騰した。4月3日以降は世界的な株安が進む中で流動性確保のために金を現金化する動きもあり、7日にかけて3,000ドル/トロイオンスを割り込むまで値下がりした。しかしながら、その後米中間で相互に関税率が引き上げられる中で再び金が買われ、トランプ大統領によるFRB議長の解任に関する発言もあって4月21日には3,400ドル/トロイオンスまで高騰するなど、金価格の変動が高まった。5月12日には、米中間で関税の一時引下げが合意されたことを受けて金が売られ、3,200ドル/トロイオンス程度まで下落したが、その後は5月16日のムーディーズ社の米国債格下げによるドル安や6月2日のトランプ大統領による鉄鋼・アルミニウム関税率の引上げ発表等を受けて安全資産である金の価格は上昇基調となり、6月下旬にかけて3,400ドル/トロイオンス前後の過去最高値圏で推移した。
こうした動向の中、2021年頃までおおむね成り立っていた金価格と米長期金利との逆相関関係が2022年頃からみられなくなってきている(図3)。一般に、金の需要は実質金利が上昇すると低下し、また、不確実性が高まる局面では安全資産としての金の需要が高まるとされているが、2022年頃からは実質長期金利が上昇していく中で金価格は低下せず、2024年以降は実質長期金利が2%前後で安定的に推移する中で金価格は騰勢を強めている。2022年以降、ロシアによるウクライナ侵略やイスラエルとパレスチナ武装勢力との衝突を発端とした中東情勢の緊迫化、更には2025年の第二次トランプ政権発足に伴う米国の通商政策の大幅な転換など、地政学的リスクや政策の不透明感が高まる中で、安全資産としての金の需要が大きく高まっているものと考えられる。