第1章 2025年前半の世界経済の動向(第2節)
第2節 中国の景気動向
本節では、主に2025年前半の中国経済を概観するとともに、米国の通商政策の影響を受けた貿易の動向を分析する。
(各種政策の効果がみられるものの、景気は足踏み状態)
中国の2025年1-3月期の実質GDP成長率は、前年同期比5.4%となり、2025年3月の全国人民代表大会(以下、「全人代」という。)で示された2025年の実質GDP成長率目標の5%程度を超えるものの、2024年10-12月期の前年同期比5.4%から伸び率は横ばいとなった。「両新」政策等の各種政策の効果により、供給側のみならず、需要側の消費についても支援策の対象品目でこのところ伸びが高まっているが、支援対象以外の品目では消費の伸びが必ずしも高まっておらず、実質GDP成長率に対する消費の寄与も2024年4-6月期以降3%ポイントを下回る水準が続いている(「両新」政策についてはBox参照)。投資も後述するように低迷する一方で、2024年後半以降純輸出(外需)の寄与が2%ポイント程度で推移しており、過去の成長と比較して投資、消費の伸びが弱く輸出の増加による経済成長となっている。このように、中国経済は「両新」政策等の各種政策の効果がみられるものの、自律的な景気回復には至っておらず、景気は依然として足踏み状態となっている(第1-2-1図)。
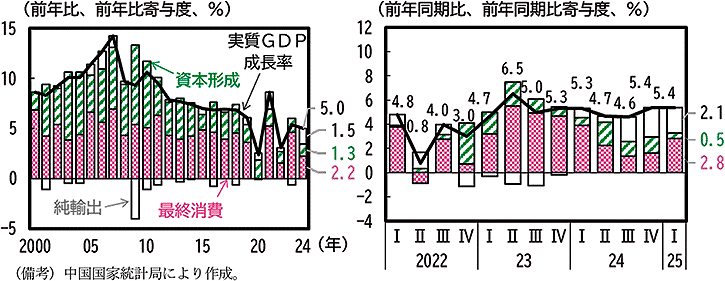
(一部品目では政策効果がみられるものの、消費はおおむね横ばい)
家計消費の動向について名目小売総額をみると、2024年は年間を通じておおむね前年同月比3%前後の伸び率であった(第1-2-2図)。2025年1月から4月の前年同月比の平均は5%程度の伸び率とやや上昇しているが、感染症拡大前(2015年から2019年)の平均が前年同月比9.7%であったことと比較すると、引き続き低い伸び率にとどまっているといえる。品目別にみると、政府による新エネルギー車28や家電などの消費財買換え支援を背景に、自動車販売額は足下ではプラスで推移し、携帯電話等のデジタル製品や電化製品を中心とした家電販売額は2024年の後半から引き続き高い伸びを示している。その一方で、服飾品等の消費財買換え支援の対象が含まれない品目の中には低い伸びとなっているものもあり、消費全体の伸びはおおむね横ばいとなっている。
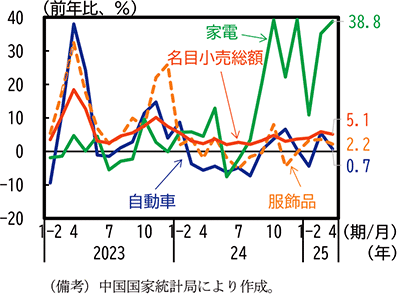
Box.「両新」政策
内需の拡大が政策課題となる中、政府は2024年から大規模設備の更新と消費財の買換えを支援する「両新」政策に取り組んでいる。2024年3月に国務院は「大規模設備更新と消費財買換え推進行動計画」を策定した。同計画では、製造業、農業、建築、交通等の各分野における設備投資の規模を2027年までに2023年比で25%以上増加させるなどの目標が定められ、製造業や建設、交通・運輸等の各分野での設備の更新、自動車や家電製品、住宅内装関連消費財の買換えを促進すること、財政・金融面での政策支援を行うことが示された。
同計画に基づき、2024年7月に国家発展改革委員会と財政部が超長期特別国債による資金約3,000億元を活用した具体的な支援策を発表した。大規模設備更新支援については約1,480億元を活用し、製造業やエネルギー、交通・運輸等の設備更新、省エネルギー改修等を支援することとした。また、関連する融資への利子補給を行うこととした。消費財買換え支援については約1,500億元を地方政府に配分し、既存の新エネルギー車等の購入補助金(最大1万元)を最大2万元まで引き上げるとともに、省エネ基準を満たす家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、パーソナルコンピュータ、給湯器、家庭用コンロ、換気扇)について販売価格の15%を補助することとした。
同支援策は2024年末まで実施することとされていたが、2025年1月には、国家発展改革委員会と財政部が2025年も支援策を拡充して継続することを発表した。大規模設備更新については、新たに電子情報、安全生産、施設農業等の分野が対象に加えられた。また、関連する融資への利子補給も増額されることとなった。消費財買換え支援については、対象となる家電製品に電子レンジ、浄水器、食器洗い機、炊飯器が加えられるとともに、新たにスマートフォン、タブレット等のデジタル製品の購入補助金(販売価格の15%)が盛り込まれた。また、3月の全人代における政府活動報告では、超長期特別国債による資金3,000億元を消費財買換え支援に充当することとされた。
さらに、4月28日に国務院の関係部門が実施した記者会見では、新たに産業用ソフトウェアの更新・高度化を「両新」政策の支援対象に加える方針が示された。
(政策効果により、自動車販売は持ち直しの動き)
2024年に拡充された新エネルギー車に対する買換え支援策の後押しを受け、2025年4月までの自動車販売台数は持ち直しの動きが続いている(第1-2-3図)。なお、販売価格が低下傾向29で推移しているため、販売台数の伸びほど名目販売額の伸びは高くない。また、自動車販売台数に占める新エネルギー車の比率は政策的な後押し30もあり2021年以降は特に高まり、2024年の通年では4割を超え、月次では2025年4月には5割近くにまで高まっている(第1-2-4図)。
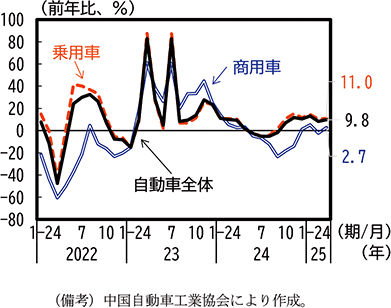
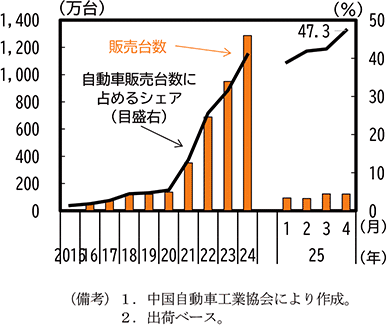
中国国内の乗用車ブランド国別の販売台数の近年の推移をみると、新エネルギー車に対する消費財の買換え支援策もあり、近年、EV車を主力製品としている中国系資本のメーカーのシェアが高まっている(第1-2-5図)。
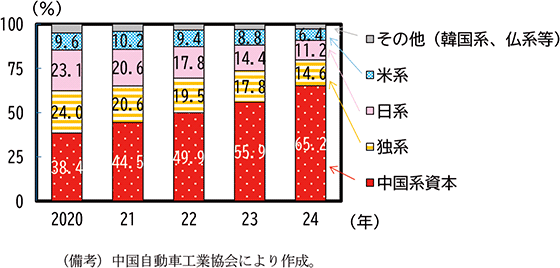
Box.国産ブランドを好む「国潮(グオチャオ)」ブーム
中国では近年、中国系資本の自動車の販売シェアが高まっているが、中国の文化的要素を取り入れたデジタル製品、アパレル製品や、化粧品などの国産ブランドの人気は高まっており31、Z世代32などの若者の多くが国産ブランドを好む傾向にある。
意識調査や先行研究をみると、中国青年報・中国高校(高等教育機関)伝媒連盟が行った大学生を対象とした調査では、回答者の79.8%の中国国産ブランド品を支持すると回答がなされている(図1)。また、李玲(2024)によると、「中国人消費者の中国国産品に対する消費態度」に関する調査結果は、中国国産品の品質を信頼する消費者の割合は 85.4%、国産品の品質向上を認める消費者の割合は 86.6% であり(図2)、Z世代の消費者は、中国の伝統的要素や文化に誇りを持ち、海外進出を果たしたブランドに対して積極的に評価し、コストパフォーマンスの高さを支持しているという。
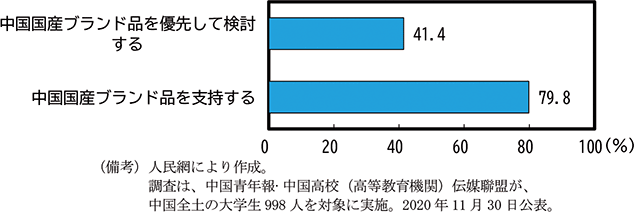
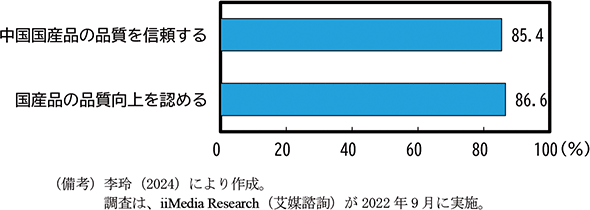
(失業率が横ばいの中、可処分所得は伸び悩み、消費者マインドは低位にとどまる)
雇用環境を都市部調査失業率からみると、若年失業率の上昇もあり全体の失業率は2024年12月から2025年2月まで3か月連続で上昇して5.4%となったが、3月に5.2%へ低下し、4月には5.1%となり、おおむね横ばいで推移している(第1-2-6図)。全人代で示された都市部の調査失業率の目標は2024年から引き続き「5.5%程度」と据え置かれており、その目標失業率を下回っているところであるが、中国では7月に新卒者が労働市場へ参入し、7月から8月にかけて失業率が上昇する傾向がある。今後、失業率上昇の可能性がある点には留意が必要である。
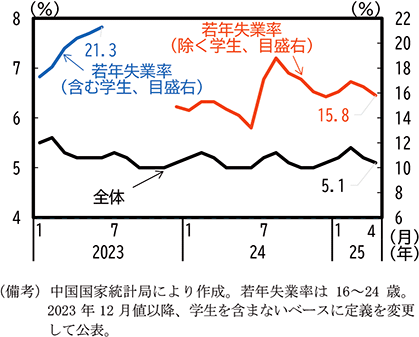
次に、所得面をみると、2024年の名目一人当たり可処分所得は前年比5.3%の伸びであったが、賃金・俸給の伸びもあり、2025年1-3月期には前年比5.5%に上昇した(第1-2-7図)。ただし、2018年から2024年の前年比の平均(6.9%)に比べると低下している。可処分所得と消費支出から平均消費性向を計算すると、2025年1-3月期は63.1%となり前年1-3月期の63.3%とおおむね同水準であった(第1-2-8図)。
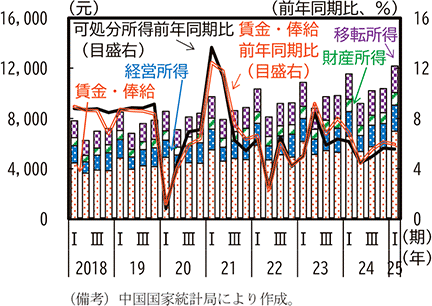
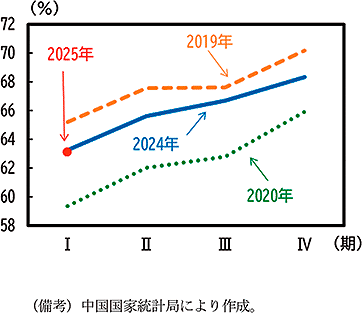
消費者マインドの動向も確認する。消費者信頼感指数は上海ロックダウンが行われた2022年春以降、判断の境目となる100を下回る状態が続いている。足下では消費意欲指数と収入指数は改善がみられるものの引き続き100を下回る状態であり、雇用指数については低い水準のままおおむね横ばいで推移している(第1-2-9図)。
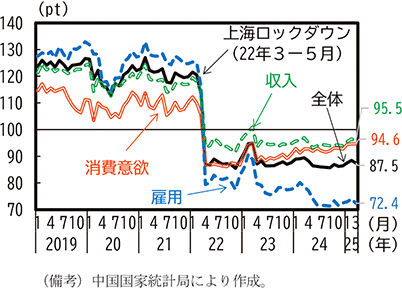
(固定資産投資は製造業投資が堅調に推移)
固定資産投資については、2025年1-4月累計で前年比4.0%と、2024年から伸びがおおむね横ばいで推移している。内訳をみると、製造業投資は「両新」政策による大規模設備更新の支援の効果もあり、2024年1-12月期累計は9.2%、2025年1-4月期累計では8.8%と高い伸び率で推移し固定資産投資全体を下支えしている。インフラ投資については2025年からは伸び率がやや高まり、4月までの累計では前年比で5%を超える伸びとなった。一方で、政府活動報告における重点分野として不動産市場の安定化が示されたものの、不動産開発投資の4月までの累計は前年同期比▲10.3%と大幅に減少している。中国は2022年から人口減少局面に入り33、それが住宅需要の下押し圧力となっていることもあり、不動産開発投資の今後の動向には留意する必要がある(第1-2-10図)。
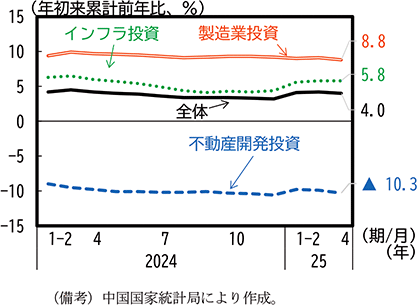
(住宅価格の下落が続く)
中国政府は不動産市場の下落に歯止めをかけ、安定回復に力を入れているところではあるが、70都市平均の住宅価格は下落が続いている。2025年4月までの都市階級別の動向をみると、1級都市(北京等)、2級都市(重慶等)では下げ止まりの動きがみられるものの、3級都市(地方都市)では下落が続いている(第1-2-11図)。
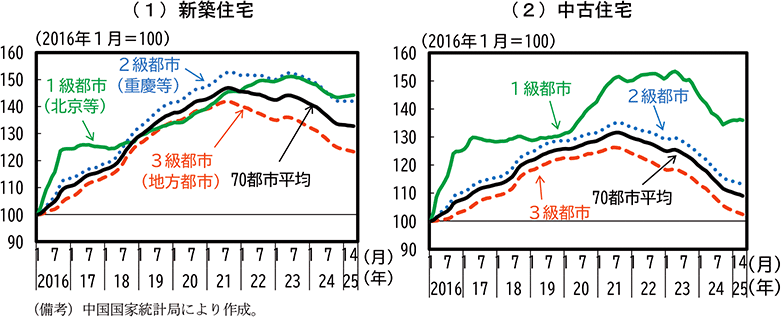
(鉱工業生産は持ち直している)
鉱工業生産は持ち直しを続けている(第1-2-12図)。主要業種の足下の動向をみると、「両新」政策の一つである消費財買換え支援の対象が含まれる電気機械器具、コンピュータ・通信・その他電子器具、自動車が前年比で高い伸びを示している。また、2025年1月から4月の前年同月比の平均は6%半ばを超える伸びとなっており、感染症拡大前(2015から2019年)の平均である同6.1%を超える水準となっている。
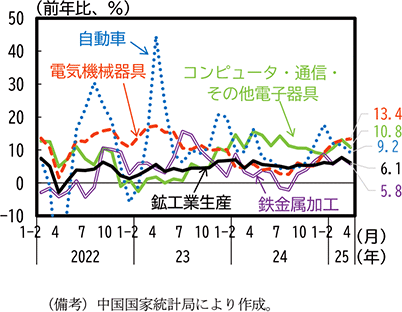
鉱工業生産の動向を補完する電力生産、貨物輸送量の動向をみると、足下では鉱工業生産を始めとして、電力生産は前年に比べると低い伸びとなっているが貨物輸送量は前年比で増加を続けており、全体として大きな変調はみられない(第1-2-13図)。
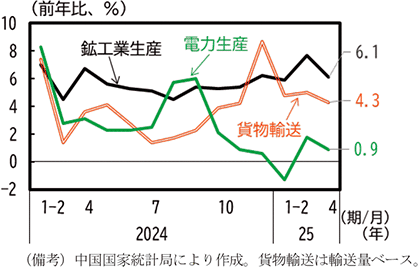
足下の製造業の景況感は持ち直しの動きに足踏みがみられる。大規模・国有企業の比重が高いとされる国家統計局の景況感調査の5月結果はマイナス幅が縮小した一方で、財新調査の5月結果はマイナス幅が拡大した。調査対象企業の相違もあるが、米国の関税率引上げ等の外部環境の急激な変化の影響を背景に、両調査で5月には新規受注指数が改善・悪化の判断の境目となる50を下回り、製造業PMIは50を下回っている(第1-2-14図)。
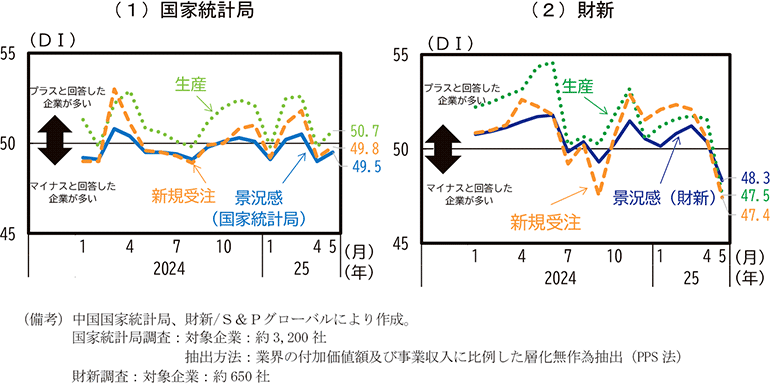
(対米貿易には通商問題の影響がみられるが、全体としては輸出は緩やかに増加している)
中国の貿易相手国・地域のシェア(2024年)から上位5か国・地域をみると、輸出は、ASEANが16.4%、米国が14.6%、EUが14.4%、中南米が7.7%、中東が6.2%、輸入はASEANが15.3%、EUが10.4%、中南米が9.3%、台湾8.4%、中東が8.2%となっている(第1-2-15図)。2025年2月以降に米国との間で関税率の引上げが繰り返された(第2章参照)が、中国の貿易構造において、米国を含めて特定の国・地域に偏ることなく多角化がなされているため、米国の通商政策による貿易への直接的な影響は限定的と考えられる。
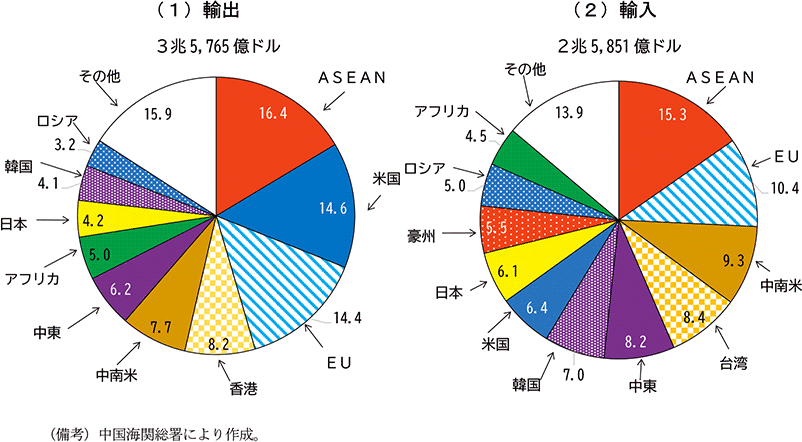
財輸出をみると、第二次トランプ政権発足前の2024年12月頃に駆け込みの動きがみられた米国向けは4月以降は大幅に減少した一方で、ASEAN向けを中心に全体として増加基調で推移し、輸出総額としては増加を維持している。その一方で輸入については、米国を始めとして主要な国・地域で減少したことから、輸入総額は2025年において前年比減少が続いている(第1-2-16図)。
品目別に中国の輸出入の動向をみると、輸出は機械類、集積回路を中心に増加に寄与している。輸入は、国際的な原油価格の低下や不動産開発投資の低迷もあり、原油や鉄鉱石など原材料を中心に減少に寄与している(第1-2-17図)。
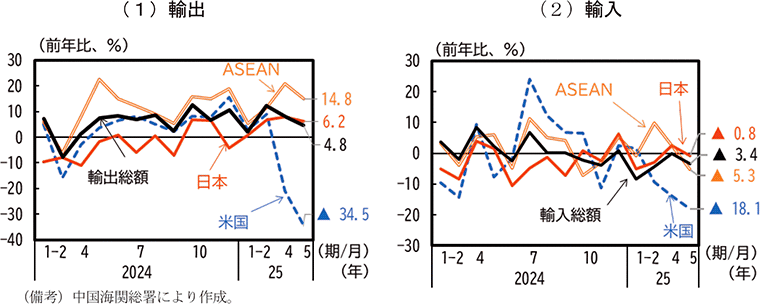
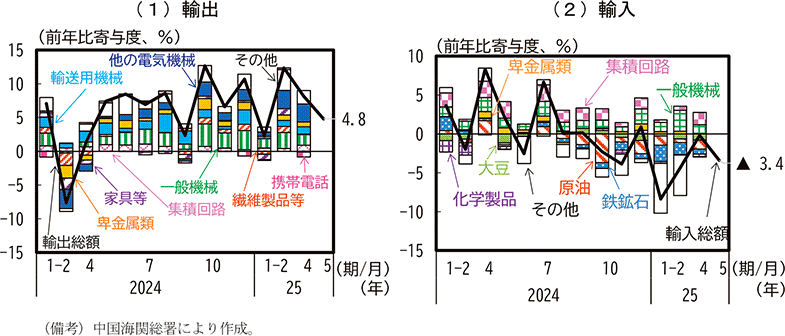
米中間の貿易構造について、2024年の米国との輸出入の品目をみると、中国から米国へは、携帯電話、コンピュータ等の電気機械や玩具、衣料・繊維製品等の消費財が多く、米国から中国へは、大豆や原油、プラスチック材料等の原材料を始め、民間航空機及び同部品といった製品が輸出されている(後述の第2-2-4図を参照)。
足下の動向をみると、中国からの輸出では、2024年12月に駆け込みの動きがみられた後、2025年4月の対米輸出総額については、同月に145%にまで追加関税率が引き上げられたこともあり、電話・通信機器などの機械類を中心に大幅に減少した。米国からの輸入では、米国の関税措置を理由として2月から石炭、原油等、3月からは農林水産品への対米追加関税措置が取られ、4月には米国からの全輸入品に対する追加関税率が125%にまで引き上げられたこともあり、原油等の鉱物性製品や大豆を中心に総額も大幅に減少している(第1-2-18図)。
このように米国の追加関税措置の影響を受けつつも、中国の輸出全体としては足下まで堅調に推移している。一方、輸入は3月以降前年比で減少が続いているが、その背景には消費を始めとした中国国内の内需の弱さもあると考えられる。
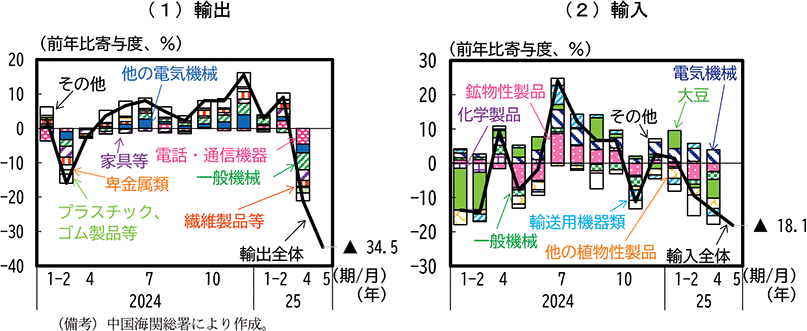
最後にレアアースの輸出動向に着目する。世界最大34のレアアース産出国である中国は2025年4月にレアアースのうち7種類35の輸出を許可制とする輸出管理の強化を行った。この結果、特に4月には中国のレアアース磁石の輸出額が大きく減少した(第1-2-19図)。レアアース磁石は自動車のモーターに使用されるなど、自動車等の生産に欠かせない中間財となっており、今後の輸出管理の動向を注視する必要がある。
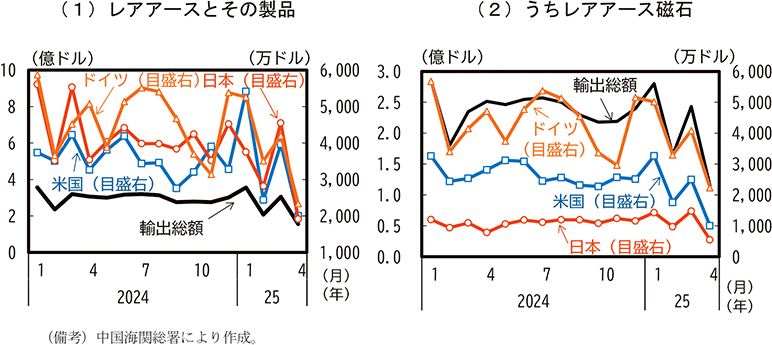
貿易統計でみた財輸出は前年比で増加が続いているが、先行きについて新規輸出受注指数をみると、米国の中国からの輸入品に対する「相互関税」等の影響を受け足下では景況感の判断の境目である50を下回って推移している(第1-2-20図)。
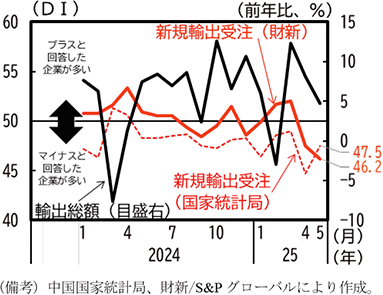
(消費者物価上昇率はゼロ近傍ながらマイナスが続く)
消費者物価(CPI)上昇率をみると、2025年2月に前年比で▲0.7%と低下した。食品、エネルギーを除いたコアCPIではプラス圏で推移しているものの、ガソリン等の燃料価格の下落に下押しされたこともあり、CPIは2025年以降、ゼロ近傍ではあるがマイナス圏となっている。2025年3月の全人代ではCPI上昇率の所期目標は2024年までの3%程度から2%程度に引き下げられたところであるが、足下までの伸びは目標を大きく下回っている(第1-2-21図)。さらに、生産者物価(PPI)については、原油を始めとした国際商品価格の下落の影響もあり2022年10月から2年以上にわたって下落が継続している(第1-2-22図)。
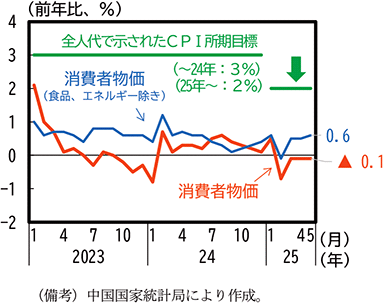
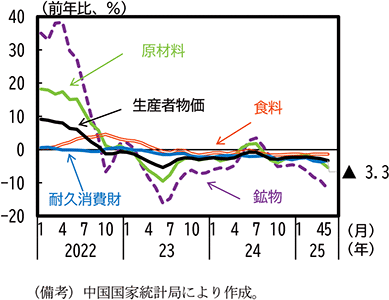
(内需拡大に向けた政策対応)
2025年3月の全人代の政府活動報告では、通商関係等の外部環境が厳しさを増し、国内経済も需要不足にあるという課題認識が示されつつも、2025年の成長率目標は前年に続き「5%程度」と設定された。財政政策のスタンスは「より一層積極的な財政政策」とされ、財政赤字対GDP比や地方特別債発行枠が引き上げられる等、2024年よりも財政拡張的な方針が示された。金融政策のスタンスは「適度に緩和的な金融政策」とされ、経済成長と物価の目標とマネーサプライ等の伸び率がつり合うよう、預金準備率36と政策金利を適時に引き下げることが明記された。
また、消費押上げと投資向上による「内需の全面的拡大」に取り組むことが重点施策の筆頭として掲げられた。2024年から発行された重要政策推進のための超長期特別国債37は2024年から3,000億元増の1兆5,000億元を発行することとし、うち3,000億元を消費財買換え支援に充てるなどの消費促進策の方針が示された(第1-2-23表)。
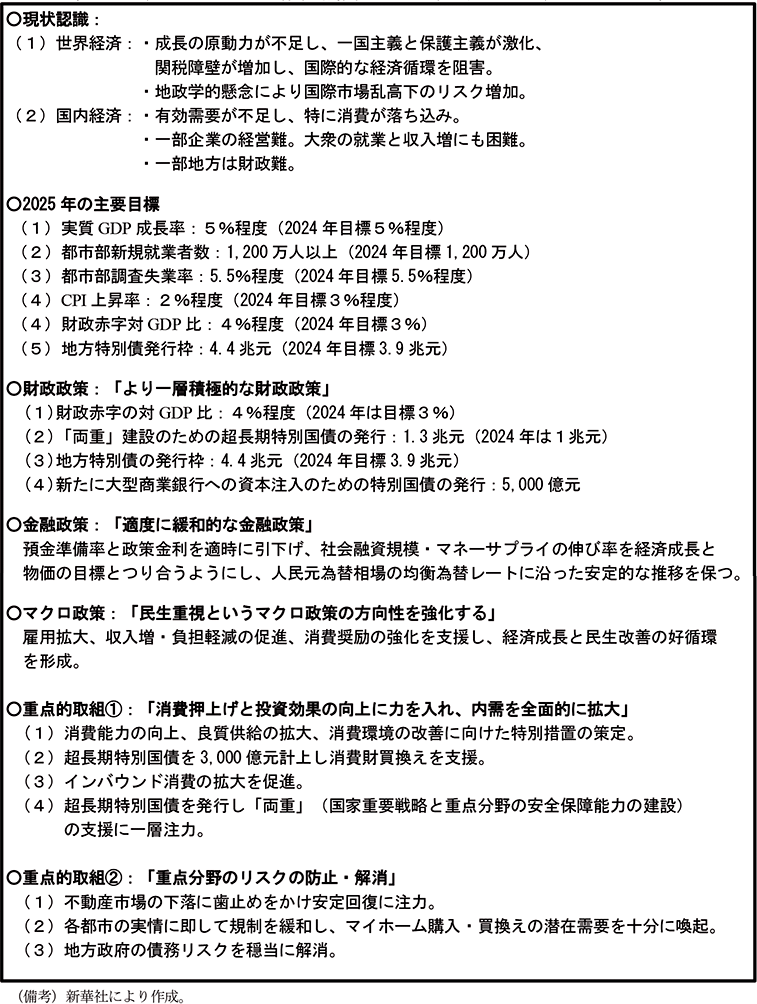
また、米国との通商関係の不透明感が増す中、2025年4月下旬以降、関係当局は相次いで追加的な経済政策・金融政策を発表38し(第1-2-24表)、インバウンド消費の拡大やソフトウェア投資の支援、追加的な金融緩和により内需の拡大、景気の下支えを図ろうとする姿勢がみられた。
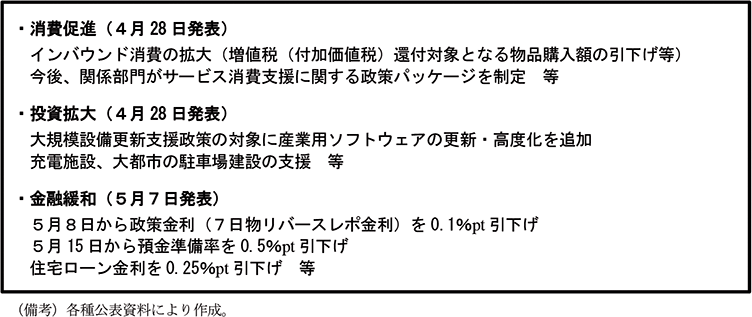
こうした方針を受け、5月8日にリバースレポ金利、同月15日に預金準備率がそれぞれ引き下げられ、同月20日にはローンプライムレート(LPR)が引き下げられた(第1-2-25図)。
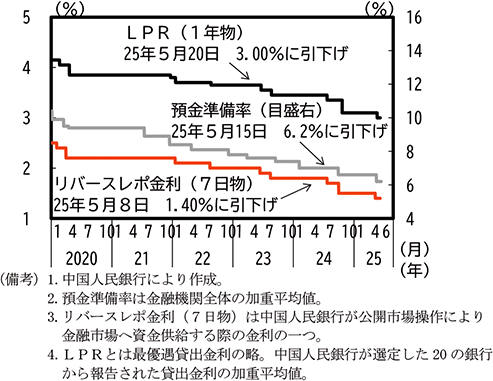
また、政府活動報告において「人民元相場の均衡為替レートに沿った安定的な推移を保つ」こととされた通貨政策については、米中間での関税率引上げが繰り返され、人民元安が進行する中、4月10日には人民元の取引基準値が2023年9月以来の元安水準(1ドル=7.2092元)に設定された(第1-2-26図)。その後、5月12日に米中間で互いに課していた追加関税率を115%引き下げる合意が成立すると人民元高が進み、2024年11月以降みられていた基準値とのかい離はおおむね解消した。
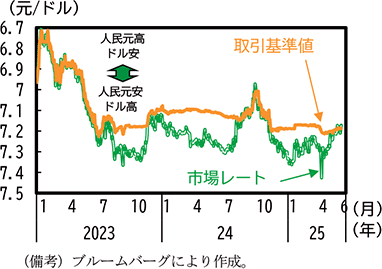
(まとめ)
以上のように、2025年前半の中国では、新エネルギー車や家電を始めとした消費財買換えの効果もあり、自動車販売台数は持ち直しの動きがみられる。一方で、政策支援の対象品目以外では消費の伸びは高まっておらず、消費全体としてはおおむね横ばいで推移している。固定資産投資は製造業投資がけん引するものの不動産開発投資は落ち込んでおり、住宅価格も70都市平均では下落が続くなど、不動産市場は停滞が継続している。内需がふるわない中、物価下落も継続し、景気は足踏み状態にある。
また、同時期の米国との通商関係をみると、2025年1月に米国で第二次トランプ政権が発足、2月以降米国との間で関税率の引上げが繰り返され、4月には米中相互の追加関税の累計が100%を超える状況(米国は4月10日に中国からの輸入品への追加関税率を145%に引上げ、中国は4月11日に米国への追加関税率を125%に引上げ。)となった。5月12日に双方で関税率を引き下げる合意がなされ、米国は中国からの輸入に対する「相互関税」率を125%から34%に引き下げ、90日間は更に34%を10%に引き下げる(違法薬物等を理由とする20%の追加関税と合わせて累計30%)一方、中国は米国からの輸入に対する追加関税率を125%から34%に引き下げ、90日間は更に34%を10%に引き下げるとともに非関税措置の停止または取りやめを行うこととした。もっとも、足下でも米中間の関税率は2024年以前よりも高い水準で維持されている上、引下げ期間経過後の双方の関税措置についてはいまだ不透明であり、今後の通商問題の動向については引き続き留意が必要である。
コラム1 近年の中国における金融政策の枠組みの改革
中国では、2025年の金融政策スタンスは、世界金融危機後の2008年11月から2010年までの期間以来の「適度に緩和的な金融政策」とされ、5月には預金準備率や政策金利の引下げが実施された。また、並行して金融政策の枠組みの改革が進められている。本コラムでは、中国の金融政策の枠組みを概観しつつ、近年の改革の動向を整理することとしたい39。
(1)政策目標
まず、中国人民銀行の政策目標を整理する。中国人民銀行の金融政策は、中国人民銀行法において、「通貨価値の安定を維持し、それをもって経済成長を促進する」ことを目標とする旨定められている。
その上で、より具体的な政策目標として、毎年の全人代における政府活動報告で、社会融資規模やマネーサプライの目標が設定されている。両指標の伸び率について具体的な数値目標が設定されていた時期もあったが、2025年の政府活動報告では、「社会融資規模40とマネーサプライが経済成長と一般物価の所期目標とつり合うようにする」とされており、具体的な数値目標は設定されていない。欧米主要国の中央銀行でも、1970年代以降にマネーサプライの伸び率を政策目標としていた時期があったが41、マネーサプライと経済活動の関係が不安定化したことから、現在では政策目標には位置付けられていない42。こうした量的目標に基づく政策は金利調節の方向性と整合的でない場合を生じさせる可能性があるといった指摘43もあり、中国人民銀行も、徐々に量的目標の政策運営上の比重を低下させ、金利の役割を拡大させる方針を示している44。
なお、中国人民銀行は欧米主要国の中央銀行が有するようなインフレ目標を掲げているわけではないが、毎年の政府活動報告では消費者物価上昇率の所期目標が示されている。福本(2022)では、国務院の一部門に位置付けられる中国人民銀行を含め、政府全体としてソフトなインフレ目標にコミットしているといえるかもしれないと評価している。近年0%近傍の消費者物価上昇率が継続してきた中で、2025年の政府活動報告では、これまで3%とされていた消費者物価上昇率の目標が2%程度に引き下げられるとともに、同目標設定の目的について、「諸般の政策と改革の相乗効果により、需給を調整し、一般物価水準を合理的な範囲内に安定させること」と記載された。このことから、物価抑制のための上限として理解されてきた物価上昇率の目標は、需給ギャップの縮小を通じて実現を目指す安定的なインフレ目標としての性質が付与された可能性もある。
(2)政策手段
(i)金利調節と金利システム改革
中国人民銀行は、市場に基づく金利システムの構築に向けた改革を進めてきた。2021年に中国人民銀行の易総裁(当時)が公表した論文では、当時の中国の金利システムについて図1のように整理している。政策金利は短期の7日物リバースレポ金利と中期貸出ファシリティ(MLF: Medium-term Lending Facility)金利の2種類とされ、それぞれベンチマーク金利であるDR007(預金取扱金融機関の7日物レポ金利)とLPRを経由し、短期及び中期の市場金利に波及するという経路が想定されている。この点は、欧米の主要中央銀行が専ら短期金利のみを政策金利とし、金利の期間構造を通じて中長期の金利に影響を与えるという金融政策運営を行っていることとは対照的である。
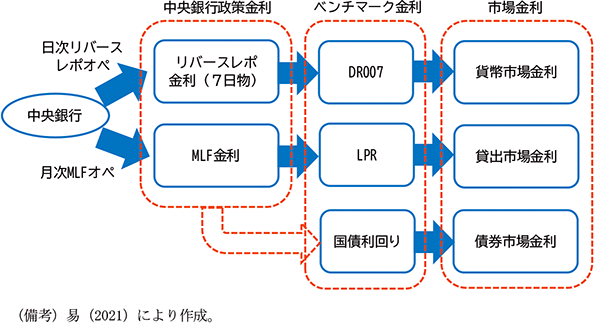
こうした短期と中期の二本立ての政策金利体系について、足下では次のように改革されている。2024年7月、中国人民銀行は7日物リバースレポ金利が現在の主要政策金利であると明言するとともに、MLFオペのタイミングをLPRの公表後に変更し、LPRが7日物リバースレポ金利を参照するように促した。同年9月に発表した政策金利の引下げにおいては、主要政策金利である7日物リバースレポ金利を引き下げるとし、その結果、MLF金利やLPRも引き下げられるとの説明がなされた。その上で、2025年3月からMLFの入札方式を単一価格方式から複数価格方式に変更したことに伴い、MLF金利の公表が停止された。この点について、中国人民銀行は「MLF金利は政策金利の機能から退出した」と説明しており45、中国の政策金利は短期の7日物リバースレポ金利に一本化されたといえる。中国人民銀行の説明によると、今後は政策金利である7日物リバースレポ金利に基づき、金利の期間構造に沿ってLPRが形成されていくことが想定されていると考えられる。
また、ベンチマーク金利とその影響を受ける市場金利との関係についても改革が進展している。2019年以降、中国における商業住宅ローン金利はLPRに固定のプレミアムを上乗せして決定することとされている。しかしながら、金利の引下げが進展し、過去に契約された住宅ローンのプレミアムと新規住宅ローンのプレミアムとの水準差が拡大してきたことを受け、2024年9月には、借り手と銀行との合意によりLPRに上乗せするプレミアムを可変とすることができるよう制度改正が行われた。この制度改正は、近年進行してきた利下げの恩恵を既存の住宅ローン契約者にも及ぼすとともに、市場に基づく住宅ローン金利の形成を更に進めることにつながるものである。ただし、住宅ローン金利の変動性を高める改革であり、将来的に金利が上昇する局面では家計の利払い負担を増幅させる方向に働く可能性もある。
(ii)預金準備率操作
欧米の主要中央銀行では近年ほとんど利用されなくなっているが46、中国では金利調節と並ぶ金融政策手段として預金準備率操作が多用されている。預金準備率の引下げは貨幣供給量を増やす金融緩和効果を持つこととなる。中国の預金準備率は金融機関全体の加重平均で6.2%(2025年5月末時点)と、欧米の主要中央銀行が設定している水準(2025年5月末時点でFRBは0%、ECBは1%)よりも高いことから47、近年は専ら金融緩和の手段として預金準備率の引下げが行われている。また、後述する構造的金融政策手段のように、特定の分野への融資を行う金融機関の預金準備率だけを操作し、当該分野への融資の拡大を促すことにも利用されている。
(iii)構造的金融政策手段
このほか、欧米の主要中央銀行ではあまりみられない政策手段として、構造的金融政策手段と呼ばれるものがある。これは、特定の産業振興や政策目的のために用いられる政策金融的な手段であり、中国人民銀行は主要な国家戦略事業や主要産業、脆弱な分野等に金融機関が金融サービスを提供するよう導く役割があると説明している48。近年は停滞が続く不動産市場対策として構造的金融政策手段が活用されているほか、2025年5月には新たにサービス消費と高齢者福祉に関する5,000億元の再貸出枠が設けられ、消費の拡大等の政府の重点政策に金融面から貢献しようとする姿勢がみられる。他方、こうした特定の分野を対象とする融資枠は市場を通じた効率的な資源配分を歪める可能性があるとの指摘もある49。

