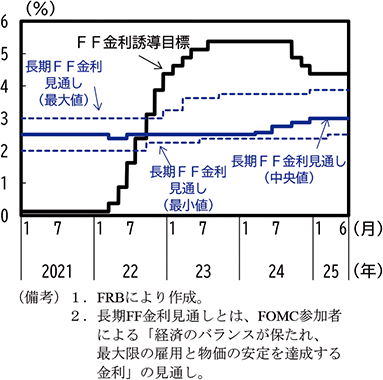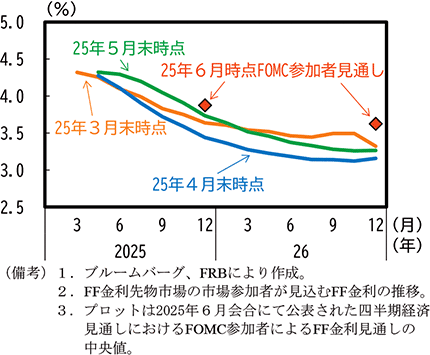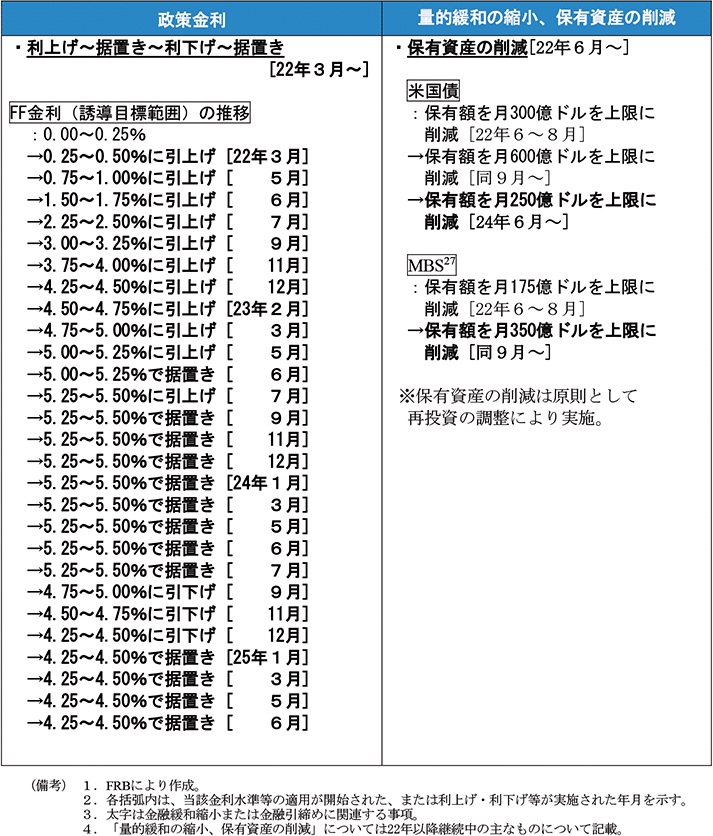第1章 2025年前半の世界経済の動向(第1節)
第1節 米国の景気動向
本節では、主に2025年前半の米国のマクロ経済の動向を概観する。
(米国では、景気の拡大が緩やかとなる中、関税率引上げに伴う駆け込み需要やその反動の影響、不透明感がみられる)
米国では、景気の拡大が緩やかとなる中、関税率引上げに伴う駆け込み需要やその反動の影響、不透明感がみられる。2025年1-3月期の実質GDP成長率(第3次推計値)は前期比年率▲0.5%となり、2022年1-3月期以来、12四半期ぶりにマイナスとなった(第1-1-1図)。その背景としては、個人消費の伸びが鈍化したことに加え、関税率引上げ前の駆け込み需要による輸入の急増がある(第二次トランプ政権の通商政策の詳細については、第2章第2節で後述)。また、輸入の増加に伴い、企業による在庫の積増しがみられている。
ここで、国内民間最終需要1を確認する。2024年の国内民間最終需要は、米国のGDPの86%を占める(第1-1-2図)。2025年1-3月期の国内民間最終需要は、前期比年率+1.9%であり、2024年の伸び(前年比+3.0%)を下回っているものの、プラス成長を維持している2(第1-1-1図)。ただし、2025年1-3月期の民間設備投資は、関税率引上げ前の駆け込み需要の影響による情報通信機器投資の増加という特殊要因により押し上げられている点には留意が必要である(詳細は後述)。
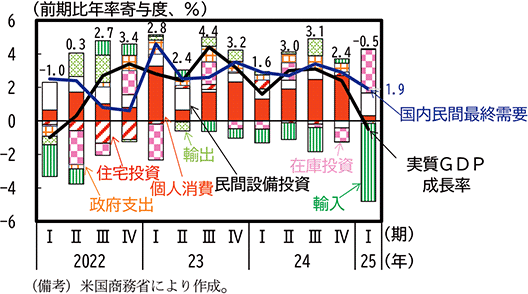
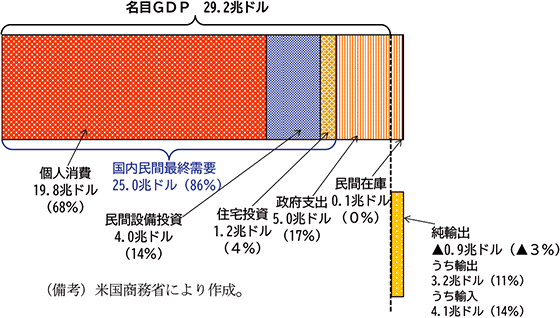
(個人消費の伸びは緩やかになっているが、関税率引上げに伴う駆け込み需要の影響がみられる)
実質個人消費支出は、2025年以降、伸びが緩やかになっている。実質個人消費支出は、耐久財消費(消費全体の約1割)、非耐久財消費(消費全体の約2割)、サービス消費(消費全体の約7割)に分けることができる。非耐久財消費とサービス消費は、2025年以降、伸びが緩やかになっている。耐久財消費は、関税率引上げに伴う駆け込み需要の影響により、2024年11月以降、変動が大きくなっている。
トランプ大統領は、大統領選の選挙期間中から関税率引上げを主張してきたことから、2024年11月の大統領選挙の結果を受け、関税率引上げを見越した駆け込み需要が生じたことにより、2024年11月、12月の耐久財消費が自動車や娯楽用品を中心に増加した。2025年1月には、その反動で自動車や娯楽用品が減少に転じた。2025年1月のトランプ大統領就任後、各種関税措置が発表されたことから、関税率引上げ前の駆け込み需要により、2025年3月に耐久財消費が自動車や娯楽用品を中心に再度増加した後、5月にはその反動で減少に転じた(第1-1-3図)。
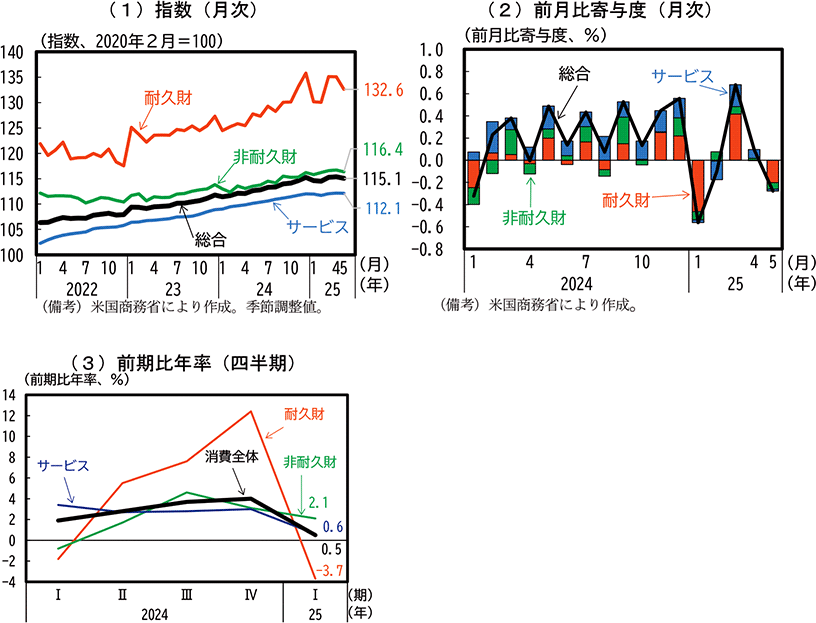
新車販売台数に着目すると、第二次トランプ政権発足後の関税率引上げを見越した駆け込み需要から2024年11月、12月に増加したのち、2025年1月にはその影響がはく落した。その後、自動車の関税率引上げ前の駆け込み需要により、25年3月は1,783万台(年換算)、4月は1,726万台(年換算)と15年から19年の平均販売台数である1,724万台を超えた。その後、駆け込み需要ははく落し、25年5月には、1,565万台(年換算)となった(第1-1-4図)。
第1-1-5図は、日系自動車メーカーの2024年米国内新車販売台数上位4社における2025年の新車販売台数(前年比)と、各社の米国内新車販売台数に占める当月の輸入台数の割合を示したグラフである。完成車の輸入割合が高いメーカーは、5月の前年比がマイナスとなっており、販売が伸び悩んでいる。6月以降、関税率引上げを踏まえた値上げの実施または検討を各国メーカーが発表しており、今後の自動車販売台数への影響には注視が必要である。
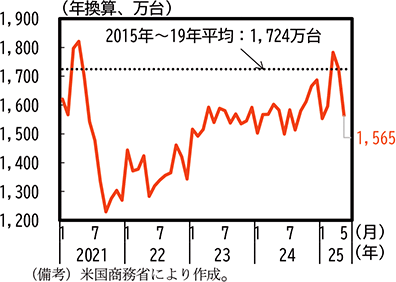
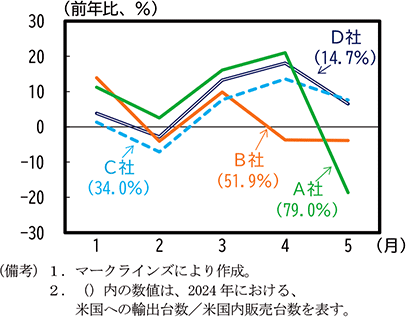
(消費者マインドは、第二次トランプ政権が発足した2025年以降、低下)
トランプ大統領の就任以降、消費者マインドは低下が続いた。ミシガン大学が公表している消費者マインドの総合指数は、24年12月以降、25年4月まで4か月連続で低下し、4月確報値の52.2は、2022年7月の51.5以来の低水準となった(第1-1-6図)。その要因について、調査元3は、主に通商政策に関する不透明感の継続や今後インフレが再燃する可能性等を消費者がリスクとして認識していると指摘している。
消費者マインドを支持政党別にみると(第1-1-7図)、大統領選挙を境に民主党支持層と共和党支持層で動きが対称的になっている。民主党支持層の消費者マインドは、大統領選が行われ、トランプ候補の勝利が確定した2024年11月に前月から10ポイント以上も低下し、25年4月まで急激な低下が続いた。それに対し、共和党支持層の消費者マインドは24年11月に前月から15ポイント以上上昇した後、25年以降もその高い水準から更に上昇傾向にある。
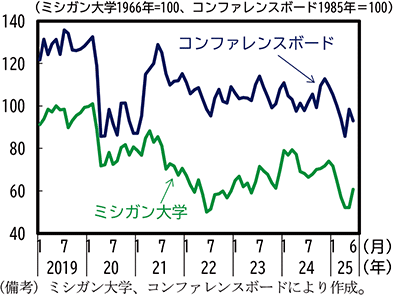
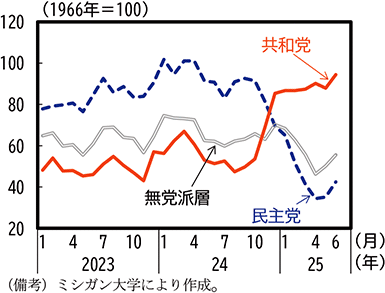
(民間設備投資は関税率引上げに伴う駆け込み需要の影響もあり、このところ増加)
次に、民間設備投資の動向について確認する(第1-1-8図)。民間設備投資は、24年10-12月期に13四半期ぶりに減少した後、25年1-3月期は、関税率引上げに伴う駆け込み需要の影響により機械・機器投資が急増し、民間設備投資全体で前期比年率+10.3%の増加となった。特に、情報通信機器投資が前期比年率+72.9%と急増しており、そのうちコンピュータ・周辺機器と通信機器が高い伸びとなっている。また、知的財産投資についても、24年10-12月期は前期比でマイナスだったが、25年1-3月期にはプラスに転じており、増加に寄与している。
25年1-3月期は駆け込み需要という特殊要因による増加の寄与が大きいことから、4-6月期はその反動が民間設備投資を押し下げる可能性がある点には留意が必要である。
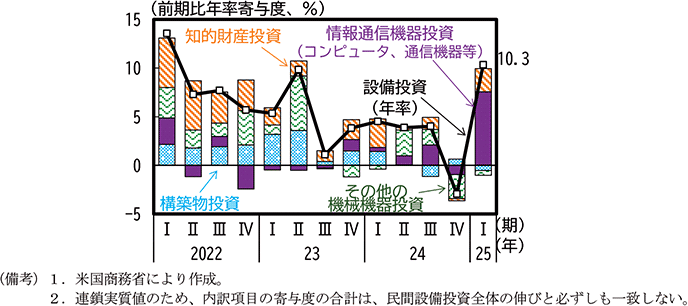
(住宅着工はおおむね横ばい)
住宅着工は、2025年前半にかけておおむね横ばいで推移している(第1-1-9図)。
住宅着工件数を地域別にみると、最大市場の南部では、2020年に新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)拡大とともに一旦大きく落ち込んだ後、2022年前半頃まで、低金利環境もあって堅調に推移したものの、2022年におけるインフレ率の高まりに伴うFRBによる政策金利引上げを受け、住宅ローン金利が上昇したことにより、住宅着工件数は2022年後半にかけて低下した(第1-1-10図)。その後はおおむね横ばいで推移しており、2025年に入ってからは75万件前後で推移している。西部の住宅着工件数については、同様に、住宅ローン金利の上昇を受けて2022年頃から低下し、2023年初めを底にやや持ち直している。直近では、2025年1月にカリフォルニア州で大規模な山火事が発生し、州政府の支援策も相まって即時的な再建需要が喚起され、2025年2月の住宅着工件数は2022年4月以来の水準まで増加した4。一方、中西部・北東部の住宅着工件数については、2022年後半頃に一時的に落ち込む局面がみられたものの、2023年に入ってからは減少分を取り戻し、おおむね横ばいで推移している。
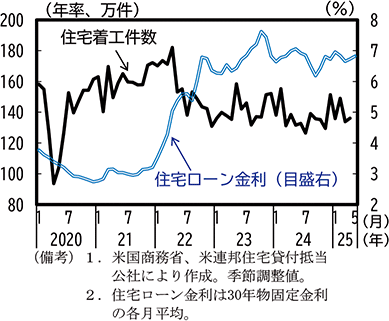
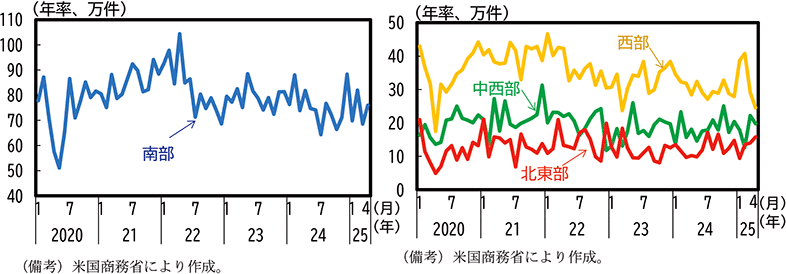
住宅着工の物件種類ごとの推移を確認すると(第1-1-11図)、一戸建て住宅については、2022年の金利上昇を受けて新規着工件数は減少に転じたものの、中古市場を含めた住宅市場全体としては感染症拡大後から供給不足局面にあることもあり、2023年には一戸建て住宅の着工件数も回復し、住宅着工件数全体としても増加に転じた。2024年に入ると、住宅ローン金利の高止まりによって住宅需要が弱まり、着工数全体が再び減少に転じた。なお、集合住宅の着工件数は、2023年から24年にかけて減少が継続してきたが、25年に入ってから持ち直している。
また、集合住宅の供給動向をより詳細に確認するため、住宅着工以降の各建設段階の統計を用いて確認する(第1-1-12図)。集合住宅は2020年から21年の旺盛な住宅需要を受けて2023年頃まで住宅着工が増加した。しかし、2020年の感染症拡大に伴うサプライチェーンの混乱や、人手不足等により、着工はなされたものの未完工である物件が増加し、2023年半ばに建設中件数は100万件に達した。2023年以降、着工件数が減少する中、完工した集合住宅が増加すると、建設中の集合住宅も減少に転じた。住宅完工の急速な進展も2025年に入ると一服し、足下では完工件数は減少傾向にある。
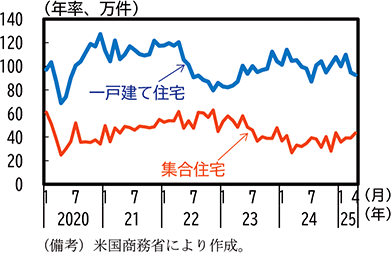
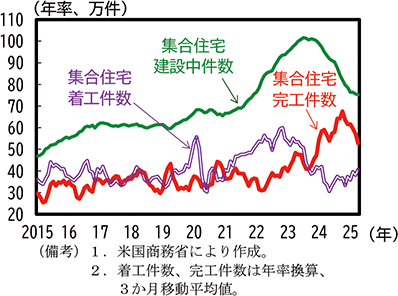
住宅在庫についてみると、住宅バブル崩壊に端を発した2008年の世界金融危機以降、低下基調にあり、慢性的に供給不足が続いていた5。こうした中、感染症拡大後の低金利環境下で住宅需要が高まり、その後の金利上昇局面では住宅の住み替えが抑制されたことによって、市場の中古物件が減少した。こうした背景から、住宅需要に見合うための住宅を供給するために新築住宅の着工が進み、新築住宅在庫が増加した。なお、直近では中古住宅の在庫についても持ち直しの動きがみられる(第1-1-13図)。
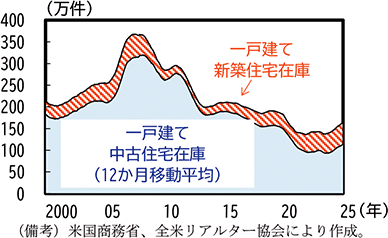
さらに、住宅在庫月数(在庫と月間販売件数の比率)を確認する。新築住宅は建設許可取得時点または着工開始時点で販売可能在庫に計上されるため、一般的に中古住宅在庫よりも在庫月数は多くなる6。
一戸建て住宅については(第1-1-14図)、前述のとおり、感染症拡大後に住宅ローン金利が低下する中、中古住宅在庫月数は低下した一方、住宅着工が増加したことにより、新築住宅在庫月数は2022年にかけて上昇した。住宅在庫の約7割は中古住宅が占めるため、結果的に新築住宅及び中古住宅の在庫月数は、2022年に一時2.1か月まで低下した。2022年後半以降、住宅ローン金利の上昇に伴い住宅需要は減速したものの、ロックイン効果7により市場に出回る中古物件数が回復せず、中古住宅在庫月数は感染症拡大前と比べて低水準で推移した。
しかし、2025年にかけて住宅供給は回復してきており、2025年4月には新築住宅及び中古住宅の在庫月数は4.9か月と、2015年11月以来の水準にまで上昇した。全米ホームビルダー協会(NAHB:National Association of Home Builders)によると、適切な一戸建て住宅在庫は5~6か月程度8とされており、その水準に近づいている。
集合住宅については(第1-1-15図)、市場の多くを占める中古物件の在庫月数についてみると、一戸建てと同様に2020年後半から2022年にかけて低下したものの、2022年後半以降は上昇傾向にある。直近では、2025年4月の在庫月数は6.2か月と、感染症拡大直後の2020年5月以来の水準まで上昇している。
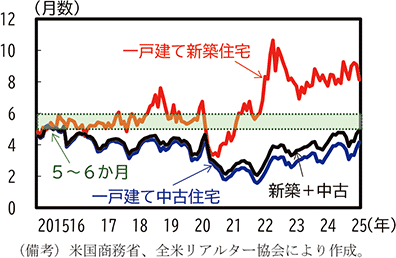
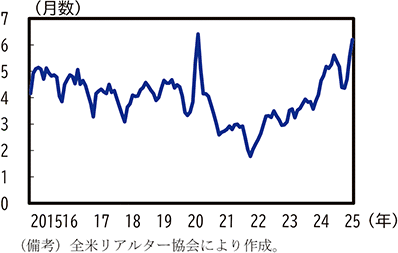
次に、一戸建て住宅、集合住宅の販売状況について確認する。
まず、一戸建て住宅市場について、住宅販売をみると、住宅市場の大部分を占める中古住宅の販売件数は、感染症拡大前と比較して低い水準でおおむね横ばいで推移している(第1-1-16図)。なお、新築住宅販売は主に住宅建設業者の販売奨励策に支えられ9、住宅ローン金利が上昇した2022年後半以降も底堅く推移している。
集合住宅については、低金利環境下で中古集合住宅の販売件数は増加し、2020年後半から2022年前半にかけて高水準での推移が続いた。その後、金利が上昇した2022年後半以降は、2015-19年平均を大きく下回る販売件数で推移している(第1-1-17図)。
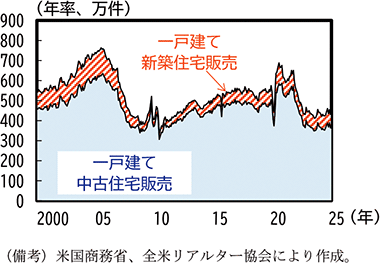
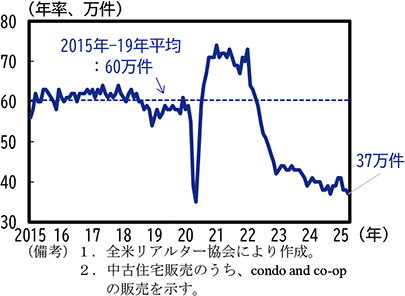
住宅の買い手(消費者)を取り巻く環境について確認する。
住宅ローン金利(30年物固定金利)は、2023年以降、政策金利の引上げに伴って上昇し、感染症拡大前の水準と比較して高い状態が続いている(第1-1-18図)。ピーク時の2023年10月には7.6%となったが、これは2000年11月以来の高水準であった。住宅ローン申請件数(住宅購入目的)は、住宅ローン金利が上昇局面にあった2021年後半頃から低下し、低水準での推移が続いている。
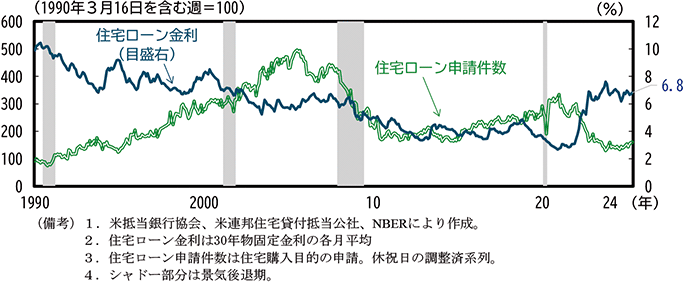
また、消費者の住宅購入に対するマインドの変化について確認する。まず、現況について、ミシガン大学による消費者マインド調査における住宅購入判断(「今は住宅を購入するのに適した時期か」という質問に対し、「適した時期」と「不適な時期」と答えた人の割合の差から算出される指数)と、購入に「不適な時期」と答えた回答者の理由について確認すると(第1-1-19図)、2021年頃に住宅価格が上昇したことから、住宅購入判断指数は低下に転じた後、FRBによる政策金利の引上げが開始された2022年以降に住宅ローンが上昇したことにより、指数は一段と低下した。2025年にかけても、住宅購入判断指数は低水準での推移が続いているが、「先行きが不透明」であることを理由に、住宅購入に消極的な消費者が増えている。これは、関税措置を始めとした第二次トランプ政権の政策により経済の先行きの不透明感が高まっていることが影響している可能性がある。
先行きについて、コンファレンスボード消費者マインド調査における「住宅購入計画」をみると、2024年には住宅ローン金利のピークアウトとともに下げ止まり、上昇に転じたものの、2024年末にかけては再び落ち込んだ(第1-1-20図)。直近の2025年5月には反発したが、金利の高止まりや経済先行きの不透明感を鑑みると、マインド改善が今後も持続するのか注視する必要がある。
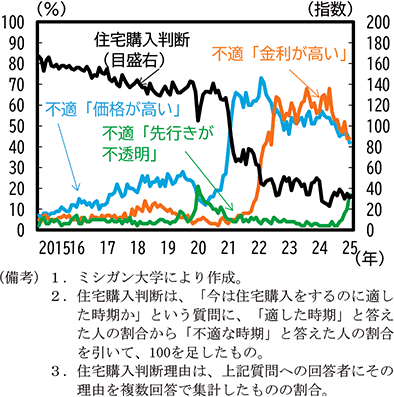
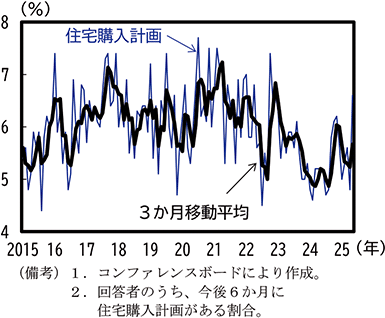
こうした中、住宅市場の住宅販売者数(販売中の物件)が増加する一方で住宅購入希望者数は低調に推移しており、2025年4月には販売者数が購入希望者数を約50万人上回った(第1-1-21図)。これは、記録に残る2013年以降で最も大きなかい離であり、住宅市場が大きな需要不足になりつつあることが示唆されている10。
統計の発表元によると、ロックイン効果によって保有している物件を売却するのに消極的だった人たちが、転職やオフィス出勤の義務化などによって引っ越しを余儀なくされ、今の住宅に留まり続けることが困難になった結果、住宅販売者数は増加しつつあるとの見方が示されている。一方、住宅購入希望者数については、住宅ローン金利の高止まりや消費者マインドの悪化が要因で減少している。
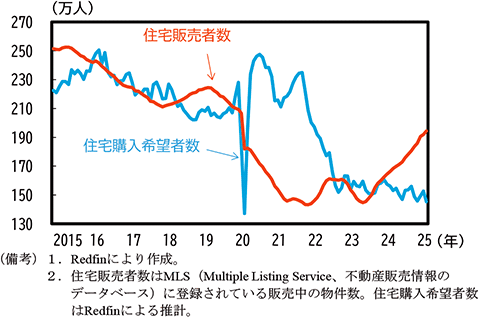
最後に、住宅価格について確認する。
一戸建て中古住宅を対象とするS&Pケースシラー住宅価格指数11の推移を第1-1-22図に示す。2020年半ば以降、住宅ローン金利の低下やリモートワークの普及等によって住宅需要が増加したことに加え、建設資材の高騰や人手不足によって投入コストが高まり、住宅価格は上昇した。2022年頃にはFRBにより政策金利が引き上げられる中、住宅価格は一時低下に転じたものの、それ以降は住宅不足が続く中、安定した価格上昇が続いてきた。
しかし、前述のとおり、住宅在庫が増加する中、需給は緩和方向にあり、2025年3月には前月比▲0.1%の下落に転じた。前月比ベースでみると、価格は2023年1月以来、初めて下落し、長く続いた住宅価格が緩やかに上昇する局面から変化が生じつつある可能性がある。
また、一戸建て住宅の販売価格の中央値を新築住宅・中古住宅別でみると、前述の通り、在庫に過剰感が見られる新築住宅は価格が頭打ちとなっている一方、中古住宅(12か月移動平均)は緩やかな上昇トレンドにある(第1-1-23図)。しかし、前年比でみると2025年5月に+1.8%と、4カ月連続で低下して2023年7月以来の低水準となっており、中古住宅価格の伸びは減速方向にあることが確認される。
買い手と売り手の間の不均衡が拡大しているため、米国の住宅価格は2025年末までに1%下落するとの推計もある12。また、住宅供給は2025年を通して増加を続け、住宅市場における雇用者数も継続して増加するとの見方もあり13、住宅価格には更に下落圧力がかかる可能性がある。
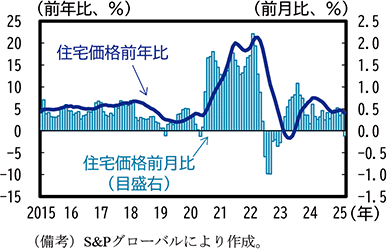
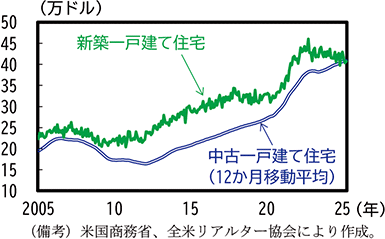
(労働需給は緩和が継続)
米国の労働市場では、労働需給の緩和が継続している。雇用統計事業所調査14における非農業部門雇用者数について、2023年以降は主に医療・介護等、政府部門の雇用増がけん引し、雇用者数は感染症拡大前の平均前月差15である20万人前後で増加を続けてきた16(第1-1-24図)。2024年末にかけては、年末ホリデーシーズンにおける消費者の旺盛な需要に応えるため、小売業や輸送・倉庫業、レジャー・接客業など、サービス部門での労働需要が堅調であったことにより、雇用の伸びは拡大した。
2025年1月以降、雇用者数の前月差は20万人を下回っており、3か月移動平均でみても雇用増のすう勢は2024年末と比べて弱まっている。これは米国経済が2024年末と比べて減速したことに加え、第二次トランプ政権における不法移民に対する厳しい態度を受けた不法移民労働者の減少が影響していると考えられる17。また、政府部門の雇用者数については、2025年2月以降、おおむね横ばいでの推移が続いている。
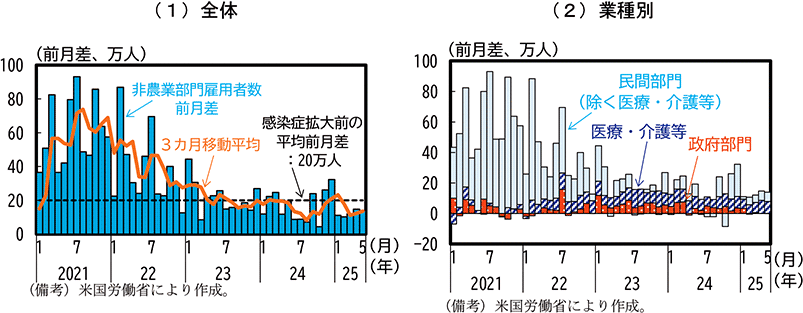
政府部門の雇用者数において、2022年半ば以降の増加をけん引しているのは州・地方政府の雇用である。特に、2024年前半までは教育部門の伸びが高く、感染症拡大期に解雇された、または、離職した教員の補充が行われてきたためと考えられる。
一方、連邦政府の雇用者数については、2023年から2024年末までは緩やかな増加が続いていたものの、2025年2月以降、前月差で減少が継続している。その結果、政府部門全体での伸びはおおむね横ばいとなっている。連邦政府の雇用者数の減少については、第二次トランプ政権において設置された「政府効率化省」(DOGE:Department of Government Efficiency)による連邦政府職員の解雇や各省庁の規模縮小が影響していると考えられる。連邦政府の雇用者数は、2025年2月から5月までの累計で▲5.9万人減少した(第1-1-25図)。
連邦政府職員の解雇は、勤続年数が主に1年未満の試用期間職員の解雇から進められ、2025年2月以降には更に大規模な人員削減の実施方針が各省庁で発表された。2月以降の政府部門の人員削減数は28万人超に及んでいる18(第1-1-26図)。
また、2025年1月24日に署名された米国国際開発庁(USAID)の外国援助のほぼ全てを凍結する大統領令によって、約1万人の職員のほとんどが解雇された。その他、内国歳入庁や教育省などでも数千人程度の人員削減が進められている。
1月28日には連邦職員の早期退職プログラムが発表され、約7.5万人(全体の約3.2%)が応募したとされている。同プログラムに応募した職員は給与が9月30日まで支払われるため、給与支払いデータを基にして調査を行う事業所調査データにはまだ影響が反映されていないものの、今後、統計上に表れてくる可能性がある。
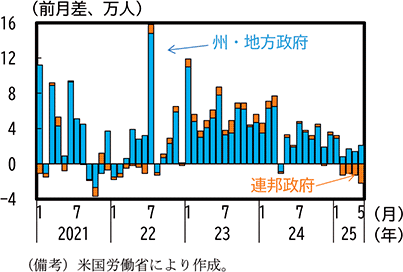
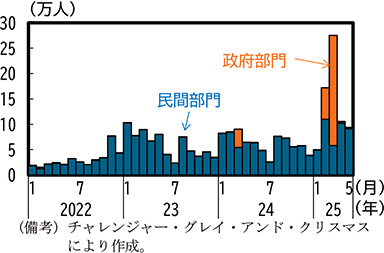
全体として、雇用者数は緩やかな純増が続いているが、雇用者の採用(増加要因)と離職(減少要因)の動向をみると、感染症拡大に伴う変動後、2022年以降、採用率と離職率ともに低下傾向にある(第1-1-27図)。さらに、企業による解雇率も依然として低水準で推移19しており、これら3つの指標は全て感染症拡大前の2020年2月の値を下回っている。よって、企業は新しい人材の採用には慎重になりつつある一方、既存人員の解雇を含めた離職数も低調であるため、労働市場の需給はおおむね均衡していると言える。
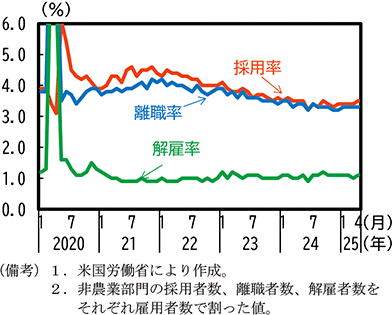
家計調査における失業率は、2022年半ばから23年半ばにかけて3.5%前後の水準で推移した後に上昇し、FOMC参加者の長期失業率見通し20である4.2%近傍でおおむね横ばいでの推移が続いている(第1-1-28図)。また、各年の1月から12月の失業率の変化を、人口要因のうち米国生まれ人口要因、人口要因のうち外国生まれ人口要因、労働参加率要因、就業者数要因に分解したものを第1-1-29図に示す21。2023年から24年にかけて、就業者数要因が一定の下押し圧力となる中、主に外国生まれ人口の増加による労働供給の増加が、失業率の上昇に寄与した。一方、2025年は、外国生まれ人口が減少に転じ、米国生まれ人口の増加と就業者数の減少が失業率の押上げ要因となっている。
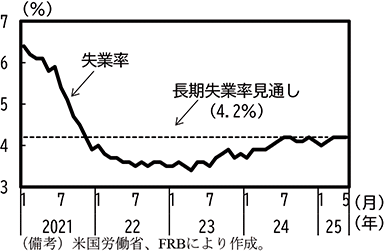
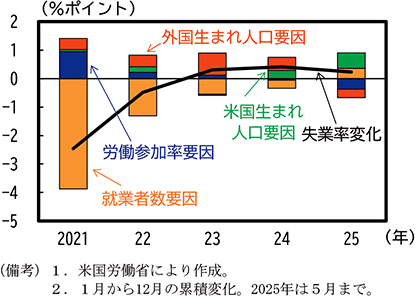
ここで、労働供給の状況について確認する。
労働参加率を見ると、2023年以降、感染症拡大後の回復傾向に頭打ちがみられ、おおむね横ばいで推移している(第1-1-30図)。属性別にみると、55歳以上の労働参加率は感染症拡大前の水準に戻らず、低調に推移している。一方で、感染症拡大後の労働参加率の回復をけん引してきた25~54歳(プライムエイジ)の労働参加率は、2024年半ばをピークに、2025年以降は頭打ちとなっている。
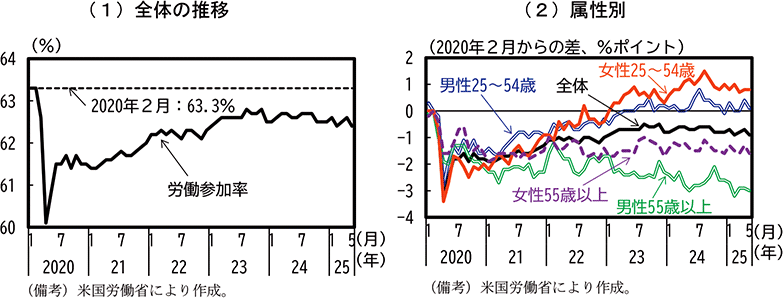
また、昨今の労働供給の変動については、移民の受入れによるところが大きく、政策動向に左右される。議会予算局の推計によると(第1-1-31図)、毎年100万人前後だった移民の純流入は、2020年以降、不法移民の流入増によって増加し、2023年には年間330万人の移民が流入した。これには、中南米諸国の情勢不安、米国の堅調な経済と労働市場による移住先としての高い魅力、バイデン政権の寛容な移民政策など複合的な要因が作用していた。バイデン政権下の4年間(2021~24年)における不法移民の純流入の合計は700万人以上と推計されている。このため、特に2023年以降の米国労働市場における需給ひっ迫の緩和には、移民を中心とする人口増加が寄与したと考えられる22。
2025年1月の就任以来、トランプ大統領は南部国境における緊急事態を宣言し、国境警備の強化や不法移民の排除及び各種移民政策を厳格化する大統領令に署名した。加えて、米国内に2022年時点で約1,100万人23いるとされる不法移民の強制送還にも着手し、移民政策はバイデン政権下と比較して厳格化された24。その結果が南西部国境における入国希望者との遭遇者数は2025年2月以降に急速に減少し、ピーク時に30.2万人だった遭遇者数は約1万人に減少した(第1-1-32図)。
一方、直近では、移民増を抑制する大統領令に対し連邦地裁による差止め措置が行われていることや、移民取締まりに対する大規模デモの発生、取締り当局25の人的制限や予算制約などが問題点として浮上している26。
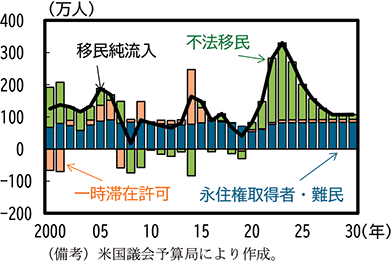
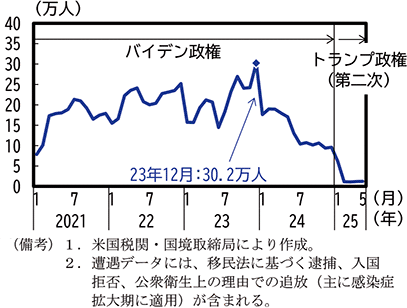
次に、労働需要については、JOLTS求人件数及びIndeed求人件数をみると、2022年初をピークに減少が続いた後、2025年にかけては、おおむね感染症拡大前の水準で推移している(第1-1-33図)。
また、失業者一人当たりの求人件数である求人倍率については、感染症拡大前の水準である1.22倍を下回る水準まで低下した後、2024年後半以降は1.0倍をやや上回る水準でおおむね横ばい推移している。さらに、労働需要と労働供給に分けて確認すると(第1-1-34図)、感染症拡大直後に急速な経済の回復に伴い、労働需要が急増したことにより労働需給がひっ迫した。その後、労働需要が緩やかに減少していくことによって、労働需給のひっ迫は解消し、足下ではおおむね労働需給は均衡していると考えられる(第1-1-35図)。
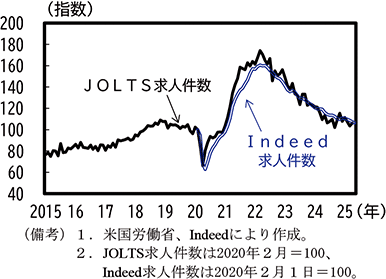
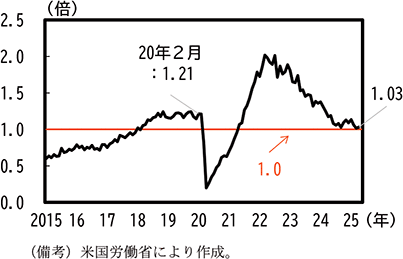
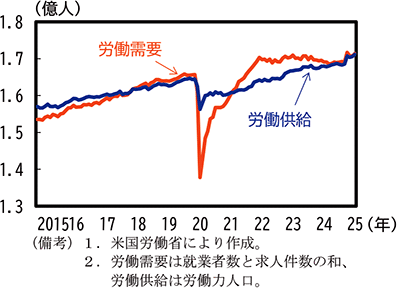
労働市場に対する消費者マインドは弱含んでおり、労働需給のバランスの悪化の懸念がみられる。労働市場における現在の状況について、「雇用は豊富にある」と答えた人から「職探しは困難」と答えた人を引いた割合は、感染症拡大後の回復以降、徐々に低下してきており、2025年6月には11.1%ポイントと、2021年3月以来の低水準にまで低下した。一方、先行きについては、「今後12か月間で職を失う確率」は2023年にかけて悪化し、その後2024年にかけては一時低下したものの、2025年に入ってから再び上昇へ転じている。また、「今日仕事を失った場合、今後3カ月以内に仕事が見つかる確率」についても、2025年以降は、50%程度の低い水準で推移している。
先行指標となるソフトデータの動きから、今後数か月で雇用者数や失業率などの悪化がみられ始める可能性がある。

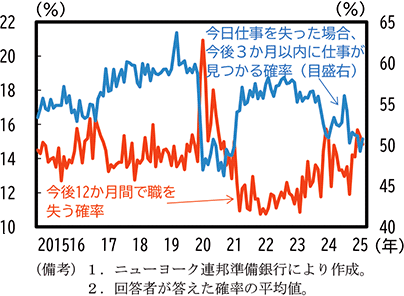
(賃金上昇率は4%近傍で安定的に推移)
感染症拡大後の労働需給のひっ迫が解消する中、賃金動向について確認すると、前年比でみた時間当たり賃金の伸びは、2024年半ばにかけて鈍化した後、年末にかけては4%を超える水準に一時上昇し、2025年に入ってからは3.9%と、おおむね安定的に推移している(第1-1-38図)。アトランタ連銀が公表するWage Growth Tracker(WGT)及び米国労働省が公表する雇用コスト指数も、2022年末のピーク以降、伸びが減速し、2025年に入ってからはおおむね横ばいで推移している(第1-1-39図)。
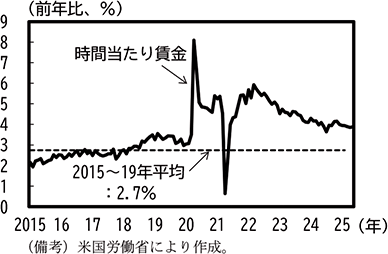
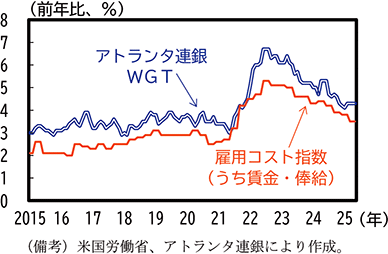
(消費者物価上昇率は2%半ばで安定して推移)
消費者物価指数(CPI)(総合)をみると(第1-1-40図)、前年比は2022年6月(9.1%)をピークに低下したのち、23年7月以降、3%前後でおおむね横ばいで推移してきた。2025年3月以降、CPI全体の約35%のウェイトを占める住居費が前年比寄与度1.4%ポイント程度で安定して推移する中、CPI全体が2%半ばで安定して推移している。
なお、中国からの輸入割合が高い一部の耐久財(音響機器、コンピュータソフトウェア及び周辺機器、家具)は、第二次トランプ政権の関税措置による影響もあり、2025年4月以降、他の財と比較して上昇幅が大きい(第1-1-41図)。第2章で詳述するが、関税率引上げが行われたのち、川上の産業が生産する財から川下の産業が生産する財に価格転嫁が行われるには、一定の時間がかかることから、今後の通商政策の帰すうによっては消費者物価が上昇する可能性がある。
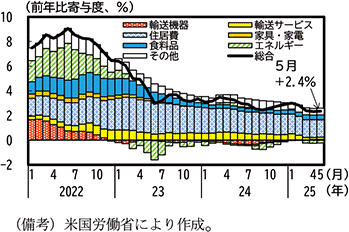
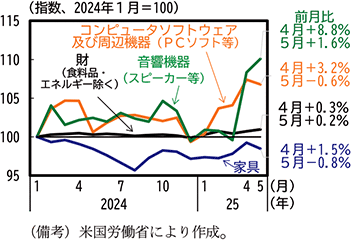
(政策金利は据置き)
これまでみてきたとおり、物価上昇率が2%台で推移し、労働市場の需給が緩やかに緩和される中、政策金利は据え置かれた。
FRBは、2023年9月以降、FF金利の誘導目標範囲を5.25~5.50%に据え置いていたが、2024年9月の利下げ以降、同年末にかけての3会合(2024年9月、11月、12月)で累計1%ポイントの利下げを行った。2025年1月のトランプ大統領の就任以降は、4会合連続でFF金利の誘導目標の据置きが続いている(第1-1-42図、第1-1-44表)。
2025年6月会合にて公表された四半期経済見通し(Summary of Economic Projection)によれば、2025年末までに0.5%ポイントの利下げ(1回の利下げ幅を0.25%ポイントとすれば、2回分の利下げに相当)、2025~26年末までに更に0.25%ポイントの利下げ(1回分の利下げに相当)が行われる可能性が高いことが示されている。なお、金融市場が見込むFF金利の推移は、2025年4月に下方修正され、2025年末までに1.0%ポイント近くの利下げが織り込まれていたが、6月時点では0.5%ポイント程度となっている(第1-1-43図)。
同見通しにおける、FOMC参加者による長期のFF金利(いわゆる中立金利と解釈されることが多い)の想定を確認すると、2024年以降、中央値が上昇すると同時にその見通しの幅も合わせて上昇しており(第1-1-44表)、長期的な政策金利、いわゆる中立金利の水準をめぐる不確実性は大きい。