第2章 持続的な経済成長と労働市場(第2節)
第2節 労働生産性及び賃金の動向
世界の先進国では、労働生産性の向上が中長期の成長政策の上で重要な課題として認識されている。労働生産性とは労働投入一単位当たりで生み出される付加価値をいう。労働者がどれだけ効率的に成果を生み出したかを定量的に数値化したものであり、労働者の能力向上や効率改善に向けた努力、経営効率の改善等によって向上すると考えられている。
労働生産性の伸びを高めることは政策的に重要な意味を持つ。一国全体の経済を考えた場合、豊かさの指標として、しばしば利用される一人当たりGDPをとりあげてみよう。一人当たりGDPは、労働生産性と「労働投入量(労働者一人当たり労働時間×労働者数)÷人口」の積として表すことができる。先進国において、一人当たり労働時間や、労働者の人口に対する比率を高めるには限界がある。したがって、国民生活の所得(労働の対価としての賃金所得を含む。)の改善は労働生産性の伸びに依存していることが分かる。
翻って、日本では90年代以降、労働生産性の伸び悩みがしばしば指摘される。例えば、OECD対日審査報告(21年12月)では「主要な事実」として「(日本の)生産性の向上は総じて精彩を欠く」との指摘がある。
他方、GDPのうち労働者に報酬として分配される所得の割合を「労働分配率」という。労働分配率は通常、時系列で安定しているため、GDPが伸びればそれと同程度、雇用者報酬も伸びることが想定される。したがって、労働生産性が伸びれば、労働の対価として支払われる賃金も同程度伸びることが期待される。しかしながら、近年先進国では、労働生産性の伸びと賃金の伸びのかい離も指摘されており、その背景について10年代後半には様々な議論が行われてきた199。
世界経済は現在、コロナ禍からの回復が続く中で、先進各国の労働市場も失業率の持続的な低下や、需給のひっ迫を背景とした賃金上昇がみられている。こうした中、今後の労働生産性や賃金の動向に改めて注目が集まっていると考えられる。本節では、こうした問題意識の下、労働生産性、賃金の動向や、両者の関係を先進国間の国際比較を通じて客観的に概観する。
1.先進国の労働生産性の動向
労働生産性や賃金の動向について分析に入る前に、2000年以降の主要な先進国の人口一人当たり潜在成長率の動向をみてみよう(第2-2-1図)。潜在成長率は、潜在生産量の伸び率であり、例えば、IMFによれば「インフレ率の上昇を伴わずに保持できる最大の生産量」と定義200されている。先進国のうち、スウェーデンはユーロ圏の平均と比べて、アメリカ、カナダはG7の平均と比べて過去20年間にわたって潜在成長率が高い。他方、イタリアはユーロ圏の平均と比べて、日本はG7の平均と比べて潜在成長率が過去20年間にわたって低い。一人当たり潜在成長率の伸びと労働生産性の伸びには安定的な関係がある。
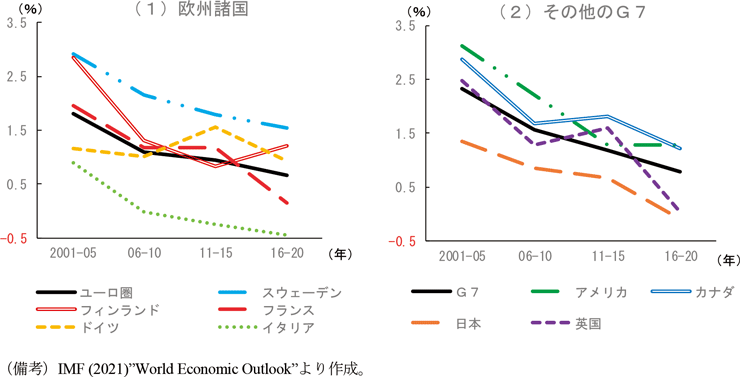
主要な先進国の労働生産性の動向をみてみよう(第2-2-2図)。労働生産性の具体的指標として、労働投入一単位当たりで生み出される付加価値(実質GDPを国全体の総労働時間で割ったもの)の伸びをみると、2000年以降、欧州では東欧(ハンガリー、ポーランド)やスウェーデンがOECD平均と比較して労働生産性の伸びが高い一方、スペインなどではOECD平均と比較して労働生産性の伸びが低く、イタリアでは労働生産性が低迷している。他方、その他のG7ではアメリカがOECD平均と比較して労働生産性の伸びが高い。
既存研究での指摘をみると、例えば、近年のイタリアでの生産性低迷の背景としては、非競争的な市場環境での構造転換の遅れ(サービス部門など労働集約型産業が中心)、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)への参画の遅れ、研究開発投資の遅れとフロンティア企業の欠如、人的資本投資の遅れ、家族主義経営等が指摘されている201。スペインの生産性の伸びが低い要因としては、低生産性部門からの構造転換の遅れ、規制改革の遅れによる競争の欠如や労働市場の硬直性等が指摘されている202。ポルトガルは資本装備率の上昇が労働生産性上昇につながらず、また、R&DやICT投資の遅れによる生産性の伸び悩みが指摘されている。同国では、開業率が高い一方、廃業率も高水準にあり、スタートアップ企業が育っていないとされている203。
以上から、先進国の生産性の動向に影響を及ぼす共通の課題として、非貿易部門への投資の遅れ、GVCへの参画の遅れ、研究開発投資や人的投資の遅れ、ビジネスダイナミズム(開廃業率)の問題等が挙げられる。
これに対しスウェーデンでは、グローバル企業(エリクソン、ボルボ、IKEAなど)が経済をけん引するのみならず、ICT分野等での多数のユニコーン企業(Skype、spotifyなど)を輩出し、ICT分野のサービス輸出にも支えられ204、90年代、2000年代を通じて高い生産性の伸びを実現してきた。
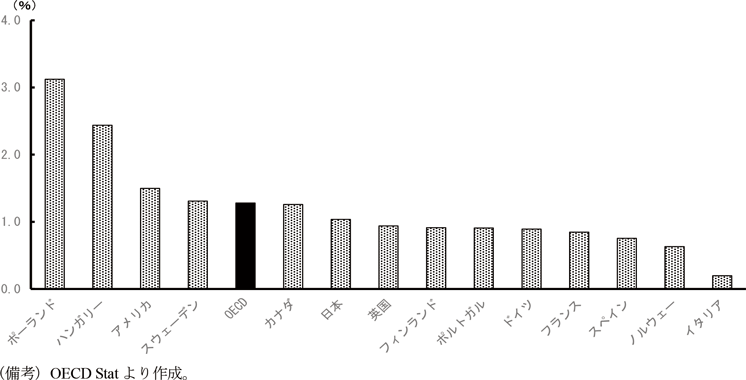
2.先進国の賃金の動向
同様に、賃金の動向についてみてみよう(第2-2-3図)。以下では特に断りがない限り賃金は物価上昇分を調整した実質値を指す。労働者の単位時間当たり賃金の伸びは、2000年以降、東欧(ハンガリー、ポーランド)、北欧(ノルウェー、スウェーデン)等でOECD平均よりも高い。これに対し、ポルトガル、スペイン、イタリア、日本では賃金の伸びが低迷し、OECD平均よりも低水準で推移している。
賃金の伸びが高い北欧諸国に注目してみると、流動的な労働市場で、賃金面でのステップアップにつながる転職機会が多いことから、結果的に高い賃金上昇率が実現している可能性が示唆される。2章1節で述べたようにスウェーデンやフィンランドでは転職率が高く、欧州諸国の中では労働市場が流動的と考えられる。また、ノルウェーやスウェーデンでは、職種構成比率を時点間で比較すると、より技能レベルが高く高賃金の職種のウェイトが高まっていることがうかがえることから、労働者が職種転換を伴う転職などを通じて高賃金の仕事に移っていくケースが相対的に多い可能性がある。さらに、北欧諸国では、技術の変化などに伴って変化する労働者の技能ニーズを予測することなどを通じて、社会人に対して様々な職業訓練や教育の機会を提供しており、こうした積極的な労働市場政策が労働者の技能アップにつながった結果、賃金が伸びている可能性も考えられる(2章1節参照)。
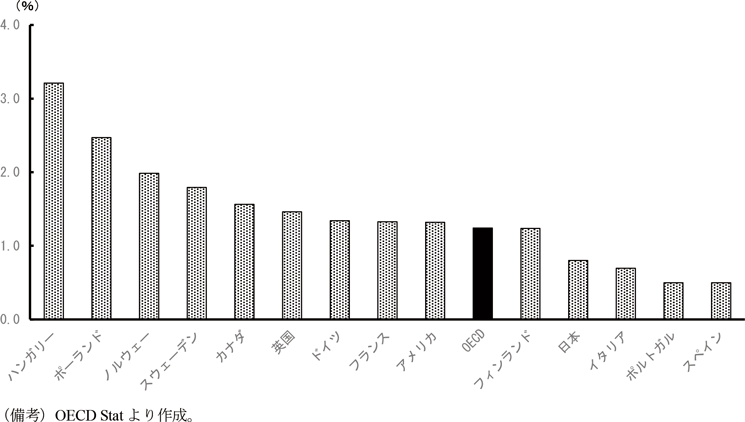
3.労働生産性の伸びと賃金の伸びの関係
次に、労働生産性の伸びと賃金の伸びの関係性についてみていこう(第2-2-4図)。OECD平均でみると、労働の成果は長期的にみれば賃金として分配されており、労働生産性の高まりに見合うように、賃金も増加傾向となっている。ただし、より詳細にみると国別に違いがある。例えば、日米韓、ポルトガルでは労働生産性の伸びを賃金の伸びが下回っている。他方、英国、フランス、イタリアでは、労働生産性の伸びを賃金の伸びが上回っている。
第2-2-4図で紹介した労働生産性と賃金について、G7や北欧、西欧の先進国の01~20年の伸び率の平均をとりプロットしたものが第2-2-5図の散布図である。労働生産性の伸びと賃金の伸びが大きい順に各国をグループA、グループB、グループCに分けて丸印をつけている。OECD平均や日本は、労働生産性の伸びと賃金の伸びがグループAとグループCの間に位置している。つまり、日本の労働生産性の伸びと賃金の伸びは、アメリカ、スウェーデン等には及ばないものの、イタリア、スペイン、ポルトガルよりは高い。アメリカ、スウェーデン等の労働生産性の伸びと賃金の伸びは、OECD平均よりも高い一方、イタリア、スペイン、ポルトガルの労働生産性の伸びと賃金の伸びは、先進国内で比較しても相対的に低い。
また、第2-2-5図には45度線が引いてある。縦軸が賃金の伸び率、横軸が労働生産性の伸び率となっているため、45度線の上方にあるプロットの国では賃金の伸びが労働生産性の伸びを上回っていることを意味する。一方、45度線の下方にあるプロットの国では賃金の伸びが労働生産性の伸びを下回っていることになる。グループAやグループCには労働生産性の伸びよりも賃金の伸びが高い国も低い国もあるが、グループBの国々では専ら労働生産性の伸びを賃金の伸びが上回っている。一般に、労働生産性の伸びよりも高い賃金の伸びを実現し続けると、利潤が減少して企業経営が立ち行かなくなる。したがって、中長期的にはこうした国々の特徴は持続不可能である。労働政策はただ単純に賃金の伸びを目指せばよいというものではなく、あくまで労働生産性の伸びに見合った賃金の伸びを実現させることがよいと考えられる。こうした観点からすると、OECD平均や日本は労働生産性の伸びに比して賃金がバランスよく伸びている。
労働生産性の伸びと賃金の伸びのかい離の背景の一つには、賃金決定に係る制度的要因があると考えられる。賃金設定ルールに関する国別の特徴のうち、団体交渉の協調(団体交渉における主要な参加者による、賃金水準(または賃金上昇)及び賃金以外の労働条件に係る決定に、それ以外の参加者が計画的に倣う行動)がない場合、労働生産性の伸びと賃金の伸びの関係が強くなることが予想される(2章2節4項参照)。第2-2-6表には先進国の91~20年の労働生産性の伸びと賃金の伸びの相関係数、団体交渉の協調度を記載している。第2-2-6表において、労働生産性の伸びと賃金の伸びが正相関となった国々では協調がない傾向がみられ、予想と整合的な結果が得られた。
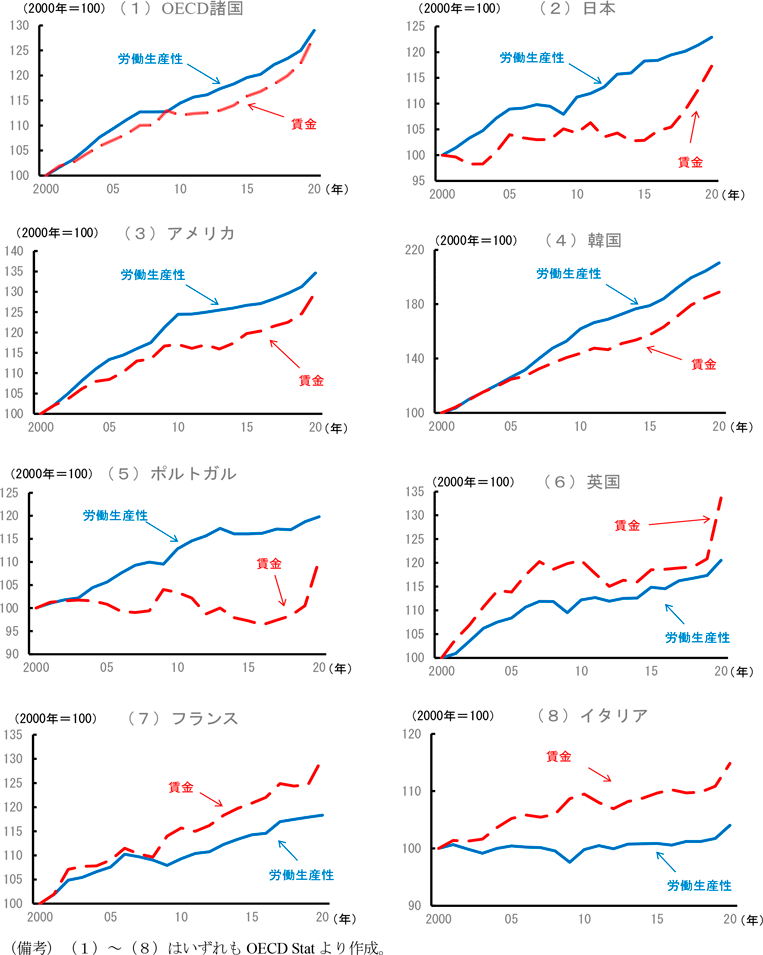
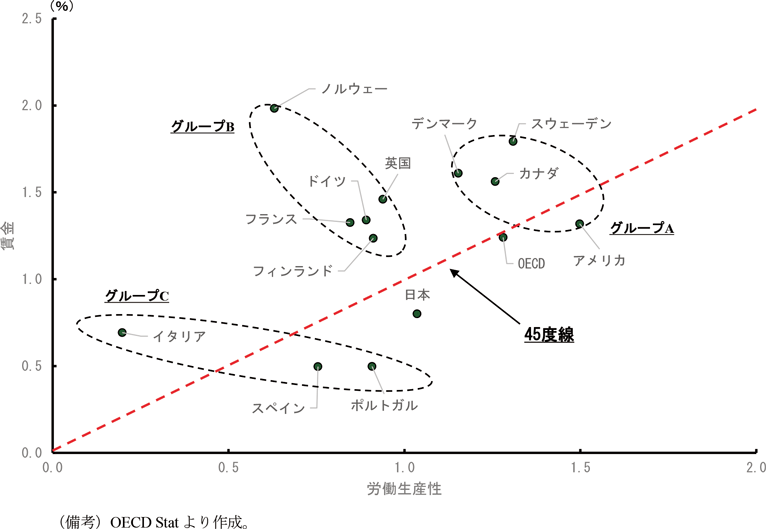
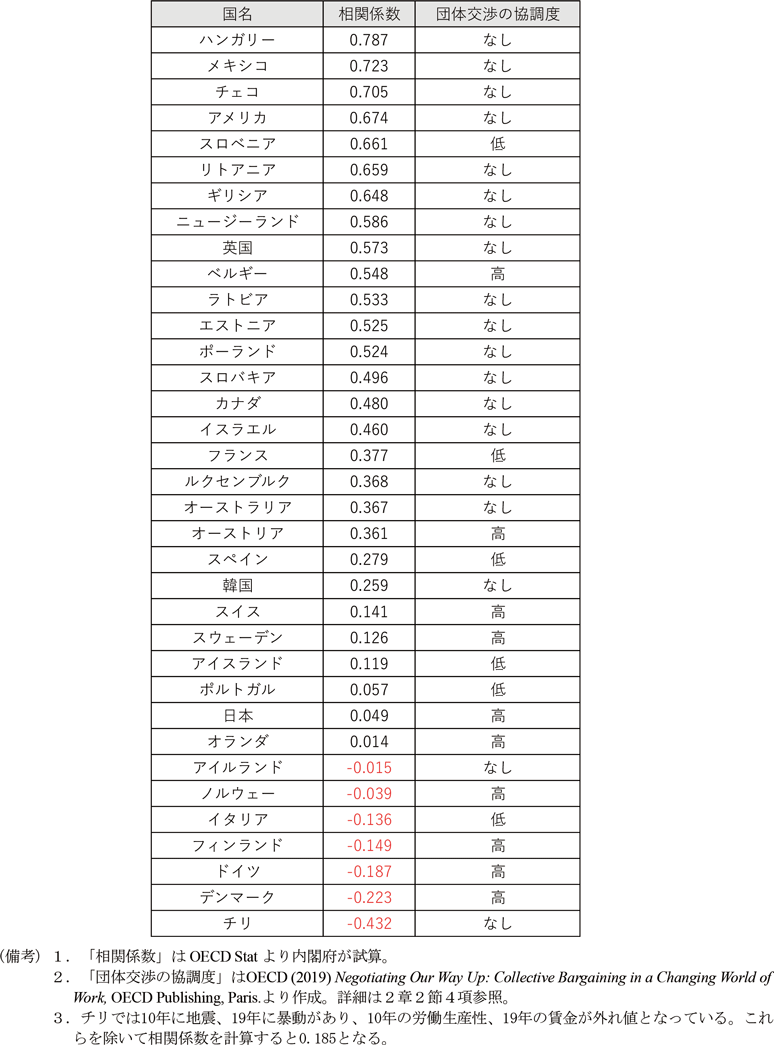
Box.労使交渉と買い手独占
本文でみたように、OECD平均でみると、2000年以降は、賃金の伸びが労働生産性の伸びを下回って推移していた。こうした状況を踏まえ、賃金の引上げによって労働者の賃金水準を向上させ生活を改善させることが必要との指摘205もみられる。また、最低賃金の引上げによって非効率な企業の退出が促され、生産性向上につながるとの指摘206もある。一方、中小企業を中心に賃金の引上げは経営を圧迫し、ひいては廃業や雇用の喪失につながるため慎重に検討されるべき、との声も存在する。
労働市場の需給という観点からは、買い手側(企業)の交渉力が売り手側(労働者)の交渉力を上回る場合には、賃金の伸びが労働生産性の伸びを下回る状態が一般的になり得る。これに対して、国により有無や程度の違いはあるが、団体交渉を通じて、労働組合と使用者の間で賃金決定を始めとする労働協約を結ぶことが行われている。
経済学では、賃金を始めとする労働協約について二つの見方207がある。第一の見方は、個人のレベルを超えて同一の賃金等の労働条件を設定するため、市場の歪みを生み出して望ましくないというものである。第二の見方は、労働市場が現実には不完全競争にあることを前提とすれば、企業の市場支配力の緩和、労使交渉の定型化による取引コストの減少、企業の競争条件の平等化等を促す観点から、労働協約は効率性を高めるというものである。
ここでは、労働協約を通じた賃金水準の引上げについて、第二の効率性を高めるという見方についてもう少し詳しくみてみよう。労働市場で企業側の交渉力が強い場合、賃金引上げによって、雇用は減少するだろうか。これについては、賃金が上昇しても雇用は減りにくいと考えられる。なぜなら、この前提においては、生産性の伸びを賃金の伸びが下回り、ギャップがあるため、賃金を引き上げても利潤を減らすことでそれを吸収できるからである。仮に、労働市場が完全競争の場合、人材の引き抜きのようなことが頻繁に起こる。この下では、生産性が大きく伸びた場合、企業側は賃金を大きく伸ばして労働者の離職を防ごうとするため、完全競争下では生産性の伸びと賃金の伸びにかい離は発生しない。逆に、雇用主が賃金の伸びを生産性の伸びよりも抑えながら必要な労働力を確保できるのは、不完全競争の場合、特に、買い手独占(モノプソニー)が生じており、雇用主が賃金を決定する十分な力を持っている時と考えられる。こうした考え方に立つと、労働協約は、労働者の市場での交渉力を強化することを通して、企業の強い市場支配という市場の失敗を緩和する側面があることが分かる。
こうした労働市場における交渉力の問題以外にも、多くの先進国で生産性の伸びと賃金の伸びにかい離が生じてきた背景については、国際機関等において様々な議論が行われてきた。例えば、労働力を代替するような技術進歩と二極化の進展や、労働分配率が低い、生産性フロンティアに位置する企業(GAFAが典型例)の市場シェアの拡大等が指摘208されている。
一方、協定の下で、賃金上昇率がむしろ生産性を上回り、高止まりするケースもみられる。例えば、イタリアの賃金の伸びが高い理由としては、国レベルの協定賃金契約でカバーされる賃金の比率が9割を超え、生産性と賃金のかい離が顕著であること、フランスについても協定賃金契約のカバー率が高いことや、相対的に高い最低賃金による制約があるため、特に景気後退期に賃金の伸びと生産性伸びのかい離が生じやすいことが指摘209されている。
4.主要国の賃金設定ルールの特徴
労働生産性の伸びと賃金の伸びの関係が薄くなっているとすれば、労働市場での賃金決定メカニズム、具体的には団体交渉の役割が一つの構造的要因となっている可能性がある。この点について、先進国では、労働組合への加入率や団体交渉のカバレッジには顕著な低下がみられるものの、団体交渉の仕組みは、引き続き多くの国々で賃金の決定等で重要な役割を果たしていることが指摘されている(OECD(2021))。
団体交渉の結果、労働組合と使用者の間で結ばれる労働協約では、主に賃金及びその他の労働条件、例えば労働時間や訓練、解雇、安全衛生等を決定する。団体交渉がどのように労働市場のパフォーマンスに影響するかは、交渉での戦略や制度的な仕組み、製品や労働市場の構造に依存すると考えられる。
団体交渉の制度の鍵となる特徴として、OECD(2021)は(1)団体交渉のカバレッジ、(2)交渉が行われるレベル(国レベルか企業レベルかなど)、(3)柔軟度、(4)協調(後述)の四点を挙げている。
賃金が企業ごとまたは業種ごとに一律に決定される傾向が強くなると、個人にとっては労働生産性とは関係なく賃金が決定されることになり、マクロ経済でみた場合にも労働生産性の伸びと賃金の伸びの関係に影響を及ぼす可能性がある。こうした観点から、ここでは上記四点のうち、「(4)協調」の仕組みに注目して議論したい。「協調度」とは、交渉における主要な参加者の決定に、それ以外の参加者が計画的に倣う度合いを意味する。こうした協調行動は、異なるレベルでの交渉主体間210でも、同一レベルの交渉主体間211でも起こり得る。
こうした協調の方法の違いに応じて、実質賃金や労働時間がマクロ経済ショックに対して調整される際の柔軟度が異なることが多くの既存研究で指摘されている(OECD(2021))。
協調の方法は(1)パターン交渉212、(2)国が設定、(3)組織横断的なガイドラインの設定、に分けられる。OECD(2019)では、この分類に沿って各国を当てはめ、協調度合いの高低を比較している(第2-2-7表)。パターン交渉は、北欧諸国や日本でみられ、協調度合いは高いと評価されている。国が設定するケースは、ベルギーなど、数は限られている。ベルギーでは、賃金は生計費の上昇とインデクセーションされているが、周辺国の賃金上昇や最低賃金によって上限・下限が設定されている。組織横断的なガイドラインでは、主要な組織体が何らかの規範やゴールを設定し、それを参照してより下位レベルの交渉が行われる。北欧諸国や我が国では、パターン交渉に加えてこうした方法も用いられている。
ここで紹介した協調度が実際のデータとどのように関係しているかをみていこう。第2-2-6表の「団体交渉の協調度」の列には第2-2-7表において「協調度合い高」の国に「高」、「協調度合い限定的」の国に「低」、その他の国に「なし」と記載してある。そのうえで改めて第2-2-6表を見ると、交渉団体に協調がない国において、労働生産性の伸びと賃金の伸びが正相関となる傾向がみられる。協調がある国では労働生産性の伸びと賃金の伸びは正相関、無相関、負相関と国ごとに関係にばらつきがあり、協調行動がマクロ経済でみた労働生産性の伸びと賃金の伸びの関係に影響を及ぼしていることがうかがえる。OECD(2019)では、協調度が高い国では、周囲と賃金上昇の足並みを合わせないといけないため、企業や業種レベルでみて、労働生産性の伸びと賃金の伸びにずれが生じやすくなる可能性が指摘されている。
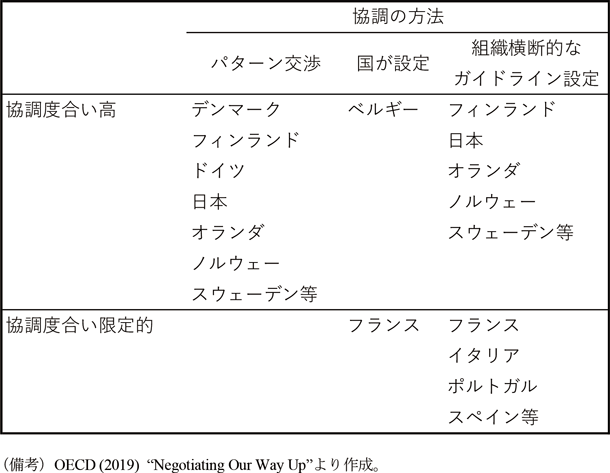
5.労働生産性に係る賃金弾性値
業種別のデータを用いて労働生産性に係る賃金弾性値(労働生産性(名目)が1%上昇している時に賃金(名目)が何%上昇しているかを示すもの)を推計する。この分析では、「業種間の協調がない場合には弾性値が正値で有意となる」という仮説を検証する。
なお、生産性と賃金の関係は、一方向の因果というよりも、むしろ、両方向に影響し合うものと考えられる。賃金設定が団体交渉ではなく、労働者個人レベルで行われる場合、成果主義に基づいた賃金設定等でインセンティブを高めることで、生産性の上昇が促されると考えられる。これに対し、生産性上昇率が高ければ、賃金を引き上げる余地が大きくなり、労働者側の交渉力が強い場合には賃金上昇につながる可能性が考えられる。他方、賃金が団体交渉で決まる場合、団体交渉により賃金が高水準で決められると、人件費負担の増加に伴い生産性の低い企業が退出を余儀なくされ、平均的に見て生産性の上昇につながることが指摘されている。また、賃金が高く設定されれば労働者のモチベーションが上がり生産性上昇にもつながり得るのに対し、抑制されればモチベーションを低下させ、生産性の伸びを低下させる可能性がある。
OECD Stat STAN databaseの25か国×82業種×時系列(70~19年)のパネルデータを用いて労働生産性に係る賃金弾性値を推計した(第2-2-8表)。70年代と2000年代以降では各国の経済構造に変化が生じている可能性があるため、70~19年、2000~19年の期間別に推計を行った。推計に際し、各国固有の要因、景気変動要因及び各国での政策の変更等の影響を除くため、国と年次を識別するダミー変数の交差項を説明変数に加えた。結果として、先進国の弾性値は水準、有意性ともにおおむね頑健であることが確認された。
第2-2-8表の推計結果をみると、東欧、韓国、ルクセンブルク、ドイツ、英国では労働生産性に係る賃金弾性値が正値に有意で0.2以上となった。これは、これらの国々では労働生産性が1%上昇した時に賃金が平均的に0.2%ポイント以上、上昇する傾向があることを示している。「団体交渉の協調度」の列を見ると、ドイツを除いてこれらの国々では協調がない。これは、団体交渉の協調がない国では、ある業種が同国内の他の業種と賃金上昇の足並みを揃えずに自業種の労働生産性の伸びに応じて賃金の上昇率を設定するため、業種間の労働生産性の伸びと賃金の伸びの相関が強くなると解釈できる。また、これは国別データの分析(第2-2-6表)で判明した、協調のない国で労働生産性の伸び率と賃金の伸び率が正相関になる傾向と整合的である。
また、ドイツについては鉱業・採石業、印刷業・記録媒体複製業、公務・防衛において労働生産性に係る賃金弾性値が0.9以上で有意となっていた。ドイツではこうした一部の労働集約型産業において労働生産性に係る賃金弾性値が際立って高く、一国の平均値を押し上げている可能性がある。
既述のように団体交渉は企業に対して相対的に交渉力が弱くなりがちな労働者の交渉力を高め、賃金分布や仕事の質などの面でプラスの影響をもたらすことも指摘されている。デジタル化などの新たな技術の登場等を通じ、近年、労働市場では自営業者比率の高まりや仕事がなくなるリスクの高まりなど、大きな変化の波が押し寄せているが、こうした変化は団体交渉ではカバーしきれない労働者の増加をもたらすものと考えられる。団体交渉でカバーされない労働者は、市場で労働条件に関する直接交渉を行うことが必要となるが、交渉力の差から不利な労働条件を受け入れることになる可能性もある。団体交渉は、適切に設計されれば、こうした課題への対応策となり得る制度であり、今後もその役割に注目していくことが重要と考えられる。
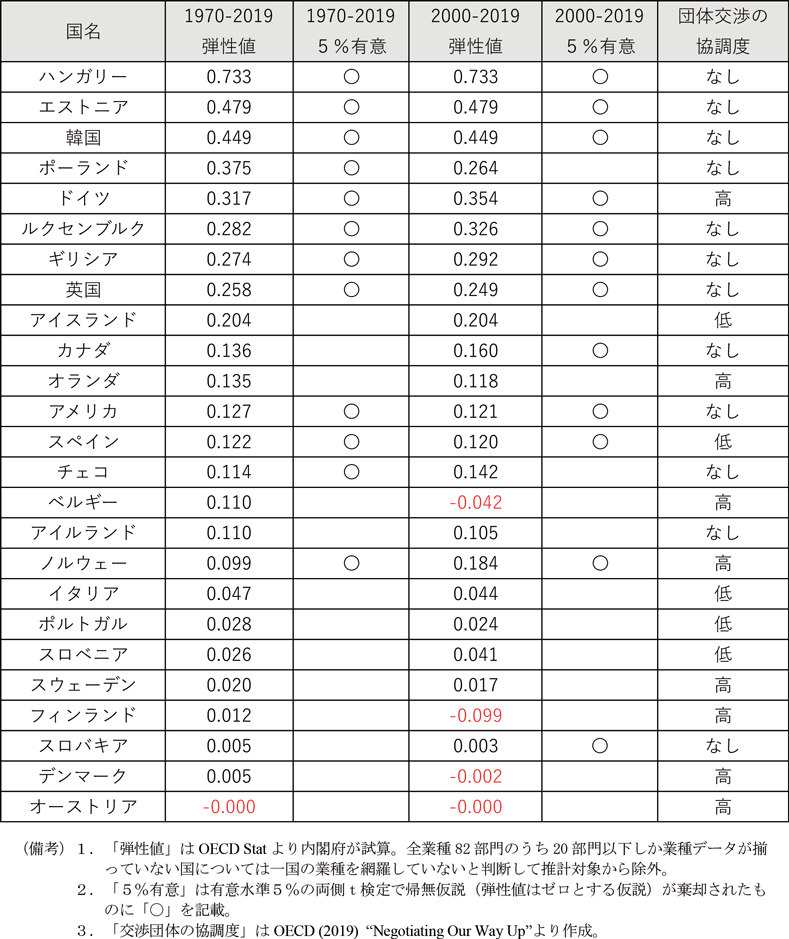
6.団体交渉が労働市場の流動性や労働者の技能を高める仕組み
先進国では、団体交渉の枠組みに基づき、技術革新等により仕事がなくなった労働者に対し、速やかに良い仕事に戻れるような手助けをソーシャルパートナーが提供する事例がみられる。スウェーデンでは、非営利団体であるJob Security Councils (JSCs)が職を失った労働者への支援を行うとともに、一斉解雇時に訓練やリスキリングの機会へのアクセスを提供し(OECD(2021))、公的職業安定機関によるサービスの補完や上乗せを行っている213。団体交渉下にいる労働者は全員、JSCsにもカバーされている。さらに、これらのソーシャルパートナーは、時には技能ニーズの予測に基づいた労働者の技能向上にも取り組んでいる。
こうしたことから、団体交渉のカバレッジは低下傾向にあるものの、不足する技能の予測や技能ニーズへの対応という面でのソーシャルパートナーの役割の重要性が高まっていると考えられる(OECD(2021))。欧州では、一部の労働組合は、生涯学習に関する条項を団体協約に盛り込んでいる一方、主に費用負担の観点から雇主の反対に直面する組合も存在している。また、欧州の多くの国々で労働者の生涯学習が法制化されている214が、そのうち例えばドイツでは、政府の生涯学習政策は団体交渉による労働協約に基づき設計されており、16州のうち14州で、労働者は年間5日間、訓練受講日を取得する権利が与えられている(Simons, et al. (2020))。
7.小括
2章2節では、以下のような視点で先進国の労働生産性の伸び及び賃金の伸びの状況や両者の関係について議論を行った。
(1)先進国の労働生産性、賃金の動向
2000年以降の先進国の労働生産性の平均伸び率をみると、東欧を除けば、アメリカ、スウェーデンでOECD平均よりも高く、南欧ではOECD平均よりも低い伸びがみられた。背景として、スウェーデンではグローバル企業やICT分野のユニコーン企業等、成長分野やフロンティア企業による労働生産性の伸びのけん引がみられた。これに対し、イタリア、スペインでは非競争的な国内市場においてビジネスダイナミズムが緩慢となり、低生産性の非貿易部門における構造転換や企業のグローバル市場への参加が遅れ、R&DやICT分野への投資が滞っていることなどが指摘されていた。
他方、2000年以降の先進国の賃金の平均伸び率をみると、東欧を除けば、北欧や米英などでOECD平均よりも高く、南欧や日本ではOECD平均よりも低い伸びがみられた。背景として、北欧や米英では労働市場が流動的であり、これらの国々では転職時に賃金増を伴うことが多い可能性等が考えられる。
(2)先進国の労働生産性と賃金の関係、及び賃金設定ルールが両者の関係に与える影響
通常、労働生産性の伸びに見合うように賃金も伸びることが予想されるが、過去20年の動きをみると、先進国のうち日米韓等では賃金の伸びが労働生産性の伸びを下回る期間が長かったのに対し、英仏伊等では逆に賃金の伸びが労働生産性を上回って推移することが多かった。また、OECD平均と比較すると、スウェーデンやアメリカでは労働生産性の伸び、賃金の伸びがともに高い一方、南欧では両者ともに低い。
多くの先進国で、賃金の決定には団体交渉の仕組みが重要な役割を果たしているが、こうした団体交渉の役割が強い国では、賃金の伸びが自らの労働生産性の伸び以外の要因で決まる場合が多く、両者の伸びの関係は薄いことが予想される。先進国のデータを用いて関係をみると、以下のとおり予想と整合的な結果が得られ、労働生産性の伸びと賃金の伸びの関係には、団体交渉の特徴等、制度的な要因が影響している可能性が示唆された。
(1)団体交渉時に協調がない国ほど、労働生産性の伸びと賃金の伸びの間の正の相関が明らかであった。
(2)こうした国々では、労働生産性に係る賃金弾性値が0.2~0.7程度であり、特に東欧の一部の国々で弾性値が大きかった。
(3)対照的に、北欧諸国では弾性値が有意にならず、団体交渉の協調度合いも高い。
Visco, I. (2020) “Economic growth and productivity: Italy and the role of knowledge,” EuroScience Open Forum 2020, 4 September 2020.
Luca, D.L. and Luca, M. (2018) “Working Paper Survival of the Fittest: The Impact of the Minimum Wage on Firm Exit”, Harvard Business School Working Paper 17-088.

