第2章 持続的な経済成長と労働市場(第1節)
第1節 デジタル化など新たな技術と労働市場
労働市場において、技能165の観点で、仕事と労働者の組み合わせが最適ではない状態にあるとき、国や地域レベルで技能のミスマッチが存在していると言われる。また、労働者が就いている仕事で要求されている技能と、労働者が持っている技能が合っていないとき、個人(または個々の仕事)レベルで技能のミスマッチがあると言われる。こうしたミスマッチが生じていると、経済全体や個人の潜在的な生産性が発揮されない可能性が指摘されている166。さらに、技能のミスマッチは労働者の転出入につながりやすく、企業にとっては採用や訓練コストの増加になるとの指摘もある167。
技能のミスマッチが生じる要因としては、景気・構造の両面が考えられる。景気要因としては、不況期に生じやすくなることが指摘されている。これは、求職に対して求人が相対的に少なくなるなかで、求職者側が要件に合わない仕事でもやむを得ず就業することなどによる。また、構造要因としては、人口動態、技術革新、グローバル化などの構造変化を受け、部門間の雇用変動に伴って生じる。こうした技能のミスマッチは、生産性や失業率、格差などにマイナスの影響をもたらすとの認識から、近年では研究成果が蓄積されてきている。
本節では、まず、構造的要因のうち技術革新要因、特に過去数十年の間に急速な進展を遂げ、労働市場(雇用や必要とされる技能など)への影響が注目されてきたデジタル化の影響に注目し、技能のミスマッチの状況を整理した上で、雇用や格差への含意と人的投資の重要性について議論する。その際、先進国の中でも技能のミスマッチが相対的に小さく、前節でみたように相対的に高い生産性や賃金の伸びを達成している北欧の動向を紹介する。
これに続いて、技能のミスマッチと生産性との関係を概観し、技能のミスマッチを解消するための政策の方向性について議論する。
1.技能のミスマッチと人的投資の重要性
(1)技能のミスマッチの計測
技能のミスマッチの定量的な把握は、労働者の観点から、自身が保持すると認識する技能・資格と、自身が求められていると認識する技能・資格との比較による計測が一般的である。具体的には、雇用者に対し、「現在の仕事よりも要求水準が高い仕事をするのに十分な技能を持っているか、またはトレーニングを受ける必要があるか」尋ねる方法(自己申告型ミスマッチ)か、各人が持っている認知能力と就いている仕事での同能力の平均値または中央値との比較で評価する方法(実現ベースでのミスマッチ)のいずれかで測ることが多いとされている168。前者の方法は、主観的な回答のバイアスは懸念されるものの、サーベイ調査等で比較的容易に用いることができるとされている。
ここでは、EU機関により2014年に実施されたEU諸国に対する調査169を用いてミスマッチの状況を把握する。本調査は、国別・属性別の自己申告型ミスマッチの度合いを、仕事を行う上での能力・技能が十分かという観点から評価を与えている。具体的には、以下では、この結果を用いて分析を行う。
(i)国別に見た技能不足度合いの特徴
EU機関である欧州職業訓練開発センター(CEDEFOP)は、「技能」を教育課程や働いている間に身に着けた知識、能力、技量及び経験の全てと定義した上で、回答者が自らの仕事をする上で必要とされる技能のレベルと比較して、自分の能力がどの程度の水準であるか、0から100までの値で回答を求めている(0は必要とされる技能を全く持っていない、100は全て持っている)。各労働者の技能不足の度合いを、100と技能レベルの差分(%)として定義し、この値が小さければ労働者の技能は完全に生産的に活用されている一方、大きければ継続的なトレーニングや技能向上策を通じて、潜在的な生産性を高める余地が大きいことを指摘170している。EU全体の技能不足の平均値は18%であり、100と回答した人の割合は14%に留まることから、大半の回答者は自分の技能を高める必要を感じていると評価できる(第2-1-1図)。
技能不足度合いを国別に見ると、東欧諸国(ルーマニア、チェコ、ブルガリアなど)やバルト諸国等で技能不足の度合いが高いのに対し、ルクセンブルグやオランダ、北欧諸国(フィンランドやデンマーク)では低い。技能不足の度合いが低い国々は、総じて一人当たりGDP水準(ドルベース)が高い傾向がみられる。
この背景として、一人当たりGDP水準が高い国では経済的なインフラ、例えば効率的な資源配分を促すような制度(製品や労働市場規制の緩和や倒産法制見直しなど)の整備や、社会人教育への参加度合いが高いことが指摘171されている。
上述の要因のうち、社会人教育への参加度合いを国ごとに比較したのが第2-1-2図である。先進国等の25~65歳の年齢層に対して、過去1年間の教育・訓練プログラムへの参加の有無と、今後より多くのプログラムへの参加希望があるかのアンケート調査結果に基づき、プログラムに参加した実績も希望もない人の割合をみると、北欧4か国では30%台と低く、オランダやドイツもOECD平均の50%を下回るが、イタリアは70%でOECD平均を上回っている。また、過去1年間でプログラムに参加したことがある人の割合は、北欧諸国及びドイツ・オランダで5割を超えているが、イタリアは21%にとどまり、OECD平均の40%を下回っている。イタリアのようにプログラムへの関与が低くても技能不足の度合いが小さい国もあるが、総じてみれば、教育訓練プログラムへの参加や関心が高い国では、主観的な技能不足の度合いが小さい傾向にあると考えられる。
OECDの分析172によれば、低技能労働者や低学歴の労働者ほど、技能向上や教育訓練プログラムへの参加への関心が低い。背景には、プログラム参加によって期待されるリターン(賃金上昇など)が低技能労働者では同じ職業に就く場合には限られていることが挙げられている。低学歴者については、学習によって得られる便益の大きさを認識していない可能性があり、学習機会への参加を促す取組も行われている(後述第1節2)。


(ii)年齢・性別にみた技能不足度合いの特徴
技能不足度合いは、性別を問わず、年齢が上がるほど小さくなる傾向がみられる。これは、年齢が上がるほど、経験に基づく知見や技能が高まることから、労働者側としてもミスマッチを回避できるようになり、自然な結果173と考えられる。しかし、国によっては、ある程度の年齢に達すると、それ以降は技能不足が改善しないケースもみられる。
例えば、技能不足の度合いが小さいオランダと、不足度合いが大きいスペインを比較すると、20代では技能レベルに大きな差はみられないが、特に40代以上では男女ともに、オランダの技能不足度合いがスペインよりもはるかに小さいことが分かる(第2-1-3図)。スペインでは特に女性の技能レベルが、年齢が上がっても小さくならず、キャリア形成を通じた経験や知識の蓄積が限られている可能性が考えられる。また、同様に、不足度合いが小さいドイツと大きいチェコを比較すると、ドイツでは年齢に比例して技能レベルが上昇するが、チェコではこうした比例関係はみられない。さらに、不足度合いが相対的に小さい北欧(デンマーク及びスウェーデン)でも、年齢を重ねることで技能レベルの上昇がみられるが、両国ともに男女共通して、30代後半の時期に技能の顕著な高まりがみられる。キャリアの比較的早い段階で技能レベルを高めていることが、両国の特徴と考えられる。
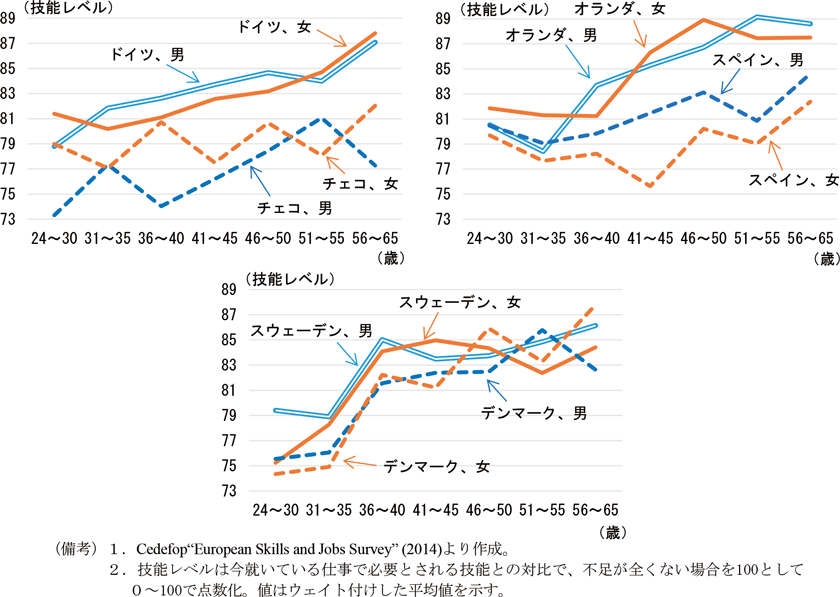
(2)新しい技術が雇用に及ぼす影響
(i)近年の研究
本節の冒頭でも述べたように、新しい技術の登場により、それを用いる労働者に新たな知識や技術の習得が必要となることから、対応が十分ではない移行期には技能ミスマッチが生じる可能性が高い。また、従来は人が行っていた業務の一部が機械で行えるようになったり、業務が大幅に効率化されることに伴い、労働者の業務の一部は削減されることも考えられる。
近年の研究では、デジタル化を始めとする機械化等の技術革新は労働力を代替する一方、新技術による需要創出や、新たな技能の必要性等を通じた雇用創出があるとの指摘もみられる。OECDが国別に、機械化の影響で失われるリスクのある雇用者比率を推計した結果、ドイツや日本では高く、北欧諸国では低いとの結果が得られている(第2-1-4図)。国ごとの比率の違いは、業種構成の違いよりもむしろ、職種構成の違い、さらには同じ職種でも高度な認知能力などを用いる仕事174が多いかどうかに依存していることが指摘されている。
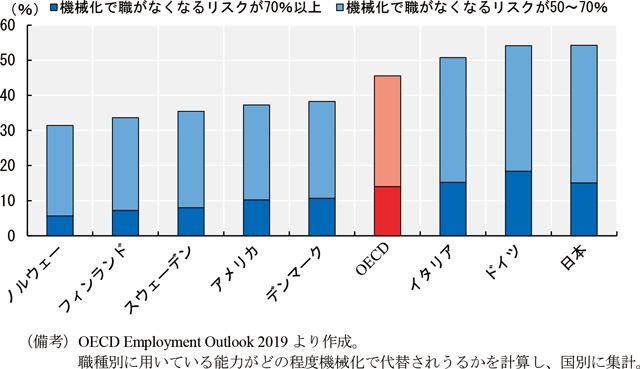
また、職種別に既存の雇用に対する技術革新の影響を分析した結果175によれば、特にデジタル化の影響が進んできた2000年以降、先進国では業務を行うのに高度な技能を必要とする「高技能」の雇用(具体的には経営者・専門家・技術者など)が相対的に増え、中程度の技能を必要とする「中技能」の雇用(事務員・サービス提供者・営業職・工場労働者など)が相対的に減少する二極化が進んでいることが指摘されている。これに対し、新興国では中技能の雇用が増えている国がみられる(第2-1-5図)。
以上のような変化に伴い、労働者の側も必要とされる技能を新たに身につけたり、転職時に異なる職種を選択することも想定される。
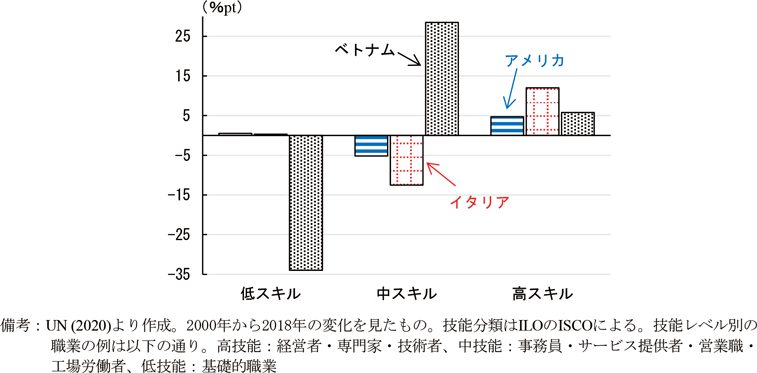
(ii)北欧諸国の事例
既述のように、北欧4か国は他の先進国と比較して、機械化で失われるリスクがある仕事が少ないことが指摘されている(第2-1-4図)。デジタル化の進展が顕著だった2000年以降の25~64歳の就業率の推移をみると、どの国も目立った低下傾向はみられない(第2-1-6図)。背景として、国際競争力のある輸出産業の成長が、労働集約的な業種を含む国内の他業種の設備投資や消費などの内需の増加につながったことが指摘されている。
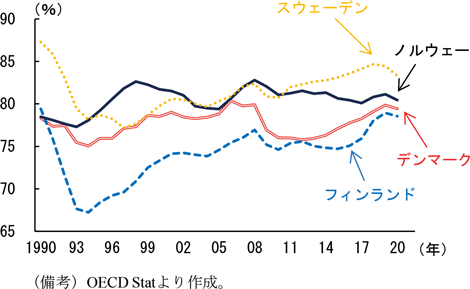
就業率に大きなトレンドはみられないとして、就業者の職種構成、特に技能レベルに応じた増減はどのように起きているだろうか。これを調べるため、技能のレベルはおおむね賃金水準とリンクしていることから、賃金階級別の職種構成の変化をみることとしよう。具体的には、Berglundらの研究では、15年時点の各国の民間部門の職種別の月給の中央値を用いて職種を月給に応じた五分位に分類し、11~15年のそれぞれの職種における雇用者数の変化率を計算している(第2-1-7図左)。その結果、デンマークでは低~中賃金階層の職種の雇用者が減少するとともに、高賃金階層の職種の雇用者が増加しており、アメリカやイタリアでみられた二極化(第2-1-5図)傾向に近い。これに対し、他の3か国(スウェーデン、ノルウェー、フィンランド)では、低賃金階層が減少し高賃金階層が増加する、いわゆる底上げ傾向が示唆された。具体的にどのような職種の雇用者の変化が大きかったかを調べると、国によって異なるものの、おおむね専門職で増加し、事務職や販売職等で減少がみられた(第2-1-7図右)176。
なお、各国とも看護師や介護士の不足がみられる。移民の受入れ等による対応が進められているものの、顕著な増加はみられない177。高齢化の進展と人手不足に対応するため、北欧諸国の高齢者ケアサービス業では、デジタル化を通じた労働力の代替が進めているが、それに伴い新たに必要とされる技能も指摘されている(Box.参照)。
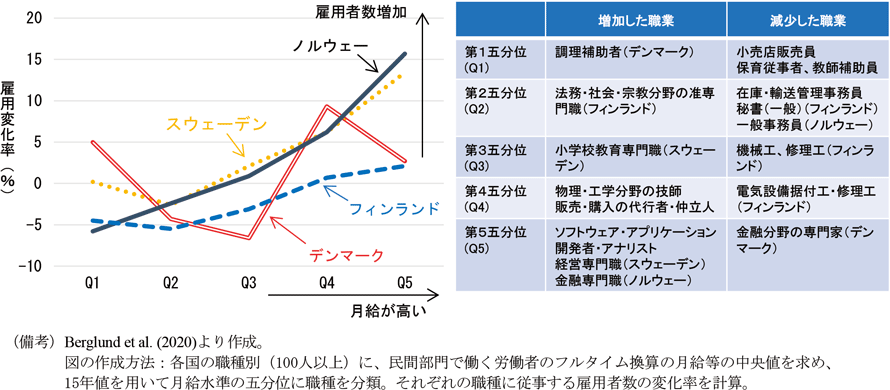
次に、こうした賃金階級別の職種構成の変化を、製造業とサービス業に分けてみてみよう。北欧4か国の製造業の雇用者数は、ロボット化等の技術革新やグローバル化の進展を背景に、いずれの国でも減少傾向にあり、対照的にサービス業の雇用者数は増加傾向にある(第2-1-8図)。上記と同様に、製造業・サービス業のそれぞれで、賃金階級別の職種構成の変化をみるため、15年時点の各国の製造業・サービス業それぞれの職種別の月給の中央値を用いて職種を月給に応じた五分位に分類し、11~15年の雇用者数の変化率を職種別に計算した結果が第2-1-9図である。
これによれば、製造業では雇用者数の減少傾向を反映し、デンマーク以外の国々では、増加がみられるのは高賃金(第4、5五分位)の職種のみとなっている(具体的に増加・減少がみられた職種の例は第2-1-10表)。こうした変化の背景には、労働集約的な生産工程がグローバル化の影響で国外に移転したことや、機械化やデジタル化の進展等により、高付加価値を生む職種のみが国内に残ったことが指摘されている。この結果、ノルウェーやスウェーデンでは職種構成の底上げが進み、高所得の職に雇用が集中している。サービス業については、特にスウェーデンで底上げ傾向が顕著であるが、この背景には主としてICT関連の技術革新を反映した先進的かつ輸出可能なサービス生産の伸びがあると考えられている(第2-1-11図)。こうした技術革新を踏まえた先進サービスの出現の影響は、デンマーク(風力発電技術)やノルウェー(海事産業や海洋資源利用関連技術)でもみられ、それぞれ高賃金の職種の雇用増がみられる。一方、デンマークでは低賃金の雇用も増えたことから、二極化が進んでいる。


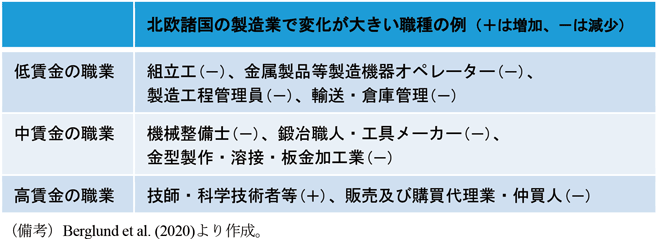
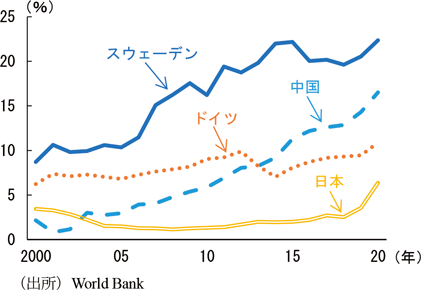
Box.北欧諸国での高齢者ケアサービス業種のデジタル化
北欧諸国でも、高齢化に伴い、高齢者に対するケアサービス業種への需要は今後数十年増加の見通しとなっている。これらの国々では、近年、自宅でケアを受ける65歳以上の要介護者の比率が上昇傾向にあり、OECD平均以上になっている(第2-1-B1図)。有資格の准看護師数も増加がみられ、OECD平均を上回る水準となっている(第2-1-B2図)が、並行してデジタル化も積極的に進められている。フィンランドやスウェーデンのヒアリング調査結果によれば、デジタル技術として具体的には、服薬管理ロボット、ジオフェンシング1向けのGPSアラーム、訪問経路最適化システム等が用いられ、フィンランドの訪問ケアサービス従事者の6割が、勤務時間の少なくとも半分でデジタル技術を活用しているとの調査結果がある。これらの技術の導入により、ケアサービス提供に必要な人員数が抑えられ、フィンランドの推計結果では、ロボット化によって介護労働者の業務の約2割が代替可能とされている。同時に、ケアサービス提供者には、ICT技術やデジタルデバイスを使いこなす技能のみならず、デジタル技術に関するメンテナンスと問題解決能力、技術(例えば監視技術)の活用に伴う法・倫理的問題(例えばプライバシー問題)に対応する管理能力など新たに求められる技能もあり、こうした技能の向上のための時間やリソース配分が求められている。
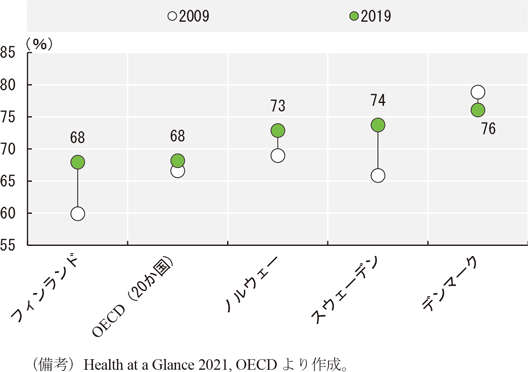

1 位置情報を使ったサービスの一種。GPS、Wi-Fi、携帯データ通信等を使い、特定の場所の周りに仮想的な境界(ジオフェンス)を設定。モバイルデバイスなどがその境界を出入りした際に、アプリなどのソフトウェアで決められたアクション(例えばプッシュ通知の送信、警告の表示)を行う。
出所:Dølvik et al. (2020) “Digitalization of services – A diverse picture.”
(3)技能不足が生産性に及ぼす影響
技能不足が生じていれば、企業にとっては未充足求人の発生や、希望に技能レベルが満たない労働者の採用、新技術の採用の遅れなどを通じて、生産性の押下げにつながると考えられる178。また、企業間の労働資源配分が効率的でなくなることでも平均生産性は低下すると考えられる179。また、労働者の側から見ると、就いている仕事に対して技能不足の労働者は、同様の仕事に就いている技能が合っている労働者と比べて、賃金が平均して17%低いとの結果も示されている180。こうした技能不足の労働者が職場にいれば、本人及び周囲のモチベーションの低下を通じて生産性に負の影響がある可能性も考えられる。
企業へのアンケート調査結果(18年)によれば、採用時に適材と考えられる人材を見つけるのに何らかの困難に直面した企業の割合は、先進国平均では42%181であったが、日本では89%と非常に高く、一方でオランダでは24%、英国で19%、ノルウェーで25%と低い182。こうした困難に直面した企業は、採用を行ったとしても、技能が十分ではないと考えられる人材を採用している可能性がある。
加えて、従業員に十分な技能がない場合には、企業が先進的な設備投資を導入する際の阻害要因となる可能性もある。例えば、欧州投資銀行(European Investment Bank)の21年調査結果183によれば、EU全体では79%の企業が、必要とされる技能を持っている従業員が不足していることを、投資を行う上での長期的な制約と回答している。アメリカではこの比率が92%と更に高い。この比率は、EU、アメリカともに他の制約要因(先行き不確実性など)と比べても高く、企業にとって最大の制約要因となっている。日本については、中小企業庁の委託調査によれば、中小企業がICT投資を行わない理由として、ITを導入できる人材がいない(43.3%)や社員がITを使いこなせない(25.7%)などが挙げられている。
こうした技能不足が生産性に及ぼす影響を検証することは容易ではないが、本項ではEU諸国について、上述の技能不足度合いと労働生産性水準の相関関係を、製造業及び卸小売業について国ごとに調べた(第2-1-12、13図)。14年の技能不足度合いと労働生産性水準(PPP、ドルベース)の間には、製造業・卸小売業ともにマイナス幅が0.5を上回る負の相関関係が見られ、1%水準で相関関係がないとする帰無仮説は棄却される(製造業-0.514、p値 0.0085、卸小売業-0.509、p値 0.0080)184。本項の結果は限られたサンプルでの国レベルの主観的な指標を用いたものであり、十分な幅を持って解釈される必要があるが、理論的に指摘されているように、技能不足が解消されれば労働生産性が高まる可能性を示唆しているとみることができる。なお、技能の不足度合いと労働生産性水準の関係を散布図で描くと、上記で示唆されるように、負の傾向線が描かれる。傾向線より左下に位置する国々(製造業の場合、イタリアやポルトガル及び東欧諸国など)では、生産性水準に比して自己評価の技能レベルが高く、不足しているとの実感が小さい。こうした国々では、技能不足度合いが高い国と比べて技能レベルが十分であるとは限らないことに留意する必要がある。例えば新しい技術の導入や、生産性向上に向けた業務効率化の進展が遅れており、結果として従来からの仕事の仕方やマネージメントが維持されているため、技能向上の必要性が自覚されにくかった可能性も考えられる185。

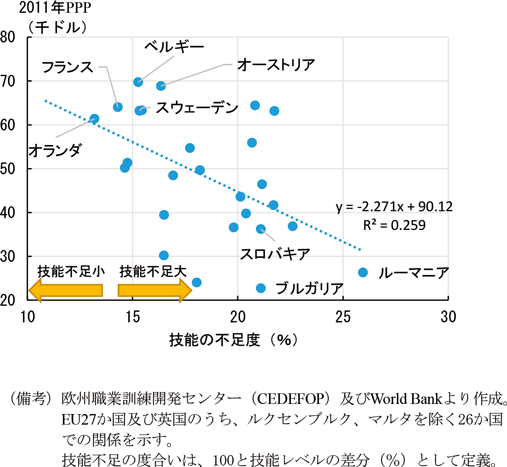
2.技能のミスマッチを解消するための施策
こうした技能のミスマッチを解消するために、各国はどのような政策を進めようとしているのだろうか。通常、技能形成は学校教育からスタートし、各個人の生涯にわたって、企業での訓練の受講や仕事を通じた習得によって行われる。こうした技能への投資が過少になる要因としては、個人や企業に帰属するリターンと、社会全体に帰属するリターンが一致していない(後者は他の労働者の生産性の押上げやイノベーションにつながり得る)ことや、投資を行った従業員が他の企業に転職することなどが背景にあると指摘186されている。ここでは、OECD(2019)の提言に沿って、各国の政策の代表的な例を取り上げてみたい。
(技能の需給調整)
先進国では、技能のミスマッチを解消するために求職者と雇主を結びつけることを目的とした公的雇用関連サービス(Public Employment Service)を始め、訓練プログラムの実施や支援等を含む、様々な政策(積極的労働市場政策)を行っている。各国の積極的労働市場政策に対する公的支出額(対GDP比)を比較すると、19年にOECD平均(0.63%)より比率が上回っていたのは、ニュージーランド(4.14%)、オーストラリア(1.79%)及び北欧3か国(デンマーク、フィンランド、スウェーデン)等である(第2-1-14図)。一方、日本は0.15%とアメリカに次いで低い水準となっている。

以下では、このうち社会人教育や訓練等、人的投資に係る政策に焦点を絞って、主な取組を紹介しよう。人的投資は経済社会にとって、イノベーション機会や生産性の上昇、格差是正等を通じた正の外部効果をもたらす。しかしながら、企業での人的投資が進みにくい要因として、(i)時間の制約、(ii)自社の技能や訓練ニーズを的確に把握できていないこと、(iii)プログラムを実施するための社内体制整備の遅れ、(iv)オンライン学習を可能にするシステム整備の遅れ等が指摘されている。また、技術革新に伴い仕事を失いやすい労働者に焦点を当てたプログラムを行っている企業は限られているとの指摘もある。人的投資を行う主体は民間企業(雇主側)、労働者のいずれもあり得ると考えられるが、民間企業による投資を促すための政策的な支援も重要と考えられている187。こうした政策支援の具体的なツールとしては、例えばOECDの整理に従い、以下のような5つの分類が考えられる(第2-1-15図)。また、各国の特徴ある人的投資支援策の事例を紹介する(Box.を参照)。

Box.
【1】 デジタル化を踏まえたフィンランドの職業教育訓練プログラム
フィンランドでは、18年に職業教育訓練システムを包括的に改革し、デジタル学習や職場での学習を強化した。デジタル化が職業教育訓練に大きな影響を与えることについては広く合意が得られており、同改革は各人の能力により応じた、かつ学習側志向のシステムの構築と、学習効率の向上を目的としている。教育訓練プログラムの活動や学習環境のデジタル化(例えば実地研修プログラムのデジタル化)を促すため、フィンランド国立教育機関と教育文化省は合同で、バーチャル学習環境の開発に補助金を拠出している。また、労働市場の需要に応えることを目的とした教育システム(職業教育及び高等教育)の設計のため、ビッグデータを用い、中長期的な将来、製造業やソーシャルサービス・ヘルスケアにおいて必要とされる能力やスキルの予想モデル(Dynamo model)の開発にも多額の投資を行っている(*)。
【2】 デンマークのデジタル成長戦略と訓練プログラム
デンマークでは18年に、業種・経済・財務省がデジタル成長戦略を公表し、デンマークの企業をデジタルフロントランナーとするためのビジネスモデルの提案を行った。戦略の背景にある基本的な考え方に、「誰もが適切なデジタルスキルを持ち、新たな機会を捉える備えがあること」の重視が挙げられる。職業教育訓練に関しては、労働者全体のデジタルスキル向上と、労働市場で急速に変化するニーズへの適応を目指すべきとし、これによって19年にICT活用センターが設置された。また、17年には教育省によって、職業教育訓練を受けている受講生のサポートを行うナレッジセンターが設置され、教育におけるICT活用の可能性を模索することが提案されている(**)。
【3】 オランダの生涯学習支援プログラム
オランダでは、22年から当初予算規模2億ユーロの「個人学習・能力開発予算」(STAP)が始動する。この予算では、18歳から定年までの年齢の全ての個人を対象に、年間上限1,000ユーロの訓練受講に対する補助金を支給する。受講先機関は認定された700の教育機関であり、先着順でオンラインで受講するプログラムを申し込むと、補助金が対象となる教育機関に給付される。2億ユーロは、現在必要とされている技能向上ニーズを満たすには少額であるが、雇主による追加的な資金援助も可能とされている(***)。
(*) Koukku, A. et al. (2020)
(**) Andersen (2020)
(***) OECD Economic Surveys Netherlands (2021)
3.労働市場の流動性と賃金動向
ここまでは、労働市場のミスマッチの状況を整理し、技術革新が雇用や格差に与える含意をみてきた。こうしたミスマッチの解消や、ミスマッチの存在に伴う格差の解消には、労働市場の流動性の高低が鍵となる。
労働市場の流動性は、労働法制(解雇コストの存在)、職種に応じた資格制度、情報収集コスト等転職に伴うコストや賃金以外の仕事の属性に対する選好の違いなどによる摩擦の存在により制約されていると考えられる。この摩擦により、労働生産性の伸びと賃金の伸びの関係の強さが変化する。
労働市場の流動性と労働生産性との関係は一概には言えない。流動的な労働市場(すなわち労働移動が活発な市場)であれば、労働者と職位の間のミスマッチ(労働者の持つ技能や知識が職位で求められる技能や知識と合わないことを指す)が解消されやすくなり、個々の労働者の生産性の上昇につながりやすいとの指摘がある。これに対し、頻繁な労働移動は企業に固有の技能や知識の蓄積を損ない、企業のマネージメントの効率性を低下させることから、企業の生産性、ひいてはマクロの生産性にマイナスの影響があるとの見方もある。
労働市場の流動性を、生産年齢人口に対する転職者比率でみると、欧州については、流動性が高いのは英国、デンマーク、スウェーデンなど(10~11%)、低いのはイタリア、ギリシャなど(5~6%)、中程度なのはフランスやドイツである。同じ尺度でみるとアメリカでは20%超であり、欧州諸国より流動性が高い188(第2-1-16図)。アメリカは従来、流動性の高い労働市場で生産性の高い新興企業等への労働者の転職が活発に行われることで、結果的に高い賃金上昇率が実現してきたとの見方があることから、以下ではアメリカの労働市場のダイナミクス189と賃金上昇の動向をみていきたい。
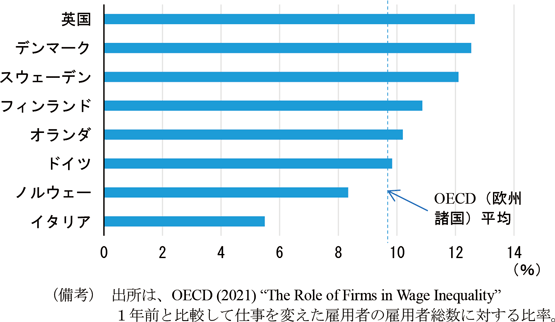
(アメリカの労働市場の流動性と賃金変化)
最初に、アメリカの労働市場の流動性の状況を、米労働統計局「四半期労働力指標」(Quarterly Workforce Indicators)で確認してみよう。男性の入職率(四半期の間に新たに仕事を始めた人数対雇用者数の比率)190は、90年代以降低下傾向にあり、08~19年の期間平均で男性は12%程度で推移している。離職率(四半期中に仕事が終わった(次の四半期に同じ仕事が続かない)人数対雇用者数の比率)は入職率をわずかに下回っている(第2-1-17図)。若年層(25~34歳)に限定してみても、入職率・離職率ともに水準はやや高いものの、全体とおおむね同様の状況がみられる。
上述の通り、アメリカの労働市場での転職率は欧州の主要国と比較しても高水準であるが、日本とはどの程度の違いがあるのだろうか。単純な比較は困難だが、厚生労働省の「雇用動向調査」(19年)によれば、男性の転職入職率が年間で25~29歳は17.8%、30~34歳では12.5%191で、平均するとアメリカの四半期の入職率の14.3%とほぼ同水準であることから、大まかにみれば日本の入職率はアメリカの四分の一程度と考えられる。
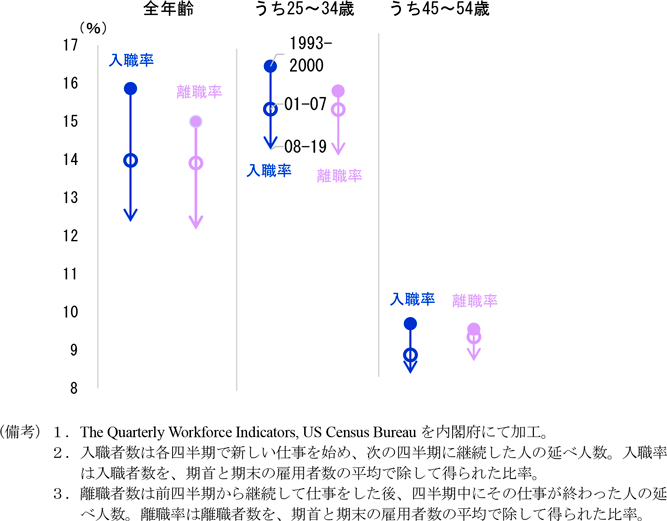
次に、アメリカでの賃金変化率の状況を、1年前と比べた名目賃金の変化率のデータを用いてみてみよう。連邦労働統計局が公表しているCurrent Population Survey(CPS)のマイクロデータを用いて作成されたWage Growth Trackerによれば、名目賃金の前年比の中央値は90年代以降徐々に低下傾向にあったものの、90年以降足下までの期間で平均してみると3.6%程度192であった(第2-1-18図)。また、コロナ禍以降の回復期には労働市場の需給のひっ迫を反映し前年比に顕著な高まりがみられている。

(年齢別、転職経験の有無別にみた賃金上昇)
ここからは、アメリカの賃金上昇の背景に、上述のような活発な労働移動があるのか、または継続就業者の賃金上昇が中心なのかを、労働者の属性別にみていこう。Wage Growth Trackerでは、過去1年間に転職経験の有無別に系列を提供193している。これを用いて、転職者、転職者以外の労働者(以下継続就業者)の賃金上昇率を年齢階層別に比較する(第2-1-19図)。16~24歳の若年層、25~54歳の中堅層ではいずれも、93年以降の各期間で、継続就業者より転職者の方が賃金の伸びが高い。なお、各グループの賃金の中央値をみると、若年層や中高年層(08年以降)では継続就業者と転職者でほぼ同水準であるのに対し、中堅層では転職者グループの方が分布の中央値がやや低い。賃金上昇率もやや高いことから、中堅層での転職者は1年前の賃金が相対的に低く、転職を通じて賃金が上昇するケースが多い傾向がうかがえる。
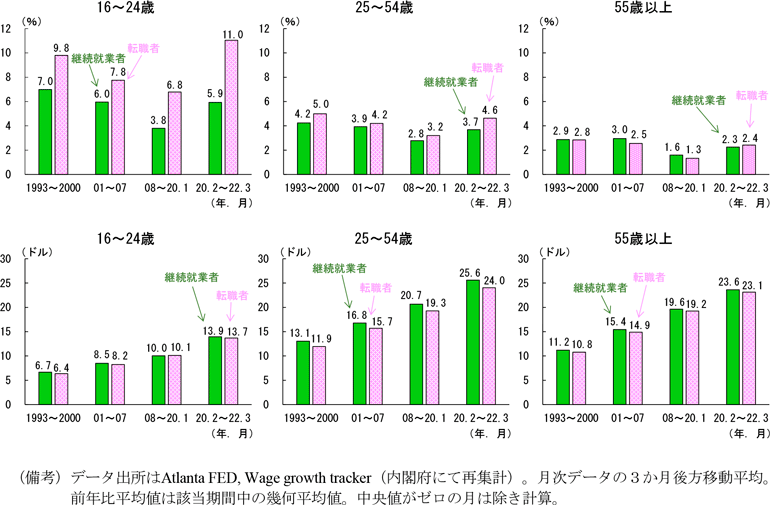
(賃金水準別、転職経験の有無別にみた賃金上昇)
次に、継続就業者と転職者の賃金上昇率を賃金の水準別に比較する(第2-1-20図)。具体的には、賃金水準を四分位に分け、第1四分位(賃金水準が下から25%。以降「低賃金層」)と第4四分位(賃金水準が上から25%。以降「高賃金層」)のグループについて上昇率の中央値を求めた。その結果、継続就業者では、2000年代末から10年代を通じて、高賃金層の賃金上昇率が低賃金層の上昇率を平均的に見て上回っている。他方、転職者については、93年以降一貫して、低賃金層の賃金上昇率が高賃金層の上昇率を上回っており、低賃金の労働者が転職を経て相対的に大きな賃金の上昇を経験していたことがうかがえる。また、低賃金層では継続就業者と比べて転職者の方が賃金上昇率が高い一方、高賃金層では転職者の賃金上昇率と継続就業者の上昇率には大きな違いがみられない。これは、低賃金層にとっては、転職が賃金上昇のドライバーになっているのに対し、賃金水準がある程度以上になると、継続就業による知識や経験の蓄積が、より賃金上昇に反映されやすくなることを示唆している。

(職種別にみた賃金水準と変化率)
アトランタ連銀の分析では、11の職種(occupation)について、求められる技能や知識の種類別に3グループに分類している。ここでは、職種の特徴に注目し、それぞれの職種で転職または継続就業がどの程度の賃金上昇をもたらしているかを、男性労働者のデータを用いて比較する。
高度な判断を求められる経営企画業務に従事する人やICT関連の技術職の労働者等は、賃金水準が高く、かつ、1年以内に他の職種から転職してきた労働者の賃金が相対的に低い一方、同じ職種内で転職した人の賃金は転職していない人の賃金を中央値でみてやや上回る傾向が見られる(第2-1-21図)。こうした専門性の高い職種では、当該職種で蓄積してきた経験や知識の豊富さが、転職時に高く評価される傾向がうかがえる。一方、1年前と比べた賃金変化率(中央値)は、継続就業者が最も低く安定的に推移しているのに対し、転職者では振れが大きいものの高い水準で推移している。専門性の高い職種では、転職入職することで賃金面で大幅なステップアップを経験する労働者が多いことが示唆される。
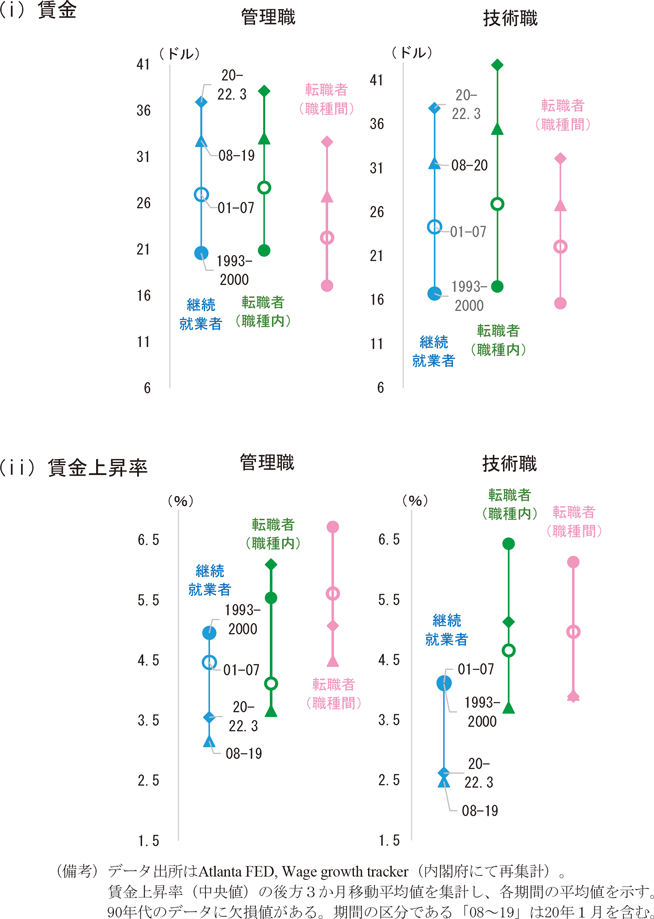
次に、マルチスキル及び対人サービスや加工・製作に関わる職種に就く労働者の賃金(中央値)は、転職経験の有無による差が小さく、特に事務職では転職者と継続就業者の賃金はほぼ同じ水準である。生産や製造工程に従事する労働者の場合は他の職種から入職した人の賃金はやや低い。背景には、事務職と比較して、生産や製造工程に従事する労働者の場合は経験(熟練)が重要である可能性が考えられる(第2-1-22図)。賃金上昇率でみると、転職した人の方が、継続就業者よりも高い上昇率を経験していることがうかがえる。

最後に、主に作業や運転に関わる職種についてみてみよう。このグループの労働者の賃金(中央値)は、転職者・継続就業者がほぼ同じ水準となっており、こうした傾向は特に飲食・ビル施設管理の職で顕著である(第2-1-23図)。他方、飲食・ビル施設管理の職種では、同じ職種からの転職者の賃金上昇率が相対的に高く、同一職種内でのステップアップの可能性をうかがうことができる。また、同職種では営業・販売と同様にコロナ禍後の継続就業者や他の職種からの転職入職の場合の賃金上昇率の高まりが顕著であり、相対的にみて需給がひっ迫していることが示唆される。

このように、求められる職種別にみた場合でも、賃金上昇率は転職者の方が高い傾向にあることが示唆された。また、中央値で賃金水準を比較すると、2000年代以降の技術職や営業・販売職では同じ職種内で1年以内に転職した人の賃金水準が相対的に高く、キャリアを積むことでより高い賃金の仕事に就いている可能性がある。これに対し、事務職や飲食・ビル施設管理では、継続就業者と職種内転職経験者の賃金水準は中央値でみてほぼ同水準であり、賃金上昇率にも大きな違いが見られないことから、転職が必ずしも高賃金に直結しているとは限らないことがうかがえる(第2-1-24表、第2-1-25表)。
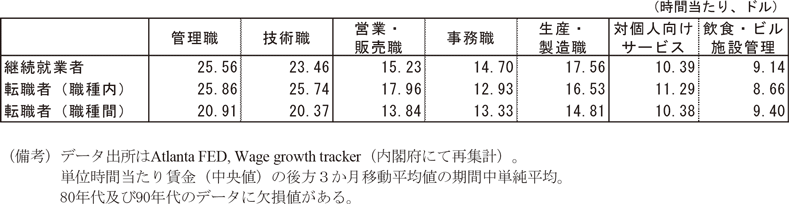
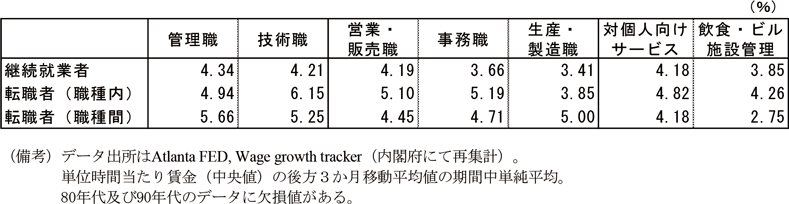
(属性別に見たマクロの平均月給の動向)
ここまで、各労働者の賃金変化率の中央値をみることで、アメリカの労働市場では転職を通じた賃金上昇率が総じて高く、継続就業の場合でも相応の賃金上昇がみられるものの、転職を契機に賃金面でのステップアップを実現している人が多くみられることが明らかになった。これに対し、先進国でみられる2000年前後以降の賃金上昇率の鈍化は、主として継続就業者の賃金上昇率の低下によるものであるが、アメリカでは転職を通じた賃金上昇率も低下傾向にある、との指摘もみられる194。こうした指摘を検証するため、ここからは、マクロの平均賃金の変化を、継続就業者の賃金変化による部分と、離職や入職による部分に分けてみていきたい。そのためには、継続就業者・入職者・離職者それぞれの人数や賃金の状況を把握する必要がある。このため、上述の「四半期労働力指標」を用いて、平均賃金の上昇率について考察195する。併せて、成長部門への労働移動の状況を確認するため、企業規模別のデータの確認も行う。
(i)年齢階層別にみた賃金変化率
年齢階層別に男性労働者の平均賃金の変化率をみると、経年では低下傾向にある(第2-1-26図)。例えば25~34歳の年齢層では、93~2000年の期間では年率換算で平均賃金は7.0%の上昇と高い伸びを示していたが、2000年代以降は2.0%程度と伸びが大きく低下している。平均賃金の変化は、同じ職で継続して働く人の賃金変化による部分と、入職・離職に伴う構成変化による部分に分けられる196が、25~34歳の年齢層では、入職者賃金が離職者賃金を上回ることが多く、特に10年代以降はかい離が目立つ(第2-1-27図)。90年代は、入職・離職を通じた賃金上昇と、継続就業者の高い賃金上昇があいまって平均賃金も高い伸びを示していたが、2000年代以降、転職要因の寄与が小さくなり、10年代半ば以降は再び転職要因の寄与が高まったものの、継続就業者賃金の伸びが相対的に低下したことで、全体の伸びが低下したと評価できる。
これに対して、45~54歳の年齢層では、同じく93年から2000年の期間では平均月給は5.1%と高い伸びを示していたが、入職者平均賃金を離職者平均賃金が上回り、入職・離職に伴う変化は90年代からマイナス寄与であった。入職者の賃金と離職者の賃金を比較すると、コロナ禍の時期を例外として、期間を通じて離職者の平均賃金の方が高い。前述の賃金変化率データでみれば、転職を通じて上昇する人の方が多いものの、例えば労働時間の違いなども反映して、入職時の平均月給が離職時よりも5~10%ポイント程度低いことから、月給面でみれば若年層と比べて転職が相対的に不利であると考えられる。
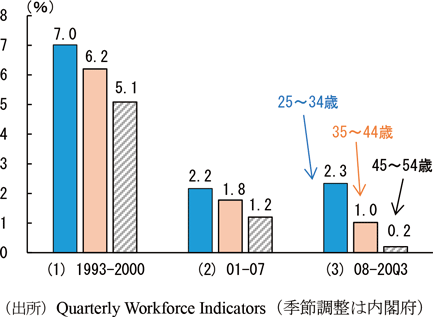
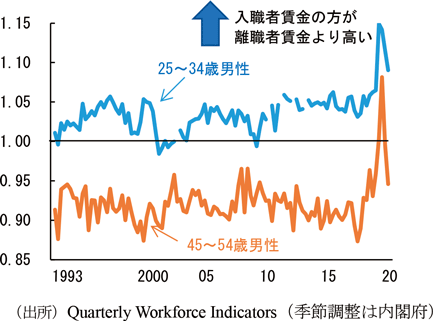
(ii)企業規模別にみた月給変化率
次に、企業規模別の男性労働者の平均月給の変化率をみる。従業員数が20人未満の最も小さい区分の企業では、リーマンショック時を例外として、入職者平均月給が離職者平均月給を上回っている。また、入職者月給は継続して働く人の月給との対比で、10年代後半以降上昇傾向にある。これに対し、従業員数が500人以上の最も大きい区分の企業では離職者平均月給が入職者平均月給を上回っている(第2-1-28図)。20人未満の小規模企業では、リーマンショック時やコロナ禍を除いて入職率(入職者数対継続雇用者数)が離職率(離職者数対継続雇用者数)を平均で1~2%ポイント程度上回って推移しており、雇用者数の伸びが続いているとみられるが、こうした成長企業では、労働者の転入・転出による平均賃金の押上げが目立つ(第2-1-29図、第2-1-30図)。これに対し、大企業では転入・転出による平均賃金への影響はマイナスであり、継続して雇用されている労働者の賃金上昇が平均賃金の伸びに寄与しているとみられる。大企業で相対的に賃金が高い従業員の離職が多い背景の一つには、アメリカの労働力人口の年齢構成変化、すなわち一定年齢に達した労働者の退職要因197が考えられる。

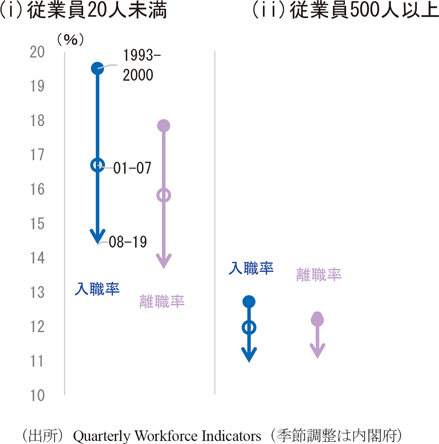
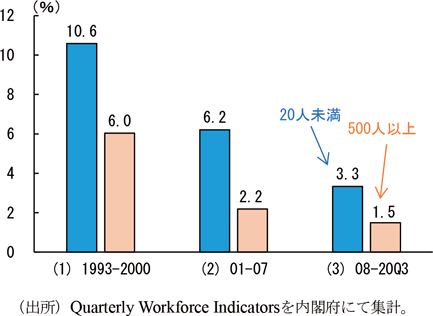
最後に、こうしたアメリカの賃金動向と我が国の賃金動向を可能な範囲で比較してみたい。我が国では、事業所調査である賃金構造基本統計調査(厚生労働省)の公表結果を用いて、雇用者の属性別や企業規模別の平均時給198の動向をみることができる。データが利用可能な01~07年の時給伸び率(年率)と、08~19年の同伸び率を計算した(第2-1-31図、第2-1-32図)。日本では、両期間ともに時給の変化が小さく、年齢階層別では年率換算の伸びは08年以降の若年層を除き、いずれの年齢層もわずかなマイナスまたはゼロ、業種別では製造業や飲食・宿泊サービス業でゼロ近傍の伸びとなった。ただし、01~07年の間アメリカの消費者物価(総合)は平均3.2%程度の伸びで日本の-0.2%を大きく上回っていたことから、実質平均月給の伸びではむしろ日本の方が上回っていた可能性もある。なお、08~20年では消費者物価上昇率(年平均)はアメリカで1.7%強、日本では0.3%程度と1.5%ポイント程度のかい離があることから、実質賃金の伸びで言えば、35~44歳及び45~54歳ではアメリカより日本の方が高かったことが示唆される。
各労働者の賃金の変化率については、我が国では公的統計データは利用できないものの、転職入職者に対する転職前後の月給の変化を尋ねた雇用動向調査(厚生労働省)の2019年調査結果をみると、「変わらない」と答えた人の割合が最も高く3割程度である一方、減少率が少なくとも1割を超える人も3割弱を占めている(第2-1-33図)。労働時間の減少を伴う転職もみられると考えられ単純な比較はできないが、同じ区分でアメリカの転職入職者の賃金の変化を集計すると、1割未満の増加が最も多く、日本の結果と比べて分布が全体に増加傾向に偏っている。こうしたことからも、アメリカでの転職を通じた賃金のダイナミズムの力強さをうかがうことができる。
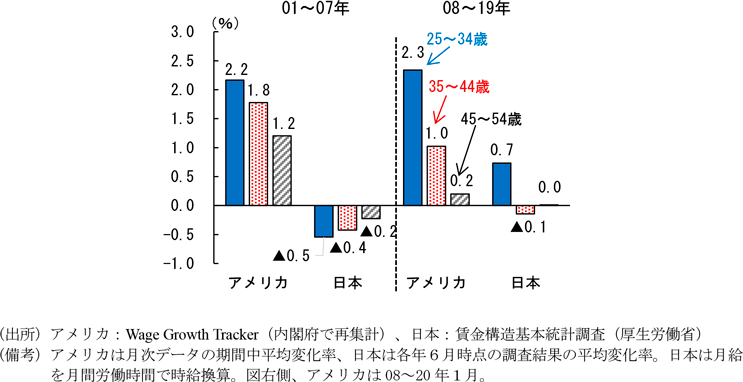
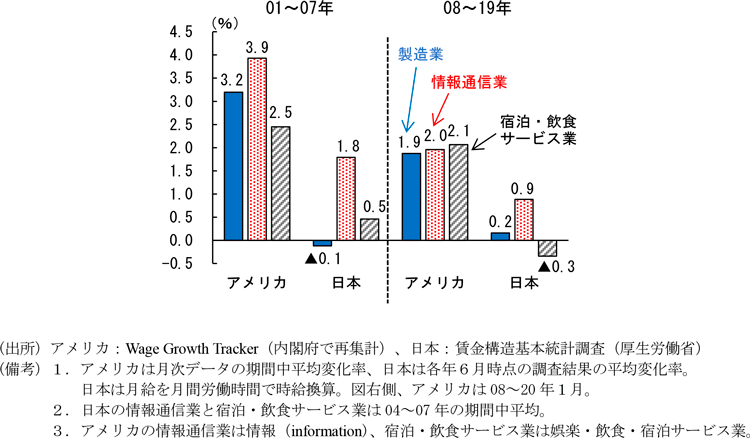
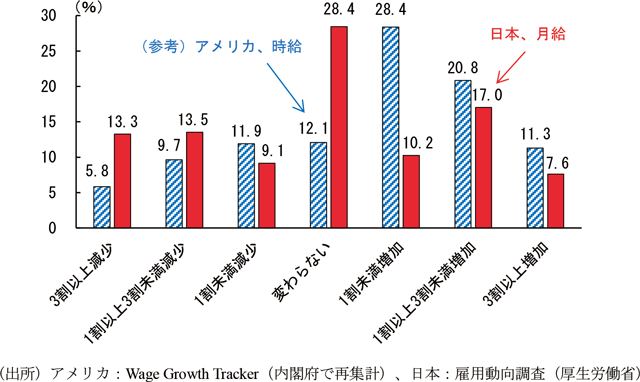
(小括)
本節では、労働市場での技能のミスマッチの状況を整理した上で、デジタル化を始めとする技術革新が雇用や格差に与える含意を考察した。本節の議論を整理すると、以下の通り。
・欧州のデータからは、技能不足度合いには国ごとにばらつきがあることが分かった。技能不足の度合いが小さい国においては、その背景の一つとして、教育訓練プログラムへの参加や関心が高い傾向にある。
・技能不足度合いが小さい国では、男女ともに年齢が上がるほど技能不足が小さくなる傾向がみられ、技能が蓄積されていることがうかがわれる。
・国別に見ると、技能不足の度合いが小さいほど労働生産性が高い傾向にある。
・技術革新による雇用減や二極化への懸念については、北欧諸国の事例からは、目立った雇用の減少はみられず、また二極化傾向だけではなく、底上げ傾向のある国も多かった。底上げ傾向のある国では技術革新を反映した先進的かつ輸出可能なサービス生産の伸びなどが背景としてある。また、そうした業種からの波及効果が労働集約的な業種を含めた内需の増加につながったとみられている。
・技能のミスマッチを解消するために各国が行っている政策を整理した。各国の状況に応じて、他国の優良な取組を取り入れていくことが重要である。
ミスマッチ解消に向けては、転職や技能の転換・向上に向けた教育訓練投資が重要と考えられる。主観的なミスマッチレベルが低い北欧諸国では、全般に市場の流動性が高いことに加え、教育訓練投資の機会も多く、キャリアの比較的早い段階で技能レベルを高めている可能性が示唆された。
技能不足に直面している企業側から見ると、足りない技能を埋めるには、従業員に対する教育訓練を行うか、もしくは外部人材を採用したり、業務をアウトソースするという選択肢がある。自社の従業員の技能アップが実現すれば、その後の生産性の上昇と持続的な成長の可能性が拡大する。他方、教育訓練投資には外部効果も大きいことから、企業に訓練投資を拡充するモチベーションを与えるための政策的な支援の一層の拡充も重要と考えられる。
最後に、労働市場の流動性と賃金動向に関する議論を整理する。
日本の労働市場と比較して、北欧を始めとする欧州各国の労働市場の流動性は高いと言えるが、アメリカの労働市場は欧州を上回って労働者の入職・離職が活発である。流動的な労働市場では、労働者が生産性の高い成長部門や高賃金部門に速やかに移動しやすいことから、転職に伴う賃金上昇率の押上げが予想される。流動性の高いアメリカのデータを見ると、90年代以降、若年層や低賃金層を中心に転職者の賃金上昇率が高く、平均賃金を底上げしている。これに対し、相対的に多くの知識や技能の蓄積が求められる職種では、転職者の中でも同じ職種からの転職入職者の賃金が水準・変化率ともに高い一方、他職種からの転職入職者の賃金は転職に伴い大きく上昇するものの、水準は相対的に低い。転職に伴う賃金変化率は、日本と比べてアメリカでは分布が増加傾向に偏り、アメリカでの転職を通じた賃金変化のダイナミズムが確認された。
他方、アメリカの平均賃金の変化率は、90年代までは高水準であったが、2000年代以降大きく低下している。主な背景としては、継続就業者の賃金の伸びの低下傾向が挙げられ、大企業などでの定年退職者の増加等の構成要因に加え、労働生産性の伸びの低下を反映して全ての年齢層で賃金の伸びが低下した可能性がある。また、2000年代には転職による平均賃金の押上げ寄与も小さくなり、実質ベースでは日本の平均賃金変化率を下回っていた可能性もある。時系列でみると2000年代以降アメリカの労働市場のダイナミズムは低下していたとみられるが、コロナ禍以降の回復期には、労働市場の需給ひっ迫を背景に、転職者・継続就業者双方で賃金上昇率が高まっており、今後の動向が注目される。
t期の平均月給変化率
=(t + 1期の期首雇用者数 × t + 1期の期首雇用者平均月給 - t期の期首雇用者数 × t期の期首雇用者平均月給)÷(t期の平均雇用者数)
=【(t期の入職者数 × t期の入職者平均月給 -t期の離職者数 × t期の離職者平均月給)+(t期の継続就業者の平均月給変化額)】÷(t期の平均雇用者数)
=【(t期の入職者平均月給 - t期の離職者平均月給)× t期の入職者数+(t期の入職者数 - t期の離職者数)× t期の離職者平均月給 +(t期の継続就業者の平均月給変化額)】÷(t期の雇用者数)
https://www.atlantafed.org/chcs/labor-force-participation-dynamics.aspx

