第2節 主要国・地域の経済の現状
1.アメリカ経済の現状
(1)緩やかな回復が続くアメリカ経済
アメリカ経済は、雇用者数の増加等雇用環境の改善に加えて、個人消費が緩やかに増加していることなどから、全体としては緩やかに回復している。なお、14年1~3月期には大雪・寒波の影響もあって実質経済成長率が前期比0.1%と鈍化した(第1-2-1-1図)。
また、金融政策では、FED(連邦準備制度)が13年12月に追加金融緩和(いわゆるQE3)の縮小開始を決定しており、資産購入額は、14年5月には毎月450億ドルまで減額されている。
本項では、緩やかに回復を続けるアメリカ経済について、実体経済の回復の度合いを分析するとともに、これまで経済を下支えしてきた金融緩和の縮小をめぐる動きについて概観する。
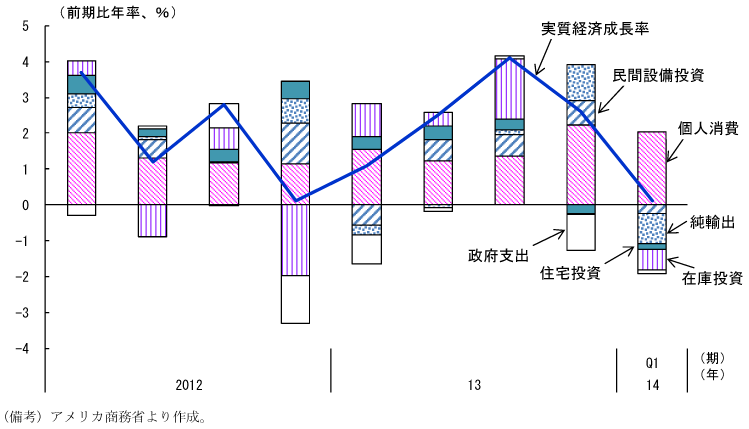
議会予算局(CBO)によると、アメリカの潜在成長率は2000年頃には3%程度であったものの、世界金融危機後の09年には1%台に低下した(第1-2-1-2図)。その後、10年を底に回復基調にあり、12年実績は1.6%となっている。13年以降も次第に回復し、16年以降は2.0~2.5%程度で推移するとみている。
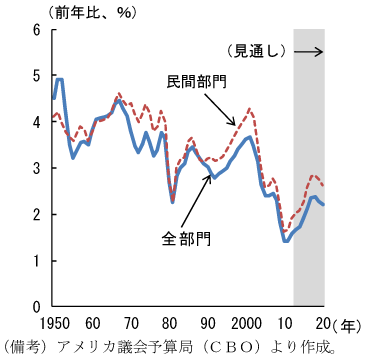
CBOは毎年経済見通し等を公表しているが、世界金融危機前と最近の潜在成長率のデータを比較すると、危機前の推計では潜在成長率は2.5%程度で推移するとの見方であった。それが、危機後の推計では、潜在成長率は一時1%台に低下し、その後2%強に回帰するとの見方に変わった(第1-2-1-3図(1))。さらに、危機後の推計の中でも危機直後はすぐに2%台の成長率に戻ると考えられていたが、最近では金融危機の影響が相当程度残るという見方に変わってきている1。緩やかな景気回復が続く中、最近の推計によるGDPギャップは縮まる方向にある(第1-2-1-3図(2))。
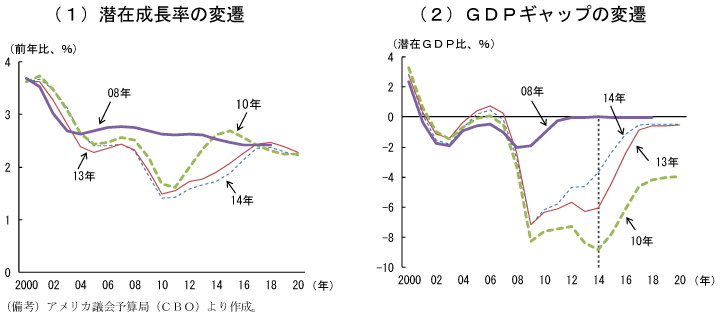
(i)緩やかな増加が続く個人消費
個人消費は緩やかなペースで増加が続いている(第1-2-1-4図)。13年初の給与(社会保障)税減税や高所得者に対する所得税等の減税措置の一部等の失効、13年3月1日から実施された歳出の自動削減2等を含む財政緊縮が個人消費にマイナスの影響を与えることが懸念されたものの、雇用環境が順調に改善したことや家計のバランスシート調整がほぼ終了したとみられることなどが要因と考えられる。
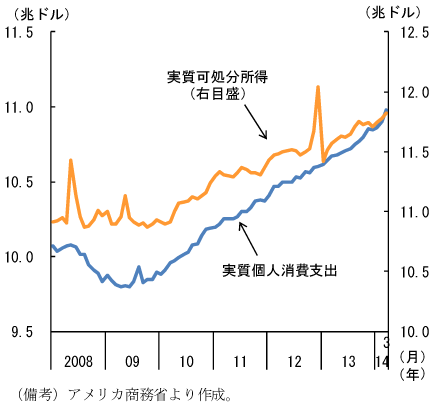
個人消費の動向を財別にみると、13年前半は耐久財が大きく個人消費をけん引した。うち、自動車販売をみると、12年前半にガソリン価格が断続的に高騰した際に横ばいとなったものが、その後価格がいったん低下したことや上昇しても12年のような水準まで迫ることがなかったことなどから、順調に増加していった。これは、雇用環境の改善や家計のバランスシート調整が進んだこと、金融機関の貸出態度が緩和し信用が拡大したことなどが背景にあると考えられる(第1-2-1-5図)。今冬の厳しい寒さ等のため13年末以降売行きが鈍化したが、寒さが緩んだことから販売は持ち直している。
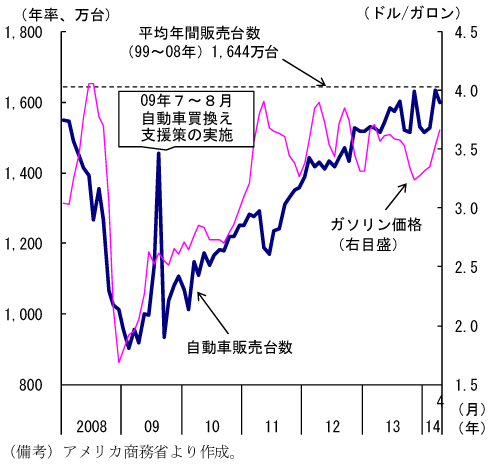
雇用情勢をみると、雇用者数の増加ペースは13年12月に大きく鈍化したものの、その後は徐々に回復しており、14年2月から4月にかけて3か月連続で前月比20万人以上増加している(第1-2-1-6図)。12月を中心とした雇用者数増加のペースの鈍化は、第一に小売業が年末セールに向けて営業時間を延長するなど販売促進に向けた動きが活発だったものの、1月に入って反動がみられたこと、第二に大寒波により雇用者数が減少に転じたことも要因として考えられる。寒波の影響は建設業等でもみられ、3月のFOMCにおいても影響が指摘されている。
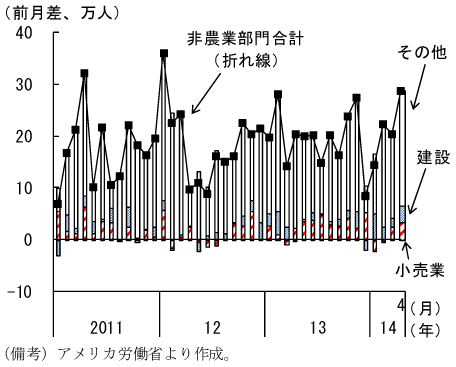
また、雇用者報酬の伸びは14年2月に一時的に鈍化したものの、基調としては12年後半以降緩やかな上昇傾向で推移している(第1-2-1-7図)。2月の伸びの鈍化は建設業、娯楽業等で減少したことによるもので、寒波による労働時間の減少が寄与したと考えられる。3月にはこうした状況も改善し、労働時間が増加するなどした結果、雇用者報酬も再び増加した。
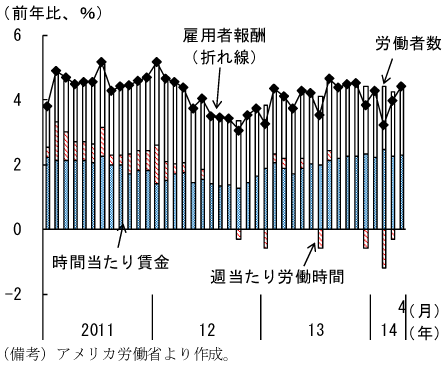
家計のバランスシートの動きをみると、資産側では株価が高値圏で推移していること、住宅価格は上昇を続けていることなどから金融危機以前の資産残高を超え、堅調に増加している。一方、負債側では住宅ローンがおおむね横ばいで推移している一方、自動車販売が13年末以前は好調に推移していたこと等から消費者ローンが増加するなどした結果、負債額もやや増加傾向にある(第1-2-1-8図)。ただし、全体としてみれば、資産額の伸びが負債額の伸びを上回って推移しており、また、新たなローンの増加といった要因もあることから家計のバランスシート調整は全体としてはおおむね終了していると考えられる(第1-2-1-9図)。
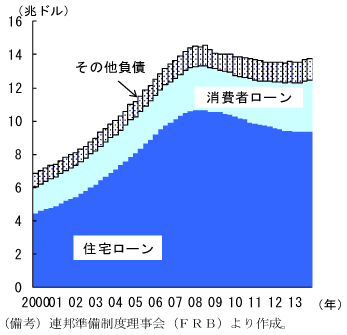
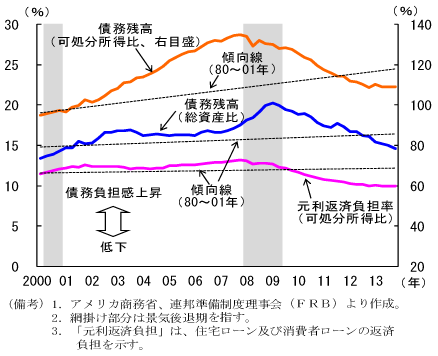
経済が緩やかに回復する一方、貧困レベル3以下の世帯割合は、10年以降横ばいとなっているものの金融危機以前と比べて高い割合となっており、景気回復の恩恵は一部にとどまっていることを示唆している(第1-2-1-10図)。
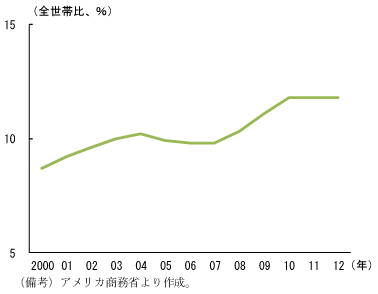
(ii)回復ペースが鈍化した住宅市場
(ア)最近の住宅市場
住宅市場は、住宅バブルの崩壊以降回復の途上にあるが、13年末には減速の動きがみられる。GDP統計の住宅投資をみると、10年の10~12月期に伸び率がマイナスからプラスへ転じて以後、二けた成長をみせるなど堅調に推移していたが、13年10~12月期には前期比▲7.9%とマイナスに転じ、14年1~3月期も同▲5.4%となった。
住宅着工件数は13年初にかけて増加を続けた後、3月以降、金融緩和縮小懸念が生じ金利が上昇したことを背景に横ばいで推移した。しかし、9月のFOMCにおいて資産購入額縮小が見送られると、9月縮小開始を見込んでいた金融市場には驚きをもって受け止められ、金利が低下した。こうしたことから11、12月には駆け込み需要が発生し、年率100万件を超す強い数字となった(第1-2-1-11図)。
一方、14年になると着工の増勢は鈍化している。背景には、13年末に大きく伸びた反動減に加えて、地域によっては13年末以降アメリカを襲った20年ぶりの寒波・大雪の影響が14年1、2月に発現したと考えられる(第1-2-1-12図)。
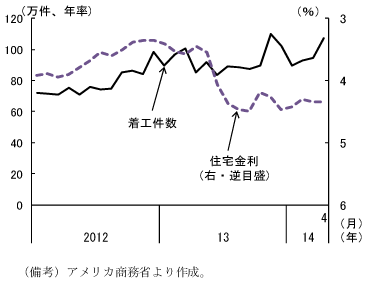
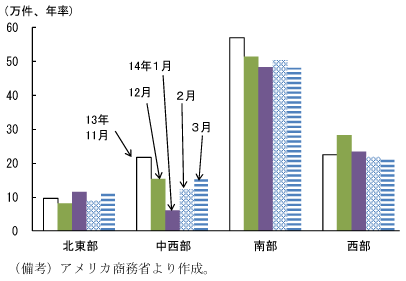
住宅着工件数の先行きについては、需給がひっ迫していることから今後回復が続くという見方が多い。ただし、金利の先高感があること、住宅が一戸建てから集合住宅へとシフトしてきていること、労働者や土地の供給制約が指摘される中で建設途中の物件が増え続けていることなどから13年11、12月にみられたような急激な伸びを期待することは難しいとも考えられる(第1-2-1-13図、第1-2-1-14図)。
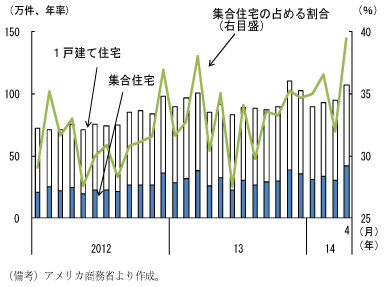
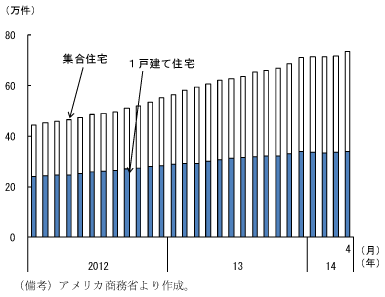
住宅着工件数の動きを需要側の動きから確認するため、住宅販売件数を住宅着工の動きに対応する「新築」と、「中古」に分けてみる4。13年後半以降、新築住宅販売は横ばいであるのに対し、中古住宅販売は低下している(第1-2-1-15図)。アメリカの住宅販売は中古住宅の割合が9割程度5
を占めるが、在庫件数が低水準で推移する中、手ごろな低価格物件が少なくなってきている点が背景にあるとの指摘がある(第1-2-1-16図)。また、建築業者のマインド指数も14年に入り低下している(第1-2-1-17図)。
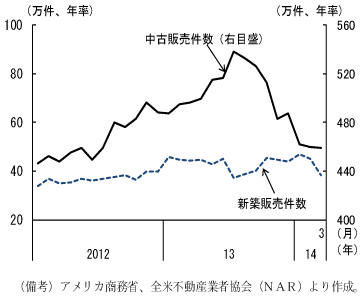
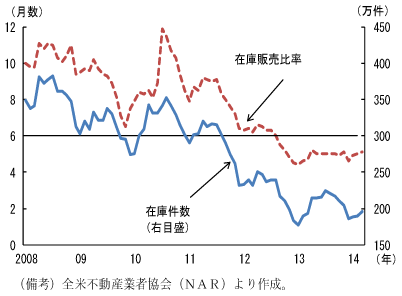
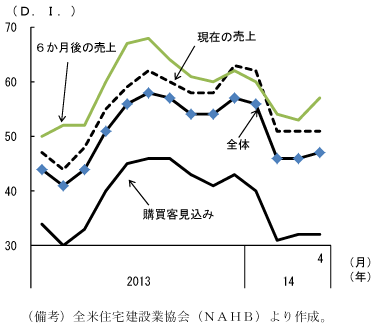
一方で、住宅価格は上昇を続けている。世界金融危機前のピークである06年4月と比較すると、8割程度まで回復している(第1-2-1-18図)。景気の谷は09年6月だが、住宅価格は12年になってようやく上昇に転じ、その後は速いペースで上昇している。背景には、景気回復が続く中、第一に在庫件数が低水準となり、在庫と販売の比率も適正といわれる6か月を下回ったまま推移するなど供給不足となっていること(前掲第1-2-1-16図)、第二に市場価格の8割程度で販売され住宅価格を下押しする差押物件が減少傾向にあることなど、住宅市場の調整の進展がある(第1-2-1-19図)。
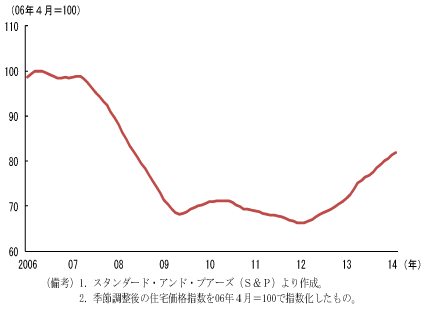
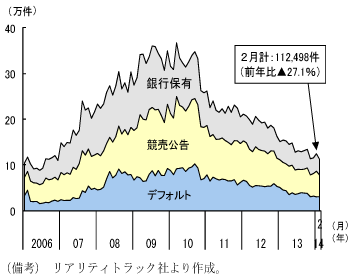
(イ)住宅市場の先行き
住宅市場の先行きとしては、雇用・所得環境の改善が見込まれ、住宅金利も歴史的にみれば低水準にあることから住宅市場の回復が続くことが期待される。また、ベビーブーマー6の子供世代が世帯形成を進める年齢となっており住宅購入の需要も見込まれることから、住宅価格の上昇が継続すると推測される。
ただし、可処分所得の伸びが住宅価格の伸びを下回って推移していることなどから、住宅取得可能指数7に低下がみられる(第1-2-1-20図)。米消費者金融保護局(CFPB)が定めた住宅ローンに関する新基準(14年1月施行)では、貸手に対し住宅ローン組成前に借り手の返済能力を確認、証明することなどを義務付けている。基準を満たした住宅ローンは適格住宅ローン(Qualified Mortgage)として認定され訴訟リスクが低減する一方、厳格な審査を行うためコスト上昇要因となろう。
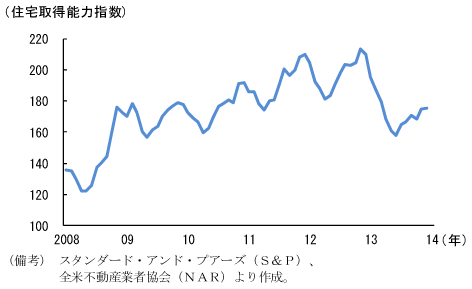
(iii)持ち直しが続く企業部門
13年半ば以降の企業部門は、連邦政府機関の一部閉鎖といった不透明な要因があったにもかかわらず、国内・海外経済の景気回復による需要期待から、各指標に持ち直しがみられた。しかし、13年12月からのアメリカ全土を襲った大寒波により、弱い動きもみられる。ここでは企業部門の設備投資、生産の動向について過去の回復局面との比較により概観する。
まず、企業の設備投資は持ち直している。GDP統計の民間設備投資はリーマンショック以降、おおむねプラス成長で推移している。13年半ば以降は、前期比年率4~5%台の成長で推移しており、13年10~12月期は前期比年率5.7%増となった。なお、13年12月の設備投資減税終了に伴い、機械機器投資8が同10%を超えるなど駆け込みの影響もあったものとみられる(第1-2-1-21図)。
一方、構築物投資、知的財産投資9は過去の減税失効時10
ほど駆け込みの動きがみられなかったことから、14年1~3月期の設備投資は前期比▲2.1%となり、反動減は軽微なものにとどまった。
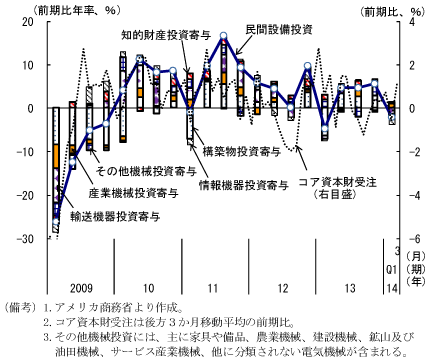
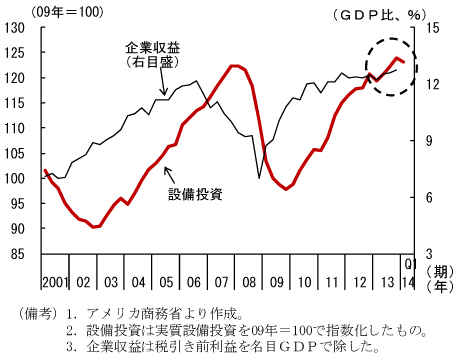
設備投資を過去の回復期と比較すると、今回は景気後退が深刻で落ち込みが大きく、14年1~3月期では世界金融危機前の景気の山の水準は回復しているものの、回復のテンポはやや弱めになっている(第1-2-1-23図)。
項目別では、構築物投資の回復は過去の回復期においても、総じて緩慢となっている。大幅な増産に結び付く大規模な投資を控え、機器の稼働率や雇用者による調整を行う傾向があるものとみられる11。
また、今回の回復期における構築物投資は、鉱業部門がシェール革命により過去の回復期を大幅に上回って推移しており、それを除いた部分は更に弱いといえる12。一方で、更新サイクルの短い知的財産投資(ソフトウェア投資)や、機械機器投資は堅調に拡大しているものの、13年12月で失効した設備投資減税等の政策効果による面も大きい。
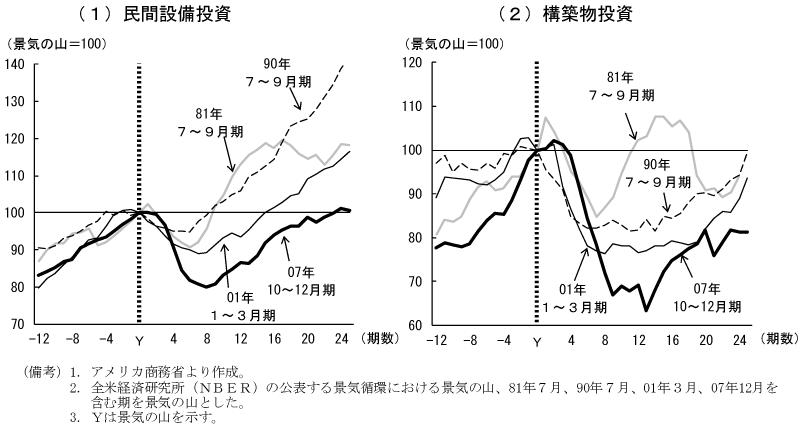
次に企業収益についてみてみると、企業収益は堅調に推移している(前掲第1-2-1-22図)。現在の景気回復局面において、企業は余剰資金を設備投資よりも自社株買いや配当に回す傾向にあり、直近も大きな変化はみられない。内部留保の増加、緩和的な金融環境や、長期金利も過去と比較すると低位で安定しており、引き続き設備投資環境は良好といえる。米大手金融機関の調査13では、投資を控えることは長期的には企業価値低下を招くことから企業に対し増益を事業拡大にいかすべきとの指摘もあり、今後の企業の投資行動が注目される。
鉱工業生産の動向をみると、13年7~12月期にかけて持ち直しの動きが顕著となり、13年10~12月期は前期比年率4.6%増と堅調に推移した。13年12月から14年2月にかけての大寒波の影響により、14年1月は総合で前月比▲0.2%、製造業で▲0.9%となっている14(第1-2-1-24図)。しかし、直近の指標は回復を示しており悪化は一時的であったとみられる。また稼働率は08年以来の高水準となっている。
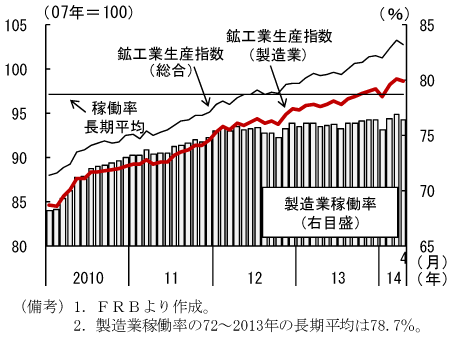
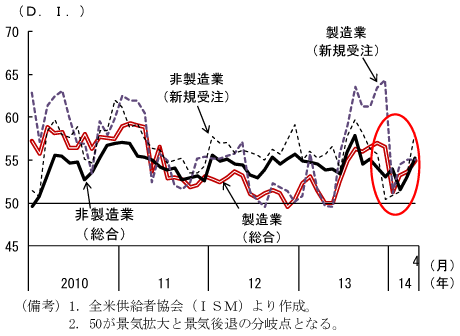
寒波の影響は企業のマインドに顕著に現れている。製造業、非製造業ともに13年12月から14年2月にかけて低下している(第1-2-1-25図)。しかし、改善と悪化の分岐点である50を上回って推移していることから、寒波の影響は限定的だったとみられる。
ISMの景況調査における企業のコメント15においても、13年12月~14年2月は天候による悪影響を指摘するコメントが多くみられたが、3~4月のコメントは楽観的なものとなっており、直近の堅調な経済指標と整合的である。
また、総労働時間を生産活動の代替指数として回帰してみると相関がみられる(第1-2-1-26図)。金融危機後の景気の谷である09年6月前後で比較すると、製造業において生産性が向上した可能性がある。これは企業が危機後に雇用者を減少させていく中で、IT化、省力化を進めたことが要因といえる。
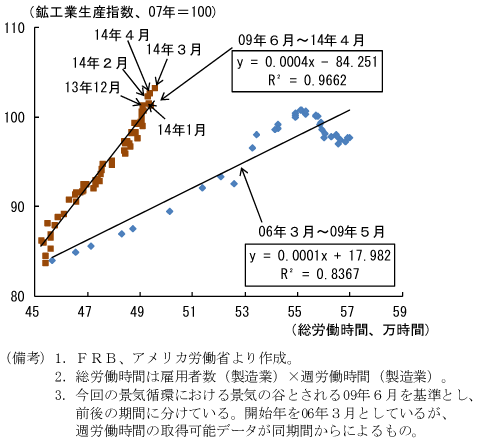
また、業種別に鉱工業生産を過去の回復期と比較すると、落ち込みが大きく、景気の山の水準は回復しているものの、回復ペースは緩慢となっている(第1-2-1-27図)。鉱工業生産の約7割を占める製造業生産は景気の山の水準に回復していない。そのうち耐久財は主要な機械、コンピュータ電子機器、自動車がけん引し回復しているが、非耐久財の回復は緩慢で化学製品等の回復が弱い。
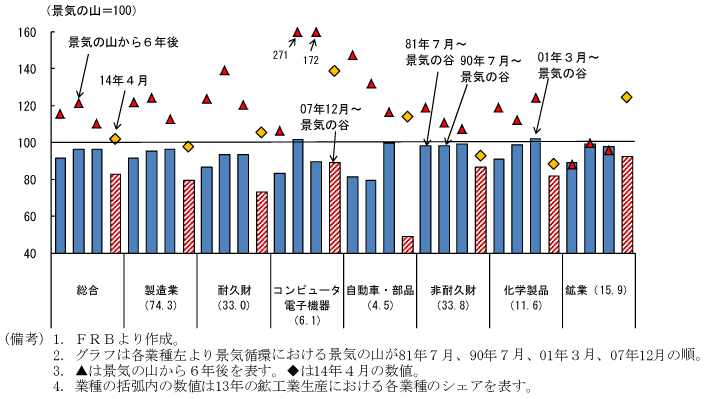
設備投資の先行きとして、フィラデルフィア連銀とニューヨーク連銀が行う設備投資計画をみると、14年初の寒波の影響により低下したが、悪天候の影響が解消されたとみられる4月調査以降では1~2月より回復している16。
また、フィラデルフィア連銀が実施している14年3月の特別調査では、14年の設備投資計画を増加するとの割合が13年と比較すると約10%ポイント増加しており、売上げの増加や更新需要を受けて、企業経営者の設備投資マインドは高まっている(第1-2-1-28図)。その他の調査でも設備投資に対する意欲は総じて上昇している17。企業が設備投資に踏み切ることを抑制する要因であった財政をめぐる先行き不透明感が解消されていることが、企業経営者の投資マインドを下支えしているとみられる。
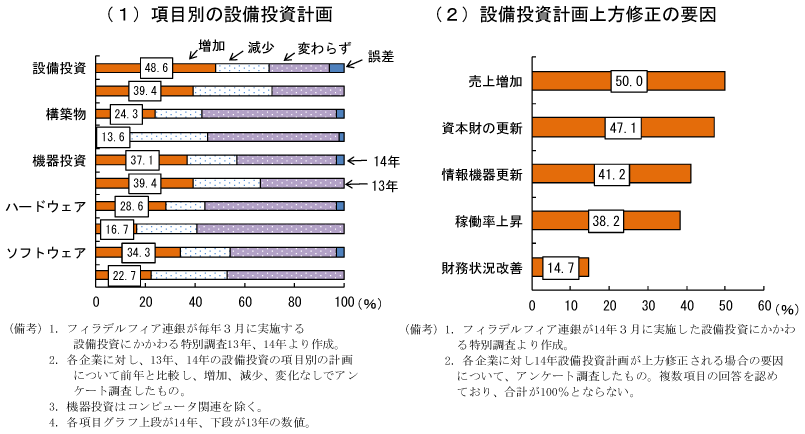
在庫投資の動きをみると13年7~9月期に急伸した(第1-2-1-29図)。これは国内需要の増加、ヨーロッパや中国に持ち直しの動きがみられるなど、海外需要増加期待もあり在庫投資に動いたとみられる。リーマンショック後に圧縮された在庫残高の復元もおおむね終了している中、企業行動の積極化が反映されている。在庫の内訳をみると、大寒波による小売売上の減速もあり小売在庫が増加している(第1-2-1-30図)。意図せざる在庫増との指摘もあるが、在庫販売比率の推移をみると金融危機前とおおむね同水準であり、それほど過剰感はないとも考えられる。ただし今後在庫投資の伸びは鈍化するものとみられ、14年半ばにかけて経済成長率を下押しするといった指摘もなされている。
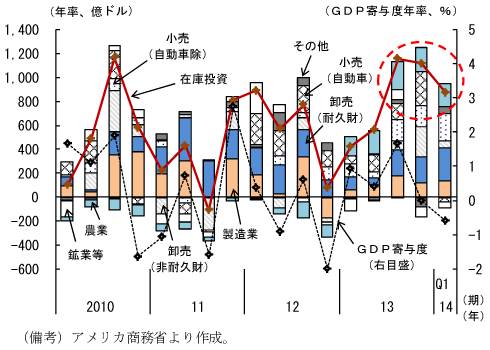
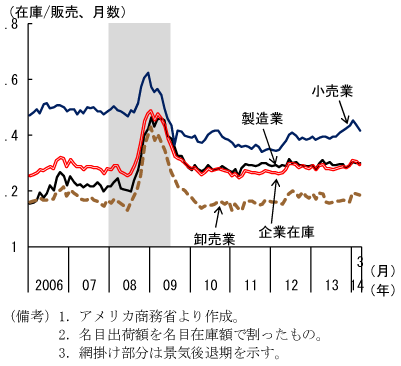
今後14年4~6月期以降の企業部門は、大寒波による影響が解消され、回復基調が続くとみられる。ただし、13年末の回復トレンドに回帰し持続的な回復を歩むことができるか、動向が注目される。
(2)財政政策をめぐる政府の動向
(i)当面回避された財政問題
いわゆる「財政の崖」、歳出の自動削減、債務上限問題等、財政問題はその対応ぶりも含めて断続的に景気に対してマイナスに影響したとされる18。14年度に入っても、当初は暫定予算すら成立せず、債務上限の引上げをめぐるオバマ大統領・議会民主党と議会共和党との間の調整は不調に終わり、96年以来の一部連邦政府機関閉鎖という事態が発生するとともに、米国債のデフォルト懸念が非常に高まった19
。
13年10月1日以降、連邦政府機関の閉鎖が2週間以上続く中、10月16日に1月までの暫定予算が認められ、債務上限問題についても14年2月まで上限を設けないことが両党の間で合意された。これにより連邦政府機関の閉鎖や米国債のデフォルト懸念が当面回避されることになったが、14年度暫定予算等が成立してから3~4か月間という期間で、何度も調整が不調に終わり解決できなかった問題が進展するのか、引き続き市場等の注目を集めた。しかし、これらの財政問題は14年11月に行われる中間選挙に向けて与野党の利害が一致20したことから、13年12月に14年度本予算が成立するなど、13年12月以降相次いで進展がみられた(第1-2-1-31表、第1-2-1-32図)。
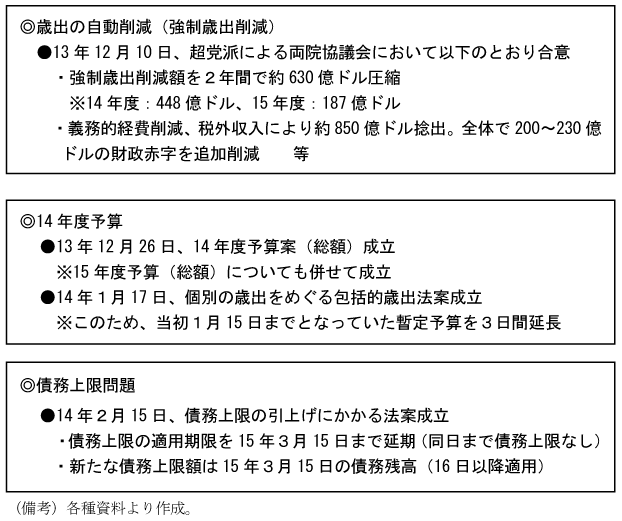
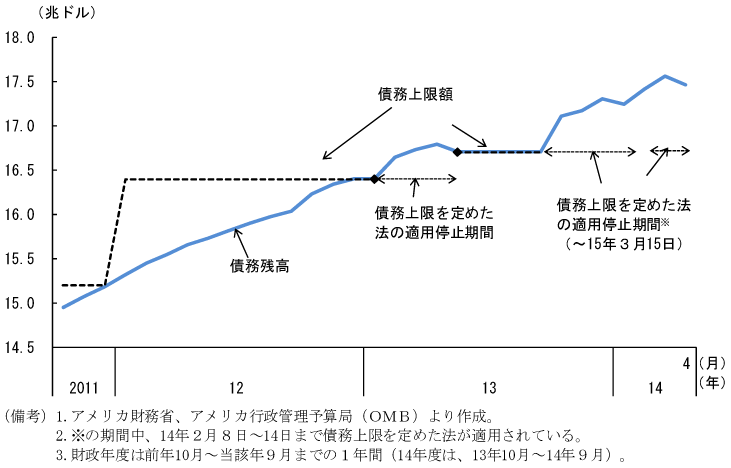
一方で、例えば、歳出の自動削減等は、短期的には景気下押し圧力となったものの、結果として財政収支を改善させる効果を発揮した21(第1-2-1-33図)。13年は、いわゆる「財政の崖」に伴う増税と歳出削減、加えて政府支援機関(GSE)からの配当金の国庫への充当から財政赤字が大きく減少しており、その後も景気が順調に回復すれば、18年にかけて財政赤字は低下していくとみられている22
。
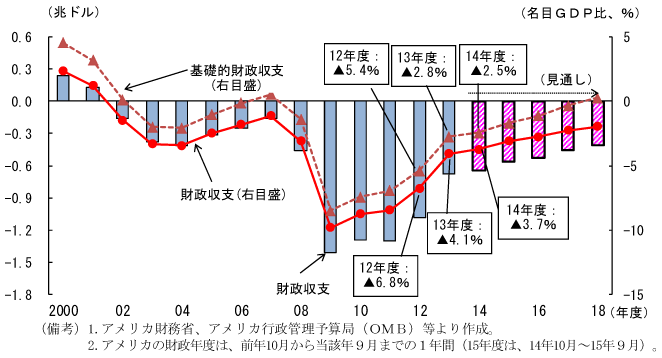
(ii)財政をめぐる動き
例年2月に公表される予算教書23は、予算の成立が遅れたことから15年度は14年3月に公表された。歳入面では、中間層の強化に向け減税を実施する一方で、富裕層に対する税負担を強化することとしており、歳出面では引き続き歳出削減に向けた努力を続けるとしている(第1-2-1-34表)。
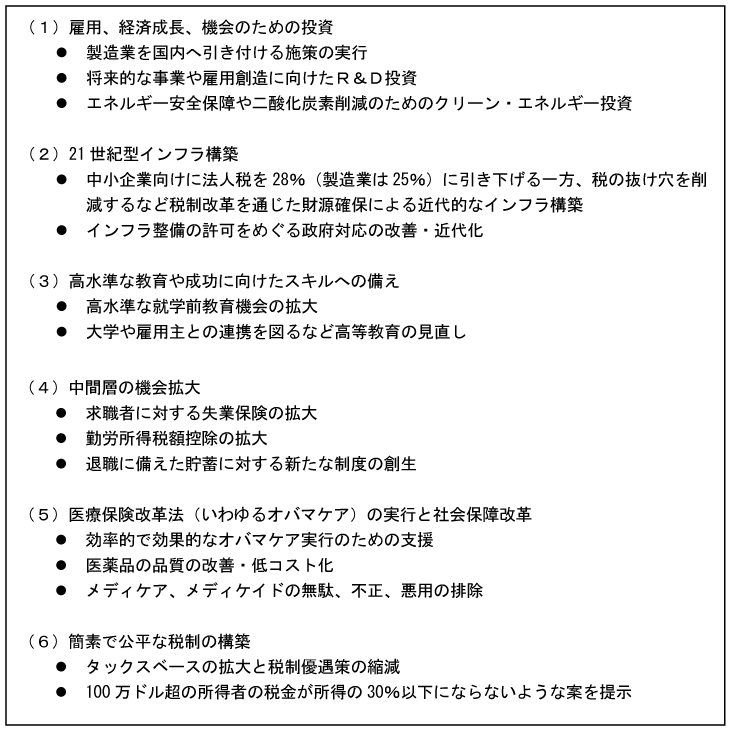
(3)金融政策の動向
(i)資産購入額縮小の影響
FEDは13年12月、12年9月に開始した追加金融緩和(いわゆるQE3)の縮小開始を決定した。同時に、フォワードガイダンスに、「失業率が6.5%を下回っても、物価上昇率が委員会の長期目標である2%を下回り続けると予想されれば、十分な期間(well past the time)現在のFFレートを維持することが適切になるだろうと引き続き予想する」との文言が追加された。また、バーナンキFRB議長(当時)は記者会見において(資産購入の縮小ペースはデータ次第と前置きした上で)「各FOMCで慎重な縮小を続け、14年後半に終了する」との見通しを示した。市場では各FOMCで100億ドルずつ資産購入額を減額し、14年10月もしくは12月のFOMCにおいてQE3の終了を決定するとの見方が大勢となっている。
新興国通貨の下落時等、縮小ペースを緩めるとの見方も一部で出る局面もあったが、14年4月までの各FOMCで100億ドルずつ減額が継続し、14年5月からは毎月450億ドル(国債250億ドル、MBS200億ドル)まで減額が進んでいる。
14年3月、イエレンFRB議長体制での最初のFOMCにおいては引き続きQE3縮小を決定、フォワードガイダンスについて修正を行った。失業率6.5%を利上げ検討のしきい値としていたものは取りやめ、幅広い情報から判断することが改めて示された。
(ii)最近の雇用情勢
イエレン議長は14年3月の講演において、労働市場には相当なスラック(considerable slack)があるとし、その証左として、第一に経済的理由によるパートタイム労働者の多さ、自発的退職者数の少なさ、第二に過去の景気回復局面と比べて失業率の低下が賃金の上昇に結び付いていないこと、第三に長期失業者24の割合の高さ、第四に労働参加率の低下、を挙げた。以下では、これらの現状から労働市場の回復の程度を分析する。
経済的な理由でパートタイム労働に従事している労働者の就業者に占める割合は金融危機後に急増した。同割合のその後の低下ペースは緩慢であり、過去の景気回復局面と比べても、依然として高水準にある。(第1-2-1-35図)。14年2月のベージュブックでは非正規(temporary)雇用から正規(permanent)雇用への転換が進んでいる地区も報告されており、労働市場の改善を示唆していると考えられる。
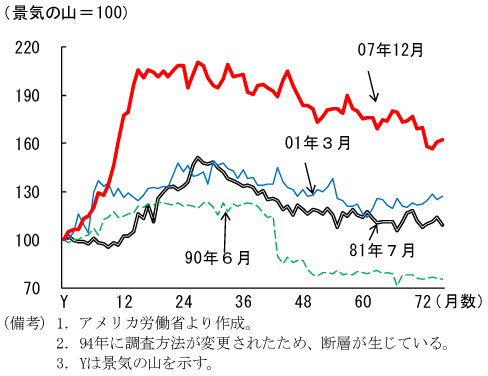
新規就業者、離職者ともに増加しており、労働市場が活発化している様子がうかがわれる(第1-2-1-36図)。離職者の内訳をみると、解雇等による離職者はおおむね横ばいで推移している一方、自発的な離職者は増加している(第1-2-1-37図)。自発的な離職はキャリアアップ等が理由と考えられ、その増加は労働市場の改善を示唆していると考えられる。
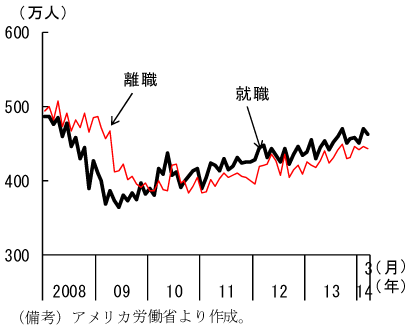
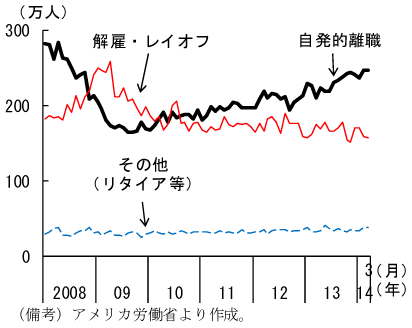
報酬をみると、危機後に伸びは低下し、12年以降は前年比2%程度で横ばいとなっている(第1-2-1-38図)。要因としては、パートタイム労働者の割合が金融危機後に高まり、そのまま高止まりしていることが考えられる。パートタイム労働者はフルタイム労働者と比べて時間当たり報酬が半分程度であり、景気回復局面において伸びも低くなっていた(第1-2-1-39図)。ただし、13年10~12月期の伸びはおおむね同水準となっており、前述のとおり非正規雇用から正規雇用への転換が進んでいることにかんがみれば、今後は報酬の伸びが高まっていくことが期待される。
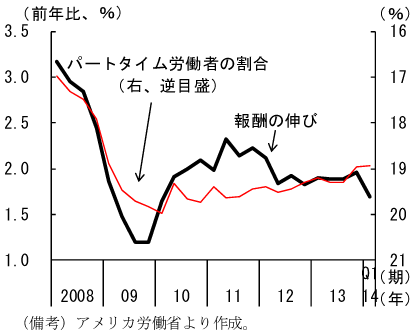
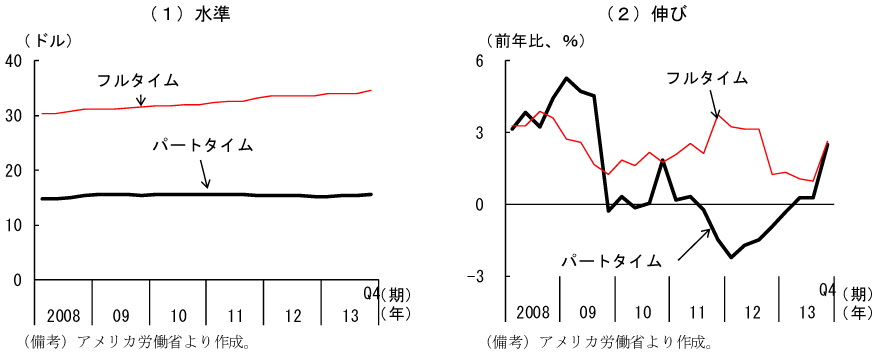
景気回復局面での短期失業率と賃金上昇率の関係をみると、まず短期失業率がおおむね横ばいの状態で賃金上昇率が低下、次に短期失業率は改善するものの賃金上昇率はおおむね横ばい、最後に短期失業率が4%を下回る水準まで改善すると賃金上昇率が加速する、といった経路をたどる傾向がうかがわれる(前掲第1-1-3-2図)。14年4月の短期失業率は4.1%となっており、今後も労働市場の改善が続けば賃金上昇率が加速する可能性がある。ただし、過去の景気回復局面と比べ、高い長期失業率、パートタイム労働者数の多さなど異なる点も多数あり、イエレン議長は14年4月の講演において、「短期失業の方が長期失業より物価上昇率に与える影響が大きい」といった研究25について、正しいかどうか判断を下すのは「時期尚早」と述べている。
長期失業者数は世界金融危機後に急速に増加した。その後、減少はしているもののそのテンポは緩やかであり、過去の景気回復局面と比べても高水準にある(第1-2-1-40図)。
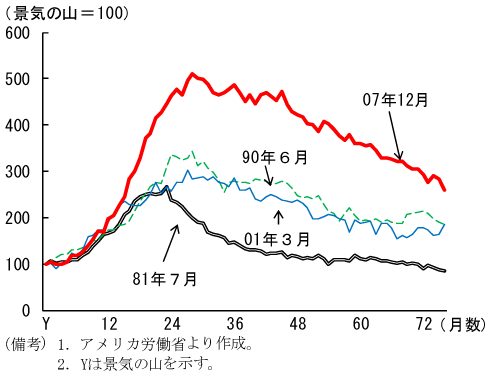
労働参加率と高齢化率26の関係をみると、2000年頃までは高齢化は進展しているものの、多くの女性が労働市場に参入したことにより労働参加率は上昇した27
(第1-2-1-41図)。以降は女性の労働市場への参入が一服したこともあり、高齢化の進展とともに労働参加率は低下している。13年は特に低下のペースが速かったが、13年10月以降、変動はあるもののおおむね横ばいとなっている(第1-2-1-42図)。CBO28
によると、07年から13年にかけての労働参加率の低下のうち、半分程度が高齢化、残りの半分程度が就職をあきらめた人の存在、就業機会のミスマッチと推計されている。雇用者数やパートタイム労働者数は雇用環境の改善を示唆しており、就職をあきらめた者が労働市場に戻ってきた結果、労働参加率は短期的には下げ止まりの兆しがみえていると考えられる。
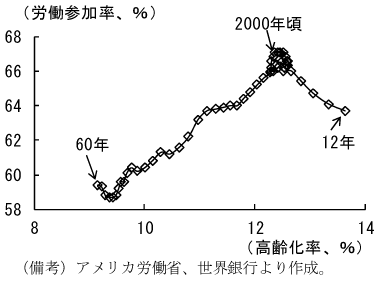
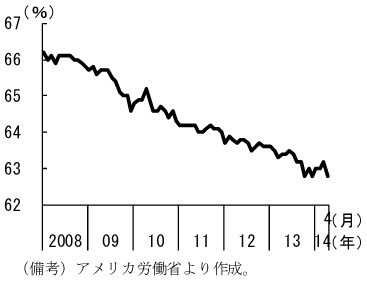
(iii)最近の物価動向
物価上昇率については14年3月のPCE総合は前年比1.1%、PCEコアは同1.2%とFEDの長期的な目標である2%を下回る状態が続いている(第1-2-1-43図)。
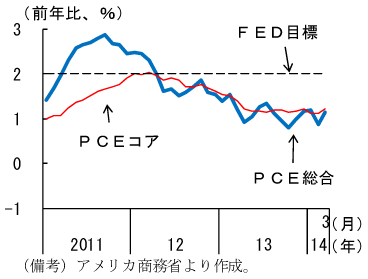
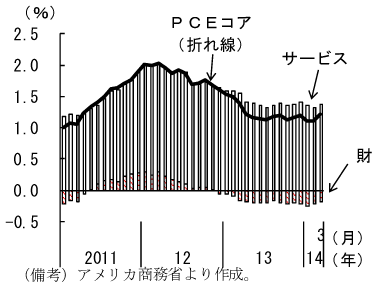
PCEコアの項目別寄与をみると、13年1月以降、財についてはマイナス寄与が続いている(第1-2-1-44図)。ドルの増価により輸入物価が前年比マイナスで推移していることが影響していると考えられる。一方、サービスについては13年4月に一段と寄与が低下した。これは歳出の自動削減により医療費の削減が行われ、ヘルスケアサービスの価格が低下したためと考えられる。前年比でみると14年3月に影響が一巡することから今後はサービスの上昇への寄与が大きくなるとの見方もある。

