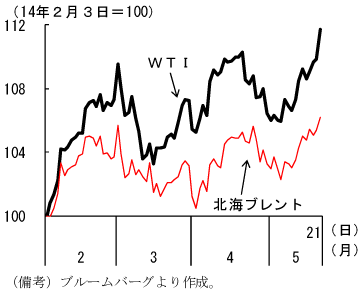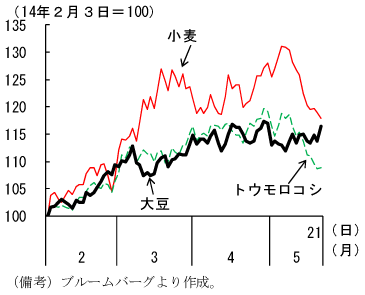第1節 世界経済の概観
1.世界経済の現状
(1)13年以降の世界経済の動向:先進国で回復モメンタムが強まる
世界の景気動向について、G20諸国合計の実質経済成長率をみると、2012年は欧州政府債務問題の影響で伸びが低くなったが、13年から14年にかけては、緩やかに回復し、成長率は各四半期前期比年率3%前後で推移している(第1-1-1-1図)。この中では、先進国では全体として回復基調がより明確となる一方、中国やその他新興国では景気の拡大テンポが緩やかとなり、成長の重心が新興国から先進国に若干移動した格好になっている。
アメリカでは、家計債務の減少が既に一段落している中で、雇用・所得・消費の回復が継続している。13年10月の政府閉鎖や冬季の寒波・大雪の影響にもかかわらず、回復モメンタムが持続している。ヨーロッパは、回復力は弱いものの、13年4~6月期にプラス成長に転換した後は、次第に上向きの動きが定着しつつある。新興国は13年半ば以降の通貨下落等の国際金融面の不安定性がみられる中で、成長率の若干の低下がみられている。他方、新興国の中でも通貨下落の影響がほぼなかった中国は、14年初より成長率に低下がみられている。
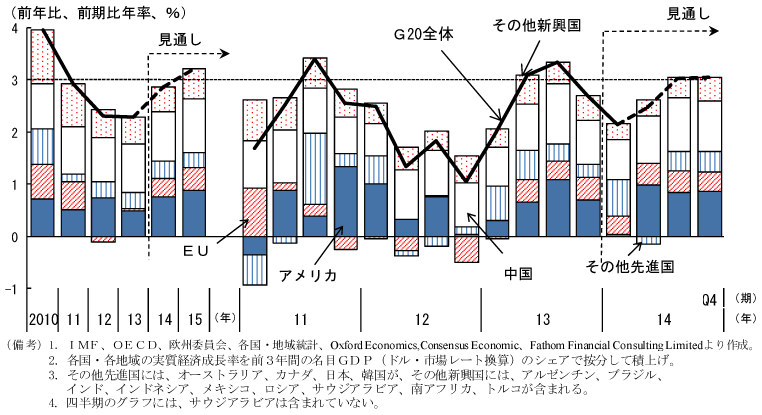
(2)世界の生産・貿易の動向
世界の生産及び貿易は、13年以降は回復基調がやや強まっている(第1-1-1-2図)。ただし、貿易は14年1~3月期に若干低下がみられる。
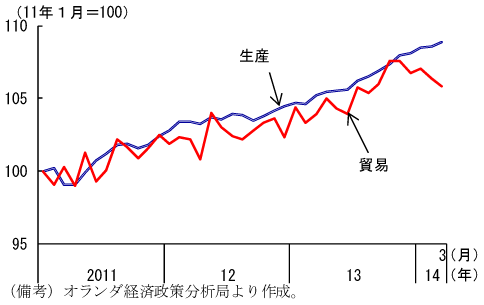
先進国と新興国の貿易の状況を確認すると、先進国については、新興国向け、先進国向けともに輸出は底堅い動きとなっている(第1-1-1-3図(1))。一方、新興国では輸出は増加基調にあるが、新興国から先進国向けは総じて増加しているものの、13年後半は中国向けが鈍化した。また、直近では寒波の影響によるアメリカの一時的な需要後退の影響もあり、アメリカ向けの輸出が若干低下している。
生産は、先進国を中心として回復傾向にある(第1-1-1-3図(2))。先進国は、13年後半以降日本を中心に増加しており、アメリカ ユーロ圏でも持ち直しており、世界全体として生産の回復をけん引している。一方新興国は、13年後半以降、アジア新興国の生産の伸びが鈍化しているほか、石油需要が伸びない中でアフリカや中東の生産が減少しており、総じて伸びが鈍化している。
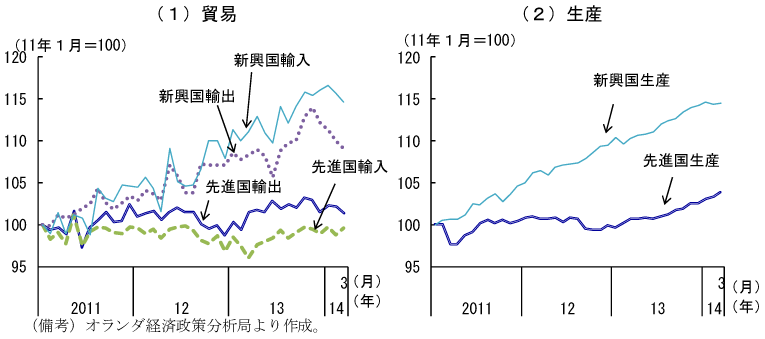
各国の経常収支については、12年以降のユーロ圏の黒字化とその拡大、12年後半以降の中国の黒字拡大1及び12年以降の新興国の赤字の拡大がみられる(第1-1-1-4図)。
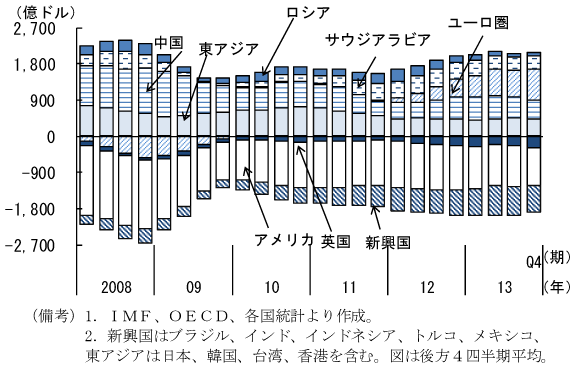
ユーロ圏については、12年は財やサービス輸出の増加が輸入の増加を上回ることで黒字の拡大に寄与していたが、13年4~6月期以降の黒字の拡大は、財輸出の増加に陰りがみられる一方で、内需の低迷による財輸入の減少と所得支払の減少によってもたらされている(第1-1-1-5図)。
これに対応する形で、赤字幅が12年以降、13年半ばにかけて拡大しているのが新興国である。13年半ばから新興国をめぐる国際金融の不安定性がみられた背景に、こうした対外的不均衡の変化があったことを指摘できる。
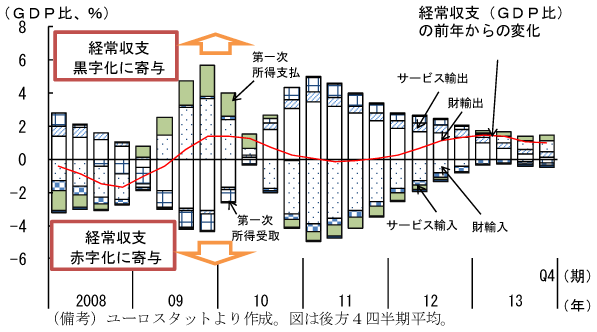
(3)金融緩和の状況と課題
世界の物価動向をみると、先進国では物価上昇率が低位に落ち着いている。他方、中国以外の新興国では物価上昇率に高止まり傾向がみられる(第1-1-1-6図)。
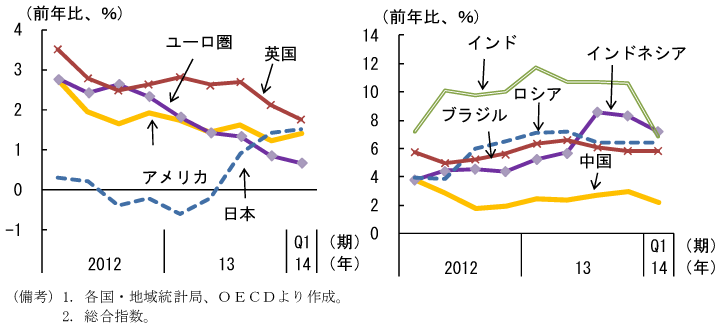
住宅価格の動向をみると、上昇している国が多くなっている。また、住宅価格の上昇度合いをみると、多くの国においては、名目経済成長率を上回っている(第1-1-1-7図)。先進国では、英国、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリアで上昇が大きい。また、ユーロ圏では全体としては低下しているものの、ドイツでは名目経済成長率を上回る上昇がみられる。新興国では、インド、ブラジル、インドネシア、南アフリカ、メキシコ等の経常収支赤字を抱え高インフレの国を中心に住宅価格も上昇している。
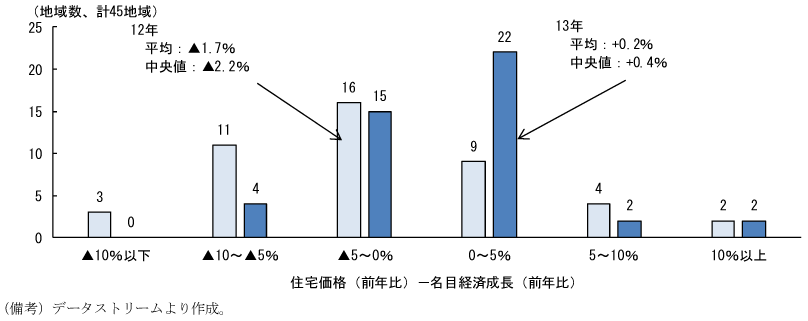
また、住宅価格上昇の背景には、主要中央銀行の金融緩和姿勢がある。マネーサプライは、アメリカ、カナダ、ユーロ圏で拡大が続いているのに加え、英国では13年以降に増加に転じている(第1-1-1-8図(1))。一方、中国以外の新興国では、金融引締めの影響もあり低下傾向にある。加えて、家計債務は一部の主要国・地域で高水準にある(第1-1-1-8図(2))。家計債務の推移をみると、住宅価格の上昇がみられるシンガポール、香港、ニュージーランド等で所得の上昇を上回るペースで拡大している。英国では11年以降は低下傾向となっているものの、家計債務所得比率の水準は比較的高い状況にある。
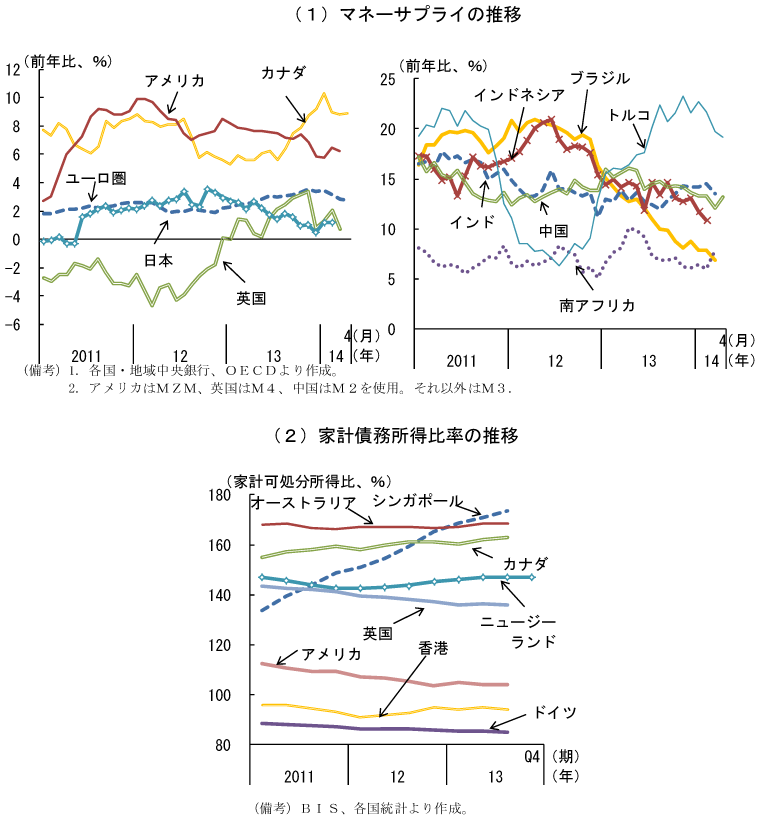
以上のように、世界の各地域では先進国を中心として世界金融危機以降の回復がみられるが、景気の局面は異なっており、これに合わせてマクロ経済政策の運営も異なっている。
先進国では、アメリカで量的緩和の縮小を進めており、政策金利は相当の期間、低水準に維持されるとみられているが、その後の利上げも議論されている。回復が遅れているユーロ圏はデフレリスクも散見される中で追加緩和が検討されている状況である。一方、一部の先進国では物価上昇率は低いものの住宅価格の上昇や信用拡大が注目されており、例えばニュージーランドは利上げを開始するなど、こうした国での金融政策をめぐる議論が注目される。新興国では、通貨不安定の中でインフレ高止まり等への対応の観点から、インド、インドネシア、ブラジル、トルコ等で利上げを行った。
2.世界経済の見通しとリスク
(1)世界経済
世界の景気は、中国や新興国等一部に弱さがみられるものの、アメリカの緩やかな回復やヨーロッパの持ち直し等、全体として緩やかに回復している。以下では、15年までの経済見通しとそのリスク要因について概説する。
(i)経済見通しとメインシナリオ
アメリカ経済の緩やかな回復、ヨーロッパ経済の持ち直しが続くこと等により、緩やかな回復が続くと期待され、14年にはおおむね3%、15年にはおおむね3%台半ばの成長となることが見込まれる。この数値は、国際機関や民間機関の見通しと比較しても整合的であるといえる(第1-1-2-1図、第1-1-2-2表、第1-1-2-3表)。
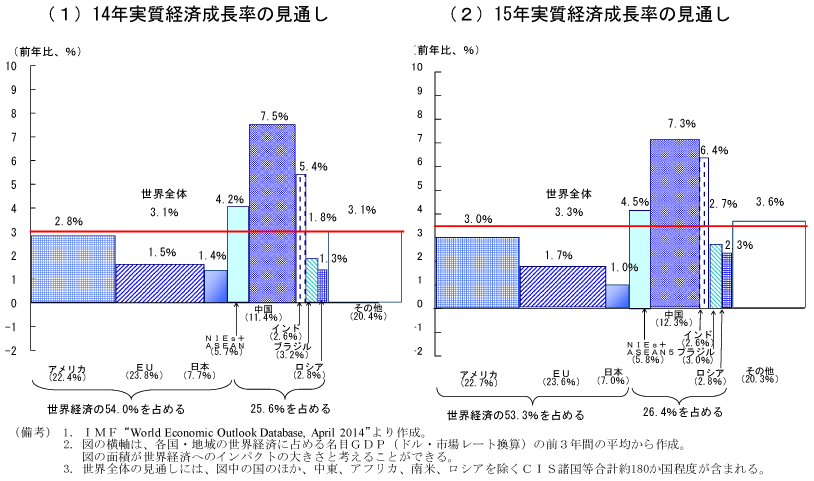
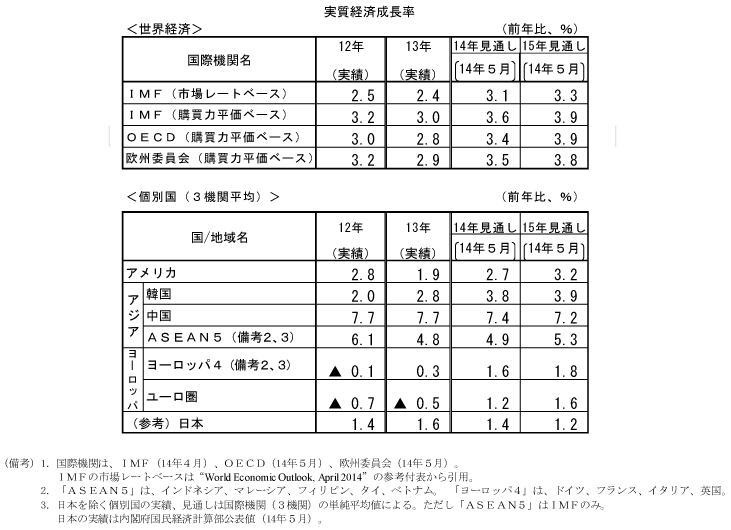
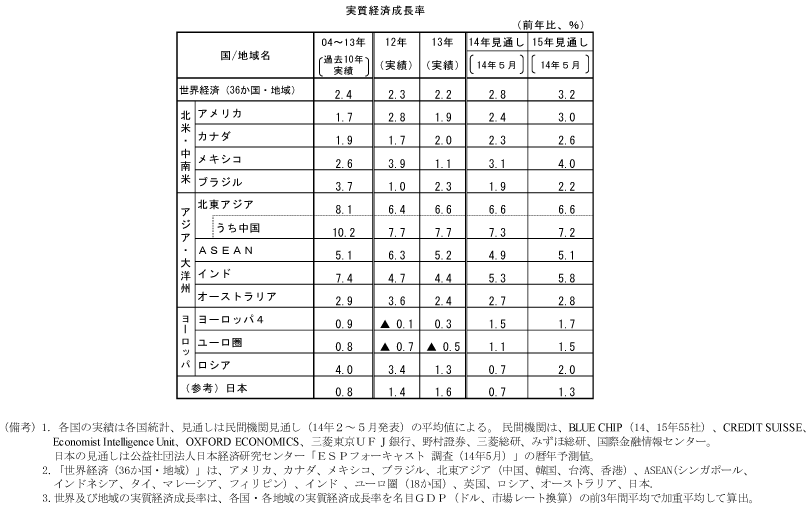
(ii)経済見通しに係るリスク要因
アメリカにおいては、金融緩和縮小に伴い想定以上に金利が上昇し、成長が鈍化するリスクがある。
ヨーロッパにおいては、ユーロ圏の低インフレが長期化し、期待インフレが低下した場合、実質債務負担の増加や実質金利の上昇等により景気が下押しされる懸念がある。また、南欧諸国等の財政の先行きに対する不安が再燃した場合の金融面への影響に留意が必要である。
中国においては、理財商品等のデフォルト懸念等から信用リスクが高まり、金融市場が急激に収縮するリスクがある。また、過剰な不動産投資や生産能力の抑制によって金融や実体経済が想定以上に急激に縮小する懸念がある。
その他の新興国においては、アメリカの金融緩和縮小に伴う金融市場の不安定化が再燃するリスクがある。また、新興国通貨下落を防ぐための金融引締めによる景気減速懸念がある。
加えて、ウクライナ情勢等をめぐる地政学的リスクの高まりによって国際商品価格の急騰等が引き起こされるリスクがある。なお、VIX指数2の推移をみるとおおむね安定して推移しており、地政学的リスクが国際金融市場に与える影響は今のところ限定的であるといえよう(第1-1-2-4図)。
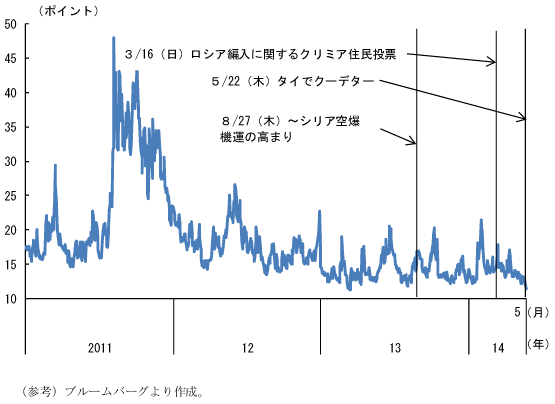
(2)アメリカ経済
(i)経済見通しとメインシナリオ
アメリカ経済は、雇用者数の増加が続いていることに加え、個人消費が緩やかに増加するなど、緩やかな回復を続けている。14年1~3月期の実質経済成長率は大雪・寒波の影響もあったことから、前期比年率0.1%にとどまったものの、基調としては緩やかな回復が続くと見込まれる。
国際機関等の見通しをみると、14年は2%台後半、15年は3%を上回る成長率が見込まれている(第1-1-2-5表)。

(ii)経済見通しに係るリスク要因
経済見通しに係るリスクバランスは依然として下方に偏っており、中でもFEDの資産購入額縮小の住宅投資等への影響に注視する必要がある。
(ア)下振れリスク
- 資産購入額縮小に伴う住宅投資等の減少
FEDは13年12月に追加金融緩和(いわゆるQE3)の縮小開始を決定しており、資産購入額は、14年5月からは毎月450億ドルまで減額されている。こうした動きが想定以上に金融市場に影響をもたらす場合には、住宅ローン金利の上昇を通じて住宅市場が冷え込むおそれがあり、また、耐久消費財の購入等にも悪影響を及ぼす可能性がある。
- 新興国経済の減速長期化
新興国は、資源を始めとする先進国の輸入動向によって経済が左右される面が強く、先進国の景気下振れ等によって、新興国の成長鈍化が長期化する場合、当該国への輸出減少を通じてアメリカの景気が下押しされるおそれがある。
(イ)上振れリスク
一方、メインシナリオの想定以上に景気回復のテンポが加速する場合の要因としては以下が考えられる。
- 資産価格の上昇
雇用環境の改善や企業業績の好調が持続し、また、金融政策における資産購入額の縮小及びその不透明感による影響が軽微にとどまり、株価や住宅価格が更に上昇する場合、家計のバランスシート調整が大きく進展して家計の負担が一層軽減されるとともに、資産効果を通じて個人消費が拡大する可能性がある。
- 信用リスクの低下
景気の回復や住宅価格の上昇に伴って、金融機関の家計に対する信用リスクが低下し、また、資産購入額の縮小及びその不透明感による影響が軽微にとどまることにより、金融機関の信用創造が喚起され、貸出が増加する場合には、個人消費や住宅投資が拡大する可能性がある。
(3)ヨーロッパ経済
(i)経済見通しとメインシナリオ
ヨーロッパ経済は、英国で回復していることに加え、ユーロ圏もドイツがけん引する形で持ち直しの動きが続いていることから、全体としては持ち直している。
先行きについてみると、金融市場の緊張緩和及び財政再建ペースの減速による消費や投資の増加に加え、アメリカ等の域外経済の回復に伴って輸出が増加することによって、持ち直しが続くとみられる。国際機関等の見通しをみると、14年、15年と成長率が加速することが見込まれている(第1-1-2-6図、第1-1-2-7表)。
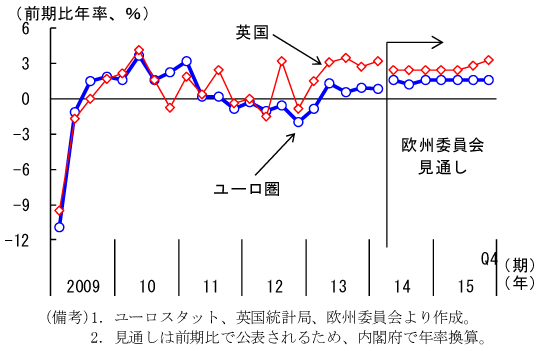
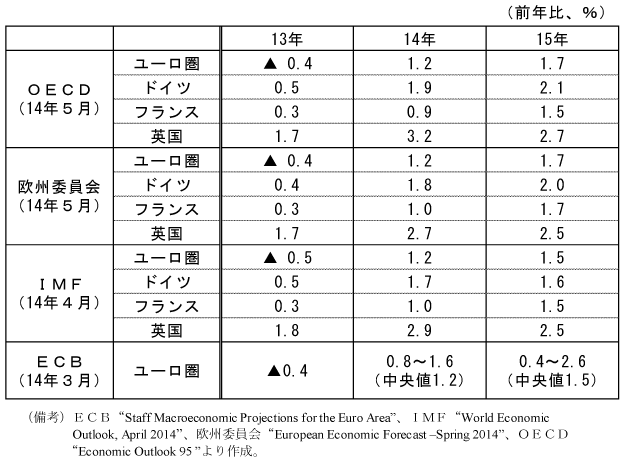
(ii)経済見通しに係るリスク要因
経済見通しに係るリスクバランスは下方に偏っており、特に欧州政府債務問題が再燃した場合は、世界経済にも重大な影響を及ぼす可能性がある。
南欧諸国等の国債利回りやソブリンCDSは、各国の財政再建に向けた取組やECBを中心としたユーロ圏レベルでの様々な対策により大幅に低下しており、13年12月にアイルランド及びスペイン、14年5月にポルトガルが予定どおり支援プログラムを終了した。しかし、ギリシャに対する追加支援問題等、先行きに対する懸念は依然存在している。欧州政府債務問題が再燃した場合は、ヨーロッパ経済全体に対する不確実性が再び高まり、企業や消費者の先行き見通しの悪化等を通じて、景気に対する大きな下押しリスクとなる。
また、ユーロ圏の主要輸出先であるアメリカや、近年シェアを高めているアジア経済が減速した場合、景気のけん引役である輸出が減少する上、生産や消費に対するマイナスの波及効果が考えられることから、景気に対する下押しリスクとなる。
さらに、ユーロ圏の失業率は引き続き高水準で推移しており、失業率が高止まりした場合は、所得や消費者マインドの悪化を通じて個人消費を下押しするリスクがある。
他方、物価上昇率は低水準で推移しており、低インフレが長期化し、期待インフレが低下した場合は、実質債務負担の増加や実質金利の上昇等により、景気が下押しされるリスクがある。
(4)アジア経済
(i)経済見通しとメインシナリオ
中国では、12年以降、実質経済成長率は前年比8%を割り込み、14年1~3月期は同7.4%まで低下し、景気の拡大テンポは緩やかになっている。先行きについては、政府の構造改革等と景気のバランスを重視した経済運営が円滑に進展し、緩やかな拡大傾向が続くと期待される。
韓国、台湾では、景気は持ち直しており、先行きについては、持ち直し傾向が続くと見込まれる。
ASEAN諸国では、景気は足踏み状態となっており、先行きについては、比較的堅調な内需とともに、ほかのアジア地域同様、世界景気の底堅さが増すことに従い外需も回復し、全体として再び持ち直しに向かうと見込まれる。
インドでは、成長率は12年以降低い伸び率にとどまっており、景気は底ばい状態が続いている。先行きについては、新政権の発足とともに、センチメントの改善や投資の持ち直し等により成長率は回復に向かうことが期待されるが、当面は過去のトレンドより低めの成長となることが見込まれる。
国際機関の見通しをみると、14年に中国は政府目標でもある7.5%前後、韓国、台湾は3%半ば、ASEAN諸国は4%台前半、インドは5%程度の成長率が見込まれている(第1-1-2-8表)。
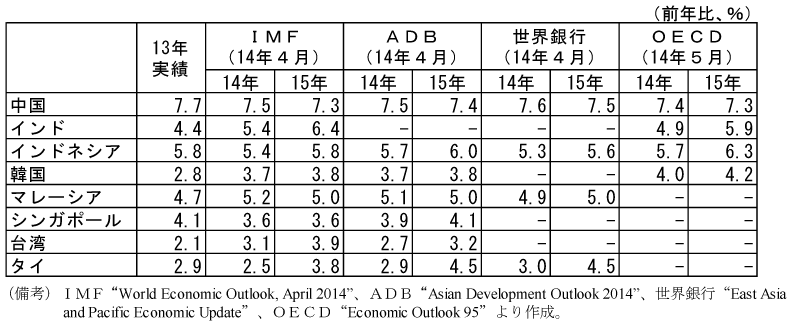
(ii)経済見通しに係るリスク要因
経済見通しに係るリスクバランスは下方に偏っている。
中国では、13年秋以降、政府の不動産価格抑制策の影響により、不動産価格はこれまでの上昇局面から反転し伸びが鈍化しており、不動産投資は先行指標を含め、弱い動きがみられる。今後、不動産価格に大幅な下落が生じる場合には、地方政府の財政悪化等が引き起こされ3、シャドーバンキングを通じた金融危機の発生や、投資等の実体経済が急激に冷え込む可能性もある。
その他、アメリカの金融政策の変更の影響も引き続き注視が必要であろう。最終需要地である欧米景気を通じた輸出への影響、株価下落等の資産効果を通じた個人消費の鈍化や信用収縮に伴う資金調達コストの増加による投資の抑制といった内需の縮小等が考えられる。
アジア地域全体では、中国の景気の拡大テンポの鈍化により、景気回復に足踏みが生じるおそれがある。
3.世界経済の主要リスクとその動向
世界経済は、先進国を始めとして緩やかに回復しており、14年にかけて全体としては経済成長率が上昇することが見込まれる。その実現のためには、主要なリスクの回避が課題となる。すなわち、アメリカの金融緩和縮小の円滑な進展、ユーロ圏のデフレ転落の回避、新興国をとりまく国際金融の安定化、中国の金融リスクの鎮静化、ウクライナ情勢の安定化である。
以下では、こうした課題について概観し、併せてリスクの顕在化をみる上で注視すべき指標等について簡単に整理する。
(1)アメリカの円滑な金融緩和縮小
アメリカの金融緩和の縮小(いわゆる「テーパリング」)や利上げといった政策変更においては、市場や経済の動向に急変がないように推移することが重要である。13年5月以降のテーパリング議論の際には,金利が急上昇し、住宅投資等に金利先高感から一定程度の下押しになったと思われる。市場の行動が、経済的な「事実」だけでなく、市場参加者の「認識」に大きく左右されることを踏まえれば、後者に影響する政策議論の展開も注目されるところである。そこで以下では、量的緩和が導入された際に示された量的緩和の「コストとベネフィット」という視点に沿って、政策議論を整理し、政策の観点から重視される指標の動きを概観する。
まず、量的緩和のコストについては、それによる低金利の下で過度なリスクテイクが行われることが挙げられる。実際に、テーパリングについてバーナンキ議長が発言した5月にかけて高リスクの社債の発行が増加した4。その後の動きについて確認してみよう。
株価の動きをみると、ダウは年末にかけて史上最高値を更新するなど比較的好調に推移し、リスクの高い株式が多いと考えられるNASDAQは年末にかけて大きく上昇した後、14年は落ち着いている。一方、この間のPERの推移をみると長期的な水準からは大きく外れておらず、株式市場を歪めているとまではみられない。
一方、社債の動きについてみると、リスクの高い社債であるハイイールド債の発行額は、13年5月の発言以降、やや低下して推移していたが、14年に入ってからは高くなっている。ただし、利回りの低下はリスクの低い高格付けの社債対比では直近にかけてみられていない(第1-1-3-1図)。
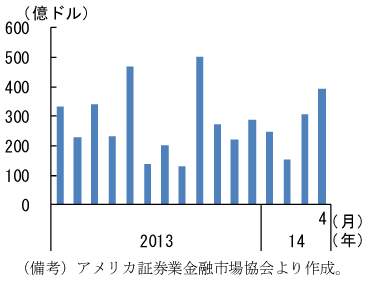
その他、株式市場における信用買いの増加や一部株式の積極評価、信用リスクの高い層向けの消費者ローンの増加に対する懸念が14年3月のFOMC会合で指摘されている。こうした過度なリスクテイクの動きに拡大がみられないかどうかは今後も注目に値する。
次に、ベネフィットという面については、量的緩和によって経済の好転とそれによる失業等の遊休資源(スラック)の解消、安定的な物価動向の実現がどの程度進んだかである。ただし、スラックとは、概念的には広く共有されているが、それを一意的に表す指標は定まっていない。それもあって、現時点でのスラックの評価は以下でみるように分かれている。
スラックと物価の基本的な関係を表すフィリップス曲線の推移をみてみよう。失業率は、テーパリングを開始した13年12月の6.7%にかけて、ピークの09年10月の10.0%から低下してきている。一方、物価上昇率は落ち着いている。2000年代からフィリップス曲線は水平な形になっている5。
こうした状況の中で、スラックの評価に関しては、二つの対立する見方から論じられている。第一の見方は、物価上昇率がマイナスになっていないと考えれば、スラック自体は失業率が示すよりも小さいのではないかという見方、第二の見方は、賃金上昇が緩慢なままであることをみると、失業率でみている以上に比較的スラックは大きいのではないか、という見方である。
第一の見方で注目される指標の一つとして、失業者のうちの短期失業者の推移が挙げられている。長期失業者は、労働市場において賃金決定交渉力が弱いため、賃金上昇は短期失業者の減少(短期失業率の低下)に左右される度合いが高いことから、短期失業率が賃金上昇や物価上昇に与える影響に注目するとの見方である。
そこで、過去の景気回復局面における短期失業率と賃金上昇率の関係を確認しよう。これまでの経験では、短期失業率が4%を下回ると、賃金の上昇がみられている(第1-1-3-2図)。短期失業率は13年10~12月期以降は約4%と、過去の平均とほぼ同じ水準にまで低下してきている。諸条件が仮に過去と同じであれば、賃金はまもなく上昇する段階となっているが、最近までに変化はみられていない。賃金上昇率が低い現状は、労働環境は失業率が表すよりも厳しい可能性を示唆している。
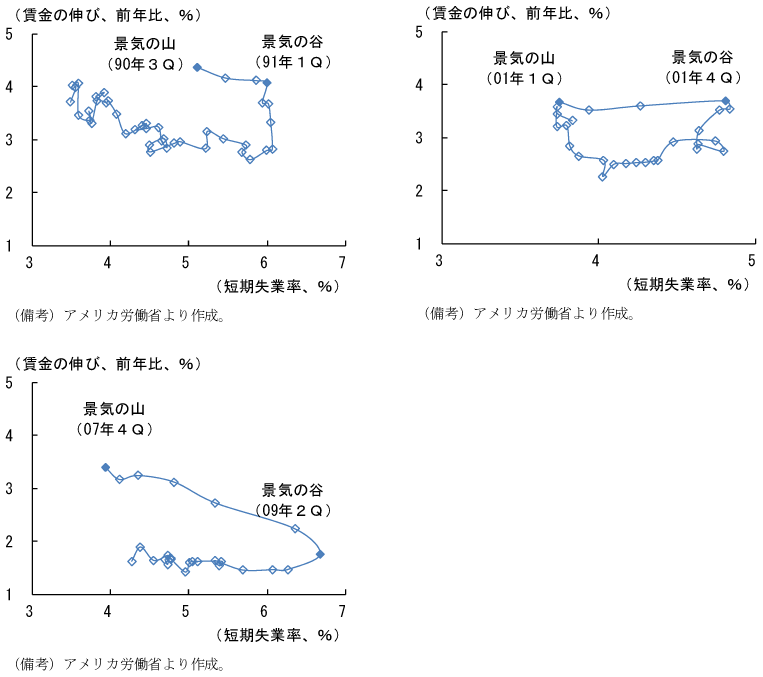
次に、第二の見方から、失業率が低下している背景にある労働参加率の低下(すなわち労働市場から退出する者の増加)に注目する。その推移をみると、08年1月に66.2%だったのが、13年末には62.8%となっている。労働参加率の低下の理由としては、雇用環境が厳しいために求職をあきらめた者(就業意欲喪失者)の退出、高齢化の進展による高齢者の退出が挙げられている。高齢化比率と労働参加率の関係をみると、高齢化の進展に合わせて労働参加率は低下している(後掲第1-2-1-42図)。しかし、他国と比較した場合、アメリカの労働参加率の低下は顕著であり、高齢化だけの影響とは考えられない。議会予算局も労働参加率の低下のうち、高齢化の影響は半分程度としている。
また、この見方からみた、もう一つの指標として、パートタイム労働者比率の水準が過去と比較して高いことがある(後掲第1-2-1-38図)。パートタイム比率が高いと、賃金の水準が低いこともあって、労働市場がひっ迫した際でも賃金上昇率が低くなる。
政策当局にとっても、以上みたように、労働市場の回復の進捗が過去とは異なり、失業率の低下だけでは十分な評価が難しい。このため、単一の指標だけでなく、複数の指標に基づき総合的な判断が求められる状況にある。3月のFOMCでは失業率6.5%をしきい値とするフォーワードガイダンスを変更し、今後は「どのように政策決定するのか質的な情報を提供する」としている。
イエレン議長は、14年3月の講演において、労働市場には相当なスラックがあるとし、その証左として、(1)経済的理由によるパートタイム労働者の多さや、自発的退職者数の少なさ、(2)過去の景気回復局面と比べて失業率の低下が賃金の上昇に結び付いていないこと、(3)長期失業者の割合の高さ、(4)労働参加率の低下を挙げている6。
また、厳しい労働市場の状況の一部については、構造問題であり、金融政策では対応しきれないとの見方もある。例えば、長期失業者の就職やベバレッジ曲線でみるようなミスマッチの増加である。労働問題への対応において、短期景気問題と長期構造問題との視点で分け、金融政策は前者のみに対応するという概念整理はあり得る。他方で、その具体的な線引きは明確ではない。ベバレッジ曲線のシフトについては、景気が弱い段階では企業も求人は出すが、積極的に採用活動をしないので欠員率が上昇することが理由との見方もある7。また、短期的な失業も放置されれば長期的構造的失業になってしまうという問題を踏まえれば、早い段階での対応が重要となる。イエレン議長は就任時の議会証言において、そうした「履歴効果」があることを指摘し、問題意識を表明している。
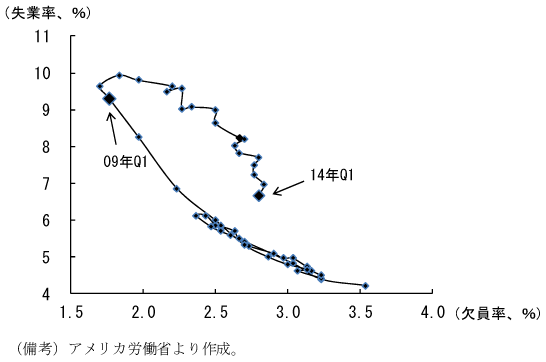
以上でみたように、アメリカの金融政策の縮小をめぐっては、そのタイミング、スピード等について様々な議論が行われている。こうした中で、経済や市場に大きな変動がないよう、政策当局が市場との適切な対話を行うことが重要であろう。
(2)ユーロ圏のデフレ懸念
ユーロ圏の消費者物価上昇率は、13年10月に前年比0.7%となって以降、1%を下回って推移しており、3月には同0.5%まで低下した(第1-1-3-4図)。こうした物価動向を背景に、13年秋以降、ユーロ圏のデフレ懸念について指摘がみられる8。
ユーロ圏の消費者物価の動向を、品目別にみると、12年まで物価の押上げ要因となっていたエネルギーが13年8月以降はマイナスとなっており、これが最大の物価押下げ要因となっている。また、食料品(アルコール・タバコを含む)の上昇率が鈍化していることも物価上昇率の低下に寄与している。財・サービス別にみると、財の上昇率が14年3月に0.0%となったのに対し、サービスは低下傾向にあるものの1.1%となっている。なお、3月の低下は、前年のイースター休暇の大部分が3月であった9ことによる一部品目の価格上昇の反動という特殊要因もあり、4月には総合の上昇率は0.7%に戻った。
圏内の国別の推移をみると、ギリシャでは13年3月から、ポルトガルでは14年2月から、スペインは3月に消費者物価上昇率がマイナスとなっており、確かに周辺国では物価の低下がみられている(第1-1-3-4図)。
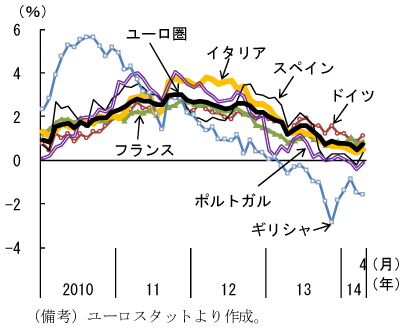
そこで、以下ではユーロ圏がデフレに陥るリスクがどの程度あるのか検討する。
まず、物価を左右する要因を総合的にみるという観点から、IMFの研究に基づくデフレリスク指標で確認してみよう。これによれば、ユーロ圏のデフレリスクは、デフレに陥った98年や09年頃の日本が相当高い水準であったのに対して、中程度に収まっている10(第1-1-3-5図)。
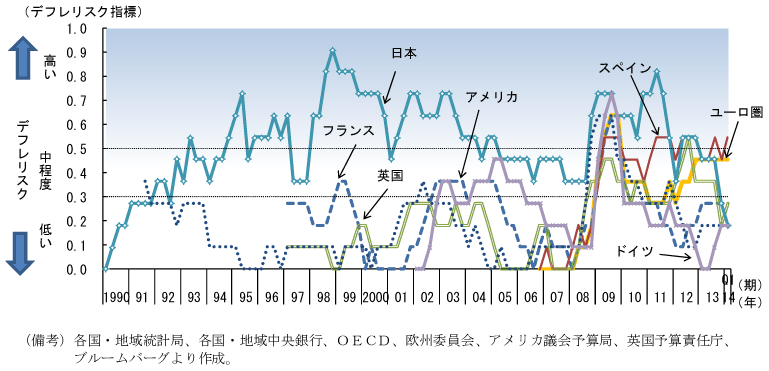
時系列の推移をみると、ユーロ圏のデフレリスク指標は13年以降横ばいで推移している。他方、デフレリスク指標を構成する各指標に分けて、その動きをみると、ここ数年はマイナスの方向となっている指標もみられる。例えば、ユーロ圏のGDPギャップは拡大傾向で推移し直近では3%台で推移しており、日本の90年代の動きにも似ている。銀行貸出の動向についても、日本の90年代初めからの動きと同様に減少している。このように、幾つかの指標は改善が遅れており、物価動向を取り巻く経済環境が基調として強くない点には留意が必要であろう。
次に、デフレリスク指標には入っていない賃金に着目してみたい。主要国において、失業率と賃金との関係をみると、前年より失業率が上昇すると賃金上昇が低位となる(第1-1-3-6図(1))。また、失業率をその過去の平均値(長期平均)と比較した場合、失業率が高い水準にある場合には賃金上昇が低位となる傾向がある(第1-1-3-6図(2))。英国やアメリカでは、13年は前年に比して失業率が低下し、失業率の水準としても長期平均に近づいており、賃金の抑制圧力は緩和している。一方、ユーロ圏では、13年は前年比で失業率が若干上昇しており、水準も高く、賃金上昇の重荷となっている。
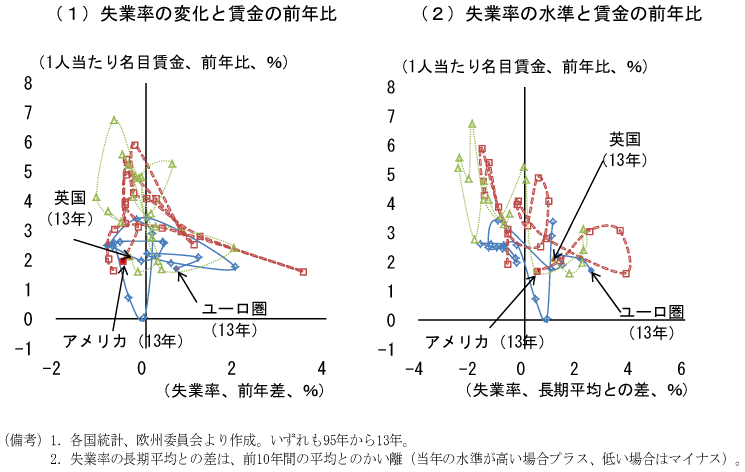
実際、時間当たり賃金上昇率の推移をみると、アメリカ、英国では、13年10~12月期以降、持ち直しているのに対して、ユーロ圏は13年4~6月期から鈍化しており、こうした労働市場の違いを反映した動きとなっている(第1-1-3-7図(1))。
ユーロ圏を国別にみると、スペインでは、13年1~3月期に前年比マイナスとなり、その後も低い上昇が続いている。スペインやギリシャといった周辺国においては、内需の回復が弱い中で、ユーロ圏において通貨切り下げという手段を採りえない以上、コスト低下によって輸出競争力を改善し、輸出の増加を起点とした景気回復に結び付けていくことが課題となっている。その意味で、第2節でみるように労働市場改革の進展による賃金コストの低下に伴う国内物価上昇率の低下は、積極的に評価できる面もある。しかしながら、比較的高い賃金上昇が見られていたドイツにおいても、13年4~6月期以降、伸びが鈍化している(第1-1-3-7図(2))。域内の景気のけん引役となっているドイツの賃金が今後も伸び悩んだ場合、ユーロ圏全体としてデフレに陥るリスクが高まることが考えられ、注意が必要である。
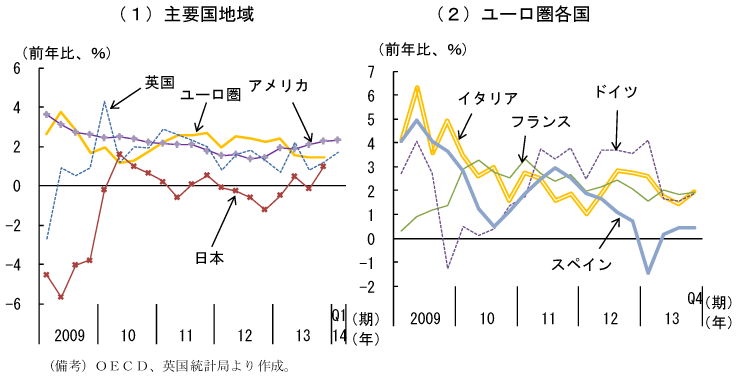
さらに、金融面からデフレ懸念についてみてみよう。ユーロ圏ではこれまでも金融の分断化が問題とされてきたが、これが悪化した場合には、周辺国では借入れコストの増加により企業収益が悪化し、景気や物価を下押しするおそれがある。しかし、ユーロ圏各国の非金融法人向け新規貸出金利の推移をみると、周辺国においては貸出金利が中核国に比べ依然高いものの低下傾向にあり、金融分断化はある程度改善されている。一方、物価の低下が金融に及ぼす影響を考えると、実質金利上昇による企業収益の圧迫や債務負担の増大等により、銀行収益も悪化する懸念がある。この点について、ヨーロッパの銀行株価の推移を確認すると、全業種平均との対比でみても上昇幅が相対的に高いことから、現時点においては物価上昇率の低下による銀行収益への下押しの影響に関して市場はそれほど懸念していないようである(第1-1-3-8図)。
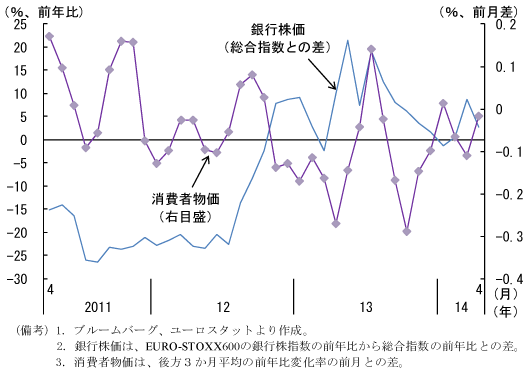
このように、デフレリスク指標では、ユーロ圏の物価上昇率は低位であるものの、デフレに転落するリスクは高くはないことが示されていたが、労働面のギャップが大きい中、賃金は低位で推移しており、景気回復に伴って着実に賃金が増加することが重要である。基本的なシナリオとしては、ユーロ圏の景気は、ドイツの景気回復や域外の需要の拡大等により持ち直しが着実さを増していき、インフレの下押し圧力が徐々に緩和していくことが見込まれているが、想定以上の外需の減速等の需要面でのショックが起きた場合には、デフレに陥るリスクもある。
仮にデフレに陥った場合、ユーロ圏においては、企業や銀行のバランスシート調整が進んでいるところではあるが、依然債務は大きく、実質金利上昇による景気へのマイナスの影響は大きい。そのため、企業の過剰債務の圧縮や債務銀行の健全性を確保・向上することが課題である。この点からも、14年11月にかけてECB等によって進められている銀行部門の包括的審査11の着実な推進に注目が集まる。
(3)新興国からの資金流出
13年5月以降、新興国の通貨は断続的に下落する局面がみられ、各国をめぐる国際金融面では不透明感が広がった。14年半ばにかけてはやや安定化もみられているが、今後ともアメリカを始めとする一部先進国での景気回復を受けて金融緩和縮小が進むと見込まれている。こうした外部環境変化による新興国経済の為替、株価、国際収支への影響を確認する。
為替の動向をみると、13年5月22日のバーナンキFRB議長の発言を契機とする形で各国の通貨の下落がみられた。こうした動きが強くなったのは13年8月頃であり、最大で同年5月半ば対比で20%程度下落した。その後、13年9月のアメリカの量的緩和縮小見送りから12月の同実施直後は落ち着いていたが、14年初以降、1月末にかけて再び下落がみられた。1月は、アルゼンチンで当局の為替レート下落容認発言を受けて急落したほか、トルコで政情不安定を受けて下落が続いたこと、中国の景況感が悪化したことなどを受けて各国市場は2月初まで軟化した。
また、資本移動の動向をみると、各国の資本流入(グロスベース)は、インドでは、13年7~9月期に海外から資本流入が流出となっている、トルコでは、13年7~9月期に資本流入が急減したほか、14年1~3月期も証券投資が流出超になっている、また、ブラジル、南アフリカでも、13年10~12月期に証券投資が流出超になっている。このように、一部の新興国において、証券投資等の短期資金を中心に資本流出の動きがみられる局面があった(第1-1-3-9図)。
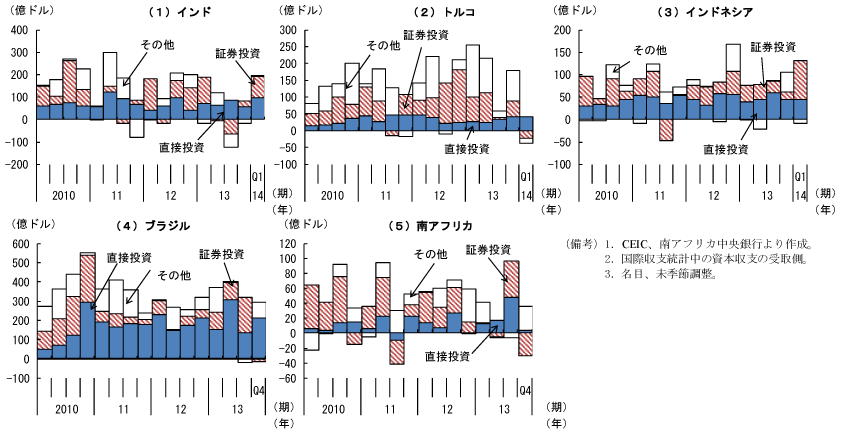
今回の通貨下落の動きは、アメリカの量的緩和縮小観測が契機となった面はあるが、それだけとは言い切れない面もある。これまでの途上国の通貨危機の経験等から、一般に通貨急落の要因として、(1)経常赤字の拡大等のファンダメンタルズの弱さ、(2)リスク回避の伝染という心理的要因が指摘されている。
ファンダメンタルズ面をみると、まず、13年初より新興国の先行きについて減速懸念が出ていた。新興国の株価動向は全体としてみると先進国と比較して13年初より軟調に転じていったが、この時期は中国やユーロ圏という経済規模の大きい地域での減速がみられていた。特に、次章でみるように、新興各国の中国輸出依存度は上昇してきていた。
また、これらの期間を通じてみると、当初は全面的な通貨安もみられていたが、その後はファンダメンタルズの違いを反映した選別色もみられるようになり、特に経常赤字が大きい国では下落傾向が大きくなった(第1-1-3-10表)。
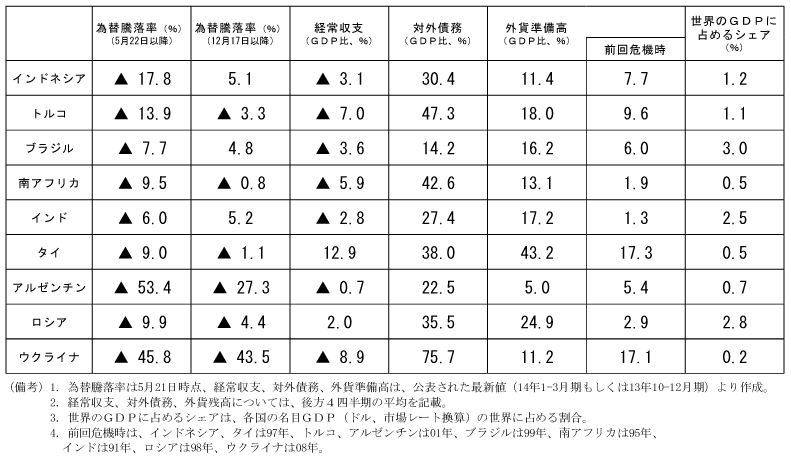
次に、心理面の影響としては、リスク回避度を表すVIX指数が高水準となる場合、いわゆるリスクオン通貨としての新興国通貨が下落、リスクオフ通貨としての先進国通貨が上昇する局面もみられたが、短期的には、VIX指数のボラティリティが高まる局面では新興国通貨に対するリスクオフ、先進国通貨に対する逃避傾向が観察された。こうした心理的要因が為替レートの変動を大きく左右する局面もみられたものの、中長期的にみると顕著な連動性は認められないほか、VIX指数の水準は、ほかの世界規模での混乱期と比較すれば低いことが分かる(第1-1-3-11図)。
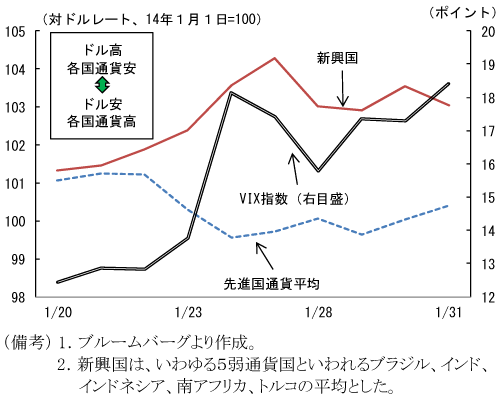
今回の為替急落の程度については、現時点においては、過去と比較すると小規模にとどまっている(第1-1-3-12図)。例えば、94年のメキシコ通貨危機、97年のアジア通貨危機と比較すると、為替下落率は当時は4割程度であったのに比べて、今回はこれまで最大20%程度の下落率にとどまっている。また資本流出の程度についても、直接投資については堅調に推移している。
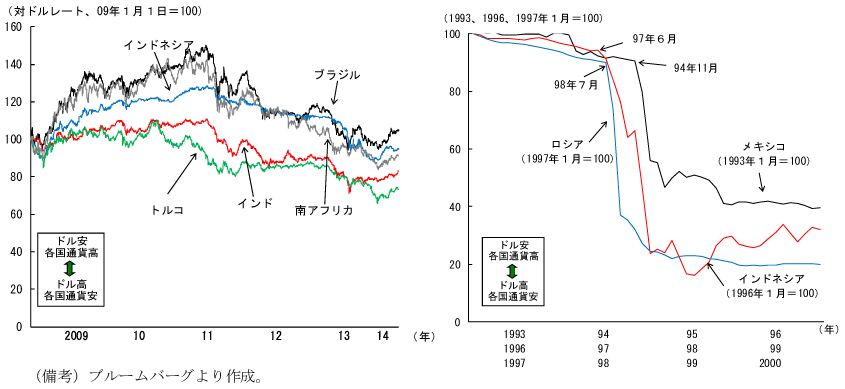
この背景としては、(1)当時と比較して多くの国で変動制に移行したこと、(2)新興国各国は外貨準備を積み増すなどして耐性を高めたことが挙げられる12。主な通貨危機における通貨下落の例として挙げられる93年のメキシコ、96年のインドネシア、97年のロシアはいずれも固定的な通貨制度を用いていた13
ところ、13年に通貨下落が着目された5か国はいずれも変動相場制を用いている。為替レートが固定制の場合は、対外的な調整が進みにくいこと、投機筋から通貨アタックを受けやすいこともある。一方、変動制の場合、調整は常に起こり、その態様としては急激というより徐々に起こるため、下落幅が小さくなっている面もあるが、各国とも過去の危機等の経験から外貨準備を積み増し、短期債務比率を減少させるなど総じて耐性を高めている。
新興国での通貨安定に向けて、各国ファンダメンタルズ改善の取組が期待されるが、そのコストはどの程度だろうか。対外的な調整を経常赤字拡大の反転の局面ととらえて、過去の経験をみてみよう。
過去の経常赤字反転の例を確認すると、新興国は経常赤字が反転すると経済成長率はマイナスとなる傾向にある14。ブラジル、インド、インドネシア、南アフリカ、トルコの5か国について、80年以降の過去の経常赤字の落ち込みが大きかった時期15
と最近3年を比較すると、インド、トルコにおいて11年、12年に大幅な(▲2%以上の)落ち込みをみせているものの、その後の経済成長率の落ち込みは過去の例に比して軽微である。(第1-1-3-13図)。これは、上述の通り、変動相場制に移行したことから、ショックを吸収する耐性ができたことなど、制度的要因が寄与したとの指摘もある。

これまで、消費者物価上昇率の高止まり等に対して政策金利引上げ等の金融引締めの実施(トルコ、ブラジル、インド、インドネシア等)等の対応を取っているほか、通貨下落を背景に輸出が若干増加している面もある。
今後も、緩やかな調整が進むことが期待されるが、上記にみたように急激なセンチメントの悪化が生じるような事象が起きないことも重要である。その意味では、市場心理の急変が生じないような、適切な政策アナウンスメントも重要といえよう。
(4)中国のシャドーバンキング問題
中国経済の減速の背景として、シャドーバンキングによる過剰な信用拡大と、それを抑制する取組が指摘される。以下では、過剰信用拡大の結果として生じた地方財政の悪化や、シャドーバンキング抑制が融資や貿易等へもたらした影響について確認する。
シャドーバンキングとは、比較的厳格な銀行規制を回避するような銀行貸出以外の形で行われる金融仲介である 。中国の実態からみて、こうした「規制裁定」であるシャドーバンキングの具体例として挙げられるのは、銀行理財商品と信託貸出である。これは、先進国でのサブプライム・ローン等の高度に発達した金融商品というより、投資信託に近いものといえよう16。
これまでの銀行理財商品等の推移をみると、12年以降に大きく成長している。銀行預金金利は、金利規制の下で現在は基準金利(1年物)が3.0%と低水準となっており、平均利回り5%と相対的に高い理財商品が成長した。
また、シャドーバンキングの問題に密接にかかわる問題として、13年に上昇傾向となった不動産価格の動向も注目されている。理財商品や信託貸出の資金供給先として、不動産会社や、地方政府の資金調達機関である「融資平台」も含まれているからである。これに対応する形で、地方政府の債務も増加傾向にある17(第1-1-3-14図)。
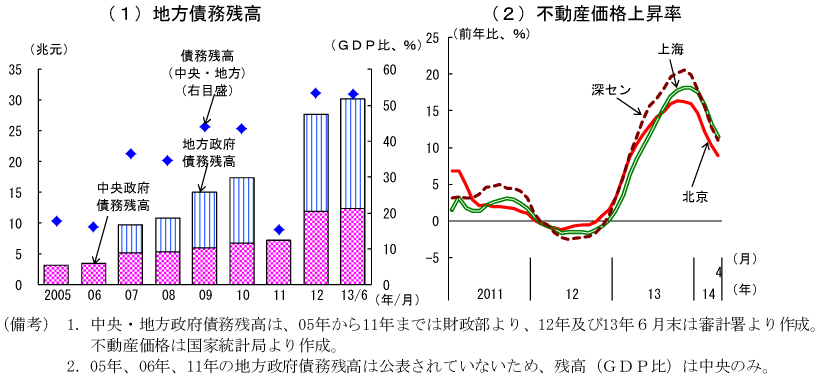
14年初より、いわゆる「シャドーバンキング部門」の一端である理財商品等において、デフォルトやデフォルト懸念の複数の事態が発生した。こうした動きを受け、上海銀行間取引金利(7日物)は1月下旬~2月中旬には5%台に上昇するなど、一時的に高めに推移し、金融市場に不安定な動きがみられた(後掲第1-2-3-18図)。
また、シャドーバンキング部門からの資金への依存度合いが比較的高いとみられる中小の製造業、不動産業等を中心に、リスクプレミアムの上昇や融資の縮小等が大きければ、経済活動を下押しする可能性がある(第1-1-3-15図)。
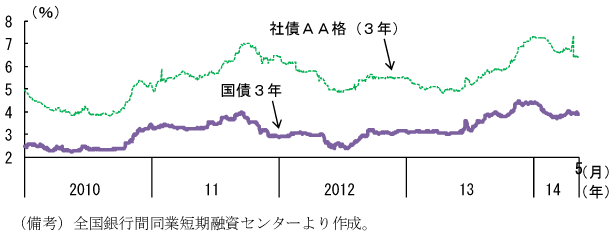
実際、14年初より固定資本投資や生産活動において、弱めの動きがみられているが、実体経済が悪化すれば、金融市場の不安定性も増すという関係も指摘できる。例えば、企業の業況感を示す製造業購買担当者指数(PMI)は、13年後半より低下がみられ、50前後で推移している(第1-1-3-16図)。このように金融の不安定性と成長率の低下が相乗的に拡大していけば、経済の下押しの影響がより明確になっていく可能性もある。
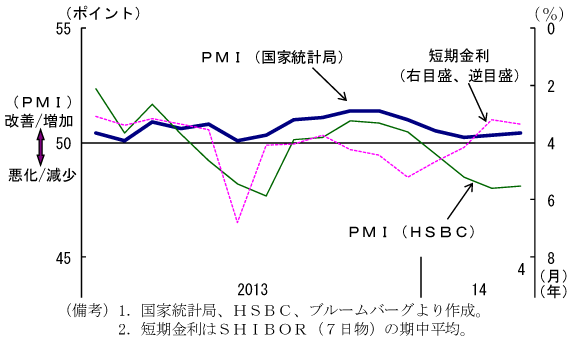
こうした動きの背景には、政策対応が挙げられる。中国政府は14年3月に開催した全国人民代表大会(以下、「全人代」という。)で14年の経済成長目標を13年と同様に7.5%前後と13年並みのやや高めに設定するとともに、金融改革を進め金融リスクの監督強化を進める方針を示している18。特に、全人代に先立って、13年末に金融機関に対して国務院通達を出し理財商品の規制強化を進めてきている。
中国のシャドーバンキングは、銀行システムには直接関わっていないため、システミックリスクにはならないとの見方もある一方で、これは銀行の貸出制限等を回避するものであるため、元本保証の必要がなくとも結局は銀行が保証する「剛性兌付19」という暗黙の保証が付与されている場合もあるとの指摘もある20
。また、理財商品の対象となる企業に対し、ほかの銀行が貸し付けているケースもある。
シャドーバンキングに対する規制の影響としては、次の二点がある。
まず、理財商品等のデフォルト等の発生について、こうした債務の再構築が秩序だって行われれば、ハイリスク・ハイリターンという認識を市場により促すとともにモラルハザードを抑制することとなり、金融リスク管理強化の観点からはむしろ評価できる。
次に、これまでのところ信用供給を総じてみれば、理財商品等を減らし銀行貸出を増やす動きもみられる(第1-1-3-17図)。特に13年7~9月期以降は非金融企業向けの中長期貸出の増加が続いている。中長期貸出が伸びているのは、シャドーバンキングや社債から貸出(中長期)に移行するなど資金調達方法の変更によるものとみられる。
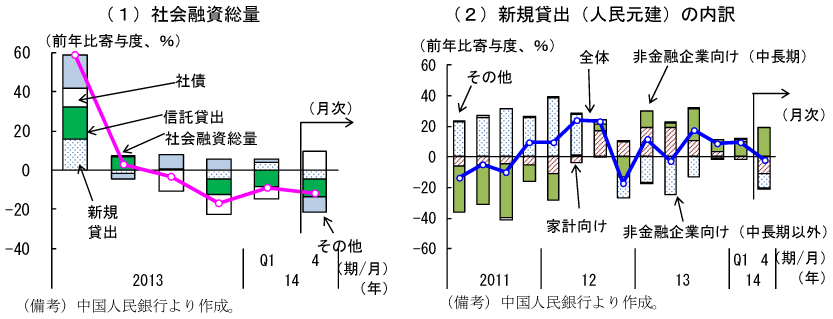
理財商品から銀行融資へのシフトの評価については、信用が急速に縮小しない効果はあるがリスク管理の観点からは慎重にみる必要がある。そもそも、中国では国有銀行を中心に行われる金融制度であったことから、銀行以外に金融市場の導入(市場化)、国有行以外に民間行の参入(民営化)、規制金利から市場金利への移行(自由化)等の動きを進めてきた。これは、多くの途上国と同様に、市場が機能するための金融インフラの整備の発展に合わせて市場化等を進めてきたともいえる。
しかし、そのテンポを超えた動きとして、理財商品等が、「規制裁定」として、いわば自然発生的に成長した。これを単純に融資に戻すことは、金融改革の流れと方向が逆になるだけでなく、インフラ整備の推進が遅れたままになるおそれもある。
長期的な視点に立った金融市場の健全な発展につなげるためには、秩序ある形でのデフォルト発生を容認することによるモラルハザードの是正21、適切なリスク評価、資金偏在の是正等のほか、適切な管理の下での理財商品等の発達等を通じて、健全な形で市場を育成していく必要もあろう。
(5)ウクライナ情勢
ウクライナにおいては、国内の親EU派と親ロシア派の政治的な対立から、14年2月に親ロシア派のヤヌコビッチ政権が崩壊した。直後に親EU派からなる暫定政権が誕生したが、3月初めにはロシアによる軍事的な介入が行われるのではないかという懸念が広がり、加えてEUやアメリカ等が対ロシア制裁にむけた動きをみせるなど、国際的な問題へと発展した(第1-1-3-18表)。
こうした動きを受け、ロシアにおいては、株価や通貨が一時大きく下落した(第1-1-3-19図)。また、ロシアとの経済的なつながりが大きいヨーロッパにおいても、ドイツのDAX等、主要な株価が一時下がった(第1-1-3-20図)。このように、ウクライナをめぐる国際的な緊張が高まった当初には、ロシアやヨーロッパの一部の金融市場に地政学的リスクの高まりの影響が一時的にみられた。
3月半ば以降も、ウクライナにおいてはクリミアのロシア編入の動きやウクライナ東部州の自立(独立、自治拡大、ロシアへの編入等)を目指す動き等がみられ、情勢の緊迫化が続いている。一方、国際社会においても、アメリカやEU等がロシアやウクライナの一部関係者・企業に対して渡航制限や資産凍結等を行うなど、緊張が断続的に続いている。しかしながら、金融市場への影響については、ウクライナにおける武力衝突が限定的であることや欧米とロシアの対立が深刻化するとの懸念がやや落ち着いたことから、これまでのところ限定的である(第1-1-3-20図)。
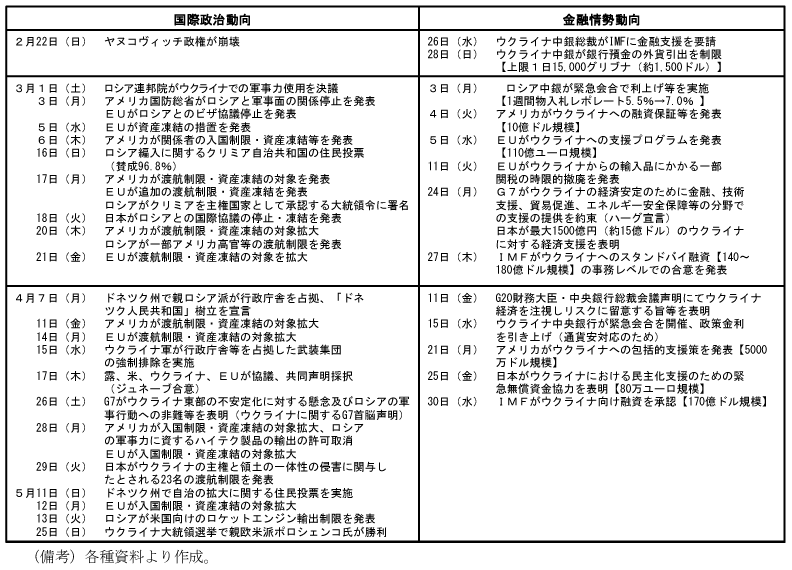
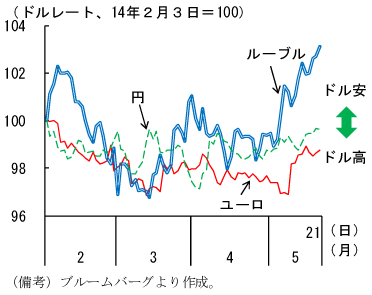

ただし、今後の情勢次第では、ロシアやウクライナとつながりの深い地域や一部の商品に影響が出る可能性がある。まず、ロシアは、原油や天然、穀物等の一次産品の供給元として世界市場で多くのシェアを占めており、また、ウクライナも小麦等の世界的な生産地である。そのため、14年2月以降、原油価格や小麦等の穀物価格が上昇した(第1-1-3-21図、第1-1-3-22図)。また、ヨーロッパの国は、エネルギーをロシアに少なからず依存しており、例えば、ギリシャ、ドイツ及びイタリアは、国内で消費する天然ガスの約4~6割をロシアから輸入している。今後、地政学的な緊張がさらに高まった場合、商品価格の上昇等、国際金融市場に影響が生じる可能性やロシアからのエネルギー輸出に影響が生じ、ヨーロッパ経済に影響が生じ得ることが考えられる。また、そうした金融面、実体面の影響を通じて、世界経済が下ぶれするリスクがあることから、引き続きウクライナ情勢を巡る国際的な政治・経済情勢には留意が必要である。