3.世界経済の減速の影響を強く受けるその他アジア地域の経済
第1章第1節で触れたとおり、韓国、台湾、ASEAN諸国(以下「その他アジア地域」という。)も、11年半ば以降の欧州政府債務危機の再燃等による質への逃避による為替の減価といった金融面の影響や、世界経済の減速により、特に輸出を中心とした実体経済面で影響を受ける結果となった。
(1)GDPは一部の国でマイナス成長も
その他アジア地域では、11年7月以降の欧州政府債務危機を背景にした海外需要の鈍化の影響を受け、インドネシアを除く国、地域において実質経済成長率は低下し、11年10-12月期の経済成長率(前期比年率)は、シンガポール、台湾等の一部の国でマイナス成長となった。また、タイは11年秋以降、洪水の影響により、同期の実質経済成長率(前期比年率)は▲36.4%と大幅なマイナス成長となった(第2-2-50図)。
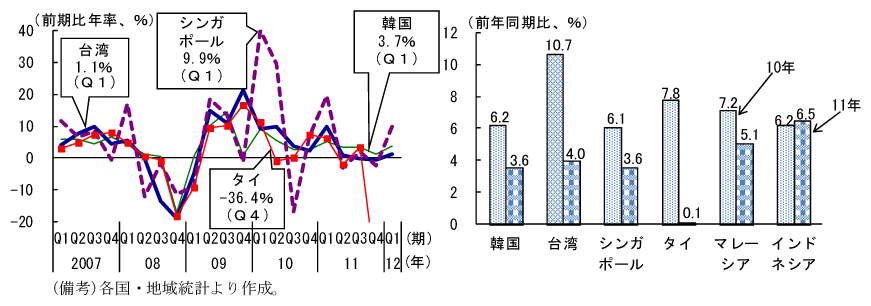
個別の指標をみると、生産、輸出ともに、11年後半以降、弱含んでいる。中でもタイでは、洪水の影響により製造業生産指数が07年水準の70%程度まで落ち込んだ(第2-2-51図)。12年に入り、生産については台湾以外の国々においては持ち直しの動きがあるものの、輸出に関しては、主にEU及び中国向けの伸び悩みにより、シンガポール、タイ以外の国、地域では、持ち直しといえる状況には至っていない(第2-2-52図)。
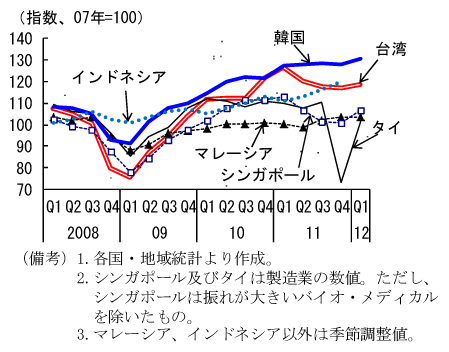
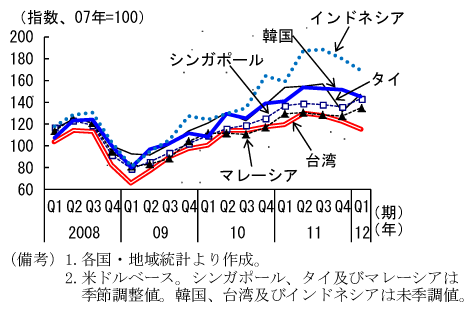
こうした景気の足踏み状態を受け、一部の国、地域では財政出動等による景気対策の動きも出てきている。なお、韓国やマレーシアでは12年から13年にかけて大統領選や総選挙が予定されているため、今後も積極的な財政政策運営となりやすい状況にあると考えられる(第2-2-53表)。
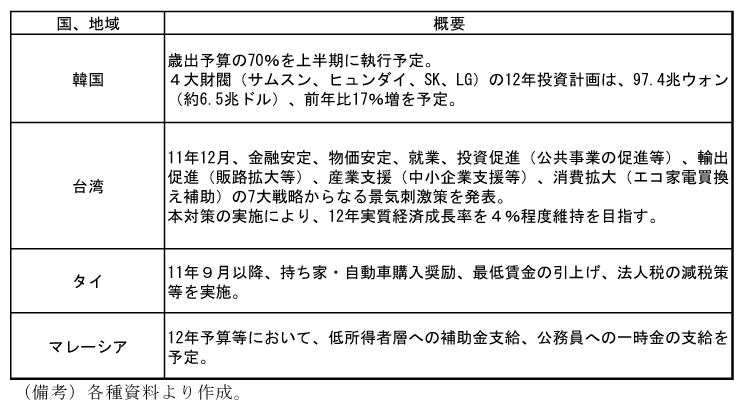
消費者物価上昇率の動きをみると、11年からの食料品価格上昇等、主に供給要因による物価上昇圧力が緩和したこと、景気が足踏み状態となったことで需要側からの物価上昇圧力が低下したこともあり、総じて低下傾向にある(第2-2-54図)。輸入物価上昇率についても、消費者物価上昇率と同様、低下傾向にあるものの、特に資源を輸入に頼る韓国、台湾は、5%近い上昇率となっており、依然として高い伸びが続いている(第2-2-55図)。
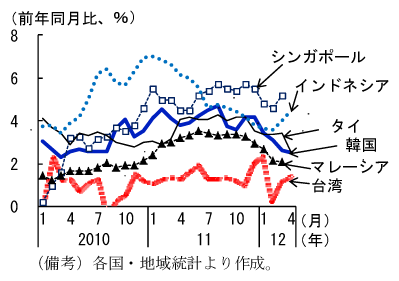
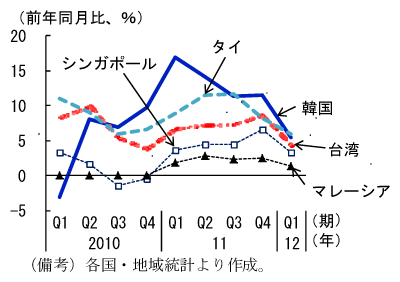
金融政策については、インドネシア、タイにおいて、11年10月以降、世界経済の先行き不透明感や物価の落ち着き、これに加えて、タイでは洪水被害の拡大による景気減速を主な理由に、12年3月までにそれぞれ1%ポイント、0.5%ポイントの政策金利の引下げを行った。その他の国・地域においても、11年夏以降、景気が足踏み状態となったことにより、これまでの金融引締め政策は打ち止めとなっており、韓国やマレーシアでは11年5、6月に政策金利の引上げが行われて以降、据置きとなっている(第2-2-56図)。
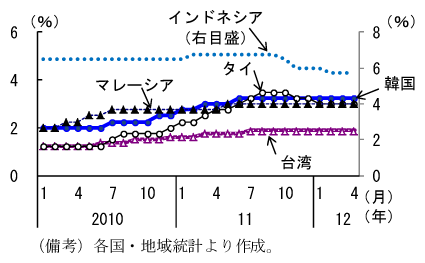
(2)欧州政府債務危機による金融面でのその他アジア地域への影響
11年9月以降の欧州政府債務危機の再燃は、その他アジア諸国に飛び火した。前述のように、輸出等を通じた実体経済への影響は大きかったが、ここでは株価、与信残高等の国内金融面への影響を検証していく。
アジア諸国にとってヨーロッパは輸出相手国として高いシェアを占めている。11年7月以降の欧州政府債務危機に対する懸念から、インドと同様にその他アジア地域の株価は11年7月から11月後半にかけて大きく落ち込んだ(第2-2-57図)。
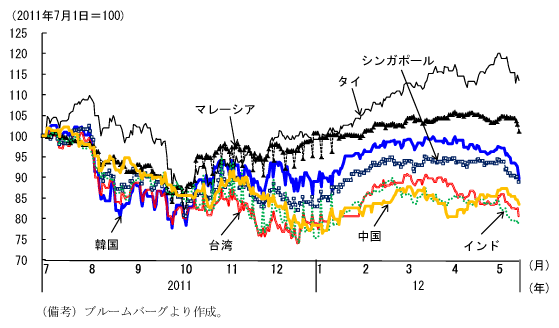
国際決済銀行(BIS)統計への報告国銀行による国際与信残高の推移をみると、アジア諸国でも特に韓国、台湾等において、欧州銀行の与信残高の減少がみられる(第2-2-58図)。
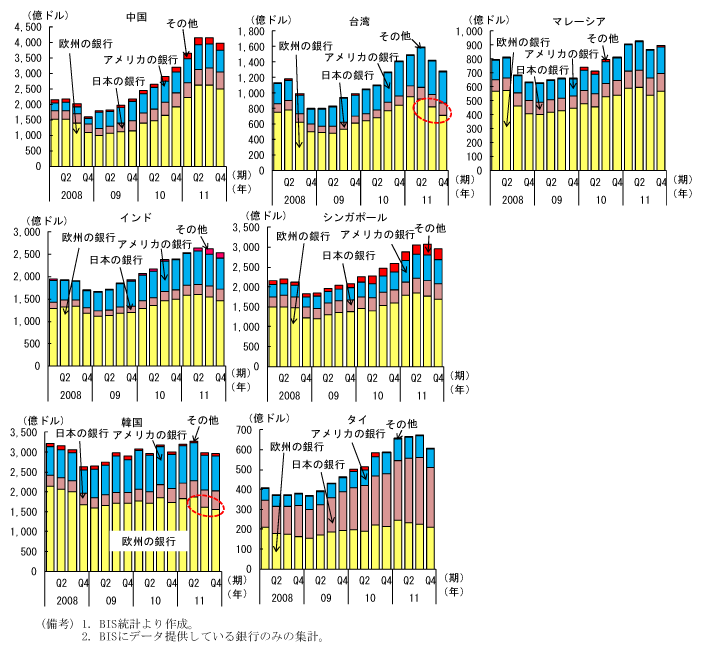
与信残高の動きを、株価の変動が大きかった韓国及び台湾の資本収支からみてみよう。まず、韓国では11年7~9月期に銀行借入等のその他投資収支が約190億ドル減少した(第2-2-59図)。この規模は、08年の世界金融危機時の10~12月期の流出額の半分程度にまで及んだ。しかし、同年10~12月期には約20億ドルの流入超に転じていること、年明け以降、アメリカの緩やかな景気回復及び欧州政府債務危機懸念に安定化に向かう兆しがみえたことを足掛かりに、欧州銀行によるデレバレッジが比較的短期間の後に一服したものとみられる。
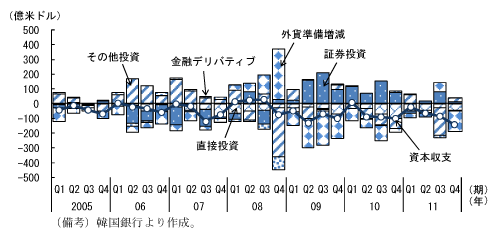
一方、台湾では、11年11~12月期にその他投資収支が約85億ドル減少しており、その金額は世界金融危機時の約2倍にものぼる規模となった。アジア各国の中でも欧州銀行による与信残高減少の影響に規模や時間に差があることが分かる(第2-2-60図)。
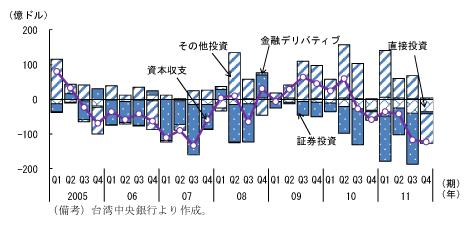
(3)中国経済とその他アジア諸国経済で高まる連動性
その他アジア地域では、中国と域内各国、地域間の貿易が拡大している。輸出額全体に占める中国向け輸出のシェアは、11年で台湾、韓国でそれぞれ約4割、3割を占めるほか、ASEAN諸国でも、シェアの一番少ないマレーシアで約2割を占めている。輸出シェアの変化を、2000年と11年のシェアをもとにした相関図からみると、全ての国・地域においてASEAN域内向け輸出のシェア拡大以上に中国向け輸出のシェアが拡大している(第2-2-61図、第2-2-62図)。
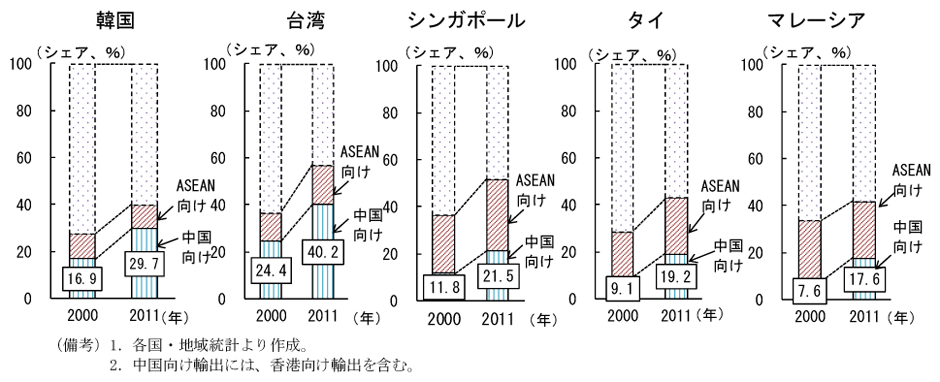
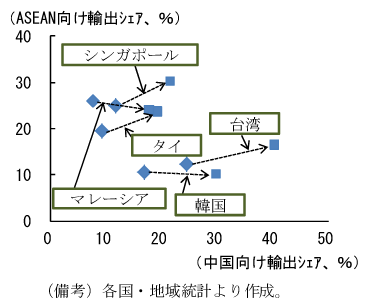
こうしたその他アジア地域における中国との貿易拡大の背景の1つとして、東アジア域内において貿易、投資の活性化が図られている点が挙げられる(第2-2-63表)。
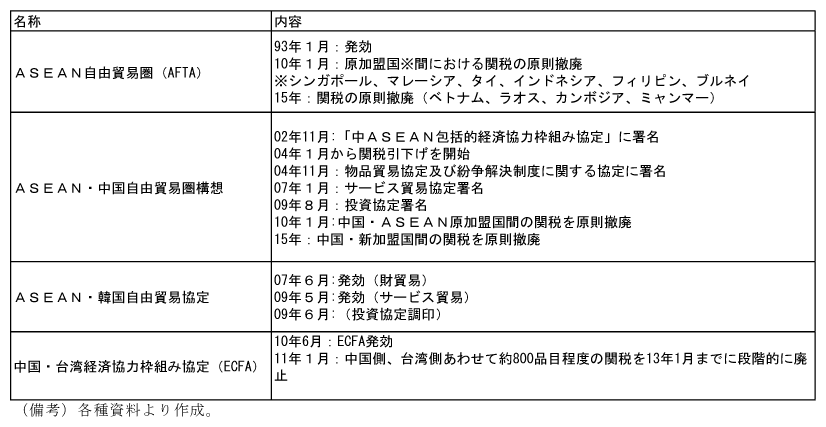
ASEANは93年以降、域内の自由貿易圏の形成(ASEAN自由貿易圏:AFTA)に取組んでいる他、中国や韓国との間においても、それぞれ02年、07年に貿易自由化のための枠組み、協定を署名、発効している。また、その他アジア地域から中国への直接投資の規模は、シンガポールを中心としたASEAN+3において、10年で2000年比約124%増となるなど、着実に増加している(第2-2-64図)。
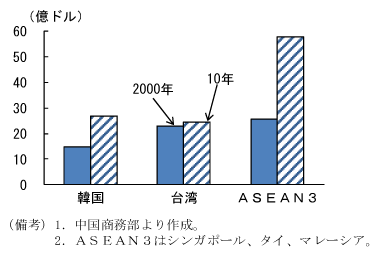
最近の輸出動向をみると、欧州政府債務危機の影響を受け、11年7~9月期から10~12月期にかけて、EU向け輸出の寄与が低下しているのに加え、中国経済の景気拡大テンポが緩やかになっていることにより、同国向け輸出の寄与も同様に低下したことを主な理由に輸出の伸びが低下した(第2-2-65図)。その他アジア地域においても中国経済のプレゼンスが拡大したことにより、中国の景気動向の影響を受ける傾向が近年ますます強まっていることがうかがえる。
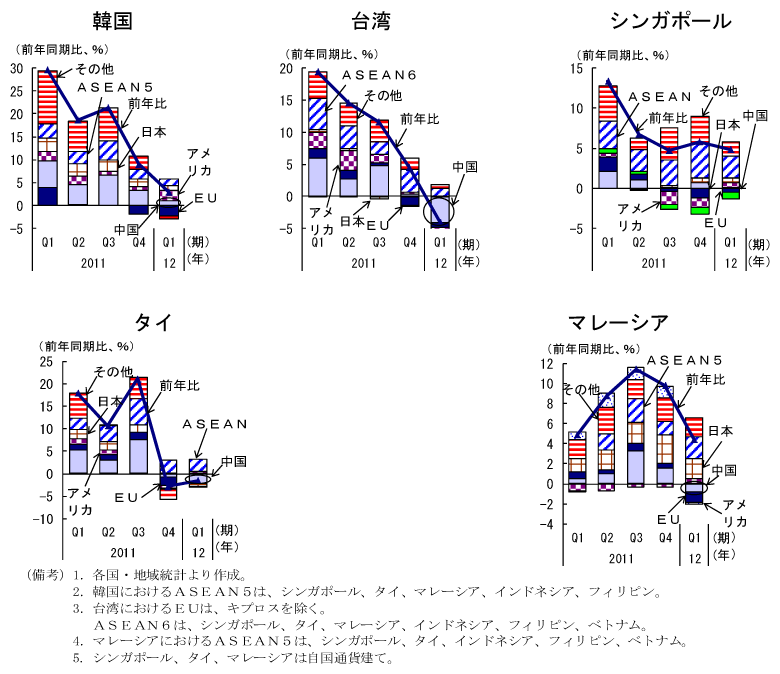
そこで以下では、その他アジア地域と中国を中心にした貿易構造に関して、(1)その他アジア地域の財別輸出、(2)中国の財別輸出入動向を調べることで、その他アジア地域と中国経済の連動性についてみていくこととする。
(i)その他アジア諸国から中国への輸出
従来から、中国とその他アジア地域からみた貿易ネットワークは、その他アジア地域等から中間財を輸入し、その財を中国で加工した後、最終需要地となるアメリカ、EU等へ供給するという、いわゆる「世界の工場」としての役割を担っているといわれている(第2-2-66図)。
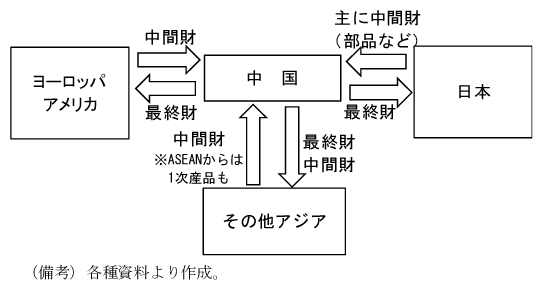
上記の構造を検証すべく、まず、その他アジア地域からの財別輸出の動向をみると、その他アジア地域における中国への輸出は、主に部品等の中間財のシェアが高いことが分かる。特に韓国、台湾では2000年以降、輸出に占める中間財のシェアは低下傾向にあるものの、10年間一貫して8割近いシェアを有している(第2-2-67図)。また、その他アジアからの中間財輸出を、財の受け手である中国の輸入からみると、その他アジア地域からの輸入比率が全体の5割近くを占めており、上記国、地域における中国への中間財輸出の規模の大きさがうかがえる(第2-2-68図)
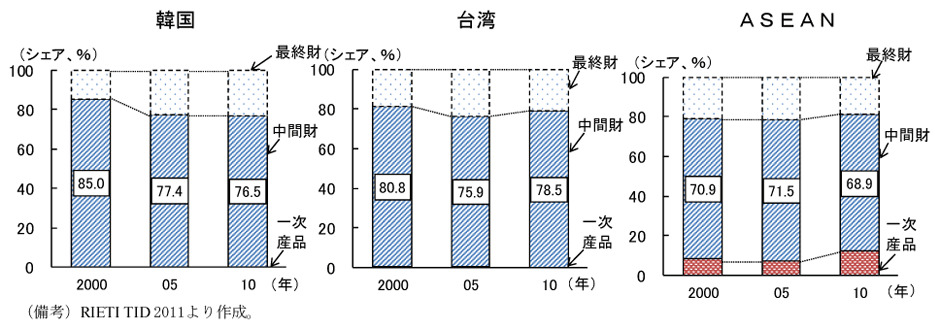
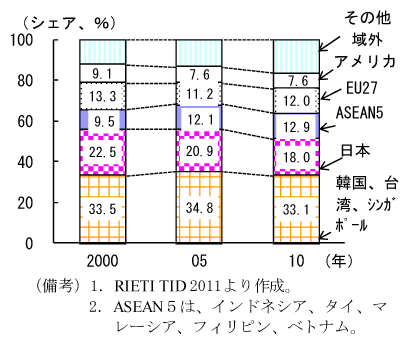
(ii)中国の中間財輸入及び財別輸出の動向
次に、中間財の受け手である中国の財別輸出をみると、2000年以降、輸出全体に占める最終財の輸出割合は低下しているものの、10年間を通じて約6割を占め、従来からのその他アジア諸国から輸出された中間財等を加工し、最終財を国外へ輸出している構造に大きな変化はみられないことがうかがえる(第2-2-69図)。
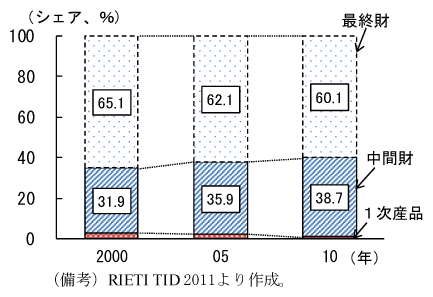
さらに中国の財別輸出で割合が最も大きい最終財について、資本財及び消費財に分けてみると、2000年以降、消費財の割合が低下する一方、資本財の割合が増加しており、最終財の輸出に関しては、産業の高度化に伴う構成の変化が見受けられる(第2-2-70図)。
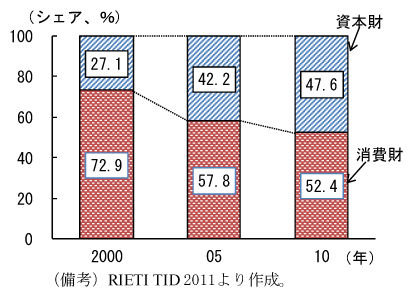
こうした資本財、消費財の中国からの輸出先をみると、2000年と比較して、いずれもアメリカは、EUと並び最大の最終財輸出先となっていることに変わりはないものの、インド、ブラジル、ロシアなどをはじめとしたその他域外への輸出割合が増加しており、輸出先の多様化がみて取れる(第2-2-71図、第2-2-72図)。
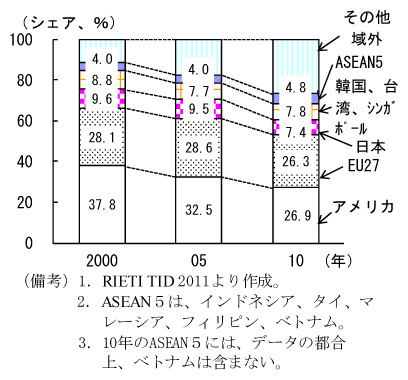
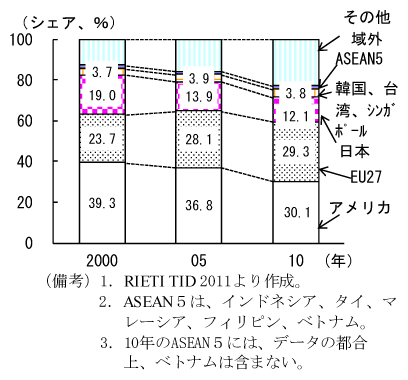
(iii)韓国と台湾における中国との輸出の連動性
最後に、中国への輸出割合が高い韓国及び台湾側から中国の輸出との連動性についてみていく。
韓国及び台湾の中国への輸出品目についてみると、主要品目はそれぞれ、品目別分類における機械輸送機器及び機械電気となっている。その割合は、ともに11年で約4割を占め、韓国では2000年と比較して10%ポイント以上増加し、台湾は04年と比較してほぼ横ばいとなっている(第2-2-73図)。上記の通り、韓国と台湾は中国との輸出面での結びつきが強いため、その面での連動性が強く出る傾向がある。07年以降の中国の輸出(総計)、韓国及び台湾の中国向け輸出の動向をみると、中国の輸出の動きと連動して推移しており、両者の動きを2000年から05年と06年から11年の相関係数から比較しても、ともに強い正の相関が検出できる(第2-2-74図)。特に台湾は、中国と締結した自由貿易協定であるECFA(両岸経済協力枠組協議)が11年から発効したこともあり、近年は相関性の高さが際立っている。
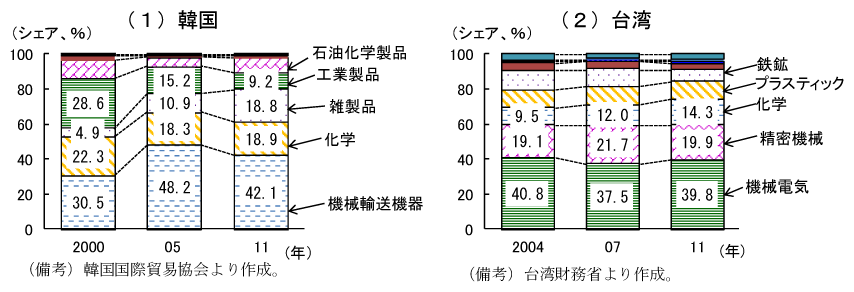
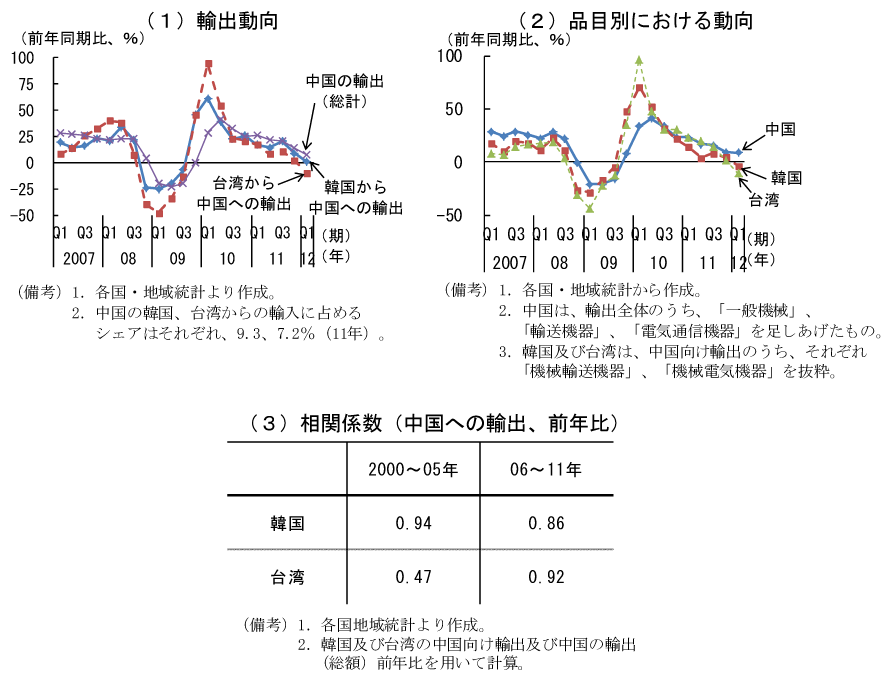
以上みてきた通り、2000年以降のその他アジア地域をめぐる輸出ネットワークに関しては、08年の世界金融危機を経た後も、その他アジア地域から中国へ主に中間財を輸出し、中国において加工した後、最終財を欧米諸国に輸出するという基本構造に大きな変化はみられない。しかしその一方で、その他アジア地域の中国への経済的結びつきはますます高まっていることが分かる。このため、これらの国・地域は今後、これまで以上に中国との経済関係のあり方を含めた持続的な経済発展のための成長戦略を持つことが重要となると考えられる。
コラム2-6:韓国・台湾における半導体等の生産、出荷在庫状況
「産業の米」ともいわれる半導体。パソコンやテレビだけでなく、日常使う製品から自動車まで幅広く活用されており、その用途は幅広い。半導体の市場規模は、05年比で10年には1.3倍の約3,000億ドルに達している(図1)。
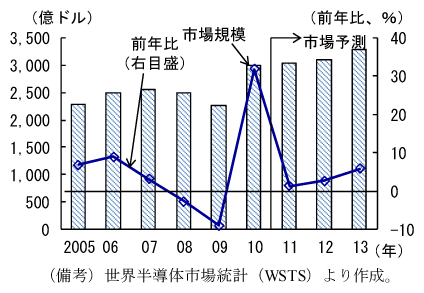
しかし10年以降、生産、出荷ともに減少局面となっており、半導体世界全体の生産能力、生産のための投入数からみた生産稼働率をみると10年4~6月期をピークに減少している他、出荷も11年7月以降、前年比マイナスの伸びが続いている。(図2)
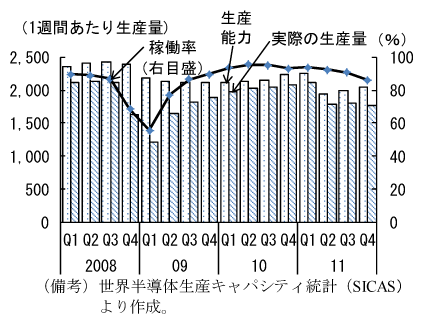
中でも、日本を除くアジアは半導体出荷額の5割以上を占めており、世界の半導体生産において大きな役割を担っている(図3)。特に韓国、台湾は鉱工業生産指数に占めるウェイトは大きく25、10年以降の半導体生産及び出荷の減少による生産活動への影響は大きいと考えられる。
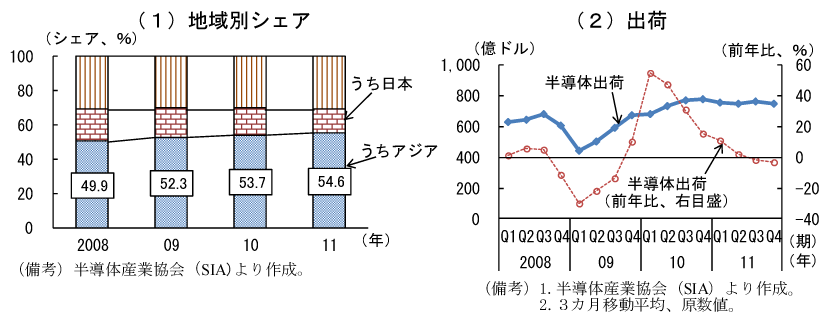
そこで、韓国、台湾における半導体、IT部品の出荷、在庫状況について在庫率指数及び出荷在庫ギャップからみてみると、韓国の半導体在庫率指数(在庫指数/出荷指数)は、約2年周期で推移しており、11年以降は4~6月期を底に上昇し、12年1~3月期では、08年9月の世界金融危機時を超える率まで達している。また、製造業在庫と比較しても半導体の在庫率指数の高さは際立っている。ただし、半導体在庫率指数は、出荷在庫ギャップにおける出荷増加局面である09年4~12月及び11年1~6月においても在庫率指数は100%を超えており、恒常的に高い在庫となっていることがうかがえる。一方で、台湾の在庫率指数は、製造業、IT部品で出荷とほぼ一定で推移している(図4)。この背景には、台湾では受注製造(EMS26)に特化していることが1つの要因として考えられる。
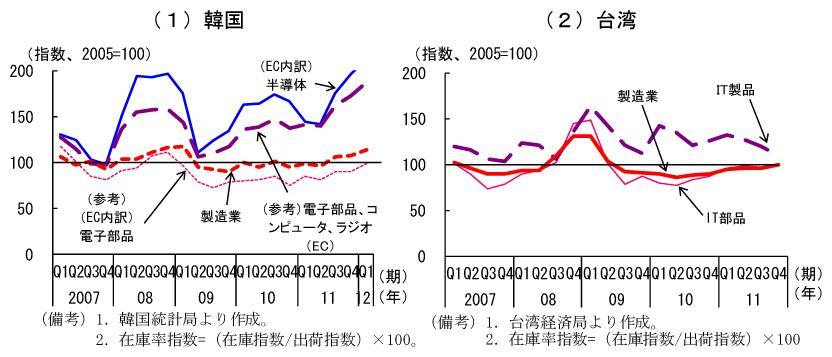
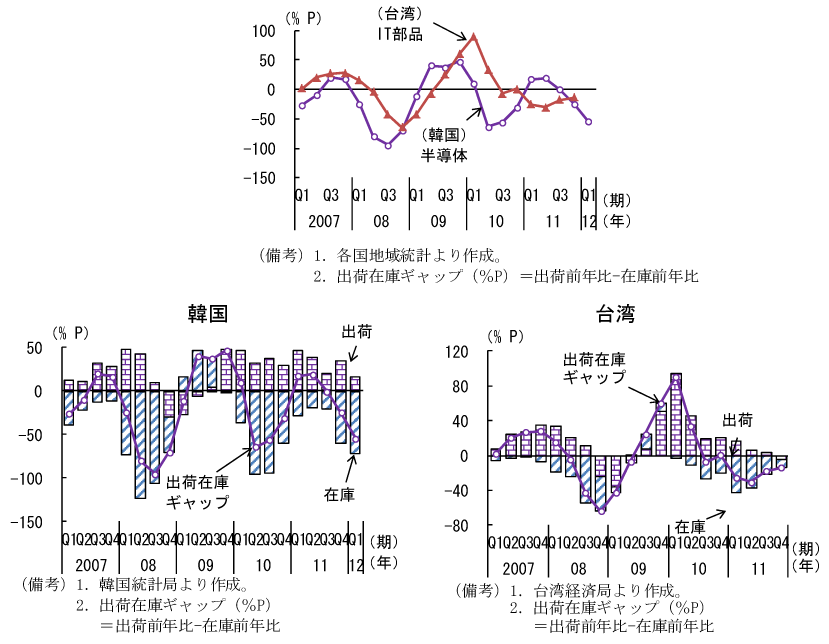
こうした在庫の積み上がり、調整局面にある要因の1つとして、テレビ用液晶パネル及びパソコン出荷の減少等が考えられる。10年、11年の液晶テレビ、ノートパソコンの出荷数をみると、ともに前年比の伸びはほぼ横ばいにまで鈍化した(図6)。一方でタブレット端末は10年比で200%の伸びとなっており、ノートパソコンの出荷減少は、タブレット端末が、インターネット閲覧やメールの送受信等、パソコンで行える最低限の機能を利用するライトユーザーを中心に需要を取り込んだことなどにより、ノートPC需要を代替したことが主な要因と考えられる。
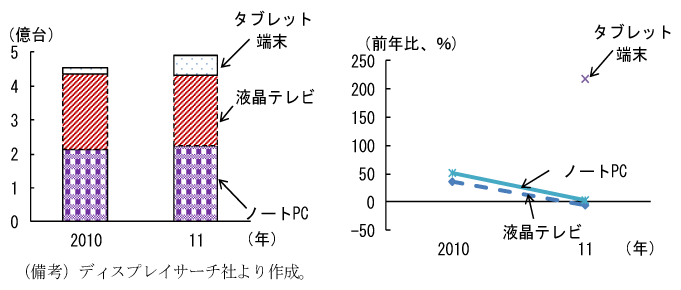
テレビやパソコンに関しては、有機EL技術、パソコンではウルトラブック等、新たな技術を使用した製品の販売も始まっていること、また12年夏は世界的スポーツイベントであるサッカー欧州選手権、ロンドンオリンピック等の開催を控えていることから、テレビを始めとした需要見通しの改善も予想され、今後も動向が注目される。

