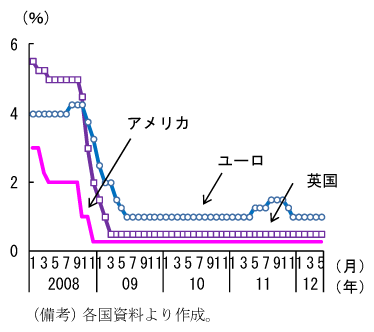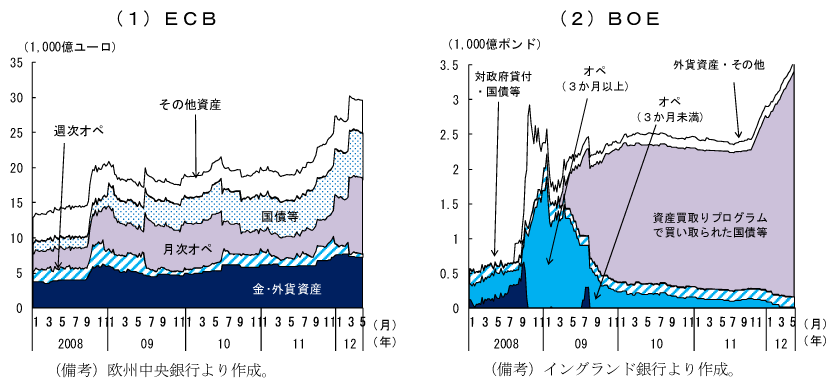3.新興国の政策対応の変化:金融政策に変化の兆し
欧州政府債務危機やヨーロッパの実体経済の悪化は、欧米に一層緩和的な金融政策を促すとともに、これまで引締め基調であった新興国等の金融政策をも緩和的なものへと転換させた。以下、この点について概観する。
(1)世界経済の減速から一部の新興国は金融緩和へ転換
新興国等では、物価上昇を抑えるため10年半ばから利上げや預金準備率引上げといった政策が相次いで採られてきたが、11年半ば以降、政策スタンスが緩和的になりつつある(第1-2-14図)。この背景として、欧州政府債務危機を受けてヨーロッパ経済が減速し新興国等の景気も下押しされたことや、高まり続けてきた物価上昇率にやや落ち着きが出てきたこと、これまでの引締め政策が内需の鈍化につながってきたことなどが挙げられる。例えば、ブラジルやロシアでは、欧州政府債務危機による世界経済の減速の自国への影響が懸念され、利下げが実施された。中国では、物価上昇率が低下する一方で自国経済の拡大テンポが緩やかになっていることから、12年に入り預金準備率引下げが3回にわたり行われ、インドでも経済成長の鈍化を背景に12年4月に政策金利が引き下げられた。
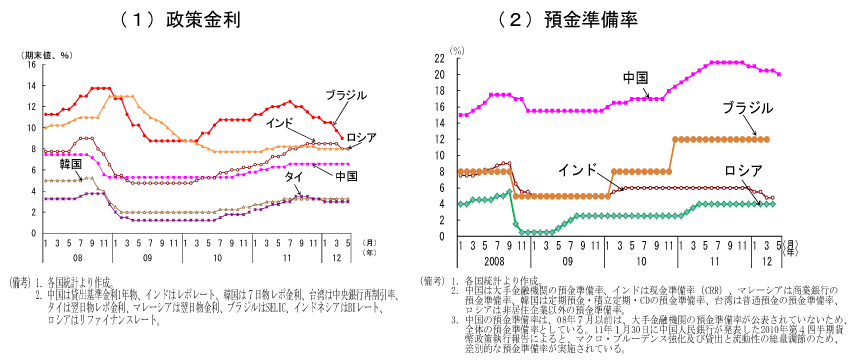
(2)先進国は金融緩和を継続
欧米でも、欧州政府債務危機などを背景とする経済の現状ないし先行きに対する懸念から、緩和的な金融政策が継続している(第1-2-15図)。欧州中央銀行(ECB)は、物価上昇率が低下する以前から景気下振れ懸念を背景に金利を引き下げはじめ、11年12月には世界金融危機発生後に記録した過去最低水準の1%まで利下げを行った。また、11年12月と12年2月に、異例の長さである3年物の長期資金供給オペを行った。イングランド銀行(BOE)は、12年2月に国債の買取規模を3,250億ポンドに増額した。この結果、ECBとBOEのバランスシートは11年後半に急拡大した(第1-2-16図)。なお、アメリカ連邦準備制度理事会(FRB)も12年1月、異例の低金利が妥当となると見込まれる期間をそれまでの「2013年半ばまで」から「2014年遅くまで」に変更し、緩和的スタンスを強めた。