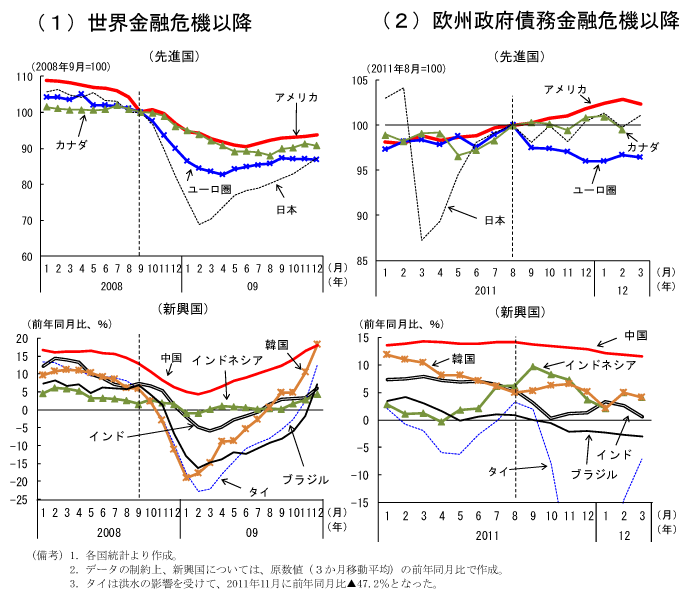2.貿易を通じた実体経済面への影響
11年夏以降に再燃した欧州政府債務危機は、金融機関の資金調達環境の悪化、企業活動の低下、消費マインドの低下等により、ヨーロッパ諸国の内需を低迷させた。こうしたヨーロッパの内需低迷は、貿易を通じて他の国々の経済に影響を及ぼし、アジアを中心とする一部の国の景気減速の一因となったと考えられる。ここでは、欧州政府債務危機がアジアといったヨーロッパ域外の国々に貿易面で如何なる影響を及ぼしたのかを概観する。
ユーロ圏向け輸出シェアをみると、中国をはじめとしたアジア主要国が2割を超えており、中でも中国は、ユーロ圏にとっての最大の貿易相手先となっている(第1-2-9図)。
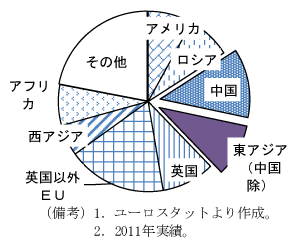
次に、ユーロ圏向け輸出の国別動向をみると、中国をはじめとするアジア諸国からユーロ圏への輸出が11年後半に減少しており、欧州政府債務危機を背景としたユーロ圏の需要低迷が、特にアジアからの輸出に影響を与えたことが分かる(第1-2-10図)。輸出依存度が高いアジア諸国ではとりわけヨーロッパ向け輸出の比重が高く、ユーロ圏向け輸出の減少がアジア諸国の輸出全体の減少をもたらしたものと考えられる。
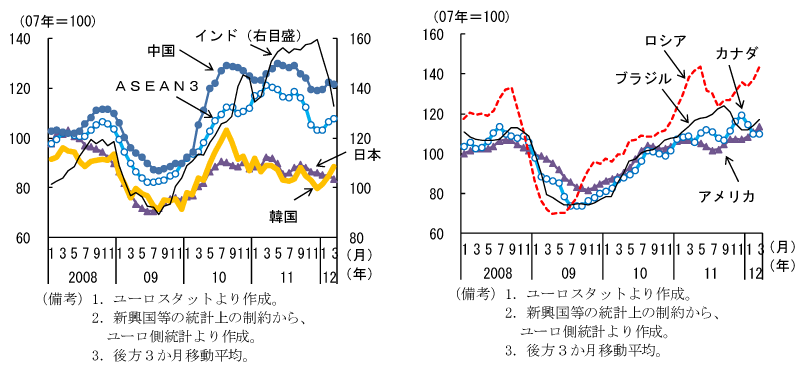
このような輸出の伸びの鈍化を一つの重要な背景として、アジア地域諸国では成長率が鈍化し、台湾やシンガポールなど一部の国・地域においては11年10-12月期の実質経済成長率がマイナスとなった4。
また、商品別のユーロ圏向け輸出動向をみると、11年秋以降の原油価格の高騰を背景に鉱物性燃料等のみが増加しており、アメリカ、カナダ、ロシアといった主に資源、燃料を輸出している国の輸出が減少していないことと整合的な動きとなっている(第1-2-11図)。一方、その他の品目は総じて低調な動きとなっており、とりわけ11年後半の電気製品等を含む一般・輸送機械の減少は、中国や韓国からのユーロ圏向け輸出全体の減少に大きく寄与していると考えられる(第1-2-12図)。ただし、12年に入るとこれら品目にも復調の動きがみられる。
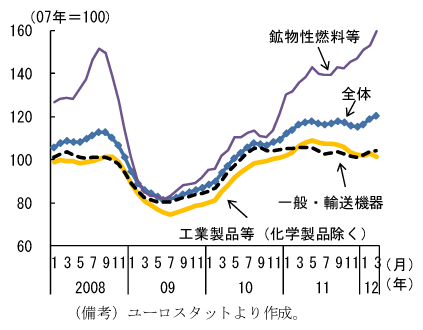
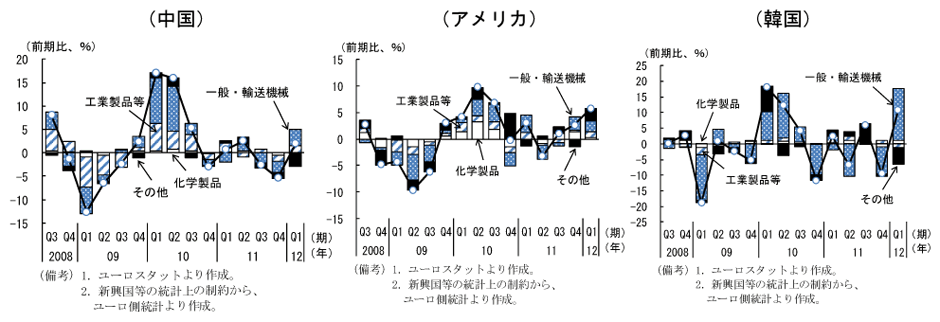
なお、輸出減少の生産への影響をみると、規模やスピードにおいて世界金融危機時ほどの深刻さはみられないが、11年末にかけて緩やかな減速を示している国が多い。タイの洪水といった他の要因の影響も関係している面はあるものの、欧州への輸出動向から一定の影響を受けていることが推察できる(第1-2-13図)5。