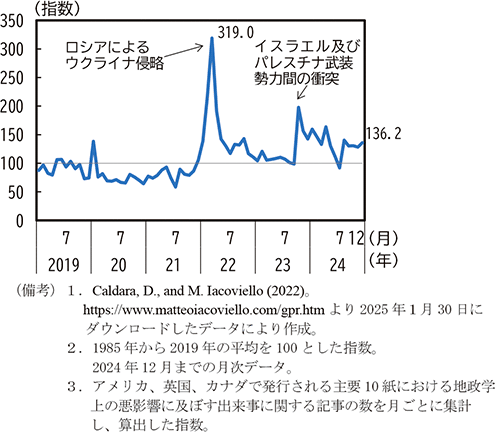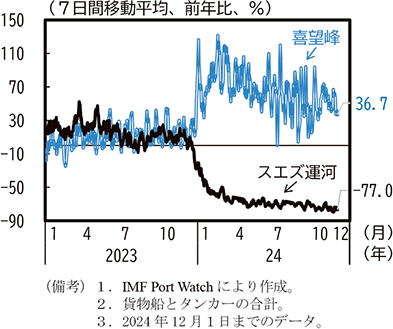第2章 2024年後半の世界経済の動向(第3節)
第3節 世界経済のリスク要因
これまで、第1章で中国経済について、第2章第1節、第2節で欧米経済について分析した。本節では、前節までの分析結果及び世界経済の見通しを踏まえて、先行きのリスク要因について分析する。
1.世界経済の見通し
(世界経済は安定して成長する見込み)
2024年12月に公表されたOECDの経済見通しでは、金融引締めの影響が緩和していくとともに、物価上昇率の低下に伴う政策金利の更なる引下げが金利動向に敏感な民間投資等を支えることにより、2025年の世界経済の成長率は3.3%に高まると予測されている(第2-3-1図)。2025年1月に公表されたIMFの中間見通しにおいても、2025年の世界経済の成長率は3.3%と堅調に推移することが予測されており、各国についてもおおむねOECDと変わらない見通しとなっている(第2-3-2図)。
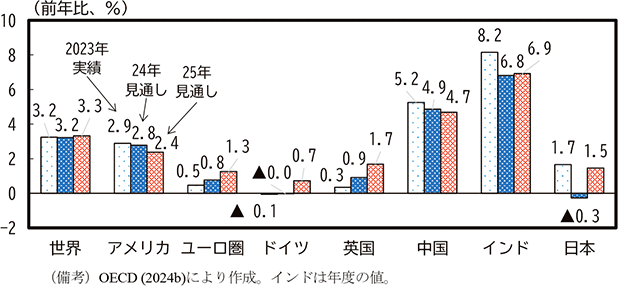
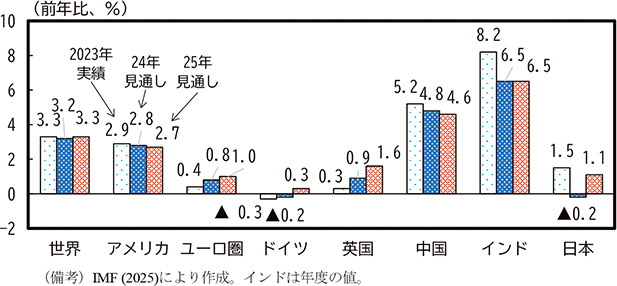
2.先行きのリスク要因
国際機関は2025年の世界経済について安定的な成長を予測しているが、本項では、前節までの分析結果を踏まえた先行きのリスク要因について整理する。
(アメリカの政策動向)
2024年11月5日179に行われたアメリカ大統領選挙では、中国に対する関税の引上げ、法人税率の引下げ、不法移民の強制送還等の政策を主張した共和党のトランプ候補が民主党のハリス候補に勝利し、2025年1月20日に大統領に就任した。第2章第1節で示したとおり、トランプ大統領は、就任直後、移民政策やエネルギー政策、気候変動対策等、アメリカ内外の経済に影響を与え得る様々な分野についての大統領令に署名を行った(第2-1-68表)。
アメリカは世界のGDPの約4分の1を占めており、アメリカ経済の動向は世界経済に大きな影響をもたらし得る。特に関税については、第一次トランプ政権時の米中貿易摩擦では、2018年以降数次にわたり、米中間で相互に関税を引き上げた結果180、2018年後半以降、アメリカ・中国ともに輸出は頭打ちとなった(第2-3-3図)。通商政策は、貿易等を通じて、直接的・間接的に世界各国の経済へ影響を与える可能性があることから、アメリカの政策動向とその影響には留意が必要である。
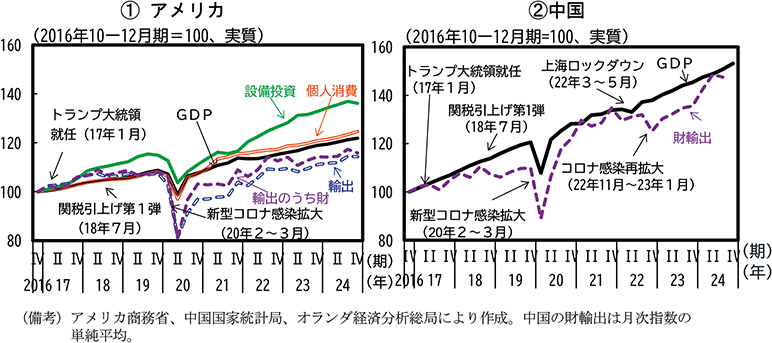
(欧米における高い金利水準の継続)
欧米の中央銀行の政策金利は、2023年夏以降のピーク時からは低下したものの(第2-1-107表)、依然としていわゆる中立金利よりは高い水準が継続している(第2-3-4表)。
欧米において政策金利が引き下げられる一方で、アメリカの長期金利は2024年10月以降上昇に転じており、アメリカの金利上昇に連動して英国でも長期金利は上昇、ドイツも2025年初にかけて上昇基調となっている(第2-3-5図)。このため、家計の住宅ローンの利払い費負担や企業の資金調達コストの高止まりから、経済活動が過度に抑制されることにより、景気が下振れるリスクは継続すると考えられる。また、政府による利払い費の高止まりにより、財政悪化への懸念が高まり、更に長期金利が上昇するリスクも考えられる。
さらに、ドイツやフランスでは、第2章第2節で示したとおり、財政規律の維持をめぐる状況が消費者マインドや設備投資マインドの低下を通じて消費や設備投資を押し下げる可能性があることにも留意する必要がある。
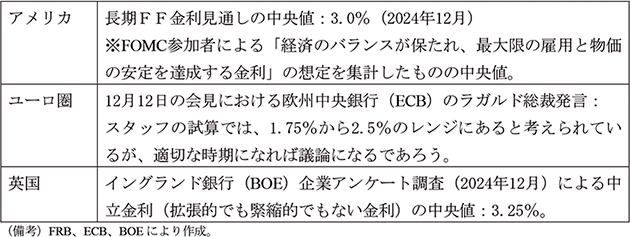
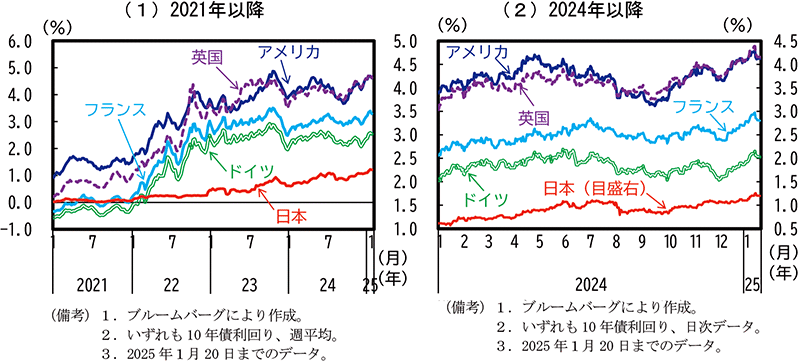
(中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響)
第1章で分析したとおり、中国では、不動産市場の停滞が継続する中で、相次いで打ち出された政策は製造業投資等の供給面の増加をもたらしているが、政策支援を受けた一部の品目を除けば消費は横ばいにとどまっており、景気は足踏み状態が続いている。我が国のバブル崩壊後の経験も踏まえると、人口減少局面での不動産市場の停滞は、解消に時間を要し、当面継続することが考えられる。不動産市場の停滞が長期化したり、住宅価格等の一層大幅な下落が生じたりすることによって更に中国の景気が下押しされた場合、貿易や投資を通じて世界全体としても景気が下振れるリスクがある。
(中東地域やウクライナ侵略をめぐる地政学的リスク)
足下の地政学的リスク指数をみると、ウクライナ侵略開始の影響があった2022年3月、イスラエル及びパレスチナ武装勢力間の衝突が発生した2023年10月と比較すると低いものの、中東情勢が悪化した2024年8月以降再び水準が高まっている(第2-3-6図)。
中東情勢は、イスラエル及びパレスチナ武装勢力間の衝突が発生した2023年10月7日以降、緊迫が続いており、欧州とアジア間の海運がスエズ運河を回避し、喜望峰回りとなる動きが続いている(第2-3-7図)。
また、ウクライナ侵略を受けて、欧州におけるエネルギー供給制約も継続しており、こうした地政学的緊張の高まりによって、例えば原油供給の減少、途絶が発生した場合、エネルギー価格の上昇を通じて、世界各国の物価上昇率に影響を与える可能性が考えられるため、中東地域やウクライナ侵略をめぐる情勢を引き続き注視する必要がある。