第2章 2024年後半の世界経済の動向(第2節)
第2節 欧州の景気動向
本節では、主に2024年後半のユーロ圏及び英国経済を概観するとともに、両地域の主要需要項目である個人消費、設備投資及び輸出を中心に分析する。あわせて、消費動向の背景にもあると考えられる雇用についても分析する。
1.ユーロ圏経済の動向
(景気は、総じて持ち直しの動き)
ユーロ圏経済の動向を実質GDPの推移から概観136すると、2022年後半以降、急激な物価上昇と金融引締めを受けて、実質GDPが横ばい傾向で推移してきた。その後、物価上昇率の低下に伴う実質賃金の上昇等を受けて消費は持ち直しの動きがみられること等から、2023年7-9月期以降実質GDP成長率はプラスで推移しており137、景気は、一部に足踏みがみられるものの持ち直しの動きがみられる(第2-2-1図)。
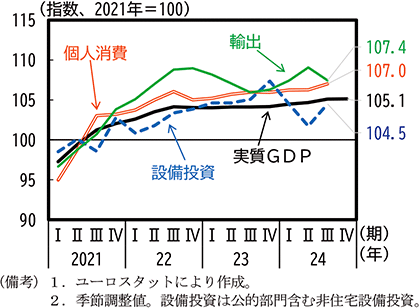
以下では、主要な需要項目である個人消費、設備投資及び輸出について分析する。
(個人消費は、持ち直しの動き)
はじめに、個人消費の動向を財の消費動向から確認する。
まず、実質小売販売額の動向をみると、2021年秋以降、感染症収束に伴う経済活動の再開やウクライナ侵略に伴うエネルギー価格等の高騰を受けた消費者物価の上昇により、実質小売販売額は、低下傾向が続いた。2023年後半以降は消費者物価の上昇の鈍化と名目賃金の上昇を受けて実質賃金がプラスで推移する中、消費は持ち直しの動きがみられている(第2-2-2図)。
しかしながら、自動車の新規登録台数の動向をみると、供給制約が解消された2023年9月以降も感染症拡大前の2019年を下回る水準で推移し、2024年12月においてもこの傾向が続いており、後述のとおり高額商品に対する購買意欲は戻っていない(第2-2-3図)。
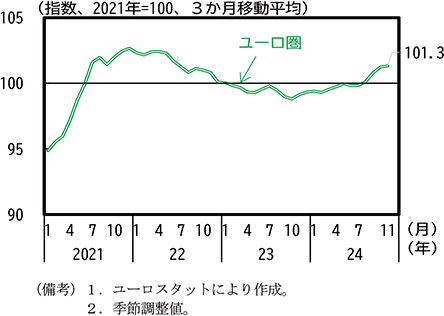
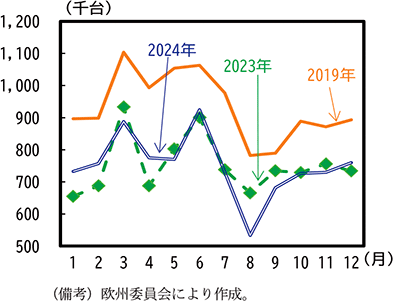
このような消費動向の説明要因となり得る、実質賃金の動向を確認する。前述の要因により、消費者物価上昇率が名目賃金上昇率を上回り、実質賃金の上昇率が2021年1-3月期以降マイナス傾向で推移していたが、消費者物価上昇率の低下と名目賃金上昇率の上昇を受けて、2023年7-9月期以降は実質賃金の上昇率がプラスで推移している(第2-2-4図)。
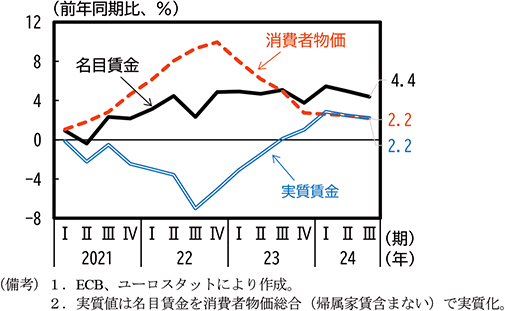
実質賃金の上昇率がプラスで推移している中でも消費の回復が緩やかなものにとどまる背景には、消費者信頼感(消費者マインド)138の改善ペースの弱さが考えられる。消費者マインドを構成する、家計の現状と先行き、経済見通し及び高額商品購買意欲の推移をみると、2024年に入って以降、家計の先行きは、消費者物価上昇率の低下を受けて、ほぼゼロ近傍まで改善しているが、経済見通しや高額商品購買意欲は、後述する雇用不安や物価見通しを受けた貯蓄志向の高さから、停滞している。
加えて、2024年6月以降、欧州中央銀行(ECB)は4回政策金利を引き下げているが、依然として政策金利は高い水準にとどまっており、これに伴うローン金利の高止まりもあいまって、高額商品購買意欲は改善の動きがみられず、消費者マインドは全体として改善ペースが弱い状況にある(第2-2-5図)。
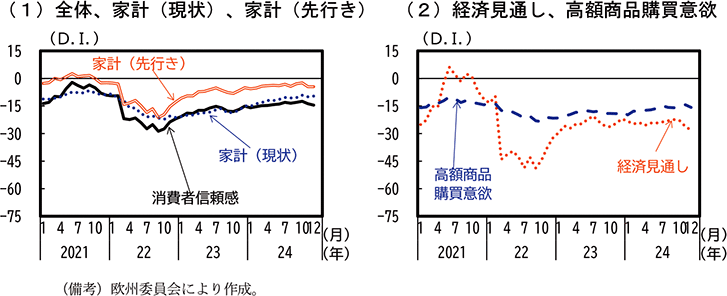
このように消費者マインドの改善ペースが弱いことから、超過貯蓄は引き続き増加傾向となっている。感染症拡大前の2019年各四半期の貯蓄額と比較して積みあがった超過貯蓄を、フロー及びストックベースでみると、フローは感染症収束に伴い低下傾向となっていたが、2022年半ば以降は緩やかな上昇傾向に転じている。これを受けて、ストックは、増加が継続している。この結果、超過貯蓄ストックは、GDP比でみて、ユーロ圏では2024年4-6月期は約11.4%(約1.7兆ユーロ)となっており、貯蓄を積み増す動きが続いていることが確認できる(第2-2-6図)。
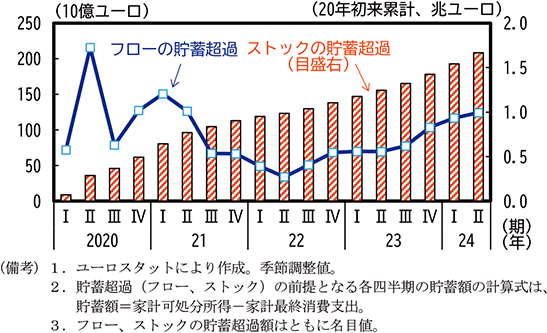
こうした超過貯蓄の増加の背景には、貯蓄志向の高まりが指摘されている。欧州委員会は、政策の先行き不透明感や雇用不安により、貯蓄志向が高まっていた可能性を指摘している。そこで貯蓄志向をみてみると、2022年2月以降、消費者物価上昇率の急激な高まりを受け貯蓄志向はマイナスに転じた。その後、消費者物価上昇率の低下を受け、2023年4月以降、貯蓄志向はプラスに転じ、2024年に入ってからはプラス幅が拡大し、感染症拡大前の2015年から2019年までの平均のマイナス3.3を上回って推移するなど、貯蓄志向の高まりが確認できる。加えて、雇用不安については、失業見通しをみてみると、感染症拡大期の2020年に大きく上昇したものの感染症の収束を受けて2021年夏頃には大きく低下している。さらに、ウクライナ侵略を契機としたエネルギー価格の上昇を受けた生産調整を背景に雇用不安は再び上昇に転じ、感染症拡大前の2015年から2019年までの平均の11.0を上回って推移している(第2-2-7図)。特に2024年夏以降は、ドイツの大手自動車メーカーが創業以来初となる国内工場閉鎖を検討していることが報じられたこと等により雇用不安は高まっており(第2-2-8表)、失業見通しは大きく上昇するとともに貯蓄志向は高止まりしている。
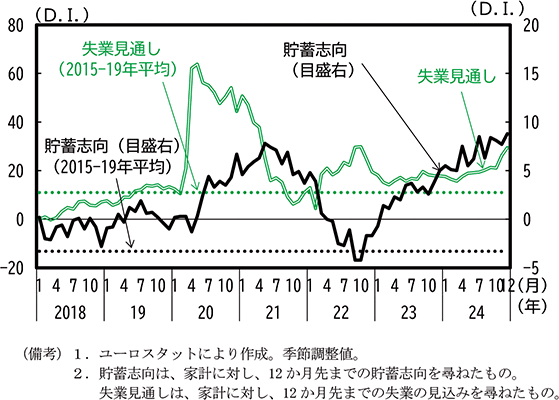
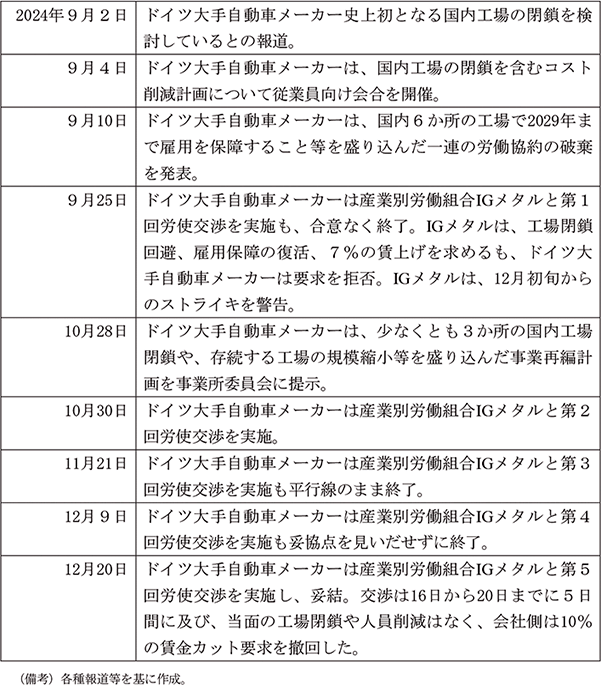
以上のように、消費は、総じてみれば持ち直しの動きがみられている。その背景には、実質賃金の持ち直しの動きがある。他方、持ち直しの動きが緩やかな背景には、政策の先行き不透明感や雇用不安を背景とした貯蓄意欲の高まりを受けた消費者マインドの改善ペースの弱さがある。
(設備投資は、弱含んでいる)
続いて、設備投資の動向を確認する。
2021年以降は、政策対応139を受けた脱炭素やデジタル化に向けた投資需要を中心に、知的財産生産物投資140、機械・機器投資及び構築物投資のいずれも持ち直しの動きがみられていた。しかし2023年以降は、政策の先行き不透明感に加え、高い金利水準の継続や中国等の輸出先の資本財需要の低下を受けた工場建設等を控える動きがみられ始めたことから、知的財産生産物投資、機械・機器投資及び構築物投資のいずれもおおむね横ばいとなっている。さらに、2024年半ば以降は、機械・機器投資は弱含んでおり、設備投資全体としても弱含んでいる (第2-2-9図)。
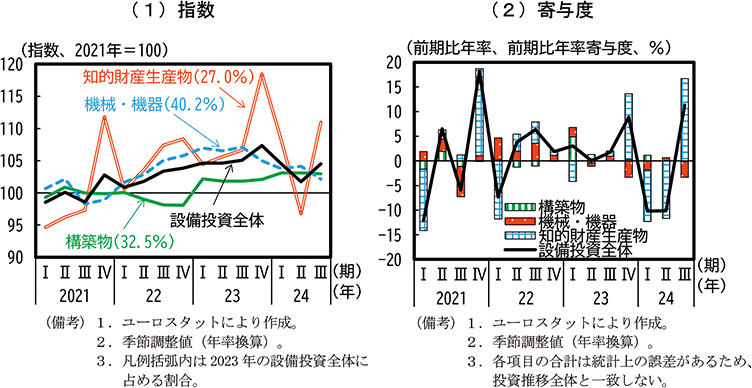
この背景には、政策の先行き不透明感による設備投資マインドの弱さが指摘されている。例えば、ドイツにおいては、成長機会法が規模を大幅に縮小して成立するなど政策の先行き不透明感に加え141、政府内対立を受けた政局の先行き不透明感から(第2-2-10表)、設備投資マインドの低下傾向が続いている(第2-2-11図)。
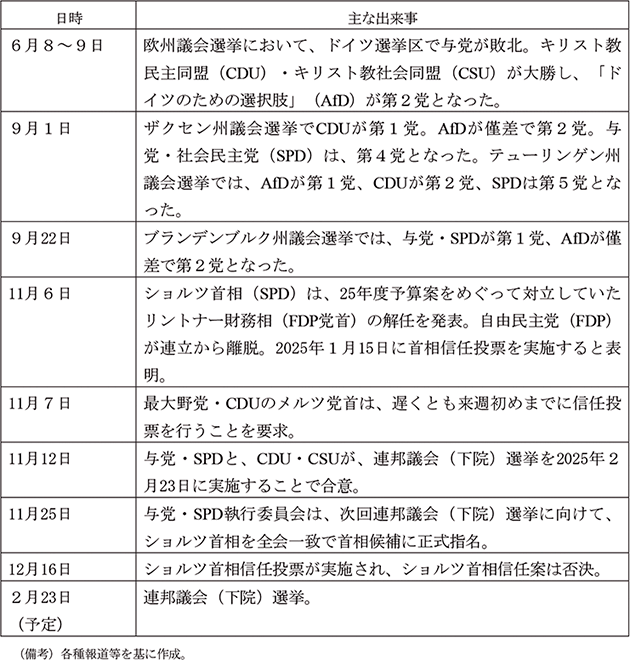
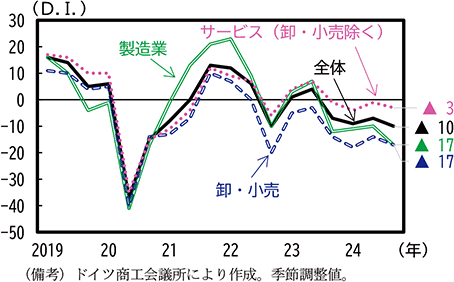
(財輸出は弱含んでいる)
続いて輸出の動向を確認する。
まず、財輸出及びサービス輸出の動向をみると、感染症拡大後の落ち込みから持ち直したものの、総じてみれば、2022年以降停滞している。輸出のうち、対GDP比で34.6%を占める財輸出では、2022年7-9月期以降弱含んでいる。一方、対GDP比で15.9%を占めるサービス輸出は2021年以降増加傾向にある(第2-2-12図)。
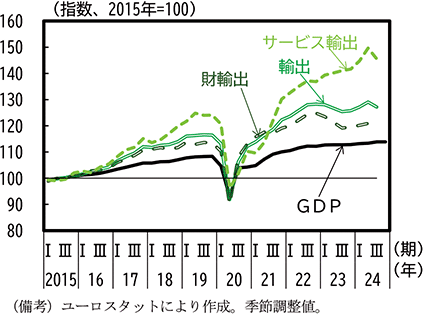
こうした動きの背景には輸出相手国の需要動向が考えられるため、相手国別の動向をみてみる。
まず、ユーロ圏外輸出における主要貿易相手国は米国(構成比15.9%)、英国(10.0%)、中国(7.1%)である。英国のEU離脱と感染症拡大を受けて2020年1月以降、財輸出は低下したが、米国向け輸出にけん引されて2020年8月以降は持ち直しの動きに転じた。2023年以降は中国の需要減退を受けて中国向け輸出は緩やかな減少傾向にあることから(詳細は後述)、財輸出は弱含んでいる(第2-2-13図)。
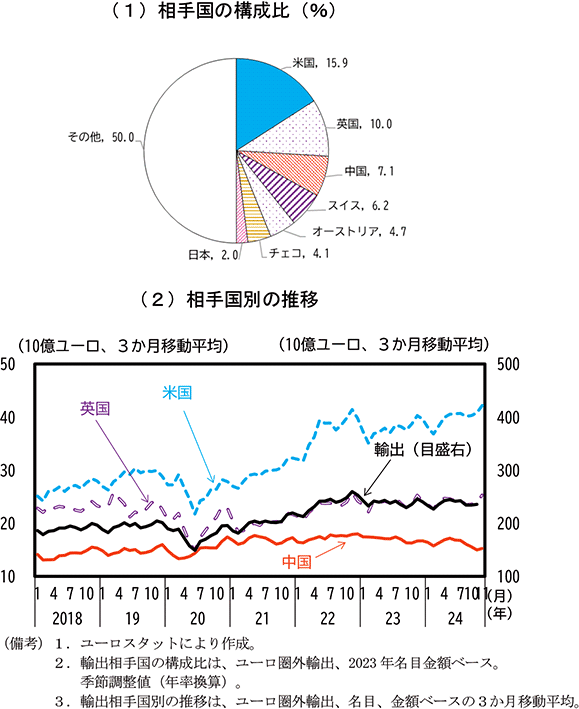
また、ユーロ圏外輸出の品目別では、化学・基礎薬品(構成比19.3%)、機械・機器(同12.7%)、自動車(同11.7%)が主要品目である。化学・基礎薬品は感染症が拡大する中でも堅調に推移しており、2020年以降財輸出をけん引している。アイルランドには大手製薬企業が集積していることから、医薬品の輸出が堅調に推移142しており、米国向けや英国向けの化学・基礎薬品がユーロ圏の財輸出をけん引していると考えられる。一方、機械・機器や自動車は、2022年秋以降停滞している(第2-2-14図)。
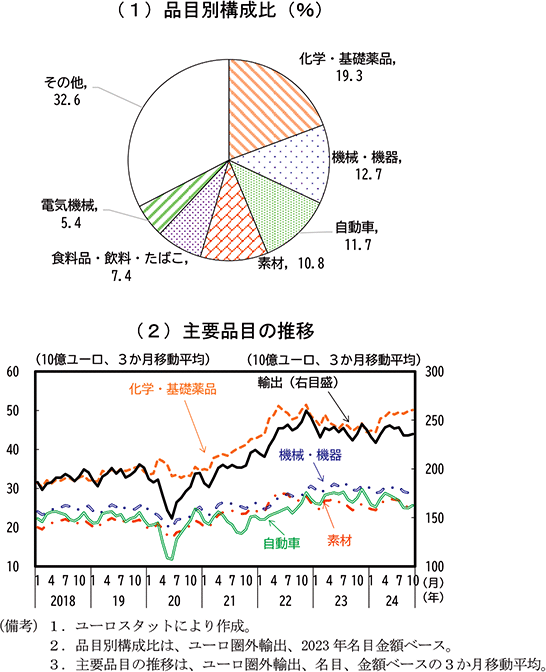
中国向けの財輸出の品目構成比をみると、機械・機器(18.1%)、化学・基礎薬品(17.8%)、自動車(14.4%)となっている。また主要品目の推移をみると、機械・機器は振れを伴いつつも緩やかな増加基調にあったが2024年6月以降減少に転じている。化学・基礎薬品は2023年2月から3月にかけて急増、2023年4月の上海ロックダウン発生後に急落し、その後はおおむね横ばいで推移している143。自動車については、2022年から2024年にかけて27.4%減少しており144、自動車輸出の低下が中国向け輸出を下押ししている(第2-2-15図)。
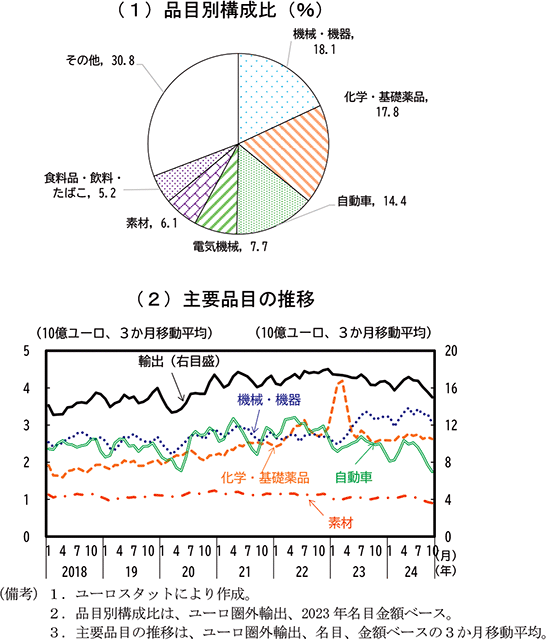
以上のように、圏外輸出は中国向け輸出が押し下げているが、自動車の中国向け輸出の鈍化がその主な要因であると考えられる。
(労働需給のひっ迫が続く)
続いて、消費動向の背景にある労働市場の動向を確認する。
まず、就業者数は、2021年以降増加傾向で推移しているが、2024年4-6月期以降伸びが緩やかになっている(第2-2-16図)。
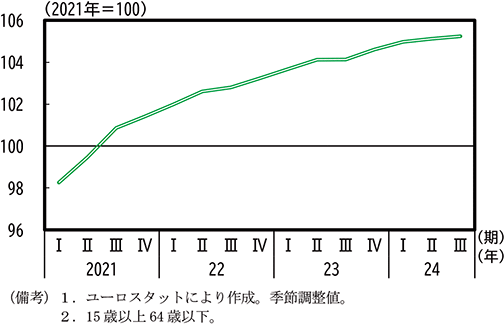
さらに、労働参加率をみると、感染症拡大以前から男女ともに労働参加率は上昇傾向にあるものの、女性の労働参加率は2024年7-9月期には70.8%と男性に比べ9.2%ポイント低く、労働力不足への対応の観点から改善の余地が大きいことが確認できる145(第2-2-17図)。
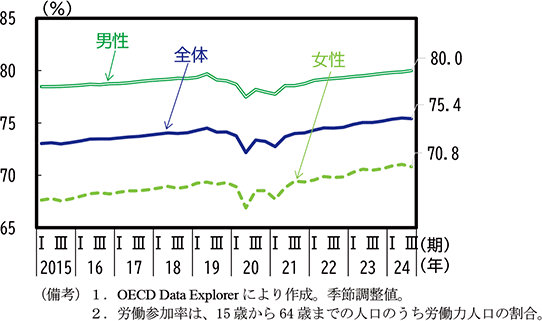
続いて、労働需要の強さを求人率146の動向から確認する。2021年以降、経済活動の再開等を受けて労働需要が増加したことから求人率が上昇し、2022年前半にかけて3.4%となった。その後、金融引締めを受けた労働需要の減速により低下傾向となったが、2024年7―9月期には2.5%と感染症拡大前の5年間平均と比べて0.6%ポイント高い水準にとどまり、引き続き感染症拡大以前と比べて大きな労働需要がみられる(第2-2-18図)。
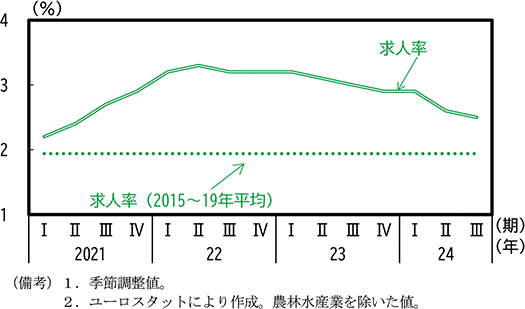
以上のように、就業者数は2021年以降増加傾向にある中で、求人率は、感染症拡大前をなお上回っている。
こうした中で、感染症拡大以降の労働需給のひっ迫を受け低下してきた失業率は、2024年12月において6.3%と引き続き歴史的な低水準を維持し、労働市場は引き続きひっ迫していると考えられる147(第2-2-19図)。
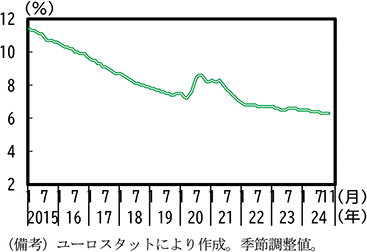
(輸入インフレ圧力は弱まりつつあり、消費者物価上昇率は低下傾向)
消費者物価上昇率(総合、前年比)は、2022年半ば以降低下傾向となり、2023年10月以降2%台で推移している(第2-2-20図)。要因としてはエネルギー価格上昇率の寄与の低下が挙げられる。住居費以外のその他サービス価格上昇率はおおむね横ばいで推移していたが、労働市場のひっ迫が続き、2023年7-9月期以降実質賃金のプラス幅が拡大していることを受け、2024年5月には物価上昇に対する寄与が高まっている。
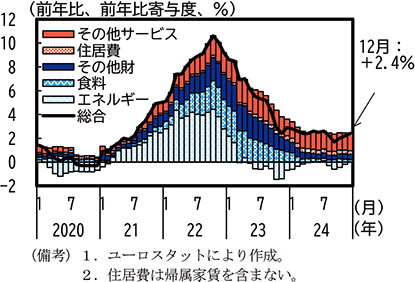
エネルギー、食料及びその他財の価格上昇率が低下している背景としては、輸入インフレ圧力の収束が考えられる。財及びサービスの輸入物価149(前年比)の動向をみると(第2-2-21図)、2022年前半から年半ばにかけては、ウクライナ侵略を受けたエネルギー及び食料価格の高騰(コラム2:図1)により、財を中心に輸入物価上昇率は加速した。しかしながら、2022年後半以降は、金融引締めの進展に伴う通貨高に加え(第2-2-22図)、エネルギー及び食料価格の下落(コラム2:図1)並びに国際物流コストの低下(第2-2-23図)を受け、輸入物価の上昇率は低下傾向となり、2023年以降はマイナスで推移している。こうしたことから、輸入インフレ圧力は一旦収束していると考えられる。
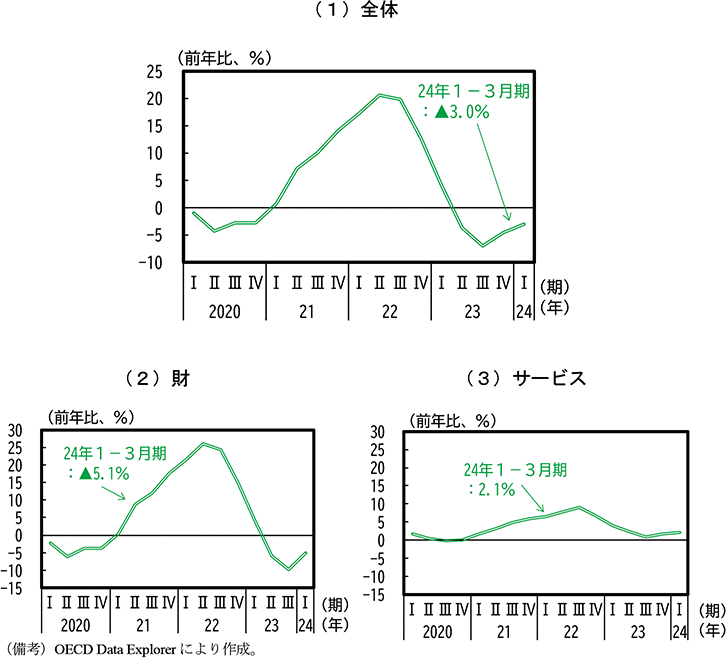
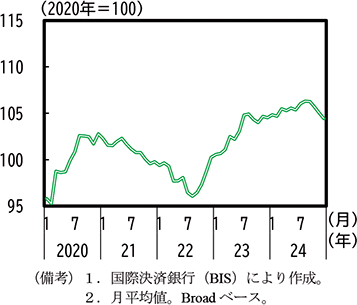
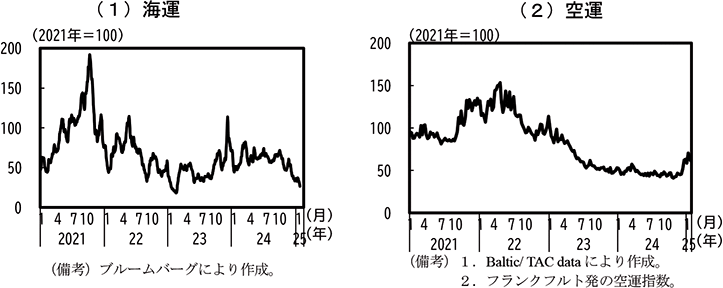
(ECBは物価上昇率の低下を受けて政策金利を引下げ)
ECBは、2022年夏以降、消費者物価上昇率の加速を受けて政策金利の引上げを継続してきたが、2023年秋以降は政策金利を据え置いてきた。その効果もあり消費者物価上昇率は2022年末以降低下傾向となった。2023年10月以降、消費者物価上昇率が安定的に2%台で推移してきたことを受け、ECBは2024年6月に政策金利である預金ファシリティ金利を0.25%ポイント引き下げて以降、9月、10月、12月、2025年1月とそれぞれ0.25%ポイント引き下げ、2.75%とした150 (第2-2-24図、第2-1-107表)。
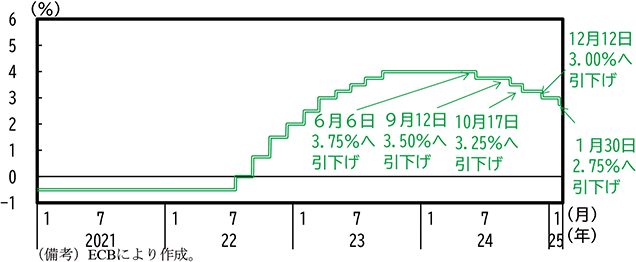
ECBは、今後の金融政策については、2024年1月の理事会において、データに依拠し、会合ごとに適切な政策スタンスを決定するアプローチをとるとしている。また、今後の政策金利については、経済・金融データによる物価上昇の見通し、基調的な物価変動、金融政策の波及状況に基づいて、会合ごとに決定するとしている。さらに、量的引締めに向けた保有資産の削減については、ECBはパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)において償還された元本の再投資を2024年7月より一部停止し、2025年1月以降は全て停止した(第2-1-107表)。
(財政規律の維持をめぐる状況)
感染症拡大に伴って一時的に停止した財政規律の再適用の動きがみられている。
欧州委員会では、一年の一般政府財政赤字の対GDP比が3%を超えないように義務付ける財政ルールである安定成長協定があるが、感染症拡大に伴って2020年から一時的に適用を停止していた。その後感染症収束を受け、2024年から安定成長協定が再適用されたものの、フランス等一部の国では安定成長協定に基づく財政規律の維持が直ちには困難であるため、2029年から2031年までを財政調整期間として中期財政計画を策定し、財政健全化を図ることとなっている。
ドイツでは、2024年の実質GDP成長率が2年連続でマイナス成長となった。このような状況の中、2025年予算案151において財政規律の維持をめぐる与党内の対立が生じた結果、リントナー財務相が解任される事態となっている。
またフランスでも、欧州委員会へ提出された中期財政計画に基づく2025年予算案について、歳出削減等が盛り込まれていたことから野党の強い反対を受け、2024年12月に否決されるとともに、バルニエ内閣が総辞職する事態に至っている(第2-2-25図)。
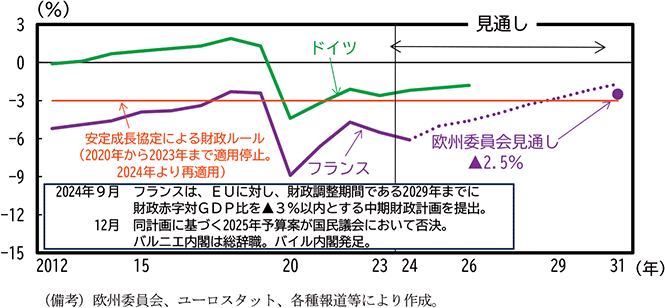
このように、財政規律の維持をめぐり対立する状況が消費者マインドや設備投資マインドの低下を通じて消費や設備投資を押し下げる可能性もある。財政政策の動向を注視する必要がある。
2.英国経済の動向
(景気は、総じて持ち直しの動き)
英国経済の動向を実質GDPの推移から概観152すると、英国では2022年後半以降、急激な物価上昇と金融引締めを受けて、実質GDPが横ばい傾向で推移してきたが、物価上昇率の低下に伴う実質賃金の上昇等を受けて、2023年10-12月期以降実質GDP成長率はプラスで推移しており153、景気は持ち直している(第2-2-26図)。
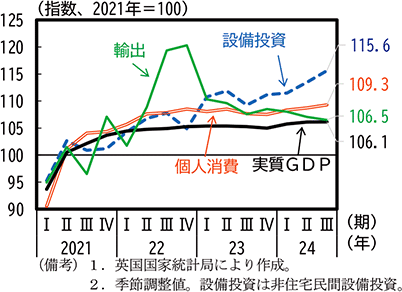
以下では、主要な需要項目である個人消費、設備投資及び輸出について分析する。
(消費は持ち直している)
はじめに、個人消費の動向を財の消費動向から確認する。
まず、実質小売販売額の動向をみると、2021年秋以降、感染症収束に伴う経済活動の再開やウクライナ侵略に伴うエネルギー価格等の高騰を受けた消費者物価の上昇により、実質小売販売額は、低下傾向が続いた。2023年後半以降は消費者物価の上昇の鈍化と名目賃金の上昇を受けて実質賃金の上昇率がプラスで推移する中、持ち直している(第2-2-27図)。
また、自動車の新規登録台数の動向をみると、供給制約が解消された2023年9月以降も感染症拡大前の2019年を下回る水準で推移したが、2024年12月においては感染症拡大前の水準に回復している(第2-2-28図)。
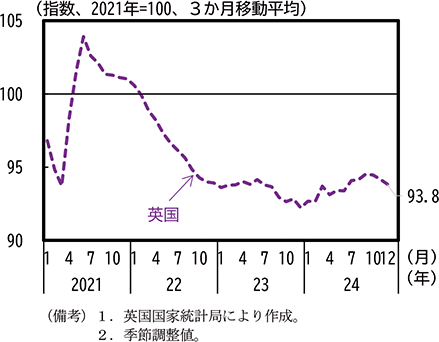
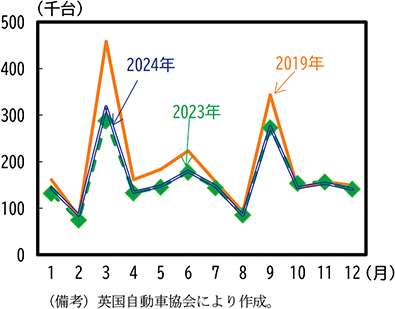
このような消費動向の説明要因となり得る、実質賃金の動向を確認する。前述の要因により、消費者物価上昇率が名目賃金上昇率を上回り、実質賃金の上昇率が2022年4-6月期以降マイナス傾向で推移していたが、消費者物価上昇率の低下と名目賃金上昇率の上昇を受けて、2023年4-6月期以降は実質賃金の上昇率がプラスで推移している(第2-2-29図)。
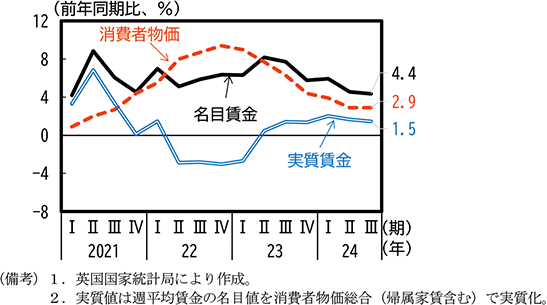
また、消費者信頼感をみると、2024年に入って以降、家計の先行きは、消費者物価上昇率の低下を受け改善が続き、2024年6月にはプラスとなった。しかし、2024年8月、10月末に提出される秋季予算において家計負担が増える可能性が報じられたことを受け154、2024年9月に家計の先行きはマイナスに転じるとともに、経済見通しや高額商品購買意欲はマイナス幅が拡大した。2024年10月末に発表された秋季予算では、国民年金保険料の負担を企業に求めるものであることが判明すると、高額商品購買意欲のマイナス幅は縮小に転じ、2024年12月には、家計の先行きはプラスに転じている。
ただし、2024年6月以降、イングランド銀行は2回政策金利を引き下げているが、依然として政策金利は高い金利水準にとどまっており、これに伴うローン金利の高止まりもあいまって、高額商品購買意欲は改善の動きが鈍く、消費者信頼感(消費者マインド)は全体として改善ペースが弱い状況にある(第2-2-30図)。
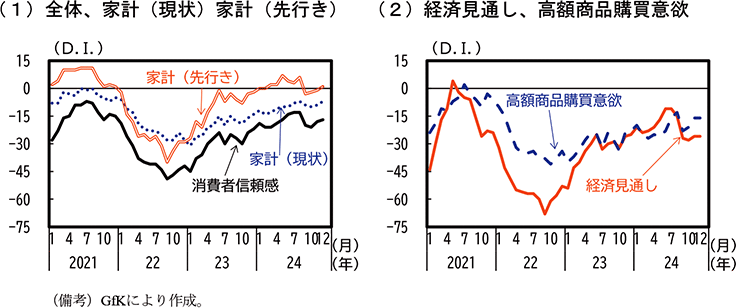
このように消費者マインドの改善ペースが弱いことから、超過貯蓄は引き続き増加傾向となっている。感染症拡大前の2019年各四半期の貯蓄額と比較して積みあがった超過貯蓄を、フロー及びストックベースでみると、フローは感染症収束に伴い低下傾向となっていたが、2022年半ば以降は緩やかな上昇傾向に転じている。これを受けて、ストックは、同様に2022年半ば以降は緩やかな増加傾向にある。この結果、超過貯蓄ストックは、GDP比でみて、2024年7-9月期は約13.8%(約0.4兆ポンド)となっている(第2-2-31図)。
こうした超過貯蓄の増加の背景について、OECD155は、スナク内閣の支持率は低迷し、政策の先行き不透明感から、貯蓄志向が高まっていた156と指摘している。
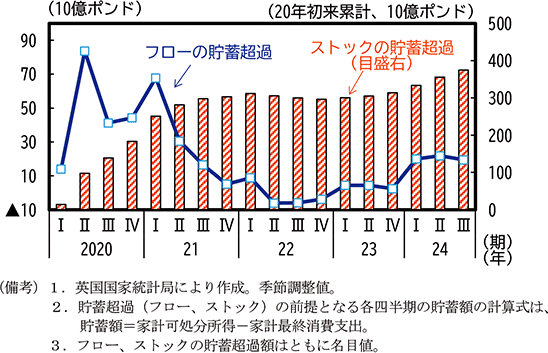
以上のように、消費は、実質賃金が持ち直しの動きをみせる中でも、政策の先行き不透明感から消費者マインドの改善ペースの弱さがみられるが、総じてみれば持ち直している。
(設備投資は、持ち直しの動きがみられる)
英国においても、ユーロ圏と同様に政策対応を受けた脱炭素やデジタル化に向けた設備投資需要から、2021年以降、知的財産生産物投資、機械・機器投資及び構築物投資のいずれも持ち直してきた。金融引締めやEU離脱に伴う経済の先行きに対する懸念、さらには2023年半ば以降は政策の先行き不透明感もあいまって機械・機器投資及び知的財産生産物が減速した。2024年7月にスターマー内閣が発足して以降、設備投資マインドは上向いており、2024年7-9月期には機械・機器投資及び知的財産生産物が持ち直しの動きがみられている。設備投資全体としては持ち直しの動きがみられている(第2-2-32図)。
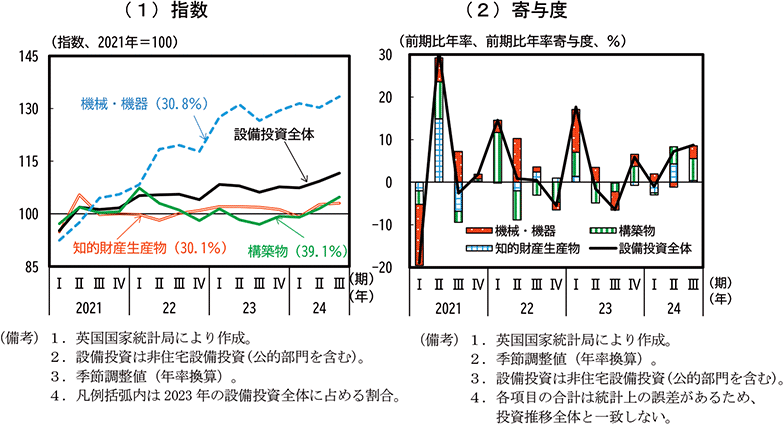
加えて、設備投資マインドをみてみると、2023年11月以降、政局不安から設備投資マインドは横ばいで推移していたが、2024年7月のスターマー内閣の発足と2024年8月以降の政策金利の引下げもあいまって、設備投資マインドはプラスで推移しており、引き続き設備投資は持ち直しの動きが続いていくことが期待される(第2-2-33図)。
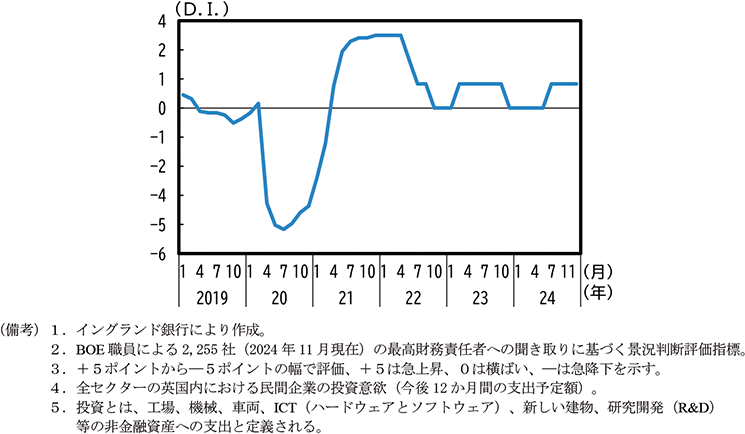
以上のように、高い金利水準の継続の中でもマインドの改善を受け、設備投資は持ち直しの動きがみられている。
(財輸出は、持ち直しているがこのところ一服感がみられる。サービス輸出は、緩やかに増加しているものの、一服感がみられる)
続いて輸出の動向を確認する。
2020年1月のEU離脱と、感染症拡大があいまって、2020年4-6月期に財輸出、サービス輸出ともに大きく減少した。その後、対GDP比で14.6%を占める財輸出は、一時的な増加を除き157減少傾向にあった。2024年4-6月期を底に持ち直しているものの158、感染症拡大前の水準を回復していない。対GDP比で16.5%を占めるサービス輸出は、感染症の収束を受けて緩やかに増加傾向が続き、2024年7-9月期以降一服感がみられるものの159、感染症拡大前の水準を超えて推移している(第2-2-34図)。
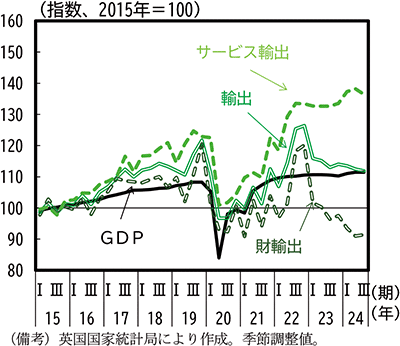
こうした動きの背景には輸出相手国の需要動向が考えられるため、相手国別の動向をみてみる。
まず財輸出の輸出相手国別の動向をみると、主要輸出相手国は、米国(構成比15.3%)、ドイツ(8.6%)、オランダ(7.8%)、アイルランド(7.1%)、中国(5.6%)となっており、ユーロ圏160に比べ、英国は、中国への依存度が低い。輸出相手国別の推移をみると、財輸出は2023年9月以降緩やかな低下傾向にあるが、米国向け財輸出は高止まりする一方、ドイツやアイルランド等ユーロ圏向けの輸出は2023年以降減少傾向が続いており、英国の財輸出を下押ししている161(第2-2-35図)。この要因について、OECD162は、英国のEU離脱の影響を指摘している。なお、中国向け輸出は、中国における感染症拡大時の2021年12月と、2022年2月のウクライナ侵略を受けた2022年10月に急増している163が、おおむね2023年以降、停滞している。
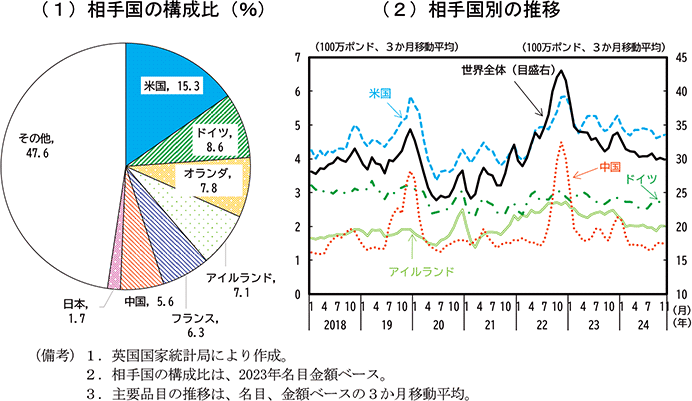
次に、サービス輸出の動向をみると、主要輸出相手国は、米国(27.0%)、アイルランド(6.3%)、ドイツ(6.2%)となっている。また相手国別の推移をみると、米国向けがけん引する形で緩やかな増加傾向にある。また、ドイツやアイルランド等ユーロ圏向けのサービス輸出も緩やかな増加傾向にあり、総じてみれば緩やかな増加傾向にある164(第2-2-36図)。
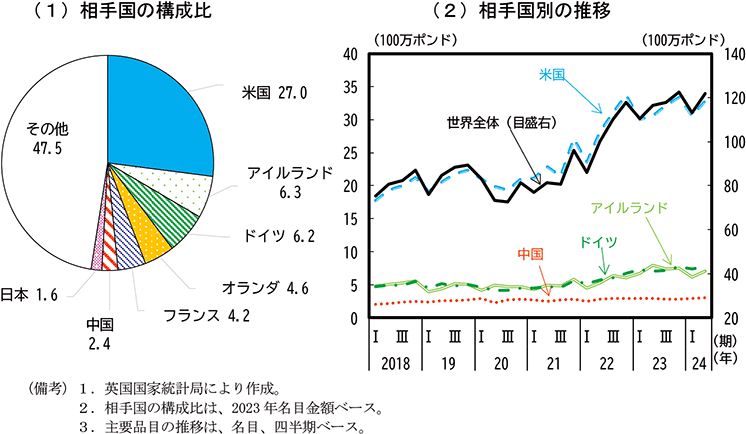
以上のように、財輸出、サービス輸出とも対米国向け輸出が堅調に推移している。しかしながら、財輸出は、EU離脱の影響等からユーロ圏向けが停滞しており、総じてみれば緩やかな減少傾向にあるが、このところ持ち直している。サービス輸出は、米国向けに加えユーロ圏向けも堅調に推移しており、総じてみれば緩やかな増加傾向にある。
(労働需給のひっ迫は解消)
続いて、消費動向の背景にある労働市場の動向を確認する。
まず、就業者数は2021年以降増加傾向にあったが、2023年以降おおむね横ばい傾向で推移している(第2-2-37図)。
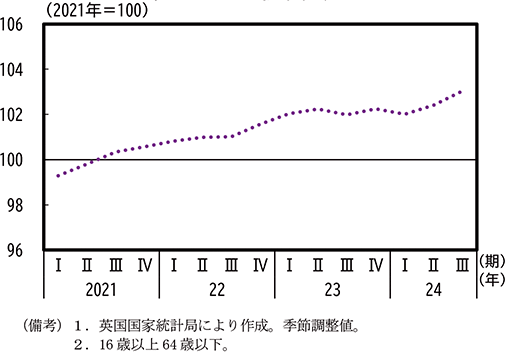
さらに、労働参加率をみると、感染症拡大後、男性の労働参加率が精神疾患等長期疾病に伴う非労働力化等の影響を受け、2019年10-12月期から2024年4-6月期にかけて2.7%ポイント低下したこと等から、全体としては2.4%ポイント低下しているが、ユーロ圏と比較して高い水準を維持している(第2-2-38図)。
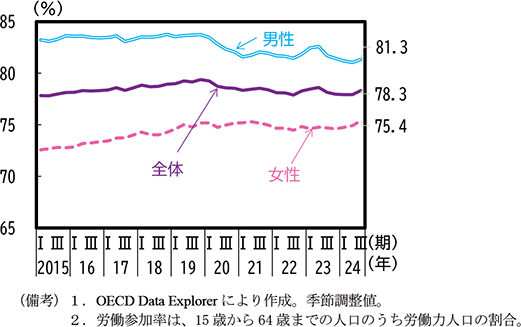
続いて、労働需要の強さを求人率165の動向から確認する。2021年以降経済活動の再開等を受けて労働需要が増加したことから求人率が上昇し、2022年前半にかけて3.8%となった。その後、金融引締めを受けた労働需要の減速により低下傾向となった。2024年7-9月期には2.5%と感染症拡大前とおおむね同水準まで低下しており、労働需要はおおむね感染症拡大以前と同水準まで縮小したものと考えられる(第2-2-39図)。
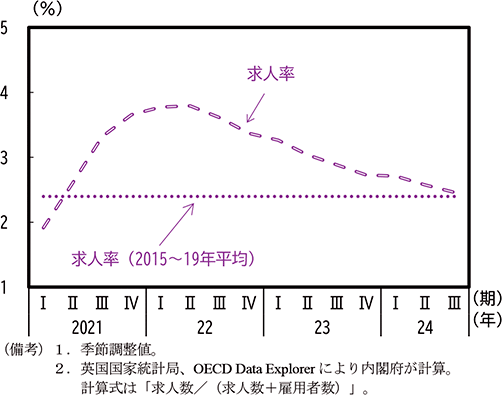
以上のように、就業者数は2023年以降はおおむね横ばい傾向で推移し、労働参加率は引き続き高い水準を維持している。求人数は、おおむね感染症拡大前と同水準まで減少したものとみられる。
このため、失業率は、低い水準にあった2022年に比べ2023年に入って以降は上昇し、その後おおむね横ばいで推移していることから、労働市場のひっ迫が解消しつつあると考えられる166(第2-2-40図)。
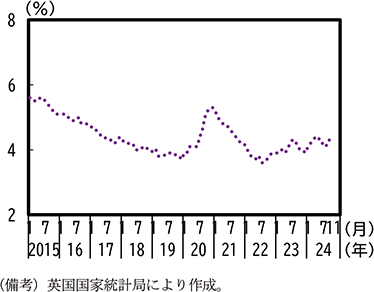
コラム4 英国の雇用統計の動向
英国の雇用情勢を計測する統計については、労働力調査や求人数調査等が存在するが、代表的なものは労働力調査である。
労働力調査は国家統計局が実施するもので、失業率、就業者数、失業者数、非労働力人口(People economically inactive)等を167、サンプルとして抽出された家計に対し対面で実施する調査である。感染症拡大前の2019年10-12月期の回答率は約40%程度であったが、感染症拡大期において対面形式での調査が困難となったことから電話形式に切り替えた結果、回答率が大幅に落ち込み、2023年7-9月期には約13%まで低下した(図1)。
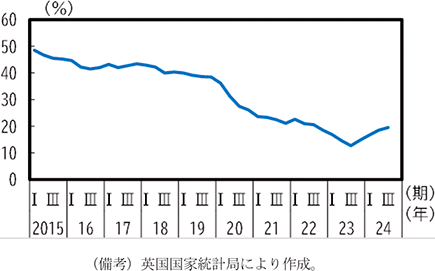
このため、労働力調査で把握される就業者数の動向が、後述する源泉徴収票ベースの雇用者数調査で把握される雇用者数の動向とかい離する168等、統計上の不確実性が高まっていたことから、英国国家統計局は2023年10月169以降、労働力調査により公表される失業率、就業者数、失業者数及び非労働力人口について公表を停止した(図2)。
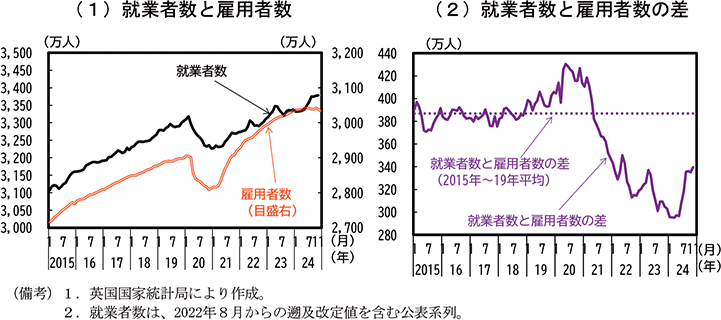
この問題に対処するため、国家統計局は、サンプル数の増加170や、オンラインでの調査の試行等回答率の向上を図る対策を講じた。
また、統計上の不確実性が高まっていた要因には、移民の純流入が適切に反映されていなかったことも考えられた。このため、移民の動向を反映した2021年国勢調査におけるイングランド及びウェールズの調査結果が2023年11月に先行的に公表されたことを受け、2024年2月、推計の基礎データを差し替えて失業者数等を暫定推計値として公表を再開した。この際、公表を停止していた2023年8月値以降のデータも遡及的に公表する形で公表した171(図3~図6)。
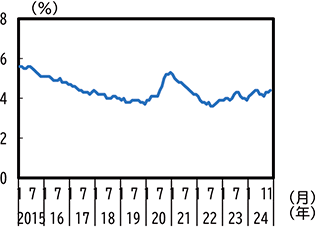
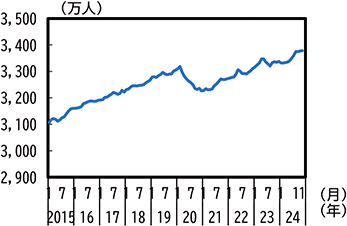
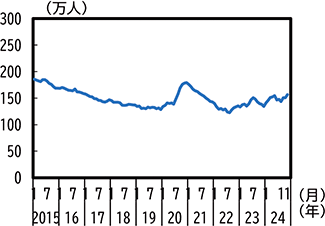
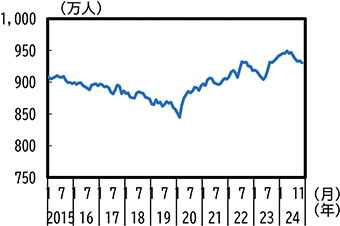
(備考)1. 英国国家統計局により作成。
2. 2022年8月からの遡及改定値を含む公表系列。
しかしながら、労働力調査においては統計としての信頼性の不透明感が依然として残るため、英国当局は労働市場の分析等をする際には、労働力調査だけでなく他の雇用統計も考慮に入れることを推奨している。
国家統計局が考慮すべき雇用統計として例示しているものには、求人数統計(Vacancy statistics、図7)や源泉徴収票ベースの雇用者調査(Earnings and Employment from Pay As You Earn Real Time Information、図8)等が挙げられる。
国家統計局が作成する求人数統計は、企業へのアンケートを通じて、企業の総求人数を算出したものであり、2001年4月より毎月作成されている(2023年6月から公式に国家統計となった)。サンプルとなる企業数は約6,100社であり、毎回含まれる1,400社の大企業と、四半期ごとにランダムに抽出される残りの4,700社の中小企業から構成されている。
源泉徴収票ベースの雇用者調査は、歳入関税庁(dsHis Majesty's Revenue and Customs)及び国家統計局が英国に在住する雇用主が当局に提出する税関連の情報を用いて作成しており172、2014年7月より毎月公表されている。この調査はオンラインで行われる、全雇用者を対象とした全数調査である。2024年12月時点では、約3,034万人が調査対象となっている規模の大きなオープンデータ173であることに加え、オンラインで行われる業務統計を2次利用しているため速報性が高いという特徴がある。
国家統計局は、労働力調査については2025年1―3月期に、2024年10-12月期のモニタリング結果を公表することとしており、失業率等についての信頼性の不透明感は今後も続く可能性がある。このため、内閣府においては、英国の労働市場を分析する際には、これら2つの統計も踏まえ総合的に雇用情勢を判断している174。
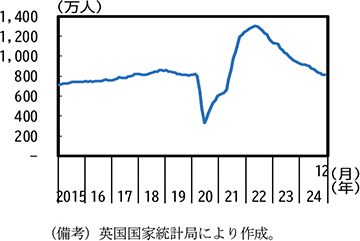
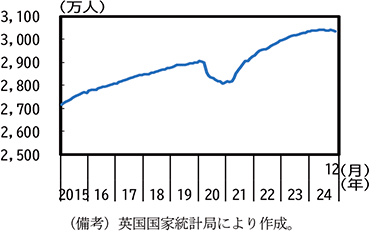
(輸入インフレ圧力は弱まりつつあり、消費者物価上昇率は低下傾向)
消費者物価上昇率(総合、前年比)は、2022年半ば以降低下傾向となり、2024年5月には2.0%まで低下している(第2-2-41図)。要因として、エネルギー及び食料等財価格の上昇率低下が挙げられるが、2023年10月以降は、エネルギー価格上昇率の低下が全体の消費者物価上昇率を1%ポイント程度押し下げている。住居費以外のその他サービス価格上昇率はおおむね横ばいで推移している。
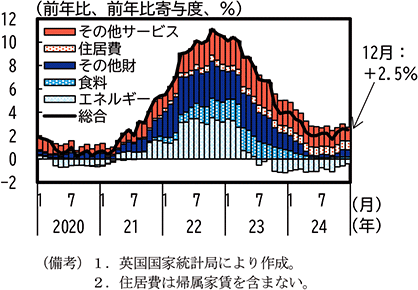
エネルギー、食料及びその他財の価格の上昇率が低下している背景としては、輸入インフレ圧力の収束が考えられる。財及びサービスの輸入物価175(前年比)の動向をみると(第2-2-42図)、2022年前半から年半ばにかけては、ウクライナ侵略を受けたエネルギー及び食料価格の高騰(コラム2:図1)により、財を中心に輸入物価上昇率は加速した。しかしながら、2022年後半以降は、金融引締めの進展に伴う通貨高に加え(第2-2-43図)、エネルギー及び食料価格の下落(コラム2:図1)並びに国際物流コストの低下(第2-2-44図)を受け輸入物価の上昇率は低下傾向となり、2023年以降はマイナスで推移している。こうしたことから、輸入インフレ圧力は一旦収束していると考えられる。
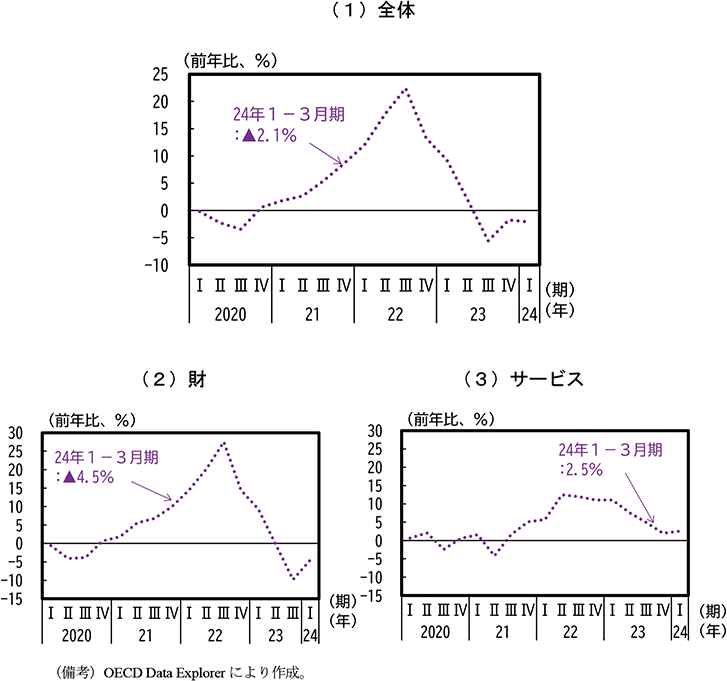
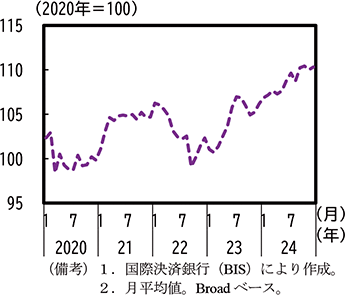
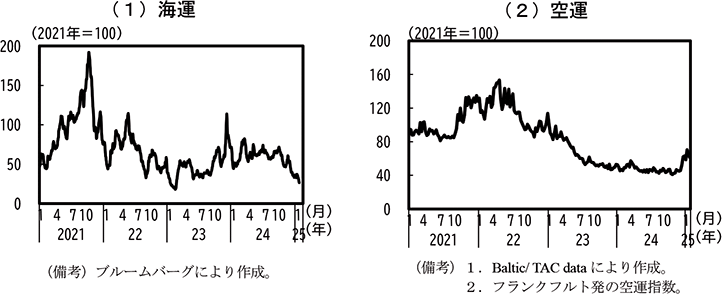
(BOEは物価上昇率の低下を受けて政策金利を引下げ)
イングランド銀行(BOE)は、2021年末以降、消費者物価上昇率の加速を受けて政策金利の引上げを継続してきたが、2023年秋以降は政策金利を据え置いてきた。金利引上げの効果もあり消費者物価上昇率は2022年末以降低下傾向となった。2024年5月以降、消費者物価上昇率が2%台で推移してきたことを受け、BOEは政策金利のバンクレートを2024年7月、11月、2025年2月とそれぞれ0.25%ポイント引き下げ、4.50%とした(第2-2-45図、第2-1-107表)。
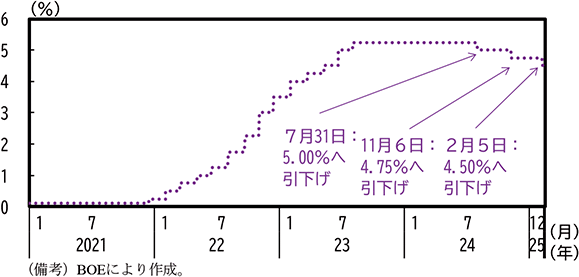
また、BOEは、保有する英国国債の削減を進めている。2022年2月に満期を迎えた国債の再投資を中止して以降、金融政策目的で保有する国債を削減しており、2024年9月の金融政策委員会において、2025年9月までに金融政策目的で保有する国債を1,000億ポンド176削減することを公表している。
今後の金融政策については、2025年2月の金融政策委員会において、中期的に物価上昇率を持続可能な形で2%の目標まで戻すためには、委員会の任務に沿って、十分な期間、十分に制約的な金融政策であり続ける必要があるとの認識を示した(第2-1-107表)。
(利払い費の拡大等財政状況に留意が必要)
英国においては、財政規律と競争力の向上に資する財政支出の両立が課題となっている177。英国国債の長期金利は、おおむね米国国債の長期金利に連動して上昇傾向にあるが、2025年1月には、いわゆるトラスショックが生じた2022年9月当時と同水準まで急激に上昇している(第2-2-46図)。
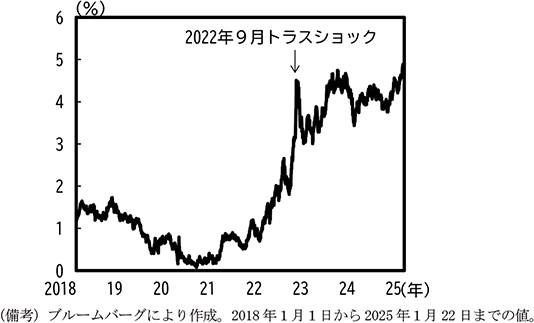
この背景には、財政状況に対する市場参加者の懸念が考えられる。そこで、公共部門債務残高対GDP比178をみてみる。
2024年3月に公表された2024年春季予算における予測値において、公共部門債務残高対GDP比は、2024年-2025年の98.8%をピークに低下傾向になり、2028年-2029年には94.3%となる見通しが示されていた。しかし2024年10月に公表された2024年秋季予算における予測値において、公共部門債務残高対GDP比は、2024~25年に98.4%とピークを迎えるもののおおむね横ばいで推移し、2028年-2029年には97.1%となる見通しが示されている(第2-2-47図)。
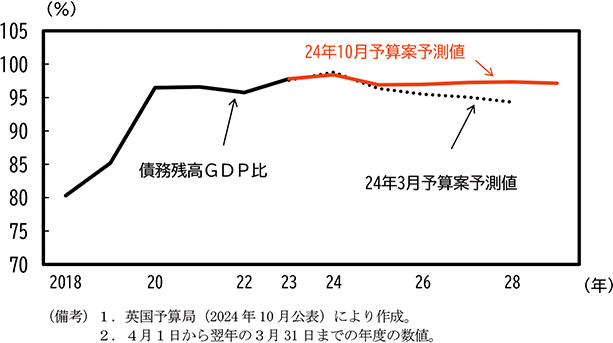
さらに、公共部門支出対GDP比をみると、英国国債の利払い費は感染症拡大前である2019年の1.7%から、2023年には3.9%と2.3倍となっており、2024年以降も同程度で推移する見通しとなっている(第2-2-48図)。
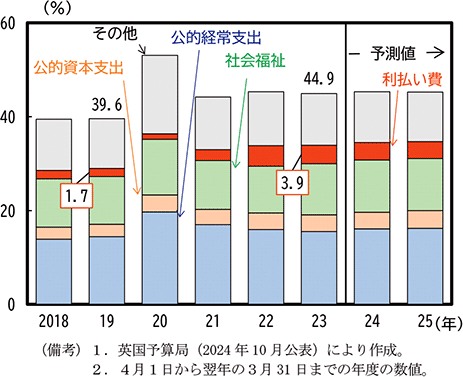
このように、英国国債金利の上昇が続き、利払い費の増加は高止まりする見通しである等、財政状況に留意する必要がある。
(まとめ:景気の先行きは持ち直しが期待される)
これまでみてきたように、物価上昇率が低下する中で、ユーロ圏、英国ともに実質GDP成長率は2024年7-9月期でプラスとなり、景気は総じて持ち直している。なお、英国と比べると、ユーロ圏では消費、設備投資及び輸出の弱さがみられるなどの違いもみられる。
先行きについては、ユーロ圏及び英国ともに、政策金利の高止まりの長期化に伴う下振れリスクには留意する必要があるものの、景気は持ち直すことが期待される。個人消費は、名目賃金の上昇傾向が続く中で、消費者物価上昇率の低下を受けた実質可処分所得の増加とともに、政策金利引下げ期待の高まりによる消費者マインドの改善、それに伴う超過貯蓄の取崩しを受けて、緩やかに持ち直していくことが考えられる。
設備投資については、英国では、政策金利の引下げとともに脱炭素やデジタル化に向けた政策効果が発現する一方、ユーロ圏では、政策の不確実性により、引き続き弱含みで推移することが懸念される。
さらに、ユーロ圏、英国ともにアメリカの政策動向を受けた世界経済の変動に留意する必要がある。英国については、これに加え、2024年12月に発効したCPTPPへの加盟による市場拡大の影響に留意する必要がある。
また、ユーロ圏、英国ともに財政状況をめぐる動向を注視する必要がある。

