第2章 2024年後半の世界経済の動向(第1節)
第1節 アメリカの景気動向
本節では、主に2024年後半のアメリカ経済を概観するとともに、州ごとの構造的な問題について分析する。
1.マクロ経済の動向
(アメリカの景気は拡大している)
アメリカ経済は、個人消費を中心とした景気拡大が続いている。実質GDPと潜在GDPの推移をみると、2021年4-6月期以降、実質GDPが潜在GDPを上回る状況が続いている(第2-1-1図)。実質GDP成長率をみると、2022年1-3月期は輸入の増加により純輸出がマイナス寄与したことから、一旦、減速したものの、2022年4-6月期はプラスに転じ、2022年7―9月期以降、前期比年率で3%程度の成長を続けている(第2-1-2図)。2024年10-12月期(1次推計値)は前期比年率2.3%と同年7―9月期(前期比年率3.1%)からやや減速したものの、GDPから外需や在庫投資を除いた国内最終需要43は前期比年率3.1%と伸びが高く、GDPの68%を占める個人消費44は堅調な成長を続けている(第2-1-3図)。
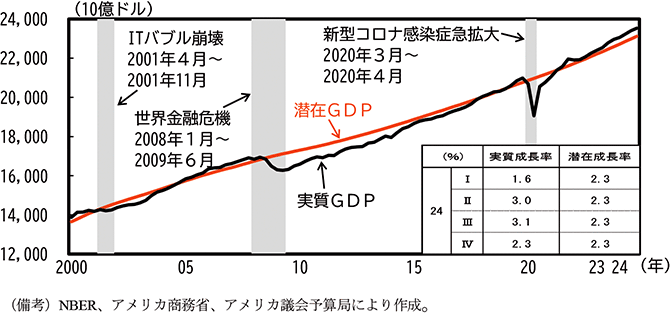
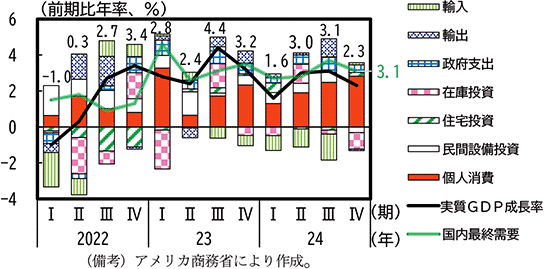
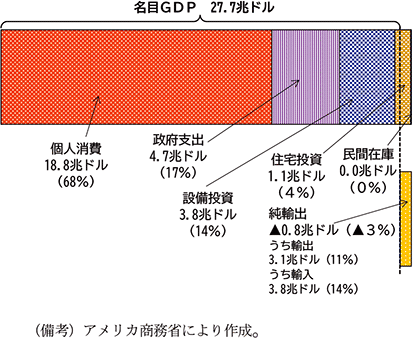
2024年9月26日にアメリカのGDP統計45の2024年年次改定(2024 Annual Update)が行われ、2019年以降のGDP等の計数が改定された。その結果、2019年以降の各四半期において実質GDPの水準が上方改定された(第2-1-4図)。2022年以降の実質GDPの平均成長率46は、改定前の年率2.0%から改定後には年率2.3%に上方改定されており47、近年のアメリカ経済がこれまで想定されていたよりも力強く成長していたことが示されている。
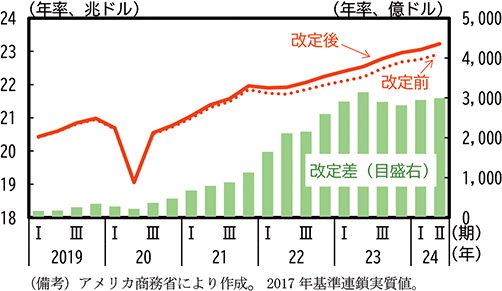
コラム1 アメリカのGDP統計の年次改定について48
アメリカのGDP統計は、各四半期に3回、1次推計値(Advance Estimate)、2次推計値(Second Estimate)、3次推計値(Third Estimate)として公表されるほか、年に1回、年次改定が行われる(表1)。年次改定では、「サービス年次調査」(Service Annual Survey)や「年次小売取引調査」(Annual Retail Trade Survey)等の新しく入手可能となった年次の基礎統計の反映等が行われ、過去5年程度の計数の改定が行われる49。今回の 2024 年年次改定では、2019 年以降の計数の改定が行われている。
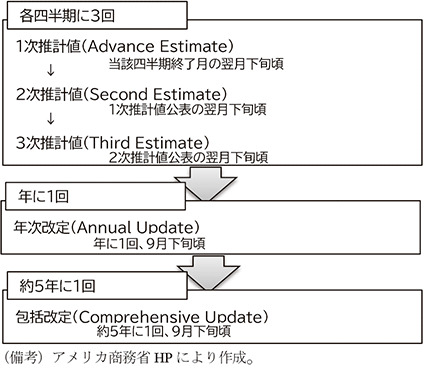
2024年9月30日に行われた全米企業エコノミスト協会の年次会合(National Association for Business Economics Annual Meeting)における質疑応答の中で、アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は2024年年次改定について、(1)GDIが大きく上方改定される形でGDPとGDIとのかい離が縮小したこと、(2)個人可処分所得が大きく上方改定されたことについて言及している。ここでは、2024年年次改定における上記2点について確認する。
まずは支出面のGDPと分配所得面の国内総所得(GDI)のかい離の縮小について確認する50。前述のとおり、2022年以降の実質GDPの平均成長率は、改定前の年率2.0%から改定後には年率2.3%に上方改定されたが、2022年以降の実質GDI51の平均成長率52をみると、改定前の年率0.9%から改定後は年率2.2%に上方改定されており、GDIの平均成長率の改定幅はGDPの平均成長率の改定幅よりも大きかった。GDIの上方改定によって、改定前に存在していたGDPとGDIとのかい離幅は縮小した(図2)。FRBのパウエル議長は、GDIがGDPと整合的な形で上方改定されたことを踏まえ「経済に対する下方リスクが取り除かれたといえるだろう」と述べている53。
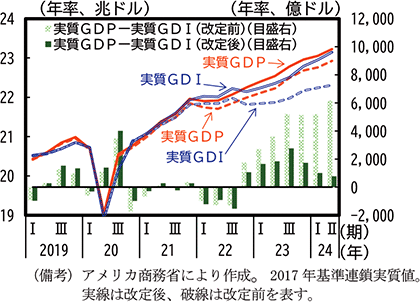
次に個人可処分所得の上方改定について確認する。個人可処分所得と個人消費支出の改定前後の推移をみると(図3)、特に2023年半ば以降、実質個人消費支出の上方改定以上に、実質個人可処分所得54が大きく上方改定されている。これにより、個人貯蓄率は、2023年6月以降、上方改定された(図4)。改定前は2024年7月の個人貯蓄率が2.9%と、感染症拡大前の景気拡大局面の平均値(6.1%)を大きく下回る水準で推移していたことから、消費者が所得以上に個人消費を増加させてきたことにより現在の消費水準が今後持続可能でないというリスクが存在すると考えられていたが、改定後には 2024年7月の個人貯蓄率は 4.9%(同年8月は 4.8%)に上方改定され、当該リスクが低減したといえる。FRBのパウエル議長は、これを踏まえ「消費支出の水準は持続不可能かもしれないという、これまで考えられていた下方リスクが取り除かれた」と述べている55。
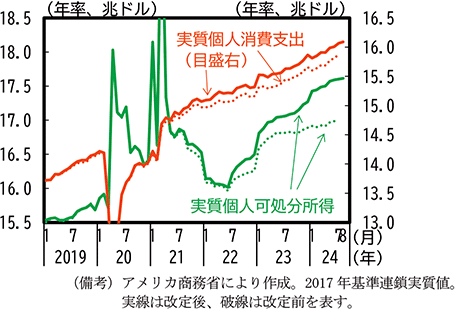
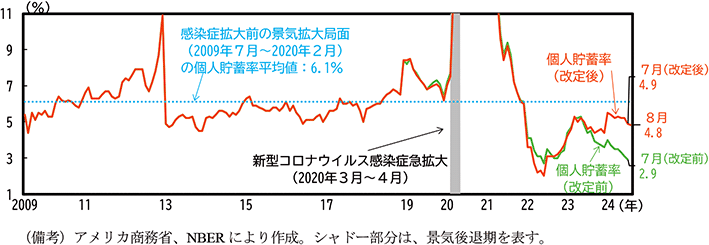
(個人消費は、財・サービスともに増加している)
実質個人消費支出は、財・サービスともに増加傾向が続いている(第2-1-5図)。実質個人消費支出の7割弱を占めるサービス消費では、新型コロナウイルス感染症拡大以降、医療・介護等が増加に寄与しており、中でも外来患者向けサービスが大幅に増加している。飲食・宿泊は23年後半以降増加していたが、24年3月以降、おおむね横ばいで推移している。財消費では娯楽用品が感染症拡大以降大幅に増加しており、近年では特にコンピュータ・ソフトウェア及び付属品、パソコンやタブレット及び周辺機器が増加に寄与している。家具・住宅設備は、特に24年4月以降、増加に寄与している(第2-1-6図)。
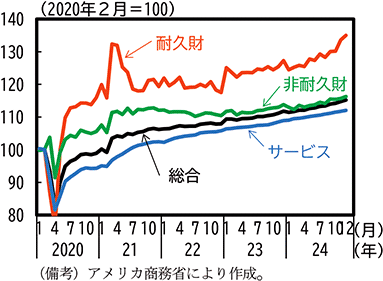
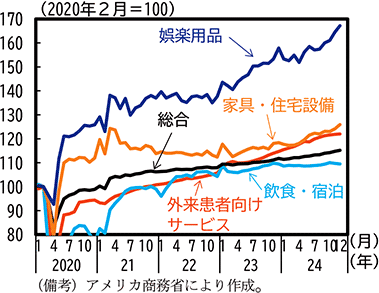
こうした堅調な個人消費から、2024年初以降、実質個人消費支出の伸びが実質個人可処分所得の伸びを上回り、個人貯蓄率は低下傾向にあり、感染症拡大前の景気拡大局面の平均値(6.1%)を下回っている(第2-1-7図)。
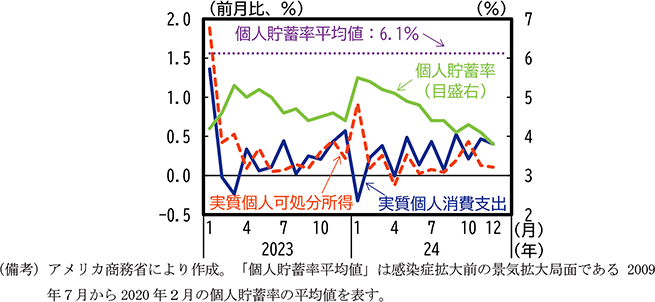
次に、耐久財消費の約4分の1を占める自動車販売について確認する。自動車(新車)販売台数(年換算)は、2023年半ば以降、1,500万台程度の水準でおおむね横ばいで推移しており、感染症拡大前の平均的な販売台数である1,724万台までは回復していない(第2-1-8図)。
2024年6月には、自動車販売店向けに顧客や在庫管理を行うシステムを提供するソフトウェア会社がサイバー攻撃を受けたことも影響し、同年6月の新車販売台数は前年同月比で▲5.4%と落ち込み、その後、同年7月から9月にかけて、その反動で販売台数が上下している。
自動車販売台数が感染症拡大前の平均的な販売台数を下回っている背景として、(1)自動車価格の高止まり(第2-1-9図)、(2)高金利の長期化による自動車ローン金利の上昇(第2-1-10図)、(3)自動車保険価格の上昇(第2-1-11図)が考えられる。
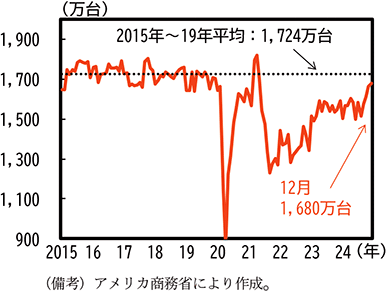
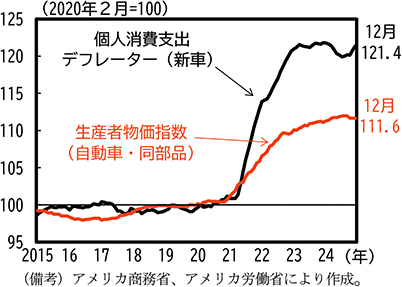
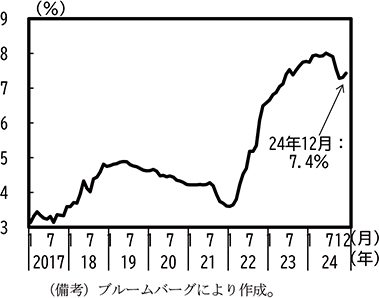
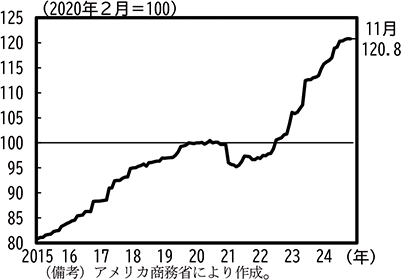
また、ミシガン大学が公表している消費者マインドでは、消費者の自動車購入意志とその理由を公表しており、第2-1-12図では、今後12か月程度は新車を購入するのに適した時期かという質問に対して「不適な時期」と回答した消費者がその理由として挙げた回答の割合を示している56。2021年以降、世界的な車載用半導体の供給不足により供給が停滞し販売台数が減少した際には、「供給不足」と「価格が高い」の回答割合が大幅に上昇している。供給制約の緩和した2022年後半以降、「供給不足」と回答した割合は低下しているのに対し、「価格が高い」の割合は高止まりし、「金利が高い」の割合が上昇している。消費者が直面する自動車価格が高止まりしている背景として、自動車・同部品の生産者物価が高止まり、自動車生産に必要なコストが大きい状況が続いていることが考えられる(第2-1-9図)。こうした自動車価格と自動車ローン金利の高止まりが、2023年半ば以降、自動車販売台数が1,500万台で推移した背景にあるといえる。
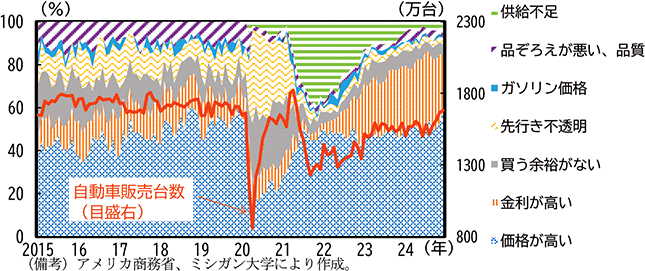
なお、2024年秋以降、自動車販売台数(年換算)は、10月に1,625万台、11月に1,650万台、12月に1,680万台となり、持ち直している。自動車販売台数の持ち直しの背景としては、FRBによる24年9月以降の政策金利引下げに伴う自動車ローン金利の低下のほか、将来の価格上昇を見越して現在を購入の好機と捉える消費者の割合が増加していることが背景として考えられる(第2-1-13図)。
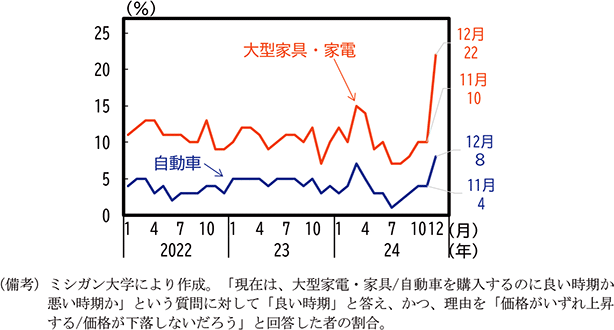
先行きについては、政策金利の引下げが進み自動車ローン金利が低下し、持ち直しが続くことが期待されるが、物価上昇率が再度上昇した場合には、自動車ローン金利が高止まりする可能性には留意が必要である57。
マクロでの堅調な個人消費が続く中で、高所得者層と低所得者層との間での消費の二極化が進行している可能性がある。FRBとNBERのエコノミストによる試算によると(Hacioglu-Hoke et al. (2024))、所得階層別実質小売支出は、感染症拡大以前は全ての所得層において支出の伸びが同程度であったのに対して、2021年半ば以降は高所得層と低所得層の支出の伸びのかい離が拡大している(第2-1-14図)。また、アメリカ労働省による個人消費の所得階層別分布の推計値によると、個人消費全体のうち所得階層上位10%が占める割合が3割弱を占めている。特に、自動車等の耐久財や飲食・宿泊サービスは所得階層上位10%が3~4割程度を占めており、高所得者層と低所得者層との消費の格差が大きいことが分かる(第2-1-15図)。
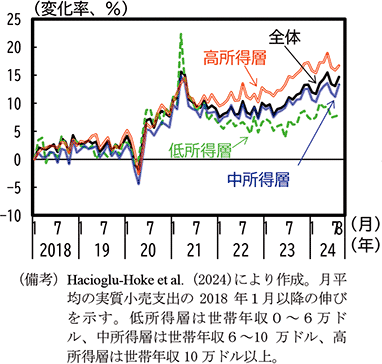
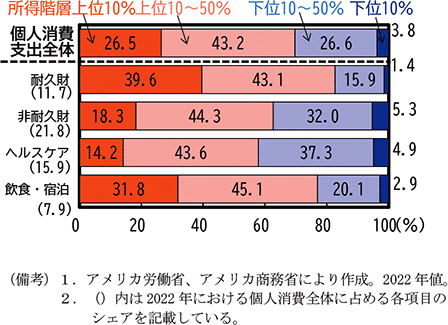
こうした消費の二極化が進んだ背景として、高所得者層の方が配当の伸びの恩恵をより多く享受していることが挙げられる。名目個人所得の内訳をみると、賃貸料58及び配当の感染症拡大後の伸びが個人所得全体の伸びを上回って推移している一方で、雇用者報酬の伸びは個人所得全体の伸びを下回っている(第2-1-16図)。ここで、名目個人所得の内訳項目別の所得階層別シェアをみると(第2-1-17図)、配当は所得階層上位10%が75%のシェアを占めていることが分かる。このことから、配当の感染症拡大後の伸びによる恩恵を高所得者層がより多く享受しており、高所得者層の消費を支えていると考えられる。
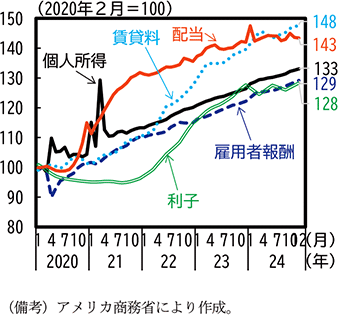
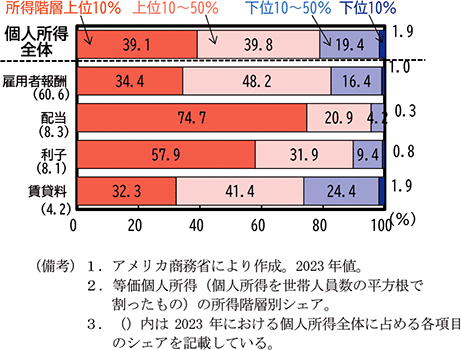
配当で高所得者層のシェアが高い背景には、所得階層別の資産保有割合の違いがある。所得階層別の資産内訳をみると(第2-1-18図)、所得階層上位20%は株式等の保有資産に占める割合が他の所得階層よりも高いことから、高所得者層の方が低所得者層よりも配当の伸びによる所得増加の恩恵を受けやすいといえる。一方、所得階層が低いほど不動産の保有資産に占める割合が高く、所有する不動産が居住している住居である場合、資産価値が増大しても売却することが難しいと考えられる。
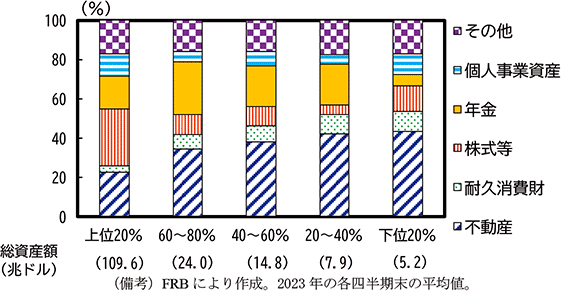
なお、クレジットカードローンの新規延滞への移行率は2021年以降上昇している(第2-1-19図)。ニューヨーク連銀の調査(Felix, Daniel and Wilbert (2024))では、経済的に不安定な者60ほどBNPL(Buy Now Pay Later)61の利用頻度が高いことも指摘されており、低所得者層における消費の持続性には留意が必要である。
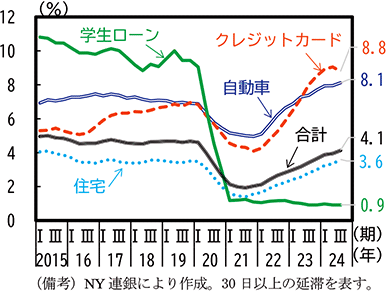
(設備投資は緩やかに増加している)
次に、設備投資の動向について確認する。2023年10-12月期以降、設備投資は緩やかに増加している(第2-1-20図)。感染症拡大以降、知的財産投資が設備投資の伸びをけん引してきたが、2024年4-6月期及び7―9月期の設備投資の伸びは、主に機械・機器投資によってけん引されており、中でも航空機、コンピュータ・周辺機器の増加寄与が大きい(第2-1-21図、第2-1-22図)。ただし、2024年10-12月期は前期比年率▲2.2%と2021年7-9月期以来、13四半期ぶりに減少した。機械・機器投資のうち航空機がマイナスに寄与しているが、これは後述のボーイング社によるストライキの影響を受けていると考えられる。なお、構築物投資は、インフレ抑制法やCHIPS及び科学法(半導体法)等の政策効果により2023年以降は製造業向けの構築物投資が増加に寄与していたが、2024年7-9月期以降はおおむね横ばいとなっており、効果は一巡したとみられる(第2-1-23図)。
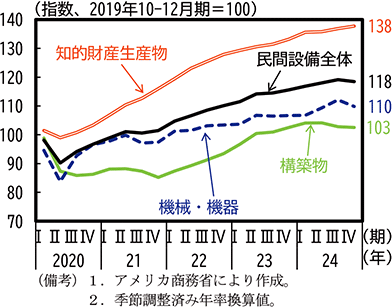
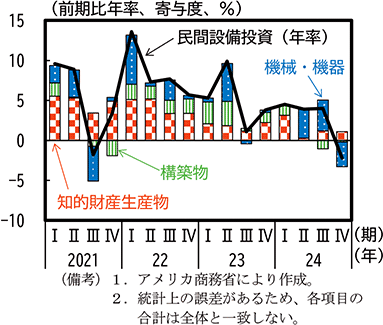
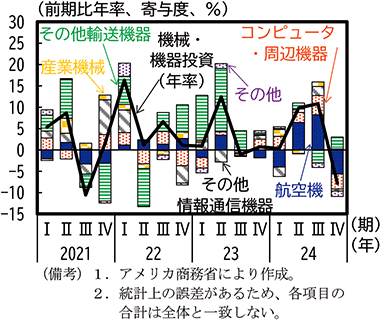
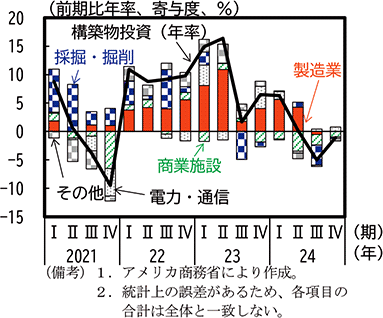
ここで、設備投資をめぐる金融環境を確認する。2022年以降、金融引締めの進展に伴って、金融機関の商工業向けローンの貸出態度は厳格化してきていたが、2023年9月以降、FRBが政策金利を据え置く中、緩和に向けた動きが進んでいる(第2-1-24図)。また、企業側の資金需要についても、2022年以降、金融引締めの進展に伴って軟調になってきていたが、2023年7-9月期以降、堅調の方向に動いている(第2-1-25図)。2024年9月、11月、12月にはFRBによる政策金利の引下げが行われたところであり、今後の設備投資をめぐる金融環境には注視が必要である。
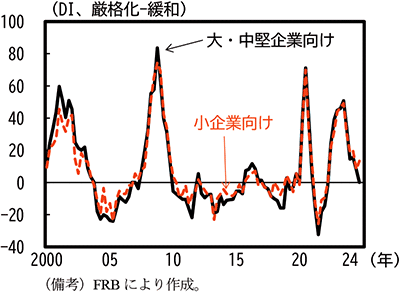
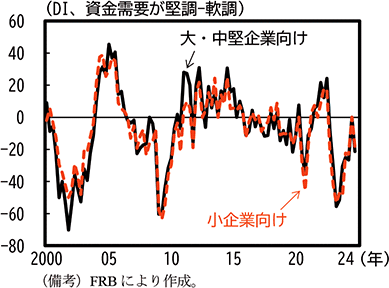
Box.構築物投資の改定について
ここでは、構築物投資における前述のアメリカのGDP統計の2024年年次改定の影響について確認する。改定前は、構築物投資は2021年7-9月期から5四半期連続でマイナス成長が続いていたが、改定後には押下げ要因となっていた電力・通信及び商業施設のマイナス寄与が縮小したこと等により、2022年にはプラス成長に転じている。また、改定前は2023年1-3月以降は半導体法等の政策を受け製造業向けの構築物投資(工場建設等)が増加に大きく寄与していたが、改定後では製造業が構築物投資をけん引する絵姿自体は変わらないものの、改定前と比較すると製造業の寄与は縮小している。このことから、半導体法等による製造業向けの構築物投資の押上げ効果は、改定前に考えられていたほどは大きくなかったことが示唆される(図1)。
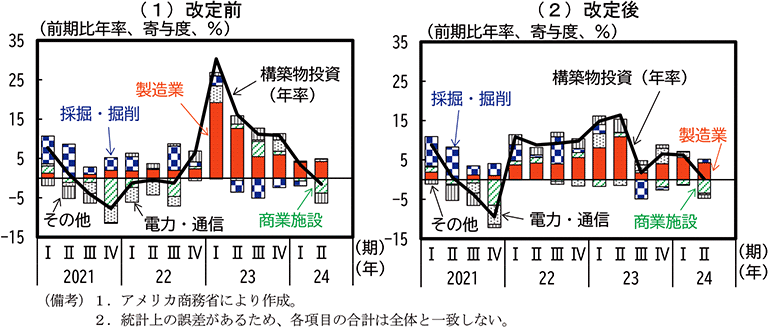
(住宅着工はおおむね横ばい)
住宅着工は、2024年後半にかけておおむね横ばいで推移している62(第2-1-26図)。
物件種類毎の推移を確認すると(第2-1-27図)、一戸建て住宅の着工件数は22年以降、住宅ローン金利が急上昇する中大きく減少したが、23年以降は中古住宅の在庫不足による新築住宅の供給喚起もあり、増加に転じていた。しかし、住宅ローン金利の高止まりが長期化する中、24年以降は足踏みがみられている。
一方、集合住宅の着工件数は、22年末にかけて緩やかに増加していたが、23年以降は減少が継続し、おおむね感染症拡大前の水準に回帰している。
以下、一戸建て住宅市場、集合住宅市場それぞれについて確認していく。
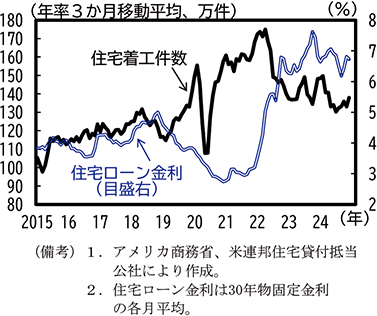
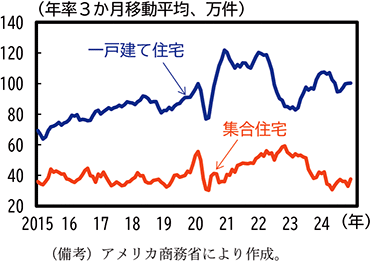
感染症拡大後の一戸建て住宅市場では、在庫不足が顕著となっている。住宅在庫は2000年代後半以降、趨勢的に減少63していた中、20~21年にかけての低金利環境下で住宅販売が急増したことにより、22年初にかけて一段と減少した。その後、住宅ローン金利が大幅に上昇したことにより、いわゆる「ロックイン効果64」が生じ、中古住宅市場に出回る物件が少ない状態が継続している。24年末にかけて、新築住宅在庫が積み上がる中、中古住宅在庫も24年末にかけては反発の兆しがみられるものの、住宅市場全体として依然として歴史的な低水準となっている(第2-1-28図)。
次に、住宅販売をみると、新築住宅販売は23年以降、増加に転じているものの、住宅ローン金利の高止まりや中古住宅の在庫不足により、住宅販売市場での規模が大きい中古住宅の販売は減少傾向にある。したがって、住宅市場全体としてみれば、依然として低迷が続いている(第2-1-29図)。
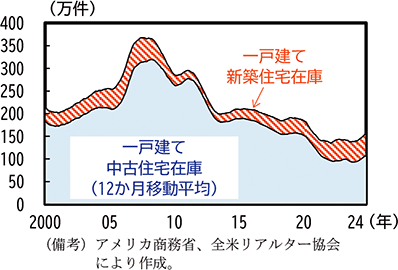
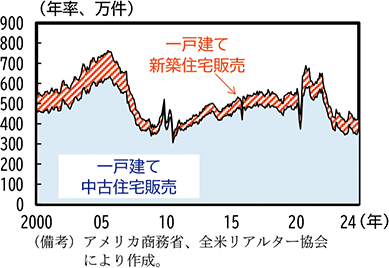
このように、一戸建て住宅市場では、住宅ローン金利の高止まりと中古住宅の在庫不足、加えて、後述の住宅価格の高騰により、販売が低迷していると考えられる。こうした販売動向に加えて、新築住宅の在庫の積増しが進んでいることが、24年末にかけての一戸建て住宅着工件数の弱い動きの背景となっている可能性がある。
次に、集合住宅の現状を確認する。アメリカ商務省センサス局が公表する月次新築住宅建設統計(Monthly New Residential Construction)では、住宅建設の各段階の状況を確認することができる(第2-1-30図)。
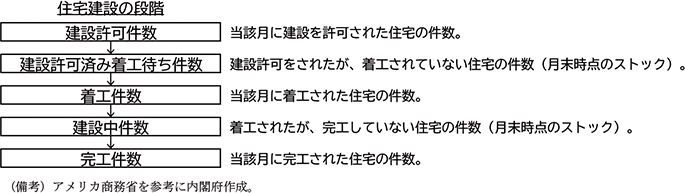
前述のとおり、集合住宅の着工件数は2023年以降に減少に転じ、24年末にかけては感染症拡大前の水準でおおむね横ばいで推移しているが、その背景について、集合住宅の需給動向に着目して考察する。
まず、集合住宅の需要動向をみると、低金利環境が続いていた2020年後半から集合住宅販売(中古)は増加し、2022年初まで高水準での販売が継続した。しかし、FRBが金融引締めに転じた2022年春以降、集合住宅販売は減少し、2024年末まで低迷が続いている(第2-1-31図)。
次に、集合住宅の供給動向を、住宅着工以降の各建設段階の統計を用いて確認する。集合住宅の着工件数は、2020年~21年にかけての旺盛な集合住宅需要を受けて住宅開発が進んだことにより、2022年末にかけて大きく増加した(第2-1-32図 紫二重線)。しかし、着工件数が増加する中で、感染症拡大によるサプライチェーンの混乱や、熟練労働者を始めとする人手不足等によって65住宅建設期間が長期化した(第2-1-33図)。結果として、着工はされたものの未完工である、建設中件数は大きく積み上がり、23年半ばには100万件に達した(第2-1-32図 緑細線)。着工件数が減少に転じる中、23年半ば以降、集合住宅の建設が進み完工件数が増加する中、建設中件数は解消が進んでいる(第2-1-32図 赤太線)。
以上より、集合住宅市場では、高金利下で販売が低迷する中、2024年末にかけては、22年以降に着工された物件の完工が進んだことによって供給が増加している局面にある。
なお、地域別の集合住宅完工件数をみると、南部の住宅完工件数が全体の伸びをけん引していることが分かる(第2-1-34図)。
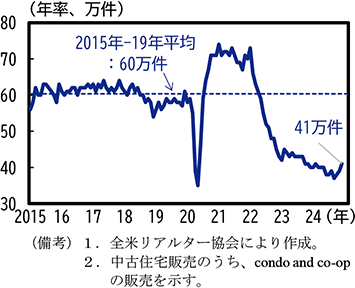
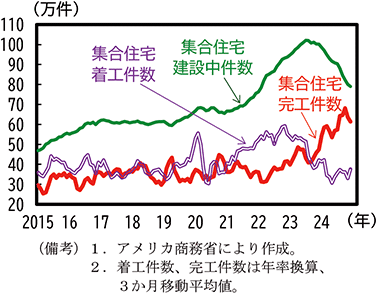
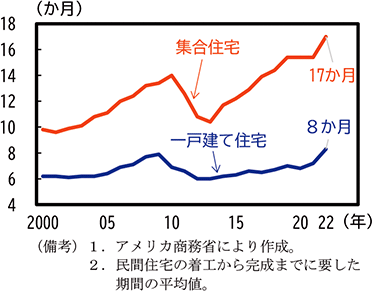
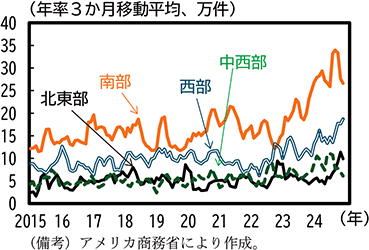
ここで、空室率66を用いて集合住宅の需給動向を確認する。アメリカにおいて集合住宅は賃貸物件として使用されることが多い67ため、賃貸住宅の空室率をみると(第2-1-35図(1))、2024年末にかけて緩やかに上昇しており、集合住宅需給は緩和する方向にある。ただし、空室率の水準は過去と比べて低く、集合住宅市場の需給が緩んでいる状況ではないと考えられる。また、地域別の賃貸物件空室率を確認すると(第2-1-35図(2))、集合住宅の供給が増加している南部においても、空室率の急上昇はみられていない。
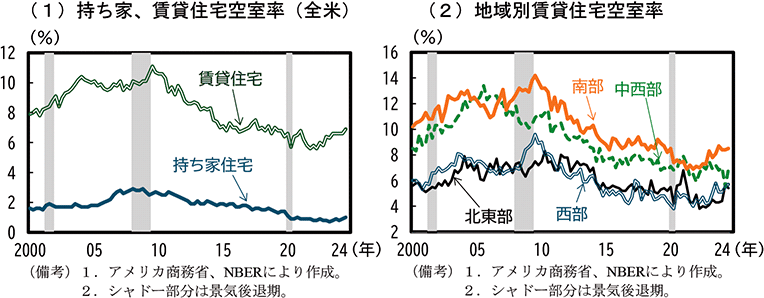
ただし、集合住宅の2024年末の建設中件数は約80万件と、感染症拡大前(2015年~19年)平均である59万件と比べれば高水準にある。これまでに続き、建設中件数の解消が進んだ場合、集合住宅の供給は引き続き高水準となる可能性が高いことから、集合住宅の需給動向には引き続き注視が必要である。
次に、金融環境、各種景況感及び住宅価格について整理し、先行きについて考える。
まず、金融環境について確認する。
住宅ローン金利(30年物固定金利)は、2024年末にかけても感染症拡大前の水準と比較して高い状態が続いている。住宅ローン申請件数(住宅購入目的)は、住宅ローン金利が上昇に転じた2021年後半から減少に転じた後、2024年末にかけて低水準で推移している(第2-1-36図)。
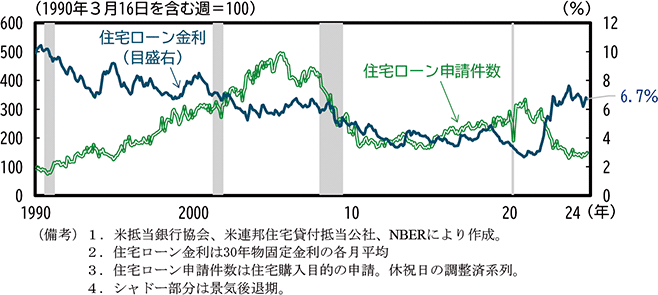
次に、事業者側及び消費者側双方の景況感を確認する。
住宅建設業者の景況感であるNAHB住宅市場指数68は、2025年1月時点で47と、中立水準である50を9か月連続で下回っている(第2-1-37図(1))。内訳別にみると、「足下の販売(current sales)」指数は24年末にかけて50を挟んでおおむね横ばいで推移し、「見込み客の往来(traffic of prospective buyers)」指数は50を下回る水準で推移する一方、「先行き6か月の販売見込み(sales expectations in the next six months)」指数は中立水準の50を超えている(第2-1-37図(2))。住宅ローン金利の高止まりを主因として、足下の業況については明確な改善傾向はみられないものの、先行きについては改善を見込んでいることがうかがえる。
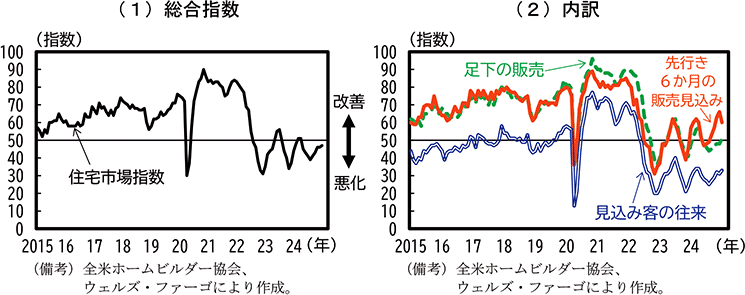
消費者側の景況感を現況、先行きに分けて確認する。まず、現況について、ミシガン大学による消費者マインド調査における住宅購入判断を確認すると(第2-1-38図)、後述のとおり、住宅価格が大幅に上昇した2021年以降低下に転じた後、FRBによる金融引締めが開始された22年初以降一段と低下、24年末にかけても低迷している。住宅購入に不適と答えている理由として、住宅価格の高さと金利の高さが多く挙げられており、これらが住宅需要を抑制している構図が読み取れる。
先行きについて、コンファレンスボード消費者マインド調査における「住宅購入計画」をみると、2024年初以降、住宅ローン金利のピークアウトとともに下げ止まり、反発をしていたが、2024年末にかけては再び落ち込んでいる(第2-1-39図)。後述のとおり、2024年末にかけて、金融市場が見込む2025年中の利下げ回数が減少しており、住宅ローン金利高止まりへの懸念が高まっている可能性がある。
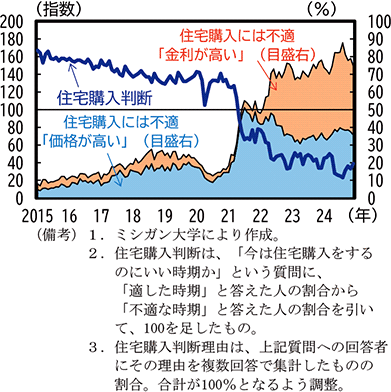
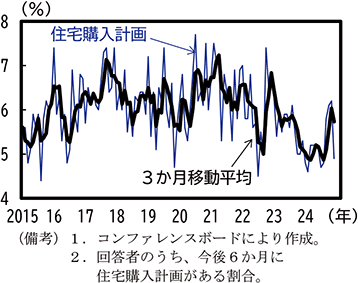
最後に、住宅価格について確認する。
2000年以降の住宅価格の推移を確認すると69、2000年代初頭以降の住宅バブル及びその崩壊を経て、2010年代半ばから感染症拡大前の2019年にかけては、おおむね年率5%程度での上昇が続いていた70(第2-1-40図)。その後、2020年半ば以降は、住宅ローン金利の大幅な低下71や、リモートワークの普及72等によって住宅需要が拡大する一方、建設資材の高騰や人手不足によって投入コストが高まった(第2-1-41図)こと等によって73住宅価格は急伸した。
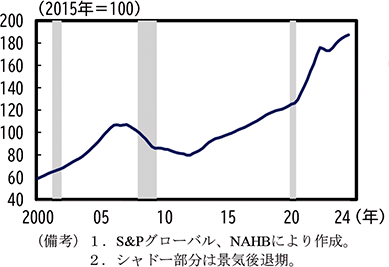
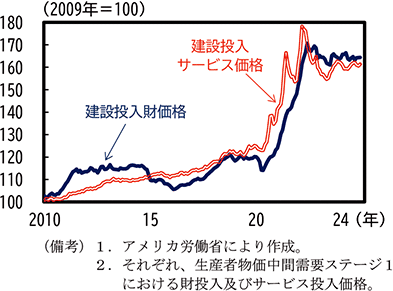
2022年初以降、FRBの金融引締めが行われると住宅価格は一時低下に転じたが、大きな値崩れを起こすことはなく、24年末にかけて前月比0.3~0.4%前後での緩やかな上昇が続いている(第2-1-42図)。
なお、住宅価格の水準を新築住宅・中古住宅別でみると、前述のとおり、在庫の積み上がりがみられる新築住宅は価格が頭打ちとなっている一方、中古住宅は緩やかに上昇している(第2-1-43図)。
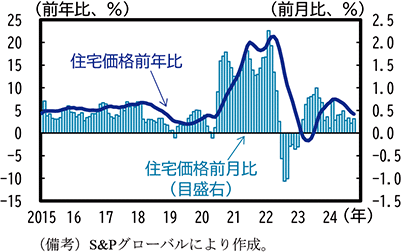
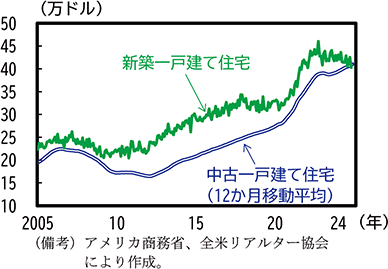
住宅価格の割高感を確認するために、世帯収入中央値に対する住宅価格をみると、新築住宅・中古住宅いずれもおよそ5倍と過去最高に近い水準にあり、住宅購入における家計負担は厳しさを増している(第2-1-44図)。
次に、アメリカの標準的な家計による標準的な住宅の購入における負担感について、住宅取得能力指数74を用いて確認する。住宅取得能力指数は、住宅価格が上昇した2021年以降低下に転じ、FRBによる金融引締めが開始された2022年初以降一段と低下、足下にかけては感染症拡大前よりも低い水準で低迷している。
ここで、先行きについて、FRBによる利下げが行われる中、住宅ローン金利が緩やかに低下すると仮定した時、(1)住宅価格の上昇ペースが加速する場合(年率6.2%)、(2)住宅価格の上昇ペースが鈍化する場合(年率2.4%)、それぞれにおいて、住宅取得能力指数がどのように推移するかを試算した(試算方法の詳細については付注2-1参照)。
試算の結果、第2-1-45図のとおり、今後の住宅価格の上昇ペースが鈍化した場合においても、住宅取得能力指数は2026年末にかけて感染症拡大前の水準を大幅に下回ることが示唆された。すなわち、感染症拡大後の住宅価格の急上昇に世帯収入の上昇が追い付いておらず、仮に住宅ローン金利が感染症拡大前の水準に回帰し、住宅価格の伸びが先行き緩やかになったとしても、家計が住宅を購入する際の負担は感染症拡大前に比べて大きくなったままであるということになる。
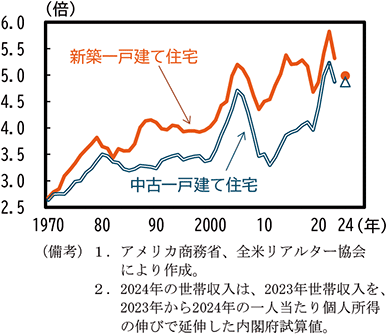
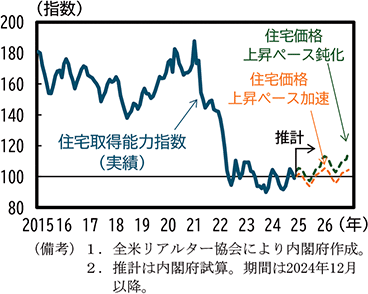
以上より、先行きについて考えると、各種マインドからは住宅ローン金利のピークアウトとともに、住宅投資が回復に向かうことが示唆される。ただし、住宅ローン金利が今後低下していくとしても、世帯収入に対する住宅価格の割高感により住宅購入を諦めざるを得ない層が感染症拡大前よりも増えていることにより、住宅投資の回復ペースは緩慢なものとなる可能性もあるため、住宅市場の動向については引き続き注視する必要がある。
(財輸入の増加が財輸出の増加を上回り、財の貿易赤字は拡大傾向)
次に、貿易の動向について確認する。
まずは、財・サービス別の輸出額の動向をみると、財・サービスともに輸出は増加傾向にあり、特に、知的財産権使用料や情報通信等のデジタル関連サービスがけん引し、サービス輸出の比率は上昇傾向にある(第2-1-46図)。
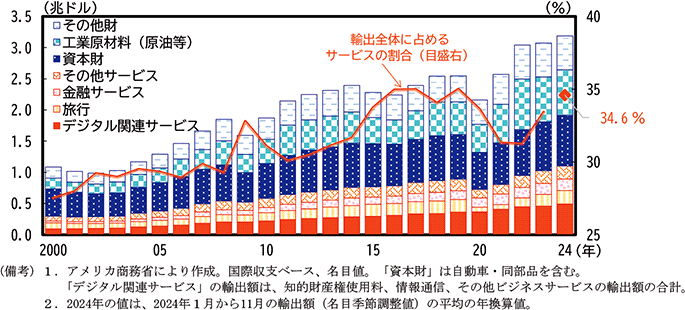
以下、財・サービス別に貿易の動向を詳細に確認する。
まずは、財貿易の動向をみると(第2-1-47図)、足下では財輸出は緩やかに増加する中で、財輸入は財輸出を上回るペースで増加している結果、財の貿易赤字は拡大傾向にある。ただし、より長い期間でみた場合は(第2-1-48図)、財の貿易赤字は拡大傾向にあるものの、貿易収支対GDP比は2008年の世界金融危機後はおおむね横ばいで推移している。これは、貿易赤字の増加ペースが、GDP全体の増加ペースとおおむね同じペースであることを意味する。
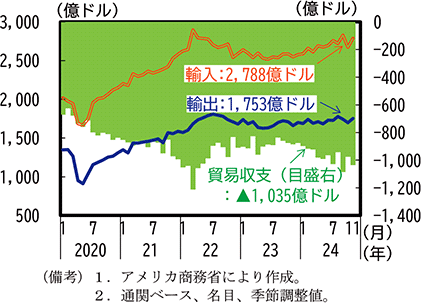
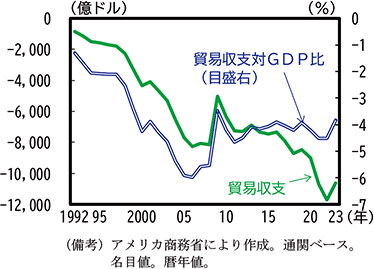
以下、輸出入をけん引する品目や、アメリカを取り巻く貿易状況について確認する。
財輸出の内訳をみると(第2-1-49図)、工業原材料、資本財、消費財が財輸出に占めるシェアが高い。また、財輸出の推移をみると(第2-1-50図)、感染症拡大以降、資本財と消費財が財輸出をけん引してきたことが分かる。
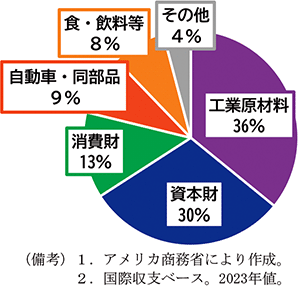
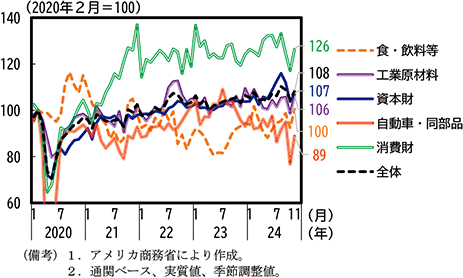
まず、財輸出の36%を占める工業原材料の品目別の内訳をみると(第2-1-51図)、エネルギー製品(原油、ガス等)が半分を占めている(シェールオイルを多く生産するテキサス州及びアメリカ全体のエネルギー生産については、第3項を参照)。
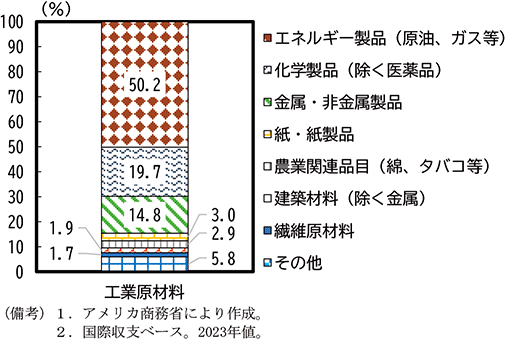
次に、財輸出の3割を占める資本財の内訳をみると、民間航空機・同部品のシェアが大きい(第2-1-52図)。民間航空機の生産、輸出の推移をみると(第2-1-53図)、増加傾向にある。ただし、2024年9月は生産、輸出ともに落ち込んでおり、これは、同年9月3日にボーイング社でストライキが発生したことが背景にあると考えられる。
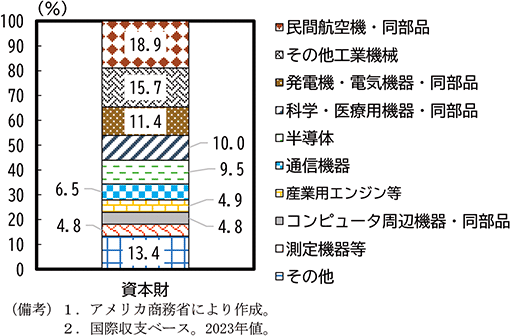
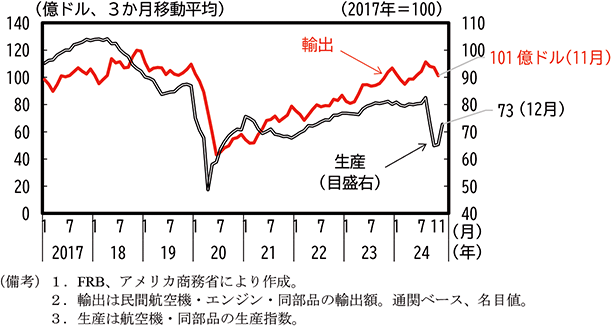
次に、財輸出の13%を占める消費財の内訳をみると、医薬品等のシェアが大きい(第2-1-54図)。医薬品の輸出の推移をみると(第2-1-55図)、新型コロナウイルス感染症のワクチンが開発された2021年からアメリカの医薬品輸出は大きく増加し、2024年でもその規模を維持している。また、アメリカ内における医薬品の生産をみても、生産全体を大きくけん引していることが分かる。
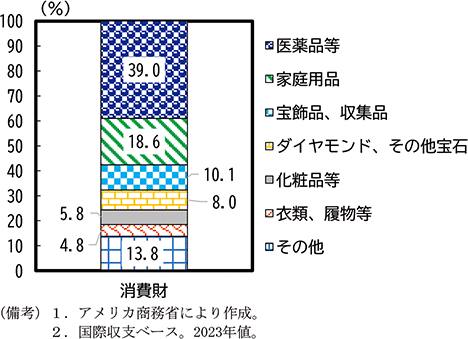
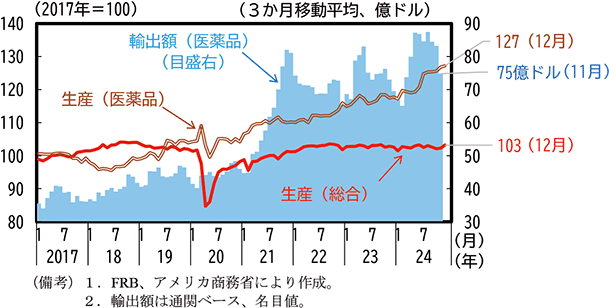
次に、財輸出の9%を占める自動車・同部品の内訳をみると(第2-1-56図)、自動車部品のシェアが半数以上を占めている。また、カナダ向けの自動車・同部品のシェアは約4割となっている。同品目の国別輸出額の推移をみると(第2-1-57図)、アメリカに接するカナダ、メキシコ向けの輸出額が大きく、USMCAが発効された2020年以降は、カナダ、メキシコ向けの輸出が増加傾向にある。
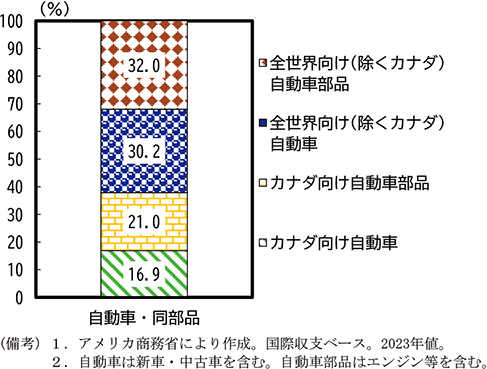
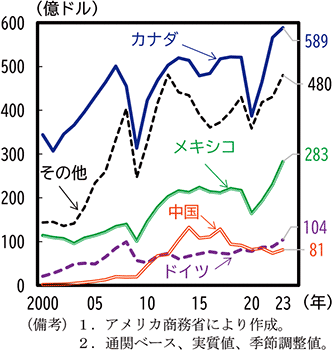
最後に、財輸出の8%を占める食飲料等お訳をみると(第2-1-58図)、穀物等、その他農産品等のシェアが大きいが、他の品目と比較して、輸出品目の偏りが小さいことが分かる。
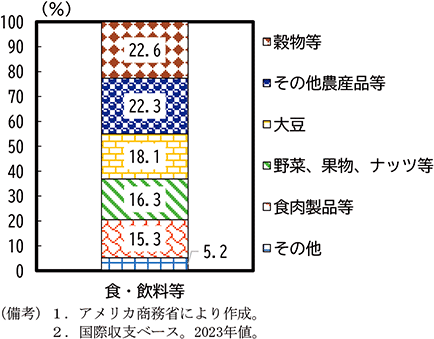
次に、財輸入について確認する。財輸入の内訳をみると(第2-1-59図)、資本財、消費財、工業原材料が財輸入に占めるシェアが高い。また、財輸入の推移をみると(第2-1-60図)、感染症拡大以降、資本財と消費財が財輸入をけん引してきたことが分かる。なお、2024年9月の財輸入の急増は、国際港湾労働者協会(ILA)(以下「港湾組合」という。)と使用者団体の米海運連合(USMX)との間で2024年9月末に更新を控えていた新たな労働協約に関する交渉が予定どおりに進む見通しが立たず、港湾組合がストライキに突入する可能性が高まり、アメリカの企業が駆け込みで商品を輸入したことによる一時的要因と考えられる。
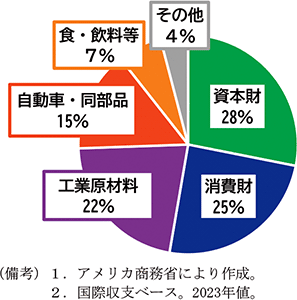
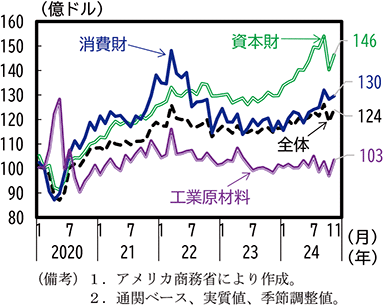
2024年5月14日、バイデン政権は、1974年通商法第301条(いわゆるスーパー301条)に基づき、EVや半導体等中国からの輸入品180億ドル相当75に対する関税の引上げを発表した。具体的には、「中国の不公正な貿易慣行からアメリカの労働者と企業を守るため」として、主にバイデン政権下で戦略的分野として投資を行ってきた品目76を対象に、現行0~25%の関税率を25~100%まで引き上げることとした。翌週22日にはアメリカ通商代表部(USTR)が関税引上げ対象品目や適用除外品目のリスト77、引上げ時期等を示した官報案を発表しパブリックコメントを受け付け、同年9月13日にパブリックコメントを踏まえたリストの見直し結果が公表された。
第2-1-61表のとおり、品目別に2024年、25年、26年の3つの時期に分けて関税引上げが実施されることとされており、2024年の関税引上げ品目については2024年9月27日以降、2025年の関税引上げ品目については2025年1月1日以降、関税の引上げが実施されている。
2024年5月に公表されたリストから大きな変更点はなかったものの、パブリックコメントを踏まえ、医療品(注射器と注射針、呼吸器、フェイスマスク、医療用手袋)については、関税引上げのタイミングや関税率について変更があった78。
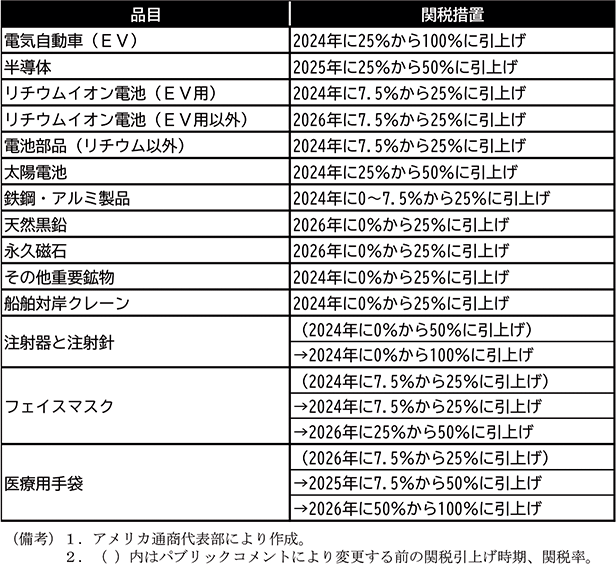
また、パブリックコメントの結果を通知した官報では、新たに半導体等の製造に使用されるタングステン、ポリシリコン、ウエハー80について2025年から25%の関税引上げを検討していることが示された81。2024年12月11日には当該品目について実施したパブリックコメントを踏まえ、2025年1月1日からタングステンは25%、ポリシリコンとウエハーは50%関税が引き上げられることが決定した。2023年における該当品目の上位輸入国をみると(第2-1-62図)、タングステンは中国からの輸入が1位、ポリシリコン、ウエハーは中国からの輸入が2位となっており、今後の当該品目の輸入動向を注視する必要がある。
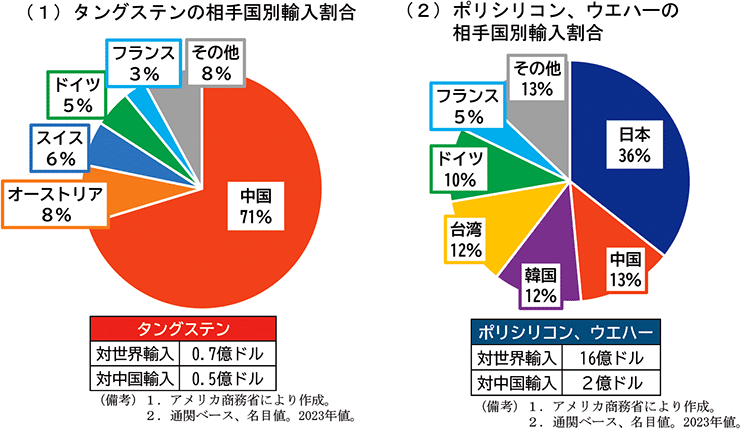
次に、アメリカと中国の財の輸出入の推移をみると、2018年以降、中国からの財輸入は頭打ちで推移している(第2-1-63図、第2-1-64図)。中国からの財輸入が頭打ちとなっているのは、第一次トランプ政権下に起きた米中両国間での追加関税の応酬が影響している(第2-1-65表)。一方、感染症拡大以降はASEAN(特にベトナム)、メキシコからの財輸入は増加傾向にある。
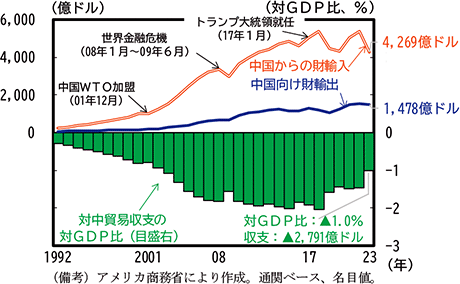
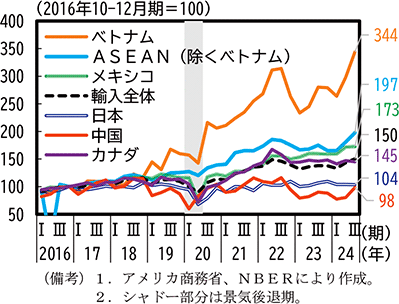
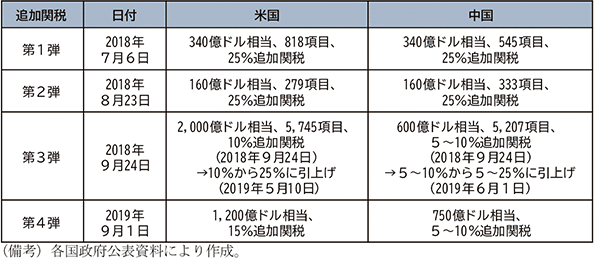
次に、貿易収支の推移をみると、前述のとおり、財の貿易赤字は拡大しているものの、経済成長を続けていることから、貿易収支対GDP比では2008年の世界金融危機後はおおむね横ばいで推移している(第2-1-66図、第2-1-67図)。また、前述のとおり、2018年以降、中国からの財輸入が頭打ちとなる中、感染症拡大以降、ASEAN・メキシコからの財輸入は増加傾向にあることから、対中国の貿易赤字対GDP比は2018年以降は低下している一方で、メキシコ、カナダ、ASEAN諸国がその分を補うように拡大しており、アメリカの貿易相手国に変化が生じていることが分かる。
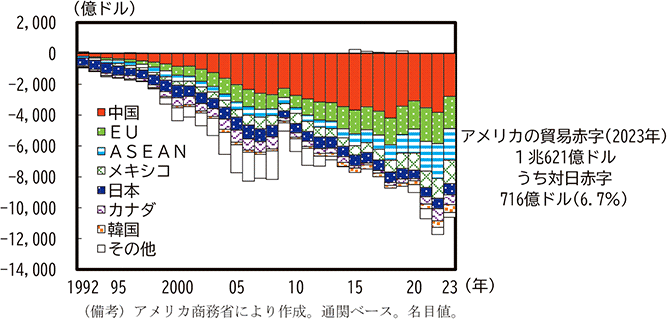
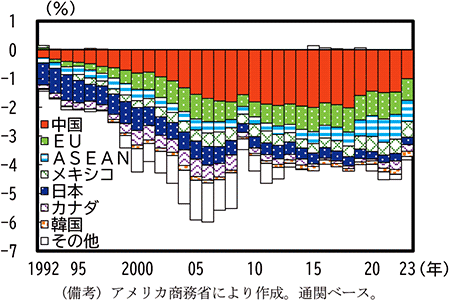
トランプ大統領は就任日(2025年1月20日)に複数の大統領令に署名を行った(第2-1-68表)。そのうちの一つの「米国第一の貿易政策」(America First Trade Policy)では、長期にわたる大きな財貿易赤字の理由及びそれによる経済・安全保障上のリスクや、他国による不公正な貿易慣行等について、2025年4月1日までに調査することを閣僚に指示している。
また、2025年2月1日に、カナダ及びメキシコからの輸入品に原則として25%82、中国からの輸入品に10%の追加関税を課す大統領令に署名を行った。カナダ及びメキシコについては、発動前に1か月間の延期が決まったものの83、中国からの輸入品に対しては2025年2月4日に10%の追加関税を発動している。
カナダからは原油等の工業原材料、メキシコからは自動車・同部品、中国からは玩具等の消費財の輸入が大きく、カナダ、メキシコ及び中国の3か国からの財輸入額はアメリカの財輸入額全体の約4割を占めることから、これら3か国との通商政策の動向はアメリカ経済に一定の影響を与え得ると考えられる(第2-1-69図)。
今後のアメリカの通商政策の動向には注視が必要である。
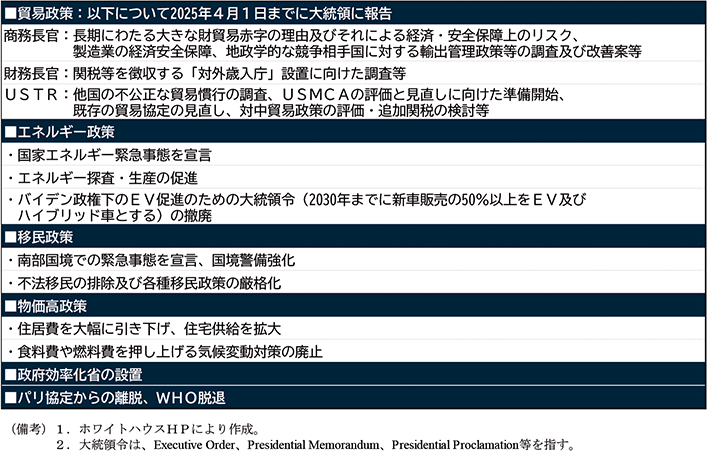
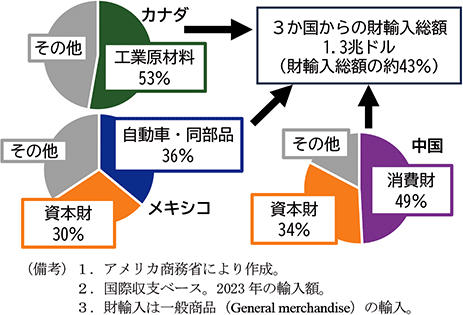
(サービス輸出はデジタル関連サービスを中心に拡大傾向)
次に、サービス貿易の動向をみると(第2-1-70図)、サービス輸出、輸入はともに感染症拡大期に一時的に減少したものの、2020年半ば以降、増加傾向にある。サービス輸出とサービス輸入がともに増加する中、2023年半ば以降、サービス収支の黒字幅はおおむね横ばいで推移している。以下では、感染症拡大期のサービス輸出の減少要因と、サービス輸出をけん引している品目及び輸出相手国について確認する。
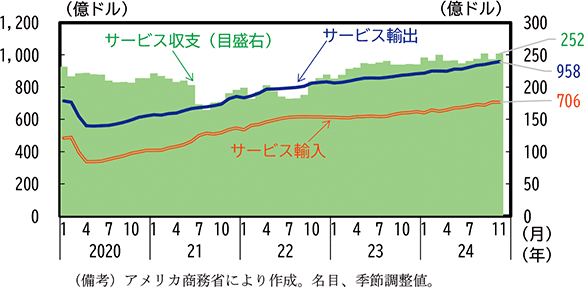
サービス収支を相手国別にみると(第2-1-71図)、アイルランドに対するサービス黒字は大きくかつ拡大傾向にあることが分かる(詳細は後述)。また、2020年から2021年にかけて、特に中国、カナダに対するサービス収支の黒字幅が縮小している。これは、感染症拡大による渡航禁止が影響していると考えられ、同期間における旅行サービス輸出額の減少に起因していることが確認できる(第2-1-72図)。
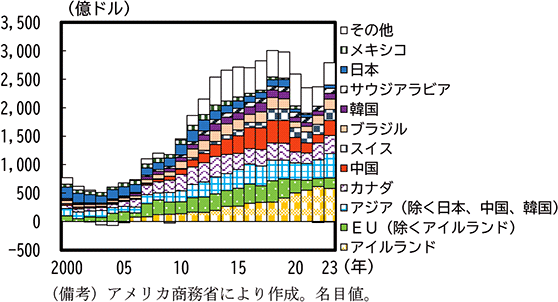
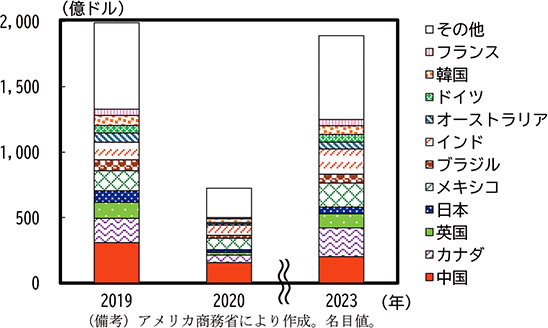
ここで、サービス輸出の品目別割合をみると、その他ビジネスサービス84や旅行の割合が高いことが分かる(第2-1-73図)。一方、サービス黒字が拡大傾向にあるアイルランド向けの輸出をみると、デジタル関連サービス(「知的財産権使用料」「情報通信」、「その他ビジネスサービス」)の割合が9割弱と高い(第2-1-74図)。アイルランド向けの輸出全体に占めるデジタル関連サービスの輸出の割合が高い背景としては、アイルランドは、法人税率が低いことに加え、若年人口比率や教育水準が高く英語圏であることから、多国籍企業がアイルランドに集積していることが挙げられる85。
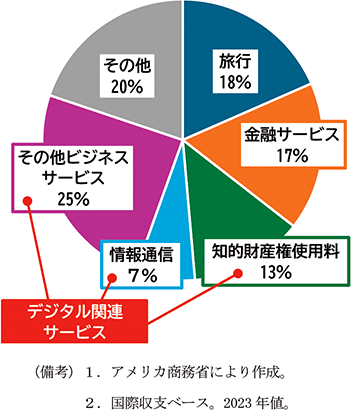
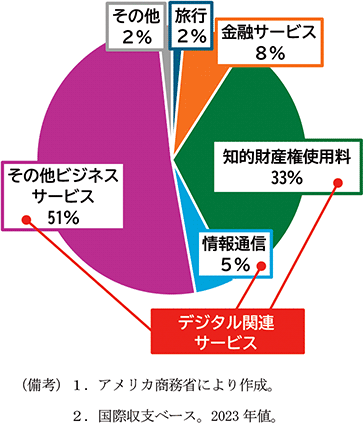
2.労働市場、物価、金融政策、財政の動向
(労働需給は緩和が継続)
アメリカの労働市場では、労働需給の緩和が継続している。2024年後半にかけてのアメリカ雇用統計事業所調査86における非農業部門雇用者数は、3か月移動平均でみると、感染症拡大前の平均前月差87である20万人をやや下回るペースで、緩やかに増加している88(第2-1-75図(1))。業種別の雇用者数前月差を確認すると、医療・介護等及び政府部門89の伸びが底堅い一方で、医療・介護等を除く民間部門の伸びが徐々に縮小している(第2-1-75図(2))。
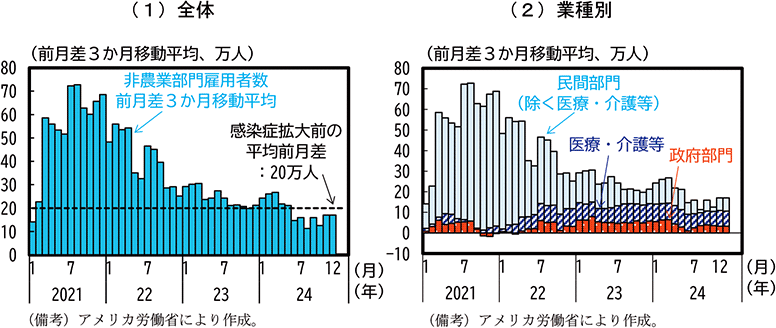
Box.ストライキ、ハリケーンによる雇用統計への影響
2024年10月の非農業部門雇用者数は前月差3.6万人と、9月分(同25.5万人)から増勢が鈍化したが、一部企業によるストライキ及びハリケーンによる一時的な要因が影響している可能性がある。ここでは、これらが雇用統計に及ぼす影響を整理する。なお、失業率は家計調査を基に、非農業部門雇用者数は事業所調査を基に推計されている。
(1)ストライキ
事業所調査の雇用者数90には、調査対象期間全体にわたってストライキに参加し、給与を受け取らなかった者は含まれない91。
一方、家計調査は、調査対象者の質問票への回答を基に就業者数を推計する。家計調査における就業者の定義は図1のとおりであり、調査対象期間にストライキ(労働争議)を行っていた労働者は就業者とみなされる。
(2)ハリケーン
ハリケーンを含む悪天候による事業所調査の雇用者数への影響を見積もるのは難しい92が、悪天候によって労働者が調査対象期間全体にわたって無給で休む場合は、雇用されているとはみなされない。
一方、家計調査では、悪天候によって調査対象期間中に働けなかった労働者(図2)は、その期間に賃金が支払われたか否かに関わらず、就業者とみなされる。
以上より、家計調査により作成される失業率はハリケーンやストライキによる一時的影響を受けにくい一方で、事業所調査により作成される非農業部門雇用者数はこうした一時的影響を比較的受けやすいといえる。
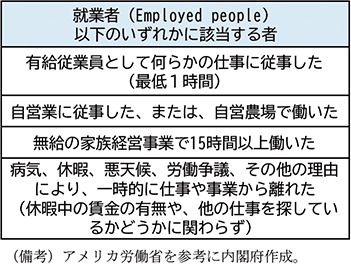
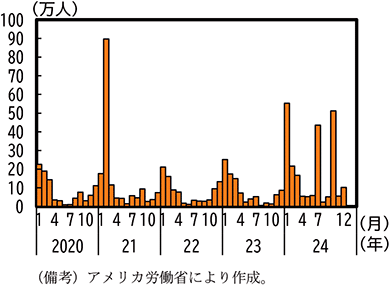
家計調査における失業率は、2022年半ばから23年半ばにかけて3.5%前後の水準で推移した後、やや上昇したが、24年半ばからは連邦公開市場委員会(FOMC)の参加者による長期失業率見通し93である4.2%近傍で、おおむね横ばいで推移している(第2-1-76図)。23年以降の失業率の累積変化を人口要因のうちアメリカ生まれ人口要因、人口要因のうち外国生まれ人口要因、労働参加率要因、就業者数要因に分解94すると、労働需要である就業者数要因が一定の下押し圧力となる中、主に外国生まれ人口の増加による労働供給の増加が、失業率の上昇に寄与してきたことが分かる(第2-1-77図)。
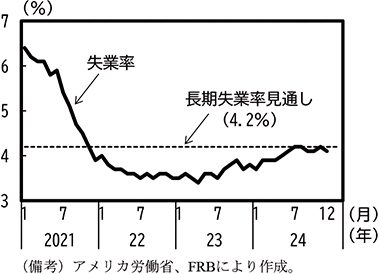
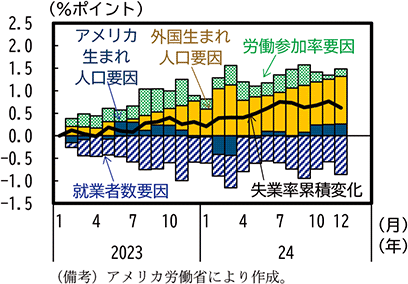
ここで、23年以降の労働供給の増加要因を、労働参加率と人口(生産年齢人口)に分けて分析する。
まず労働参加率をみると、23年以降、感染症拡大後の回復傾向に頭打ちがみられる(第2-1-78図)。55歳以上の労働参加率が感染症拡大以降、低水準で推移する中、感染症拡大後の労働参加率回復のけん引役となっていた25~54歳、特に女性の労働参加率が24年末にかけて頭打ちとなったことから、労働参加率は全体として回復傾向が頭打ちとなっている。
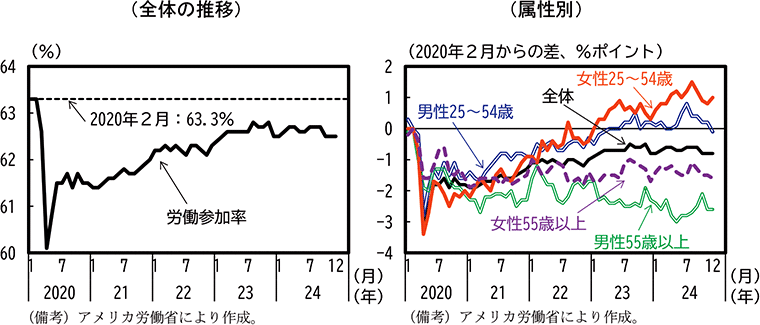
なお、長期的にみると、労働参加率は全体として緩やかな低下傾向にある(第2-1-79図)。CBO(アメリカ連邦議会予算局)の見通しによると、主に人口の高齢化、特に、ベビーブーマー世代95の退職が継続することにより、2030年代半ばにかけて緩やかに低下していくことが示されている。
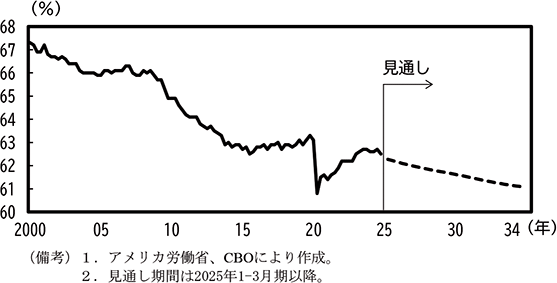
次に、人口について確認する。家計調査における16歳以上人口の推移を出生地別に確認すると、2020年以降、アメリカ生まれ人口の伸びが鈍化する一方、外国生まれ人口の伸びが加速してきたことが分かる(第2-1-80図(1))。特に、23年以降、16歳以上人口の増加は、ほとんど外国生まれの人口の増加によるものであることが分かる(第2-1-80図(2))。
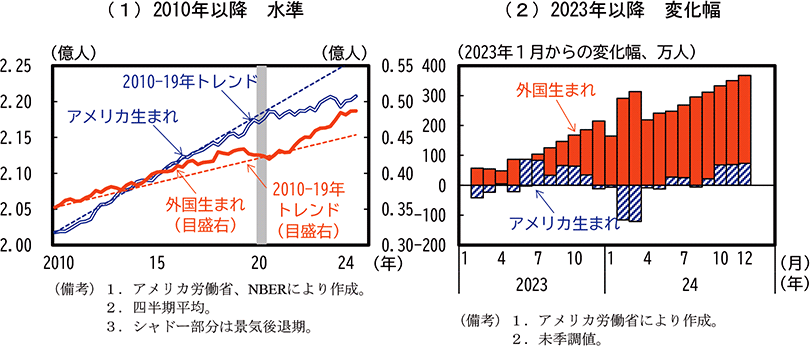
外国生まれ人口96について、アメリカに帰化した者(Naturalized U.S. citizen)と非米国市民(Not a U.S. citizen)に分けて確認すると、特に、23年については、非米国市民の増加が人口全体の増加をけん引していることが分かる(第2-1-81図)。非米国市民には、永住権の取得者や一時的滞在者、難民及び不法移民が含まれるが、23年にはメキシコ国境において遭遇した入国希望者97のうち約6割がアメリカ国内に入国しているとの指摘98もあり(第2-1-82図)、23年における非米国市民の伸びには、不法移民の大幅な流入も寄与していることが示唆される。
このため、感染症拡大後、特に23年以降のアメリカ労働市場における需給ひっ迫の緩和には、移民を中心とする人口増加による労働供給の拡大が大きく寄与したと考えられる。
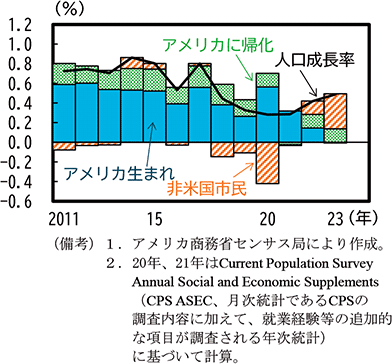
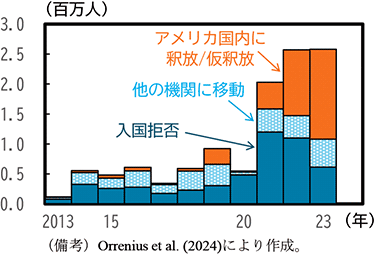
ただし、アメリカにおける移民の受入れは政策動向による部分が大きい。24年9月までのメキシコ国境における入国希望者との遭遇データを確認すると、21年以降に大幅に増加99したものの、24年以降は減少に転じ、バイデン政権が24年6月にメキシコ国境からの不法越境者の流入を制限する大統領令を発表して以降、一段と減少している(第2-1-83図)。
トランプ大統領は就任初日(2025年1月20日)にアメリカ南部国境における緊急事態を宣言し、国境警備の強化や不法移民の排除及び各種移民政策を厳格化する大統領令に署名した(第2-1-68表)。加えて、アメリカ国内に2022年時点で約1,100万人100いるとされる不法移民の強制送還も開始しており、移民政策はバイデン政権下と比較して厳格化している。アメリカにおける業種別就業者に占める外国生まれの人の割合を確認すると、建設、農業等101に加え、飲食・宿泊等102において、外国生まれの人、特に不法移民等が含まれる非米国市民の割合が他の業種に比べて高く、第二次トランプ政権における厳格な移民政策の影響を受けやすいと考えられる(第2-1-84図)。こうした業種別の影響を含め、移民政策によるアメリカ労働市場への影響を注視する必要がある。
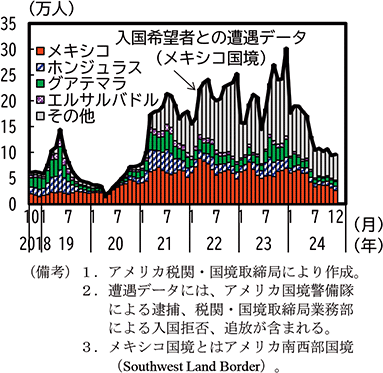
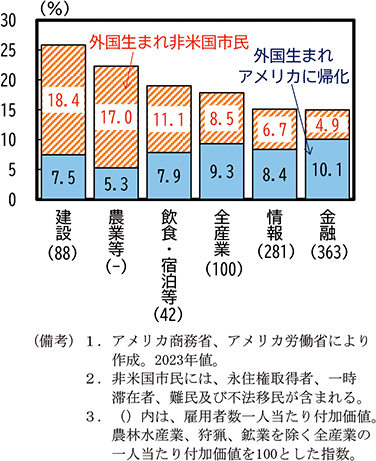
Box.失業率を変化させない雇用者数の伸び
失業率の変動と、非農業部門雇用者数の増減には一定の負の相関がみられるが、失業率の前期差と非農業部門雇用者数の前期差を、感染症拡大前後でプロットすると(図1)、失業率の前期差が0%ポイントとなる雇用者数の伸び(図1の切片)が感染症拡大以降、大きくなっていることが分かる。
家計調査、事業所調査それぞれから作成される雇用者数が同じであると仮定すると103、例えば、労働力人口が10万人増加した場合、家計調査における失業率を4%で一定とするためには、事業所調査における非農業部門雇用者数が9万6千人増加しなければならない。すなわち、失業率を変化させない雇用者数の伸びは、主に労働力人口の拡大ペースに左右されることになる(図2)。
Petrosky-Nadeau and Stewart (2024)は、感染症拡大後の労働参加率の回復及び移民の急増を背景として、同期間の失業率を変化させない雇用者数の伸びが、一時的に高まっていた可能性を指摘している。長期的なトレンドとされる前月差7~9万人104から、多ければ前月差23万人程度まで高まっていた可能性があるとしており、特に、2023年半ば以降、非農業部門雇用者数が前月差20万人を超えて拡大する中、失業率が上昇していたことと整合的である105。なお、先行きについては、2025年末までに10万人を下回る長期的なトレンドまで減少すると予測されている。
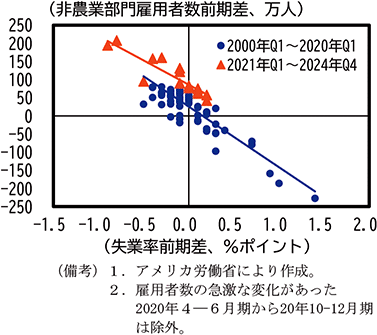
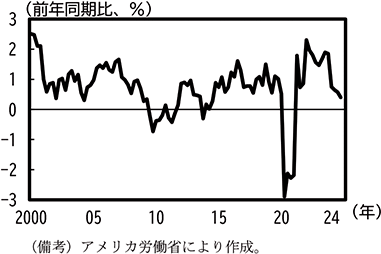
次に、労働需要について、JOLTS求人数106及びIndeed求人数107をみると、22年初をピークに減少が続いた後、24年末にかけては、おおむね感染症拡大前の水準で推移している(第2-1-85図)。
また、求職者(失業者)一人当たりの求人数である求人倍率は、感染症拡大前の水準をやや下回るまで低下した後、24年末にかけては下げ止まっている(第2-1-86図)。感染症拡大後の労働需給ひっ迫は、おおむね解消したといえる。
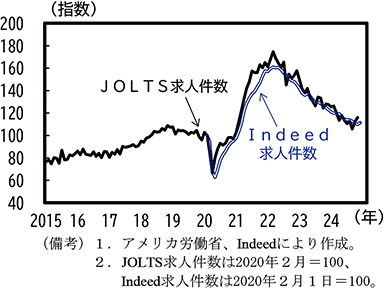
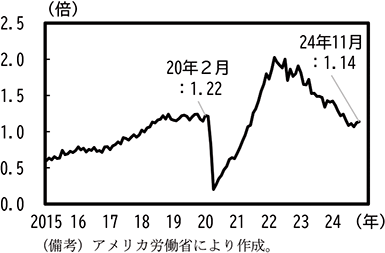
一方、企業による人員削減及び解雇率は低位で推移しており(第2-1-87図)、労働投入の調整を人員削減によって行う動きは限定的であることがうかがえる108。UV曲線では、失業率が低位にとどまる中、欠員率がおおむね感染症拡大前の水準まで低下しており、ソフトランディングへの道のりをたどっている109(第2-1-88図)。
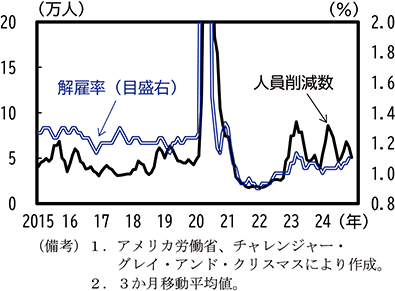
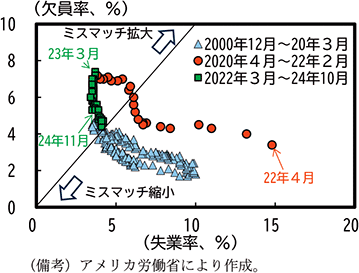
(賃金の伸びはおおむね横ばい)
感染症拡大後の労働需給ひっ迫が解消する中、賃金動向をみると(第2-1-89図)、前年比でみた時間当たり賃金の伸びは、2024年半ばにかけて鈍化した後、24年末にかけては4%前後でおおむね横ばいで推移している。アトランタ連銀が公表するWage Growth Tracker (WGT)及びアメリカ労働省が公表する雇用コスト指数も、22年のピーク以降、伸びが鈍化し、24年末にかけては4%程度で推移している(第2-1-90図)。
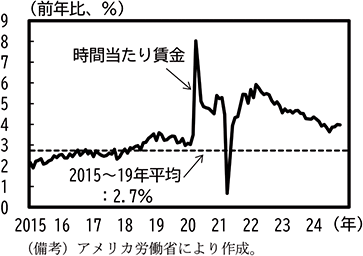
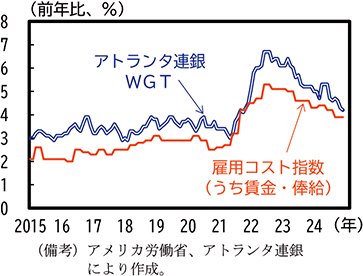
ここで、感染症拡大前から足下にかけての時間当たり名目雇用者報酬の伸びを労働分配率、実質労働生産性、付加価値デフレータの3つの要因に分けて考える110(第2-1-91図)。物価上昇率(コアPCEデフレータ)が2%前後で安定していた2017~19年頃にかけての時間当たり名目雇用者報酬は、労働分配率がおおむね一定の下、労働生産性、デフレータの寄与がそれぞれ1.5%ポイント、2.0%ポイント前後の、あわせて3.5%~4.0%で推移をしていた。その後、感染症拡大に伴い、3つの要因がそれぞれ大きく変動した後、2024年初以降、労働生産性、デフレータの寄与がともに2%ポイント前後で推移する中、労働分配率のプラス寄与が続いている。
以下では、労働生産性と労働分配率の動向を確認する。
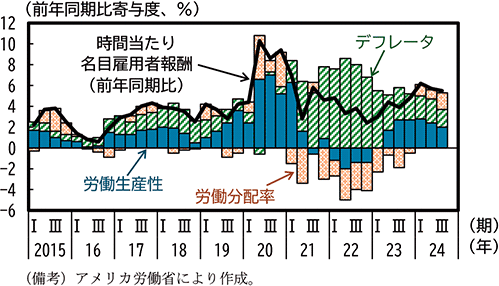
まず、労働生産性について、アメリカ労働省が公表する非農業民間部門の労働生産性は、前述のGDP統計の2024年年次改定を受けて上方改定された結果(第2-1-92図)、2020~23年の実質労働生産性の伸び(年率)は1.9%と、感染症拡大前の2015~19年の伸び(年率)である1.2%を大きく上回ることとなった(第2-1-93図)。
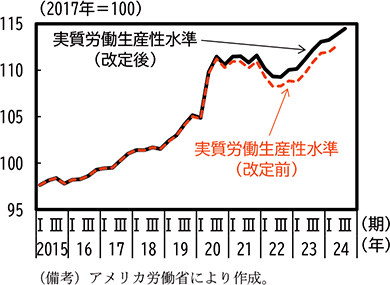
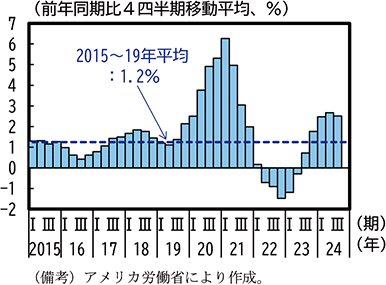
感染症拡大期の2020年後半~21年前半にかけて、労働生産性の伸びが大きく上昇したことについては、一時的な労働者構成の変化や資本装備率の高まり等によるものであることが指摘されている111。実際に、感染症の収束に伴って経済が再開した21年以降の労働生産性の伸びは低下に転じ、2022年にはマイナスに落ち込んでいる。ただし、2023年末以降の実質労働生産性の伸びは2015~19年平均の年率1.2%を上回る伸びとなっており、賃金上昇を下支えしている。
次に労働分配率について確認する。
アメリカの労働分配率は長期的に低下傾向にある(第2-1-94図(1))。アメリカを含めた先進諸国の趨勢的な労働分配率の低下の背景については、(1)資本財価格の(賃金に対する)相対的な低下、(2)貿易や海外へのアウトソーシングを含めたグローバル化、(3)労働市場や制度の変化、(4)生産性が高く労働分配率の水準が低い資本集約的な「スーパースター企業」が経済活動に占めるシェアの上昇、が指摘されている112。なお、アメリカにおいては特に、(4)の「スーパースター企業」のシェアが上昇したことにより、労働分配率が低下してきた可能性が指摘されている113。
2010年代以降の労働分配率はおおむね横ばいで推移してきたが、感染症拡大後に一時的に上昇した後、2023年末にかけては過去最低水準まで低下した。なお、2024年末にかけては反発がみられており(第2-1-94図(2))、短期的には、時間当たり名目雇用者報酬の下支え要因となっている。
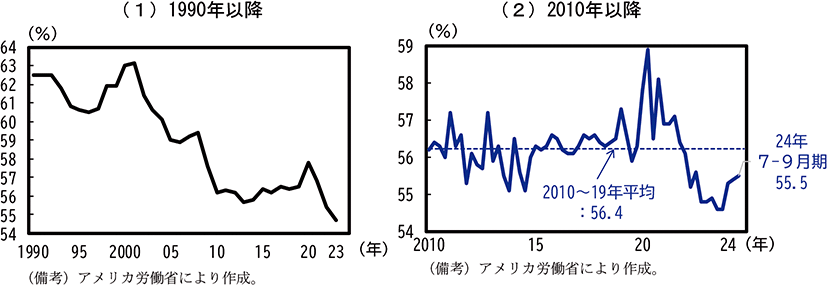
以上のように、アメリカにおける2024年末にかけての賃金上昇の底堅さの主な背景として、感染症拡大前と比較して高い労働生産性の伸びが継続していることが挙げられる。労働分配率を含め、賃金動向に大きな影響を与えるこれらの要因について、引き続き注視していく必要がある。
(消費者物価上昇率は2%台まで低下)
消費者物価指数(CPI)(総合)をみると、前年比は2022年6月(9.1%)をピークに低下したのち、23年7月以降、3%台でおおむね横ばいで推移してきた。24年4月以降は低下傾向にあったものの、24年10月以降上昇し、24年12月は2.9%となった。また、FOMCが重視しているPCEデフレータ(コア)の前年比をみると、2024年5月以降、2.7~2.8%前後でおおむね横ばいで推移している(第2-1-95図)。
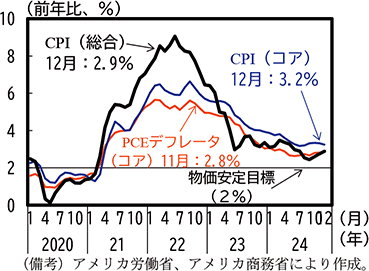
次に、CPIの推移を項目別に確認する。変動の大きいエネルギー、食料品を除いたCPI(コア)の前年比をみると、3%台でおおむね横ばいで推移している。CPI(コア)は、コア財(エネルギー、食料品を除く財)、住居費、スーパーコア(電力、ガス、住居費を除くサービス)の3つに分解することができ、これらの前年比の推移をみると、コア財が大きく低下している一方、住居費、スーパーコアは依然として高い水準にとどまっている(第2-1-96図)。
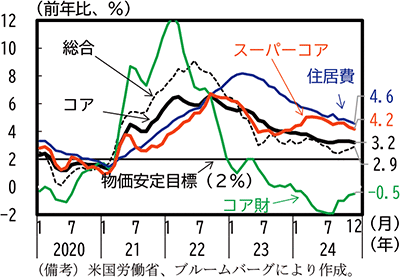
以下、住居費及びスーパーコアについて詳細に確認する。
CPIの住居費には主に、賃借人が実際に支払っている「家賃」と、家を所有人が自身の家を借りていると仮定した「帰属家賃」が含まれる。これら2項目(以下「CPI家賃」という。)がCPI全体に占めるウェイトは約35%と、物価動向に与える影響は大きく、2023年以降の消費者物価上昇率の鈍化ペースが緩やかになっている要因の一つとなっている(第2-1-97図)。
CPI家賃を作成する上で実施されるCPI Housing Surveyのサンプルには、新たな物件の賃貸契約をしたばかりの人のほか、同じ物件に住み続けている人も含まれる。前者が支払う家賃は、賃貸住宅市場における募集賃料とおおむね同様の動きをする一方で、後者が支払う家賃は、基本的には契約期間中は上昇しないことから、賃貸住宅市場における募集賃料の変動に対してラグが生じる。こうしたことから114、CPI家賃は、賃貸住宅市場における募集家賃を民間企業が集計・作成している家賃指標(以下「民間家賃指標」という。)に約1年程度遅れて推移するとされていた115。
しかし、民間家賃指標の伸びが2023年半ば頃には感染症拡大前の水準まで鈍化した一方で、CPI家賃の伸びは2024年末においても感染症拡大前の水準を上回っており、そのラグが長期化している(第2-1-98図)。
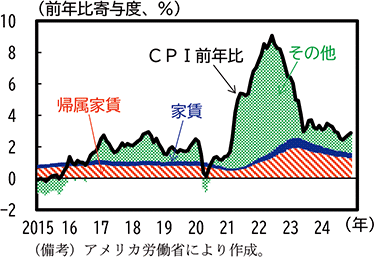
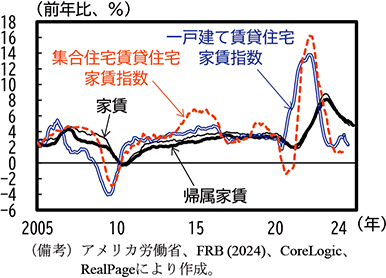
CPI家賃の民間家賃指標への遅れが長期化している背景としては、以下2点が指摘されている116。1点目は、CPI Housing Surveyのサンプルにおいて、新たな物件の賃貸契約をしたばかりの人の割合が低くなっており、民間家賃指標の動向がCPI家賃に反映されるまでに要する期間が長期化していることである。現在住んでいる賃貸物件に過去1年以内に引越してきた人の割合は2000年以降低下しており、2023年時点で過去最低に近い水準にある(第2-1-99図)。2点目は、感染症拡大後の賃貸住宅市場における募集賃料の伸びが急速に上昇したため、同じ物件に住み続けている人の家賃に反映されるのにこれまでよりも時間を要していることである。募集賃料の伸びが急速に上昇した2021年以降、新たな物件の賃貸契約をしたばかりの人の家賃が大幅に上昇する一方で、同じ物件に住み続けている人の家賃の上昇は緩やかなものにとどまった(第2-1-100図)。結果、募集賃料の水準と同じ物件に住み続けている人の家賃水準との差が過去よりも大きくなったことから、そのキャッチアップに時間を要している可能性がある。
以上を踏まえると、CPI家賃と民間家賃指標とのラグが長期化してはいるものの、2024年末にかけて民間家賃指標が感染症拡大前の伸びで推移する中、CPI家賃も感染症拡大前の伸びの水準に緩やかに回帰すると考えられる。
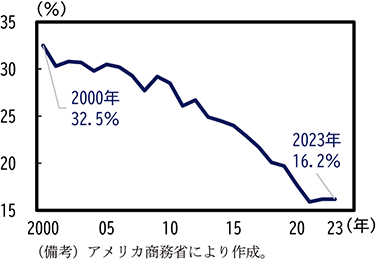
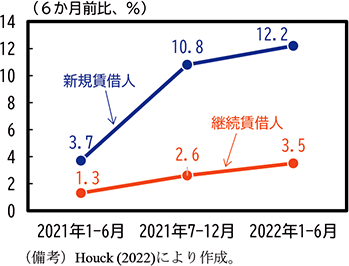
次にスーパーコアを確認する。CPIのスーパーコアを品目別にみると、自動車保険の上昇が大きいことが分かる(第2-1-101図)。保険の物価上昇をより細かく確認するために、PCEデフレータの保険(insurance)の品目別の寄与度をみると、2023年頃から自動車、その他運送保険純額を中心に保険が全体的に上昇していることが分かる(第2-1-102図)。
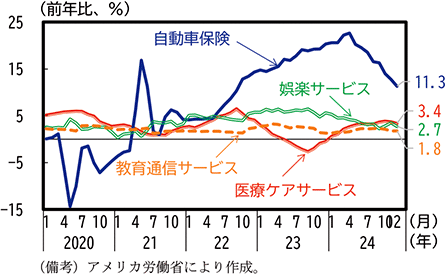
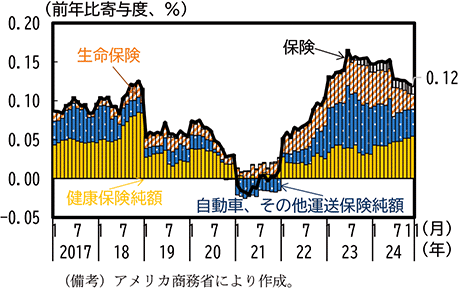
自動車保険料が上昇している要因として、ビリオンダラー災害(被害額が10億ドルを超える災害)の件数が増加傾向にあることが挙げられる117(第2-1-103図)。自然災害の増加を受け、保険会社は保険金の支払い規模が拡大することを忌避し、住宅向け損害保険の引き受けから相次いで撤退し、残された会社は保険料を引き上げるといった事象が発生している。自然災害は年々増加傾向にあることから、今後、保険関係の物価上昇を注視する必要がある。ただし、2024年11月のFOMC後の記者会見においてパウエル議長が言及118したとおり、住居費、保険にはキャッチアップインフレが起きている可能性があり、必ずしも現在のインフレ圧力を反映しているわけではないことには留意が必要である。
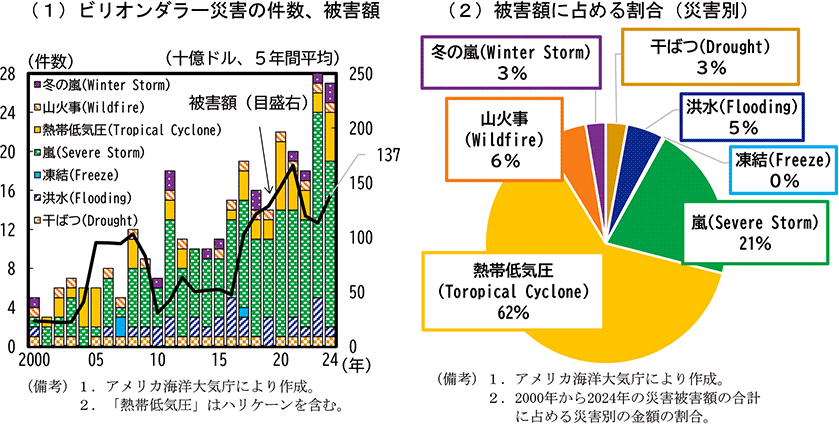
ここで、感染症拡大前、物価高騰期、そして直近の3つの期間における消費者物価上昇率の品目数の構成比を確認する(第2-1-104図)。具体的には、①消費者物価上昇率の前年比が2.0%だった2019年4月、②消費者物価上昇率が前年比9.1%と感染症拡大以降最も高い水準にあった2022年6月、③直近の2024年12月の品目ごとの物価上昇率をみると、以下のようにまとめられる。
① 大半の品目の物価上昇率が▲2%~4%の範囲にとどまり、左右対称の単峰型を形成。
② 財を中心に多くの品目の物価上昇率が10%以上となり、右に偏った分布を形成。
③ 大半の品目の物価上昇率が▲2%~4%の範囲にとどまり、左右対称の単峰型に戻りつつあることがうかがえる。
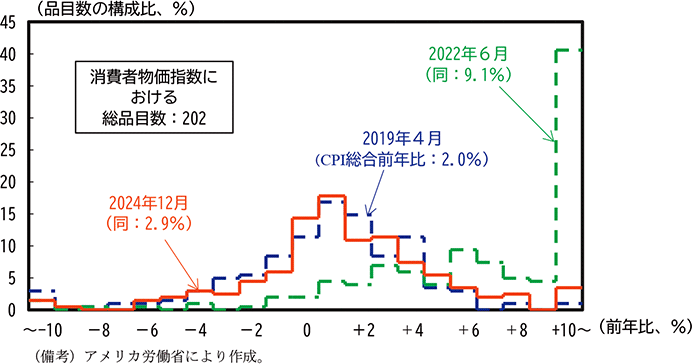
コラム2 国際商品市況
本コラムでは、各国の物価動向や景気動向に影響を与える可能性のある原油、天然ガス、小麦の価格動向について概観する。まず、2021年~2024年6月までの国際市場における各商品の価格の動きを振り返り、その後2024年7月以降の足元の価格の動きを詳しくみていく。
(ⅰ)原油
原油価格(WTI)(図1(1))は、2021年当初は60ドル/バレルであったが、2022年2月に起きたウクライナ侵略をきっかけとして一時120ドル/バレルまで上昇した。その後は値下がりに転じたが、2023年10月のパレスチナ武装勢力によるイスラエルへの攻撃を契機とした中東情勢の緊迫化から、100ドル/バレル近くまで上昇した。その後は、価格はやや下落し、2024年6月は80ドル/バレル前後で推移した。
足下の動向をみると(図2(1))、2024年7月当初は83ドル/バレルであったが、中東情勢の緊迫化懸念の後退や中国の景気後退観測等から、7月末には75ドル/バレルまで下落した。8月に入ると、中東情勢が再度緊迫化したことから80ドル/バレルまで上昇する場面もあったが、その後は下落に転じ、8月下旬には73ドル/バレルまで値下がりした。9月には、アメリカの景気の減速懸念やOPECの原油需要予測の下方修正等を受けて65ドル/バレルまで下落した。その後は持ち直しの動きとなり、10月初旬にはイランのイスラエルへのミサイル攻撃を契機とした中東情勢の悪化懸念から77ドル/バレルまで上昇したが、中旬以降は中東情勢の悪化懸念が後退したことから、下旬には70ドル/バレルまで下落した。11月に入ると、OPECの自主減産縮小の延長等から下値が抑えられ、おおむね横ばいでの動きとなり、68ドル/バレル前後で推移した。12月はイスラエルとレバノンのシーア派民兵組織であるヒズボラとの停戦合意を受け下落したのち、シリア情勢の不透明感の高まりから71ドル/バレルまでやや上昇した。1月中旬には、米英によるロシア石油生産・輸出に対する制裁強化の発表を受け、78ドル/バレルまで上昇した。
(ii)天然ガス
欧州における天然ガスの先物価格(TTF)(図1(2))は、2021年当初は20ユーロ/メガワット時であったが、2021年冬期の低い気温に起因する需要増によって上昇した後、ロシアによるウクライナへの侵略により、一時210ユーロ/メガワット時まで上昇した。2022年8月には、ロシアのガスプロムによるノルドストリーム・パイプラインの定期修理とその間のガス供給停止の発表により供給不安となり、一時300ユーロ/メガワット時まで上昇した。2023年10月には、パレスチナ武装勢力によるイスラエルへの攻撃等の中東情勢の悪化を受け、50ユーロ/メガワット時まで上昇した。その後は、おおむね横ばいでの推移となり、2024年6月下旬には34ユーロ/メガワット時となった。
足下の動向をみると(図2(2))、2024年7月当初は33ユーロ/メガワット時であったが、8月にはウクライナ軍によるロシアのクルスク州への越境攻撃を背景とした地政学的リスクの高まりから、40ユーロ/メガワット時まで上昇した。9月に入ると、初旬は弱めの需要からやや下落したが、中旬以降はウクライナ情勢の緊迫化への懸念等から上昇傾向に転じ、10月には、40ユーロ/メガワット時まで値上がりしたが、在庫の多さなどにより上値が抑制され、その後はおおむね横ばいでの推移となった。11月に入ると、気温の低下による在庫の取り崩しやウクライナ情勢の悪化懸念等から、48ユーロ/メガワット時まで上昇した。12月は、初旬は比較的温暖な気候が予測され価格は下落したが、中旬にロシアのプーチン大統領によるウクライナとのガス輸送協定を延長しないとの発言を受け、月末に50ユーロ/メガワット時まで値上がりした。1月に入ると、気候が比較的温暖となったため、48ユーロ/メガワット前後で推移した。
(iii)小麦
小麦価格(シカゴ商品取引所)(図1(3))は、2021年当初は6.5ドル/ブッシェルであったが、2022年2月のウクライナ侵略を受けて、供給不安が高まり、12.9ドル/ブッシェルまで上昇した。その後は、アメリカの供給量増の見通しから値下がりし、2022年末には7.5ドル/ブッシェルまで下落した。2023年以降は需給が安定したことで、やや下落し、2024年6月下旬には5.7ドル/ブッシェルとなった。
足下の動向をみると(図2(3))、2024年7月当初は5.8ドル/ブッシェルであったが、世界最大の輸出国であるロシアの減産懸念が緩和し、アメリカ等でも豊作の観測が高まったため下落し、7月末には5.3ドル/ブッシェルとなった。その後、8月はおおむね横ばいで推移したが、9月に入ると、天候不順の影響を受けた世界的な供給減から価格は上昇し、10月初旬には6.0ドル/ブッシェルまで値上がりした。しかし、その後は小麦生産国であるカザフスタン等で豊作が見込まれたことから供給増の見通しとなり、価格は低下し、11月下旬には5.5ドル/ブッシェルとなった。12月から1月は需給の変化が少なく、横ばいでの動きとなり、5.5ドル/ブッシェル前後で安定的に推移している。
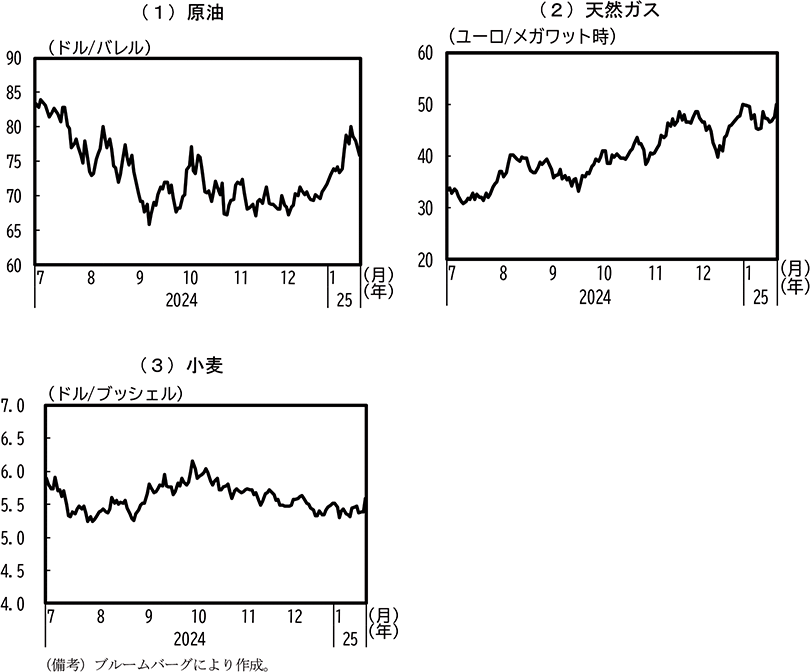
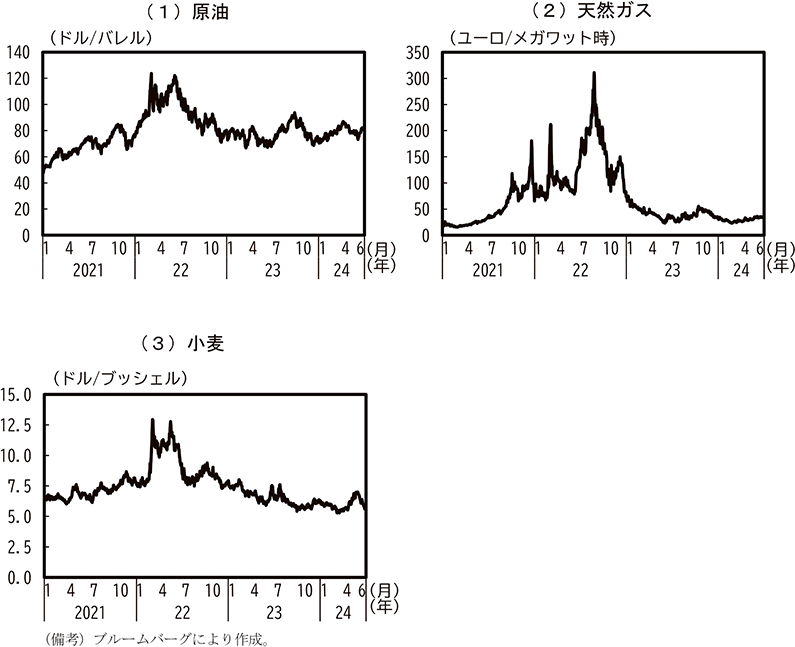
(政策金利は引下げ)
ここまでみてきたとおり、物価上昇率が2%台まで低下し、労働市場の需給緩和が進む中、政策金利は引き下げられた。
FRBは、2023年9月以降、FFI金利の誘導目標範囲を5.25~5.50%に据え置いていたが、24年9月の利下げを皮切りに、同年末にかけての3会合で累計1%ポイントの利下げを行った。トランプ大統領の就任後初となる2025年1月会合では、4会合ぶりにFFI金利の誘導目標範囲を据え置いた(第2-1-105図、第2-1-107表)。
今後の金融政策決定に関して、25年1月会合では、「(トランプ政権の政策が)どのように実行されるか、我々の政策対応がどうあるべきかを理解するところまでは、急がないつもり」と、先行きの政策決定における慎重なスタンスを示した。
2024年12月会合にて公表された四半期経済見通し(Summary of Economic Projection)によれば、25年末までに0.5%ポイントの利下げ(1回の利下げ幅を0.25%ポイントとすれば、2回分の利下げに相当)が行われる可能性が高いことが示されている。なお、金融市場が見込むFFI金利の推移は、24年9月以降切り上がった結果、24年12月時点では、25年末までに0.25%ポイント程度の利下げしか織り込まれていない(第2-1-106図)。
同見通しにおける、FOMC参加者による中立金利(長期FFI金利)の想定を確認すると、2024年以降、中央値が切り上がると同時にその分散も大きくなっており(第2-1-105図)、中立金利の水準をめぐる不確実性は大きい。
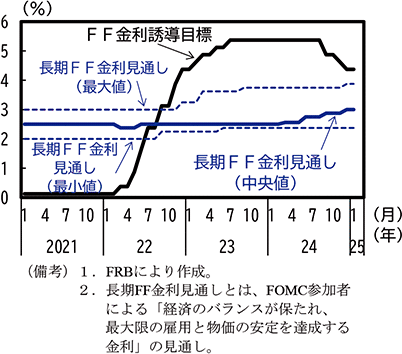
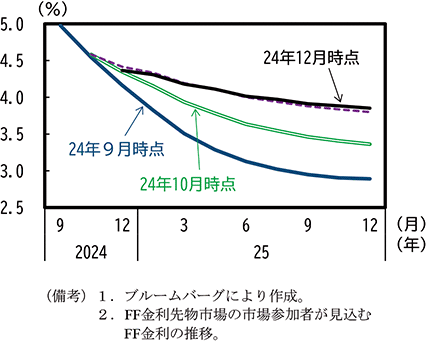
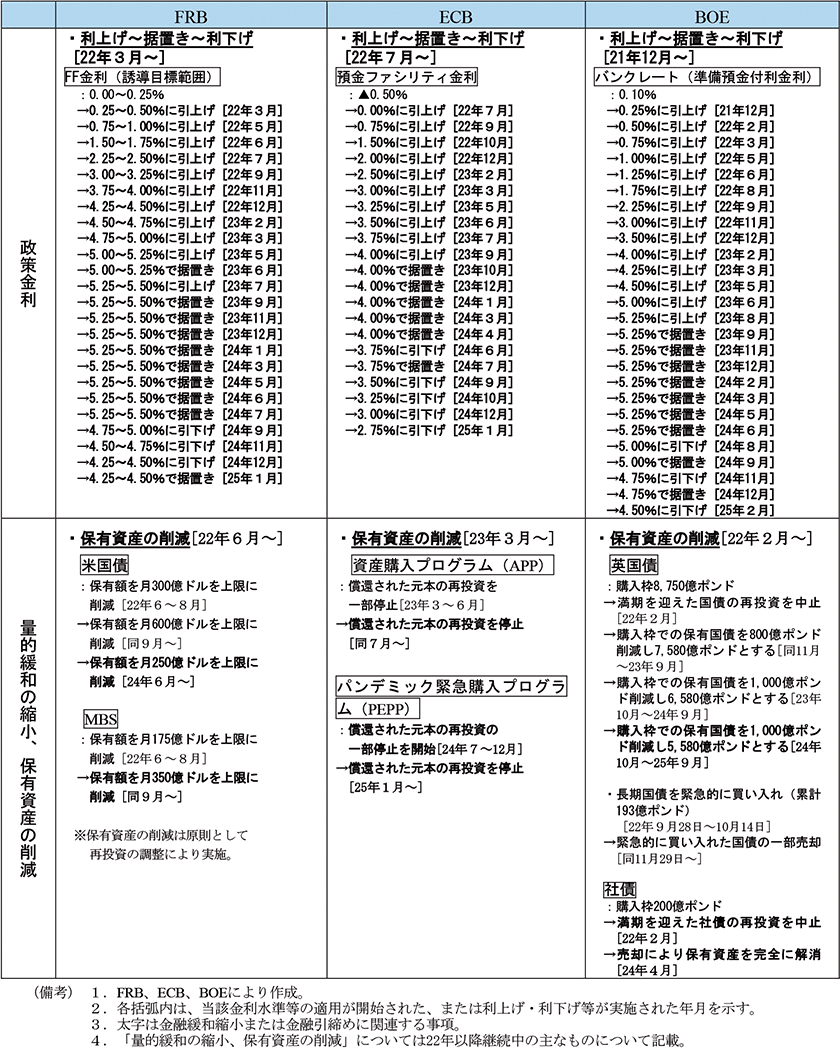
(財政赤字は拡大傾向)
政権交代による財政への影響に注目が高まる中、以下では、アメリカの一般政府の財政状況について確認した後、赤字が拡大している連邦政府の財政状況について整理する。
まず、アメリカの一般政府の財政状況について確認する。
2024会計年度119における一般政府の歳入・歳出120をみると、歳入7.8兆ドル、歳出9.7兆ドルと、歳出が歳入を上回ることで1.9兆ドルの財政赤字が生じている(第2-1-108図(1))。連邦政府、州・地方政府別に確認すると、連邦政府が歳入4.9兆ドルに対して歳出6.8兆ドル、州・地方政府が歳入3.8兆ドルに対して歳出3.9兆ドルと、2024会計年度における一般政府の財政赤字のほぼ全てを連邦政府の財政赤字が占めていることが分かる(第2-1-108図(2))。
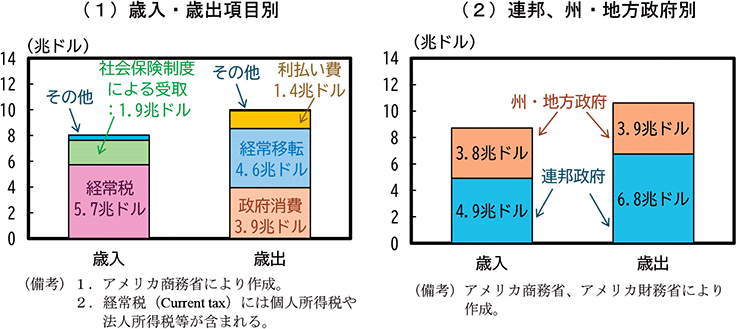
一般政府の財政収支の推移をみると、2001年以降、連邦政府の財政赤字の拡大を主因として赤字が拡大している(第2-1-109図)。こうした状況下で、一般政府債務残高は積み上がっている(第2-1-110図)。
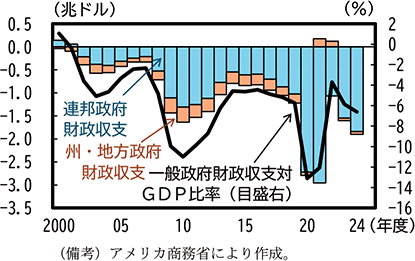
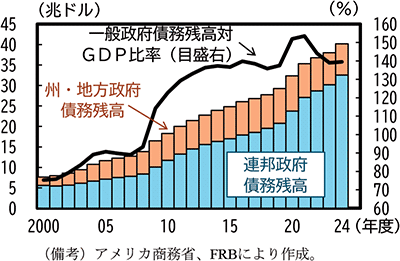
以下、一般政府の財政赤字の主因となっている連邦政府の財政状況について確認する。
2024会計年度における連邦政府の歳入は4.9兆ドル、歳出は6.8兆ドルであり、結果として財政赤字は1.8兆ドルと、前会計年度の1.7兆ドルから拡大した。2024会計年度の歳入、歳出の内訳をみると、歳入は大きい順に個人所得税(2.4兆ドル)、社会保障税等(1.7兆ドル)、法人所得税(0.5兆ドル)となる一方、歳出は社会保障費(1.5兆ドル)、保健(0.9兆ドル)、利払い費(0.9兆ドル)、メディケア(0.9兆ドル)、国防費(0.9兆ドル)と続く(第2-1-111図)。
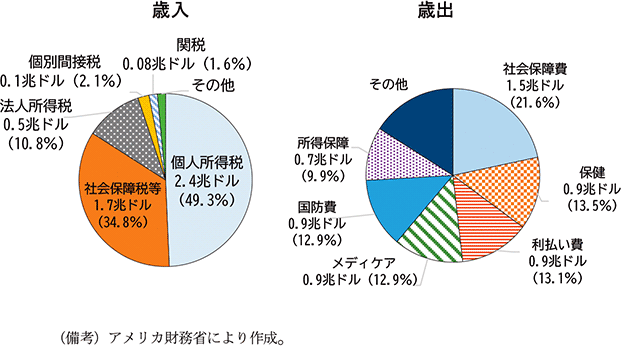
次に、連邦政府の財政収支の推移を確認する。1998年度から2001年度まで黒字となっていた連邦政府の財政収支121は、2002年度以降、赤字に転じた122。その後は、世界金融危機や感染症拡大に伴う大規模な財政支出により一時的に赤字が拡大する局面を挟みながら、赤字は拡大傾向にあり、財政収支対GDP比は低下傾向にある(第2-1-112図、第2-1-113図)。結果として連邦政府の債務残高は積み上がっており、対GDP比でみてもおおむね上昇傾向にある(第2-1-114図)。
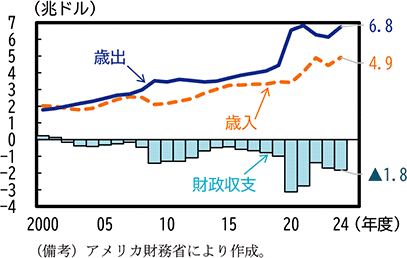
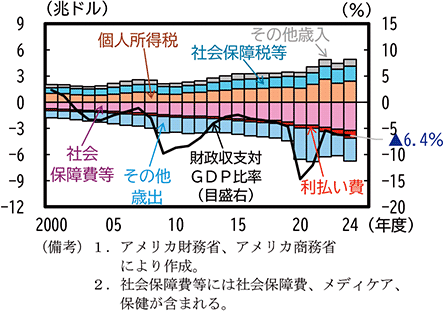
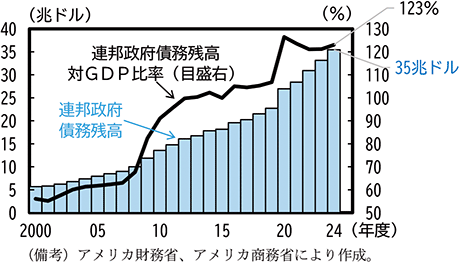
以下では、主な歳入・歳出項目について詳細に確認する。歳入について、感染症拡大前の個人所得税収入は、2018年1月から個人所得税率の引下げ123が実施されたにも関わらず、2019年度にかけて緩やかに増加した。その後、感染症拡大期の2020年度にやや減少したものの、22年度にかけては景気の回復に伴う良好な雇用・所得環境を支えに急拡大し、24年度にかけても底堅く推移している。法人所得税は2016年度以降伸び悩んでいた中、2018年1月から実施された連邦法人税率の引下げ124等を受け、18~20年度は2,000億ドル程度まで落ち込んだ。しかし、その後は、感染症拡大からの景気回復を背景として急伸し、24年度には5,000億ドルを超えた(第2-1-115図)。関税収入は、第一次トランプ政権下で導入された累次の関税措置の影響を受け、2019年度以降、拡大している(第2-1-116図)。
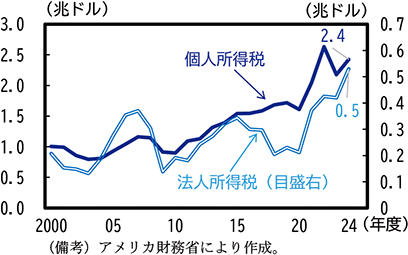
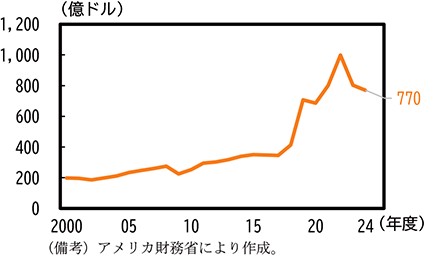
歳出面では、最大の支出項目である社会保障費は、高齢化を背景として長期的に増加傾向にある(第2-1-117図)。こうした中、2022年度以降、長期金利の上昇とともに利払い費が増加しており、2024年度には、国防費やメディケア等の支出項目と同程度の水準まで増加した(第2-1-118図)。なお、CBOの見通しによれば先行きも利払い費は増加していくことが見込まれている(第2-1-119図)。
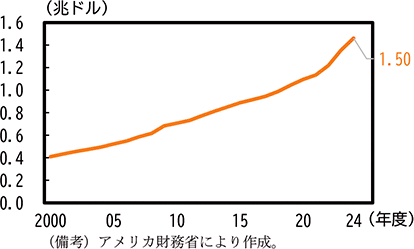
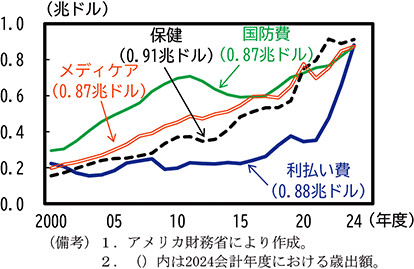
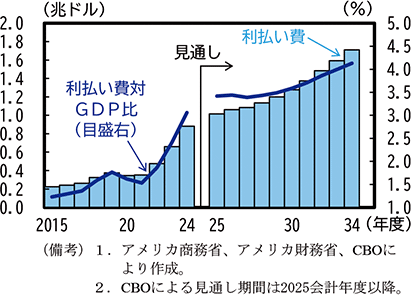
(長期金利は高止まり)
2024年半ば以降、低下基調となっていたアメリカの長期金利は、同年10月以降、市場の予想を上回る経済指標の公表が続いたことにより上昇に転じ、24年末にかけては4.6%を上回るまで上昇した(第2-1-120図)。
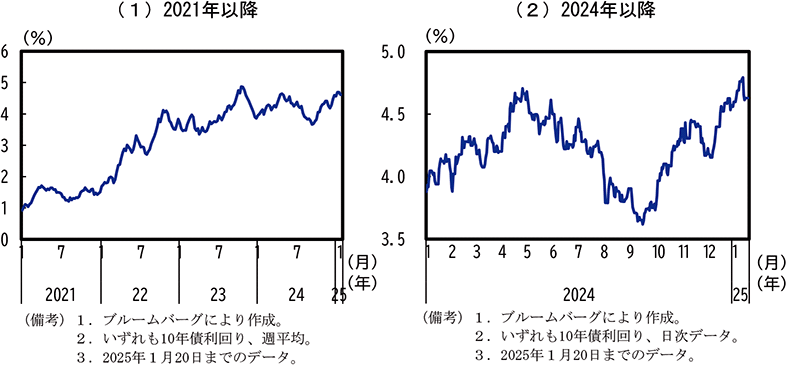
長期金利は将来の短期債利回りの予想とターム・プレミアム125に分けることができ、ニューヨーク連銀がそれぞれについて推計をしているが、24年10月以降、ターム・プレミアムが大きく上昇しており、それにより長期金利が押し上げられていることが分かる(第2-1-121図)。
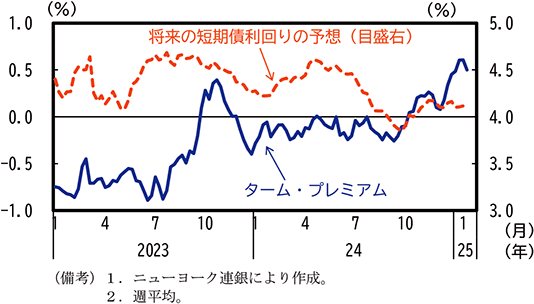
米国債のイールドカーブを確認すると、2024年9月以降、利下げ局面に入ったことにより短期債の利回りが低下する一方で、前述のとおり長期債の利回りは上昇している(第2-1-122図)。2年、10年債の利回り差(10年債利回り―2年債利回り)は、2022年半ば以降で初めてプラスに転じている(第2-1-123図)。
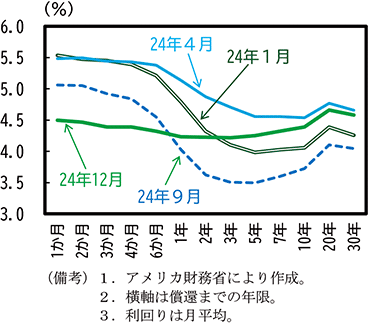
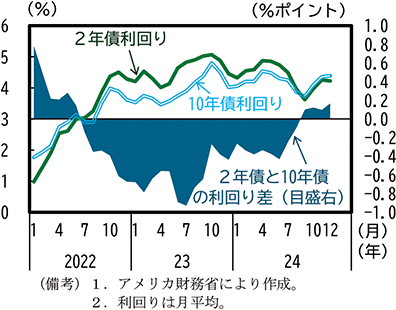
3.産業別・州別の経済動向
1項ではアメリカ経済は総じて景気拡大が続いていることを確認した。ただし、産業ごと、州ごとに景気回復の程度や早さにはばらつきがあると考えられる。本項では、感染症拡大後のアメリカの産業別、州別の経済動向について確認する。まずは人口・経済規模の大きい4州(カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州、ニューヨーク州)の経済動向について確認し、これらの州が感染症拡大後のアメリカ経済をけん引してきたことを確認するとともに、州ごとの産業構造等の違いについて確認する。その後、いわゆる「ラストベルト」と呼ばれる4州(ミシガン州、ウィスコンシン州、ペンシルバニア州、オハイオ州)の経済動向について確認し、これらの州の経済成長率が低い126要因を産業構造等から考察する(第2-1-124図)。
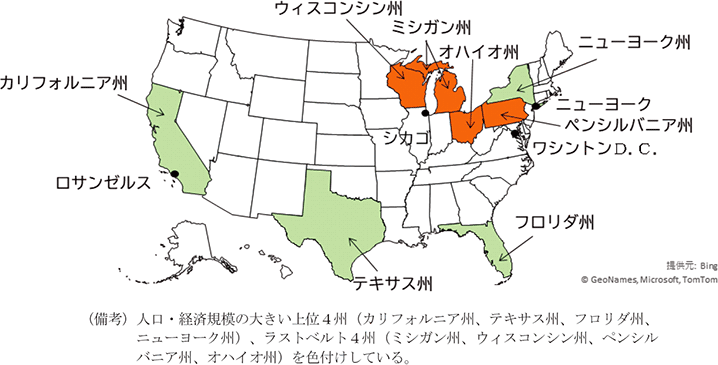
(人口・経済規模が大きい州が感染症拡大後のアメリカの景気回復をけん引)
まずは、アメリカの州別の人口をみると(第2-1-125表)、1位がカリフォルニア州、2位がテキサス州、3位がフロリダ州、4位がニューヨーク州である(以下、これらの4州を総称して「人口上位4州」という。)。また、人口上位4州のGDP・個人消費をみると、カリフォルニア州はともに1位、テキサス州はともに2位、フロリダ州はGDPが4位で個人消費は3位、ニューヨーク州はGDPが3位で個人消費は4位となっており、人口上位4州は経済規模も大きいことが分かる。
なお、人口上位4州の2023年の名目GDPを諸外国の名目GDPと比較すると(第2-1-126表、第2-1-127図)、カリフォルニア州(3.87兆ドル)は世界5位のインド(3.57兆ドル)、テキサス州(2.58兆ドル)は世界8位のイタリア(2.30兆ドル)、ニューヨーク州(2.17兆ドル)は世界9位のブラジル(2.17兆ドル)、フロリダ州(1.60兆ドル)は世界15位のスペイン(1.62兆ドル)と、それぞれ同程度の経済規模をもっていることが分かる。
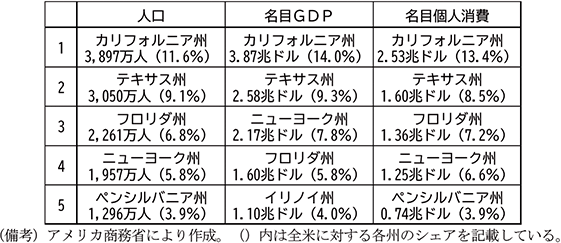
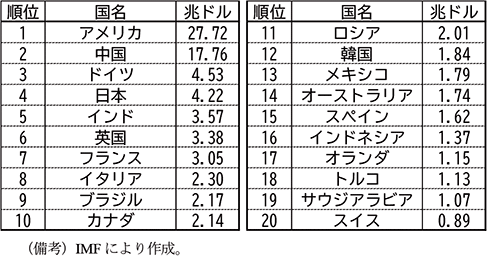
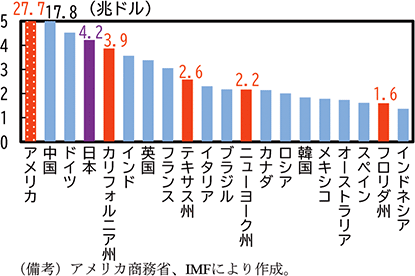
GDPシェアの37%127を占める人口上位4州の感染症拡大後の実質GDPの推移をみると(第2-1-128図)、人口上位4州のうち特にテキサス州やフロリダ州が全米を上回る伸びで経済成長を続けてきたことが分かる。また、アメリカの実質GDP成長率を州別に寄与度分解を行うと(第2-1-129図)、人口上位4州の感染症拡大後の実質GDP成長率寄与度の合計は4.2%ポイントであり、同期間の全米の成長率9.4%の44%を占めている128。中でも、GDPの伸びが高いテキサス州やフロリダ州、そして、GDPの伸びは全米と同程度であるものの経済規模が全米1位のカリフォルニア州が大きくプラスに寄与している。このことから、感染症拡大以降のアメリカの景気回復をカリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州がけん引してきたことが分かる。
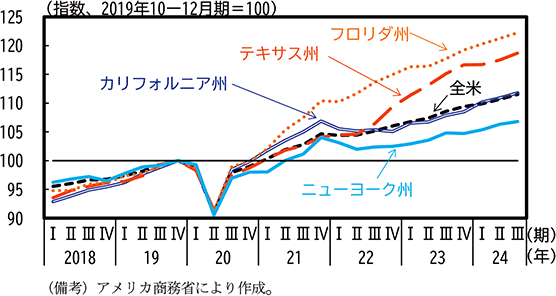
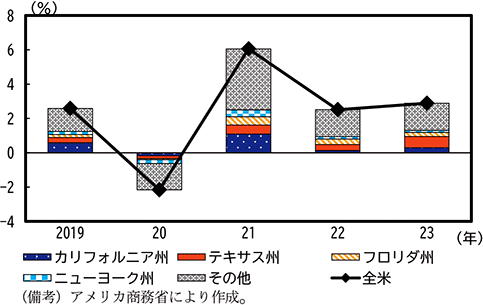
感染症拡大後のテキサス州、フロリダ州の実質GDPの伸びが全米を上回っている理由としては、同州の人口増加が挙げられる。人口上位4州の人口の推移をみると(第2-1-130図)、テキサス州とフロリダ州は2000年以降、全米を上回る伸びで人口が増加しており、感染症拡大後も全米を上回る伸びでの人口増加が続いている。一方、ニューヨーク州の人口の伸びは、2000年以降、全米の伸びを下回っており、また、カリフォルニア州の人口の伸びは感染症拡大前までは全米とおおむね同じ伸びで推移していたが、感染症拡大以降は、ニューヨーク州、カリフォルニア州ともに人口が減少傾向にある。なお、一人当たり実質GDPをみると(第2-1-131図)、カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州は全米を上回って伸びているのに対して、フロリダ州の伸びは全米を下回っていることから、フロリダ州の経済成長は人口増加によるものが大きいことが分かる。
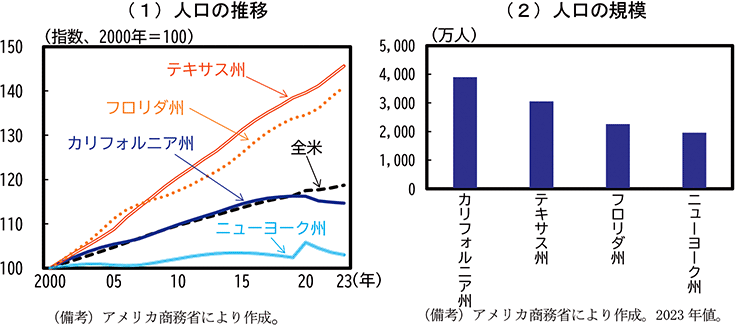
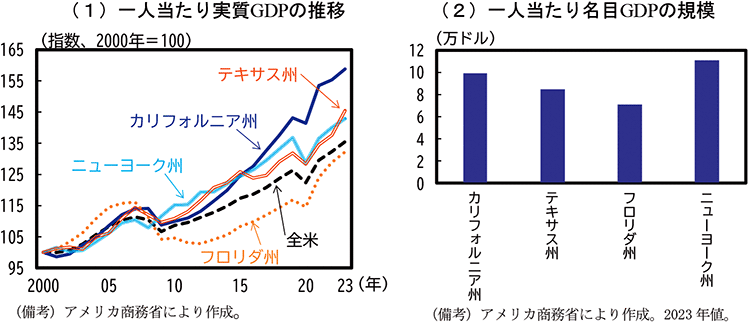
(カリフォルニア州は情報産業を中心に経済成長)
それでは、人口上位4州は、感染症拡大後、どのような産業で付加価値を生み出してきたのだろうか。このことを確認するために、州別の基本情報及び産業構成についてみてみよう。
まずは人口・GDP・個人消費ともに全米1位のカリフォルニア州の産業構成をみると、専門ビジネスサービスや情報等の産業構成比が全米と比較して高い(第2-1-132図、第2-1-133図)。また、製造業の中でも特にコンピュータ電子機器の構成比が高い点が特徴的である。
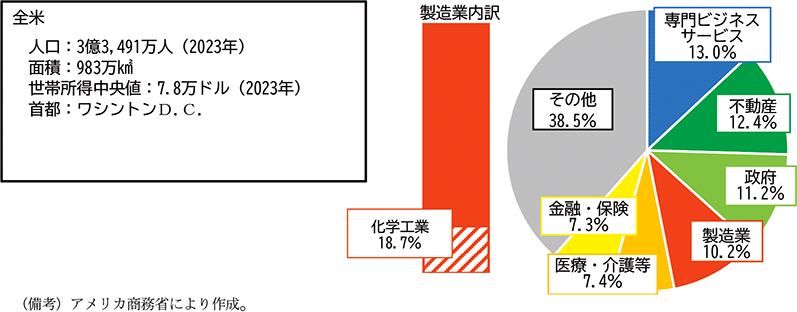
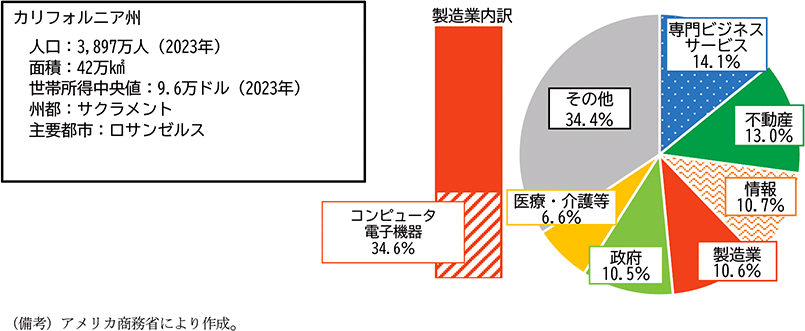
カリフォルニア州の感染症拡大以降の実質GDP成長率を産業別にみると(第2-1-134図)、カリフォルニア州の主要産業である情報産業は感染症拡大以降、成長をけん引してきた。一方で、専門ビジネスサービスについては2021年は大きく伸びたものの、2022年以降はプラス寄与が縮小している。
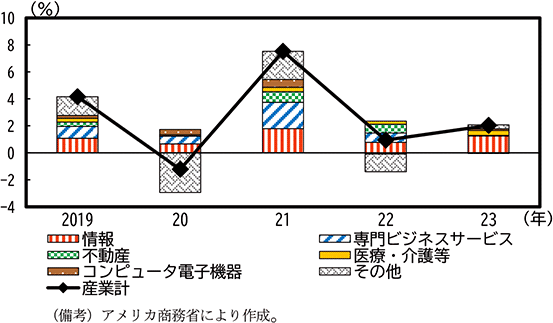
2022年以降、専門ビジネスサービスのプラス寄与が縮小した要因としては、テキサス州やフロリダ州では専門ビジネスサービスの付加価値が全米を上回って伸びた一方で、カリフォルニア州では専門ビジネスサービスの付加価値の伸びが全米を下回る伸びにとどまったことが挙げられる(第2-1-135図)。専門ビジネスサービスの内訳をみると、カリフォルニア州におけるコンピュータシステムの設計及び関連サービスや企業経営部門129の付加価値の伸びが2022年以降、全米を下回る一方で、テキサス州やフロリダ州は高い伸びとなっている(第2-1-136図)。
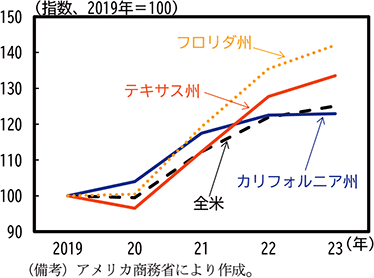
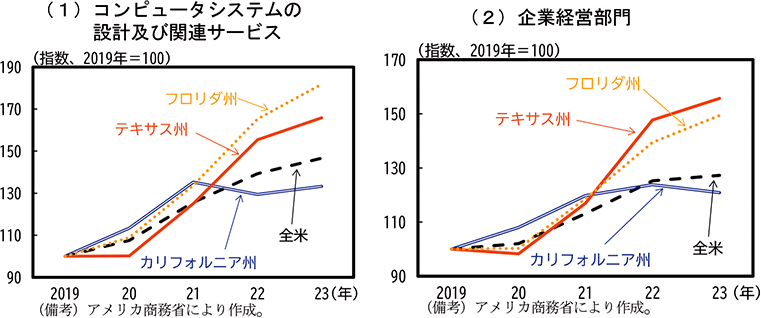
(テキサス州は鉱業や専門ビジネスサービスを中心に経済成長)
次に、人口・GDP・個人消費ともに全米2位のテキサス州の産業構成をみると(第2-1-137図)、全米と比較して製造業や鉱業等の産業構成比が高い。また、後述のとおり、原油生産量が多い州であることもあり、製造業の中でも特に化学工業の構成比が高く、全米を上回っている。
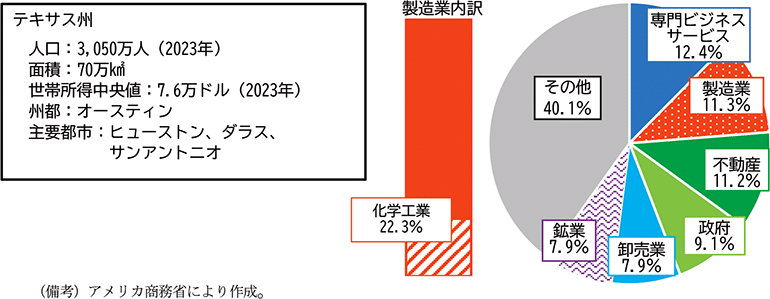
テキサス州の感染症拡大以降の実質GDP成長率を産業別にみると(第2-1-138図)、2021年・2022年は前述のとおり専門ビジネスサービスがプラス寄与したほか、人口の増加に伴い不動産業がプラスに寄与している(詳細は後述)。一方、主要産業である鉱業は2021年・2022年はマイナスに寄与していたものの、2023年は大きくプラスに寄与し、成長をけん引した。テキサス州の鉱業の実質付加価値が2023年に増加した背景としては、テキサス州の主要な原油生産地であるパーミアン地域において、掘削装置当たりの生産量が増加していることが挙げられる(詳細はBox参照)。
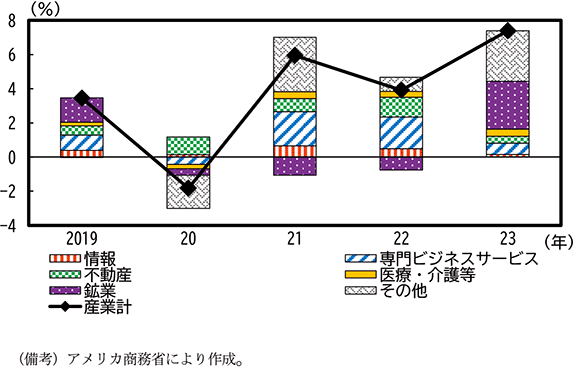
Box.アメリカの鉱業の特徴や近年の動向
ここでは、アメリカの鉱業の特徴や近年の動向について確認する。
アメリカでは2010年代に入って以降、国内でのシェールオイルの採掘効率が向上し、規制緩和も進んだ。これによりシェールオイル生産量が増加した結果(図1)、原油、石油製品の輸入が減少する一方で、輸出が増加してきた(図2)。2020年には輸出が輸入を上回り、その差は拡大傾向にある。
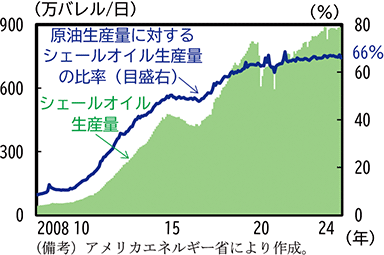
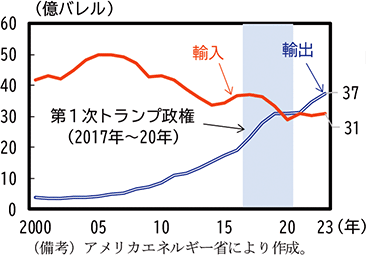
2022年における州別の一次エネルギー生産量のシェアをみると、テキサス州は26%と全米の中で大きなシェアを占めている(図3)。また、後述のとおり、2023年における鉱業の付加価値の全米に占めるシェアの約5割を占めており、テキサス州がアメリカの鉱業を大きくけん引していることが分かる。
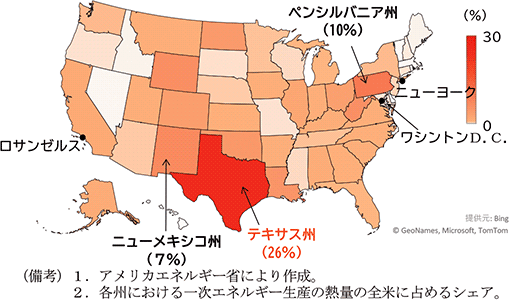
この理由としては、テキサス州に原油、特にシェールオイルの生産地が多く立地していることが挙げられる。アメリカエネルギー省が公表しているシェールオイル生産の主要な7地域のうちパーミアン、イーグルフォード、アナダルコ、ヘインズビルの4つの地域はテキサス州に位置している130(図4)。
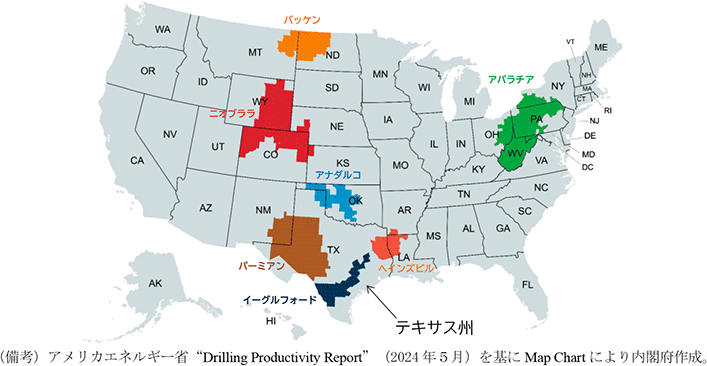
全米最大のシェールオイル生産量を誇るパーミアン含め、テキサス州に位置する4地域で、シェールオイル生産の主要な7地域の原油生産全体の約8割を占めている(図5)。
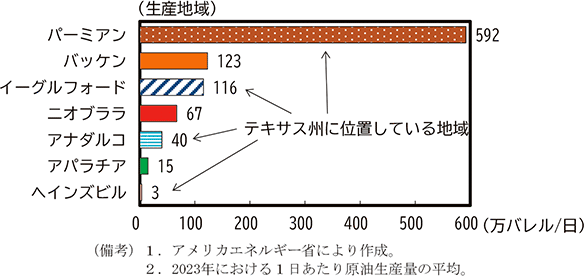
パーミアンでの原油生産量は増加傾向にあり、また、掘削装置当たりの生産量(資本の生産性に相当)も足下では緩やかに増加している(図6)。なお、先行きについては、アメリカエネルギー省が公表している見通しでは、アメリカ全体での原油生産は今後も伸びていくとされている(図7)。
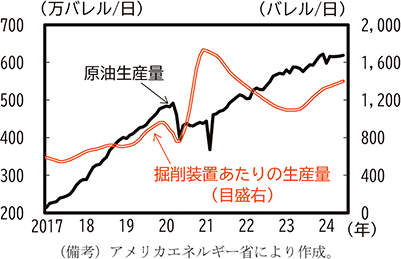
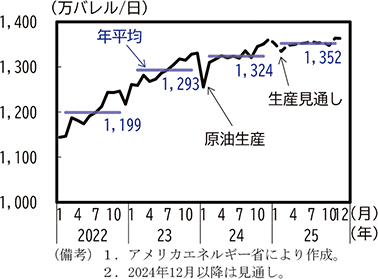
(フロリダ州は専門ビジネスサービスや不動産を中心に経済成長)
次に、人口・個人消費が全米3位、GDPが全米4位のフロリダ州の産業構成をみると(第2-1-139図)、全米と比較して不動産業や専門ビジネスサービス等の産業構成比が高い。また、全米と同様、製造業の中では特に化学工業の構成比が高い。
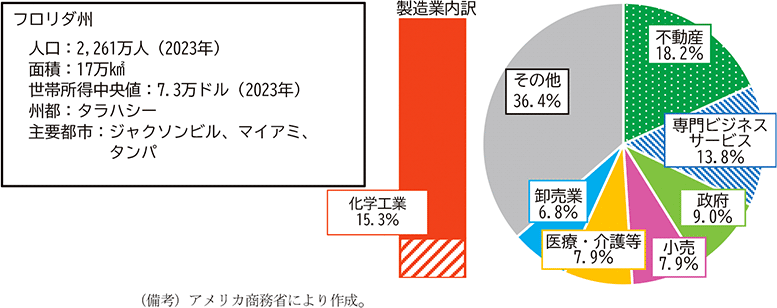
フロリダ州の感染症拡大以降の実質GDP成長率を産業別にみると(第2-1-140図)、2021年以降、不動産業や専門ビジネスサービスが成長をけん引している。
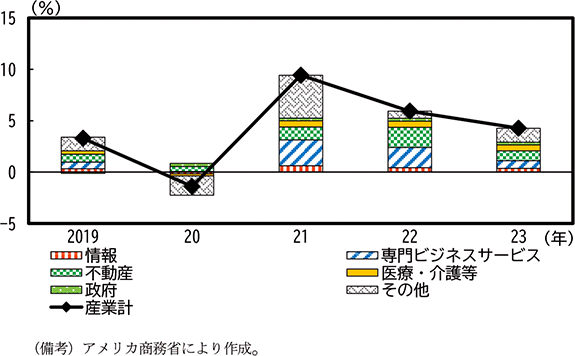
フロリダ州で不動産業の付加価値が大きくプラスに寄与している要因として、人口の増加が挙げられる。前述のとおり、テキサス州やフロリダ州の人口の伸びは、全米の伸びを上回っており、特に感染症拡大以降、大きく上昇している。こうした人口の増加に伴い、家賃等の住居費の州全体の支出総額が増加したことから(第2-1-141図)、不動産業の付加価値が増加していると考えられる。
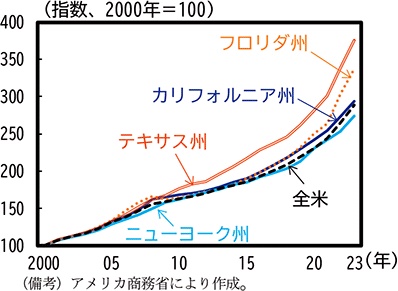
コラム3 ハリケーンの鉱工業生産への影響について
本コラムでは、2024年にアメリカに上陸したハリケーンが生産に与えた影響を確認する131。アメリカでは例年、6月から11月頃にかけてハリケーンが上陸し、特に南部から東海岸にかけての沿岸部が被害を受けやすい。ハリケーンは風速別に5つのカテゴリーに分けられるが、カテゴリー3~5はMajor hurricane(大型ハリケーン)と呼ばれており、特に警戒が必要とされている。また、ハリケーンは勢力が弱まった後も熱帯低気圧として竜巻や豪雨、洪水等様々な災害を引き起こす。アメリカ海洋大気庁では、ビリオンダラー災害(被害額が10億ドルを超える災害)を公表しているが、このうち、ハリケーンを含む「熱帯低気圧」の発生件数をみると、2024年は5つのハリケーンがアメリカ本土に上陸しており(表1)、2000年代(2000~2024年)の平均に比べて多い(図2)。
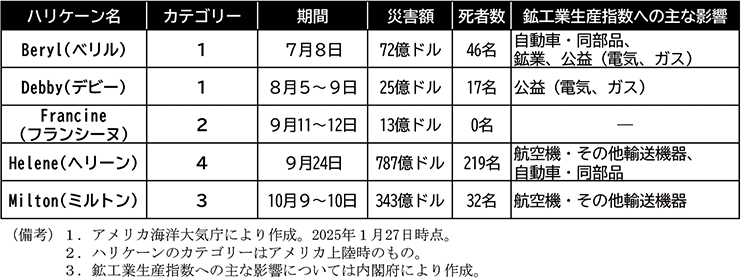
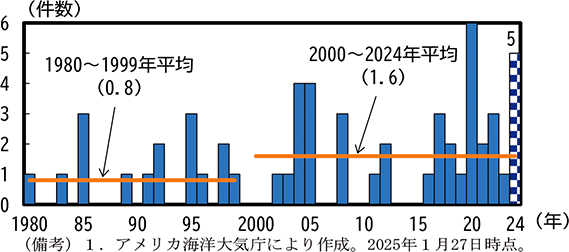
また、9月にアメリカに上陸したハリケーン・ヘリーンは洪水や停電も引き起こし、海岸から離れた内陸部にも被害を及ぼした。このため、同年のハリケーンによる被害額の総額は1,240億ドルとなった。また、2024年までの熱帯低気圧による州別被害額をみると、特にハリケーンが勢力を保ったまま上陸した南部、東海岸付近の州の被害額が大きい(図3)。
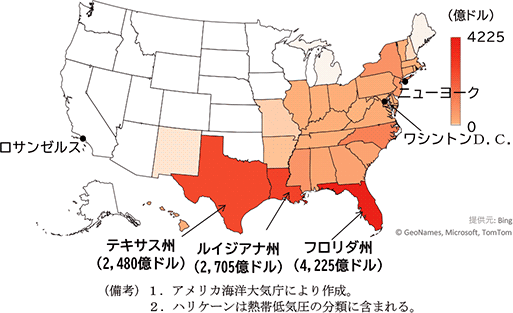
2024年に上陸したハリケーンが生産に与えた影響を確認するために、まずはアメリカの鉱工業生産指数を品目別に確認する。鉱工業生産指数の品目別前月比寄与度をみると(図4)、2024年7月は自動車・同部品、公益(電気、ガス)、鉱業がマイナスに寄与、同年8月は公益がマイナスに寄与、同年9月は航空機・その他輸送機械がマイナスに寄与、同年10月は自動車・同部品、航空機・その他輸送機械がマイナスに寄与している。
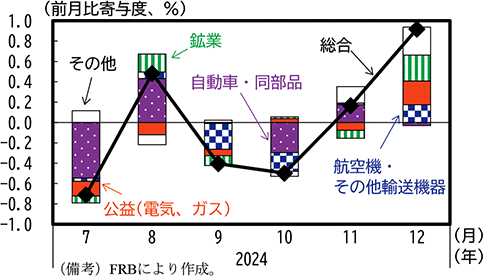
以降では、産業別の州別付加価値シェアの地図と熱帯低気圧(ハリケーン含む)の進路を重ね合わせることにより、2024年に上陸したハリケーンが生産に与えた影響を各月ごとに確認する(付図2-3参照)。
24年7月は、ハリケーン・ベリルがテキサス州に上陸し、同州の付加価値シェアが高い鉱業及び公益の生産に影響を及ぼしたと考えられる(付図2-3:図1、図2)。また、熱帯低気圧に変わった後も、自動車の付加価値シェアが比較的高いミシガン州及びインディアナ州周辺にまで到達したことにより、自動車・同部品の生産にも影響を及ぼしたと考えられる132(付図2-3:図3)。
24年8月にフロリダ州に上陸したハリケーン・デビーの被害額は、2024年にアメリカに上陸したハリケーンの中では比較的小さいが、公益の付加価値シェアが比較的高いフロリダ州を通過したことから、公益の生産に影響を及ぼしたと考えられる(付図2-3:図2)。
24年9月は、前述のとおりボーイング社でストライキが発生したことに加え、ヘリーンの上陸が生産に影響を与えた133。へリーンは、航空輸送の付加価値シェアが比較的高いフロリダ州及びジョージア州、自動車・同部品の付加価値シェアが比較的高いインディアナ州を通過したことから、24年9月の航空輸送及び自動車・同部品の生産に影響を及ぼしたと考えられる(付図2-3:図3、図4)。なお、24年10月17日にFRBが公表した24年9月の鉱工業生産指数のプレスリリースでは、ストライキとハリケーンが指数全体を▲0.6%下押ししたと試算されている。
24年10月は、ハリケーン・ミルトンが、航空輸送の付加価値シェアが比較的高いフロリダ州に上陸した(付図2-3:図4)。へリーン及びミルトンが、24年10月の航空機・その他輸送機器の生産に影響を及ぼしたと考えられる。
以上みてきたように、2024年7月以降、アメリカに上陸したハリケーンの影響により、航空機や鉱業等の生産が一定程度押し下げられたと考えられる。今後も、ハリケーン等の一時的要因が発生した場合には、鉱工業生産指数等の経済指標にどのように影響を与えたのか、注意深くみていく必要がある。
(ニューヨーク州は金融・保険の落ち込みから経済成長率が全米を下回る)
次に、人口・個人消費が全米4位、GDPが全米3位のニューヨーク州の産業構成をみると(第2-1-142図)、全米と比較し金融・保険の構成比が2割弱と高いことが特徴的である。また、全米と同様、製造業の中では特に化学工業の構成比が高い。
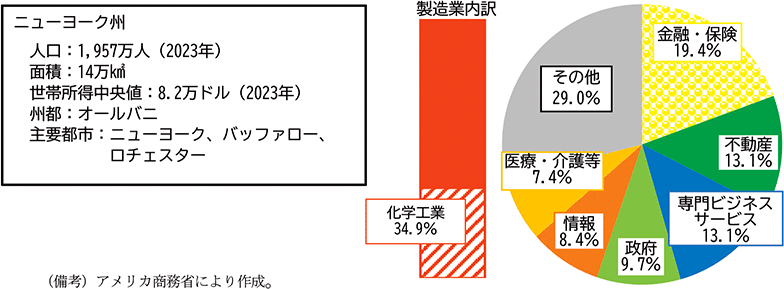
ニューヨーク州の感染症拡大以降の実質GDP成長率を産業別にみると(第2-1-143図)、2021年は専門ビジネスサービスや金融・保険が成長をけん引したものの、2022年以降は専門ビジネスサービスのプラス寄与が縮小する中、金融・保険がマイナス寄与した結果134、感染症拡大以降の実質GDPの伸びは全米の伸びを下回っている。
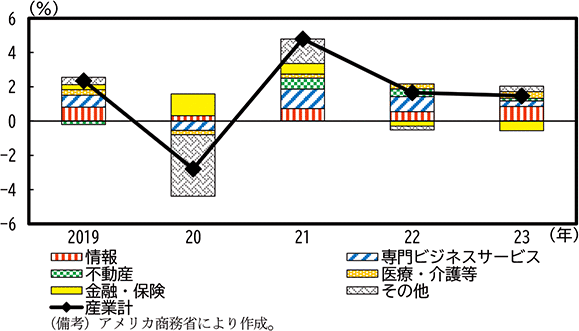
(人口上位4州が情報産業や専門サービス等を中心にアメリカの景気回復をけん引)
以上、みてきたとおり、人口上位4州を中心に、情報産業や専門サービス等の知識集約型の産業が大きく成長に寄与してきた。加えて、テキサス州やフロリダ州を中心に、人口増加に支えられ、不動産業等も成長に寄与してきた。こうした人口上位4州のけん引もあり、アメリカ全体としても、情報産業、専門ビジネスサービス、不動産業が感染症拡大後の経済成長をけん引してきた(第2-1-144図)。さらに、2024年後半はハリケーンによる一時的な影響を受けたものの、テキサス州では鉱業が感染症拡大後の成長をけん引してきた。こうした多様な産業が感染症拡大後のアメリカの景気回復を支えてきたことが分かる。
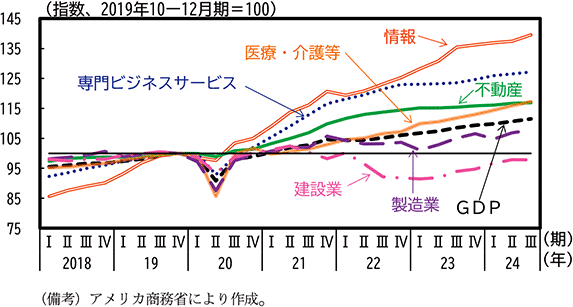
(いわゆる「ラストベルト」と呼ばれる州では、景気回復が遅れている)
人口上位4州が大きな付加価値を生み出して、感染症拡大後のアメリカの景気回復をけん引してきた一方で、いわゆる「ラストベルト」と呼ばれる州では景気回復が遅れている。ラストベルトは主として製鉄業等重厚長大型産業を基幹産業としており、1950年代以降衰退した地域とされることが多い135。ここでは、ラストベルトと呼ばれる州のうちミシガン州、ウィスコンシン州、ペンシルバニア州、オハイオ州の4州について確認する(以下、4州をまとめて「ラストベルト4州」という。)。
ラストベルト4州の感染症拡大後の実質GDPの推移を確認すると(第2-1-145図)、全米を下回る伸びとなっている。また、ラストベルト4州の人口の伸びは全米の伸びをいずれも下回っている(第2-1-146図)。
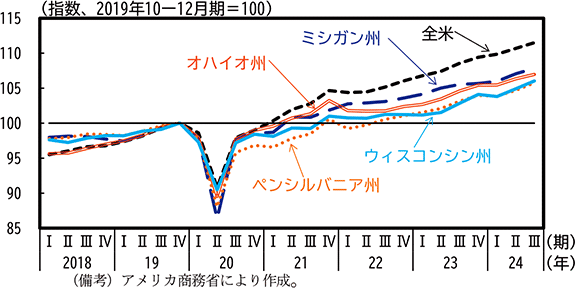
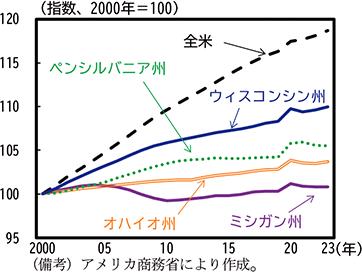
(ラストベルト4州では製造業の産業構成比が高く世帯所得中央値は全米を下回る)
以降、これらのラストベルト4州が景気回復が遅れている要因を考察する。ラストベルト4州の産業構成を確認すると、いずれの州も製造業の産業構成比が全米と比較して高いことが分かる(第2-1-147図、第2-1-148図、第2-1-149図、第2-1-150図)。
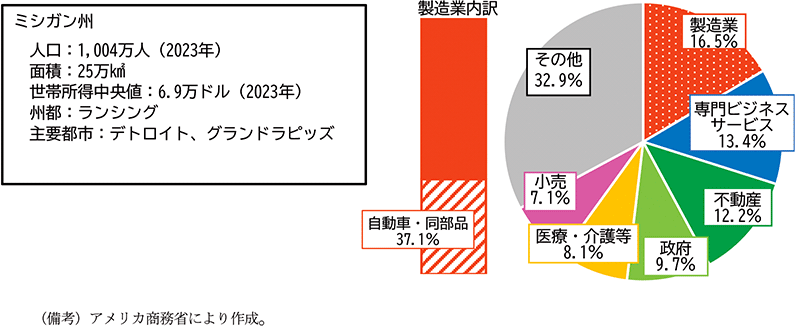
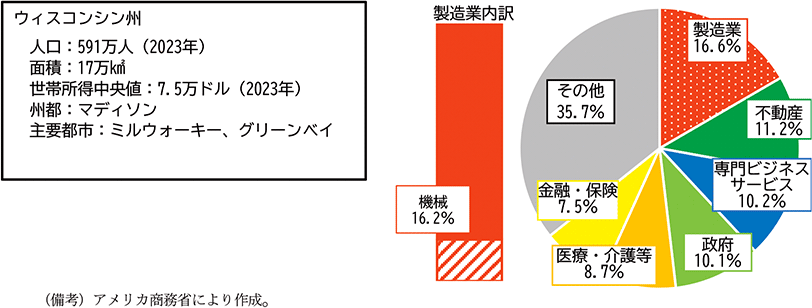
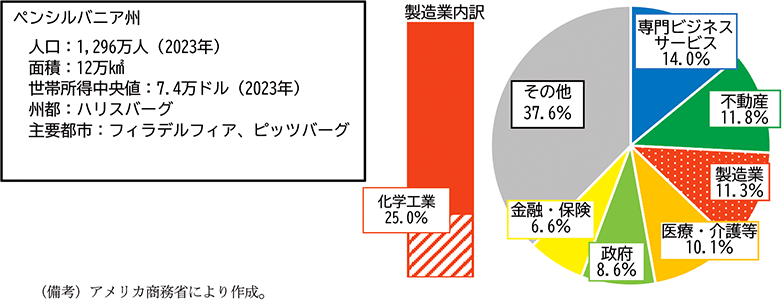
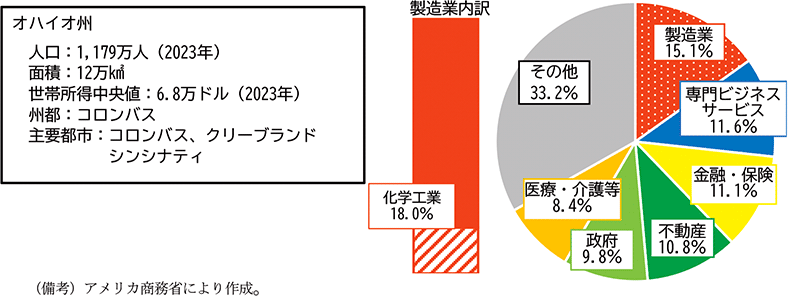
製造業従事者比率を州別にみても(第2-1-151図)、ラストベルト4州では製造業従事者比率が高く、製造業を中心の産業構成となっていることがうかがえる。
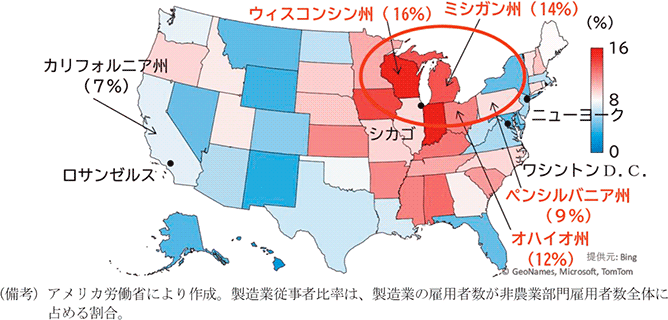
また、ラストベルト4州の世帯所得中央値をみると、1969年、2000年は全米を上回っていたものの、2023年は全米を下回っている(第2-1-152図)。
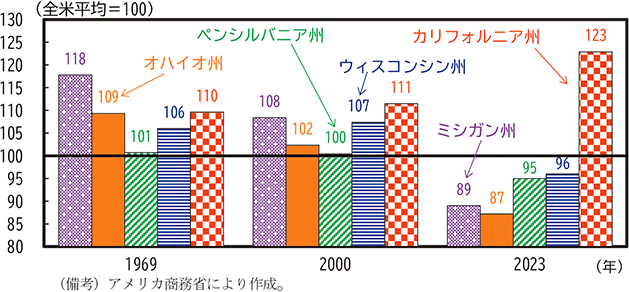
(ラストベルト4州では製造業の労働生産性の伸びが低い)
ここで、製造業の労働生産性をみると(第2-1-153図)、ラストベルト4州は全米と比べて、製造業の労働生産性の伸びが小さいことが分かる。一方、製造業従事者比率の推移をみると(第2-1-154図)、ラストベルト4州ともに全米よりも高く、2010年以降、おおむね横ばいで推移している。労働生産性の伸びが低い製造業の企業が多いことや、それに従事する労働者が多いことが、ラストベルト4州の実質GDPの伸びの低さにつながっている。
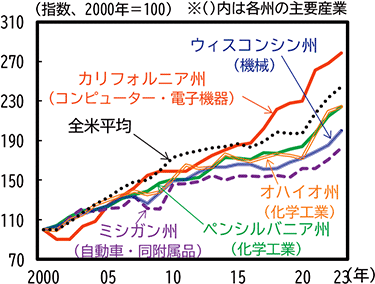
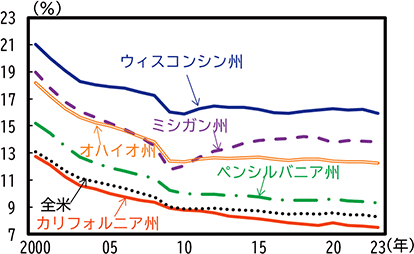
(備考)アメリカ商務省、アメリカ労働省により作成。製造業の労働生産性は、製造業の付加価値額を製造業の非農業部門雇用者数で除して算出。()内は2023年における各州製造業のうち付加価値額が最大の産業を記載している。製造業従事者比率は、製造業の雇用者数が非農業部門雇用者数全体に占める割合。
(ラストベルト4州では外国生まれの人口比率が低く、高齢化率が高い)
ラストベルト4州において、製造業の労働生産性の伸びが低いにも関わらず、製造業従事者比率が低下しない背景の一つとして、人口構成が挙げられる。
総人口に占める外国生まれの者の人口比率を州別に確認すると(第2-1-155図)、人口上位4州では外国生まれの人口比率が高い一方で、ラストベルト4州では外国人生まれの人口比率が低い。
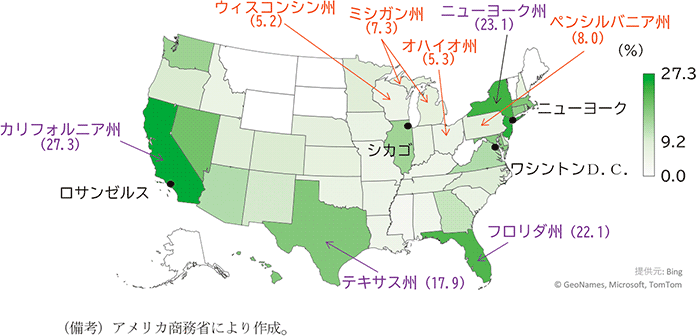
より詳細に、人種別学歴別の人口割合をみると(第2-1-156図)、ラストベルト4州では白人の大卒未満の割合が全米よりも高い。また、高齢化率についても、全米を上回っている。
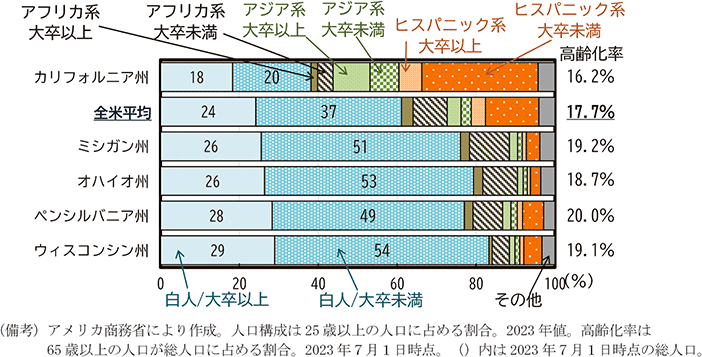
製造業の労働生産性が低い場合、より労働生産性が高い産業に労働者が移動することにより、州全体の労働生産性を高めることができる。ただし、高齢化率が高く、また、学歴別の人口割合に偏りがみられるラストベルト4州では、産業間の労働移動や知識集約型の労働生産性の高い産業を振興することが容易ではないと考えられる。こうした構造的な要因が、情報産業や専門サービス等の知識集約型の産業を中心に大きな付加価値を生み出している人口上位4州との経済成長の差につながっている可能性がある。

