1.国ごとにばらついているヨーロッパ経済
(1)ヨーロッパ経済の現状
ヨーロッパ経済全体は、2008年9月の世界金融危機による景気後退の深刻化により、実質経済成長率のマイナス幅が拡大し、09年1~3月期にユーロ圏では前期比年率▲10.2%を記録した。しかし、09年7~9月期からユーロ圏全体の実質経済成長率はプラスに転じ、8四半期連続のプラス成長となっている。しかしながら、各国ごとの経済状況をみると、国ごとにばらついている。
まず、実質経済成長率について、ユーロ圏全体が大きく落ち込んだ09年1~3月期と11年4~6月期の伸び率を比較すると、ドイツ、フィンランド、オーストリア等では大きく回復している。一方で、ギリシャやポルトガル等では、11年4~6月期の実質GDPが依然として09年1~3月期の水準に達しておらず、回復が遅れている。
次に失業率についてみると、実質GDPの回復が遅れているギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペインでは10%以上の高水準となっており、実質GDPの回復が遅れている国ほど失業率が高いという相関がみられる(第2-1-1図(1))。
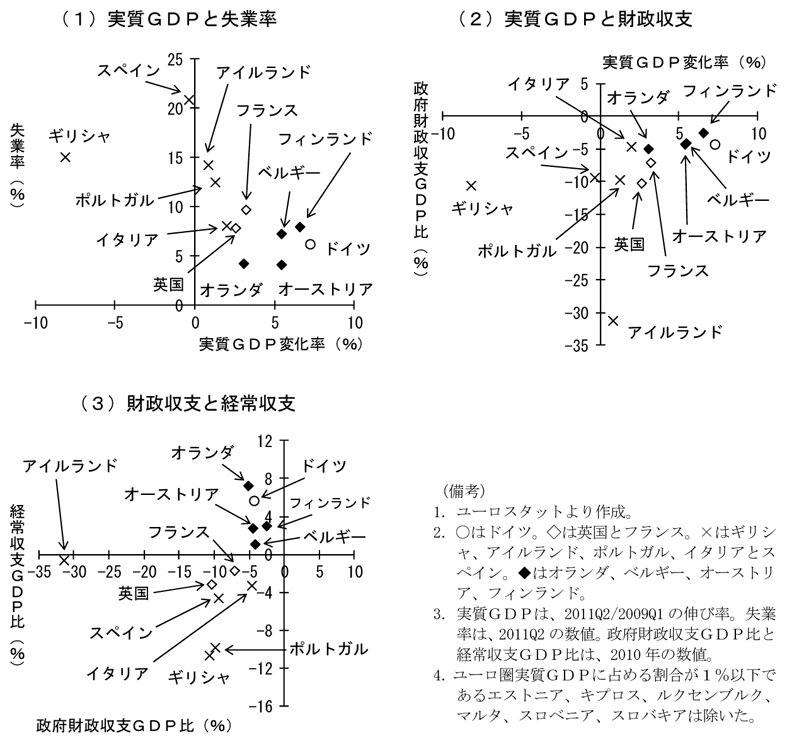
また、10年の一般政府財政赤字GDP比をみると、実質GDPが大きく回復しているドイツやフィンランド等では、安定成長協定1の基準である3%の近傍にあるなど財政状況は比較的良好な水準まで戻っている。これに対し、実質GDPの回復が遅れているアイルランドでは財政赤字GDP比は30%を超え、ギリシャ、スペイン、ポルトガル等でも10%前後にあるなど、安定成長協定の水準を依然大きく上回る状況に陥っている。このことから実質GDPの回復に見られる経済状況の改善が遅いほど、財政状況の改善が順調に進んでいないという関係が伺われる。(第2-1-1図(2))。
最後に、財政収支と経常収支の関係をみると、ドイツやフィンランド、オランダ等経常収支が黒字の国々では財政赤字GDP比が低い。これに対し、ギリシャやポルトガルは経常収支赤字、財政赤字とも高水準であり、スペインやイタリア、英国、フランスも双子の赤字となっていることがわかる。経常収支が赤字となることは、対外的な資金流入に依存せざるを得ないことを意味し、財政赤字幅が大きいことは今後採り得る財政政策の自由度が狭いことを意味するため、これら双子の赤字国は対内、対外の両面において持続可能性の点で脆弱な構造となっていることが推察される(第2-1-1図(3))。
以上のようにヨーロッパ経済は国ごとにばらつきがみられるが、以下では(1)急速な景気回復を示したドイツ、(2)ドイツに次いで経済規模が大きいが景気が足踏みしている英国とフランス、(3)景気が低迷し財政状況の悪化が続いている南欧諸国等に大きく3つのグループに分類して、その経済構造等の特徴を分析する。
(2)輸出主導で回復を遂げる経済大国ドイツ
(i)急速な景気回復を示したドイツ経済
ヨーロッパにおける最大の経済大国であるドイツは、08年の世界金融危機の発生後、輸出主導により景気後退を脱すると、好調な輸出が個人消費や投資等の内需に波及することで自律的な景気回復をいち早く達成している。世界金融危機直前にあたる08年7~9月の各国の実質GDPの水準を基準としてその後の推移をみると、他の主要国であるフランス、英国、イタリアと比べて、ドイツは危機直後最も大きく低下したが、その後最も速いテンポで回復を示しており、11年に入ると他国に先駆けて危機前水準を上回っていることがわかる(第2-1-2図)。
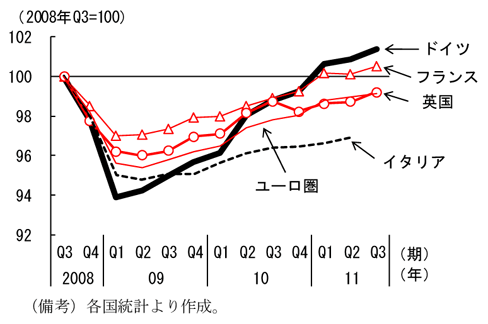
以下では、自律的な景気回復を達成しているドイツ経済の実態について詳細にみていく。
(ii)ドイツを巡る輸出環境の優位性
これまでドイツの景気が自律的な回復をみせてきた要因の一つとして、そのけん引役である輸出への依存度の高さが挙げられる。ヨーロッパ主要国の輸出依存度2を比較してみると、ドイツ以外の4か国では1996~2000年、01~05年、06~10年平均に大きな差はみられないものの、ドイツでは各々10%程度の顕著な上昇がみられ、10年には50%を上回った(第2-1-3図)。
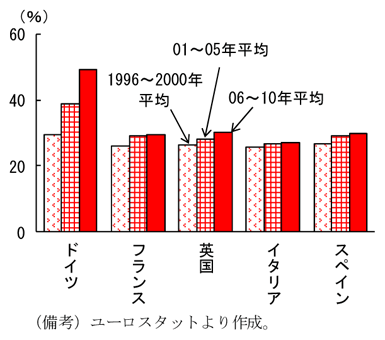
ドイツの輸出依存度が2010年までの10年間で他の主要国より大幅に上昇した背景の一つとして、域内共通通貨のユーロの導入3がドイツにとって優位な輸出環境をもたらしたことが考えられる。ユーロ導入前はドイツ国内が好景気になるとマルクが増価し輸出競争力の低下につながったが、ユーロ導入によりドイツのユーロ圏域内向け輸出が為替変動リスクから免れ国内価格水準がストレートに域内での価格競争力に反映されるようになった。さらにユーロはドイツだけでなく導入国全体の経済状況を反映して変動するため、仮にドイツ経済による為替増価要因があったとしてもそれが必ずしもユーロの増価に直結せず、ユーロ圏域外向け輸出の面で結果としてドイツの輸出産業にとって恩恵的な為替水準がもたらされた可能性があったとみられる。
そこで、ドイツのユーロ圏域内向け価格競争力指数をみると、ユーロが導入された99年以降、一貫して低下しており、価格競争に優位な状況が続いてきたことがみてとれる(第2-1-4図)。また、ドイツのユーロ圏外に対する価格競争力をみるために、ユーロの実質実効為替レートをみると、ユーロ導入直後に大きく減価した後、03年以降導入時の水準を上回って推移している。しかし、09年後半以降、ギリシャを始めとした南欧諸国等の債務問題の顕在化も背景に加わりユーロの減価が急速に進んでおり、ドイツにユーロ圏域外への輸出についても価格競争力の面で有利な環境が再びもたらされている(第2-1-5図)。
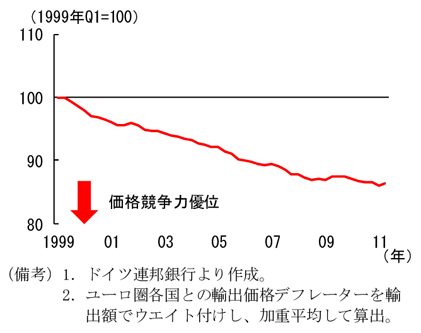
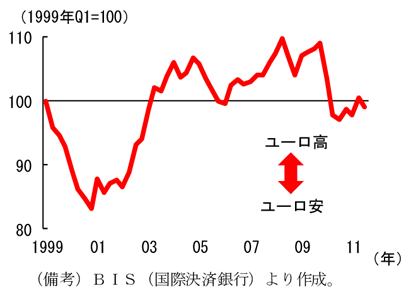
ちなみに10年の地域別輸出動向をみると、ユーロ圏向けは持ち直しに力強さを欠き、前年のマイナスの落ち込みを取り戻せていない一方、アジア向けが顕著に増加している(第2-1-6図(1))。さらに、アジア向けの内訳をみると、世界金融危機の影響が比較的軽微で内需の拡大が著しい中国向けが特に大きく寄与している。このことから10年以降のドイツの輸出は、ユーロ安に加え中国を中心とするアジア諸国の旺盛な需要が追い風となっていることが推測される(第2-1-6図(2))。
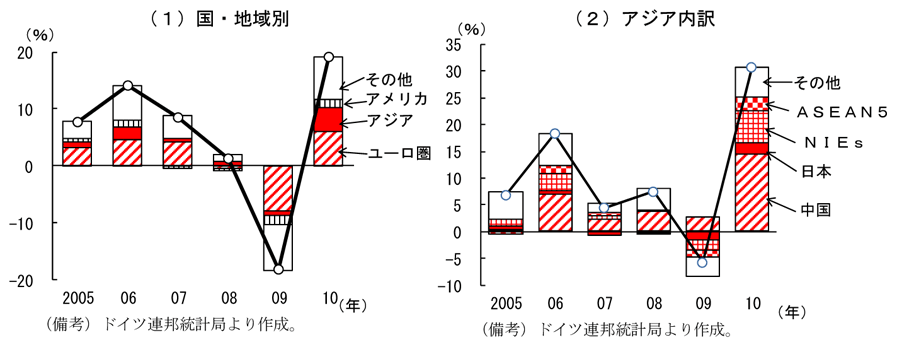
ユーロ導入を機に、ユーロ圏内での価格競争力を優位にし、ユーロ圏外に対して導入以前よりも通貨安の恩恵を受けやすい環境下で輸出を増加させていったドイツは、ユーロ導入期の99年~02年にかけて貿易収支黒字が倍増し、2000年まで赤字が続いていた経常収支は2001年以降黒字が常態化している(第2-1-7図)。
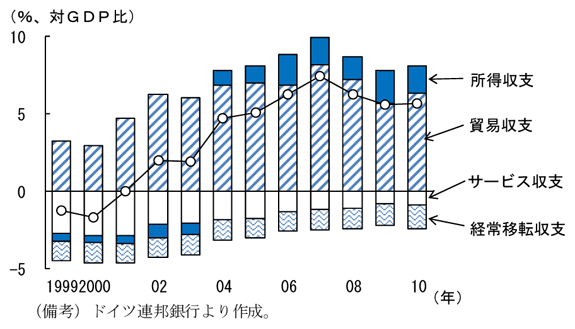
(iii)ドイツ製造業の高い国際競争力の背景
ドイツの輸出依存度がユーロ導入以降他の主要国よりも大幅に高い水準にまで上昇した背景には、前述のユーロ導入によるドイツ産業全体にわたる輸出環境の優位性が挙げられるが、個別にみても特に国際的に競争力のある産業や企業の存在を指摘することができる。ドイツ製造業の企業売上高をみると、売上高全体に占める10年の国外売上シェアは46.3%を占めている。国内・国外別の売上高を業種別にみると、売上高の高い「自動車」、「一般機械」、「化学・医薬品」で約6割、「電子部品」、「電子機械」でも約5割を国外売上高が占めており、「自動車」、「一般機械」はユーロ圏外の売上高がユーロ圏内売上高の2倍となっている。また、05年から10年への売上増加額のうち、「自動車」で約90%、「一般機械」、「化学・医薬品」、「電子部品」で約80%が国外売上高となっており、「自動車」及び「一般機械」の国外売上高増加額は7割以上がユーロ圏外での売上げとなっている(第2-1-8図)。
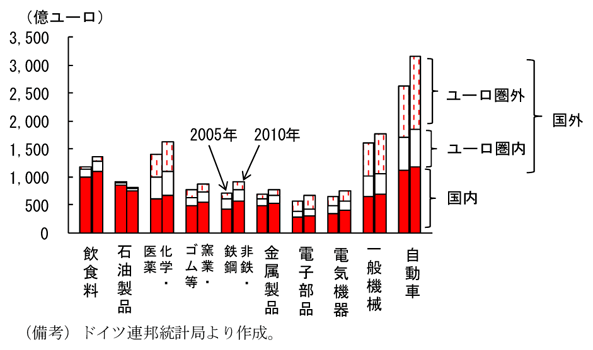
製造業のうち国際競争力のある業種を明らかにするため、業種別の競争力係数4をみると、自動車、一般機械、電気機器、金属製品、窯業・ゴム等、化学・医薬といった幅広い業種でユーロ圏内、圏外の双方に対し競争力を持っていることがわかる(第2-1-9図)。特に、ユーロ圏外向け売上高の大きかった「自動車」や「一般機械」はユーロ圏外向け競争力係数も突出しており、これらはユーロ圏外に対しても高い競争力を保持しているものと考えられる。
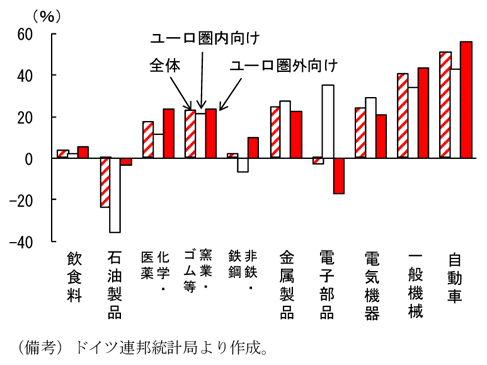
そこで、自動車を例に10年の輸出動向を輸出先別にみると、09年から10年にかけて、ユーロ圏内向けがほとんど伸びなかった中で、世界金融危機後の大規模な景気刺激策に支えられた中国をはじめ、北米や日本、韓国向け等、ユーロ圏外向けが増加している(第2-1-10図)。実際に主な国・地域の新車販売市場におけるドイツブランド車のシェアをみると、EU、アメリカ、日本、ロシアの市場でシェアの拡大がみられる(第2-1-11図)。中国市場でのシェアはほぼ横ばいだが、09年以降中国の新車販売市場そのものが大きく拡大(分母が大きく増加)しており、09、10年の中国市場におけるドイツブランド車の販売台数は3~4割の増加が続いている。世界金融危機後、景気刺激策として各国政府が相次いで実施した新車買換え支援策は、国際競争力が高く、世界的なブランドメーカーを擁するドイツ自動車産業の追い風になったといえる。
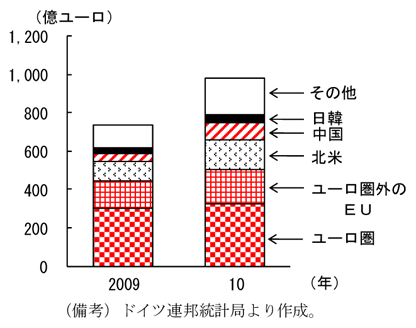
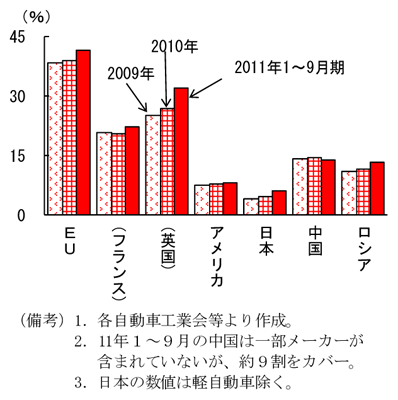
国際市場での価格競争力を規定する要因として、前述の為替レートの要因に加え、労働コストと労働生産性の関係が重要となる。2000年以降のドイツ製造業の単位労働コスト(ULC)をみると、世界金融危機直後頃を例外として労働生産性の上昇率が労働コストの上昇率を上回る局面が相対的に長く、このことは労働生産性の上昇が労働コストの上昇を吸収するために価格競争力がコスト上昇でも失われにくい生産構造が定着していることを表しているとみられる(第2-1-12図)。
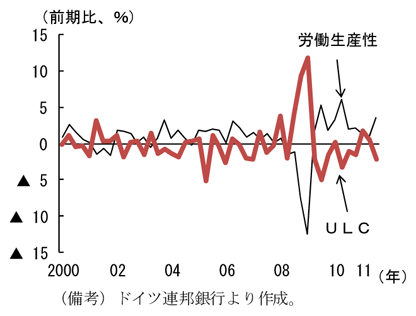
このようにドイツの製造業は、ユーロ導入による輸出環境の優位性が保たれる中で、従来から国際競争力が強い業種や企業の存在、コスト面で優位な生産構造、更に世界金融危機後に世界各国で実施された景気支援策等の効果が重なり、輸出を増加させたことが10年後半からの急速な景気回復につながったと評価することができる。
(iv)収益力が高いドイツ企業
世界金融危機による急速な景気後退を背景としてヨーロッパ主要国の企業の営業余剰は08年、09年に大幅に落ち込んだ。英国やフランスでも営業余剰の落ち込みはみられたが、特にドイツでは07年から09年にかけて対GDP比で3%ポイントの低下と他の主要国に比べ大幅な減少となっている。これはドイツでは輸出に依存する企業が多いため、欧米を中心した需要の収縮により輸出が激減した影響をより受けやすく、企業の収益環境が急激に悪化したことを示している。しかし、10年にはいずれの国でも営業余剰が増加する中、特に輸出主導で回復を示しているドイツでも収益環境は最悪期を脱しているとみられる。
こうした変動がある中でも、ドイツの営業余剰(対GDP比)は2000年以降、最悪期を含めても一貫して英国やフランスの水準を上回っており、ドイツ企業は輸出の変動による影響を強く受けつつも高い収益水準を確保してきたと考えられる。
また、総資産利益率(営業利益÷総資産。以下「ROA」という。)をみると、ドイツ(全産業ベース)は5.7%となっており、オーストリア(6.4%)には劣るものの、フランス(5.6%)や英国(5.3%)を上回っている(第2-1-14図)。製造業に限ればドイツのROAは6.7%であり、オーストリアを抜いてヨーロッパ主要国の中では最も高い。ドイツの企業は、他国の企業よりも資産を効率的に利益に結びつけているとみられる。
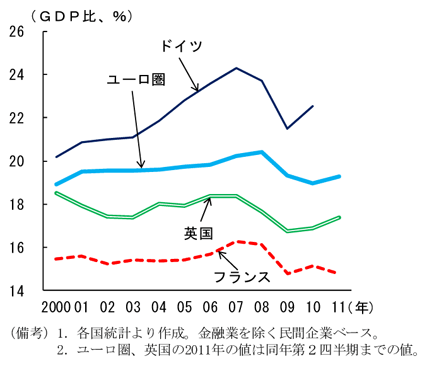
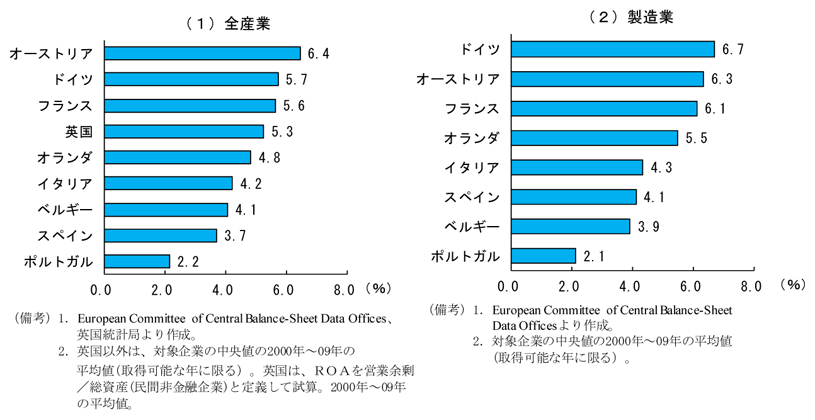
一方、負債面に注目すると、ドイツ企業の債務残高は10年時点で営業余剰の2倍程度と英国やフランスと比較すれば低水準にとどまっている(第2-1-15図)。民間企業の債務残高の営業余剰に対する比率の高さでみると、ドイツ企業のバランスシート調整圧力は比較的軽微であると考えられる。バランスシート調整圧力が強ければ、収益が改善しても企業は投資を行わず、負債圧縮を優先的に行う可能性が高い。ドイツ企業は、他国の企業と比べれば利益を借金返済に回す度合いは小さく、設備投資が増加しやすい環境にあったことが示唆される。
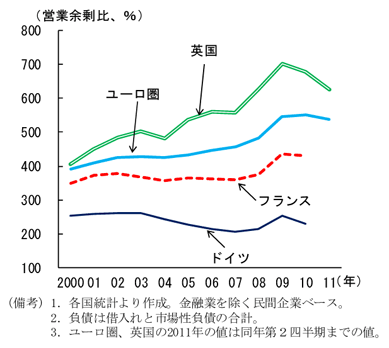
(v)労働市場の柔軟化を進めたドイツの改革
第二次大戦後のドイツの労働市場は、解雇規制等の雇用保護に重点を置いた労働政策と、失業者を福祉面から手厚く保護する社会政策とによって硬直化し(後述コラム2-1参照)、失業率は景気情勢による変動を繰り返しながら、総じて高まる傾向をみせていた。しかし、2000年代前半の労働市場改革を機に労働市場の柔軟化が進み、世界金融危機後の戦後最悪の景気後退以降、ドイツの失業率だけが09年後半から低下を続け、11年4月以降は東西ドイツ統一後の最低水準を更新している状況にある(第2-1-16図)。
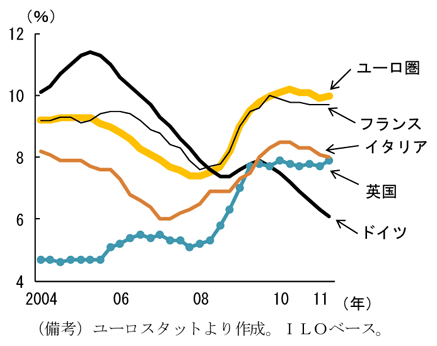
以下では、かつて硬直的であったドイツの労働市場において、2000年代前半の労働市場改革がどのような成果をもたらし、11年4月以降、失業率が東西ドイツ統一後の最低水準を更新する状況に至ったのかを明らかにする。
(ア)ハルツ委員会報告等に基づく労働市場改革
02年、シュレーダー政権より労働市場改革案の策定を諮問されたフォルクスワーゲン人事担当取締役のペーター・ハルツ氏を委員長とする諮問委員会(以下、「ハルツ委員会」)は、同年8月に労働市場政策全般に係る改革を提案する報告書を提出した。この報告書に基づき「労働市場の現代的サービスのための第I法~第IV法」(以下、「ハルツ第I法~第IV法」)の4つの法律が制定され、03年から05年にかけて施行された。また、03年12月には労働市場改革法5も施行された。
ハルツ委員会報告等に基づく一連の労働市場改革の特徴は、大きく3つのポイントに整理できる。
1つ目は、失業給付制度の改革である。それまで重複支給等が問題となっていた従来の「失業扶助6」と「社会扶助7」の一部を統合した「失業給付II」の創設や、失業給付期間の短縮8等により、連邦・地方政府の財政負担が軽減されるとともに、失業者が就労意欲を低下させる「失業の罠(Unemployment Trap)9」に陥る状況は大きく改善された。
2つ目は、職業紹介、就労支援体制の強化である。1)連邦雇用庁の連邦雇用エージェンシーへの改組等の組織改革や、2)従来「社会扶助」を受給していた者のうち就労可能な者の失業登録の義務化、3)民間の人材派遣会社等を活用した人的サービス機関(PSA)の設置等により、就労の履行を強く要請するための組織・制度改正が図られ、求職者に対して自助努力を促しつつ就労支援を強化する体制が整えられた。
3つ目は、労働市場の柔軟化である。ミニジョブ・ミディジョブの導入10や解雇制限法の改正11等の規制緩和により、未熟練労働や単純労働を活用出来る労働市場が広げられ、雇用形態の多様化や就労機会を拡大させる条件が整えられた。
こうしてドイツの労働市場政策を手厚い社会保障から就労促進へと転換させる仕組みが整備された。
(イ)労働市場改革後の雇用情勢
労働市場改革の成果として、まず、労働市場の硬直性改善度を長期失業者の動向からみると、労働力人口に占める長期失業者の割合は05年頃をピークに大きく低下し、11年第4~6月期には2.9%と、統計で遡及可能な1993年以降の最低水準となっている(第2-1-17図)。また、失業率もハルツ第IV法が施行された05年をピークに低下を続け、09年には世界金融危機の影響で僅かに上昇したものの、その後の景気回復も相まって11年4月以降、東西ドイツ統一後の最低水準を更新しており、雇用情勢は着実に改善している(第2-1-18図)。
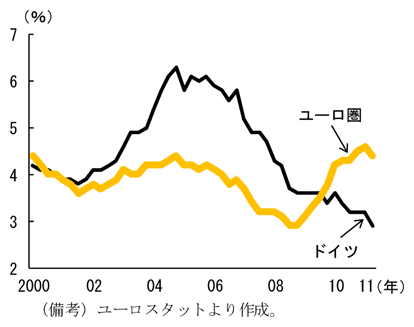
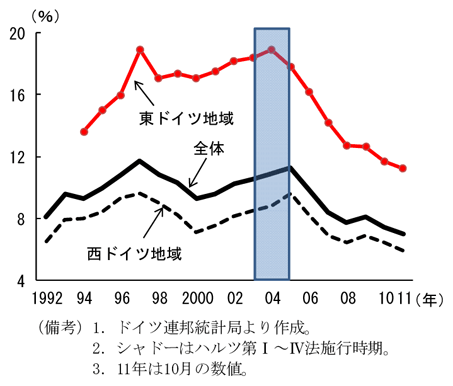
次に失業給付受給の状況をみると、これまで170万人を下回ることがなかった「失業給付I12」の受給者は、ハルツ第IV法が施行された05年以降大きく低下し、10年に102万人となった(第2-1-19図)。「失業扶助」と「社会扶助」の一部が統合された「失業給付II」は、従来「社会扶助」を受給していた者のうち就労可能な者については新たに失業登録が義務付けられたこともあり、05年から06年にかけて増加したものの、10年には489万人まで低下している。政府の労働政策への歳出状況をみると、09年は世界金融危機の影響で増加しているものの、05年から08年にかけては前年比マイナスが続き、連邦・地方政府の財政負担が軽減している(第2-1-20図)。
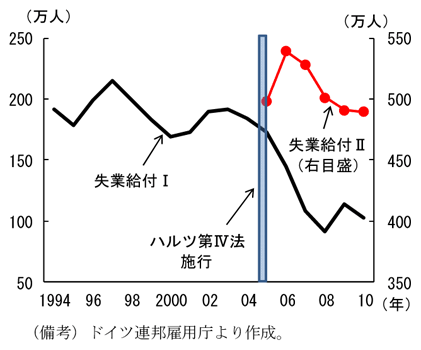
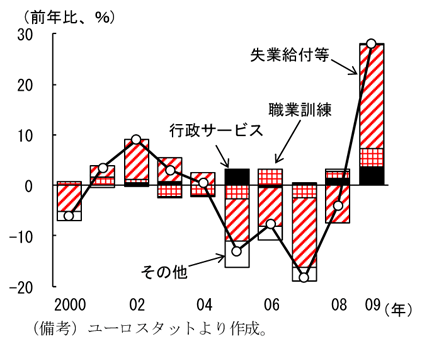
(ウ)世界金融危機による景気後退期の雇用喪失緩和
2011年4月以降、ドイツの失業率が東西ドイツ統一後の最低水準を更新している要因としては、03~05年に実施された一連の労働市場改革の成果に加えて、「労働時間貯蓄制度13」や「操業短縮手当制度14」の活用により、操業時間を短縮してワークシェアを行うことで雇用を維持し、世界金融危機後の失業者増加を最小限に抑えたことも挙げられる(第2-1-21図、第2-1-22図)。労働時間貯蓄制度によって、労働者は勤務時間を柔軟に設定することが可能になり、それがワークライフバランスに資する一方、企業側としては労働需要の短期的な変動にコストをかけず対応することが可能となった。また、連邦政府が景気対策の柱として制度の拡充15を行った操業短縮手当制度によって、企業は操業短縮が比較的容易になった。こうした制度の存在が急激な景気後退による操業時間の短縮等のショック緩和に役立ち、フランスや英国で失業率が2%ポイント程度の顕著な高まりをみせ、それぞれ10%近傍、9%前後へ悪化したのとは対照的に、ドイツのそれは0.5%ポイント程度の高まり、8%台前半への上昇にとどまった。
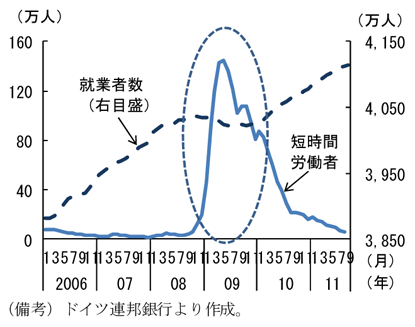
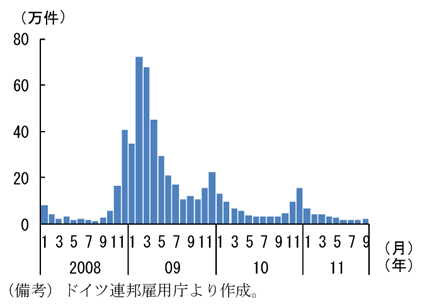
以上のように、ドイツの労働市場は、一連の労働市場改革により柔軟化が進展し、05年以降の雇用情勢は大きく改善している。また、戦後最悪の景気後退期において操業短縮手当等の制度を活用することで雇用喪失を緩和し、熟練労働力や技能労働力といった人的資本を維持できたことは、景気回復期に入ってからの人材需要に即応できることを意味しており、10年後半からのドイツの急速な景気回復に寄与したものと考えられる。
(vi)バランスシート調整圧力が小さいドイツの家計
ドイツの家計部門に特徴的な点として、家計貯蓄率が英国よりもかなり高く、フランスと並んで高水準であることが挙げられる(第2-1-23図)。高い貯蓄率は、所得のうち消費に回る割合(消費性向)が低いことを意味し、それだけをみれば景気にとって必ずしもプラスではない。しかし、貯蓄率が高く家計が金融資産を蓄積していれば、所得が突然減少しても貯蓄の取り崩しで消費を平準化できるというメリットもある。世界金融危機後にはドイツの家計の所得環境も悪化したが、他国よりも個人消費の落ち込みが限定的だったのは、こうした要因も影響したとみられる16。
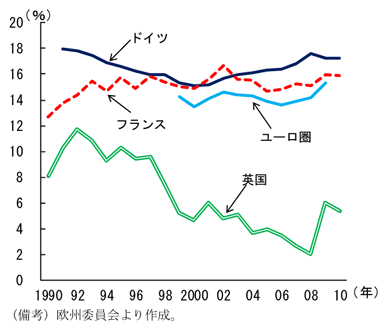
また、ドイツの家計の債務残高は一貫して低下傾向をたどっている(第2-1-24図)。ドイツでは2000年代に住宅バブルが発生しなかったため家計債務が積み上がらず、バランスシート調整圧力は高まっていないとみられる。そうした背景もあり、政策による後押しを追い風に危機後の個人消費は増加基調となっていると考えられる17。
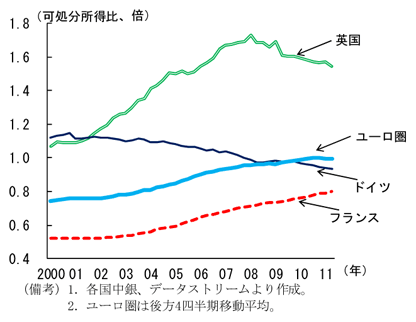
(vii)景気回復に減速感がみられるドイツ経済
世界金融危機後、10年後半から11年1~3月期まで自律的な回復を見せていたドイツ経済は、同年4~6月期の実質経済成長率が前期比年率1.1%、7~9月期が同2.0%と1~3月期の同5.5%から上昇率を大幅に低下させ、景気回復のテンポが緩やかになっている(第2-1-25図)。
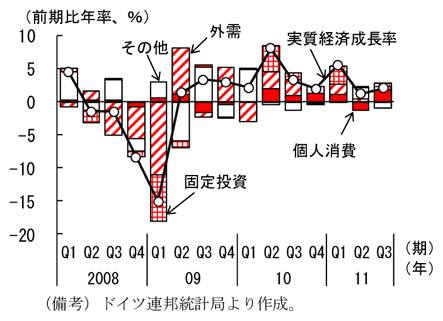
11年4~6月期以降の実質経済成長率が鈍化した要因としては、個人消費と外需の弱さが挙げられる。
ドイツの可処分所得は、11年に入り物価の上昇幅が拡大していることもあり、同年1~6月期の実質値は前期比マイナスが続いた(第2-1-26図)。こうした家計の所得環境の悪化傾向を背景に、4~6月期の個人消費は前期比年率▲2.4%と5四半期ぶりのマイナスとなり、総じて弱い動きとなった。なお、7~9月期は前期の反動等もあり同3.3%となっているが、消費マインドはユーロ圏のソブリン問題再燃による経済情勢見通し等の悪化により、8月以降悪化傾向にある(第2-1-27図)。
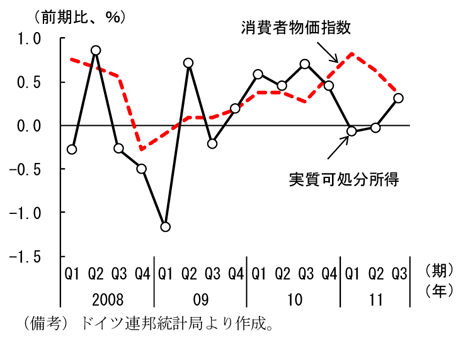
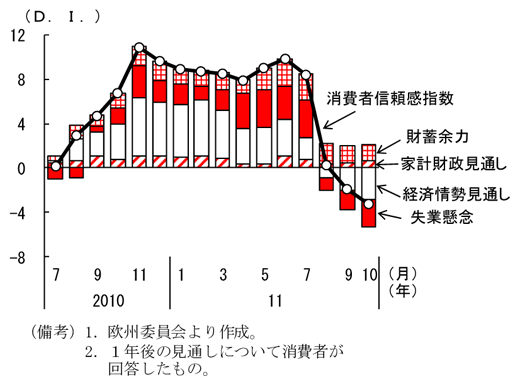
外需についてみると、11年4~6月期以降も輸出は大量の受注残に支えられ依然堅調な増加を続けているが、同時期に電子機器や金属製品等の業種で輸入が増加し、全体として外需を押し下げる方向に作用している(第2-1-28図)。
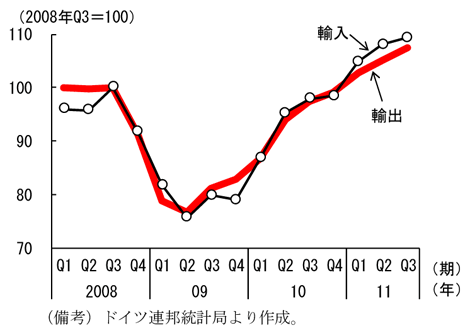
企業部門をみると、原油価格の高騰による輸入物価の上昇を受け、交易条件が悪化しており、11年以降の交易損失は大幅に拡大し、150億ユーロ近傍で推移している。こうした収益環境の悪化によって企業の営業余剰も11年に入り伸び悩んでいる(第2-1-29図)。生産活動についても、8月以降受注状況の低下により弱い動きとなってきている。
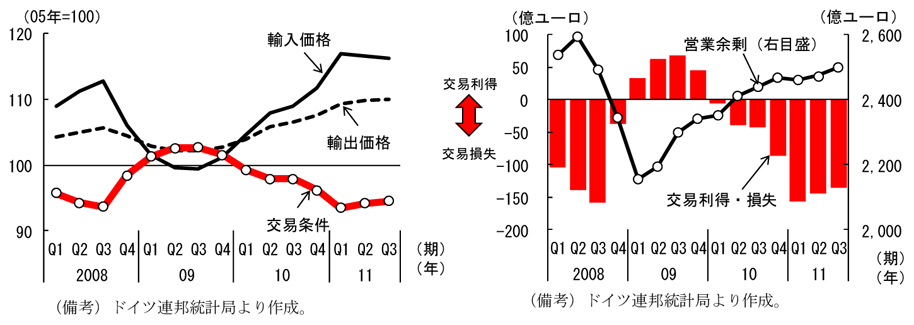
09年以降、一貫して低下を続けてきた失業率にみられた雇用の改善状況についても変化の兆しが表れている。失業率が11年6月以降横ばいとなっていることに加え、企業の雇用見通しDI、個人の失業懸念DIにも悪化傾向がみられ、雇用の先行きに慎重な見方が広がっている(前掲第2-1-18図)。
これまで輸出主導で急速な回復を遂げてきたドイツ経済であるが、他のヨーロッパ主要国同様、世界的な景気の下振れ懸念に巻き込まれており、不透明感を増しているといえる。
コラム2-1:かつて硬直的であったドイツの労働市場と労働市場改革
(ア)東西統一ドイツ以前からの制度問題
西ドイツ時代の厳格な解雇規制や手厚い社会保障制度は、硬直的な労働市場を形成する要因となっていた。1951年に制定された「解雇制限法」は、労働者の安易な解雇を阻止する内容となっており、後に強い解雇規制が新たな雇用創出の弊害になっていると指摘されることになった(注1)。また、69年に制定された「雇用促進法」では、社会保険方式による「失業給付」と、失業給付の受給期間終了者を主たる対象とした「失業扶助(注2)」が定められ、当初は離職前の賃金に連動した給付額が無期限で支給されていた(注3)。しかし、これらは地方自治体が管轄していた「社会扶助(日本の生活保護に相当)」と、受給要件等の制度上の区別が曖昧であり、重複して受給する者も少なくなかった。こうした制度上の問題は、いわゆる「失業の罠(Unemployment Trap)(注4)」に陥りやすい状況を作り、失業者の就業意欲の低下を招いた。
(イ)東西ドイツ統一後の労働市場政策
旧西ドイツの制度を引き継いだ統一後のドイツは、旧東ドイツからの大幅な需要増を主因に高成長を遂げたが、旧東ドイツからの需要一巡により設備投資がストック調整局面に入ったことなどから景気が後退し、失業率は97年に統一後の最高水準に近い11%後半まで高まった。こうした状況を受け、雇用創出措置(注5)等の積極的な雇用促進政策や自治体による「就労扶助」の強化(注6)等が実施された。失業率は景気回復もあって緩やかな足取りで9%前半まで低下したものの、2001年半ばを底に再び上昇へ転じ、これらの取組も抜本的な雇用情勢の改善には至らなかった。さらに、失業の長期化とともに社会保障制度を支える財政負担の増大が続き、ドイツ経済や連邦・地方政府の財政状況に重くのしかかっていった。
(ウ)シュレーダー政権下の労働市場改革
1998年9月の選挙で政権交代を果たしたシュレーダー連立政権は、前政権で中断していた「雇用のための同盟(注7)」を早々に立ち上げ、雇用情勢改善へ向けた対話、協議を精力的に進め、若年失業者への対策(注8)等を実施した。こうした政権の取組に加え、景気回復もあいまって、2000年の失業者数は大台である400万人を下回り、失業率も緩やかな低下がみられた。しかし、01年半ばのITバブル崩壊に伴う世界経済の後退懸念が顕在化し、ドイツの景気回復にも減速がみられ、02年に入り、失業者数は再び400万人を上回った(注9)。そうした中、02年2月、公共職業安定所で職業紹介の実績が水増しされていたことが発覚し、あわせて「失業扶助」と「社会扶助」の重複支給の問題や職業紹介行政の非効率に対する批判等も噴出した。
こうした状況を受け、シュレーダー政権はハルツ委員会(注10)に連邦雇用庁の組織改革と労働市場政策を抜本的に見直すための改革案の策定を諮問した。就労促進により失業者を半減させることを目標に議論を重ねたハルツ委員会は、02年8月に労働市場政策全般に係る改革を提案する報告書を提出した。この報告書に基づき「ハルツ第I法~第IV法」が制定され、03年から05年にかけて施行された。また、2003年12月には労働市場改革法が施行された。こうして、手厚い社会保障や厳格な解雇規制等により硬直的であったドイツ労働市場の柔軟化が進められる仕組みが整備された(表1)。
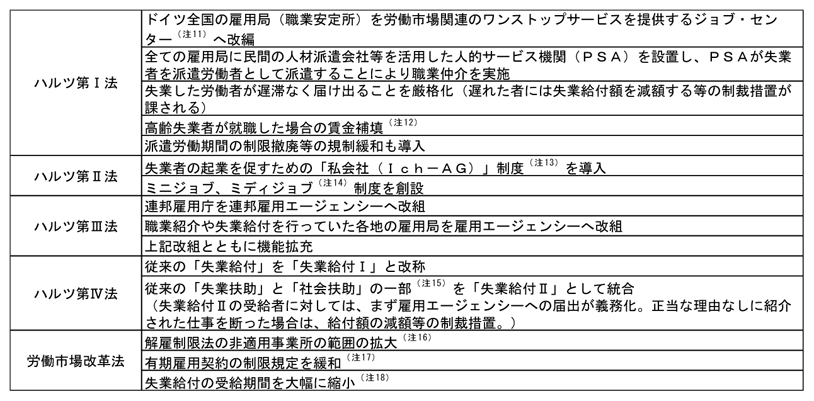
(3)景気が足踏み状態にある英国とフランス
ここでは、ドイツに次ぐ経済規模を誇る英国とフランスの動向について、両国を対比させながらみていく。
英国の実質GDP成長率は、11年7~9月期に前期比年率+2.1%となった(第2-1-30図)。同年4~6月期(同+0.4%)より伸びは高まったが、特殊要因のはく落による押上げを除けばおおむね横ばいにとどまるとみられ、景気は足踏みを続けている18。フランスにおいては、11年4~6月期の実質GDP成長率が前期比年率▲0.2%と9四半期ぶりに減少した後、同年7~9月期(同+1.6%)に増加したが、同年1~3月期(同+3.8%)と比して減速感が鮮明で、景気は足踏み状態となっている。
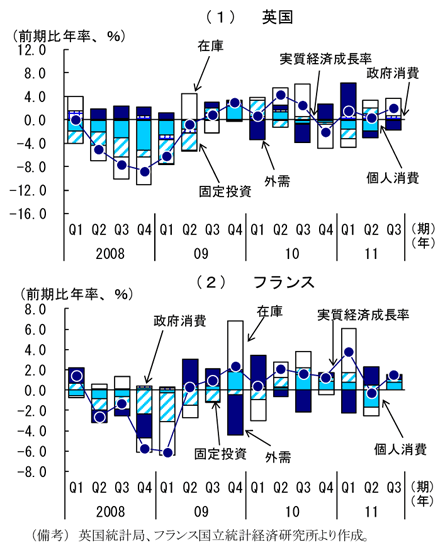
英国とフランスで景気が足踏み状態となっている一因として、個人消費の弱さが挙げられる。英国の個人消費は、11年4~6月期(前期比年率▲2.4%)にかけて4四半期連続で減少した。フランスでも11年4~6月期に前期比年率▲2.9%と9四半期ぶりに落ち込み、同年7~9月期は同+1.3%と反発力が弱かった。外需主導のドイツとは対照的に内需主導の国である両国で、景気のけん引役たる個人消費が弱い動きとなっている背景には、雇用・所得環境の厳しさがある。英国とフランスの失業率は、世界金融危機後に上昇した後も低下の兆しがうかがえない(第2-1-31図)。特に若年層の失業率が高水準となっている。
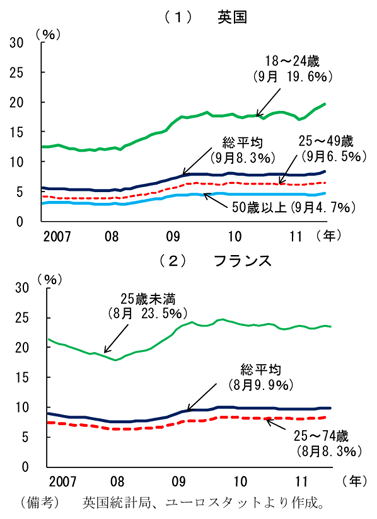
所得環境をみると、エネルギー価格等を中心に物価が上昇していることから、英国の実質可処分所得は09年4~6月期以降、減少基調となっている(第2-1-32図)。11年4~6月期においては実質可処分所得が同年1~3月期より増加したが、貯蓄率が上昇して消費増には結びつかなかった(第2-1-33図)。失業率の高止まり等から家計の先行きに対する不安が高まり、予備的貯蓄に繋がったとみられる。また、家計のバランスシート調整も影響しているとみられる。英国の家計債務残高は高水準であり、家計は借入れ抑制だけでなく、消費を控え、所得を債務返済に充当している可能性がある(前述第2-1-24図)。
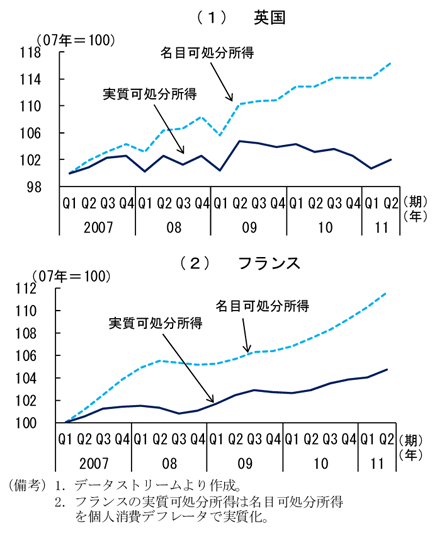
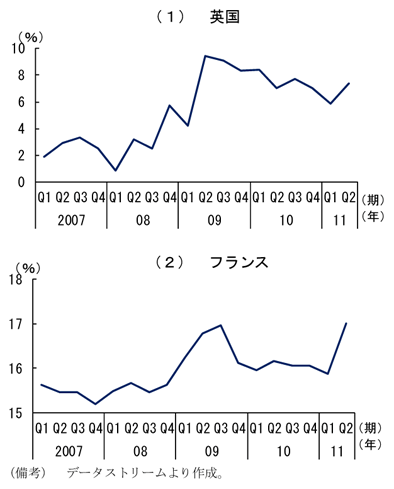
実質可処分所得の緩やかな増加が続くフランスでも、11年4~6月期には貯蓄率が上昇する中で消費が減少しており、英国と同様、予備的貯蓄によって消費が抑制されている可能性がある19。
次に設備投資についてみると、11年秋にかけて英国の稼働率は金融危機前のピーク近くまで持ちなおした(第2-1-34図)。危機の直後は稼働率が急低下し、企業は過剰設備を抱えたが、過剰感はほぼ払拭されている。フランスでは、稼働率がピークより8%程度落ち込んでいるが、最悪期を脱し、徐々に設備過剰感は払拭されている。しかし、設備投資は、特に英国で危機前のピークを大幅に下回っている(第2-1-35図)。過剰感が払拭されつつあり、収益環境も改善しているにも関わらず投資が伸び悩む背景には、バランスシート調整圧力の高さが影響していると考えられる(前掲第2-1-15図)。
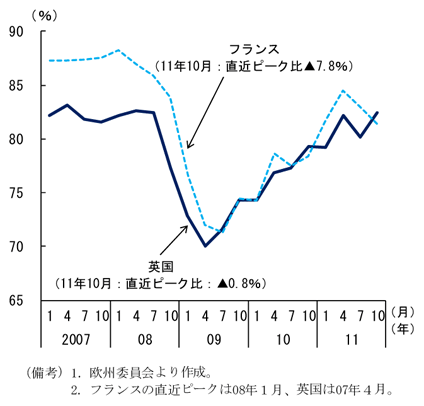
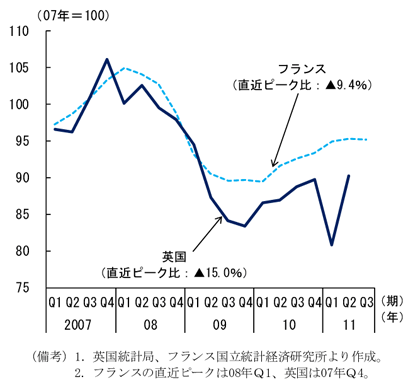
このように内需に弱さが残る中にあっては、輸出の動向が極めて重要になる。輸出は、英国、フランスともに全体の半分程度のシェアを占めるユーロ圏向けがけん引役となって、09年の半ばより増加基調となった(第2-1-36図、第2-1-37図)。アジア新興国向け輸出についても、中国で固定投資が盛り上がったことなどを背景に、両国でおおむね増加基調となった。また、英国に関してはアメリカ向けの寄与も大きかった。アメリカの景気が持ち直す中で燃料需要が回復し、石油製品の輸出シェアが大きい英国がその恩恵を受けた。
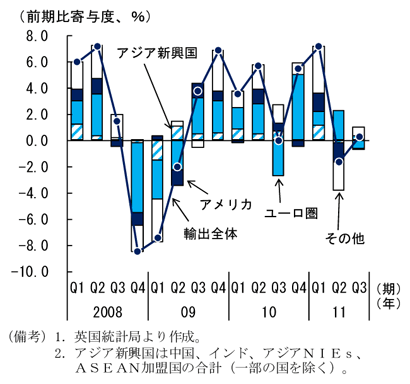
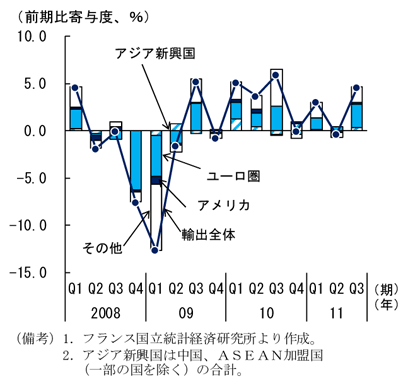
為替レートの減価も両国の輸出を押し上げる要因になったとみられる。世界金融危機後、09年にかけてポンドは主要通貨に対して大幅に減価し、その後も低水準で推移している(第2-1-38図)。ユーロに関しても、ポンド程ではないものの減価している。その結果、両国の輸出競争力が高まり、輸出回復の一助になったと考えられる。
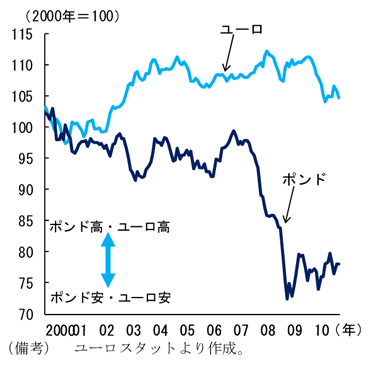
ただし、11年の夏場以降、輸出向け受注が弱い動きとなっており、内需に弱さが残る中で外需の下振れに注意が必要である(第2-1-39図)。
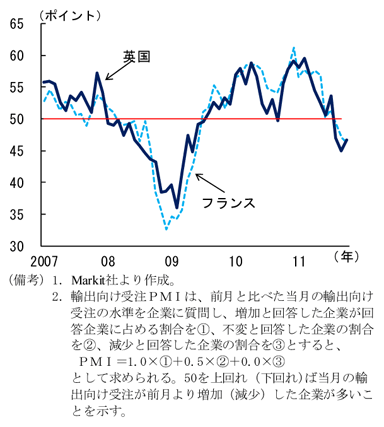
(4)景気が低迷している南欧諸国等
ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペイン、イタリアの5か国20は、世界金融危機等に起因する景気後退から脱却出来ないまま、ソブリン問題に翻弄され、景気低迷を余儀なくされている。これらの国で景気低迷が続く背景には、財政緊縮策が景気の重石となっている点が挙げられる。しかし、それに加え、各国経済が構造的な弱さを抱えていることも影響していると考えられる。経済の構造的な脆弱性は5か国で共通する部分もあれば、一部のみが抱える面もあるとみられる。以下では、南欧諸国等を取り巻く情勢やそれらが抱える構造的な問題について検討する。
(i)内需主導の経済成長で行き詰った南欧諸国等
2000年以降の南欧諸国等の実質GDP成長率をみると、07年まではプラス成長が続いていた(第2-1-40図)。特にアイルランドに関しては、2000年から07年の年平均成長率が5.0%と高かった。かつてアイルランドは生活水準が低く成長率も低迷していたが、80年代の後半からは高い成長を続け、「ケルトの虎の奇跡」と称されるようになった。それ以外の国では、ギリシャ(00年~07年の年平均成長率:4.2%)やスペイン(同3.4%)の平均成長率が高かった一方、イタリア(同1.1%)やポルトガル(同1.1%)は相対的に低成長であった。
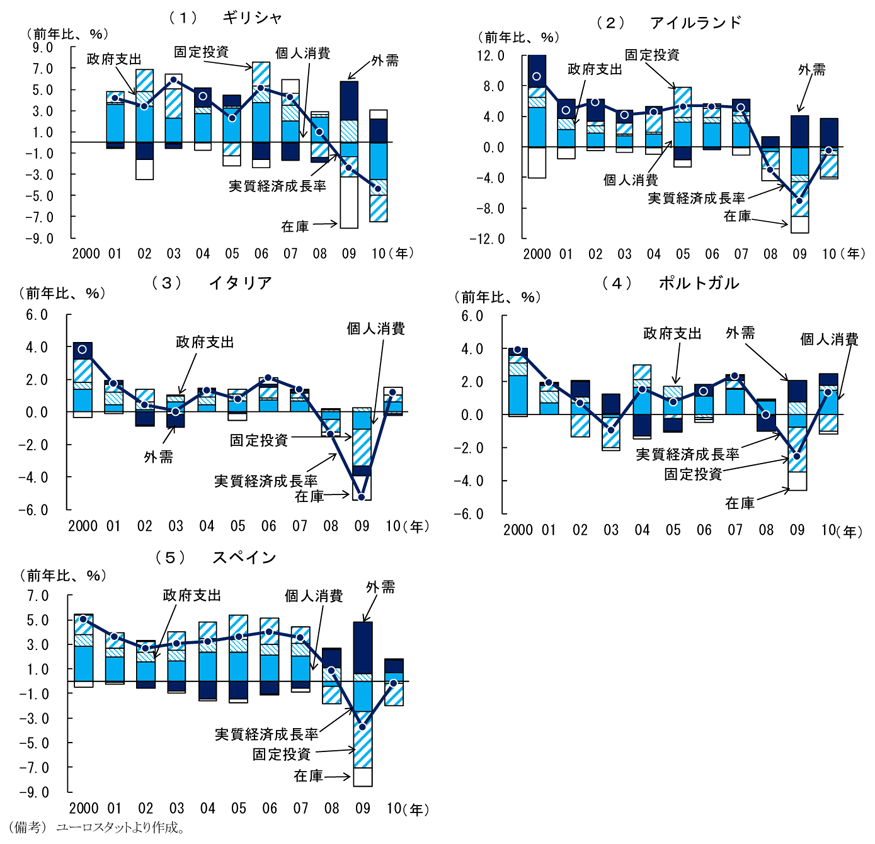
成長率の内訳をみると、個人消費や固定投資の寄与が大きく、内需主導の成長を続けてきたことがわかる。アイルランドでは、外需と内需がともに好調だった。
南欧諸国等で内需が好調だった一因は、資本流入の増加にある。ユーロ加盟で域内投資の際の為替リスクが消滅したことなどから、南欧諸国等への資本流入は2000年から08年半ばにかけて加速した(第2-1-41図)。南欧諸国等の家計や企業は資金を調達しやすくなり、消費や投資が増加したほか、一部の国では住宅バブルが生じた。
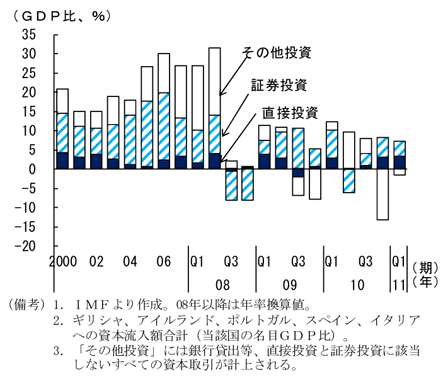
しかし、資本流入の裏側で対外債務が積み上がっていた(第2-1-42図)。そして、世界金融危機後には海外からの資金が引き揚げられ、09年の南欧諸国等の実質GDP成長率は内需が押し下げる形で大きく落ち込んだ。10年についても、内需回復が遅れる中、一部の国ではマイナス成長が続いた。南欧諸国等の内需主導型成長は、海外からの資金引き揚げに脆弱という構造的に問題を抱えた成長であったとみられる。
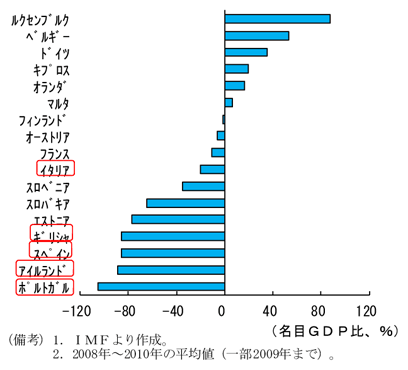
(ii)競争力が低い南欧諸国等の産業構造
南欧諸国等で内需の寄与が大きかった理由として、外需が景気のけん引役になることが難しかった点も挙げられる。産業毎に生産構造をみると、アイルランドを除き、農林漁業や個人向けサービス・運輸業のシェアがユーロ圏平均と比べて高い(第2-1-43図)。内需依存型の業種のシェアの高さは、輸出関連業種のシェアの低さ、ひいては輸出競争力の低さを示唆しており、内需が不振になると外需にも頼れず、景気のけん引役を失うことを意味する。南欧諸国等は財政緊縮の影響で内需が低迷する中で外需にも期待することが出来ず、景気低迷を余儀なくされていると考えられる。
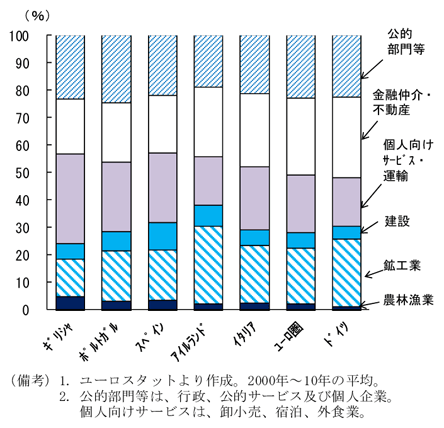
一方、アイルランドは農林漁業、個人向けサービス・運輸業のシェアがユーロ圏平均を下回り、鉱工業のシェアが高い。ユーロ創設を契機にビジネスチャンスを活かすべくアメリカ等からの直接投資が増加し、ITセクターを中心に生産拠点が設けられたことが影響しているとみられる。
なお、南欧諸国等については公的部門の肥大化が持続的な財政赤字の一因であるとの指摘が聞かれるが、公共セクター等の比率がドイツやユーロ圏平均から突出して高いわけではない(前掲第2-1-43図)。しかし、これについては、統計の作成上、公的部門等には個人企業が含まれているため、公共セクターの実体を表しているとは言い切れない面がある。歳出に占める政府部門人件費の割合でみると、南欧諸国等の値はユーロ圏平均と比べて高い(第2-1-44図)。歳出ベースでは公的部門は肥大化しており、財政悪化の一因になっていることが示唆される。
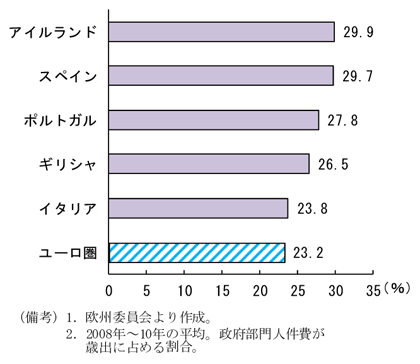
南欧諸国等の製造業単位労働コストは、ギリシャ(00年から08年の上昇率:56%)、イタリア(同31%)、スペイン(同28%)、ポルトガル(同12%)で大幅に上昇し、ドイツ(同▲3.1%)のように低下している国とは対照的である(第2-1-45図)。これらの国は、低コストを武器にして輸出を拡大させることが難しかったと考えられる。
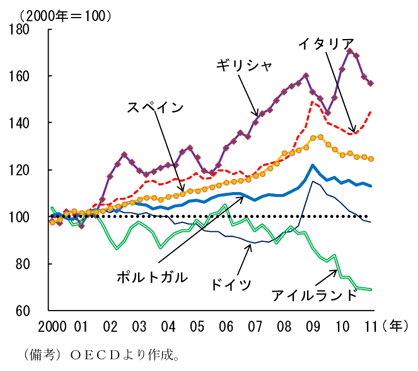
一方、アイルランドでは、単位労働コストが2000年から08年にかけて7%低下した。同国では鉱工業部門の生産シェアが高い(前掲第2-1-43図)が、この背景には低コストを追い風に輸出拡大を実現できたことがあるとみられる。
南欧諸国等の単位労働コストが上昇した一因は、賃金の上昇にある。ユーロ圏に加盟したことで自国通貨の減価を通じて競争力を高めることが事実上不可能となり、競争力向上には賃金の引下げが必要であった。しかし、これらの国では資本流入の影響等からインフレが続く中、一部の国では物価連動型の賃金決定メカニズムとなっていたこともあり21、生産性を反映した賃金決定を行うことが難しかった。南欧諸国等では労働コスト上昇率が生産性上昇率を上回っており(アイルランドを除く)、ドイツとは対照的な構図となっている(第2-1-46図)。
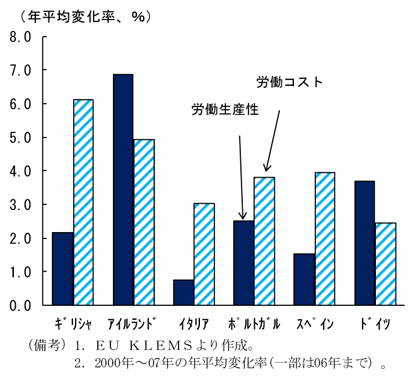
(iii)労働生産性が伸び悩む南欧諸国等
南欧諸国等の単位労働コストが上昇を続けたもう一つの理由として、労働生産性の伸び悩みが挙げられる。アイルランドを除く南欧諸国等では生産性上昇率がドイツを下回り(前掲第2-1-46図)、全要素生産性22(Total Factor of Productivity。以下、TFP)が押し下げに寄与した(第2-1-47図)23。TFP以外の要因(資本装備率の上昇等)はいずれの国でも労働生産性を押し上げたが、イタリアとスペインではその度合いが小さく、労働生産性が伸び悩んだ。一方、アイルランドではTFPの押し下げを資本装備率の上昇等で補ったほか、ドイツではTFPが労働生産性を大幅に押し上げた。
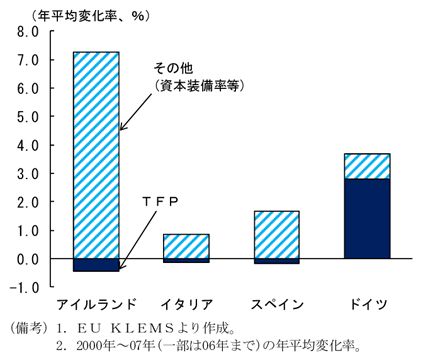
TFPが労働生産性を押し下げた背景として、ECB(2008)は競争の不活発を指摘している。参入規制等によって競争が促進されなければ、企業が他企業との差別化等のために投資を行うインセンティブが低下し、技術革新は遅れると考えられるからである。南欧諸国等について競争が阻害されている度合い24をみると、ギリシャやポルトガル、イタリアは相対的に高い(第2-1-48図)。ヨーロッパ平均を下回っているアイルランドやドイツと比べ、労働生産性が伸び悩みやすかったと考えられる。
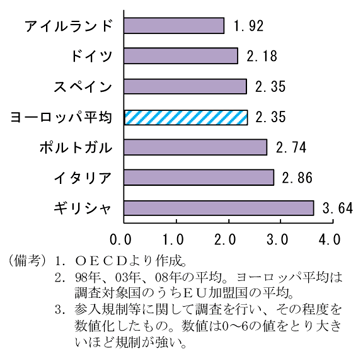
また、低スキル労働者が増加したことを労働生産性低下の理由と考える見方もある25。2000年から07年にかけての南欧諸国等における有期雇用26(全産業ベース)の増加の大半は、低スキル労働者であった(第2-1-49図)。雇用契約の柔軟化は雇用者数を増やし、失業率の低下をもたらしたが、製造業でも有期雇用の増加の過半が低スキル労働者によって占められていたとすれば、技術水準の低い雇用者の流入をもたらし、製造業の生産性が伸び悩む要因になったとみられる27。
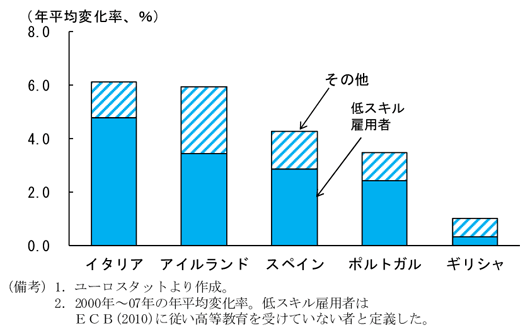
(iv)対外不均衡が恒常化した南欧諸国等
競争力の低さを踏まえた上で、南欧諸国等の輸出構造を概観しよう。財別にみると、食料品・農産物、繊維品、パルプ・紙製品のシェアが高い(第2-1-50図)。これらが輸出全体に占めるシェアは、ギリシャ(43.0%)、ポルトガル(41.1%)で半分近くあるほか、スペイン(26.6%)、イタリア(24.4%)でも高い数値となっている。機械類が高付加価値製品であるのとは対照的にこれら製品の付加価値率は低く、価格競争力の高低で輸出動向が決まりやすい。しかし、前述のとおりこれらの国の競争力は低く、南欧諸国等が外需主導の景気拡大を実現できない理由となっている。
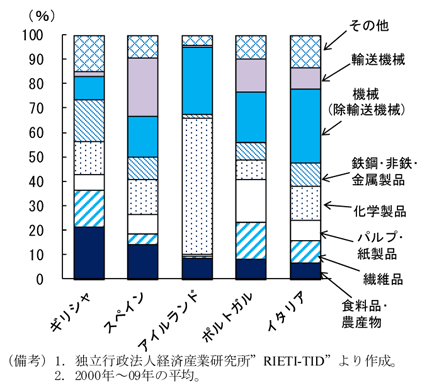
次に輸出先ごとにみると、EU向けの割合が大きい(第2-1-51図)。特にポルトガルやスペイン、ギリシャでは南欧諸国等向けのシェアが高い。南欧諸国等の景気が低迷を続ける限り、ギリシャ、ポルトガル、スペインの輸出は力強さを欠き、結果的に更なる景気低迷を招くという悪循環に陥る可能性がある。
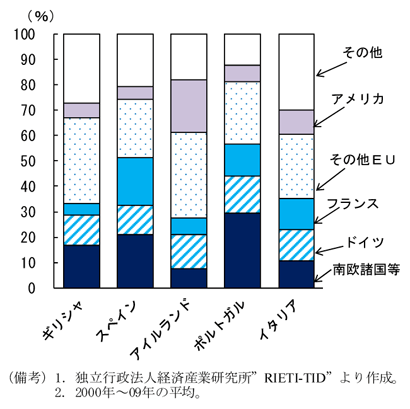
なお、アイルランドは財別にみると化学製品のシェアが突出して大きく、輸出先別ではアメリカ向けの割合が高い。これは、アメリカの製薬企業や化学メーカーがアイルランドを生産拠点としていることが影響していると考えられる。
以上の結果、貿易・サービス収支はアイルランドを除けば赤字が続き、経常収支赤字の主因となっている(第2-1-52図)。また所得収支も赤字となっているが、これは現地企業の配当や証券投資等による収益が本国へ還流していることが影響していると考えられる28。特にアイルランドでは所得収支の赤字が大きく、貿易・サービス収支の黒字を相殺している。海外企業の進出はアイルランド国内の雇用を創出するなどプラスの面もあるが、投資収益のうち国外に流出した部分も大きいことが示唆される。
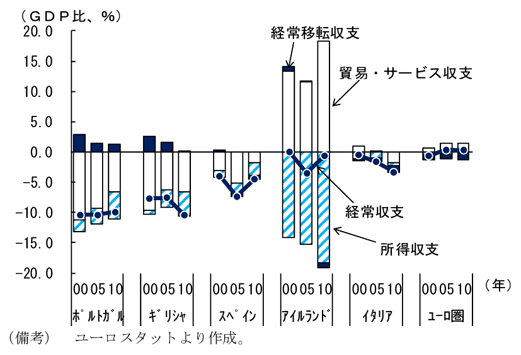
このように経常収支が赤字の南欧諸国等は、国内の資金不足を国外からの借入れでファイナンスした。ユーロ導入によって域内投資の為替リスクが解消したほか、ヨーロッパの銀行が高収益の見込まれる南欧諸国等への貸出を増加させたことが、そうした動きを活発化させた。しかし、その結果、南欧諸国等の対外債務が積み上がり、海外からの資金引揚げに脆弱な経済構造となってしまった(前掲第2-1-42図)。
(v)住宅バブルの後遺症に悩むアイルランドとスペイン
ここまで、南欧諸国等の競争力の低さとその背景についてみてきた。しかし、南欧諸国等の一部ではそれ以外にも構造的な弱さを抱えた国がある。それが、住宅バブルの後遺症に苦しむアイルランドとスペインである。
ユーロ加盟によって金融政策が統一される中、高インフレの国では実質金利が大幅に低下し、家計や企業は資金調達を容易に行うことができるようになった。そのため、移民増等の構造的な追い風もあり、アイルランドとスペインの住宅価格は2000年以降上昇を続け、07年半ばのピークには00年の2倍以上となった(第2-1-53図)。しかし、05年末頃よりインフレ抑制のためにECBが利上げを行ったことなどから実質金利は上昇し、住宅価格は下落に転じてバブルは崩壊を迎えた。その後遺症で、アイルランドやスペインの家計は可処分所得対比で高水準の債務を抱え、債務返済の負担が個人消費や住宅投資回復の足かせとなっている。
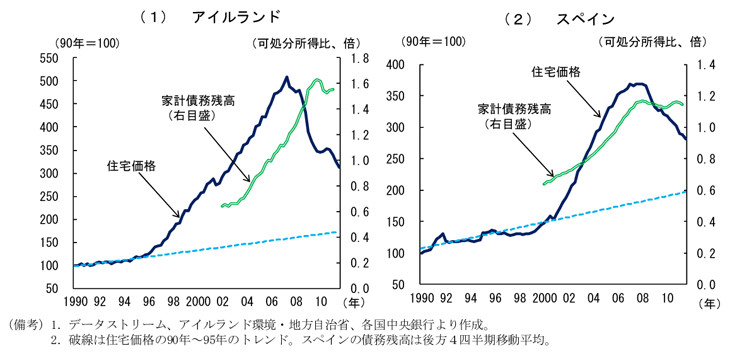
住宅バブルの崩壊で建設・不動産業の雇用は削減され、就業者全体を大きく押し下げることになった(第2-1-54図)。雇用回復は遅れており、スペインの失業率は11年に入ってから20%を上回り、アイルランドでも14%程度と高水準にある29。
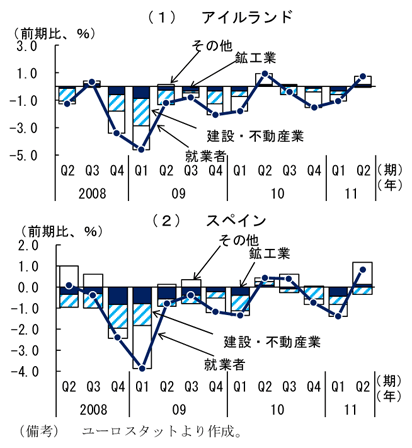
さらに、金融セクターも住宅バブルの後遺症を抱えたままである。住宅価格はピークから大幅に下落したもののバブル発生前のトレンドから上振れており、下げ止まりの兆しはうかがえない。両国の銀行の不良債権比率は高水準にある(第2-1-55図)が、住宅価格の下落が続いて住宅ローン等の与信が焦げ付けば、不良債権比率が一段と上昇するリスクがある。その場合、金融機関が貸出を抑制するなど現地企業の資金調達環境が厳しくなり、実体経済に悪影響を及ぼす可能性がある。
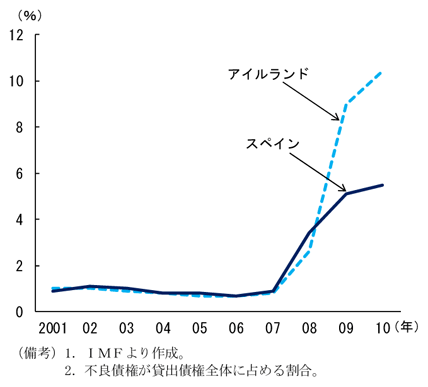
(vi)財政再建と構造改革の両立が求められる南欧諸国等
以上みてきたように、2000年以降の南欧諸国等の内需主導の経済成長は海外からの借入れに支えられた面も大きかったため、世界金融危機後に海外資金が引き揚げた結果、その成長パターンは持続不可能となった。労働生産性の改善等に向けた対策が講じられなかったために競争力も低く、外需主導の経済構造に転換することもできなかった。そうした中でソブリン問題が深刻化し、南欧諸国等は厳しい財政再建の実行を迫られ、景気回復は一段と遅れることになった。
南欧諸国等のソブリン問題は、これらの国に対する与信を多く抱えるヨーロッパの銀行の信用リスク問題に繋がる。信用リスクが高まって銀行の資金調達環境が悪化すれば、金融システムの正常な仲介機能は失われ、企業や家計までもが流動性不足に苦しむなど、実体経済に多大な負の影響を及ぼしかねない30。その解決は急務であり、南欧諸国等は財政再建策を実行し、市場の信認を取り戻す必要がある。
同時に、南欧諸国等は自身が抱える構造的な問題を解決して競争力を向上させ、持続的な経済成長を実現しなければならない。経済に構造的な弱さを抱えたままであれば、景気低迷が長期化して財政赤字の削減が進みにくい。一方、財政の持続可能性が保たれないままでは、債務危機が金融危機に波及し、世界金融危機のように実体経済に大きなショックを生じさせるリスクがある。ソブリン問題に未だ沈静化の兆しはみえないが、南欧諸国等は中期的な成長ビジョンを持ち、財政再建と構造改革を着実に両立させていくことが求められている。

