第4節 経済活性化に向けて
(人口減少・高齢化と経済成長)
人口減少や高齢化が今後さらに本格化することは最早不可避であり、それが経済に多大な影響を及ぼすことは、論を俟たない。しかし、人口減少や高齢化は、景気変動で浮沈する他の経済指標と異なり緩やかに進むため、その事実は多くの者が認識しているものの、実際の経済への影響となると実感に乏しい。多くの先行研究でも労働供給や財政及び社会保障等への長期的影響としては論じられるが、足元の経済動向への影響について定量的に分析されることは少ない。
本章の分析においては、各地域の労働市場では、15歳以上人口の減少や高齢化の進行による労働力率の低下を通じて、既に足元で影響を及ぼし始めていることを、第1節でみた。第2節の生産面での分析では、各地域の産業構造や就業構造の観点から産業の成長及び雇用需要について検討した。第3節は、消費需要に対して人口や人口構成の変化が現時点でどの程度影響を及ぼしているかを、定量的に示した。これらの分析からは、人口減少や高齢化が今後さらに加速すれば、その経済への影響度合いも必然的に高まっていくことが示唆される。
では、そうした状況下にあって、我が国経済は今後プラス成長を期待することは出来ないのだろうか。我が国の経済成長に対する悲観的見方あるいは経済衰退論は、不可避なのか。そして、その中で地域経済の将来はどうなるのか。
(成長に対する労働供給の寄与)
成長悲観論の最も有力な論拠は、労働供給の減少による実質成長率の低下であろう。実質成長率は資本投入、労働投入及び全要素生産性(TFP)の寄与に分解できるという成長会計の枠組みを前提に、人口減少や高齢化に伴い労働投入の寄与が減少するために、実質成長率は必然的に低下するという考え方である。
こうした成長悲観論に対する吉川(2003)や藤田・吉川(2011)の指摘は、示唆に富む。そこでは、戦後の我が国の経済成長を回顧した上で、これまで経済成長においては労働投入の寄与よりも資本投入やTFPの寄与の方がはるかに大きかったことが指摘されている。具体的には、1960年から2000年までの期間を10年ごとに区切って、それぞれにおける実質GDP成長率を資本投入、労働投入、TFPの寄与度に分解している91。これによると、全期間を通じて資本投入の寄与度が最も大きく、TFPの寄与度もそれに次いで寄与が大きい。それに対して、労働投入の寄与度は、プラスであった80年代までの時期をみると、0~0.4%ポイントに過ぎないという結果になっている。
上記の試算は、90年代で終わっているので、改めて、2000年代も含めて試算してみよう。80年から2010年までの期間を10年ごとに区切り、潜在GDP成長率を寄与度分解した結果が、第3-4-1図である92。これをみると、80年代には資本投入とTFPの寄与がが相半ばして成長を大きく牽引しているのに対して、労働投入の寄与度は潜在成長率全体の1割強程度に止まっている。90年代以降になると、労働投入の寄与度はマイナスに転じるが、資本投入やTFPのプラスの寄与度がこれを補って余りあるため、潜在成長率全体はプラスを維持している。
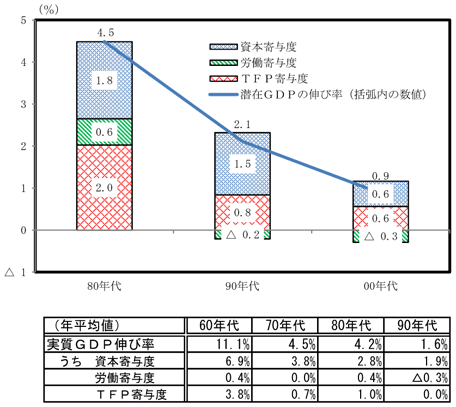
- 上図は内閣府「国民経済計算」「民間企業資本ストック」、厚生労働省「一般職業紹介状況」「毎月勤労統計調査」、総務省「労働力調査」、経済産業省「鉱工業指数」「第3次産業活動指数」、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」より作成。
- 潜在GDPの推計方法については、詳細は内閣府(2011)を参照。
- 80年代は81年から89年、90年代は90年から99年、00年代は00年から09年のそれぞれ平均値。
- 下表は吉川(2003)より作成。分析の出所は通商産業省「平成10年版通商白書」。
このことから分かることは、人口減少や高齢化が直ちに経済成長を諦めさせることにはならないということである93,94。資本投入やTFPのプラス寄与が維持・強化されれば、労働投入のマイナス寄与をカバーすることが可能なのである。しかし、資本投入やTFPのプラス寄与が維持・強化することは必ずしも容易なことではない。人口減少や高齢化は、国内貯蓄を減少させたり、規模の経済を働きにくくさせたりする面もあるからである。このように考えてくると、潜在成長率を将来的に維持するためには、①労働投入のマイナスの寄与を最小限にするために、長期的には少子化対策を推進し、中期的には女性や高齢者の労働参加を促しながら、②外国貯蓄をこれまで以上に活用できるようにしたり、③技術進歩等によりTFPの上昇率を高めたりすることが重要であることが確認できるであろう。
(人口減少社会における供給制約と需要不足)
人口減少や高齢化の進行が供給サイドへの影響を通じて潜在成長率にマイナスの影響をもたらすことは今みたとおりであるが、他方、人口減少や高齢化の進行は、需要サイドへのマイナスの影響を通じて実際の経済成長を制約することにもなる。人口減少や高齢化が個人消費や住宅投資を縮小させる影響を有していることは、第3節でみたとおりである。
実際、現状では、人口減少・高齢化の影響は、労働供給減少による供給力不足というよりは、むしろ需要不足とそれに伴う雇用需要・所得の低迷として現出している感が強い。今後の経済を展望してみても、人口の減少に伴う労働供給が制約となって経済成長が抑制される懸念がある一方で、個人消費需要の低迷等による需要の不足の方が深刻となり、慢性的な需要不足の下で経済が縮小均衡過程に陥り、労働市場でも高い失業率が顕在化するといった懸念についても、十分に留意する必要がある。
(イノベーションの役割)
このように考えてくると、今後、経済の供給サイドの改革を進めるにあたっても、需要サイドへの働きかけを視野に入れる必要があるということになる。その意味では、例えば、イノベーションを促進するにしても、それによって需要の伸びが大きい新しい商品・サービスを生み出すことによって、新たな需要が創出されることが必要となる。言い換えると、「イノベーションと需要の好循環」がつくりだされることの重要性が指摘できる95。また、規制や取引慣行のために、潜在的には豊かな需要があるにもかかわらず、それが顕在化していないような商品・サービス分野がある場合には、制約となっている規制や取引慣行を取り除くような、いわば「需要顕在化型の制度改革」を進めることが重要となる。
(地域経済へのインプリケーション)
以上の議論を踏まえると、地域経済の活力を維持し、所得や雇用を守っていく上で、どういった方策が重要となるのであろうか。何が地域経済を再生させ、域内の所得や雇用を安定的に確保させることができるのか。
地域経済の活力を高めるためには、地域を支える産業として、今後有望な需要を持ち、域内の発展を牽引する移輸出産業と、高齢化の進行を背景に医療介護サービス等今後伸びが期待できる地域消費型産業とが、バランス良く成長していくことが重要である。その中で特に留意すべき点として、2点指摘したい。
第1は、輸出の重要性である。域内需要は今後人口減少や高齢化を理由に減少せざるを得ず、長期的にはその域内市場の開拓にも一定の限界があるだろうが、海外に目を向ければ、アジア諸国を始め成長著しく需要が急拡大する経済圏が多い。こうした旺盛な経済活力を取り込み、海外市場に開けた経済発展を図るための政策形成が不可欠であり、地域経済においても、海外をも視野に入れた地域独自の経済成長戦略を持つことが必要な時代になっている。ただし、その際には、地域の現状や特性を踏まえた戦略であることが必要であることは言うまでもない。
第2には、新たな需要の創出の重要性である。たしかに人口減少や高齢化は今後の消費需要にとって不利な条件ではあるが、そうした動きが不可避である以上、むしろそれを見越して隠れた潜在需要を見出すことが必要であり、また、そこにこそ企業にとっても新たなビジネスチャンスが存在する。そうした需要拡大は、受け身で座して待つべきものではなく能動的に行動することが求められるものであり、そのためには地域の産業の競争力を常に研ぎ上げていることが必要条件となる。

