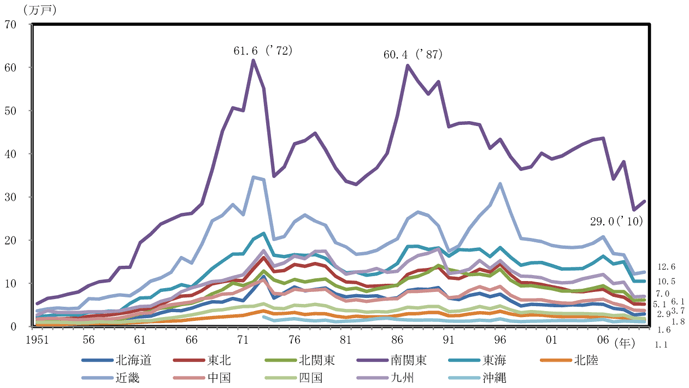第3節 消費の推移と高齢化
(1)各地域の個人消費
(各地域の消費及び住宅投資の長期的推移)
ここまでは生産や産業構造等経済の供給サイドを中心に検証してきたが、本節では、需要サイドがこれまでどのように推移し、人口動態の変化をいかに受けているのかについて検証する。
まず家計消費の長期的推移をみてみる。第3-3-1図は、内閣府「県民経済計算」データによる各地域の家計最終消費支出額についての長期グラフであるが、これをみると、80年代、90年代と年代を追う毎にその傾きが緩くなり、多くの地域で90年代後半以降はほぼ水平の傾きとなっている84。直近の2008年度の数値が96年度よりも大きく伸びているのは、沖縄(+16.3%)、東海(+12.6%)、南関東(+10.2%)地域であり、これら地域では同期間の人口増加率がそれぞれ+7.4%、+7.0%、+4.0%と高いことから、消費の伸びと人口の伸びの間の相関を想起させる。逆に、消費の伸びが小さかった北海道(△0.5%)、近畿(+0.1%)、東北(+1.1%)地域では、やはり人口の減少も概して大きいことが見て取れる。
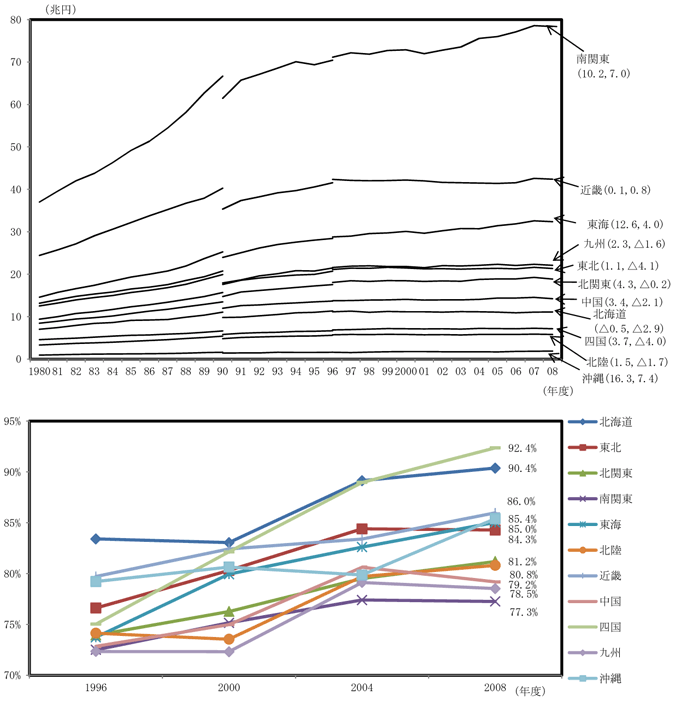
- 内閣府「県民経済計算」、総務省「人口推計」により作成。
- 上図の地域名の括弧は、左側が2008年度の数値の対1996年度伸び率。右側が人口の同伸び率。
- データ未公表のため、下図の南関東に東京は含まれない。
- 県民経済計算は90年までが68SNA・平成2年基準、90~96年が93SNA・平成7年基準、96年以降が93SNA・平成12年基準を使用。
- 地域区分はA。
次に、近年の平均消費性向の推移をみると、趨勢として全地域で上昇傾向にあり、ほぼ全地域で96年度と2008年度の間に6-7%ポイント程度上がっている。また、北海道、四国地域で消費性向が9割を超える一方、南関東地域で77%と一番低くなっている。
住宅投資の動向についてもみておこう。第3-3-2図は、地域別の新規住宅着工戸数を51年からの長期系列で示している。新規住宅着工戸数は、各地域とも70年代前半までの高度成長期に急速に増加して2桁の伸びを示しており、特に南関東、近畿、東海地域の都市部で大きく増加したが、73年にオイルショックを迎えた後にはマイナスの伸びで推移している。80年代半ばからのいわゆるバブル景気に入ると、再び1桁台後半の高い伸び率を示したが、その崩壊とともに90年代以降は減少傾向で推移している。例えば南関東地域でみると、2010年には29.0万戸で、ピーク時である72年61.6万戸、あるいはバブル期の87年の60.4万戸の半分以下にまで下がっている。
(2)消費と人口動態
(人口の変化と消費の関係)
人口及び人口構成の変化は、消費の動向に大きな影響を与えることが指摘できる。まず、人口が減少すればその分だけ消費主体が減少するため、消費額自体が減少することが考えられる。
この点について、第3-3-3図は、全11地域の80年以降の期間における家計最終消費支出額と人口のそれぞれの伸び率の相関をみたものである85。これによれば、80~90年及び96~2008年の期間では傾向線が有意に求められ、決定係数(自由度修正済)もともに0.72と高く、人口の増加と消費の伸びには強い正の相関があることが示されている。90~96年のいわゆるバブル崩壊後の時期においては、消費支出と人口の動きの間に明確な相関関係はみられない。
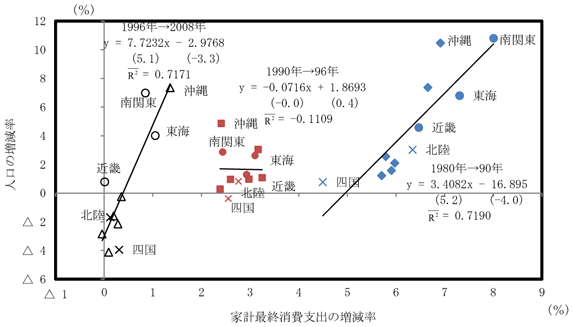
- 内閣府「県民経済計算」、総務省「国勢調査」、「人口推計」より作成。
- 家計最終消費支出は年度の値、人口は10月1日現在人口。
- 県民経済計算は90年までが68SNA・平成2年基準、90~96年が93SNA・平成7年基準、96年以降が93SNA・平成12年基準を使用。
- 括弧内はt値。
- 地域区分はA。
人口の変化が各地域の消費規模に影響を及ぼしていることが確認されているといえよう。
(人口減少及び高齢化が地域の消費に与える影響)
では、人口や人口構成の変化がどれくらい地域の消費に影響を及ぼすのか、定量的に検証してみよう86。ここでは、消費の動きを恒等式から、平均消費性向要因、一人当たり所得要因、人口要因に分解してその影響度合いをみる。すなわち、
(消費額C)=(平均消費性向C/Y)×(一人当たり所得Y/P)×(人口P)
となるが、人口減少及び高齢化は、①人口(P)、②一人当たり所得(Y/P)、③平均消費性向(C/Y)のそれぞれを通じて、消費を引き下げる方向に働く。
具体的には、まず①の人口減少は消費主体の減少を意味するため、消費額を減少させる。また、ライフサイクル仮説に従えば、高齢者は勤労期に働いて蓄えた貯蓄を高齢期に入ると取り崩して消費に充当する。高齢者の収入は総じて低いため、高齢化は、②の一人当たり所得の減少を通じて消費にマイナスに働く。他方、高齢となって財・サービスへのニーズが若干低下するにしても、一定程度の消費支出は必要であるから、結果的に③の平均消費性向は上昇、すなわち貯蓄率が低下する87。社会全体で高齢化が進行し人口構成が変化すると、②及び③を通じた消費への影響は大きくなる。
これまでの各地域の消費の推移を、実際に上記3要因に分解してみる。SNA統計の家計可処分所得と家計最終消費支出のデータを総人口と組み合わせて、要因分解を行った結果が、第3-3-4図である。これによると、80年代は家計最終消費支出額が概ね年率5~6%程度の伸びをしていたが、その大部分は一人当たり所得の伸びで説明でき、人口の増加も1%弱消費を押し上げていた。
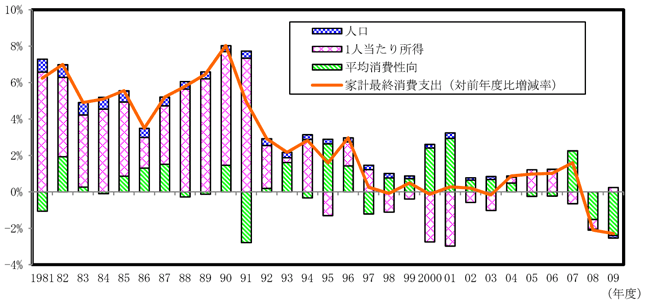
しかし、90年代後半からは、消費支出額の伸びがゼロ近傍で推移するようになり、一人当たり所得は景気局面に合わせて増減し、個人消費に対してプラス・マイナス両方向に寄与するようになった。2000年代になってから、一人当たり所得と消費性向が逆方向に寄与することがしばしば見られるようになったが、これは消費には慣性が働いて所得の変化と同じ程度には変化しない(ラチェット効果)ため、例えば所得が減少しても消費の減少は小幅にとどまり、結果的に消費性向が上昇するという状況が生じているものと考えられる。人口要因は、人口増加ペースの緩和を反映して消費押上げ効果が徐々に縮小し、2008年度以降は若干ながらマイナス方向に寄与し始めている。
地域別に要因分解したものをみると、いくつかの傾向がみてとれる(第3-3-5図)。第1に、地方部では人口要因は90年代後半から消費にマイナスの寄与をしており、四国、中国地域では影響の度合いが大きい。また、2000年代に入って北海道、東北、四国、中国地域でその影響度が拡大している。第2に、一人当たり所得の寄与にも地域差がみられ、2000年代では北海道、近畿、四国地域等でマイナス寄与が比較的大きい。第3に、消費性向のマイナス寄与が近年、北海道、東北、中国、九州地域等で見受けられる。
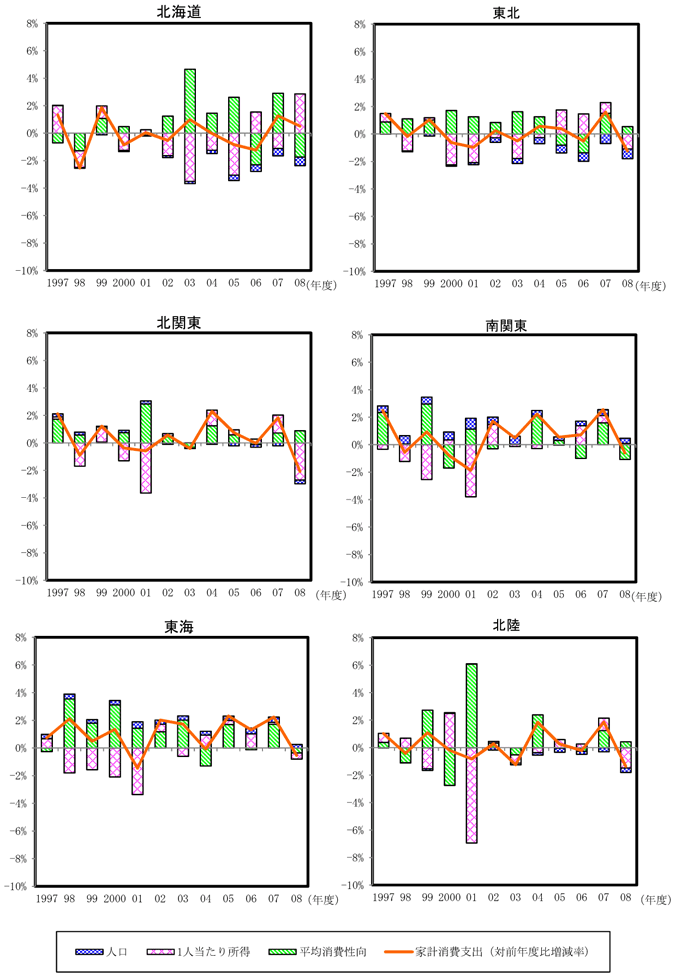

- 内閣府「県民経済計算」より作成。
- 地域区分はA。ただし、データ未公表のため、南関東に東京は含まない。
- (消費額)=(平均消費性向)*(一人当たり所得)*(人口)。
(高齢化による貯蓄性向の低下)
前述のとおり、人口の高齢化が進むと消費を押し下げる方向に働くことが考えられる。すなわち、高齢者になると消費性向が上昇するものの、所得は減少することが多いため、全体として消費額は減少する傾向がある。
これを総務省「全国消費実態調査」のデータを使って確認してみよう(第3-3-6図)。
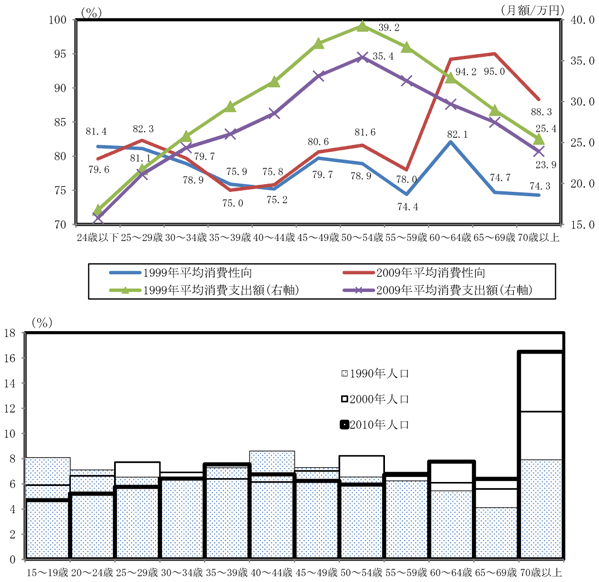
- 総務省「国勢調査」、「全国消費実態調査」より作成。
- 勤労者世帯ベース。平均消費支出額は月額。
データ制約上、世帯単位でかつ勤労者世帯に限定されるが、2009年調査では、明らかに高齢者の平均消費性向は高く、60歳代後半で95%、70歳代以上で88%となっており、ライフサイクル仮説の妥当性が確認できる88。しかし、所得の低下を背景に、消費支出額は、50歳代前半をピークに年齢を経るにつれ減少傾向にある。こうした中で、下図の年齢層別人口構成比の推移にみるように、高齢者層の比率が高まっていくことから、高齢化は消費額を減少させる方向に働くこととなる。
(人口の変化による消費内容の変化)
なお、人口構成の変化は、消費額のみならず、需要される消費財・サービスの内容にも影響を与える。年齢が進むにつれて、ライフステージに合わせて消費する費目は大きく変化していく。例えば、若中年層人口の減少は、彼らを主要な購買層とする乗用車・住宅の販売の低迷をもたらす。また、高齢者の増加は、医療・介護サービスへのニーズを高める方向に働く。地域内でこうした消費需要の変化が生じた場合、それに対応した財・サービスの供給体制が必要となる。
まず、その年齢層別の消費支出の具体的内容を家計調査のデータでみてみよう。第3-3-7表は、2010年のデータを使って、世帯主年齢層別に各支出項目の特化係数を計算して表にしたものである89。これをみると、20、30歳代の若年層は、家賃や外食代、洋服・履物、交通・通信費への出費が多いが、40、50歳代の中年層では、教育費や仕送りといった教育関係費や和服などに多く支出している。これに対して、60歳代以上の高齢層では、食料品や住居の修繕・維持費、保健医療費や家事サービス等に支出を振り向けているのが分かる。
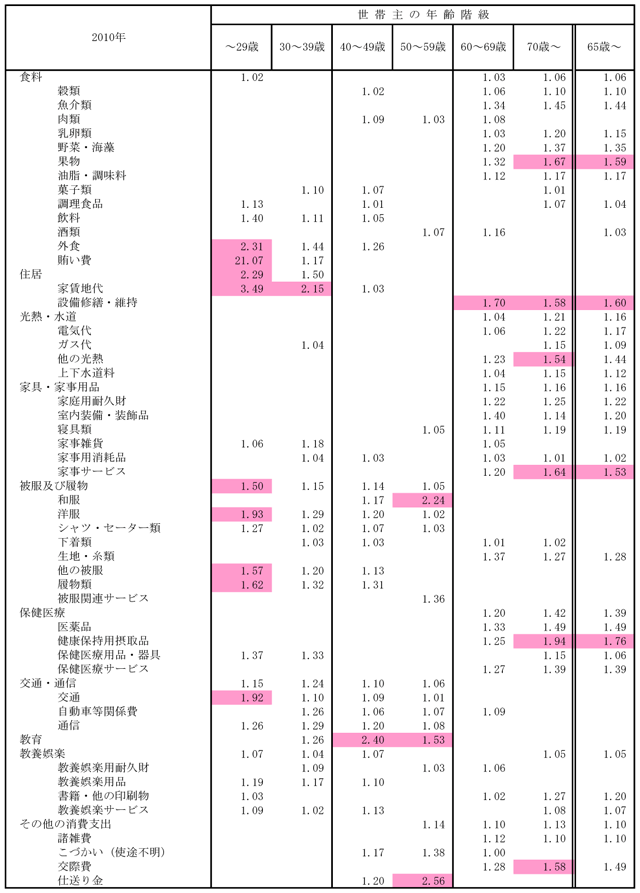
- 総務省「家計調査」より作成。
- 白抜きは特化係数が1未満、塗りつぶしは1.5より大きいもの。

(人口の変化による住宅需要への影響)
この高齢化等人口構成の変化や人口減少により大きな影響を受けることが予想される典型的な需要項目に、住宅投資が挙げられる。第3-3-8図は、総務省「住宅・土地統計調査」データで世帯主の年齢層別に持家率をみたものであり、折れ線グラフが持家率、棒グラフがその前の年齢層の持家率との差を示している。このグラフによれば、持家購入による住宅需要は、30歳代から40歳代前半に大きいことがうかがわれる。人口の減少及び高齢化により、こうした世代の人口が減少すれば、必然的に住宅需要は低下せざるを得ない。
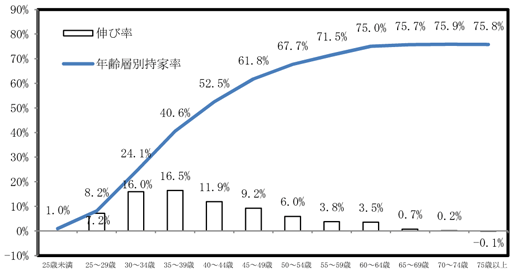
実際の人口変化が住宅需要にどのように影響を及ぼしたのかを、実績データを使ってみてみる。第3-3-9図は、60年から10年毎に、横軸に人口増加率、縦軸に新規住宅着工戸数の伸び率を取り、各地域のデータをプロットしたものである。60年代には、人口増減率に関係なく住宅着工戸数は各地域とも10%以上の伸びを記録し、旺盛な住宅需要がみられた。しかし、70年代には住宅需要の伸びは地域によりプラス・マイナス相半ばしており、いわゆるバブル景気を含む80年代に再びプラスの成長となったもの、90年代以降は各地域とも減少方向となっている。各年代の地域データを横断面データとして人口増加率と住宅着工戸数増加率の相関を取ると、必ずしも正の相関が確認できない。しかし、年代を経るに従って、座標の分布が右上から左下へ、第1象限から第3象限へと移行してきており、人口と住宅需要がともに縮小方向に向かっていることが示唆されている。
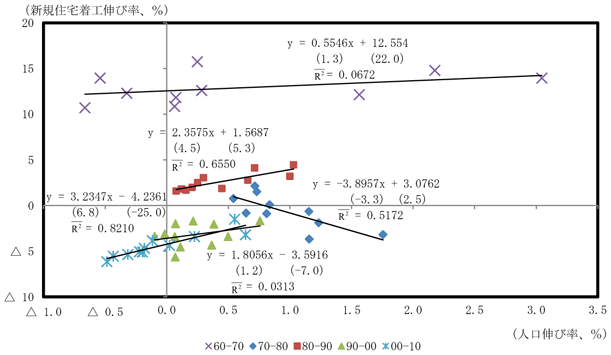
- 国土交通省「建築着工統計」、総務省「国勢調査」より作成。
- 伸び率は年率換算した値。
- 沖縄のデータは1973年から存在するため、60-70年と70-80年には沖縄は含まれない。
- 括弧内の値はt値。
- 地域区分はA。
本節では、消費や住宅需要について検証してきた。人口減少及び高齢化が経済に与える影響として、労働供給の減少や労働生産性の低下による潜在成長力の低下を懸念する声が大きいが、家計消費や住宅需要にみるように、今後人口減少や高齢化が加速するにつれて、国内需要の減少という、需要面からの影響がさらに大きくなることが予想される90。したがって、それに対応した企業等の供給体制の再編、新たな需要の開拓や海外需要の取込みが、将来の経済成長の重要な鍵となる。この点については、次節でさらに論じる。