第3章 企業行動の変化と投資拡大に向けた課題(第1節)
第1節 我が国企業の貯蓄超過の実態
本節では、過去40年間程度の企業行動を振り返り、堅調な収益が設備投資や賃金の実態に必ずしもつながらず、企業部門において貯蓄が投資を上回る「貯蓄超過」の状態が長期的に根強く続いている背景を分析する。
1 過去40年間の企業行動の変化
(経常利益の増加に比して、設備投資は抑制傾向)
まず、我が国企業の経常利益と設備投資について、我が国経済がデフレ的な状況に陥る前の時期から、具体的には1980年代以降過去40年間程度の長期的な動向を、「法人企業統計1」で確認する(第3-1-1図(1))。企業が通常行っている全ての業務によって得られる利益である経常利益は、短期的には景気の拡大局面において増加し、後退局面において減少しているが、長期的な動向としては、バブル期以前の1985年4-6月期2が5.3兆円であったのに対し、足下2023年7-9月期には27.2兆円と40年弱の間で5倍以上に増加している。バブル期のピークであった1989年頃の10兆円程度と比較しても3倍弱増加している。この間、国内における企業の生産的ストックである固定資産に毎期新たに追加された額、すなわち設備投資は、経常利益と同様に景気循環とともに増減しているが、長期的な動向としては、1985年4-6月期の7.5兆円から、2023年7-9月期に13.2兆円と2倍以下の水準の増加にとどまっており、また、過去最高値であるバブル期直後の1991年10-12月期の15.3兆円を下回っている。
両者の水準をみると、1990年代までは、設備投資が経常利益を上回っていたが、2000年以降、2008年のリーマンショック前まではおおむね同程度となった。その後、2010年代以降は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって経常利益が急激に落ち込んだ2020年4-6月期を除いて、常に経常利益が設備投資を上回る状態が続いており、両者の差は拡大傾向にある。経常利益に対する設備投資の水準を散布図でみると、1990年代から2000年代、2010年以降と進むにつれて傾きが緩やかになっており、企業部門が、経常利益の増加ほどには国内での設備投資を増加させてこなかったことが明らかである(第3-1-1図(2))。

(企業の収益力は過去30年間で向上)
また、経常利益の売上高に対する比率(売上高経常利益率)をみると、バブル期以前には2%台半ば程度であったが、バブル期の景気拡大とともに1980年代末にかけて4%程度まで上昇し、バブル崩壊後、1993年末までに1%台半ば程度まで低下した(第3-1-2図)。その後は、1997年のアジア通貨危機や金融危機後、2000年代初頭のITバブル崩壊後、2008年のリーマンショック時、米中の貿易摩擦等も背景に世界経済の減速がみられた2019年、2020年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大期など、一時的に低下する局面がみられるが、長期的なトレンドとしてみれば上昇基調で推移している。
このように、1993年末を底として、その後の約30年間において、企業は売上高の増加に比して経常利益を大きく増加させており、収益力を高めてきた。
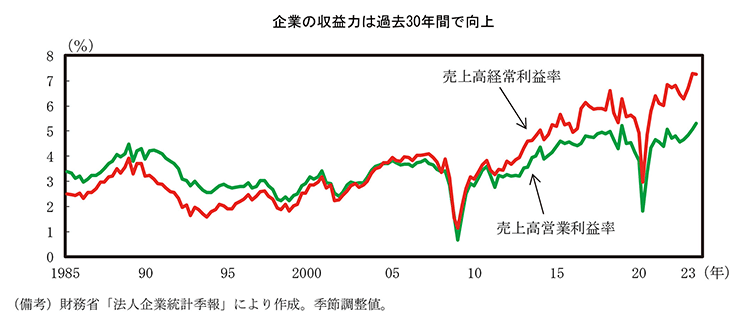
(コストカットと海外展開が経常利益の増加に寄与)
以上のように、我が国の企業部門は過去30年間で収益力を大きく高めてきた一方で、企業部門の経常利益と設備投資との関係性は、1980年代や1990年代と比べて大きく変化し、利益に比べ投資が抑制されるようになっている。こうした変化がなぜ生じてきたかを紐解く手がかりとして、以下では、「法人企業統計」の年次別調査結果を基に、経常利益の増加がどのような形でもたらされてきたのかを確認する。
ここでは、1993年度を起点とした経常利益の変動を、①売上高要因(売上の増減によるもの)、②変動費要因(原材料費など変動費の増減によるもの)、③固定費要因(人件費、減価償却費、支払利子等の増減によるもの)、④営業外収益要因(海外子会社からの配当金などの増減によるもの)に分解し、利益の増加を生み出した要因をみてみよう(第3-1-3図(1))。
まず、売上高要因は、時期によって1993年度対比でみてプラス・マイナスのいずれにも寄与するなど、景気動向によって変化している。これに対して、変動費要因は、リーマンショック前の原油等資源価格の高騰時を除き、総じてプラスに寄与しており、生産効率の改善などの企業努力を含め、企業が原材料コストを低く抑えてきたことが経常利益の増加を支えてきた様子がうかがえる。変動費の対売上高比率を業種別にみると、製造業では、リーマンショック前まで上昇傾向で推移し、その後は2010年代半ばまで総じて低下傾向となるなど、原油等資源価格の影響も大きく受けているとみられる一方、非製造業では、各年の変動はあるものの、一貫して低下傾向で推移している。我が国企業部門の変動費の面からのコスト削減の長期的傾向は、主に非製造業によってけん引されていたことがわかる(第3-1-3図(2))。
次に、固定費要因を確認する。固定費のうち人件費要因を取り出すと過去約30年間を通じ、総じて抑制的であったといえる。2000年代前半は、人件費要因は経常利益のプラス要因となっているが、これは1993年度対比で人件費が削減されてきたことを示している。その後、2010年代後半以降にマイナス寄与となるまでは人件費要因は経常利益に大きな影響を及ぼす要因にはなっていない。人件費の大宗を占める従業員人件費について、1980年度以降の推移をみると、1990年代半ばまでは、一人当たりの単価が上昇する中で人件費全体が増加してきたが、1990年代末から2000年代前半までは一人当たり単価が下落して人件費全体が抑えられてきた(第3-1-3図(3))。こうした中で、人件費の対売上高比率は、製造業を中心にリーマンショック前後での売上高の大幅な増減により大きな低下・上昇がありつつも、1990年代半ば以降について、全産業ベースで均してみれば横ばいに近い動きとなっている(第3-1-3図(4))。
人件費以外の固定費要因についてみると、国内で行った設備投資の結果として蓄積された固定資産に応じて計上される費用である減価償却費は、先述したとおり、経常利益の増加に比して設備投資の伸びが抑制的であったことから、過去30年間における収益に与える影響は小さい。一方、支払利息等については、経常利益に対して常にプラス寄与になっており、かつプラス寄与幅は総じて拡大傾向にある。後述するように、バブル崩壊以降、企業の債務過剰の解消が進展し自己資本が強化される中で、借入金の残高が2000年代半ばまで減少するとともに、低金利環境が継続してきたことがあいまって、資金調達面のコストが傾向的に低下してきたことが影響したものと考えられる。
また、企業が本業以外の活動で経常的に得ている収益である営業外収益要因は、2010年代半ばから1993年度対比でプラスに転じ3、その後プラス寄与が着実に拡大している。営業外収益の対売上高比率を業種別にみると、特に製造業の増加が著しく、グローバル化の進展、海外生産の拡大に伴い、海外子会社などからの配当金受取が増加していることがうかがえる(第3-1-3図(5))。ただし、営業外収益には、雇用調整助成金をはじめとして、コロナ禍での雇用維持や事業継続のための法人企業向けの補助金・支援金の支給額が計上されており4、特に2020年度や2021年度の営業外収益の対売上高比率の改善の動きにはこれらの政策の影響が含まれていることに留意が必要である(コラム3-1)。
このように、過去30年間における企業の経常利益の増加に対しては、売上高要因は景気の動向によって変動し、期間を通じて均してみれば主要な押上げ要因とはならない中で、主として、生産効率化も含めた変動費率の低下、人件費等の抑制5、過剰債務の解消等による支払利息等の減少といった企業のコストカット、また、海外生産の拡大に伴う営業外収益の増加によってもたらされてきたといえよう。
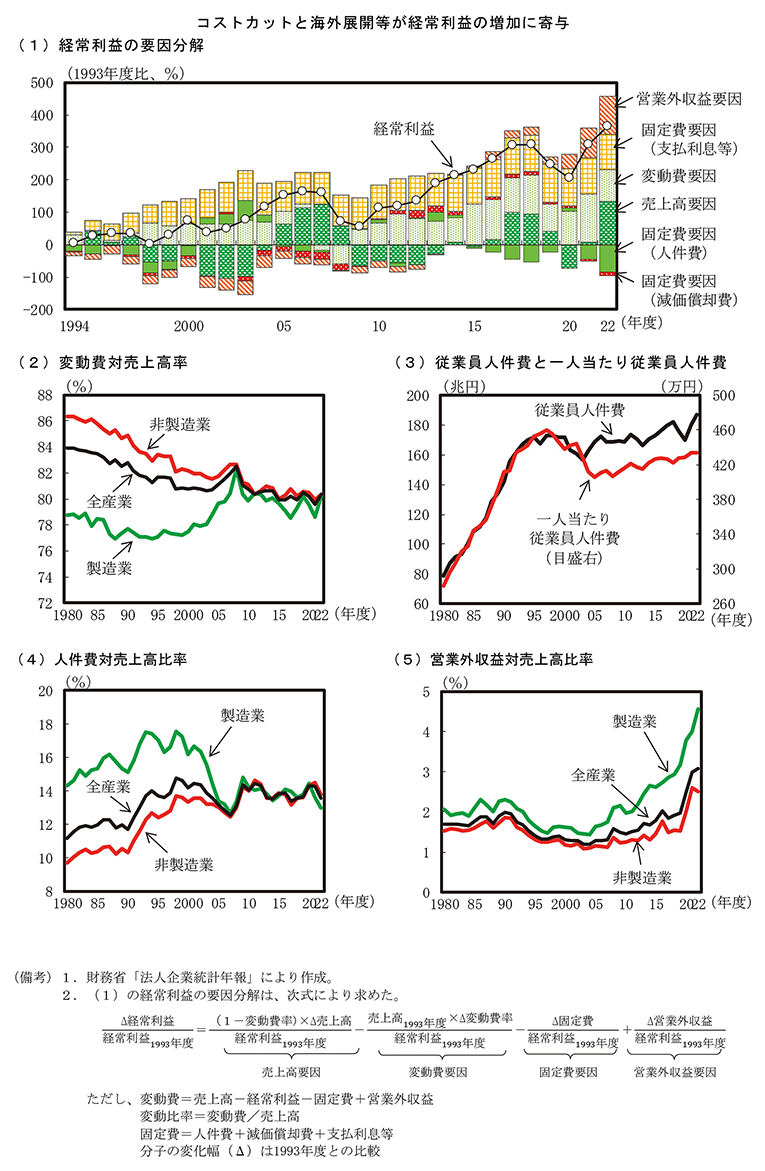
コラム3-1 営業利益と経常利益のかい離
経常利益と営業利益は、2000年代前半においては、両者ほぼ同水準であったものが、それ以降、経常利益が営業利益を上回って推移し、直近の2022年度には経常利益が営業利益を約4割程度上回る状態となっている(コラム3-1-1図)6。本論でも述べているとおり、これは、主には、グローバル化が進む下で、企業による海外子会社の設立や海外企業のM&Aが進み、海外生産活動が活発化したことにより、海外子会社等から国内に還流する配当収益等が増加したことによる。

ここで、経常利益と営業利益の差である営業外損益(営業外収支)について、内訳が確認できる「法人企業統計季報」を用い、その要因を受取利息等(配当を含む)、その他の営業外収益、営業外費用に分けると、受取利息等が継続的に営業外収支を押し上げ、その押上げ幅が拡大していることがわかる(コラム3-1-2図)。また、その他の営業外収益や営業外費用も緩やかにプラス幅を拡大しており、特に2020年度以降はプラス幅が大きく拡大した。2020年度以降、その他の営業外収益のプラス幅が拡大しているのは、本論でも述べているように、コロナ禍での各種企業支援策による補助金等が、企業の判断によってその他の営業外収益(もしくは特別利益)に計上されているためである。なお、2022年度はその他の営業外収益とともに、その他の営業外費用も増加しているが、これは、為替レートの急速な変動による為替差益・差損の影響が大きいものと考えられる。このように、2000年代半ば以降の営業利益と経常利益の差の拡大は、大きなトレンドとしては海外直接投資の拡大に伴う海外子会社からの配当収入等の増加傾向が影響する一方、コロナ禍期間、特に2020年度、2021年度にかけては、政府による雇用維持・事業継続支援の影響も大きかった点には留意する必要がある。

(利益増加は企業の自己資本強化に活用)
次に、企業が獲得した利益の配分状況を確認すべく、経常利益に、臨時に発生する損益や長期保有の有価証券や固定資産の売却損益などの特別損益を加えた税引前当期純利益の処分状況に関する内訳をみてみよう(第3-1-4図)。まず、法人税等の支払額は、利益が増加する一方で、法人税率が段階的に引き下げられてきた中で、期間を通じてみれば大きく変化していない。過去20年間で大きく増加してきたのは、配当支払のほか、社内留保である。直近の2022年度の税引前当期純利益は、リーマンショック前のピークである2006年度と比較して2倍超(+100.6%)に増加しているが、その内訳寄与をみると、法人税等の支払は+6%、配当金の支払は+33%、社内留保が+61%となっており、企業が生み出した利益のうち最終的に社内に残る分が特に大きく増加している。

このように、社内留保が増加してきたことの結果として、企業のバランスシートの総資本(負債・資本の部。貸方)の面では、過去20年間にわたって、利益剰余金と資本金及び資本準備金が着実に増加してきた(第3-1-5図(1))。バブル崩壊後の1993年度対比での総資本の伸び率とその内訳寄与をみると、総資本は2022年度までに+65%増加しているが、そのうち利益剰余金の寄与は+33%、資本金及び資本剰余金は+16%と、両者で総資本の増加の75%を占めている。一方、借入金は1990年代後半から2000年代半ばにかけて減少しており、1993年度対比での総資本の増加に対する借入金の寄与は、1999年度以降、コロナ禍で借入金を大きく増加させた2020年度までマイナス寄与で推移してきた。
言い換えれば、企業の資金調達は、他人資本から自己資本へと移ってきた。総資本に対する借入金と利益剰余金の比率をみると、企業規模や業種を問わず、前者が低下する中で後者が上昇している(第3-1-5図(2))。結果として、1990年代までは20%を下回る水準であった自己資本比率は、2010年代後半には全規模全産業ベースで40%を超える水準まで高まっている(第3-1-5図(3))。このように、企業は、1990年代末以降、増加してきた企業利益を活用し、バブル崩壊後に企業活動の足かせとなってきた過剰債務を解消させ、自己資本を強化し、財務基盤を強固にしてきたといえよう。
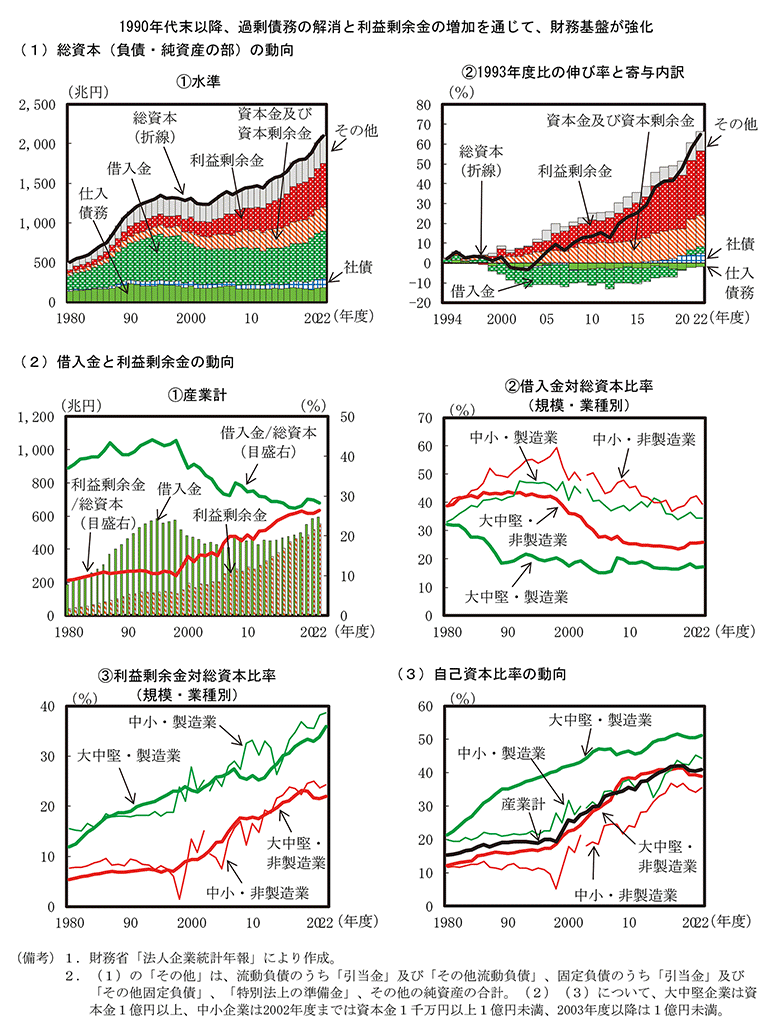
(国内投資が抑制される一方、海外投資と手元流動性が増加)
それでは、このように強化されてきた自己資本は、どこに向かっているのか。利益剰余金は、借入金や社債発行、株式増資などの他の資金調達と同じように、設備投資や不動産、有価証券、あるいは現金・預金など、何らかの資産に形を変えて運用されているものであるが、これをバランスシートの資産面(借方)の動向から確認する。
総資産のうち、2000年代以降、特に大きく増加しているのは投資有価証券である(第3-1-6図(1))。投資有価証券は、長期保有目的の株式、公社債、その他の有価証券の合計であるが、そのうちの9割は株式であることから、投資有価証券の拡大は、主に国内企業による海外子会社の設立や海外企業のM&Aが拡大してきたことによると考えられる7。また、現金・預金についても、2000年代半ば以降、緩やかなペースにて着実に増加基調で推移してきている。一方で、土地を除く有形固定資産は、企業の投資姿勢が消極化したことから、1990年代末から2010年代初頭まで減少傾向で推移した後、2010年代前半以降にようやく増加に転じている。総資産の伸び率とその内訳寄与をバブル崩壊後の1993年度対比でみると、投資有価証券と現金・預金の増加が総資産の増加をけん引してきたことがわかる。総資産は、総資本と同様、1993年度から2022年度までに+65%増加したが、そのうち投資有価証券の寄与が+25%、現金・預金が+12%と、両者の合計で6割弱を占める。一方、土地を除く有形固定資産は、2000年代半ばから2018年度まで一貫してマイナス寄与で推移し、2019年度にマイナスを解消してその後はプラスに転じたが、プラス寄与幅は2022年度で+2%とわずかである。また、ソフトウェアや特許権等の無形固定資産は、期間を通じて徐々に増加しているものの総資産全体に占める割合は小さい。
これらを総資産に対する比率でみると、企業行動の変化の特徴は一層明らかである。1990年代後半以降、有形固定資産の比率が低下するのとほぼ時期を同じくして投資有価証券の比率が上昇傾向で推移しており、2010年代後半には両者の比率が逆転するに至っている(第3-1-6図(2))。このことは、過去四半世紀ほどの期間において、企業部門は、国内での設備投資を抑制する一方で、より市場の拡大が見込まれる海外において、現地法人の設立やM&A等による生産・販売拠点の拡大に積極的に取り組んできたことを示している。企業規模別にみると、こうした動きは主として大・中堅企業において顕著であり、海外向け投資の拡大が、配当金を通じた営業外収益の増加という形で、経常利益を支えてきた面がある。
また、総資産に対する現金・預金の比率についても、2000年代半ばから上昇に転じている。企業規模別にみると、大・中堅企業においても緩やかに増加しているが、特に、1990年代後半以降の中小企業における現金・預金の蓄積が著しいことがわかる。規模が小さく経営資源に制約がある中小企業では、一般的に、大・中堅企業に比べて海外展開が難しく、したがって、投資有価証券よりは現金・預金での蓄積が進んだものと考えられる。こうした現金・預金の蓄積により、企業の短期的な支払能力を計る尺度である手元流動性8も2000年代半ば以降上昇している(第3-1-6図(3))。収益の増加に比して賃金や国内向け投資を抑制してきた結果であるほか、リーマンショックやコロナ禍によって売上が急減するなど経済的な危機を経験する中で、手元流動性を多く確保しておくといった企業行動も表れていると考えられる。
このように、企業は自己資本の増加を通じて財務基盤を強化する中で、資金の運用面では、海外投資(投資有価証券の増加)と現金・預金を拡大させる一方、国内向け設備投資(土地を除く有形固定資産)は総じて抑制してきた。

2 企業の設備投資拡大に向けた課題
(投資抑制による貯蓄超過がほぼ四半世紀にわたり継続)
前項で確認したとおり、長期的にみて、企業の経常利益の増加は、主として、変動費率の低下や人件費の抑制等によるコストカット、また、海外生産の拡大に伴う営業外収益の増加によってもたらされてきた。そのようにして得られた利益は、主として、①利益剰余金の増加を通じた財務体質の強化、②現金・預金の増加を通じた手元流動性の確保、③海外投資の拡大に用いられてきたといえる。財務体質の強化と手元流動性の確保については、バブル崩壊後に直面した債務・雇用・設備の3つの過剰を解消し、また、リーマンショック等の世界的な経済危機を経験する中で、これらに備えたリスク耐性を得るためには、企業にとって必要な構造変化であったともいえよう。また、海外直接投資の拡大は、アジアを中心により高い収益率の見込める地域に生産拠点を立地して現地市場の需要を取り込むことのほか、東日本大震災も経て、サプライチェーンの海外移転によるリスク分散や電力コストのより低廉な地域への生産拠点の移転など、各企業にとって合理的な意思決定の結果として進んできた面がある。
他方、企業が財務体質の強化や海外需要の取り込み等を優先してきた反面として、人件費や国内での設備投資が抑制されてきた。その結果として、我が国の企業部門では、1990年代末以降、恒常的に貯蓄超過の状態が継続している。非金融法人企業の貯蓄投資バランスについて、「国民経済計算(SNA)」における純貸出(+)/純借入(-)や「資金循環統計」における資金過不足をみると、いずれも1990年代後半に、それまでの投資が貯蓄を超過する状態(資金不足)から、貯蓄が投資を超過する状態(資金余剰)に変化し、その構造が約四半世紀にわたって継続していることがわかる(第3-1-7図(1))。なお、2022年度にかけては、SNA、「資金循環統計」のいずれでみても貯蓄超過幅が縮小しているが、これは、設備投資の増加に加え、コロナ禍における雇用維持・事業継続のための政府からの補助金等が剥落したことで貯蓄が減少したこと等による。2023年度に入って以降の動向を「資金循環統計」における資金過不足(季節調整値。民間非金融法人企業)でみると、2022年度から反転して資金余剰が増加傾向にあり、企業部門の貯蓄超過が解消したという状況には至っていない。
次に、非金融法人企業の資金過不足の長期的な動向を金融面から詳細にみると、バブル期までは、旺盛な借入による資金不足要因が、現金・預金の増加による資金余剰要因を上回り、全体として資金不足状態が続いていたことが確認される(第3-1-7図(2))。しかし、バブル崩壊を経て、1990年代終盤以降は、バブル期に積み上がった債務の返済が進展して借入が資金余剰要因に転ずる中で、現金・預金もプラス傾向で推移したことで、全体として資金余剰構造に転換している。2000年代半ばには、長期的な景気回復の下で資金余剰幅が縮小する局面もあったが、2008年のリーマンショックを経て、借入を減少させるとともに現金・預金を積み上げるという姿勢が再び顕著になった。2010年代以降は、過剰債務の圧縮が進んだことも背景に、借入が増加に転じ資金不足要因となった一方、現金・預金の積み上がりは続き、また、対外直接投資フローが着実に増加する中で、全体として資金余剰が継続した。上述したように、企業の利益が拡大していく中で、その利益は、海外直接投資と手元流動性の増加に充てられ、借入の増加がみられても、これは海外M&A等に回されたと考えられ、国内への支出は限定的だったといえる。

(長期にわたる企業の貯蓄超過傾向は、主に非製造業の影響が大きい)
次に、こうした動きを貯蓄と投資という実物面から、「法人企業統計」の年次調査結果を用いて、業種別の動向も含めて確認する。ここでは、貯蓄側は、当期純利益に減価償却費を加算し、配当支払額を控除した「内部資金」を、投資側は、設備投資9、在庫投資、土地投資を合計した「資金需要」をとり、両者の差を貯蓄投資バランスとしている。貯蓄投資バランスの対付加価値比率について、上記の内部資金と資金需要の二つの要因に分けてみていくと、内部資金については、バブル期にかけての増加、バブル崩壊後の減少、リーマンショックやコロナ禍による減少等の変動はあるものの、2000年代以降は相対的に安定して増加傾向で推移している(第3-1-8図(1))。これに対し、資金需要は変動が大きく、1980年代後半から1990年代初頭のバブル期にかけて急速に増加したが、バブル崩壊後、2000年代初頭まで減少傾向で推移した。その結果、企業の貯蓄投資バランスは、1990年代末にそれまでの投資超過の状態を解消した。その後、資金需要はリーマンショックやコロナ禍による一時的な減少を除けば緩やかな増加基調で推移しているが、ほぼ一貫して内部資金を下回っており、貯蓄超過構造が定着してきた。
こうした企業の貯蓄投資バランスを業種別にみると、製造業・非製造業ともに、1990年代前半まではおおむね投資超過、1990年代終盤以降は貯蓄超過という傾向は共通しているが10、全体の貯蓄投資バランスの動向を形作っているのは非製造業であることがわかる(第3-1-8図(2))。非製造業では、1980年代のバブル期において土地投資を含む資金需要が旺盛であり、付加価値対比でみた貯蓄投資バランスの赤字幅が製造業の2倍程度となるなど、投資が過熱していた様子がうかがえる。一方で、こうした積極的な投資の裏で過剰債務が蓄積されたため、バブル崩壊後はその解消が急務となり、バランスシートの調整過程で資金需要を大きく減少させたものと考えられる11。2000年代以降は、製造業では景気回復の下で2000年代半ばに投資超過となった時期がみられるのに対し、非製造業ではその間も貯蓄超過であるなど相対的に貯蓄超過構造が根強い。

(G7諸国でも、企業の貯蓄超過はみられるが、日本の貯蓄超過の一貫性は突出)
このように、企業が1990年代末に投資超過主体から貯蓄超過主体へと転換した主因は、貯蓄の増加というよりも、投資の減少であったといえる。また、2000年代以降は、資金需要が一貫して内部資金を下回って推移しており、投資が常に抑制的であったことで貯蓄超過の状態が継続してきた。
ここで、企業部門の貯蓄投資バランスの長期的な動向について、SNAベースにおける非金融法人企業部門の純貸出(+)/純借入(-)によって主要先進国との比較を行いたい。ここで、貯蓄は、固定資本減耗を含む総貯蓄(gross saving)12であり、投資は、総資本形成(設備投資、在庫変動)に、土地の純購入など非金融非生産資産の純取得等13を加えた「総投資」(gross investment)の概念である。このようなSNAベースの貯蓄投資バランスを付加価値(GDP)比で、比較可能な1990年代半ば以降の動きをみると、アメリカやフランス、英国では、各年での変動はあるものの、おおむね総貯蓄と総投資がバランスしている。イタリアとカナダについては、コロナ禍後に貯蓄超過の傾向がみられるが、コロナ禍以前はおおむねバランスしていた。一方、ドイツについては、2000年代終盤以降に貯蓄投資バランスが黒字、すなわち貯蓄超過傾向が定着している(第3-1-9図)。日本は、上述のとおり、1990年代終盤から一貫して、総貯蓄が総投資を恒常的に上回る貯蓄超過体質が続いており、また、GDP比でみた貯蓄超過の度合いも大きく、ドイツを除く主要先進国との対比では黒字構造が突出しているといえる。なお、ドイツでは、1999年のユーロ圏発足以降、他国に比べて、企業による無形固定資産を含む設備投資の伸びが緩慢であったことが、企業部門の貯蓄超過につながっているという指摘がある14。以上のように、国際資本移動の自由化と新興国の成長に伴う海外向け投資の拡大といったグローバルな投資環境が変化していること自体は各国共通であることを踏まえると、主要先進国の中で、我が国企業が収益に比して国内投資を抑制してきた状況が際立っているということができる。

コラム3-2 企業の貯蓄投資バランスと海外直接投資
海外M&Aや現地法人の設立を通じた我が国企業の海外直接投資の残高は、この約四半世紀で10倍に増加し、フローでみた海外直接投資の民間設備投資に対する比率は、2018年度に25%弱に達するなど長期的に増加傾向で推移している(コラム3-2-1図)。ここでは、こうした海外直接投資が、我が国企業の貯蓄投資バランスとどのように関係しているのかを整理する15。
まず、一国の経済動向を捉えるSNAや資金循環統計で対象となる非金融法人企業は、国内に居住する企業である。これらの統計の基礎となる「国際収支統計」では、国内に主たる事業所を有する法人や、外国法人等が国内に持つ支店等は、我が国の「居住者」である一方、国内法人等が外国に持つ支店等は「非居住者」と位置付けられる。よって、日本企業の場合、SNA等の記録対象となるのは、あくまで国内に所在する事業所分となり、企業会計上で連結決算の対象となる海外子会社等は含まれない。

貯蓄投資バランスは、こうした国内居住企業における営業余剰(固定資本減耗を含む)に利子・配当等の財産所得の純受取等を加算し、直接税の支払を控除したものを総貯蓄、国内における設備、在庫、土地への投資等を合計したものを総投資として、その差額となる。ここで、海外直接投資に関しては、①海外子会社等から支払われる配当は、財産所得の受取として記録される。また、②海外子会社等における当該期間の留保利益は、「海外直接投資に関する再投資収益」という形で、一旦国内の親会社に還流したものと擬制して、財産所得の受取に記録される16。他方、当該期に海外M&Aにより外国企業を取得した場合、被買収企業の設備を取得することになるが、あくまで非居住者である海外子会社において設備が増加したと記録されるものであり、SNA上の国内居住企業の設備投資や貯蓄投資バランスには反映されない17。
金融面からみた「資金循環統計」の資金過不足は、国内企業における金融資産の純増(資産の取得マイナス処分)と負債の純増(負債の増加分マイナス減少分)の差額である。海外直接投資に関連する金融取引としては、当該期間にX円の海外M&Aが行われた場合、(議論の単純化のため、内部資金を元手に行われたとして、)「対外直接投資」資産の増加としてプラスXが記録される一方、「現金・預金」資産の減少としてマイナスXが記録され(金融資産の振替)、結果として、資金過不足には影響しない。また、海外子会社からの配当は現金・預金という形で金融資産に、海外子会社の留保利益分は、一旦国内企業に還流した後、再度海外に投資(再投資)されるものとして、「対外直接投資」という金融資産に加算される。
このように、国内居住企業を計測の対象とするSNAにおける非金融法人企業の貯蓄投資バランス等には、当該期に行われた海外M&A分は原則として関係しない。他方、企業の視点に立てば、各期の国内居住企業分の収支バランスとしては、SNA等であくまで統計上擬制的に記録される海外子会社等の留保利益分は勘案すべきでない、という議論はあり得る。仮に、資金過不足から「海外直接投資に関する再投資収益」の純受取分を控除すると、2010年度以降、黒字幅が縮小傾向にあるという点は変わらないが、より縮小が進む姿となり、2022年度は若干の資金不足に転じる(コラム3-2-2図)。ただし、本論で述べたように、2023年度に入ってからは資金余剰幅が再び拡大していることから、現段階において、我が国企業部門の貯蓄超過傾向が解消されたと判断するには尚早であろう。

(設備投資は、フロー面に比べストック面の財務状況により大きく影響)
このように、バブル崩壊以降、我が国企業では、財務面の体質強化が優先され、収益力の増加は主にコストカットと海外需要の取り込みによってもたらされてきた。こうした中で設備投資が抑制されてきたことで、設備の老朽化が進んで資本の平均年齢(ヴィンテージ)は上昇し18、さらには、資本投入寄与が縮小することで潜在成長率が低下してきた。第1章においてみたとおり、過去の景気拡大局面における潜在成長率とその内訳寄与を比較すると、全要素生産性(TFP)上昇率と資本投入の寄与が縮小してきたことが明らかだが、とりわけ2000年代以降は資本投入の寄与が0.1または0.2程度と著しく低下している(前掲第1-1-16図(2))。我が国経済の供給力を強化していくためには、国内の設備投資の拡大が喫緊の課題である。
それでは、企業が設備投資を拡大するうえで、いかなる条件や環境が必要であるか。その手がかりを探るため、設備投資がどのような要因によって影響を受けるのか、国際比較可能な企業財務データに基づく企業単位の投資関数を推計し、アメリカ企業との比較も交えた分析を行う。
一般に、企業の設備投資は、実物資産の収益性と金利コストの差である投資採算性といった基礎的な要因の影響を受けるとされる19。それに加えて、資金調達面についても、借入や社債発行といった外部資金の調達には、内部資金と比べてより大きなコストがかかるため、設備投資は内部資金量の制約による影響も受けると考えられる。また、これ以外の資金調達面からの制約としては、企業が過剰債務を抱えている場合には、財務リスクの高まりにより外部資金調達が困難になり、その分設備投資が制約される可能性がある。
以上のような点を考慮して、ここでは、花崎・羽田(2017)等を踏まえつつ、各企業の設備投資20が、資本の限界生産性の代理変数である資本収益率(ROA)、資本コスト(企業の支払利息の有利子負債残高に対する比率)といった基礎的な要因に加え、内部資金であるキャッシュフロー比率(キャッシュフローの資本ストックに対する比率)及び現預金比率(現金・預金の総資産に対する比率)、負債比率(有利子負債残高の総資産に対する比率)といった要因に影響を受けると想定して、その影響を推計した21。推計にあたっては、Osirisという国際企業財務データベースを用い、上場企業等2,810社(連結ベース22)の1995年度から2022年度までのパネルデータを用いた。また、国際比較の観点から、アメリカの上場企業等3,111社(連結ベース)についても同様に分析を行った。
推計結果の全体を概観すると(第3-1-10図(1))、第一に、投資採算性に相当する基礎的な要因について、資本収益率の係数は日本・アメリカともに有意にプラスであり、資本収益率が高いほど投資が増えるという理論とも整合的な結果となっている。資本コストについては、日本では有意にマイナスとなり、資本コストが高いほど投資が抑制されるとの理論と整合的な結果となっている一方、アメリカでは有意にプラスとなっている。第二に、内部資金に関する要因について、キャッシュフロー比率及び現預金比率の係数は日本では有意にプラスとなり、投資が内部資金の影響を受けるとの結果が示されている。一方のアメリカでは、現預金比率の係数は有意にプラスと日本と同様の結果だが、キャッシュフロー比率については有意にマイナスとなっており、ストック面では内部資金制約が認められる一方、フローでは必ずしもそうではない結果となっている。この点については、アメリカ企業の中に、キャッシュフロー比率の分子に含まれる当期利益が赤字であり、かつ分母である資本ストックが極端に少ない企業がある程度存在することが影響している可能性がある。第三に、負債比率の係数は、日米いずれも有意にマイナスとなっており、高い負債比率は信用リスクや債務の過剰さなどを反映し、外部資金調達が困難になるために投資が抑制されるという理論と整合的な結果となっている。
日米の推計値を比べると、キャッシュフロー比率と資本コストの符号条件には違いがみられた一方で、資本収益率や現預金比率、負債比率については係数の符号、絶対値ともに大きな差は見受けられず、総じてみれば、日米企業の投資行動を規定する要因には目立った違いがみられない形となっている23。
次に、サンプルを製造業と非製造業に分けた推計結果を日米で確認する(第3-1-10図(2))。全体的な推計結果は、製造業、非製造業ともに全産業ベースとおおむね姿が変わらないが、製造業については、日本のキャッシュフロー比率の係数が、全産業とは異なり、アメリカと同様に有意にマイナスとなっている24。
ここで、内部資金の影響に着目すると、第一に、現預金比率については、日米、製造・非製造業ともに有意なプラスであるが、製造業に比べて非製造業の係数が大きくなっている。これは、設備投資がストック面での内部資金によって制約を受ける程度は、日米ともに、製造業に比べて非製造業で相対的に大きいことを示唆している。第二に、キャッシュフロー比率については、アメリカの製造業・非製造業、日本の製造業では有意にマイナスだが、日本の非製造業は有意にプラスとなっており、日本の非製造業ではストック・フローの両面で設備投資が内部資金によって制約を受けている可能性が考えられる。
以上のように、企業の収益性や財務状況は、設備投資に対して影響を持つことが確認され、日米企業ともに、資本収益率やキャッシュフロー比率と比べて、現預金比率や負債比率の係数の影響力が大きいという特徴がある。このことは、設備投資が、直近のフロー面での収益状況よりもストック面での財務状況によって大きく影響を受けることを示唆している。

(投資拡大に向けた条件は整いつつあり、企業の成長期待を引き上げる取組が重要)
このように、今回の設備投資関数の推計結果では、企業が設備投資を拡大するうえでは、収益性のほか、総資産に対する現預金及び負債の規模が重要な条件であることが示された。これまでみてきたとおり、過去20~30年間の対応により、企業の自己資本比率は40%を超えるまで高まり、1990年代と比べて財務体質は格段に強固なものとなっている。また、手元流動性も20%を超え、リーマンショック前(10%程度)と比べても、危機時のリスク耐性も相当程度強化されており、これまでのコストカットや海外向け投資の拡大により、収益力も高まっている。さらに、バブル崩壊後に債務と並んで過剰状態であった雇用と設備についても、日銀短観の雇用人員判断DI及び生産・営業用設備判断DIはいずれも足下で不足超過となっており、歴史的にみても不足感が強い状況にある(第3-1-11図)。
第1項の冒頭でもみたように企業の収益力は過去最高水準に高まっていることに加え、財務体質は過去と比べて相当程度強固なものとなっていることを踏まえると、我が国企業において、今後の投資拡大に向けた環境は十分に整っていることを示唆しているとも考えられる。
一方で、収益力の向上と財務体質の改善は、投資の前提条件であるとしても、それだけで国内設備投資の活発化にはつながらない。この点、国内設備投資の積極化には、企業が我が国経済の成長力に対して持つ期待、つまり期待経済成長率が重要である。企業による今後5年間の我が国経済の実質期待成長率と、設備投資の対キャッシュフロー比率の関係には正の相関があり、また、非製造業では製造業よりも相関が大きい(第3-1-12図)。上述の設備投資関数の推計結果でみたとおり、非製造業では、キャッシュフロー比率と現預金比率の係数が有意にプラスであり、すなわち、フローとストックいずれの面でも内部資金が設備投資に対して正の関係性を有している。このことは、海外展開がより容易で活発な製造業に比べ、内需型産業であり国内市場の成長性が重要な非製造業において、設備投資拡大において国内経済の成長期待とそれに伴う内部資金の増加がより影響力を持つということを示唆している。こうした観点からは、我が国企業の期待成長率を引き上げ、これを通じ国内投資の積極化につなげていくことが極めて重要といえる。



