第1章 マクロ経済の動向(第1節)
第1節 日本経済の動向と持続的な回復に向けた課題
本節ではまず、2023年に入って以降の日本経済の動向を振り返る。その上で、力強さに欠ける個人消費に関して詳細な分析を行い、消費の持続的な回復に向けた課題を整理する。
1 2023年の日本経済と先行き
(コロナ禍からの正常化により、景気は緩やかに回復し、GDPは過去最大に)
まず、我が国の国内総生産(GDP)の動きを確認する。物価変動の影響を除いた実質GDP成長率についてみると(第1-1-1図(1))、2023年1-3月期は、個人消費、設備投資など内需がバランスよく増加したことにより前期比でプラス成長となった。続く4-6月期は、個人消費は物価上昇の影響もあって、また設備投資は前期の高い伸びの反動もあって、それぞれ2四半期ぶりのマイナスとなり、内需は停滞した。一方で、輸出は、半導体の供給制約の緩和による自動車生産の増加やインバウンド需要の回復を主因に増加し、控除項目である輸入の減少1もあいまって、外需が大きく増加したことにより、実質GDP成長率は3四半期連続のプラス成長となった。7-9月期には、個人消費は、飲食などサービス消費は着実に増加が続いたものの、物価上昇の影響が続き、財消費を中心に小幅なマイナスとなった。また、設備投資は、機械投資や建設投資を中心に2四半期連続のマイナスとなり、実質GDP成長率は4四半期ぶりのマイナスとなった。
GDPの水準をみると(第1-1-1図(2))、名目GDPは、2022年10-12月期にコロナ禍前のピーク(2019年7-9月期)を超えた後、物価上昇もあって2023年前半は高い水準が続き、7-9月期は約595兆円と過去最高水準となっている。実質GDPは、物価上昇の影響で名目GDPに比べれば抑制されているものの、2023年4-6月期にはコロナ禍前のピーク(2019年7-9月期)を超えている。
コロナ禍前の2019年10-12月期を起点として、実質GDP水準の動向を主要先進国と比較すると、日本は、アメリカほどではないものの、欧州各国と比べると、コロナ禍前対比で力強く回復してきたことが確認できる(第1-1-1図(3))。ただし、需要項目別にみると、日本は、輸出の回復は他国よりも大きいものの、個人消費の回復はアメリカに比べると弱く、設備投資の回復も相対的に緩やかなものにとどまっていることが分かる。

(個人消費は持ち直しているが、所得の伸びが物価の伸びを下回り、力強さを欠く)
GDPの約55%を占める個人消費は、2022年秋頃から徐々に持ち直しの動きがみられており、名目では、比較可能な1980年以降で過去最高の水準に達している。一方、物価上昇の影響もあって、実質では、コロナ禍前の水準を超えて持ち直してはいるものの、力強さを欠いている(第1-1-2図(1))。
この背景として所得面をみると、雇用者報酬は、名目では、30年ぶりの高い賃上げもあって増加基調にあるものの、名目賃金の上昇が物価上昇を下回っていることから、実質では減少傾向が続いている(第1-1-2図(2))。次に、雇用者報酬に加え、自営業主の利益や利子・配当等の財産所得、年金等の給付を加え、税や社会保険料等の負担を控除した家計可処分所得をみると、名目では、コロナ禍における各種給付金の影響による振れはみられるが、大宗を占める雇用者報酬の動きを反映して、緩やかな増加基調にある。ただし、今回の物価上昇局面における名目家計可処分所得の動きを分解すると、過去2年間で、雇用者報酬を中心に収入は増加した一方、所得税等の直接税や社会保険料が増加していることから、可処分所得の伸びは雇用者報酬の伸びをやや下回っている。また、実質では、名目可処分所得の伸びが物価の伸びに追い付いていないため、雇用者報酬と同様に減少傾向が続いている(第1-1-2図(3))。
次に、個人消費を耐久財(自動車、家電等)、半耐久財(衣服等)、非耐久財(食料品や消耗品等)、サービスの4形態別にみると、約56%と過半を占めるサービス消費は、2023年5月に新型コロナが5類に移行し、経済社会活動の正常化が進んだことにより、飲食や宿泊等の対面サービスを中心に回復が続いている(第1-1-2図(4)、(5))。一方、財消費については、物価上昇の影響で食料品等の非耐久財が2023年4-6月期以降前期比マイナスで推移し、耐久財も後述する自動車における特殊要因もあって減少しているなど、全体として個人消費が力強さを欠く要因となっている。
このように、物価上昇による雇用者報酬など所得の実質ベースでの減少傾向は、財消費の下押し要因となっているが、個人消費全体として、実質所得に比べて、2023年4-6月期以降の減少が抑制されているのは、過半を占めるサービス消費が、コロナ禍での消費機会の制約による大きな落ち込み・停滞からの回復過程の中で着実に増加してきていることによる。

(経済社会活動の正常化が進む中で、対面サービス消費は増加傾向が継続)
次に、サービス消費の動向を、各種統計・データから確認する。まず、旅行について、日本人の国内延べ宿泊者数は、全国旅行支援が2022年秋以降の押上げ要因となっていたが、2023年のゴールデンウィークに一時停止されたことなどから2、一旦減少した。その後、各都道府県で支援策が終了に向かう中にあっても、持ち直しの動きが続いている(第1-1-3図(1))。また、鉄道旅客数や航空旅客数共に持ち直し傾向が続いている(第1-1-3図(2)、(3))。一方、海外旅行について、出国日本人数をみると、コロナ禍後、着実に回復しているものの、コロナ禍前対比では6割程度の水準にとどまっている(第1-1-3図(4))。海外旅行消費(居住者家計の海外での直接購入)の名目値は、コロナ禍前の9割弱まで回復しており、この間、デフレーター3はコロナ禍前(2019年平均)対比で5割強上昇していることから、海外の物価上昇と為替レートの円安により、海外旅行需要の回復が抑制されているといえる。
外食については、物価上昇もあり名目額の増加が続くとともに、物価変動の影響を除いた実質でみても緩やかな増加基調にあり、コロナ禍前の水準をほぼ回復している(第1-1-3図(5))。内訳をみると、ファーストフードの回復が顕著である一方、居酒屋等では名目でみてもコロナ禍前対比で7割までの回復となっており、第2章で述べるように、テレワークの一定の定着もあって、こうした一部サービスにおいては消費水準が構造的に低下している可能性がある(第1-1-3図(6))。

(財消費は、物価上昇の影響もあって減少)
次に、財消費に目を向けると、新車販売台数は、2022年後半頃から、生産面における半導体の供給制約が徐々に緩和されてきたことにより、2023年に入る頃から大きく増加し、消費の持ち直しを支えてきた。秋頃にかけては、生産水準がコロナ禍前近くの水準に回復し、これまで供給制約で積み上がってきた受注残高が徐々に取り崩される中で、新車販売台数の増加ペースは落ち着いてきた。この間、7月から10月にかけて、部品工場の火災やシステムの不具合等による工場稼働停止という一時的要因が重なり、増減を繰り返す不安定な動きが続いた。さらに、12月下旬には、一部メーカーにおいて、国の認証取得の不正問題に伴う全面的な生産・出荷停止が生じたこともあって、新車販売台数は下押しされている(第1-1-4図(1))。
家電販売は、コロナ禍での巣ごもり需要による増加の後、テレビやパソコンを中心に、2023年前半まで弱い状況が続いたが、2023年夏以降は増加傾向で推移している(第1-1-4図(2))。背景には、①エアコンが、2023年夏の猛暑の影響で販売が増加したこと、②インバウンドの回復に伴い外国人旅行者による理美容家電やゲーム機、携帯電話などの持ち帰り可能な家電消費も増加しているとみられること、③関西地方でプロ野球チームの優勝に伴い家電消費が9月及び11月に大幅に増加したことなど複合的な要因がある。こうした要因を割り引いて考えると、家電販売は、全体としては下げ止まり、おおむね横ばい圏内の動きとなっている4。
財のうち食料品や日用品といった非耐久財消費の動向として、食料品については、コロナ禍以降の中期的なスパンでは、外食消費との代替により減少傾向にある。スーパーの食料品売上高と外食の売上高を実質化して、コロナ禍前対比の水準を比較すると、コロナ禍で外食消費は大きく落ち込んだ後、振れを伴いながらも徐々にコロナ禍前水準に回復しているのに対し、スーパーの食料品については、対照的に、巣ごもり需要で大きく増加した後は減少傾向にある(第1-1-4図(3))。さらに、足下までみると、2023年初以降、外食がコロナ禍前水準におおむね回復する一方、スーパーマーケットの食料品はコロナ禍前の水準を下回っており、物価上昇による押下げも影響しているとみられる5。POSデータを用い、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストアの売上動向を確認すると、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの売上高は、食料品を中心に価格転嫁が進んだことで、価格効果6が主な押上げ要因となり、2022年末以降、前年比で増加が続いている(第1-1-4図(4)、(5))。一方、数量効果は、食料品等の価格上昇による買い控えを背景に前年比でマイナス傾向が続いていると考えられる。
また、ドラッグストアの動向をみると、2022年央以降、商品入替効果によって前年比での売上高増加が続く中で、数量効果についてはわずかなマイナスにとどまっている(第1-1-4図(6))。コロナ禍前からの比較でみると、ドラッグストアは売上高を約4割増加させており、増分の6割強は食料品や日用品による(第1-1-4図(7))。ドラッグストアでは、保存性が高い商品を比較的安価で取り扱っていることから、物価上昇の中での消費者の低価格志向に対応し、需要を取り込んでいると考えられる。

(個人消費の持続的な回復には、実質所得の継続的な増加が重要)
個人消費の先行きに関しては、まず消費者マインドは、コロナ禍後の経済正常化の本格化への期待もあって、2023年春頃から持ち直してきたが、秋頃には物価上昇の影響から一時的に持ち直しに足踏みがみられた(第1-1-5図(1))。食料品等の物価上昇は特に低所得者層への影響が大きく(第1-1-5図(2))、消費者が物価動向への警戒感を高めていたとみられるが、後述するように食料品の値上げ一服によって消費者物価の上昇がこのところ緩やかになっており、2023年末には、消費者マインドは再び持ち直している。また、本節次項で後述するように、コロナ禍で積み上がった家計の超過貯蓄は全体として引き続き高水準にあり、これが取り崩されていけば、個人消費の増加を支える要素となる。
一方、個人消費の持続的な回復には、購買力の増加、すなわち、名目所得の伸びが物価の伸びを上回って推移する姿が継続的に実現するという見通しが重要である。この観点からは、本章第2節でも述べるように、2024年度において、春闘に代表される賃上げが力強いものとなることが極めて重要となる。
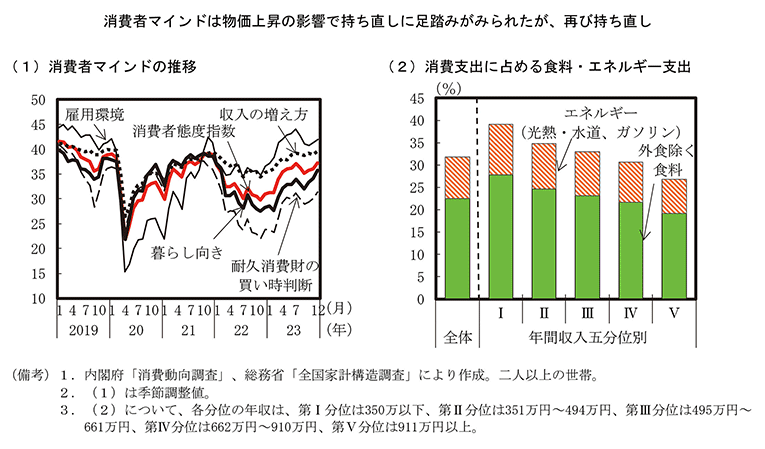
(雇用情勢は改善の動きが続く一方、人手不足感はバブル期以降の過去最高水準に)
雇用情勢については、改善の動きが続いている(第1-1-6図(1))。完全失業率は、コロナ禍からの経済の回復に伴い、2021年、22年と緩やかな低下傾向を続けた後、2023年に入ってからは、自己都合による離職や新たな求職活動の増加により上昇するなど、やや振れのある動きとなったが、コロナ禍前の2019年の平均(2.4%)に近い水準で推移している。就業率(15歳以上人口に占める就業者数の割合)については、第2章でも述べるように、女性の正規雇用者の増加を主な要因として、2023年春にコロナ禍前のピークを上回った後も、緩やかな上昇傾向で推移している。就業者数としては、コロナ禍前の2018年から約190万人増加しているが、産業別にみると、卸売・小売業が2018年対比で減少しているほか、コロナ禍で大きく減少した宿泊・飲食は、2022年以降、回復傾向にあるが、依然としてコロナ禍前の水準を下回っている。一方、医療・福祉や情報通信の就業者数は、コロナ禍前に比べ大幅に増加しており、それぞれ高齢化の進行の下での需要、デジタル化の進展を背景とした需要の増加が影響しているものとみられる(第1-1-6図(2))。
企業の人手不足感に目を転じると、日銀短観の雇用人員判断DIは、全規模全産業で、バブル期以降最大の不足超となっている。特に、中小企業の非製造業については、バブル期やコロナ前のピークも超えて過去最大の不足超となっている(第1-1-6図(3))。非製造業における人手不足感を業種別にみると、コロナ禍後の経済正常化やインバウンド復活で需要が回復している宿泊・飲食のほか、建設、運輸など幅広い業種で不足超幅の拡大傾向が続いている(第1-1-6図(4))。
一方、公共職業安定所(ハローワーク)における求人動向をみると、新規求人数は、2022年末までは緩やかに増加してきた後、2023年以降は全体として横ばい圏内で推移し、有効求人倍率も同様の動きとなっている(第1-1-6図(5))。有効求人倍率は1倍を超え、求職者一人に対して一つ以上の求人数があるという、需給ひっ迫の状態を示す。職種別にみると、建設や介護・医療、宿泊・飲食、自動車運転といった職種の有効求人倍率は平均を大きく上回っているという点では、上述の人手不足感における傾向と同様である(第1-1-6図(6))。しかしながら、過去においては、人手不足感と有効求人倍率の相関が高かったが、コロナ禍からの回復局面では、人手不足感(全規模全産業)がコロナ禍前ピーク近くまで高まっているのとは対照的に、有効求人倍率は、コロナ禍前ピークを下回った状態にあり、かい離が近年大きくなっている(第1-1-6図(7))。

(求人動向の把握に際しては、ハローワークに加えて、多様な経路を確認する必要)
こうしたかい離の背景の一つには、労働需給のマッチングの場が、ハローワークから民間職業紹介を含む多様なチャンネルにシフトしていることがある。実際、入職経路別の入職者の割合をみると、ハローワークのシェアはこの10年程度で約27%から15%まで低下し、広告のほか、民間職業紹介所のシェアが高まっている(第1-1-7図(1))。民間職業紹介の求人件数をみると、正社員の求人件数は着実に増加が続き、パート・アルバイトは、直近では頭打ち傾向にあるものの、コロナ禍前を超えた高水準で推移している(第1-1-7図(2))。また、デジタル化に伴う求職手段の多様化が進む中、ハローワークを通じた求職者の属性の変化も、有効求人倍率の上昇が相対的に弱い背景となっている可能性もある。具体的には、ハローワークを活用している失業者数の動向を求職経路別・年齢階級別にみると(第1-1-7図(3))、2019年対比で、高年齢層で増加し、相対的に若い年齢層では減少している。仕事に就けない理由別にみると、2019年対比で増加しているのは、希望する職種・内容の仕事がない等となっている。ハローワークを主に利用する求職者において、比較的マッチングが難しい高年齢層が増加していることが、有効求人倍率の改善を抑制する一因となっている可能性がある。加えて、宿泊・飲食など比較的若年の非正規雇用へのニーズが高い分野では、若年層がハローワークを利用しない傾向が強まっていることから、ハローワークには求人を出さず、他の媒体に求人をシフトさせるという変化が生じている可能性もある。特に、パート・アルバイトについては、民間職業紹介や広告等を介しない、いわゆるすき間時間を活用したスポットワークという形での求人・求職が増加しており7、ハローワークにおける求人のみならず、上述の民間職業紹介等を通じたパート・アルバイト求人件数の頭打ち傾向にもつながっている可能性も考えられる。
なお、ハローワークを活用している失業者の動向を失業期間別にみると、コロナ禍前対比で、1か月未満の短期失業者が増加傾向にある(第1-1-7図(3))。雇用保険における失業給付の支給状況をみると、基本手当と比べ、高年齢求職者給付金の受給者数は高止まっている。高年齢受給者は、求職活動を継続していることが失業給付の受給要件とはならないこと等により8、就職意欲がない場合であっても、短期的にハローワークを利用することで失業給付を受給している者が存在している可能性も考えられる。こうした点も、統計上、有効求人倍率の改善を抑制し得る要因となる(第1-1-7図(4))。
このように、求人動向を把握する上では、ハローワークのデータのみならず、民間職業紹介を通じた求人動向、さらには、近年、企業・労働の双方で活用が広がっているスポットワークのマッチングサービスなど幅広いデータをみていくことが重要である。

(住宅の新設着工戸数は、建築費の高止まりから、持家を中心に弱含みが続く)
住宅建設については、新設着工戸数が、年率80万戸程度に減少し、全体として弱含んでいる(第1-1-8図(1))。利用関係別にみると、持家(注文住宅)の着工戸数は、木材価格の上昇は一服したものの、コンクリート等の資材価格の上昇が続いていることや、労務費の上昇により、建築費は高止まりしている(第1-1-8図(2))。こうしたコスト高が個人の持家の建設需要の下押しにつながっていると考えられる。
貸家の着工戸数は、横ばいとなっている。建築主別にみると、会社(不動産会社やREIT)による建設は、住宅購入価格が上昇する中で、二人以上世帯向けの旺盛な賃貸需要を背景に、引き続き底堅い。一方、個人建築主による建設は、2022年末以降、前年比で減少傾向が続いているが、これは、建築費が上昇する下で、賃料の上昇が限定的であり、長期金利の上昇もあいまって、収益性が低下していることが背景にあると考えられる(第1-1-8図(3))。
分譲住宅の着工戸数については、戸建分譲(建売住宅)は、持家(注文住宅)と同様に、主に建築費の高止まりにより弱含んできたが、持家に比べコスト面での優位性があることも反映し、下げ止まりつつある。共同分譲(マンション)は、大規模物件の着工の有無によって振れが大きいが、建築費の上昇のほか、適当な用地の取得に時間を要するといった供給制約9もあいまって弱含んでいる(第1-1-8図(4))。
このように住宅の新設着工戸数は全体として弱含んでいるが、GDP上の住宅投資の約1割を占める既存住宅の改装・改修(リフォーム)の動向をみると、住宅リフォームの受注は、省エネリフォームへの各種補助金の効果10もあって、2023年以降、工事費上昇の影響を除いた実質ベースでも対前年比で増加している(第1-1-8図(5))。住宅については、中長期的には人口減少の進行が新設着工戸数の下押し要因となり続ける中で、既存の住宅をリフォームにより維持、機能向上して使用する動きが増していく可能性があり、景気動向を判断する上でも、住宅建設のみならず住宅リフォームの動向も確認していくことが重要である。

(企業の業況や収益は共に好調)
次に、企業部門の動向を確認する。日銀短観から企業の業況判断DIをみると(第1-1-9図(1))、売上高の7割を占める非製造業では、コロナ禍から平時へと移行する中で、娯楽や宿泊・飲食などの対面サービス、卸売・小売などを中心に、2023年12月調査にかけて7期連続で改善している。業況判断DIの水準は、大企業・中小企業共に、バブル期以降の最高水準にある。また、製造業では、大企業は、自動車生産の回復や世界的な半導体市況の底打ちなども背景に、3期連続で改善している。また、これまではマイナス圏で推移し、厳しさが残っていた中小企業でも、2期ぶりに改善し、2019年3月調査以来、4年3期ぶりに「良い」が「悪い」を上回り、プラス圏に浮上した。このように、企業の業況は、規模・業種を問わず幅広く改善がみられる。
こうした業況の改善の背景には、企業の収益の改善がある。企業の経常利益や、本業の利益を示す営業利益は、売上の回復が続く中、2023年7-9月期には過去最高を更新した(第1-1-9図(2))。業種別に経常利益の前年同期比の動向をみると(第1-1-9図(3))、製造業では、供給制約の緩和による自動車販売の回復及び円安による収益改善があった輸送用機械や、2022年以降原材料費等の高騰を販売価格に転嫁することに成功した食料品製造業が大きくプラスに寄与する一方、これまでの半導体市況の低迷により情報通信機械がマイナスに寄与している。非製造業については、経済社会活動の正常化を受けて、小売業や飲食サービスを含め、幅広い業種において増益となっている。
製造業、非製造業ごとに売上高経常利益率の前年同期からの変化幅を要因分解すると(第1-1-9図(4))、製造業では、売上高原価率の寄与は、今回の輸入物価を起点とする物価上昇局面で原価コストの増加によりマイナス寄与が続いてきたが、資源価格の落ち着きにより、2023年7-9月期にはプラス寄与に転じている。非製造業についても、売上高原価率の寄与は、2022年中はマイナス寄与が続いていたが、中間投入に占める財の割合が低いことから原材料価格上昇の影響が相対的に小さく、2023年以降は、経済社会活動の正常化が進む下で、売上が大きく回復したこともあり、プラス寄与に転じている11。このように、企業部門は全体として好調であるが、収益の回復が賃金や投資に必ずしも回っていない状況にある点は留意が必要である。

(倒産件数はコロナ禍前の水準を超えて高まっているが、長期的には低い水準)
企業収益が好調さを増す中で、倒産件数をみると、コロナ禍の2020年中は、各種の資金繰り支援もあり低下傾向で推移し、2021年に入ってからは月当たり500件程度に抑制されていたが、2022年秋以降、経済活動が正常化に向い、資金繰り支援が終了していく中で増加傾向に転じ、2023年12月は月841件(季節調整値)と、2014年9月(868件)以来の水準となっている(第1-1-10図(1))。倒産件数を業種別・規模別にみると、飲食や娯楽といったサービス関連業種で件数が多く、増加基調にあり(第1-1-10図(2))、従業員規模別では10人未満の小規模企業が約9割、負債金額別では1億円未満の企業が約4分の3と多くを占めている(第1-1-10図(3))。このように、現在の倒産は、過去の金融危機等による景気悪化局面でみられたような大規模企業の倒産が増加するという状況にはない。また、長期的な倒産件数の動向をみると、バブル期前の1980年代前半は、現在の倍程度の月1,500件前後で、負債金額が比較的大きい倒産が多いなど構成も異なっていたことが分かる(第1-1-10図(4))。
なお、コロナ禍において民間金融機関を通じた実質無利子・無担保融資(以下「ゼロゼロ融資」という。)を受けた中小事業者は、元本返済が不要な据置期間を3年に設定するケースが多くみられた。支援開始から3年以上が経過する中で、支援先中小事業者にどのような変化が現れているのかを確認する。具体的には、2023年3月末時点から8月末時点にかけての支援先中小事業者の状況の変化をみると(第1-1-10図(5))、据置期間中の割合は低下する中で、完済や借換の割合が増加する一方、条件変更や代位弁済の割合は微増にとどまっている。借換については、2023年1月から開始されたコロナ借換保証(ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度)の利用事業者の増加によるものであるが、同制度は、事業者が経営行動計画書を作成した上で、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を引き下げるものであり、中小事業者の事業再構築につながることが期待される。条件変更については、金融機関の応諾率(実行率)は99%程度と高い水準にあり(第1-1-10図(6))、中小企業の資金繰り判断DIも安定している(第1-1-10図(7))。現時点において、ゼロゼロ融資の返済開始が中小事業者の事業継続に悪影響を及ぼしているわけではないといえる。人手不足や物価上昇の影響を含め12、中小事業者の倒産動向には注視していくことが必要である。

(生産は、一部自動車メーカーの生産・出荷停止の影響に注意が必要)
2023年の生産動向について、鉱工業生産指数から確認すると(第1-1-11図(1))、年初は、市況の悪化に伴う半導体の在庫調整と、それを受けた海外での半導体製造装置の投資先送り等により、電子部品・デバイスや生産用機械でマイナス傾向となるなど弱含んでいた。一方、2021年秋から続いてきた半導体の供給制約が緩和される中で、2023年春以降、輸送用機械の増加傾向が強まり、また、半導体市況の底打ちにより、2023年半ば以降、電子部品・デバイスが下げ止まり、振れを伴いながら増加傾向に転じるなど、生産は、全体として持ち直しの兆しがみられてきた。
輸送用機械は、2023年の夏から秋にかけ、火災やシステム不具合等による工場稼働停止の影響を受けつつも底堅い動きで推移してきた。ただし、12月下旬には、国の認証取得の不正問題により、一部自動車メーカーにおける全工場の生産・出荷が停止されることとなった。同社は、他メーカーの車種の受注生産を含め自動車国内生産台数の1割強を占めるほか、部品をはじめとする裾野分野への影響もあることから、今後の輸送用機械の生産動向等には注意が必要な状況となっている(第1-1-11図(2))。
生産用機械については、2022年秋頃にかけて、半導体製造装置や建設・鉱山機械を中心に大きく増加したが、半導体製造装置は、世界的な半導体需要の減少の影響もあって、納期延長等がみられたことで、2023年初にかけて減少し、その後もおおむね横ばいの動きとなっている。先行きについては、世界の半導体製造産業は2023年10-12月期を底に回復したものと見込まれており、今後、我が国の生産にも前向きな影響をもたらすことが期待される。また、建設・鉱山機械は、アメリカを中心に、住宅需要や資源開発等が堅調に推移する中で増加傾向が続いている(第1-1-11図(3))。
電子部品・デバイスは、2023年初以降、在庫の前年比増加幅の縮小が進み、夏以降は増加から減少に転じる一方、出荷の前年比減少幅が縮小することで、出荷・在庫ギャップがプラスに転じており、在庫循環上、回復局面に転じているとみられる(第1-1-11図(4))。先行きについては、生成AI向けの需要が堅調であるほか、世界のPCやスマートフォン出荷台数も底打ちしたとみられ(第1-1-11図(5))、世界的なIC売上高は、2024年にはプラスに転じ、2022年の水準を超えると見込まれている(第1-1-11図(6))。これらに伴って我が国の電子部品・デバイスの生産も持ち直しが続くことが期待される。

(企業の設備投資計画は堅調である一方、実際の投資に結び付いていない)
設備投資は、2020年4-6月期に大きく減少した後、振れを伴いながらも持ち直し、名目では、2023年1-3月期に年率99兆円と、バブル期以来の100兆円に迫る水準にまで増加した。しかしながら、2023年度に入ってからは、名目ではほぼ横ばい、実質では2四半期連続で減少するなど、持ち直しに足踏みがみられる状況となっている。一方で、日銀短観の設備投資計画では、2023年12月調査時点で、2023年度の設備投資は前年度比+12.6%と堅調な伸びが示されている。このように、企業の投資意欲は強いものの、これが実際の設備投資として現れていない状況にあるといえる(第1-1-12図(1)、(2))。
まず、設備投資の約45%を占める機械投資をみると、一致指数である資本財総供給(除く輸送用機械)は、その約7割を占める国産品を中心に軟調に推移している(第1-1-12図(3))。国内出荷分に加えて輸出分を含む点に留意する必要があるが、資本財出荷を品目別にみると、研究開発等に広く用いられる分析機器等は堅調に推移する一方で、半導体製造装置や産業用ロボットがこのところ減少傾向にある(第1-1-12図(4))。原材料費等のコスト上昇やこれまでの世界的な半導体需要の減少の影響のほか、不動産市場問題が長引く中国を中心とした海外経済に係る不透明感等を背景に、機械設備を購入する需要側において納入の延期等があったものと考えられる。
機械投資の先行指標である機械受注の民需(除く船舶・電力)も、2023年半ば以降はおおむね横ばいとなっているが、電力を含む民需全体では、2022年末頃以降、振れはあるものの相対的には堅調に推移してきた(第1-1-12図(5))。日本政策投資銀行「2023年度設備投資計画調査」によると、電力会社では原子力関連投資や既存火力の維持更新投資等が計画されており、それらが反映されていると考えられる。また、機械受注の受注残高は高水準が続いており、物価上昇の影響を受けないとみられる手持月数も高水準となっている(第1-1-12図(6))。受注残高には、民需のほか外需や公需が含まれる点には留意が必要であるが、民需分についても相応の受注残が蓄積されているとみられる。発注企業による納入の延期や、キャンセルの動きが大きくならない限りは、こうした受注残が、今後、実際の販売すなわち設備投資として顕在化するものと期待される。
次に、設備投資の約25%を占める建設投資をみると、GDPの設備投資に反映される民間の建築・土木の工事出来高は、2023年春頃から減少傾向にあった(第1-1-12図(7))。この背景には、既往の大型案件の工事が進捗した結果、工事出来高の増加が一服したことが影響している。具体的には、先行指標である建設工事費予定額は、2022年春から秋頃にかけて、大手半導体メーカーの工場新設を中心とした大型案件が相次いだことで大きく増加した。着工が開始された案件は、進捗に応じて工事出来高として徐々に表れるため、建設工事出来高は、予定額の動きにある程度遅れる形で2022年の後半から2023年初にかけて大きく増加したが、建設工事費予定額が2022年秋以降減少局面に転じたことを受け、2023年春以降は減少した。ただし、建設工事費予定額は、2023年秋以降、半導体や倉庫関連の大型案件のほか、製造業等で広く工事着工がみられ、再び増加に転じている(第1-1-12図(7))。今後、これらの案件の進捗が進むにつれて、工事出来高についても、再び増加局面に転じると見込まれる。なお、建設コスト増や労働者不足に伴う工事の着工延期や工期長期化の可能性には留意が必要である。
設備投資の約30%を占める知的財産生産物のうちソフトウェア投資をみると、販売側統計である「特定サービス産業動態調査」、購入側統計である「法人企業統計」のいずれでみても増勢が続いている(第1-1-12図(8)(9))。労務費上昇に伴いソフトウェアの販売価格が上昇している面はあるが、実質化した場合でも、前年比で高い伸びが続いている。デジタル化の進展、人手不足への対応としての省力化投資が相応に進んでいるとみられ、ソフトウェア投資は総じて堅調といえる。また、設備投資の20%を占める研究開発投資も、2023年度は堅調に増加する見込みとなっている(第1-1-12図(10))。
このように、機械投資や建設投資を中心に、設備投資は持ち直しに足踏みがみられているが、堅調な企業収益に加え、機械受注残高や建設工事費予定額等の動向を踏まえれば、今後再び持ち直しに向かうことが期待される。

(財の輸出は、自動車生産の回復を中心とした持ち直しの動きに足踏み)
次に、外需の動向をみる。まず、財の輸出(輸出数量指数)は、2022年半ばから半導体市況が悪化する中で、アジア向けを中心に弱い動きが続いてきたが、2023年に入り、供給制約の緩和を背景に自動車の輸出が急速に持ち直し、また、2023年央には、世界的な半導体需要の底打ちも背景としてICを中心に情報関連財も下げ止まるなど、輸出全体として、持ち直しの動きがみられるようになった(第1-1-13図(1))。ただし、中国向け工作機械などアジア向けの資本財輸出は低調であるほか、欧州経済の弱さを反映して、2023年末には持ち直しの動きに足踏みがみられている。
日本の輸出先の約56%を占めるアジア向けについてみると(第1-1-13図(2))、上述のとおり、2022年半ば以降、情報関連財を中心に機械機器が減少に大きく寄与してきたが、IC等情報関連財の下げ止まりや自動車関連財の増加等により、持ち直しの動きがみられてきた。この間、輸出先の約19%を占める中国向けについては、中国の製造業部門が軟調に推移していることを受け、工作機械の減少が続いている一方、ICや半導体製造装置といった情報関連財は回復している(第1-1-13図(3)、(4))13。また、これまで悪化が続いてきた世界的な半導体需要の底打ちにより、経済状況が改善している台湾や韓国向けの輸出も情報関連財を中心に下げ止まっている。
一方、輸出先の約19%を占めるアメリカ向け輸出についてみると(第1-1-13図(5))、アメリカ経済が、堅調な個人消費を中心に回復が続いていることを背景に、2023年に入って以降、機械機器を中心に増加し、持ち直し基調が続いている。供給制約の緩和を背景とした自動車の増加に加え、住宅需要や資源開発等が堅調に推移する中で建設用・鉱山用機械の増加がけん引してきた。また、EU向け輸出(輸出先の約10%)は(第1-1-13図(6))、2023年春以降、持ち直し傾向にあったが、ドイツを中心とする欧州経済の弱まりを受けて、情報関連財や資本財を中心に弱含んでいる。中南米や中東などその他地域向け(輸出先の約15%)は(第1-1-13図(7)、(8))、輸出金額の半分近くを占める輸送用機械の輸出にけん引されて増加してきたが、2023年夏以降はこの動きが一服し、おおむね横ばいで推移している14。
先行きについては、世界経済の持ち直しが続く中、持ち直していくことが期待される。ただし、アメリカにおける既往の金融引締めが同国の経済に与える影響、不動産市場の停滞が続く中国の下振れリスク及びこれに伴うアジア経済への影響など輸出の先行きについては十分な注意が必要である。
一方、財の輸入(輸入数量指数)は、2022年秋以降減少してきたが、2023年春以降は下げ止まり、全体としておおむね横ばいの動きが続いている(第1-1-13図(9))。品目別に15みると(第1-1-13図(10))、輸入総額の28.4%を占める鉱物性燃料は、電力向けのLNG在庫の積み上がりもあって、2023年4-6月期にかけて減少したが、その後は下げ止まっている。また、27.5%を占める機械機器は、国内のパソコン需要の低迷等を受けてアジアからの電算機類やICの輸入が軟調に推移する一方、2023年夏頃にかけて大きく減少した携帯電話機は、新製品発売の効果もあって8月から急回復し、全体として横ばいで推移した。11.5%を占める化学製品は、新型コロナワクチンの減少もあって、2023年央にかけて減少してきたが、2023年秋開始接種に伴いワクチンの輸入が増えるなど持ち直しの動きがみられた。

(サービス貿易はインバウンドで輸出が回復の一方、デジタル関連中心に輸入が増加)
サービス貿易に目を転じると、輸出については、2022年10月に政府の水際対策が緩和16されて以降、インバウンドが大幅に回復した。訪日外客数は2023年10月に252万人と、コロナ前の2019年同月の水準に回復し、2023年12月時点では2019年同月を1割弱上回っている(第1-1-14図(1))。国・地域別にみると、コロナ禍前に3割前後で最大の割合を占めていた中国からの旅行者数は、持ち直し傾向にはあるものの、コロナ禍前の水準の回復にはなお距離がある17。他方、訪日外客数の回復をけん引しているのは、韓国、台湾などであり、中国以外からの旅行者数は、2023年7月以降、コロナ禍前(2019年同月)の水準を継続的に上回っている。
訪日外国人消費額をみると、2019年の4.8兆円から2023年には5.3兆円に増加し、過去最高となった。一人当たり消費額では、同期間に15.9万円から21.2万円に増加している。1人当たり消費額の増加は、この間、為替レートが大幅な円安となっている影響も大きいとみられるが、訪日外国人の平均宿泊日数をみると2019年の6.1日から2023年は6.9日に増加しており、為替変動の影響を割り引いてみても、訪日外国人の消費は堅調に回復しているといえる(第1-1-14図(2))。
一方、アウトバウンドについては、個人消費の項でも触れたとおり、持ち直しはみられるものの、海外における物価上昇と円安を受け、出国者数や実質海外旅行消費額のコロナ禍前への回復は道半ばにある(前掲第1-1-3図(4))。
こうした旅行関係を除いたサービスの輸出入18の動向をみると、近年、輸入が拡大傾向にあり、実質GDP成長率を押し下げる要因となっている19。これらサービス輸出入のGDP成長率への寄与度について2018年を起点とした動きをみると、コロナ禍までは、サービス輸入の拡大がGDP成長率を押し下げる方向に作用し、コロナ禍でサービス輸出入が共に減少し、一旦、この動きが落ち着いたが、コロナ禍を経て、近年、再びサービス輸入の拡大がGDP成長率を押し下げる方向に寄与している(第1-1-14図(3))。
この背景について、国際収支統計から、2018年対比で、サービス収支の変化を項目別にみると、専門・経営コンサルティングサービス(ウェブ広告サービスを含む)や著作権使用料(動画配信サービスを含む)といったデジタル関連で赤字が拡大しているほか、自然災害の頻発による損害保険の再保険料の上昇等を背景に保険・年金サービスの赤字も拡大している(第1-1-14図(4))20。これらには円安の影響も多分に含まれると考えられるが、コロナ禍を契機にデジタル化の流れが一層進む中、デジタル関連サービスを中心とした日本のサービスの競争力の向上も課題となっている。

(脱炭素化の流れを踏まえた自動車関連財の競争力の強化が重要)
デジタル化に加えて、グリーン化・脱炭素化の流れも、日本の外需に大きな影響を与えている。上述のとおり、2023年の輸出の持ち直しの動きは、主に自動車の生産回復に支えられており、乗用車の輸出台数は、2023年10月には2019年平均を上回った(第1-1-15図(1))。これをパワートレイン(エンジンやモーター、変速機や車軸などを含めた動力を駆動輪に伝える装置)別にみると(第1-1-15図(2))、総台数の大半を占めるガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車(ICEV)は、持ち直しに寄与してはいるものの、コロナ前との比較では8割程度の回復にとどまっており、電動車(ハイブリッド車:HV、プラグインハイブリッド車:PHV、電気自動車:EV)がコロナ禍前の水準への回復のけん引役となっている。この背景には、各国における気候変動対策としての脱炭素化の動きがあり、各国・地域において自動車の電動化の目標等が掲げられる中21、世界の乗用車輸出台数に占める電動車のシェアは、2019年から2022年にかけて、ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車は91.4%から75.6%に低下した一方、HVは4.8%から11.1%に、PHVは1.1%から3.8%に、EVは2.3%から8.0%にそれぞれ上昇した(第1-1-15図(3))。日本の主な乗用車輸出先国・地域における乗用車国内販売台数に占める電動車の比率をみると、いずれも2019年から2022年にかけて上昇しており、乗用車の電動車シフト、とりわけEVへのシフトが顕著であることが分かる(第1-1-15図(4))。
こうしたEV化に伴い、自動車部品についても需要構造が変化するとみられる。自動車部品について、2022年のデータをもとに顕示比較優位(RCA)指数22を算出すると(第1-1-15図(5))、日本はトランスミッション、点火・始動用装置、エンジン部品などで輸出競争力が高いが、こうした部品はICEVに利用され、EVには基本的に搭載されないため、世界的な自動車のEV化が進展するにつれて需要が縮小する可能性が高い。この点、中国の自動車部品のRCA指数をみると、リチウムイオン電池やスタティックコンバーターなど、自動車の電動化の進展により需要の拡大が見込まれる部品の輸出競争力が高いことが分かる。2022年の世界の輸出金額について2019年からの変化を品目別にみると、トランスミッションとエンジン等は2019年の水準を下回る一方、スタティックコンバーター等は同水準を大幅に上回っている。
自動車は日本の輸出において主力品目であるうえ、産業としての裾野が広く、輸出の多寡は生産や雇用など経済に大きな影響を与える。世界的に自動車のEV化が進展する中、部品も含めた自動車産業全体の競争力維持のため、EV化に向けた生産へのシフトや、そのための研究開発、新規の設備投資が一層重要となろう。

(潜在成長率は主要先進国の中で低水準にとどまり、供給力の引上げが課題)
これまでみてきたように、コロナ禍からの経済社会活動の正常化が進む中で、景気は緩やかな回復基調にあり、企業部門は業況や収益の観点で非常に好調であるものの、その好調さが賃金や投資に必ずしも回っておらず、個人消費や企業の設備投資などの内需は力強さを欠いている。
加えて、供給力の面でも課題がある。1990年代のバブル崩壊以降、長引くデフレ等を背景に、企業は収益の確保のために、賃金や成長の源泉である投資を抑制し、結果として低成長が続いた。設備投資の抑制は、生産的資本ストックの蓄積を妨げ、これを主因として我が国の潜在成長率は0%台と、G7諸国の中でも最も低くとどまっている(第1-1-16図(1))。
具体的に、我が国のこれまでの景気拡大局面における潜在成長率について、資本投入、労働投入、全要素生産性(TFP)の3つの要素に分解すると、1980、90年代の景気拡大局面では、労働投入の寄与がわずかなプラスないしマイナスの中、資本投入と生産性(TFP)の伸びが潜在成長率を引き上げていたが、近年は、特に資本投入の寄与が0.1%程度にまで低下している(第1-1-16図(2))。潜在成長率の引上げのためには、3つの要素それぞれについて対処が必要となる。労働投入の面では、人口減少の進展が下押し圧力となる中で、人々が意欲と能力に応じて労働市場で活躍できるよう、就業調整を解消するための「年収の壁」への対応や、リ・スキリングの拡充、副業の促進などが重要となる。関連する論点は第2章で扱う。また、資本投入、全要素生産性という面では、過去四半世紀にわたり、企業収益に比して抑制的であった国内設備投資の拡大や、研究開発等の無形資産投資の促進による新しい価値の創造等が鍵となる。こうした論点については第3章で議論することとする。

コラム1-1 令和6年能登半島地震の経済に与える影響
2024年1月1日16時10分に、石川県能登地方の深さ約15km でマグニチュード7.6(暫定値)の地震が発生した。この地震により、石川県羽咋郡志賀町や輪島市で最大震度7を観測したほか、能登地方の広い範囲で震度6弱以上の揺れを観測した。
この地震により特に被害の大きかった石川県は、県内総生産が約4.5兆円(日本全体の約0.8%)であり、電子部品や半導体メーカー等の工場が多く立地している。2024年1月下旬時点で、これらの工場の大部分は、生産再開又は再開の目途が立っているものの、一部については、再開に時間を要する模様となっている。また、石川県は、日帰りを含む観光客数が年間1,800万人を超え(2022年)、能登地域については年間約540万人(同)であるが、同地域では旅館やホテルの休業がみられるなど観光にも影響が出ている。
内閣府政策統括官(経済財政分析担当)においては、今回の地震による経済への影響を分析する一環として、東日本大震災(2011年3月)や熊本地震(2016年4月)の際の試算方法を踏まえ、市町村ごとの震度等をもとに、過去の大地震における損壊率を参照しつつ、住宅や社会資本等のストックがどの程度毀損したかについて、暫定的な試算を行った。試算結果によれば、石川・富山・新潟の三県において合計約1.1兆円から2.6兆円のストックが毀損した可能性がある23。ただし、この試算は、被害額を積み上げたものではなく、市町村ごとの震度等に基づいた機械的な試算であり、幅をもってみる必要がある。
今回の地震では、住宅や社会資本等のストックの損壊に加え、停電や断水が広範囲に発生した。これらは地域住民の生活のみならず、上述のとおり、生産や観光など経済活動に影響を及ぼしている。今回の地震が経済に与える影響については、引き続き十分留意する必要がある。
2 コロナ禍前後の家計貯蓄の動向と消費の持続可能性
前項で述べたように、我が国のGDPの55%を占める個人消費は、サービスを中心に持ち直し基調が続いているものの、これまでの物価上昇の影響もあって、財消費を中心に力強さには欠けている。後述するように、輸入物価上昇を起点とする物価上昇のテンポは緩やかになり、消費者マインドが再び持ち直すなど明るい動きもみられるが、個人消費の持続的な回復には、まず何よりも名目賃金や名目可処分所得の伸びが物価上昇を継続的に上回ることが重要であり、この点は、本章第2節においてデフレ脱却に向けた展望を行う中で議論する。ここでは、コロナ禍において消費機会が制約されるなどで積み上がってきた超過貯蓄の実態を様々な角度から整理し、我が国でも、2021年後半以降のアメリカのように取崩しが進み、個人消費の回復を支えるかどうか、といった点を中心に議論を行う。
(コロナ禍で大きく上昇した家計貯蓄率は、コロナ禍前をやや下回る水準に低下)
コロナ禍以降のマクロの消費や所得の動向について、国民経済計算(SNA)からみると、コロナ禍発生直後の2020年4-6月期は、個人消費は、緊急事態宣言による行動制限や外出自粛の中で大幅に落ち込んだ一方、可処分所得は、一人当たり10万円の特別定額給付金等の政策支援により大きく増加した(第1-1-17図)。その後、2021年以降は、可処分所得は、2021年末から2022年初にかけての子育て世帯や住民税非課税世帯への10万円の臨時特別給付の影響を除いても、緩やかな増加傾向で推移する中で、個人消費も、感染症再拡大の影響を受けて振れを伴いながらも増加傾向で推移してきた。この間、家計の貯蓄率をみると、個人消費の急減と可処分所得の急増により2020年4-6月期に20%超まで一時的に高まった。その後、貯蓄率は、特別定額給付金等の要因の剥落により大きく低下し、2020年末以降は緩やかなペースで低下しており、2023年以降は、コロナ禍前の2018年頃の貯蓄率の水準(1%程度)をやや下回る程度となっている。

(コロナ禍で積み上がった家計の超過貯蓄の取崩しは未だ緩慢)
このように、コロナ禍の発生以降、これまでの間の家計貯蓄率の動きをみると、コロナ禍前の平時といえる水準を上回って推移してきた。毎四半期の貯蓄は、その期における可処分所得(収入)と消費(支出)との差額というフローの意味での貯蓄であり、コロナ禍以降は、コロナ禍前のトレンドに比べて、こうした毎期のフローの貯蓄が過剰に積み上がってきたことになる。このように、コロナ禍で積み上がった貯蓄は「超過貯蓄」と呼ばれるが、その規模について、SNAベースで一定の仮定24を置いて試算すると、2020年以降増加し、2022年10-12月期をピークに、2023年に入って以降、若干減少し、2023年7-9月期には53兆円(GDP比9%程度)となっている(第1-1-18図(1))。

こうしたSNAベースの試算値に加え、「資金循環統計」から得られる家計部門の現金・預金残高の動向からも超過貯蓄を試算することができる。具体的には、コロナ禍前は、家計の現金・預金残高は安定的な増加傾向にあったことから、2015年3月末以降、コロナ禍直前の2019年12月末までのトレンドを計算し、2020年以降、このトレンドで現金・預金残高が増加した場合と、実際の現金・預金の残高を比較し、その差をとる。この現金・預金残高からのアプローチによると、2022年12月末時点でピーク(50兆円程度)を打ち、その後は、極めて緩やかなペースで減少し、2023年9月末時点では46兆円程度となっている(第1-1-18図(2))。
このように、用いる基礎統計や試算方法によって結果に幅があることに留意が必要であるが、両試算値で共通しているのは、コロナ禍で超過貯蓄はGDP比10%程度まで積み上がり、その後取崩しはみられるものの、未だ限定的である、という点である。
この点、諸外国の状況と比較するために、SNAベースで、上述の日本の場合と同様の考え方で試算した結果をみると、アメリカは2021年7-9月期にピーク(2.6兆ドル、GDP比10.7%)を打った後、超過貯蓄は減少に転じ、2023年7-9月期には1.8兆ドル(GDP比6.5%)まで減少している(第1-1-19図(1))。一方、ユーロ圏については、超過貯蓄の増加ペースは緩まっているものの、減少に転じることはなく、2023年4-6月期で1.2兆ユーロ(GDP比8.2%)まで積み上がっている(第1-1-19図(2))25。諸外国との比較では、日本は、個人消費が持ち直していることからユーロ圏ほど超過貯蓄が積み上がり続けているわけではないが、アメリカでは、着実に超過貯蓄を縮小し、個人消費に回ってきたという違いがある(第1-1-19図(3))。こうした姿は、前掲第1-1-1図で確認したコロナ禍後の個人消費の動きと同様である。

(相対的に低所得、低資産の消費者は超過貯蓄を取り崩している可能性)
超過貯蓄については、コロナ禍で消費機会が制限された結果、積み上がった貯蓄であるとすれば、いずれかの段階で、アメリカのように本格的に取崩しが起こり、個人消費を支えていくと期待されるが、なぜ日本では、超過貯蓄の取崩しが現時点では目立って起きていないのであろうか。この点を確認するため、まず、家計の属性別に超過貯蓄を確認する。
第一に、「家計調査」を用い、SNAベースの試算と同様の考え方により超過貯蓄を試算する。家計調査の場合、二人以上世帯が対象となるが、一世帯当たりの貯蓄率26をみると、SNAベースと同様に、コロナ禍発生直後に急上昇した後、緩やかに低下するという傾向は同じであるが、コロナ禍前よりもより高く切り上がった水準にまでしか貯蓄率は低下していないことが分かる(第1-1-20図(1))。SNAベースと家計調査ベースの貯蓄率には、概念上や計測上の様々な違いからこうしたかい離が生じるため、SNAベースの超過貯蓄と整合的な形での家計属性別の分析は困難である点を念頭に置きつつ、二人以上世帯について、勤労者世帯と高齢無職世帯27に分け、それぞれ高所得世帯と低所得世帯28の動向を確認する(第1-1-20図(2))。これによると、勤労者世帯平均としては、超過貯蓄が一貫して増加し積み上がっているが、その程度は高所得層の方でより顕著となっている。一方、高齢無職世帯では、平均では、2022年10-12月期をピークとして、その後、超過貯蓄がやや減少している。高所得層では、2022年10-12月期以降おおむね横ばいで推移する一方、低所得層では2021年後半以降、超過貯蓄が減少傾向で推移し、直近の2023年7-9月期ではゼロ近傍でややマイナスとなっている29。

第二に、日本銀行「預金者別預金」統計を用い、個人部門の預金残高を残高階層別に確認する。「預金者別預金」は、日本銀行と取引のある国内銀行(ゆうちょ銀行を除く)と信用金庫について捕捉しており、日本全体の個人預金残高(約1,000兆円)の7割弱をカバー30している。加えて、預金残高階層別の預金額が把握可能であり、おおまかには、「資金循環統計」に基づく預金残高の動向を預金残高階層別に確認することが可能となる。ただし、本預金残高階層別のデータは、預金口座を複数保有する個人が多くいるとみられる中で、あくまで銀行一口座当たりの情報を集約したものであり、個人ごとの名寄せができるものではないという点には留意が必要である31。その上で、預金残高階層別に、「資金循環統計」を用いた試算と同様の手法で超過貯蓄を試算すると、預金残高が1,000万円~1億円未満の層を中心に預金残高が大きい層では、超過貯蓄の取崩しがみられず、むしろ増加傾向が続いていることが分かる(第1-1-21図)。一方で、預金残高1000万円未満の合計では、2022年3月末をピークに超過貯蓄が減少に転じており、特に300万未満の口座では取崩しの動きが顕著であることが分かる。300万円~1,000万円未満についても直近では、わずかながら超過貯蓄が減少に転じているとみられる。
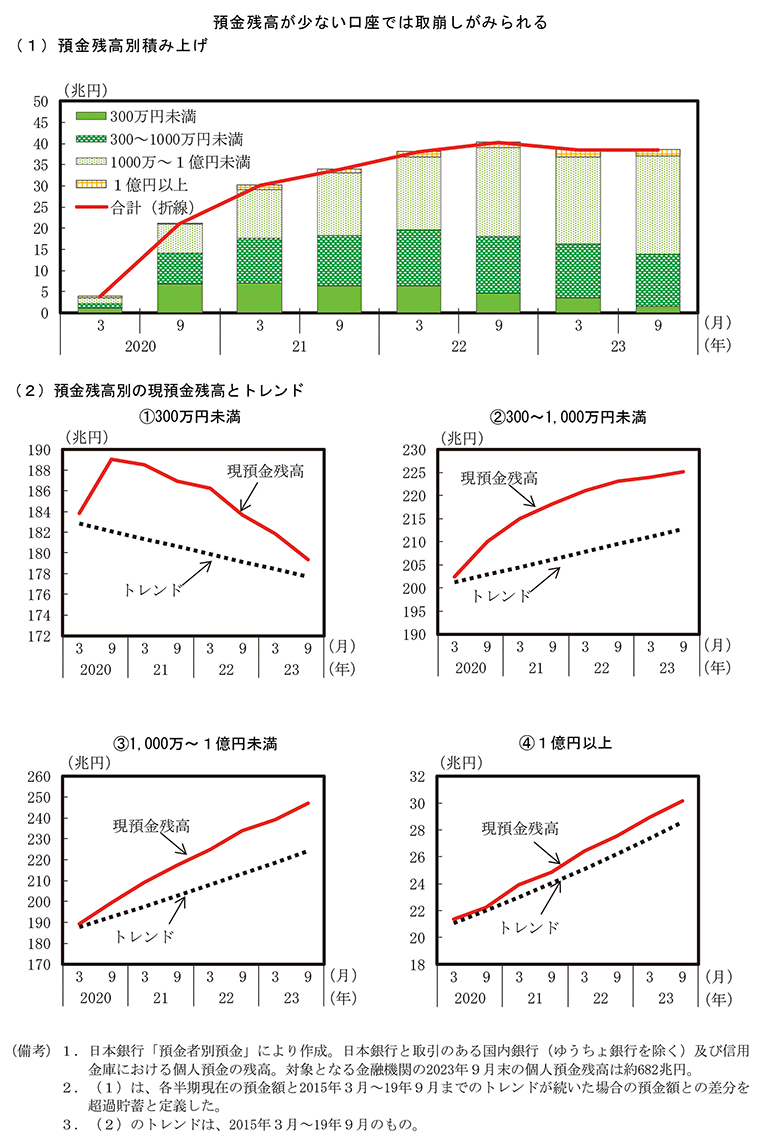
これらの属性別の分析からは、必ずしも確定的な含意が得られるわけではないが、総じていえば、相対的に高所得の世帯や、預金残高という意味で比較的大きな資産を持っている層では、超過貯蓄の取崩しが起きておらず、逆に、第1-1-20図(2)における高齢無職世帯や第1-1-21図(2)の預金資産が相対的に少ない世帯では、超過貯蓄の取崩しが起きているという傾向が読みとれる。今回の40年ぶりとなった物価上昇局面の中で、相対的に低所得、低資産の消費者は超過貯蓄を取り崩して消費に回さざるを得なかった一方、より高所得、高資産の消費者は、貯蓄を取り崩すほどには消費支出を積極的に行わなかった可能性がある。
(所得が相対的に高い勤労世帯では、貯蓄率はコロナ禍前に比べて切り上がっている)
以上のように、我が国において、経済全体として超過貯蓄の取崩しが緩慢であるのは、相対的に所得ないし資産が大きい層の消費・貯蓄行動に起因する可能性がある。高所得層において超過貯蓄がより積み上がったという現象は海外でも指摘され、様々な議論が行われている32。
そこで、そもそもより所得が高い層において、超過貯蓄の取崩しが進まない(むしろさらに積み上がっている)背景について、いくつかの観点から議論を進める。まず、フローの貯蓄率の世帯属性別のコロナ禍前後の変化に着目する。SNAベースでは世帯属性別の動きをみることはできないため、「家計調査」(二人以上世帯。勤労者世帯、無職世帯を含む)から作成した属性別の貯蓄率をみると(第1-1-22図)、高齢無職世帯については、高所得層ではほぼコロナ禍前に貯蓄率の水準が戻り、低所得層ではコロナ禍前を下回って低下が進んでいる。一方、勤労者世帯については、低所得世帯でもコロナ禍前に比べた貯蓄率水準が切り上がっているものの、徐々にコロナ禍前水準に近づく傾向がみられる一方、超過貯蓄の積み上がりが顕著な高所得世帯では、コロナ禍後の貯蓄率は、コロナ禍前に比べて切り上がり(消費性向としては切り下がり)、かつ、直近においては上昇傾向にある。勤労者の低所得世帯、高所得世帯について、2018年初を起点とした貯蓄率の変化を消費支出要因と可処分所得要因に分解すると、低所得世帯では、可処分所得がコロナ禍前よりも増加した状態にあり、貯蓄率の引上げ要因となっている中、直近では、この要因はおおむね横ばいとなっている一方で、消費支出要因はマイナスに転じ、貯蓄率を押し下げる要因に効いている。これに対し、高所得世帯では、可処分所得はコロナ禍前よりも切り上がった状態にあり、貯蓄率の引上げ要因となっている点は共通しているが、直近では、所得要因がやや縮小する一方で、消費支出が減少し、貯蓄率の押上げに効くようになっている。これら世帯では、コロナ禍後、2022年終わりから2023年前半の期間に消費支出要因が2018年初対比で若干マイナスとなったが、総じて、所得の拡大に比べて消費の水準が抑制されていることが分かる。コロナ禍で外出の機会が減少したことから、外出関連の選択的な消費を減らした状態に適応し、コロナ禍が収束した中でも、これらを中心に消費を抑制した状態を維持しているという、一種の習慣形成が働いていることも考えられる。

(過去の経済ショック時は、実質賃金の減少が続くと超過貯蓄が積み上がる傾向)
次に、コロナ禍で超過貯蓄が蓄積した中で、経済ショックが生じる場合の貯蓄の増加の背景として、Voinea and Loungani(2022)等が提唱している、「補償的貯蓄(compensatory saving)」という仮説について考察する。Voineaらは、貯蓄率の高まりを説明する議論として用いられることが多い予備的貯蓄(precautionary saving)は、将来の所得等に対する不確実性が高まると貯蓄が積み増される33とするのに対し、補償的貯蓄とは、将来の不確実性ではなく、既に生じている資産の損失を取り戻す(補償する)ために貯蓄を積み上げる行動としている。具体的には、実質賃金が減少する際に、減少し始めて以降の累積減少額(累積賃金ギャップ)が拡大する過程で、貯蓄が増加し、逆に実質賃金が増加に転じ、その後、累積賃金ギャップが縮小していく過程で、貯蓄が減少するという考え方となっている。Voineaらは、アメリカを例に、世界金融危機後及びコロナ禍発生後の経済ショック局面でこうした補償的な動機による超過貯蓄の蓄積が生じた可能性が高いとの議論を行っている。
そこで、日本について、同様の考え方で、①アジア通貨危機や金融危機前後の1998年頃以降、②リーマンショック前後の2008年以降、③コロナ禍発生前後の2020年以降の動きを確認する。家計貯蓄率はSNAベースの値を用い、実質賃金も同様にSNAベースの実質雇用者報酬を使用する(以下、ここでは「実質賃金」という。)。ただし、日本の場合、①や②の局面で実質賃金は、減少が始まって数年のスパンでは減少前の水準を下回り、累積賃金ギャップはマイナス幅が常に拡大する姿となり34、その間でも貯蓄率が上昇し続けたわけではないことから、補償的貯蓄の仮説はそのままの形では日本のケースに当てはまるわけではない(第1-1-23図(1))。
そこで、賃金ギャップについて、累積ではなく、実質賃金の減少前水準と各期の水準の差とした場合をみる35。また、家計貯蓄率については、特に①の局面前後は長期的な低下トレンドがあったことから、トレンドと実績のかい離として評価する(第1-1-23図(2))。この場合、①(1998年頃以降)については、当初、実質賃金の下落局面で貯蓄率がトレンドよりも高く推移し、その後1999年頃から実質賃金が増加に転じ、賃金ギャップが解消に向かう中で、貯蓄率もトレンドに回帰していった。また、②(2008年以降)については、賃金ギャップ拡大の中、貯蓄率が上昇した後、①ほど明確ではないが、2009年後半から実質賃金が増加傾向に転じる中、貯蓄率は2010年にかけてトレンドに回帰する状況が生じていた。

(実質賃金が上昇に転じていくことが超過貯蓄の本格的な取崩しにつながる可能性も)
次に、③のコロナ禍発生の2020年以降については幾分様相が異なる。コロナ禍発生直後に実質賃金が一時的に減少し、その後2021年前半に賃金ギャップが一旦解消に近づいた一方、貯蓄率は、特別定額給付金の影響の剥落の後も、トレンドよりも高い水準にとどまっていた。また、2022年4-6月期から物価上昇の下で実質賃金が下落をはじめ、賃金ギャップが拡大する中で、貯蓄率は緩やかに低下しつつ、2023年に入って以降はコロナ禍前水準をやや下回る水準となっている。このように、賃金ギャップが拡大する中でも貯蓄率が上昇しているわけではない点を含め、過去の経済ショック時とは動態が異なり、補償的貯蓄の仮説と整合的であるとは言えない。
一方、前掲1-1-22図で見たように、超過貯蓄の積み上がりが顕著な二人以上勤労世帯の高所得世帯は、2022年後半から貯蓄率が上昇に転じている。実質賃金の下落が続く中で、これらの消費者が、賃金ギャップの拡大を踏まえ、貯蓄率を高めている可能性も考えられる。他方、勤労者のうち低所得世帯については、コロナ禍前の水準は上回るものの貯蓄率の緩やかな低下傾向が続いており、賃金ギャップを踏まえた動きというよりは、物価上昇により実質賃金・購買力の下落が続く中で、必要な消費支出額を賄うため、貯蓄率を低下させて対応していると推察される。補償的貯蓄仮説は、必ずしも現在の超過貯蓄の高止まり傾向を説明できるものではないが、仮に、実質賃金が上昇トレンドに転じ、賃金ギャップが縮小を始めれば、比較的高所得の消費者等において、貯蓄率がトレンドを下回るようになり、超過貯蓄の取崩しに転じる可能性もある。
(将来への不安等が今後の超過貯蓄の取崩しを抑制する可能性には留意)
最後に、予備的貯蓄について議論する。予備的貯蓄に関しては、我が国の若年世代において、従来のような年功序列の下で長く勤続すれば賃金所得が増加していくという見通しが立てづらくなっていること、平均余命の伸長により長生きリスクがより意識されるようになっている可能性があること等、老後の生活への不安が高まっていることから、より多くの貯蓄残高を保有するようになっているという考え方は根強い。
「家計の金融行動に関する世論調査」によれば、若年層について、老後の生活資金を理由として金融資産を保有する者の割合が、2000年代後半から2020年前後にかけての過去10年超の間に増加している36。この間、厚生労働省「完全生命表」によれば、平均余命については、2005年から2020年にかけて、男性であれば78.56歳から81.56歳に3年、女性であれば85.52歳から87.71歳に2年程度それぞれ伸長している。加えて、これはあくまで余命の平均値であり、死亡者数が最も多い年齢(最頻値)は、2020年において男性で88歳、女性で93歳と平均余命をそれぞれ5~6年上回るなど長生きリスクという意味での不確実性は高いといえる37。このように、中長期的な観点では、老後の不確実性に対する予備的貯蓄動機が働いているとも考えられる。他方、コロナ禍前後の数年間の状況(2018-2019年から2021-2022年)をみると、コロナ禍の影響もあって、平均余命はほぼ横ばいから微減であるのに対し、現役世代38のうち老後の生活資金を理由として金融資産を保有する者の割合は増加している39(第1-1-24図(1))。ここで、同じ二時点間において、現役世代が実際に保有する金融資産額の分布と、目標とする金融資産額の分布を比較すると、二人以上世帯については、コロナ禍前からコロナ禍以降にかけて、保有額はより低い方へ分布がシフトしているのに対し、目標額はより高い方にシフトしている(第1-1-24図(2))。単身世帯については、コロナ禍前からコロナ禍以降にかけて、保有額はわずかながらより高い方にシフトしているが、目標額についてもより高い方へシフトしている。
このように目標とする金融資産残高が近年引き上がる中で、現役世代の家計にとって、コロナ禍で積み上がった超過貯蓄水準が「参照点」となり、その水準からの取崩しが一種の損失と認識され得るため、これを回避するべく消費水準を抑制して超過貯蓄残高を維持しようとする行動が生じている可能性もある。こうした場合は、比較的若い世代を中心に超過貯蓄が取り崩される可能性が低くなり得る。
以上のように、我が国において、現時点でコロナ禍後に積み上がった家計の超過貯蓄の取崩しが目立ってみられない背景には複合的な要因があると考えられる。継続的な賃金上昇が実現し、実質賃金の改善につながれば、超過貯蓄の取崩しにつながり得る面がある一方で、コロナ禍を経た習慣の変化が生じていたり、老後不安に対する予備的動機が強ければ、今後の超過貯蓄の取崩しが制約される可能性もある。


