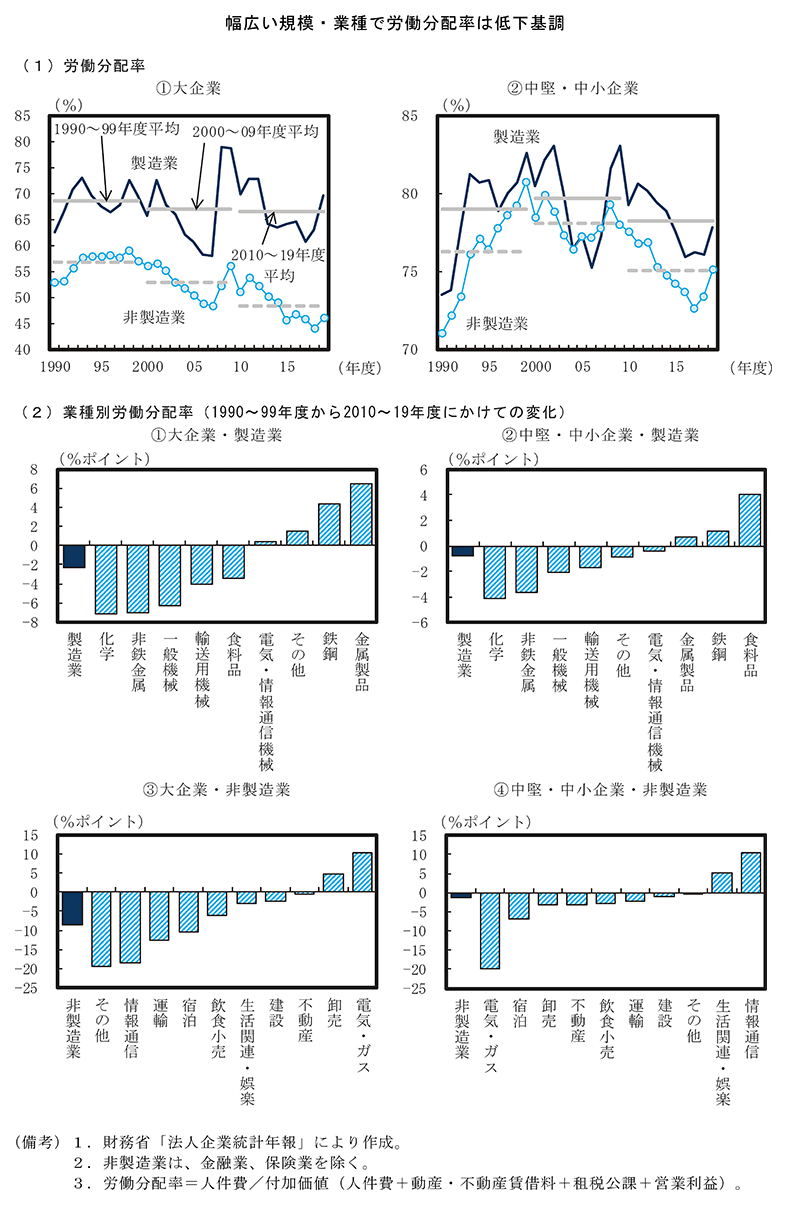第2章 成長と分配の好循環実現に向けた企業部門の課題(第1節)
第1節 企業収益と分配・投資スタンスの長期的な動向
本節では、近年の景気回復局面における我が国企業の収益・分配の動向を整理する。我が国の企業部門は、売上高が伸び悩む中、経常利益を引き上げることに成功してきたが、国内での設備投資や人件費には積極的に支出してこなかった。この間、海外への投資や投資家への配当は増加傾向にあるが、同時に未活用資金も積み上がっている。
1 我が国企業部門の収益構造
(近年、売上げが伸び悩む中で収益性を改善する動きが顕著)
我が国経済は感染症の拡大に伴う落ち込みから、持ち直しの途上にある。経済社会活動の正常化に伴い、景気の改善が継続し、経済の成長と分配の好循環の実現が期待されるが、この好循環の中で重要な位置を担う企業部門について、過去の収益の成長とその仕組みの変遷を改めて確認しておく意義は大きいと考える。こうした問題意識から、直近の景気回復局面である第16循環(2012年度~2018年度)の売上げ・経常利益の動向について、過去の景気回復局面との比較を通じて確認する。
まず、全産業ベースで売上高と経常利益の推移をみると、1990年度以降の全期間を通じて、売上高が伸び悩むのに対して、相対的に経常利益の改善が大きいことがわかる。特に、2009年度以降の景気回復局面では、2000年代前半と比べて売上対比での経常利益の改善幅が大きくなっている(第2-1-1図(1))。また業種別にみると、製造業・非製造業ともに同様の傾向が確認できる(第2-1-1図(2)、(3))1。
特に、第16循環(2012年度~2018年度)についてみると、全産業ベースで売上高が約1割程度の増加にとどまる一方で、この間に経常利益は約7割増加しており、過去の景気回復局面と比較して、売上対比でみた経常利益の改善幅が際立っている。
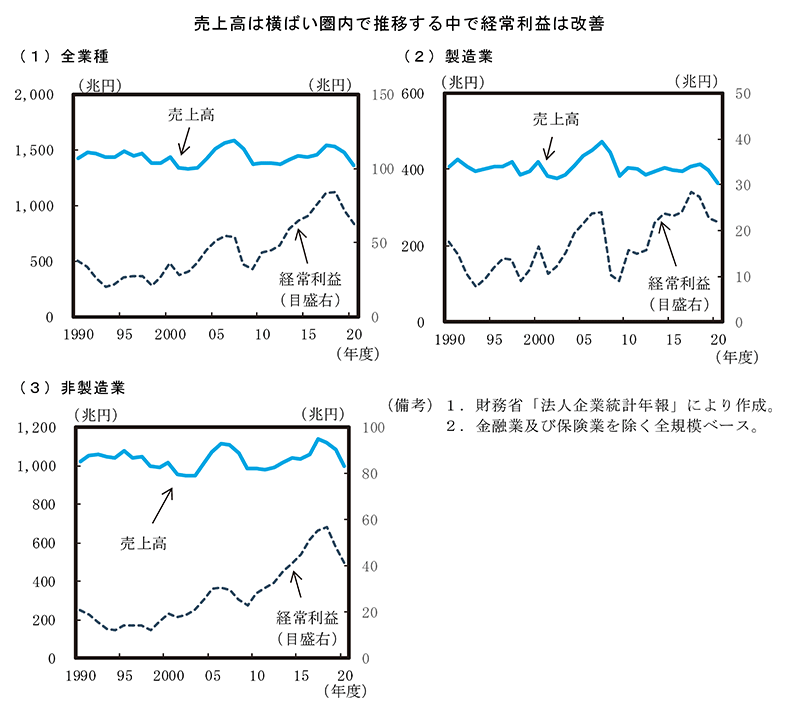
(2009年度以降の収益性の改善には人件費や設備投資の抑制が寄与)
次に、売上高が伸び悩む中で、我が国企業部門がどのように収益を改善させてきたのかを確認する。1990年代以降、我が国の企業部門は、売上高が伸び悩むのに対し、利益は相対的に増加させてきており、この傾向は最近になるにつれて強まっていることをみた。これについて、1997年から1998年の金融危機をきっかけに、財務体質の強化が至上命題とされる下、経営の合理化を進めることができたとの解釈もあり得る2。他方、経営合理化の過程で、国内での設備投資や人件費も抑制された結果、成長と分配の好循環の実現を弱めた可能性も懸念される。こうした問題意識から、1990年代以降の景気回復局面における企業の経常利益改善幅を、①売上高要因、②変動費要因(原材料費等)、③人件費要因、④減価償却費要因、⑤営業外収益要因(配当・利息の受け払い等)、⑥その他固定費要因の6つに要因分解することを通じて、経常利益の改善要因を確認する(第2-1-2図)3。
まず、大きな特徴としては、第12循環(1993年度~1997年度)や第14循環(2002年度~2007年度)といったリーマンショック前の景気回復局面と比較すると、第15循環(2009年度~2011年度)と第16循環(2012年度~2018年度)といった直近の景気回復局面では、売上高要因の寄与が小さくなる一方で、経常利益の年間改善幅は大きくなっている。企業は需要の成長鈍化に直面する中で、企業収益をより成長させてきた。
次に、人件費要因・減価償却費要因・その他固定費要因といった項目の下押し寄与が、直近の景気回復局面では大きく縮小している。このことから、企業経営の合理化の中で進められた固定費削減が企業収益の改善に大きな役割を果たしてきたことがわかる。
ただし、こうした固定費削減の動きについては、経済の好循環を弱めてきた可能性があり、課題も指摘できる。人件費要因の経常利益に対する下押し幅の縮小(すなわち、人件費の増加幅が縮小)は、企業が生み出した付加価値のうち雇用者へ分配する割合が低下していることを示唆している。減価償却費は、国内で行った設備投資に伴って企業に蓄積される有形固定資産等の規模に応じて発生する4。そのため、減価償却費要因の下押し寄与の縮小は、企業の設備投資スタンスが消極化してきた結果と解釈することができる。
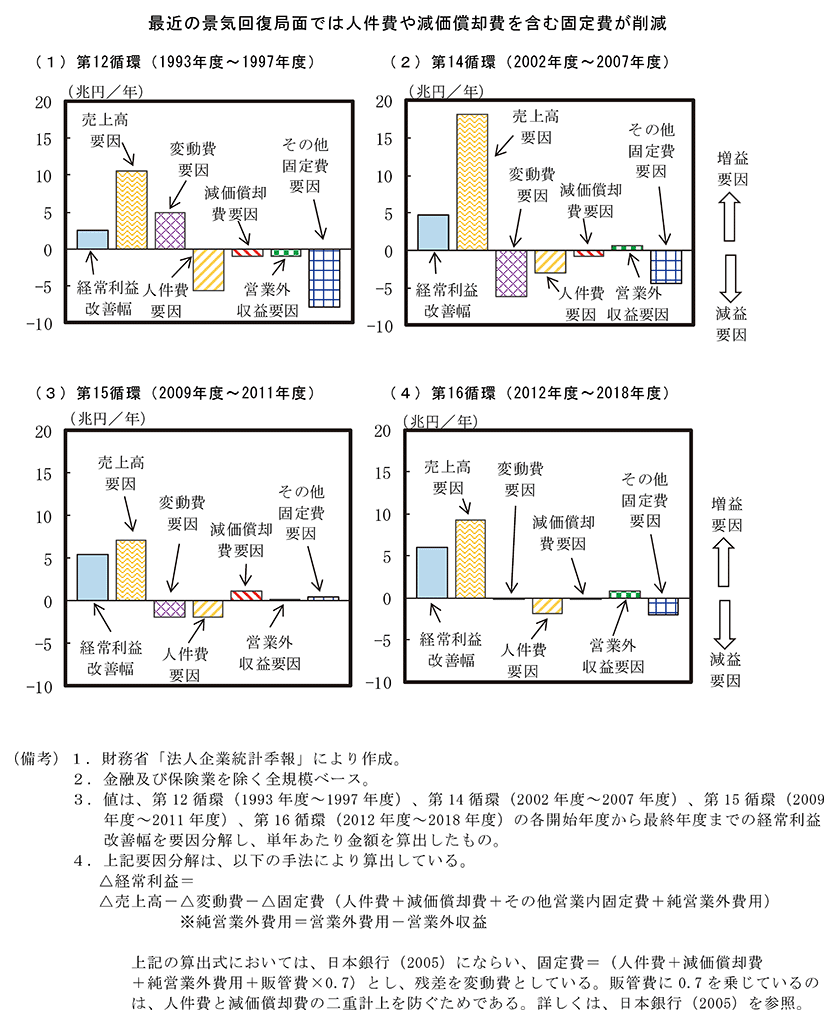
2 企業の分配・投資スタンスと貯蓄動向
(投資家への配当金比率が上昇する一方で、人件費比率は低下傾向)
前項で見たとおり、我が国企業部門は、固定費削減により、収益力を改善させてきたことがわかったが、こうした収益の改善は、経済全体における成長と分配の好循環の実現という観点からは、結果的にこれを弱めていた可能性がある。ここでは、経済全体の動きをみる観点から、企業が生み出した「付加価値」を取上げ、これとの対比でみた分配・投資の動向を整理する。
企業の生み出した付加価値の使途は、税金支払いなど企業側に裁量の余地のない支出項目を除くと、①賃金支払いによる雇用者への分配、②配当による株主への分配、③内部留保として社内に蓄積、に大別される。また、今後の成長に向けては、上記の内部留保に加え、借入れ・資本調達も利用の上、④設備投資5・無形資産投資・海外M&A等への投資活動への支出、⑤現預金として保有、に大別される。
まず、雇用者への分配である人件費比率(=人件費/付加価値)と、投資家への分配である配当金比率(=配当金/付加価値)をみると、人件費比率は、足下の2020年度に感染拡大の影響で上昇したが、トレンドとしては低下傾向にある一方で6、配当金比率は上昇傾向にある(第2-1-3図(1))。人件費比率の低下は、前項で見たとおり、景気回復局面において企業収益の改善対比で、賃金の上昇が見劣りしてきた結果であると考えられる。配当金比率の増加の背景については、日本版スチュワードシップ・コード7やコーポレート・ガバナンス・コード8の制定もあり、企業と投資家の対話の取組が本格化し、企業が株主還元を進めてきた結果であると考えられる9。
(国内での設備投資は抑制的だが海外M&Aは増加)
次に、投資活動の動向についても確認する。企業の設備投資対付加価値比率は、リーマンショック以降は回復傾向にあるものの、依然としてリーマンショック前の水準を下回っており、慎重な設備投資スタンスは続いていると見受けられる(第2-1-3図(2))。この点、設備投資には計上されないが、企業が投資活動として認識している海外M&Aを加えると、特に直近の景気回復局面である第16循環(2012年度~2018年度)に振れを伴いながら上昇し、リーマンショック前を超える水準にある。また、近年、世界的に無形資産の収益性が有形資産を上回っており10、長期的な成長力強化に向けて無形資産の重要性が高まっているとの指摘もある。そこで、経済産業研究所「JIPデータベース」の試算を用いて、企業の研究開発投資やソフトウェア投資、教育訓練投資等の無形資産投資を含めた投資をみると、付加価値に占める割合は大きく上昇する11。もっとも、個別に無形資産投資比率の推移をみると、リーマンショック前の2007年頃までは上昇傾向にあったものの、近年は増勢が鈍化している(第2-1-3図(3))。この間、相対的にみると、海外M&Aの伸びが目立っており、技術革新等に伴う事業環境の変化や経済のグローバル化が進む中で、既に実績のある海外企業をM&Aによって取り込むことは、比較的短期間のうちに成果を上げられる投資手段として企業から選好されてきたとみられる12。
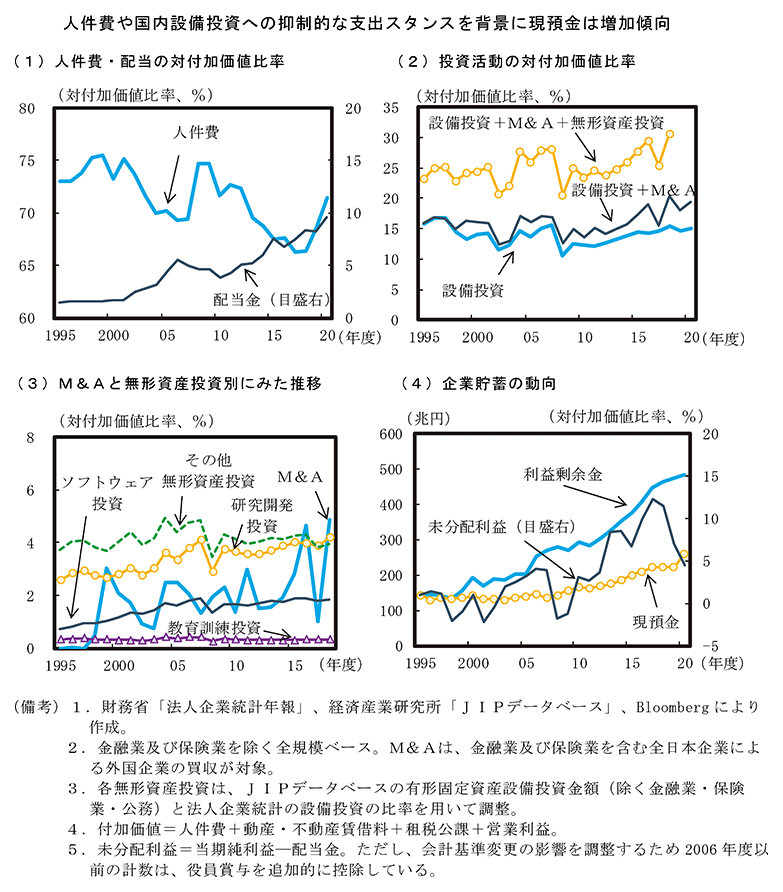
(企業貯蓄は増加し、現預金も積み上がり傾向)
以上みてきた通り、企業は投資分野を変容させており、一律に投資を絞っている訳ではない。しかしながら、総じてみれば、雇用者への分配は抑制傾向にあり、国内での設備投資を中心とした企業の投資スタンスも慎重に推移してきた。その結果、企業貯蓄のフローに該当する概念である当期未分配利益(=当期純利益─配当金)の対付加価値比率は、第16循環(2012年度~2018年度)に既往最高の水準まで上昇した(第2-1-3図(4))。
こうしたフローが積み上がった結果、ストックにあたる利益剰余金は上昇傾向にあり、現預金もリーマンショック後に上昇ペースが加速している。この背景として、企業収益が改善する中にあっても、為替レートの変動など経営環境悪化への警戒感が根強いほか、バブル崩壊や世界金融危機などの経験を踏まえた安全志向から、手元資金を厚くする動きが影響しているとの指摘がある13。もっとも、こうした現金保有志向が、人件費や設備投資の抑制要因となり、このことが低成長につながり、さらに企業の慎重な分配・投資スタンスを促す負の循環に陥っている可能性がある。そのため、企業が投資や分配に前向きになれる事業環境を構築することが重要である。
(対外直接投資収益の多くが現地での内部留保に)
企業が認識する投資活動のうち、特に近年伸び率が高いのは、海外M&Aであったが(前掲第2-1-3図(2)、(3))、企業がM&Aにより海外で取得した企業や新設した現地法人の収益を表す対外直接投資収益は、どの程度国内に還元されているのだろうか。対外直接投資収益の内訳推移をみると、2014年~2020年の対外投資収益の増加のほとんどは、海外拠点の内部留保である再投資収益の増加によって説明されることがわかる(第2-1-4図(1))。特に2016年以降は、対外直接投資収益のうち半分以上が海外拠点の内部留保になっている。また、配当として国内に還元された資金の使途を確認しても、「研究開発・設備投資」「雇用関係支出」といった項目への回答割合は限定的となっており、企業が海外投資で稼ぐ収益を我が国経済の成長と分配の好循環につなげるという観点からも、課題が残っていると考えられる(第2-1-4図(2))。
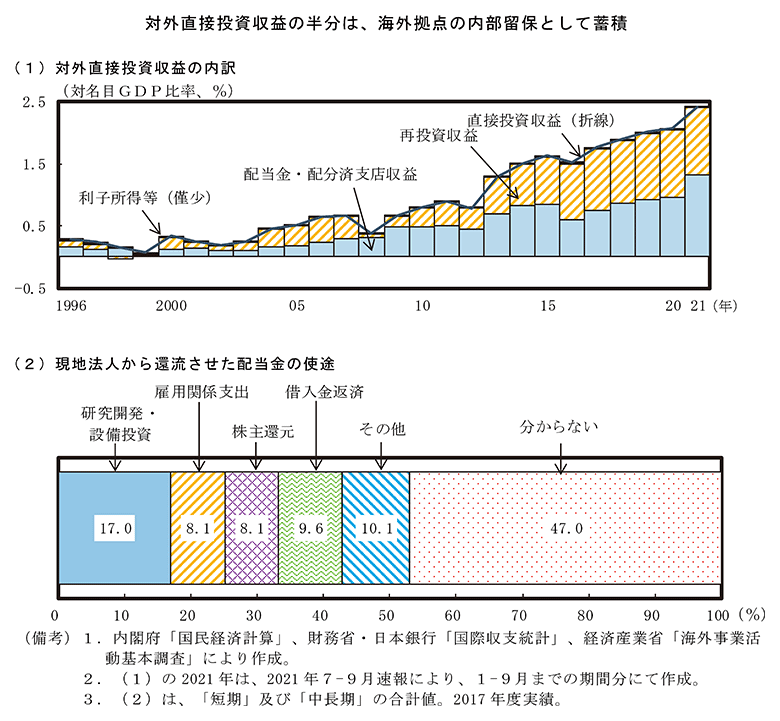
(企業の労働分配率は幅広い業種で長期的に低下傾向)
企業が事業活動の中で生み出してきた付加価値の分配先は、雇用者に対する人件費、株主や債権者に対する資本コスト、政府に対する税金に分けることができ、付加価値に占める割合をそれぞれ労働分配率、資本分配率、租税分配率と呼ぶ。
労働分配率は、分母の付加価値額の変動が、分子の人件費の変動と比較して大きいため、一般に景気悪化局面で大きく上昇する傾向があり、短期的な変動をみる上では留意が必要である。ここでは、規模・業種別に景気循環の影響をならして労働分配率の推移を確認する観点から、10年ごとの平均の推移(1990年代、2000年代、2010年代)をみると、労働分配率はいずれの業種・規模でも2010年代の水準は1990年代の水準と比較して低下している(第2-1-5図(1))。さらに、業種別内訳について子細にみると、幅広い業種でこの間の労働分配率は低下傾向にあることが分かる(第2-1-5図(2))。
このように、我が国での労働分配率の低下傾向は、幅広い業種・規模で生じており、成長と分配の好循環に向けた課題となっている14。