第2章 新たな産業変化への対応(第2節)
第2節 新たな産業革命に対応するための課題
現在進行しつつある第4次産業革命のメリットを最大限に引き出し、生産性の上昇と国民の豊かさの向上につなげるためには、イノベーションを促進する能力、ICTへの適応力、それを支える人的資本の充実が重要である。以下では、これらの観点から、我が国経済の生産性の現状と、その向上に寄与するR&D投資やICTへの適応の状況について概観するとともに、今後、第4次産業革命に迅速に適応するための課題について検討する。
1 労働生産性からみた我が国の課題
我が国の労働生産性は、アメリカやドイツといった先進国と比べると、低い水準となっているが、この背景には、全要素生産性(Total Factor Productivity、以下「TFP」という。)の伸びが相対的に低く、ICT投資の寄与も低いことなどがある。
(日本の生産性はアメリカやドイツのそれよりも低く、その差も近年拡大傾向)
日本、アメリカ及びドイツの労働生産性について1970年以降の動きをみると、日本は、1990年代半ばまではアメリカに急速にキャッチアップし、その差を縮めていたが、1990年代後半以降、アメリカの伸びが高まる一方、日本の伸びは鈍化し、両者の差は拡大した(第2-2-1図)。2008年の世界金融危機後以降は両国ともに伸びが鈍化した結果、その差は縮まっていない。
ドイツとの対比では、1970年から世界金融危機まで一貫してドイツの労働生産性が上昇する中で、日本とドイツの差は振れを伴いながらも、緩やかに拡大していた。世界金融危機以降、ドイツの伸びは鈍化したため、差の拡大は一服している。
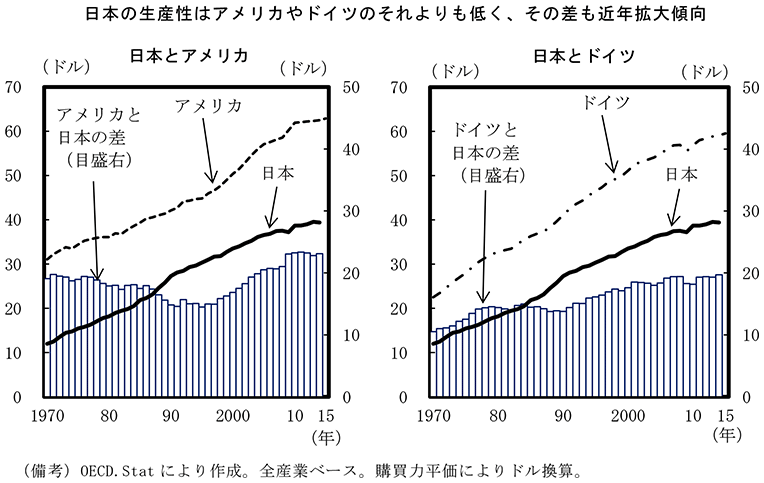
(日本はTFP、ICT資本装備率要因において米独に劣後)
このように日本の労働生産性はアメリカ及びドイツのそれよりも低い水準にとどまっているが、どのような要因が影響しているのであろうか。
これを確かめるために、労働生産性の上昇率について、労働者一人当たりの情報通信技術資本(以下「ICT資本」という。)、すなわちICT資本装備率による寄与と、労働者一人当たりの機械設備などの一般資本、すなわち非ICT資本装備率による寄与、及びそうした生産要素がどれだけ効率よく生産活動に用いられているかを示す全要素生産性(TFP)による寄与に分解してみよう1。
これをみると、TFP要因、ICT資本装備率要因において日本はアメリカを下回っていることが分かる(第2-2-2図))。し細にみると、TFP要因については、日本はアメリカの半分弱、ドイツの4分の1程度であり、ICT資本装備率要因については、日本はアメリカやドイツの3分の1程度となっている。
次にTFP要因やICT資本装備率要因において差異が生じてしまった背景について考察する。ただし、TFP要因に影響を与えるものとして、一般にはR&D投資、人的資本投資、資源配分の効率化、経済を支える制度など様々な要因が考えられているが、以下では、第4次産業革命に適応する上で特に重要と考えられるR&D投資、ICTへの適応、人的資本の蓄積に焦点を絞って考察する。
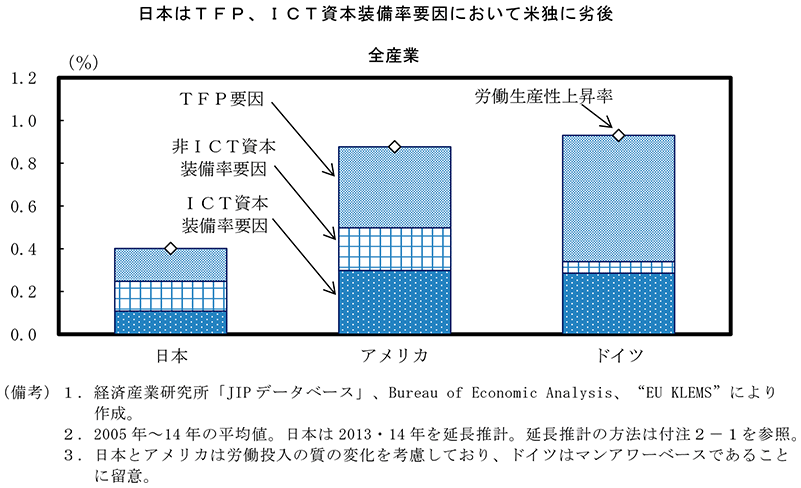
2 我が国のイノベーション競争力
日本はアメリカ及びドイツよりもTFPの伸びが低くなっているが、TFPはプロダクト・イノベーションと強く関わっている2。そこで、こうしたプロダクト・イノベーションを生み出す源泉の一つであるR&D投資とTFP上昇率や企業の収益性との関係を確認してみよう。
(日本のR&D投資は米独と比べ大きいが、TFPや企業収益に結びつきにくい)
R&D投資・名目GDP比率について、日本、アメリカ及びドイツで比較すると、1990年以降、日本は一貫して他国の水準を上回って推移しており、最近では、日本はアメリカ、ドイツの1.3倍程度にも及んでいる。これより、日本のR&D投資の規模は他国よりも大きいことが分かる(第2-2-3図(1))。
しかし、R&D投資とTFP3の関係をみると、日本におけるR&D投資・名目GDP比率に対するTFP上昇率の程度は、諸外国の平均的な関係よりもやや低い(第2-2-3図(2))。一方、アメリカは諸外国の平均的な関係をやや上回っているほか、ドイツのそれはおおむね諸外国の平均的な関係と同様であることから、日本のR&D投資はアメリカやドイツのそれよりもTFPに結びつきにくいといえる。
また、TFP上昇率という生産性指標だけではなく、営業利益といった企業の収益性指標でR&D投資との関係を時系列でみると、2005年以降のデータでは、2006年以降、日本は一貫してアメリカ、ドイツを大きく下回っている(第2-2-3図(3))。
さらに、当該3か国について、各国企業を対象にした、営業利益に対するR&D投資の感応度をマクロ要因や企業ごとの固有の要因をコントロールした上で推計すると、R&D投資が1%増加したときの営業利益への影響は、日本は0.1%程度、アメリカは0.5%程度、ドイツは0.3%程度となっており、やはり日本は他国よりも低いことが分かる(第2-2-3図(4))。
以上のことから、日本は他国よりもR&D投資が生産性や収益性に結び付きにくくなっている。それでは、なぜ日本のR&D投資はイノベーションなどに結び付きにくいのであろうか。
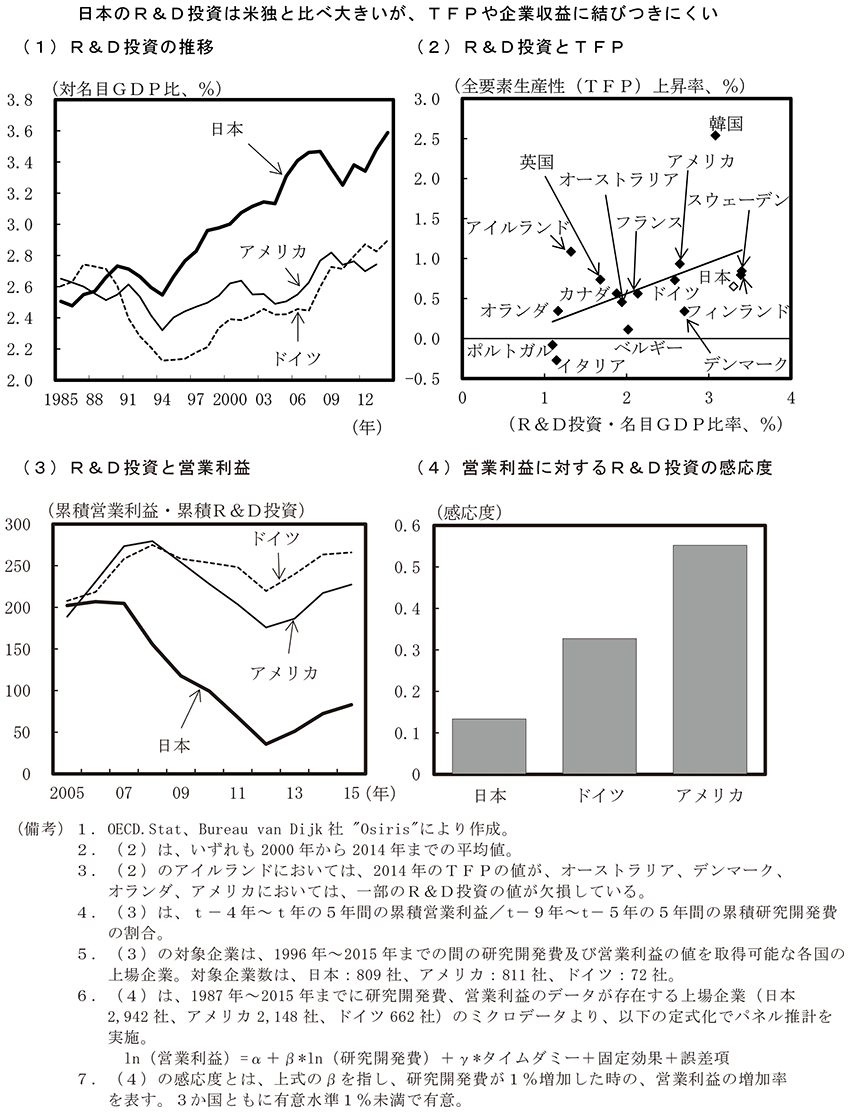
(日本のR&D投資は新事業よりも既存事業の改良に注力)
第一に、プロダクト・イノベーションへの取組が他国と比べて低調であることが挙げられる。科学技術・学術政策研究所の全国イノベーション調査より、プロダクト・イノベーションを実現した企業の割合をみると、日本はアメリカ、ドイツよりも低くなっている(第2-2-4図(1))。この背景には、日本のR&D投資の目的がプロダクト・イノベーションにつながる新しい財・サービスの創出よりも既存の技術の強化に重点をおいていることが考えられる。実際、独立行政法人経済産業研究所が実施したR&Dに関する実態調査でも「新事業の創出・自社の技術基盤の強化」を目的として挙げる企業の割合では、日本は約3割にとどまる一方、アメリカでは約5割となっている(第2-2-4図(2))。また、「既存事業の強化」を目的として挙げる企業の割合では、日本では7割近くとなっている一方、アメリカでは5割以下にとどまっている。
また、R&Dに要する期間に対する考えについて日本企業に調査したものをみると、開発期間を「短期(1~4年程度)」とする企業の割合が8割程度に及ぶ一方、「中長期(5年程度)」とする企業は2割強となっている。また、10年前との比較では、中長期の開発の比率が低下したと回答した企業と上昇したと回答した企業の割合は共に2割程度と拮抗しているのに対し、短期の開発の比率が上昇したと回答した企業は3割程度であり、低下したと回答した企業の割合を2割程度上回っており、短期化の傾向がみられる(第2-2-4図(3))。
要約すれば、日本企業のR&Dはプロダクト・イノベーションにつながる新事業の創出より既存事業の強化に充てられており、こうしたことを背景に、日本企業は開発期間が短期のR&Dを増やしている。第4次産業革命では、既存事業の延長線上にはない財・サービスに対する需要が増加する可能性があり、その意味で新事業の創出や技術基盤を一層強化していく必要がある。
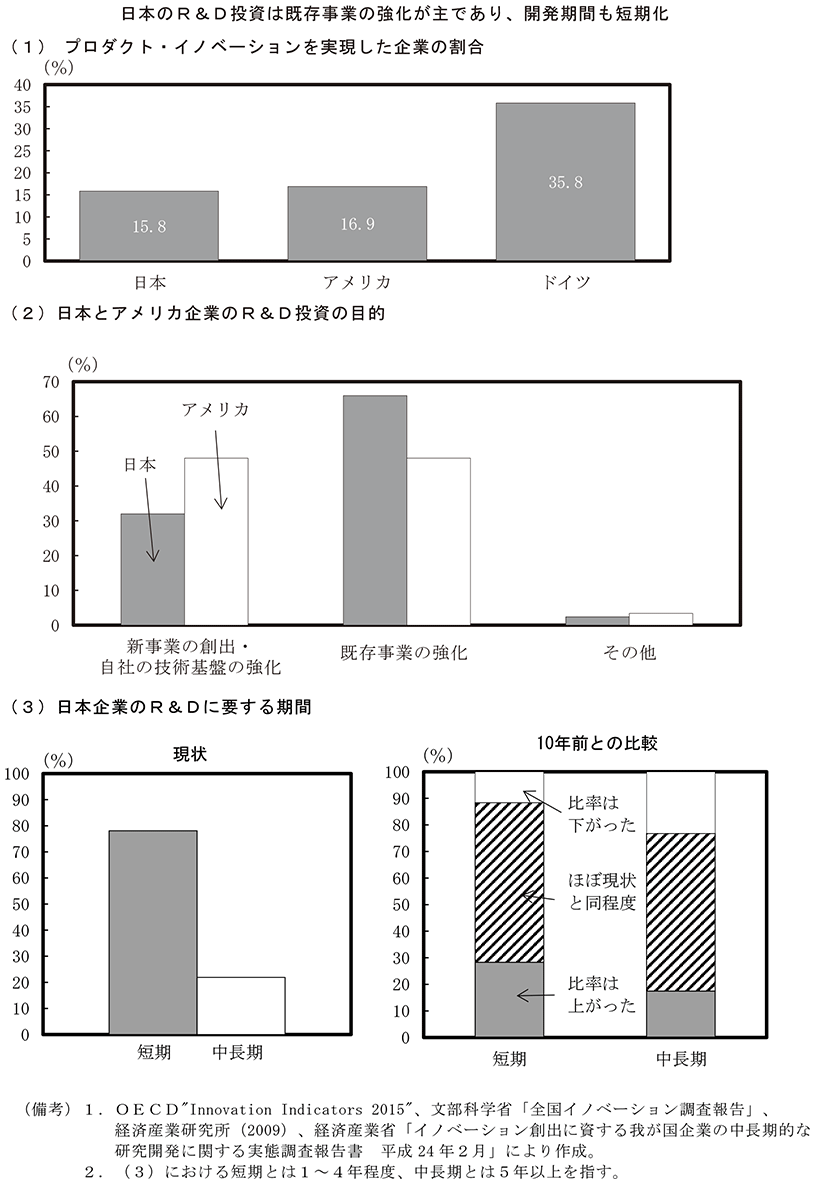
(硬直的なR&D投資への配分)
第二に、我が国では、R&D投資に配分される資金の決定が硬直的となっており、新しい財・サービスの開発に向けた機動的な資金の活用が行われていない可能性がある。その傍証として、日本企業のR&D投資が売上高に依存して決定される傾向がみられる。
上場企業の売上高とR&D投資の相関関係をみると、日本とドイツが高く、アメリカが低い(第2-2-5図(1))。さらに、マクロ要因や企業の個別要因をコントロールしても売上高とR&D投資の相関をみると、ドイツが0.65と最も高く、次いで日本が0.45、アメリカは0.2となっており、日本とドイツは比較的R&D投資が売上高に依存するのに対し、アメリカはそのような傾向は弱い(第2-2-5図(2))。
これより、我が国企業は自らの売上高が拡大しないと、将来需要が急拡大し得る財・サービスのためのR&D投資は抑制してしまう傾向があるため、このままでは日本は第4次産業革命など未来のイノベーションに向けたR&D投資がアメリカなどよりも遅れてしまう可能性がある。
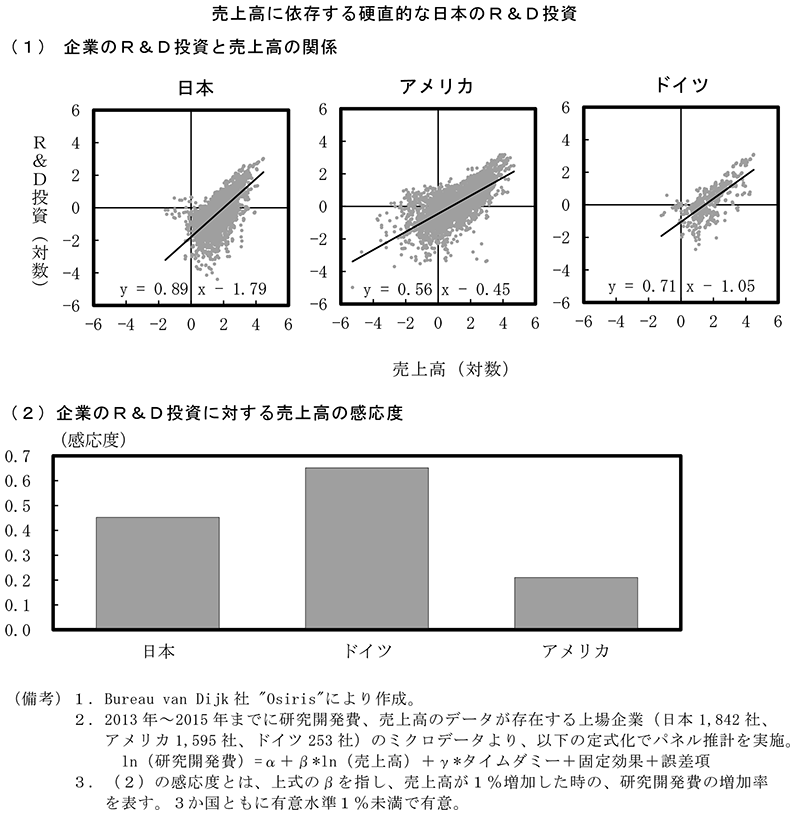
(オープンイノベーションへの取組に課題)
第三に、R&D自体が、近年サイエンス・イノベーションの進展に対応して専門化・高度化する中で、大学・研究機関、政府・自治体、個人・ユーザなど企業の枠を超えたオープンイノベーション4(Open Innovation、以下「OI」という。)への企業の取組が不足していることも要因として挙げられる5。
この背景には、OIを実現する人材の不足やOIの意義に対する経営層の認識不足などが指摘されている。経済産業省が実施した企業経営者へのアンケート調査6によると、「10年前と比べてOIへの取組がほとんど変わらない」ことの背景として、「連携先との協業をコーディネートできる人材の不足」といった専門人材の不足を挙げる企業が65%程度と目立つほか、「トップの経営層のOIの必要性、目的の理解が不十分」や「事業部門のOIの必要性、目的の理解が不十分」など経営者のOIの活用に関するマインド面の遅れを挙げる企業が2~3割弱存在する(第2-2-6図(1))。
また、企業がOIの意義を認識している場合でも、OIを推進するための人的リソースが乏しいことも課題として挙げられている(第2-2-6図(2))。同様のアンケート調査で、「10年前と比べてOIの取組が活発化」している企業による回答をみると、経営層の認識不足を指摘する割合は少ないが、「連携先との協業をコーディネートできる人材の不足」を挙げる企業が6割を超えている。このように、OIに積極的な企業でも大学や研究所などとの連携においてそれを実現できる人材の不足が課題となっていることが分かる。
こうした点は、第4次産業革命においても、自前主義ではなく、様々な技術やノウハウを持った企業や大学などの関係者と連携することで対応していくことが求められる。
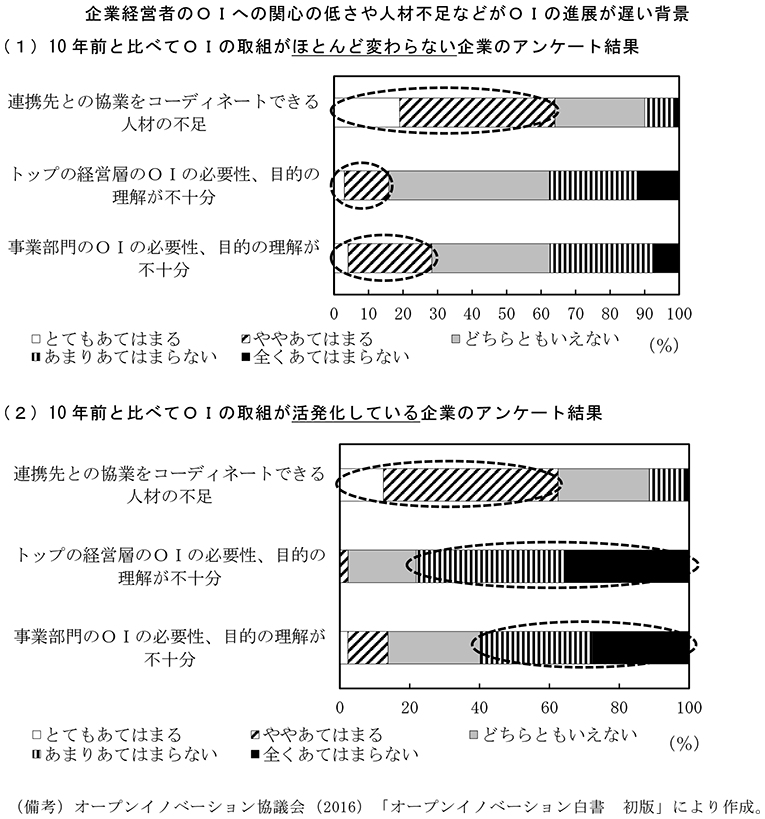
(イノベーション競争力向上に向け、先進的製品の政府調達も課題)
我が国のR&D投資が企業業績等の向上につながっていない背景として以上のような要因を指摘したが、実際、世界経済フォーラムのイノベーション競争力指数をみると7、日本はドイツ、アメリカよりも「企業のイノベーション能力(Capacity for innovation)」、「産学連携(University-industry collaboration in R&D)」について大きな差がある様子がみて取れる(第2-2-7図)。こうした指標の弱さは、日本企業が上記で述べたような既存技術開発への偏重や企業の売上に依存する硬直的なR&D投資、OIへの取組の遅れなどが影響していると考えられる。
一方、日本のイノベーション競争力が弱い要因として、これら以外に、イノベーションに対する政府の関与が弱いことが挙げられる。具体的には、日本はドイツ、アメリカに比べて「先進的製品の政府調達(Government procurement of advanced technology products)」の指数が低くなっている。アメリカの研究では、政府が企業への発注において最先端技術を要求することで、企業のR&D投資が促されていることがマイクロデータで示されている8。政府が公共投資等において、IoTやAIなどの最先端技術を用いるような仕様を企業に要求することで、こうした企業が設備投資に前向きになる可能性がある。実際、政府の成長戦略の新たな司令塔である「未来投資会議」においても、2016年9月に第4次産業革命による建設現場の生産性革命に向けて、「3年以内に、橋やトンネル、ダムなどの公共工事の現場で、測量にドローン等を投入し、施工、検査に至る建設プロセス全体を3次元データでつなぐ、新たな建設手法」の導入が決定されるなどの動きがみられている。
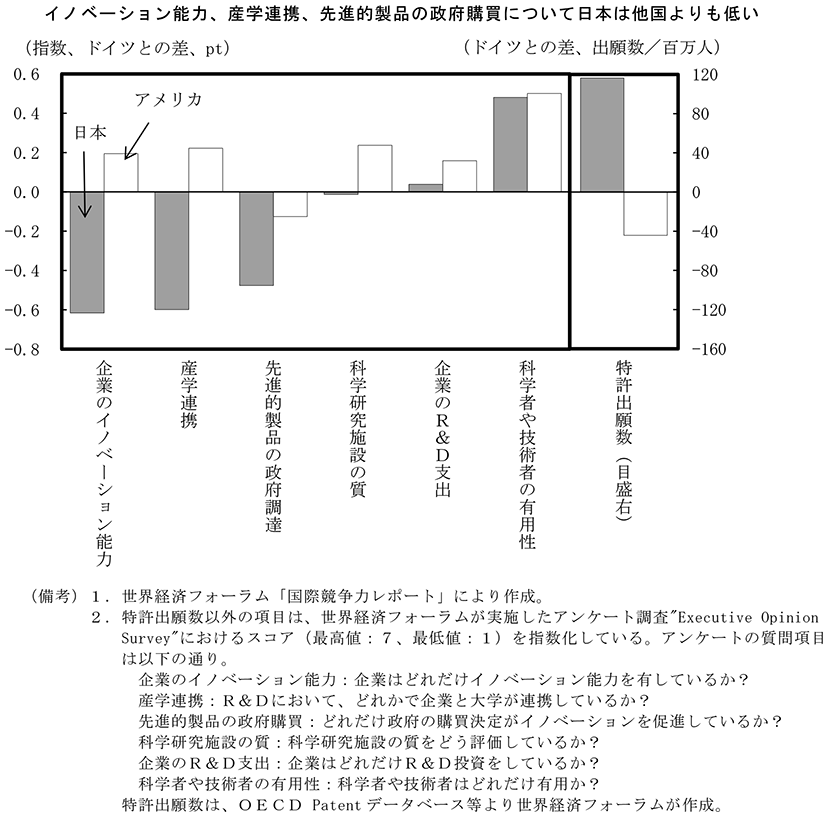
コラム2 R&D支出の資本化について
平成27年度国民経済計算年次推計においては、最近の国際基準である2008SNAへの対応を含む平成23年基準改定が行われた9、10。大きな変更点の一つとして研究開発に対する支出(以下「R&D支出」という。)がGDPの構成要素である投資(総固定資本形成)に記録されることとなったことがあるが、当コラムではその背景とインパクトについてみてみよう。
(R&D支出が資本化される背景)
この背景には、2008SNAにおいて、R&Dは知識ストックを増加させ、それを活用して新たな応用を生むような創造的活動として位置付けられたことがある。このため、R&D支出は、原則として、1993SNAのように中間消費でなく、総固定資本形成に記録し、その蓄積の結果であるストックは固定資産(内訳としては知的財産生産物)として記録することとなった11。この点について、今までの1993SNAに準拠する平成17年基準と2008SNAに準拠する平成23年基準におけるR&D支出の取扱いの違いはコラム2-1図のようにまとめられる。
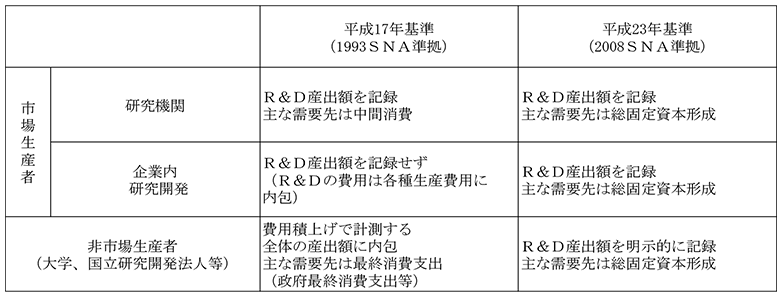
(R&D産出額の推計方法とR&D支出資本化のインパクト)
我が国におけるR&D産出額は、R&D統計調査の標準的なマニュアルに準拠した総務省の科学技術研究統計の研究費などの生産費用の積上げから推計する。これにより、国際的にみてもR&D投資が高いとされる日本のGDP水準について、既に2008SNAに移行している諸外国12との比較可能性が向上した。
R&Dの資本化によって、基準年である2011年では、名目GDPの水準は16.6兆円増加し、2015年度では19.2兆円増加するなど、改定前GDP比では2011年で3.5%13上昇した(コラム2-2図)。また、民間企業設備について新旧基準を比較すると、直近の2015年度では旧基準の70.1兆円から新基準の81.2兆円に11.1兆円増加した14。
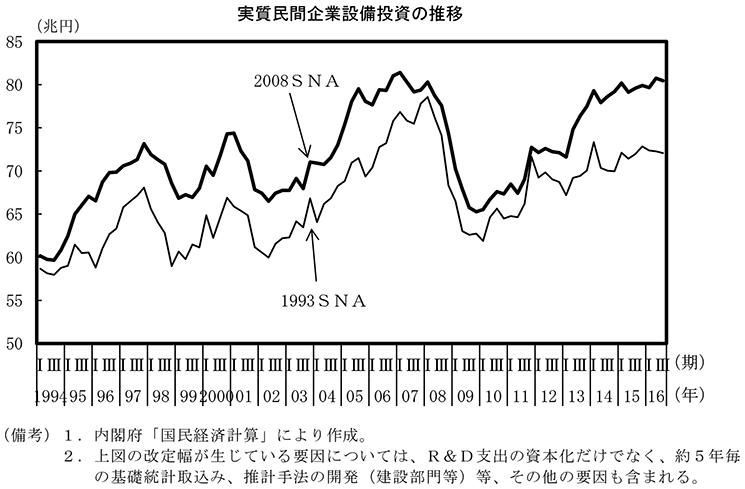
名目GDPの押上げ幅は諸外国に比べ大きい15が、本節で論じている通り、我が国のR&D投資がTFPや企業収益に与える影響は諸外国対比低く、今後、第4次産業革命に向かう中で、企業努力や政府の施策によりR&D投資によるTFPや企業収益の向上が必要とされる点には変わりはない。
3 ICTへの適応の遅れ
(日本のICT投資はアメリカよりも低調)
ICT投資・名目GDP比率の推移を日本、アメリカ、ドイツで比較すると、一貫して日本はアメリカよりも低い水準で推移している(第2-2-8図(1))。さらに、我が国のICT投資・名目GDP比率について業種別に分けてみると、製造業は2009年までは上昇傾向にあったが、ここ数年は低下している。また、非製造業では、2002年以降ほぼ一貫して低下傾向にある(第2-2-8図(2))。第2章第1節でみたように非製造業のうち、特に飲食・宿泊や個人サービスなどのサービス業では、労働生産性の向上に向けてICT投資による稼働率上昇が求められるが、当該業種においてこのようにICT投資が低調であれば、今後、我が国は第4次産業革命に乗り遅れかねない。実際、中小企業では経理業務のソフト・システムの普及が最近でも進んでおらず、例えば、給与、経理業務のパッケージソフトや調達、販売、受発注管理などのソフトを導入している中小企業は半数以下16となっているほか、財務・会計領域においてクラウド・コンピューティング17を活用している中小企業は約2%18にとどまっている。
このように我が国のICT投資は他国よりも低調であるが、この背景には何があるのであろうか。先行研究によれば、日本のICT投資における費用対効果の低さを指摘する向きが多い。以下ではそれを確かめてみよう。
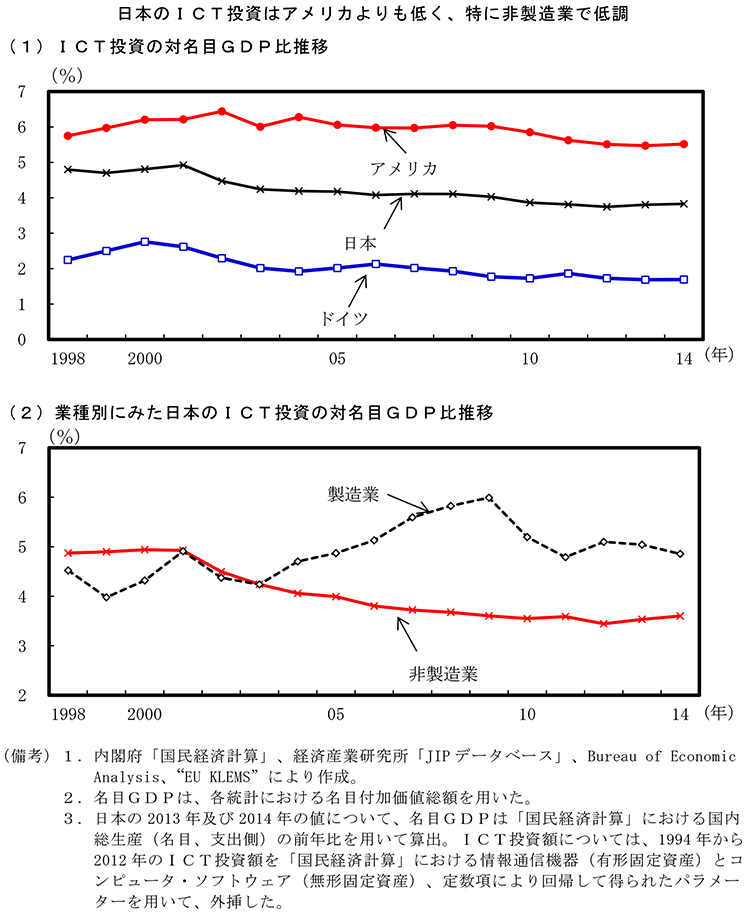
(ICT導入コストは日本の方がアメリカよりも高い)
ICT導入コストを簡易的に日米比較すると、日本の方がアメリカよりも高コストとなっていることが分かる。
企業がソフトウェア1単位を導入するのに係る費用として、ソフトウェア価格指数をみると、日米ともにパッケージソフトが低下傾向にある一方、受託開発はおおむね横ばいとなっている(第2-2-9図(1))。こうした中、企業のICT投資における受託開発とパッケージソフトの比率をみると、アメリカでは受託開発とパッケージソフト比率が6:4であるのに対し、日本では9:1となっている(第2-2-9図(2))。
このように日本企業の方がアメリカ企業よりもICT投資に係るコストが割高となる傾向がみて取れる。しかし、コストが高いからといって、必ずしも費用対効果が低いとは限らない。日本企業のICT投資がコストの掛かる受託開発が主であっても、そうしたコストを上回る効果を上げていれば費用対効果は高い場合もある。そこで、次に企業アンケートからICT投資の効果を確認しよう。
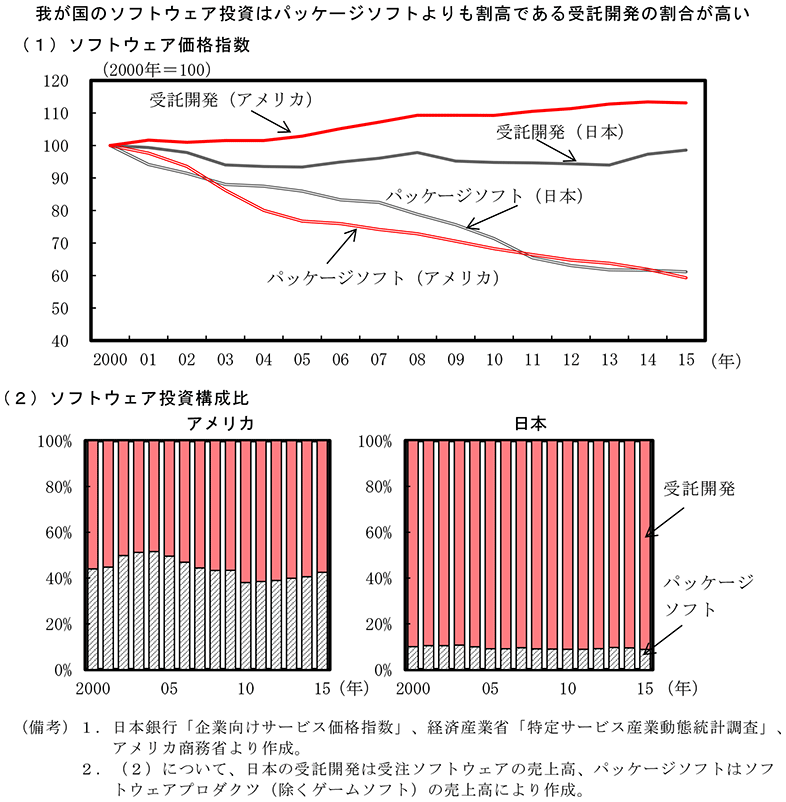
(我が国では企業組織改革を伴わないICT投資は効果が得られにくい)
ICT投資による経営面、顧客面、コスト面など様々な効果について、日本、アメリカ、ドイツ、韓国の企業に対して実施したアンケート調査19をみると、日本企業は導入効果がみられなかったと回答する企業が多い一方、アメリカやドイツの企業は効果があったと回答する企業が多い(第2-2-10図(1))。特にアメリカの企業は業績面、顧客面、付加価値面20において、他国よりも相対的に導入効果を指摘する企業が多い一方、日本企業は全ての面で他国に対して相対的に効果が乏しい結果となっている。
こうした分析結果と日本企業はICT投資における受託開発の割合が高いこととを踏まえると、ICT投資における費用対効果は低いと言えるが、なぜ受託生産、すなわち企業の業務の状況に合わせたICTにもかかわらず、その効果が得られなかったと感じている企業が多いのであろうか。
この問題意識に立って当該アンケート調査結果を分析した研究21によると、我が国では、ICT投資に際し、組織改革として「経営陣と中間管理職の間での権限の見直し」を実行した企業では、そのうち8割程度が経営計画の立案と実行能力の向上効果があったと回答した一方、こうした組織変革を実施しなかった企業では、その4割程度しか当該効果があったと回答していない(第2-2-10図(2))。これは、日本企業はICT投資の効果を上げるためには、組織変革を同時に行わなければならないことを示している。実際、他の研究22では、我が国では新たなICT関連システムの導入に伴って必要となる業務プロセスの見直しや組織改革がスムーズに行われていないため、ICT関連のシステムを導入しても部門ごとでの最適化にとどまり全社的な最適化が行われていない結果、当該システム導入による効果は限定的であると指摘されている。
先のアンケート調査結果をし細にみると、アメリカ、ドイツでは、組織変革の実施の有無にかかわらず、導入効果があったとする企業の割合はおおむね7割以上と高いほか、我が国の場合と比較して両者の差も小さい。日本企業では両者の間に大きな差があったが、なぜアメリカ、ドイツの企業ではそのような違いがみられないのであろうか。篠崎・佐藤(2011)23によると、アメリカやドイツでは、経営の「仕組み」がもともとICTに親和的であり、企業改革がなくとも一定の効果が得やすかったことがあるとしている。実際、製造業を対象に企業組織内部において管理職にどの程度権限が与えられているか、すなわち、企業組織の分権度を調査した他の研究24では、日本の分権度は対象国12か国中、最下位から2番目である一方、アメリカは最上位から2番目、ドイツは4番目となっている(第2-2-10図(3))。ICT資本に合わせた人材の再配置を伴う事務フロー等の見直しは、管理職が現場の人員構成や仕事内容を変える権限を有しているかに依存する面がある。こうしたことから我が国とアメリカ、ドイツとの間の企業組織構造の違いがICTの導入と企業業績に影響した可能性がある。
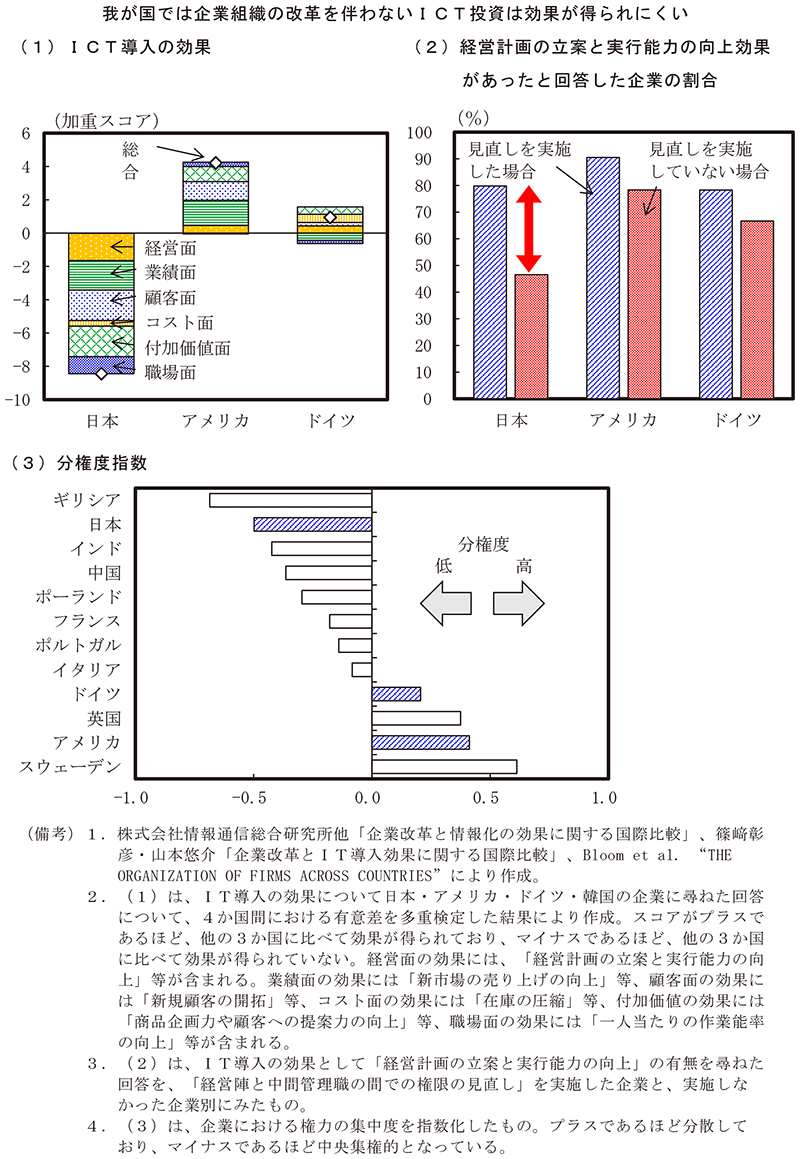
4 第4次産業革命に対応した人的資本の充実
こうした課題を抱えつつ、日本が第4次産業革命のメリットを最大限享受するために、力を入れていくべきこととして、科学技術イノベーションを支える人材力の徹底的な強化がある。
(イノベーションを支える人材)
第一に、研究者の育成である。若手研究者のキャリアパスの明確化とキャリアの段階に応じ能力・意欲を発揮できる環境整備が必要である。具体的には、大学等におけるシニアへの年俸制導入や任期付雇用転換等を通じた若手向け任期なしポストの拡充促進、テニュアトラック制の原則導入促進、大学の若手本務教員の増加などが挙げられる。
第二に、研究人材の流動化である。OIを推進していくためには、人材が移動し、人材・知・資金が結集する「場」が形成されることが重要である。科学技術基本計画では、企業・大学・公的研究機関における推進体制強化により、セクター間の研究者移動数を第5期科学技術基本計画期間中に2割増、大学・国立研究開発法人の企業からの共同研究受入額を同期間中に5割増となることを目標として設定している。また、人材の流動化や所属する企業を超えた交流を促進するためにも、副業や兼業の許可なども重要である。
第三に、データ分析を行う専門的な人材としての「データサイエンティスト」の育成がある。IoT及びビッグデータの活用により、生産効率の向上や消費者の需要に対応した財・サービスを開発するためには、単に企業内・組織内のデータを集約して処理するだけの人材ではなく、そこから有用な知見を引き出した上で、企業の意思決定に活かすことのできる人材が求められる。こうした人材に必要なスキルとしては、統計学に関する知識、分析ツールやデータ処理基盤を使いこなす能力、ビジネスを理解した上で問題を発見し解決できる能力、データ分析で得られた知見を他人に伝えるコミュニケーション能力などが挙げられており、政府・企業・教育機関は、こうした人材を育成するために、現時点で能力開発に必要な資金や時間が乏しい人々も含めた、幅広い労働者のスキル底上げのためにも、能力開発に係る公的な支援を実施する必要がある。

