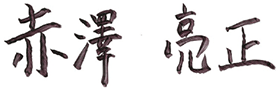令和7年度年次経済財政報告公表に当たって
日本経済は、緩やかな景気回復が続く中で、2024年には名目GDPが初めて600兆円を超え、設備投資は過去最高を更新し、2025年の春季労使交渉における賃上げ率が33年ぶりとなった昨年を更に上回るなど、明るい動きが各所にみられています。一方で、食料品など身近な物の価格の上昇が続き、GDPの過半を占める個人消費の回復は、賃金・所得の伸びに比べて力強さを欠いた状況にあります。こうした中で、米国の第二次トランプ政権における追加関税措置は、日本経済を直接・間接的に下押しする大きなリスクとなっています。
日本経済にこうした逆風が吹く中、これまでのコストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせずに、民需主導の成長型経済への移行を確実なものにするためには、「賃上げこそが成長戦略の要」との認識の下、物価高を上回る賃上げを実現していくことが何よりも重要です。2029年度までの5年間で、日本経済全体で、持続的・安定的な物価上昇の下、実質賃金で1パーセント程度の上昇を賃上げの新たなノルムとして我が国に定着させるという目標を実現するため、地域の中堅・中小企業の最低賃金を含む賃上げの環境整備として、適切な価格転嫁や生産性向上、経営基盤を強化する事業承継・M&Aを後押しするなど、施策を総動員し、全国津々浦々で物価上昇以上の賃金上昇を早急に実現すべく、全力で取り組んでいく必要があります。また、こうした賃上げの効果が出るまでの対応として、物価高に苦しむ家計や事業活動に与える影響に細心の注意を払いながら、物価高対策に取り組んでいくことも極めて重要です。
令和7年度年次経済財政報告は、昭和22年に発刊されて以来、今回で79回目となります。今回の報告では、現下の実体経済や賃金・物価の動向に関して、様々な統計・データを駆使し、米国の関税措置による我が国経済への影響や今後のリスクを詳細に点検しています。また、個人消費の回復が力強さを欠く要因を多面的に分析するとともに、その鍵となる持続的な賃金上昇に向け、企業の豊富な資金を国内投資や賃上げに結び付けていくための課題や、賃金をシグナルとした円滑な労働移動の実現に向けた課題等を議論しています。さらに、国際社会が戦後培ってきた自由で開かれた貿易・投資体制が転換点を迎えている中、我が国のグローバル経済との関わりを詳細に分析した上で、世界経済の持続的な成長に資する観点からも、我が国として、CPTPPの拡充・発展等を通じ、自由で公正なルールに基づく国際経済秩序の維持・強化に取り組むことの重要性を確認しています。
本報告での客観的データと分析が、日本経済の抱える短期、中長期の課題解決のため、政策立案・遂行のための基盤として活用されるとともに、広く経済の現状認識や実証分析などにも活用されるものとなることを心より祈っております。
令和7年7月
経済財政政策担当大臣