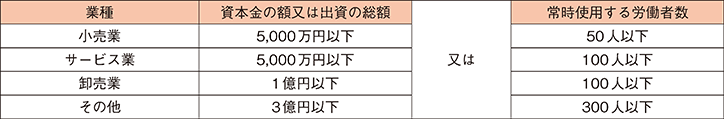第2章 労働力の確保・質の向上に向けた課題 第1節
第1節 成長と分配からみた課題
我が国の一人当たり賃金や世帯所得が伸び悩んできたのはなぜか。本節では、これらの伸び悩みの動向とその要因について確認するとともに、成長と分配それぞれの面からの課題について確認する。
1 成長からみた課題
はじめに、賃金や所得の動向を左右する経済成長の姿について概観する。経済成長率を供給面から労働、資本、全要素生産性(TFP)の寄与に分解し、主要先進国との比較等を通じた我が国の特徴を明らかにする。
●労働時間当たり実質GDPは主要先進国と遜色のない伸び
我が国と主要先進国の経済動向について、まず、1990年を100とした実質GDPの推移を比較したい。我が国の実質GDPは、1990年代半ば頃までは他の主要先進国と比べて増加テンポに大きな差はないものの、その後は成長率に顕著な差が表れ、緩やかなものにとどまってきた(第2-1-1図(1))。
一方で、人口一人当たり実質GDP1の推移をみると、我が国は主要先進国よりも先に人口減少に転じたことから、主要先進国との増加率の差は縮小し、特にリーマンショック以降感染拡大前までの増加テンポはフランスを上回っている(第2-1-1図(2))。
さらに、実質GDPを就業者数×一人当たり労働時間で示されるマクロの総労働時間(マンアワーベースの労働投入量)で割った労働時間当たり実質GDP(時間当たり労働生産性)をみると、アメリカには劣るものの、ドイツやフランスを上回るなど主要先進国と遜色のない伸びとなっている(第2-1-1図(3))。我が国の就業者一人当たり労働時間が減少し、総労働時間が人口減少のテンポを上回って減少してきたことが背景にある。今後、人口減少が一層進む中では、人への投資の強化を通じ、時間当たり労働生産性を更に高めていくとともに、子育て支援や働き方改革等により労働参加を促し、総労働時間を確保していくことが重要となる。
●人口減少と労働時間の減少が中長期的に経済成長を押下げ
我が国の実質GDP成長率が緩やかなものにとどまってきた背景には、例えば内閣府(2021)でも指摘しているとおり、デフレ下での設備投資の伸び悩みなど様々な要因があるが、本章で焦点を当てる「人」を取り巻く環境変化についてみると、上記で確認したように、人口減少と労働時間の減少という二つの減少要因が大きな影響を与えてきたことがわかる。そこでこれらの動向について詳細を確認してみよう。
まず人口についてみると、生産年齢人口(15~64歳)が1997年をピークに減少に転じ、人口も2008年をピークに減少が続いている(第2-1-2図(1))。感染拡大前の2019年の人口は、ピーク時からは男女合わせて約150万人減少した。こうした中、男性の就業者数・雇用者数は生産年齢人口と歩調を合わせる形で1990年代半ばから2000年代半ばにかけて緩やかに減少してきたが、2010年代半ばまでおおむね横ばいで推移した後、感染拡大前の2019年までは緩やかに増加してきた。また、女性の就業者数は、2012年頃まで緩やかに増加が続いてきたが、その後は、労働参加が更に進んだことを背景に、感染拡大前の2019年まで顕著に増加してきたことがわかる。
次に、一般労働者の労働時間の推移について確認したい。ここではおおむねフルタイムの労働者である一般労働者に着目する。一人当たり労働時間(月間所定内労働時間)をみると、男女ともに1990年代半ばにかけて大きく減少した後、緩やかな減少が続いている(第2-1-2図(2))。こうした背景には、完全週休二日制の普及2に加え、2019年以降は働き方改革の取組3による影響もあると考えられる。また、一人当たり労働時間は、男性に比べて女性の方が少ない状況が続いている。さらに、詳しくは後述するが、短時間労働者4の女性や高齢者の労働参加が増加し、就業者全体に占める割合が高まることにより、これらも含めて平均した一人当たり労働時間は、更に減少することになる。
●一人当たり労働時間の減少が実質GDPの押下げに寄与
実質GDPの動向を左右する要因について、労働面からみると、人口減少を背景とした就業者数の減少や一人当たり労働時間の減少は、経済成長の供給面の源泉の一つであるマクロの総労働時間(マンアワーベースの労働投入量)の減少につながる。その影響を確認するため、実質GDP成長率を要因分解すると、1990年から感染拡大前までの2019年までの累積で実質GDPは26%(年率0.8%程度)成長したが、時間当たり労働生産性の上昇と就業者数の増加が押上げに寄与する一方、一人当たり労働時間が押下げに大きく寄与し、就業者数と一人当たり労働時間を合わせた総労働時間の寄与はマイナスとなっている(第2-1-3図)。具体的には、時間当たり労働生産性の伸びは累積で40%ポイント程度(年率1.2%ポイント程度)、実質GDPを押し上げている。また、就業者数の押上げ寄与は、2012年頃に一旦ほぼ無くなったものの、その後の就業者数の増加により、2019年時点では実質GDPを累積で8%ポイント程度(年率0.3%ポイント程度)押し上げている。一方、労働時間は累積で21%ポイント程度(年率0.7%ポイント程度)、実質GDPを押し下げている。
●2013年以降、TFPと労働の寄与が高まる一方、資本の寄与が大幅に縮小
それでは、マンアワーベースの労働投入量以外の要因は経済成長にどのような影響を与えてきたのだろうか。OECDのデータを用いて、実質GDP成長率を全要素生産性(TFP)、ICT資本、非ICT資本、労働投入量に寄与分解して、傾向をみてみたい。デフレ状況となった2000年から2012年の我が国では、労働投入量がマイナスに寄与した一方、TFPや資本が成長に寄与している(第2-1-4図)。ただし、デフレによる投資低迷等を背景に特に非ICT資本の寄与が小さく、ICT資本と合わせた資本全体の寄与は主要先進国の中で最も小さい。
デフレ状況ではなくなった2013年以降についてみると、我が国ではTFPの寄与は大きく高まり、2000年代はマイナスに寄与していた労働投入量も女性や高齢者などの労働参加が進んだことによりプラス寄与に転じた。一方、資本の寄与は2000年代から更に縮小し、他の主要先進国との差は更に拡大した。特に、経済活動での重要性が高まったICT資本の寄与はほぼゼロとなっている。
今後、経済成長を高めていくためには、人口減少や高齢化が本格化する中で、労働投入量を引き続き確保する努力を続けるとともに、人への投資を強化し、労働の質をいかに高めていくかが重要となる。労働の質の向上はTFPの拡大につながる。また、デフレ状況でなくなったにもかかわらず、低迷してきた資本の寄与を高めることも引き続き大きな課題である。そのため、本章では、第2節において労働の量について、第3節において労働の質の向上に関する課題に焦点を当てて議論を進めることとしたい。資本をめぐる課題は第3章で取り上げることとする。
2 分配からみた課題:一人当たり賃金の動向
前項では、我が国の労働時間当たり実質GDPは主要先進国と遜色のない伸びであることを確認したが、本項では、その分配先である賃金の動向についてみていきたい。その際、一人当たり賃金の動向とともに、その背景にある雇用者数の属性の変化や一人当たり労働時間の変化等についても確認することとしたい。
●過去30年間にわたり、我が国の一人当たり賃金はおおむね横ばい
まず、一人当たり賃金の動向について、主要先進国との比較や年齢別にみていこう。1991年を100とした我が国と主要先進国の一人当たり名目賃金の推移を比較すると、1991年から感染拡大前の2019年までの間、フランス(年率約2.3%)から英国(年率約3.2%)まで伸びに違いはあるものの、いずれの国においても安定して増加しているのに対し、我が国では約30年間、おおむね横ばいにとどまっている(第2-1-5図(1))。一人当たり実質賃金を比較しても、主要先進国の伸びが物価上昇分だけ低下する一方、長引くデフレの下で我が国の一人当たり実質賃金がおおむね横ばいにとどまってきた姿は大きくは変わらない(第2-1-5図(2))。
一人当たり賃金の伸び悩みの要因としては、<1>デフレが長期化する中で企業行動が慎重化した結果、投資が低迷し稼ぐ力が十分に高まらなかったこと、<2>賃金が人への投資ではなくコストと捉えられた結果、実質賃金の伸びは時間当たり労働生産性の伸びを下回り、十分な分配も行われなかったこと(第1章第2節参照)、<3>女性や高齢者の労働参加が進む中で中長期的に非正規雇用者比率が高まってきたこと(後掲第2-3-1図(2))、<4>定年延長等もあり、賃金カーブが緩やかになってきたこと(後掲第2-3-6図)、などが挙げられる。
次に、このような賃金の伸び悩みの背景を定量的に探るべく、雇用者全体を男女別、64歳以下・65歳以上の年齢別、一般・短時間労働者別の8つの属性に分けた上で、一人当たり名目賃金の変化を、<1>属性ごとの時給の変化、<2>属性ごとの労働時間の変化、<3>各属性間の構成比の変化、に寄与分解してみたい。なお、ここでは、比較可能な統計で最も遡ることができる1993年と比較した。その結果、まず、<1>デフレの下、1997年以降2013年まで時給が上昇してこなかったことに加え、<2>労働時間と<3>構成比の変化の要因が一人当たり賃金の押下げに寄与してきたことがわかる(第2-1-6図)。<2>労働時間については、第1項でもみたとおり、減少が続いてきたことが明らかであるが、<3>構成比の変化については、相対的に賃金水準が低い非正規の女性や高齢者が増加したことによるものであり、詳細は次の段落で確認することとしたい。一方で、2013年以降は、<1>時給の増加によるプラス寄与が拡大していることが確認できる。詳細は二つ後の段落で確認することとしたい。しかしながら、第1章第2節でも論じたとおり、労働時間当たり実質GDPの伸びと比較すると、時給の伸びはこれまで十分とはいえない。今後、正規雇用での就業を希望する非正規雇用労働者の正規化や同一労働同一賃金の徹底等に加え、時間当たり労働生産性の伸びと物価上昇率の合計に見合った時給や賃金上昇の実現に向けた取組が期待される。
●賃金水準の低い非正規雇用者数が女性や高齢者を中心に増加
次に、雇用の構成変化について、より詳細に確認するため、1990年以降の雇用者数の推移を男女別・雇用形態別・年齢別の属性別にみていきたい。
男性では、44歳以下の正規雇用者数が減少する一方で、これらの年齢層における非正規雇用者数が2010年代半ばにかけて増加した後、おおむね横ばいで推移している(第2-1-7図(1)<1>、<2>)5。また、前述のような高齢者の雇用機会の確保が進む中で、55歳以上については、正規・非正規雇用者数ともに増加し、特に2010年代半ば以降、65歳以上の非正規雇用者数が大幅に増加した。一方、女性では、2000年代半ばにかけて減少した正規雇用者数は、2010年代半ば以降、全ての年齢層において増加した。非正規雇用者数は2000年代半ばにかけて全ての年齢層で増加し、2010年以降は45歳以上を中心に大幅に増加した(第2-1-7図(1)<3>、<4>)。
なお、データが利用できる2007年と2021年との間で産業別の雇用者数を比較すると6、男性の正規雇用者では約15年間で大きな変化はみられないものの、非正規雇用者では卸売・小売業、製造業、医療・福祉、宿泊・飲食サービス業等で増加している(第2-1-7図(2)<1>、<2>)。一方、女性の正規雇用者は、製造業等において減少する一方、介護を含む医療・福祉業の雇用者がその減少幅を上回って増加し、全体としても増加している。非正規雇用者でも正規雇用者と同様の動きに加え、卸売・小売業や宿泊・飲食サービス業をはじめ幅広い産業で増加している(第2-1-7図(2)<3>、<4>)。
前掲第2-1-6図において雇用者の構成比の変化が一人当たり名目賃金を押し下げてきたことをみたが、ここで整理したように、女性や高齢者の労働参加が進み、相対的に賃金が低い非正規雇用者がこれらの層を中心に増加したことが、平均的な一人当たり名目賃金の伸び悩みの背景にあることが確認できる。
●時給の増加は、短時間労働者や女性の一部にとどまる
時給の増加は一人当たり名目賃金の増加に寄与し、特に2013年以降、プラス寄与が拡大してきたことを確認したが、このような時給の増加は全ての属性の労働者においてみられるのだろうか。まず一般労働者の時給について、男女別・年齢別に確認したい。女性の時給は総じて緩やかに増加しており、特に、2000年代半ば以降、40代・50代を中心に時給の増加が顕著にみられている(第2-1-8図(1))。一方、男性の時給は、年齢階級計でみると、デフレ状況となった2000年前後以降、緩やかな減少に転じ、2013年頃から上昇に転じている。2000年代の時給の減少は30代・40代で顕著であり、40代は直近まで減少傾向が続いている。50代については、定年延長等の取組が実施される中で、1990年代初めや2010年代半ば以降緩やかに増加している。なお、20~50代の全ての年齢階層において男性に比べて女性の時給が低い状況は変わっておらず、年齢が高まるほどその差は広がっているが、男女間の賃金格差については第3節で論じる。
続いて、短時間労働者の時給についてみると、調査方法の変更や集計要件の見直し7により、男性を中心に、30~50代の時給水準が大幅に増加している点には注意が必要であるが、それらの影響を除いてみても、30~50代の女性を中心に、2010年代半ば以降、緩やかな増加が続いている(第2-1-8図(2))。
このように、時給の増加は、短時間労働者や女性の一部が中心となってきたことから、今後も継続的・安定的な賃上げが進むとともに、同一労働同一賃金8の取組や賃金格差の見える化等を通じ、雇用形態間での賃金差の是正が進むことが期待される。
3 分配からみた課題:世帯所得の動向
前項では一人当たり賃金の動向を確認したが、以下では世帯所得の動向についてみていく9。中長期的な世帯所得の分布の変化やその背景にある要因を明らかにし、再分配前・再分配後の所得の特徴と課題を整理することとしたい。
●高齢者世帯や単身世帯の増加に伴い、相対的に所得が低めの世帯の割合が上昇
はじめに、「全国消費実態調査」及び「全国家計構造調査」を用いて、1994年から2019年の25年間で、我が国の平均的な世帯所得の分布にどのような変化があったかを確認する10。まず、全世帯の所得分布をみると、再分配前・再分配後ともに、25年間で中央値は100万円以上減少した(第2-1-9図(1))。特に、再分配前でみて、世帯所得500万円以上の世帯の割合が低下する一方で、所得が低めの400万円未満の世帯の占める割合が上昇している。この理由としては、高齢者世帯が増加したこと、単身世帯数が大幅に増加したことが挙げられ11、特に所得200万円未満の65歳以上の高齢単身世帯が大幅に増加した(第2-1-9図(2))。
●中長期的には35~54歳の世帯の所得の中央値の減少が顕著
次に、所得分布の変化を世帯主の年齢階級別に詳しくみていきたい。まず再分配前の所得分布の中央値をみると、65歳以上の世帯では25年間で大きな変化はみられないものの、25~64歳の各世帯ではいずれも減少している(第2-1-10図(1))。中でも、35~44歳、45~54歳の世帯の中央値は大きく減少しており、所得500万円未満の世帯所得の割合が全体的に上昇している。再分配後の所得分布についてみると、全ての年齢階層において、中央値が減少しており、特に35~44歳、45~54歳の世帯での減少が顕著となっている(第2-1-10図(2))。
●35~54歳の世帯では、おおむね世帯主所得が減少しており、背景には非正規雇用の増加も
各年齢階級の所得分布の中央値が減少している背景の一つには、前述のとおり相対的に低所得の単身世帯の増加が挙げられる(前掲第2-1-9図(2))。加えて、所得分布の変化は、世帯類型の変化や所得稼得者の状況変化などにも左右されることから、全世帯のほか、単身世帯、夫婦のみ世帯、夫婦と子世帯、ひとり親世帯の類型に分けて、世帯主の所得分布の変化についてみていきたい。
2019年の世帯主所得は、1994年と比べて全体的にその水準が低下し、かつ年齢が高まっても増加が緩やかになっており12、特に夫婦のみ世帯やひとり親世帯においてその傾向が強くみられる(第2-1-11図(1))。また、大幅な世帯所得の中央値の減少がみられた35~54歳の世帯では、いずれの世帯類型においてもおおむね世帯主所得が減少している。これらの年齢層について世帯主の雇用形態を確認すると、非正規雇用者比率が高まっていることから、世帯主の雇用形態の変化も世帯主所得の減少に大きな影響を及ぼしていると考えられる(第2-1-11図(2))。また、ベースアップや定期昇給のペースが緩やかになっている13ことも影響しているとみられる。
なお、単身世帯や夫婦のみ世帯を中心に、55~64歳の世帯主所得が増加している。これらの世帯主の非正規雇用者比率も上昇しているが、世帯主所得の増加要因としては、定年年齢の引上げや年金支給開始年齢の引上げ等に伴い、正規・非正規を問わず、労働所得を得る者の割合が上昇したことがあると考えられる。65歳以上の高齢者の労働参加の進展により、今後は65歳以上の世帯においても、同様の所得増加の実現が期待される。
●共働き世帯が増加しているものの、配偶者の所得は引き続き50~150万円に集中
さらに、世帯主に続いて配偶者の所得分布の変化についても確認したい。ここでは特に世帯所得の減少が顕著だった35~54歳の世帯の背景を確認するため、世帯主が49歳以下の世帯に焦点を当て、夫婦のみの世帯、夫婦と18歳以下の子を持つ世帯の所得の動向についてみていくこととする。
まず、配偶者の就業形態を確認すると、両世帯ともに、1994年に比べて2019年では、共働き世帯が全体の約4~5割から約7~8割にまで増加している(第2-1-12図(1))。1994年と2019年で就業形態の分類に違いがある点には注意が必要であるが、正規、非正規の双方での就業割合が大きく高まっていることがわかる。
こうした中で、配偶者の所得分布をみると、夫婦のみ世帯・夫婦と子世帯ともに、2019年は非正規雇用の配偶者の所得分布がより高い所得階級にまで広がっており、正規雇用の配偶者の所得分布割合も、夫婦のみ世帯を中心に、より高い所得階級で上昇していることがわかる(第2-1-12図(2))。すなわち、世帯主所得が減少する中で、配偶者の所得が家計を支えているといえよう。ただし、いずれの世帯類型においても、配偶者所得の低い階級では非正規雇用が多く、所得階級が高くなるにつれて、正規雇用の割合が大きくなる点については、変化はみられない。
また、1994年・2019年ともに、いずれの世帯類型においても、配偶者所得は50~100万円の階級の割合が大きく、2019年では100~150万円の階級の割合も大きい。この要因の一つとしては、配偶者が収入を一定の金額以下に抑えるために就職時間や就業日数を調整する「就業調整」が考えられ、詳細は次節で述べることとしたい。