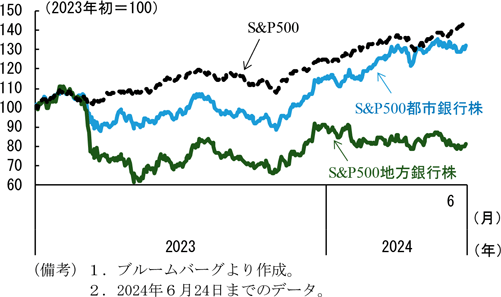第2章 2024年前半の世界経済の動向(第1節)
第1節 アメリカの景気動向
本節では、主に2024年前半のアメリカ経済を概観するとともに、景気拡大が継続している背景や住宅市場が抱える構造的な問題を中心に分析する。
1.マクロ経済の動向
(景気は内需主導で拡大)
アメリカ経済は、個人消費主導で景気は拡大している。2023年7-9月期には、実質GDPが潜在GDPを上回り、景気は回復局面から拡大局面に転換した(第2-1-1図)。実質GDPは22年7-9月期以降、8四半期連続でプラス成長が継続しており、前期比年率でおおむね2%以上の内需主導の高成長が続いている(第2-1-2図)。特に23年後半は、個人消費や設備投資の増加により、潜在成長率を大幅に上回る成長を遂げた。24年1-3月期の成長率は7四半期ぶりに2%を下回ったものの、外需や在庫投資の下押し寄与が大きく、こうした要因を取り除いた国内最終需要40では前期比年率2.4%となっており、内需は依然として強さが継続している。その後、24年4―6月期は、個人消費や設備投資の寄与が前期と比べて増加する中で、前期比年率2.8%と高成長が続いている。
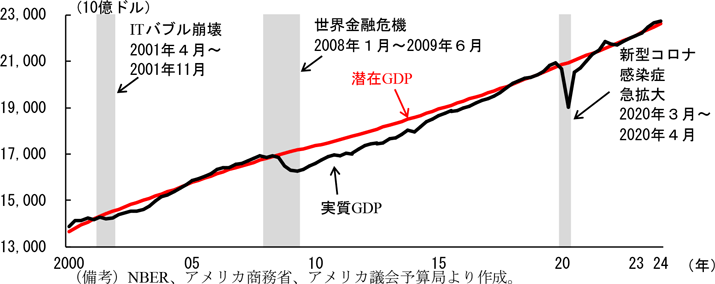
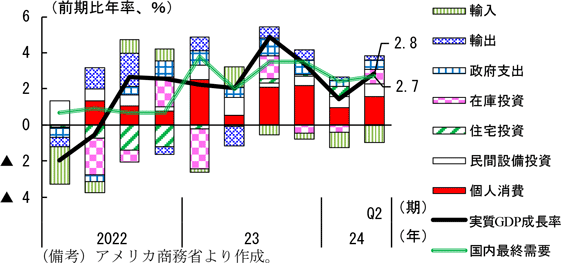
このように23年以降のアメリカ経済は、政策金利(フェデラル・ファンド・レート(FF金利))が5.25~5.5%ポイントで高止まる下でも、個人消費や設備投資の大幅な減速はみられず、実質GDP成長率は事前の予想を上回り続けてきた41。
アメリカ経済の高成長が続く理由としては、(1)物価上昇を上回る名目賃金上昇の継続、(2)超過貯蓄の取崩し、(3)半導体法等の財政政策による設備投資の押上げ、(4)移民流入の上振れによる潜在成長率の上昇が要因として考えられるところ、本項においてはこれらの要因について確認する。また、中長期的には需給はひっ迫しているものの、このところ弱い動きがみられる住宅市場の動向や、米中貿易摩擦の影響がみられる財貿易の動向についても確認する。
(個人消費は、物価上昇を上回る賃金上昇や超過貯蓄の取崩し等を受け、増加)
まず、名目賃金と超過貯蓄の推移について確認する。過去20年程度を振り返ると、消費者物価上昇率(総合)は平均で前年比2.6%であったが、名目賃金上昇率は同3.2%であり、長期的には物価を上回る賃金上昇が実現されている。感染症拡大後は経済活動の再開とロシアによるウクライナ侵略(以下「ウクライナ侵略」という。)の影響もあり、両者の関係が逆転する局面がみられたものの、23年半ば以降は名目賃金上昇率が消費者物価上昇率を上回り、実質賃金の上昇につながっている(第2-1-3図、第2-1-4図)。
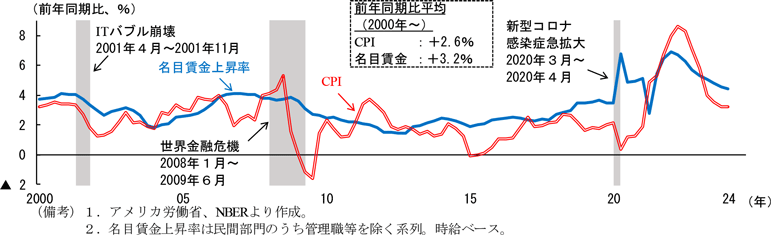
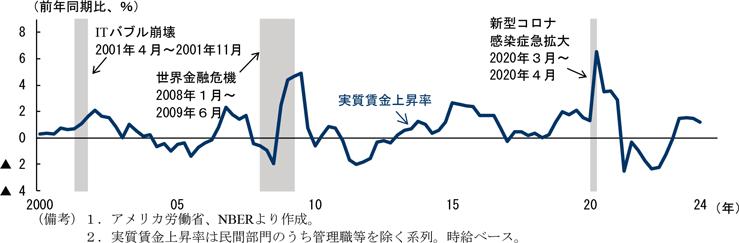
また、感染症拡大を受けた消費抑制及び連邦政府による現金給付等により形成された家計の超過貯蓄は、物価上昇の影響を除いた実質ベースでみると、残高は21年に2.3兆ドルに達した後、21年後半以降緩やかな取崩しが進み、個人消費を下支えしていると考えられる42。なお、残高は24年1-3月期時点で約1.3兆ドル残っており、更なる取崩しの余地がみられる(第2-1-5図)43。
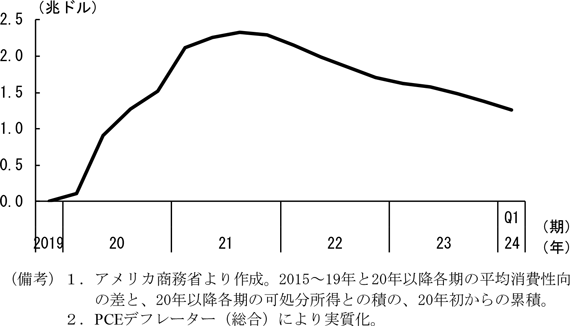
以上のような実質賃金の上昇と超過貯蓄の取崩しの進展を背景に、実質個人消費支出は、サービス消費を中心に増加傾向が続いている(第2-1-6図)44。サービス消費の内訳をみると、介護サービス等が含まれるヘルスケアが安定的に増加する中で、23年後半以降は株高を背景として金融・保険サービスも大幅に増加し、全体的に増加傾向となっている。財消費は、23年に大幅に増加した後、23年末から24年初にかけて、寒波の影響もあり一服感がみられたものの、その後再び増加に転じている。なお、24年に入ってからはガソリンや衣料品、輸送サービス等、限定的ではあるが減速感がみられる項目も確認できる。これらの項目では、24年以降、物価上昇率が加速していることが背景にあると考えられる。
さらに、耐久財消費の約4分の1を占める自動車の販売動向について確認する。2022年10月以降は供給制約の緩和に伴って自動車販売台数は持ち直し傾向に転じ、2023年4月に1,500万台(年率)を超えるまでに回復したが、その後はおおむね横ばい傾向で推移している(第2-1-7図)。感染症拡大前の平均的な販売台数は1,700万台(年率)であったが、その水準まで回復しない背景として、23年後半における部品不足による工場の稼働停止や、大手自動車メーカー3社における一斉ストライキによる在庫回復の遅れが考えられる。2024年以降は、自動車の供給増により在庫は一段と改善したが、24年4月の在庫/販売比率は1.3か月と、依然として感染症拡大前の平均的な水準(2015年~19年平均:2.6か月)より低く、販売店における店頭ラインナップが不十分な状態が続いている(第2-1-8図)45。
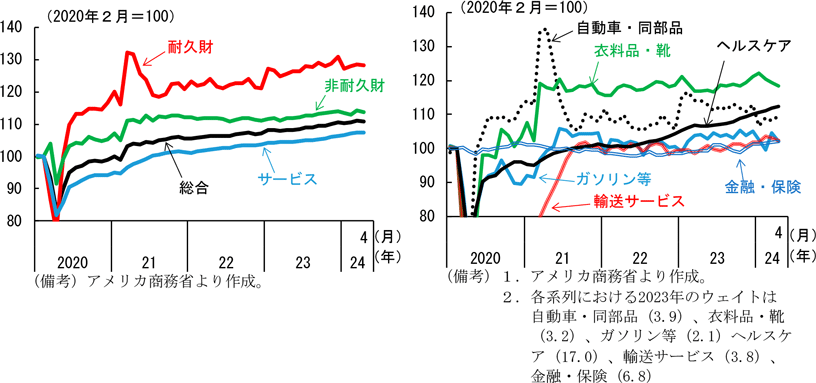
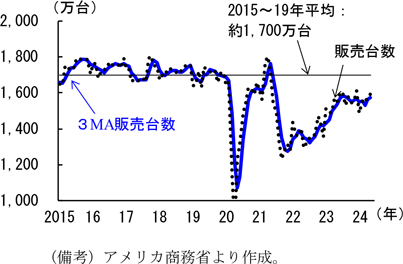
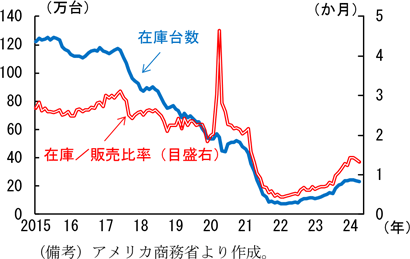
Box.大統領選挙と消費者マインドの関係
アメリカでは大統領選挙の結果が消費者マインドに影響を与える傾向がある。ミシガン大学が公表している消費者マインドは、属性別データとして支持政党別のデータが公表されており、民主党政権期には民主党支持層のマインドが総合指数を上回り、共和党支持層のマインドは総合指数を下回る傾向にある(共和党政権期は逆になる)(図1)。
近年では、20年11月の大統領選挙までの期間は共和党支持層のマインドが総合指数を大幅に上回っていたが、選挙の結果、バイデン大統領(民主党)が勝利すると、民主党支持層のマインドが逆転した。このように自身が支持する政党が与党であるか否かが、マインドに大きく影響する傾向があり、近年両者のマインドの差が広がっていることから、政治情勢が個人消費に与える影響にも留意が必要である。
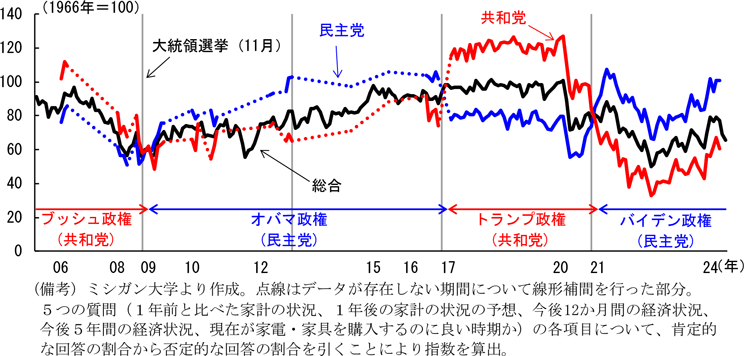
(設備投資は、半導体法等により、緩やかに増加)
続いて、設備投資の動向について確認する。設備投資は、研究開発やソフトウェア投資等からなる知的財産生産物投資を中心に緩やかに増加している(第2-1-9図)。さらに23年以降は、半導体法等の政策を受けた製造業向けの構築物投資(工場建設等)が増加に寄与してきた(第2-1-10図)。24年に入ると、工場に設置する製造装置等の機械機器投資が増加しており、特に半導体製造装置が含まれる特殊産業用機器の寄与が大きい(第2-1-11図)。このような政策による投資の促進や企業収益の改善46が、政策金利が高止まりする中においても、設備投資が減速しない要因の一つになっていると考えられる47。
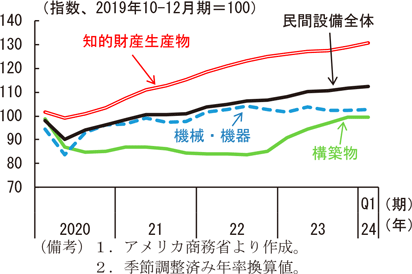
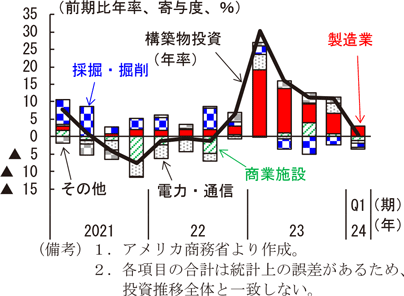
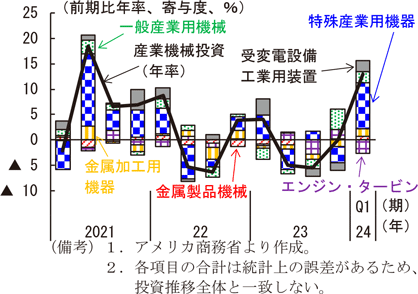
(潜在成長率は、移民流入の上振れにより、上昇)
さらに、移民流入の上振れによる潜在成長率の上昇について確認する。
アメリカ議会予算局(CBO)による最新(2024年)のアメリカ人口動態見通しでは、22年~26年にかけての人口成長率の推計値が、昨年の推計値から大幅に上方修正されているが、その大半は移民純流入の推計値の上方修正を受けたものである48(第2-1-12図)。これは、推計に用いている各種データから、アメリカへの移民流入が感染症拡大前よりも増加している可能性が高まったためである。例えば、アメリカ国土安全保障省(DHS)の税関・国境取締局(CBP)が公表している、アメリカ国境における入国希望者との遭遇データをみると、2021会計年度49以降の遭遇数が、感染症拡大前と比較して大幅に増加していることが分かる。こうした状況を踏まえ、移民純流入推計及び人口成長率が大きく上方修正されている。
この推計を前提とすれば、同期間のアメリカの潜在成長率がこれまでの想定よりも高くなる(第2-1-13図)。20年代半ばのアメリカの潜在成長率は23年見通しでは1.8%程度と推計されていたが、本見通しでは2.2%程度に上方修正されている。潜在成長率の修正幅の内訳をみると、同期間の労働生産性の寄与が小幅に下方修正される一方で、移民純流入の拡大を背景とした労働投入寄与の大幅な上方修正により、潜在成長率が押し上げられており、供給力の高まりに伴い、より高い経済成長を実現できると想定されている(第2-1-14図)。
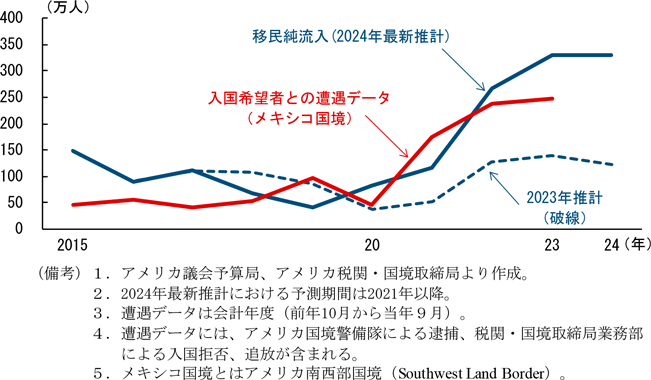
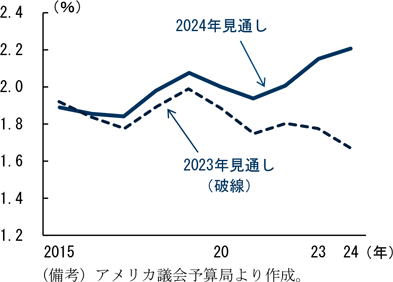
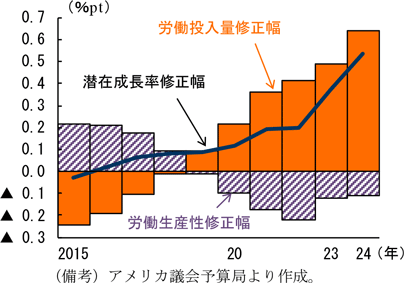
(住宅着工は2024年前半は弱い動き)
住宅着工は、2024年前半は23年後半と比べて弱い動きがみられている。物件の種類毎の推移を確認すると(第2-1-15図)、住宅着工の基調を示す一戸建て住宅の着工件数は23年以降増加傾向が継続50していたが、住宅ローン金利が高止まりする中で、24年以降は足踏みがみられている。さらに、集合住宅の着工件数は、23年以降、減少が継続している。
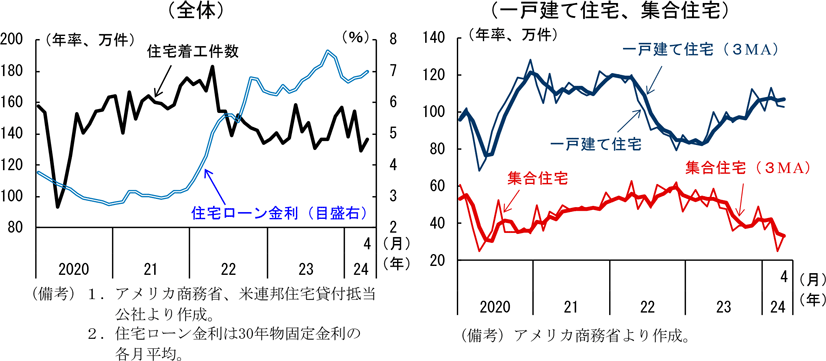
23年以降、集合住宅着工が低調な背景について、集合住宅の完工件数及び建設中件数を確認すると、いずれも感染症拡大以前と比べて水準が高いことが分かる(第2-1-16図)。感染症拡大後、22年頃にかけて着工された多くの集合住宅の建設が現在進んでいる状態であり、完工して市場に供給される物件も増えていることを受け、新規集合住宅着工の減少が継続していると考えられる。
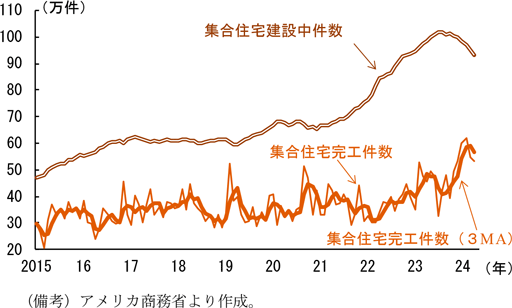
また、住宅許可件数は、24年に入ってから減少しており、住宅市場の景況感である住宅市場指数や住宅取得能力指数も再び低下に転じている(第2-1-17図、第2-1-18図)。住宅ローン金利は、23年末にかけて一旦低下した後に、24年初以降は10年債利回りの再上昇に伴い、上昇に転じている。こうした市場環境の下で、住宅価格については、23年に入り前月比で上昇ペースが加速していたものの、同年10-12月期以降は上昇ペースが緩やかになっている(第2-1-19図)。
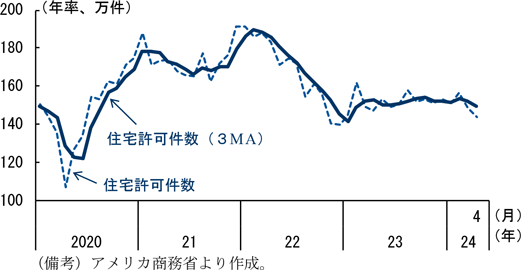
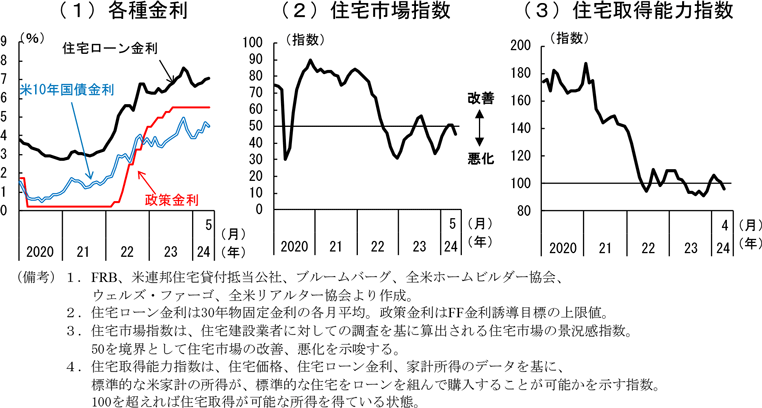
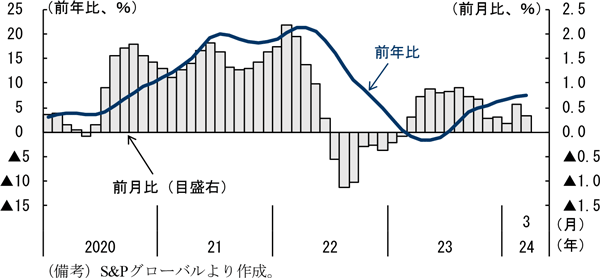
(住宅供給は長期的には不足)
一方で、住宅市場における中長期的な課題として、住宅不足に近年注目が集まっており、Khater et al. (2021)では21年時点で380万軒、Zandi (2022)では22年時点で約150万軒の住宅が不足していると指摘されている。これらの推計はいずれも空室率の実績と、住宅市場が機能するための理想的な空室率を比較して推計されたものだが、実際の空室率をみると、賃貸物件では2022年以降は小幅に反発こそしているものの、持ち家物件とともに、過去20年間で最低水準にあることが分かる(第2-1-20図)。すなわち、住宅需給はひっ迫している状況にあると言える。
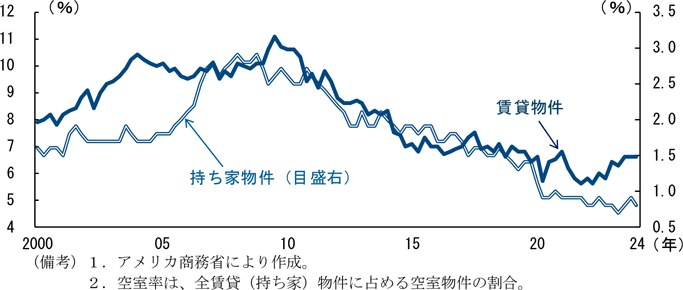
この住宅需給のひっ迫の要因を、まず、供給側についてみていく。アメリカにおいては長期的に世帯数の増加に伴って住宅ストック数が増加してきた51(第2-1-21図)。ここで、両者のフローについて詳しくみるために、世帯数の対前年増加幅と住宅着工件数の対前年増加幅の関係をみると、1959年から07年までは世帯数の増加を上回る住宅が供給されてきた年が大半であり、同期間においては十分な新規の住宅供給が行われていたことが示唆される。しかしながら、住宅バブル崩壊に端を発した世界金融危機後の08年から19年の期間では、世帯数の増加に住宅着工件数の増加が追いつかない年が半数となり、新規の住宅供給が大幅に鈍化したことが分かる(第2-1-22図)。
世界金融危機後に新規の住宅供給が大きく鈍化した背景の一つとしては、住宅バブルの崩壊に伴い住宅建設業が大幅に縮小したことが挙げられる。住宅建設業の雇用者数は06年初にかけて約102万人まで急速に増加したが、その後減少に転じ、世界金融危機を経た11年初にかけては約56万人まで大幅に減少した。その後、明確に回復に転じたのは12年後半と、非農業部門全体の10年初と比べて遅く、供給力の回復が遅れる中、10年代は、世帯数の増加に見合うだけの新規の住宅供給が行われなかった可能性がある(第2-1-23図)。
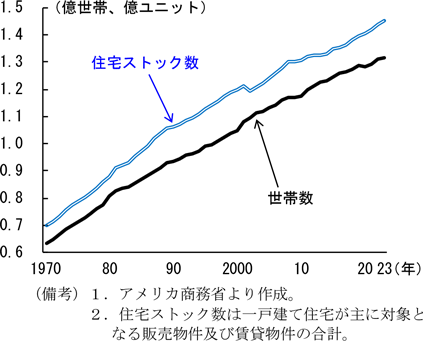
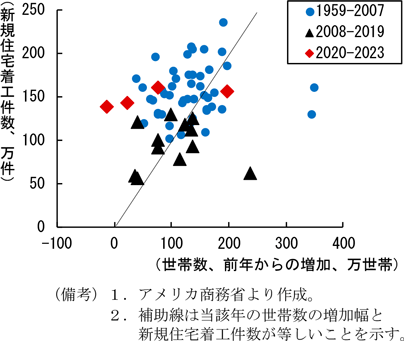
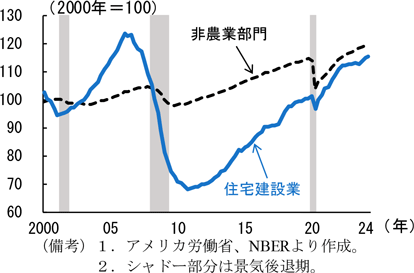
また、より長期的にアメリカの新規住宅供給を下押ししてきた要因として挙げられるのが各種ゾーニング(土地利用)規制である。ゾーニング規制とは、当該土地の利用目的や、建物の要件を定めている規制である。利用目的としては、住宅用地(一戸建て専用区画等)や工業用地といった区分が定められており、建物の要件としては、一戸建て住宅の場合、最低ロットサイズ52、床面積、駐車場に関する要件等が定められている。ゾーニング規制の内容は自治体ごとに大きく異なり、例えば、コネチカット州の一戸建て住宅用地の81%は、1エーカー(約1,224坪)以上の敷地面積が必要と定められており(Bronin (2023))、デトロイトでは駐車場の最低面積要件があることから、中心地の約30%が駐車場となっている(Sorens (2023))。
ゾーニング規制の先駆けとなったのは、1800年代後半に、当時のと畜場等を住宅用地から遠ざけるために導入された条例であった。しかしながら、その後、住民生活の更なる保護という目的の下で、様々な規制が導入された。ゾーニング規制と新規住宅供給の関係について、複数の研究が、厳しいゾーニング規制は新規住宅供給の価格弾力性を低下させ、住宅建設を減少させると報告している(Lee, Kemp, and Reina (2022))。また、全米の住宅用地の約70%は一戸建て住宅用地となっている(Frank (2021))ことから、専有土地面積に対して多くの住宅を新規に供給できる集合住宅の建設が制限され、住宅供給不足の一因となっている可能性も考えられる。加えて、前述したような厳しい土地使用規制は土地価格の上昇の要因となっていることも指摘されている(CEA (2024))。
こうした住宅供給不足を背景に、近年、バイデン政権の政策対応(詳細は後述)もあり、複数の州でゾーニング規制の改革機運が高まっている(第2-1-24表)。しかしながら、手頃な価格の住宅建設に対し、自宅の資産価値への影響を懸念してNot In My Backyard (NIMBY)53と呼ばれる態度を取る地域住民も少なくないとされており54、手頃な価格の住宅供給が順調に進むかどうかは不透明な状況である。
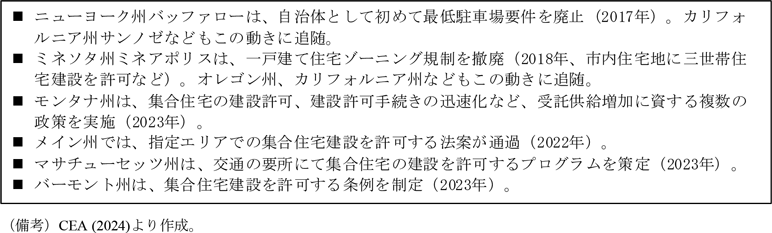
以上、供給側の要因をみてきたが、人口動態等の需要要因も住宅需給をひっ迫させている要因であると考えられる。
23年の年齢階層別人口と、各年齢階層の持ち家比率を確認すると、世代区分のうち最大の人口割合を占めるミレニアル世代(80年代~90年代後半にかけて生まれた世代:24年時点で20歳台半ば~40歳程度)が、持ち家比率が大きく上昇する年齢層(住宅の一次取得層)55に入っていることが分かる(第2-1-25図)。ミレニアル世代の世帯のライフステージの変化が、10年代頃からの持ち家住宅需要を下支えしてきた可能性がある。
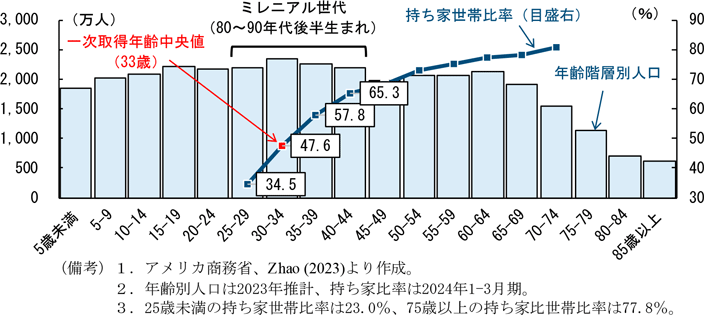
このような需給のひっ迫を受け、住宅価格は10年代以降、上昇ペースは消費者物価指数総合や所得(世帯年収中央値)を上回っている(第2-1-26)。
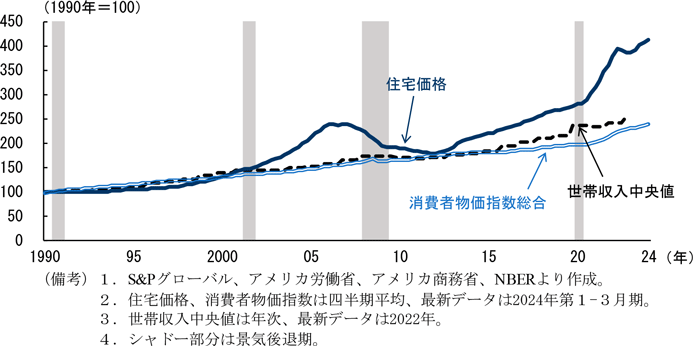
実際に販売された(取引が成立した)住宅の価格帯別の割合をみると、新築住宅、中古住宅ともに15年以降、25~30万ドル未満の低価格帯の物件の割合が低下傾向にある一方、50万ドル以上の高価格帯物件の割合は上昇傾向にあり、感染症拡大を経て特に新築物件で高価格帯物件の割合は大幅に上昇した(第2-1-27図)。
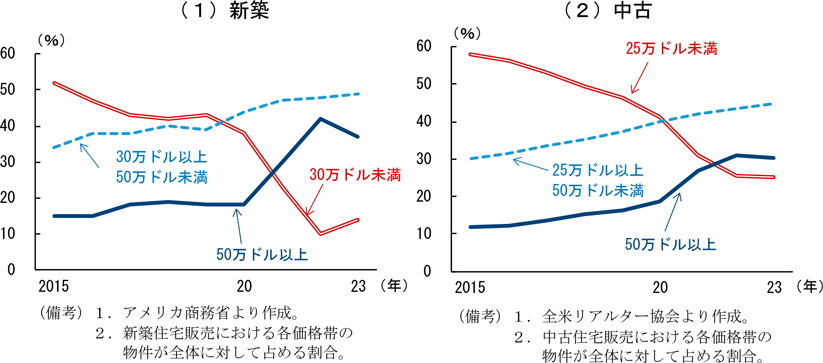
このような住宅価格の上昇により、Lee, Kemp, and Reina (2022)は、アメリカ含め先進各国で、世帯の住宅取得可能性の低下が課題となっていることを指摘している56。持ち家の取得が困難な状況では、賃貸住宅に住み続ける世帯が多くなると考えられるが、アメリカでは、賃貸住宅に住む世帯のうち、家賃の支払いが収入の30%以上57となっている世帯の割合が、60年の約20%から22年時点で約45%まで上昇していると指摘されており(CEA(2024))、賃貸住宅においても、住居費の負担は高まってきている。加えて近年、住宅向け損害保険料の高騰58により、住居費に加えて住宅関連支出の負担が増加しており、住宅価格及び家賃の上昇幅以上に、家計の負担感は強まっている可能性もある。
生活の基盤となる住居の取得可能性が低下していることを問題視したバイデン政権は、中低所得の初回住宅購入世帯を対象とした税額控除や、ゾーニング改革へのインセンティブとしての自治体に対しての補助金政策59等を実施している。こうした政策は需要、供給の両面を刺激することによって、今後の民間住宅投資を下支えすることが期待される。
(財輸入では、中国は輸入相手国の首位から2位に低下)
財貿易は、米中貿易摩擦の影響がみられる。2018年から2020年にかけて、米中両国間で追加関税の応酬が続き、その後も相互に輸出規制が行われるなど米中貿易摩擦が高まっている(第2-1-28表)。
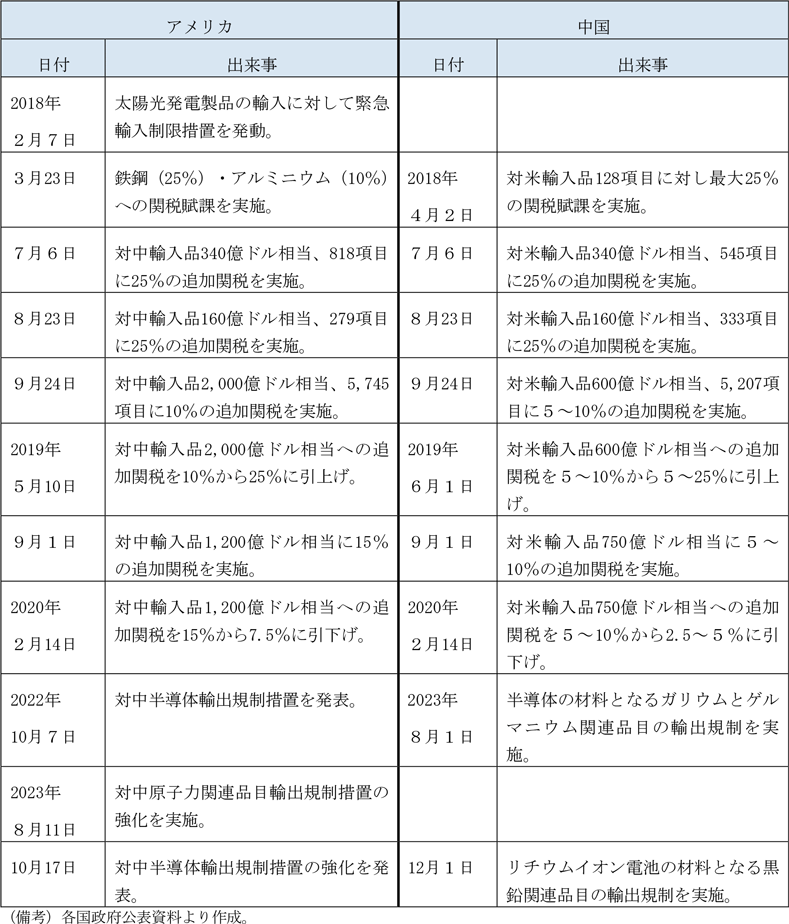
こうした中で、財輸入は、減少傾向にあった資本財や消費財を中心に23年後半から増加に転じ、全体として横ばいから増加傾向となった(第2-1-29図)。また、輸入相手国のシェアの推移をみると、23年は09年以来14年連続で首位であった中国が2位となり、メキシコが首位に浮上した(第2-1-30図)。中国は90年代以降急速にシェアを拡大し、17年には21.6%に達したが、トランプ政権が中国に対して追加関税措置を開始した18年以降はシェアを縮小し、23年には13.9%まで落ち込んでいる。バイデン政権ではトランプ政権時代の追加関税措置を継続しつつ、フレンドショアリングやニアショアリングを進めており、近年はメキシコやカナダのシェアが拡大している。
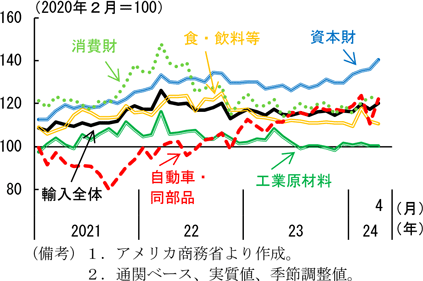
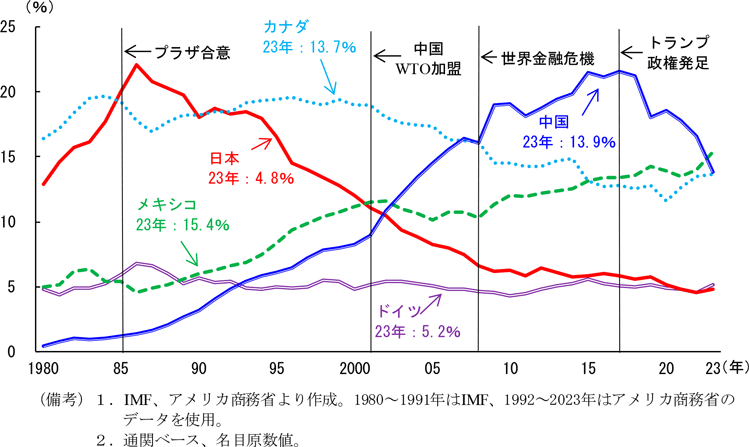
24年5月14日、バイデン政権は、1974年通商法第301条(いわゆるスーパー301条)に基づき、EVや半導体等中国からの輸入品180億ドル相当60に対する関税の引上げを発表した。具体的には、中国の不公正な貿易慣行からアメリカの労働者と企業を守るため、主にバイデン政権下で戦略的分野として投資を行ってきた品目61を対象に、現行0~25%の関税率を25~100%まで引き上げることとした。翌週22日にはアメリカ通商代表部(USTR)が関税引上げ対象品目や適用除外品目のリスト62、引上げ時期等を示した官報案を発表し、6月28日までパブリックコメントを受け付けた。関税引上げ時期は品目別に24年8月1日、25年1月1日、26年1月1日と分かれている。
官報案で示された関税引上げ品目について、引上げ時期ごとに対世界輸入額をみると、24年引上げ対象品目(電気自動車(EV)、EV用のリチウムイオン電池、その他電池部品、太陽電池、鉄鋼・アルミニウム製品、重要鉱物(天然黒鉛、永久磁石を除く)、船舶対岸クレーン、注射器、フェイスマスク)が近年増加していることが分かる(第2-1-31図)。次に対中国輸入額とシェアを確認すると、主に26年の引上げ対象品目(EV用以外のリチウムイオン電池、天然黒鉛、永久磁石、医療用手袋)において近年伸びが著しく、シェアも大きくなっている。なお、25年に引き上げる品目(半導体)は、輸入額、シェアともにおおむね横ばいで推移している。このため、追加関税の影響は、中国のシェアが小さい品目が対象となっている24年や25年の関税引上げでは直ちには現れず、26年頃から現れる可能性がある(第2-1-32図)。また、26年7月には、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の見直しも控えていることから63、貿易をめぐる動向の変化に注意が必要である。
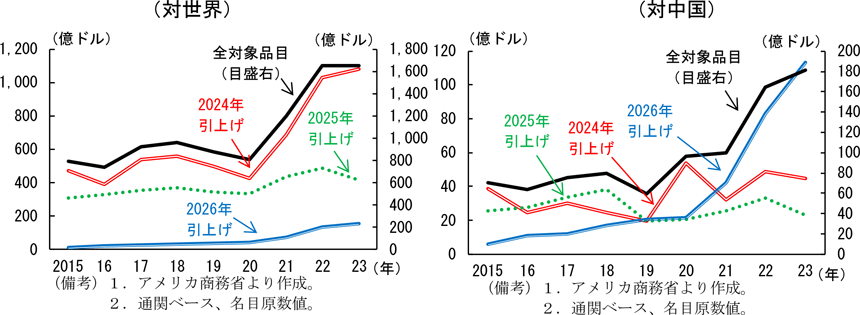
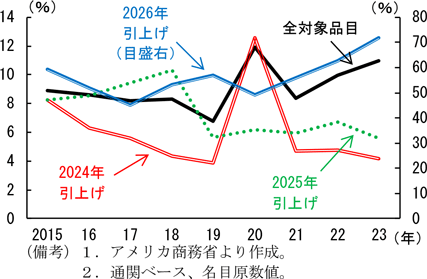
2.労働市場及び物価の動向、金融政策及び金融資本市場の動向
(労働需給は緩和傾向にあるものの、依然としてひっ迫)
雇用動向をみると、雇用者数前月差は、2022年の増加ペースからは鈍化しているものの、力強い国内需要を背景として、基調としては感染症拡大前の景気拡大局面の平均的な前月差である20万人を上回って推移している(第2-1-33図)。業種別では、特にヘルスケアが24年以降も7~10万人程度増加しており、雇用者数全体の増加への寄与が大きい状況が続いている。
失業率は、23年後半以降は1970年代のオイルショック以降の最低水準である3%台後半で推移していたが、24年5月には22年1月以来の4.0%台となり、6月の連邦公開市場委員会(FOMC)の四半期経済見通し(Summary of Economic Projection)における失業率の長期見通し64である4.2%に近付いている65。求人倍率(失業者1人当たりの求人数)は、24年5月時点で1.24となり、感染症拡大前の20年2月の1.22とおおむね同水準まで低下しているが、15~19年平均である0.93は依然として上回っている(第2-1-34図)。
このように、労働需給の緩和は続いているものの、依然としてひっ迫していると考えられる。
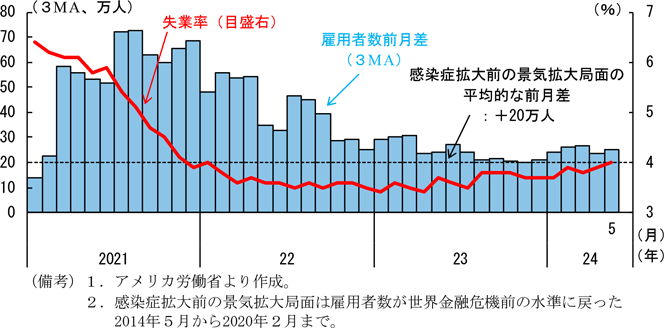
このような労働需給のひっ迫を受け、名目賃金上昇率は23年後半以降、感染症拡大前の平均値を上回る水準で、おおむね横ばい傾向で推移している。
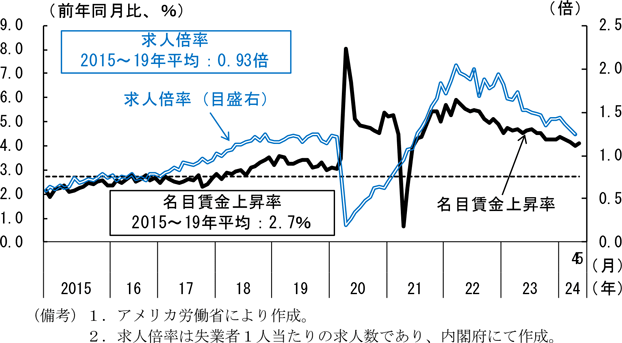
(物価上昇率は下げ止まり)
物価上昇率は、財の寄与が縮小したことで、ピーク時と比べれば鈍化したものの、家賃等の住居費を中心にサービスの寄与が底堅く推移していることで、前年比で下げ止まっている(第2-1-35図、第2-1-36図、第2-1-37図)。
まず、消費者物価指数(CPI)(総合)をみると、前年同月比は22年6月にピーク(9.1%)に到達した後、23年6月には3.0%まで低下したものの、その後は横ばいで推移しており、24年5月時点で3.3%にとどまっている。
また、FOMCが重視しているコア物価上昇率(コアPCE)をみると、前年同月比は22年2月にピーク(5.6%)に到達した後、23年末には2.9%まで低下したが、その後は横ばいで推移しており、4月時点では2.8%にとどまっている。これを受け、FOMC5月会合の声明文における物価判断では、「インフレ率は緩和しているものの、依然として高水準」と、これまでの判断を維持した上で、「ここ数か月は2%の目標に向けた進展に乏しい」という表現が新たに追加された。さらに、FOMC6月会合で示された四半期経済見通し(Summary of Economic Projection)では、24年末のコアPCEの見通しが2.8%に引き上げられ、本見通しに基づけば24年中は物価上昇率が下がらないことが懸念される。
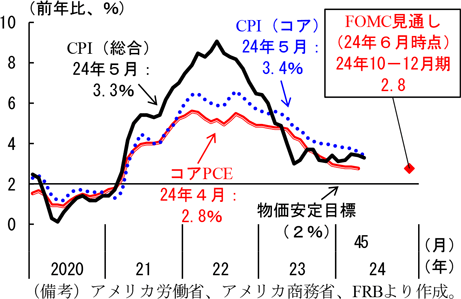
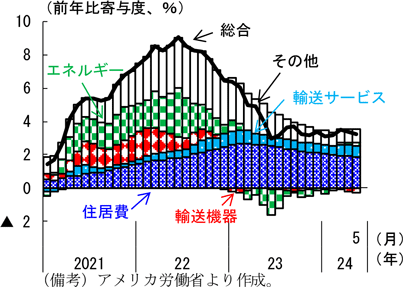
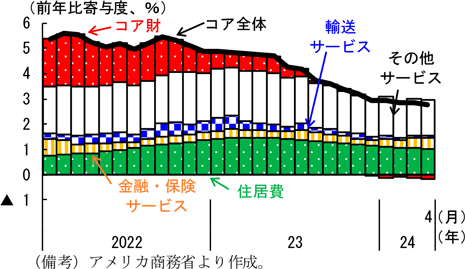
物価上昇率が前年比で下げ止まっている背景として、財価格については、22年後半以降、物価上昇率の下押し要因であった輸入価格低下や供給制約の緩和による下押し圧力が一服したことが挙げられる(第2-1-38図)。その要因として、金融引締めの進展に伴いドル高になったことにより輸入価格が下押しされていたが、23年7月以降は政策金利が据え置かれたことを受けてドルの価値はおおむね横ばい傾向となり、為替を通じた輸入価格の下押し圧力が一服していることが挙げられる(第2-1-39図)。加えて、パナマ運河の干ばつに伴う海運コストの上昇66、食料生産国における一部作物(カカオ豆・オレンジ)の不作67が考えられる(第2-1-40図、第2-1-41図)。こうした中で、輸入財価格は、24年5月の食料品の上昇率が前年同月比5.6%、工業原材料は同2.0%と上昇率が加速している。
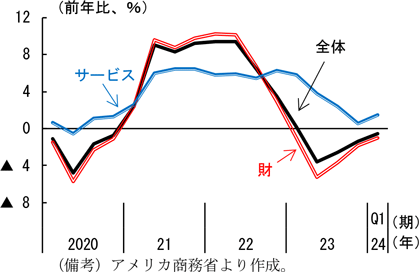
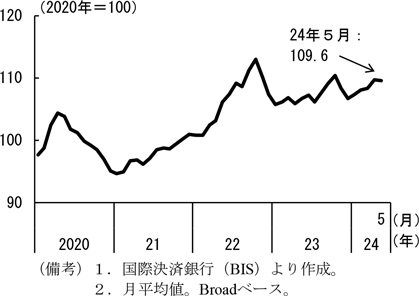
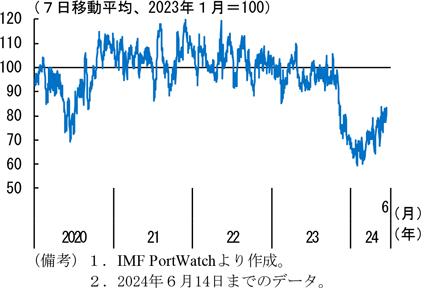
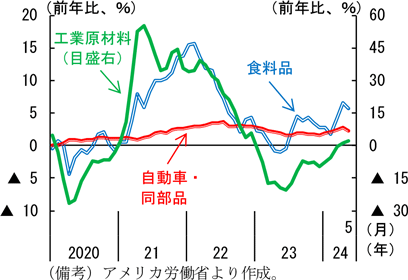
また、サービス価格については、住宅価格の上昇を背景として、住居費(家賃等)が前月比0.4%程度の高い上昇率を維持したまま横ばい傾向で推移しており、全体の中での寄与の大半を占めている。さらに、サービスの輸入価格デフレーターが前年比1.5%のプラスで推移していることや、名目賃金上昇率が感染症拡大前の平均を上回る伸び率で推移していることを受け、その他のサービス価格上昇率の低下が進まないことも、物価上昇率が前年比で下げ止まっている背景として考えられる(第2-1-42図、第2-1-43図)68。
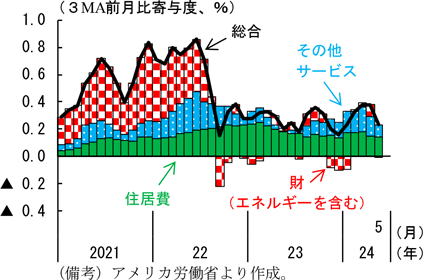
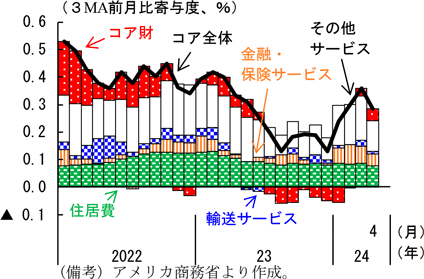
予想物価上昇率についても、市場参加者の長期(10年先)の予想物価上昇率は2%程度でアンカーされているものの、消費者の中期(5年先)の予想物価上昇率は15~19年の平均と比べてやや高い状況が継続しており、消費者の短期(1年先)の予想物価上昇率は22年4月以降低下方向にあったが、24年1月の2.9%を底にして以降、下げ止まっている。このことからは、消費者が中期及び短期的には15~19年の平均よりも高いインフレの持続を予想していることが示唆される(第2-1-44図)。
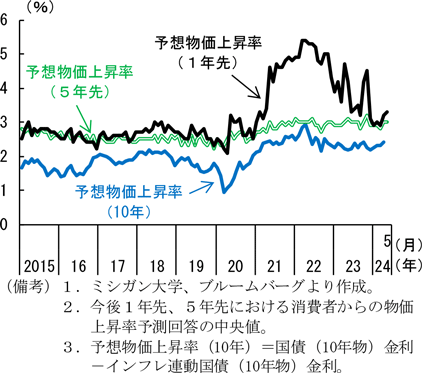
コラム2:国際商品市況
本コラムでは、各国の物価動向、ひいては景気動向に大きな影響を与える主要な商品である原油、天然ガス、小麦の価格動向について概観する。2024年初以降の約半年間のそれぞれの商品価格の動きをみると、原油はやや上昇し、天然ガスはおおむね横ばいで推移し、小麦はやや低下している(図1)。以下、商品ごとに推移を確認する。
(i)原油
原油価格(WTI)は、2024年初は70ドル/バレル程度であったが、ウクライナ情勢や中東情勢の緊迫化及びOPECプラスの減産継続等を受けて、4月下旬には83ドル/バレル付近まで上昇した69。5月に入ると、米原油在庫の増加による原油の需要減の懸念から原油価格は70ドル/バレル付近まで反落したものの、米利下げ期待の高まりにより反発し、6月下旬では80ドル/バレル程度で推移している。
(ii)天然ガス
欧州における天然ガスの先物価格(TTF)は、欧州の暖冬の影響や世界的な景気の弱さによる需要減の影響を受け、2024年初の35ユーロ/メガワット時程度から、2024年2月に入ると、25ユーロ/メガワット時程度まで下落した。その後は、寒波による在庫使用やノルウェー大陸棚でのガス施設メンテナンスを受けてやや上昇し、4月中旬には中東情勢の緊迫化等もあり30ユーロ/メガワット時程度まで上昇した。5月に入ると、アジア地域の需要増等も受けて上昇基調は続き、6月下旬では35ユーロ/メガワット時程度で推移している。
(iii)小麦
小麦価格(シカゴ商品取引所)は、2024年初は6ドル/ブッシェル程度であったが、豊作となったロシアが安値で輸出を拡大したことに加え、ウクライナも堅調な輸出を継続し、供給が増加したことから、2024年2月から3月にかけて値下がりし、3月中旬には5.5ドル/ブッシェルまで下落した。その後、4月下旬には中東情勢の緊迫化等を受けて6ドル/ブッシェルまで値を戻した。5月下旬には生産国での天候異常等による供給減があり、7ドル/ブッシェル程度まで値上がりしたが、その後の供給回復を受けて値下がりし、6月下旬では5.5ドル/ブッシェル程度で推移している。
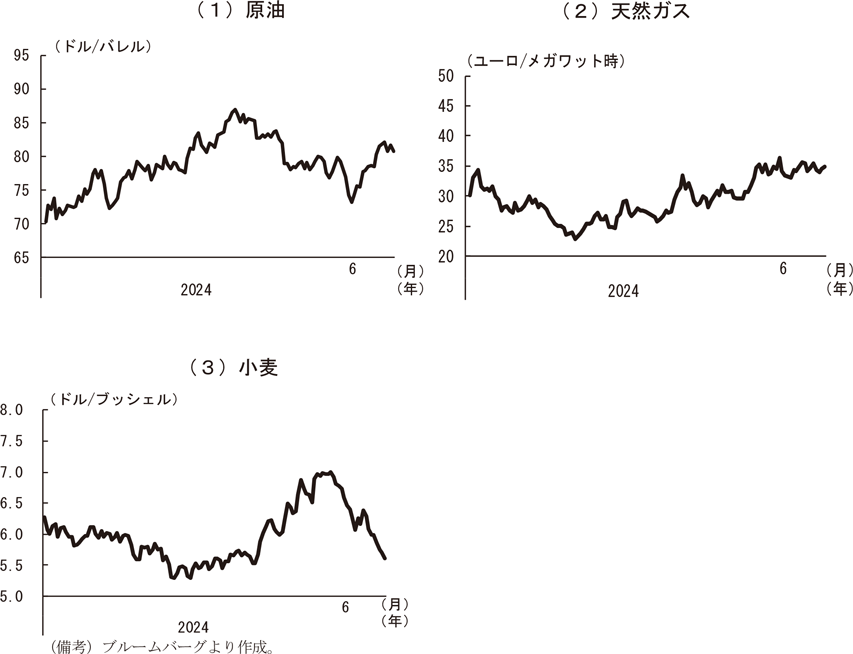
(政策金利は、物価上昇率の下げ止まりを受け、高止まり)
このような物価上昇率の下げ止まりを受け、政策金利は高止まりしている。
アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)は、2022年3月のFOMCにおいて、FF金利の誘導目標範囲を0.25%ポイント引き上げて以降、2023年7月までに累計で5.25%ポイント引き上げた(第2-1-47表)。その後、同年9月以降は、24年6月のFOMCまで7会合連続で誘導目標範囲が据え置かれており、政策金利の水準としては01年以来の高水準が維持されている(第2-1-45図)。今後の金融政策決定に関して6月のFOMCでは、「インフレ率が2%に向かって持続的に低下しているという、より確かな確信を得られるまでは、利下げは適切ではないだろう」とし、23年7月に最後の利上げを行って以降、早期の利下げ転換に対して慎重なスタンスを貫いている。
なお、金融市場が見込む24年の利下げ回数(第2-1-46図)は、年初時点では約6回であった70が、24年に入り、物価上昇率の下げ止まり等を受けて、6月中旬時点では約2回程度まで減少している。6月のFOMC会合で示された四半期経済見通しにおけるFOMC参加者のFF金利見通し(ドット・チャート)でも、24年末までの利下げ幅は0.25%ポイント(1回の利下げ幅を0.25%ポイントとすれば、1回分の利下げに相当)となっており、物価上昇持続への警戒感が増していると考えられる。
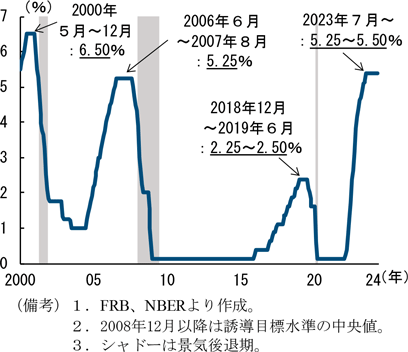
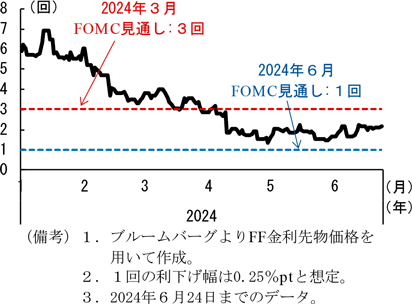
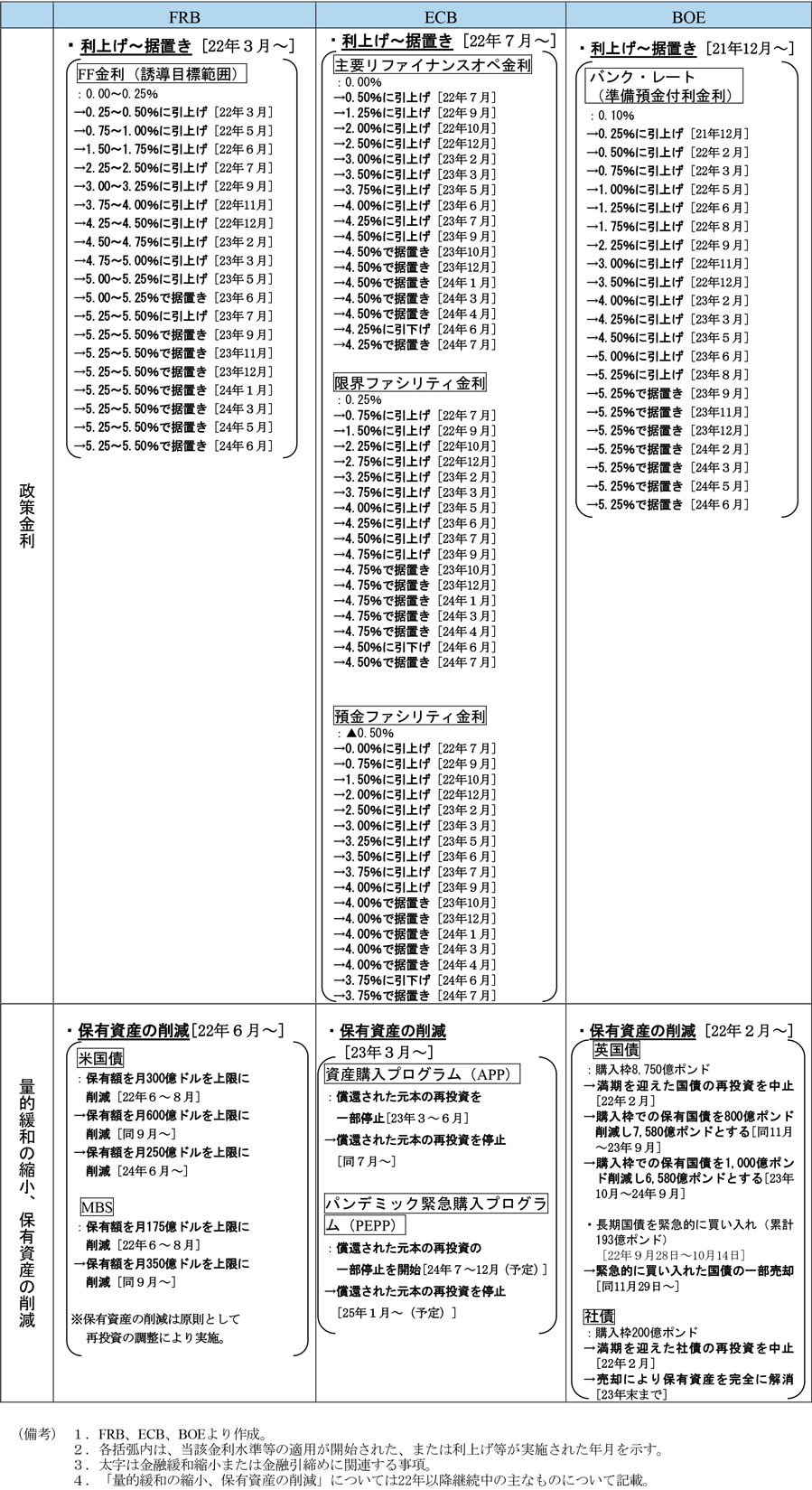
(量的引締めは資産削減ペースが減速)
このように政策金利が高止まりする一方で、量的引締めについては変化がみられており、24年5月1日のFOMCでは、FRBの保有資産削減のペースを同年6月から減速することを決定した71。具体的には、米国債の月当たり削減上限額がこれまでの600億ドルから250億ドルまで引き下げられた。これにより、24年6月以降は米国債と不動産担保証券(MBS)を合わせて、月当たりでおよそ400億ドルのペースでの保有資産削減となると考えられる72。以下では、本引締め局面における量的引締め政策を振り返ると共に、先行きについて考える。
FRBのバランスシートの規模を確認すると(第2-1-48図)、保有資産の削減が始まった22年6月の約9兆ドルから24年5月には7兆ドル強まで減少している。
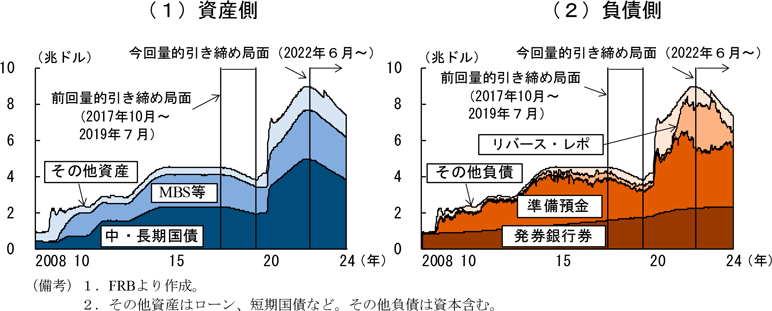
ここで、バランスシートの内訳を確認する。FRBのバランスシートの資産側は大きく分けて、中・長期国債、MBS・政府機関債、短期債やローン等のその他資産が計上されており、負債側には、発券銀行券、準備預金、リバース・レポ及びその他負債が計上されている。資産・負債の内訳を、保有資産の削減が始まった22年6月時点と、24年5月時点で比較すると(第2-1-49図)、資産側では、中・長期国債、MBS等合わせておよそ1.6兆ドル減少している。そして、この資産側の減少に対応して負債側で減少しているのが、リバース・レポである。
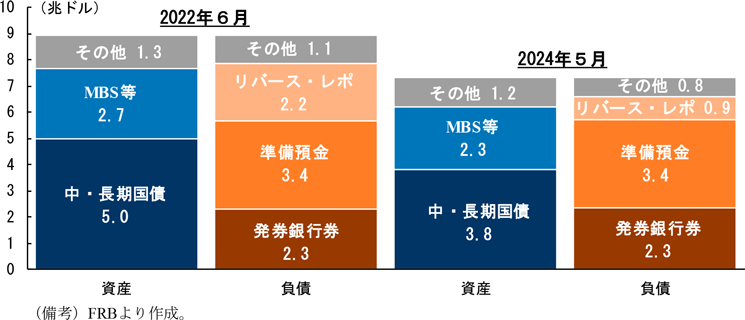
リバース・レポとは、リバース・レポ(ONRRP : Overnight Reverse Repurchase)73・ファシリティに基づいて取引されるレポ取引の残高であり、マネー・マーケット・ファンド(MMF)を中心とした資金運用主体によるFRBに対しての貸付残高である。15年以降のリバース・レポ残高の推移をみると(第2-1-50図)、21年3月頃の2000億ドル程度から大幅に拡大し、22年の6月頃にかけて2.5兆ドル程度まで積みあがった。このリバース・レポの急拡大の背景については、政策金利の急上昇や短期国債発行が減少したこと等が指摘されている74。その後、23年6月以降、リバース・レポ残高は急速に減少し、24年6月にかけて9,000億ドル程度まで縮小した75。他方で、準備預金残高の水準は今回量的引締め開始以降おおむね変化していない(第2-1-51図)。

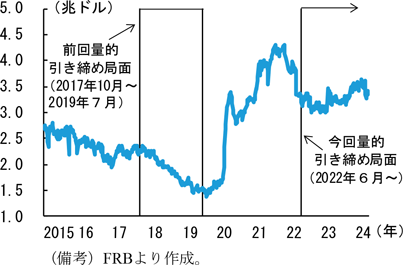
量的引締めについて、FRBは、預金金融機関が中央銀行に預ける準備預金の水準を、現在の「豊富な(abundant)」水準から、「十分な(ample)」水準をいくらか上回る(somewhat above)水準まで減少するまで、バランスシートを縮小するとの方針を示している。ここで、FRBが目指す準備預金の「十分な」水準について、準備預金水準と金利の関係の概念図で確認する(第2-1-52図)。準備預金の水準が一定水準を下回ると、需要曲線の傾きは急になり、金利は急騰する一方、08年に導入された準備預金への付利(IORB:Interest on Reserve Balances)、13年に導入されたリバース・レポ・ファシリティにより、「十分な」水準をいくらか上回る水準以上では、需要曲線の傾きはゼロとなり、金利は準備預金への付利とリバース・レポ金利の間で安定的に推移する。すなわち、FRBが目指している「十分な」水準をいくらか上回る水準は、第2-1-52図のシャドー部分となる。
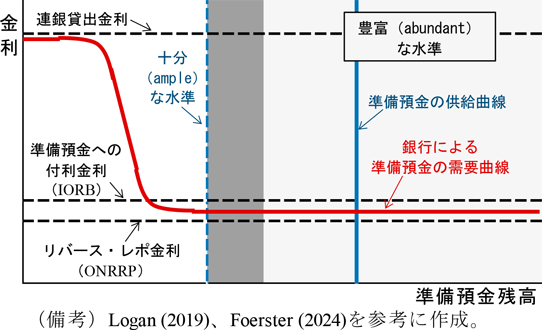
FRBが前回の保有資産の削減を行っていた19年9月には、実効フェデラル・ファンド金利(EFFR)が一時的にFOMCの目標レンジの上限を超え、担保付翌日物調達金利(SOFR)76は5%超まで急上昇するなど、短期金融市場に緊張が走った(第2-1-53図)。この背景については、法人税納税期限や入札国債の受渡日が重なったことによる銀行システム内の資金の減少といった一時的要因に加え、17年10月以降FRBが進めてきた保有資産の削減に伴う準備預金残高の減少も背景となったと指摘されている77。この事態を受け、FRBは保有資産の縮小を予定よりも前倒しで終了した。
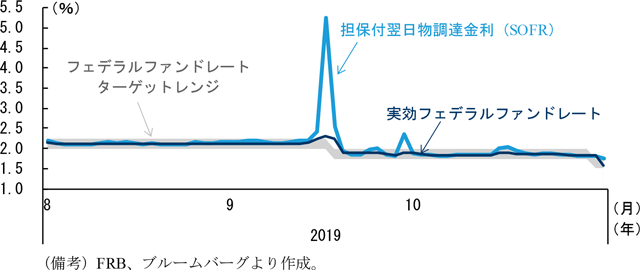
なお、ニューヨーク連銀が公表する“Open Market Operations during 2023”では、保有資産削減の先行きの方針を準備預金の対名目GDP比をもとに試算しており、準備預金の「十分な」水準が不透明であるため、「十分な」水準が相対的に高位である場合と、相対的に「低位」である場合の2つのシナリオを提示している。いずれのシナリオでも、準備預金は削減、メンテナンス、拡大という3つのフェーズ78を辿り、高位(低位)シナリオでは、準備預金の名目GDP比が12%(10%)に達したところで削減フェーズのペース減速が行われ、11%(9%)でメンテナンス・フェーズへ移行し、10%(8%)で拡大フェーズに移行する(第2-1-54図、第2-1-55図)。高位シナリオ、低位シナリオともに、保有資産の削減が停止されるのは25年頃と見込まれているため、しばらくは保有資産の削減が続く可能性がある。
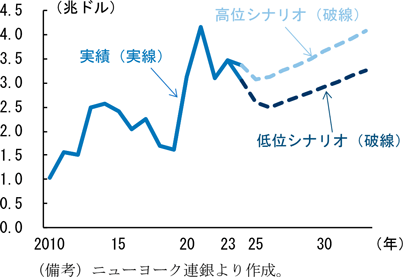
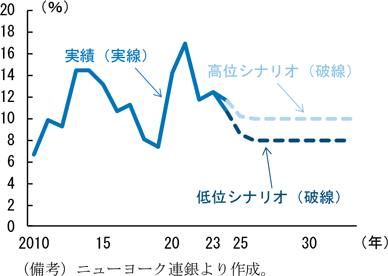
以上みてきたように、FRBによる今回の保有資産削減においては、前回の例などを参考にしつつ、短期金融市場の動向を注視しながら、削減ペースを管理していくことになると考えられる。
(長期金利は高止まり)
こうした政策金利の高止まりや、保有資産の削減を受け、アメリカの長期金利はおおむね4%台で高止まりしており、欧州の長期金利もアメリカに連れて、高水準で推移している(第2-1-56図(1))。
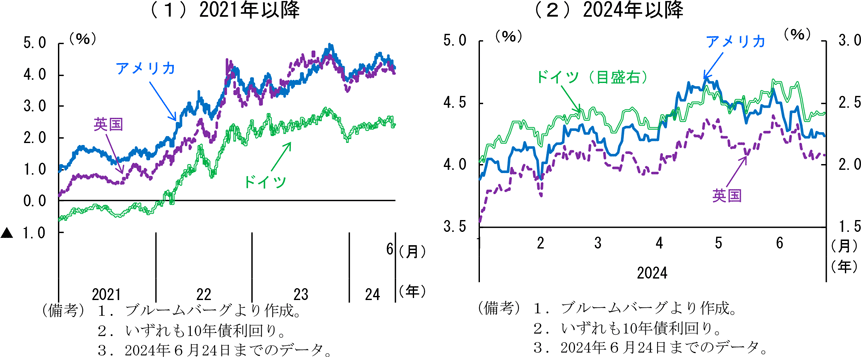
24年以降をみると(第2-1-56図(2))、年初以降、市場予想を上回る経済指標の公表が続いたことにより、早期の利下げ期待が後退する中、5月頃にかけてアメリカの長期金利は4%台後半まで、英国では4%台前半まで、ドイツでは2%後半まで上昇した。その後、6月にかけた物価指標の下振れ等を受けて、アメリカの長期金利が低下方向となる中、欧州の長期金利も上昇が一服している。
3.現状の総括と先行き
(景気拡大が継続するも、政策金利の高止まりの長期化が懸念)
アメリカ経済は、移民流入の上振れにより潜在成長率が高まった状況下で、個人消費は、物価上昇を上回る名目賃金上昇の継続や超過貯蓄の取崩しにより、増加傾向が続いている。設備投資は、半導体法等の効果が継続し、緩やかな増加傾向が続いている。一方で、住宅着工は、住宅ローン金利の高止まりを受けて、弱い動きがみられることには留意が必要であるが、総じてみれば、力強い国内需要を背景に、景気拡大が継続している。
こうした中で、労働需給が依然としてひっ迫していること等を受けて物価上昇率は下げ止まっており、FOMC6月会合で示された四半期経済見通しに基づけば24年中は物価上昇率が2%を上回る状況が続く可能性が示されている。結果として、政策金利の高止まりが続く可能性が懸念される。
一方で、金融引締めの影響を受けやすい住宅市場では、住宅購入の手控えが継続し、住宅着工の弱い動きが継続する可能性がある。また、設備投資も、資本コストの上昇を通じて、今後減少する可能性もある。これらは国内需要を減少させ、物価上昇率を低下させる可能性があることから、政策金利の引下げが早まる可能性もある。今後とも予断を排して景気動向を注視する必要がある。
コラム3:アメリカにおける予算審議の動向
アメリカでは、24年3月23日に24年度(23年10月1日~24年9月30日)の本予算が成立した。24会計年度に入ってから本予算が成立するまでに約半年を要したこととなる。本コラムでは、アメリカの予算編成について整理したうえで、24年度本予算成立をめぐるアメリカ議会の動向を振り返る。
アメリカの会計年度は、当暦年の前年10月1日から当暦年9月30日までとなっており、新年度予算を10月までに成立させる必要がある(例えば24年度予算の場合、23年10月まで)。新年度までに予算が成立しなかった場合、連邦政府は予算を執行できなくなることにより、政府の活動が停止する、いわゆる政府閉鎖に陥る。政府閉鎖を防ぐためには、(1)新年度までに予算を成立させる、または(2)つなぎ予算を成立させ、予算成立期限を延長する、のいずれかを行う必要がある。しかしながら、アメリカ議会における予算編成プロセスが与野党対立の延長線上にあることから、予算編成は毎年度のように、新年度までには間に合わず、基本的には(2)のつなぎ予算の成立によって期限を延長することが多い。なお、延長した期限までに本予算を成立できない場合もしばしばあり、直近では、トランプ政権下の18年12月22日から19年1月25日にかけて政府閉鎖79となっていた。
前述のとおり、予算が新年度までに成立しないことが多いアメリカの予算編成プロセスであるが、24年度本予算編成にあたっては、そもそもの予算全体の歳出規模に加えて、ウクライナ支援80、アメリカ南西部の国境警備強化81等、与野党間で意見の対立する論点が多かった。さらに、22年の中間選挙にて、アメリカ議会が上下院で多数派政党の異なるねじれ議会となっていたことや、下院において共和党が僅差で多数派となっていたことで、共和党保守強硬派議員らの発言力が大きくなっていたこともあり、新年度開始直前の23年9月下旬になっても前述した論点での意見対立の溝は埋まらず、一部では政府閉鎖の可能性も指摘されていた。しかし、23年9月30日に当時の下院議長である共和党のマッカーシー氏が、下院で超党派の支持を得ることで、予算執行を11月中旬まで継続できるつなぎ予算を成立させ、政府閉鎖を回避した。
ただし、その後、マッカーシー氏は、つなぎ予算の成立にあたって共和党の要求を盛り込まず、民主党との協力でつなぎ予算案を下院で通過させたことが問題視され、アメリカ史上で初めて下院議長が解任される事態となった。後任下院議長の選出においては、候補者が十分な支持を得られず撤退する状況が続き、下院は約3週間の機能停止状態を経た後、10月15日に新議長として共和党のマイク・ジョンソン氏を選出した。
ジョンソン新下院議長の下でも予算審議は難航したが、2度目のつなぎ予算、3度目のつなぎ予算の成立を経て、3月23日に本予算の予算協議が決着した。成立した本予算は、総額1.66兆ドル規模であり、共和党が求める歳出大幅削減は見送られ、国境警備のための予算は含まれていない。また、民主党の求めるウクライナ支援法案は、本予算のパッケージから分離されており、当初争点となっていた部分の大半は、解決が先送りされている。なお、ウクライナ支援については、24年4月に、ウクライナへの約610億ドルの支援を含む追加予算が成立しているが、国境警備については、24年5月に、国境管理の強化法案を上院が否決82するなど、意見の対立が続いている。こうした政治的な対立は、移民政策や政府歳出及び政府債務残高の方向性に大きな影響を及ぼし、ひいてはアメリカの経済成長の先行きにも影響しうることから、動向の注視が必要である。
コラム4:アメリカにおける商業用不動産市場の最近の動向
2023年3月のアメリカ地方中小銀行の経営破綻以降、商業用不動産83の動向が一段と注目されるようになった84。商業用不動産のうちオフィスローンを含む非農業・非住宅向け貸出残高をみると、大手行はおおむね横ばいで推移している一方、中小銀行は積み増しが進んでいる(図1)。融資総額に占める割合をみても、2024年5月末時点で3割程度と大きい85(図2)。このように、中小銀行が商業用不動産市場の動向に対して相対的に脆弱な環境の下で、2024年1月末にはニューヨーク・コミュニティー・バンコープ(NYCB)の決算発表86を受けて中小銀行をめぐる懸念が高まり、6月初旬には大手格付け会社による中小銀行6行の格下げに関する報道が伝わるなど、アメリカの中小銀行の経営をめぐる懸念は依然として払拭されていない。こうした問題意識に基づき、本コラムでは、商業用不動産市場の最近の動向を整理する。
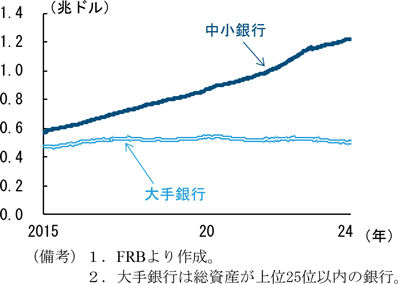
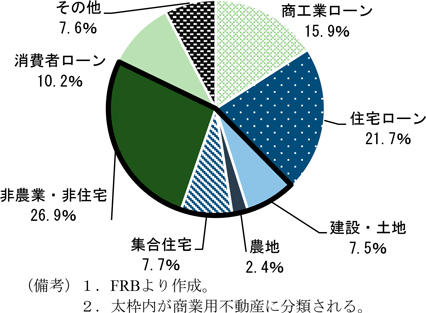
まず、商業用不動産全体の価格指数をみると、2023年末以降は下落が一服していることがわかる(図3)。しかしながら、MSCI (2024)によれば、工業用物件価格は、半導体法等を受けて堅調に推移する一方87、都市部88のオフィスについては、感染症拡大後のリモートワークの普及による構造的なオフィス需要の減退89等を受け、2024年6月時点では感染症拡大前の2019年6月比で▲44.9%下落している。
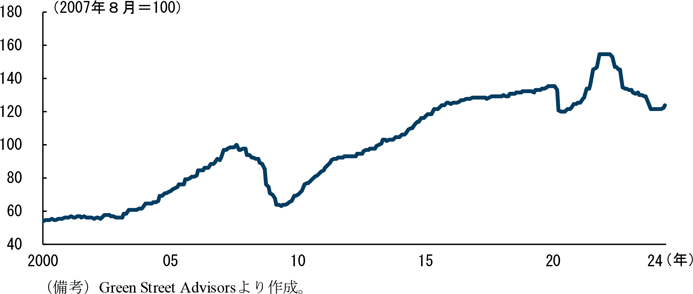
また、オフィスを担保とするローン及びCMBS(Commercial Mortgage Backed Securities:商業用不動産担保証券)の延滞率をみると、2023年以降、商業用不動産全体の延滞率を上回って上昇している(図4、図5)。一方で、全米抵当貸付銀行協会90によれば、2023年に償還を迎える予定だった商業用不動産貸付資金の一部の満期が延長されたことで、2024年には4,410億ドルの銀行融資、2,340億ドルのCMBSの償還を迎えるとされており、更なる延滞率の上昇が懸念される。
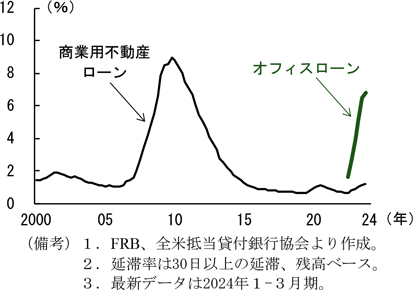
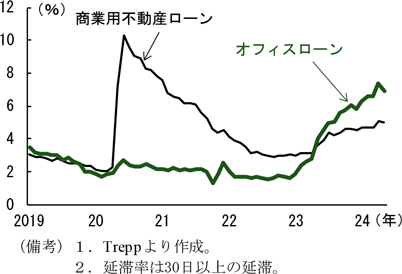
こうした背景の下、地方銀行株指数は2023年3月に急落して以降、総じて横ばい圏内となっており、商業用不動産等に対する市場の懸念は引き続き根強く残っている状況にあると考えられる(図6)。