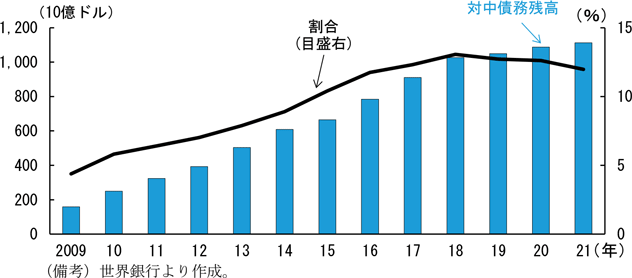第1章 2023年前半の世界経済の動向(第2節)
第2節 経済の先行きをみる上で重要なトピック
前節においては欧米の景気・物価動向及び金融政策、及び中国の景気動向の分析等を踏まえて世界全体の景気動向を概観した。本節では、その内容を補完するとともに、経済の先行きをみる上で重要な、アメリカ、中国、ヨーロッパの各地域及び国際金融におけるトピックについて分析する。
1.アメリカ:米中貿易摩擦、自動車販売、住宅市場及びMBS債、労働市場
アメリカ経済は緩やかな回復がみられているものの、貿易面では米中貿易摩擦が継続するとともに、急速な金融引締めが消費や住宅投資に与える影響が懸念されている。また、労働市場の動向は金融政策上の主要な論点である。このような構造問題及び需給両面の動きは経済の先行きをみる上でも重要なテーマであることから本項では、米中貿易摩擦、消費のうち自動車販売、住宅市場及びMBS債、労働市場の動向を分析する。
(1)米中貿易摩擦の動向
(政権交代の2021年以降も、米中貿易摩擦は継続)
2018年4月における、アメリカによる1974年通商法第301条(いわゆるスーパー301条)に基づく中国からの輸入品に対する追加関税の発表を契機に、米中両国の間で貿易摩擦が生じた74(第1-2-1表)。その結果、中国は追加関税措置75が始まった2018年から2019年にかけてアメリカの輸入に占めるシェアを大きく落とし、2022年にはEUを下回ることとなった(第1-2-2図)。
2021年1月のバイデン大統領の就任後は、国家安全保障や経済繁栄を理由として半導体やバッテリー等のサプライチェーンの国内回帰の動きが促進されており、特に中国を主眼に置いて輸出規制や調達制限の措置が取られている。今後はこれらの措置が米中貿易の動向に影響を及ぼしていくと考えられるところ、次に主な措置について概観する。
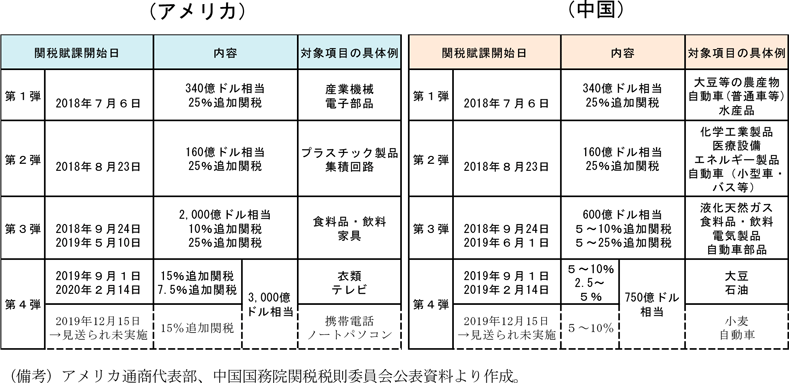
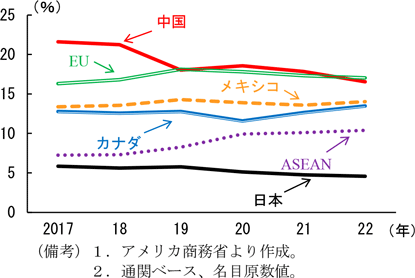
(輸出規制により、中国向け半導体輸出は減少)
輸出規制の影響が特にみられるのは半導体である。2022年10月7日にアメリカ商務省産業安全保障局(Bureau of Industry and Security: BIS)は、中国への先端半導体、スーパーコンピューター、半導体製造装置及びその関連品目に対する新たな輸出規制の暫定最終規則(Interim Final Rule: IFR)76を発表した。それまでは中国の一部企業に限定していた輸出管理規則(Export Administration Regulations: EAR)77の対象範囲を拡大し、先端半導体等を中国に輸出する場合は許可が必要となった。また、アメリカ人78が中国国内でこれらの分野における開発や生産を支援する場合にも許可が必要となった。新たな措置の概要は第1-2-3表のとおりであり、2022年10月中に順次発効されることとなった。
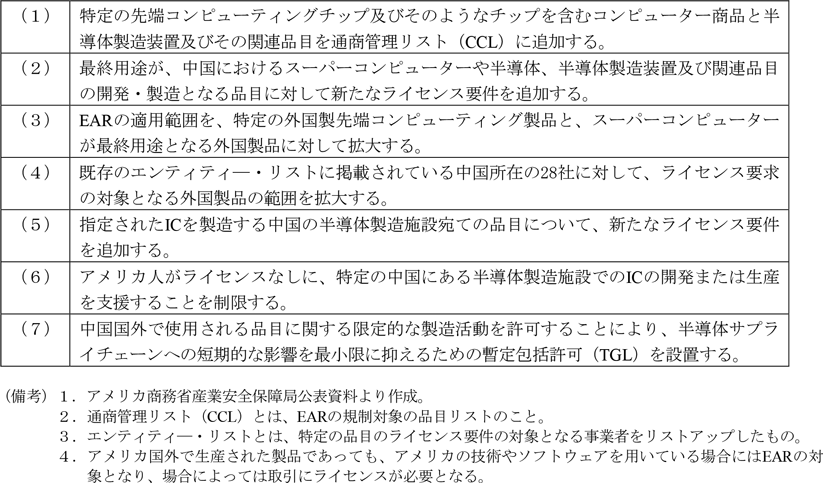
そこで、半導体関連品目の中国向け輸出を確認すると、2022年3月以降は緩やかな減少傾向であったものの、同年10月以降は、世界全体向けに比べても中国向けの落ち込みがより大きくなっていることが分かる(第1-2-4図)79,80 。中国は当該措置についてWTOに提訴しており、引き続き動向が注目される。
なお、中国商務省と海関総署は2023年7月3日に、国家の安全と利益を保護するとの目的で、8種類のガリウム関連品目及び6種類のゲルマニウム関連品目の輸出を同年8月1日より規制することを発表した。ガリウムとゲルマニウムは半導体の材料として使用されるため、対中輸出規制に対する対抗措置である可能性があるところ、同製品の対米輸出を中心とした輸出動向を今後注視する必要がある。
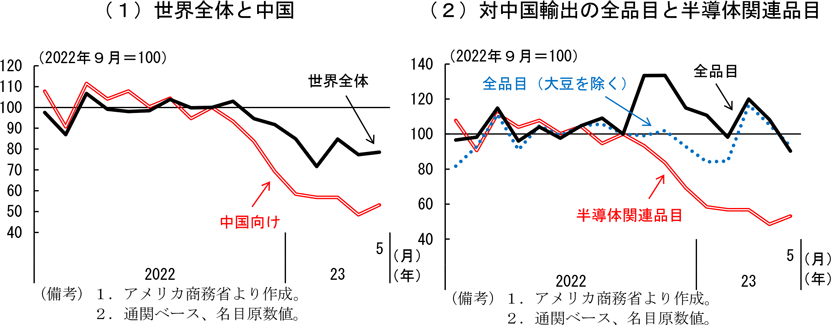
(米中貿易摩擦の影響はアメリカの輸出だけではなく、輸入にも現れている)
米中貿易摩擦の影響はアメリカの輸出だけではなく、輸入にも現れている。2022年8月に成立した「インフレ抑制法」では、電気自動車の購入者に対して最大7,500ドルの税額控除が盛り込まれた。2023年4月18日に発効した税額控除要件には以下の項目が含まれており、他の条件81を満たした上で、この2つとも満たしていれば7,500ドルの税額控除、1つを満たしていれば3,750ドルの税額控除となる。
(i)バッテリーに含まれる重要鉱物に係る要件:
アメリカまたはアメリカと自由貿易協定を結んでいる国で抽出または加工された重要鉱物が、バッテリーに含まれる重要鉱物のうち一定割合以上であること。
(ii)バッテリー部品に係る要件:
北米で製造または組み立てられた部品が、バッテリー部品のうち一定割合以上であること。
現状、アメリカのバッテリーの輸入シェアの大部分を中国が占めており、本要件は中国からの輸入集中を脱却することを目指している(第1-2-5図)。上記要件の割合82は年々引き上げられていくこととなっており、各メーカーが北米での工場新設を次々に発表していることを踏まえると、今後はカナダやメキシコがシェアを拡大していく可能性がある。
また、2022年12月に成立した2023年度国防授権法5949条では、連邦政府機関が、特定の半導体製品やサービスを含む電子部品、製品及びサービスを調達する契約を結ぶことを禁止することが盛り込まれた83。当該措置は本法の制定日から3年以内に禁止令を制定することとしており、5年後には発効となる。また、アメリカ商務省は本法の制定日から180日以内に、(i)国内及び同盟国の半導体設計・生産能力の分析をし、(ii)特定の半導体が連邦システムや、連邦システム以外を含む請負業者及び下請け業者のサプライチェーンにもたらすリスクの評価をし、(iii)連邦政府の要件を満たすために必要な国内半導体の設計・生産能力の向上及び供給業者の支援のための戦略策定を行うこととなっている。
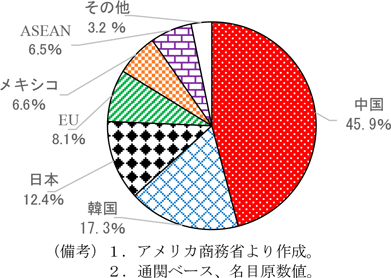
(米中貿易摩擦の拡大は、アメリカの企業の設備投資にも影響)
米中貿易摩擦の拡大は貿易面だけではなく、アメリカの企業の設備投資にも影響を及ぼしている。2021年6月にアメリカエネルギー省(Department of Energy: DOE)は「リチウムイオンバッテリーに関する国家計画84」を発表した。本計画は世界全体での膨大なリチウムイオンバッテリー需要増に対応できるような体制構築をするための投資を誘導することを目的としている85。また、中国は世界最大のEV市場であり、リチウムイオンバッテリー製造のサプライチェーンを支配していると指摘しており、急速に生産能力を拡大し続ける中国を追い上げなければならないとしている。また、2022年5月にDOEはこの計画を踏まえ、2021年11月に成立した「インフラ投資・雇用法86」に基づき、以下のとおりバッテリーの国内製造に関する助成金を発表している(第1-2-6表)。
これらは、2030年までに販売される乗用車及び小型トラックの新車の50%をバッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、燃料電池電気自動車を含むゼロエミッション車にするという2021年8月の大統領令の目標達成を支援するものとなっている。2020年以降、電気自動車のシェアの拡大とともにバッテリーの輸入金額は増加し続けており、なかでも徐々にシェアを拡大している中国への依存度は高まっている(第1-2-7図)。
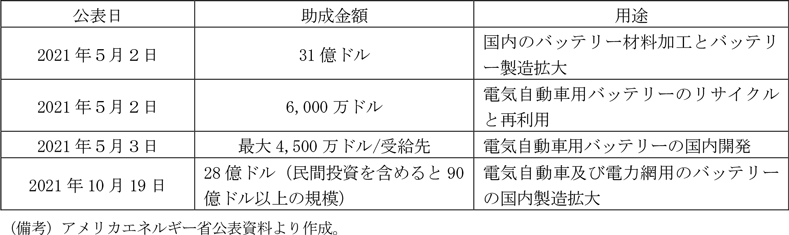
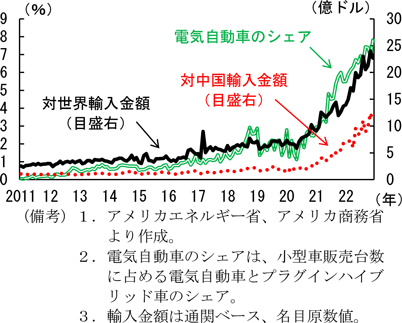
また、バッテリー同様に半導体においても、2021年2月の「アメリカのサプライチェーンに関する大統領令87」を受けて法整備が進められ、2022年8月に「CHIPS及び科学法」が成立した88。同法の背景には、アメリカは半導体を発明したが、現在では世界の供給量の約10%、先端半導体においては皆無に等しい量しか生産しておらず、その代わり世界の生産量の75%を東アジアに依存しているという問題意識がある。そして、CHIPS及び科学法は、生産コストの低下や雇用創出、サプライチェーンの強化及び中国への対抗のために、アメリカの半導体の研究、開発、製造、人材育成に527億ドルを支出するほか、半導体及び関連機器の製造に必要な資本費用に対して25%の投資税額控除を提供するとしている(第1-2-8表)。
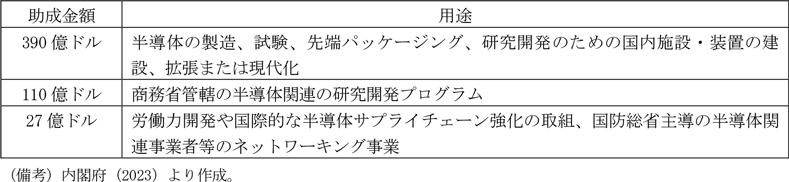
以上のように、米中貿易摩擦は現代において特に重要な製品であるバッテリーや半導体の対外依存の低下と自立をめぐる対立である。バッテリーや半導体の安定供給は、自動車産業を始め、多くの産業にとって欠かせない要件であることから、供給制約が生じた場合の経済への影響は大きく、今後も動向を注視していく必要がある。
(2)自動車販売の動向
(自動車販売台数は持ち直しの動き)
アメリカの自動車関連支出は個人消費支出額の4%程度、耐久消費財支出の4分の1程度を占めており、個人消費を分析する上では重要な要素である。自動車販売台数の動向をみると、2023年に入ってからは持ち直しの動きが続いている。自動車販売台数は変動が激しいため、基調(トレンド)を確認するために、ホドリック=プレスコット分解(HP分解)により平滑化してみる89。リーマンショック前後の期間を除くと、2000年代前半や2010年代後半は年率換算でおおむね1,700万台程度をトレンドとして推移している。現在のトレンドはおおむね1,500万台前後で推移しており、感染症拡大前からトレンドは低下している(第1-2-9図)。一方で、2022年後半以降の自動車販売台数の実数は、HP分解で推計した現在のトレンドを上回って推移しており、感染症拡大前への回帰を示している。本稿では、このような状況の中、自動車ローン金利や、供給制約の問題が自動車市場にどのように影響を与えたのかを分析していく。
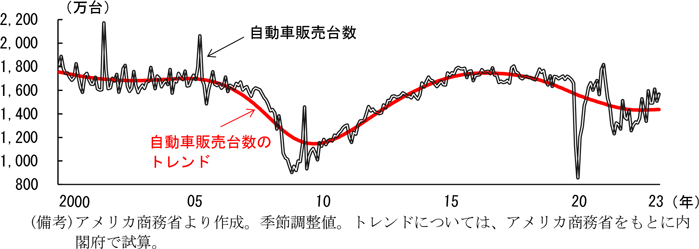
(販売台数は価格や失業率に対して感応的だが、所得や金利に対しては非感応的)
まず、自動車ローン金利が自動車販売台数に与える影響について考察する。2022年3月以降、政策金利が急速に引き上げられる中で、自動車ローン金利も2009年以来の水準まで急上昇した。金利の上昇は購入コストの増加につながることから、一般的には需要を減らす効果がある。しかしながら、自動車販売台数と実質自動車ローン金利の関係を長期的にみると、過去に高金利で推移していた時期についても、自動車販売台数は1,700万台前後で安定的に推移している(第1-2-10図)。
そこで、自動車販売台数の需要関数を推計し、一人当たり実質可処分所得や実質自動車ローン金利、自動車価格、失業率の説明力を定量的に確認すると90、自動車価格や失業率の上昇に対して自動車販売台数の伸び率は低下する傾向がみられた。一方、所得や金利のパラメータ推定値については、統計的に有意ではないことから、アメリカの自動車販売台数に対する自動車ローン金利の影響は大きくないと考えられる。
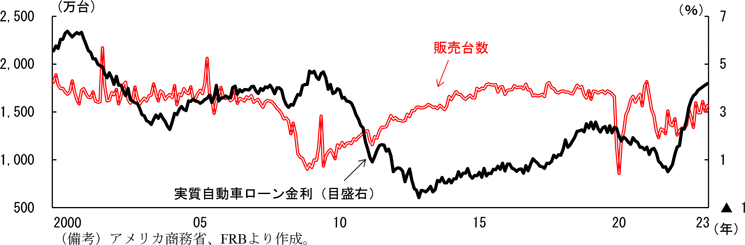
(最近の販売台数増加は供給制約の緩和によるもの)
続いて、供給制約が自動車販売台数に与えた影響について考察していく。2021年以降は、世界的な車載用半導体の供給不足に陥り、自動車の生産に多大な影響を与えた。自動車生産の停滞は自動車在庫を減少(販売店における店頭ラインナップを減少)させ、自動車販売台数を減少させる要因になる。
ここで供給制約と自動車生産台数の関係をみるために、供給制約の程度を測る指標としてISM製造業景況感の入荷遅延を用いる(第1-2-11図)。本指標は販売(需要)に比べて入荷(供給)がどの程度対応しているかを測る指標であり、本指標の低下は需要に生産が追い付いていないこと、すなわち供給側に何らかの制約があることを含意する。2021年からの両者の推移をみると、入荷遅延の低下(入荷の待ち時間増)にやや遅れて自動車生産台数も連動して減少している。一方で2022年後半からは入荷遅延が改善傾向となり、自動車生産台数も回復し始め、緩やかながら、自動車在庫も持ち直しの動きがみられている91(第1-2-12図)。
このように、2021年以降の自動車販売台数については、需要に見合った供給量の確保がより重要な決定要因であると考えられる。
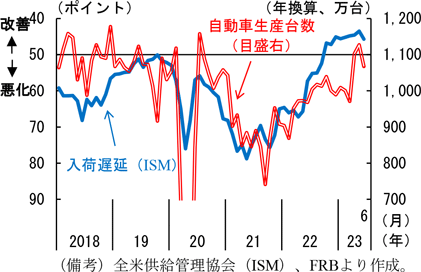
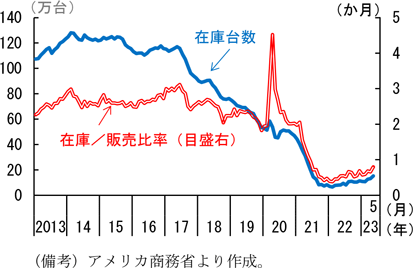
(3)住宅着工の動向とMBS債
(住宅着工はおおむね横ばいとなり、需要には底堅さがみられる)
住宅投資は金融引締めの影響を特に受けやすいことから、現下の景気動向を分析する上では重要な需要項目である。これまでの動向を振り返ると、感染症拡大に伴う郊外の住宅需要の高まりや低金利を受けて住宅購入者が増加したことから、住宅着工件数は増勢が続いてきたが、2022年以降は政策金利の引上げに伴い住宅ローン金利が上昇したことから、住宅着工は減少傾向にあった(第1-2-13図)92。しかしながら、金融引締めの進展下でも住宅市場の景況感は2023年に入って上昇するとともに(第1-2-14図)、住宅ローン金利が高止まりする中でも住宅着工件数は2023年になりおおむね横ばいで推移しており、住宅需要には底堅さがみられている93。
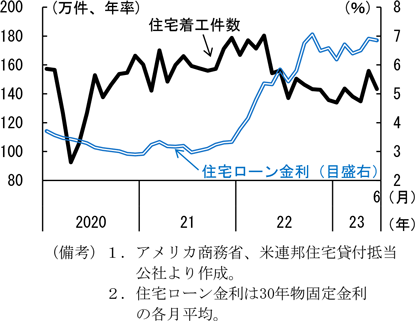
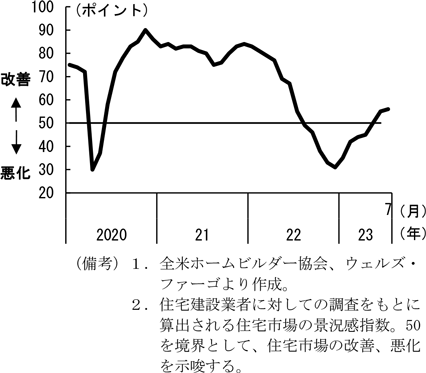
(住宅販売増や価格上昇、借り換え需要によりMBS債発行は増加)
また、住宅市場の動向を金融面からみると、2020~2021年にかけてMBS債の発行が大きく増加した(第1-2-15(1)図)。MBS債とは住宅ローン債権担保証券のことであり、低リスク資産として多くの金融機関で保有されている。感染症拡大以降、MBS債の発行が増加した理由としては以下の3点が考えられる。
1点目として、同時期に住宅販売件数が増加したことが挙げられる。
2点目として、住宅価格の上昇に伴い住宅販売件数一件当たりのMBS債発行額が増加したことが挙げられる。2000~2020年は住宅販売件数一件当たりのMBS債発行額はおおむね30万~40万ドル程度であったが、住宅価格が高騰した2020年、2021年は60万ドル以上に増加している(第1-2-15(2)図)。
3点目として、低金利下で住宅ローンの借り換えが増えたことが挙げられる(第1-2-16図)。アメリカでは、できるだけ長期で元利金償還を一定額に固定し、長期金利が低下した際には借り換えを行う傾向が強い94ことから、金利が低下すると借り換え需要が高まる傾向がある。
こうしたことからMBS債の発行額は増えたものの、2022年の発行額は感染症拡大前の水準まで減少している。なお、2023年は住宅着工がおおむね横ばいとなったこともあり、MBS債の発行額は下げ止まる可能性がある。
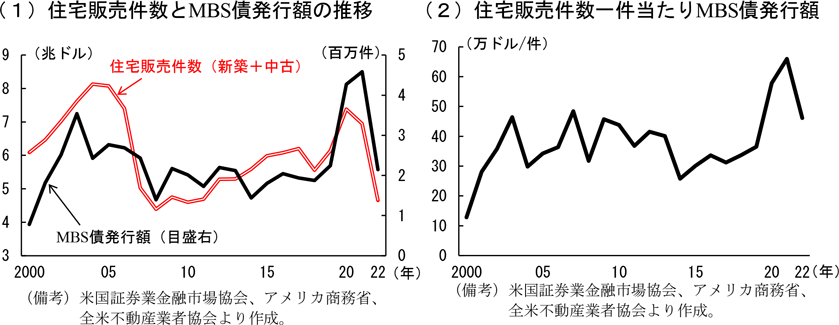
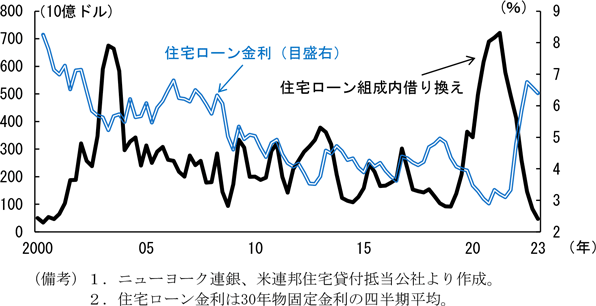
(MBS債はFRBと商業銀行が主に保有)
発行額が増加したMBS債の主な保有者は、FRBと預金取扱金融機関、特に商業銀行であった(第1-2-17図)。FRBの保有割合は量的緩和政策(QE)とともに上昇したことから、2022年6月以降は低下に転じている。また、商業銀行の保有割合は、米国債よりも高い利回りを期待できることから上昇したが、政策金利の引上げに伴って含み損の発生リスクが高まったことから売却が進み、このところ低下している。なお、2023年3月から5月にかけて破綻した銀行のうち、特にSVBでは、資産の中にMBS債が多く含まれており、金利リスクの管理が適切に行われず、金利上昇に伴い含み損が拡大したことも破綻の一因となった。
このように、金融緩和及び引締めは、住宅市場を通じて金融機関の財務状況にも影響を及ぼす。今般のSVB破綻の影響は限定的であったものの、金融機関の規模によっては経済全体にも影響が波及する可能性がある。
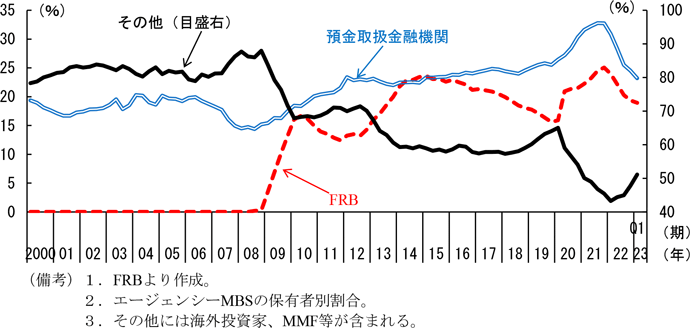
(4)労働市場の動向
(雇用者数は増加傾向が続いているが、業種によって違いが生じている)
労働市場の動向は金融政策上の主要な論点である。感染症拡大に伴い、雇用者数は2020年4月にかけて大きく落ち込んだものの、それ以降は堅調な回復を続けており、2022年6月には感染症拡大前の水準を回復した。さらに、急速な金融引締めが進展する中においても、雇用者数は増加を続けている(第1-2-18図)。
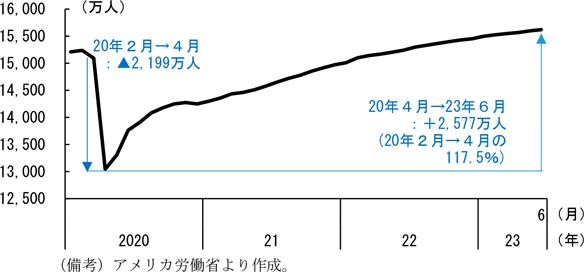
しかし、雇用の強さの中にも、一部業種においては増加に足踏みがみられるなど、変化の兆しが現れてきている。まず、2022年12月には情報サービスの雇用が減少に転じ、金融等の業種でも頭打ちになっている(第1-2-19図)。特に情報サービスについては、2022年秋以降、米大手IT企業を中心に大規模なレイオフが進行しており、その動きは2023年に入ってからも続いている(第1-2-20表)。感染症拡大以降、IT分野への需要が急速に拡大した同業種では、需要の頭打ち等によって雇用に余剰感が生じていることがレイオフの主な理由として考えられている95。
その一方、レジャー・接客業の雇用者数は感染症拡大前の水準に戻っておらず、依然として高い増加率がみられている。レジャー・接客業は雇用者数全体の1割以上を占めていることから、雇用者数全体の増加に対する寄与は大きく、同業種が完全に充足するまでは全体の雇用者数も増加し続ける可能性がある。
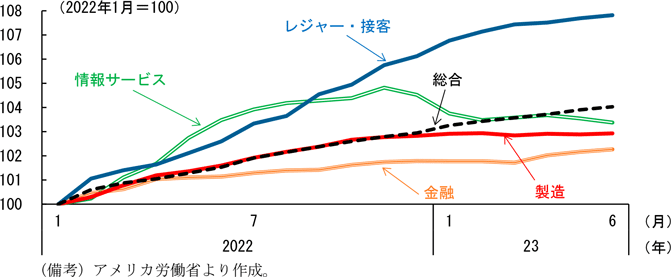
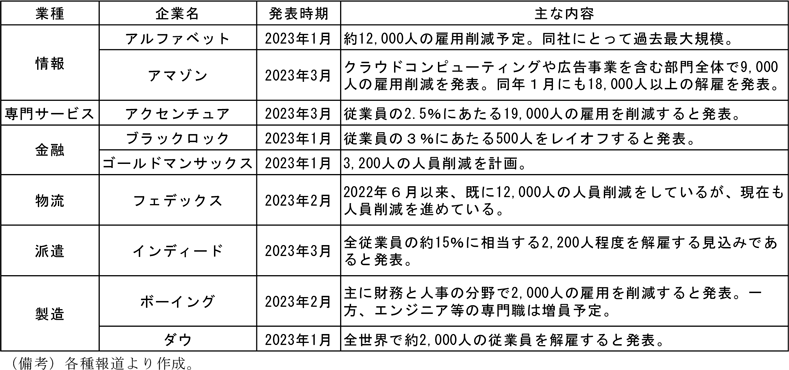
(低賃金の業種では賃金上昇率は高いものの、賃金水準には大きな差が残る)
次に、賃金動向をみると、全体の賃金上昇率は高水準で推移する中、高賃金業種(第1-2-22表で上位に分類されている業種)の賃金上昇率が比較的低く、前述のレジャーのような低賃金業種(第1-2-22表で下位に分類されている業種)の賃金上昇率が高いという傾向がみられる。例えば、2020年2月から2023年6月までの賃金上昇率が11%である情報サービスに対し、同期間に、レジャー・接客業は25%伸びている。しかし、当初の水準差が大きいことから、2023年6月の時間当たり賃金には2倍以上の差がある。こうした相対的な低賃金が、レジャー・接客業の労働需要が超過する要因になっているとも考えられる(第1-2-21図、第1-2-22表)。
このように、アメリカの雇用情勢は依然として強さを保っているものの、変化が生じ始めていることに留意する必要がある。
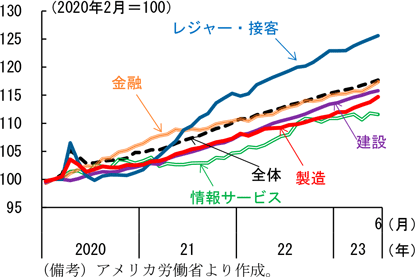
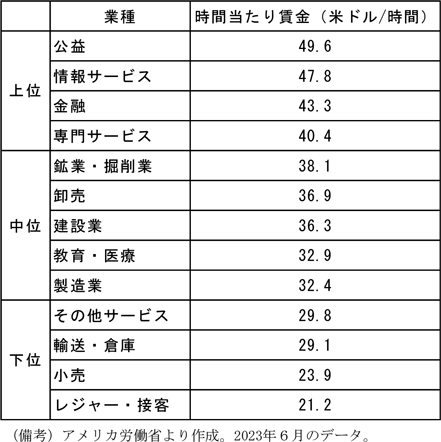
Box.アメリカの転職者の賃金動向と労働需給
アメリカでは転職者の方が継続就業者よりも賃金上昇率が高くなる傾向があり、特に2022年以降は過去と比べて両者の差がより開いていることが確認できる(図1)。これは転職者に対してより高い賃金を企業側が提示しているためであるが、その背景としては労働需給のひっ迫が考えられる。そこで労働需給の動向をみてみると、過去に労働需給がひっ迫していた時期は転職者と継続就業者の賃金上昇率の差がより開いており、緩和している時期は両者の差が縮小しているようにみえる(図2)96。
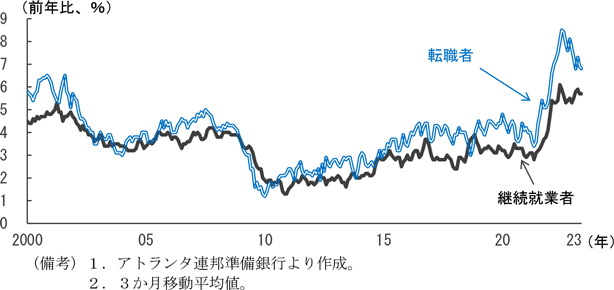
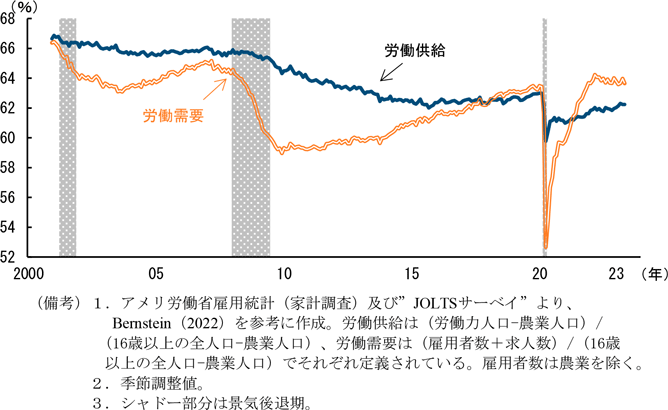
そこで、賃金ギャップ(ここでは転職者と継続就業者の賃金上昇率の差)を被説明変数、労働需給ギャップ(ここでは労働需要と労働供給の差、プラスが需要超過)の1期ラグを説明変数としてOLS推計97を行うと、労働需給ギャップが1%拡大すると賃金ギャップが0.21%拡大する傾向が示される(図3)。すなわち、アメリカでは労働需給のひっ迫が転職者の賃金を更に引き上げていると考えられる。
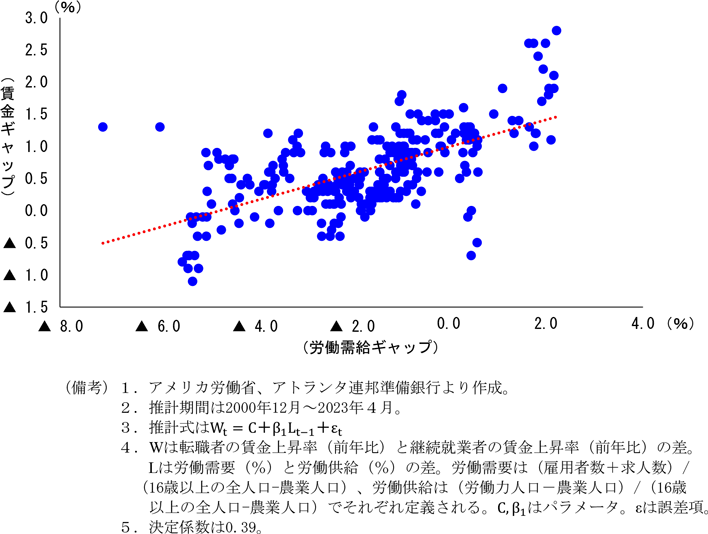
コラム6:アメリカ連邦政府の債務上限問題
アメリカでは、連邦債務残高の上限額は法定となっている。債務残高が法定上限に達した場合、国債の新規発行が不可となり、過去の債務の元利払いのための資金が調達できないことから、債務不履行(デフォルト)となる可能性がある。法定上限に達した場合は、上限引上げの法改正(または、債務上限の一時適用停止)を行う必要があるが、議会が上下院で多数派の党派が異なる「ねじれ議会」である場合は、この法改正が難航することがある。
最近の例を振り返ろう。2023年1月19日に債務残高が法定上限(約31兆4,000億ドル)に到達し、その後は特別措置によって手元資金を確保してきた。5月3日に大統領経済諮問委員会(CEA)がデフォルトに陥った場合の見通しを公表し、5月12日には議会予算局(CBO)が6月第1~2週に債務履行が不可能となる見通し98を公表した。こうした中、6月前半に満期を迎える短期国債(1か月債)の利回りが急上昇するなど金融市場に不安定な動きがみられた(図1、図2)。
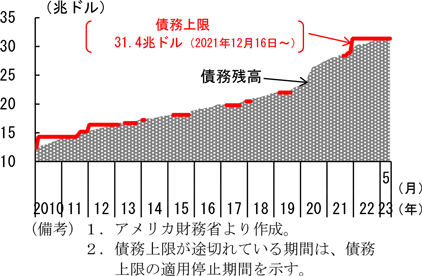
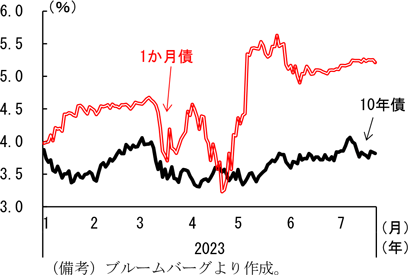
5月に入って以降も、野党(共和党)が大幅な歳出削減を求める中で、与党(民主党)がそれを受け入れず、対立は長期化していた。野党の主な要求内容は、連邦政府の歳出を4兆5 ,000億ドル削減し、伸び率を今後10年間は毎年1%に抑制するものであり、結果としてインフレ抑制法に基づく各種施策を廃止に導く内容であったことも99、与野党の対立が長期化する原因となった。5月下旬でも与野党での合意には至らず、徐々に金融市場において不安が広がっていたが、5月27日に基本合意に達すると、国債利回りが低下するなど、市場でもストレスの緩和がみられた。5月31日には新たに提出された財政責任法案(Fiscal Responsibility Act of 2023)が下院を通過し、6月1日には上院で可決され、2023年の債務上限問題は収束した。
同法では、2025年1月1日までの間、債務上限を適用停止としている。また、野党が求めていた歳出削減については、2024年度と2025年度における裁量的支出の上限を新たに設定している。その他、歳出削減に関する主な内容は以下のとおりとなっている。
・新型コロナウイルス対策で措置された予算のうち未消化分の取消
・内国歳入庁の体制整備に係る予算のうち未消化分の取消
・SNAP(低所得者向けの食料援助)の就労要件の拡大
・TANF(貧困家庭向け支援策)の就労要件の拡大
このように野党側の要求が一定程度受け入れられた一方で、野党側の主な削減対象となっていたメディケイド(低所得者向け医療費支援策)等については、今回の合意では変更されておらず、全体の予算規模もおおむね同程度で維持されている。
議会予算局(CBO)の試算では、同法により裁量的支出が2年間(2024年度、2025年度)で2,482億ドル(約33兆円)抑制されるとしているが、同期間の裁量的支出の総額は約3.9兆ドル(約520兆円)と見込まれており、歳出抑制効果は対裁量的支出比で約6%にとどまる見込みである100。
なお、今般の債務上限問題が収束して約2か月後の8月1日に、格付け会社大手のフィッチ・レーティングスは、アメリカの長期外貨建て債務格付けを、最上級であるAAAからAA+へと一段階引き下げると発表した。同社は今回の引下げ理由は、(i)債務上限問題にも現れているアメリカ政府のガバナンスの低下、(ii)悪化が見込まれる財政収支、(iii)高水準かつ増加が続いている政府債務残高、の3点と説明している。これに対し、イエレン米財務長官は同日中に「古いデータを用いた恣意的な格下げである」、「データは改善を続けている」等、今回の格下げに反論する旨の声明を発表した。しかしながら、2011年以来約12年ぶりとなる格下げが行われたことで、6月に成立した財政責任法の執行を含めて、今後、アメリカ政府のガバナンスや財政状況についての金融資本市場からの評価がより厳しくなることも考えられる。
2.中国:地方財政
中国では、地方政府の財政悪化が大きな懸念事項となっており、現行の第14次五か年計画(2021~2025年)では、「地方政府の隠れ債務を穏当に解決する」と五か年計画において「隠れ債務」が初めて言及された。また、2023年の政府活動報告においても「地方政府の債務リスクの防止・解消」が同年の重要政策方針として挙げられている。
本項では、中国の地方政府の債務状況について、不動産市場の停滞との密接な関連を確認しつつ整理する。
(政府の財政収入は感染症再拡大と不動産市場停滞により減少)
中国政府の財政収入は、感染症拡大等により2020年及び2022年は減少した(第1-2-23図(1))。2020年には、感染症拡大による経済の停滞、また政策対応として大規模減税(1章1節4項参照)を行ったことにより、税収等が減少したことが主因であった。2022年は、感染症再拡大を経ながらも税収等は前年比横ばい程度となっていたが、土地使用権譲渡収入101が大幅な減少に転じたために、財政収入全体も前年を下回る結果となった。従来、土地使用権譲渡収入はほぼ一貫して増加しており、2021年には特別会計の収入の89%相当に達していた。2022年に不動産市場の停滞を受けて土地使用権譲渡収入が減少すると、財政収入全体が大きな影響を受けることとなった。
なお、2020年以降、財政収入が伸び悩む一方で、社会保険基金支出等を中心として、財政支出は増加を続けている(第1-2-23図(2))。
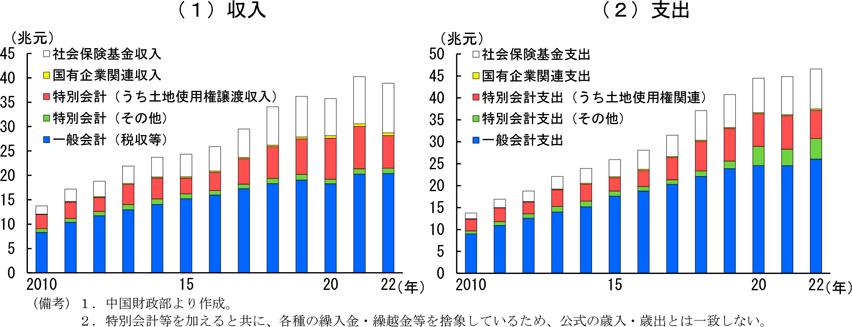
(地方政府が大きく依存する土地使用権譲渡収入は2023年上半期も減少が継続)
土地使用権譲渡収入は、2022年は不動産市場の停滞を受けて前年比▲23.2%もの大幅な減少となった(第1-2-24図)。2022年11月より相次いで実施された不動産市場支援策102を受けて、2023年1-3月には住宅価格や不動産販売面積等に持ち直しがみられていたが、感染症拡大下で蓄積されていた繰越需要の発現が一巡すると、不動産市場は改めて軟調な動きとなった(第1章1節4項参照)。土地成約(面積・価格)の停滞が続く中、土地使用権譲渡収入は2023年に入っても前年比二桁の減少が続いており(1-6月累計で前年比▲20.9%)、地方政府の財政収入に大きな下押し圧力となっている。
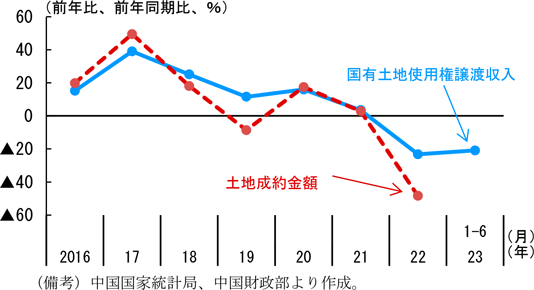
中国政府の財政収入について、中央と地方を分けてみると、中央政府は税収等が全体の9割以上を占めるのに対し、地方政府は税収等の比率が低く、国からの移転と土地使用権譲渡収入に大きく依存している(第1-2-25図)。また、社会保険基金収入は地方政府に集中しているが、これは社会保障財源として義務的支出に充てられる(第1-2-26図)。景気対策等の実施は地方政府が主体的に取り組む必要があるものの、税収等が乏しい中で慢性的な財源不足となっている103。近年、中央政府は地方への移転支出を増やしているものの、土地使用権譲渡収入が回復しない場合、地方政府にとって厳しい状況が続くこととなる。
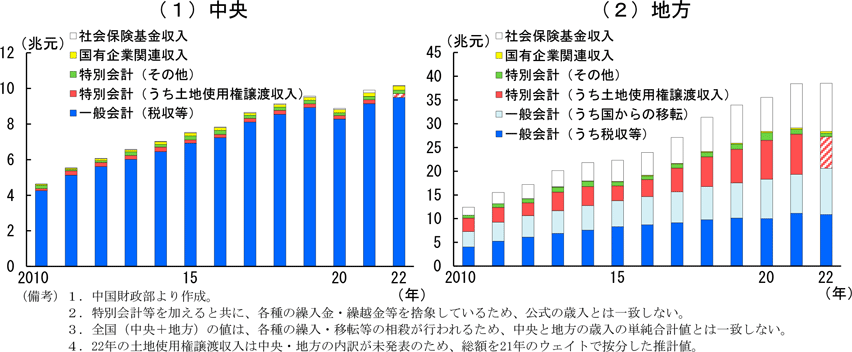
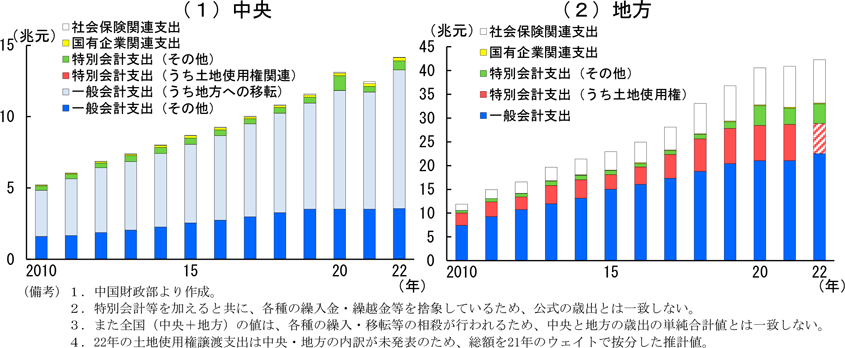
(地方政府の債務残高は内陸部の省で上昇)
税収や土地使用権譲渡収入が停滞する中で、地方政府の債務を取り巻く環境は悪化が続いており、一部ではデフォルト(債務不履行)が懸念されている。報道によれば、内陸部に位置する貴州省貴陽市の財政局は、2023年5月に公表した年次報告において、「債務削減のための技術的手段は既に使い果たしており」「一部の地方は債務金額が比較的大きく、償還資金を確保できなければ、債務リスクがいつでも発生し得る」等と表明した104。貴州省等の内陸部では、貿易や各種産業の集積を通じて発展が進む沿海部に比べて成長産業に乏しく、人口流出も進む中で税収が停滞し、債務問題の面でも格差が拡大していることが指摘されている105。
では、地方政府の債務の実態はどのような状況だろうか。各地方政府(北京や上海等の大都市と省)の債務残高について、経済規模に応じた調整(対GDP比106)を行った上で、当該地方の発展段階を近似的に表す一人当たりGDPとの対応関係を散布図でみると、北京や上海といった大都市は、一人当たりGDPが高く、債務残高対GDP比が非常に低い(第1-2-27図(1))。一方で、内陸部の青海省や当局が債務リスクに言及したとされる貴州省は、一人当たりGDPが低く、債務残高対GDP比は高水準で、一人当たりGDPと債務残高対GDP比はおおむね逆相関となっている。散布図に近似直線を当てはめると、説明変数(一人当たりGDP)の係数は▲2.0となり、一人当たりGDPが1万元(約20万円相当)低い地方では、債務残高の対GDP比が約2ポイント高い傾向があることを示している。加えて、散布図に近似曲線を当てはめると、原点に対して凸型の曲線となる。これは、一人当たりGDPが小さくなるほど、債務残高の対GDP比が更に高まる傾向を示している107(第1-2-27図(2))。
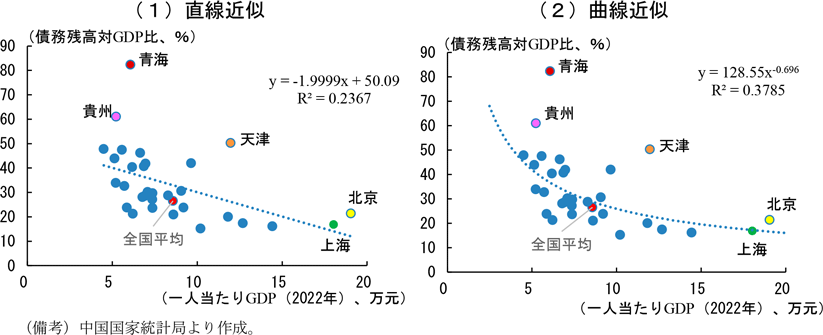
(地方政府には隠れ債務が存在)
以上では、各地方政府発表の公式な債務残高のデータを用いた。しかしながら、地方政府の債務については、公式統計ではカウントされていない部分(いわゆる「隠れ債務」)のリスクが高まっていることが指摘されている。
IMFは、Jin and Rial (2016) の手法を用いて、地方政府が特別目的会社(「地方融資平台」)を活用し、簿外(オフバランス)で資金調達を行い都市インフラ開発プロジェクト等を進めている状況を整理した。また累次の対中4条協議報告書108や世界金融安定報告書(Global Financial Stability Report109)において、地方融資平台を活用した「隠れ債務」の推計値を示しつつ、債務リスクに警鐘を鳴らしている。2023年2月時点の推計値をみると、地方融資平台の債務の推計値は対GDP比で44%になり(第1-2-28図)、中央・地方政府の公式債務を合わせた値(47%)とほぼ同規模に達している。また政府系ファンドも合わせた債務残高の対GDP比は101%となっており、今後も増加していくと見通している。
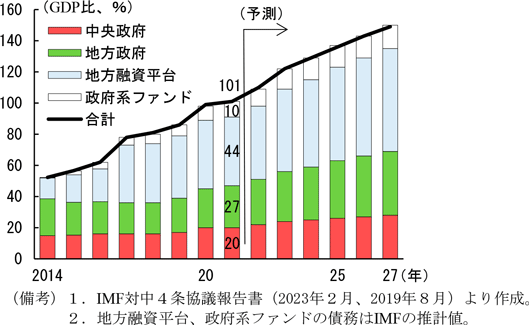
(隠れ債務への対応が重要な課題)
地方政府が財源不足の中、「地方融資平台」を活用して資金を調達してインフラプロジェクトを進めるプロセスの概要は、以下のように整理される110,111 。
(1)地方政府は、特別目的会社としての「地方融資平台」(「〇〇建設集団」等)に、都市開発(インフラ整備、宅地開発等)事業を発注し、土地使用権や国有エネルギー会社の株式等の資産を払下げ。
(2)地方融資平台は、金融機関からの融資や都市投資債券の発行により資金を調達。その際、地方政府からの資産や「暗黙の保証」が機能。
(3)地方融資平台は、調達した資金を元に工事を発注(住宅は不動産業者、その他工事は建設企業)。完成後、プロジェクトの売却益(土地の値上がり益)から、融資への返済、都市投資債券への償還を実行。
上記プロセス(3)において、都市開発や住宅販売が順調な時期には返済も順調であったが、人口動態の転換点や都市化の天井を迎えつつある中で、「地方融資平台」の資金繰りが悪化している。2020年以降は感染症拡大期の経済停滞、特に2022年には不動産市場の悪化が重なることで、以下のような逆回転が生じることとなる。すなわち住宅販売や土地の値上がりを前提としたビジネスモデルが立ち行かなくなり、これを前提とした地方政府の政策プロセスにも不透明感が広がっている。
(3’)建設企業、不動産企業の工事が停滞。地方融資平台はプロジェクトの売却益(土地の値上がり益)が減少。
(2’)地方融資平台の財務体質が悪化。都市投資債券の格付け低下、利回り上昇(利払い負担増加)、金融機関からの資金調達が停滞112。
(1’)地方政府は土地譲渡収入が減少、各種政策のための財源が不足113。
今後は、地方融資平台のデフォルトが発生するか、発生した場合にはそれが一部にとどまるか全国に伝ぱするのか114、そうした事態を防ぐためにどのような政策措置が事前に採られるのかを注視する必要がある。政府は2023年5月に組織改編を行い金融監督部門等を再編した国家金融監督管理総局を発足させ、金融監督体制の強化を図るなど、金融安定を本年の重要課題に位置付けているところ、問題の先送りにとどまらない具体策が待たれる。
3.ヨーロッパ:エネルギー確保と脱炭素、半導体サプライチェーンの域内構築
ヨーロッパでは、2023~2024年の冬に向けた短期的なエネルギー確保及び長期的な脱炭素に向けた取組が、経済の先行きを考える観点のみでなく経済安全保障の観点からも重要な課題となっている。関連して半導体サプライチェーンの域内構築に向けた取組についても同様に重要な課題となっていることから、本項ではそれらの現状について概観する。
(1)エネルギー確保の取組と脱炭素に向けた取組
(エネルギー貯蔵量は高水準で推移し、2024年冬の天然ガス需要分は確保の見込み)
EUは2022年2月のロシアによるウクライナ侵略以降、ロシア産化石燃料への依存から段階的な脱却を進めるとともに、エネルギー確保及び消費削減に努めてきたことから、エネルギー需給状況については改善がみられている。2022~2023年冬は比較的暖冬であったこともあり、同期間における域内の天然ガス消費は前年比▲16%と需要が抑えられるとともに115、アメリカからの輸入量が増加したこと等もあり116、2023年に入り、天然ガス貯蔵量は過去(2015~2020年)の貯蔵量の最大値レベルで推移している(第1-2-29図)。
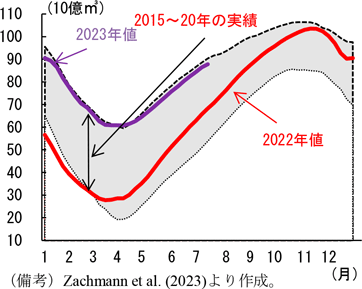
欧州評議会は2023年3月23日、委員会と加盟国に対して、来冬に向けた天然ガス備蓄の充填の準備と緊急時の計画を策定するよう求めていた。2023年5月時点では、同計画を踏まえれば、2023年の天然ガス使用量は2022年比で▲5%となる見込みである117。内訳としては、消費抑制策と再生可能エネルギーの利用拡大により電力部門における天然ガス使用量が前年比▲15%となるとともに、産業部門においては天然ガス価格の低下により同+5%となる一方、家計においては同▲4%と見込まれている。
このように2023年前半における天然ガス貯蔵量が過去(2015~2020年)の最大値にあるとともに、2023年の天然ガス使用量見込みが前年比▲5%程度と更に削減されることを踏まえると、現時点においては来冬の需要を賄うだけの天然ガスを確保できる可能性が高いと考えられる。ただし、世界全体の天然ガス需給や厳冬など天候要因等にも左右され得るため、引き続き状況を注視する必要がある。
(欧州では二酸化炭素の排出削減が進む)
脱炭素については、英国は温室効果ガス削減目標として2035年に1990年比で▲78%、EUは2030年に1990年比で少なくとも▲55%を掲げている。この進捗状況を確認するために、1990年=100として欧州主要5か国及びEU全体の二酸化炭素排出量をみると、2021年の英国は57.7(▲42.3%)、EUは71.4(▲28.6%)となっている。EUの内訳は、ドイツが60.8(▲39.2%)、フランスが77.7(▲22.3%)、イタリアが80.1(▲19.9%)、スペインが100.4(0.4%)となっている(第1-2-30図)。
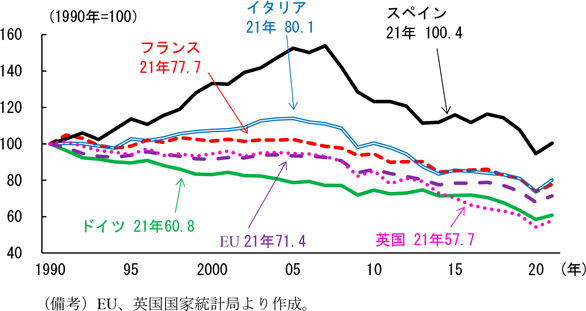
(脱炭素に向けて合成燃料の使用等の新たな取組が進められるが、時間を要する見込み)
これまでもEUは脱炭素に向けて積極的な取組を進めており、2030年の温室効果ガス削減目標達成に向けた政策パッケージである「Fit for 55」に基づく取組として、EU排出量取引制度の強化118等の施策を推進してきた。また、ウクライナ情勢を受けて欧州委員会が2022年3月に公表した「REPowerEU」計画に基づきガス供給源の多様化等を進めてきた。さらに、EU理事会は2023年3月には、欧州議会と2022年10月に暫定合意したエンジン車の新車販売を2035年から禁止するとしていた方針を転換し、合成燃料(e-fuel)119の使用を条件に販売継続を認めることでEU議会と合意し、Fit for 55の実現に前進がみられた。
個別国の動きとしては、ドイツ政府が、国内の航空産業向けに、2030年までに持続可能なジェット燃料を少なくとも年間20万トン生産する目標を掲げているほか、国内においてカーボンニュートラルな合成燃料を大規模製造する初の大型設備に対し600万ユーロ(約8.8億円)の投資を行うこととしている。英国は、2023年3月、長期的なエネルギー安全保障と自立の強化を目指し、安価かつクリーンな国産電力の拡大、グリーン産業の構築を目的とした「パワーアップ・ブリテン」を発表した。具体的には、全国の電気自動車(EV)充電インフラ強化に3億8千万ポンド(約556億円)の資金提供を行うなどにより、炭素排出のネットゼロを達成しながら英国の国際競争力の強化を目指すこととしている。
ただし、これらの取組を実施するには時間を要することに留意する必要がある。合成燃料を利用した自動車の開発は、その費用が高額になると見込まれるため、ドイツでは高級車を中心に検討が進められており、低価格化等による合成燃料車の普及には時間を要すると考えられる。
(2)半導体サプライチェーンの域内構築に向けた取組
(英国やEUでも経済安全保障の取組が進む)
英国及びEUにおいては、米中貿易摩擦を受けた経済安全保障の重要性の高まりを受けて、半導体等の重要な製品のサプライチェーン(供給網)を域内に構築する動きが引き続きみられている。
英国では2022年1月、国家安全保障・投資法が制定・施行され、国家安全保障上重要な事業分野における外国企業による投資受入れについては事前届出を義務付けるとともに審査を実施している。また2023年5月、国家半導体戦略を発表して半導体を重要産業として位置付け、英国内における研究開発に加え、生産を英国内で行うなど国内供給網の強化等を図ることとしている。
EUにおいては加盟国各国が個別に投資規制を設けているが120、2020年10月に域内直接投資審査規則が全面施行され、加盟国は個別案件の審査において他の加盟国から必要な情報提供を受けつつ審査を実施している。
(経済安全保障と経済成長のバランスは引き続き課題)
これらの措置を受けて、英国及びユーロ圏では、域外からの投資を拒否する動きがみられている。英国では、2022年11月、オランダに本社を置く中国系半導体製造企業による英国内のマイクロチップ工場の買収について、国家安全保障・投資法に基づき撤回命令が出されている。また、ドイツでは、同月、中国系企業によるドイツ国内の半導体工場の買収について、ドイツの秩序と安全保障を脅かす可能性があるとの理由から不許可としている。
サプライチェーンリスク等に対する経済安全保障の観点は重要ではあるものの、経済成長とのバランスは引き続き重要な論点であり、経済のデカップリングに至らないよう、慎重な対応が今後とも求められる。
4.国際金融:人民元の国際化、途上国債務問題
本項では、長期的に重要な国際金融上のテーマと考えられる、国際金融危機を契機に進められてきた中国人民元の国際化の動向に加え、感染症拡大を契機に債務返済のリスクが高止まりしている途上国債務問題への対応について概観する。
(1)中国人民元の国際化
中国では、2008年の世界金融危機を契機に、資本規制は残しながらも、貿易取引上の決済通貨として人民元建ての取引等が増加し、人民元の国際化が進んだ。また、中国人民銀行(中央銀行)の主導により、独自の人民元国際決済システム(CIPS:Cross-border Interbank Payment System)が構築され、海外との貿易決済を従来のドル建てから人民元建てに変更する動きがみられている。ここでは、人民元の国際化に向けたこれまでの主な取組を概観し、CIPSの利用状況等を踏まえ、人民元の更なる国際化の可能性について考察する。
(国際金融危機を契機に人民元の国際化が進む)
まず人民元の国際化に向けたこれまでの主な取組について概観する。
一般的に、通貨の国際化とは、当該通貨が、貿易や金融等の国際取引において、価値尺度、決済手段、支払準備としての用途が拡大することを指す121。以下では決済手段及び支払準備の観点から人民元の国際的な用途拡大の状況をみてみる。
2009年7月、中国通貨当局は、上海及び広東省の4市(広州、深セン、珠海、東莞)に居住する者に対し、香港・マカオ及びASEAN諸国からの輸入の決済のために人民元を使用することを認めた。これにより海外との貿易決済における人民元の使用122が始まった。
また、2009年以降、中国人民銀行は世界の中央銀行と通貨スワップ協定を締結し、相手国が国際流動性不足に陥った際に人民元を引き出して対応することを認めることとなった。そのため、2009年から2021年末までに計39の中央銀行との間で通貨スワップ協定を結び、その後は協定の延長・更新を行っている。
2016年には、人民元はIMFの特別引出権(SDR)通貨バスケットの構成通貨に新たに組み入れられ、IMF加盟当局間では「自由に使用可能」(freely usable)な通貨と認定された。なお、SDR通貨バスケットにおける人民元のウェイトは組み入れ時点では米ドル(41.73%)、ユーロ(30.93%)に次ぐ10.92%で、円(8.33%)や英ポンド(8.09%)を上回ることとなった123。
2022年以降、資源取引における人民元決済は拡大している。特に、ロシアによるウクライナ侵略に伴い、ロシアがG7とEU、オーストラリアからの経済制裁により、国際銀行間通信協会(SWIFT:Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication、後述)を通じた決済システムから排除されたことを受け、ロシアとの原油等の貿易決済には人民元の活用が増加124している。また、中国当局は2国間の合意として、ブラジルとは取引全般に対する決済通貨を人民元とレアルに限定する方針を公表(2023年3月)し、アルゼンチンとは中国からの輸入商品に対する決済通貨を米ドルから人民元建てに切り替える方針を公表した(2023年4月)。
(資本規制もあり利用割合は小さい)
このように人民元の国際化は進んでいるものの、世界経済における中国の経済規模(18.5%(2022年名目GDPでの構成比))125と比べると、国際決済通貨としての利用割合は小さい(2.77%(2023年6月時点))(第1-2-31表)。また、各国が保有する外貨準備に占める比率をみると、2021年末までは上昇傾向で推移したものの、2022年には上昇傾向に一服感がみられており、水準としても低位にとどまっている(2.69%(2022年10-12月期))(第1-2-32図)126。
経常取引と資本取引は表裏一体であることから、資本取引の自由化が通貨の国際化の進展に重要となる。しかし、中国は、金融政策の自由度を保ちつつ管理変動相場制を維持するために資本規制127を行っており、人民元の国際化には制約が課されている。一方で、中国当局は貿易決済等に係る市場からの要請と事務の効率性の観点から人民元の国際化の必要性を主張しており128、そのための取組としてCIPSの導入が進められている。
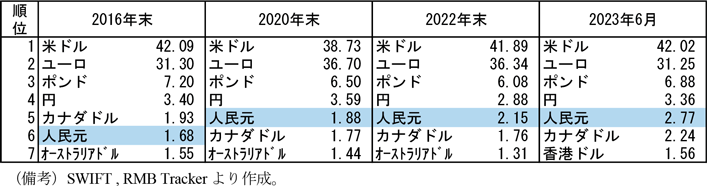
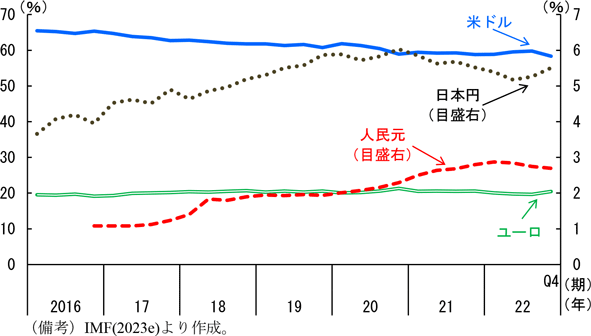
(CIPSは導入が進むも、SWIFTの代替は限定的)
中国人民銀行は人民元の更なる国際化を推進し、人民元決済を容易にする独自の国際決済システムとして、2015年にCIPSの稼働を開始した。CIPSには2023年6月30日時点で111か国・地域から1,452銀行が参加している。このうち、中国の国内銀行から構成される直接参加行が89行、海外銀行から構成される間接参加行が1,363行となっている。なお間接参加行は、直接参加行を通じて、人民元建ての貿易取引、直接投資、融資、個人送金等の国際決済を行うことができる。
しかしながら、CIPSはSWIFTに大きく依存する129。CIPSを利用する中国国内の直接参加行間の決済情報の伝達はCIPSの専用回線で行われるものの、中国国外の間接参加行と直接参加行の間の決済情報伝達はSWIFTで行われることから、CIPSがSWIFTを代替できる範囲は限られるとみられる130。
実際に、CIPSの利用機関数と決済処理件数・金額は増加しているものの、その利用状況はまだ限定的である。2022年における1日当たりの平均取扱件数は1万7,650 件、決済処理金額は590億ドル程度であり、SWIFTの1日平均4,480万件、5兆ドルと比べると小さい規模にとどまる(第1-2-33表)。
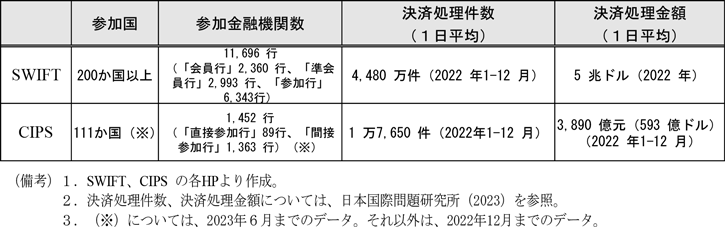
(人民元の更なる国際化は限定的となる可能性)
前述のとおり、中国人民元は、資本規制等もあることから、世界経済における中国の経済規模と比べると、国際決済通貨としての利用割合は小さい。また、外貨準備比率をみると、2022年には上昇傾向に一服感がみられている。
加えて、CIPSについては、2023年6月までの1年間に間接参加行が98行増加しており、国際的な人民元決済の広がりは進みつつあるものの、SWIFTを代替できる範囲は引き続き限定的であると考えられる。
以上を踏まえれば、現状では人民元の更なる国際化については限定的となる可能性があるが、今後、資本規制の緩和等により国際化の推進が加速されるか否か、注視する必要がある。
コラム7:デジタル人民元の動向
中国においては、現金に代わる電子的支払手段である中央銀行デジタル通貨(デジタル人民元)の導入に向けた実証実験が積極的に進められている。以下ではデジタル人民元の導入に向けた取組について概観する。
まず、デジタル人民元の開発の経緯を確認する。2014年、中国人民銀行は同行内に専門チームを設置してデジタル人民元の研究をスタートさせ、2019年11月、同行は基本的設計の完成並びに試験運用を行う地域・サービスを選択すると発表した。2020年3月にはデジタル人民元の流通に関連する法律の作成に取り組むことが公表され、同年10月、人民銀行法改正法案を公表した。
中国人民銀行は、2020年4月から8月にかけて、深セン、蘇州、雄安新区、成都の4地域でデジタル人民元の試行を行い、同年10月以降、本格的な実証実験を深セン、蘇州、北京、西安、海南など国内主要都市で実施した131。実証実験は、2022年9月19日までに、中国国内の17省・26都市(北京市、上海市、広東省等)において行われ、2022年8月末までに累計での取引回数は3.6億回、取引金額は1,000億元(約1.9兆円)となっており、2022年末時点で流通残高は136.1億元(約2,600億円)とされる132。デジタル人民元の正式導入のスケジュールは発表されていないが、2022年9月には実証実験を段階的に、広東省、江蘇省、河北省、四川省の全域に拡大する方針を示し、導入に向けた実証実験を重ねている。また、最近の実証実験133では、地方政府や銀行で職員の給与をデジタル人民元で支給する動きもみられている。
中国がデジタル人民元の発行に向けた動きを加速化する理由として、主に次の点が専門家から指摘されている134。(i)民間のデジタル通貨135や暗号資産(ビットコイン等)からの自国通貨の保護、(ii)国際取引におけるリアルタイム、低コスト・高効率、低リスクな経済取引及び為替取引の実現、(iii)二国間や複数国間でのデジタル法定通貨の同盟の確立及び国際的な規範や基準の策定、(iv)中国人民銀行による経済活動や国内外の金融・資本取引のリアルタイムでの追跡(トレーサビリティ)、(v)個人への直接の現金送金による需要喚起策の実現、(vi)資金洗浄(マネーロンダリング)、テロ資金動員、脱税等の金融犯罪の取締まり、(vii)きめ細かい金融政策の調整の実現。
このような取組の現状を踏まえ、専門家からは、中国はデジタル通貨の技術・運営・規制面等の国際基準の策定においては先行する可能性があると指摘されている136。
(2)途上国債務問題
途上国137の対外債務の現状をみると、対外債務残高の対名目GDP比は2010年代前半は緩やかな上昇傾向が続いたものの、2010年代後半から2021年にかけては横ばい傾向となり、債務問題の悪化傾向はマクロの観点からは一旦落ち着いたようにみえる(第1-2-34図)138。しかしながら一部の途上国では、欧米の急速な金融引締めを受けて、自国通貨が米ドル等の主要国通貨に対し下落傾向を示している139。一般的に、債務の多くが米ドル建てとなる中、自国の通貨安は債務負担増となり、返済能力が低下するとともに、金利引上げに伴う借り換え時の利払いも増加するというリスクを途上国は引き続き抱えている。以下では、途上国の債務返済リスクの現状、対外債務問題についてのこれまでの取組、及び問題解決に向けた最近の取組を概観する。
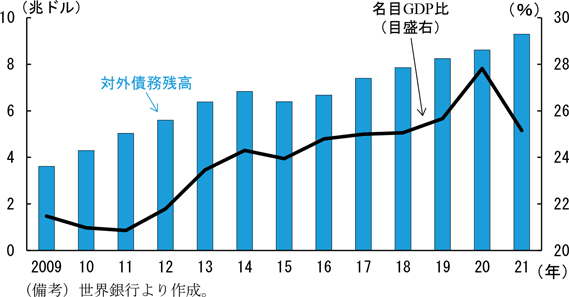
(途上国の多くが債務返済上のリスクを抱える)
途上国のうち低所得国の債務返済リスクを評価するIMFの債務持続性分析140(DSA)をみると、評価対象となる低所得国は70か国程度でおおむね一定である中で、2020年以降は「過剰債務」及び「高リスク」の割合は全体の5割以上を占めており、感染症拡大を契機に債務返済のリスクが比較的高い途上国の割合は高止まりしていることが確認できる(第1-2-35図)。そのリスクは一部顕在化し、2022年末にガーナは事実上のデフォルト141に陥った。また中所得国ではあるが、スリランカも2022年にデフォルトに陥った142。2023年5月末時点においても、低所得国70か国のうち、11か国が債務支払に問題があり、26か国が高リスク、26か国が中リスク、7か国が低リスクと評価(デフォルト国を除く)されている(第1-2-36表)。
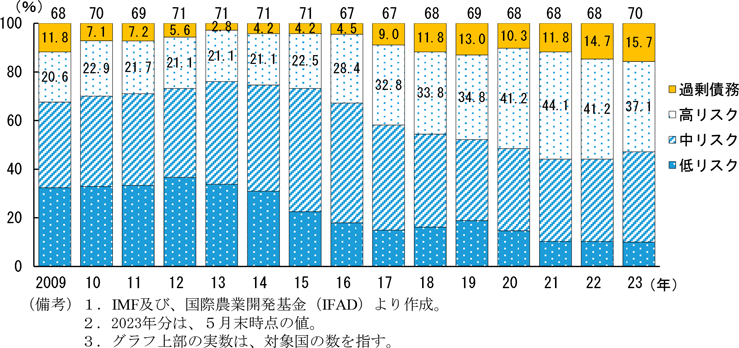
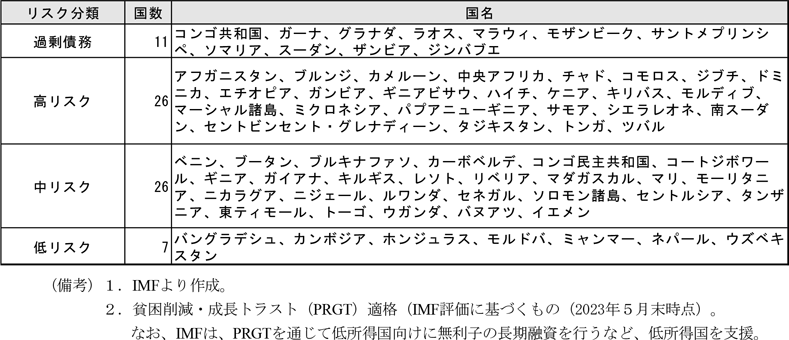
(金利上昇等を受けて、途上国の対外債務問題対応は流動性支援から構造改善にシフト)
このように、一部の低所得国においては、過去に債務救済143を受けたにもかかわらず、近年、再び公的債務が累積し、債務持続可能性が懸念されている。この背景として、債務国側では、自国の債務データを収集・開示し、債務を適切に管理する能力が不足していること、債権者側では、資金供給の担い手が多様化しており、新興債権国や民間債権者による貸付割合が大幅に増加する一方で、パリクラブ144参加国による貸付割合が相対的に減少していることが指摘されている。
感染症拡大を受けて、G20及びパリクラブは、2020年4月に「債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)」を立ち上げ、低所得国が抱える公的債務の支払いを一時的に猶予する措置を実施した。DSSIは2021年12月末に終了したが、2020年11月に合意された「DSSI後の債務措置に係る共通枠組」(以下、「共通枠組」という。)の下で、債務救済を実施することとなった145。
その後、欧米の金融引締め等を受けた途上国の債務返済能力の低下を受けて、2023年2月に開催された20か国財務大臣・中央銀行総裁会議(G20)の議長総括では、「低・中所得国の債務ぜい弱性に対処する緊急性を認識する」と指摘され、債務破綻状態の国に対する協調した債務措置の促進に向け、予測可能かつ適時に、秩序立った方法で連携して、共通枠組の実施を強化する旨が盛り込まれた。また、「債務の透明性の向上に引き続き取り組むため、民間債権者を含む全ての関係者による協働を歓迎する」と民間債権者の参加が促された146。
途上国の対外債務問題への対応は、これまで支払猶予等の流動性支援が中心だったが、利上げの長期化に伴い、債務比率を引き下げ、途上国の支払能力を構造的に改善する方策に議論が移りつつある。対外債務問題の解決には、債務国と債権者が協力して、同じ枠組みの中で債務に関する情報共有や対話を積み重ねることにより債務の透明性を高め、全ての債権国が協調して取り組むことが必要とされている。
(債権者構成の変化に伴い、新たな協調の枠組みを構築)
途上国の対外債務問題を考えるに当たり、債権者側の構成に生じている変化にも注意を払う必要がある。近年、中国の債権者としての存在感が増大し、2021年末時点において、中国は途上国全体の対外債務残高の1割程度を占める最大の債権国となっている(第1-2-37図)147。しかし、二国間公的債務の債務救済措置を取り決める役割を果たしてきたパリクラブに中国は参加しておらず、債務問題発生時には債権者のコンセンサスを要する債務減免等が難航することがある。
このため、多国間での協調を通じた債務問題への解決に向けて、2023年2月にG20、IMF、世界銀行が共同でグローバル・ソブリン債務ラウンドテーブル(GSDR)148を設立し、民間債権者も参加しての途上国債務問題解決への議論が進められている。また、2023年4月のG7財務大臣・中央銀行総裁会合では、IMF貧困削減・成長トラスト(PRGT)149を通じ、低・中所得国向け支援拡大等が表明され、途上国支援が拡大された150。加えて、2023年5月の同会合では、フランス、インド、日本の3か国共同議長の下、スリランカのための債権国会合151の立ち上げが歓迎されるとともに、債務問題を抱える途上国の債務の透明性向上に向けた取組等について合意がなされた。
今後は、途上国の債務問題解決に向けてG7、中国を含む債権国全てが主体的役割を果たすとともに、民間債権者の協力を促す取組を続けていく必要がある。ただし、債務削減に向けた取組の実効性を担保するためには、途上国の債務実態の透明性が確保された下で、返済リスクが正確に評価され、過剰融資や借入れも抑制されることが重要と考えられる。これは、借り手側のモラルハザードを防ぐことにもつながると考えられる。