第1章 2023年前半の世界経済の動向(第1節)
第1節 世界経済の現状
2023年前半の主要先進国の景気は、欧州では足踏み状態となっているものの、アメリカは自律的に回復しており、総じてみれば底堅さを維持している。欧米ともに失業率は引き続き低水準で推移しているが、両者の間には回復力に差をもたらす諸要因が存在している。労働需給の引締まりを受けて欧米ともに高い賃金上昇率を示しているが、アメリカでは活発な転職、ユーロ圏では物価上昇を受けた労使交渉による賃上げ圧力が作用しているなどの違いがある。このような賃金上昇を受け、雇用者報酬は、アメリカでは増加ペースが物価上昇を上回り実質所得及び消費も緩やかに増加している。一方、欧州では雇用者報酬の増加と物価上昇が拮抗し、実質所得及び消費はおおむね横ばいとなっている。これに加えて、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)拡大時に形成された貯蓄超過は、アメリカでは取崩しが進み消費を下支えしているが、ユーロ圏では引き続き積み増しがみられる。さらに交易利得をみると、アメリカではエネルギー価格下落後も交易利得が発生し、欧州では交易損失が発生している。以上のように賃金、物価、貯蓄の取崩し、交易利得・損失が欧米の回復力の違いをもたらしている。
欧米の消費者物価は、エネルギー価格の下落を受けて上昇テンポに一服感がみられている。しかしながら、アメリカの住居費以外のサービス価格は、制度要因等の影響を除き、上昇率が高止まりしている。さらに、労働コストは欧米ともに上昇傾向だが、ユーロ圏は景気が足踏み状態の中で賃上げが継続し、労働コストの上昇が財・サービス価格に更なる上昇圧力を加えている。このために、欧米中銀は引締めを継続している。さらに、アメリカでは、3月の銀行経営破綻を受けて地方銀行の経営には市場からの厳しい評価が続いている。こうした金融面からの引締め圧力が続く中、企業向け貸出基準が更に厳格化し、貸出残高は減少傾向である。不動産向け貸出も6月上旬以降は横ばいとなり、貸出全体も伸び悩み、経済活動が鈍化する可能性も考えられる。
中国は、感染症が収束し経済活動の正常化が進むが、世界的な半導体不況の影響や不動産市場の低迷等から、生産・消費の回復テンポは緩やかであり、失業率は若年が過去最高水準で推移している。
本節では、このような2023年前半の世界経済の動向を、欧米の景気、雇用及び物価動向、欧米の金融・財政政策及び金融資本市場、並びに中国の景気動向の観点から分析する。
1.物価上昇下での欧米の回復力の違い
(1)欧米の景気動向
ここでは、実質GDP及び主要項目の動向から欧米の景気を概観し、主要需要項目である個人消費及び設備投資の動向について更に分析する。
(アメリカのGDPはプラス基調を維持し、ユーロ圏や英国ではおおむね横ばいで推移)
まず実質GDPから先進国経済を概観すると、2023年1-3月期から4-6月期はアメリカはそれぞれ前期比年率2.0%及び同2.4%とプラス成長を維持している。一方でユーロ圏はそれぞれ前期比年率0.0%及び同1.1%、英国は2022年10-12月期から2023年1-3月期にかけては前期比年率0.5%及び同0.5%となり、おおむね横ばいで推移している(第1-1-1図)。
次に、GDPの需要項目別の動向を確認する。個人消費については、サービス消費によるけん引が各国に共通にみられる中で、アメリカにおいては、名目雇用者報酬が物価指数を上回って上昇基調にあることや貯蓄超過の取崩しが進んでいることを背景に(後述)、緩やかに増加している。一方、ユーロ圏及び英国においては、名目雇用者報酬と物価指数の上昇率が拮抗していることも受け、おおむね横ばい傾向となっている1。
設備投資については、各国ともに機械・機器投資がけん引する中で、知的財産生産物投資はアメリカと英国においては設備投資をより引き上げる動きがみられている(後述)。また、アメリカの設備投資の持ち直しペースはユーロ圏及び英国よりも強いことが確認できる。
住宅投資については、経済活動の再開に伴い、アメリカにおいては金融緩和や郊外住宅需要の高まり等を受けて2020年後半から2021年1-3月期にかけて、感染症拡大前の2019年10-12月期比で約120%の水準まで急速に回復した後、高い水準が維持されてきた。その後、2022年4-6月期以降は急速な金融引締めを受けて前期比年率▲20~▲30%程度で急速に低下したものの、2023年4-6月期においては同▲4.1%と減少ペースが緩やかとなっている(1章2節参照)。一方、ユーロ圏と英国については、住宅需要の回復基調がアメリカと比べ緩やかであったものの、急速な金融引締めを受けて2022年半ば以降は緩やかな低下がみられている。
また、貿易面をみると、輸出については、アメリカは2022年後半から2023年1-3月期にかけては原油や天然ガス等の工業原材料を中心に緩やかに増加した後に4-6月期にはおおむね横ばい状態となり2、ユーロ圏及び英国は持ち直しから足踏み傾向となった。輸入については、アメリカは国内需要が財からサービスへとシフトしたこと等を受けて2022年以降は総じてみれば横ばいとなっており、ユーロ圏及び英国においては減速傾向となっている(第1-1-2図)。
以下では、主要な需要項目である個人消費と設備投資について更に分析を行う。
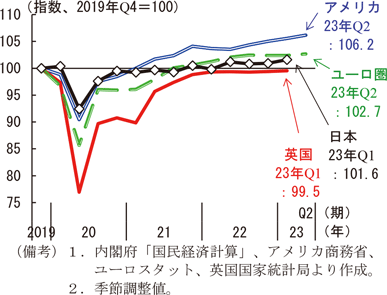
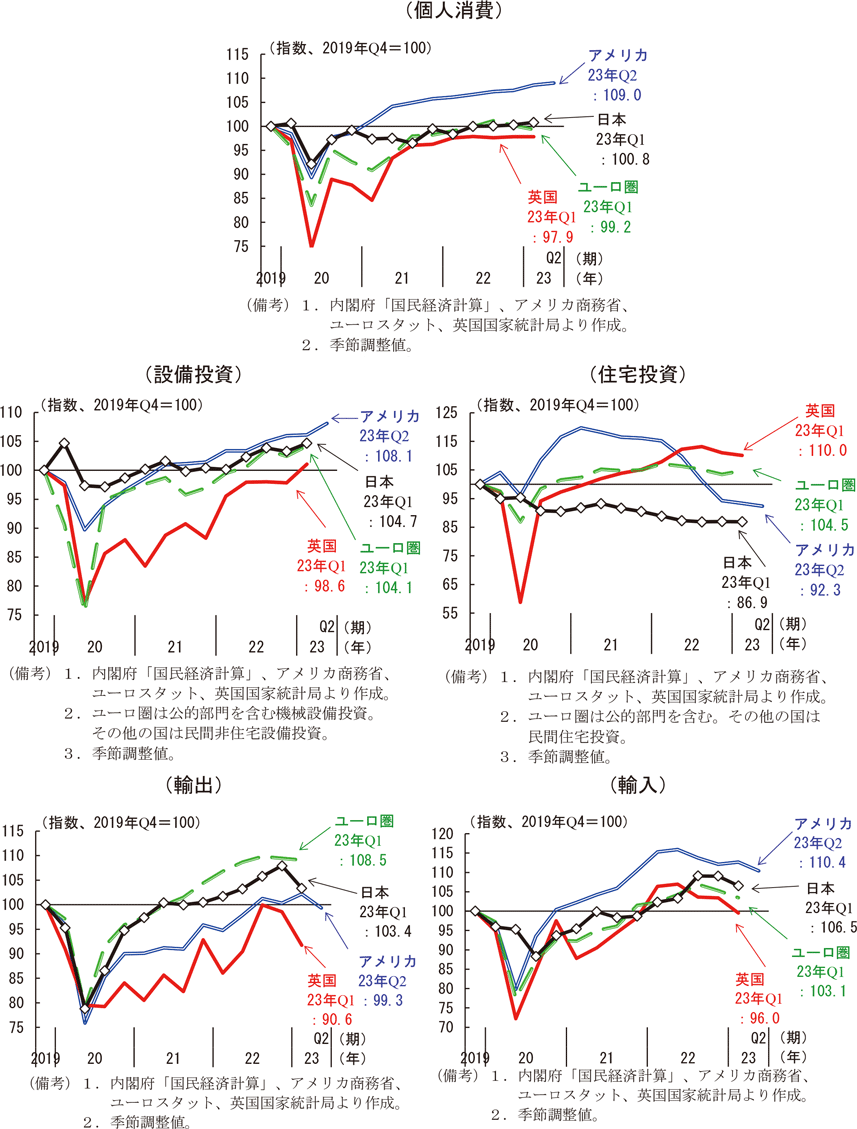
(個人消費(1):欧米ともにサービス支出が消費をけん引)
まず、個人消費をみると、米欧ともにサービス支出によりけん引されていることが確認できる。アメリカについては、経済活動の再開に伴うサービス需要の回復とその持続から、サービス消費は緩やかな上昇傾向が続いている。サービス消費の内訳をみると、経済活動再開に伴う飲食・宿泊サービスは引き続き上昇傾向が続く中、介護サービス等のヘルスケアへの支出が消費をけん引している(第1-1-3図)。なお、これまで回復が遅れていた娯楽サービスについては2023年1-3月期にはおおむね感染症拡大前の水準を回復したものの、輸送サービスについては引き続き回復に足踏みがみられている3。
また、欧州についても、旅行代理店、宿泊業、飲食サービス業を含むサービス業の景況感は2022年後半において低下したものの、2023年に入り、暖冬等を受けて旅行が活発になったこと等から引き続き上昇傾向で推移しており、消費をけん引していることがうかがえる (第1-1-4図)。
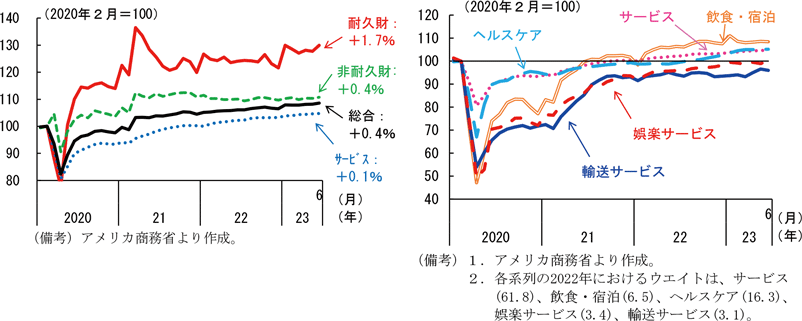
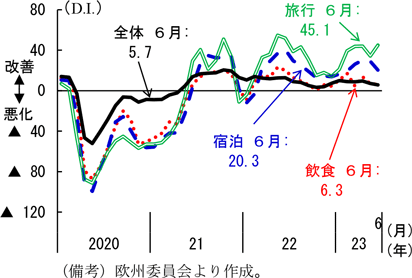
(個人消費(2):アメリカでは雇用者報酬が物価を上回るも、欧州では両者が拮抗)
続いて、個人消費の推移を所得面から確認するために、アメリカ、ユーロ圏及び英国において、感染症拡大以降の名目雇用者報酬、物価指数4及び実質個人消費支出を比較してみる。
3つの国・地域ともに感染症拡大後の名目雇用者報酬の回復基調はおおむね同じであるが、アメリカにおいては2021年央以降は名目雇用者報酬が物価指数を上回って推移しており、実質的な購買力の向上を伴った自律的な個人消費の緩やかな増加が続いている。一方でユーロ圏と英国においては2022年半ば以降は、名目雇用者報酬はユーロ圏では加速し、英国では減速する動きがみられるものの、物価指数との関係をみると、名目雇用者報酬と物価指数の上昇ペースが拮抗している。そのために実質的な購買力の向上はみられず、個人消費はおおむね横ばい傾向となっている(第1-1-5図)。
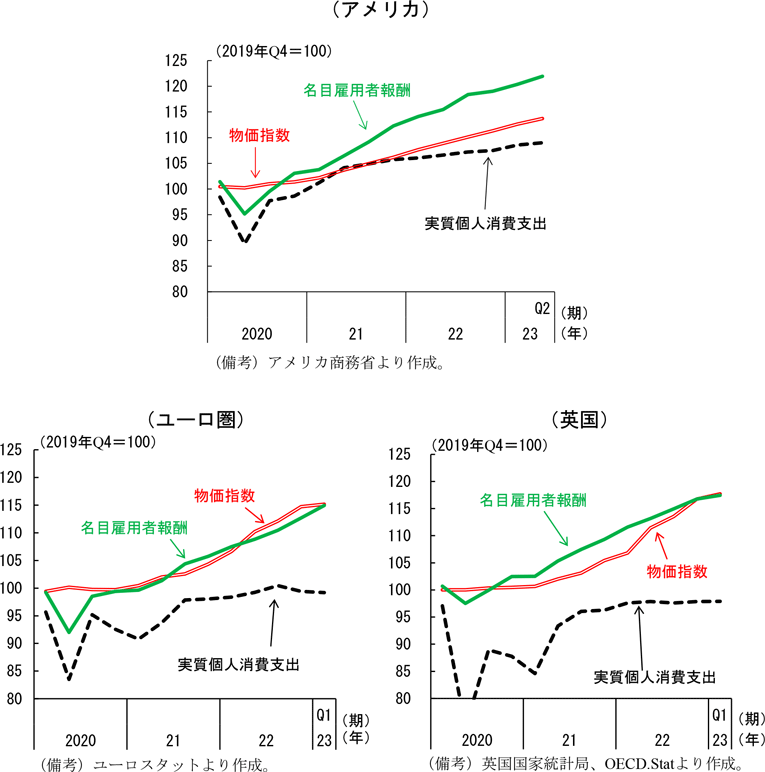
(個人消費(3):貯蓄超過はアメリカにおいては取崩しが進み、消費を下支え)
また、貯蓄超過の取崩しの有無も消費の回復力の差異をもたらしていると考えられる。感染症拡大前(2019年)までのフローの貯蓄額を超える分を積み上げた貯蓄超過ストックは、実質ベースでみるとアメリカにおいては2021年4-6月期にかけて約2.0兆ドル(対実質GDP比約10%)まで増加した。2021年10-12月期以降は物価上昇の高まりによる目減りもみられたものの、2023年1-3月期においても約1.1兆ドル(対実質GDP比約5%)分が残されている5。この間、毎期0.1~0.3兆ドルが取り崩され消費を下支えしている。
一方、ユーロ圏においては、物価上昇下ではあるものの、緩やかながらも貯蓄を積み増す動きが続き、2022年10-12月期では実質ベースの貯蓄超過ストックは約1.1兆ユーロ(対実質GDP比約3.8%)残されており、消費の下支えには寄与していない(第1-1-6図)。
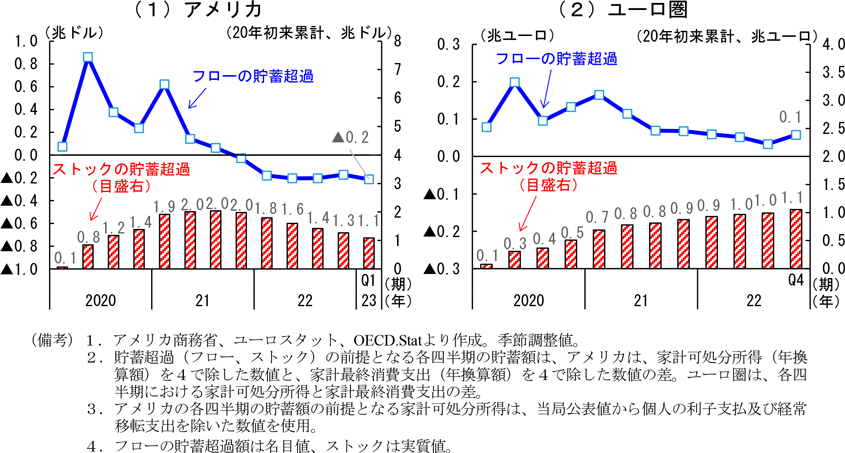
(設備投資:欧米では機械・機器投資に加えて知的財産生産物投資が設備投資をけん引)
続いて、設備投資の動向を確認する。アメリカにおいては、2023年4-6月期にかけて、機械・機器投資が振れを伴いながらもプラス寄与の傾向で推移している。加えて、R&Dやソフトウェアといった知的財産生産物投資が一貫して上昇傾向で推移するとともに、感染症拡大以降はマイナス寄与が続いていた商業施設がプラスの寄与に転じたこと等を受けて構築物投資が回復した。このことから、設備投資全体は感染症拡大以前の水準を超えて緩やかに持ち直している(第1-1-7図)。
ユーロ圏においては、知的財産生成物投資は、感染症拡大前の水準を回復していないものの、変動を伴いながら緩やかな上昇傾向で推移している。一方、機械・機器投資及び構築物投資は、既に感染症拡大前の水準を超えており、引き続き緩やかな上昇傾向で推移している。そのために設備投資全体としては緩やかに持ち直している(第1-1-8図)。
英国においては、構築物投資が感染症拡大以降は横ばいで推移しているものの、機械・機器投資や知的財産生産物投資が感染症拡大前の水準を超えて上昇傾向で推移している。設備投資全体としては、感染症拡大前の水準には届かないものの、緩やかに持ち直している(第1-1-9図)。
以上のように、各国ともに機械・機器投資がけん引する中で、知的財産生産物投資はアメリカと英国においては設備投資をより引き上げる動きがみられており、総じて緩やかに持ち直している。
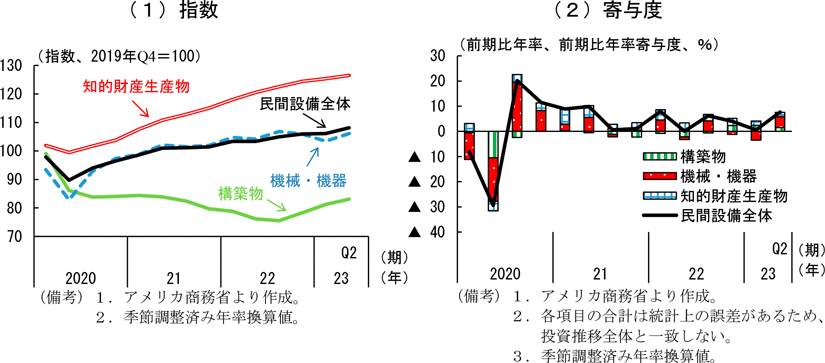
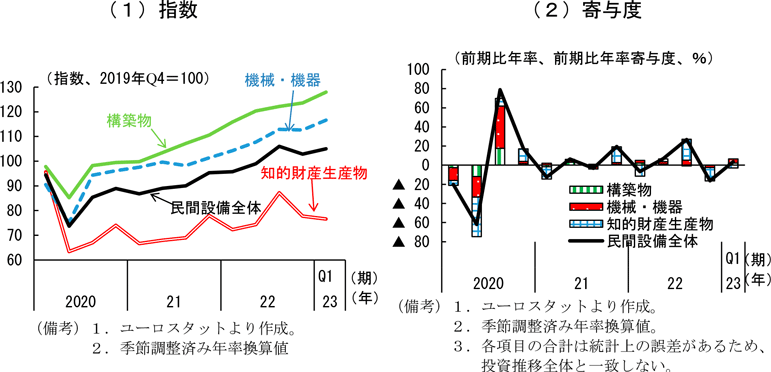
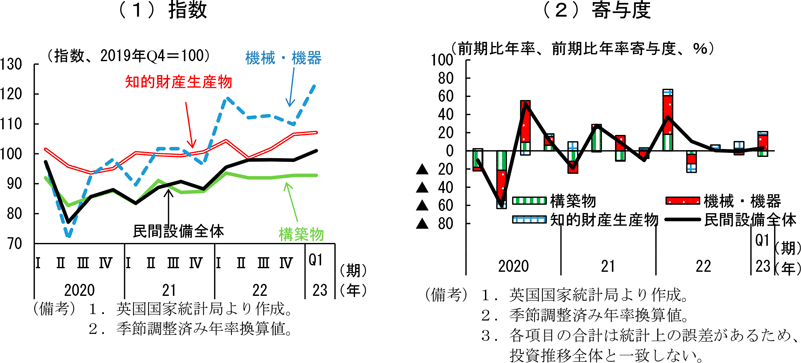
コラム1:設備投資と実質金利
基本的なマクロ経済理論では、企業は設備投資をコストとベネフィットが等しくなるように決めると考えられている。つまり、企業は資本の限界費用と限界生産性が等しくなるように資本ストックを調整、すなわち設備投資を決定するが、資本の限界費用として最も重要なものは実質金利である。実質金利が上昇すれば、それに見合った効率的な生産ができる水準まで資本ストックを減らす、すなわち設備投資を減耗分以下に減らすことも、企業にとっては合理的な選択となる。
この実質金利が割安か割高かを測る一つの基準として、ヴィクセルが19世紀末に提唱した自然利子率という概念がある。ヴィクセルは「商品価格に対して中立的であり、商品価格を上昇させることも低下させることもない一定の貸出金利が存在する。これは、貨幣が使われず、全ての貸出が実物資本財の形で行われた場合、需要と供給によって決定される金利と必然的に同じになる。これを資本に対する自然利子率の現在価値と表現しても、ほとんど同じことになる。6」と述べており、物価を安定させるとともに実物市場(財市場)の需給を均衡させるような実質金利を自然利子率と呼んでいる。
この自然利子率の概念は、現代でもマクロ経済学及び金融政策当局にも受け継がれている。Holston et al. (2017)においては、自然利子率は「生産が自然成長率7と等しく、インフレ率が一定である場合の実質短期金利」と定義され、NY連銀より推計値が公表されている8。さらに、IMF (2023e)では自然利子率を「経済成長を刺激もせず収縮もさせないような実質金利」と説明している9。
そこで、自然利子率と設備投資の関係について、2000年以降のアメリカにおける実質金利と自然利子率との差分と設備投資対GDP比の関係を例に、確認する。理論的には、実質金利が自然利子率よりも高いほど資本の限界費用が割高となるので設備投資は鈍化すると考えられる。推計の結果10、実質金利と自然利子率にかい離がない場合、設備投資対GDP比は13%程度となり、そこから実質金利と自然利子率のかい離幅が1%ポイント広がると、平均的にみて設備投資対GDP比が0.76%ポイント低下する傾向がみられた(図1)。これは理論的示唆と整合的である。なお、2023年4-6月期は実質利子率と自然利子率の差が0.8%ポイントまで開いたものの、設備投資対GDP比は14.9%と高止まりしている。
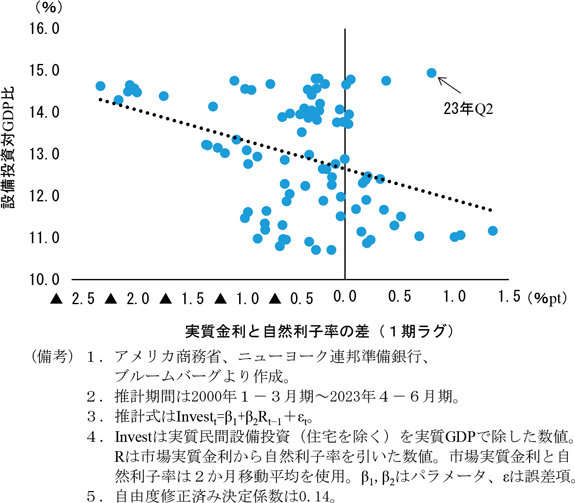
次に、IMF (2023e)のデータを用いて米欧の自然利子率と実質利子率の推移を確認してみる。実質金利は米欧ともに物価上昇を受けて2021年末にかけて低下傾向が続いたものの、2022年以降は金融引締めを受けて、アメリカは実質金利が急速に上昇しており、英国は緩やかに上昇、ドイツにおいては横ばい傾向で推移している(図2)。しかしながら、2022年10-12月期にかけてはいずれの国においても実質金利が自然利子率を下回っており、資本コストは割安であり、金利を引き上げたにも関わらず、景気刺激的な金融環境であったことが示唆されている。
なお、IMF (2023e)によれば、自然利子率の主な決定要因は人口やTFP成長率等である。人口が増え、技術進歩が進めば自然利子率は上昇すると考えられ、同一の物価上昇率の下での実質金利は相対的に低くなり、より投資促進的な環境となり得る。そのために少子化対策や成長戦略は設備投資促進の上でも重要な政策と考えられる。
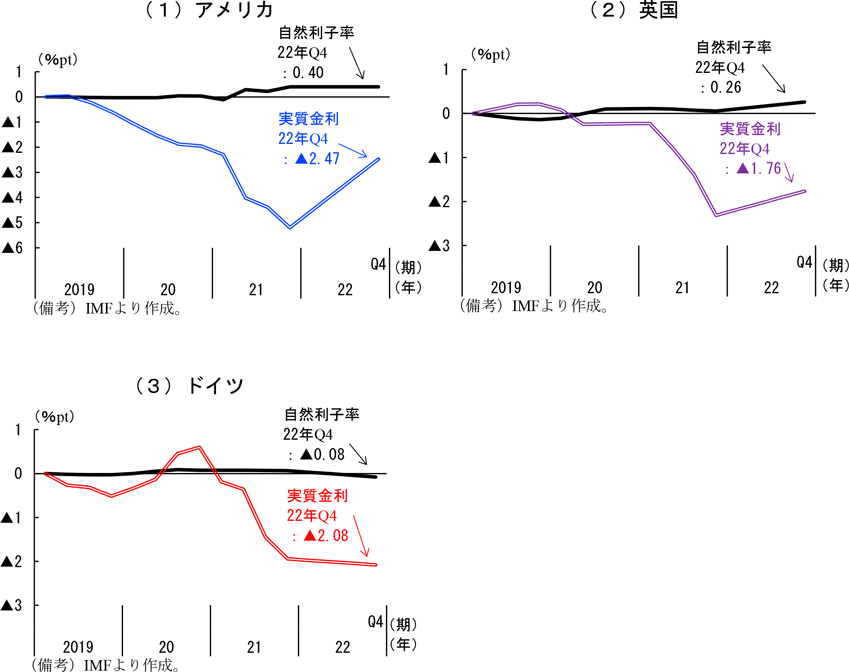
(交易利得・損失:格差は縮小するものの、アメリカには利得、欧州には損失)
上記のように、個人消費と設備投資において、アメリカがユーロ圏と英国を上回って推移しているが、その要因の一つに交易利得及び損失も考えられる。
アメリカは、2022年に入りウクライナ情勢を背景としたエネルギー価格高騰等を受けて、2022年4-6月期には交易利得が対GDP比で1.4%まで拡大した。その後はエネルギー価格の下落等を受けてやや減少したものの、2023年1-3月期でも、対GDP比1.2%の交易利得が発生している(第1-1-10図)。
一方、ユーロ圏及び英国では、ウクライナ情勢によりエネルギー価格が高騰したこと、また2022年7-9月期にはユーロ及びポンドの対ドル為替レートの下落も加わり、ユーロ圏の交易損失は対GDP比で▲2.8%、英国は同▲1.9%まで悪化した。その後エネルギー価格の下落や為替レートの上昇等を受けて、2023年1-3月期にはユーロ圏では対GDP比▲1.3%、英国では同▲0.9%まで縮小したものの、引き続き大幅な交易損失が発生している。
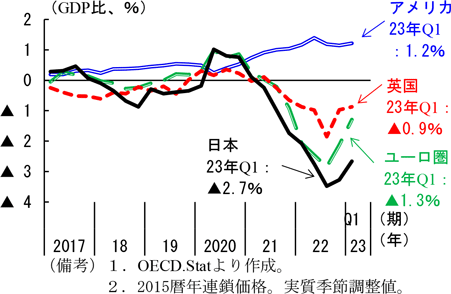
(アメリカの回復力がユーロ圏・英国よりも強いのは実質所得の違い)
以上より、アメリカ、ユーロ圏及び英国の景気動向について整理する。
個人消費については、サービス支出がけん引する構造は、アメリカ、ユーロ圏及び英国ともに変わらない。しかし、アメリカにおいては実質的な購買力の向上を伴った自律的な個人消費の緩やかな増加が続いているが、ユーロ圏と英国においては実質的な購買力の向上はみられておらず、個人消費はおおむね横ばい傾向となっている。さらに、貯蓄超過はアメリカでは取崩しが進み、個人消費を下支えしている。
設備投資については、各国ともに機械・機器投資がけん引する中で、知的財産生産物はアメリカと英国においては設備投資をより引き上げる動きがみられている。また、アメリカの設備投資の持ち直しペースはユーロ圏及び英国よりも強いことが確認できるが、各国・地域ともに総じて緩やかに持ち直している。また、住宅投資については、金融引締めが進む下でもアメリカは減少ペースが緩やかとなっている一方で、ユーロ圏と英国については緩やかな低下がみられている。
以上をまとめると、アメリカの景気は主に個人消費の自律的な回復に支えられ、回復力はユーロ圏や英国に比べて相対的に強い。また、このような動向の差異を生み出すマクロ的な要因の一つとして、アメリカにおける交易利得、欧州における交易損失も考えられる。欧米を総じてみれば、ユーロ圏及び英国は景気は足踏み状態ではあるものの、景気は底堅い状況が続いていると考えられる。
(2)欧米の雇用動向
ここでは、需給両面から労働市場の動向を分析し、労働供給はおおむね感染症拡大以前の水準を回復しているものの、労働需要が引き続き強いことから、労働市場の引締まりが続いていることを確認する。
(欧米ともに労働供給は感染症拡大以前の水準をおおむね回復)
まず、感染症拡大以降の労働供給の回復状況を生産年齢人口(15~64歳)における労働力人口(就業者+完全失業者)及び労働参加率(各年齢層の労働力人口が当該年齢層の人口に占める割合)から確認する。
生産年齢人口における労働力人口をみると、アメリカ及び英国においては感染症拡大前をおおむね回復しており、ユーロ圏は感染症拡大前の水準を超えて労働供給が増加している(第1-1-11図)。
続いて、労働参加率の動向を、生産年齢人口(15~64歳)、その内訳の25~54歳及び55~64歳、加えて65歳~74歳の各年齢階層においてみてみる12(第1-1-12図)。生産年齢人口における労働参加率をみると、アメリカにおいては2023年1-3月期において感染症拡大前の水準を回復しており、25~54歳のみならず55~64歳においても回復していることが確認できる。ユーロ圏においては感染症拡大前の水準を上回って推移しており、特に55~64歳においては、感染症拡大に伴う労働参加率の低下が軽微であり、2021年以降は上昇傾向が続いていることが確認できる。英国においては、経済不活発率の上昇13,14により低下傾向が続き、回復に遅れがみられていたが、2023年1-3月期に感染症収束に伴い短時間労働者が増加したこと等により急回復し、感染症拡大前の水準をおおむね回復している。
さらに、65~74歳における労働参加率をみると、アメリカでは感染症拡大以前の水準からおおむね1%程度低い水準で横ばいで推移しており、ベビーブーマー世代の引退の影響がみられている。一方で、英国においては感染症拡大以降もおおむね横ばいで推移した後で2022年10-12月期以降はやや上昇しており、前述の経済不活発率の上昇の影響はみられておらず、ユーロ圏においては緩やかな上昇傾向がみられている。
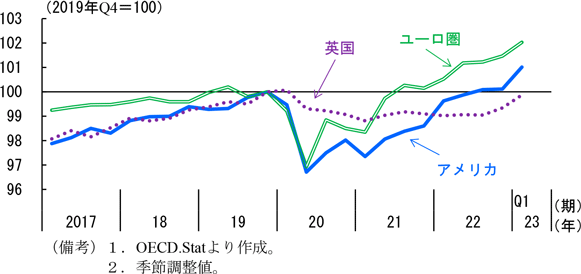
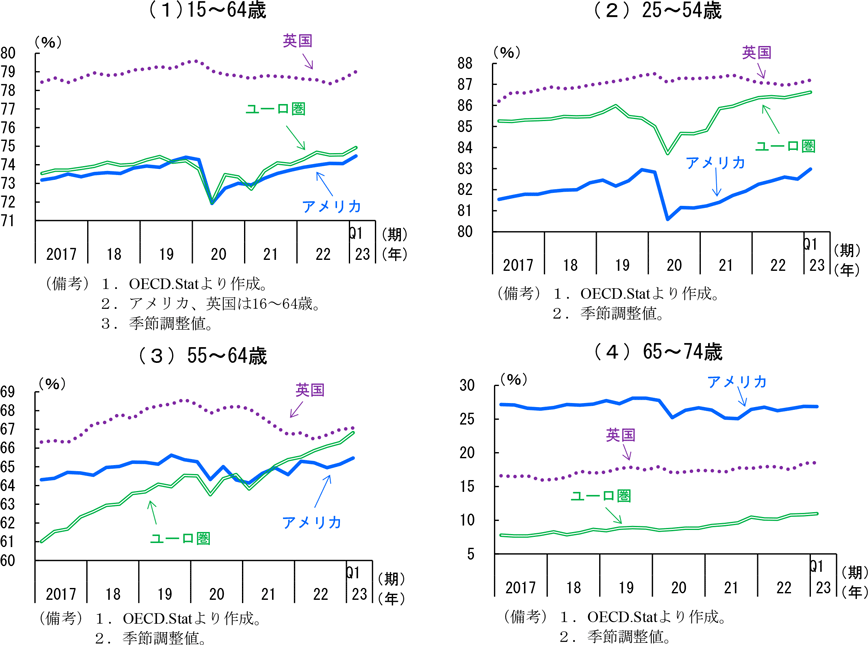
コラム2:労働力人口の変化の要因分解
労働力人口は労働参加率と人口の積で表されることから、労働力人口の変化分は労働参加率を固定した場合の人口変化によるもの(人口要因)と、人口を固定した場合の労働参加率の変化によるもの(参加率要因)に分解できる。これにより感染症拡大及び収束に伴う参加率の変化分のみを抽出できる。
2020年1-3期を基準としてみると、アメリカでは、感染症拡大に伴う労働参加率の低下により2020年4-6月期には約535万人の労働力人口が減少したが、2023年1-3月期までに74歳以下の階層においては参加率要因だけで約555万人増加し、減少分を回復していることが確認できる。また、ユーロ圏においては、74歳以下の階層において参加率要因だけで約822万人増加し、労働力人口の増加が労働参加率の向上のみでほぼ説明できる。一方で英国においては、参加率要因による回復幅は十分ではないものの、減少幅と比較してもその差は小さく、人口要因も考慮すると感染症拡大前の水準はおおむね回復しているといえる。
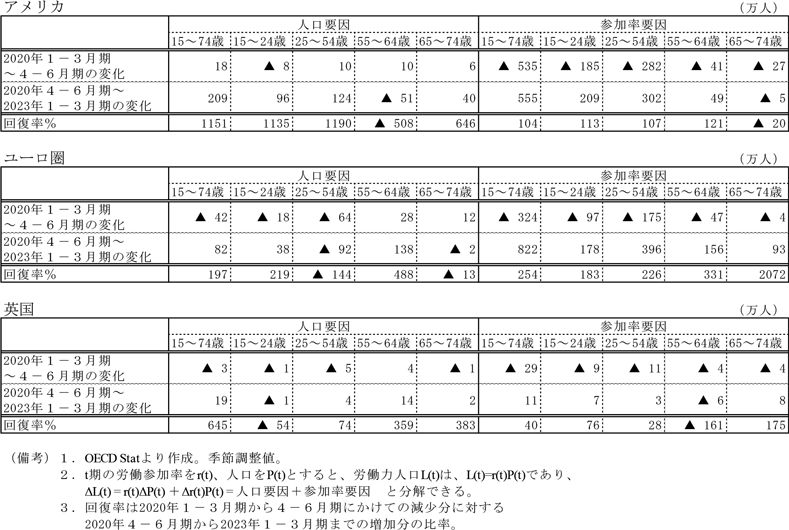
(総じて、女性の労働参加率がより上昇)
次に、生産年齢人口の労働参加率を男女別に分けて、労働供給の回復状況を確認する。各国・地域ともに女性の労働参加率の回復が早い一方で男性の参加率の改善は遅れ、特に英国の男性は経済不活発率の上昇を受けて回復に時間を要している(第1-1-13図)。
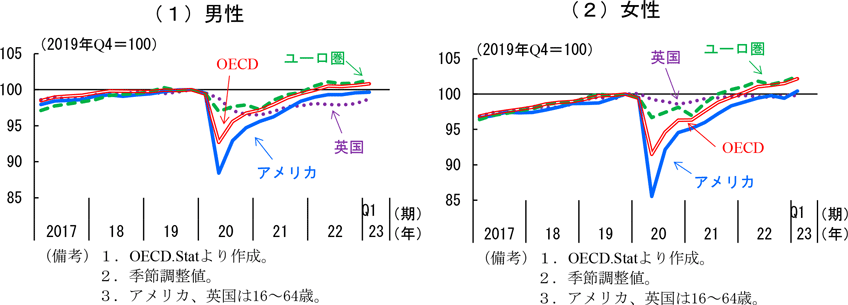
Box.女性の労働参加率の長期的な傾向
女性の労働参加率の動向について長期的に確認すると、ユーロ圏及び英国の女性の労働参加率は上昇傾向である一方で、アメリカは1990年代後半をピークとして、その後は緩やかな低下傾向にあった(図1)。アメリカの大統領経済報告15はこの理由として、行政による子育て支援や医療支援が少ないことを挙げ、公的支援が向上すれば労働参加が促されるとの見解を示している。
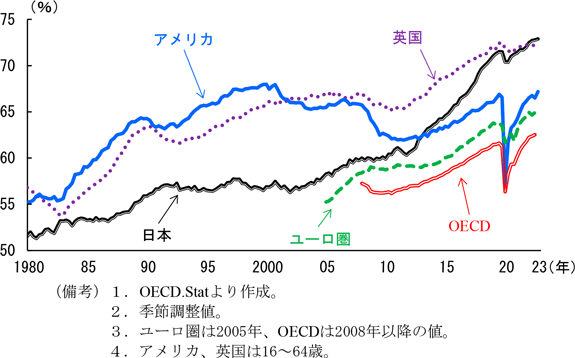
(欧米ともに労働需要は引き続き強く、労働市場は依然引き締まっている)
続いて、経済活動再開に伴う労働需要の強さを求人率(求人数/(求人数+雇用者))の動向から確認する。2020年後半から米欧ともに経済活動の再開等を受けて労働需要が増加したことから求人率が上昇に転じ、2022年前半にかけてアメリカは6.9%、ユーロ圏は3.2%、英国は3.8%と、感染症拡大前(2019年10-12月期)と比べてそれぞれ2.7%ポイント、1.0%ポイント及び1.4%ポイント上昇した。その後、金融引締めが進んだこともあり、求人率は各国ともに緩やかな低下傾向となったものの、2023年1-3月期においては、アメリカは感染症拡大前(同)から1.7%ポイント、ユーロ圏は0.8%ポイント、英国は0.8%ポイント高い水準で推移しており、労働需要の強さが引き続きみられている(第1-1-14図)。
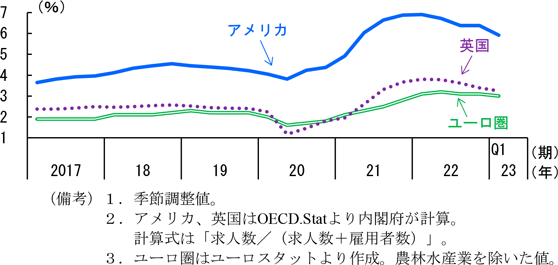
欧米ではこのように、労働供給が感染症拡大以前の水準をおおむね回復する、ないしは増加傾向がみられる中で、労働需要も引き続き旺盛な状況が続いていることから、労働需給は結果として依然として引き締まった状況が続いている。アメリカの失業率は2023年6月は3.6%、ユーロ圏は同年5月は6.5%、英国は同4.0%といずれの国・地域も低水準16で推移している(第1-1-15図)。
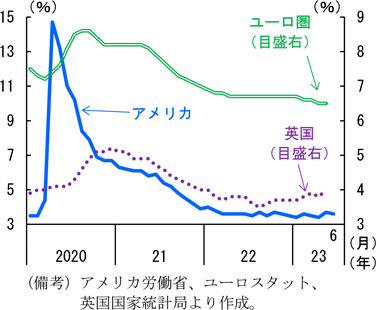
(3)欧米の物価動向
一般的に、労働市場の引締まりは労働コストの上昇を促し、国内に起因する物価の押上げ要因となる。ここでは、こうした労働コストの動向についてみていく。また、それ以外の物価の押上げ要因として、輸入物価の動向も確認する。
(単位労働費用はユーロ圏において米国よりも上昇ペースが加速)
前述のような労働市場の引締まりが物価に与える影響を考察するために、賃金及び労働コストの指標である単位労働費用(実質GDPを一単位生産するために必要な名目総労働費用)の推移をみてみる。
欧米の賃金17の伸び率(前年同期比)は、2010年代後半は各国とも2%台であったが18、感染症拡大後はいずれの国も労働需給の引締まりを受けて伸び率の上昇がみられている(第1-1-16図)。アメリカは、活発な転職も賃金上昇に寄与していることから(2節参照)、伸び率は2022年1-3月期にかけて5.6%まで上昇した後、2023年4-6月期にかけて4.4%まで低下するものの、引き続き高い伸び率となっている。ユーロ圏は2021年7-9月期は2.2%であったが、物価上昇を受けた賃上げも加わり、2023年1-3月期は4.3%まで上昇した。英国は、2021年9-12月期は3.6%であったが、2023年1-3月期には6.8%まで上昇している。
このような賃金上昇を背景に、単位労働費用は2021年半ば以降は各国ともに上昇傾向が続いている。特に2023年1-3月期にかけて、アメリカは実質GDPの成長が続く下、賃金及び名目雇用者報酬の伸びの低下を受けて単位労働費用の上昇ペースが鈍化する一方、ユーロ圏は景気が足踏み状態となる中で賃金及び名目雇用者報酬の伸びが加速したことを受けて、単位労働費用の上昇ペースが加速する動きがみられている(第1-1-17図)。なお、英国においては賃金上昇率が加速しているものの名目雇用者報酬の伸びが横ばいとなっているが、この背景としては前述の労働参加率の回復の遅れ等が考えられる。
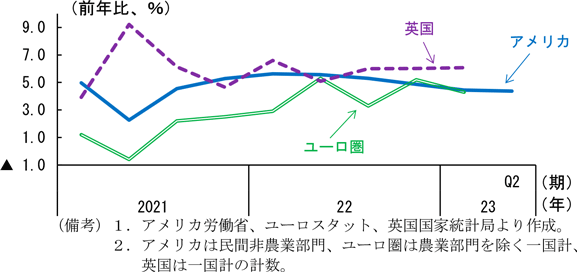
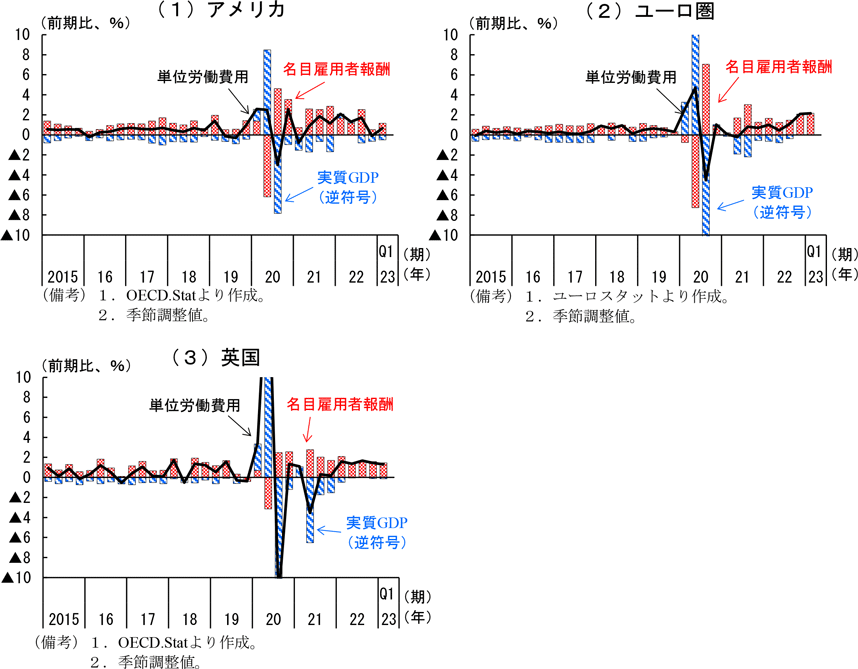
(欧州はアメリカと異なり、実質賃金上昇率が労働生産性の改善を上回る傾向)
次に、実質賃金(時間当たりの一人当たり実質賃金額)と労働生産性(労働時間当たりの実質GDP)に関して、アメリカは相対的に実質賃金の平均上昇率が労働生産性の改善を下回る一方で、欧州各国は実質賃金の平均上昇率が労働生産性を上回る傾向があることが確認できる19(第1-1-18図)。この理由として、欧州においては協定賃金契約のカバー率の高さ等が挙げられている20。なお、物価上昇を受けた賃上げ要求のためのストライキも数多く発生21しており、今後の賃金上昇に与える影響を注視する必要がある。
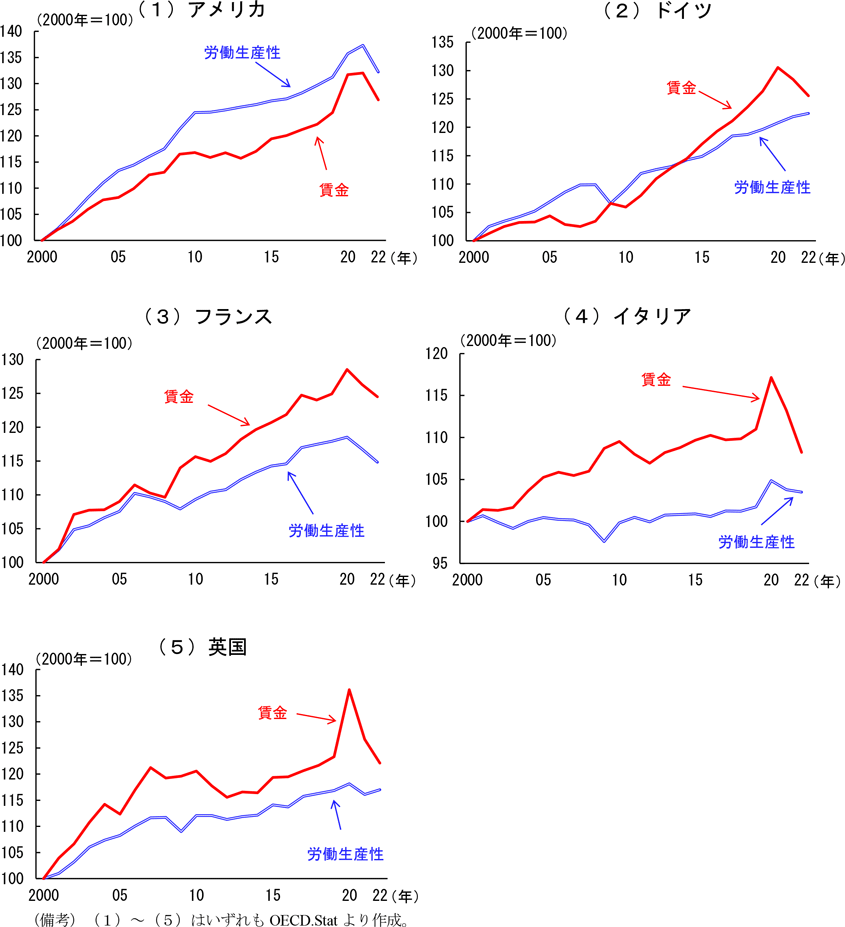
(輸入インフレ圧力は低下し、消費者物価の上昇にも一服感)
国内由来のインフレ要因である賃金が上昇していることを確認したが、次に輸入インフレ圧力についても確認する。財及びサービスの輸入価格(前年比)の動向をみると、2022年年央までは上昇率の加速がみられたが、その後は低下傾向が顕著である(第1-1-19図)。2022年年央までは、感染症拡大後の経済活動の再開に伴う貿易量の増加(第1-3-1図)による国際物流コストの上昇(第1-1-20図)、さらに、2022年になりウクライナ侵略を受けたエネルギー価格高騰が上昇率の加速要因であった。その後は、エネルギー価格の下落及び国際物流コストの低下を受けて、輸入物価は欧米ともに減速基調となり、輸入インフレ圧力は低下した。ただし、エネルギーを輸入に依存する欧州においてはアメリカに比べて輸入インフレ圧力が強い状況が続いている。
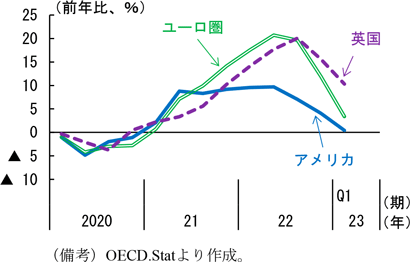
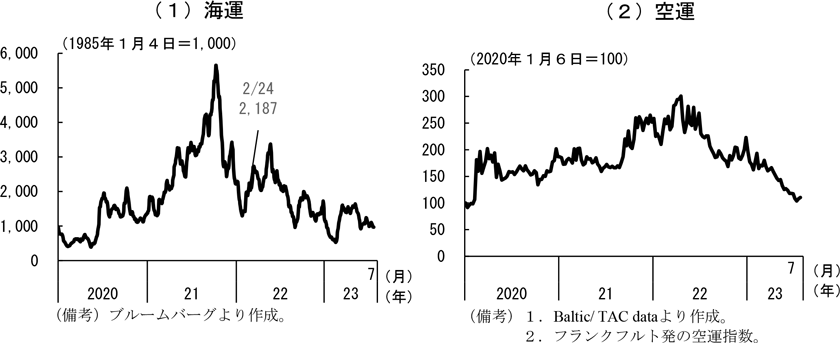
ところで、単位労働費用も輸入物価も、物価上昇の供給側の要因である。OECD (2023)は、GDPデフレーターの要因分解を通じて、欧米の物価上昇の要因として単位労働費用とともに利益マージン率の上昇を指摘している22。以下では、このような利益マージン率の動向、及び前述の輸入インフレ圧力の違いを踏まえて、各国ごとに単位労働費用の動向と物価動向の関係を確認する。
まず、アメリカをみると、財価格の上昇率は2021年4-6月期以降、感染症拡大後の耐久消費財等の財需要拡大の一服感もみられ、減速している(第1-1-21図)。また、住居費を除くその他サービス価格の上昇率は、2023年に入り横ばい傾向となっている(後述のBox参照)。前述の単位労働費用はマクロ全体の動向を示しており、業種ごとの分析は難しいものの、このような財及びその他サービス価格の動向は、単位労働費用の伸びの鈍化とおおむね整合的と考えられる。家賃及び帰属家賃からなる住居費23の上昇率はおおむね横ばいで推移している。このために、アメリカのコア物価指数は2023年に入りおおむね横ばいで推移している。
続いて、ユーロ圏をみると、財及びサービス価格の上昇率はおおむね横ばいとなっているが、単位労働費用の伸びの加速や利益マージン率の上昇傾向を踏まえると財及びサービス価格の上昇率の押し上げ圧力が働いていると考えられる。また、英国においては、財及びサービス価格の上昇率はおおむね横ばいで推移しているが、単位労働費用の上昇率は減速していることから、利益マージン率の上昇が寄与している可能性が考えられる24。さらに、ユーロ圏及び英国における輸入インフレ圧力はアメリカより高いことから、食料品を含めた財を中心に物価上昇率がより高くなる傾向があると考えられる。
このために、財及びサービス価格の上昇率は、各国ともにおおむね横ばいとなる中で、エネルギーの寄与が2022年後半以降に縮小からマイナス基調となり25、2023年6月の欧米の消費者物価上昇率(総合、前年比)は、アメリカ3.0%、ユーロ圏5.5%、及び英国7.9%と、上昇基調に一服感がみられている26。
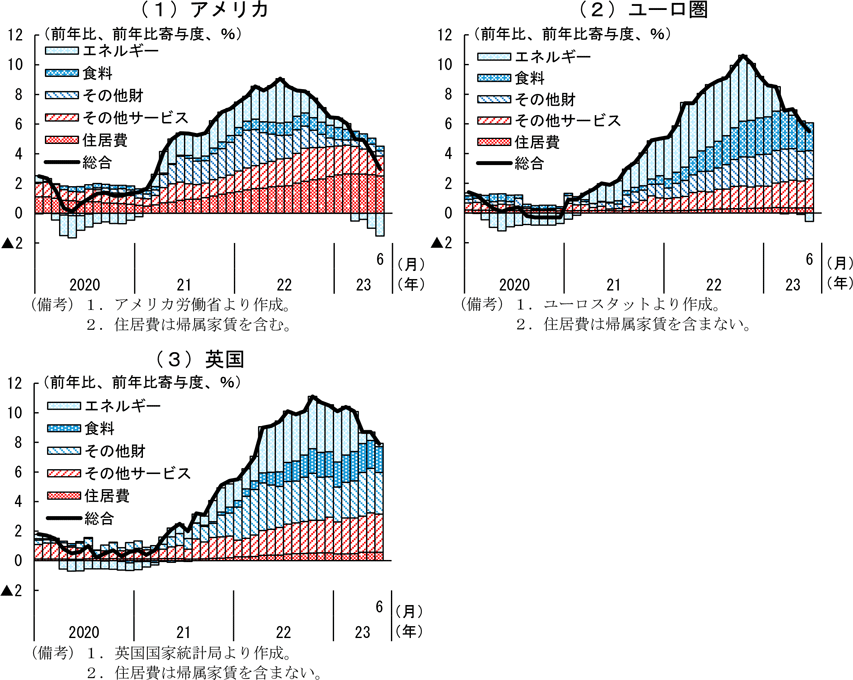
Box.アメリカ消費者物価指数における住居費以外のサービス価格の動向
アメリカの消費者物価指数における住居費以外のサービス価格を更に細かくみてみると、医療サービスは2022年後半から、輸送サービスは2023年に入ってから前年比上昇率が減速傾向であることが確認できる。これは医療サービスについては医療保険料の引下げ28、輸送サービスについては主に原油価格下落を受けた燃料費の低下が寄与しているためである。これら以外の教育・通信及び娯楽サービス、そしてそれ以外のサービスについては上昇率は高水準でおおむね横ばいとなっている(図1)。
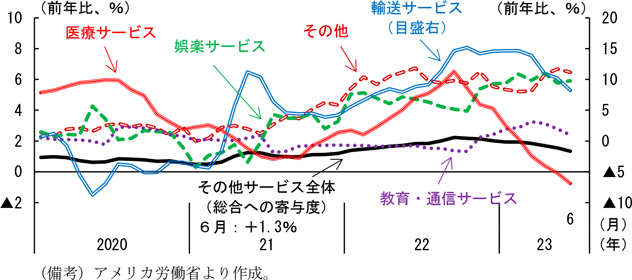
コラム3:国際商品市況
ここでは、原油、天然ガス、小麦の2023年前半の価格動向について概観する。いずれもロシアによるウクライナ侵略以前の水準まで下落して推移している(図1)。
(i)原油
原油価格(WTI)は、2023年初から3月初旬までは、70ドル台半ばを下限、80ドル台前半を上限としたボックス圏内で推移した。需要面では、金融引締め継続に伴う世界景気の減速懸念、中国における景気回復の遅れ等に伴う需要減の動きがみられた。また、供給面では、OPECプラスの減産合意の継続、ロシアによる減産、トルコ・シリア地震による中東地域からの原油供給の先細り懸念等がみられた。
3月中旬には、アメリカにおける銀行の経営破綻等に伴う景気減速への懸念から60ドル台後半へ下落したものの、金融当局の迅速な対応等もあり、同月下旬には70ドル台前半へ上昇した。さらに4月初旬には、OPECプラスの主要産油国による自主的な減産決定を受けて再び80ドル台前半に上昇した。
5月下旬には、アメリカ連邦政府債務上限問題をめぐる懸念等から一時60ドル台後半まで下落した。その後、6月初旬のOPECプラスによる協調減産の延長や、7月中旬のアメリカの金融引締め長期化への懸念の後退等を受けて、70ドル台後半まで上昇した。
(ii)天然ガス
欧州における天然ガスの先物価格(TTF)は、欧州の記録的な暖冬の影響による需要減の影響を大きく受け、2022年末の80ユーロ/メガワット時台後半から、2023年1月に入ると、60ユーロ/メガワット時台後半まで下落した。2月下旬には、地下ガス貯蔵量も高水準となったこと等供給面の緩和もみられたことから、40ユーロ/メガワット時台後半まで下落した。
3月以降は春の気温上昇等による需要減少の影響を受けるとともに、5月中旬までは、地下ガス貯蔵量の増加見込みを受けた供給面の緩和もあり、30ユーロ/メガワット時台前半まで下落した。6月中旬から下旬にかけては、ノルウェーのガス関連施設の定期修繕による供給停止等を受け、30ユーロ/メガワット時台後半まで上昇したものの、7月初旬には、定期修繕が完了したことから20ユーロ/メガワット時台後半まで下落した。
(iii)小麦
小麦価格(シカゴ商品取引所)は、2023年に入ると、ロシア、ウクライナでの収穫増、ロシアによる外貨獲得のための積極的な輸出等による供給増を受け、1月中旬には7ドル/ブッシェル台前半に値を下げた。2月中旬には、ロシアとウクライナの戦闘激化によるウクライナ産の小麦輸出の先行き懸念等から、8ドル/ブッシェル台前半まで上昇した。
その後、3月中旬におけるウクライナ産小麦の輸出再開に関するロシアとの合意(以下、「合意」という。)の再延長、5月末における合意の更新等から5ドル/ブッシェル台後半まで値を下げた。しかしながら、7月中旬における合意の更新停止及びウクライナの穀物輸出拠点(オデーサ港)へのロシアによる攻撃を受け、7ドル/ブッシェル台前半まで値を上げた。
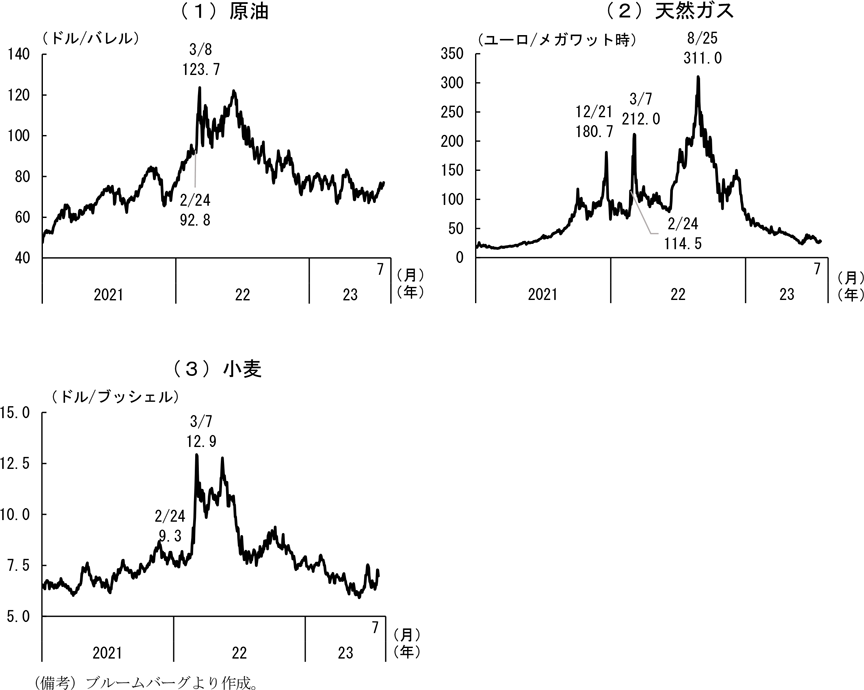
(粘着価格の緩やかな変化が物価の低下を遅らせる)
前述のように消費者物価上昇率(総合、前年比)については一服感がみられてきたが、価格改定頻度が物価上昇率に与える影響をみるために、柔軟価格指数、粘着価格指数29の推移を確認する(第1-1-22図)。
価格改定頻度の高い品目で構成される柔軟価格指数(平均的な価格改定頻度は2.6か月)の上昇率は、エネルギー、新車及び中古車・トラック価格等の下落を受けて2022年半ば以降急速に低下し、2023年6月には上昇率が前年比▲2.6%まで低下した。一方で、価格改定頻度の低い品目で構成される主にサービスが含まれる粘着価格指数(平均的な価格改定頻度は10.7か月)は上昇率が2022年年末頃からおおむね横ばい傾向で推移し、2023年6月の上昇率は前年比5.8%と高止まりしている(第1-1-23図)。
緩やかにしか変化しない粘着価格指数が、消費者物価指数の上昇率の低下を遅らせており、物価上昇率の引下げのために持続的な金融引締めが必要になっていると考えられる。
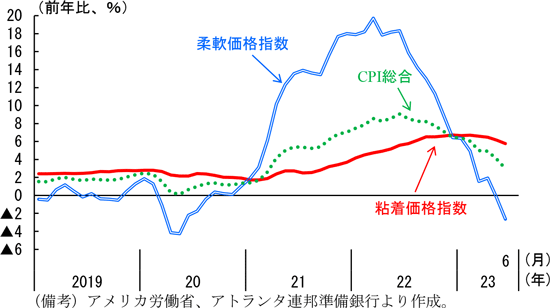
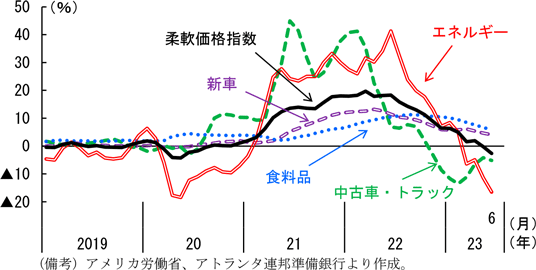
2.物価上昇を受けた金融引締めの進展と金融市場の動向
本項では、財・サービス価格の上昇を受けた欧米の金融引締めの進展内容を確認するとともに、長期金利の動向や金融市場における不確実性について確認する。
(欧米中銀は財・サービス価格の上昇を受けて引締めを継続)
欧米中銀は、財・サービス価格の上昇を受けて金融引締めを継続している(第1-1-24図、第1-1-25表)。
アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)は、2022年3月の連邦公開市場委員会(FOMC)においてフェデラル・ファンド・レート(FF金利)の誘導目標範囲を0.25%ポイント引き上げて以降、同年6月から11月までは0.75%ポイントの大幅な引上げを行い、その後、引上げ幅を縮小させながらも2023年7月までに累計で5.25%ポイント引き上げた。同月のFOMCでは、金融引締めの効果は遅れを伴って現れることが強調されており、その効果を慎重に測った上で、最新のデータに基づいて、その都度利上げの要否を検討していく姿勢が示された。今後の利上げ予定については、6月のFOMC参加者の見通しによれば、更なる利上げが適切とされており、年内に追加で1回(0.25%ポイント)の利上げが行われる可能性が示唆されている。
欧州中央銀行(ECB)は、2022年7月の理事会において主要リファイナンスオペ金利を0.50%ポイント引き上げて以降、同年9月及び11月は0.75%ポイントの引上げを行い、その後2023年7月までに累計で4.25%ポイント引き上げた。また、2023年7月の理事会においては、金融機関がユーロシステムに預ける最低準備金の付利を、9月20日以降は0%に引き下げることを決定した。今後の利上げの予定については、ECB理事会において、経済・金融データによる物価上昇の見通し、基調的な物価変動、金融政策の波及状況に基づいて会合ごとに決定するとしている。
また、イングランド銀行(BOE)は、2021年12月の金融政策委員会においてバンク・レートを0.15%ポイント引き上げて以降、2022年11月には0.75%ポイントの引上げを行い、その後2023年8月までに累計で5.15%ポイント引き上げた。今後の利上げの予定については、8月の金融政策委員会において、物価上昇率を中期的に持続的に2%の目標まで戻すために、政策金利が十分な期間、制限的であることを約束するとしている。
さらに、量的引締めに向けた保有資産の削減については、ECBは2023年3月より資産購入プログラム(APP)における償還された元本の再投資を一部停止し、7月以降は再投資を全て停止することを決定した(第1-1-25表)。
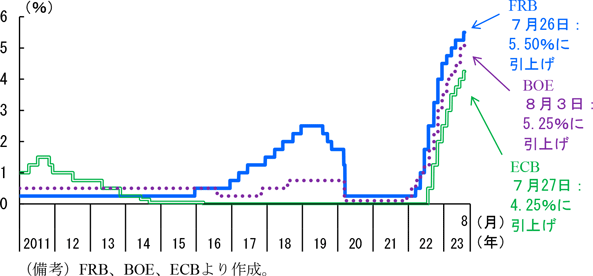
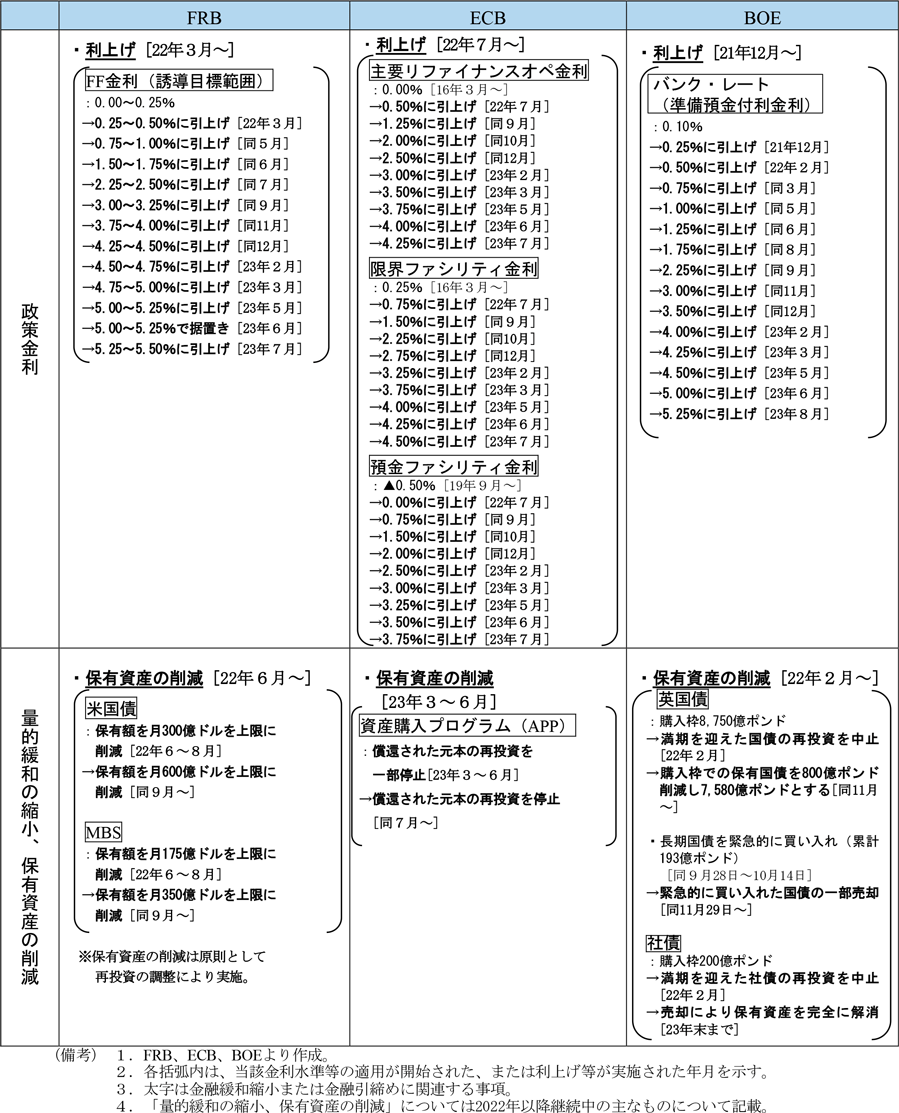
(長期金利は欧州では上昇傾向で推移)
このような政策金利の引上げや保有資産の削減を受けて、長期金利は2022年初から上昇傾向となっていたが、夏から10月にかけて欧米中銀がそろって政策金利を大幅に引き上げたこと等から、2022年10月頃には長期金利が3%ポイント以上上昇した(第1-1-26図)。その後、2023年3月には米欧における2件の銀行経営破綻及び銀行買収事案を受けて安全資産である国債に資金が流入したことを受けて金利は急落した。7月にかけては、アメリカやドイツにおいては各中銀の利上げ局面が終盤に近付きつつあるとの思惑から、長期金利は横ばい傾向で推移している。一方英国においては、高止まりしている物価指標や堅調な雇用指標を受けて、BOEの利上げ継続期待が徐々に高まる中、長期金利は2022年9月のトラス・ショック30以来の水準まで上昇している。
なお、金利上昇が銀行経営に与える影響については、銀行の資金調達コストは上昇するものの、一般的には市場金利の上昇ペースよりも緩やかであることから、銀行の純利ざやは通常は増加することとなる。欧米の金融監督当局は、今般の急速な金利引上げ局面においても、債券の評価損は生じるものの銀行部門全体としてはこのような収益性確保のメカニズムは維持されているとしている31。
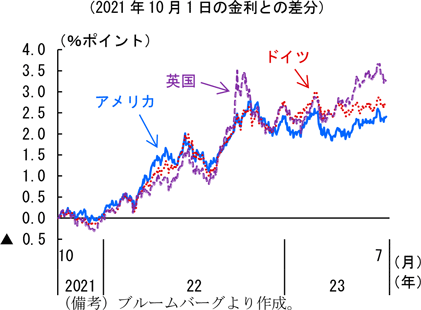
(金融市場における不確実性は高い状態が続く)
アメリカにおいては、株式市場における不確実性を表す指標(VIX指数)及び国債市場における不確実性を表す指標(MOVE指数)が、銀行経営破綻を受けてともに急上昇した(第1-1-27図)。とりわけMOVE指数は一時、2008年のリーマンショック以来となる水準まで急伸するなど、金融市場は大きく動揺した。7月にかけては両指数ともに低下傾向にあるものの、今後の物価上昇率についての見通しや銀行経営破綻の実体経済への影響、それらを踏まえたFRBの金融政策決定等についての不確実性が引き続き高いとみられることから、MOVE指数はFRBによる金融引締め開始前と比べて高い水準で推移している。
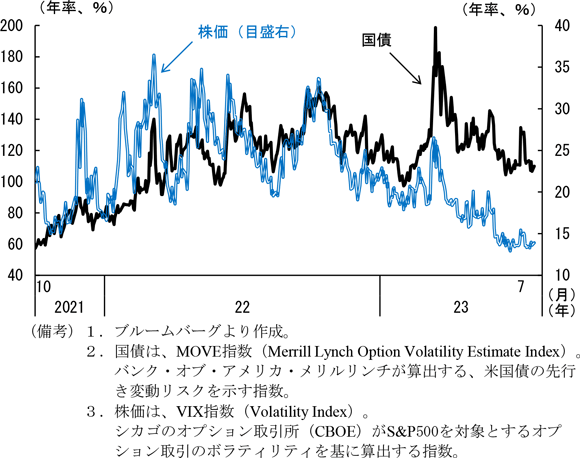
コラム4:アメリカの企業債務
アメリカの民間部門の債務を家計と企業に分けてみると、その推移は大きく異なる。家計債務は2008年のリーマンショックを機に圧縮が進み、対GDP比率は低下傾向にある。一方で、企業債務の対GDP比率はリーマンショック時以上の水準まで上昇している(図1)。
企業債務は、負債証券(主に社債)と借入に大別される。2023年1-3月期時点での残高は、社債が約6.9兆ドル、借入が約5.1兆ドルと、規模としては社債が借入を上回る。ここで、借入について「米国預金取扱機関(米銀)からの借入」と「米銀以外からの借入」に分けた上で、社債と借入の推移を確認する。社債発行は、感染症拡大期に発行ペースが加速したものの、長期的にはおおむね同じペースでの増加傾向をたどっている。一方の借入については、2010年代後半以降、米銀以外からの借入が米銀からの借入を大幅に上回って増加していることが分かる(図2)。
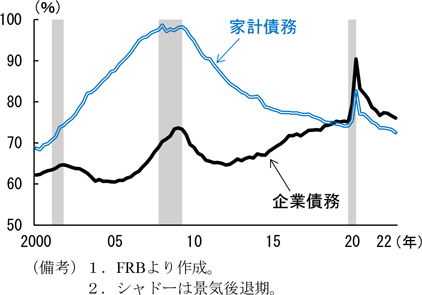
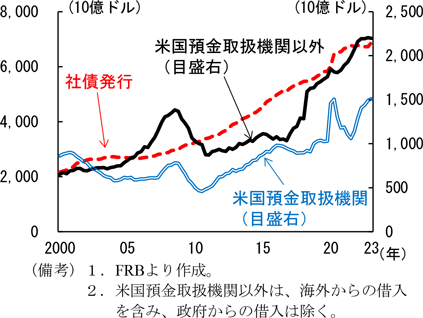
米銀以外からの借入についてその内訳をみると、金融会社(貸金業者)や生保等その他金融機関からの借入が2010年代以降はおおむね横ばいで推移する中、証券化商品を通じたアメリカ国内及び海外からの借入が2010年代後半から増加していることが分かる(図3)。
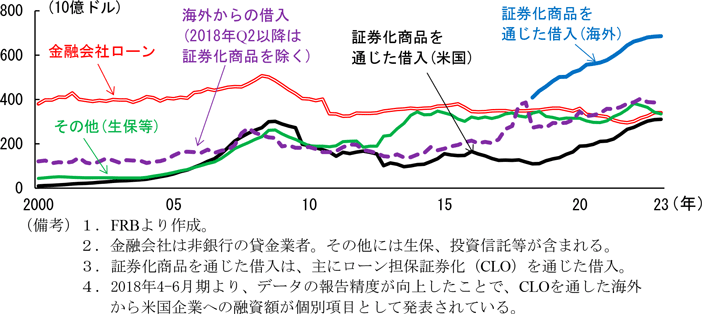
証券化商品を通じた借入とは、主にローン担保証券(CLO)32を通した借入を指し、現状は、投資適格級未満の企業の実質的な債権者が、証券化商品を通して米国内及び海外の多様な投資家へと広がっている状況にあるといえる。特に比較的高リスクの商品の保有先は、資本要件やリスク管理において銀行ほど厳しい規制の課せられていない33ノンバンクに偏っていると指摘されている(図4)。
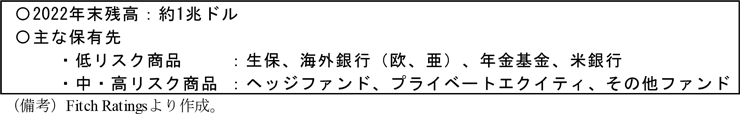
このために、これまでの金融引締めによって、今後、借入企業の業績が悪化し、CLOの価格が急落する場合は、CLOを保有するノンバンクの経営悪化や、それに伴う資産売却等で、金融資本市場が過度に変動する可能性も考えられる。アメリカの企業債務の動向には引き続き注視が必要である。
3.金融引締めが進む中での銀行破綻や金融機関の買収
本項では、欧米における急速な金融引締めが進む中、2023年3月以降に発生したアメリカの銀行破綻及びその影響を受けた欧州における金融機関の買収の概要及び影響について整理する。
(1)米銀の経営破綻
2023年3月、アメリカの地方銀行であるシリコンバレー銀行(SVB)が破綻した。その後、これを契機とした金融不安を受けて同月にシグネチャー銀行(SBNY)が、5月にはファースト・リパブリック銀行(FRC)が経営破綻した(第1-1-28表、第1-1-29表)。特にSVBの破綻は、商業銀行の破綻規模としては2008年9月のワシントン・ミューチュアル銀行が破綻して以来の規模34であり、その9日後には、欧州でも大手投資銀行クレディ・スイスが買収されるなど、金融不安は市場に連鎖的な影響を与えた。以下では、破綻の背景や原因、金融資本市場に与えた影響等について分析していく。
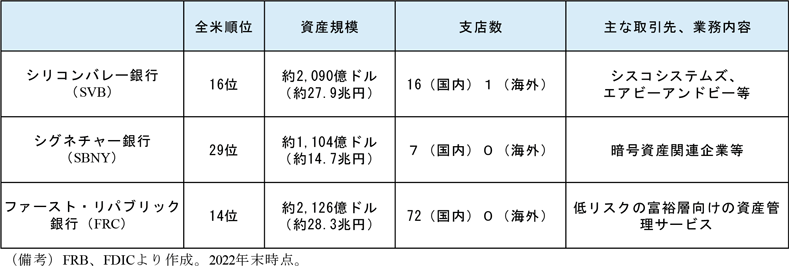
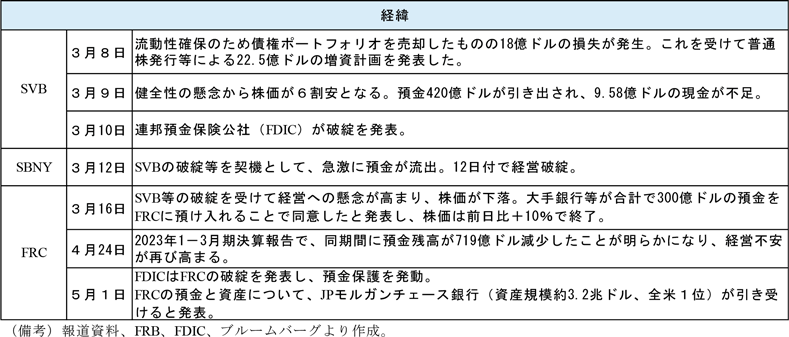
(今回はSNSを通じた取り付け騒ぎによるデジタル・バンク・ラン)
今回の銀行破綻の直接の原因は、取り付け騒ぎにより急速に銀行預金が流出したことであるが、その取り付け騒ぎがSNS上で発生し、預金引出がネットバンキングを通じて瞬時に行われたことが過去の取り付け騒ぎとは異なる点である(いわゆる「デジタル・バンク・ラン」)。以下ではSNSと株価の関係から、SNSが銀行破綻に与える影響について考察していく。SVBやSBNYに続いて破綻したFRCについてみてみると、TwitterでFRCに関するネガティブなツイートが増加する中で3月10日にかけて株価が急落したことが分かる(第1-1-30図)。大手銀行等が救済措置を公表した3月16日にはポジティブなツイートが増加し、一時的に株価が上昇した場面もあったが、その後4月24日に預金残高が急減したことが明らかになると、再びネガティブなツイートが急増し、株価も下落した。過去の大規模な銀行破綻の前例と比べても、今回の銀行破綻では状況が急速に悪化したといえる。FRCは、わずか1日で株価が前日比▲60%程度下落したが、2008年9月に経営破綻した商業銀行であるワシントン・ミューチュアル・バンクは、9月19日を境に株価が急落し始めてから▲60%程度下落するまでに6日を要している(第1-1-31図)。このようにSNSを通じた情報拡散は、金融システムの安定にとって新たなリスク要因となっている。
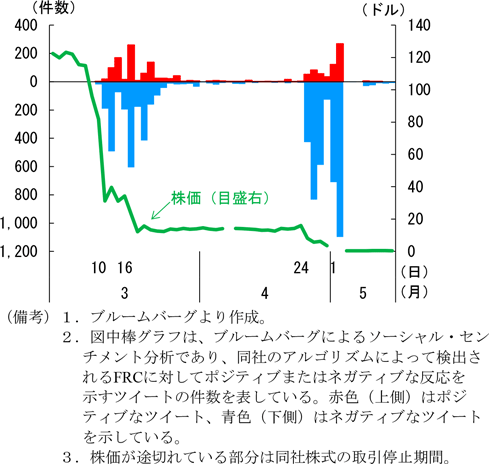
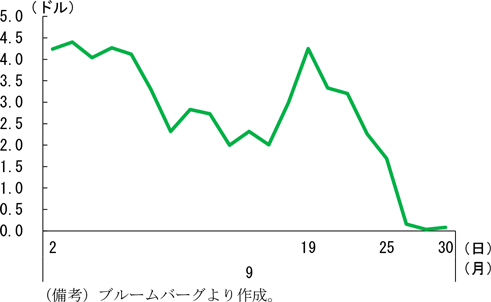
(銀行破綻は経営上の問題が大きいが、規制緩和の影響で含み損の表面化に遅れも)
今回の事案においては、銀行経営を悪化させた根本的な原因はマクロ経済環境や金融システム全体の問題というよりも、破綻した個別銀行固有の問題であるとの見方が多い(第1-1-32表)。金融引締めが始まって以降、今回破綻した銀行に限らず、銀行保有債の含み損は増加傾向にあったため(第1-1-33図)、これに対するリスクヘッジは米銀全体の共通の課題となっていたが、今回破綻したSVBとSBNYの2行ではそのリスク管理を怠っていた。また、アメリカでは感染症拡大下で銀行預金が急増したことを背景に預金保護の上限を超える預金(無保険預金)が増加し(第1-1-34図)、流動性リスクの管理も米銀共通の課題となっていた。しかし、大口の無保険預金に依存していた2行では流動性リスク管理が不足していたことも破綻の原因になった。
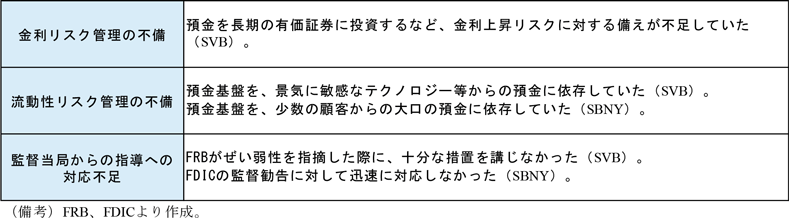
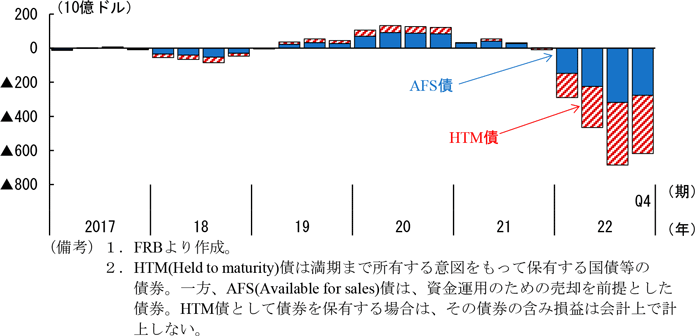
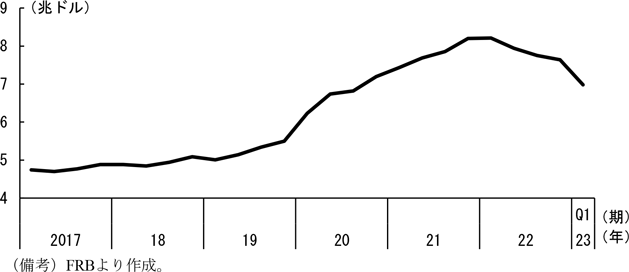
また、規制緩和も影響を与えていた。2008年の金融危機を受けて、アメリカではオバマ政権下でドッド=フランク法の制定をはじめ、金融規制が強化されてきた。その後、トランプ政権下では、経済成長・規制緩和・消費者保護法(ドッド=フランク法改正法)の導入をはじめとする、主に中小銀行への規制を緩和する方針へと舵を切っていた。一般的な規制緩和のデメリットとして、規制対象(銀行)が抱えるリスクの把握が困難になることが挙げられるが、FRBが4月28日に公表したSVBの経営破綻に関する報告書でも「ドッド=フランク法改正法に伴うFRBのテーラリング・アプローチ35と監督方針の変化は、効果的な監督を阻害した」としている。トランプ政権下で進んだ中小銀行への規制緩和は、今回の銀行破綻の遠因になったとの見方である。
トランプ政権下で緩和された規制の一つに、自己資本比率の算出についての項目があり、自己資本比率の算出の際にその他包括利益累計額(保有資産の含み損益)の反映が義務ではなくなっている。これにより、引き続き反映が義務付けられる一部の大手銀行36以外では、AFS債37に含み損が生じた場合でも、必ずしも自己資本比率の低下として表面化するわけではなくなった。結果として、現在のように金利が急速に上昇し、保有債券の含み損が拡大している局面では、大手銀行以外ではその含み損を加味したときに自己資本がどれだけ毀損しているかを把握しづらくなっている。実際に、破綻直前期のSVBは流動性確保のために資産売却を行ったことで、金利上昇で膨れ上がっていたAFS債の含み損を実現し、信用不安が加速する一因となった。
前述のFRB報告書に添えられたバーFRB金融監督担当副議長の書簡では、今回の一連の事案を受け、主に資産規模1,000億ドル以上の銀行に対して、AFS債の含み損益を資本要件に反映させることの検討等を含む、複数の金融規制の強化方針が示されている。金融規制の強化に当たっては、野党(共和党)からの反発も想定されるところ、今後の動向に注意が必要である。
コラム5:アメリカの銀行監督体制
アメリカの銀行監督体制は、二元銀行制度を取っており、連邦政府(国)と州政府(地方)にわたる二重の規制・監督機関が存在することから、銀行によって監督当局が異なる38。今回の場合、SVBはFRBとCA州金融当局が、SBNYはFDICとNY州金融当局が主に監督しており、両者の違いは表1のとおりである。両者の監督権限は基本的に同じであるが、FDICは他の監督当局が監督する銀行にも監督権限を行使することができる(バック・アップ権限)。また、FRBが監督する銀行は、銀行検査を州当局による検査で代用することができるが、FDICが監督する銀行については必ずFDICの検査官による検査が必要であるなど、検査方法にも違いがみられる。
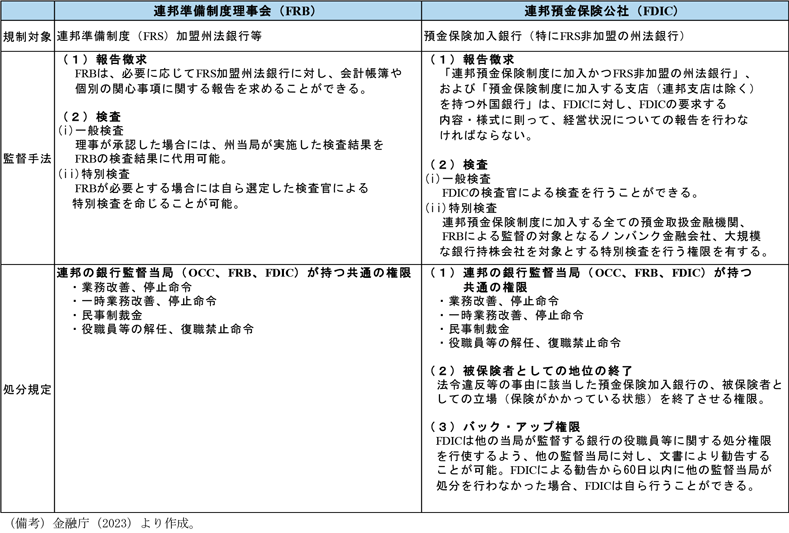
(金融資本市場においては主に中小銀行への影響がみられた)
今回の銀行破綻は、金融資本市場にも一定程度の影響を与えた。まず、今回の銀行破綻の直接的な原因となった預金流出による流動性不足に対応するために、FRBは従来から行ってきた金融機関に対する流動性供給の枠組みである連銀貸出に加え、バンク・ターム・ファンディング・プログラム(BTFP)39を緊急措置として講じた。BTFPは連銀貸出等と比べて低金利の資金調達手段であったため、利用額は急増した(第1-1-35図)。
株式市場への影響は、全体としては軽微であったものの、中小銀行(地方銀行)の株価は大きく下落し、5月に入ってからもFRCが破綻したこともあり、再び大きく下落しており、市場からの厳しい評価が続いている(第1-1-36図)。
中小銀行を中心に金融不安が生じたことは預金残高の推移からも確認できる。アメリカの銀行預金残高は、今回の銀行破綻が生じる前から下落傾向であったが40、SVB破綻後には中小銀行の預金残高が急減している。一方で、大手銀行の預金の減少ペースには足踏みがみられるとともに、SVB破綻後に前週比で増加している週もあることから、中小銀行から大手銀行への預金移動が一定程度行われたと考えられる(第1-1-37図)。
中小銀行の預金の流出先として、大手銀行の預金よりも動きが目立ったのはマネー・マーケット・ファンド(MMF)である。MMFは、個人や機関投資家、事業会社等から集めた資金を、短期国債やレポ、CP等、主に短期金融市場にて安全性の高い運用を行う投資信託の一種であり、銀行預金に代わる運用方法としてアメリカ国内で広く活用されている。今般の銀行破綻以前から政策金利引上げ等を受けて利回りは上昇傾向となり残高は増加傾向にあったが、SVB破綻後は残高は急増している(第1-1-38図、第1-1-39図)。このことから、中小銀行の預金は主にMMFへ流出したと考えられる。
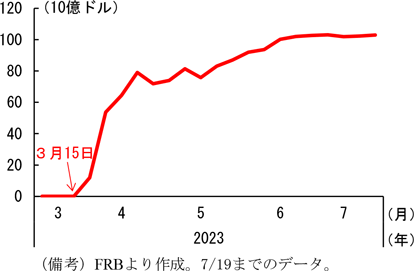
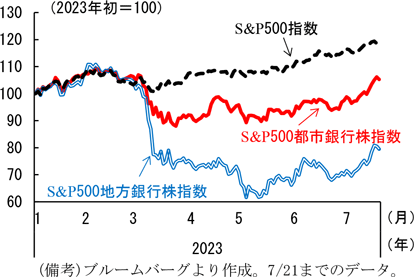
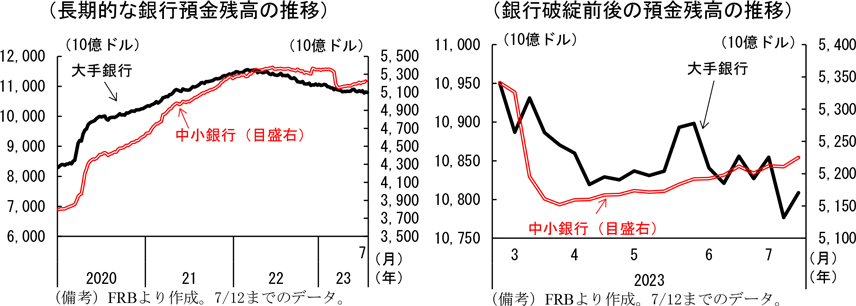
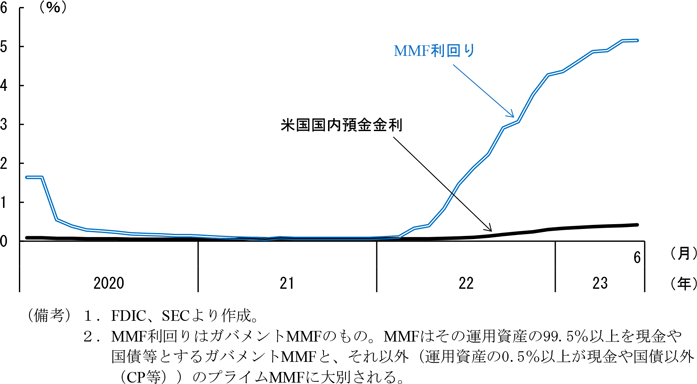
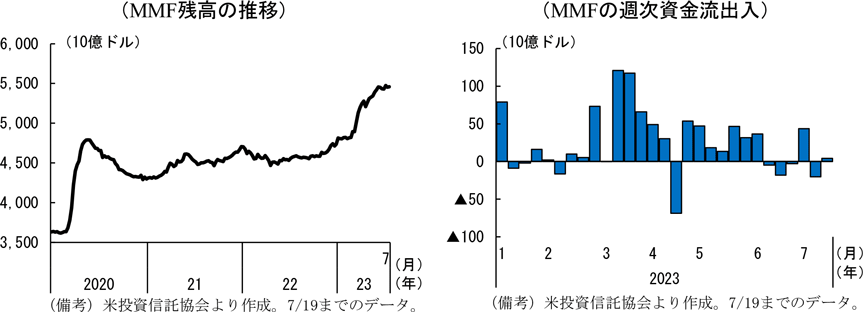
(銀行貸出の厳格化により、経済活動が鈍化する可能性)
SVBの破綻直後は、銀行の貸出残高は、個人消費の緩やかな増加に伴い消費者向け貸出が上昇傾向を維持する一方、企業向け貸出や不動産ローンが減少した。消費者向け貸出はその後も上昇傾向を維持したが、6月下旬以降は低下傾向に転じた。不動産ローンは4月中旬頃にはSVB破綻前の水準に回復した後に5月下旬まで上昇傾向で推移したものの、6月上旬以降は横ばい傾向となっている。企業向け貸出は更に減少しており、銀行貸出全体は伸び悩んでいる(第1-1-40図)。大・中堅企業向けの商工業ローン貸出基準をみても、金融引締めにより2022年から銀行貸出基準の厳格化が進む中、2023年4-6月期にかけて更なる厳格化が進んだことが確認できる(第1-1-41図)。
このような貸出基準の厳格化を背景に、2022年以降は倒産件数は緩やかながらも上昇傾向がみられている(第1-1-42図)。銀行が貸出態度を更に厳格化し、貸出を減らすことは、更なる倒産件数の増加等を招き、経済活動を鈍化させる可能性があるところ、今般の銀行破綻を受けた信用収縮の動きについては今後とも注視する必要がある。
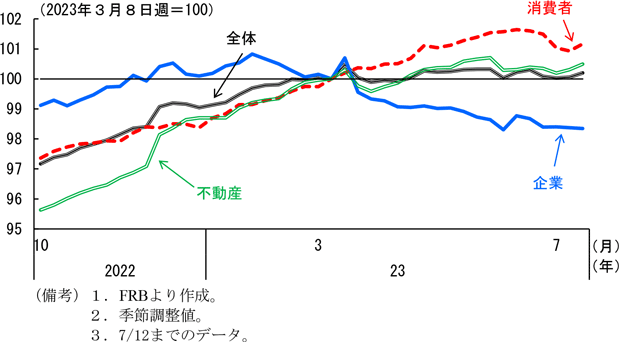
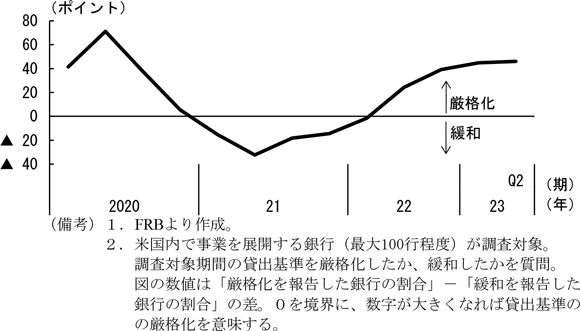
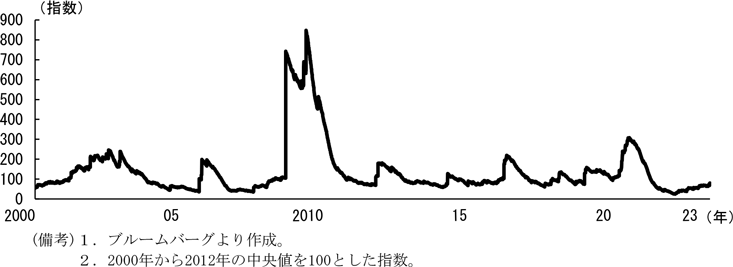
(2)クレディ・スイスの買収とAT1債の無価値化
(クレディ・スイス買収は永久劣後債の無価値化を随伴)
前述のアメリカの銀行破綻はスイスの大手金融機関クレディ・スイス41(CS)の経営にも影響を与えることとなった。
CSについては、内部管理体制の不備42と投資銀行部門の不調43が近年指摘されていた。また、2023年3月14日に監査法人からも内部統制の有効性について「不適正」とする監査意見が表明されていた(第1-1-43表)。
3月15日、アメリカの銀行破綻を受けて金融不安が高まる中、筆頭株主のサウジ・ナショナル・バンクが追加出資をしないとの報道を契機に、欧州株式市場で同社株価が急落するとともに、5年物クレジット・デフォルト・スワップは過去最高を更新した。これを受け同日、スイス国立銀行(中央銀行)及びスイス金融市場監査局(FINMA)はCSに対し「必要があれば流動性を供給する」と支援を表明した。
3月19日、スイスの大手金融機関UBS44がCSを総額30億スイスフラン(約5千億円45)で買収すると発表し、スイス国立銀行は同買収支援のため最大1億スイス・フラン(約14.9兆円)の流動性支援ローンを供給すると発表した。
さらに、スイス政府はUBSに対し、CS買収に関連して発生し得る損失をカバーするため90億スイス・フラン(約1.4兆円)の保証を付与するとともに、同社が発行した永久劣後債(Additional Tier1債(AT1債))160億スイス・フラン(約2.4兆円)をゼロ評価(無価値化)すると発表した。
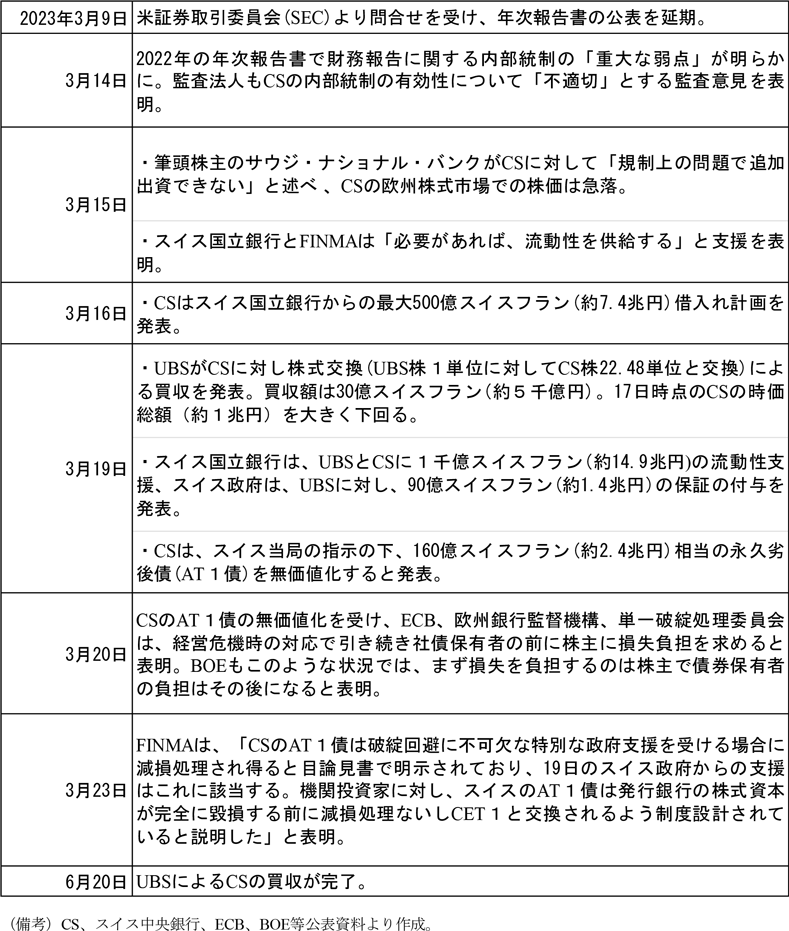
(バーゼルI I I46においてはAT1債は損失吸収手法との位置付け)
ここで、現行の銀行規制であるバーゼルIIIにおけるAT1債の位置付けについて整理する(第1-1-44図)。バーゼルIIIでは、株式等のリスク・アセットに対する銀行の自己資本の比率を8%以上とする規制が課されている。また、国際統一基準行については追加的に最大5%の資本の上積みが求められ、さらにグローバルなシステム上重要な金融機関(G-SIBs)と認定された銀行は追加的に最大2.5%の資本の上積みが求められる47。CSについては、G-SIBsに位置付けられていた。
自己資本には、「普通株式等Tier1資本(CET1:Common Equity Tier1)」が4.5%、国際統一基準行には、資本保全バッファー2.5%が上乗せされ、景気後退時の取り崩し余地の確保を目的としたカウンターシクリカル・バッファーとして最大2.5%、G-SIBsと認定された銀行は追加資本賦課(HLA:Higer Loss Absorbency。より高い損失吸収を持たせるためG-SIBsに対して求められる上乗せ資本。)として追加的に最大2.5%の資本の上積みが求められる48。
また、自己資本には銀行が実質的に破綻認定されたタイミングで元本削減を行うための資本であるバーゼルIII適格「Tier2債」を含めることが認められている。さらに、債権の性質として見た場合、CET1よりは損失吸収力が弱いものの、Tier2債に比べると破綻に至る前に十分な損失吸収がなされる債権として「その他Tier1債(AT1:Additional Tier1)」を含めることが認められている。
このAT1債の特徴49としては、満期がない債券であること(永久性)、仮に銀行が破綻した場合に預金者へ損失が及ばないように秩序ある破綻をもたらすこと(劣後性)が挙げられる。通常の破綻であれば、まず株式の価値が毀損され次いで劣後債の価値が毀損された結果、預金者の保護が図られる。このため、AT1債は預金者保護のためのバッファーとしての意義を有するとともに、普通社債よりも金利が高い一方でリスクは株式よりも低い安全商品と考えられ、低金利環境下で積極的に購入されてきた。
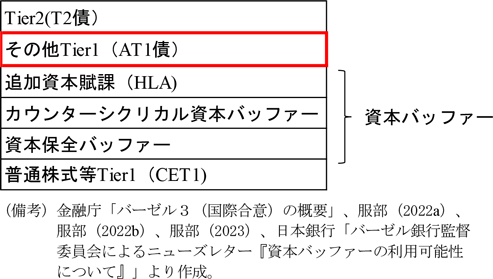
(市場参加者からの反対意見もみられるAT1債の無価値化)
CSのAT1債のゼロ評価(無価値化)発表を受けAT1債の取引市場は混乱し、ECB及び欧州銀行監督機構、単一破綻処理委員会は、経営危機時の対応で引き続き社債保有者の前に株主に損失負担を求めると表明した。また、BOEは、市場の動揺を抑えるため、このような状況でまず損失を負担するのは株主で、債券保有者はその後になると表明した。
一方でFINMAは、「CSのAT1債は、破綻回避に不可欠な特別な政府支援を受ける場合に減損処理され得ると目論見書で明示されており、19日のスイス政府からの支援はこれに該当する。また、スイスのAT1債は、発行銀行の株式資本が完全に毀損する前に、減損処理ないしCET1と交換されるよう制度設計されている旨を機関投資家に対し説明している。」と表明した。
このようなFINMAの説明に対しては反対も多く、4月末にはスイス連邦行政裁判所は、CSのAT1債を保有する投資家によるFINMAに対する訴訟が、これまでに数百件に達していることを明らかにしている。CSはG-SIBsに指定されており、その買収及び手続については今後の各国の金融監督にも影響を与えると考えられるところ、国際的な理解を得る努力が引き続き求められる。
4.感染症収束後の中国の景気動向
欧米では、共通課題となっている物価上昇に対して金利引上げを講じているが、両者の回復力には実質的な購買力の違いによる差がみられた。中国はどうだろうか。以下では、中国の景気動向について確認する。
(景気はサービス業を中心に持ち直しの動き)
2022年末に広がった感染症の収束を受け、2023年1-3月期の成長率は前年同期比4.5%とプラス幅が拡大した(第1-1-45図)。内訳は、最終消費の寄与が3.0%ポイント、資本形成の寄与が1.6%ポイント、純輸出が▲0.1%ポイントとなり、外需の弱さが続く中で、国内では繰越需要の発現もあり内需を中心に成長率が2022年10-12月期よりも上昇した。4-6月期は前年同期比6.3%となり、持ち直しの動きが続いている(内訳は、最終消費5.3%ポイント、資本形成1.2%ポイント、純輸出▲1.1%ポイント)。ただし、前年4~5月に上海ロックダウンの影響があった点には留意が必要である。
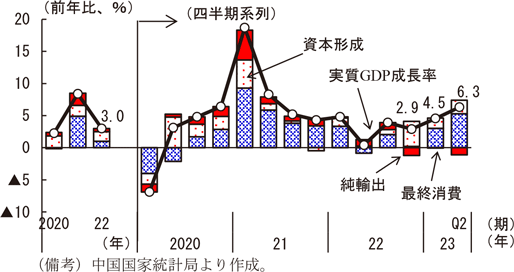
景気の持ち直しの動きは、外食や旅行をはじめとしたサービス業を中心に進んでおり、4月のサービス業生産は前年同月比で13.5%、鉱工業生産も同5.6%と伸び率の上昇が続いた(第1-1-46図)。ただし、これらの値は、前年4~5月が上海ロックダウンの影響で著しく低下した影響を含んでいる。この影響を除くため、2年前同月比(年率換算)をみると、サービス業生産は4月は3.2%、鉱工業生産は同1.3%となる。サービス業生産は堅調に持ち直しているものの、鉱工業生産は、外需が伸び悩む(後述)中で、回復のペースは緩やかなものにとどまった。その後も両指標は緩やかな改善傾向が続いている(6月の2年前同月比は、鉱工業生産は4.1%、サービス業生産は4.0%)。
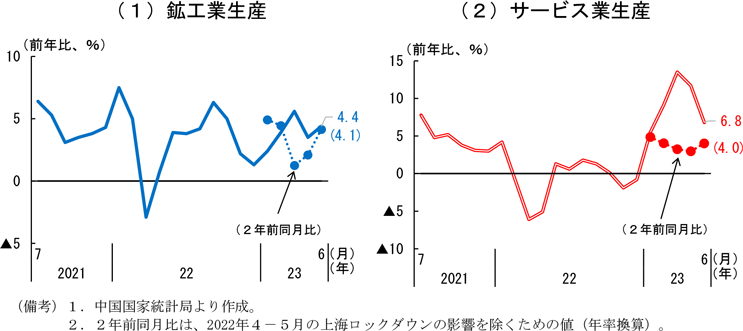
Box.中国衛生当局は感染収束を宣言
中国では、2022年11月から感染症対策の段階的な緩和を開始し、2023年1月には感染症分類を引き下げ、いわゆるゼロコロナ政策を終了した50。2022年冬季の感染症再拡大期には、PCR検査の非義務化を受けて受検者数が急減したために日次の感染者数データの発表が取りやめられ、2023年2月からは、自発的なPCR検査における陽性者数、発熱外来受診者数等の感染症関連指標が公表されることとなった(表1)。各指標は2022年12月末から2023年1月初旬がピークとなり、2月6日時点では大幅に減少しており、4月27日時点まで低水準での推移が続いている。中国衛生当局は、「昨年末からの感染拡大は基本的に収束した」と宣言するとともに(2月28日)、2022年12月から2023年2月の間に国内人口の82%以上が感染したとの推計値を発表した(4月28日)。
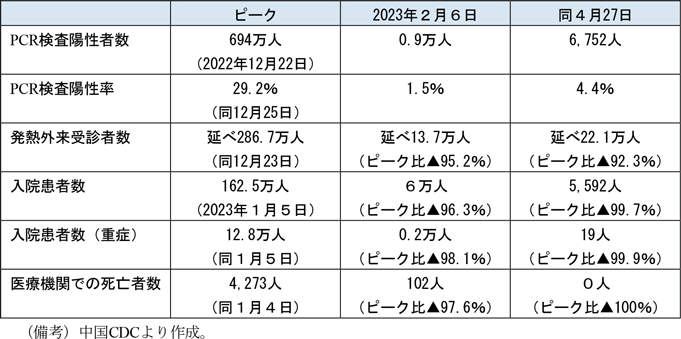
(個人消費はサービスを中心に持ち直すが、財消費は弱い)
サービスを中心に進んだ個人消費の持ち直しの動きは、小売総額(名目)の内訳である飲食サービスでも確認できる(第1-1-47図(1))。財については、社会経済活動の正常化を受けて、衣類等一部の品目については高い伸び率となった51(第1-1-47図(2))。他方、感染症収束に伴う繰越需要の発現の影響が低い財の伸び率は低く、特に家電等の住宅関連財の伸び率は不動産市場が軟調であることも受けて(後述)、低調に推移している52。
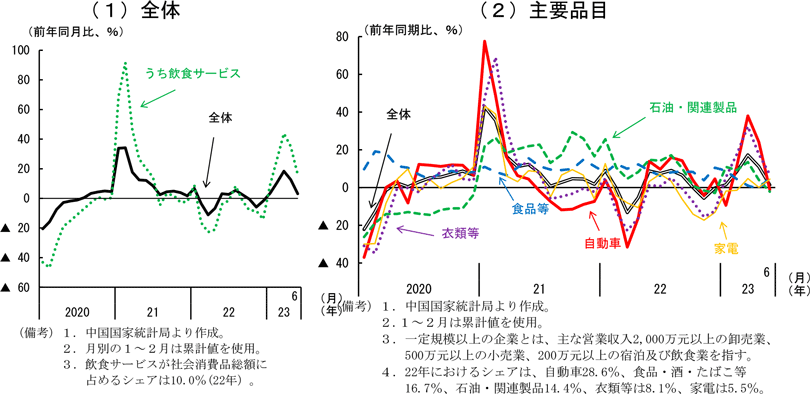
なお、自動車については、半導体不足が緩和し供給が改善する中で、2022年末に一律の自動車減税や補助金が終了することを受けて、同年後半にかけて駆け込み需要が発生し、2023年年初にはその反動減がみられた(第1-1-48図)。その後は、新たな環境基準の導入53に向けた在庫調整のために大幅な値下げ販売が実施されたことから、販売台数には増加がみられている。しかしながら自動車業界54は、自動車の需要はまだ完全には回復しておらず、過度な販促に対して消費者の様子見が続いていると指摘している55。
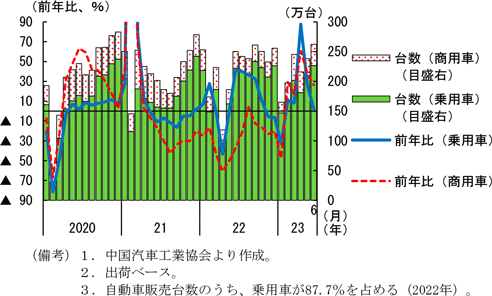
このように財消費の回復力が弱いことを受けて、中国政府は、消費回復を促進する方針を打ち出している。2022年12月の中央経済工作会議において、国内需要の拡大に注力する方針を示した。さらに2023年3月の政府活動報告では、自動車や家電等単価の高い「大型消費」の安定化を重視する方針が打ち出された。こうした方針を踏まえ、内需の回復、拡大を図るため累次の消費喚起策が示されている(第1-1-49表)。具体的には2022年12月以降に40以上の省区市で消費券が発行され、広東省等においては自動車購入補助が実施されるとともに、湖北省においては小口融資制度が新設されている。
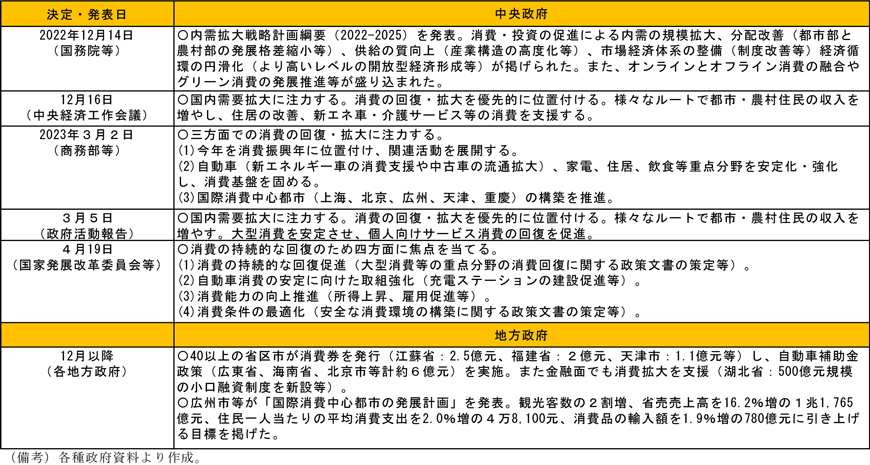
(感染症拡大以降は所得が伸び悩む一方で貯蓄が増加)
財消費の回復力が弱い背景としては、2020年以降の累次の感染症拡大の後遺症として、所得の伸び悩みと貯蓄率の上昇、すなわち消費性向の低下もある。
所得の動向をみると、一人当たりの実質可処分所得は2022年は前年比2.9%、2023年1-3月期は同3.8%、4-6月期も同5.8%と、感染症拡大前の上昇率(年平均7.1%56)と比べ低い伸び率にとどまっている57(第1-1-50図)。
貯蓄率をみると、2022年以降は上昇基調となっており(第1-1-51図)、また家計の預金額も右肩上がりで増加している(第1-1-51図)。この背景としては、中国人民銀行の調査58によると、2020年の感染症拡大以降、より多く貯蓄する意向の預金者が増加基調となっており、2022年10-12月期には61.8%と2002年の調査開始以来最も高い値になったことが挙げられる(第1-1-53図)。このために家計の消費性向は、2022年には2020年と同程度まで低下しており、2023年上半期も感染症拡大前の2019年を下回る水準となっている(第1-1-54図)。
実質可処分所得が伸び悩み、所得面からの下支えが弱い中で貯蓄率が上昇し、サービス消費は感染症収束に伴い持ち直しているものの、財消費の回復力は弱められていることから、個人消費の自律的な回復にはまだ至っていないと考えられる。中国政府は消費喚起策を打ち出しているが、これが呼び水となり貯蓄率の引下げを伴う消費拡大につながり、景気の自律的な回復に向かうことができるか、引き続き注視が必要である。
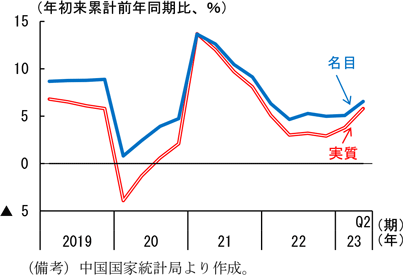
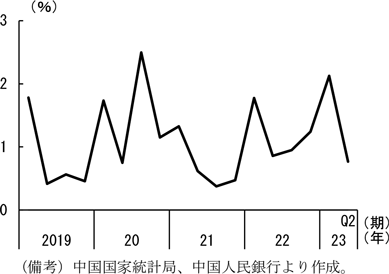
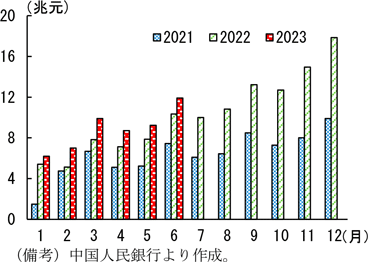
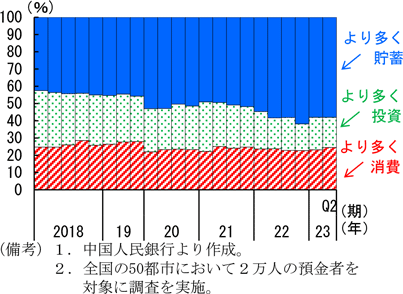
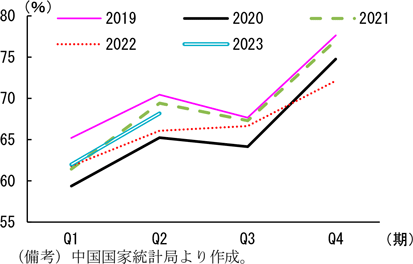
(輸出は持ち直しの動きの後停滞)
中国の財輸出額59は、2022年10月に前年比でマイナスに転じて以降、2023年3月にプラス転換したが、5月以降は改めてマイナスとなり、停滞がみられている(第1-1-55図(1))。数量ベースでは、2022年ほど力強くはないものの、2023年入り後に持ち直しの動きがみられた(第1-1-55図(2))。主要品目の動向を金額ベースでみると、世界的に半導体やパソコンの需要減速がみられる中で、年末年始にかけて電子集積回路やパソコン等は前年を下回って低調に推移したが、2023年年初からは、前年の反動もあり伸び率のマイナス幅は縮小している(第1-1-56図(1))。
財輸入額は、2022年は弱い動きが続いていたが、内需の減少等を受けて、2022年11月以降は減少傾向が顕著になっている(第1-1-55図(1))。数量ベースでも2023年は低水準が続いている(第1-1-55図(2))。主要品目の動向を金額ベースでみると、電子集積回路は2022年5月以来、前年比のマイナス幅が拡大している(第1-1-56図(2))。こうした状況は、世界的な需要減速のほか、米国による対中半導体規制の強化も影響しているとみられる60。また、原油については、価格の下落を背景に2022年の年央以降、伸びは低下が続いている。
なお、近年中国では、中間財から最終消費財までを国内で生産する内製化が進んでおり、加工貿易(再輸出)用の輸入の比率は低下している一方、国内消費用の一般貿易の比率は高まっている(第1-1-57図)61。こうしたことから、従前に比べ、内需不足による輸入停滞がより顕著にみられるようになっていると考えられる。
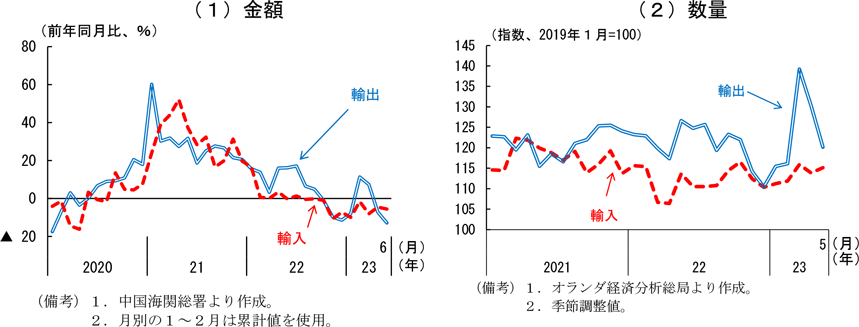
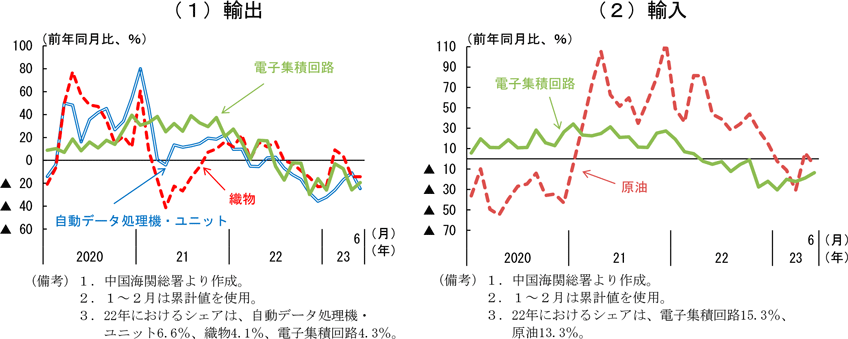
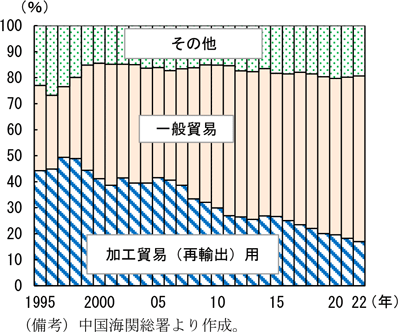
(政策支援があるものの、不動産市況は軟調な動き)
中国では、不動産ディベロッパーの資金繰り問題が長引く中、2022年11月からの累次の不動産市場支援策の実施を受けて62、住宅価格は、地方都市(3級都市63)も含めて前月比プラスで推移し好転がみられているが、その伸び率は徐々に低下している(第1-1-58図)。不動産販売面積は、繰越需要が1-3月期に集中的に発現したことからマイナス幅が顕著に縮小したものの、4月以降は再びマイナス幅が拡大しており、市況は軟調な動きとなっている(第1-1-59図)。
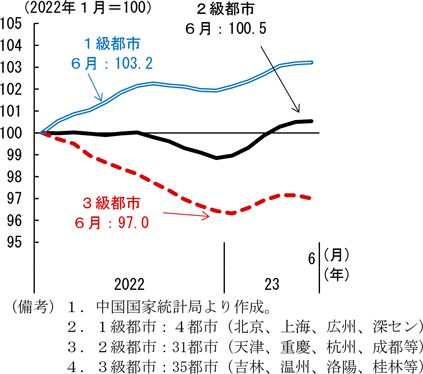
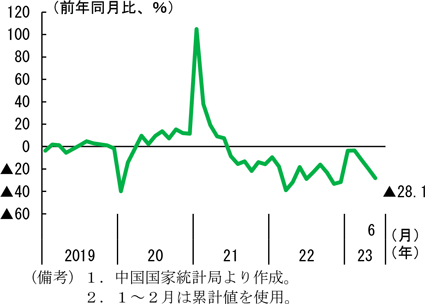
需要回復が遅れる中、不動産開発投資のマイナス幅も拡大に転じている(第1-1-60図)。こうした中で、不動産関連融資残高は前年比のプラス幅の縮小が続いている(第1-1-61図)。内訳をみると、不動産開発向け貸出には持ち直しの動きがみられる64ものの、住宅ローン向け貸出は2023年1-3月期に前年比▲0.2%と減少に転じており、引き続き需要の弱さが確認できる。
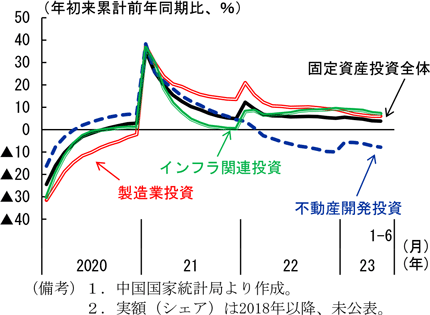
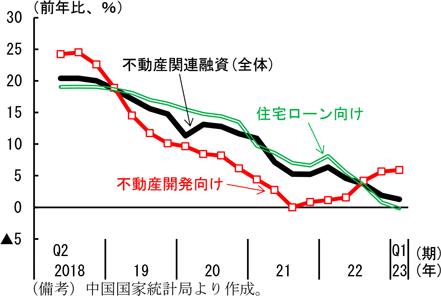
住宅需要の伸び悩みは、関連する小売や生産にも影響を及ぼしている。住宅関連財(建材・内装、家具)の小売は2023年初頭に前年比でプラス転換したが、3月からは再び弱い動きとなっている(第1-1-62図)。生産面でも、家具や建材は前年比マイナスでの推移が続いている(第1-1-63図)。小売・生産ともに全体では持ち直しの動きがみられているものの、住宅関連部門が足かせとなっている。
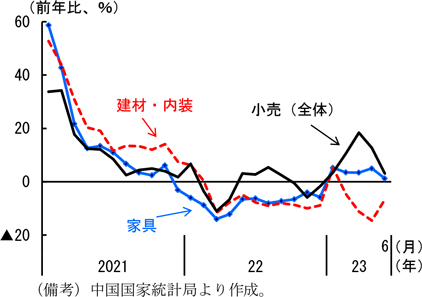
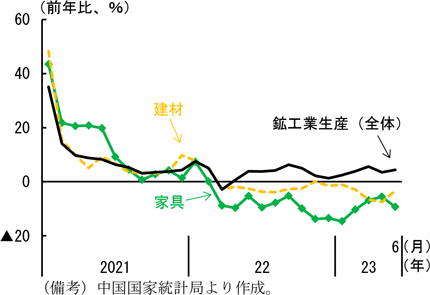
なお、中国の不動産セクターは、関連部門も含めてGDPの3割相当とされ、経済全体への影響も大きい。2022年11月以降の不動産市場支援策の効果の息切れがみられる中で、不動産セクターにおける過剰債務問題の構造的な解決には至っておらず65、追加支援策も含め、今後の動向に注視が必要である。
(経済・金融の安定を重点方針に掲げた2023年の全人代)
2023年の全国人民代表大会(全人代66)では、政府活動報告において、同年の成長率目標を「5.0%前後」と設定した。成長率目標は、2022年の成長率が感染症の影響で3.0%にとどまったことでベースが低いことを踏まえると、やや保守的な水準に設定されている。また、経済政策の重点事項では、消費の回復、拡大を優先課題に位置付け、重大経済金融リスクの防止・解消に努めることとしている67(第1-1-64表)。
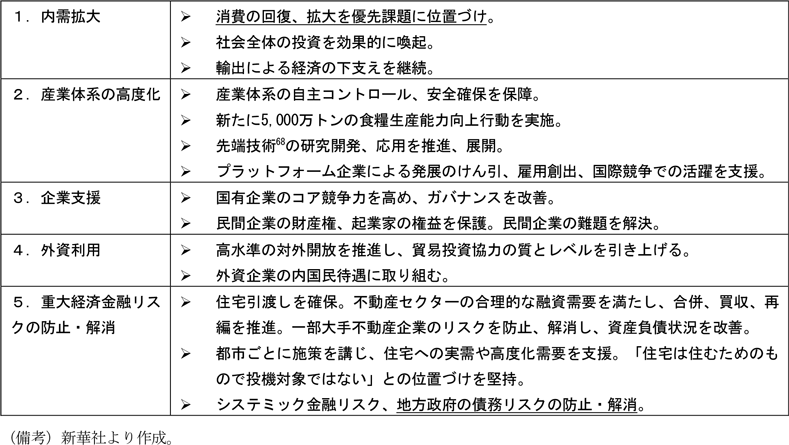
また、政府活動報告において、金融政策については「穏健な金融政策は的確で強力なものにする」「人民元為替相場の合理的な均衡水準での堅調な推移を保つ」との方針を示している。これを受け中国人民銀行は、2023年3月の全人代閉幕後速やかに、預金準備率の引下げを発表した(第1-1-65図)69。さらに同年6月には、事実上の政策金利と位置付けられる中期貸出ファシリティ(MLF)金利70の引下げを発表し、これに連動して市中銀行の最優遇貸出金利(LPR)71も低下した。感染収束後の景気回復のペースが緩やかなものにとどまる中で、金融面からの景気の下支えが図られている。
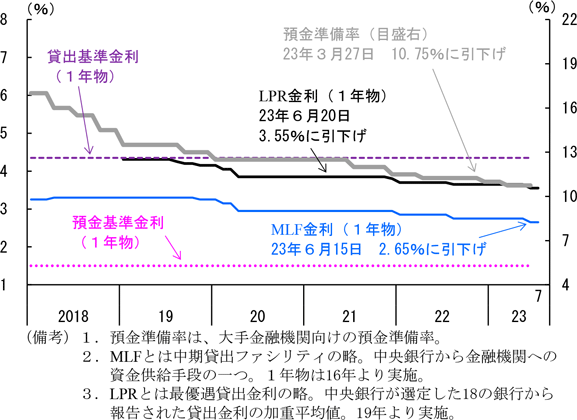
(地方財政の健全性に問題がある中、減税規模は縮小)
2023年の政府活動報告によると、2022年までの5年間の累計減税額は5.4兆元に上り、2022年には減税規模は過去最大となった(第1-1-66図)。財政部は、2023年の新規の税金・費用の減免額は1.2兆元としており、2022年の規模からは縮小がみられる。背景には、感染症収束を受けた経済活動の正常化に合わせた政策の正常化という側面に加え、地方財政のひっ迫問題があるとみられる(1章2節2項参照)。本年の政策の重点事項においても「地方政府の債務リスクの防止・解消」が掲げられている。
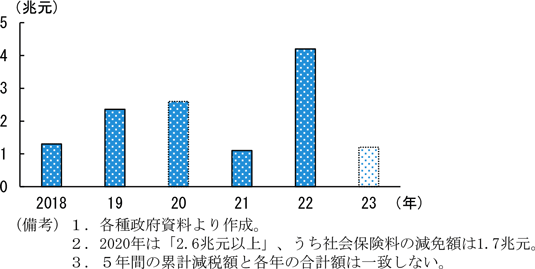
(今後も金融政策面からの支援が続く可能性)
中国では2020年以来、感染症の一時的な収束後(2020年6月、2022年6月)にはV字回復がみられており、2023年上旬にも感染収束を受けての力強い回復が期待されたが、4月以降の経済指標では、外需の弱さの影響もあり、繰越需要が一巡した後の持続的な需要72が不足する状況となっている。当面はサービス業を中心とした持ち直しの動きが続くとみられるものの、貯蓄率の上昇がみられることから、消費の回復には不確実性が伴っており、また、不動産企業の過剰債務問題を始めとした構造的問題の解決にも更なる期間を要するとみられ、不動産市場及び関連部門の停滞が回復の足かせとなり得る。
このような問題に対処するための政策支援の財源にも不安を抱えることから(1章2節2項参照)、金融政策面での下支えが続けられる可能性があるが73、年後半にかけ回復力を高めることができるか、引き続き注視が必要である。
また、本指摘の論拠となったGrigoli and Sandri (2022)では、ドイツの100万個以上の信用口座から得られる日次取引データを用いて、金融引締めは裁量財との代替効果により食料等の必需品消費を緩やかに増加させ、またその影響は高所得世帯により強く表れることを確認している。

