第2章 ポストコロナに向けたデジタル化(第2節)
第2節 デジタル化と経済成長
デジタル技術の急速な進歩は、経済に様々な可能性をもたらしている。こうしたデジタル技術は製造業や小売業等の生産性を高めるとともに、次々に新たな財やサービスを生み出し、消費や企業の設備投資増加につながる成長の源泉と考えられる。加えて、コロナ禍での経済活動制限や人々の行動様式の変化に伴い、デジタル技術の重要性が従来に増して高まっている。本節では、こうしたデジタル技術を生産活動のベースとするICT製造業やICTサービス業(定義は後述)の動向を調べるとともに、非ICT部門も含めた経済活動全般へのデジタル技術の活用の動向についても概観し、デジタル技術の活用が進むことと経済成長との関わりを考える。
1.ICT部門の成長と研究開発投資82の動向
(1)国レベルで見たICT部門の成長と研究開発投資
(EU27か国及び英国の動向)
ICT部門83は成長のけん引役の一つとされている。EU27か国及び英国(以降、EU28か国84)のICT部門の付加価値額の伸びを経済全体の付加価値額の伸びと比較するため、95年を基準(100)とした付加価値額の動向を19年までの期間についてみると、ICT部門の付加価値額の伸びは経済全体の付加価値額の伸びをはるかに上回っている(第2-2-1図(1))。加えて、1人当たりでみた労働生産性の伸びも、リーマンショックまではICT部門の方が顕著に上回って推移している(第2-2-1図(2))。指数で比較すると、19年時点でICT部門の付加価値額が280であるのに対し、経済全体の付加価値額は152にとどまっている。95年以降の指数の推移をみると、ICT部門の付加価値額・労働生産性ともに、リーマンショック時にやや低下し、以降上昇ペースは緩やかになっている。水準が落ち込んだ09年を100として比較すると、付加価値額では全体の117に対してICT部門は138とリーマンショック以降の期間に限ってみても高い水準だが、労働生産性では順に110、111とほぼ同水準となり、ICT部門の伸びは経済全体の伸びと同程度となっている。
95年以降のICT部門の付加価値額や労働生産性の高い伸びの背景には、研究開発投資の増加がある可能性が考えられる。EUのレポート85によれば、民間部門の研究開発投資支出の伸びは95年以降10年代半ばまでは、ICT部門の伸びが全体の伸びを上回って推移してきた。それと同時に、ICT部門の付加価値額の伸びも高かったため、研究開発投資支出の動向を付加価値額当たりでみると、経済全体では上昇傾向にあるのに対し、ICT部門ではむしろ低下傾向にある。言い換えれば、ICT部門では、95年時点と比較して研究開発投資1単位当たりの付加価値額が高まっているとみることもできる。
なお、ICT部門のうちICT製造業とICTサービス業86の動向をみると、EU28か国では研究開発投資支出はICTサービス業で大きく上昇しているのに対し、ICT製造業では2000年以降緩やかな低下傾向にあり、対照的な動きとなっている(第2-2-2図)。
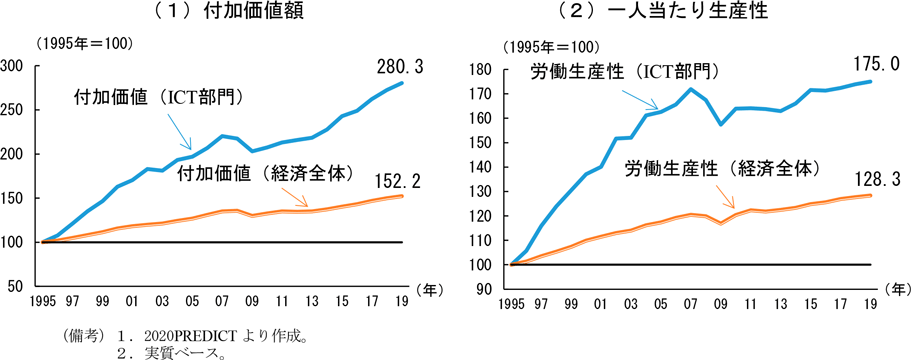
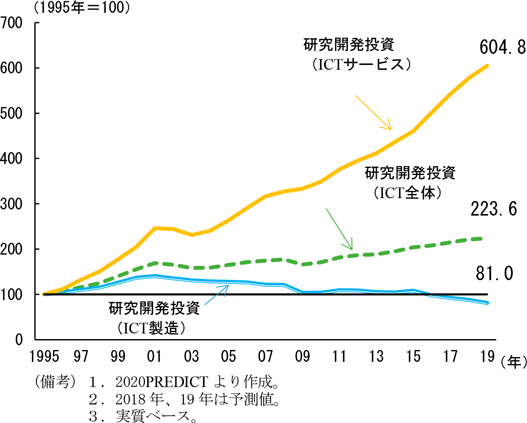
(国際比較)
次に、ICT部門の付加価値額対研究開発投資比率を17年時点で国際比較すると、EUは5.1%、日本は8.1%であるが、これに対し韓国20.2%、台湾11.9%、アメリカ10.6%と2桁の水準となっており、特に韓国・台湾で研究開発投資の比率が高いことが指摘できる(第2-2-3図(1))。これらの国々での民間部門の研究開発投資の特徴を見ると、韓国・台湾ともにICT部門の中でもICT製造業(特に電子部品)のシェアが高い。また、台湾ではICT部門の研究開発投資額が民間の研究開発投資額の75%程度を占めている。
研究開発投資は生産性を高め、プラスの波及効果をもたらすことが指摘されている。主要国やEU加盟国でのICT部門の民間研究開発投資額(対GDP比)と同部門の労働生産性の関係をみると、両者の間には弱い正の相関がみられ、アメリカや北欧諸国の一部では研究開発投資が活発で労働生産性も高い(第2-2-3図(2))。なお、これらの国々でのICT部門の労働生産性成長率(06~17年の年率)をみると、伸びが高いのはアイルランドや一部の東欧諸国及びアジア諸国であり、民間研究開発投資額(対GDP比)との関係は明らかではない(第2-2-3図(3))。
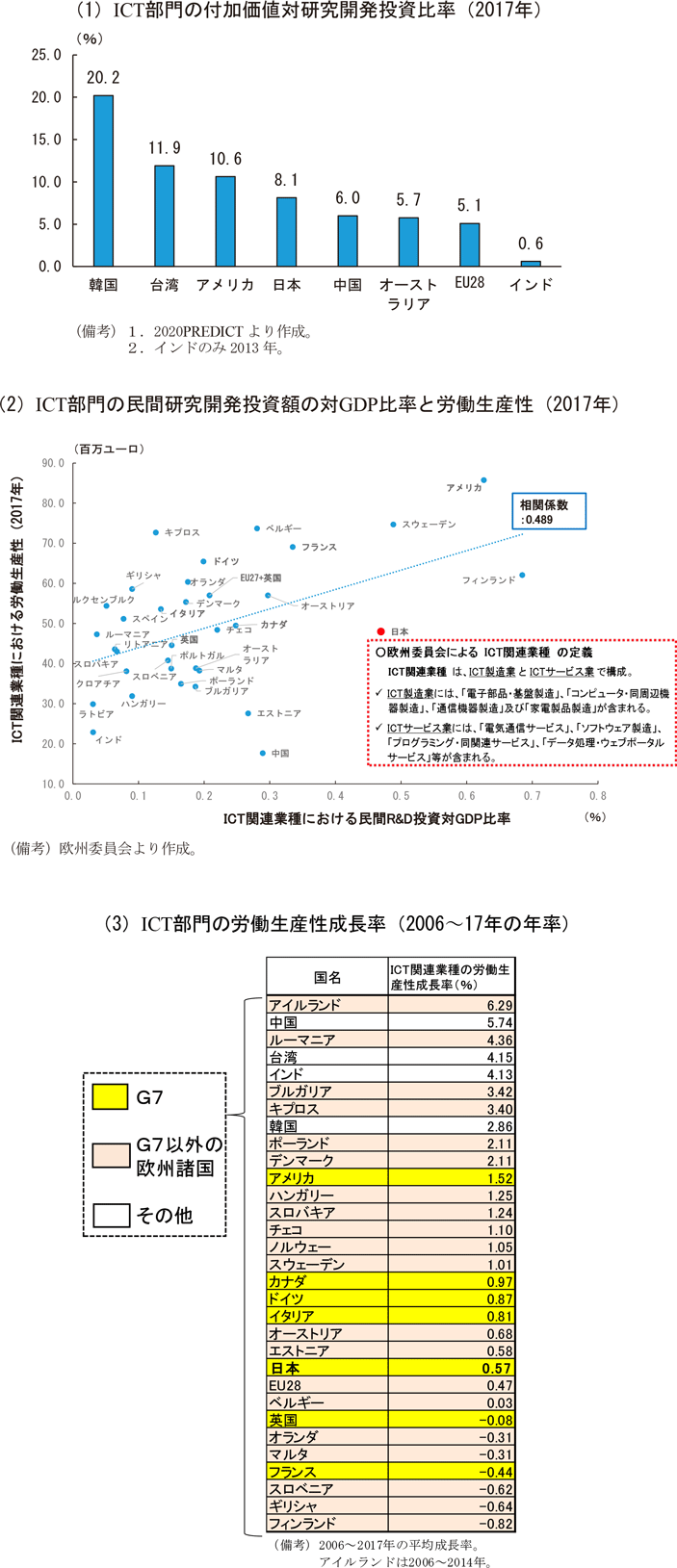
それでは、こうした研究開発投資比率の違いは、ICT部門の成長率にどのように影響しているだろうか。ICT部門の付加価値額の成長率(前年比)は、17年には中国13.0%、豪州8.8%、台湾7.2%、アメリカ7.0%、EU6.5%であり、日本の2.0%より高い。06~ 17年の年平均成長率では、中国やインドで高い伸びとなっているのに次いで、韓国や台湾でも特にICT製造業がけん引する形で、ICT部門の成長率が経済全体の伸びを上回っている(第2-2-4図及び表)。総じてみれば、17年時点で日本より研究開発投資比率が高い3か国(韓国・台湾・アメリカ)では、ICT部門の成長率は経済全体との比較で高いのに対し、日本は特にICT製造業の伸びが低迷し、ICT部門全体の伸びもマイナスとなっている。
他方、政府以外の研究開発投資に対する政府の財政支援(政府の予算配分額)は、GDP比でみると、18年で日本0.69%(うちICT関連の研究開発投資に対する支援0.07%)、アメリカ0.64%(同0.05%)、EU28か国0.63%(同0.04%)といずれも日本がアメリカやEUを上回っており、ICT関連を含め、日本では研究開発投資に対してほぼ同程度の政府支援が行われていると考えられる。また、ICT部門への財政支援の分野別内訳をみると、アメリカでは財政支援全体のうちICT部門向けは2%程度であるが、そのほぼ全額が通信向けであるのに対し、EUでは財政支援全体のうちICT部門向けは4%超とアメリカより高く、分野別にもコンピュータ・同関連サービスと通信向けの比率がほぼ等しく、その他(通信機器や電子部品等)にも幅広く支援が行われている(第2-2-5図)。
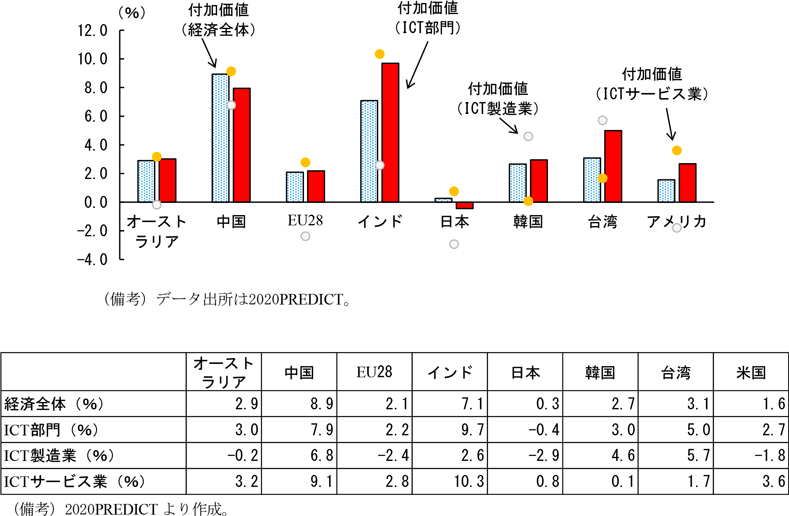
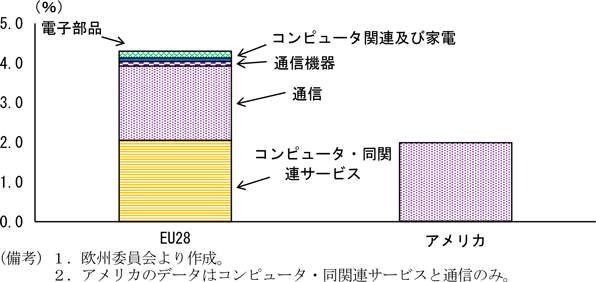
06~17年の時間当たり労働生産性の平均成長率を比較すると、国によって特徴が異なる。アメリカでは、ICTサービス業の労働生産性の伸びがICT製造業の伸びを上回っており、中国以外の各国の伸びを上回っている(第2-2-6図)。韓国・台湾・中国ではICT製造業で5%前後と高水準であるが、ICTサービス業については中国のみ高成長で、韓国や台湾では低い伸びとなっている。日本では、ICT製造業の労働生産性の伸びがICTサービス業の伸びを上回っているが、他国と比較するといずれも低く、EUも日本と同様の特徴がみられる。なお、国によって労働生産性の伸びの動向に大きな違いがみられる理由として、当該成長率が購買力平価換算ベースで計測されていることに留意する必要がある。
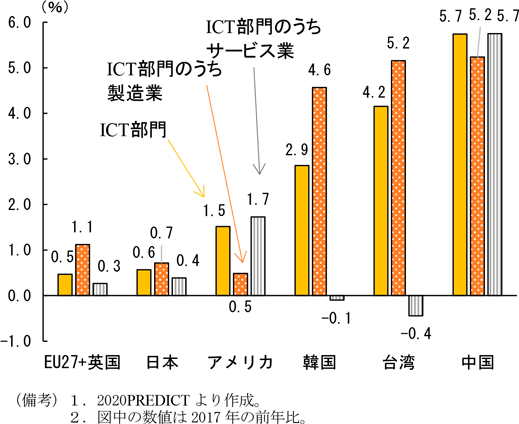
民間部門の研究開発支出の対GDP比率は、06年には日本が2.5%と最も高く、次いで韓国(2.2%)、アメリカ(1.8%)であったが、17年には韓国(3.6%)や台湾(2.6%)が比率を高め、日本(2.5%)を上回っている(第2-2-7図、第2-2-8図)。また中国も06年の1.0%から17年には1.7%と大きく比率を高めている。内訳をみると、韓国ではICT、非ICTの両方で比率が高まったが、台湾ではICTを中心に上昇している。こうした研究開発投資の強化が、両国でのICT部門の高い成長につながった可能性が指摘できる。これに対し、日本では欧米などと比較すればICT部門に相応の研究開発投資を行ってきたが、同部門における付加価値成長率や労働生産性の伸びは低い。
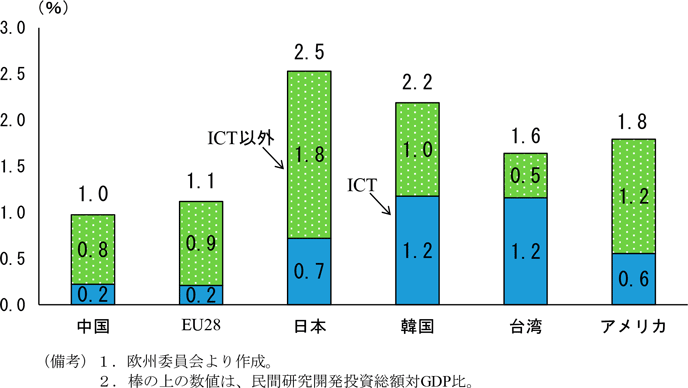
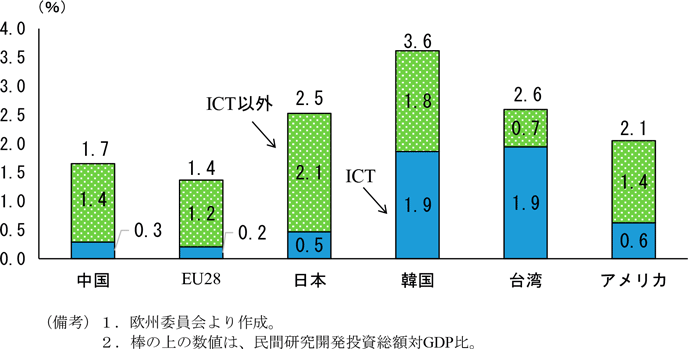
(2)企業レベルで見たICT部門の成長・収益性と研究開発投資
(EUの研究開発投資データベース)
ここまでは国別のデータを用いて、ICT部門に焦点を当てて、研究開発投資の動向が成長の鍵となる可能性についてみてきた。本稿では、企業レベルの情報を用いてICT部門及びその他の成長業種での研究開発投資の動向と企業パフォーマンスの比較等を行う。
分析に用いたのは、欧州委員会が年1回公表している民間企業の研究開発投資スコアボード87(各国の上場企業のうち研究開発投資額88の上位2,500社の財務データ)である。個社レベルのデータが14~19年の各年について、企業名を含めデータベースとして公表されていることから、同じ企業の異なる年次のデータを接続することもできる。しかし上位2,500社は各年で入れ替わりがあることから、異なる年次のスコアボードを用いて業種別・国別の比較分析を行う場合は、データのカバレッジに留意が必要89である。ただし、各業種の主だった上場企業は継続的にカバーされており、国×業種のレベルで全体の傾向を把握するには問題ないと考えられる。なお、欧州委員会がこうしたデータベースを整備し、継続的に公表している背景の一つには、EU諸国の構造的な課題として、民間企業の研究開発投資が少ないことによるイノベーションの遅れが認識され、これを打開するための材料として、国際比較等の分析が進められていることがあるとされている。
上記スコアボードを用いて、19年の売上高(純売上90)が大きい業種91について、それぞれの売上高の伸びを比較すると、14~19年の間で伸びが最も大きかったのがソフトウェア・コンピュータサービス(年率14.1%)、次いで医薬品・バイオテクノロジー(同6.8%)、テクノロジー・ハードウェア及び機器(同5.7%)であった。これらの業種は研究開発投資集中度(研究開発投資比率(対売上))が他業種と比較して高く、全業種の平均比率4.3%に対し、順に11.8%、15.9%、9.0%である(第2-2-9表)。また、研究開発投資集中度と過去5年間の売上伸び率の関係を業種別の散布図(第2-2-10図)でみると、研究開発投資集中度が相対的に高いソフトウェア・コンピュータサービス、医薬品・バイオテクノロジー、テクノロジー・ハードウェア及び機器では他業種と比較して売上の伸びも高く、次いで電子・電気機器や自動車・同部品が研究開発投資集中度、売上伸び率ともに比較的高い水準となっている。さらに、過去5年間の研究開発投資額伸び率と、同じ期間の売上伸び率の関係を業種別にみたものが第2-2-11図であるが、過去の研究開発投資額伸び率が高い業種ほど、売上伸び率も高い傾向がうかがえる。特に日本企業に注目してみると、自動車・同部品では、研究開発投資伸び率、売上伸び率ともに日本企業は世界の平均と同水準であるが、ソフトウェア・コンピュータサービスやテクノロジー・ハードウェア及び機器、電子・電気機器ではいずれも、日本企業は研究開発投資伸び率、売上伸び率の両面で世界平均より低い。他方、化学では、日本企業の売上伸び率は世界平均と同水準であるが、研究開発投資額の伸び率は世界平均より高く、業種によって日本企業の相対的なパフォーマンスが異なることが示唆される。
欧州委員会はデータベース報告書の中で、ソフトウェア・コンピュータサービス、テクノロジー・ハードウェア及び機器及び電子・電気機器等をまとめてICT関連産業92としているため、本稿でもこれらの業種に特に注目して分析を行った。
なお、ICT関連産業及び自動車・同部品の4業種について、研究開発投資額上位10社の研究開発投資額と売上高の関係を、14年と19年のそれぞれで比較したのが第2-2-12図である。ここでは、業種ごとに研究開発投資額の上位10社を示しているが、図の右下にあるほど売上高対研究開発投資額比率が小さく、左上にあるほど同比率が大きい。14年と19年を比較すると、19年にはソフトウェア・コンピュータサービス及びテクノロジー・ハードウェア及び機器のいずれの業種においても、研究開発投資額の上位3社は、研究開発投資額が突出して高くなっており、また、売上高も高水準にある。さらに、g社を除く5社では、売上高に対する研究開発投資額比率も相対的に高水準となっている。また、4業種のうち電子・電気機器や自動車・同部品では14年時点で上位10社入りしている日本企業が多いが、その多くは19年にも上位10社にとどまり、研究開発投資規模において相対的に高い地位を維持している。
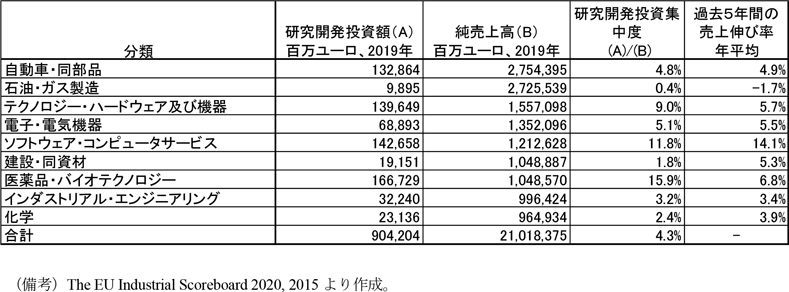
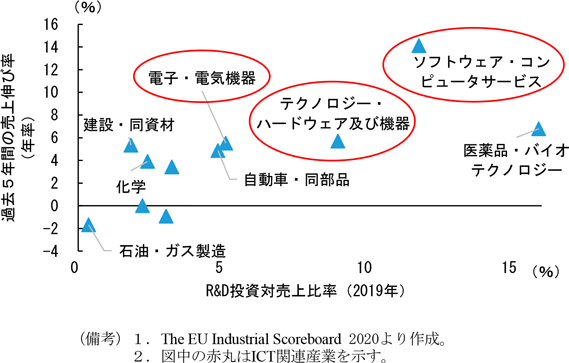
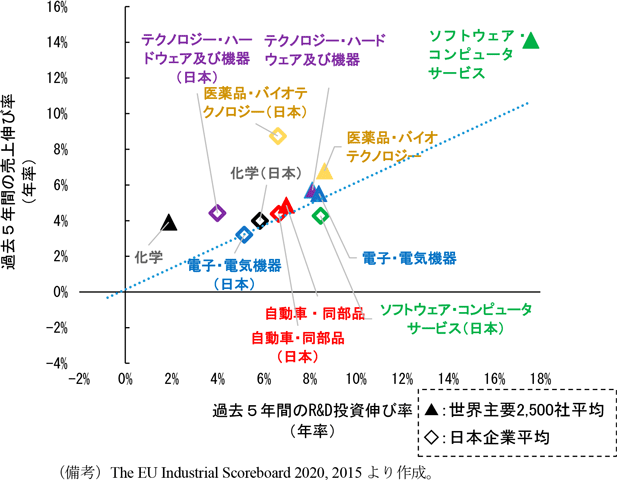
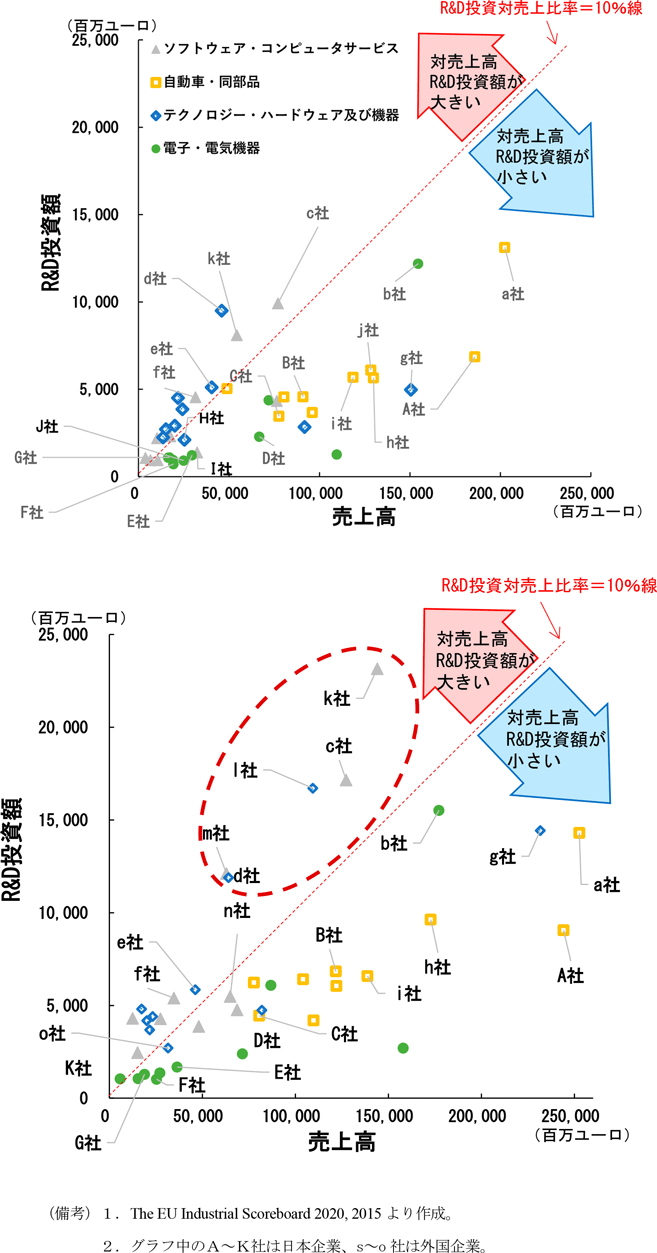
以下では、成長業種であるソフトウェア・コンピュータサービス業並びにテクノロジー・ハードウェア及び機器業をICT部門として、個別企業の研究開発投資の動向と、パフォーマンスの関係を分析した。加えて、ICT部門以外の成長業種として医薬品・バイオテクノロジー業等の企業動向も比較検証した。
(企業別にみた研究開発投資と利益率)
(ア)ソフトウェア・コンピュータサービス業
ソフトウェア・コンピュータサービス業では、14~19年の間の研究開発投資の伸びは年率17.6%であり、売上の伸び(同14.1%)を上回る93。同業種で研究開発投資額が大きい企業はアメリカと中国に集中している。研究開発投資額上位2,500社のうち、中国のソフトウェア・コンピュータサービス業の企業数は、14年の32社から19年には62社に急増しており、アメリカでは逆に161社から153社に減少している。これに伴い、研究開発投資額のシェアも中国は6%から14%に増加しているが、アメリカのシェアは77%から72%と低下するも、依然として世界全体の3/4程度の投資を行っている。とりわけ、19年時点では世界全体の37%はアルファベット、フェイスブック及びマイクロソフトの3社が占めており、存在感が大きい。なお、日本のシェアはもともと低水準であったが、5年間でやや低下している(第2-2-13図)。
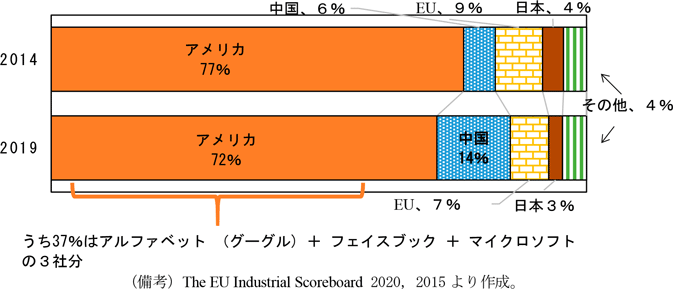
14年、19年の各年について、売上高が相対的に大きい企業と小さい企業の特徴をみるため、売上(対数値)の上位25%超の企業、下位25%未満の企業及び全企業のぞれぞれについて、研究開発投資対売上高比率、売上高利益率、研究開発投資の伸び、及び売上高の伸びの中央値を比較したのが第2-2-14表である。例えば19年の値をみると、売上高利益率の中央値は売上規模が大きい企業で14.3%、小さい企業でマイナス13.7%と、規模の大小に応じて符号が異なり、分布に大きな違いがみられ、小規模企業では利益率が負の企業が過半を占めている。研究開発投資対売上高比率は規模が小さい企業の方が高い傾向にあることから、こうした企業では低利益率の下で相対的に多額の研究開発投資を行っていることが示唆された。これらの背景としては、ソフトウェア・コンピュータサービス業には多くのベンチャー企業が存在することがあり、そうした企業は研究開発比率が高くかつ利益率が低い傾向にあることも考えられる。
売上の対前年伸び率については、規模が小さい企業が中央値で18.4%、大きい企業が同9.7%と、規模が大きくなるほど伸びも小さくなる傾向にあるが、研究開発投資の伸び率については、規模の大小にかかわらず中央値にはほとんど違いがみられず、企業規模が大きくなっても研究開発投資を積極的に拡大させていることがうかがえる。また、14年の結果と19年の結果を比較するとほぼ類似の結果が得られたが、研究開発投資の伸び率に関してのみ、14年時点では企業規模が大きい企業の方が小さい企業に比べ伸びが低い傾向にあることから、近年、企業規模の大きい企業が活発な研究開発投資を行う一方、小規模企業の研究開発投資の伸びが低下する傾向がみられる。
ソフトウェア・コンピュータサービス業の特徴として、研究開発投資を集中的に行った企業が新規サービスの提供等により売上を伸ばし大企業に成長し、市場を寡占化することにより高い利益率を得るケースがあることや、寡占企業も多額の研究開発投資を続け、売上を伸ばし続けるとともに高い利益率を実現しやすいことが指摘されている。上述の結果は、こうした指摘と整合的と考えられる。加えて、ソフトウェア・コンピュータサービス業では、ベンチャー企業等を中心に小規模企業が研究開発投資を活発に行っているものの、市場では寡占企業の競争力が圧倒的に強く、その多くは巨大な寡占企業ほどの利益率を実現できないどころか利益がプラス転換しないまま、M&Aの対象となったり、競争力を維持できずに市場から退出している可能性もある94と考えられる。第2-2-15表では、ソフトウェア・コンピュータサービス業で14年時点の研究開発投資対売上比率が高く、かつその後5年間の平均的な売上伸びも高い企業の例を挙げている。研究開発投資対売上高比率、売上伸びともに高い企業の多くはソフトウェア開発等を行う、年間売上が数億ドル規模の企業であるが、フェイスブックやツイッターのようにSNSの提供等で順調な事業拡大を続け、19年時点の売上が数百億ドル規模の企業でも、売上対比で20%を超える研究開発投資を実施していたことがわかる。
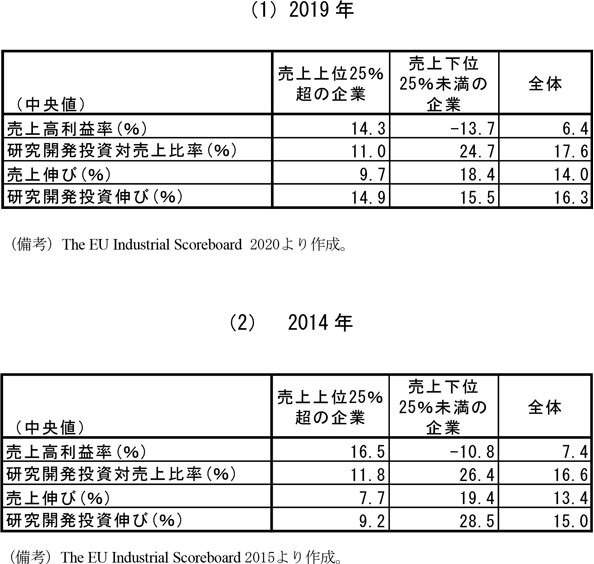
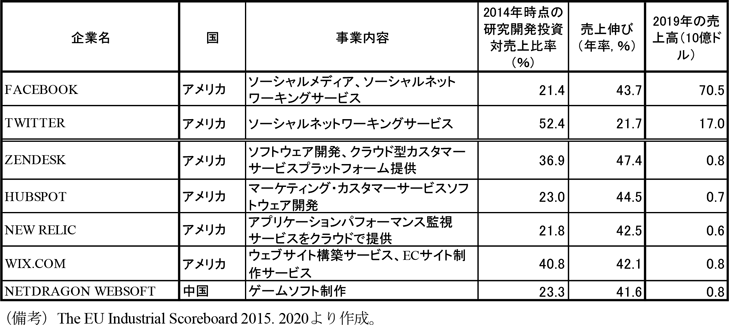
(イ)テクノロジー・ハードウェア及び機器業
テクノロジー・ハードウェア及び機器業でも、14~19年の平均変化率でみて、研究開発投資の伸び率(8.1%)は売上高の伸び率(5.7%)を上回っている。14年と19年の売上のシェアを国別に比べると、中国企業が12.4%から20.7%にシェアを高める一方、アメリカ・日本・台湾の各企業のシェアはいずれも低下している。研究開発投資額についても、中国企業のシェアが4.8%から18.1%に大きく高まる一方、アメリカ企業のシェアは60.7%から54.9%にまで下がっている(第2-2-16図)。なお、中国の大企業(ファーウェイ)の研究開発投資額(167億ユーロ)はアメリカの大企業(アップル144億ユーロ、インテル119億ユーロなど)を19年に上回っており、中国ではファーウェイ1社の売上や研究開発投資額が突出しているのに対し、アメリカは複数の大企業間の競争状態となっている。また、ソフトウェア・コンピュータサービス業とは異なり、米中ともに利益率がマイナスの企業は限られているが、売上対研究開発投資比率と利益率の間には負の関係がうかがえる(第2-2-17表)。
テクノロジー・ハードウェア及び機器部門では、研究開発投資対売上高比率は、平均的にみてソフトウェア・コンピュータサービスよりやや低く、投資額の伸び率も低めであるが、規模が大きい企業の方が、小さい企業と比べて売上高の伸び率、研究開発投資の伸び率ともに高めであり、高い利益率を実現していることがうかがえる。また、14年と19年を比較すると、売上高の伸び率が低下し、特に規模が小さい企業での低下傾向が顕著である。併せて、小規模企業では19年には研究開発投資の伸びを抑える傾向にあることも示唆されている。
第2-2-18表では、テクノロジー・ハードウェア及び機器業で14年時点の研究開発投資対売上高比率が高く、かつその後5年間の平均的な売上伸びも高い企業の例を挙げている。研究開発投資対売上高比率、売上伸び共に高い企業の多くは半導体関連製品の製造等を行う、年間売上が数億~数十億ドル規模の企業であるが、ブロードコムやエヌビディアのように19年時点の売上が数百億ドル規模の企業でも、売上対比で20%を超える研究開発投資を実施していたことがわかる。
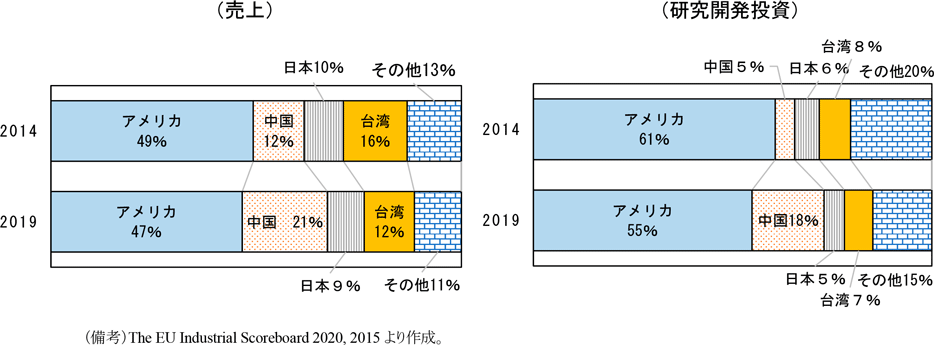
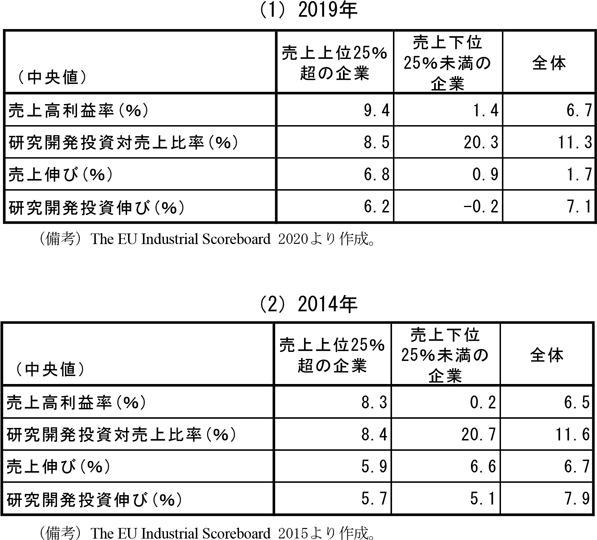
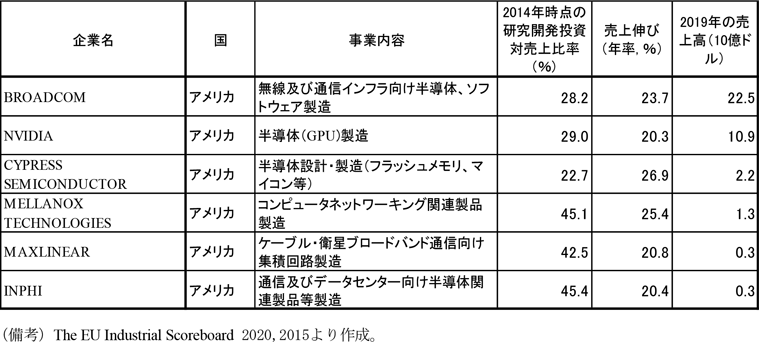
(企業別にみた投資比率と売上伸び)
次に、14~19年の期間での企業レベルの売上高の伸び率と、14年時点の売上対研究開発投資比率、もしくは設備投資95比率の関係をみてみよう。この分析により、14年時点でこれらの投資比率が高い企業ほど、その後5年間の売上高の伸び率が高い傾向にあるか、検証を行う。第2-2-19図はソフトウェア・コンピュータサービス業とテクノロジー・ハードウェア及び機器業の各社の研究開発投資対売上比率を横軸に、売上高の伸び率を縦軸に取ったものである。ソフトウェア・コンピュータサービス業、テクノロジー・ハードウェア及び機器業それぞれの中央値を比較すると、売上高の伸びは順に10.8%、7.1%であり、研究開発投資対売上高比率は15.9%、11.3%、設備投資額対売上高比率は3.6%、3.4%と設備投資比率ではほぼ同水準であるものの、いずれも前者の方が高い(第2-2-20表)。また、いずれの業種でも、14年時点の研究開発投資額対売上高比率と売上高の伸びの間には有意な正の相関がみられた。
さらに、投資水準と事後の売上高成長率の関係をより詳細にみるため、業種別に以下のような推計を行った96 97。
Sales_growth2019-2014=α+β1RD_intensity2014+β2Capex_intensity2014+ε(1)
Sales_growth2019-2014: 2014年から19年の売上高伸び率(年平均)
RD_intensity2014: 2014年の研究開発投資額対売上高比率
Capex_intensity2014: 2014年の設備投資額対売上高比率
α: 定数項、β1, β2: 係数、ε: 誤差項
推計の結果、ソフトウェア・コンピュータサービス業、テクノロジー・ハードウェア及び機器業いずれの業種でも、研究開発投資比率、設備投資比率ともにプラスで有意の係数が得られた。因果関係は不明であるが、少なくとも、14年時点で両投資比率が高かった(低かった)企業の売上の伸びは、その後5年間高い(低い)傾向にあることが示唆された(第2-2-21表)。また、こうした投資比率が売上伸びを説明できる割合(決定係数)はソフトウェア・コンピュータサービス業の方が高く、係数も大きいことから、企業の成長はテクノロジー・ハードウェア及び機器業よりも研究開発投資や設備投資の相対的な水準の影響を受けやすい傾向もうかがえる。
結果の頑健性を確認するため、14~19年に加え、14~17年、もしくは17~19年の期間で同様の推計を行ったところ、ソフトウェア・コンピュータサービス業では両期間ともに研究開発投資、設備投資のいずれの比率でもプラス有意となり、テクノロジー・ハードウェア及び機器業では14~17年で同様にプラス有意であったが、17~19年はプラスであるものの有意とはならなかった。
以上の結果をまとめると、ICT部門では、企業レベルで見ても、研究開発投資や設備投資に力を入れている企業では、事後の売上の伸びも高い傾向が示唆された。
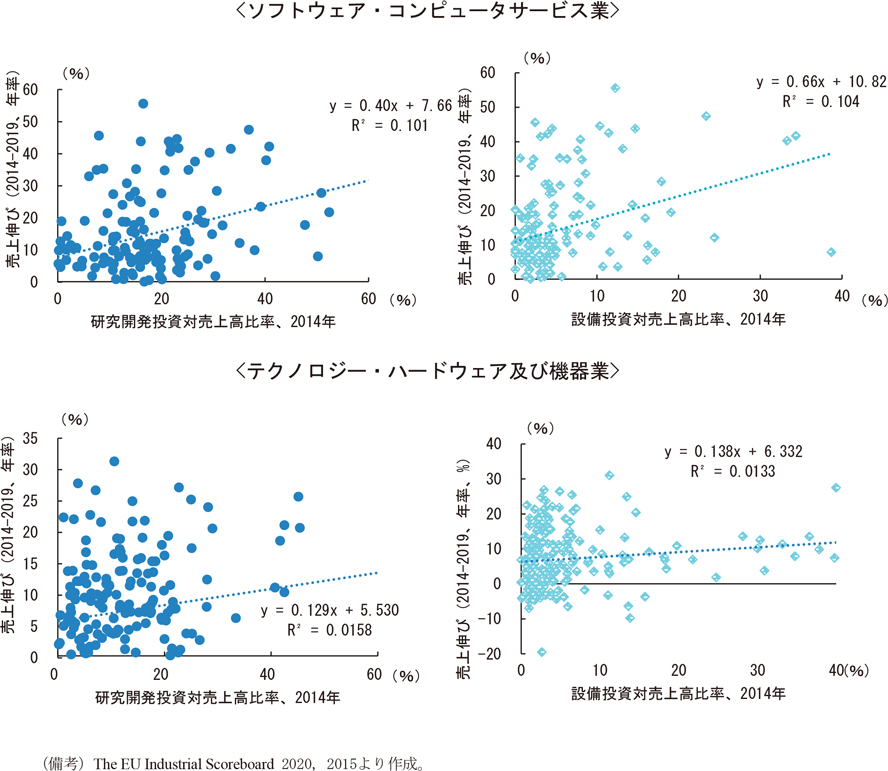
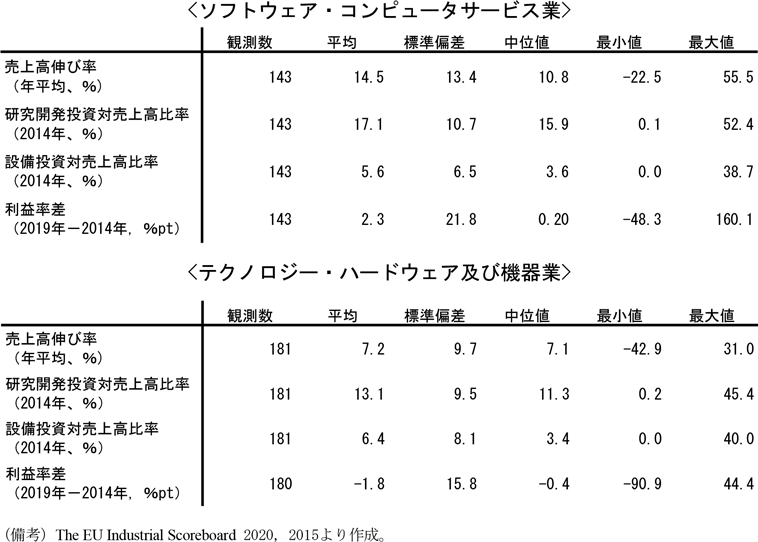
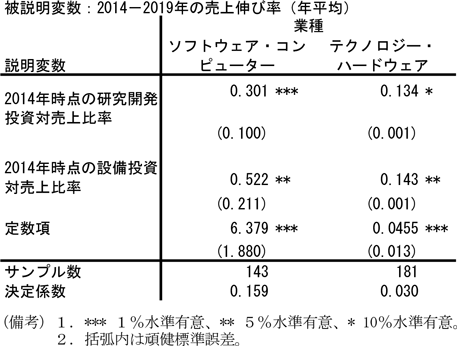
なお、両者の関係は、ICT部門以外の製造業でもプラス有意となる場合がみられる。例えば、医薬品・バイオテクノロジー産業の研究開発投資対売上高比率や設備投資対売上高比率と、5年間の売上の平均的な伸び率の相関をみると、相関係数はそれぞれ0.31、0.42で統計的にも有意である。ただし、両方を説明変数とした推計(推計式(1))を行うと、いずれの係数も有意ではなくなり、ICT部門業種よりも関係が弱い。この背景には、医薬品・バイオテクノロジー産業の研究開発投資は懐妊期間がある程度長いことや、売上に結び付かないリスクを伴うものであることが考えられる。これに対し、電子・電気機器ではどちらの投資比率も有意に正の符号となり、係数の水準もソフトウェア・コンピュータサービスに次いで大きい(第2-2-22表)。自動車・同部品では推計された係数は正であったが、サンプル数が限られていることもあり有意にはならなかった。こうしたことから、少なくともソフトウェア・コンピュータサービス、電子・電気機器、テクノロジー・ハードウェア及び機器の3業種では設備投資や研究開発投資が相対的に高水準であると、その後数年間にわたり売上の伸びも高い傾向があることが示唆された。
第2-2-23図(1)(ソフトウェア・コンピュータサービス)、第2-2-23図(2)(電子・電気機器)の推計結果を用いて、14年に研究開発投資や設備機器・構築物投資を一定程度行った場合、19年の売上がどの程度押し上げられたか試算した結果を第2-2-25図に示す。左側のソフトウェア・コンピュータサービスの場合、14年の売上を100とすると、仮に14年時点で投資を全く行っていなくても、5年後の19年には平均的にみて売上は136.2に増加する。これに加えて、14年時点で研究開発投資額が売上対比で17.1%(推計対象とした企業の平均値)だったとすると、売上の伸びが押し上げられることで19年の売上は172.6まで増加する。さらに、14年時点で設備機器や構築物に対する投資額が売上対比で5.6%(推計対象とした企業の平均値)だったとすると、19年の売上は196.7とほぼ倍増の水準となることが見込まれる。ソフトウェア・コンピュータサービスの場合、市場の拡大スピードが速く、新規投資等を行わなくても売上は伸びるが、企業が研究開発投資や設備投資を拡充するほど、売上の伸びが加速していく傾向が示唆される。
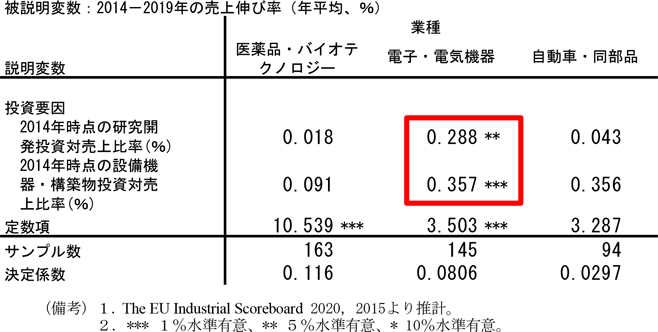
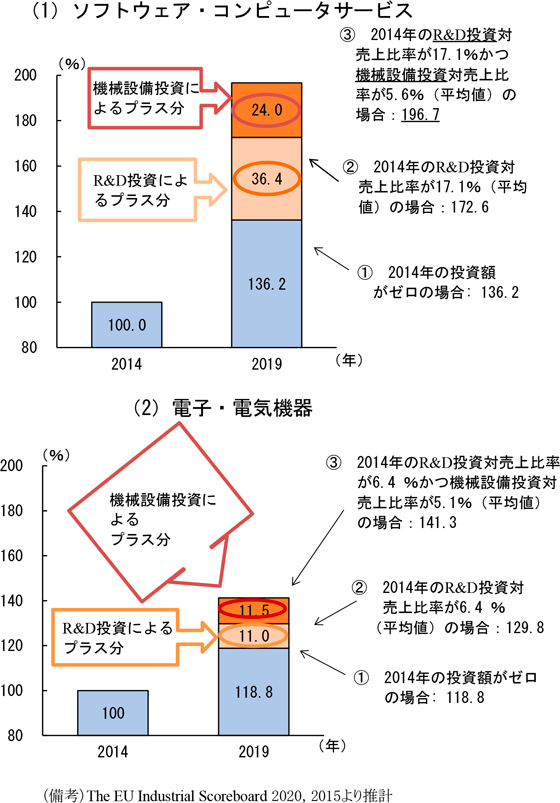
(企業別にみた投資比率と従業員数の変化)
次に、投資比率と従業員数の変化の関係を示したのが第2-2-24図である。ソフトウェア・コンピュータサービス業、テクノロジー・ハードウェア及び機器業いずれの業種でも、研究開発投資対売上高比率と、事後的な従業員数の伸びの間には正の相関がみられる。上述のとおり、研究開発投資対売上高比率が高ければ、事後的な売上の伸びも高い傾向にあり、それが従業員数の伸びにつながっている可能性もあるが、売上が伸びていても雇用が増えているとは限らず、売上はプラス変化でも従業員数がマイナス変化の企業も数多くみられる点には留意が必要である98(第2-2-25表)。
全体の傾向をみるため、14~19年の間の従業員数の平均変化率を被説明変数とし、14年時点の投資比率に回帰(下式)すると、ソフトウェア・コンピュータサービス業、テクノロジー・ハードウェア及び機器業いずれでも、研究開発投資対売上高比率ではプラス有意であるが、設備投資対売上高比率では有意な関係がみられなかった。言い換えれば、14年時点で研究開発投資に相対的に力を入れていた企業ほど、その後5年間で従業員数の増加ペースも早かったことになり、係数はソフトウェア・コンピュータサービス業の方が大きい。因果関係は明確ではないが、14年時点で研究開発投資比率が高い企業には、成長ペースが速い比較的規模の小さい企業も含まれることから、従業員数を増やす傾向にある可能性が考えられる。これに対し、設備投資対売上高比率が高い企業は成長企業である一方、労働から資本への代替が進みやすい可能性も考えられ、結果的に明確な相関がみられなかった可能性が指摘できる(第2-2-26表、第2-2-27図)。
Employee_growth2019-2014=α+β1RD_intensity2014+β2Capex_intensity2014+ε
Employee_growth2019-2014: 14~19年の従業員数伸び率(年平均)
RD_intensity2014: 14年の研究開発投資額対売上高比率
Capex_intensity2014: 14年の設備投資額対売上高比率
α: 定数項、β1, β2: 係数、ε: 誤差項
なお、他業種の動向をみると、電子・電気機器では同様に研究開発投資比率の係数が正に有意であるが、医薬品・バイオテクノロジーでは設備投資比率のみが正に有意であり、自動車・同部品ではいずれも有意とはならなかった。これらの結果を踏まえると、売上伸びと同様に、ICT関連産業(ソフトウェア・コンピュータサービス、電子・電気機器、テクノロジー・ハードウェア及び機器の3業種)では、研究開発投資が相対的に高水準であると、その後数年間にわたり従業員数の伸びも高い傾向があることが示唆された(第2-2-26表、第2-2-28表)。
また、第2-2-26表の推計結果を用いて、ソフトウェア・コンピュータサービスで14年に研究開発投資や設備機器・構築物投資を一定程度行った場合、19年の売上がどの程度押し上げられたか試算した結果を第2-2-27図に示す。14年の従業員数を100とすると、仮に14年時点で研究開発投資を全く行っていないと、5年後の19年には平均的にみて従業員数は20.7にまで減少する。一方、14年時点で研究開発投資額が売上対比で16.9%(推計対象とした企業の平均値)だったとすると、売上伸びが押し上げられることで19年の売上は119.5まで増加し、減少した従業員数を埋め合わせるだけでなく、2割程度増加させることが見込まれる。言い換えれば、ソフトウェア・コンピュータサービス業では、第2-2-24図にみられるように過去5年間の従業員数伸びがマイナスの企業も多く、雇用面で成長していくには新たなサービスを生み出すための研究開発投資が必要であることが示唆される。なお、第2-2-29表では、研究開発投資対売上比率が高く、かつその後5年間の従業員数伸びが高い企業の例を挙げている。事業内容をみると、各種のクラウドサービス提供(ストレージやオンラインミーティングサービス等)により、従業員数を急拡大させてきた企業がみられる。
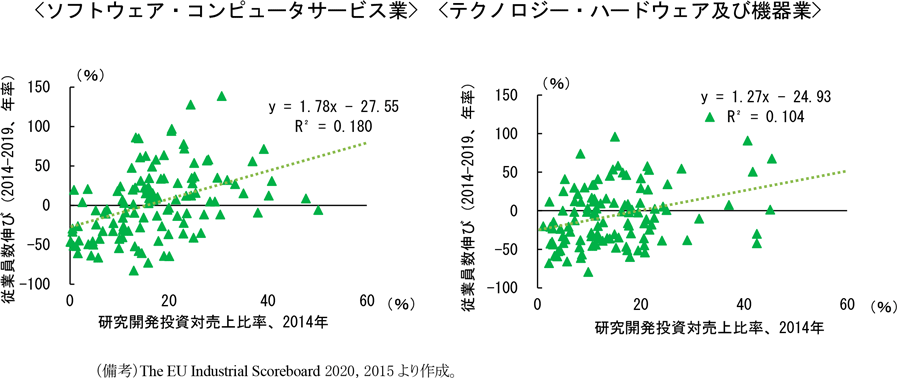
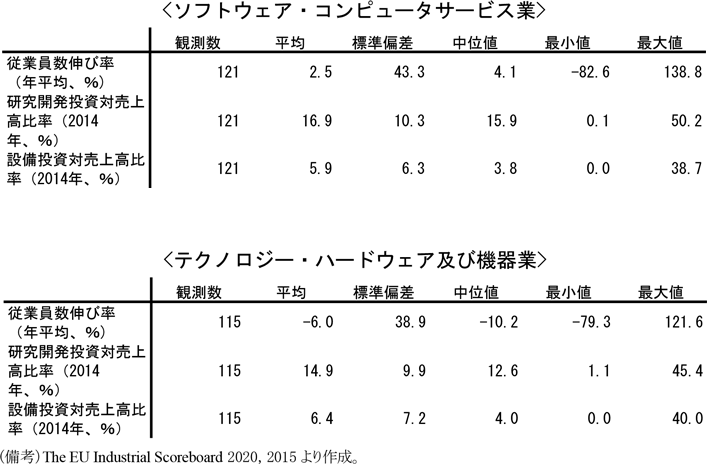
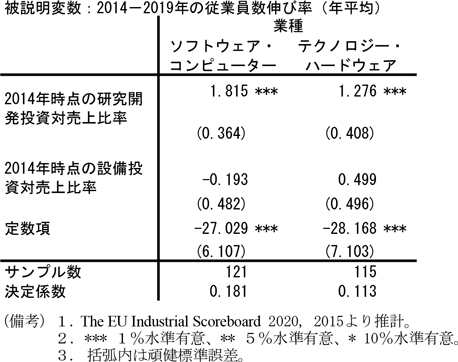
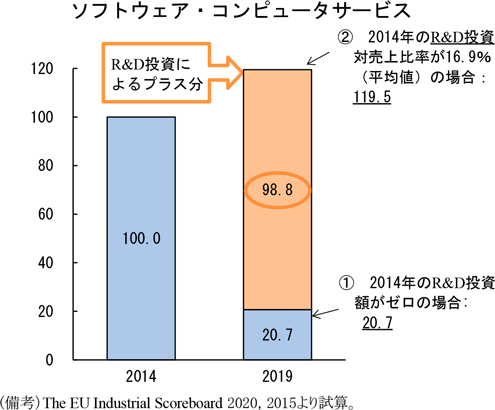
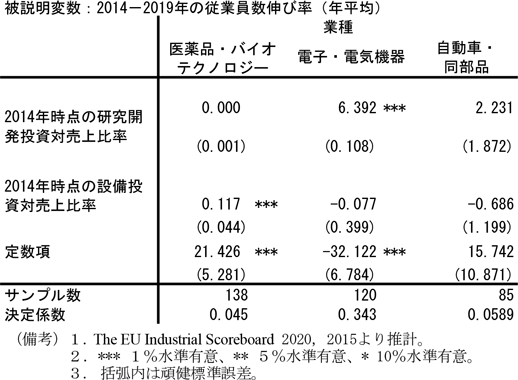
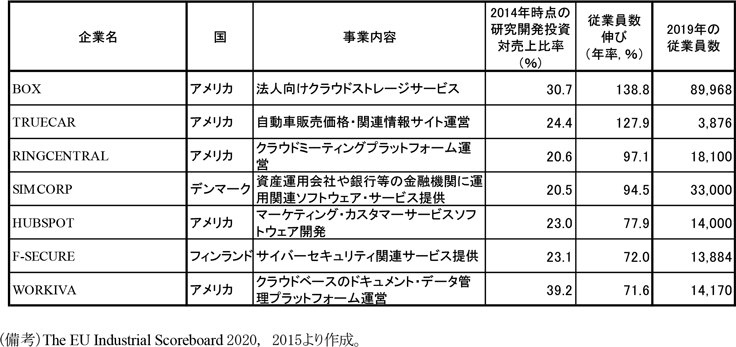
(企業別にみた研究開発投資ウェイトと利益率変化)
続いて、企業別の研究開発投資ウェイトと利益率の変化の関係を業種別に検証する。具体的には、14年時点の研究開発投資支出額対売上比率と、その後5年間の利益率の変化(19年の利益率マイナス14年の利益率)の相関関係を見たところ、ソフトウェア・コンピュータサービスについては、ややばらつきはあるものの有意な正の相関関係がみられた(第2-2-30図)。売上のみならず、利益率の観点からも、研究開発投資に一定レベル以上力を入れている企業では数年後に99利益率が上昇している傾向が示唆される。なお、利益率変化幅の中位値は第2-2-31表に示すように0前後であるが、14年時点で利益率が高かった企業ほど、19年までの間の変化幅は負値含め小さくなりやすい。言い換えれば、第2-2-30図でみられる正の相関は、14年に研究開発投資比率が高かった企業には利益率が低い企業が多く含まれ、こうした企業が5年後も市場に残っている場合、利益率が相対的に大きく上昇している傾向にあることが示唆される。また、研究開発投資額の代わりに資本的支出(CAPEX、設備投資額等)対売上比率と、収益性の変化の関係をみると有意な関係にはなく、設備投資が相対的に高水準でも事後の収益性変化とは関係しない可能性が示唆される。
なお、テクノロジー・ハードウェア及び機器では、ソフトウェア・コンピュータサービスと同様に、研究開発投資の伸びが売上伸びと相関しているが、研究開発投資比率と売上高利益率の変化の間には有意な相関がみられない(第2-2-30図、第2-2-31表)。また、電子・電気機器、及び自動車・同部品業でも、相関係数は0.1前後で有意水準は低く、医薬品・バイオテクノロジーではむしろマイナスの相関がみられた。
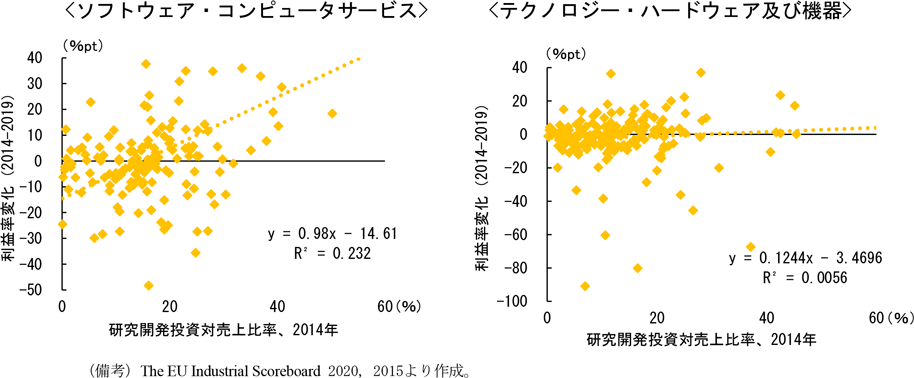
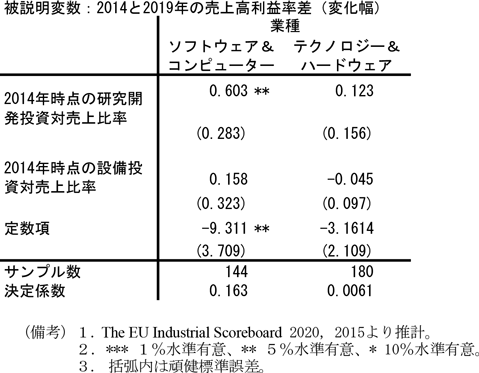
世界の主要企業の研究開発投資においては、ICT関連産業の投資ウェイトの拡大や、非デジタル関連産業でのデジタル関連製品やサービスへの投資の進展が特徴的となっている。こうした傾向は、コロナ禍で主要国の多くがマイナス成長となった20年に加速したとみられ、OECDによれば20年には自動車産業のほぼ全ての主要企業で研究開発投資額が前年比マイナスであったのに対し、ソフトウェア、コンピュータサービス及び電子機器産業では多くの主要企業で前年比プラスであったとされている100。
(各業種での日本企業の動向)
最後に、業種ごとに日本企業の14年の研究開発投資とその後5年間の売上伸び率の関係を企業レベルで概観する。業種により上位2,500社に含まれる日本企業の比率は異なり、例えばソフトウェア・コンピュータサービスでは144社中5社(3.5%)、テクノロジー・ハードウェア及び機器では181社中18社(9.9%)、電子・電気機器では145社中32社(22.1%)、自動車・同部品では101社中27社(28.7%)と後者2業種で高い。研究開発投資水準、売上伸び率からみても日本企業の位置付けは業種間で異なる。既述のように、産業ごとにみて、5年前の研究開発投資対売上比率と、その後5年間の売上伸び率の間にはおおむね正の関係がみられるが、ICT産業のうちソフトウェア・コンピュータサービスやテクノロジー・ハードウェア及び機器では、大半の日本企業の研究開発投資比率・売上伸び共に、世界の主要企業と比較して低い(第2-2-32図(1)、(2))。特にソフトウェア・コンピュータサービス業では、いずれの企業でも研究開発投資対売上比率が中央値よりかなり低く、テクノロジー・ハードウェア及び機器でも、研究開発投資対売上比率が中央値を上回っているのは日本企業の1割程度である。これに対し、電子・電気機器や自動車・同部品では研究開発投資対売上比率、売上伸び率ともに中央値より高い日本企業も複数みられ、相対的にみて世界の主要企業と比べて日本企業に競争力があり、売上を伸ばしている業種と考えられる(第2-2-32図(3)、(4))。
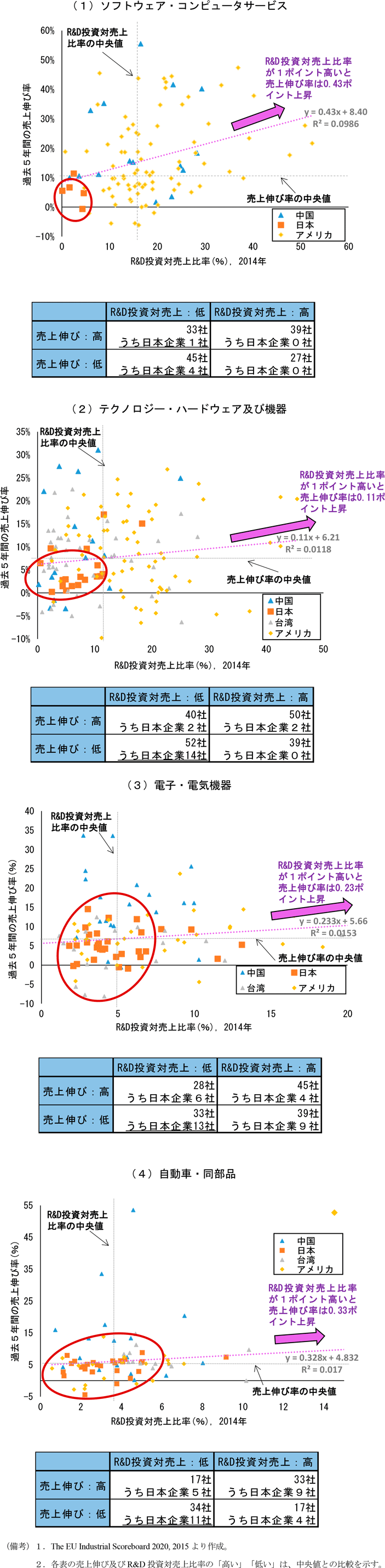
従来から我が国では、ICT関連産業の研究開発投資ウェイトが相対的に小さく、自動車・同部品など伝統的に研究開発投資を集約的に行ってきたものづくり産業のウェイトが大きかったが、こうした傾向はソフトウェア・コンピュータサービスのウェイトが3割を占めるアメリカとは対照的であり(第2-2-33図)、むしろ自動車・同部品等の研究開発投資を重点化してきたEUの立ち位置との共通点があると考えられる(第2-2-34図)。他方、主要企業1社当たりの研究開発投資額をEU、日本及び中国で比較すると、10年時点では日本企業とEU企業はほぼ同水準であったが、19年には日本企業の水準はEU企業の7割程度と相対的に伸び悩んでいる一方、中国企業の水準は急速に高まっている(第2-2-35図)。
EUでは、成長戦略の一環として研究開発投資の支援策を重視してきている。背景には、民間部門の研究開発投資の伸び悩みが続いていることに加え、上述のとおり、伝統的な製造業部門では研究やイノベーションに比較優位があるものの、知識集約型産業(欧州委員会の定義では、研究開発投資対売上比率が一定以上の業種を指し、例えばソフトウェア・コンピュータサービス、テクノロジー・ハードウェア、及び電子・電気機器が含まれる)では投資が伸び悩んでいることなどを課題として指摘している。こうした課題への対応として、欧州委員会では21~27年の財政枠組みにHorizon Europeと呼ばれる研究・イノベーションプログラムとして955億ユーロ(約11.6兆円)を計上し、基礎研究支援、グローバルな課題と欧州の産業競争力強化、及びスタートアップ支援を柱とする計画を公表している。さらに、臨時予算である復興基金では、研究・イノベーション関連施策も含め、気候変動とデジタルに主眼を置いた成長の方向性を打ち出している(第2-2-36図)。
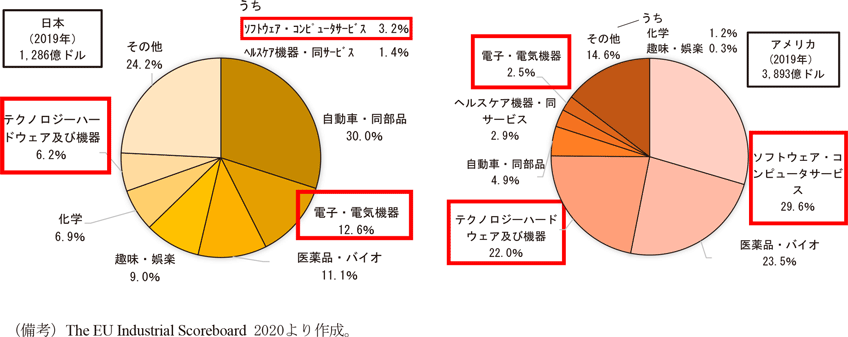
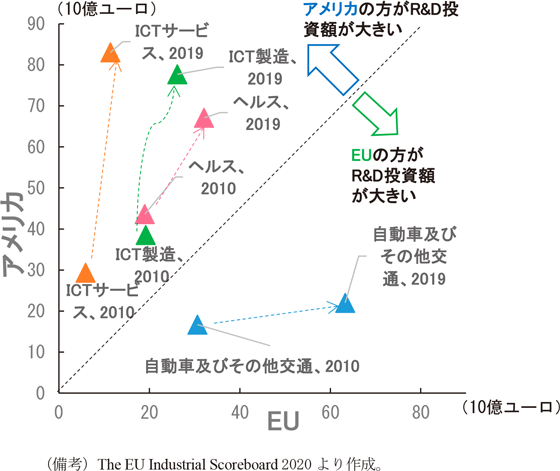
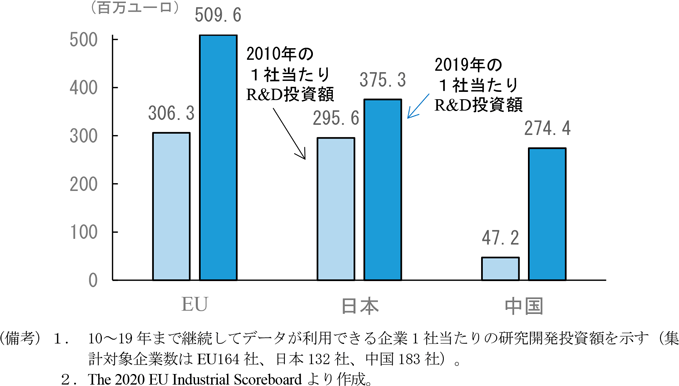
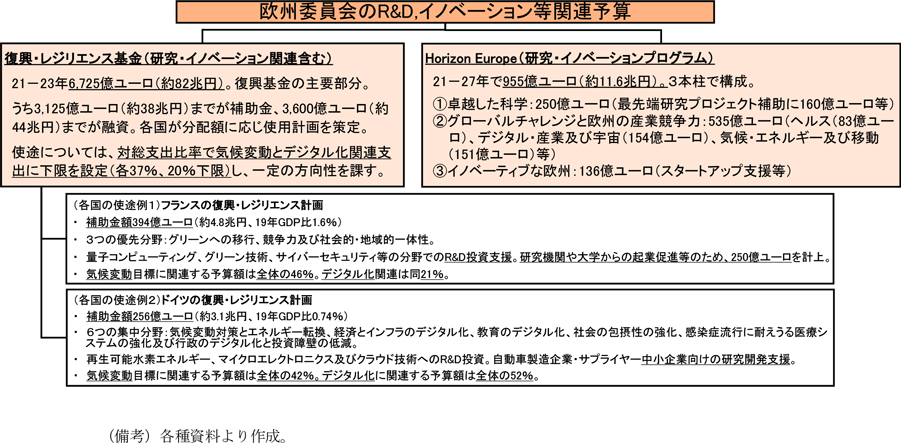
次項からは、民間部門でのデジタル技術の導入の動向や、導入が進んだ国での企業パフォーマンス等についてみていきたい。
2.企業のデジタル投資(DX)の動向
(1)欧米諸国でのDXの動向
欧州投資銀行の調査101によれば、EU諸国やアメリカでは企業によるデジタル技術の導入が徐々に進展している。EUとアメリカを比較すると、総じてみれば後者の方が技術導入が進んでいる。以下ではこの調査の結果に基づき、企業のデジタル投資の動向を簡単に紹介する。
アメリカとEUで業種別の動向を比較すると、アメリカでは特に非製造業でのIoT102導入や、建設業でのドローンの活用が進んでいるのに対し、EUではサービス業やインフラ部門でのプラットフォーム技術103活用がアメリカよりやや進んでいるなどの特徴がある。製造業では、IoTや3Dプリンターの活用はアメリカでやや進んでいるがロボット化はほぼ同程度であり、業種やデジタル技術の内容に応じて、活用度合いが異なることがうかがえる(第2-2-37図)。
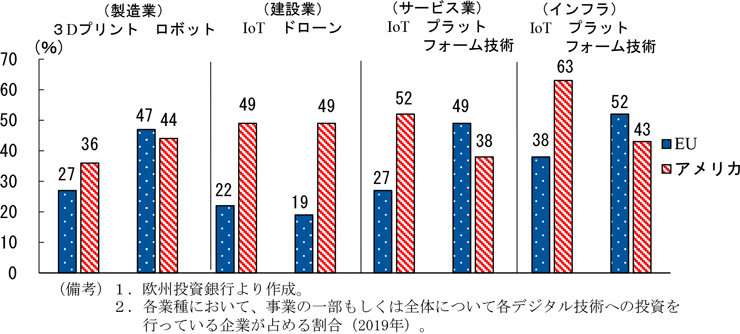
EU諸国を国別にみると、フィンランドやオランダ、チェコ等はアメリカよりもデジタル技術導入が若干進んでいる(第2-2-38図)。フィンランドの特徴は、特にサービスやインフラでビッグデータやAIの活用が進み、IoTやプラットフォーム技術を活用している企業が多い点にある(第2-2-39図)。背景としてフィンランドにはNokia本社があり、5G基地局で世界3位(18年)となっていることや、同社はハード開発・生産のみならず、研究・ソフト開発、技術者育成、スタートアップ企業育成など様々な役割を担っていることが指摘されている104。また、交通・運輸インフラでMaaS(単一のアプリケーションで複数の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約等を一括で行うサービス)提供が進んでいること、行政の支援により大学やスタートアップ企業が次世代交通システム(自動運転バス等)を開発しやすい環境が整備されていること、伝統産業である造船業でも船舶の自動運行技術の開発が進んでいることなどが挙げられる105。
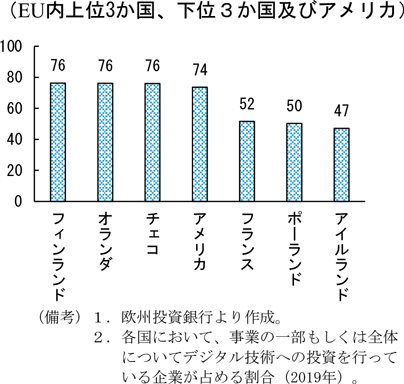
オランダの特徴は、他のEU諸国と比べてどの部門でもIoTの活用が進み、建設業ではドローン、インフラではプラットフォーム技術の活用が進んでいることである。通信大手KPNが高速の長距離通信網ネットワークを全国展開し、様々な分野の企業との連携によりIoTビジネスの拡大を図っている106。オランダには欧州最大級のセキュリティクラスタ107があり、国内外の数百の企業や大学、政府機関が連携して、サイバーセキュリティや重要なインフラの保護を行っている。他方、国内人件費が高いことから、例えば公共施設のゴミ箱の回収時にIoTを活用し、必要な箇所だけ回収する仕組みを導入したり、道路標識のメンテナンスに活用したりと、対象範囲を広げることで、コスト削減につながる取組が進められている108。また、農業分野109では、施設園芸を中心に、ITを使ったコスト管理やハウス内の栽培環境を最適に制御するシステム技術を開発することにより、農業輸出大国になったとされている110。チェコについては、製造業でのロボット化の進展が進んでおり、また製造業やサービス業でのIoTの活用、サービス業でのプラットフォーム技術の導入が特徴である。このうち製造業のロボット化については、ドイツより相対的に安価な人件費水準であったことから自動車産業等の工場進出が進み、17年頃から賃金上昇率が上昇したことも追い風となり、ロボット化に向けた投資が進んだとの指摘がある111。
他方、アイルランドはデジタル技術への投資を行っている企業の比率が最も低い国である。アイルランド製造業のデジタル化に関する政府のレポートによれば、アイルランドの製造業の中でも、小規模事業者が多く市場規制が強い食料品・飲料部門(製造業の付加価値の23%程度を生産)等では、デジタル化をはじめとする新技術の導入に遅れが生じやすいことが指摘112されている。
このように、EU諸国の中でも、企業のデジタル技術導入状況は様々であり、かつ相対的に導入が進んでいる分野も異なるが、これは各国の産業構造や中核となる大企業の存在等が背景にあるものと考えられる。以下では、こうしたデジタル技術の活用状況と、企業や経済活動のパフォーマンスの関係をみていく。
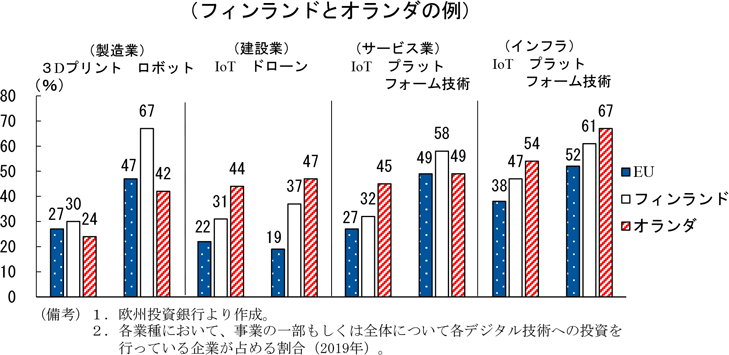
(2)デジタル技術と収益性・生産性
こうしたデジタル技術の導入が各国企業の収益性や生産性とどのように関連しているかについて、上述の欧州投資銀行調査から利用可能なデータの範囲で概観してみたい。まず、第2-2-40図は横軸にデジタル化進展度(調査回答企業が過去1年間にデジタル技術をどの程度導入したかを示す主観指標)、縦軸に過去1年間に利益を生み出した企業の割合を示す指標(左)及びTFP水準113(右)を取り、国別の傾向をみたものである。
この図はEU諸国の一部の国に限定して両者の関係をみたものであり、全体の傾向を示すものではない点に留意が必要であるが、少なくとも、デジタル技術の導入が進んでいるフィンランドやオランダは図の右上に位置し、他国と比較して高い利益やTFP水準にあること、逆に導入が相対的に遅れているフランスやポーランドは利益やTFP水準も相対的に低めであることが伺える。
次に、業種別にデジタル化進展度と利益を生み出した企業の割合の関係をみたのが第2-2-41図である。インフラやサービスで顕著であるが、全ての業種に共通して、デジタル化が進んでいるアメリカやフィンランドでは利益を生んでいる企業の割合も高く、デジタル化が進んでいないフランスやポーランドでは利益を生んでいる企業の割合が低い傾向にあることが示唆されている。第2-2-42図ではデジタル化進展度とTFP水準の関係を見ているが、4業種ともにフィンランドとオランダは高進展度、高TFP水準の傾向にあり、フランスとポーランドは低進展度、低TFP水準の傾向がみられる。
こうした傾向は一部の国における特徴に過ぎない点には留意が必要であるとともに、デジタル化と企業のパフォーマンスの間の因果関係を示すものでもない。例えば、国や業種によって企業規模の分布が異なるが、企業規模が小さい場合はデジタル技術導入の固定費負担が大きく導入が困難であることから、アメリカよりEU諸国で導入が遅れやすいことが指摘されている。また、小規模事業者ではTFP水準や収益性が低い傾向にあることから、結果的にデジタル化進展度と生産性等の間に一定の傾向がみられている可能性も考えられる。さらに、生産性や収益性とデジタル化の度合いが第3の要因、例えばマネージメントの質などによってつながりを持つ可能性も指摘114されており、デジタル化の影響をみるには、企業レベルのデータ等を用いたより詳細な分析が望まれる。
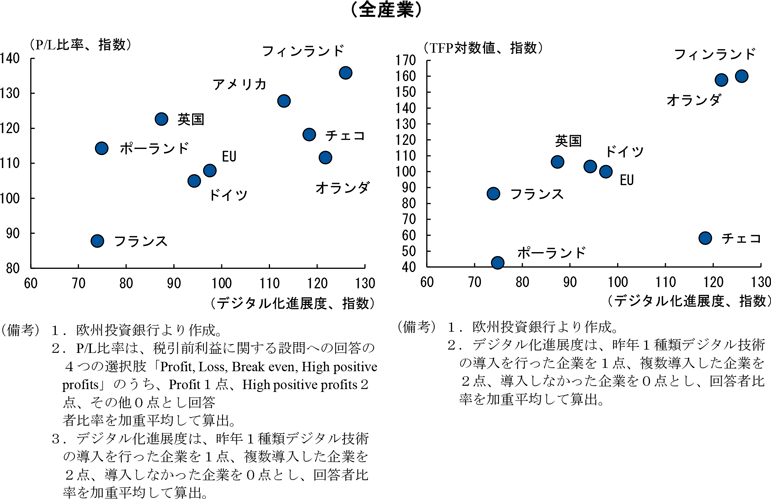
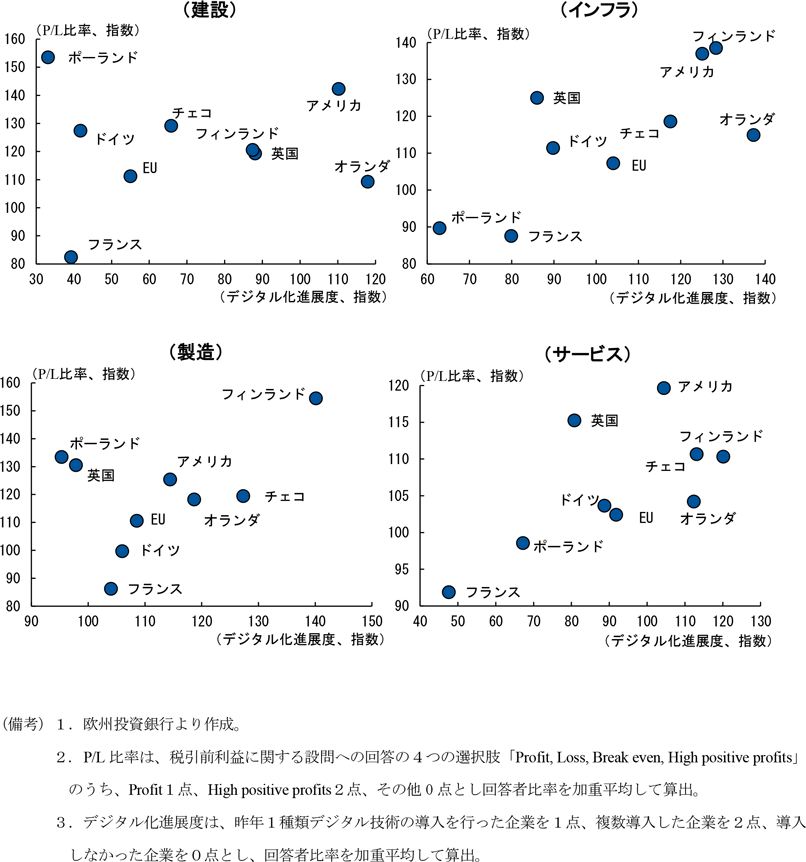
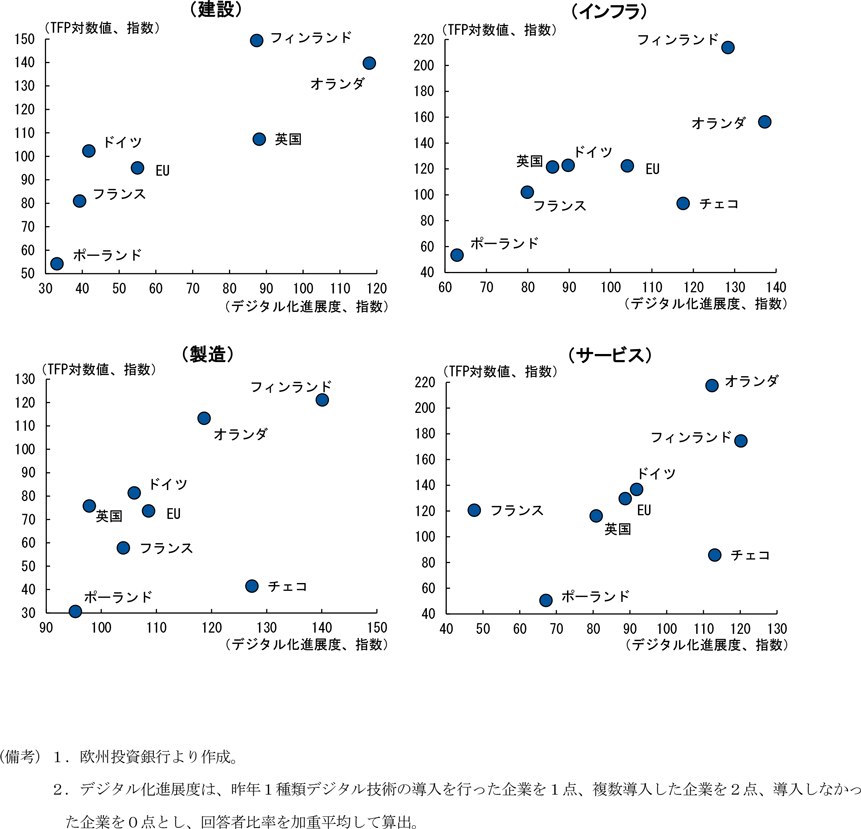
3.分析結果のまとめと示唆
本節では、国レベルや企業レベルのデータを用いて、ICT部門を中心に成長産業の動向を整理した。また、企業におけるデジタル技術の導入・活用状況がそのパフォーマンスに与え得る影響についても考察を行った。
国レベルのデータを用いた分析からは、ICT部門の付加価値や生産性上昇には、特にICTサービス部門での研究開発投資が鍵となり得ることが示唆された。我が国では、民間の研究開発投資に対する政府支援は相対的に手厚いものの、このところのICT部門の成長は他国と比べて限られていることが明らかとなった。
企業レベルのデータを用いた分析からは、以下の点が示唆された。市場規模がある程度大きい部門のうち売上の伸びが高いソフトウェア・コンピュータサービス、テクノロジー・ハードウェア及び機器、医薬品・バイオテクノロジーの3業種について、10年代後半の動向をみると、いずれの部門でも中国企業のプレゼンスが高まっている。日本企業のシェアは大きくは低下していないものの、特に前2業種で低下方向にあり、研究開発投資の伸びも相対的に低い。
さらに、ソフトウェア・コンピュータサービス、テクノロジー・ハードウェア及び機器、電子・電気機器では、14年の研究開発投資対売上比率や設備投資対売上比率と、その後5年間の売上の伸びの間には正の相関がみられた。また、3業種とも14年の研究開発投資対売上比率とその後5年間の従業員数の伸びの間に正の相関がみられたが、設備投資対売上比率との間には有意な関係がみられなかった。加えて、ソフトウェア・コンピュータサービスでは、14年の研究開発投資対売上比率とその後5年間の売上高利益率の変化の間に正の相関がみられた。これらの業種では研究開発投資により新たな財やサービスの開発に成功した企業が売上高を伸ばし従業員数も増加、さらにソフトウェア・コンピュータサービス利益率も改善する傾向がみられる。他方、成長業種とされる医薬品・バイオテクノロジーでは、高い研究開発投資比率と売上や雇用の伸びの相関は明確にはみられないことも明らかとなった。
デジタル分野は寡占が進みやすい分野であるだけに、イノベーションによる新規参入、ビジネスダイナミクスの活性化が、中長期的な成長の観点からは重要と考えられる。なお、アメリカの研究者の指摘115では、近年アメリカのビジネスダイナミクスが低下しているのは、市場の寡占化が進み、特に知識の伝播(knowledge diffusion)が進んでいないことによるとされており、こうした課題に政策的にどのように取り組んでいくかも重要な課題と考えられる。
民間企業でのデジタル技術の導入に関しては、欧米での比較の結果、業種や技術によって違いがあるものの、概してアメリカの方が技術導入が進んでいる場合が多いことが示された。因果関係は明らかでないものの、デジタル技術導入が進んでいる(遅れている)国の方が、収益性や生産性が高い(低い)場合が多い。デジタル技術の活用は、コロナによって働き方やマネージメントが大きく変化するなか、今後加速することが予想される。具体的には、AI/ソフトウェア関連技術の活用の広がり(移動制限やテレワーク普及によるデジタル通信手段への需要の急増と作業プロセスの無人化の促進など)が挙げられる。国際電気通信連合(ITU)のレポートによれば、コロナの影響により特にリモート会議やクラウドストレージへの需要が高まり、コロナ前後を比較するとZoomの1日当たり利用量は300%増、Webexは契約者が33%増、Teamsの月契約者が775%増となった116。EUのR&Dレポートでも20年代は感染症の拡大を契機として、AIによってコンピュータがデータを解析し、人間ができるより優れた方法を演繹する時代になる可能性が指摘されている。
こうした動向と併せ、現在のデジタル関連インフラのレジリエンスの向上も求められていくと考えられ、欧州諸国では政策面での取り組みも強化されている。例えば、復興基金の主要部分を占める復興・強靱化ファシリティ(1,300億ユーロ)でも、コロナ対応の一環としての5G投資の重要性を強調し、主要投資分野の一つとしている117。コロナ禍を契機に産業構造が変化していく中で、こうした各国の動向も踏まえながら、我が国も成長分野での強みを活かした設備投資や研究開発投資を促していくことが重要な課題と考えられる。
https://www.eib.org/attachments/eibis-methodology-report-en.pdf
https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00028.html
https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00028.html
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/5c20289f9e3588ea.html

