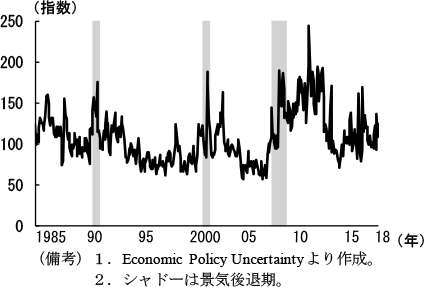第2章 主要地域の経済動向と構造変化(第2節)
第2節 アメリカ経済
アメリカ経済は、世界金融危機以降、約9年の長期にわたり景気回復が続いている。本節では、アメリカ経済が着実に回復している背景やその持続性について把握するため、アメリカ経済の最近の動向を振り返り、18年の見通しとリスク要因について整理する。また、第1章では民間債務の動向から世界経済のリスクを点検したが、長期にわたる金融緩和の中で積み上がったアメリカの民間債務の動向についても確認する。
アメリカ経済を概観すると、個人消費は、堅調な雇用・所得環境の下で増加が続いている。住宅市場は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかに増加している。企業部門をみると、良好な企業マインドや原油価格の上昇を背景とする鉱業部門の回復等から、生産は緩やかに増加している。労働市場では、雇用者数は増加、失業率は一段と低下し4%を下回る水準となっている。物価は、18年3月以降、携帯電話サービス価格の下落による一時的な押下げ要因がはく落するなど、サービス価格の上昇もあり、緩やかに上昇している。
1.アメリカ経済の動向
17年の実質経済成長率は、堅調な個人消費と民間設備投資に支えられ、一時的にハリケーン1の影響を受けつつも、前年比2.3%とこれまでの増勢を維持し堅調に推移している。18年1~3月期の実質経済成長率は、前期比年率2.2%と17年10~12月期の同2.9%から伸びが鈍化したが、これはハリケーンの復興需要等により17年10~12月期に自動車販売が一時的に増加した反動減等から個人消費の伸びが鈍化したことによる。こうした点を考慮すれば、アメリカ経済は安定して推移しているといえる(第2-2-1図)。
アメリカ経済の景気回復の長さを確認すると、世界金融危機以降、約9年の長期にわたり回復が続いている。今回の景気拡張局面は、09年6月を景気の谷として、106か月を超え、過去2番目の長さに達しているとみられる2(第2-2-2表)。
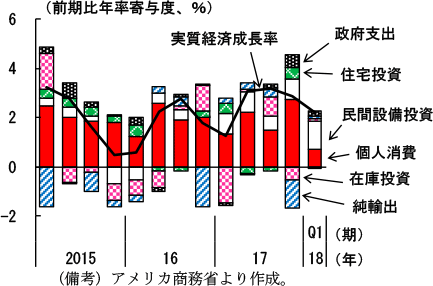
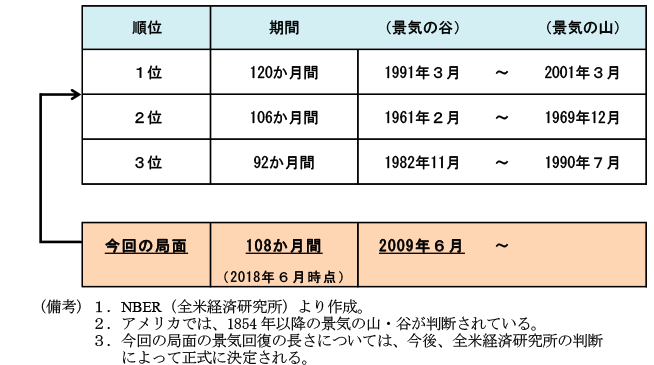
17年の実質経済成長率2.3%をCBO(議会予算局)の推計による潜在成長率と比較すると、17年の潜在成長率が1.6%であることから、17年の実質経済成長率は潜在成長率を大きく上回っている。なお、CBOは潜在成長率について、18年から22年の間は、税制改革を受けた労働供給や投資の拡大等により年平均2.0%に上昇し、23年から28年の間は、個人所得減税等の時限措置の効果のはく落等により年平均1.8%に低下すると見込んでいる。
また、四半期別のGDPギャップ3の推移をみると、GDPギャップは、世界金融危機時の深刻な景気後退により大幅なマイナスとなった後、17年の7~9月期になってようやくプラスに転じている(第2-2-3図)。
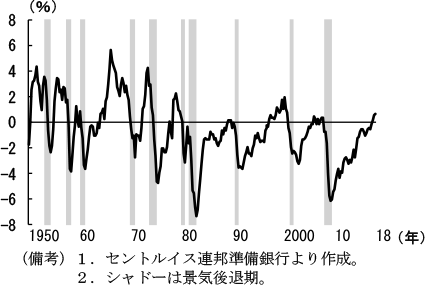
(1)個人消費
(個人消費は増加)
18年入り後の実質個人消費支出は、17年末の年末商戦における勢いが一服し、また、後述する自動車販売の弱めの動きも反映して、単月では前月比でマイナスとなる場面もあったが、堅調な雇用・所得環境の下で基調に変化はなく、全体としてみれば増加が続いている(第2-2-4図)。
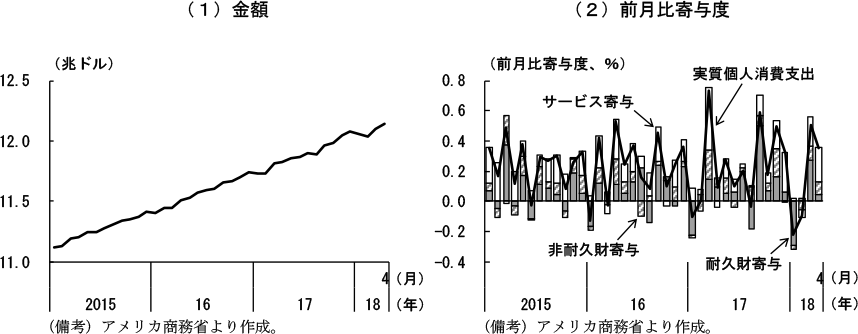
この堅調な個人消費の背景には、(1)良好な雇用環境4、(2)堅調な所得環境、(3)高水準の消費者マインドが挙げられる。このうち、所得環境についてみると、名目個人可処分所得は、雇用者報酬の安定した伸びに支えられ、17年10月には14.5兆ドルを超える勢いとなっている。18年1月以降は、17年末に成立した税制改革法(Tax Cuts and Jobs Act)の施行により、税負担額の減少も可処分所得を押し上げた(第2-2-5図)。また、消費者マインドについてみると、消費者信頼感指数5は、18年2月にみられた株式市場の不安定な動きにもかかわらず、同月に01年11月以来の高水準を記録するなど改善が続いている(第2-2-6図)。堅調な所得環境に加え、先行指標である消費者マインドも景気や労働市場の動向が好感されていることを背景に高まっており、今後も個人消費が堅調に推移することが示唆される。
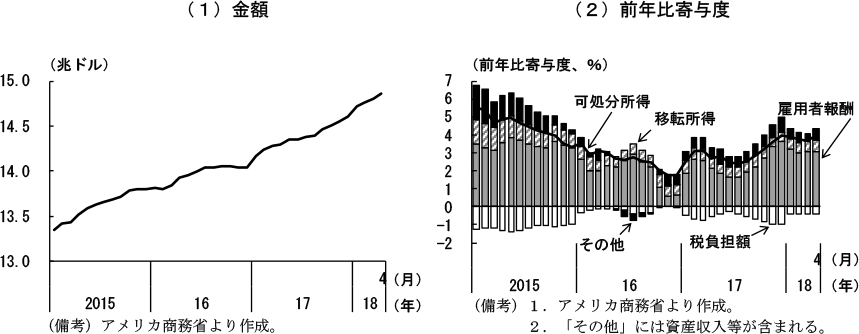
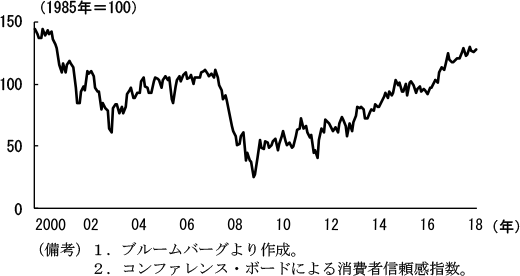
(自動車販売台数は弱めの動き)
自動車(新車)販売台数は、18年に入り弱めの動きがみられる。アメリカ国内の自動車販売台数は、16年に年換算1,746万台と高水準を記録した後、17年には減少に転じた。しかし、17年9月以降、ハリケーンによる復興需要から販売台数が上振れし、17年の水準自体は1,714万台と大きな落ち込みには至らなかった。18年前半は、17年にみられたハリケーンによる復興需要が一巡したことから、弱めの動きがみられるが、1,700万台前後と比較的高い水準での推移となっている(第2-2-7図)。
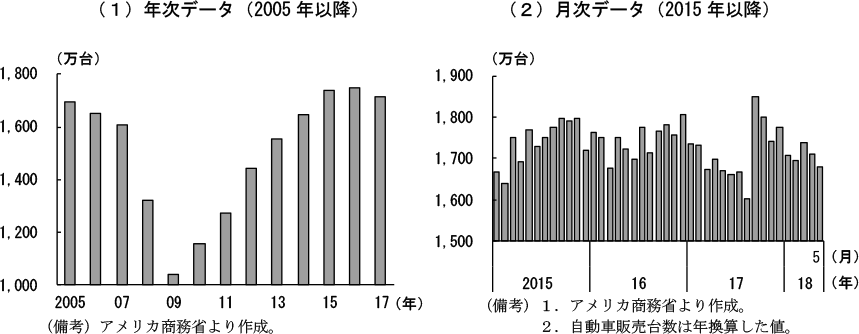
次に自動車販売台数の先行きを占うため、中古自動車価格と自動車ローン金利の動向を確認する。新車の代替財である中古車価格の低下や消費者の負担増となる自動車ローン金利の上昇は、自動車販売台数の下押し圧力となる。中古自動車価格は、16年から17年にかけて低下しており、17年の自動車販売台数減少の一因となったとみられるが、17年後半以降は上昇基調に転じている(第2-2-8図)。これは、17年の自動車販売台数が16年と比較して弱めであったことから、中古自動車の新たな供給が前年と比較して限定的となったことや、ハリケーンによる一時的な需要増による在庫の引締まり等が背景と考えられる。一方、自動車ローン金利は、FOMC(連邦公開市場委員会)による政策金利の引上げを背景に、17年後半以降、上昇基調にある(第2-2-9図)。
このように、自動車販売台数の先行きを取り巻く環境は、プラスとマイナスの両面があり、当面は横ばい圏内での動きとなることが見込まれる。
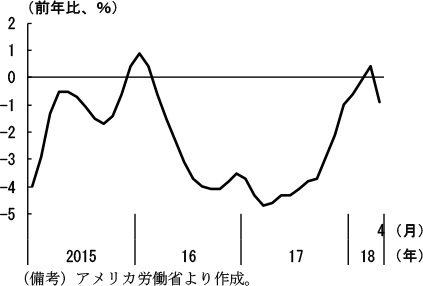
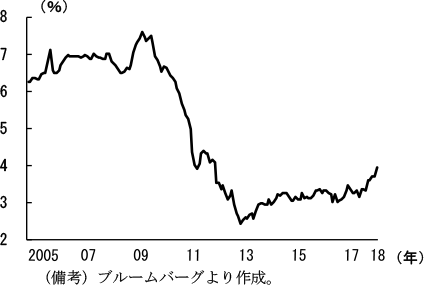
(住宅着工は緩やかに増加)
住宅着工件数は、17年後半にハリケーンの影響を受け、一時的に下振れした月もあったが、その後はハリケーンの復興需要等により持ち直し、18年入り後は復興需要の一巡にもかかわらず、3月に年換算130万件を超えるなど、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかに増加している。
住宅着工件数を一戸建てと集合住宅に分けてみると、構成比の高い一戸建てが18年入り後に90万件を超える月もあり、また、集合住宅も振れを伴いつつも40万件を超えて堅調に推移している(第2-2-10図)。住宅投資の動向と関連の深い新築住宅販売件数6をみると、緩やかに増加しており、年換算60~70万件程度となっている7。一方、住宅販売件数の約9割を占める中古住宅販売件数をみると、年換算550万件程度でおおむね横ばいで推移している(第2-2-11図)。新築住宅販売と比較して中古住宅販売が伸び悩む背景には在庫不足があり、中古住宅の住宅在庫・販売比率8をみると2000年以降で最も低い水準となっている(第2-2-12図)。
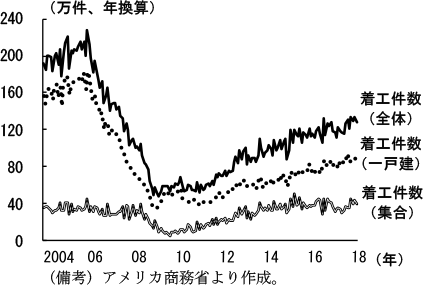
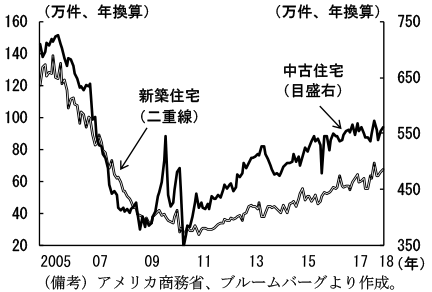
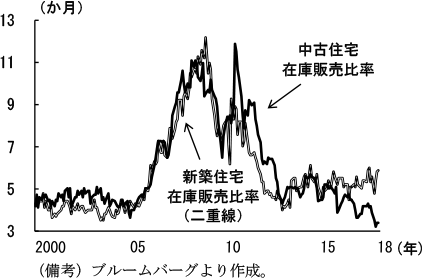
住宅着工件数の先行きを占うため、先行指標である住宅許可件数とNAHB住宅市場指数9をみると、住宅許可件数は増加傾向にあり、NAHB指数も高水準を維持していることから、当面、住宅着工は緩やかな増加が続くと期待される(第2-2-13図)。ただし、17年後半には3%台にとどまっていた住宅ローン金利が、18年入り後急上昇し4.5%に達している点は、今後の住宅需要の抑制要因となり得る(第2-2-14図)。また、消費者に対し住宅購入の意識を聞くミシガン大学の調査では、「住宅の買い時ではない」と回答した者の割合が増加しており、さらに、住宅が買い時ではない理由として「価格が高いため」と回答した者の割合が約2割にまで上昇している。近年の住宅価格の上昇は良好な雇用・所得環境による堅調な需要と建設労働者の不足等による供給制約の両面からもたらされており10、それが消費者の需要を抑制している可能性がうかがえる(第2-2-15図、第2-2-16図)。
以上より、住宅着工は、良好な雇用・所得環境の改善を背景に、当面は緩やかな増加が続くと期待されるが、住宅ローンや住宅価格の上昇の影響には留意が必要である。
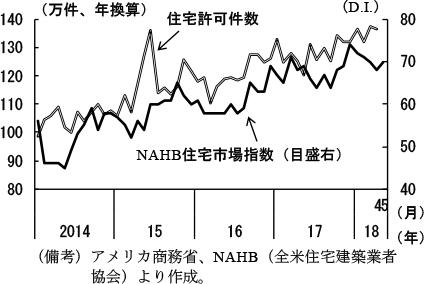
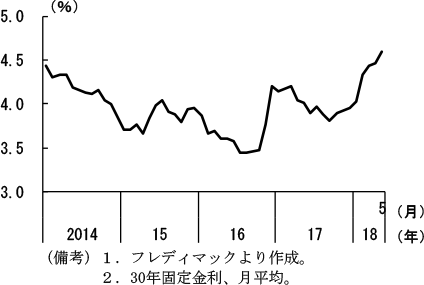
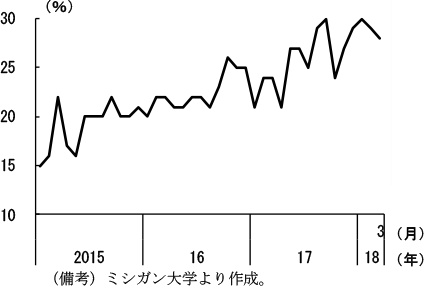
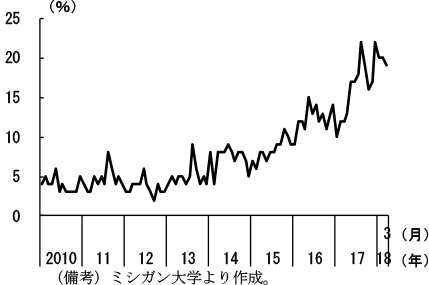
(2)改善が続く雇用情勢
雇用情勢は改善が続いている。非農業部門雇用者数の前月差は、17年は月平均18.2万人、18年は1月から5月までの平均で20.7万人となっており、雇用者数は堅調に増加している(第2-2-17図)。雇用者数の前月差を部門別にみると、財部門では、17年は月平均4.2万人と16年の月平均0.7万人から増加幅が拡大しており、18年入り後も製造業、建設業、鉱業等の3部門全てで堅調に増加している(第2-2-18図)。また、サービス部門では、16年末から情報サービス部門が幾分減少しているものの、雇用者数の多い専門サービス(コンピュータシステム設計や人材派遣サービス等)や教育・医療といった部門を中心に増加傾向にある(第2-2-19図)。
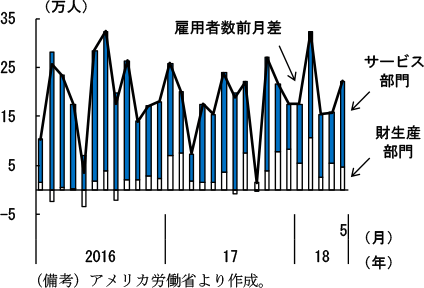
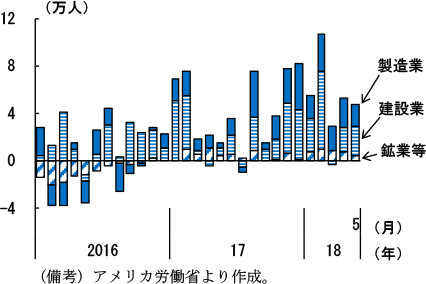
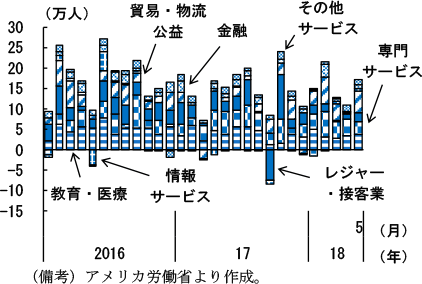
失業率(U311)をみると、09年10月の10.0%を最近のピークに徐々に低下し、18年5月には約18年ぶりに3.8%に達し、最近のボトムであった07年5月の4.4%、FOMC参加者が予測する長期失業率の4.5%(中央値)をも下回る水準となっている(第2-2-20図)。
雇用者数が増加し、失業率が低水準であるにもかかわらず、時間当たり賃金の伸びは、過去の景気拡張局面と比較して緩やかなものにとどまっている(第2-2-21図)。時間当たり賃金を財部門とサービス部門に分けてみると、財部門と比較して、サービス部門の伸びはやや加速傾向にあるが、そのサービス部門でみても過去の景気拡張局面でみられた3%を超える水準には達していない(第2-2-22図)。
この賃金の伸び悩みの一因として、先にみた失業率(U3)の低下では捉え切れない労働需給の緩み(スラック)の存在が考えられる12。すなわち、就業を希望しているが求職活動を行っていない者やフルタイムで働くことを希望しているがパートタイムでしか就労できなかった者が一定数存在し、見た目程には労働需給が引き締まっていない可能性がある。労働需給の引締まりを、これらの者の存在も加味した広義の失業率(U613)でみると、18年5月に7.6%にまで低下しており、08年9月のリーマン・ショック直前の最低水準7.9%を下回っている(前掲第2-2-20図)。
このように、通常の失業率に加え広義の失業率もリーマン・ショック前を下回って低下しており、労働需給の緩みが縮小してきていることが示唆され、賃金の伸びが高まる環境は整いつつあるとみられる。ただし、プライムエイジ(25~54歳)の労働参加率をみると、労働需給の引締まりが労働参加を促しているとみられ、女性の労働参加率が16年頃から、男性の労働参加率が17年末頃から上昇している(第2-2-23図)。全体の労働参加率はいまだに世界金融危機前の水準に戻っておらず、労働参加率の上昇が賃金上昇圧力を弱める可能性がある。また、アメリカでは失業率と賃金上昇率の関係を示すフィリップス・カーブが世界金融危機後ほぼ水平になっており、過去と比べ失業率の低下に対して賃金が上がりにくくなっている可能性がある点には留意が必要である(第2-2-24図)。
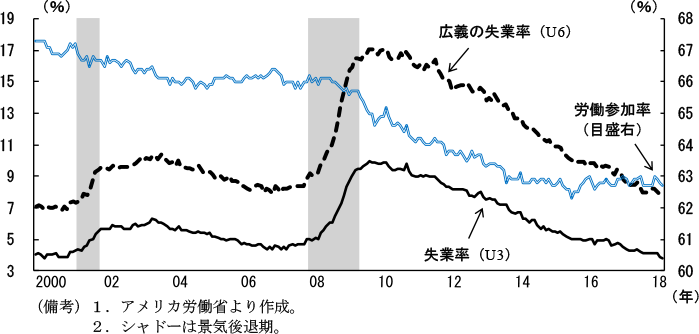
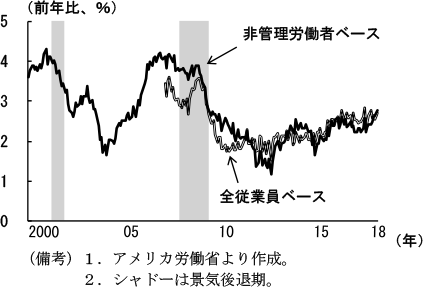
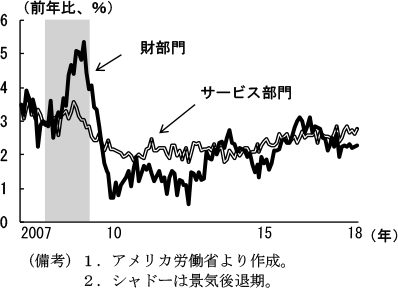
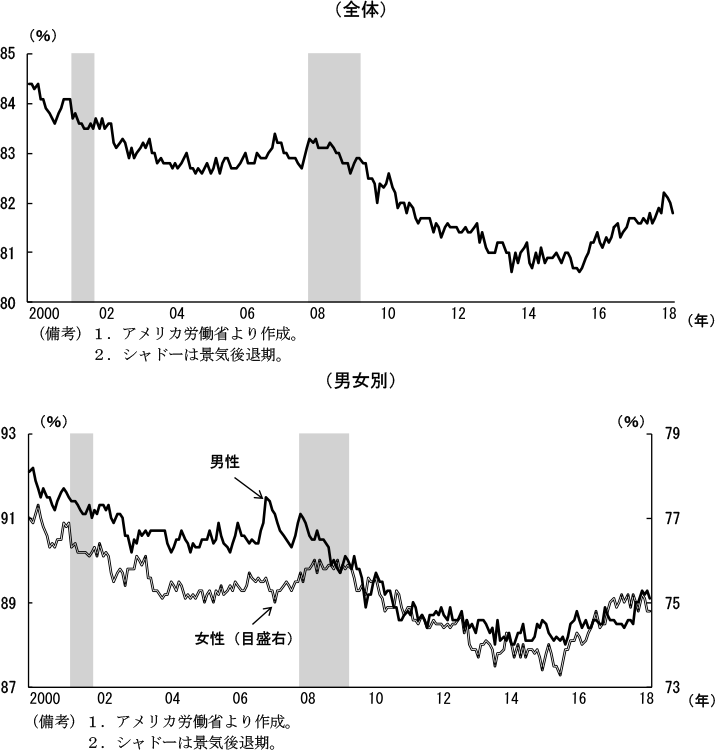
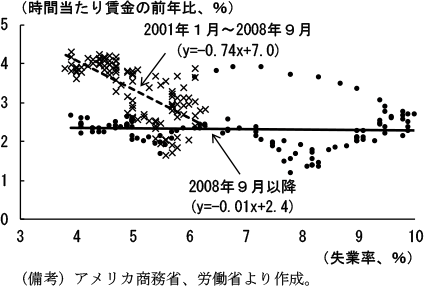
(3)企業部門の動き(生産・設備投資・輸出)
(鉱工業生産は緩やかに増加)
鉱工業生産は、17年に持ち直しの動きが鮮明となり、18年4月には過去最高であった14年11月の水準を超え、緩やかな増加が続いている。鉱工業生産増加の一因には、好調な鉱業関連の生産があり、特に近年、アメリカの原油生産量は増加の一途をたどっている。原油生産量は、17年11月に70年11月以来の日量1,000万バレル超え14となり、18年に入ってからも右肩上がりで生産量が伸びている。この背景にはシェールオイルの増産があり、このところのシェールオイルの生産は日量500万バレルを超え、原油生産量全体の過半を占めるに至っている(第2-2-25図、第2-2-26図、第2-2-27図、第2-2-28図)。
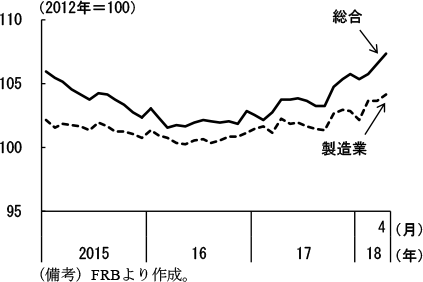
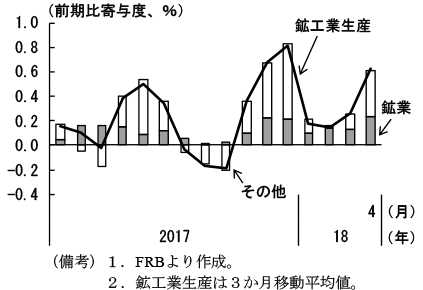
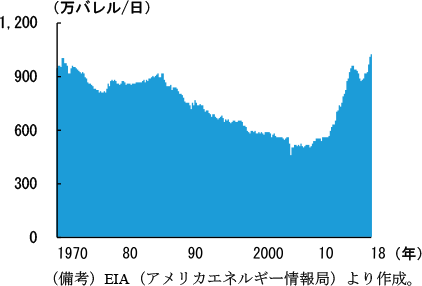
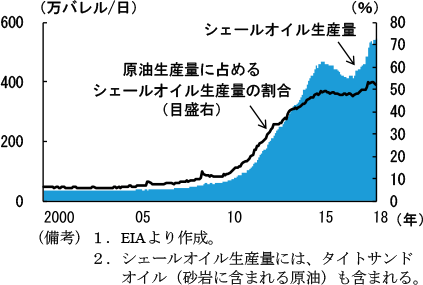
(堅調な企業マインド)
企業による景況感をISM製造業景況指数15でみると、16年初から上昇基調で推移しており、18年1月に実施された法人税改革に対する好感もあり、18年2月には60.8と04年5月の61.4以来の高い値となるなど堅調に推移している(第2-2-29図(1))。業種別にみても、17年以降、調査対象である18業種のうち平均8割を超える幅広い業種で業況の改善が報告されている。また、新規受注指数をみると、17年半ばから60を超える高い水準にあり、新規輸出受注指数についても、このところ幾分低下しているものの、過去に比べ高い水準にあることから、内外需とも好調であり、今後も企業活動は拡大していくものと見込まれる(第2-2-29図(2))。非製造業景況指数も同様に、18年に入ってからも高水準で推移しており、堅調さを示している(第2-2-29図(1))。
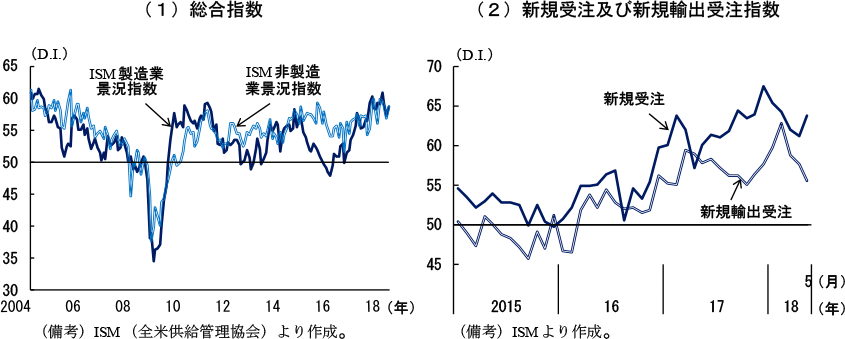
(設備投資は緩やかに増加)
民間設備投資は、17年以降、ウェイトの大きい機械・機器投資に主にけん引され、緩やかに増加している(第2-2-30図)。機械・機器投資の内訳をみると、特に情報機器が増加に寄与している(第2-2-31図)。構築物投資は、17年8~9月のハリケーンの影響もあり、7~9月期にマイナスとなったが、10~12月期以降持ち直している。構築物投資の内訳をみると、鉱業に関する採掘・掘削が一貫してプラス寄与となっている(第2-2-32図)。また、民間設備投資全体を鉱業関連とそれ以外に分けてみると、鉱業関連が17年以降プラス寄与を続けている(第2-2-33図)。先にみたとおり、シェールオイルを始めとする原油生産が好調であり、関連設備への投資が増加しているためとみられる。
民間設備投資の先行きを占うため、先行指標の動きを確認する。まず、機械・機器投資の先行指標であるコア資本財受注(民間航空機を除いた非国防資本財)をみると、17年末頃から減速し、18年初に一時前期比マイナスとなったものの、その後は持ち直しプラスでの推移となっている(第2-2-34図)。構築物投資の先行指標である民間非住宅建設投資についても、17年前半は減少傾向にあったが、17年11月に増加に転じプラス圏で推移している(第2-2-35図)。また、民間設備投資と相関の高い企業収益の動向をみると、企業収益(税引き後)は、17年7~9月期以降増加している(第2-2-36図)。さらに、鉱業関連の動向に着目すると、原油価格(WTI)が17年半ばから上昇を続けており、採算性の高まりから油井掘削リグ稼働数もこれにラグを伴い17年末より緩やかに増加し始めている(第2-2-37図)。これらから、民間設備投資は、当面も増加傾向で推移するとみられる。ただし、18年1月に実施された連邦法人税率の引下げ等を内容とする法人税改革が、企業の資本コスト(企業が投資により獲得しなければならない利益の最低水準)の引下げを通じて、どの程度設備投資を促進するかについては不確実性がある。例えば、CBOは、連邦法人税率の引下げ等により、実質民間設備投資が18年に0.2%ポイント、19年に0.4%ポイント押し上げられると試算しているが、企業が投資に対するインセンティブの変化にどの程度反応するかといった点等に不確実性があるとしている。
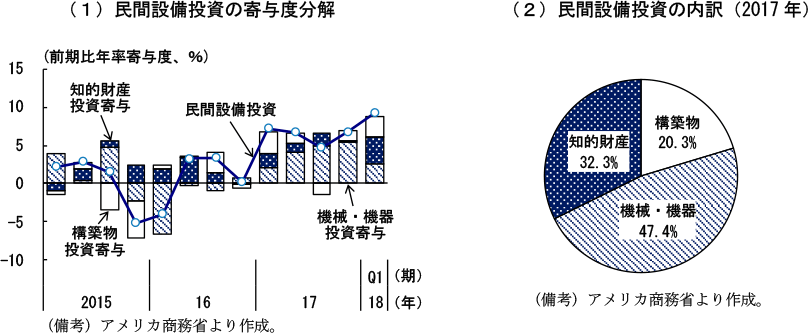
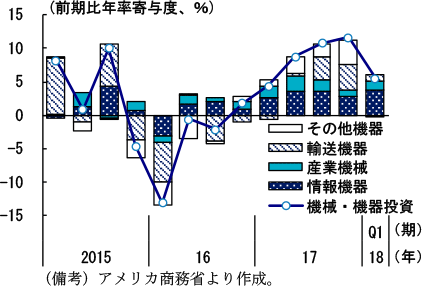
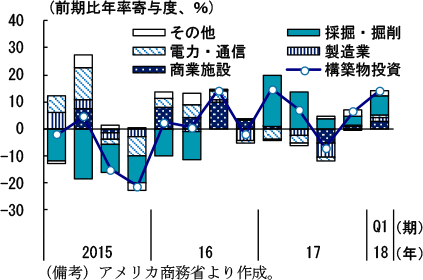
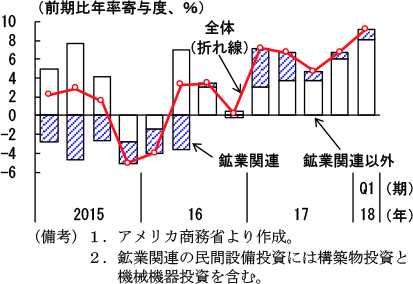
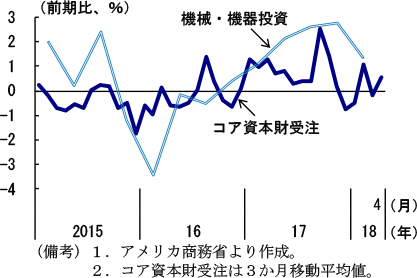
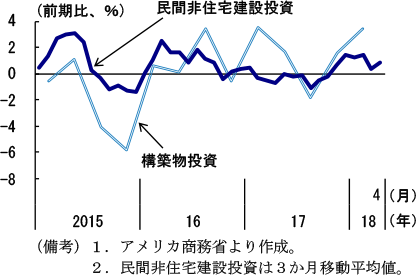
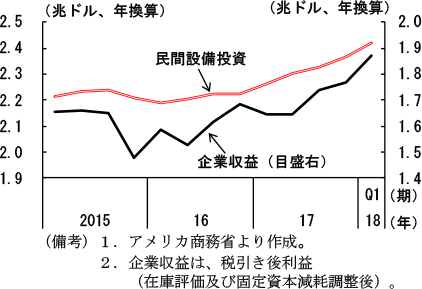
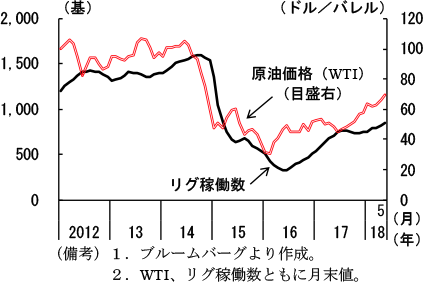
(財輸出は緩やかに増加)
次に、アメリカの貿易の最近の動きについて確認する。財輸出(通関ベース、実質、季節調整値)は、14年頃からは中国等の成長鈍化等を背景に1,200億ドル前後での横ばい圏内での動きとなったが、18年に入り緩やかに増加している(第2-2-38図、第2-2-39図)。品目別では資本財(産業機械、民間航空機、半導体等)や工業原材料(石油製品、燃料油等)が、国・地域別ではメキシコ、EU向け等が増加している(第2-2-40図、第2-2-41図)。

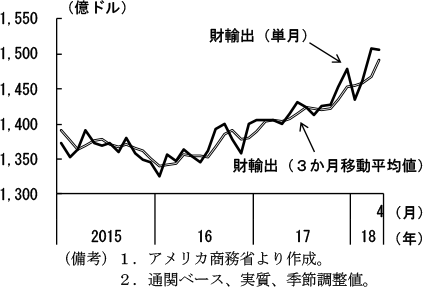
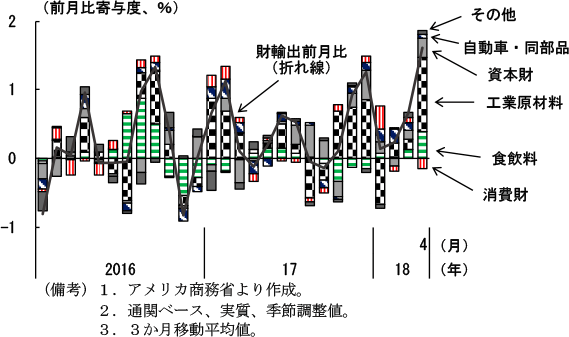
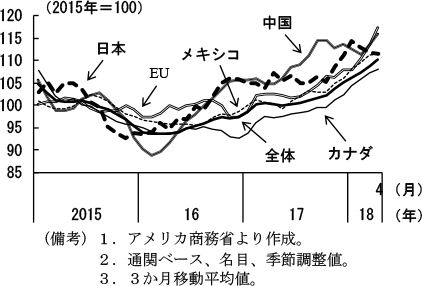
財輸出の中でも、シェールオイルの増産を背景に、原油や燃料油等のエネルギーの輸出が大幅に増加しており、17年後半には財輸出の約10%に達している(第2-2-42図)。エネルギーの輸出先の構成をみると、メキシコ、カナダ、ブラジル、中国の順に高く、特に中国は12年の1.8%から17年には6.2%に拡大している(第2-2-43図)。後述するように、米中の通商交渉ではアメリカから中国へのエネルギー輸出の拡大が合意されており、今後もアメリカのエネルギー輸出は増加していくものと見込まれる。
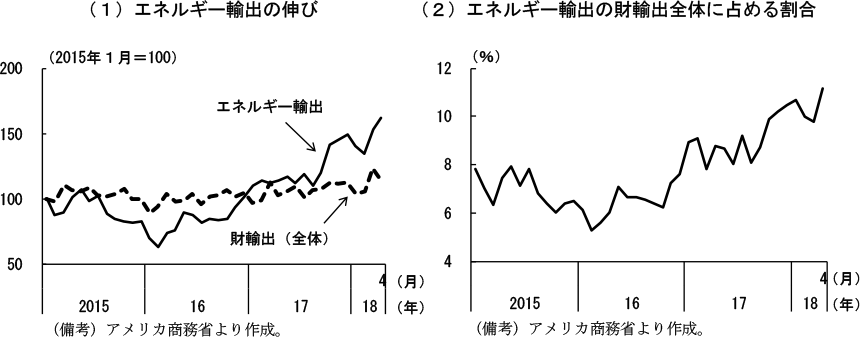
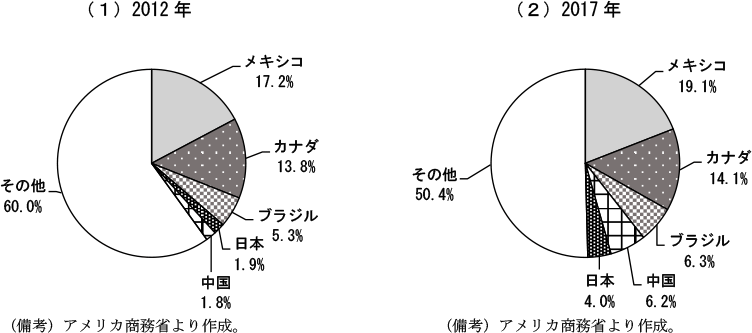
(4)トランプ政権の通商政策
アメリカの経常収支・GDP比は09年以降、-2%台で安定して推移しており、経常収支の大宗を占める貿易収支を国別にみても大きな変化はない(第2-2-44図、第2-2-45図)。しかし、トランプ政権は、中国等の間で貿易収支の赤字額が拡大していると主張し、アメリカにとっての輸出障壁を取り除き、「公正かつ互恵的な貿易取引の実現」を目指し、「既存の貿易慣行を見直す」として新たな通商交渉に乗り出している。18年3月23日には安全保障上の脅威を理由に鉄鋼及びアルミニウムへの追加関税措置を実施、5月23日に自動車輸入がアメリカ国内の安全保障に与える影響について調査を開始、6月15日には知的財産権の侵害等を理由に中国からの500億ドル相当の輸入品への関税引上げを表明、さらに6月18日にはトランプ大統領からUSTR(通商代表部)に対し、2,000億ドル相当の中国からの輸入品に10%の追加関税を課す検討指示が出された。また、94年にアメリカ、カナダ及びメキシコ間で締結された自由貿易協定であるNAFTA(北米自由貿易協定)についても17年8月から再交渉が進められている。以下では、トランプ政権の貿易政策について整理し、その影響を概観する(第2-2-46表)。
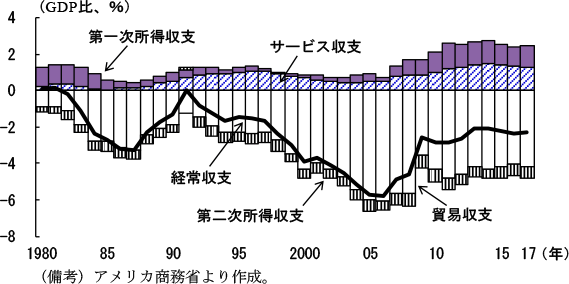
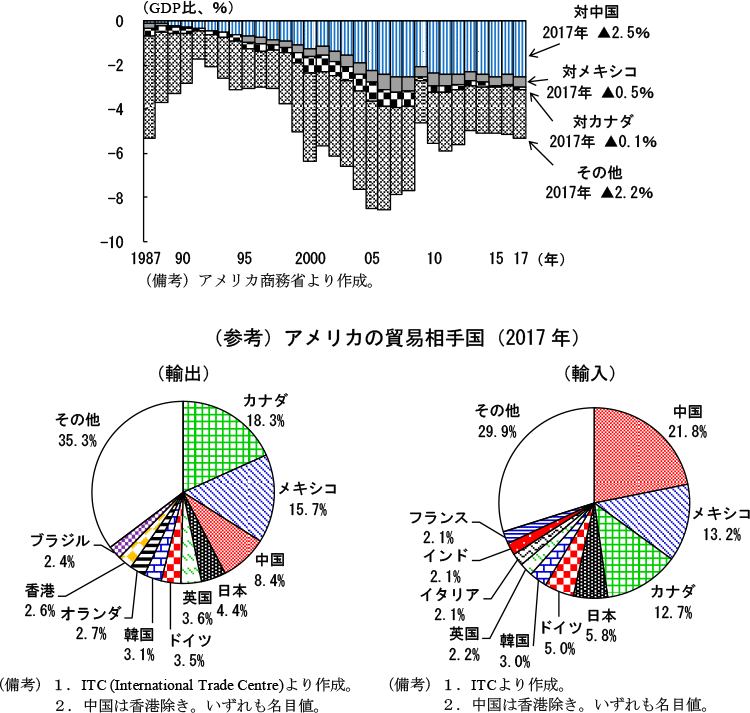

(鉄鋼・アルミニウムへの追加関税)
アメリカ政府は、18年3月8日、1962年通商拡大法第232条16に基づき、「安全保障上の脅威」を理由に、鉄鋼の輸入に25%、アルミニウムの輸入に10%の関税を賦課するとの措置を公表し、3月23日に本措置を発動した17。これに対し中国は、4月2日、本措置への対抗として、豚肉、ワイン等のアメリカからの輸入品128項目に対し最大25%の関税の賦課を実施した。
アメリカの全輸入額に占める鉄鋼及びアルミニウム輸入額の割合は4%弱と比較的小さく18、加えて、アメリカの鉄鋼及びアルミニウムの主要輸入先19であるカナダやブラジル等が18年5月末までは追加関税の適用除外とされたこともあり、アメリカ経済全体にはこれまで大きな変動はみられていない(第2-2-47表、第2-2-48図)。ただし、カナダやEUといった追加関税の適用除外となっていた国も18年6月より適用対象となったことから、本措置の経済全体に与える影響が拡大する可能性もあるため、その動向には留意が必要である20。
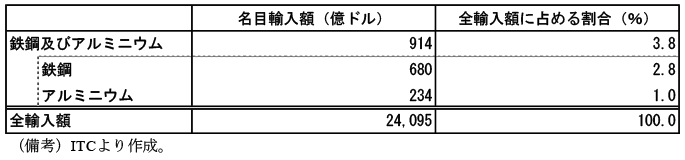
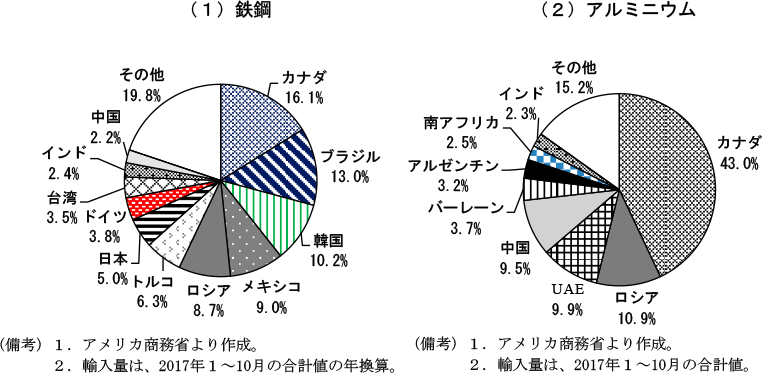
(中国からの輸入品に対する追加関税)
アメリカ政府は、18年6月15日、1974年通商法第301条21に基づき、技術移転の強要、知的財産権の侵害を理由に、中国からの輸入品に25%の追加関税を課す措置を公表した。対象リストには、年間輸入額500億ドル相当、1,102項目(産業機械や電子部品等)が挙げられている22。18年7月6日から340億ドル相当、818項目に課税し、残りの160億ドル相当、284項目については今後、パブリック・ヒアリング等を経て対象項目の最終的取り扱いと発動期日が決定される予定である。
これに対し中国政府は、18年6月16日、アメリカと同額かつ発動の時期を合わせ、18年7月6日より500億ドル相当、545項目(大豆、自動車等)に25%の追加関税を課す旨を公表した。残りの160億ドル相当、114項目(化学製品、石油等)については、最終的取り扱いと発動期日を今後決定するとしている。
トランプ大統領は、こうした中国の対応を受け、18年6月18日、USTRに対し更に2,000億ドル相当の中国からの輸入品に10%の追加関税を課す検討を行うよう指示した23。
アメリカの中国からの年間輸入額が約5,000億ドル(17年)であることから、500億ドル相当は年間輸入額の約1割、仮に合計で2,500億ドル相当となれば約5割に相当する。一方、中国側の措置については、アメリカの中国への年間輸出額が約1,300億ドル(17年)であることから、500億ドル相当は、年間輸出額の約4割に相当する(第2-2-49図)。
アメリカと中国は、18年5月3日及び4日に第1回の貿易協議を開催し、その後の18年5月18日及び19日の第2回貿易協議後の共同声明で、アメリカと中国との間の貿易赤字を実質的に減らすために効果的な手段をとること、アメリカからの農産品及びエネルギーの輸出を増加させることなどの合意内容を公表した。アメリカと中国の間では、引き続き貿易協議が進められているが、双方による関税引上げの応酬により、今後の両国間の協議の行方は不透明感が増している。
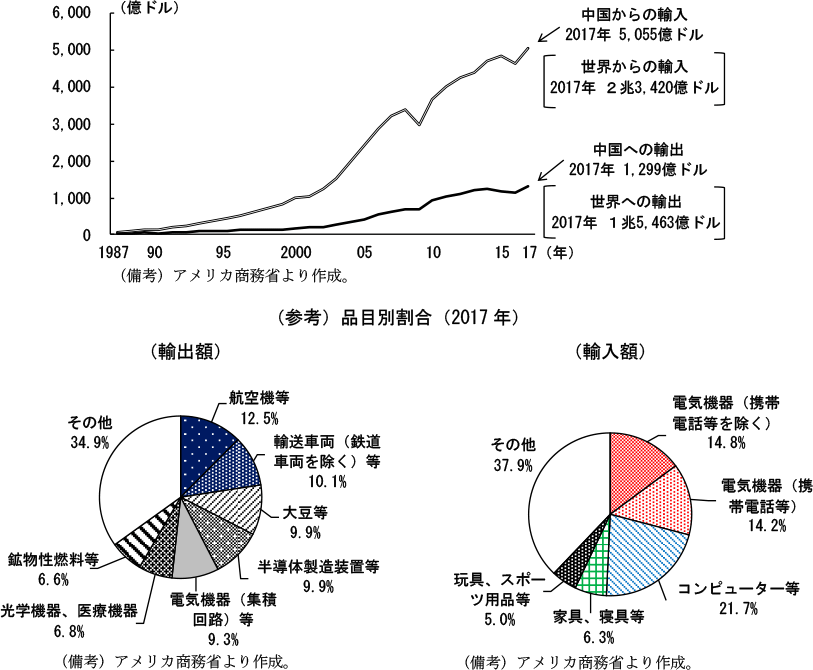
(NAFTAの再交渉)
アメリカ政府は、17年8月、「北米における貿易不均衡」を是正するとして公正な取引の確保を目指し、NAFTAの再交渉を開始した。交渉会合が17年8月から開催されているが、交渉は難航している。特に自動車分野の原産地規則については、メキシコとの間で自動車・同部品の貿易収支赤字が拡大していることなどを主張し(第2-2-50図)、アメリカ政府は、自動車・同部品に対する域内調達比率及びアメリカ産製品の割合を引き上げるよう要求している。
アメリカ政府は、18年5月23日に通商拡大法第232条に基づき、自動車・同部品の輸入が「アメリカの安全保障」に与える影響について調査を開始した。また、6月1日には、カナダ、メキシコからの鉄鋼及びアルミニウム輸入に対する追加関税の適用を開始した。これらの動きは、今後NAFTA再交渉の行方にも影響を与えていくものとみられる。
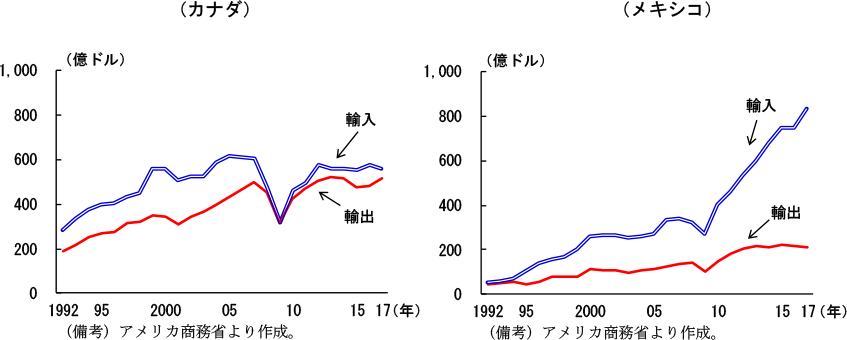
このようなアメリカの通商政策を取り巻く不確実性は、企業マインドに悪影響を与えるほか、企業活動のグローバル化が進む中で、貿易制限的な通商政策が推し進められた場合には、相手国による報復措置も加わり、貿易・投資の縮小をもたらし、世界経済全体にマイナスの影響を与える。今後の通商政策の動向には十分な注意が必要である。
(5)金融政策の正常化
FOMCは、改善を続ける労働市場や、中期的に前年比2%付近で推移すると見込む物価上昇率を踏まえ、金融政策の正常化に向け緩やかなペースでの政策金利の引上げと保有資産の縮小を進めている。
アメリカ経済は回復を続けており、労働市場においては、雇用者数が力強く増加し、失業率は低下傾向となっている。また、物価情勢については、18年3月以降、携帯電話サービス価格の下落による一時的な押下げ要因がはく落するなど24、サービス価格の上昇もあり、PCE総合及びPCEコアデフレーターともに前年比2%近辺で推移している(第2-2-51図、第2-2-52図)。FOMCは、金融政策の緩やかな調整を継続する方針であり、その下で、今後も景気の回復と労働市場の改善が続き、物価はFOMCの目標とする前年比2%近辺で推移すると見込んでいる(第2-2-53表)。
こうした認識に基づき、FOMCは政策金利であるFFレート(フェデラル・ファンド・レート)の誘導目標水準を17年に3回引き上げ、18年には3月と6月にそれぞれ0.25%ポイント引き上げ、1.75%~2.00%としている(第2-2-54図)。
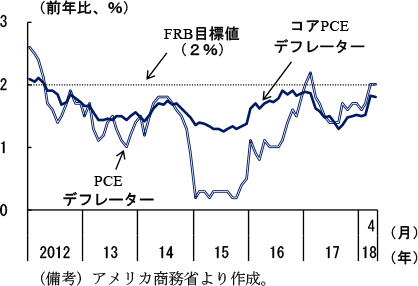
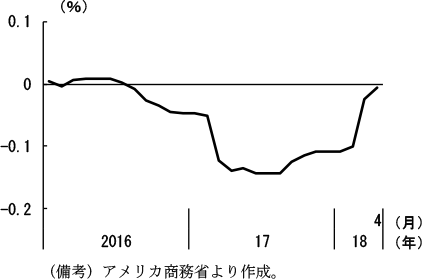
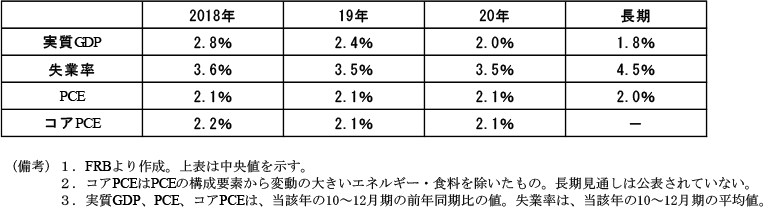
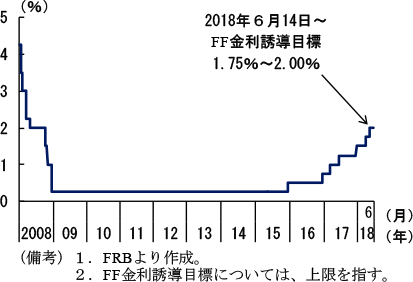
また、今後のFFレートの引上げについて、FOMC参加者による18年末の見通しをみると、その中央値が2.375%とされていることから、毎回の利上げ幅を0.25%と仮定すると18年中に更に2回の引上げが見込まれている(第2-2-55図)。
他方、保有資産の縮小については、17年9月の会合において、再投資政策の見直しを10月から開始することが決定25されて以降、漸進的な縮小が続けられている。FRS(連邦準備制度)のバランスシートの資産規模は、世界金融危機直前の08年9月時点では約0.9兆ドルあったが、再投資政策見直し直前の17年9月末時点で約4.5兆ドルとおよそ5倍に達していた。再投資政策見直し後の18年4月末時点で資産規模は約4.4兆ドルであり、満期を迎えた保有債券の再投資額を徐々に削減する形で極めて緩やかなペースで縮小が進められている(第2-2-56図)。なお、最終的な資産規模については、17年6月の「金融政策正常化に関する原則と方針」の追加文書(Addendum)において、「金融政策の効率的かつ効果的な運営に必要となる資産保有水準に達したと判断するまで、漸進的かつ予測可能な方法で資産縮小を続ける」と述べるにとどまっている。
アメリカ経済においては、減税や歳出拡大といった拡張的な財政政策が講じられており、市場においても金利上昇がアメリカ経済のリスクとして、これまで以上に強く意識されている。こうした環境下で、FOMCによる利上げは、ペースが急激な場合には景気後退のリスクに、逆に緩やか過ぎる場合には景気過熱と資産価格の行き過ぎた上昇のリスクとなることから、今後の政策金利の引上げペースについては、一層の留意が必要である。
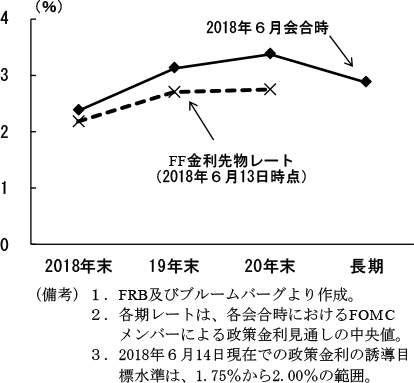
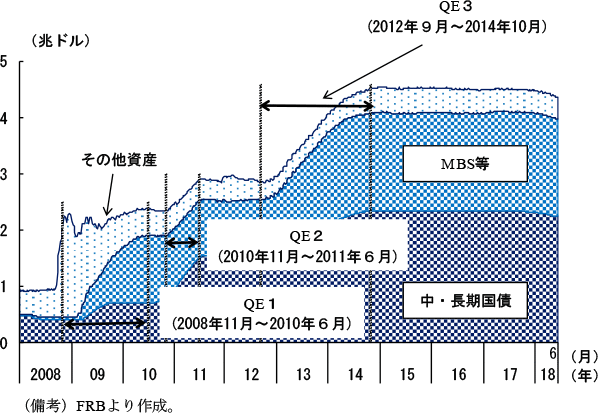
(6)トランプ政権下の財政政策
トランプ政権にとって2年目となる2018年度予算(17年10月~18年9月)は、5回の暫定予算26(Continuing Resolution)の編成を経て、ようやく18年3月23日に成立したが、18年度には、(1)10年間で約1.5兆ドルの減税を見込む税制改革(18年1月)(第2-2-57表)、(2)18・19年度予算における歳出上限の3,000億ドル引上げ(18年2月)、(3)19年3月までの債務上限の適用延期(18年2月)、(4)10年間で少なくとも1.5兆ドルを見込むインフラ投資計画(18年2月)等の財政面で注目すべき政策が打ち出されている。以下では、これらの動向を概観し27、アメリカ経済や財政収支への影響について確認する。
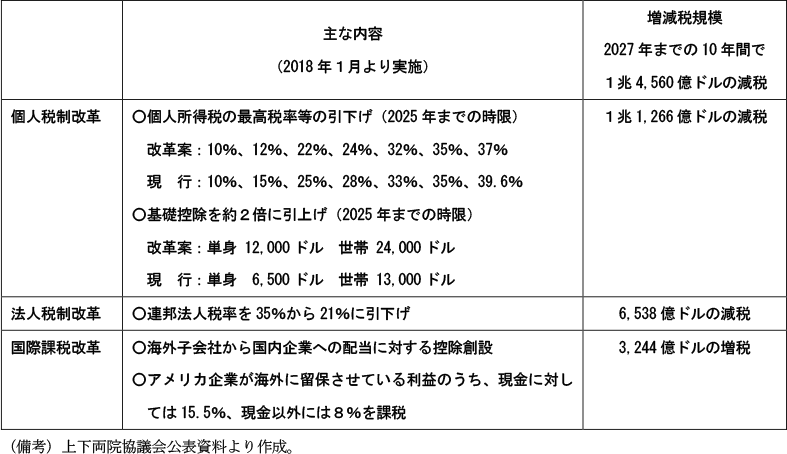
(歳出上限の引上げ、債務上限の適用延期)
アメリカでは、財政赤字の抑制を目的として、11年に予算管理法(Budget Control Act of 2011)が制定され、各年度の予算のうち裁量的経費に歳出上限が設定されている。12年度から21年度の各年度に国防と非国防の別に歳出上限28が設けられており、13年度から21年度はこの国防と非国防の上限それぞれから更に追加削減を行うとの措置が採られている。これまで歳出上限は、別途法律を定めることで毎年度引き上げられてきており29、18年度及び19年度の歳出上限についても、18年2月に成立した2018年超党派予算法(Bipartisan Budget Act of 2018)により、合計約3,000億ドルの引上げがなされた(第2-2-58図)。歳出上限の引上げは財政赤字の拡大をもたらし、金利上昇圧力を高める一方で、短期的には景気刺激効果を有する側面もある。
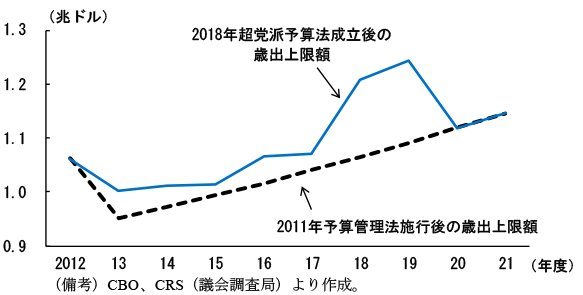
また、アメリカでは連邦政府の債務残高の上限額が、1917年の第二自由公債法(Second Liberty Bond Act of 1917)により規定されており30、実際の債務残高がこの法定上限を超えた場合、国債の新規発行を行うことができず、国債の元利払いを含め予算執行に支障が生じることとなる。2018年超党派予算法には債務上限の扱いについても盛り込まれており、同法の成立により、債務上限の適用が19年3月1日まで一時的に停止31されることとなった(第2-2-59図)。債務上限問題は、国債の格付にも影響を与え得ることから、19年3月1日の期限が迫るにつれ、その動向が注目されることになる。
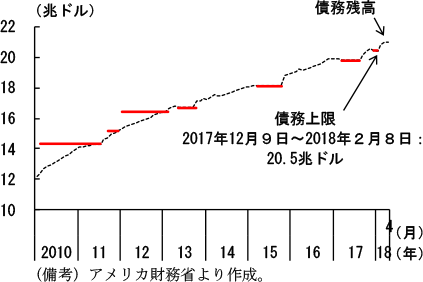
(インフラ投資計画)
トランプ政権は、18年2月、今後10年間で官民合わせて少なくとも1.5兆ドルの投資を見込んだインフラ投資計画を公表した。インフラ投資に対する連邦政府の歳出は、19年度から28年度までの10年間で約2,000億ドルが予定されており、その他については地方及び民間の負担により実現すると見込まれている。連邦政府による約2,000億ドルの内訳は、(1)地方・民間への競争的なインセンティブ補助金、(2)地方におけるインフラ投資のために必要な額の準備、(3)革新的なプロジェクトへの支出、(4)その他(既存の連邦政府のインフラプログラムの拡充等)となっている。これらのうち予算配分が多いものは(1)及び(2)であり、それぞれ1,000億ドルと500億ドルが見込まれている。また、連邦政府の歳出のピークは19年度が見込まれており、約2,000億ドルのうち約450億ドルの歳出が行われる予定である(第2-2-60図)。
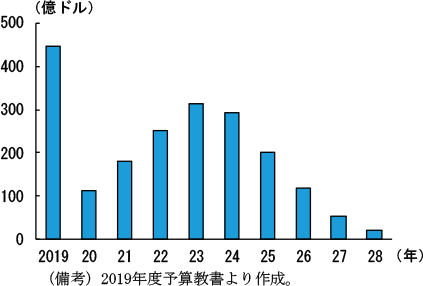
(税制改革、歳出上限引上げ、インフラ投資計画のマクロ経済への効果)
こうした拡張的な財政支出がアメリカのマクロ経済へ与える影響を確認する。CBO32は18年1月の税制改革と18・19年度の歳出上限引上げについて、それぞれ実質GDP(水準)に与える影響を試算している。税制改革の効果については、法人税率の引下げによる設備投資の拡大や個人所得税率の引下げによる労働供給の拡大等により、18年から28年にかけて実質GDPを年平均0.7%増加させると試算している。実質GDPの押上げ効果は、18年に0.3%、19年に0.6%の後、22年に1.0%とピークを付け、その後は、個人所得税率の引下げが25年までの時限措置であることや、財政赤字拡大による金利上昇が民間設備投資の一部をクラウドアウトすることから、逓減していくものと見込まれている(第2-2-61図)。また、歳出上限の引上げについては、実質GDPを18年に0.3%、19年に0.6%引き上げると試算している。
インフラ投資計画については、大統領経済報告(18年2月)において、インフラ投資の拡大による公的資本サービスの増加に伴い、民間資本の生産性も上昇することから、企業も設備投資を増やすこと、また、労働者が利用できる公的資本サービスが増加することで労働生産性が上昇することにより、向こう10年にわたり、年平均で実質GDP(水準)を約0.1~0.2%押し上げると試算されている。
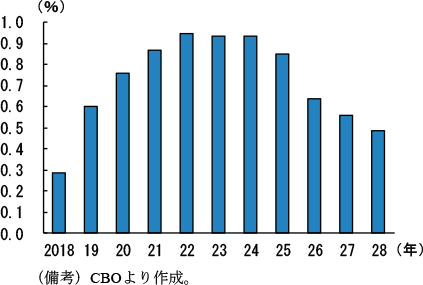
(連邦政府財政への影響)
CBOの見通し33により、こうした積極的財政政策が連邦政府財政に与える影響をみると、財政収支・GDP比は、17年度の実績値-3.5%から、18年度-4.0%、19年度-4.6%へと悪化が見込まれている(第2-2-62図)。また、連邦政府の債務残高・GDP比は、17年度の実績値76.5%から、見通し期間中一貫して拡大し、18年度78.0%、19年度79.3%となった後、見通し最終年度の28年度には96.2%にまで上昇すると見込まれている(第2-2-63図)。
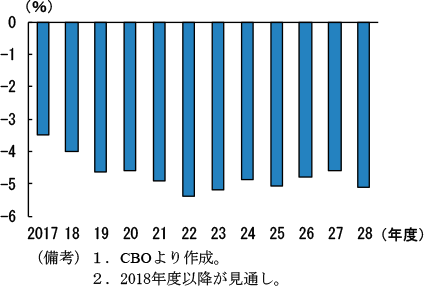
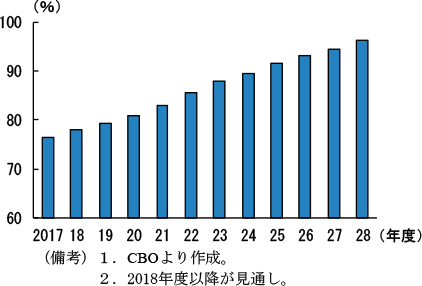
2.アメリカにおける民間債務の動向
第1章では民間債務の動向から世界経済のリスクを点検した。ここではアメリカにおける民間債務の動向をやや詳細にみていく。アメリカにおける民間債務残高は、17年末時点で、金額では約46兆ドルまで増加しているが、GDP比ベースでみると約230%と世界金融危機時の水準から低下し、14年以降横ばいとなっている(第2-2-64図)。民間債務残高を家計部門、企業部門、金融部門に分けてみると、金額ベースでは、金融危機時の最高水準を超えているのは家計部門と企業部門であり、また、GDP比ベースでみると、家計部門は金融危機時の最高水準は超えておらず、横ばいとなっている一方で、企業部門は世界金融危機時の水準を既に超過し、増加基調となっている(第2-2-65図)。
このため以下では、アメリカの家計部門と企業部門に焦点を当て、それぞれ複数の指標からその動きと背景をみていく。
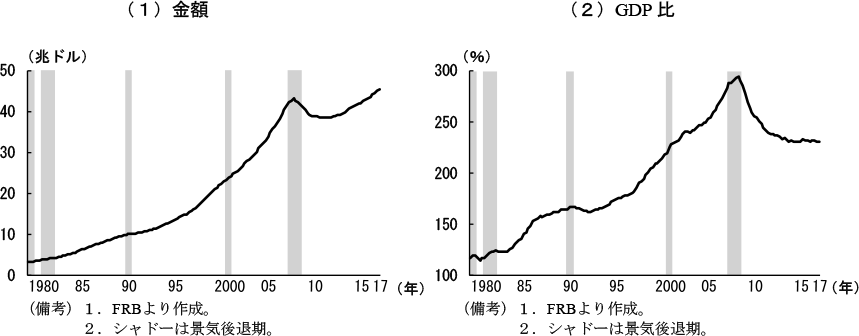
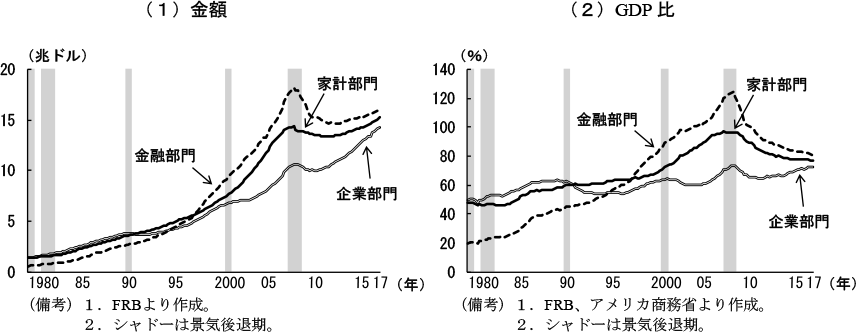
(i)アメリカの家計部門の債務
(家計部門の債務の詳細)
家計部門の債務を詳細にみると、債務の構成比は住宅ローンが約70%と最も多く、次に学生ローン、自動車ローンと続いている。債務残高を金額ベースでみると世界金融危機時の過去最高水準を超えて推移しているが、可処分所得比でみれば12年以降ほぼ横ばいで推移している(第2-2-66図)。
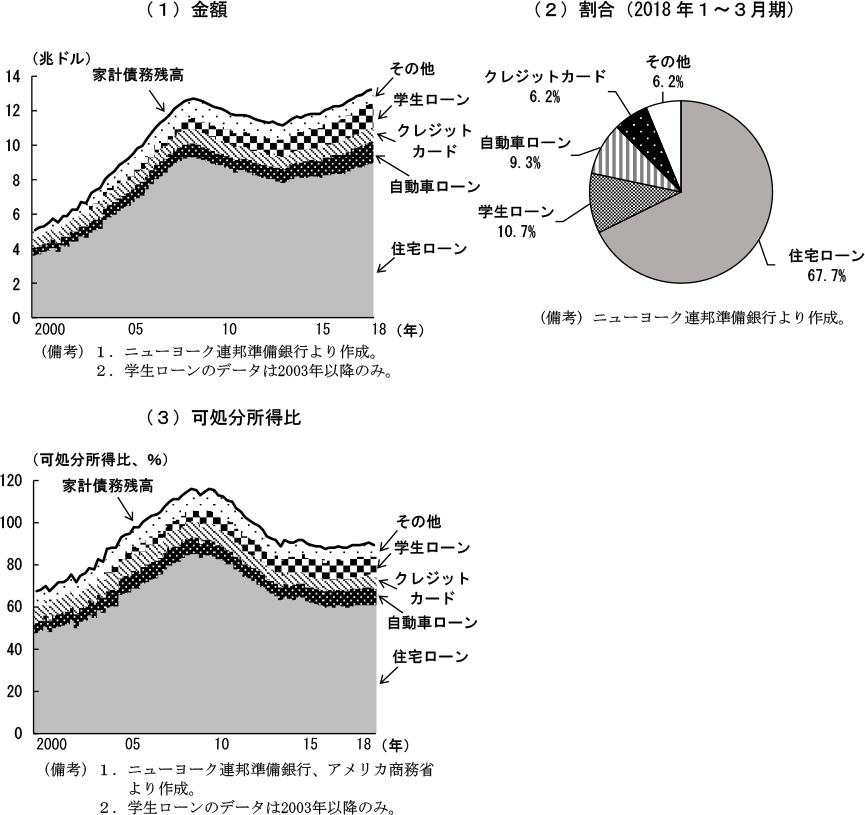
これらの延滞率をみると、住宅ローンは世界金融危機時に高水準を記録して以降、低下傾向にある。自動車ローンは危機時の水準にはいまだ達していないものの、緩やかな上昇傾向を示している。学生ローンについては、学費高騰等を背景に12年半ば以降急激に延滞率が上昇した後、11%前後でおおむね横ばいで推移している34。クレジットカードは、住宅ローン同様に金融危機時に高水準を記録して以降、低下傾向にあるが、16年頃よりおおむね横ばいで推移している(第2-2-67図)。
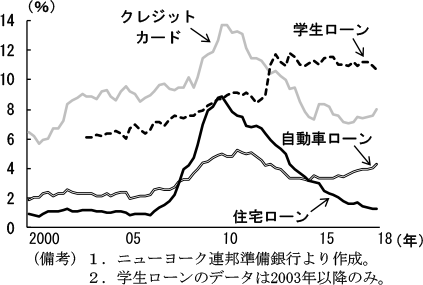
住宅ローン及び自動車ローン借入対象者のクレジットスコア35をみると、住宅ローンと比較して金額の少ない自動車ローンはサブプライム層を示す660点以下の層への貸出が世界金融危機前と比べほぼ同水準となっているが、金額の多い住宅ローンは世界金融危機以降、サブプライム層への貸出は増えていない(第2-2-68図、第2-2-69図)。また、住宅ローン及び自動車ローンへの貸出態度をみると、双方とも16年半ばより貸出態度が厳格化されているが、これらを比較すると厳格化の度合いは自動車ローンの方が高い(第2-2-70図、第2-2-71図)。さらに、破産者の推移をみても、世界金融危機前後に一時的に急増したが、その後は低下傾向にあり、近年は低水準で推移している(第2-2-72図)。
このように、家計部門の債務残高は、金額では世界金融危機時の過去最高水準を超えているが、GDP比や可処分所得比でみれば横ばいであり、また、延滞率や借入対象者のクレジットスコア、さらに貸出態度、破産者数をみても、世界金融危機時と比較して目立って危険な状況にはない。
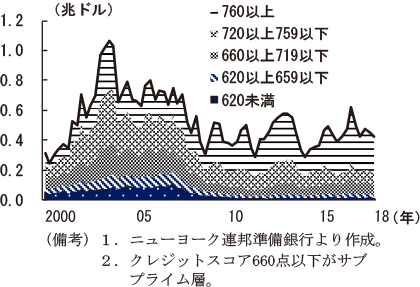
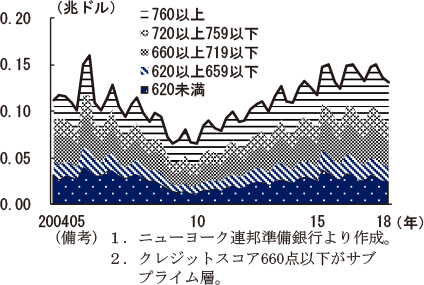
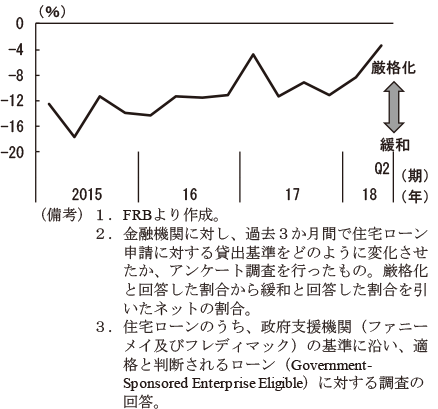
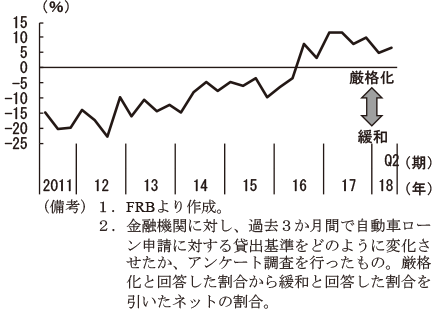
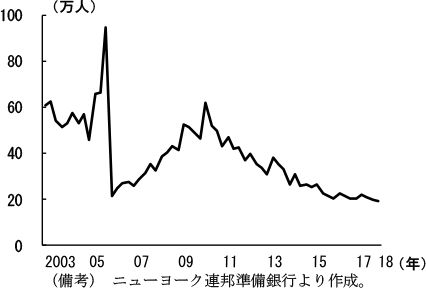
(住宅価格の上昇)
家計債務の大部分を占める住宅ローンは、前述のとおり世界金融危機時と比較して目立って危険な状態にはないが、世界金融危機時に問題となった住宅価格が、現在どのような状況にあるのかを確認する。
アメリカの住宅価格は世界金融危機後に急落したものの、その後、緩やかに上昇し、18年2月には危機直前の最高水準を超えた(第2-2-73図)。住宅市場の需要と供給のバランスを確認するため、新築・中古それぞれの住宅在庫・販売比率をみると、ともに低水準で推移していることから、旺盛な住宅需要に比べ、住宅の供給が追いついていない様子がうかがえる。特に在庫の不足は中古住宅で顕著であり、2000年以降で最も低い水準で推移している(前掲第2-2-12図)。
需要面をみると、雇用・所得環境が良好なことから、これらが旺盛な住宅需要を喚起しているものとみられる。しかし、ミシガン大学の調査によれば、住宅を買い時と回答した者の割合が低下傾向にあり、買い時と回答した者のうち、資産の評価増による投資目的を理由とする割合が、世界金融危機時とほぼ同程度の水準まで上昇している点には注意を要する(第2-2-74図、第2-2-75図)。
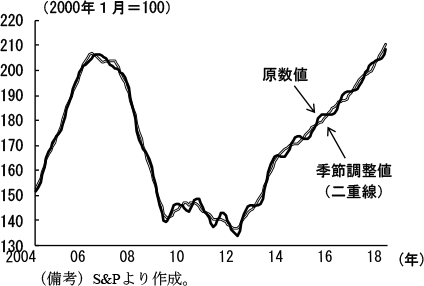
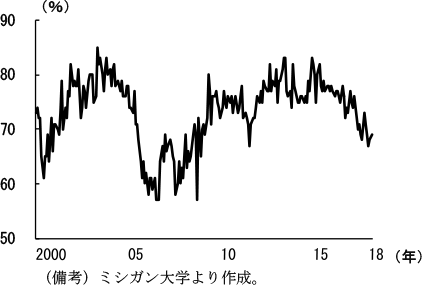
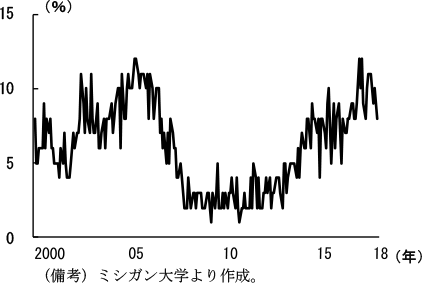
供給面をみると、建設労働者の不足が住宅供給の制約となっているとみられる36(第2-2-76図)。また、16年ごろから顕著にみられる資材価格の高騰も住宅供給の制約となっている可能性が指摘できる(第2-2-77図)。
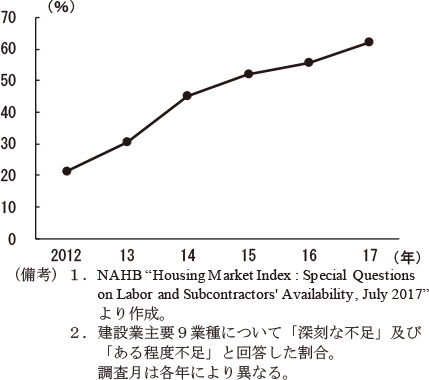
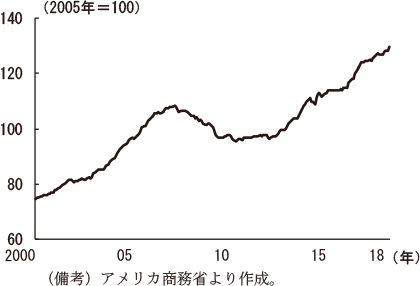
以上のとおり、アメリカにおいて住宅価格が緩やかに上昇し続けている背景には、良好な雇用・所得環境による堅調な需要面と、建設労働者の不足及び資材価格高騰による供給面の制約が存在する。また、住宅価格の上昇スピードは世界金融危機前と比較して緩やかであり、第1章でも述べたとおり、住宅価格・所得比や住宅価格・家賃比は長期トレンドから上方に大きくかい離してはいない。
(ii)アメリカの企業部門の債務の動向
企業部門の債務は、前述のとおり金額ベースでは世界金融危機時の水準を既に超え、GDP比ベースでも上昇基調で推移している(前掲第2-2-65図)。
これを企業の資金調達手段別にみると、アメリカでは銀行借入(間接金融)に比べ債券発行(直接金融)を主としてきたが、世界金融危機後はその傾向が一層強まり、債券発行が顕著に増加している(第2-2-78図)。
また、社債の平均償還年限をみると、05年ごろまでは、おおむね平均10年を下回っていたが、金融危機後は上昇傾向を示し、15年には平均17年まで上昇するなど歴史的にみても高い水準に達している(第2-2-79図)。
社債の格付別に売買高をみると、投機的格付債(ハイイールド債)は、08年の世界金融危機時に一時50億ドル程度に減少したが、その後は再び増加傾向となり、14年以降は08年の2倍以上である110億ドルから120億ドル程度となっている(第2-2-80図)。
以上より、企業部門の債務は債券発行により増加傾向にあり、また、平均償還年限の長期化や投機的格付債の売買高の増加がみられることから、今後、金融緩和の縮小に伴う金利上昇が見込まれる中で、急激な債券価格の下落といったリスクの顕在化に留意が必要である。
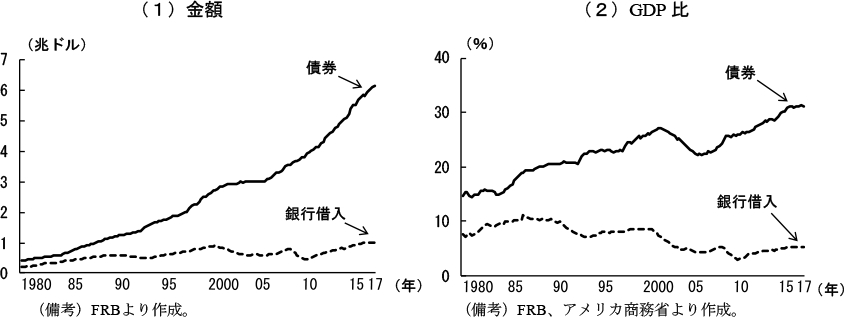
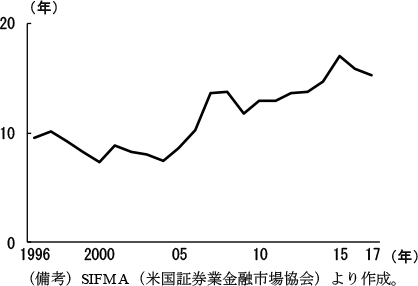
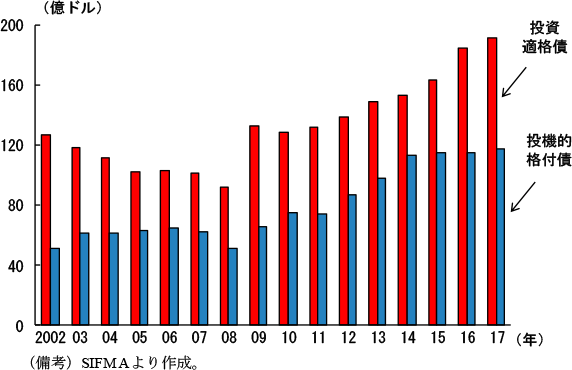
3.アメリカ経済の見通しと主なリスク要因
(着実に回復が続いているアメリカ経済)
アメリカ経済は、堅調な雇用・所得環境に支えられた個人消費の増加や、輸出、設備投資の緩やかな増加等から、当面は着実に回復が続いていくものと見込まれる。また、各種機関による経済見通しにおいても、今後も回復が続くことが見込まれている(第2-2-81表)。
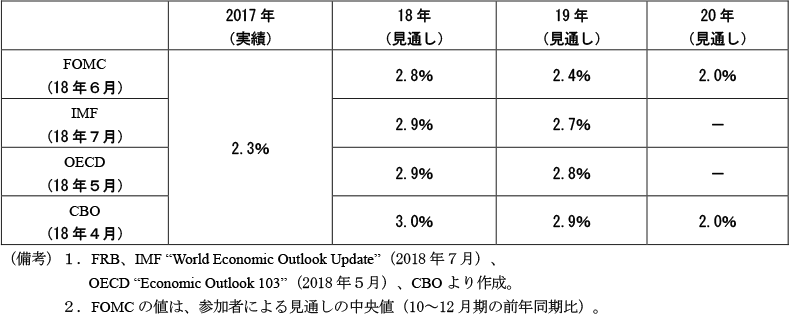
このようにアメリカ経済は回復が続くと見込まれているが、本節冒頭で述べたように、過去2番目の長期にわたる景気拡張局面にあるとみられ、景気後退の時期に関心が寄せられている。そのため、現在のアメリカ経済が景気循環の中でどこに位置しているのかを幾つかの指標を用いて確認する。
まず、NBER(全米経済研究所)が景気の山・谷を設定する上で確認している6つの月次指標(月次実質GDP、実質総売上、鉱工業生産指数、実質個人所得(移転所得を除く)、総週労働時間、非農業雇用者数)により最近までのアメリカ経済の動向をみると、これらの指標全てで18年入り後も増加基調を維持している(第2-2-82図)。
次に、ニューヨーク連邦準備銀行が長短金利差37を用いて推計を行っている1年後の景気後退確率から景気後退の兆候を確認すると、過去の景気後退直前と比べて景気後退確率が高まっている状況にはない(第2-2-83図)。
また、市場における景気後退の予想を反映する長短金利差については、これまでの景気循環においては、長短金利差がマイナスとなった場合、その多くで直後に景気後退局面入りしており、過去の経験則からは、長短金利差の動向が景気後退の先行指標の役割を果たすとみなされている。このところの長短金利差をみると、長短金利差がマイナスとなるまでにはいまだ距離があることから、過去の経験則からは、当面、景気後退に陥る可能性は高くはないとみられる(第2-2-84図)。
以上より、アメリカ経済は、以下で述べるリスク要因に留意する必要はあるものの、当面、景気後退局面入りする可能性は大きくないと考えられる。
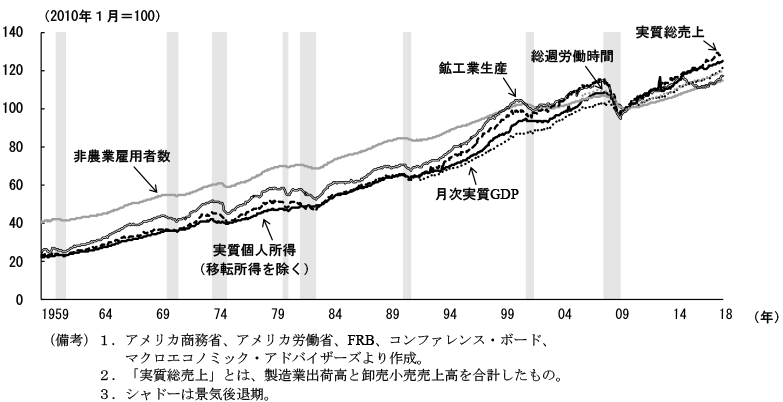
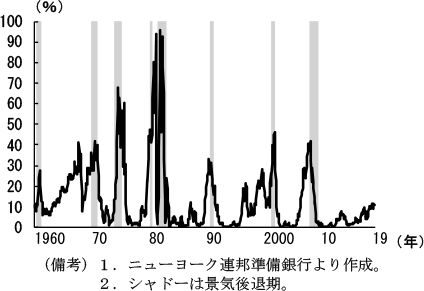
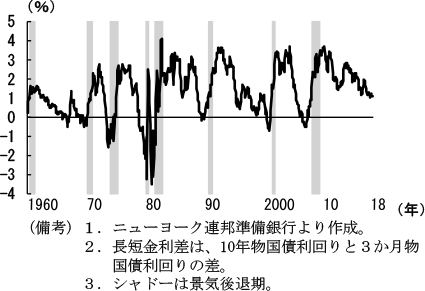
(主なリスク要因)
アメリカ経済を見通す上での主なリスク要因は以下のとおりである。
(1)トランプ政権による通商政策の動向
トランプ政権が進める通商政策が、どのように展開していくかについて不確実性がある。世界的なサプライチェーンの構築等、企業活動のグローバル化が進む中で、貿易制限的な通商政策が推し進められた場合には、相手国による報復措置も加わり、世界的な貿易・投資の縮小をもたらし、アメリカ経済にマイナスの影響を与える。
(2)金融政策の動向
金融政策とそれが経済に与える影響に留意が必要である。アメリカ経済においては、減税や歳出拡大といった拡張的な財政政策が講じられており、市場においても金利上昇がアメリカ経済のリスク要因として、これまで以上に強く意識されている。こうした環境下で、FOMCは漸進的なバランスシート縮小を進めつつ、緩やかに政策金利の引上げを行っている。FOMCによる利上げペースが急激な場合には景気後退のリスクが、逆に緩やかすぎる場合には景気過熱と資産価格の行き過ぎた上昇のリスクが見込まれる。また、長期にわたる金融緩和により、社債の平均償還年限の長期化と低格付化がみられ、価格リスクと信用リスクが相対的に高まっており、金利上昇による急激な債券価格の下落といったリスクの顕在化に留意が必要である。
なお、最後に経済政策不確実性指数(Economic Uncertainty Index)38の動向を確認すると、トランプ大統領の就任が決まった16年11月に大きく上昇し、その後は振れを伴いつつも低下傾向を示してきたが、依然として過去の景気拡張局面に比べ高い水準となっている(第2-2-85図)。