第2章 第1節
金融政策正常化に向けて歩みを進めつつあるアメリカ経済
アメリカ経済は、雇用・所得環境の改善が個人消費の増加に結び付く好循環が形成されており、景気は回復が続いている。2014年後半からの原油価格の下落も実質可処分所得の増加に寄与していると考えられる。
14年の実質経済成長率は、1~3月期に寒波・大雪等の影響で大幅に減速したことから、年後半には前期比年率5%台に加速したものの、通年では2.4%の成長にとどまった。15年に入ってからは1~3月期の成長率が前期比年率▲0.7%になるなど、景気回復のペースは緩やかになっている(第2-1-1図)。これは、(1)特に2月の記録的な寒さによる個人消費へのマイナスの影響、(2)西海岸の港湾施設の労使紛争の影響によるサプライチェーンの混乱といった一時的な要因と、原油価格の下落やドル高の企業部門へのマイナスの影響といった構造的な要因があいまっていると考えられる。
雇用情勢は改善が続いており、雇用者数は14年2月から15年2月まで前月差で毎月20万人超の増加となった。15年3月には原油価格下落の影響が鉱業に特に表れ、また寒波の影響もあって、雇用者数の伸びが一時的に鈍化したものの、4月は再度前月差20万人超えとなった(第2-1-2図)。
金融政策では、金融政策正常化の方針が取られ、連邦準備制度理事会(FRB)は14年10月に資産購入プログラムの終了を決定した。後述のとおり、年後半にも金融政策が正常化(利上げ)する見込みとなっている。
本節では、金融政策の大きな転換点を迎えつつあるアメリカ経済について、09年6月より始まった今回の景気回復局面を総括した上で、金融政策正常化に向けた動きを概観し、正常化を決定するに当たって特に注目されている賃金の動向を紹介する。また、景気回復の浸透の鍵になるとみられる中間層の動向についても分析する。
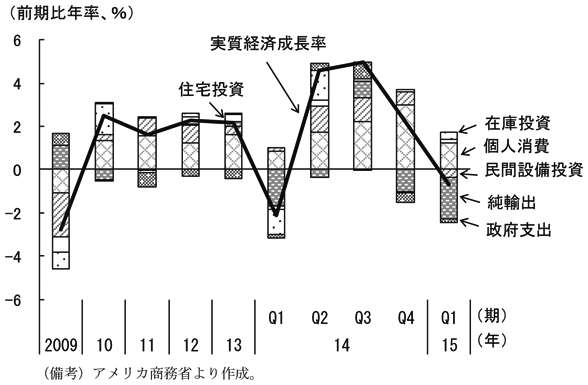
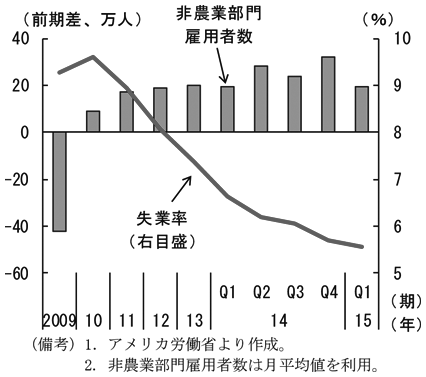
1.今回の景気回復の概観
(1)景気回復に至るまでの道のり
09年6月を景気の谷として始まった今回の景気回復局面の初期は、政策効果による下支えや新興国向けの輸出を中心とした回復であった。
いわゆるリーマン・ショック(08年9月)に端を発した世界金融危機に対応するために財政・金融政策が積極的かつ迅速に採られた。09年2月に成立した「アメリカ再生・再投資法」は総額7,872億ドル(GDP比約5.5%1)にのぼり、労働者一人当たり最大400ドル(夫婦で800ドル)の減税や特別償却の延長等による新規設備投資の支援、公共交通や高速鉄道等のインフラ整備等を盛り込んでいた。オバマ大統領の就任が09年1月だったことにかんがみると、異例の速さだったといえる。また、FRBは、中央銀行が国債に加えてMBS(不動産担保証券)を大規模に購入するという非伝統的な金融政策(いわゆる量的緩和)を導入した(第2-1-3表)。量的緩和は計3回にわたって実施され、FRBのバランスシート(資産側)は15年3月時点で4.5兆ドルと、金融危機前と比較して4.8倍となっている。
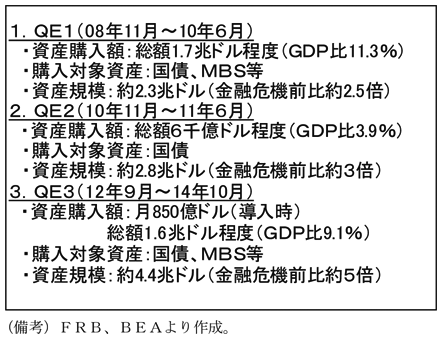
雇用面では、景気回復の初期はジョブレス・リカバリーの様相を呈し、10年半ば過ぎまで月次ベースでは増減を繰り返していた。
現在は雇用情勢の改善が続いており、個人消費が景気をけん引している。この背景には、家計のバランスシートや住宅市場の調整の進展、金融機関の信用創造の回復があると考えられる。
景気回復の初期には家計の保有資産残高の減少による逆資産効果や、家計の過剰債務の圧縮に伴う消費の抑制が懸念されていた。家計の保有資産残高は、住宅価格の低下や株価下落の影響等を受け、07年7~9月期から09年1~3月期まで毎期連続で減少した。その後、株価の持ち直しや住宅価格の上昇を受けて、12年10~12月期には金融危機前の資産残高を超えた。資産残高の可処分所得比をみても04~05年の水準まで回復している(第2-1-4図(1))。一方、家計の債務残高(総資産比)は09年1~3月期にピークをつけた後、緩やかに低下している。元利返済負担率も同様に緩やかに低下しており、債務負担感は低下している(第2-1-4図(2))。全体として、家計のバランスシート調整はおおむね終了していると考えられる。
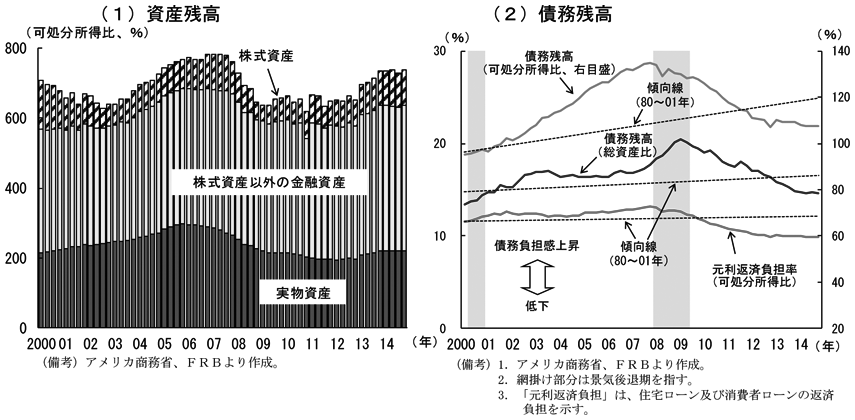
住宅部門では、価格の低下に伴って、評価額がローン残高を下回り、住宅の売却で損失を被る世帯が多かった。住宅を売却して職の豊富な地域へ移住することが出来ず、この点も雇用のミスマッチの拡大に寄与していた。ネガティブ・エクイティ物件(住宅の評価額がローン残高を下回っている物件)をみると、12年以降減少傾向にあり、14年10~12月期現在、ピーク時(11年10~12月期)の4割強となった(第2-1-5図)。住宅着工件数は05年(206.8万件)をピークとして09年には55.4万件まで落ち込み、その後の持ち直しは緩やかであるものの、14年には100万件の大台(100.3万件)を回復した。
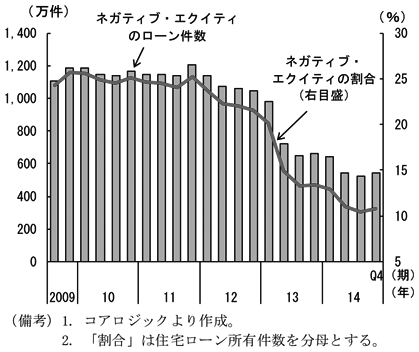
世界金融危機は、金融部門の機能低下が信用収縮等を通じて実体経済にマイナスの影響を与えていたため、金融システムの安定化が景気回復の必要条件であった2。このため、金融システム安定化に向けた包括的な施策が採られた。08年10月に大手金融機関に対して総額1,250億ドルの資本注入が行われた後、09年2月には包括的な金融安定化策が取りまとめられ、ストレステストの実施や不良債権買取りのため、5,000億ドル規模の官民投資ファンドの設立等が盛り込まれた。
商業銀行による商工業向け貸出をみると、08年後半から急速に信用収縮が進んだ後、10年2月を底に増加しており、13年4月には前回の景気回復局面のピークを超えた。その後も増加が続いている。一方、商業不動産向けの貸出は11年12月に底を付けたものの、緩やかな増加にとどまっている(第2-1-6図)。
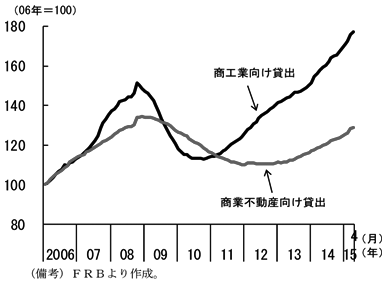
最後にGDPギャップをみると、09年4~6月期、7~9月期にともに▲7.2%まで拡大したものの、これ以降は縮小傾向にある。15年前半には▲2%弱に戻る見込みである。ただし、世界金融危機前の07年(▲0.5%)と比べるとなお大きく、スラックが残っていることを示唆している(第2-1-7図)。
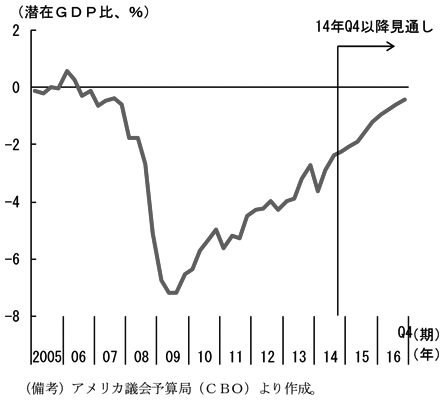
一方、世論調査によると、世界金融危機後の不況以降収入は回復しているものの、15年2月現在では低所得層ほど収入が回復していないと回答しており、景気回復の低所得層への浸透が課題となっている(第2-1-8図)。
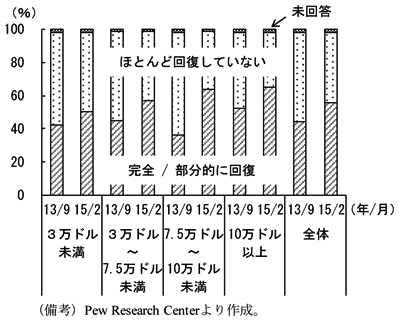
(2)FRBの金融政策正常化に向けた動き
FRBは14年10月に資産購入プログラムを終了し、金融政策正常化(利上げ)へ向けた一歩を踏み出した。利上げが開始されれば約10年ぶりとなる。本項では、前回利上げ時の経済状況や利上げプロセスを確認した後、現在の状況を検証する。
前回の利上げ開始前(04年6月~06年6月)における連邦公開市場委員会(FOMC)声明文をみると、03年12月に「緩和的な金融政策は相当な期間(considerable period)維持できる」としていたものを、04年1月に「緩和的な金融政策を解除するのに辛抱強くなれる(can be patient)」と変更した。04年5月には、「緩和的な金融政策は慎重なペースで解除される」と利上げ時期が近いことが示唆され、04年6月の会合で25ベーシスポイントの利上げが決定された(第2-1-9表)。その後、各会合で25ベーシスポイントずつ利上げし、06年6月には5.25%まで達した。

FRBの二大責務である雇用の最大化と物価の安定について当時の状況を振り返ると、非農業部門雇用者数は04年3月から5月にかけて3か月連続で前月差20万人を超え、失業率も低下傾向にあるなど、雇用情勢は改善していた(第2-1-10図)。一方、物価動向をみると、04年初から総合、コアともに物価上昇率が高まっており、利上げの背景の一つになったと考えられる(第2-1-11図)。
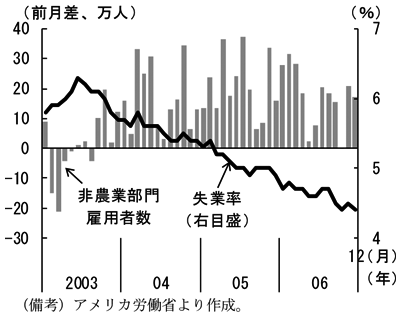
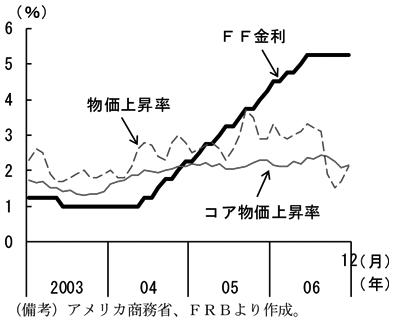
今回の局面の声明文をみると、14年12月に、14年10月まで用いられた「相当な期間(considerable time)、現在の政策金利(0~0.25%)を維持することが適切」とのフォワード・ガイダンスを修正し、「金融政策の正常化の開始に向けて辛抱強くなれる(can be patient)」とした。また、イエレンFRB議長は、同日の記者会見において「辛抱強くなれる」という声明は、少なくとも今後数会合(at least the next couple of meetings)で金融政策正常化のプロセスが始まる可能性は低いと解釈されるべきだと発言し、市場では声明文から「辛抱強くなれる」という文言がいつ削除されるのかに注目が集まった。
イエレン議長は15年2月の議会証言3においても同様の趣旨の発言を行うとともに、声明文にマーケットが過度に反応しないよう細心の注意を払っている姿勢を示した。
このように注意を払う背景としては、13年5月にバーナンキFRB議長(当時)の量的緩和縮小を示唆する発言を契機に金融市場が大きく変動した経験があると考えられる。バーナンキ発言後にアメリカの長期金利(10年債)の利回りは2%程度から3%弱まで短期間のうちに上昇した(第2-1-12図)。
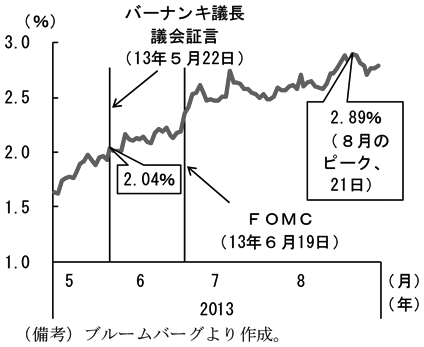
また、経常赤字を抱える国を中心に新興国通貨はドルに対して大幅に減価した(第2-1-13図)。いわゆるフラジャイル・ファイブと呼ばれた通貨を持つ5か国(インド、インドネシア、トルコ、南アフリカ、ブラジル)では、14年中にいずれも総選挙が予定されていたため、政治の先行き不透明感も通貨の下落の一因になったとみられる。
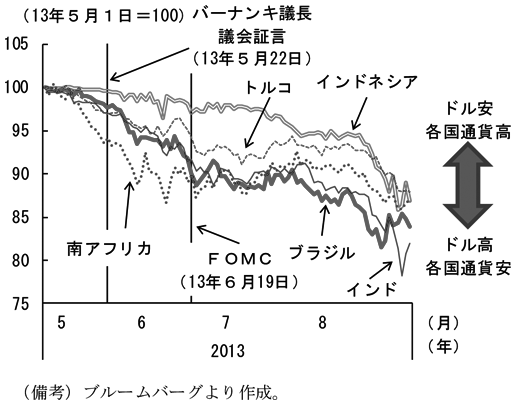
現在の雇用情勢をみると、非農業部門雇用者数は増加が続いており、失業率も5.4%(15年4月)と、OECDの推計による自然失業率(5.4%)4付近まで低下している。一方、物価上昇率は原油価格下落の影響もあって、15年4月には総合で前年同月比0.3%、コアは同1.3%とFRBの目標である2%を下回る水準となっている。
利上げ開始時期については「労働市場が一層改善し、物価上昇率が中期的に2%の目標に戻っていくと合理的な自信(reasonably confident)が得られた場合」としており、足下の物価上昇率が低くても利上げ開始があり得ることを示唆している。
また、「合理的な自信が得られる」とすることについて特定の指標の水準等で機械的な判断はせずに、広範なデータをみるとしている。イエレン議長は、賃金上昇率の加速が利上げの前提条件ではないとしつつも、賃金上昇率を注視するとも発言しており、引き続き賃金の動向が注目されている。
(3)賃金の動向
今回の景気回復局面では、失業率が5%台まで低下してきているのに対し、賃金の伸びは緩やかなものにとどまっている。理由としては、パートタイム比率の高止まりや低スキル・低賃金業種における雇用の伸長が挙げられる5。一方、15年に入って賃金の上昇を示唆する動きがみられる。全米企業者協会(National Association for Business Economics)の調査(15年4月)6
では、半数近くの回答企業(45%)が賃金を引き上げたと回答しており、前年同月の35%から増加している。また、小売を中心に賃上げを発表する企業も増えてきている。以下では、FOMCでも注目されている賃金の動向を検証する。
賃金の動向をみると、15年に入っても前年比2%程度で推移しており、賃金の伸びが「加速」している様子はうかがえない(第2-1-14図)。一方、産業別にみると、低賃金の業種(「レジャー・ホスピタリティ」や「小売」)及び高賃金の業種(「情報」や「専門サービス」)で平均よりも高い伸びを示している。前回の景気回復局面では、中程度の賃金水準の業種でも平均よりも賃金上昇率が高い業種もあったが、今回の景気回復局面では賃金の上昇が賃金水準の高い産業と低い産業に偏っていることがうかがわれる(第2-1-15図)。このような賃金動向が中間層に影響を与えている。中間層については後段で分析する。
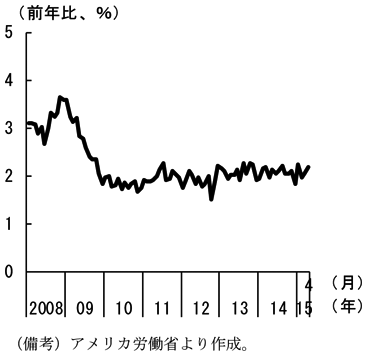
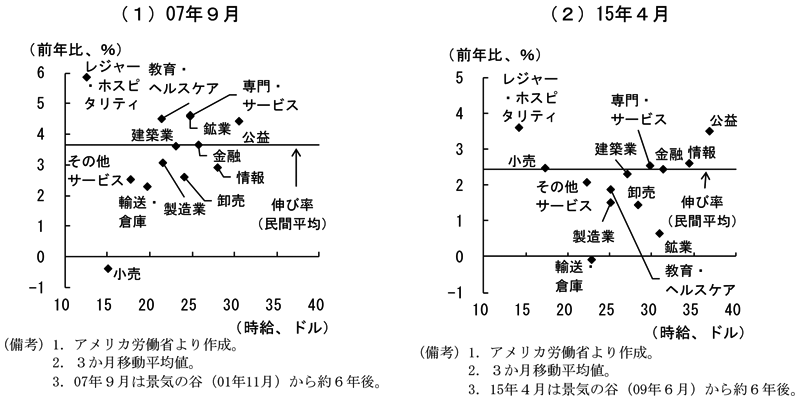
15年4月のベージュブック(FRBがまとめているアメリカの地域経済動向に関するレポート)における各地域の経済動向においても同様の傾向がみられる。賃上げ圧力は総じて緩やかとされているものの、熟練労働者(skilled workers)の一部で賃金上昇率が高まる傾向にあるとともに、非熟練労働者(unskilled workers)に対しても前回の報告時点(3月)よりは賃上げの動きがでてきていると指摘されている。
また、労働市場のひっ迫感に伴って、小売を中心に賃上げを発表する企業も増えてきている(第2-1-16表)。
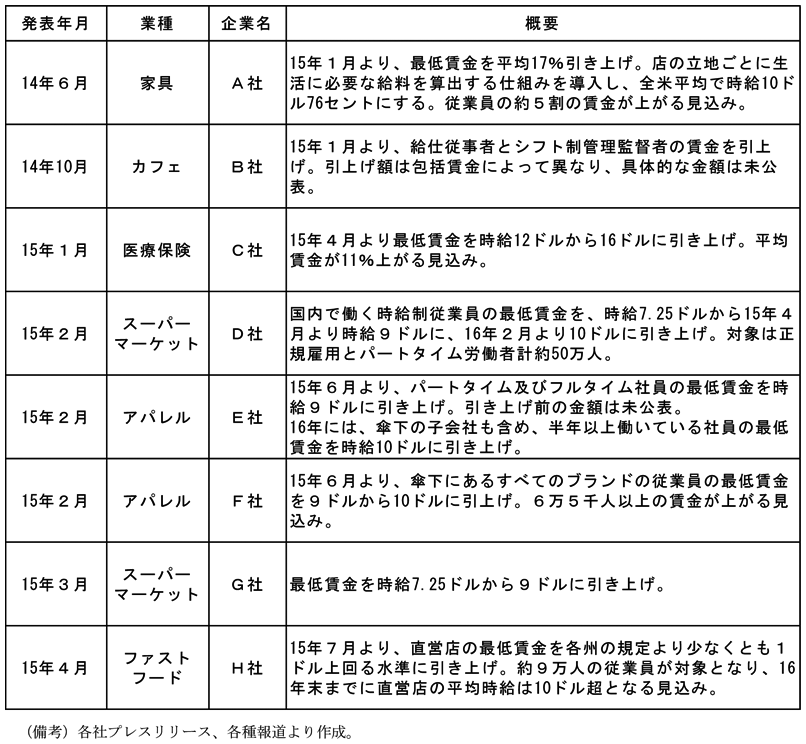
さらに、労働市場のひっ迫感から労働者の立場が強くなっていることもあって、労働組合がストに踏み切って賃上げを勝ち取るケースも出てきている。例えば、西海岸の港湾施設の労使紛争では、3日間の港湾封鎖も含めて、15年2月の暫定合意まで半年以上を要した。合意の詳細は不明であるものの、年数%の賃上げや福利厚生の拡充が盛り込まれたと報道されている。
低賃金の労働者の賃金を底上げしようという動きもみられる。オバマ大統領は14年1月の一般教書演説において、連邦最低賃金を7.25ドルから10.10ドルに引き上げる提案を行った。ただし、法案は議会に提出されたものの、両院ともに野党が過半数を占める中、成立には至っていない7。一方で、州レベルでは最低賃金の引上げの動きがみられる。14年末から15年にかけて、21の州及びワシントンD.C.で最低賃金が引き上げられた(第2-1-17表)。これら22州において14年に最低賃金、またはそれ以下で働く者は96万人(95.8万人)程度であった。最低賃金の引上げは、この近傍の賃金の上昇圧力となると考えられる。
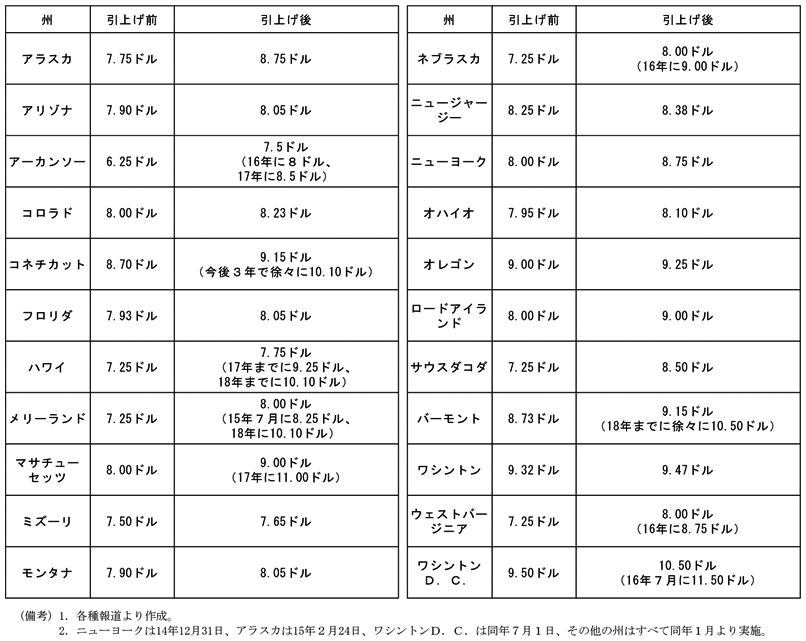
一方、「賃金・報酬」と「諸手当」(有給休暇、残業代、ボーナス、会社負担分の医療・年金保険料等)で構成される雇用コスト指数8は上昇が顕著になってきている。短期失業率(労働力人口に占める失業期間が27週未満の失業者の割合)と雇用コスト指数の関係をみると、短期失業率が4.5%を下回った辺りから雇用コスト指数の伸びが上昇し始めている(第2-1-18図)。雇用のひっ迫感に伴って雇用コストの増大につながっていると考えられる。
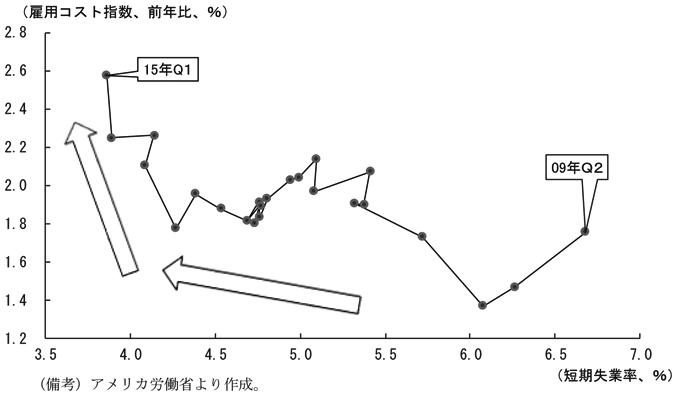
以上のように、雇用のひっ迫感に伴って賃上げの動きは出てきているものの、賃金の伸びを決定する重要な要因9である労働生産性の伸びは鈍化している(第2-1-19図)。これは、設備投資が前回の回復局面ほどは伸びていないためと考えられる。就業者一人当たりの資本ストックをみると、世界金融危機以降伸び悩んでいる(第2-1-20図)。雇用のひっ迫感に伴って賃上げの動きがみられるものの、賃金が本格的に上昇するためには積極的な設備投資による生産性の向上が不可欠と考えられる。
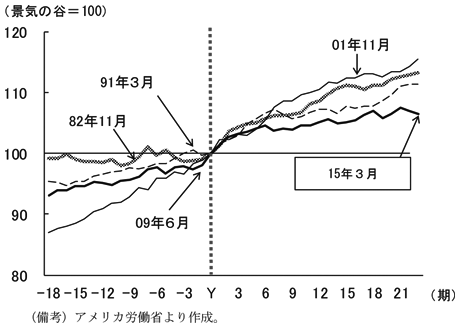
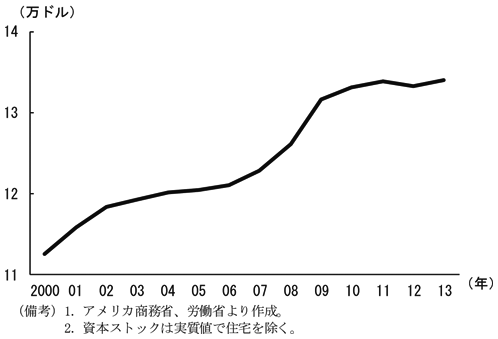
(4)見通し
アメリカ経済は、15年1~3月期は一時的要因もあってやや減速したものの、先行きのメインシナリオとしては、回復が続くと期待される。雇用情勢の改善が賃金にも波及する動きが一部でみられ始めており、雇用のひっ迫感に伴い賃金の上昇圧力が高まり、原油価格下落の影響とあいまって消費者マインドの改善や個人消費の増加が続くと期待される。これに伴い、物価にも緩やかな上昇圧力がかかり、FRBが目指す2%の物価目標に徐々に近づく道筋がはっきりしてくれば、金融政策正常化に向けた素地が整ってくると考えられる。
一方、リスク要因はいくつか挙げられる。ドルは14年10月以降、15年5月29日現在円に対して13.2%、ユーロに対して13.0%増価しており、価格競争力の低下から資本財を始めとして輸出や生産には影響が出始めているとみられる(第2-1-21図)。ただし、全米企業者協会の調査(15年4月)によると、6割強(62%)の企業はドル高の影響は15年1~3月期には特段みられなかったとしており、ドル高のマイナスの影響は一部の海外依存度の高い製造業にとどまる可能性もある。
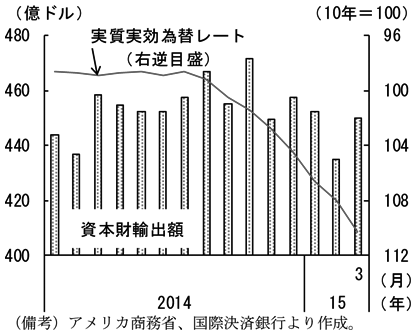
また、第1章で分析したとおり、低水準の原油価格は当面続くと見込まれるため、エネルギー関連企業の設備投資や企業収益にはマイナスの影響が生じると考えられる。企業収益の見通しをみると、エネルギー関連企業の収益は15年に大きく落ち込む見込みとなっている(前掲第1-2-11図(1))。
2.「中間層の経済」の課題
オバマ大統領は15年の一般教書演説で中間層の支援に注力する旨を表明し、これに続く予算教書や大統領経済報告においても中間層の立て直しの重要性を強調した。予算教書では、中間層への支援として、コミュニティカレッジでの技能向上やヘルスケアの充実、勤労者世帯の育児支援を盛り込んだ10。
以下では、「中間層」の定義を概観した上で、中間層が減少している背景を分析し、復活への方策を紹介する。
(1)中間層の定義
アメリカ商務省(2010)によると、中間層の定義は様々であるが、所得を使って分類する手法が最も一般的に使われている。その際の「所得」とは、(1)所得の絶対値、(2)家計の中位所得と比較した所得の水準、(3)所得4分位や5分位で分類される所得階層のある一定層や(4)貧困ラインと比較した所得水準が挙げられている11。
また、アンケート調査等で回答者の自己申告によって中間層を分類する手法もある。その際、回答者には上流層、中間層、下流層といった選択肢が示される。ただし、この手法は回答者の自己申告であるため、高所得の人も低所得の人も自分を中間層とみなす傾向にある。例えば、Pew Research Center(2012)によると、所得が100,000ドル以上の人の46%が中間層と回答したのに対し、30,000~49,999ドルの人の51%が、30,000ドル未満の人でも35%が中間層と回答した。
さらに、職種や所得、教育水準といった指標を総合したインデックスを作成して、人々の社会的立ち位置や生活水準をランク付けする試みがなされている。
平均的な中間層が希望するものとして、(1)自宅の所有、(2)世帯の大人一人ずつの自家用車の保有、(3)子供のための大学教育、(4)雇用主が提供する健康保険、(5)退職後の備え、(6)家族の休暇が挙げられている。
一方、世論調査によると、「中間層」の生活を送るために必要とされる所得は、回答者の所得や学歴によって変化し、学歴が高いほど、また所得が高いほど増加する傾向にある(第2-1-22表)。
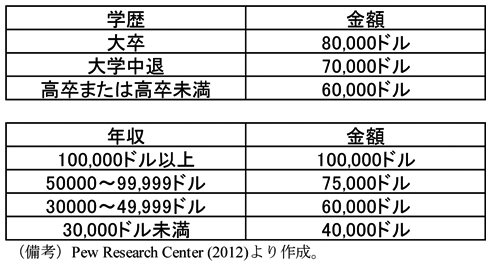
アメリカでは景気が回復しているものの、いわゆる中流意識は低下傾向にある。08年には半数以上(53%)の人が自分のことを中流とみなしていたが、15年には47%まで低下している。一方、自分を中流~下流、下流とみなす人の割合は08年の19%、6%から15年にはそれぞれ29%、10%まで上昇している(第2-1-23図)。また一生懸命働くことが成功の重要な要件であると考える人の割合も緩やかに低下している(第2-1-24図)。
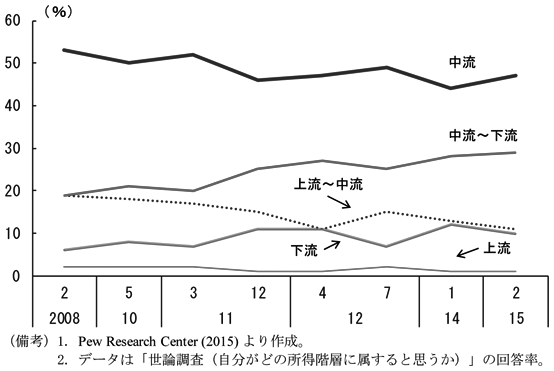
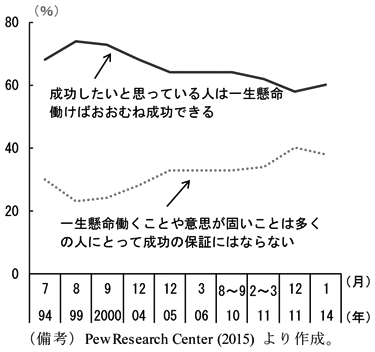
中流意識が低下傾向にある背景には、所得の伸びの低下が挙げられる。所得階層別に所得の推移をみると、所得の最も高い分位(第5分位、13年では年収18万5千ドル以上)では1990年から13年までの間に23.0%増加しているのに対し、第4分位、第3分位では7.7%、1.7%しか増加しておらず、第2分位、第1分位ではそれぞれ2.1%、5.9%減少している(第2-1-25図)。また、中間層の生活を構成する主要な3つの要素(住宅、健康保険、大学)のコストが所得よりも速く上昇しているため、中間層と意識できる生活を送るのは過去よりも難しくなっていると考えられる12。
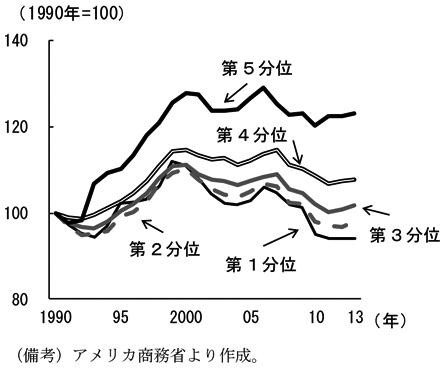
(2)中スキルの雇用が減少
(i)減少の続く中スキルの労働者
中間層に分類される労働者はスキル別にみると、中スキルの労働者に分類される。
ニューヨーク連銀の分類に従って労働者をスキル別に分けてみると、01年から14年にかけて、中スキル、とりわけ「中スキルの下」(機械オペレーターや事務サポート業務に従事する労働者)に分類される労働者の割合が顕著に低下している(第2-1-26表、第2-1-27図)。
22年までの見通し13をみると、「中スキルの下」に分類される労働者の割合は更に低下する一方、高スキル及び低スキルに分類される労働者の割合は上昇する見通しとなっている。また、「中スキルの上」に分類される労働者の割合も、これを構成する建設やコミュニティーサービスの労働者の割合が上昇することから上昇する見通しになっている。
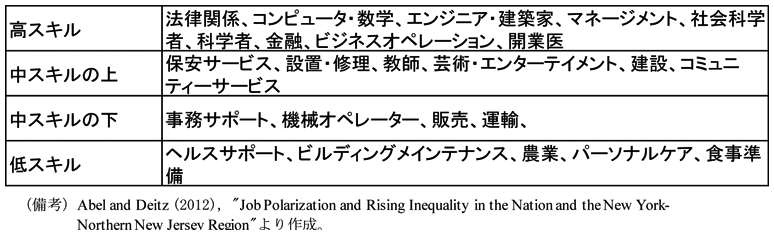
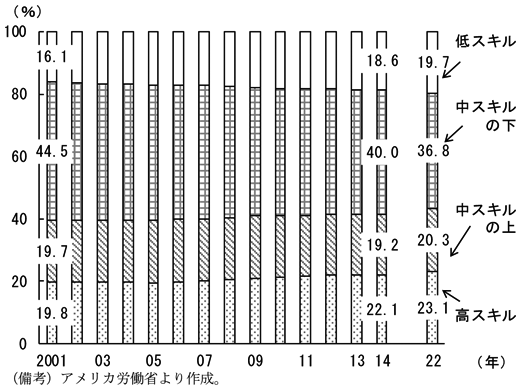
「中スキルの下」の労働者を更に詳しくみると、事務サポート部門は緩やかに減少しており、機械オペレーターは近年緩やかに増加しているものの01年比では約2割減となっている。業務のIT化やアウトソーシング、海外への生産移管等で代替が可能な職種が減少している(第2-1-28図)。
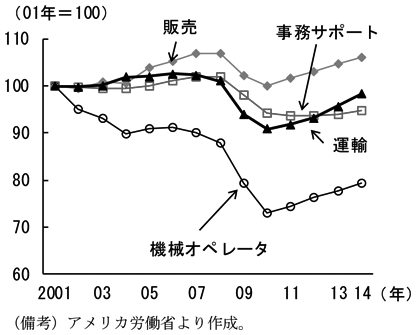
特に製造業については中国からの輸入品との競合によって、2000~07年までの製造業の雇用減の約半分強(55%)を説明できるとされる14。中国からの輸入額を確認すると、中国がWTO(世界貿易機関)に加盟した01年から14年にかけて、中国からの輸入額は4.6倍に増加しており、輸入全体の伸び(2.1倍)をはるかに上回って推移している(第2-1-29図)。中でも、アパレル製造に関連する指標をみると、01~14年にかけて国内生産が7割以上(▲75.9%)減少し、中国からの輸入額が4割弱(38.6%)増加する中で、雇用者数は半分以上(▲53.9%)減少した(第2-1-30図)。
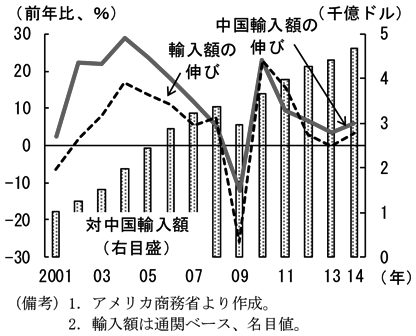
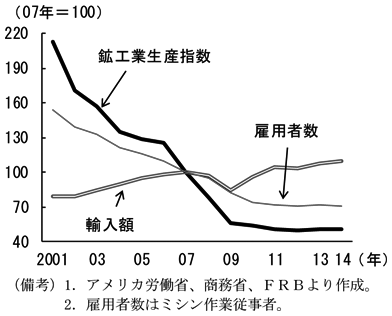
(ii)スキルが高いほど高賃金
雇用者数はスキルによって二極化が進む中、賃金はスキルが高いほど水準が高く15、賃金の伸びは高スキルの労働者の方が中・低スキルの労働者よりも高い傾向となっている(第2-1-31図)。低スキルの労働者の賃金の伸びは07年に高スキルの労働者のそれを超えたものの、その後は伸びが最も低い傾向にある。
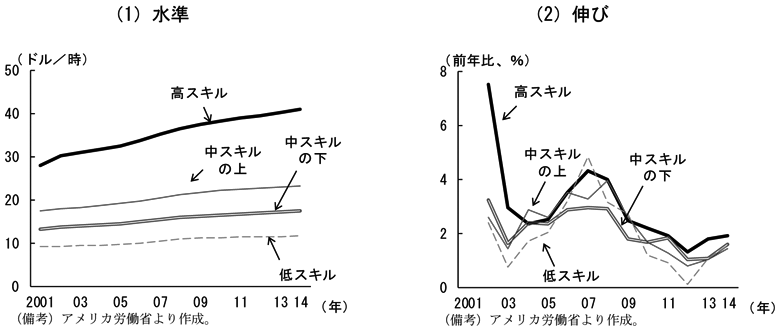
(iii)スキルの向上が重要
技術革新やグローバリゼーションの流れが今後も進むと考えられる中、労働者は自分の知識や技能を高めることが一層重要となっている。スキルと賃金の関係については、最もルーティーン的な仕事をしている労働者や高卒以下の学歴を持つ労働者は、低所得国への業務移転に伴って賃金が下がりやすい傾向にあると分析されている。一方、最もルーティーン的でない仕事をしている場合は、グローバリゼーションの賃金への影響はほとんどない16。
そのため、自動化を進めることで機械が取って代わることが可能な職種(例:機械オペレーター)や賃金の安い国に移転することが可能な職種(例:プログラマーやコールセンターのオペレーター)では、別の新たな職種に移行できるようなスキルを身に付けることが重要となっている。
なお、低スキルの業種の労働者は、主に内需向けの業種であり、海外移管や機械による代替が困難であることから、今後もシェアの上昇が見込まれている。一方、低賃金かつ賃金の伸びが低いことから、中間層の生活を送るのは難しいと考えられる。低スキルから中・高スキルの職種に移行するためには教育や職業訓練を通じてスキルを高める必要がある。
(iv)コミュニティカレッジの役割
「2015年大統領経済報告」によると、大卒の者と高卒の者の所得格差は男女ともに長期にわたって上昇傾向にある17。
一方で、大学の学費が高騰し、学生ローンの支払に苦しむ学生が増えており、大学に行くことのメリットは理解していても(特に所得階層の低い世帯に生まれた者は)大学に行けない場合も多くなっていると考えられる18。
こうした中、労働者のスキル向上のため、コミュニティカレッジの果たす役割に注目が集まっている。コミュニティカレッジは、一般に2年制の公立大学である19。専門知識・技能を身に付けるための専門学校のような役割を果たすとともに、4年制大学に編入するための教養課程が設けられているところもあり、地域に根付いた高等教育機関である。
全国には1,000を超えるコミュニティカレッジがあり、うち9割近くは公立である。13年秋時点の在籍者は1,240万人だった。年代別の在籍者は、21歳以下が37%、22~39歳が49%を占めるものの、40歳以上も14%を占めている。
コミュニティカレッジは、働きながら学業を続けられるという柔軟な対応が可能であり、11~12年時点ではフルタイムの学生のうち42%がパートタイムの仕事を持っていた。
また、4年制大学に比べて学費が安いことも特長である。公立のコミュニティカレッジの年間の平均学費は、13~14年度で3,347ドルであった(4年制の州立大学は9,139ドル)(第2-1-32図)。
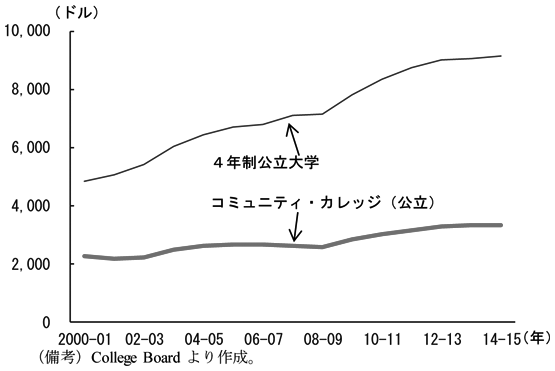
コミュニティカレッジの賃金への影響としては、準学士の学位や期間が1年以上かかるプログラム(例:医療関連職種の資格を目指すものなど)の修了証明書を取得することによって、賃金が上昇するという分析が示されている20。
労働省の分析によると、12年時点の準学士の中位年収は57,590ドルと、大学卒(67,140ドル)よりは低いものの、高卒(35,170ドル)よりは大幅に高くなっている。また、12年~22年にかけて、コミュニティカレッジを卒業した者(準学士)に対する労働者の伸びは全体を上回る見込みとなっている(第2-1-33図)。
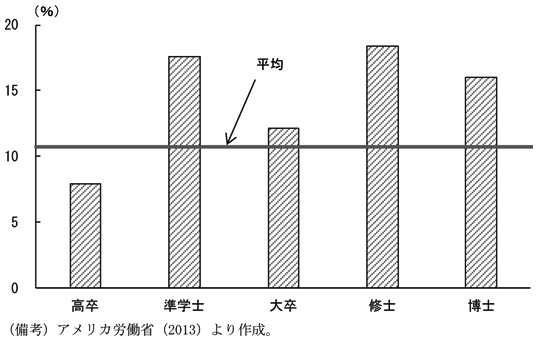
オバマ大統領は15年1月の一般教書演説でコミュニティカレッジの学費を無償とする方針を打ち出し、2月の予算教書では、基準を満たす学生(qualified students)21に対してコミュニティカレッジの学費を無償化する提案が盛り込まれた(16年度には4,100万ドルの予算計上を提案)。アメリカでは議会が予算を編成するため、予算教書は大統領の提案にとどまるが、大統領がコミュニティカレッジの無償化を方針として打ち出し、中間層の復活に向けた意思を示した意義は大きいと考えられる。
コラム2-1:天候に翻弄される冬季のアメリカ経済
アメリカ経済は14年冬、15年冬と2年連続で寒波の影響を受けた。とりわけ15年2月は北東部で史上2番目に寒い冬となった。
個人消費では自動車販売や飲食サービスが振るわず、住宅着工も北東部を中心に大幅に減少した(図1)。また、雇用者数の伸びは小さなものにとどまった。一方、おう盛な暖房需要を受けて電力・ガスの生産・消費は大幅に増加した(図2)。
ベージュブックでも14年と15年は12、13年の平均に比べて、「天候」や「寒い」という単語が多くなっており、天候の影響が大きかったことが示唆されている(表3)。
シカゴ連銀によると、降雪は自動車販売、住宅着工件数、コア資本財の出荷・受注、平均労働時間に有意にマイナスの影響を与えると分析されている(注)。
14年1~3月期の個人消費は前期比年率1.2%増にとどまったものの、寒波の影響で抑制された需要が顕在化したため、4~6月期は同2.5%増と持ち直した。15年3月には自動車販売台数が大幅に反発し、前月比5.5%増の年率1,705万台となった。15年においても天候の回復とともに消費が回復することが期待される。
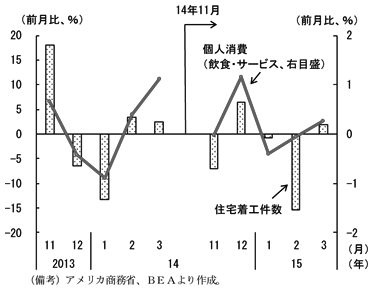
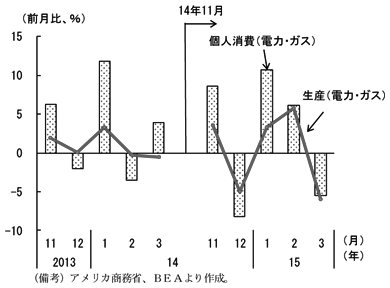

(注)Bloesch and Gourio (2015)

