第1章 第2節
先進国への影響
先進国の多くは原油の純輸入国であり、原油価格の下落は先進国全体としては経済にプラスに働くと考えられる1。以下では、先進国経済への原油価格下落の影響を、日本、アメリカ、英国、ドイツを例に、貿易収支、物価、家計、企業の面から確認する。
1.貿易収支への影響
第1節で指摘したとおり、消費エネルギー構成をみると、日本、アメリカ、英国、ドイツのいずれも石油の割合が30%以上となっており、石油への依存度が依然として高い(前掲第1-1-9図)。
主要先進国の原油の輸入依存度をみると、日本やドイツなどは80%以上と非常に高い。産油国であるアメリカでも40%以上、英国は19%となっており、両国とも純輸入国である(第1-2-1図)。そのため、これらの国にとって原油価格下落は貿易収支の改善を通じて経済にプラスの影響をもたらすと考えられる。
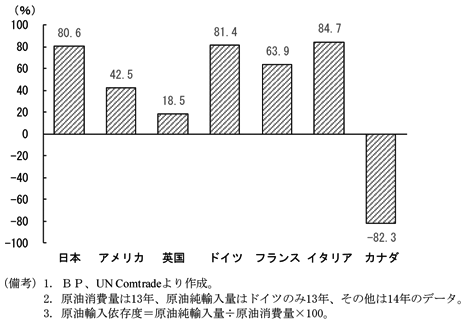
そこで、各国の原油輸入単位コスト(原油輸入金額を原油輸入量で除して算出)の14年6月から15年2月の下落率をみると、各国とも50%前後下落している(第1-2-2図)。
日本、アメリカ、英国、ドイツについて、原油の純輸入量が変わらないと仮定して原油輸入単位コスト下落による貿易収支の改善幅のGDP比(14年)を試算すると、アメリカ、ドイツはGDP比1%程度、日本は1.7%の改善が見込まれる(第1-2-3図)。
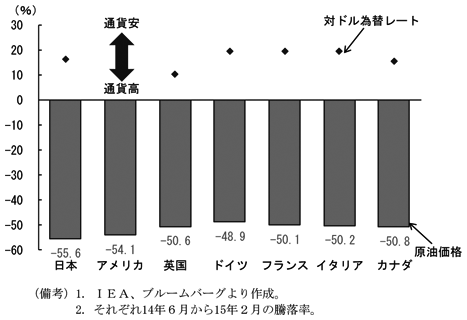
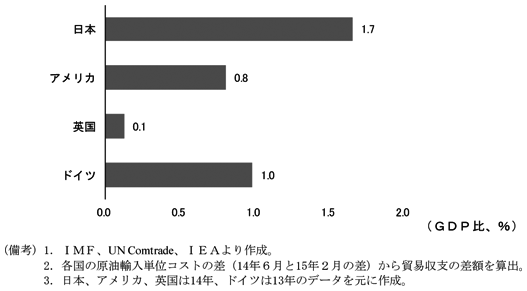
2.物価への影響
次に、原油価格下落の物価に与える影響について確認する。各国の消費者物価上昇率は、エネルギー価格の下落等を受けて14年11月頃から低下傾向が鮮明になっている。特に15年1月にはアメリカとドイツで前年比マイナスとなった(第1-2-4図(1))。
国別にエネルギーの寄与度をみると、日本はガソリン価格の下方硬直性等の影響からそれほど低下していないが、その他の国は14年12月からエネルギーのマイナスの寄与が大幅に拡大している2(第1-2-4図(2))。エネルギー価格の下落は、これまでのところ主にガソリンや灯油等の下落によるものであるが、英国やドイツ、日本では電気・ガス料金の値下げの動きもみられることから3
、今後これらの品目にも値下げの動きが広がれば、物価上昇率をさらに下押しする可能性がある。
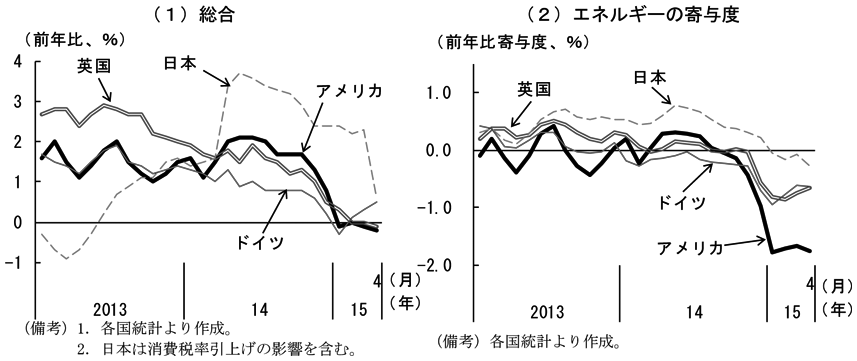
もっとも、原油価格は2月に下落が一段落しており、先行きも緩やかに上昇するとみられていることから(前掲第1-1-7図参照)、今後、エネルギー価格がさらに大きく下落し、これに伴い物価上昇率が大きく低下する可能性は小さいものと考えられる。
3.家計部門への影響
原油価格の下落はガソリン価格等の低下を通じて、家計の実質所得を押上げることが期待される。ガソリン価格をみると、国により差はみられるものの、いずれの国においても14年後半以降の原油価格下落を受けて、下落している(第1-2-5図)。アメリカでは原油価格に近い動きをしており、大きく低下しているのに比べて、英国やドイツ、日本では、価格の低下は小幅にとどまっている。各国のガソリン価格は、基本的に、本体価格と1リットル当たりの定額で課税される税(以下、ガソリン税)の合計に付加価値税率がかかるという構成になっている。このため、ガソリン税額の差異がガソリン価格の下落率に差を生み出している。付加価値税を除くガソリン価格の内訳をみると、アメリカでは税金の割合が16.7%であるが、英国、ドイツは税金の割合が60%弱と高いため原油価格の変動の影響を受けにくくなっている(第1-2-6図)。また、原油の多くがドル建てで取引されており、14年半ば以降、ドルが増価 (=他国通貨が減価)していることもアメリカ以外の国においてガソリン価格の下落幅が小さい要因となっている。
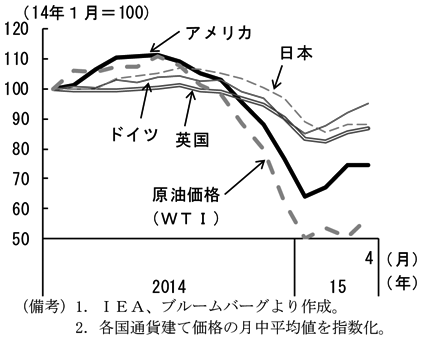
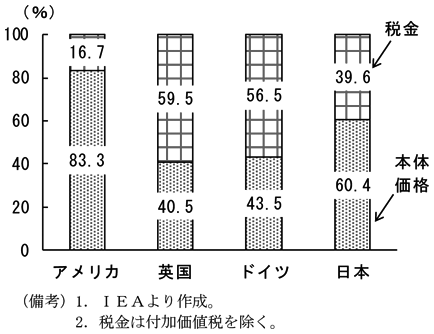
ガソリン価格の下落が消費に与える影響をみるために、ガソリン消費の減少額の個人消費に占める比率を試算すると、アメリカが1%程度となり、他の国と比べて大きくなっている(第1-2-7図)。これは前述のとおりガソリン価格が大きく下落していることによる。実際、14年6月と15年2月のアメリカの名目ガソリン消費額(季節調整値、年率換算)を比べると1,260億ドル程度減少(▲33.1%)している 。ガソリン価格の低下は実質所得を増加させ、個人消費を押上げる効果が期待される。また、アメリカの消費者マインドをみると、14年半ばから改善傾向にあり、ガソリン価格の下落もマインドに好影響を及ぼしていると考えられる(第1-2-8図)。
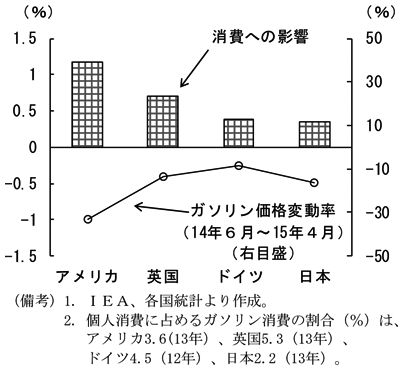
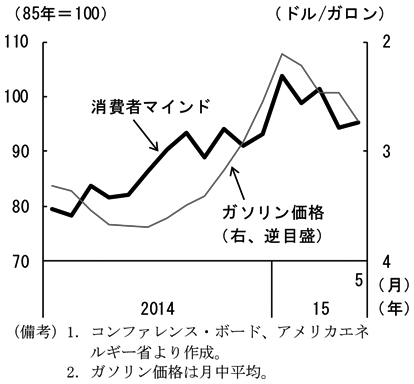
4.企業部門への影響
原油価格の下落によるエネルギー・コストの低下は、企業の生産コストの低下を通じて企業収益を押し上げる効果があると考えられる。他方、石油産業にとっては、原油価格の下落は収益の減少と財務の悪化につながるため、既にいくつかの企業では投資計画の縮小や人員削減によるコスト削減などの動きもみられる。このため、特に産油国であるアメリカや英国については、企業部門における原油価格下落のマイナスの影響を考慮する必要がある。以下では、アメリカを中心に企業収益、生産・設備投資における影響について概観する。
(1)企業収益
まず、企業収益への影響を概観する。エネルギーセクターの企業の営業収益は各国とも大幅に減少しており、原油価格下落の影響が大きいことが分かる(第1-2-9図)。他方、エネルギー以外のセクターの企業の営業収益をみると、14年10~12月期にアメリカでは前年比マイナスとなっているのに対し、ドイツと日本では前年比増加率が高まっており、原油価格下落がプラスに作用した可能性がある4。
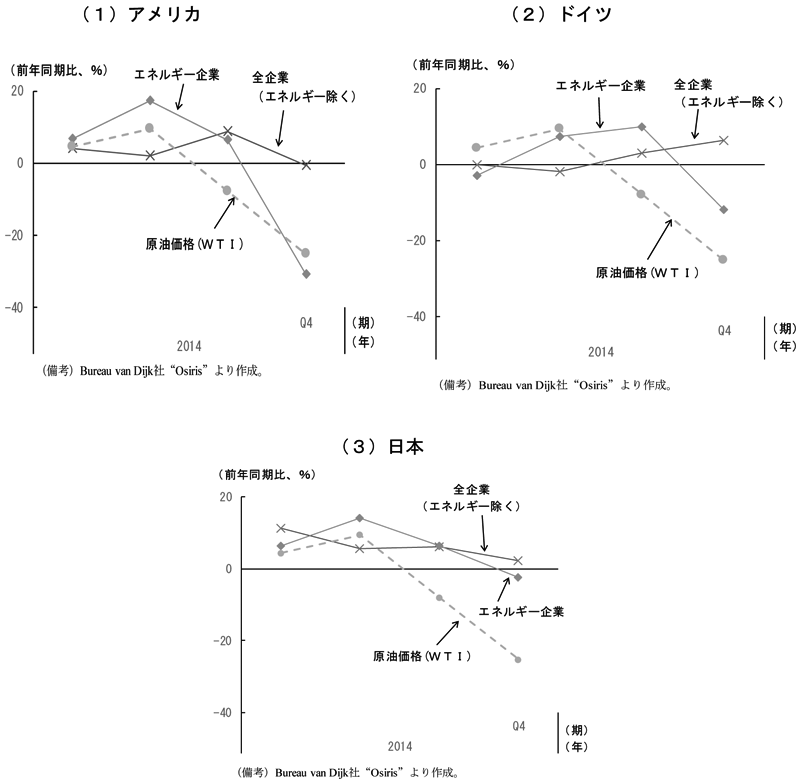
そこで、製造業PMIの販売価格D.I.から仕入れ価格D.I.を差し引いて疑似交易条件を算出してみると、日本は14年6月と比較して仕入れ価格D.I.も販売価格D.I.もほとんど低下しておらず、疑似交易条件に変化はみられない。他方、アメリカ、ドイツ、英国は仕入れ価格D.I.の低下が販売価格D.I.の低下を上回り、疑似交易条件が改善傾向にあることから、これらの国々では原油価格下落の企業収益へのプラスの影響が15年以降に出ていることがうかがわれる(第1-2-10図)。
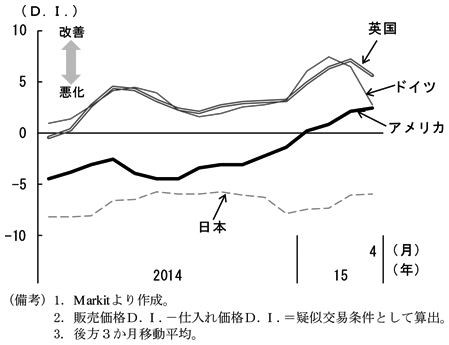
15年1~3月期の企業収益見通しをみると、アメリカ(S&P500)は前年比2.2%増加、ヨーロッパ(STOXX600)は同10.6%増加する見通しとなっている(第1-2-11図)。このうちエネルギーセクターの収益は、それぞれ同▲57.9%、同▲32.5%と大幅に落ち込む見込みとなっており、特にアメリカではエネルギーセクターの減益が企業収益全体に与えるマイナスの影響が大きいとみられる。ヨーロッパについても、15年1~3月期の企業収益見通しを国別にみると、ドイツ等はプラスとなっているのに対し、英国やノルウェーは大幅なマイナスとなっている。産油国であるアメリカや英国等では原油価格下落によるマイナスの影響が企業収益全体を下押しすることが懸念される。
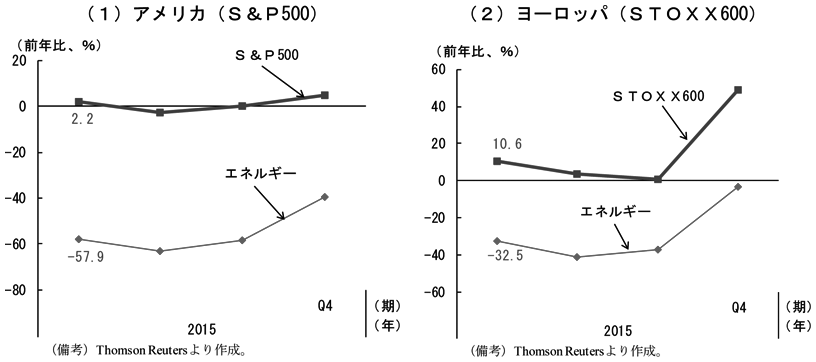
(2)生産・設備投資
次に、生産及び設備投資への影響を概観する。アメリカは、全体としてみれば原油の純輸入国であるものの、これまでシェール革命によるシェール・オイル増産の影響で生産や設備投資が鉱業を中心に高い伸びを示していた。しかし、原油価格の下落によってこれらが鈍化している。
シェール・オイルは、地中のシェール層に割れ目を入れて採掘するため、地域差はあるものの中東の産油国と比較して、生産コストは高いとされている。IEA(国際エネルギー機関)の試算(13年)によると、シェール・オイルの生産コストは約50~100ドル/バレルであるのに対し、中東や北アフリカの原油の生産コストは約17ドル/バレルとなっている。原油価格の下落によって、アメリカのシェール・オイルの生産は採算割れとなり、減産されるところも出てきている。
実際、シェール・オイルの採掘を行うための掘削設備(リグ)の稼働数は、原油価格の下落が加速した14年11月下旬以降、大幅に減少している(第1-2-12図)。リグの稼働数の減少が原油の減産に結びつくまでタイムラグがあるとみられるが、鉱業生産は15年1月以降前月比で減少しており、エネルギーセクターの投資抑制の影響が出始めている。また、15年1月以降、鉄鋼等を含む1次金属の生産も減少しており、鉱工業生産全体も減少傾向で推移している。原油安によるエネルギー関連企業の設備投資の大幅な落ち込みの影響から、石油などの採掘に使われる鋼管を製造する工場が操業停止するなどの動きもみられる。
設備投資についても、民間設備投資のうち鉱業関連の設備投資が大幅に減少しており、原油価格下落の影響がみられる(第1-2-13図)。今後、シェール・オイル関連機械への投資の減少といった直接的な影響に加え、石油化学といった関連セクターにも影響が及べば、設備投資への影響が拡大する可能性もある。
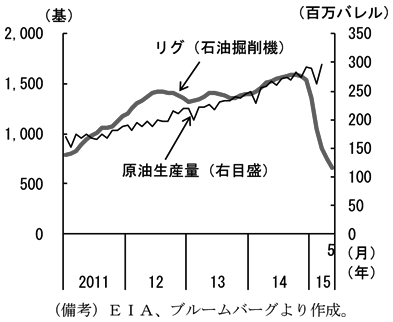
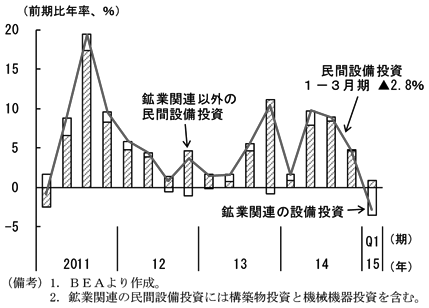
なお、こうした生産や設備投資の伸びの鈍化は、鉱業の経済に与える影響が全国平均よりも大きいアメリカの主要原油生産地域4州(テキサス、アラスカ、カリフォルニア、ノースダコタ)を中心に影響が出るとみられる(4州のGDPに占める鉱業の割合は6.6%と、全米平均の2倍以上)(第1-2-14表)。Fedが公表する地区連銀経済報告(ベージュブック、15年4月15日公表)によると、ダラス連銀管轄区(テキサス州)やミネアポリス連銀管轄区(ノースダコタ州)等のエネルギーセクターでレイオフが行われたほか、ダラス連銀管轄区等で石油・ガス産出業の15年の投資が減少する見込みとの報告があった。
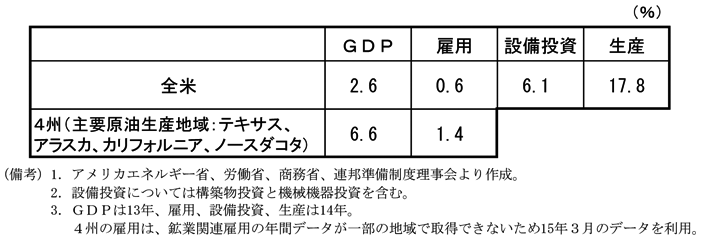
英国についても、英国の北海油田の埋蔵量の8割近くは損益分岐点が60ドル/バレル以上ともされており5、1~3月期の原油価格水準(平均58ドル/バレル)では採算割れの状況となっていた可能性がある。こうした中、石油関連企業は、投資削減や人員削減などのコスト削減策を発表している6
。鉱業生産の推移をみると、14年6月以降減少傾向にあり、北海における原油・ガス生産の減少が要因とみられている。英国の鉱工業生産に占める鉱業のシェアは15.7%とアメリカと同程度であり、鉱業の生産活動がさらに低下した場合は英国の生産活動全体の伸びが鈍化することが懸念される(第1-2-15表)。投資については、14年10~12月期の民間設備投資が前期比マイナスとなった要因として、原油価格下落等によって産油部門等の設備投資に一時的な弱さがみられること(tentative signs of weakening)が指摘されている7
。

以上のように、企業収益については、エネルギーセクターの大幅な減益が全体の収益を下押しする懸念がある。生産及び設備投資については、産油国であるアメリカや英国では既にマイナスの影響がみられるものの、鉱業がGDPに占める割合は両国ともそれほど高くないことから、経済全体への影響は限定的とみられる。

