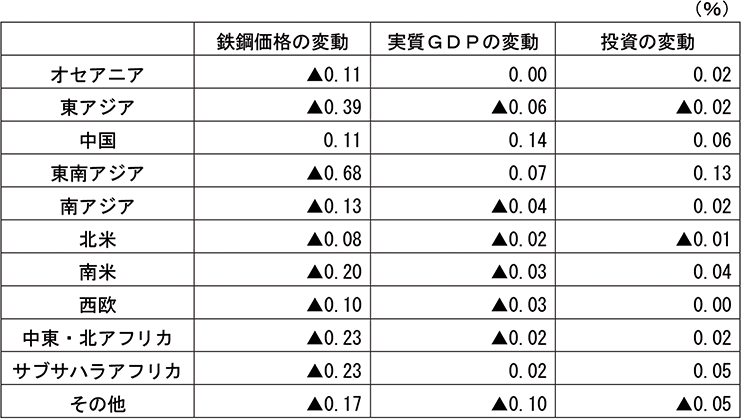第1章 中国経済が世界経済に与える影響(第2節)
第2節 中国の最近の景気動向
第1節では、人口動態や貿易構造を中心に、中長期的あるいは構造的な観点から中国経済を概観した。そうした中長期的・構造的な経済動向を踏まえつつ、本節では、より短期的な景気動向に焦点を当て、主に2024年後半の中国経済を概観する。あわせて、いわゆる「過剰供給」の実情と輸出を通じて世界の物価に与える影響について更に掘り下げて分析を行う。
1.マクロ経済の動向
(政策効果により供給の増加がみられるものの、景気は足踏み状態)
中国の実質GDPについてやや長い目で振り返ると、2000年代半ばには10%を上回るペースで成長していたが、2008年の世界金融危機以降は成長率がやや鈍化し、2010年代半ばにはおおむね7%程度の成長率で推移した(第1-2-1図)。その後、2020年から2022年にかけて断続的に感染症の影響で成長率が大きく変動した後、2023年には5.4%まで成長率が低下した。この間の実質GDPの成長を需要項目別にみると、概して政府消費を含む最終消費と在庫変動を含む資本形成が大きく成長に寄与しており、2010年代以降は資本形成の寄与がやや低下してきた一方で、最終消費の寄与は5%ポイント程度で推移してきた。
その上で、2024年後半の中国の実質GDP成長率についてみると、7-9月期には前年同期比4.6%と4-6月期の同4.7%から減速した後、10-12月期は同5.4%に伸びが加速した。この結果、2024年通年としては、2024年3月の全国人民代表大会(以下「全人代」という。)で掲げられた目標「5%前後」と一致する前年比5.0%の成長となった。需要項目別にみると、4-6月期以降は家計消費を中心とする最終消費の寄与が大きく低下する中、純輸出(外需)と資本形成の寄与が高まって通年で5%の成長率を保った姿となっている。特に2024年は純輸出の寄与が1.5%ポイントまで拡大したが、2000年以降で純輸出の寄与が1.5%ポイント以上となった例は他に2か年しかなく、こうした外需依存の高まりが2024年の中国経済の特徴であったと言えよう。
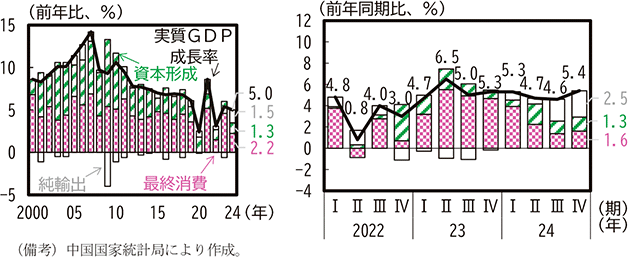
(堅調な製造業投資と生産)
成長を下支えしている固定資産投資について内訳をみると、不動産開発投資が前年同期比で大幅なマイナスとなっている一方、製造業投資が高い伸び率で推移し、固定資産投資全体を下支えする構図となっている(第1-2-2図)。製造業投資の高い伸びの背景には、政府による大規模設備更新に対する支援がある。2024年3月の国務院による通知を踏まえ、各地方政府等が行動計画を策定して取組を進めるとともに、7月には超長期国債を財源として、後述する消費財の買換え支援等と合わせて3,000億元(約6兆円)の財政支援が打ち出されている。また、インフラ投資については、2024年夏頃までは年初来累計前年比の伸び率が低下し、9月には4.1%となったが、10月以降は伸び率がやや高まり、12月には4.4%となった。インフラ投資等に活用される地方特別債の年初来累計新規発行額は夏頃まで前年を下回るペースが続いていたが、8月以降発行が加速し、9月以降は前年を上回っている(第1-2-3図)19。
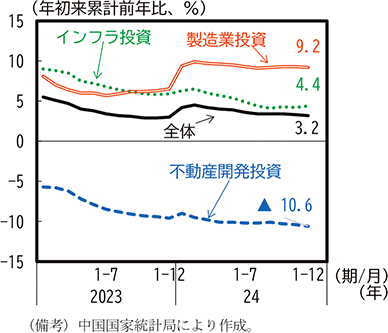
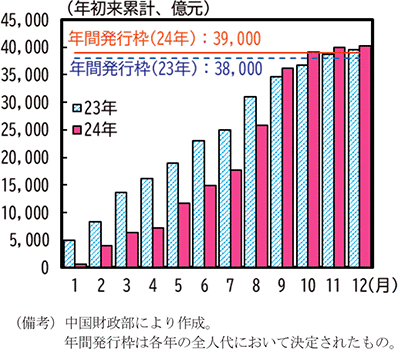
堅調な製造業投資による供給能力の拡大もあり、鉱工業生産は持ち直しを続けている(第1-2-4図)。業種別にみても多くの産業で生産が持ち直しているが、特に2023年後半から半導体サイクルが拡大局面にある中で、半導体を含むコンピュータ・通信・その他電子器具が前年比で高い伸びを示している。もっとも、2024年平均では前年同月比5.5%の伸びとなっており、感染症拡大前(2015~2019年)の平均である同6.1%と比較するとやや低い水準となっている。
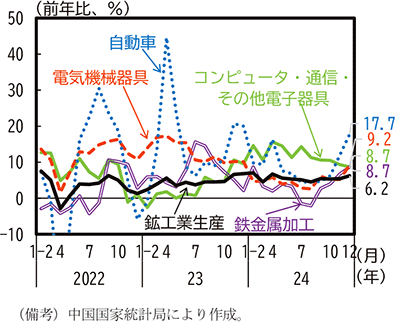
(消費はおおむね横ばい)
一方、成長の下押し要因となっているのが家計消費である。家計消費の動向について名目小売総額をみると、2024年は年間を通じておおむね前年同月比3%前後の伸び率で推移している。感染症拡大前(2015年~2019年)の平均が前年同月比9.7%であったことと比較すると、低い伸び率にとどまっているといえる。(第1-2-5図)。
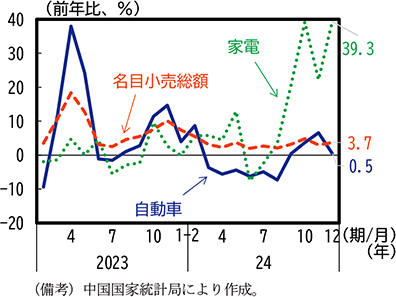
こうした消費の伸び悩みについて、背景にある雇用・所得環境、消費マインド、家計の住宅資産及び政策対応の要素に分けて確認する。
まず、雇用環境を都市部調査失業率からみると、中国において新卒者が労働市場に参入する7月から若年失業率に大幅な上昇がみられている(第1-2-6図)。若年失業率の上昇もあり、全体の失業率も7月から8月にかけて若干高まる兆しがみられたが、9月以降は夏前の水準に戻っておおむね横ばいで推移しており、全体の失業率からはマクロ的な雇用環境が明確に悪化している様子はみられない。ただし、若年失業率が依然として高い水準にあること、統計上は失業に含まれない不安定なギグワーカーや親の援助の下で非労働力化して生活している者等「隠れ失業20」が相応に存在する可能性には留意する必要がある。
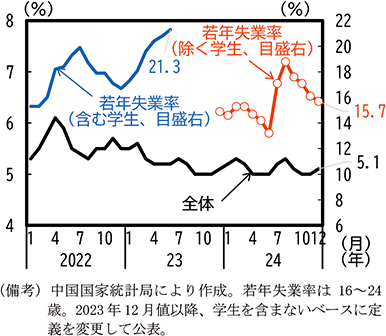
次に、所得面をみると、2024年の名目一人当たり可処分所得は前年比5.3%の伸びとなっており、2023年の前年比6.3%に比べて低下している(第1-2-7図)。所得の内訳をみると、ウェイトの大きい賃金・俸給の伸び率は感染症拡大前の水準からは低下したままとなっており、こうした所得の伸びの鈍化が消費の伸びの弱さの一因となっていると考えられる。また、「隠れ失業」による就業時間・日数の減少がマクロ的な所得の伸びの鈍化となって現れてきている可能性もある。
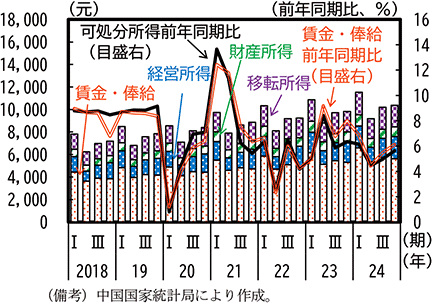
続いて、消費マインドの動向も確認する。消費者信頼感指数は感染症の影響により上海市でロックダウンが行われた2022年春以降、判断の境目となる100を下回る状態が続いている。消費意欲指数にはわずかに改善もみられる一方、特に若年失業率の上昇がみられた夏頃から雇用指数が大きく低下している(第1-2-8図)。2023年以降も消費マインドは感染症拡大前の水準に戻っていないが、消費マインドの弱さが継続する1つの要因として、2022年前後から継続している住宅価格の下落が影響していることが考えられる。
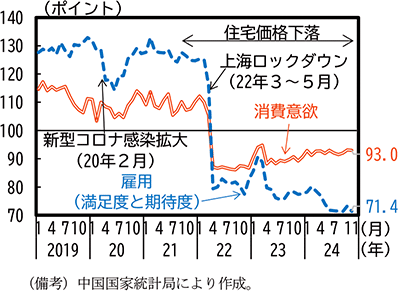
(住宅価格の下落に伴う負の資産効果)
このところの家計消費の弱さについては、住宅価格の下落が続くことによる負の資産効果も指摘されている21。ここでは住宅価格下落を受けた中国における家計の住宅資産額の減少が負の資産効果としてどの程度消費を押し下げているのか、その規模を推計する。
初めに感染症拡大前後から足下にかけての中国の住宅価格の動向を確認する。過熱していた不動産市況への対応として2020年8月に不動産融資規制22が導入されたこと等を受け、2021年9月頃から大手不動産企業の信用不安が表面化し、まず2級都市(重慶等)、3級都市(地方都市)において新築、中古いずれの住宅価格も下落に転じた(第1-2-9図)。更に2023年半ば頃から不動産企業の資金繰り難が報じられる中で、1級都市(北京等)においても住宅価格が下落に転じ、2024年末に至るまで全国的な住宅価格の下落傾向が継続している状態にある。70都市平均では、2024年12月時点において、新築住宅についてはピーク時の2021年8月と比較して▲9.3%、中古住宅ではピーク時の2021年7月と比較して▲16.1%、それぞれ価格が下落している。
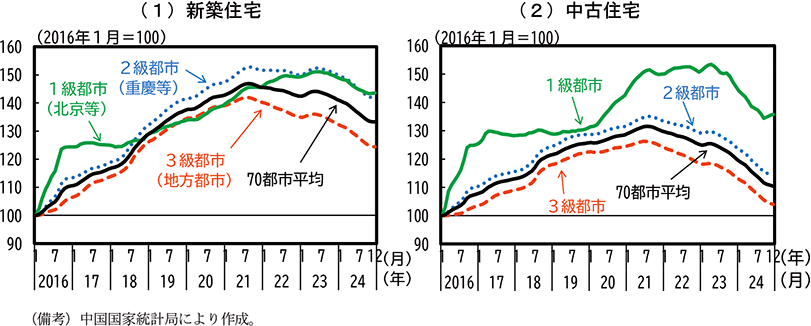
こうした住宅価格の動向を踏まえた上で、次に中国における家計の住宅資産額の動向を確認する。第1節でみた中国の一国全体のバランスシートを推計している中国国家金融発展実験室は、その内訳として家計部門の資産額全体や更にその内訳である家計の金融資産額、固定資産額等も推計しているが、固定資産の内訳までは示していない(第1-2-10図)。ただし、同シンクタンクに所属するエコノミストの論文には、2014年までではあるが、中国の家計資産額のより詳細な内訳を推計したものがある(Li (2018))。ここでは、同論文で推計された2014年末時点の家計住宅資産額を出発点に、同論文に倣った手法・データを用いて2024年6月時点まで延長試算した23。
試算された家計の住宅資産額は、主に住宅価格の上昇にけん引されて2021年まで増加(2015年から2021年までの年平均増加率は12.7%程度)を続けた後、住宅価格が下落に転じる地域が出てくる中で2022年以降はほぼ横ばいに転じた。さらに、2023年半ば以降1級都市でも住宅価格が下落に転じたことを受け、2024年6月時点の家計の住宅資産額は2023年末から4.5%程度減少したと試算される。
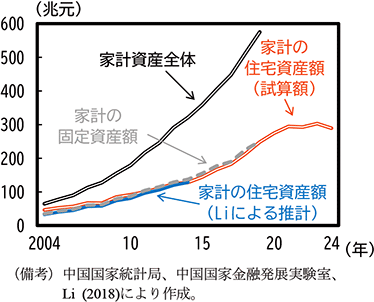
住宅資産額の変動が家計消費に与える影響については、先行研究から得られる弾力性を用いて推計する。中国における住宅資産額と消費の関係を分析したいくつかの先行研究24からは、消費の住宅資産額に対する弾力性がおおむね0.05~0.39程度、すなわち住宅資産額が10%減少すると消費が0.5~3.9%程度押し下げられる関係にあるとの結果が得られた。2024年6月時点の家計の住宅資産額は2023年末から4.5%程度減少と試算されたことから、これに先行研究に基づく弾力性を乗じると、2024年の家計消費には名目値で0.2~1.7%程度の押下げ効果(負の資産効果)が生じていると推計される。第1節でみたように、中国における家計消費の名目GDP構成比は4割程度と他の主要国に比べて低いが、名目GDP成長率にも最大で0.7%ポイント程度の押下げ効果が働いている可能性がある。
なお、上記の推計結果は住宅価格が全国的に低下に転じた2023年以降の消費の押下げ効果をみたものであるが、住宅価格が上昇していた2021年頃までは正の資産効果が働いていたと考えられることから、住宅価格下落前後の消費の伸びの変化をみる上では、住宅価格上昇局面からの資産効果の変化を推計することも重要である。2015年から2021年までの家計の住宅資産額は年平均12.7%増加していたと試算されることから、同様の弾力性を用いると、この間の資産効果としては家計消費が年0.6~4.9%程度押し上げられていたと推計される。したがって、住宅価格下落前の2021年以前と比較すると、2024年前半には0.9~6.7%程度の消費の押下げ効果が働いていたと捉えることもできる。
もっとも、ここで住宅資産額の試算に用いるデータには、未完成のまま工事が中断した不動産開発投資の影響が取り除けていない可能性があるといった制約があるほか、先行研究から得られる弾力性についても住宅価格上昇局面で推定されているため、今般の住宅価格下落局面では弾力性が変化している可能性にも留意する必要がある。したがって、この推計結果については相当の幅を持って解釈する必要がある。特に、2020年代の住宅価格下落局面における中国の住宅資産額に対する家計消費の弾力性については、今後の実証研究の蓄積が待たれるところである。
(政策効果により、自動車等の販売には持ち直しの動き)
最後に、家計消費の動向に関連する政策についても確認する。7月25日に国家発展改革委員会と財政部が発表した消費財の買換え支援策では、4月から実施されているEV等の新エネルギー車の購入に対する補助金を最大2万元まで増額するとともに、省エネ基準を満たす家電についても販売価格の15~20%を補助することが盛り込まれた。これらが各地方政府において順次執行に移された結果、9月頃から年末にかけて支援対象となった自動車や家電の小売販売額は前年同期比の伸びに高まりがみられた。家計消費における自動車の改善については、自動車販売台数のデータからも確認できる。自動車販売台数は2024年夏頃には前年同月比マイナスとなっていたが、家計向けを中心とする乗用車では9月から、主に設備投資となる商用車を含む全体でも10月から前年同月比プラスに転じている(第1-2-11図)。また、自動車販売台数に占める新エネルギー車の比率は2023年の31.6%から2024年には40.1%に上昇しており、この点からも自動車販売の動向に政策効果が発現していることが確認できる。
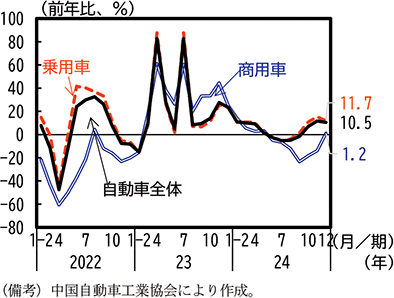
背景要因も含めて消費の動向を総合的にみると、足下では政策効果により一部品目の消費に改善がみられるものの、住宅価格の下落が継続する中で、家計の住宅資産が目減りし、負の資産効果が働くとともに、雇用・所得環境の改善も進まず、消費マインドも停滞した状況が続いており、消費全体の持ち直しには至っていない状況にあるといえる。また、足下で行われている補助金による消費の下支えは需要の前倒しにつながり、今後、反動減を生じさせるリスクもある。不動産市場の安定化や消費マインド、雇用・所得環境の明確な改善がない中では、消費の本格的な持ち直しは見通し難い状況にある。
(不動産市場の先行き)
このように、継続する住宅価格の下落は中国の家計消費に少なからぬ押下げ効果を生じさせている可能性があることから、住宅価格の下落傾向がこの先どの程度継続するのかは中国経済の先行きを占う上で一つの重要な要素となる。ここでは、関係するいくつかの指標の動向や我が国におけるバブル崩壊の経験を振り返り、手がかりを探ってみることとしたい。
まずは、中国の住宅市場における需給動向をみてみよう。2010年代後半には住宅着工面積と住宅販売面積がともに増加を続け、2019年時点では住宅販売面積15.0億平方メートルに対して住宅着工面積が16.7億平方メートルと、住宅着工面積が1億平方メートル以上上回っていたが、不動産融資規制の導入等を背景に住宅着工面積は2020年から減少に転じた。一方で、住宅販売面積はやや遅れて2022年から減少に転じ、2024年には販売面積8.1億平方メートルに対して着工面積は5.4億平方メートルと2.7億平方メートル程度着工面積が下回る状態となっている(第1-2-12図)。こうして4年以上にわたって住宅投資の調整が進められる中でも住宅在庫は2021年から増加を続けているが、2024年の前年比は18.0%と2023年の前年比22.2%からやや増加率が低下した(第1-2-13図)。
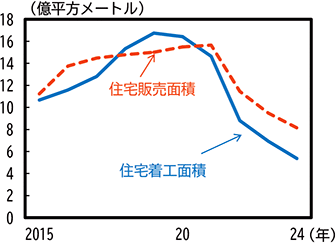
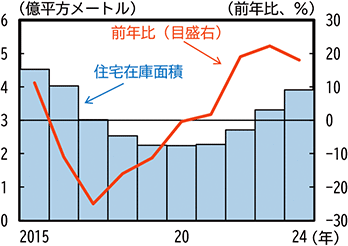
(備考)中国国家統計局により作成。住宅在庫面積は各年12月時点。
また、現在の中国における住宅価格の下落状況は我が国におけるバブル崩壊の例と比較されることがあるが、我が国におけるバブル崩壊前後における関連指標の動向をみると、首都圏のマンション価格は1990年にピークとなった後1995年まで下落を続け、1990年から1995年までの下落幅は▲32.3%であった(第1-2-14図)。一方で東京圏の住宅地価格は1991年にピークとなった後2006年まで15年にわたって下落を続け、1991年から2006年までの下落幅は▲58.7%であった。対象が異なることに留意する必要があるが、これらの下落率と比較すると中国の住宅価格のピーク時からの下落率は70都市平均で新築▲9.3%、中古▲16.1%、北京、上海等の1級都市では新築▲5.0%、中古▲11.5%となっており、相対的に小幅にとどまっている。
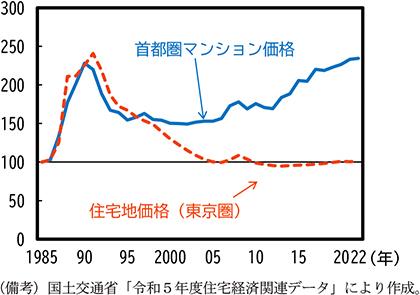
このように、いくつかの指標からは住宅市場の下げ止まりに近付いていることを示唆するような兆候もみられるところであるが、我が国のバブル崩壊後の経験に照らせば、住宅価格の更なる調整(下落)が生じる可能性も十分にあると考えられる。後述するように、特に2024年9月の中央政治局会議前後から当局は相次いで不動産市場の安定化に向けた政策25を表明しているところであるが、累積した住宅在庫や世帯数の増勢鈍化等の実需面を考慮すると、少なくとも、向こう数か月の短期間で住宅価格が反転上昇するような見通しを持つことは難しい。また、今後住宅市場が底打ちしたとしても、第1節でみたように総人口が減少に転じて世帯数の伸びも鈍化している中、これまでと同様のペースで不動産開発投資を行うことは困難であると考えられる。こうしたことから、当面は住宅価格の下落に伴う負の資産効果が消費やマクロ経済全体の下押し要因として継続する可能性に留意する必要がある。
(輸出は緩やかに増加している)
消費を中心とした内需の弱さとは対照的に、財輸出は緩やかに増加している。前節でもみたように、2024年以降は世界的な需要拡大局面にある半導体(集積回路)やここ数年拡大を続けている自動車を中心に輸出が拡大している。また、価格要因と数量要因を分解してみると、特に2023年頃から中国の輸出価格(米ドル建て)は低下を続けており、数量ベースでは金額ベース以上に輸出が拡大している姿が読み取れる(第1-2-15図)。特に、近年輸出を伸ばしている自動車や鉄鋼といった品目で価格下落が継続している(第1-2-16図)。輸出価格の下落が中国製品の輸出競争力を高めているとみることができるが、一方ではこうした動向が「過剰供給」問題として欧米を中心とした各国との摩擦につながっている。「過剰供給」の現状やそれが世界経済に及ぼす影響については後述する。
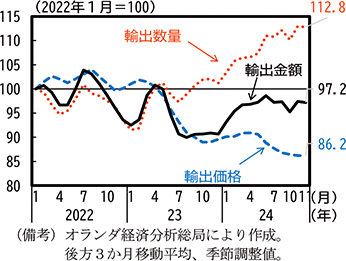
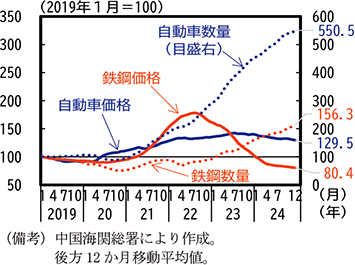
(物価は下落傾向が続く)
上述した内需の弱さは物価の下押し圧力となることが考えられる。この点について、消費者物価(CPI)上昇率をみてみると、2023年後半はマイナス圏で推移し、2024年に入って以降豚肉価格が上昇に転じたこと等によりプラス圏にあるが、おおむね0%台前半にとどまっている(第1-2-17図)。一方、生産者物価(PPI)については、2022年10月から2年以上にわたって下落が継続している。PPIは輸入物価の動向との連動性もあり、国内の需給ギャップのみが要因とはいえないが、GDPデフレータも7四半期連続でマイナスとなっており、物価の下落傾向には歯止めがかかっていない。
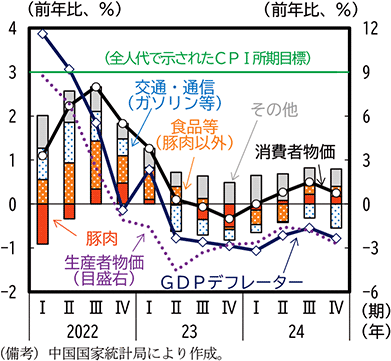
なお、輸入物価とCPI、PPIとの関連をやや長い期間でみてみると、CPIは輸入物価とあまり連動性がみられない一方、PPIについてはこれまで輸入物価と高い連動性がみられてきた(第1-2-18図)。また、両者の時差相関をとると、ラグなし(同時)での相関が最も高い。一方で、2024年夏の局面では輸入物価は一時的に上昇した一方、PPIは上昇に転じておらず、両者の動きにややかい離がみられる。PPIの内訳をみると、川上である鉱物価格や原材料価格は輸入物価と同様に2024年夏に一時上昇に転じていたが、川下の財の価格はこの時期も上昇に転じていないことから、内需が伸び悩む中で、企業が輸入品を含む鉱物、原材料価格の上昇を川下の製品価格に十分転嫁できなくなっている可能性がある(第1-2-19図)。
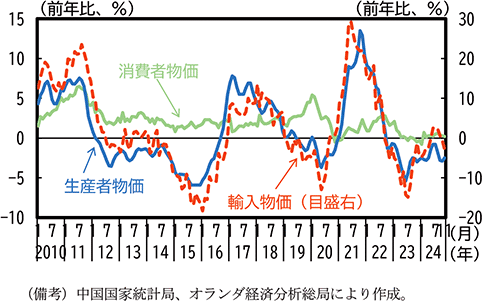
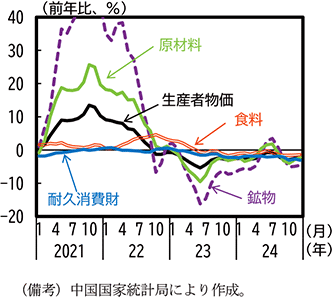
(不動産市場の安定化や内需の拡大に向けた政策対応)
内需の伸び悩みが続く中、2024年3月の全人代で設定された2024年の成長率目標「5%前後」の実現に向け、2024年秋に相次いでいくつかの政策対応が打ち出された(第1-2-20表)。
9月26日の中央政治局会議では、例年9月の会合では取り扱わない経済をテーマとし26、必要な財政支出の保証、預金準備率や金利の引下げ、不動産市場の下げ止まり・安定化の促進、低所得者等に対する支援の強化等の追加的な経済対策を打ち出していく方針が示された。
これに先立って、9月24日には、中国人民銀行ほか金融関係当局が合同会見を開き、金融面での追加対策を発表した。預金準備率や主要政策金利の引下げ、既存の住宅ローン金利の引下げ、証券会社等が株式投資を行うための新たな資金供給手段の創設等が盛り込まれ、このうち既存の住宅ローン金利の引下げについては家計の利払い負担を年1,500億元程度(家計消費の0.3%程度に相当)軽減する効果があるとの説明がなされた。この発表を受け、9月25日から29日にかけて、大手・中堅行を中心に預金準備率が▲0.5%ポイント、短期の政策金利であるリバース・レポ金利(7日物)が▲0.2%ポイント、中期の政策金利である中期貸出ファシリティ(MLF)金利(1年物)が▲0.3%ポイント、それぞれ引き下げられた。既存の住宅ローン金利については、10月末までに平均で▲0.5%ポイント引き下げられることとなった(第1-2-21図)。
その後も国慶節の連休を挟んで国家発展改革委員会や財政部が相次いで会見を行い、2025年の国家プロジェクトの総額2,000億元分(約4兆円)の前倒し実施や特別国債発行による国有商業銀行への資本注入、学生への奨学金拡充等の政策対応を表明したほか、11月の全人代常務委員会では地方政府の隠れ債務解消のために地方特別債の発行上限6兆元の引上げが議決された。ただし、これらの施策のうち、政策金利や既存の住宅ローン金利の引下げ、2025年の国家プロジェクトの前倒し実施等は消費や投資の直接的な押上げにつながると考えられる一方、国有商業銀行への資本注入や地方政府の隠れ債務解消策は必ずしも直接的、抜本的な需要拡大につながるものではないことに留意が必要である。
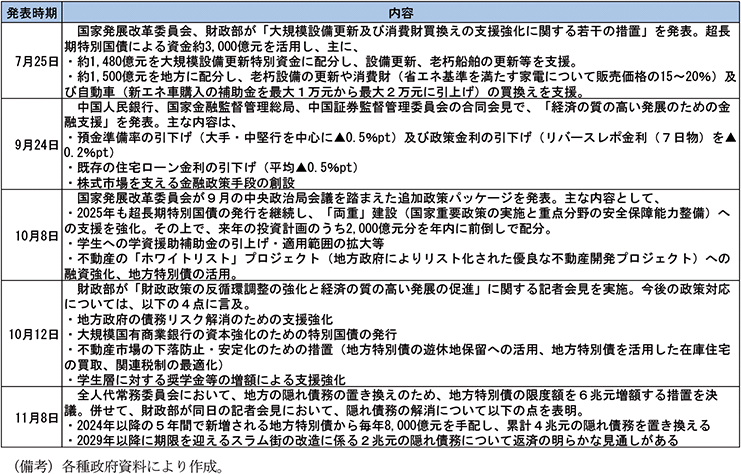
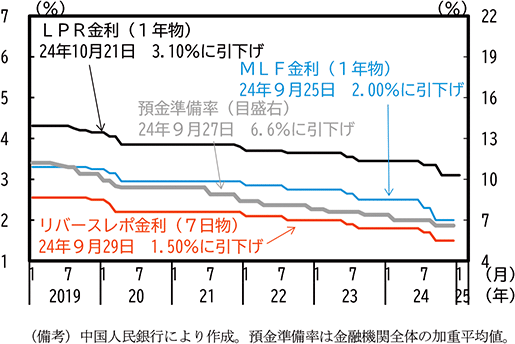
こうした中、選挙期間中から対中関税の引上げ等に言及していたトランプ候補が11月5日のアメリカ大統領選挙において当選するなど、通商関係を中心とする先行きの対外経済環境にも変化が見込まれることとなった。12月11日から12日に開催された中央経済工作会議では、内需の不足といった国内の課題とともに、外部環境の変化による不利な影響が深まっているとの課題認識が示され、2025年の財政政策スタンスは「積極的な財政政策」から「より一層積極的な財政政策」へ、金融政策のスタンスは「穏健的な金融政策」から「適度に緩和的な金融政策」へ、それぞれ景気刺激的な方向に転換する方針が示された(第1-2-22表)。より具体的には、財政政策の面では、2024年において3%となっている財政赤字の対GDP比目標水準の引上げや超長期特別国債、地方特別債の発行増が盛り込まれた。また、金融政策では適時に預金準備率や政策金利を引き下げることが盛り込まれたが、特に「適度に緩和的な金融政策」との表現が用いられるのは世界金融危機後の2008年11月から2010年までの期間以来であり、これまでよりも踏み込んだ金融緩和が行われる可能性が示唆されている。
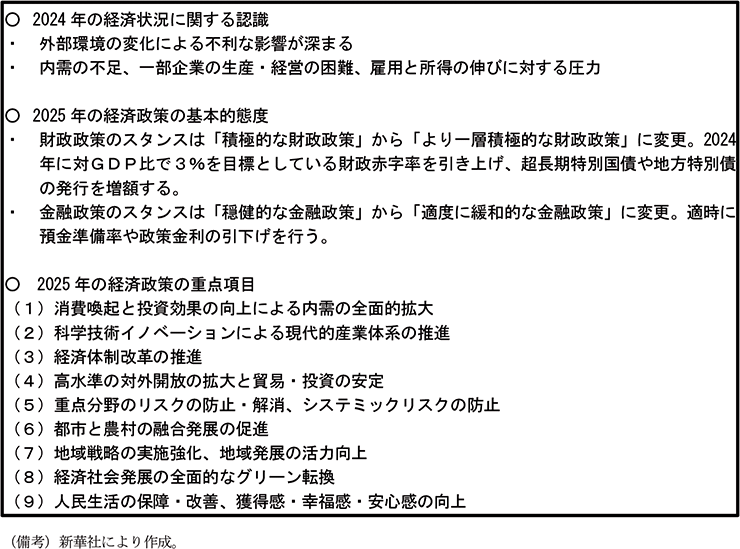
(まとめ)
以上のように、2024年後半の中国では、政策効果により供給の増加がみられるものの、景気は足踏み状態が続いている。政策的支援を背景に製造業投資が拡大を続け、一部耐久財消費も足下で増加しているが、雇用・所得環境や消費マインドの改善がみられない中で消費全体の伸びはなお弱く、供給に対して需要が弱い状態が継続、物価も下落基調となっている。こうした中で、輸出価格が低下を続ける下で数量ベースの輸出が拡大することにより、通年で5%の成長を維持した姿となっている。当局は秋以降相次いで追加の政策対応を発表したが、その中には直接的な需要喚起につながらないものも含まれている。
こうした中で、2025年1月には、大統領選挙期間中や当選後に対中関税引上げ等を主張してきたトランプ氏がアメリカ大統領に就任し、今後は通商関係等の外部環境も厳しさが増していく可能性がある。これまで相対的に好調であった輸出の動向は通商関係に大きく影響を受けることから、今後の通商関係の動向には十分留意する必要がある。12月の中央経済工作会議では、こうした内外の経済環境に対する厳しい認識と、より景気刺激的な財政・金融政策への転換を図り内需を全面的に拡大させる方針が示されたところであり、今後は3月の全人代に向けて具体化されていくと考えられるその内容や規模が焦点となる。
2.「過剰供給」の現状と世界経済に与える影響
(「過剰供給」問題)
中国では、家計消費等の内需が停滞している一方、製造業投資や生産、輸出が増加を続ける中で、2024年には欧米から「過剰供給」問題が相次いで指摘されることとなった。2024年6月のG7首脳会合のコミュニケ27では、中国の産業政策や非市場的政策・慣行が過剰生産につながり、G7諸国の労働者・産業・経済的強靭性・経済安全保障を損なっている旨の懸念が表明された。具体的に「過剰供給」が指摘される品目としては、電気自動車(EV)や鉄鋼、リチウムイオン電池、太陽光パネル等が挙げられ、実際にアメリカやEUは中国政府による不公正な補助金措置等を理由として、これらの品目の中国からの輸入に対して相次いで関税の引上げを行っている。
このように指摘されている「過剰供給」問題について、鉄鋼と自動車を例にとってデータの面から確認する。まず、企業の生産能力を品目別にみると、EVを含む自動車については2016年以降一貫して生産能力が拡大してきている(第1-2-23図)。中国政府が2015年に定めた10か年計画である「中国製造2025」において、発展させるべき重点産業の1つとして省エネルギー・新エネルギー車が掲げられており、補助金等の政策的支援が行われたことが1つの要因と考えられる。鉄鋼については、当時から課題となっていた過剰生産能力の削減の取組により2017年にはやや縮小したものの、川下のインフラ関連投資や不動産開発投資が増加していく中で、2018年以降は生産能力が再び拡大した。2022年以降は不動産開発投資は減少に転じたが、鉄鋼の生産能力の拡大が続いている。
また、稼働率をみてみると、鉱工業全体としては2022年以降緩やかに低下しているが、2016年頃よりは高い水準にある。品目別にはややばらつきがあり、自動車については2017年の82%をピークに2024年にかけて▲10%ポイント程度の低下がみられるが、鉄鋼についてはここ数年で大きな低下はみられない。ここ数年の自動車における稼働率低下は、国内販売面で急速に新エネ車への移行が進む中で、ガソリン車用の生産設備に過剰感が生じていることが一因となっている可能性がある。
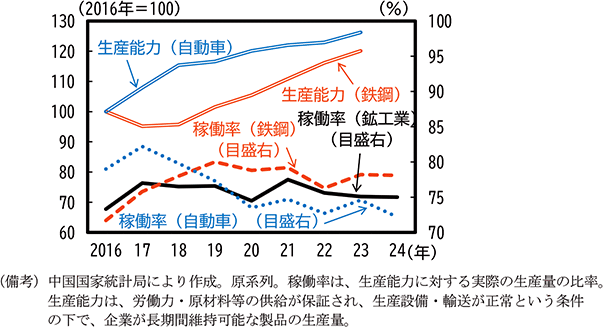
続いて、鉄鋼生産量、国内需要量をみると、2021年以降の不動産開発投資の減少に伴って国内需要量が減少しても、鉄鋼生産量は必ずしも減少していない。特に、2014~2016年、2022年以降にみられるように、国内需要量が減少しても生産量が同じペースでは減少せず、同時期に輸出量が増加していることから、そのかい離分は輸出されてきたことが示唆される(第1-2-24図)。
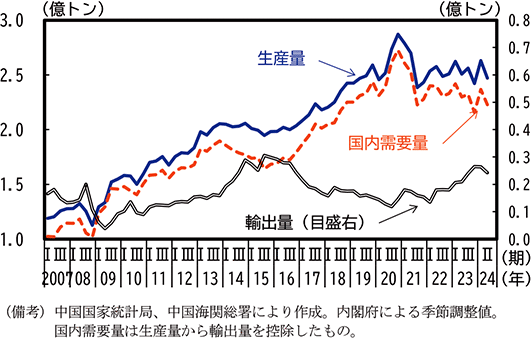
鉄鋼価格と輸出量の相関関係をみると、第1-2-25図が示すように、輸出量が増加している期間では、輸出価格が下落している。これは、国外需要が増加したことによる輸出増というよりは、国内需要が減少したことによって余剰となった鉄鋼を国外に輸出していることを示唆していると考えられる。
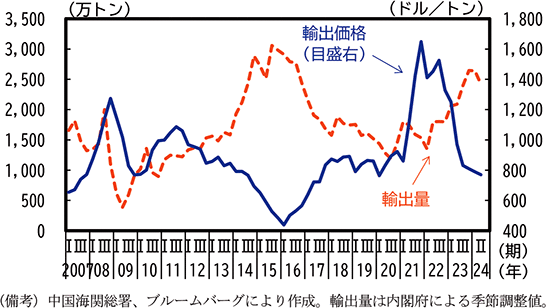
次に、中国の自動車についてみると、鉄鋼と同様に、2023年以降国内販売台数が減少傾向で推移する中、生産台数は維持されていることから、そのかい離分が輸出に回り、輸出台数の増加となっている可能性がある(第1-2-26図)。特に、2022年以降、輸出台数は急増し、2023年には491万台と日本を抜いて世界一となっている。
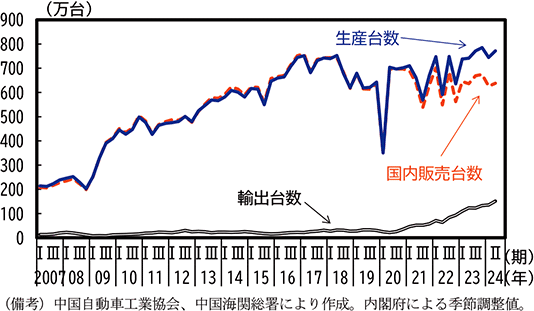
自動車の価格と輸出台数の関係をみると、第1-2-27図が示すように、輸出台数が増加している期間において、鉄鋼ほどではないものの、価格が下落している。
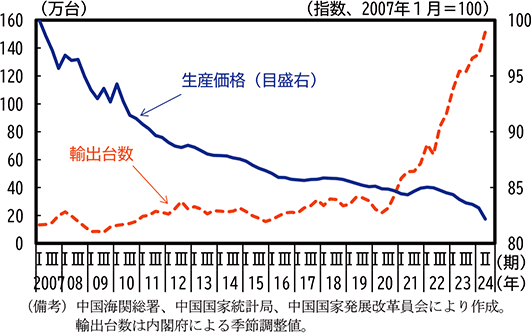
(鉄鋼・自動車の供給・需要関数の推計28)
以上のデータ観察を踏まえると、不動産市場の停滞に伴う内需全体の伸び悩みの中で、鉄鋼や自動車に対する国内需要も減退し、これらの財の価格低下と輸出量の拡大といういわゆる「過剰供給」が生じている可能性がある。これが生じているかどうかを明らかにするために、2010年代以降の中国内外のマクロデータを用いて中国の鉄鋼と自動車に関する供給関数と需要関数を同時方程式モデルで推計した29。推計に当たっては、住宅の資産効果の影響を重点的に取り入れることとした。
まず、鉄鋼の推計結果をみると、供給関数は輸出価格に関して有意水準を満たす正の係数が得られた。また、海外GDP30については、有意な推計結果が得られなかった。海外経済が好況となることによって中国からの鉄鋼輸出が増加するというよりも、中国国内の需要と供給の動向によって輸出が増減していることが示唆される。
続いて、推計された需要関数をみると、輸出価格に対しては負、中国国内の新築住宅販売価格には正でそれぞれ有意水準を満たす係数が得られた。鉄鋼需要の価格に対する反応や鉄鋼を使用する住宅価格への反応は直観的理解に一致する。
以上から鉄鋼に関しては、供給関数は右上がり、需要関数は右下がりの曲線と推計された。
・鉄鋼の供給関数と国内需要関数3132(推計期間:2016年1-3月期~2024年4-6月期)
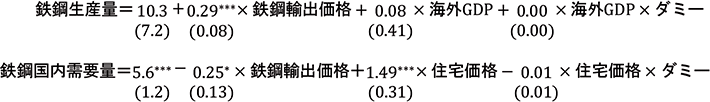
次に、自動車の推計結果をみると、供給関数は価格に関して有意な係数が得られず、供給曲線は垂直(自動車価格の変動に対して反応しない)という推計結果となった。前述したように、この間の中国では省エネルギー・新エネルギー車産業が重点的に育成されており、補助金等の支援もある中で自動車価格の動向に左右されず生産が拡大してきたものと考えられる。なお、中国の実質GDPには正に有意な推計結果が得られており、国内の需要の増加が中国の自動車生産量に正の効果を与えていることが分かる。ただし、2018年10-12月期以降は、その効果がやや減少している。需要関数については、価格に関して負に有意な係数が得られ、一般的な右下がりの需要曲線が推計された。また、住宅販売面積について正に有意な係数が得られており、住宅需要の増加も自動車需要の増加に寄与していると捉えることができる。2018年10-12月期以降はその効果が一部減少する。
・自動車の供給関数と国内需要関数333435(推計期間:2012年1-3月期~2024年4-6月期)
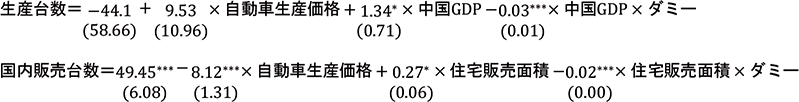
(鉄鋼、自動車の「過剰供給」の試算)
本推計では、鉄鋼の国内需要量に対しては中国の住宅価格、自動車の国内販売台数に対しては住宅販売面積が有意に正に寄与することが推計された。これらの変数の動向をみると、第1-2-28図、第1-2-29図のように、不動産市場の停滞とともに鉄鋼や自動車の国内需要が伸び悩む傾向にある。
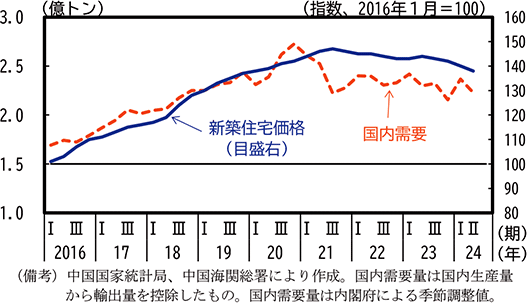
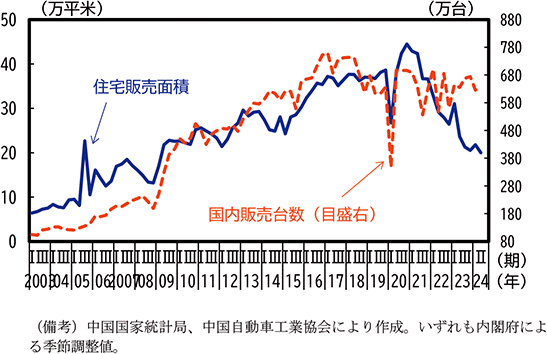
鉄鋼と自動車について、需要・供給関数の推計結果を用いて、特定の条件下での「過剰供給」の状況の試算を行う。先に確認した中国の不動産市場の状況も踏まえ、他の説明変数を一定と仮定しつつ、2023年末から2024年4-6月期までの住宅価格の下落率である2.7%、2023年1-6月期と比較した2024年1-6月期の住宅販売面積の下落率である22.2%を用いた場合、2023年値を基準とすると、鉄鋼と自動車それぞれの価格が変化しなければ、両品目の国内需要の減少分はそれぞれ1,955万トン、71万台となる。
世界市場での中国からの輸出増に対する世界全体の価格調整速度が中国と同程度であると仮定する36と、価格はそれぞれ3.8%、0.3%低下し、輸出量はそれぞれ22.3%、16.2%増加することとなる。現実には、2023年1-6月期と比較して2024年1-6月期は、価格はそれぞれ29.8%、1.8%下落し、輸出量はそれぞれ21.7%、23.0%増加している。試算値は、価格が下落しつつ、輸出量が増加するという実績値の方向性と一致し、中国の不動産市場の停滞による輸出の増加は国際市場に大きな影響を及ぼす結果となることが示唆される37。
(「過剰供給」が世界経済・物価に与える影響)
上述のように、中国の不動産市場の停滞は、中国からの鉄鋼や自動車の輸出価格の下落と輸出量の増大をもたらすことが示唆された。本稿では鉄鋼38を例にとり、GTAP39(Global Trade Analysis Project)を用いて、中国からの鉄鋼輸出が増加した場合に世界経済全体に与える影響を試算する。なお、試算はあくまで方向性を示すものであり、定量的な影響を分析するものではない。
GTAPにおいて、中国からの輸入価格低下と鉄鋼輸出の増加を疑似的に表現するための仮定として、鉄鋼について貿易の効率性を示すパラメータ40を10%向上させた場合の試算結果をみる(第1-2-30表)。
まず、中国においては、鉄鋼の輸出が増えることから鉄鋼価格、投資が上昇し、それが実質GDPを増加させる。
中国からの鉄鋼の主な輸出先である東南アジア、南アジア、中東・北アフリカ、サブサハラアフリカでは、鉄鋼価格が下落するが、東南アジアやサブサハラアフリカでは投資が増加し、実質GDPが増加している。一方、中東・北アフリカや南アジアでは投資は増加するものの、実質GDPは減少する。
鉄鋼業が盛んな東アジア、北米、西欧では鉄鋼価格の下落に伴う投資誘発効果は限定的であり、国際市場で国内の鉄鋼業が価格や輸出量の低下という影響を受けることから、実質GDPは低下する。
このように、中国において「過剰供給」となった鉄鋼の輸出の影響は、国・地域によって異なるが、これは各国・地域の産業構造の違いに起因すると考えられる。特に、競合する鉄鋼業が立地する国・地域の場合には、鉄鋼価格の下落と実質GDPの低下という負の影響を与えることになる可能性がある。