第1章 中国経済が世界経済に与える影響(第1節)
第1節 人口動態と貿易構造からみた中国経済の特徴
本節では人口動態や貿易構造からみた中国経済の中長期的な発展の特徴について確認する。
1.中国経済の概観
(世界第2位の経済規模)
中国は、1980年代の改革開放以来、実質で平均10%程度の高い成長を続け、2001年のWTO加盟等も経て、「世界の工場」として世界の成長をけん引してきた。その結果、2010年にはドル建ての名目GDPで日本を抜き、アメリカに次ぐ世界第2位の経済規模となった。2023年には、世界に占める各国のドル建て名目GDPのシェアは、アメリカが26.2%、中国が16.8%、ユーロ圏が14.8%、日本が4.0%となっている(第1-1-1図)。IMFの予測によれば、成長のスピードは現在よりやや鈍化するものの、2025年から2029年にかけて名目で5%超の成長を続け、世界第2位の経済規模を維持する見通しとなっている。
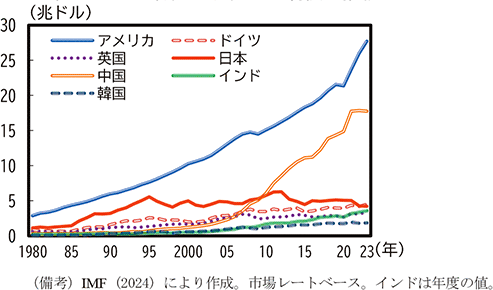
一方で、国民の所得水準を示す一人当たり名目GDPをみると、中国は2023年に1.3万ドル程度となっている。これはロシア(同1.4万ドル程度)、メキシコ(同1.4万ドル程度)、トルコ(同1.3万ドル程度)、マレーシア(同1.2万ドル程度)といった国々と同程度であり、日本と比較すると3分の1程度の水準である(第1-1-2図)。経済規模が世界第2位と世界経済で大きな位置を占めるようになって久しい中国であるが、一人当たりの所得水準でみれば高中所得国1の地位にある。
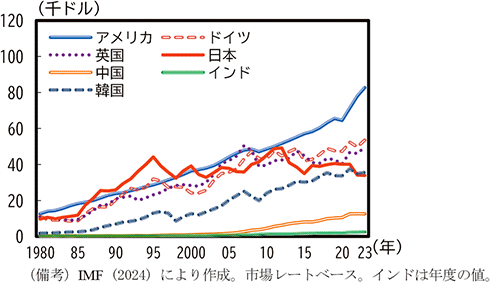
(中国のGDPの構成)
世界第2位の経済規模である中国のGDPについて、その構成を確認してみよう。まずは支出面について他の主要国と比較すると、企業の設備投資や公共投資を含む総固定資本形成が約41%と最大の構成項目となっており、これは総固定資本形成の構成比が大きかった1980年の日本の水準(約35%)も上回っている。一方、他の主要国では最大の構成項目となっている家計消費の構成比が中国では約39%と4割を下回っている(第1-1-3図)。なお、2000年の時点では家計消費の構成比は約47%であった一方、総固定資本形成の構成比は約33%であり、家計消費が最大の構成項目であった。中国では、2000年代以降、投資の伸びが家計消費の伸びを上回って推移してきたことが分かる。
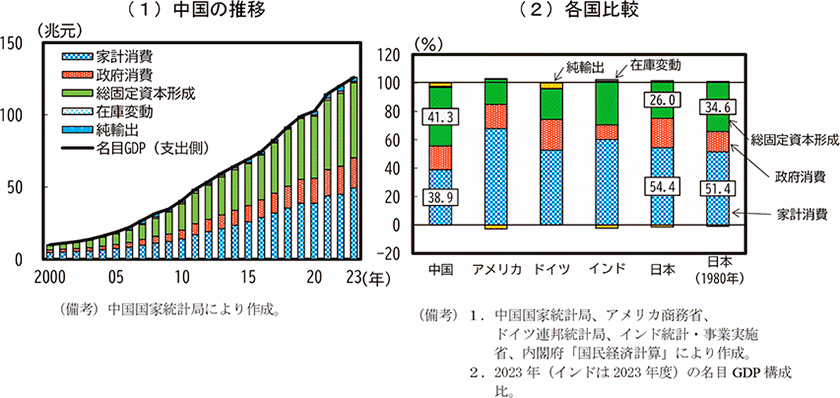
次に、中国のGDPの生産面、すなわち産業構成を確認する。主要国と比較してみると、製造業を中心とする第二次産業の構成比が約38%と他の主要国に比べて高くなっている(第1-1-4図)。この第二次産業の構成比の高さは経済のサービス化の進展途上にあった1980年の我が国と同程度の水準である。このことは、他の主要国の歴史的な経済成長の過程でみられたように、中国には経済のサービス化を通じた更なる成長の余地があることを示唆している。
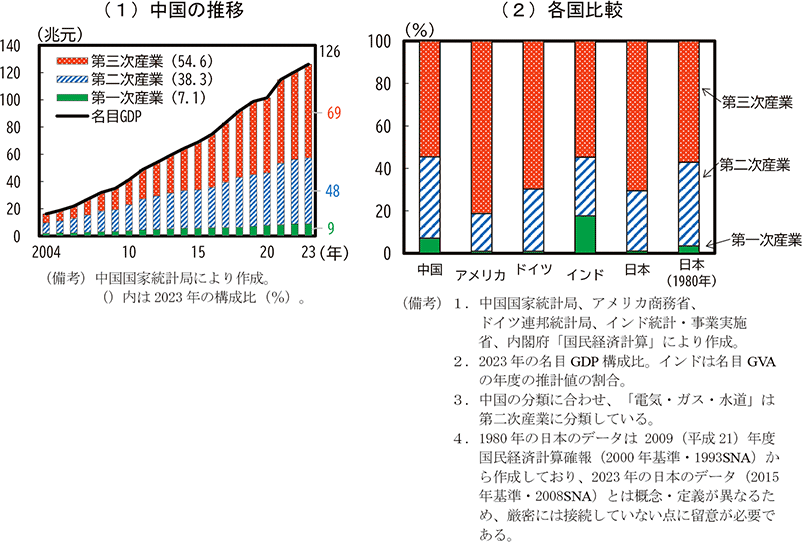
(中国経済のストック面)
次に、中国経済について、ストック面から概観する。政府系シンクタンクである中国国家金融発展実験室による2019年までのSNAベースのバランスシートをみると、一国全体では、急速な固定資本投資によって固定資産が2010年以降一貫して対GDP比で拡大を続けてきた一方、金融資産は2017年以降対GDP比で頭打ちとなっている(第1-1-5図)。2019年時点で他の主要国と比較してみると、中国では固定資産がGDPの4.5倍程度となっており、3倍程度となっている他の主要国よりも高い水準にある。これは、他の主要国に比べて資本効率が低いことを反映しているといえる。中国の金融資産のGDP比は10倍程度となっており、11倍程度となっているアメリカと同程度である。また、金融資産の構成については、持分・株式の割合が約3割となっており、これは我が国(14%)やドイツ(22%)の割合よりも高く、アメリカと同程度である。
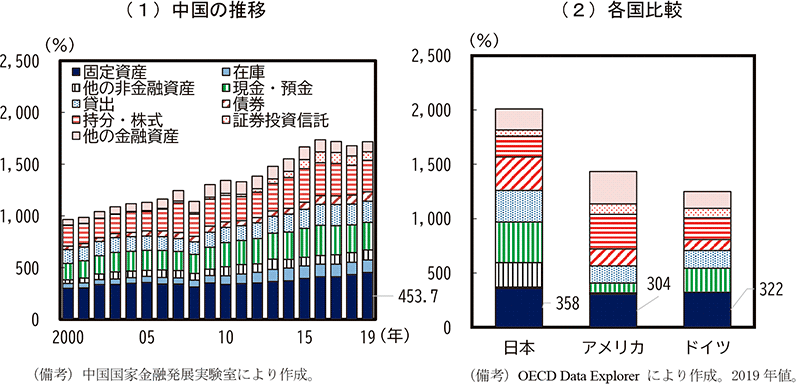
2.中国の人口動態
(人口減少が急速に進む中国)
次に、1950年以降の人口動態を俯瞰する。
1950年の中国の総人口は5.4億人、年少人口割合は34.8%、生産年齢人口割合は60.2%であった(第1-1-6図)。以降、1979年に一人っ子政策導入後(後述)も人口は増加傾向にあったが、年少人口割合は1966年(41.5%)、生産年齢人口割合は2010年(72.9%)、総人口は2021年(14.3億人)にそれぞれピーク2を迎えた。その後、総人口は減少傾向となり、2023年の総人口は14.2億人、年少人口割合は16.6%、生産年齢人口割合は69.1%となっている。国連の見通しでは2024年以降も人口減少傾向が継続し、2050年の総人口は12.6億人、年少人口割合は9.9%、生産年齢人口割合は59.1%まで低下する見込みである。
比較のため日本の数字を確認すると、1950年の日本の総人口は0.8億人、年少人口割合は35.4%、生産年齢人口は59.7%であった。以降、年少人口割合はほぼ一貫して低下してきたが、総人口は緩やかに増加を続け、生産年齢人口割合は1992年(69.8%)にピークを迎えた。総人口は、2008年(1.3億人)にピークを迎えた後、緩やかに低下し、2023年の総人口は1.2億人、年少人口割合は11.4%、生産年齢人口割合は59.4%となっている。国立社会保障・人口問題研究所の推計(中位推計)では、2050年の総人口は1.0億人、年少人口割合は9.9%、生産年齢人口割合は53.0%まで低下する見込みである。
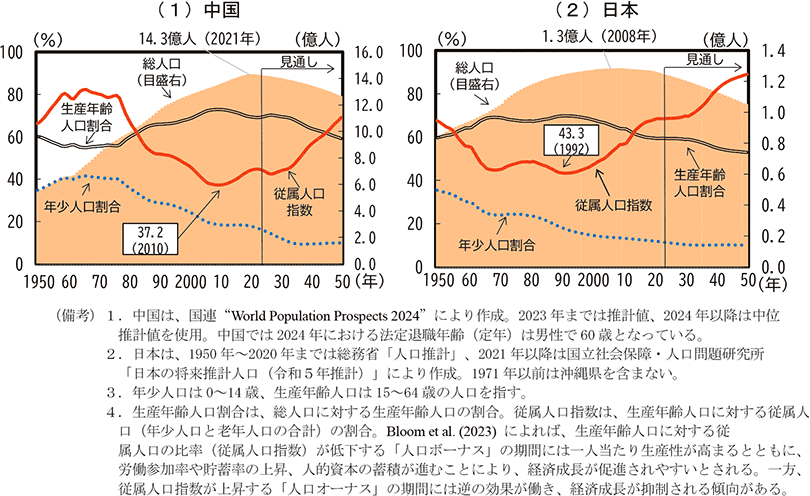
なお、国別の人口は長らく、中国、インド、アメリカの順に多かったが、中国の総人口は2022年にインドに抜かれ、第2位となった。国連によれば、インド、アメリカは、2024年以降も人口増加を続ける見込みである(第1-1-7図)。
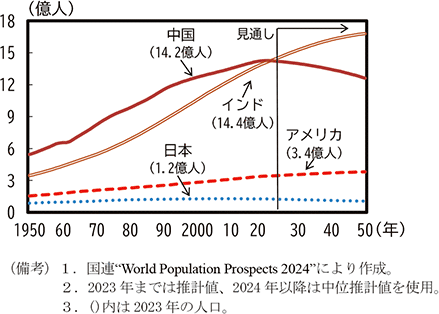
人口動態の詳細も確認しよう。出生数と死亡数から決定される人口の自然変化率3をみると、中国では2017年(5.8‰)以降急速に低下し、2021年(▲0.2‰)以降はマイナスに転じている(第1-1-8図)。日本は1950年(17.2‰)以降、出生率の低下とともに緩やかに低下し、2005年(▲0.2‰)以降はマイナスに転じている。
合計特殊出生率4をみると、中国では1970年代に6を超える水準から急速に低下5し、2000年から2017年にかけては1.6~1.8程度で推移していたものの、2023年における合計特殊出生率は1.0と1950年以降最低となり、日本の合計特殊出生率1.2を下回った(第1-1-9図)。日本では1973年(2.1)以降は低下傾向にあり、その後2005年(1.3)を底に幾分回復したものの、2015年(1.5)以降は再び低下する状況となっている。
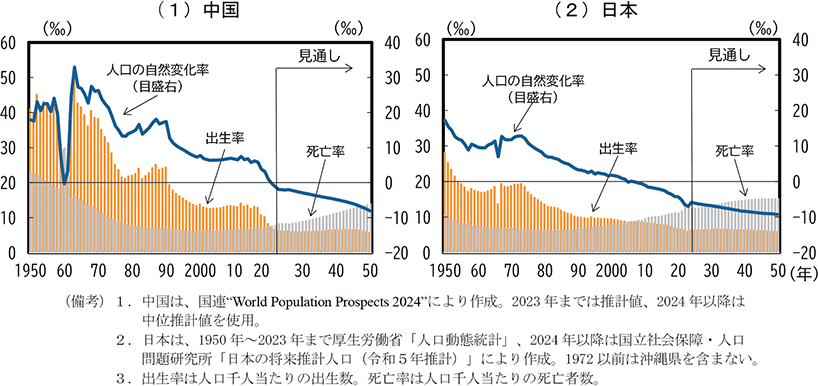
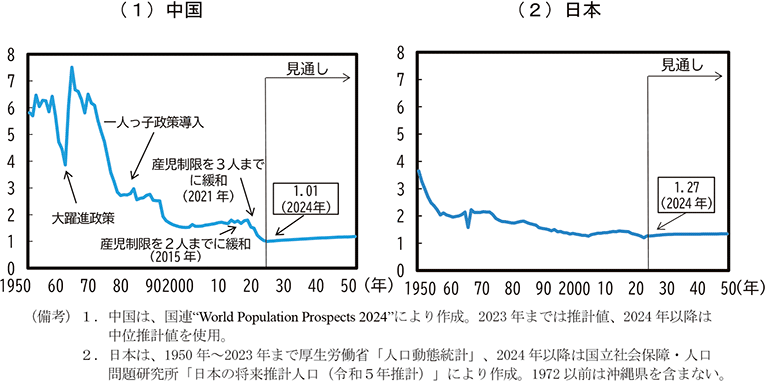
移民を考慮した人口変化率をみても、中国は2021年(▲0.0%)以降はマイナスに転じており、2024年以降もマイナスが継続する見込みである(第1-1-10図)。日本においても2011年(▲0.2%)以降マイナスとなり、今後もマイナスが継続する見通しとなっている。
こうした現状に対する中国政府の対応は後述するが、今後も中国の少子化及び人口減少の傾向は続くと見込まれる。
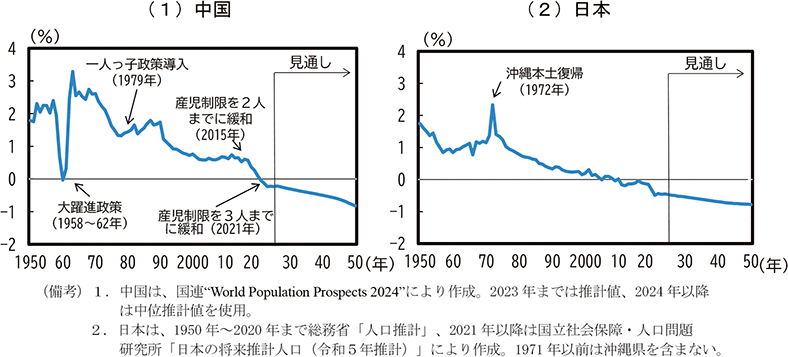
少子化及び人口減少の要因の一つとして挙げられる中国のこれまでの人口政策を振り返ると6、急激な人口増加と食糧不足への対応として1979年に一人っ子政策導入後、憲法でも計画出産の義務が規定された。その結果、人口抑制に成功したものの、労働供給の伸びの低下や高齢化の加速を背景に2002年に「人口及び計画出産法」が施行され、一定の条件下で二人目の子どもを産むことが許容された。2015年には夫婦一組につき二人の子どもを産むことが全面的に解禁され、2021年の法改正により、夫婦一組につき三人の子どもを産むことができることとなった。こうした取組により中国政府は出生率の上昇に努めたが、先にみたとおり、合計特殊出生率は2000年から2017年にかけては1.6~1.8程度で安定して推移していたものの、2018年から一段と低下している。また、長く採られた一人っ子政策の影響から、中国の若年層は男性が女性より1割程度多いという偏った人口構成となっている(第1-1-11図)。
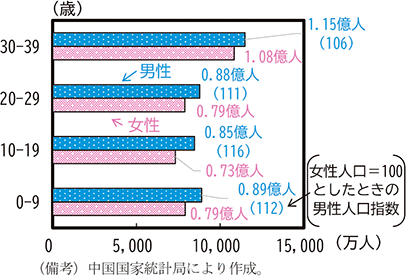
少子化に歯止めがかからない中、2024年10月に国務院は出産・育児支援に関する新たな施策を公表した(第1-1-12表)。出産・育児支援制度の改善により、出産、育児、教育にかかるコストの削減、適切な出生水準を実現し、「質の高い人口発展7」を促進するとしている。
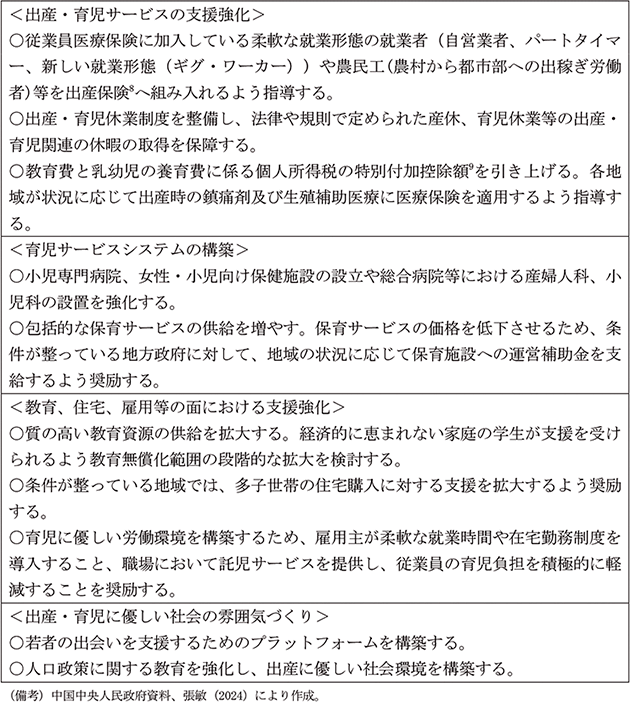
(直面する高齢化への対応)
人口減少と並行して進む高齢化を概観する。中国の高齢化の状況をみると、65歳以上の割合は2023年に14%となり10、2044年には28%と急激に上昇することが予想されている(第1-1-13図)。
また、平均寿命は1950年の43.8歳から2023年には78.0歳まで延びており、長寿命化が進んでいる(第1-1-14図)。年齢別死亡数の分布をみると、男性の約26%、女性の約46%が85歳以上まで生きる社会となっており、高齢社会への対応が課題となっている11(第1-1-15図)。
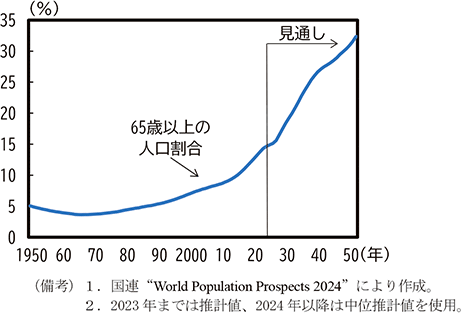
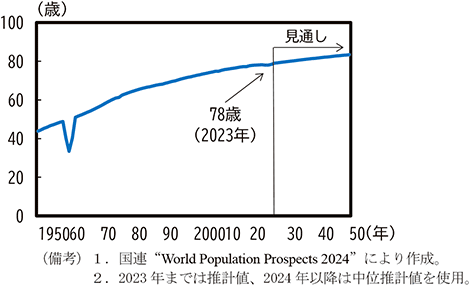
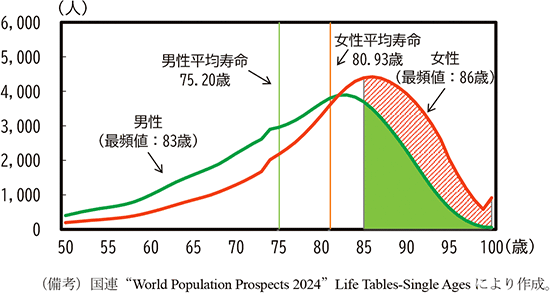
こうした人口構造の変化に伴う労働供給の減少等から、2024年9月の全国人民代表大会常務委員会において、法定退職年齢の段階的な延長が決定された12。法定退職年齢を2025年から2039年の15年間で、男性は60歳から63歳、女性の一般労働者(工人)は50歳から55歳、女性の管理職(幹部)は55歳から58歳に段階的に引き上げるとしている13。
(進行する人口動態の変動は中長期的な成長力の押下げ要因)
中国で進行する少子高齢化や総人口の減少傾向は、主に労働投入量の低下を通じて中長期的な潜在成長率を押し下げていくこととなる。Bloom et al. (2003)によれば、生産年齢人口に対する従属人口の比率(従属人口指数)が低下する「人口ボーナス」の期間には、一人当たり生産性が高まるとともに、労働参加率や貯蓄率の上昇、人的資本の蓄積が進むことにより、経済成長が促進されやすいとされる。一方、従属人口指数が上昇する「人口オーナス」の期間には逆の効果が働き、経済成長が抑制される傾向がある。中国では2010年を境に従属人口指数が上昇に転じており、中国は現在「人口オーナス」期にあるといえる(第1-1-16図)。世界銀行の推計14では、2000年代初頭には潜在成長率に対する労働投入の寄与が1%ポイント程度あったが、2010年代には0%ポイント程度まで低下し、2021年時点ではマイナスに転じている。OECDの推計でも、2010年代初頭には10%近くあった潜在成長率は低下を続け、2024年には4.5%程度となっている(第1-1-16図)。また、実際に過去の生産年齢人口変化率と実質GDP成長率の関係をみると、1980年代から2000年代にかけて生産年齢人口が増加する中で実質GDP成長率は平均10%程度で推移してきたが、2010年代以降生産年齢人口が減少に転じる中で実質GDP成長率も鈍化してきている(第1-1-17図)。なお、国連の推計を基にした2030年代の生産年齢人口増加率は平均▲0.8%となっており、これまでよりも生産年齢人口の減少ペースが加速する見通しである。
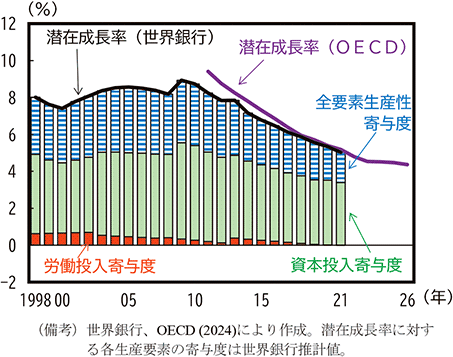
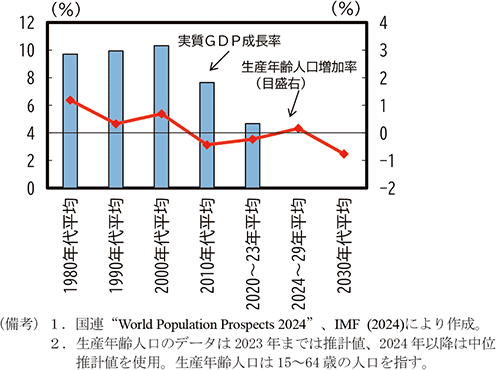
加えて、他に潜在成長率を規定する要素である資本投入や全要素生産性についても、成長期待の低下に伴う設備投資の鈍化や研究開発を担う若年人口比率の低下等を通じて下押しされる可能性がある。
こうした人口要因による下押し圧力は、段階的に実施されることとなった法定退職年齢の引上げや大学進学率の向上等を含めた人的資本投資の拡大によって一定程度軽減を図ることができると考えられるものの、中長期的に中国の経済成長を下押ししていく大きな要因となると考えられる15。
(中国の世帯数の動向)
中国においても我が国と同様に、人口が減少に転じる中でも世帯人数が減少することによって世帯数が増加してきており、2000年代には前年比1.6%~2.4%で増加を続けてきたが、2012年以降は増勢が鈍化している(第1-1-18図)。一世帯当たりの人数をみると、1996年には3.7人だったが、2022年には2.8人となっており、世帯人数の減少が進んでいることが分かる。なお、2020年の人口センサスによると、三世代以上(例:祖父母、親、子ども)の世帯は13.8%、二世代世帯(例:親と子ども)は36.7%、一世代世帯(例:単身世帯や夫婦のみの世帯)は49.5%であり、一世代世帯が半分近くの割合を占めている。
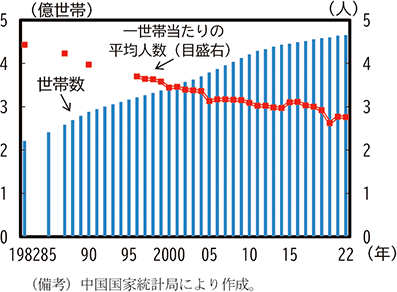
(住宅ストックの増勢は鈍化)
ここで人口動態の影響を受ける住宅ストックの状況もみてみよう。各年末(2024年については6月末)時点の住宅面積を確認すると、世帯数の増勢が鈍化していく中で、住宅ストックの増勢も2022年頃から鈍化してきていることが分かる(第1-1-19図)。
中国の不動産市場の動向については次節以降でより詳しく扱っていくが、こうした人口及び世帯数の動向が住宅需要の伸びを構造的に鈍化させていく要因となっていることを念頭に置いておくことが必要である。
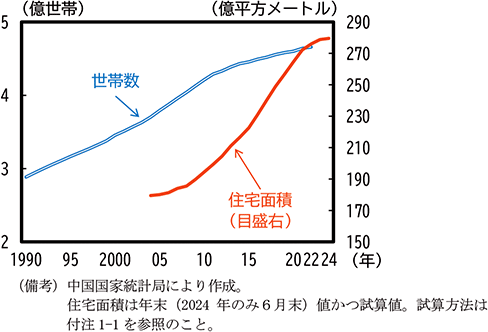
3.中国の貿易構造の特徴
これまで、経済構造や人口動態から中国経済の特徴を概観してきた。では、世界第2位の経済規模となっている中国経済の動向は、世界経済にどのような影響を及ぼすのだろうか。本項では、中国経済と世界経済との関係を捉えるべく、中国の貿易構造の特徴を確認していく。
(貿易黒字とサービス赤字)
中国経済が世界経済に与える影響を考えるに当たって、貿易・投資の動向を確認する。まず、中国の経常収支について2001年のWTO加盟後の動向をみると、貿易黒字がけん引する形で一貫して黒字となっているが、2010年代半ばから顕著となったサービス収支の赤字が経常収支の黒字幅の拡大を抑制している(第1-1-20図)。貿易収支については、2000年代半ば頃から2,000億ドルを上回る大幅な貿易黒字が継続しており、特に2020年以降は黒字幅が拡大し、2022年には過去最大の6,650億ドルの貿易黒字となった。こうした結果、中国は、2011年を除いて2006年以降毎年世界最大の貿易黒字国の地位を維持している。一方で、2010年代半ばから継続するサービス収支の赤字は主に旅行収支の赤字によるものである。2020年から2022年にかけては新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)拡大に伴う海外旅行の大幅な減少によりサービス収支の赤字幅はやや縮小したが、海外旅行の再開もあり2023年には再び赤字幅が拡大した。また、利子や配当を含む投資収益が赤字(支払超過)基調にあることから第一次所得収支16は赤字が継続している。
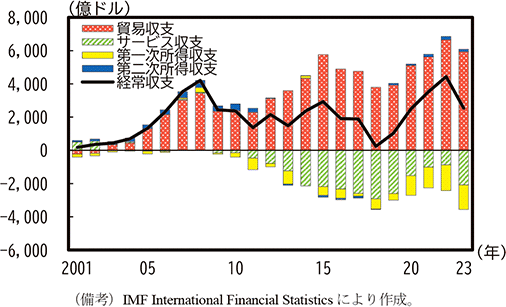
このように、中国の貿易収支は大幅な黒字を継続しており、財輸出を通じて世界経済に大きな影響を与える経済構造となっている。こうした貿易収支の動向を輸出と輸入に分けて確認してみよう。輸出金額、輸入金額いずれについても、世界金融危機後の2009年頃や内外の景気に減速感がみられた2015~2016年頃に一時的な減少があったものの、2000年から2018年にかけて年平均13%程度の増加基調で推移してきた(第1-1-21図)。その後、米中貿易摩擦や感染症拡大の影響もあり、2019年から2020年にかけて対前年で減少ないし伸びが鈍化したが、世界的な需要回復がみられた2021年には輸出金額、輸入金額とも前年比20%を上回って大きく増加した。輸入金額については内需の伸びが鈍化していく中で2022年をピークに頭打ちとなったが、輸出金額は対照的に2024年に過去最大の3.6兆ドルとなった。
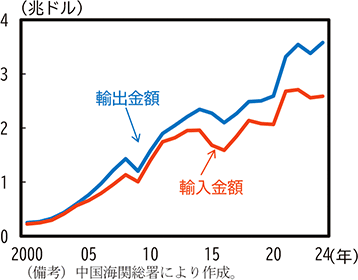
次に、中国の貿易構造を概観する。まず輸出面から品目構成をみると、2024年では、電気機械と一般機械のシェアが大きく、両者で約4割を占めている。これらはより細かい品目に分かれるが、主なものとしては、集積回路(4.5%)、リチウムイオン電池(1.7%)、携帯電話(1.5%)等が挙げられる(第1-1-22図)。この他、自動車の構成比は2019年には0.6%にとどまっていたが2024年には3.3%となり、近年急速に拡大している。
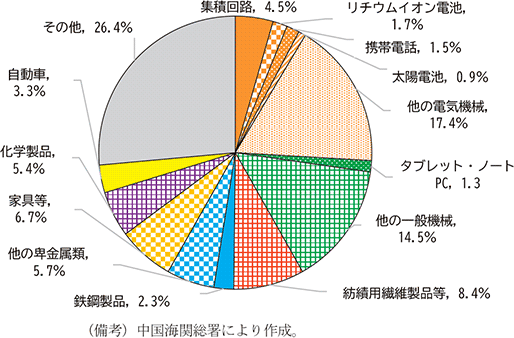
続いて、特に大きな増加がみられた2021年以降の輸出金額の動向について、財別の寄与度を確認する。輸出金額の前年同月比の変動にはやはりウェイトの大きい電気機械や一般機械が比較的大きな寄与を示しているが、輸出全体としては前年同月比でマイナスとなっている時期もほぼ一貫して自動車がプラスに寄与していることが2021年以降の動向の1つの特徴といえる。輸出全体に占める自動車の構成比はまだ必ずしも大きいものではないが、近年の中国の輸出拡大のけん引役の1つとなっている(第1-1-23図)。一方で、このところ欧米諸国から「過剰供給」が指摘されているリチウムイオン電池や太陽電池については、少なくとも中国のマクロ的な輸出金額の増加に対する顕著な寄与はみられない。
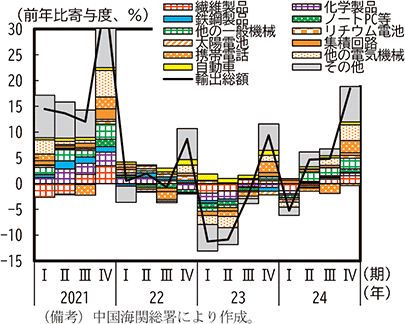
次に、輸入面を確認する。2024年上半期の輸入品目のシェアを確認すると、原油や鉄鉱石をはじめとする鉱物性資源、そして中間財である集積回路の割合が大きい(第1-1-24図)。国内の産業構成として製造業のシェアが大きいことが輸入面にも表れている。
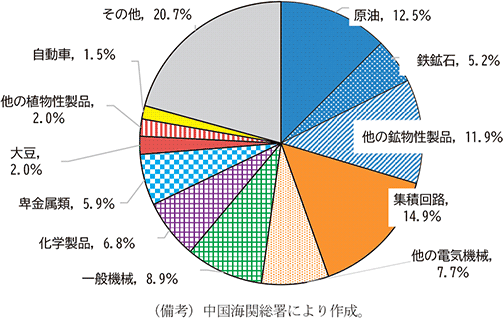
また、輸出と同様に2021年以降の輸入金額の動向について財別の寄与度をみてみる。やはり、ウェイトの大きい原油、鉄鉱石、集積回路といった原材料、中間財が輸入金額全体の動向に大きく影響している姿が読み取れる(第1-1-25図)。また、足下の動向をみると、中国の輸出は2024年4-6月期以降前年比プラス基調で推移しているのに対し、輸入については前年比でわずかな増加にとどまっている。
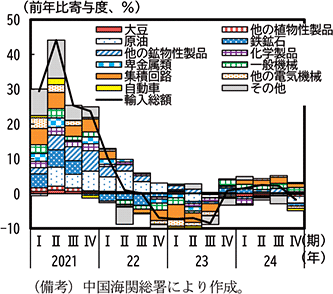
(貿易相手国・地域は欧米からASEAN、中東、中南米等にシフト)
中国の貿易構造の特徴を貿易相手国・地域の観点からも確認してみよう。まず、過去10年の輸出相手国・地域の推移をみてみると、2010年代後半の米中貿易摩擦や2020年代の欧米におけるデリスキングの進展の下、アメリカや日本、直近ではEU及び英国向けの輸出シェアが低下してきている(第1-1-26図)。一方で「一帯一路」沿線国17を含め、ASEAN諸国やロシア、中南米、中東、アフリカ向けの輸出シェアが拡大しつつある。また、香港については、2014年にはシェア15%程度とアメリカやEUと比肩する輸出先であったが、足下ではシェアが8%程度と半減している18。
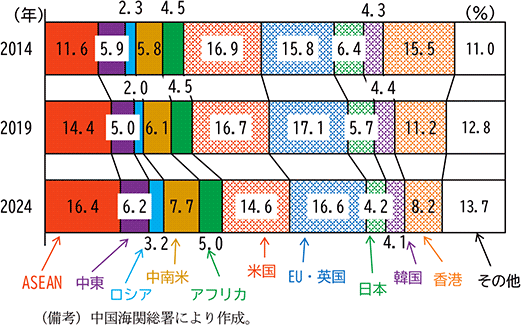
輸入相手国・地域についても、日本や韓国のシェアが低下してきた一方で、ASEAN諸国のシェアが拡大してきている(第1-1-27図)。輸出とは異なりアメリカのシェアは2019年から2024年でやや拡大しているが、ロシアや中南米のシェア拡大は輸出とも共通する傾向である。特にロシアからの輸入は2022年のロシアによるウクライナ侵略(以下「ウクライナ侵略」という。)以降、顕著に拡大している。
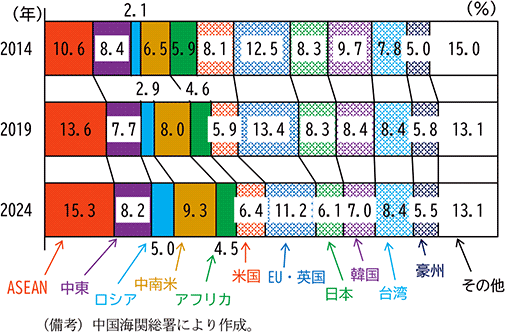
このように、特に2020年代以降、中国の貿易相手国・地域は、アメリカや日本、EU等の先進国から新興国、途上国への多角化が進んできている。これは、特定の貿易相手国・地域への依存度を低下させ、貿易相手国の経済動向や通商関係の変化に対する脆弱性を低下させていると捉えることもできる。こうした中国の貿易構造の変化を把握しておくことが、中国経済の世界経済との関係を考える上でも重要であろう。

