第1章 2023年後半の世界経済の動向(第1節)
第1節 欧米の景気
本節では、欧米の景気動向について分析する。第1項では、回復が続いているアメリカ経済を概観するとともに、個人消費等の強さがみられる分野の背景を中心に分析を行う。第2項では、景気が弱含んでいる欧州経済を概観するとともに、個人消費等の弱さがみられる分野の背景を中心に分析を行う。第3項では、低下傾向にある物価上昇率について分析を行い、欧米の金融政策の内容を確認するとともに、金融資本市場の動向について確認する。
1.アメリカの景気動向
本項では、主に2023年後半のアメリカ経済を概観するとともに、個人消費等の強さがみられる分野を中心に、その背景や構造要因を分析していく。
(景気は回復が続いている)
まず、実質GDPの推移を確認すると、2023年7-9月期は前期比年率4.9%増と大幅に増加した(第1-1-1図)。その後、10-12月期も3.3%増と増加傾向が継続し、2023年は通年で2.5%のプラス成長となった。実質GDPは2022年7-9月期以来、6四半期連続で2%1を上回るプラス成長が続いているが、内訳をみると、実質GDPの約70%を占める個人消費が2023年10-12月期は前期比年率で2.8%増加しており、同期の成長率への寄与度は1.9%ポイントとなっている。また、実質GDPの約15%を占める設備投資は、知的財産投資を中心に9四半期連続で増加している。このように、実質GDP全体の85%を占める個人消費と設備投資の安定的な増加が、アメリカ経済の回復に大きく寄与している。
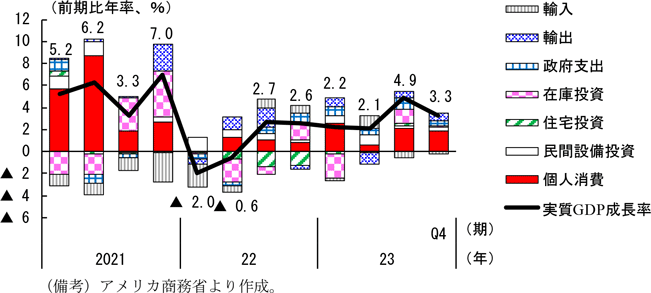
住宅投資についても、2023年7-9月期に2年半ぶりに増加に転じ、10-12月期も増加が継続するなど、住宅市場においても変化がみられている。このように、2023年のアメリカ経済は、金融引締めの進展の下でも、予想されていた個人消費や雇用の大幅な減速はみられず、国際機関等の見通し以上の強さをみせている2。
(個人消費は財・サービスともに増加基調)
次に、個人消費について分析していく。実質個人消費支出はサービス消費に加えて財消費も増加傾向が続いている(第1-1-2図)。2022年は財からサービスへの需要のシフトに伴い、耐久財消費は横ばい傾向で推移していたが、2023年は耐久財消費が再び増加傾向に転じており、前年比で4.3%増加している。
サービス消費の内訳をみると、介護サービス等が含まれるヘルスケアが安定的に増加する中で、飲食・宿泊サービスも、感染症収束に伴う経済活動再開の本格化により、2023年後半は増加傾向が顕著になっている。その他、映画館等の娯楽サービスや、海外旅行を含むその他サービスも増加しており、外出を伴うサービスの回復が、2023年後半のサービス消費の特徴と言える。
財消費の中でも高い伸びがみられる耐久財の内訳をみると、PC・AV機器等の娯楽用品の増加基調が顕著であり、2023年は前年比で7.6%の増加となっている。内訳をみると、特にテレビやPC・タブレットが前年比10%以上の高い伸びをみせている。
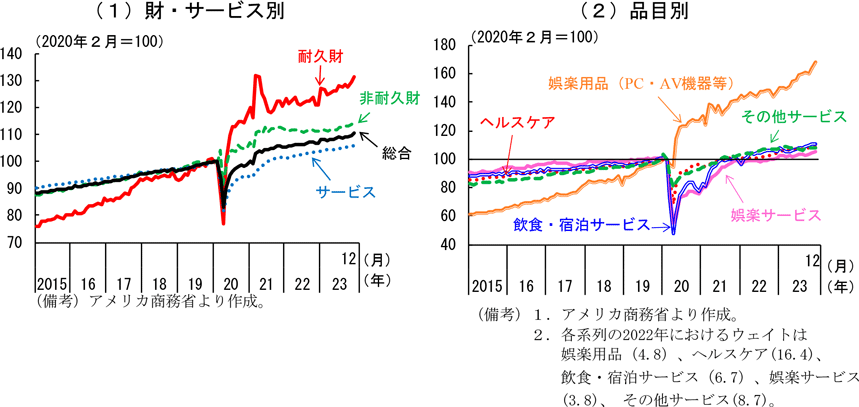
さらに、耐久財消費の約4分の1を占める自動車について確認する。2022年10月以降は供給制約の緩和に伴って自動車販売台数は持ち直し傾向に転じ、2023年4月に1,500万台(年率)を超えるまでに回復した。その後も供給側の問題3が生じたことで、自動車販売台数は感染症拡大前の平均的なトレンドである1,700万台まで戻ることなく1,500万台程度で推移しているが、2023年以降は在庫の改善が続いていることや、その他の下振れリスクが少ないとみられることから、今後も堅調に推移すると考えられる4(第1-1-3図、第1-1-4図)。
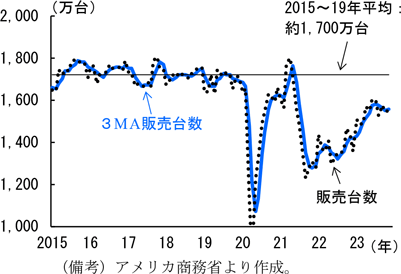
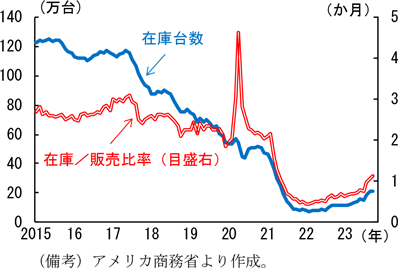
(消費増加の背景には、家計のバランスシートの改善)
このような個人消費の増加基調は、過去20年にわたり改善が続いてきた家計の良好なバランスシートに支えられていると考えられる。こうした改善傾向は感染症拡大を契機に加速し、家計の総資産は可処分所得比では2019年10-12月期は8倍程度(798%)であったが、2023年7-9月期には10倍程度(963%)と急増した(第1-1-5図)。資産構成比をみると、流動性の高い金融資産の割合が約67%(2022年)と高く、そのうち特に株式等(全体の約23%)の比率が高い(第1-1-6図)。また、住宅ローン等も含めた負債総額をみると、2000年は負債の可処分所得比が68%、総資産比が14%であったが、2022年5はそれぞれ113%、12%となっている(第1-1-7図)。負債の可処分所得比自体は増加しているものの、負債の総資産比は過去20年間で最低水準となっている。
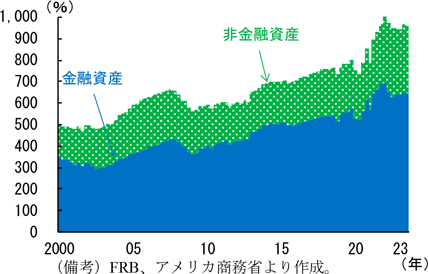
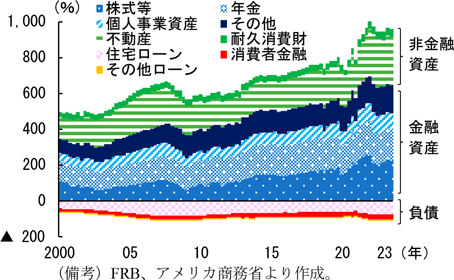
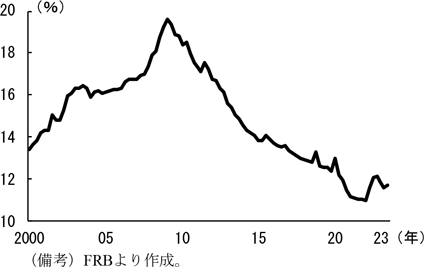
(低所得者層は資産の取崩しの余地が少なく、預金水準はコロナ禍前を下回る)
ここで、総資産額を所得階層別に確認すると、2022年においては、所得階層上位20%にあたる高所得者層が家計総資産の約68%を保有しており、上位61~100%(下位40%)の低所得者層の保有割合はわずか8%となっている(第1-1-8図)。なお、2000年の高所得者層の割合は62%、低所得者層が10%であることから、保有資産における格差が広がっていることが分かる。
さらに、保有資産の内訳をみてみると、高所得者層では流動性の高い金融資産の比率が2022年は74%と高い一方で、低所得者層は47%であり、流動性の低い非金融資産の比率の方が高い(第1-1-9図)。加えて、非金融資産のうち81%が不動産であり、その大半が居住している住居であると考えられ、消費のために取り崩すことが難しい非流動的な資産であると考えられる。
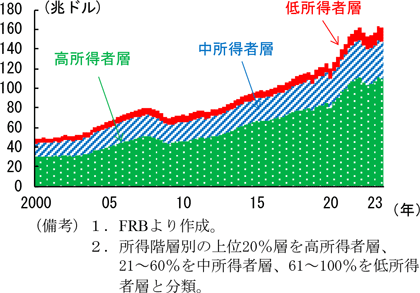
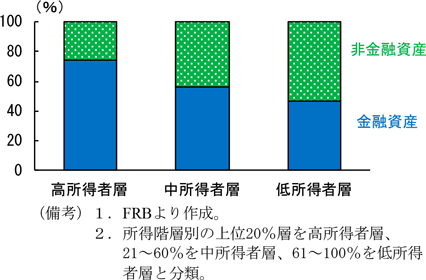
金融資産についても、可処分所得比を所得階層別に推移をみると、中・低所得者層に比べて高所得者層は上昇傾向で推移しており、2000年には228%であった可処分所得比が2019年には408%、2022年には486%まで上昇している(第1-1-10図)。高所得者層の金融資産対可処分所得比は、特に感染症拡大後に急増しており、その内訳である株式等の可処分所得比率の上昇が顕著であることから、同期間の株価上昇が寄与していると考えられる。これに対して、中・低所得者層の金融資産対可処分所得比はおおむね横ばいで推移しており、特に低所得者層は2022年で37%程度(株式等の可処分所得比は7%程度)と限られていることから、株価上昇の寄与は小さいものと考えられる。
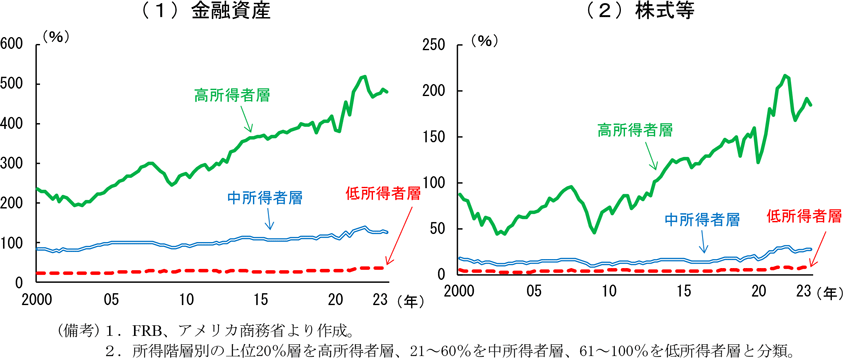
こうしたことから、低所得者層では、感染症拡大に伴う大規模な財政支出等によって形成された超過貯蓄を取り崩すことで消費を下支えしているものと考えられる。超過貯蓄については、全所得階層合計では2023年10-12月期時点で1.4兆ドルの超過貯蓄が残っているが、所得階層別の実質預金水準をみると、低所得者層では2023年4-6月期に2019年10-12月期の水準を下回っていることから、低所得者層は超過貯蓄を使い尽くしている可能性が考えられる6(第1-1-11図)。
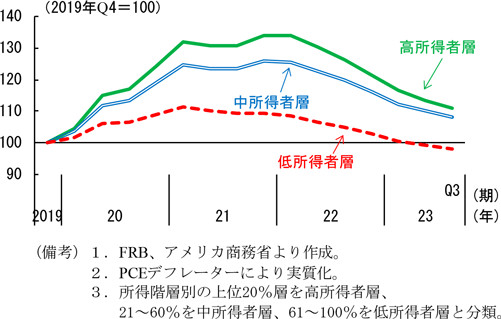
2023年後半は賃金上昇率が物価上昇率を上回り、実質所得が増加基調であることから(第1-1-12図)、低所得者層の消費が下振れするリスクがすぐに顕在化する可能性は小さいと考えらえる。しかしながら、今後、超過貯蓄を使い果たした低所得者層の消費支出の勢いが鈍化する可能性があることには留意が必要である。
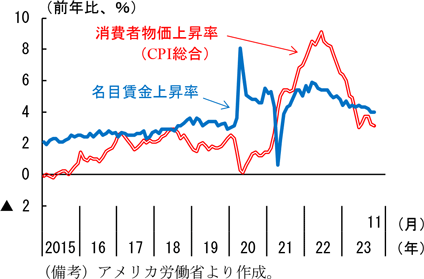
Box.所得階層別の総資産に対する負債比率の動向
前述のとおり、総資産に対する負債の比率は全体としては過去20年間で最低水準であるが、これは高所得者層に限らず全所得階層において同じ状況である(図1)。また、低所得者層と中所得者層の間には大きな差がなく、おおむね同程度で推移している。
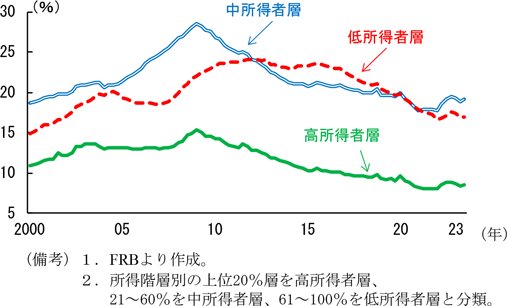
(設備投資は、金利上昇にもかかわらず、緩やかな増加傾向)
設備投資は金利上昇にもかかわらず、感染症拡大前の水準を上回り、総じてみれば緩やかな増加傾向が続いている。感染症拡大後から2022年にかけては、設備投資全体の約4割を占める知的財産投資が堅調に推移する中で、同じく約4割を占める機械・機器投資は増減を繰り返しながらも総じてみれば増勢を維持していたが、約2割を占める構築物投資は低迷していた(第1-1-13図、第1-1-14図)。
2023年に入ると、インフレ抑制法やCHIPS及び科学法(半導体法)等の政策により、製造業向けの投資が大幅に増加したことで、構築物投資(工場建設等)がプラス寄与に転じた(第1-1-15図)。
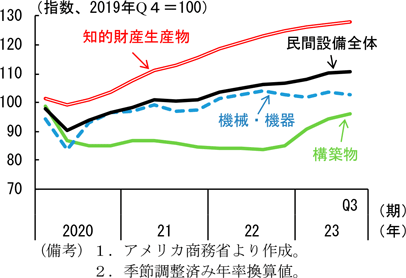
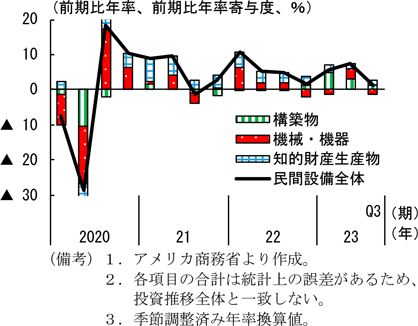
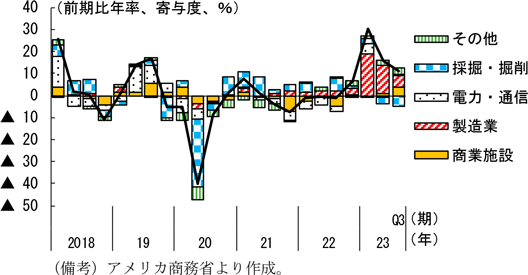
ここで、インフレ抑制法及び半導体法の概要について確認しておく。2022年8月にアメリカで成立したインフレ抑制法は、基本的には脱炭素に向けた取組が主眼の財政政策パッケージであるが、経済安全保障を意識した製造業の国内回帰につながる政策が含まれている。例えば、電気自動車の購入者に対する最大7,500ドルの税額控除が盛り込まれているが、こうした税額控除が適用されるために必要な条件は主に2つあり、いずれも電気自動車に搭載されるバッテリーに関するものである。具体的には、(i)バッテリーに含まれる重要鉱物に係る要件(アメリカまたはアメリカと自由貿易協定を結んでいる国で抽出または加工された重要鉱物が、バッテリーに含まれる重要鉱物のうち一定割合以上)、(ii)バッテリー部品に係る要件(北米で製造または組み立てられた部品が、バッテリー部品のうち一定割合以上)、の両方を満たすことが必要とされている。
このようにインフレ抑制法では、電気自動車について、アメリカの同盟国や北米を優遇する政策を採っている。上記要件で指定されている割合は年々引き上げられていく予定であることから、北米地域内への生産回帰の動きが今後更に進む可能性がある。
さらに同月には、経済安全保障の観点から、半導体サプライチェーンの強化を目的とした政策パッケージであるCHIPS及び科学法(半導体法)が成立している(第1-1-16表)。
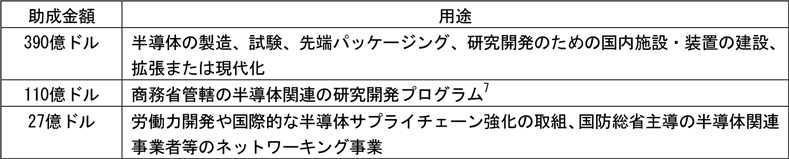
同法が成立した背景には、アメリカは世界の半導体供給量の約10%、先端半導体については皆無に等しい量しか生産しておらず、世界の半導体供給量の75%は東アジア地域が占めているため8、こうした特定の地域にサプライチェーンが集中すること自体がリスクであるという問題意識がある。同法では、半導体の製造や研究開発のための国内施設・装置の建設等に対する補助金といった支援策が盛り込まれており、生産コストの低下や雇用創出、サプライチェーンの強化及び中国への対抗のために、アメリカの半導体分野の研究開発、製造、人材育成に527億ドルを支出するほか、半導体及び関連機器の製造に必要な資本費用に対して25%の投資税額控除を行うとしている。これらの支援策が製造業における設備投資を促進していると考えられる9。
同法で定められた半導体製造支援関連の予算措置の規模は2022予算年度から2027予算年度の5年間で7.6兆円(527億ドル)となり、議会予算局(CBO)によると2023予算年度から2031予算年度にかけて毎年約0.3兆円(20億ドル)から1.3兆円(90億ドル)程度の規模で支出されることが見込まれている10。
また、同法の成立を受けて、1件当たり数百億ドル規模の投資事業として、半導体工場のアメリカ国内全域への新設の動きが活発になっており、これらが2023年の設備投資にプラス寄与しているものと考えられる。今後も、一部の事業で投資規模を更に拡大する方針や、地域内における工場新設を更に増やす計画が示されており、旺盛な投資需要がうかがえる(第1-1-17表)。
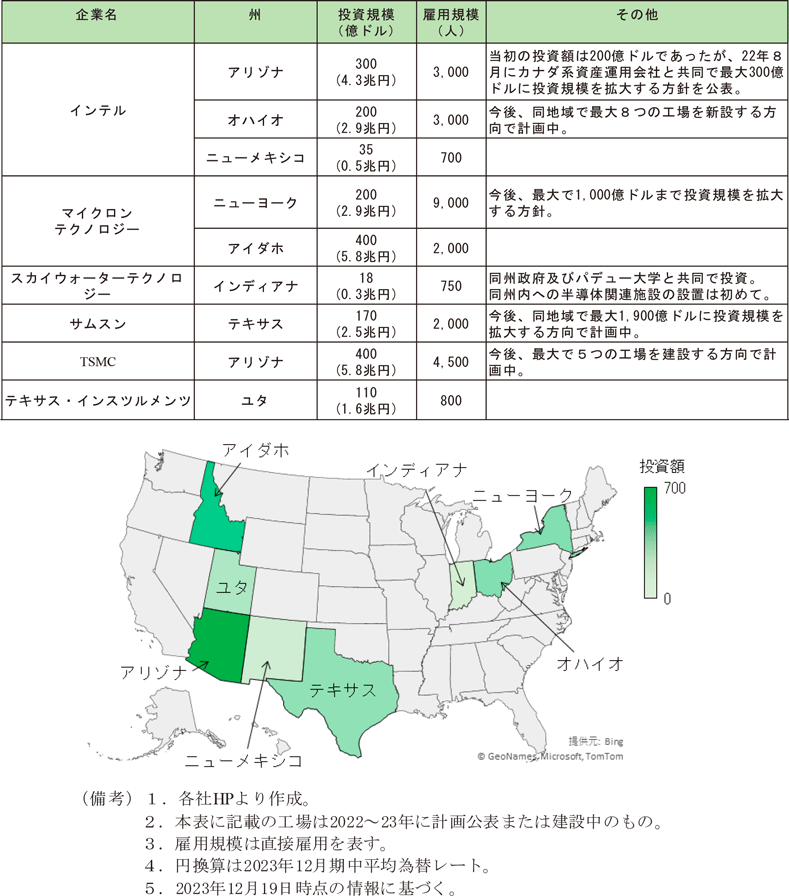
ここで、設備投資をめぐる金融環境を確認する。2022年以降、金融引締めの進展に伴って、金融機関の商工業向けローンの貸出態度は厳格化し、企業側の資金需要は軟調になってきていた(第1-1-18図、第1-1-19図)。しかしながら、2023年7-9月期には、貸出態度について「厳格化-緩和」が低下に転じ11、資金需要の「堅調-軟調」についても大・中堅企業向けでは上昇しており12、10-12月期においても、その傾向が継続している。2022年以降の金融引締めは資金調達コストの上昇を通じて企業の設備投資を抑制していたと考えられるが、今後も貸出態度の緩和に向けた動きが続き、資金需要の回復傾向が続けば、半導体法等の政策効果がはく落した後も設備投資の増勢が継続する可能性がある。また、金融引締めについても2023年7月のFOMC会合において利上げを行った後、9月以降4回連続で据置きとなっており、長期金利の上昇傾向も頭打ちになっていることから、今後、投資環境の改善が更に進む可能性がある(第1-1-20図)。
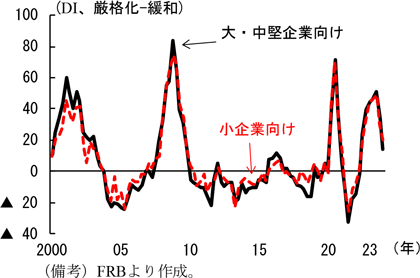
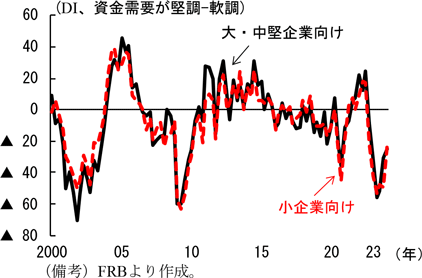
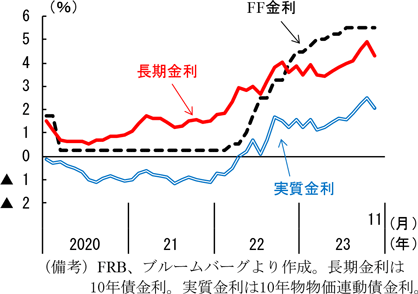
(住宅着工は回復傾向に転じる)
住宅着工は金融引締めの影響を受けやすいにもかかわらず、2023年以降は回復傾向が続いている。2022年以降は政策金利の引上げに伴う住宅ローン金利の上昇により、住宅着工は減少傾向にあったものの、2023年に入ってからはおおむね横ばいで推移していた(第1-1-21図)。その後、2023年5~7月頃にかけて持ち直した後、8月にハリケーンの影響により大きく減少し、9月以降は低水準ではあるものの緩やかな増加が続いていたが、11月に前月比14.8%と急速に増加し、ハリケーン前の水準を超えて回復している。住宅価格も再び上昇傾向に転じている(第1-1-22図)。さらに、住宅着工の基調を示す一戸建て住宅の着工件数は年初来の増加傾向を維持しており、先行指標となる住宅許可件数も増加傾向が続いていることから、住宅着工は回復傾向に転じていると考えられる(第1-1-23図、第1-1-24図)。
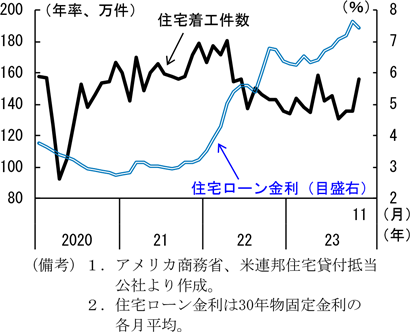
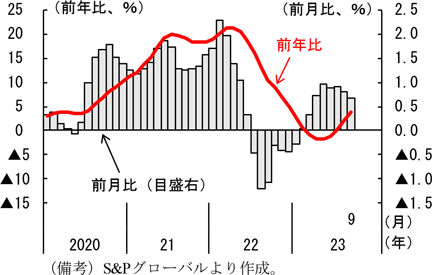
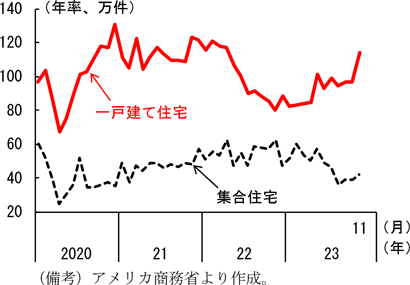
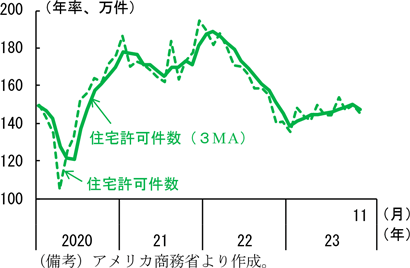
この背景には、需要側の要因として、人口動態があると考えられる。アメリカでは世帯数の増加に伴って住宅ストック数も増加する傾向があり、人口増加に伴う世帯数の増加が継続する中で、新たな住宅需要が生じるという構造的な要因があると考えられる(第1-1-25図、第1-1-26図)。議会予算局(CBO)の見通しによれば、今後もアメリカの人口は年率0.5%程度で増加が続く見通しになっていることから、新たな住宅需要が恒常的に生まれる構造は今後も続くと考えられる(第1-1-27図)。
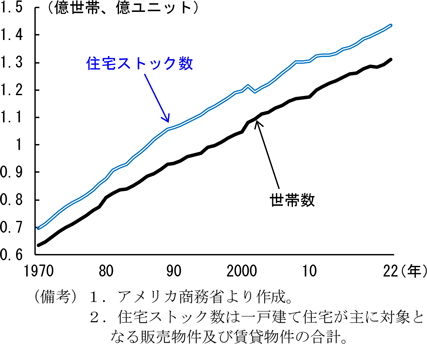
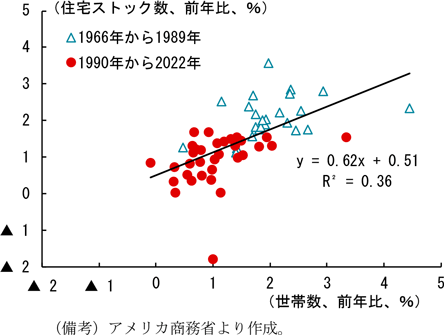
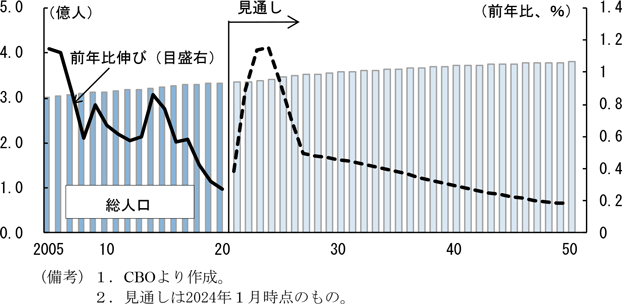
供給側の要因としては、中古住宅の在庫不足が考えられる。足下の中古住宅の在庫水準を確認すると、2020年と比べて約30%低下していることが分かる(第1-1-28図)。中古住宅の在庫減少の背景には、売り手にとって現在の住宅を手放すことのメリットが小さいことがあると推測される。アメリカでは、住宅ローンをできるだけ長期で元利金償還を一定額に固定し、長期金利が低下した際には借換えを行う傾向が強く、2020~22年初の低金利下では実際に、住宅ローンの借換えが増えている13。このことは、逆に2022年以降の金利上昇局面には借換え需要が弱まることを意味しており、低金利の住宅ローンを手放して住宅を売却するメリットが小さくなっていると考えられる。
また、このような中古住宅の在庫、すなわち供給不足を受けて、2023年に入っても中古住宅販売件数は減少傾向が続いており、その代わりに新築住宅販売件数は増加傾向に転じている(第1-1-29図)。このように中古住宅の供給不足が、新築住宅の供給を喚起しているものと考えられる。
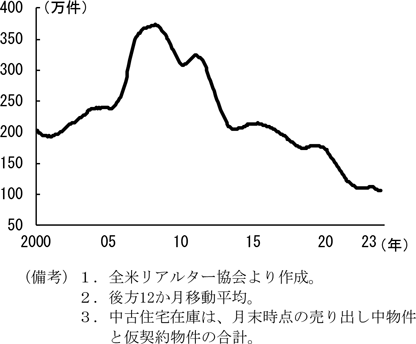
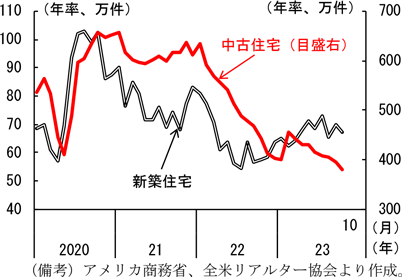
このような住宅着工の回復傾向は今後も続くことが期待される。住宅市場をめぐる金利環境をみてみると、11月に10年債利回りが低下したことを受けて、住宅ローン金利も低下しており、上昇傾向に一服感がみられる。このような金利環境の変化を受けて、住宅市場の景況感である住宅市場指数は12月に低下傾向が一旦止まっており、改善に向けて反転している14。一方で、住宅取得能力指数15は高い住宅ローン金利を背景に低下傾向が続いており、高金利下において住宅購入のハードルが高い状況が継続していることには、先行きを判断する上で留意が必要である(第1-1-30図)。
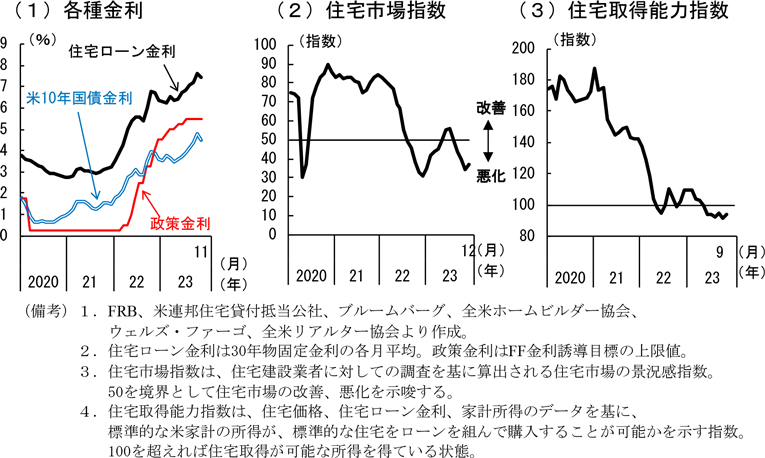
(雇用者数は安定的な増加傾向にあり、労働需給のひっ迫は依然続く)
アメリカの雇用者数は2022年6月に感染症拡大前の水準を回復した後、急速な金融引締めが進展する中においても増加を続けていたが、2022年秋以降は増勢が頭打ちになる業種もみられるなど、強さの中にも変化が生じている。2022年9月時点では3か月移動平均で40万人を超えていた雇用者数の前月差は、2023年4月以降は感染症拡大前の景気拡大局面16における平均的な前月差である20万人程度17で推移しており、安定的な増加傾向にある(第1-1-31図)。
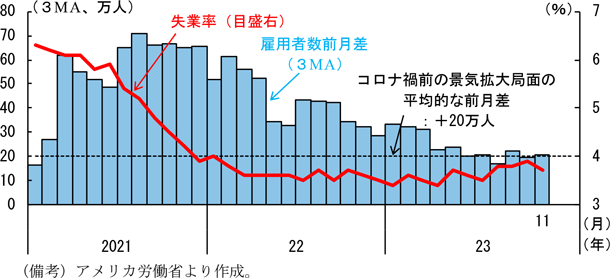
次に失業率の動向を確認する。失業率は2022年2月以降3%台で推移しており、1970年代のオイルショック以降の最低水準にある。足下の動向をみてみると、2023年4月に3.4%で底を打った後は緩やかに上昇し、同年10月には3.9%と最低値から0.5%ポイント上昇した。ただし、この失業率の上昇は必ずしも景気後退を意味するのではなく18、雇用のミスマッチの増加が背景にあると考えられる。
こうしたミスマッチの動向を確認するため、労働力のフローチャートをみると、失業率が上昇していた2023年7~10月は、非労働力人口から労働力人口に移った労働力の多くが、労働市場への参入後すぐには就業できずに失業者として滞留していたことが分かる19(第1-1-32図)。失業率の上昇の要因には、現在働いている人が職を失うこと(フローチャートでは就業者から失業者に移動すること)と、非労働力人口から求職者が流入することの両方があるが、同年7~10月の上昇局面においては、就業者と失業者の間の移動は、失業者から就業者への移動の方が多くなっており、前者の要因は限られる一方、非労働力人口から失業者への流入が大きいことがうかがえる。その後、11月には前月と比べ失業者から就業者へ多くの労働力が移動しており、失業率は3.7%まで低下している。
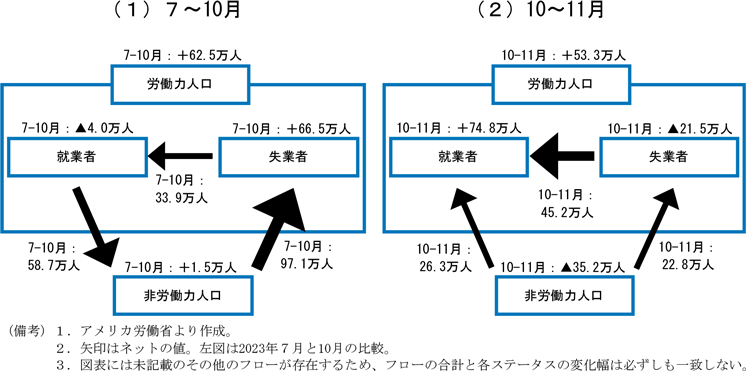
2023年7~10月に失業率が上昇した背景には、雇用のミスマッチに起因する失業の増加があると考えられる。例えば、失業者の持つ技能と求人要件が合致しない場合(構造的失業)や、職探しに時間がかかることによって発生する場合(摩擦的失業)が考えられる。このような雇用のミスマッチを分析する手法としてはUV曲線分析がある。UV曲線は右上にシフトするとマッチング効率が悪化したことを表す一方、左下にシフトするとマッチング効率が改善したことを表す。また、45度線を基準に右下に動くと需給改善(景気拡大)を表す一方、左上に動くと需給悪化(景気後退)を表す20。
これによると、失業率が特に上昇していた2023年7月以降は欠員率も上昇したことでUV曲線が月次の動きとしては右上に移動し、ミスマッチ拡大が示唆された(第1-1-33図)。その後、再び欠員率は低下しており、左方向に移動している。このことから、同期間の失業率の上昇は一時的な雇用のミスマッチ拡大によるものであると考えることができる。
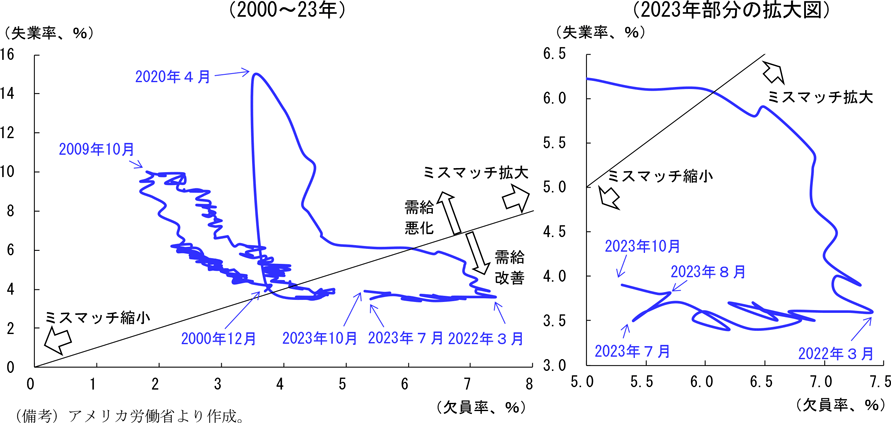
また、UV曲線から労働市場のひっ迫状況をみることができるが、Figura and Waller (2022)で示されているように、失業率の上昇を伴わずに欠員率を低下させることでソフトランディングを実現することができるとの想定が、現在の金融引締め局面におけるFRBの基本的な想定である。これまでのUV曲線の動きをみると、欠員率は2022年3月に7.4%でピークを迎えた後、一進一退を伴いながらもおおむね低下傾向で推移する一方、失業率の上昇はみられておらず、ソフトランディングに向けた動きが示唆されている。ただし、直接的に労働市場のひっ迫状況を表す指標である求人倍率も低下傾向にはあるものの、2023年10月時点では1.34倍と2015~19年の平均である0.93倍と比べれば依然として高水準であり、労働需給のひっ迫は依然続いているものと考えられる(第1-1-34図)。
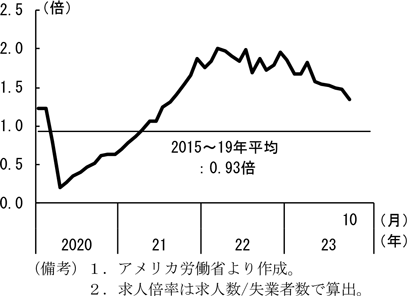
労働市場のひっ迫状況を更に分析するために、労働需要と労働供給の推移をみると、労働需給ギャップ(労働需要と労働供給の差)は縮小傾向にあるものの、依然として労働需要が労働供給を上回っている(第1-1-35図)。
人口で基準化した労働需要は、2022年3月の63.7%をピークに、2023年10月には62.8%まで低下し、感染症拡大前と同程度となっている。これに対し労働供給は増加傾向が続いているものの、2022年3月の62.0%から2023年10月の62.4%と需要と比べて変化幅は小さく、感染症拡大前の平均水準である63%を下回っている。
こうした動きを受け、労働需給ギャップは、2022年3月の2.2%ポイントから2023年10月には0.9%ポイントまで縮小し、労働需給の緩和が進んでいることが分かる。縮小分の1.3%ポイントのうち、0.9%ポイントは労働需要の減少によるものであり、現在の労働需給の緩和は需要側の要因の方がより大きく寄与している。
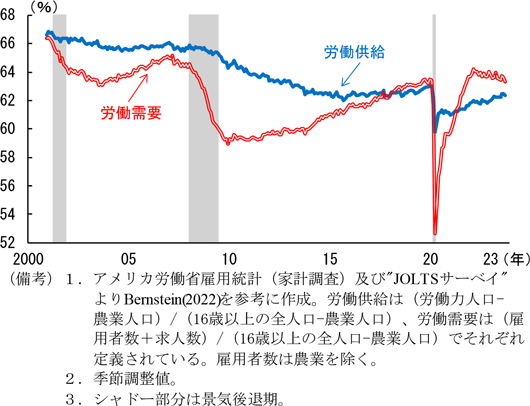
続いて労働市場の動向を業種別に分析していく。前述のとおり、雇用者数の増勢は全体としては続いているものの、2022年秋頃からは頭打ちになる業種も出てくるなど、強さの中にも変化が生じてきている。特に2023年に入ってからはヘルスケアとレジャー・接客業が雇用者数の増加の大半を占めている(第1-1-36図)。なお、レジャー・接客業では雇用者数がいまだに感染症拡大前の水準を超えておらず、需要の回復を踏まえると更なる増加の余地があると考えられる(第1-1-37図)。
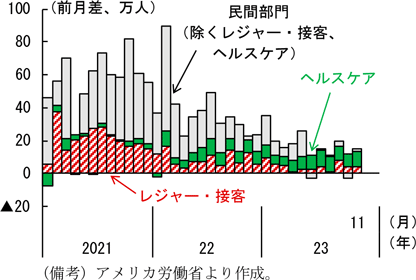
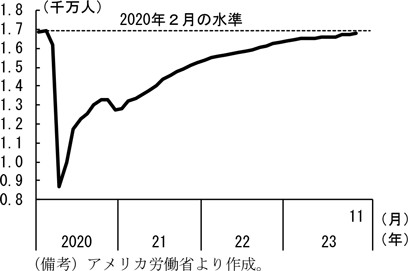
欠員率をみると、レジャー・接客業においても総じてみれば低下傾向にあるものの、全体と比べれば1~2%ポイント高い水準で推移しており、人手不足が続いていることが分かる(第1-1-38図)。名目賃金上昇率は全体としては緩やかに鈍化しているが、レジャー・接客業の賃金上昇率をみると、全体との差は徐々に縮まっているものの依然として高く、人手不足により賃金上昇率の鈍化が全体と比べて遅れていることが分かる(第1-1-39図)。
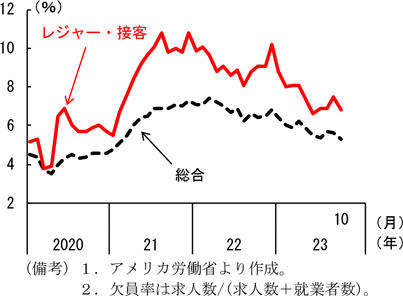
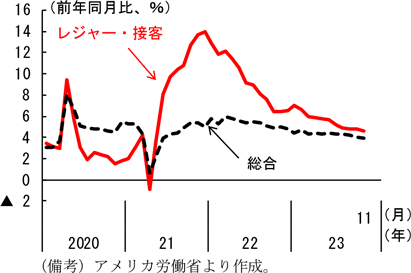
さらに、レジャー・接客業の人手不足の状況をみるために、同業種の大部分を占める飲食・宿泊サービスに従事する労働者の労働投入量の推移を、それに対応する同分野の実質個人消費支出の推移と比較してみる。ここでの労働投入量とは、雇用者数と週当たり平均労働時間の積(マン・アワー・ベース)である。それらの指数の推移をみると、2010年代はおおむね一致しており、消費と労働投入量の間には比例関係が確認できる(第1-1-40図)。しかしながら、2020年以降は消費支出の増加に労働投入量の増加が追いついておらず、その差は拡大傾向となっていることが確認できる。
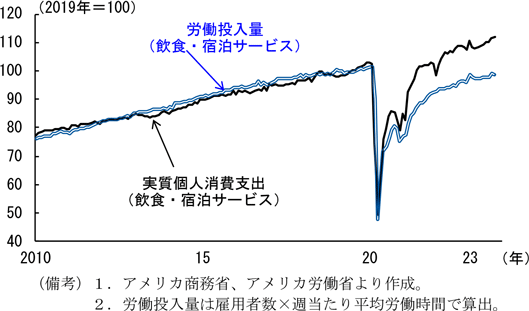
(まとめ:アメリカの景気は個人消費を中心に回復が継続)
アメリカ経済においては、個人消費は家計の良好なバランスシートに支えられて増加し、設備投資も政策効果等により緩やかな増加傾向にある。また、金融引締めが進展する中でも、住宅着工は回復傾向に転じており、雇用者数は安定的な増加傾向にあり、労働需給のひっ迫は依然続くなど、アメリカ経済は回復が続いている。
一方で、耐久消費財、設備投資や住宅投資等の需要へは金融引締めの影響が遅れて生じる可能性もある。2024年のアメリカ経済は各種経済予測においても堅調に推移することが見込まれているが21、このような下振れリスクには留意する必要がある。
コラム1:アメリカ自動車業界におけるストライキの影響について
2023年9月15日、全米自動車労組(UAW)が大手自動車メーカー3社(GM、Ford、Stellantis:ビッグ3)に対しストライキに突入した。争点は、物価上昇を背景とした急激な生計費の上昇に応じた賃上げ等の待遇改善であった22。現地時間9月14日23時59分を期限として労使交渉が続いていたものの折り合わず、ストライキに進展した。労組側が4年間で30%半ばの賃上げ要求をする中、最終的な企業側の回答は20%半ばと、労組側の要求を下回った。
当初は、ストライキはミズーリ州、ミシガン州、オハイオ州にある一部の工場(対象組合員数1.3万人)に限定されており、UAW所属14.6万人全員が職務放棄していたわけではなかったが、徐々に拡大し、10月24日には4.6万人規模となった。その間、バイデン大統領がストライキの現場を視察し、労組側への支持を表明するといった場面もみられたが、10月25日にFordで暫定合意が取り決められると、10月30日までに3社全てで暫定合意に至り、ストライキは収束した(表1)。合意内容は3社ともに共通して、新たな協約の初年度に11%の賃上げを実施するとともに、2028年までの4年間で合計25%の賃上げをすることになっている23。また、物価高騰による生活費の上昇分を賃金に上乗せする生活費調整(COLA:Cost of Living Adjustment)の復活も盛り込まれている(表2)。

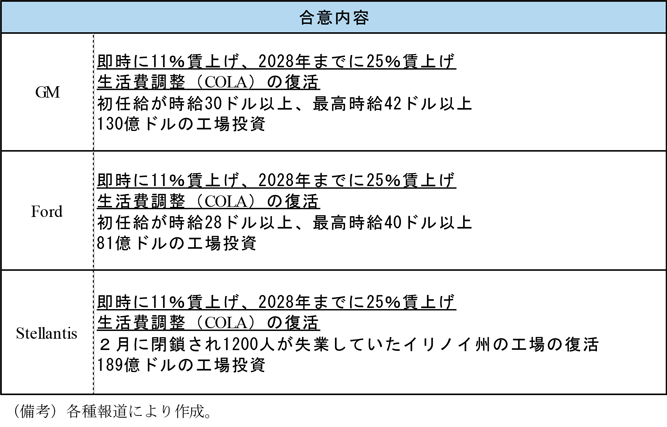
今回のストライキは全面ストまでは発展しなかったものの、自動車生産台数には大きな影響を与えた。8月に約1,056万台(年率)であった自動車生産台数は、10月には約892万台と急減した。その後11月には996万台まで回復しているものの、まだストライキ前の水準には戻っていない(図3)。
加えて、自動車業界は裾野が広い産業であることから、金属産業や機械産業等の関連産業においてもストライキの影響がみられた。鉱工業生産指数の推移をみると、製造業全体では10月に前月比▲0.8%となっており、一次金属では▲2.0%、機械では▲1.2%とそれぞれ減少している(図4)。内訳をみると、加工金属業である「塗装、彫金熱処理」では▲2.6%と大きく減少した。FRBが11月に公表したベージュブックにおいても、UAWのストライキによって、塗料等の中間財メーカーの受注が鈍化したと指摘されている。その後、11月には製造業全体では+0.3%、自動車・同部品が+7.1%、一次金属が+0.5%、機械が+0.7%と持ち直しており、ストライキ前の水準には達していないものの、ストライキの影響はおおむね収束に向かっていたものと考えられる。
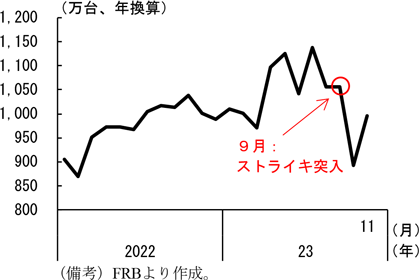
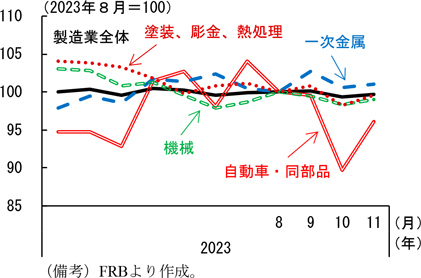
また、ストライキの影響は雇用者数にも現れている。ストライキ参加者はレイオフ(一時帰休)扱い24になることから、ストライキの前後で自動車・同部品の雇用者数が大きく変動し、10月は前月比▲3.2万人であるのに対し、11月は+3.0万人と反動増となっている。このため、雇用はおおむねストライキ前の水準に戻っていることが分かる(図5)。
このように、ストライキの影響は随所にみられたものの、2019年に発生したような全面ストライキ25までは発展しなかったことや、長期化しなかったことにより、経済全体には大きな影響が生じるまでには至らなかったと考えられる。
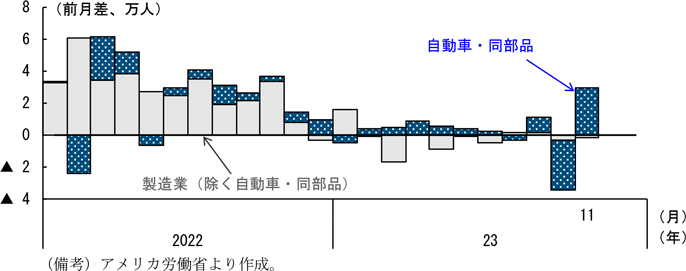
コラム2:公的統計の精度の低下に伴う政策決定への影響
英国の失業率は、調査票の回答率の低下による精度の低下が問題視されたことから、2023年8月以降の値が公表停止されていた26。公表停止に至らずとも、統計調査票の回答率の低下傾向は、例えばアメリカの雇用関連統計においてもみられている。米雇用統計における家計調査(Current Population Survey:CPS)及び事業所調査(Current Employment Survey:CES)の回答率27は、感染症拡大以前から緩やかな低下傾向がみられていたが、感染症拡大以降は低下傾向が加速していることが確認できる(図1)。また、雇用動態調査(JOLTS)の回答率は、2019年12月には58.0%であったが、感染症拡大後に大きく落ち込み、2023年9月には32.4%まで低下している。回答率の低下は、一般に統計結果の標準誤差を拡大させ統計精度の低下を招くが28、これにより適時適切な経済政策の決定を困難にし、ひいては世界経済にとってのリスクとなる可能性を高める。
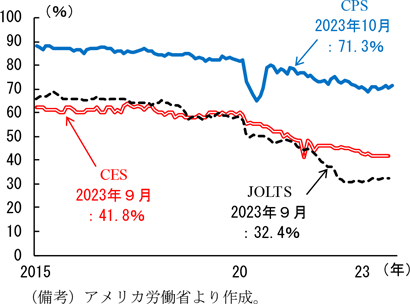
このため、回答率向上に向けて、各国政府は、回答の精度を維持しつつ、回答の負担軽減を図る必要がある29。例えば、Williams(2022)は、回答率向上に資する各国政府の取り組みについて、オンライン調査の促進、回答者との接触方法の改善30及びパラデータ31の利用を挙げている。
加えて、公的統計の作成は、国民及び事業者の協力により支えられているところ、その回答率及び統計精度の向上のために、各国政府はその目的や用途についての理解促進を図るとともに、国民及び事業者にも統計調査への回答に積極的に協力することが求められる。
2.欧州の景気動向
本項では、主に2023年後半のユーロ圏及び英国経済を概観するとともに、個人消費の弱さの背景を中心に分析する。
(景気は弱含んでいる)
最初に、実質GDPから欧州経済の動向を概観すると、ユーロ圏及び英国は感染症拡大前の水準を2021年後半には回復したものの、コロナ禍前を100としてユーロ圏は2023年7-9月期から10-12月期は、それぞれ103.0及び103.032、英国は2023年7-9月期から10-12月期は、それぞれ101.4及び101.033と横ばいから微減の動きになり、景気は弱含んでいる(第1-1-41図34)。
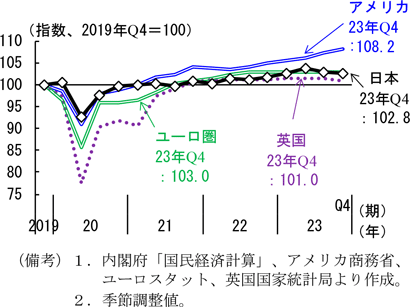
次に、GDPの需要項目別の動向を概観する。個人消費については、実質賃金が2023年後半に前年同期比でプラスに転じ、所得環境に改善がみられるものの、2022年以降急激な物価上昇が続いてきたこと等を背景に、ユーロ圏では弱含んでおり、英国では弱い動きとなっている。
設備投資については、ユーロ圏及び英国において、2022年以降持ち直していたが、金融引締めを受けて2023年7-9月期はおおむね横ばいとなっている。
外需については、ユーロ圏の輸出は英国等ユーロ圏域外の欧州35及び中国の需要の停滞から2022年10-12月期以降減少し、英国の輸出もユーロ圏内を含む欧州36の需要の伸び悩みから2023年1-3月期以降減少しており、ユーロ圏及び英国の輸出はともに弱含んでいる(第1-1-42図)。
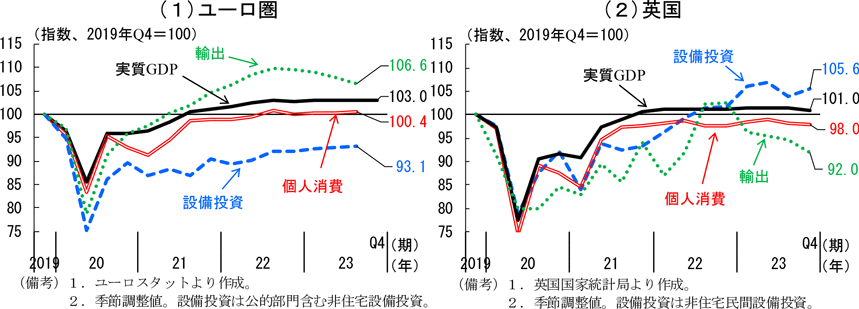
以下では、主要な需要項目である個人消費と設備投資について分析する。
(個人消費は、消費者信頼感の悪化を受け、英国はユーロ圏よりも弱い動き)
はじめに、個人消費の動向の背景を所得面から確認するため、ユーロ圏及び英国での名目賃金と物価の上昇率を比較してみる。
欧州では、感染症収束に伴う経済活動の再開やロシアによるウクライナ侵略(以下「ウクライナ侵略」という。)に伴うエネルギー価格の高騰を受けて、消費者物価上昇率が名目賃金上昇率を上回り、実質賃金の伸びがマイナス傾向で推移していたが、2023年半ばから変化がみられる。実質賃金上昇率は、消費者物価上昇率の低下と名目賃金上昇率の高まりを受けて、ユーロ圏では2023年7-9月期にプラスに転じ、英国では、2023年4-6月期以降プラスで推移している。このため、実質的な購買力は改善し始めていると考えられるものの、上述のように、実質個人消費支出には回復がみられていない(第1-1-43図)。
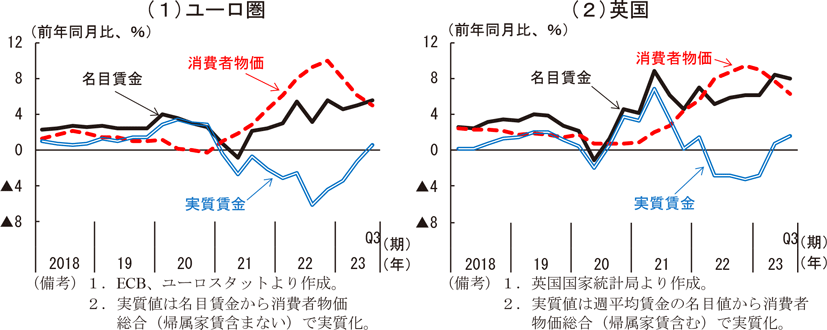
消費の弱さの背景には、消費者信頼感(消費者マインド)37の悪化が考えられる。消費者信頼感を構成する家計の現状と先行き、経済見通し及び高額商品購買意欲の推移をみると、特に、経済見通しは、英国のEU離脱が国民投票で可決された2016年6月以降、英国はユーロ圏よりも低いDI(良くなると答えた割合と悪くなると答えた割合の差)で推移しており、EU離脱を契機に、大陸の欧州諸国の市場へのアクセス悪化等への悲観的な見方が英国の消費者に広がったことが確認できる。さらに、2021年末からの金融引締めの開始以降は、構成項目のうち特に家計の先行きと高額商品購買意欲において、英国はユーロ圏よりも悪化が顕著である(第1-1-44図)。
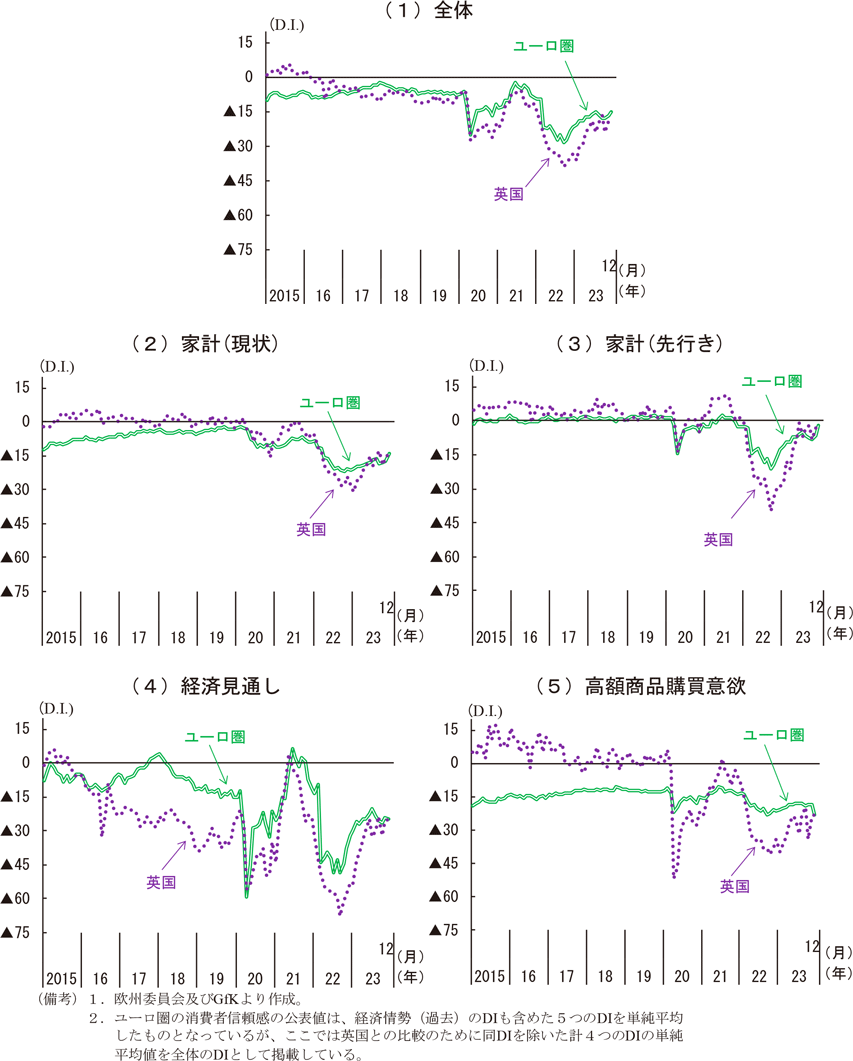
こうした違いの背景としては、金利上昇に伴う住宅ローン負担の影響の違いが考えられる。持ち家比率は、ユーロ圏と英国で同程度であるものの(第1-1-45図)、英国で5年以内に借換え時期を迎える短期の住宅ローンの比率はドイツ等と比べて著しく高く(第1-1-46図)、こうしたローンの大部分が低利で契約されているため、借換えの際の金利上昇に伴う返済額の増加の影響が大きいことが考えられる。また、イングランド銀行(BOE)も、住宅ローンを保有する世帯が金利上昇に伴う住宅ローン支払いの増加を見据えて消費を抑制し、予備的に貯蓄を積み増していることを指摘している38。
消費者信頼感の振れの幅は国によって違いがみられることに留意が必要であるが、住宅ローンの金利構造という制度的な要因も考慮すれば、消費者信頼感の相対的な悪化が、英国の消費の相対的な弱さの一因となったことを示唆していると考えられる。
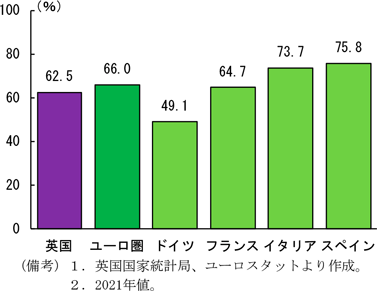
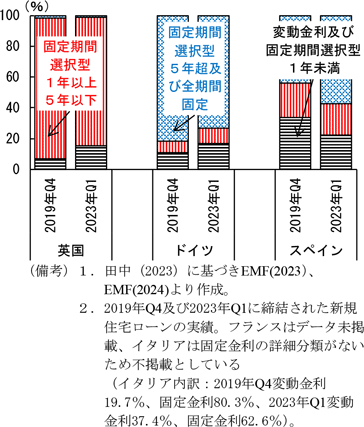
また、消費の弱さの背景には、金利上昇を受けた利子収入の増加に伴う貯蓄意欲の高まりもあると考えられる39。感染症拡大前の2019年各四半期の貯蓄額と比較して積みあがった超過貯蓄を名目のフロー及び実質のストックベースでみると、名目のフローはユーロ圏及び英国ともに感染症収束に伴い低下傾向となっていたが、2022年半ば以降は緩やかな上昇傾向に転じている。これを受けて、実質のストックは、消費者物価上昇率の低下もあいまって、同様に2022年半ば以降は緩やかな増加傾向にある。この結果、2023年4-6月期の実質超過貯蓄ストックは、実質GDP比でみて、ユーロ圏では約3.8%(約1.1兆ユーロ)、英国では約12.1%(約0.3兆ポンド)となっており、英国がユーロ圏に対して相対的に貯蓄を積み増していることが確認できる(第1-1-47図)。
なお、ECBは、2023年4-6月期時点で、超過貯蓄は高所得者層に偏ってはいるものの、低所得者層でも貯蓄超過がみられると指摘しており40、低所得者層でも貯蓄の取り崩しによる消費の下支えの余地があると考えられる。
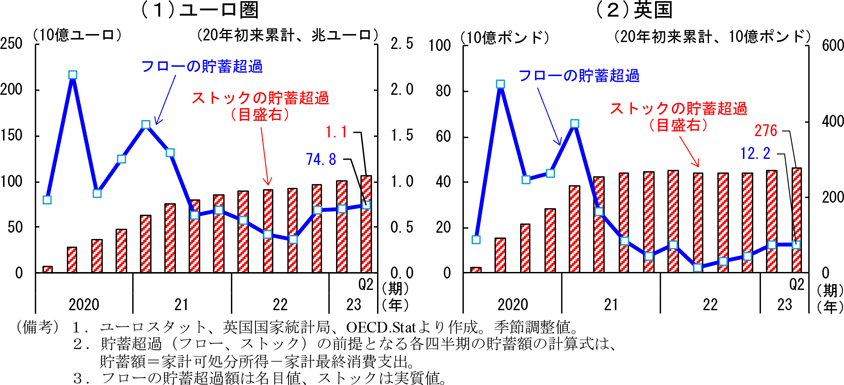
(設備投資は、おおむね横ばい)
続いて、設備投資の動向を確認する。
ユーロ圏においては、2021年以降は、政策対応(後述)を受けた脱炭素やデジタル化に向けた投資需要を中心に、知的財産生産物投資、機械・機器投資及び構築物投資のいずれも持ち直してきた。しかしながら、金融引締めやウクライナ侵略に伴う経済の先行き不透明感に加え、輸出先の資本財需要の低下を受け、工場建設等を控える動きがみられ始めたことから、2023年半ば以降は、構築物投資はおおむね横ばいとなり、設備投資全体としてもおおむね横ばいで推移している(第1-1-48図)。
なお、知的財産生産物投資は、感染症拡大前の2019年10-12月期を下回って推移しているが、背景には同期にアイルランドに対するユーロ圏外からの知的財産生産物投資が大幅に増え、高水準にあったことが挙げられる。この影響を除くため、2018年の平均値と比べると、2023年7-9月期の知的財産生産物投資は約15%増加しており、デジタル化を進めるための投資の強さがうかがえる。
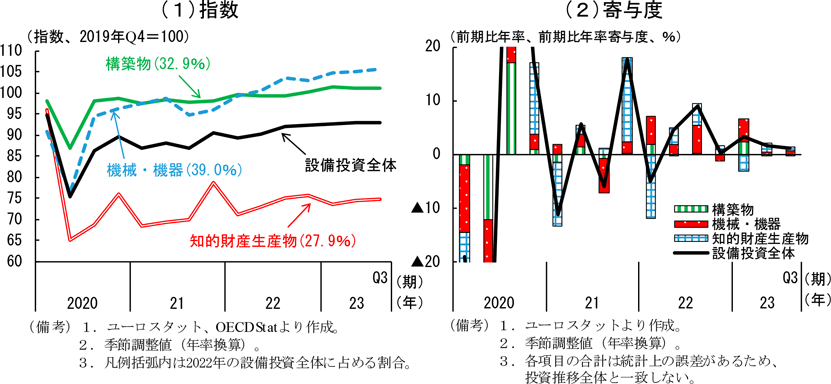
英国においても、ユーロ圏と同様に政策対応(後述)を受けた脱炭素やデジタル化に向けた設備投資需要から、2021年以降、知的財産生産物投資、機械・機器投資及び構築物投資のいずれも持ち直してきた。しかしながら、金融引締めやウクライナ侵略に加えて、英国においてはEU離脱に伴う経済の先行きに対する懸念が政策効果を弱めることとなり、2023年半ば以降は機械・機器投資及び構築物投資が減速したことを受け、設備投資全体としてはおおむね横ばいで推移している(第1-1-49図)。
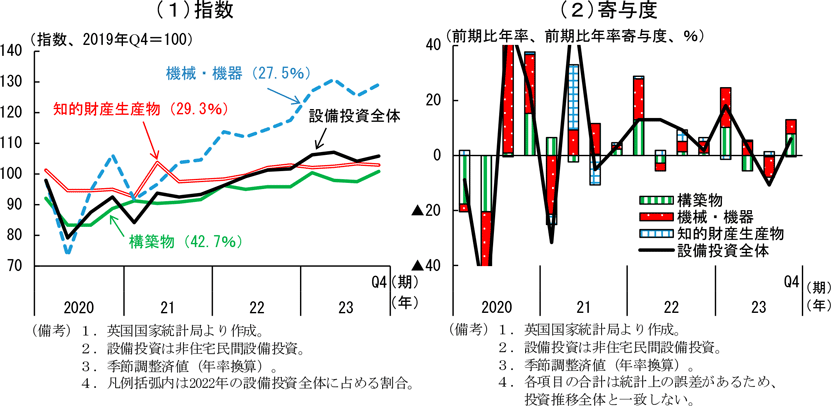
なお、金融引締めが進展する中であっても、設備投資が大きく落ち込まなかった背景には、脱炭素化等に向けた投資を促す政策の効果が考えられる。
EUは2020年12月に、2030年の温室効果ガス排出量を1990年比で少なくとも55%削減する目標を達成するための「Fit for 55」計画を、2022年3月にはウクライナ侵略を受けて「REPowerEU」計画等を策定している。また、英国は、温室効果ガス排出量を2035年に1990年比で78%削減することを目標としており、長期的なエネルギー安全保障と自立の強化等を目指し、2023年3月には「パワーアップ・ブリテン」を発表し、炭素排出のネットゼロを達成しながら英国の国際競争力の強化を目指すこととしている41。
このほか、EUにおいては、「Fit for 55」に基づきバッテリー規則を改正し、2024年以降、リサイクル済み原材料の使用割合の最低値導入、廃棄された携帯型バッテリーの回収率や、原材料別再資源化率の目標値導入義務が順次課される見込みである。域内企業にも同規則改正に基づく対応が求められることから、設備投資計画が相次いで公表されている(第1-1-50表)。
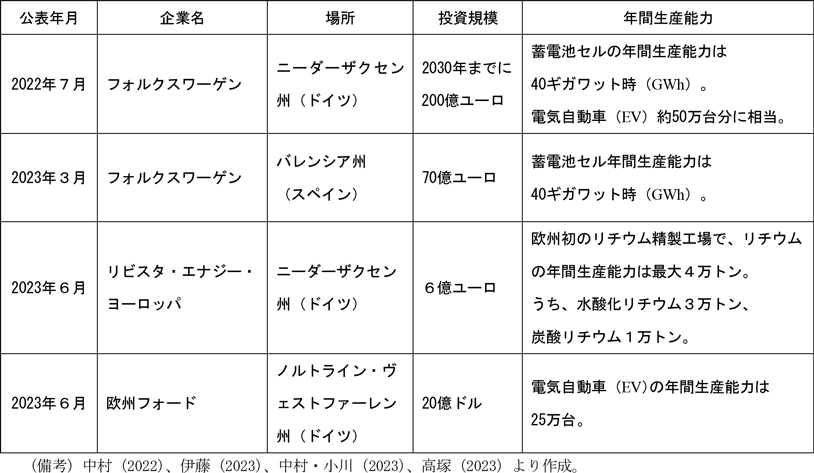
また、ドイツ政府は、2023年8月には「経済拠点としてのドイツのための計画」を公表し、研究開発費用の損金算入額の上限を現行の3倍へ引き上げるとともに、グリーン技術に係る投資額の15%を補助すること等により、2028年まで年間70億ユーロ(1.1兆円)規模の設備投資支援を行うこととしている。
これらの政策対応は、ユーロ圏、英国ともに、2023年の設備投資にプラス寄与しているものと考えられる。設備投資は、2023年半ば以降おおむね横ばいで推移しているが、政策効果の更なる発現により、今後は持ち直しの動きが期待される。
(労働需給は、ユーロ圏では引締まりが継続、英国では緩和)
続いて労働市場の動向を確認する。まず、労働供給をみると、15~64歳の労働力人口は、ユーロ圏は2021年に感染症拡大前の水準を超えた後、増加が続いている。回復が遅れていた英国でも、2023年4-6月期に感染症拡大前の水準に戻っている(第1-1-51図)。なお、就業者数についても同様の動きが確認される(第1-1-52図)。
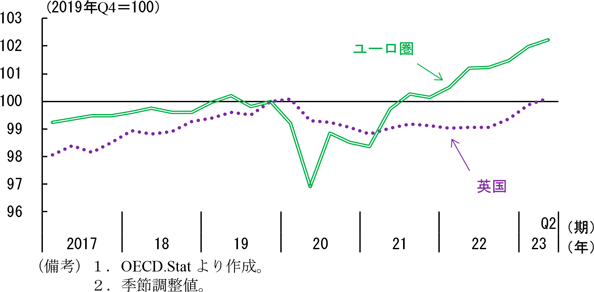
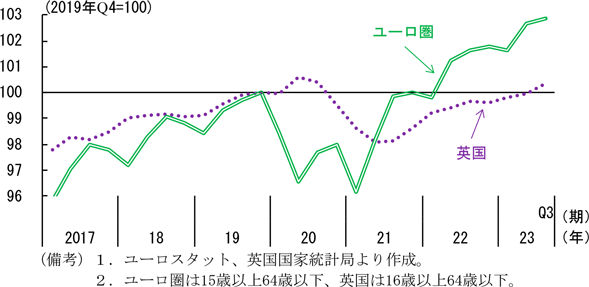
さらに、労働参加率の動向を、15~64歳、その内訳の25~54歳及び55~64歳、加えて65歳~74歳の各年齢層についてみてみる(第1-1-53図)。ユーロ圏においては、いずれの年齢層でも感染症拡大前の水準を上回って推移している。英国においては、生産年齢人口全体では感染症拡大前の水準をおおむね回復している。うち55~64歳では、感染症拡大以降、経済不活発率42は上昇し労働参加率の低下傾向がみられたが、2023年1-3月期以降、感染症収束に伴い短時間労働者が増加したことなどにより回復している43。
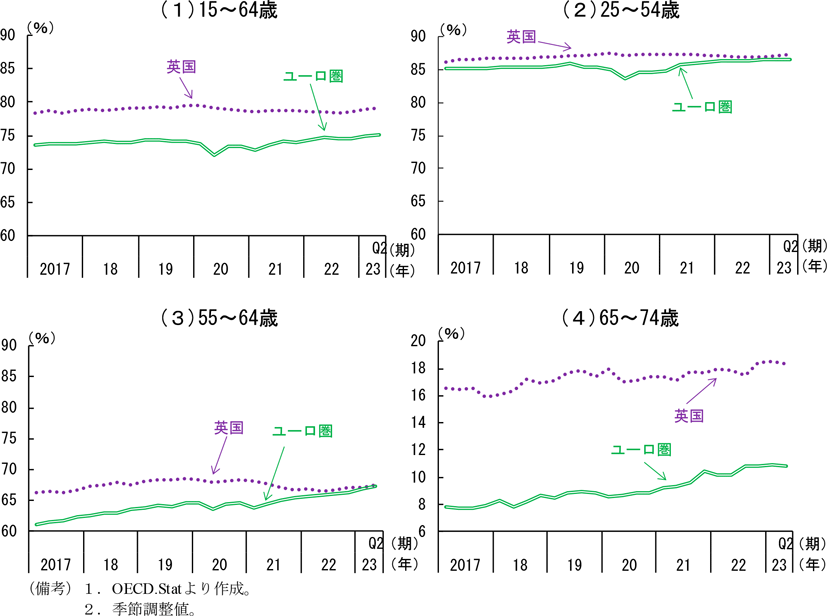
続いて、労働需要の強さを欠員率44の動向からみてみる。2020年後半以降、ユーロ圏及び英国ともに経済活動の再開等を受けて労働需要が増加したことから欠員率が上昇に転じ、2022年前半にかけてユーロ圏は3.2%、英国は3.8%と、感染症拡大前(2019年10-12月期)と比べてそれぞれ1.0%ポイント及び1.4%ポイント高い水準となった。その後、金融引締めを受けて低下傾向となっているものの、ともに感染拡大前以上の水準を維持している。ただし、ユーロ圏は2023年7-9月期には2.9%と2022年前半のピーク時から0.3%ポイント、英国は4-6月期に3.1%と0.7%ポイント低下し、英国はユーロ圏に比べ急速に労働需要が減少しているが、背景としては、前述のとおり、英国の消費がユーロ圏よりもより弱い動きを示していることが考えられる45(第1-1-54図)。
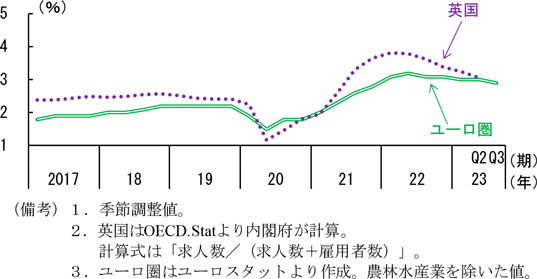
英国の労働需要の動向を確認するため、求人数の推移をみると、2022年6月以降減少傾向にある。業種別では、製造業は2022年4月以降、サービス業は同年6月、建設業は同年10月以降いずれも減少傾向にあり、いずれの業種も同年12月までに、求人数がピークから3割程度減少している46。2022年の求人数の9割程度を占めるサービス業のうち、医療・社会福祉では2023年10月、卸・小売は同年8月、飲食・宿泊は同年4月以降、いずれも減少傾向にあり、特に飲食・宿泊の減少率が大きい47(第1-1-55図)。
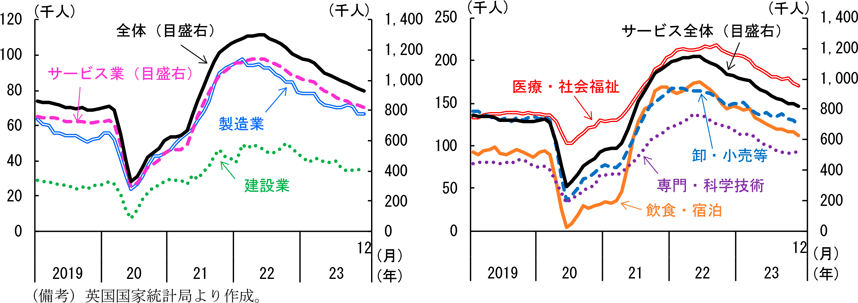
以上のように、欧州では労働供給は感染症拡大以前の水準をおおむね回復し、労働参加率の高まりもみられる一方、労働需要は感染症拡大以前の水準を上回っているが、2022年後半以降、特に英国で減少がみられている。感染症拡大以降の需給のひっ迫を受け低下してきた失業率は、ユーロ圏では、2023年10月において6.5%とおおむね横ばいを維持し、労働市場は堅調に推移48している(第1-1-56図)。他方、英国の失業率は、2023年7月において4.3%49と2023年2月以降上昇している50。この背景の1つとして、上述のように、特に飲食・宿泊等のサービス業で求人数が減少傾向にあることが考えられる(前掲第1-1-55図)。
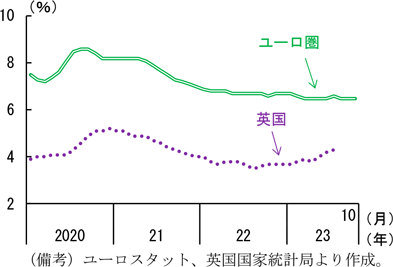
(交易利得・損失は、ユーロ圏でマイナス、英国ではプラス)
これまでみてきたように、ユーロ圏と英国の景気動向を比較すると、英国での消費の弱さや労働市場の需給の緩みは、ユーロ圏と比べて景気の下押し要因となっていると考えられる。一方、足下の交易条件の改善は、英国の景気を下支えしていると考えられる。ウクライナ侵略を受けたエネルギー価格の高騰に加え、ユーロ及びポンドの対ドル為替レートが下落したことから、2022年7-9月期にはユーロ圏の交易損失は対GDP比で2.8%、英国は同1.9%となった。その後エネルギー価格の下落や為替レートの上昇等を受けて、2023年4-6月期には、ユーロ圏の交易損失は対GDP比0.4%まで縮小、英国の交易利得は同0.5%とプラスに転じた(第1-1-57図)。
こうした交易条件の変化に伴う実質購買力の変化によって、ユーロ圏については引き続き景気の下押し圧力がみられるものの、その程度は急速に緩和しており、英国については、景気を下支えする動きがみられていると考えられる。
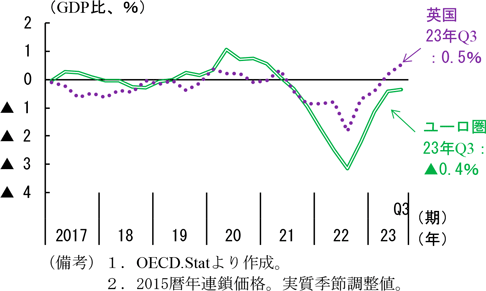
(まとめ:英国は消費と雇用はユーロ圏より弱いが、交易利得が下支え)
これまでみてきたように、ユーロ圏と英国の景気はともに弱含んでいるが、両者の動向には異なる特徴もみられる。特に個人消費については、ユーロ圏、英国ともに名目賃金上昇率が消費者物価上昇率を上回り実質的な購買力の向上がみられ始めたものの、ユーロ圏では弱含んでおり、英国においてはEU離脱決定以降の経済見通しの悪化や、金利上昇に伴い住宅ローン利払い負担が増加するとの懸念から、弱い動きとなっている。
設備投資については、ユーロ圏及び英国ともに知的財産生産物は設備投資を継続的に引き上げている一方、金融引締め等を受けて、設備投資全体はおおむね横ばいで推移している。
雇用情勢については、ユーロ圏においては引き続き労働需給がひっ迫して堅調に推移しているものの、英国においては労働需要の鈍化に伴い労働市場は緩和している。
一方で、交易損失・利得については、ユーロ圏では交易損失が発生し、景気の下押し圧力がみられるものの、その程度はこのところ急速に緩和している。英国については交易利得が発生し、景気を下支えする動きがみられている。
先行きについては、個人消費は、ユーロ圏及び英国では弱含みが続くことが懸念されるが、超過貯蓄の取崩しによって下支えされる可能性も考えられる。設備投資については、ユーロ圏及び英国では、ともに脱炭素やデジタル化に向けた政策効果の更なる発現により、持ち直しの動きが期待される。総じてみれば、ユーロ圏においては、今後景気は持ち直しに転じていくが、英国においては、EU離脱と住宅ローン利払い負担の増加が消費の回復ペースを弱め、景気は横ばい圏内で推移すると考えられる。
コラム3:ウクライナ侵略と欧州の石油・天然ガス供給の変化
本コラムでは、ウクライナ侵略を受けた欧州主要国の石油・天然ガス供給の変化と、エネルギー価格の推移について確認する。
(ウクライナ侵略前は、ドイツとイタリアはロシアへのエネルギー依存が高い)
まず、ウクライナ侵略前の2021年における、欧州各国のロシアからの石油・天然ガスの輸入金額の国別構成比をみると、主要国の中では、イタリア(17.5%)及びドイツ(13.0%)で高く、フランス(4.8%)やスペイン(3.8%)は相対的に低い(図1)。
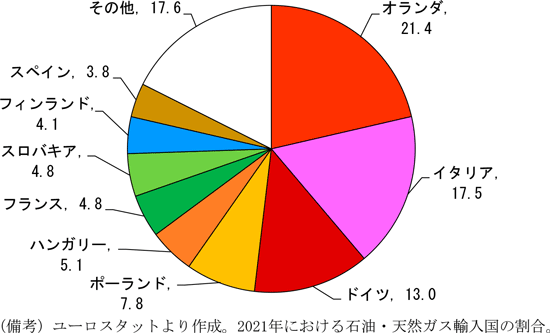
次に、ユーロ圏及び欧州主要4か国(ドイツ、イタリア、スペイン、フランス)の2021年における石油・天然ガス輸入先をみると、ユーロ圏はロシアからの輸入が21.1%、ドイツは27.1%、イタリアは25.7%であり、両国はユーロ圏全体と比較してロシアへの依存度が高い。一方、スペインは8.0%、フランスは10.6%とロシアへの依存度は低い(図2)。
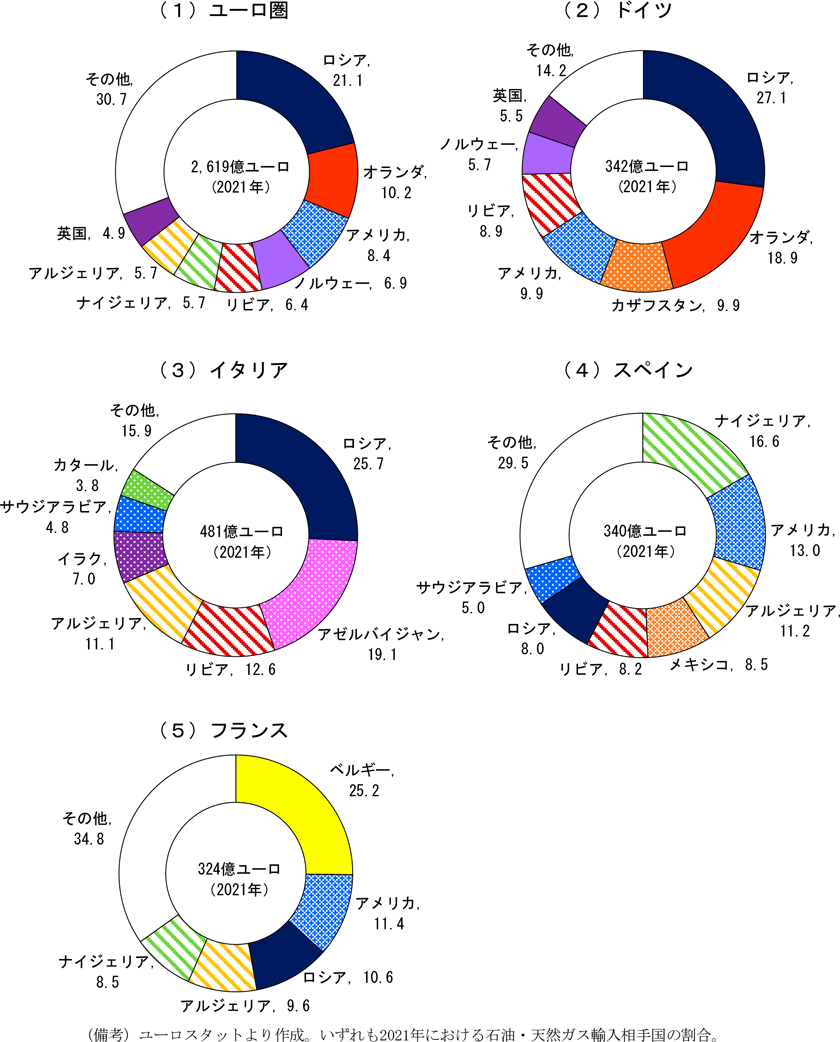
(ウクライナ侵略後のエネルギー価格高騰は、エネルギー集約度が高い産業を制約)
しかしながら、ウクライナ侵略後の2022年3月以降の石油・天然ガスのロシアからの輸入金額の推移をみると、ドイツは、2023年春以降ほぼ輸入を停止し、イタリアは、2023年半ば頃にはほぼ輸入を停止している(図3)。その結果、2023年1~9月の石油・天然ガスの輸入先は、ドイツにおいては、ロシアは0.1%(2021年は27.1%)と大幅に減少する一方、ノルウェーが13.8%(同5.7%)、アメリカが12.6%(同9.9%)、英国が9.7%(同5.5%)と大幅に増加している。イタリアにおいては、ロシアが2.7%(同25.7%)と大幅に減少する一方、アルジェリアが20.5%(同11.1%)、アメリカが10.1%(同2.3%)、ノルウェーが5.6%(同2.7%)と大幅に増加している(図4)。
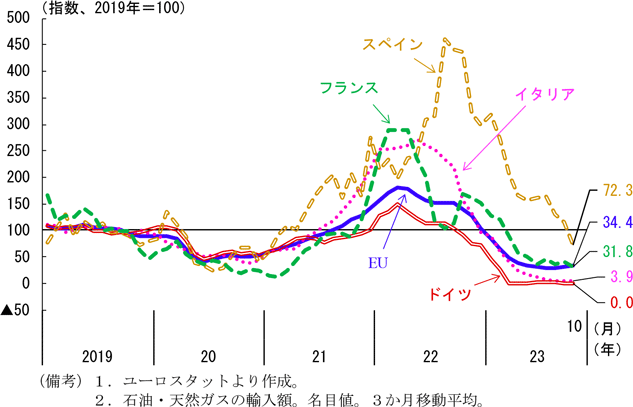
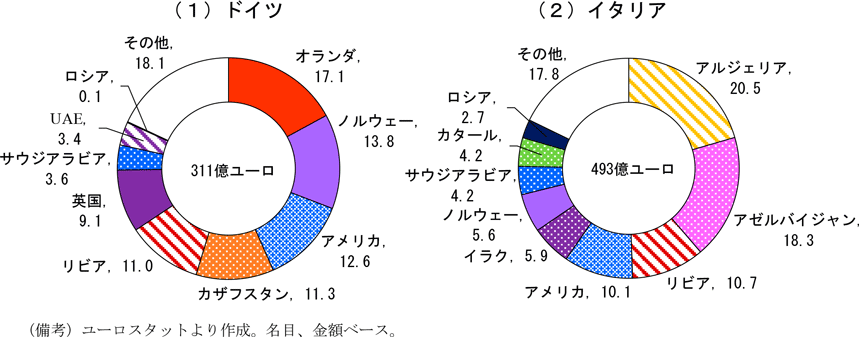
このようなロシアへのエネルギー依存を急速に減少させた結果、欧州各国のエネルギー供給量は急速に減少したことから、感染症収束に伴う経済活動の再開を受けて上昇傾向にあったエネルギー価格は更に急上昇した。特に、ロシアへの依存度が高かったドイツとイタリアはフランスやスペインに比べてピーク時の価格が高かったことが確認できる(図5)。
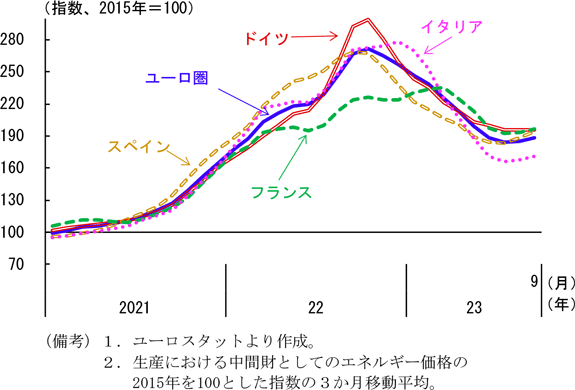
エネルギー価格の高騰は、特にエネルギー集約度(生産一単位当たりの一次エネルギー51消費量)が高い産業(金属、化学、鉄鋼等)の生産を大きく制約している可能性がある。Christian, H. and W. Enzo(2023)は、ドイツの産業別パネルデータを用いた分析で、ウクライナ侵略前にエネルギー価格が急上昇していた2021年9月以降、短期の影響として、エネルギー集約度の高い産業ほど生産の下押しがみられていたものの、ウクライナ侵略後はこうした影響が4倍以上となり、エネルギー価格の高騰がウクライナ侵略を契機にエネルギー集約度の高い産業の生産を大きく減らした52ことを示唆している。
ウクライナ侵略の今後の見通しが不透明な中で、エネルギー集約度が高い産業の生産を回復させるためには、石油・天然ガスから再生可能エネルギー等へのエネルギー源の転換を進める必要がある。しかしながら、エネルギー構造の転換には中長期的な対応が求められることから、短期的には現在のエネルギー価格高騰が、エネルギー集約度の高い産業を中心とした生産への制約になる可能性は引き続き残ると考えられる。
3.欧米の物価・金融政策の動向と金融資本市場への影響
本項では、まず、低下傾向にある欧米の物価動向及びその背景について確認する。続いて、物価動向を受けた金融政策の変化及び金融資本市場への影響について確認する。
(輸入インフレ圧力は弱まりつつあり、消費者物価上昇率は低下傾向)
消費者物価上昇率は、各国ともに2022年半ば以降は低下傾向となっている(第1-1-58図)。共通する要因として、エネルギー、食料及びその他財の価格の上昇率低下が挙げられる。
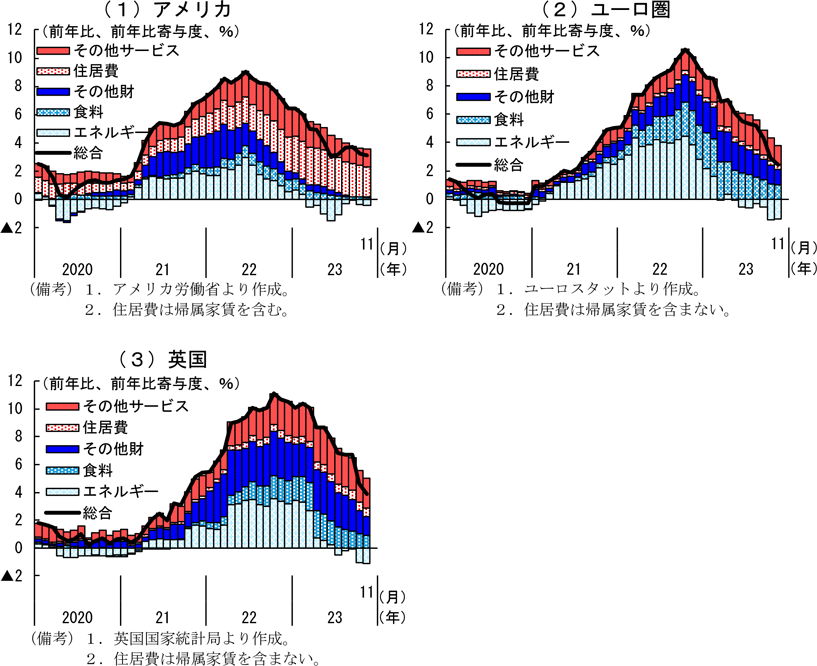
その背景としては、輸入インフレ圧力の弱まりが考えられる。財及びサービスの輸入物価54(前年比)の動向をみると(第1-1-59図)、2022年前半から年半ばにかけては、ウクライナ侵略を受けたエネルギー及び食料価格の高騰(第1-1-60図)を受けて、財を中心に輸入物価上昇率は加速した。特に、エネルギーを輸入に依存するユーロ圏では、アメリカに比べ財の輸入物価上昇率の加速が長期化していた。
しかしながら、2022年後半以降は、金融引締めの進展に伴う通貨高に加え(第1-1-61図)、エネルギー及び食料価格の下落並びに国際物流コストの低下(第1-1-62図)を受け、欧米ともに輸入物価の上昇率には低下傾向がみられ、2023年半ばにはマイナスとなった。こうしたことから、欧米ともに国内物価に対する輸入インフレ圧力は弱まりつつあることがうかがえる。しかしながら、国際海運コストは2023年11月半ばに底打ちしており、再度輸入インフレ圧力が加速する可能性がある点には注視が必要である。
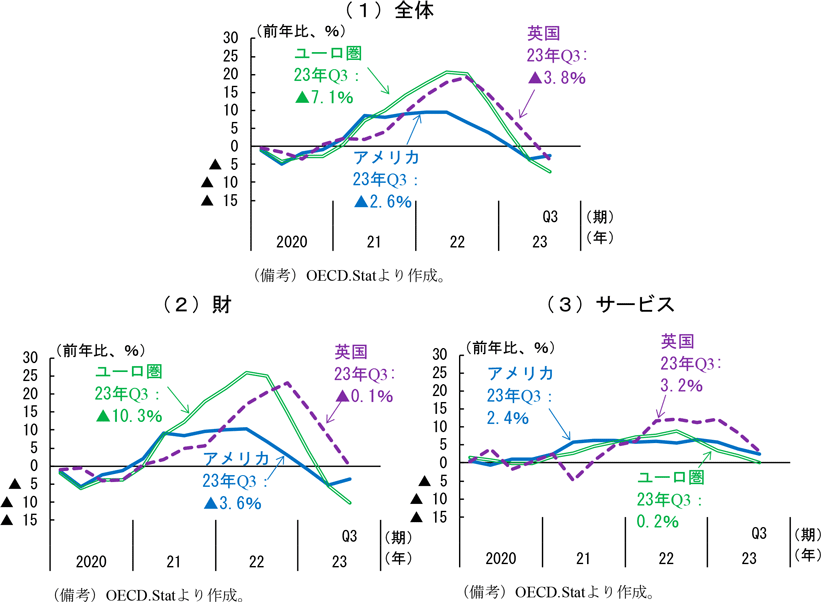
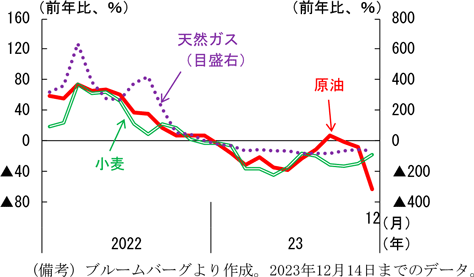
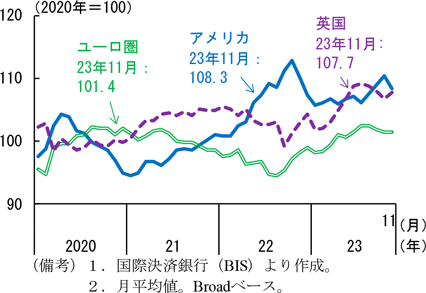
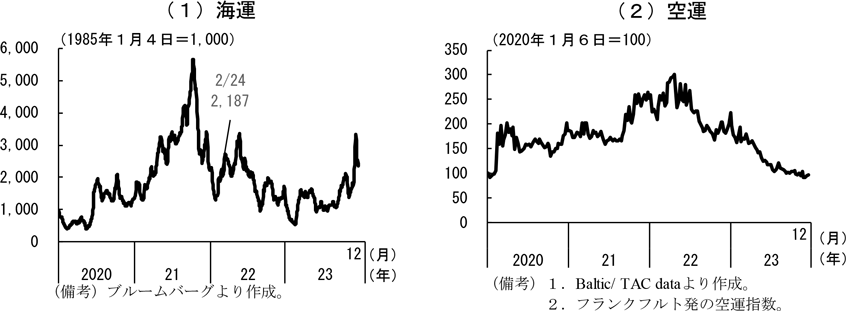
コラム4:国際商品市況
2020年以降、国際商品市況は感染症の拡大と収束、ウクライナ侵略等を受けて大きく変動した。本コラムでは、2021年以降世界的にみられた急激な物価上昇の契機となり、各国の物価動向、ひいては景気動向に大きな影響を与える主要な商品である原油、天然ガス、小麦の価格動向について概観する(図1)。分析の対象とした2023年後半の動きについては、原油価格に一時的な上昇がみられたものの、いずれの価格も総じて安定した水準で推移していた。背景には、原油についてはOPECプラスによる協調減産の拡大見送りや中国の景気後退懸念等、天然ガスについては地下ガス貯蔵量の積み増し、小麦についてはロシア産小麦の輸出量増加があったと考えられる。以下、商品ごとに動きを詳しくみていこう。
(i)原油
原油価格(WTI)は、2023年7月上旬から8月上旬にかけ、OPECプラスによる協調減産の延長等を受けた供給減により上昇し、70ドル台前半から80ドル台半ばで推移した。8月中旬には、中国の景気後退懸念等に伴う需要減を受けて70ドル台後半まで下落したものの、8月下旬から9月にかけ、アメリカの金融引締め長期化懸念の後退等に伴う需要増、サウジアラビアやロシアによる自主減産の延長表明等を受けた供給減から、90ドル台前半まで上昇した。
その後、10月中旬にはイスラエル及びパレスチナ武装勢力間の衝突に端を発する中東情勢の緊迫化を受けた供給懸念がみられたものの、12月上旬にかけ、中国の景気後退懸念の高まり、OPECプラスによる協調減産の拡大見送り等を受け、60ドル台後半まで下落した。なお、12月中旬には、アメリカ連邦政府による戦略石油備蓄(SPR)の拡大計画の公表等を受け、需要後退に対する警戒感が和らぎ、70ドル台前半まで上昇した。
(ii)天然ガス
欧州における天然ガスの先物価格(TTF)は、8月初旬から下旬にかけ、南欧での猛暑等を受けた電力需給ひっ迫等を受け、40ユーロ/メガワット時前半まで上昇した。9月上旬から10月上旬にかけ、主要な液化天然ガス(LNG)輸出基地でのストライキの影響がみられたものの、地下ガス貯蔵量の積み増しを受け、30ユーロ/メガワット時後半まで下げた。
その後、10月中旬から下旬にかけて、中東地域をめぐる情勢の悪化等を受け、50ユーロ/メガワット時前半まで大幅に上昇したが、12月中旬にかけて、暖冬も背景に、30ユーロ/メガワット時半ばまで下落した。
(iii)小麦
小麦価格(シカゴ商品取引所)は、7月中旬におけるウクライナ産小麦の輸出再開に関するロシアとの合意の更新停止等により、7ドル/ブッシェル台前半まで上昇した。その後、ロシア産小麦の輸出量増加や、価格が高いアメリカ産小麦への低調な輸出需要等を受け、10月にかけて5ドル/ブッシェル台半ばに下落した。
11月に入り、アルゼンチン産の生産量が減少する見込みから555ドル/ブッシェル台後半に上昇した後、12月中旬には、アメリカ産への輸出需要が改善したことから、6ドル/ブッシェル台前半まで上昇した。
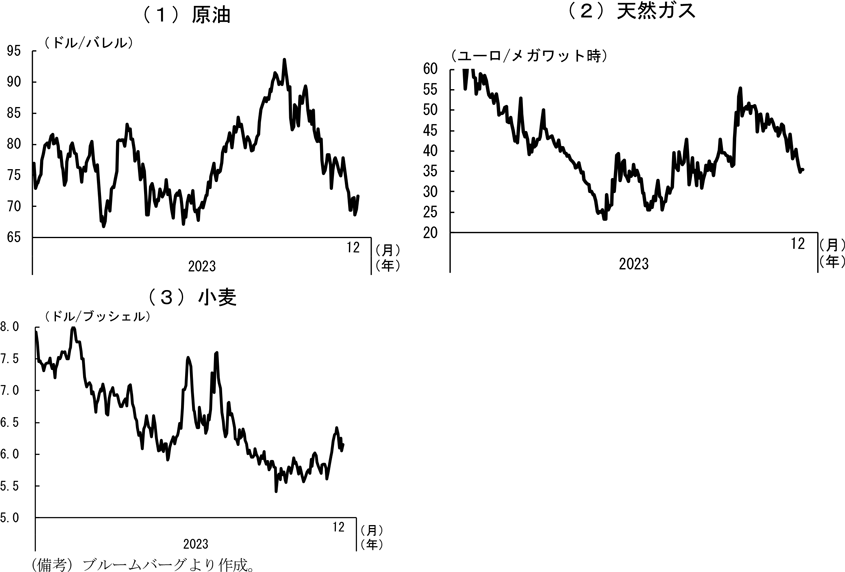
(欧米中銀は物価上昇率の低下を受けて政策金利を据置き)
欧米中銀は、2022年以降、物価上昇率の加速及び高止まりを受けて金融引締めを継続してきたが、2023年秋以降、物価上昇率が低下傾向にある中で、政策金利を据置きしている(第1-1-63図、第1-1-65表)。
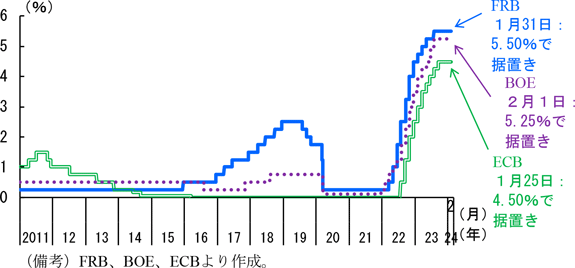
アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)は、2022年3月の連邦公開市場委員会(FOMC)において、フェデラル・ファンド・レート(FF金利)の誘導目標範囲を0.25%ポイント引き上げて以降、2023年7月までに累計で5.25%ポイント引き上げた。その後、同年9月以降は、2024年1月のFOMCまで4会合連続で誘導目標範囲が据え置かれた。今後の金融政策決定に関して1月のFOMCでは、「インフレ率が2%に向かって持続的に低下しているという、より確かな確信を得られるまでは、利下げは適切ではないだろう」と、2022年3月以降の利上げ局面の終了を示唆すると同時に、早期の利下げ転換に対しては慎重なスタンスが示された。なお、2023年12月に公表された四半期経済見通し(Summary of Economic Projections)におけるFOMC参加者のFF金利見通し(ドット・チャート)によれば、2024年末までに0.75%ポイントの利下げ(1回の利下げ幅を0.25%ポイントとすれば、3回分の利下げに相当)が行われる可能性が示されている。
また、政策金利の引上げと同時に、FRBの保有資産の削減(量的引締め)が進んでいる。FRBは2022年5月のFOMCで量的引締めの基本方針を公表し、同年6月に開始して以降、償還を迎えた米国債及び不動産担保証券(MBS)の再投資額を調整56することにより、2023年初にかけてFRBの保有資産は着実に減少してきた(第1-1-64図)。2023年3月には、アメリカにおける地方銀行の経営破綻に対応するために新たに導入したバンク・ターム・ファンディング・プログラム(BTFP)57の利用が急増したこと等を背景に、FRBの保有資産は一時的に増加したものの、その後は2024年に至るまで順調に減少している58。
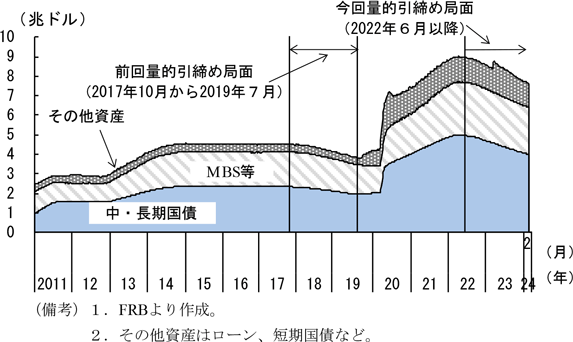
欧州中央銀行(ECB)は、2022年7月の理事会において主要リファイナンスオペ金利を0.50%ポイント引き上げて以降、2023年9月までに累計で4.50%ポイント引き上げた。その後、同年10月以降、2024年1月の理事会まで3会合連続で据え置いた。1月の理事会においては、金利は今の水準が十分に長い期間維持されれば、インフレ率が目標の2%へ戻ることに大きく貢献する水準にあると考えている、との認識が示された。今後の政策金利については、経済・金融データによる物価上昇の見通し、基調的な物価変動、金融政策の波及状況に基づいて決定するとしている。さらに、量的引締めに向けた保有資産の削減については、ECBはパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)における償還された元本の再投資を2024年7月より一部停止し、2025年1月以降は全て停止する予定としている。
また、イングランド銀行(BOE)は、2021年12月の金融政策委員会においてバンク・レートを0.15%ポイント引き上げて以降、2023年8月までに累計で5.15%ポイント引き上げた。その後、同年9月以降、2024年1月の金融政策委員会まで4会合連続で据え置いた。今後については、同年1月の金融政策委員会において、中期的に物価上昇率を持続可能な形で2%の目標まで戻すためには、委員会の任務に沿って、十分な期間、十分に制限的な金融政策であり続ける必要があるとしている(第1-1-65表)。
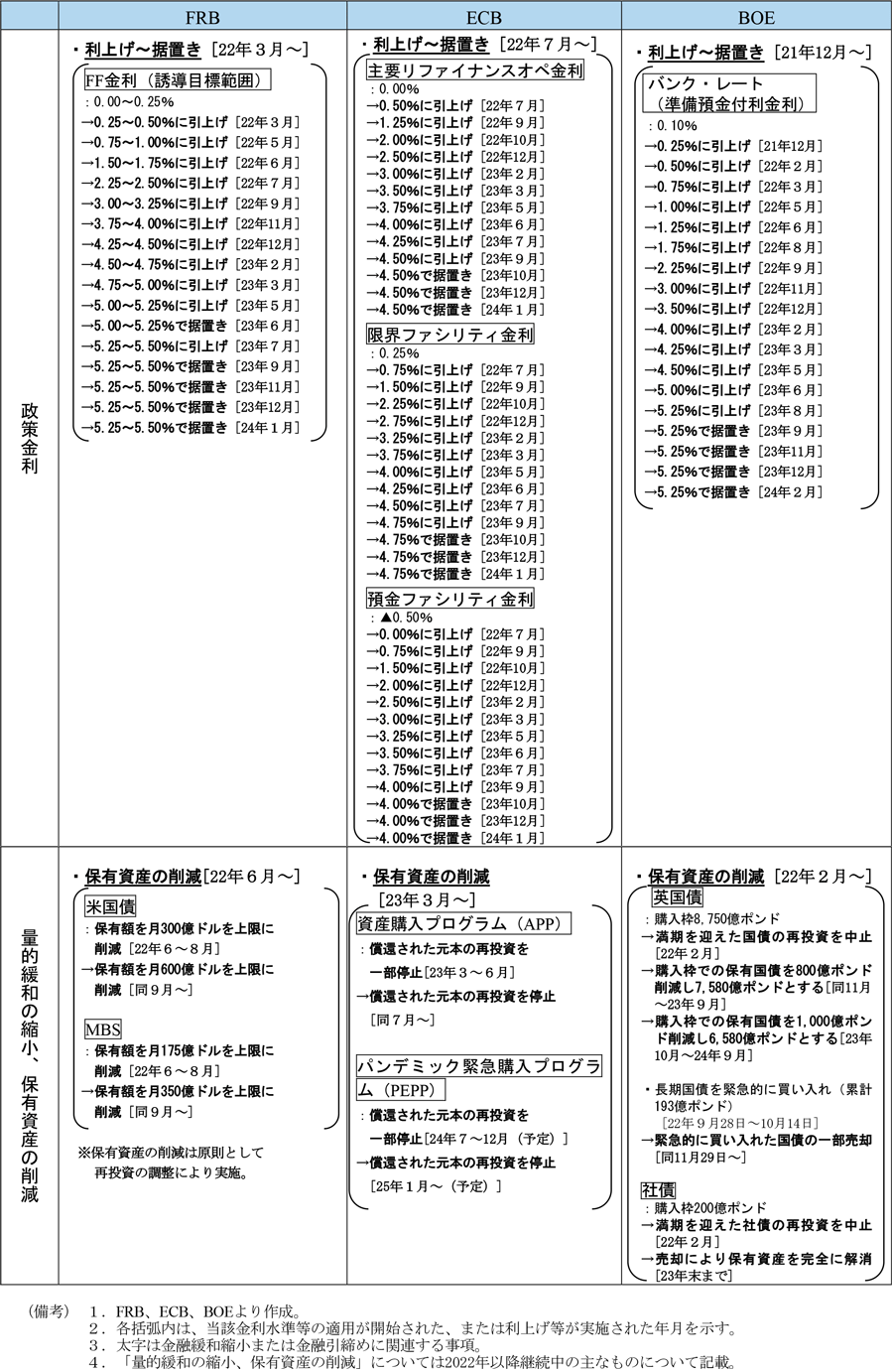
(長期金利は欧米ともに下落傾向で推移)
このような政策金利の引上げや保有資産の削減を受け、欧米長期金利は2022年初から上昇し始め、2022年10月には米、英長期金利は4%前後、ドイツ長期金利は2%台前半に達した(第1-1-66図(1))。2023年以降をみてみると(第1-1-66図(2))、3月にはアメリカにおける地方銀行の経営破綻及び欧州における大手金融機関の買収事案を受けて59、安全資産である国債に資金が流入し、欧米長期金利は急落した。しかし、5月以降、英国では物価指標の高止まりや堅調な雇用統計を受けてBOEの利上げ継続期待が高まる中、長期金利は大幅に上昇した。また、後段で詳述するが、2023年7月以降は、米長期金利が大幅に上昇し、10月半ばには2007年7月以来、約16年ぶりとなる5%台に一時到達した。なお、この間、欧州金利も米金利に連れて上昇し、ドイツ長期金利は2011年7月以来約12年ぶりに3%に迫った。
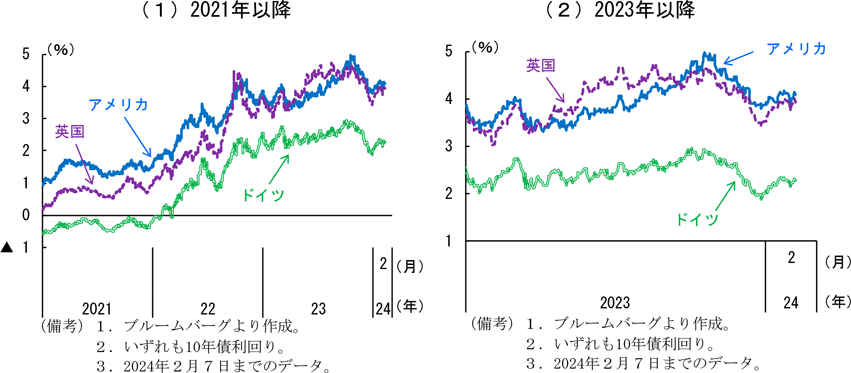
7月以降の米長期金利の上昇については、FOMCでも議論が行われており、10月31日から11月1日に開催されたFOMCの議事要旨において「様々な指標が、(2023年7月以降の)長期金利の上昇は、主にターム・プレミアムの上昇によってもたらされたことを示唆する」「米国債の将来的な供給増加が懸念されていることや、経済・政策見通しに関する不確実性が高まっていること等が、ターム・プレミアムの上昇に寄与している可能性が高いと、一般にFOMC参加者は見ている」との記述がみられた。ターム・プレミアムとは、短期債に代わり長期債を保有することにより上乗せされる金利60を指し、ターム・プレミアムの低下は長期債に対する需要の増加を、上昇は長期債に対する需要の減退を示唆する。本局面では、米国債市場の需給環境悪化懸念の高まり61や、アメリカ政府の借入能力そのものへの懸念の高まり62に加えて、金融引締めが続く中でも潜在成長率を超えるほど堅調なアメリカ経済指標が経済の不確実性として意識されたこと等が、ターム・プレミアムの上昇要因として考えられる63。実際、ニューヨーク連銀が推計する米10年債のターム・プレミアムは、2023年7月以降、10月にかけて大幅に上昇し(第1-1-67図)、同期間の米国債のイールドカーブは短期債ゾーンが小幅な上昇にとどまる一方、長期債ゾーンが大幅に上方にシフトした(第1-1-68図)。

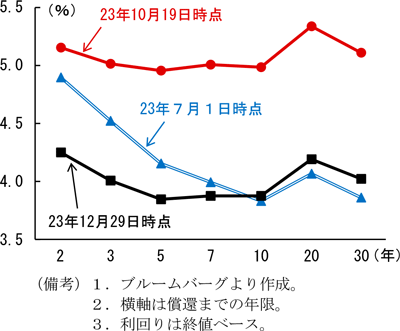
2023年末にかけての欧米長期金利は、物価指標の鈍化等を受けて大幅に低下した。しかしながら、2024年初以降は欧米主要中央銀行の理事会メンバーから早期利下げ観測をけん制する旨の発言がなされたこと等を受け、欧米長期金利は反発し、その後は米英長期金利は4%前後、ドイツ長期金利は2%台前半で、おおむね横ばいで推移している。

