第2章 主要地域の経済動向(第3節)
第3節 ヨーロッパ経済
本節では、ヨーロッパ経済の最近の動向を振り返るとともに、英国のEU離脱問題や世界的な貿易の縮小等に起因するドイツを中心とした製造業の不振、また米欧間の貿易摩擦など、ヨーロッパ経済とその先行きに影響を与えている事象を取り上げ、今後の見通しとリスク要因を整理する。
ユーロ圏経済は、良好な雇用・所得環境や緩和的な金融政策を背景に、個人消費等の内需を中心とした緩やかな回復基調で推移してきたが、輸出や生産については、英国のEU離脱問題や米中貿易摩擦、中国経済の減速に伴う外需の伸びの鈍化が重しとなり、19年末にかけて景気は弱い回復となっている。
英国では、EU離脱に係る不確実性の継続が企業の投資判断を長期にわたり抑制しているとみられるほか、英国・EU間のサプライチェーンに対する不安が企業の生産・財輸出活動に様々な影響を与えている。19年12月の英国議会下院総選挙において、保守党が総議席の単独過半数を獲得したことから、英国・EU双方による離脱協定の批准を経て、英国は20年1月末にEUを離脱し移行期間に入った。これにより、英国のEU離脱そのものへの不確実性は解消されたものの、EU離脱関連法には20年末を期限とする移行期間の延長禁止が盛り込まれているなど、離脱後の英国・EU間の経済関係をめぐる不確実性は継続している。
1.ユーロ圏と英国の経済動向
(1)ユーロ圏経済の動向
(景気は弱い回復となっている)
ユーロ圏では、景気は弱い回復となっている。実質経済成長率は、19年4~6月期は前期比年率0.6%、7~9月期は同1.1%、10~12月期は同0.2%と、13年4~6月期以降27四半期連続のプラス成長となったものの、総じて伸びは鈍化している。個人消費は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかながら増加しているが、総固定資本形成の構成項目である機械設備投資は、19年4~6月期にかけておおむね横ばいで推移していたものの、製造業の不振により7~9月期に減少に転じた。外需については、19年1~3月期は英国の当初のEU離脱期日である3月末を控えた駆込み需要の増加等もありプラスに寄与したが、4~6月期はその反動でマイナスに転じた1(第2-3-1図)。
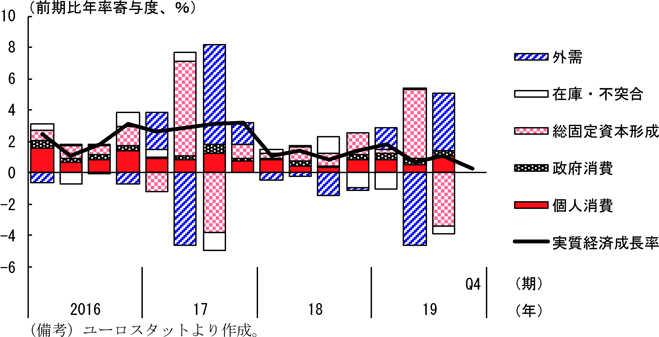
(ドイツとイタリアは弱含み、フランスとスペインは堅調)
ユーロ圏全体では景気は弱い回復となっているものの、主要国別にみると2、各国で回復の度合いは異なる。
ドイツでは、景気は弱含んでいる。19年7~9月期の実質経済成長率は、雇用・所得環境の改善を背景に堅調な個人消費が下支えして、前期比年率0.8%となった。しかし、公表元であるドイツ連邦統計局によると、10~12月期は、7~9月期に堅調であった個人消費と政府消費が大きく減速し、機械設備投資も7~9月期に引き続いて減速したことから、同0.1%と伸びが鈍化したと説明されている(第2-3-2図)。
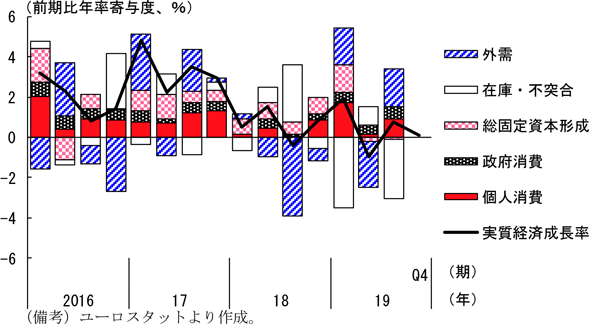
フランスの19年7~9月期の実質経済成長率は前期比年率1.0%と、ドイツ(同0.8%)やイタリア(同0.2%)と比べ堅調であったが、10~12月期は同-0.3%と低下した(第2-3-3図)。7~9月期が堅調に推移した背景としては、内需の各項目がいずれも増加し、特に総固定資本形成が成長に大きく寄与したことにある。総固定資本形成の内訳をみると、住宅投資は伸び悩んだ反面、企業投資と政府投資が伸びている。個人消費もプラス成長に貢献しているが、この背景には、マクロン政権が実施した経済社会緊急対策3の効果もあると考えられる。外需については、輸出は財・サービスともに緩やかに増加したものの、輸入が大幅に増加したことで、純輸出はマイナスに寄与している。これは、輸入が減少した4~6月期の反動に加え、好調な内需を背景に輸入が増加したことによると考えられる。一方で10~12月期については、総固定資本形成、個人消費がともに減速し成長の重しとなった。この背景としては、在庫の取り崩しに加え、マクロン政権が進める年金制度改革案への大規模な反対運動4がパリを中心に発生し、複数の労働組合による公共交通機関の運休や製油所の操業停止等のストライキが経済活動にマイナスの影響をもたらしたと考えられる。なお、12月の購買担当者景気指数(PMI)をみると、製造業PMIは、後述するようにユーロ圏が中立水準である50を下回っているのとは対照的に、19年後半は50を上回って推移している(第2-3-4図)。また、サービス業PMIについても、金融業を中心とする国内向け新規事業の増加を反映して50を上回って推移している。概してフランスの景気がドイツと比較して堅調である背景として、フランスはGDPに占める製造業5や財輸出6の比率が低く、世界経済の減速の影響を受けにくい経済構造を有していることが考えられる。しかしながら、上記の大規模なストライキやデモは20年1月以降も継続されており、今後も長引くことがあれば、同国経済の一層の停滞を引き起こす可能性がある。
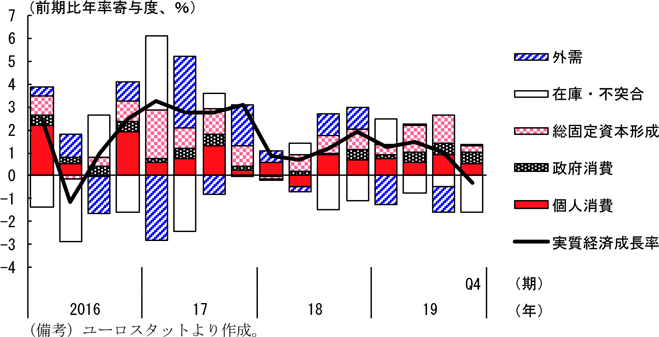
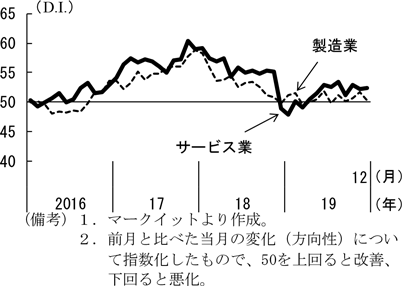
イタリアでは、19年1~3月期は設備投資を中心とする総固定資本形成や輸入の大幅な減少による外需の増加が成長にプラスに寄与したものの、在庫の取り崩しが成長にマイナスに寄与し、実質経済成長率は前期比年率0.9%となった(第2-3-5図)。4~6月期は、個人消費は伸び、また外需も成長に中立であったが、総固定資本形成の伸びが鈍化したことにより押し下げられ、同0.3%の成長となった。また、7~9月期は、輸出の大幅な減少を主因に、同0.2%の成長となった。同国経済は18年10~12月期以降低調ながらもプラス成長で推移してきたが、19年10~12月期は、同-1.3%と5四半期ぶりのマイナス成長を記録した。
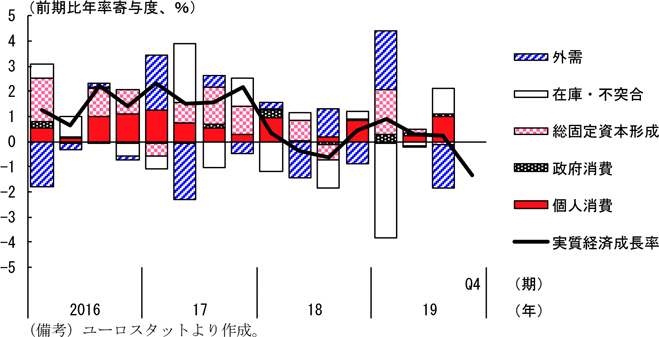
スペインの19年7~9月期の実質経済成長率は前期比年率1.6%、10~12月期は同2.1%となった(第2-3-6図)。7~9月期については、内需では個人消費と設備投資が大きく成長に寄与した。特に個人消費は、19年以降、最低賃金(月額)が前年比22.3%引き上げられた7ことにより個人所得が増加したことが背景にあると考えられる。一方、純輸出は、貿易摩擦問題やユーロ圏の景気減速による輸出の低下と好調な内需に起因する輸入増加により、マイナスに寄与している。10~12月期については、内需では前期に高い伸びを示した個人消費と総固定資本形成が反転して落ち込んだのに対し、外需では財輸出の持ち直しと輸入の減少により純輸出がプラスに寄与した。スペインは過去5年間にわたり、個人消費や設備投資等の内需に支えられ、ユーロ圏の平均を上回るペースで成長してきたが、その背景としては、欧州債務危機後に実施された経済改革8の効果により設備投資が活発化してきたことや、フランス同様にGDPに占める製造業や財輸出の比率が低く、比較的世界経済の減速の影響を受けにくい経済構造を有していることがあると考えられる。ただし、サービス業PMIは50を上回って推移する一方、製造業PMIは50を下回るなど(第2-3-7図)、世界経済の減速の影響も部分的に現れつつあると考えられる9。
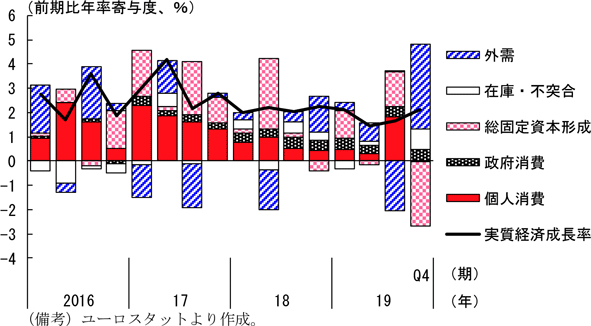
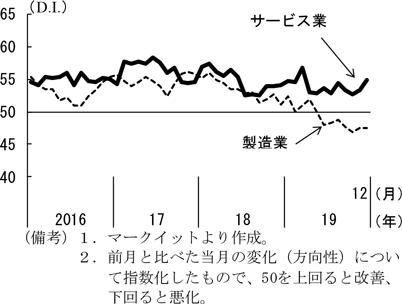
(雇用情勢の改善等により個人消費は緩やかながら増加)
ユーロ圏の個人消費は緩やかながら増加している(第2-3-8図)。この背景には、堅調な雇用情勢を反映し、家計の所得環境が引き続き改善していることがある(第2-3-9図)。今後についても、良好な雇用・所得環境や各国における拡張的な財政政策10により、個人消費がユーロ圏の緩やかな回復を支えることが期待される。一方で、企業のマインドは製造業を中心に低下傾向にあり、加えて、比較的堅調なサービス業も19年9月にやや低下した後、ほぼ横ばいで推移している(第2-3-10図)。こうした状況が続けば、やがては消費者マインドや消費の下押しにつながる可能性もある(第2-3-11図)。
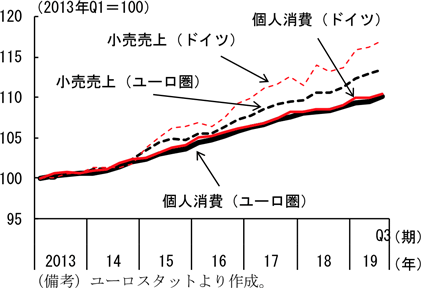
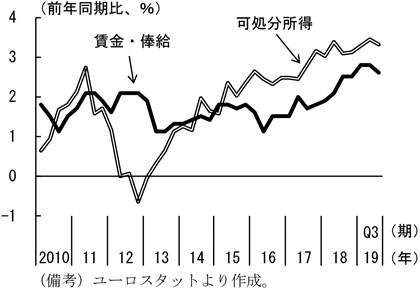
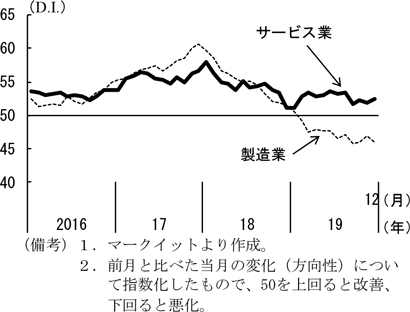
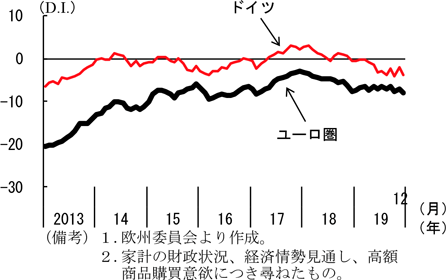
(外需の伸びの鈍化を背景に輸出は弱含み)
17年のユーロ圏経済の回復をけん引した輸出は、18年後半にかけて持ち直していたが、19年半ば以降は弱含んでいる。これは、主に、米中貿易摩擦や中国経済の減速に伴う外需の伸びの鈍化に加え、自動車に対する世界的な需要の低迷や英国のEU離脱に係る不確実性によるものと考えられる。なお、英国向け輸出については、英国の当初のEU離脱期日である19年3月末を控えた在庫積増しの反動減で、4月以降大幅に減少したが、その後離脱期日が10月末へ一旦延期されたことを受け、再度在庫を積み増す動きが幾分生じたことなどもあり、7月以降やや持ち直す動きがみられた(第2-3-12図)。
また、先行きについて輸出受注に対する企業の景況感(製造業PMI)をみると、17年11月に史上最高値を記録した後、急速に低下し、18年10月には約5年半ぶりに中立水準である50を割り込んだ。その後も依然50を下回る水準で推移していることから(第2-3-13図)、輸出は今後も低調に推移する可能性がある。
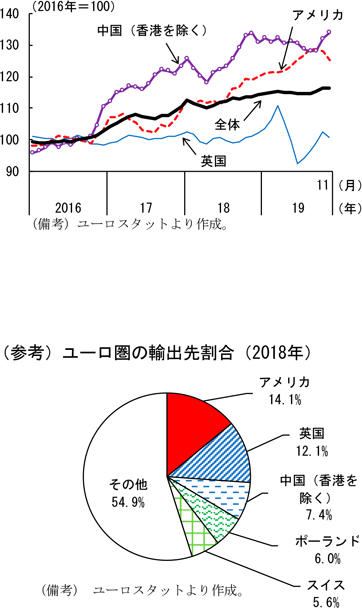
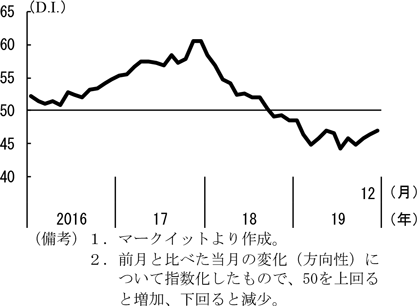
(外需の鈍化により鉱工業生産は弱い動き)
ユーロ圏の鉱工業生産は、19年半ば以降弱い動きが続いている(第2-3-14図)。この背景には、ドイツの主力産業である自動車分野の減速が、グローバル・バリュー・チェーンを通じてユーロ圏の製造業全体に波及していることがあると考えられる。製造業PMI新規受注指数も、域内外の経済の減速を受け、18年10月に中立水準である50を割り込んだ後は1年以上にわたり50以下の水準で推移していることから、当面鉱工業生産は弱い動きが続くと見込まれる。一方、サービス業については、PMI新規受注指数は50を上回ってはいるものの、9月の指数は51.6と前月の53.5から急落して以降は同程度の水準で推移しており、製造業の不振が徐々にサービス業にも波及しつつある可能性がある11(前掲第2-3-10図)。
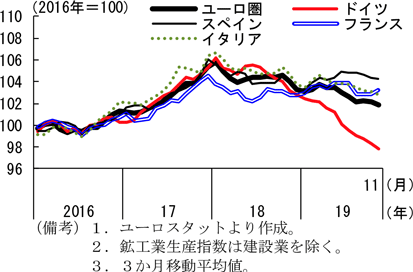
(機械設備投資はおおむね横ばい)
ユーロ圏の機械設備投資は、緩和的な金融政策の継続にもかかわらず、世界的な製造業の不振が影響して17年10~12月期をピークに減速傾向にある。19年1~3月期、4~6月期はスペインやイタリアを中心に増加したものの、7~9月期は主にドイツの低下によりおおむね横ばいとなっている(第2-3-15図)。
また、ユーロ圏の設備稼働率をみても、18年半ば以降低下傾向にあることから(第2-3-16図)、機械設備投資は引き続き低調に推移することが見込まれる。加えて、米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題等、ヨーロッパ内外の政治的・政策的不確実性の動向によっては、今後も、企業は設備投資を更に抑制する可能性がある。
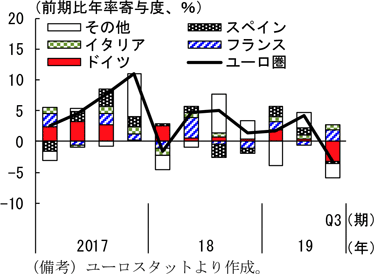
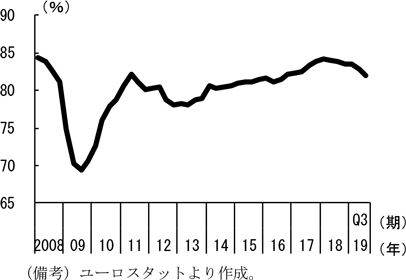
一方、建設投資(非住宅及び住宅)12については、緩和的な金融政策に支えられ19年1~3月期まで17四半期連続でプラスの伸びとなった。4~6月期には主にドイツとスペインの伸びがマイナスとなったことから、ユーロ圏全体では横ばいとなったが、7~9月期は、やや力強さを欠きながらもドイツが大きくプラス寄与となったことにより回復に転じた(第2-3-17図)。しかしながら、建設業景況観における今後の見通しは、中立水準を依然わずかに上回ってはいるものの、18年後半以降低下傾向にあり、19年9月以降一段の金融緩和が行われたにもかかわらずその傾向に変化がみられない(第2-3-18図)。経済の先行きの不透明感が建設投資にも影響を及ぼしつつある可能性があり、本格的な回復には時間を要するものとみられる。
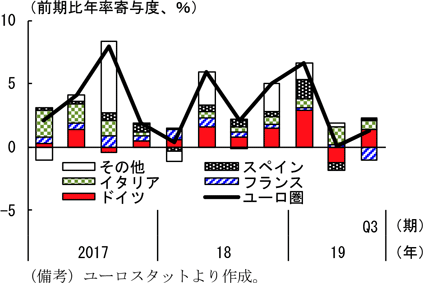
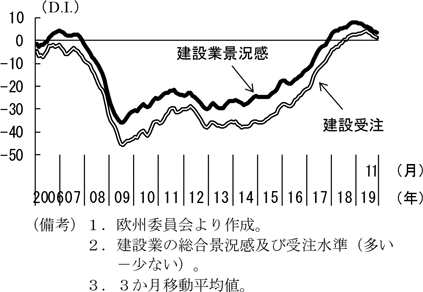
(失業率はおおむね低水準で横ばい)
ユーロ圏全体の失業率は低下傾向が続き、08年11月以来の低水準で横ばいとなっている(第2-3-19図(1))。しかしながら、企業の将来的な雇用見通しをみると、18年以降、改善と答える企業の割合が継続的に低下しており、19年9月には-4.8と中立水準であるゼロを割り込んだ後、更に低下を続けている(第2-3-19図(2))。
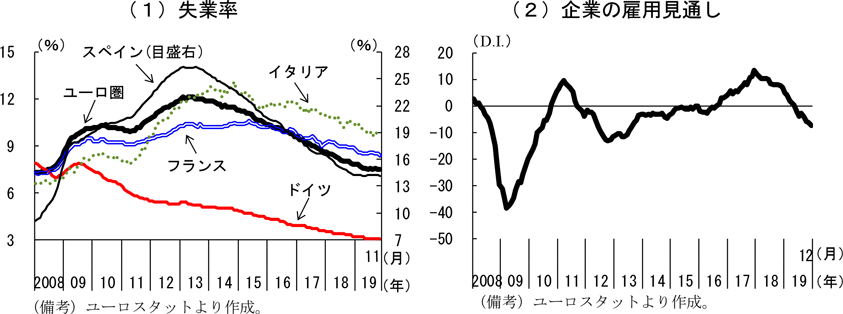
(物価はおおむね横ばい)
ユーロ圏の消費者物価上昇率(総合)は、18年末以降、エネルギーや食料価格の下落を反映して、ECBのインフレ参照値13である2%(前年比)を大きく下回り、1%前後で推移している(第2-3-20図)。コア物価上昇率も、原材料価格の高騰や賃金上昇圧力の高まりにもかかわらず、景気回復のペースが緩やかになっていることに伴う競争激化等により、川下への価格転嫁が進んでおらず、前年比1%台前半でおおむね横ばいで推移している。
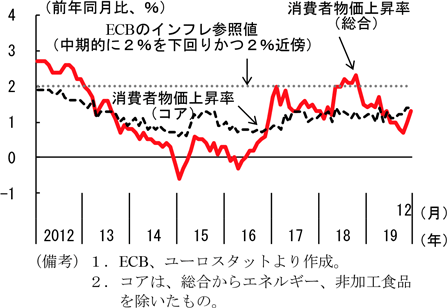
(財政政策の動向)
ユーロ圏の一般政府財政収支対GDP比は、赤字が10~14年平均の-3.9%から18年には-0.5%にまで縮小した。欧州委員会の秋季見通し(19年11月)によると、ユーロ圏の財政赤字は19年が-0.8%、20年が-0.9%と、景気減速に伴う歳入減及び拡張的な財政政策により若干拡大することが見込まれている(第2-3-21表)。
財政政策のスタンスを表すとされる構造的財政収支対GDP比をみても、ユーロ圏全体では赤字が18年-0.8%まで縮小したものの、19年-0.9%、20年-1.1%と緩やかに拡大することが見込まれている。
10月に欧州委員会に提出されたユーロ圏主要国の20年度予算をみると、各国とも財政スタンスは19年に比べおおむね拡張的となっている。フランスを始め、いずれも所得支援や減税等、低所得者層を中心とした家計向けの支援策が主な柱となっており、各国の財政拡張は20年度のユーロ圏の個人消費を一定程度下支えすることが見込まれる14。
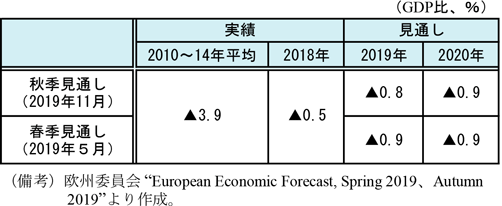
(財政ルールをめぐる動向)
EU加盟国は、「欧州セメスター」15において、財政の健全性確保やマクロ経済不均衡の是正等に向けた取組について3年間の財政計画である「安定化プログラム16」と、雇用と成長を促進するための構造改革計画である「国家改革プログラム」を欧州委員会に提出することとされており、欧州理事会(The European Council、EU首脳会議)によって承認された17勧告に基づいて予算案を作成することとされている。
また、EU加盟国は安定成長協定により、一般政府財政赤字が対GDP比3%を上回らず、公的債務残高の対GDP比が60%を下回ることが求められており、この基準を大きく逸脱する加盟国に対しては、是正措置として過剰財政赤字是正手続(EDP:Excessive Deficit Procedure)を適用して、財政規律遵守を求めている18(第2-3-22図、第2-3-23図)。イタリアについては、19年1~3月期の実質経済成長率はプラス成長となったものの(前掲第2-3-5図)、19年4月、イタリア政府は19年の実質経済成長率見通しを1.0%から0.1%に大幅に下方改定し、財政赤字対GDP比が2.2%になるとの見通しを示した19。これにより、イタリアへのEDP適用については、早ければ7月に開催される閣僚理事会で決定される可能性があったが、7月2日にイタリア政府が19年の財政赤字を76億ユーロ縮小させ、EUに対して約束した対GDP比2.04%の財政赤字水準を守ることができる見通しとなったことから、見送られた。
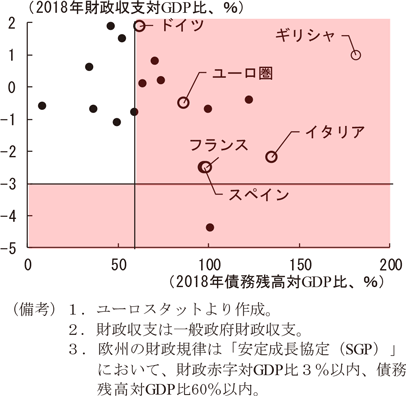
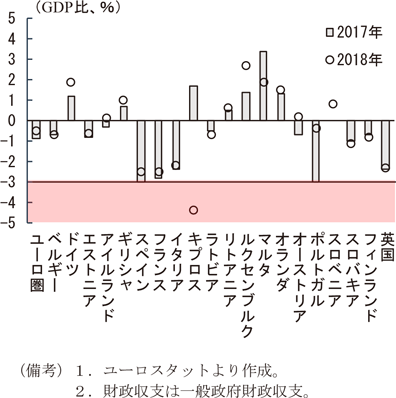
(イタリアの政局と財政)
イタリアでは、18年6月にEUに懐疑的な「五つ星運動」と「同盟」が連立し、第1次コンテ政権が発足したが、その後、財政運営や欧州委員会人事等をめぐり両党間に亀裂が生じていた。19年8月9日、副首相を務めていた「同盟」のサルビーニ党首が早期の総選挙を求めてコンテ首相に対する内閣不信任案を提出し、8月20日にコンテ首相は辞意を表明した。しかしながら、マッタレッラ大統領がコンテ首相に対して新たな連立政権を樹立するよう要請したことから、9月10日に「五つ星運動」とEUとの協調を重視する「民主党」の連立による第2次コンテ政権が成立した。コンテ首相は同政権発足に際し、EUとの融和的な関係の構築を表明したほか、経済・財務相に民主党所属で欧州議会の経済金融委員会を務めるグアルティエリ委員長を起用するなど、EUとの協調・対話の方針を示した。
10月16日、第2次コンテ政権は20年の財政赤字を19年と同じ水準(対GDP比2.2%)とする20年度予算案をEUに提出した。ただし、20年の構造的財政赤字については、EUがイタリアに対して19年(対GDP比1.2%)から0.6%改善させるよう要請していたにもかかわらず、0.2%増(対GDP比1.4%)とされていたことから、EUは同予算案に財政規律違反の可能性があるとして、10月22日にグアルティエリ経済・財務相に対し説明を要請する書簡を送付した。しかしながら、同経済・財務相は「20年の構造的財政赤字見通しは(規律を)大きく逸脱していない」と回答、その後、EUのモスコビシ欧州委員(経済・財政・税制担当)も「EUが予算案の変更を求めることはない」と述べた。同予算案は、12月16日にイタリア議会上院で、23日に下院で賛成多数で可決され、閣議了承された。
20年1月22日、「五つ星運動」のディマイオ党首は、同党内の亀裂により所属議員の離党が相次いでいる事態を受け、党首を辞任する意向を表明した。ただし、同氏は外務大臣には留まる意向を示しており、連立政権に影響が生じる可能性は低いとみられる。
イタリアの財政リスクプレミアムの動向をドイツ国債とイタリア国債の利回り格差でみると(第2-3-24図)、18年6月の連立政権発足後、欧州委員会との対立の深まりとともに拡大しており、併せてユーロ安も進行していることがみてとれる。その後、19年6月に欧州委員会がイタリアへのEDP適用が妥当と発表するまで、両国債の利回り格差は比較的高い水準で推移していたが、7月にイタリア政府が19年の財政赤字についてGDP比2.04%の水準を守る旨を発表した後、イタリアへのEDP適用は回避され、利回り格差は縮小に転じた。8月にサルビーニ副首相が解散総選挙を呼びかけたことで再び拡大したが、9月の新政権成立を受けて大きく低下した。その後、10月にEUに提出された20年度予算案がやや拡張的であったため、11月以降は若干上昇したものの、EUとの間で18年秋のような激しい対立は生じなかったことから総じて低水準で安定的に推移した。
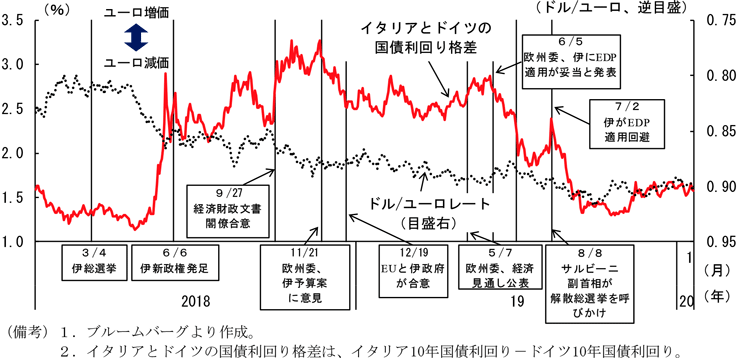
(2)英国経済の動向
(EU離脱に係る不確実性が続く中、景気は弱い回復)
EU離脱期日は、当初19年3月29日であったが、英国で離脱協定案が批准されなかったことから、19年4月12日、10月31日、20年1月31日と、3度にわたり延期が行われた。こうしたEU離脱をめぐる不確実性は、英国の経済活動に様々な影響を与えている。
19年10~12月期の実質経済成長率は、前期比年率0.1%となった(第2-3-25図)。19年4~6月期以降の実質経済成長率をみると、19年4~6月期は、当初の離脱期日である19年3月末に備えた企業の在庫積増し効果がはく落したことや、大手自動車メーカーが同期日後の4月に工場の一時閉鎖を計画・実施したことにより、マイナス成長となった。19年7~9月期は、こうした一時的要因からの反動もあり、プラス成長に転じた。19年10~12月期は、政府消費や輸出が下支えをしたものの、EU離脱をめぐる不透明感から、英国経済をけん引してきた個人消費の伸びの鈍化や、総固定資本形成の減少により成長率が押し下げられた。堅調であった雇用・所得環境にも変調がみられ、個人消費は、おおむね横ばいとなっている。民間設備投資は、不確実性による企業の投資手控えから、弱い動きとなっている。財輸出は、19年4~6月期に自動車工場の一時閉鎖により減少した後、7~9月期は新たに19年10月末とされた離脱期日に対する備えもあり増加した。また、非貨幣用金の輸出増加が、7~9月期以降の輸出の増加に寄与している。
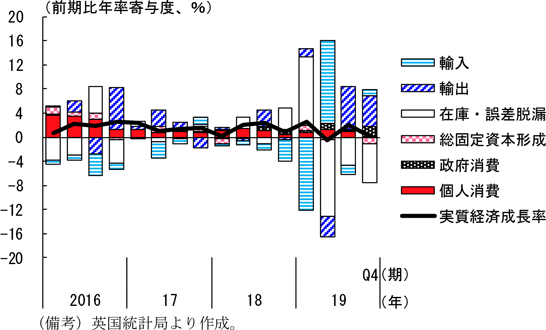
(消費はおおむね横ばい)
個人消費は、良好な雇用・所得環境に支えられ緩やかながら増加していたものの(前掲第2-3-25図)、19年半ば以降、実質賃金の伸びが鈍化していることを受けて(第2-3-26図)、おおむね横ばいで推移している。小売売上も当初のEU離脱期日である19年3月末を控えた駆込み需要20とその後の反動減の後、伸びが鈍化している(第2-3-27図)。
耐久財消費について新規乗用車登録台数をみると、18年9月からの国際調和排出ガス・燃費試験法21の導入により大きく落ち込んだ後、18年末以降も弱含んで推移している(第2-3-28図)。高額商品購買意欲をみても低い水準で推移しており、他のEU主要国と異なり、引き続き新規乗用車登録台数が弱含んでいる一要因であると考えられる(第2-3-29図)。
EU離脱をめぐる英国経済の先行き不透明感を背景に、19年の消費者信頼感(総合)指数は18年に比べ一段と低い水準のマイナス圏内で推移しており(第2-3-29図)、消費の先行きには留意が必要である。
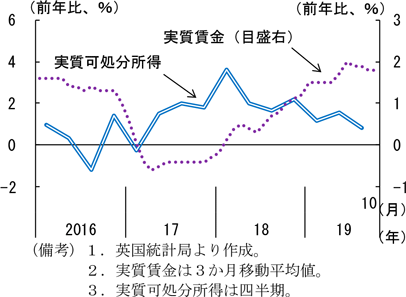
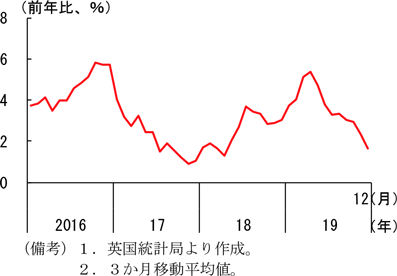
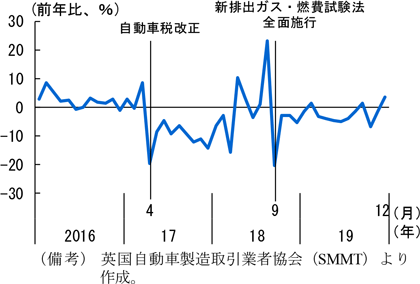
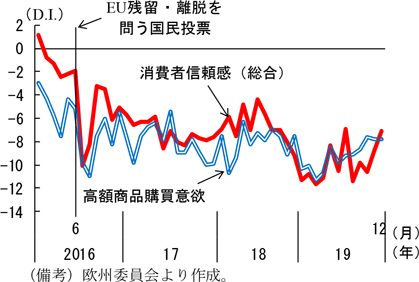
(財輸出は当初のEU離脱期日を控え減少した後、このところ増加)
財輸出は、自動車メーカーが当初の離脱期日後の19年4月に工場の一時閉鎖を計画・実施したことにより、19年4~6月は名目、実質ともに減少した。7~9月は、新たに19年10月末とされた離脱期日に対する備えもあり、EU諸国を中心に再度増加した。また、19年半ば以降は、非貨幣用金の輸出が増えていることも寄与し、このところ増加している(第2-3-30図、第2-3-31図)。
先行きについて、製造業PMIの新規輸出受注指数をみると、19年9~10月は新たに19年10月末とされた離脱期日に備えた企業の在庫積増しが一定程度は寄与したとみられるものの、基調としては中立水準とされる50を下回って推移している(第2-3-32図)。この背景には、EU離脱に係る不確実性が継続していることや、EU企業が英国企業をサプライチェーンから外す動きに加え、英国からの生産拠点の移転等があるとみられ、1月末にEUを離脱したものの、本格的な回復には時間がかかる可能性がある。
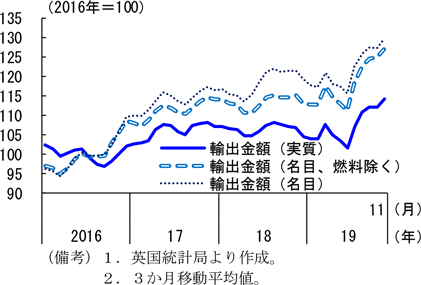
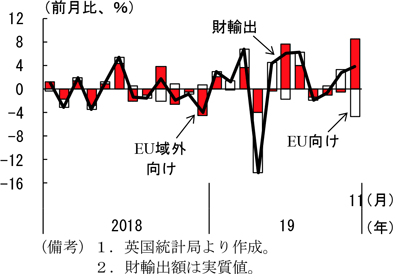
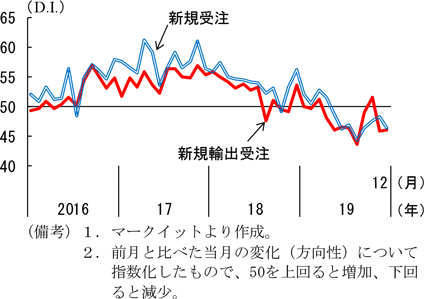
(生産は弱含んでいる)
英国の鉱工業生産は、大手自動車メーカーが当初の離脱期日後の19年4月に工場の一時閉鎖を計画・実施したことにより減少した後、新たに10月末とされた離脱期日に向けて医薬品を中心に一時的な増加がみられたものの、11月にはその反動に加え、4月と同様、大手自動車メーカーが離脱前後の混乱回避のために工場の一時閉鎖を実施したことから弱含みとなっている(第2-3-33図)。
製造業PMI在庫指数をみると、EU離脱に備えた企業の在庫積増し行動により、当初の離脱期日である19年3月までは歴史的水準まで上昇したものの、4月以降は離脱期日の延期に伴う在庫取り崩しにより低下している。また、離脱期日延長後の新たな離脱期日である19年10月末に備え、10月にはやや増加した後、11月には反動減となっている(第2-3-34図)。企業による景況感をみても、製造業PMIでは19年5月以降中立水準である50を割り込み、サービス業PMIでも19年10月末とされた離脱期日が近づいた19年9月以降、中立水準を割り込む動きもみられ、低調な推移になっている(第2-3-35図)。
先行きに関して、製造業PMIの新規受注指数、新規輸出受注指数をみると、新規受注指数は、19年9~11月にかけて改善の動きがみられたものの、19年5月以降中立水準を割り込む動きが続いている。新規輸出受注指数についても、19年9~10月は新たに19年10月末とされた離脱期日に備えた企業の在庫積増しによる改善の動きがみられたものの、離脱期日が20年1月末に再々延期された後の11月以降は、再度中立水準を割り込んでいる(前掲第2-3-32図)。
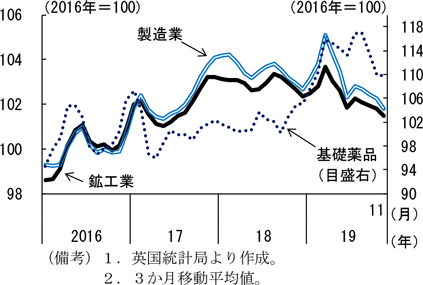
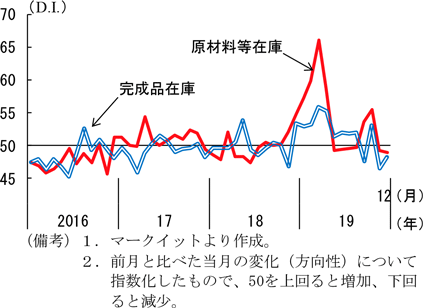
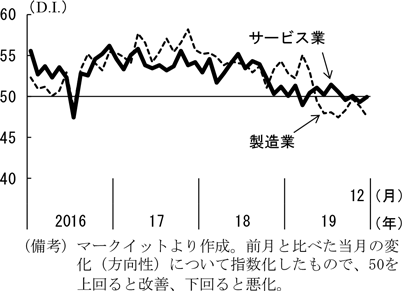
(民間設備投資は弱い動き)
民間設備投資は、18年を通じて減少を続けた後、19年1~3月期はプラスに転じたものの、19年7~9月期まで3四半期連続で伸びが低下し、19年10~12月期には再び減少するなど、弱い動きが続いている(第2-3-36図)。緩和的な金融環境や労働需給の引締り等、設備投資を促進する要素はそろっているものの、EU離脱に係る不確実性が設備投資を押し下げているとみられる。また、イングランド銀行(BOE:Bank of England)が企業を対象に実施した調査22によると、企業の設備投資意欲は18年4月以降低下傾向であったが、EU離脱期日の延長が決定された後の19年4月以降更に下落し、その後もマイナス圏内で推移している(第2-3-37図)。19年12月の英国議会下院総選挙において、保守党が総議席の単独過半数を獲得したことから、英国は20年1月末にEUを離脱し、移行期間に入った。しかし、後述するようにEU離脱関連法に20年末までの移行期間の延長禁止が盛り込まれたことから、離脱後の英国・EU間のFTA交渉は難航することが予想されている。そのため、引き続き英国・EU間の経済関係をめぐる不確実性は高止まりし、企業の設備投資意欲は低迷を続ける可能性がある。
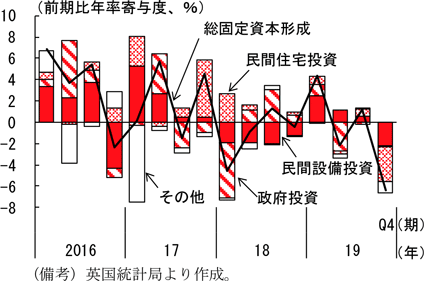
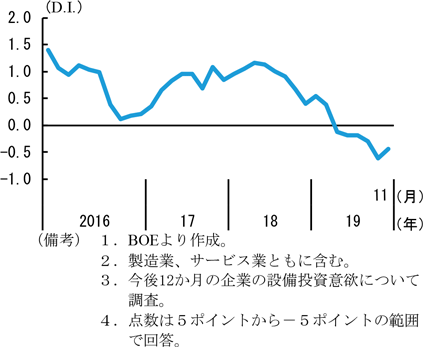
(雇用情勢はおおむね横ばい)
失業率(ILO基準)は18年2月に均衡失業率(4.25%)23を下回る4.2%にまで低下した後、熟練労働者不足を背景に改善を続け、74年以来の低水準となる3.8%前後でおおむね横ばいで推移している(第2-3-38図)。
このような労働需給の引締りに伴い、19年半ばまでの名目賃金(週平均、ボーナス除く)上昇率は堅調に伸びていた。また、19年半ばまでの実質賃金(週平均、ボーナス除く)上昇率も、消費者物価上昇率が2%近辺で安定していることを受けて(後掲第2-3-43図)、堅調に推移していた。しかし、19年半ば以降は、名目賃金上昇率、実質賃金上昇率ともに頭打ちとなっている(第2-3-39図)。
また、各種マインド調査をみると、製造業におけるPMIの雇用指数は、19年4月以降中立水準である50を割り込んで推移しており、英国の主力産業であるサービス業におけるPMI の雇用指数も、19年に入り中立水準を割り込む動きがしばしばみられることには留意が必要である(第2-3-40図)。19年12月に公表されたBOEの調査結果24をみても、企業の雇用意欲は18年後半以降低下傾向となり、19年5月以降は中立水準を割り込んで推移している(第2-3-41図)。実際、求人数は19年に入って低下傾向が続いており(第2-3-42図)、EU離脱をめぐる不確実性が雇用にも負の影響を与えつつあるとの指摘がされている。
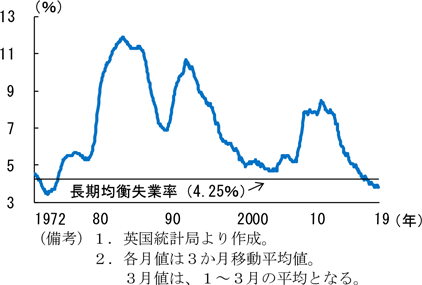
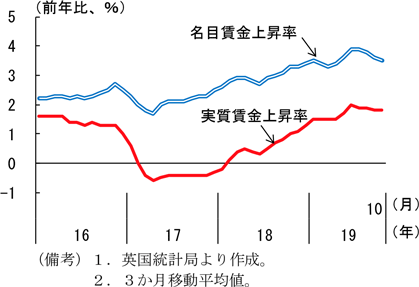
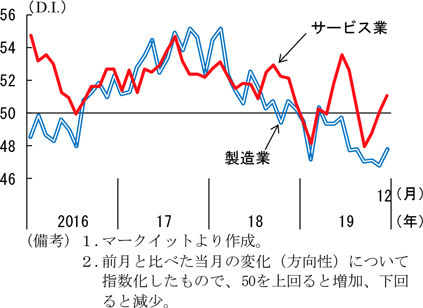
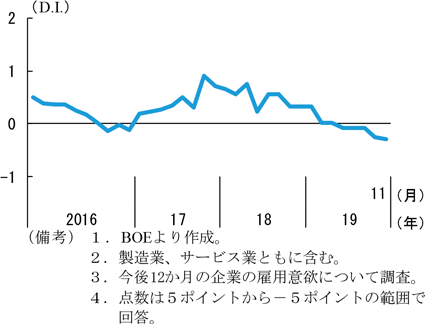
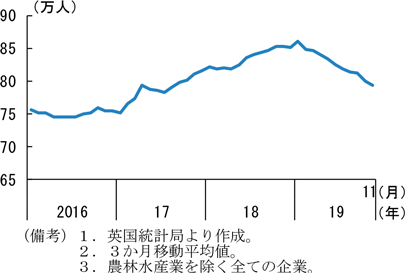
(コア消費者物価上昇率は安定的に推移)
コア消費者物価上昇率は18年に入って低下し、18年9月に前年比2%となった後は、2%を若干下回る水準で安定的に推移している(第2-3-43図)。財生産の低迷による投入財需給の緩和に加え、18年と比較した際の原油価格の下落及びポンド増価を受け、19年9月以降、川上で輸入物価や生産者投入価格が低下基調となっている(第2-3-44図)。一方、製造業、サービス業ともに、川下である製品価格の引上げの手控えをしていることがコア物価上昇率の伸びの鈍化に寄与していると考えられる(第2-3-45図)。消費者物価上昇率(総合)は、19年1月にBOEの物価目標である前年比2%を下回った後、2%近辺で安定的に推移していたが、19年8月以降、原油価格やエネルギー小売価格の低下を受けて、低下し、2%を幾分下回っている(第2-3-43図、第2-3-46図)。
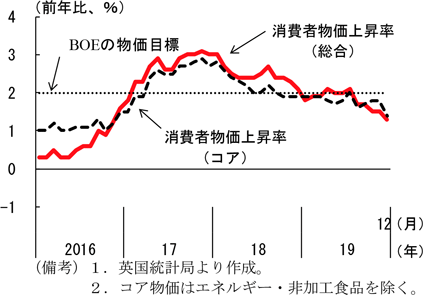
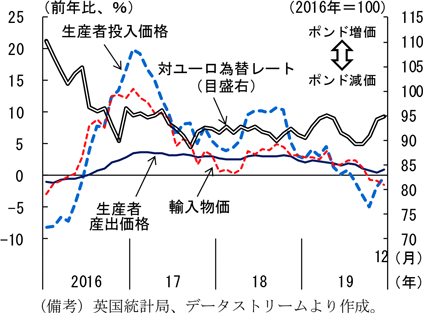
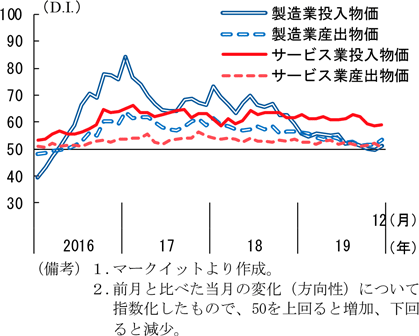
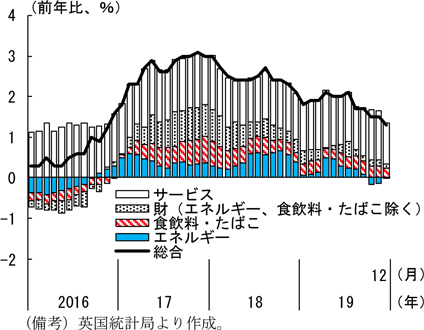
(金融政策は政策金利の据置きが続く25)
BOEは18年8月の金融政策委員会で政策金利を0.50%から0.75%に引き上げた後は、20年1月の金融政策委員会に至るまで、今後の経済の見通しによっては利上げ・利下げのどちらもあり得るとしながらも、据置きの判断を続けている26。また、09年3月に導入された量的緩和政策は、16年8月に資金枠が3,750億ポンドから4,350億ポンドに拡大された後は据え置かれ、BOEのバランスシートは18年以降おおむね横ばいに保たれている(第2-3-47図)。
19年11月の金融政策レポート27においては、同年10月に英国とEU間で新しい離脱協定案が合意されたことを踏まえ、新たにEUとのFTAが移行期間中に締結されることを前提とした見通しが示された。8月時点の見通しよりも19~21年の成長率見通しを全体的に引き下げ、潜在成長率程度までの回復は20年半ば頃とされた。ただし、回復のスピードは世界経済の回復や家計や企業における不確実性の解消度合いに大きく依存するとしており、金融政策による景気及び物価の下支えが必要となる可能性も示唆している。また、物価見通しは、エネルギー価格の低下を反映して20年には1%台前半まで低下するものの、その後需要の回復とともに上昇圧力が増加し、22年には物価目標である2%を若干上回るとした。
しかしながら、その後一連の経済指標が想定よりも弱いものとなったことを受け、EU離脱直前に公表された20年1月の金融政策レポートにおいては、19年11月時点の成長率見通しを更に引き下げるとともに、潜在成長率程度までに回復する時期を21年末頃とした。
なお、13年7月以降BOEの金融政策を指揮してきたカーニー総裁は20年3月半ばに退任し、元副総裁で現金融行為監督機構(FCA:Financial Conduct Authority)28長官のベイリー氏が新総裁に就任する予定となっている。20年1月末のEU離脱後も、英国・EU間の経済関係をめぐる不確実性は継続が見込まれることから、ベイリー新総裁による金融政策の舵取りが注目される。
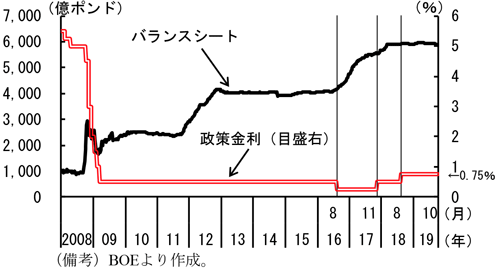
(英国のEU離脱をめぐる動向29)
英国は、16年6月23日のEU離脱を問う国民投票で離脱賛成票が残留票を上回ったことを受けて、17年3月29日、EUに離脱を通知し、その後の離脱交渉を経て、18年11月に「EU離脱協定案」と「将来関係に関する政治宣言案」が正式に合意された(第2-3-48表)。しかし、離脱協定案に含まれている北アイルランドのバックストップ30については、発動された場合、EU側の合意なしには解除することができない取り決めになっていることに加え、EU関税同盟への残留期日が明確にされていないことから、英国がEUのルールに縛られ続け主権を取り戻すことができなくなるおそれがあるとして、野党のみならず、与党・保守党の強硬離脱派からも批判を受けた。その結果、離脱協定案は英国議会下院において、3回にわたり否決された。その後、19年4月10日に開催された特別欧州理事会で、英国の離脱期日を10月31日まで再延期することが合意された。
7月24日、メイ首相は辞任し、ジョンソン氏が首相に就任した。英国政府はEU離脱期日に向けて、18年11月にメイ前政権とEUが合意した離脱協定案に代わる新提案を10月2日に公表し、EUとの協議を経て、10月17日の欧州理事会において英国とEU27か国は、新たに離脱協定案(第2-3-49表)及び将来関係に関する政治宣言に合意した。
新たな離脱協定案(以下、新離脱協定案)では、懸案のバックストップに係る項目を削除し、英領北アイルランドとEU加盟国のアイルランド共和国間の厳格な国境管理を避けるため、税関検査をアイルランド島内では行わず、北アイルランドと英国本土間で実施することとした。さらに、北アイルランドは引き続き英国の関税領域にとどまるものの、同地域に輸入される製品に対してはEUの関税法典に基づくルールが適用されるとした。また、新たな政治宣言では、英国とEUがともにFTA締結を目指すことが明記された。
英国政府は当初、10月31日の離脱期日に間に合わせるため31、10月19日に英国議会下院で新離脱協定案の批准を得ることを目指していたが、同批准を求める政府動議に対して、「合意なき離脱」の完全回避を主張する超党派議員が、EU離脱関連法32成立まで承認を見送るとする修正動議33を提出し、可決された。同動議の可決を受けて、ジョンソン首相は同日、トゥスクEU大統領(当時)に対し、EU離脱期日を20年1月31日に延期することを求めるとした書簡を送付した34。
10月29日、英国とEU27か国は最長20年1月31日までの離脱期日延期で合意し、これを受けて同日、英国議会下院は、ジョンソン首相が提出した12月12日に総選挙を実施する特例法案を可決した。下院は11月6日に解散され、12月12日の総選挙において、保守党は単独で総議席の過半数を獲得した。12月19日、ジョンソン首相は20年末までの移行期間の延長禁止を盛り込んだEU離脱関連法案を英国議会下院に提出し、20年1月9日に可決、1月23日にEU離脱関連法が成立した。さらにEU側では、1月29日の欧州議会において離脱協定案を承認、1月30日のEU理事会において離脱協定締結を承認したことで、同日、批准手続きが完了し、1月31日23時(英国時間)に英国はEUを離脱し、移行期間に入った。これにより、英国のEU離脱そのものへの不確実性は解消された。ただし、20年末までの移行期間中にEUとのFTA締結に至らない場合、「合意なき離脱」と同じ状態に陥る可能性もあり、英国・EU間の経済関係をめぐる不確実性は継続している。
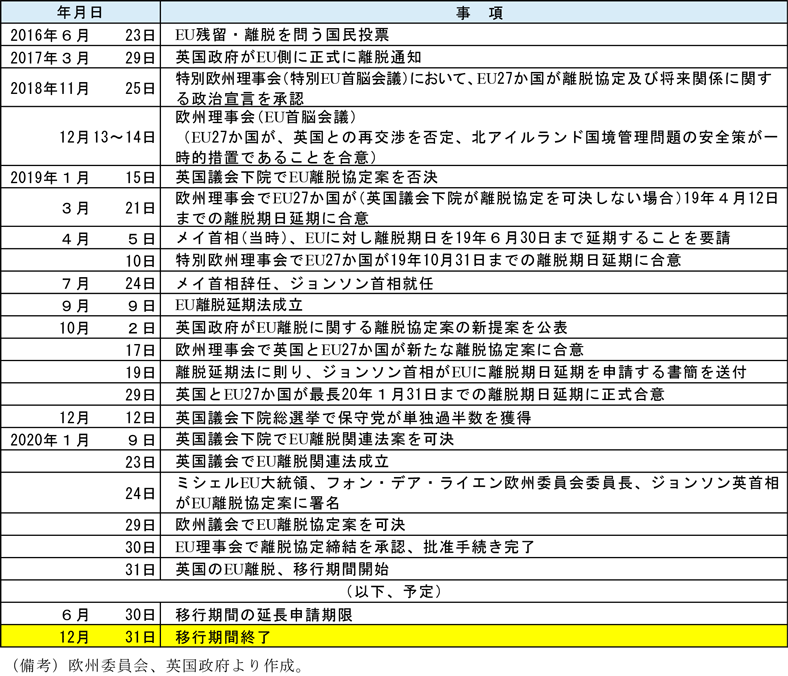
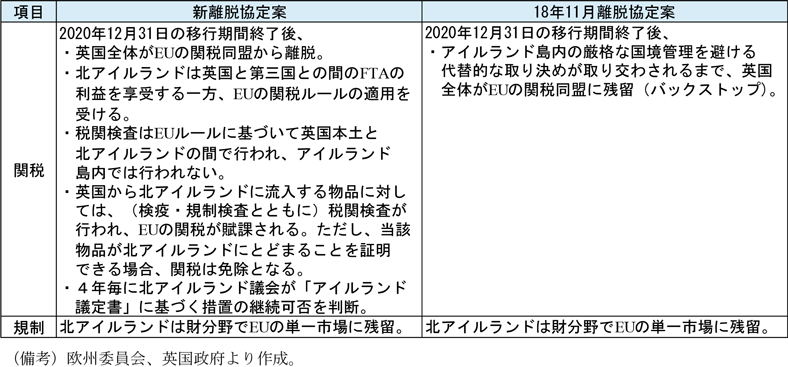
(通商協定を締結しないまま移行期間が終了した場合の英国及びユーロ圏経済への影響35)
OECD36では、英国がEUとFTAを締結しないまま移行期間を終えた場合に、英国、及びユーロ圏の実質GDPに与える影響を推計している。同推計において、FTA未締結で移行期間が終了すると、(1)関税障壁及び非関税障壁の高まりによる輸出の低下、(2)不確実性の上昇による投資の抑制、(3)移民の減少による長期的な労働力の減少や生産性の低下を通じて、英国における実質GDPが移行期間終了後最初の2年間で2.0~2.5%程度押し下げられるとしている(第2-3-50図)37。
他方で、ユーロ圏については、WTOの最恵国待遇(MFN)条件での貿易取引となることから、実質GDPは移行期間終了後最初の2年間で0.5%程度押し下げられ(第2-3-50図)、中長期的には、自動車や部品、金融サービスなどにおけるコスト増加により、英国との取引量が大幅に減少するとしている。国別では経済面で密接なつながりを持つアイルランドが最も影響を受け、アイルランドにおける実質GDPは移行期間終了後最初の2年間で1.5%程度押し下げられるとしている。
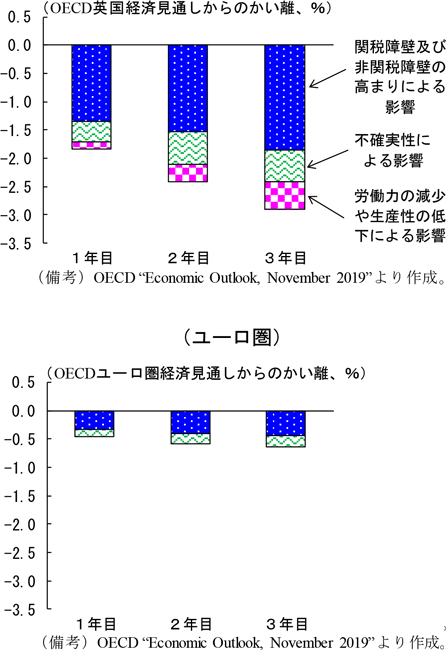
2.ユーロ圏及び英国経済の見通しと主なリスク要因
(1)ユーロ圏及び英国経済の見通し
ユーロ圏の景気は、世界的な貿易の減速や英国のEU離脱をめぐる不確実性等により、ドイツを中心とした製造業の不振が続く一方、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかに増加を続ける個人消費や緩和的な金融政策に支えられて、内需を中心に弱い回復が続くと見込まれる。また、英国においても、長期化するEU離脱問題に係る不確実性の影響から、企業設備投資の抑制が続き、景気は弱い回復が続くと見込まれる(第2-3-51図)。
20年と21年の経済成長率について、国際機関ではおおむねユーロ圏で1.1~1.3%、1.2~1.4%、英国で1.0~1.4%、1.2~1.5%をそれぞれ見込んでいる(第2-3-52表)。
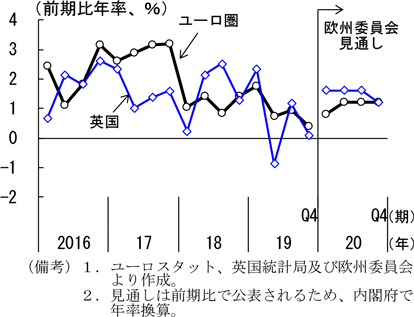
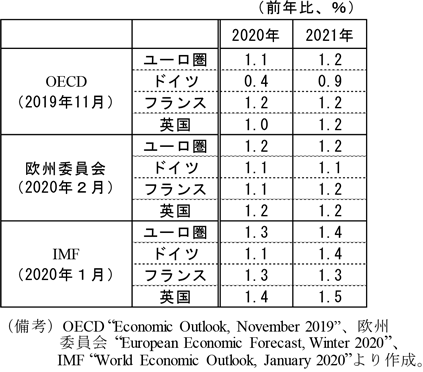
(2)ユーロ圏及び英国経済の主なリスク要因
(通商問題の動向)
ユーロ圏では外需の伸びの鈍化が輸出や生産への重しとなっており、米中貿易摩擦の更なる悪化等、外需を減速させるような通商問題の動向が景気への下振れリスクとなる。特に、EU・アメリカ間については、19年10月にWTOがEUのエアバス社への補助金給付を理由に、アメリカにEUへの対抗措置を承認する決定を行い、アメリカが追加関税措置を実施するなど、このところ緊張の高まりがみられる。アメリカは欧州諸国のデジタルサービス税導入に対抗した追加関税措置や、安全保障を理由とした自動車及び同部品への追加関税措置も検討しており、緊張の更なる増大の可能性に留意が必要である。
(英国のEU離脱)
12月12日の英国議会下院総選挙において、保守党が単独で総議席の過半数を獲得した結果、20年1月9日には、20年末までの移行期間の延長禁止を盛り込んだEU離脱関連法案が可決され、1月23日にEU離脱関連法が成立した。これにより、英国・EU双方による離脱協定の批准を経て、英国は20年1月末でEUを離脱し、移行期間に入った。これまで英国企業の設備投資意欲を低下させてきたEU離脱そのものへの不確実性は解消されたものの、離脱後、20年末までの移行期間内にEUとのFTA締結に至らない場合、「合意なき離脱」と同じ状態に陥る可能性があり、英国・EU間の経済関係をめぐる不確実性は継続している。英国・EU間の通商交渉をめぐる不確実性が英国の投資・生産活動に与える影響に引き続き注意するとともに、英国・EU間の経済関係の変化がもたらす長期的な影響にも留意が必要である。
(イタリアの財政問題)
9月に成立した第2次コンテ内閣は、EUとの協調・対話の方針を示しており、EUに提出した20年度予算案は12月にイタリア議会上院・下院で可決され、閣議了承された。ただし、イタリアでは成長率の低迷が続いているほか、コンテ首相はかねてよりEUの財政ルールは見直しが必要との立場であることから、財政政策の方向性をめぐるイタリア政府とEUの見解には引き続き留意が必要である。
(フランスにおける経済改革への反対運動)
19年12月、マクロン政権が進める年金制度改革案への大規模な反対運動が行われたほか、「黄色いベスト運動38」も継続されており、こうした動きがフランスの経済政策や経済に与える影響に留意が必要である。

