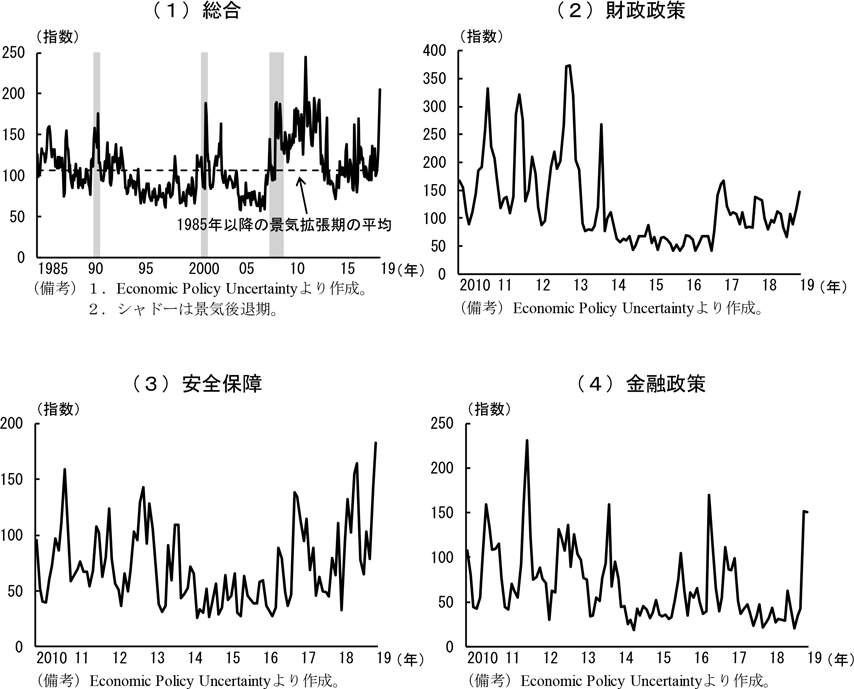第2章 主要地域の経済動向(第2節)
第2節 アメリカ経済
アメリカ経済は、世界金融危機以降、約9年半の長期にわたり景気回復が続いている。本節では、アメリカ経済が着実に回復している背景やその持続性について把握するため、アメリカ経済の最近の動向を振り返り、今後の見通しとリスク要因について整理する。
アメリカ経済を概観すると、個人消費は、堅調な雇用・所得環境の下で増加が続いている。住宅着工は、労働者不足や住宅ローン金利の上昇等を背景におおむね横ばいとなっている。企業部門をみると、生産及び設備投資は緩やかに増加しているが、企業マインドは18年末頃から低下しており、また、財輸出はドル高や米中間の追加関税措置の影響もあり弱い動きとなっている。労働市場では、雇用者数は増加しており、失業率も一段と低下して4%を下回る水準となっている。物価は、18年3月以降、前年比2%付近で安定している。
1.アメリカ経済の動向
18年の実質経済成長率は、18年1月から実施されている税制改革や歳出上限の引上げ1による拡張的な財政政策を背景として、堅調な個人消費や民間設備投資等に支えられ、4~6月期は前期比年率4.2%増、7~9月期は同3.4%増と高い伸びとなった(第2-2-1図)。アメリカ議会予算局(CBO)によると、18年の潜在成長率は1.9%と推計2されていることから、18年の成長率は潜在成長率を大きく上回る結果となることが予想される。
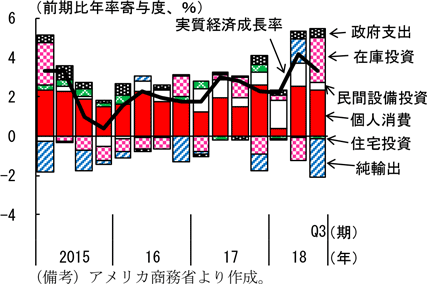
アメリカ経済の景気回復の長さを確認すると、世界金融危機以降、9年半を超える長期にわたり回復が続いている。今回の景気拡張局面は、09年6月を景気の谷として、19年2月で116か月間となり、過去2番目の長さに達しているとみられる3(第2-2-2表)。
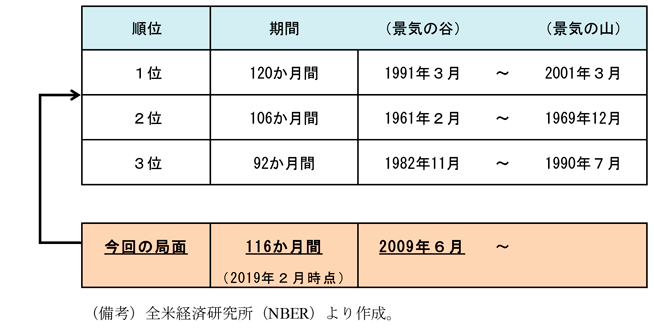
(1)個人消費
(個人消費は増加)
18年の実質個人消費支出は、17年後半におけるハリケーン4の復興需要や好調な年末商戦の反動により、18年1月及び2月は一時的に減少したものの、その後は18年1月から実施されている個人所得税率の引下げもあって実質可処分所得が増加していることを背景として、増加が続いている(第2-2-3図、第2-2-4図)。
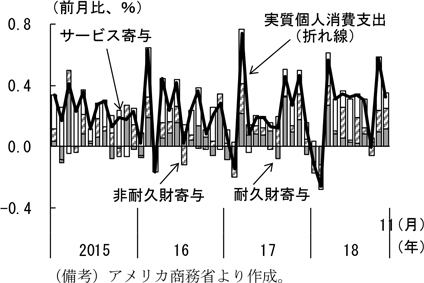
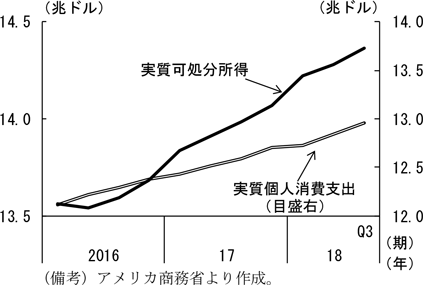
先行指標である消費者マインドについてみると、消費者信頼感指数は、堅調な雇用・所得環境を背景として高水準で推移しており、今後も個人消費が堅調に推移することが示唆される。ただし、直近である19年1月には、政府機関の一部閉鎖の影響等で低下した(第2-2-5図)。
個人貯蓄率をみると、2000年以降の平均値近傍の水準にあるものの、18年は低下傾向で推移している(第2-2-6図)。クレジットカードの延滞率は、2000年以降の平均値と比較すると低い水準にあるが、18年1~3月期にかけて緩やかに上昇し、その後横ばいで推移している(第2-2-7図)。
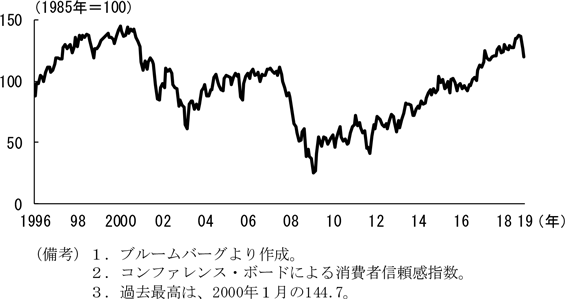

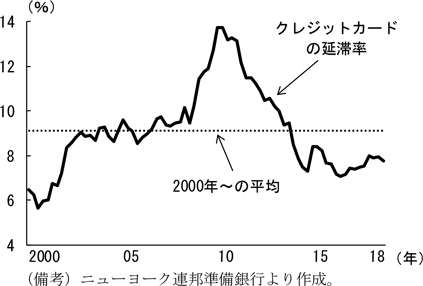
(自動車販売台数はおおむね横ばいで推移)
アメリカ国内の自動車(新車)販売台数は、良好な雇用・所得環境にもかかわらず、17年にみられたハリケーンの復興需要からの反動減や長期金利の上昇を背景とした自動車ローン金利の上昇も押下げ要因となり、18年半ばまでは弱めの動きとなった。一方、18年後半はハリケーンの復興需要等により上振れし、18年通年でみると、約1,700万台と17年からおおむね横ばいとなった(第2-2-8図、第2-2-9図)。車種別にみると、消費者の選好を反映して5、SUV(Sport Utility Vehicle)を含む小型トラックの販売台数が増加傾向にある一方、乗用車の販売台数は低下傾向にある6(第2-2-10図)。
なお、自動車ローンに対する金融機関の貸出態度は、17年以降緩和傾向にあり、信用力の低い層への貸出が増加している可能性も考えられる(第2-2-11図)。自動車ローンの延滞率が上昇傾向にある(第2-2-12図)ことと合わせ、留意が必要と考えられる。
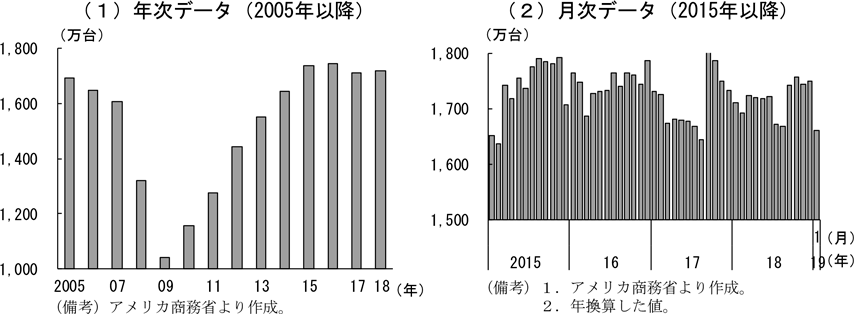
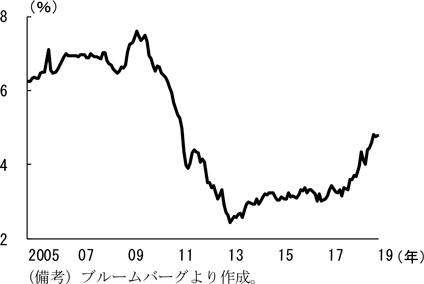
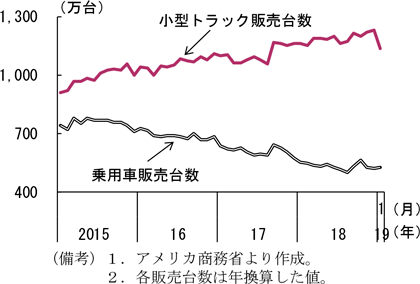
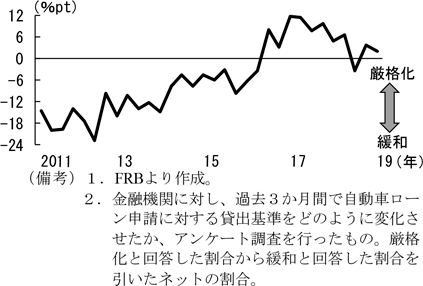
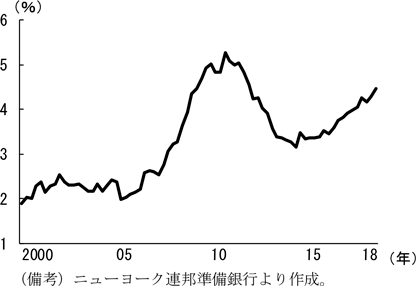
(住宅着工はおおむね横ばい、住宅価格は緩やかに上昇)
住宅着工件数は、良好な雇用・所得環境を背景に17年後半以降緩やかに増加していたが、労働者不足や住宅ローン金利の上昇等を背景に、18年半ば以降、年換算で120万件程度の水準でおおむね横ばいとなっている(第2-2-13図)。
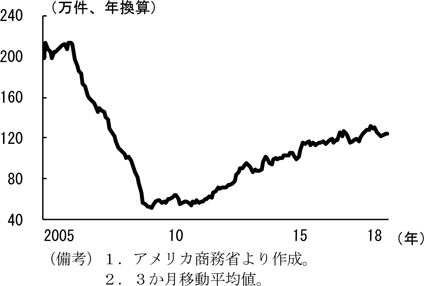
建設労働者の不足状況を全米住宅建設業者協会(NAHB)の調査で確認すると、18年は「深刻な不足」及び「ある程度不足」と回答した割合が70%弱まで上昇した(第2-2-14図)。また、NAHBが過去1年間における労働者不足が業務に与えた影響について質問した調査をみると、約80%の回答者が労働コストの増大と住宅の値上げを挙げ、約70%の回答者が完工の遅れを挙げている(第2-2-15表)。労働コストの増大を建設労働者の時間当たり賃金の伸びでみると、建設労働者の時間当たり賃金の伸びは全労働者と比較して高い傾向にあるが、18年はこの傾向が顕著であった(第2-2-16図)。建設労働者の不足が供給制約となるとともに、労働コストの増大から住宅価格が上昇したことが推察される。なお、アメリカ主要都市圏における中古一戸建て住宅の販売価格を示すケース・シラー住宅価格指数をみると、18年2月に世界金融危機前の水準を超えて2000年の統計開始以来の最高水準となり、その後も前年同月比で4%後半~6%程度の緩やかな上昇を続けている(第2-2-17図)。
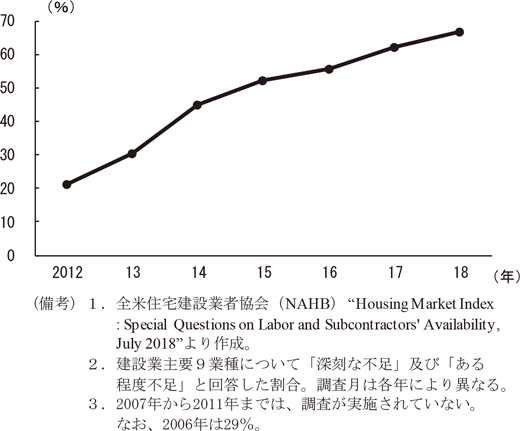
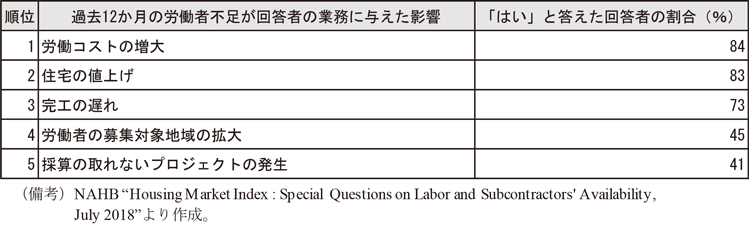
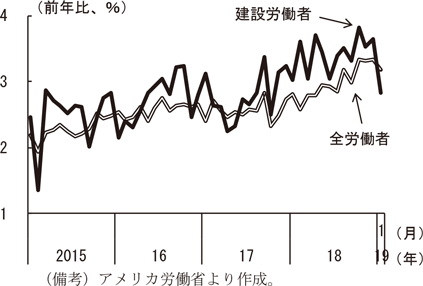
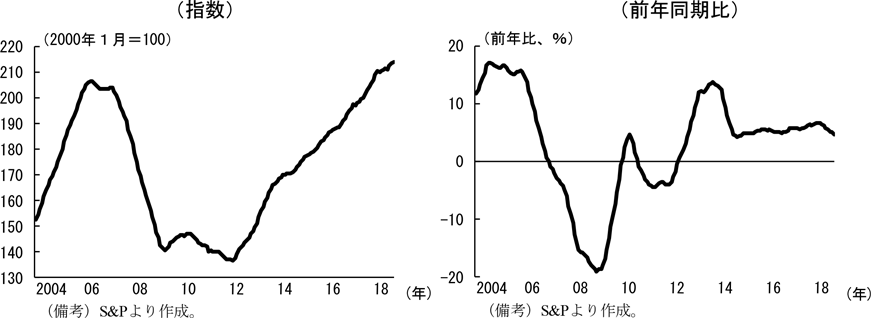
また、住宅価格の上昇に加えて、最近の住宅ローン金利の上昇が家計の負担増となり、住宅需要の抑制要因となっていると考えられる。17年後半には3%台であった住宅ローン金利は、FRBによる政策金利の引上げを背景に上昇を続け、18年後半は4.5%~5%の間で推移している(第2-2-18図)。住宅取得の容易さを、家計所得とローンを利用して住宅を購入するために必要な所得の比で表す住宅取得能力指数7でみると、「家計所得」と「最低必要収入」が一致する100(100を超えると住宅取得が容易となる)を依然上回っているものの、18年以降は低下傾向にある(第2-2-19図)。こうした状況を背景に、新築住宅の在庫・販売比率についてはこのところ在庫が緩やかに積み上がる傾向がみられる(第2-2-20図)。
住宅着工の先行きをみるため、先行指標である住宅許可件数及びNAHB住宅市場指数8を確認する。住宅許可件数は、18年7月までは130万件程度かそれ以上で推移していたものの、その後低下し、それ以後のほとんどの月では120万件台の水準で推移している。住宅建設業者による住宅市場の景況感を表すNAHB指数は、18年以降低下しており(第2-2-21図)、住宅着工の伸びは当面期待できない可能性がある。
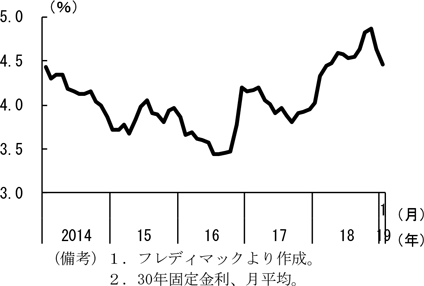
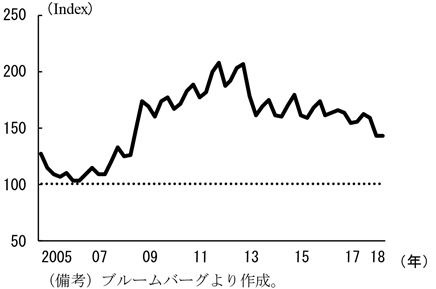
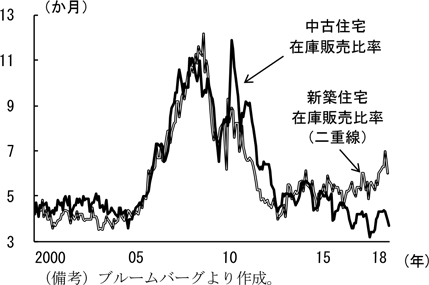
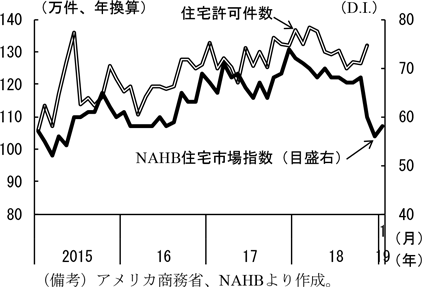
(2)改善が続く雇用情勢
雇用情勢は改善が続いている。非農業部門雇用者数の前月差をみると、18年は平均で22.3万人となっており、17年の月平均17.9万人を上回るペースで堅調に増加している。雇用者数の前月差を部門別にみると、財生産部門では17年の月平均が4.2万人であったものが、18年は月平均5.4万人、サービス部門では17年の月平均が13.8万人であったものが、18年は月平均16.9万人と財生産・サービスのいずれの部門においても堅調に増加している(第2-2-22図)。業種別にみると、全雇用者数に占める割合の高い業種を中心に増加しており、財生産部門では建設業や製造業が、サービス部門では専門サービス(コンピュータシステム設計や人材派遣サービス等)や教育・医療が増加している(第2-2-23図、第2-2-24図、第2-2-25図)。
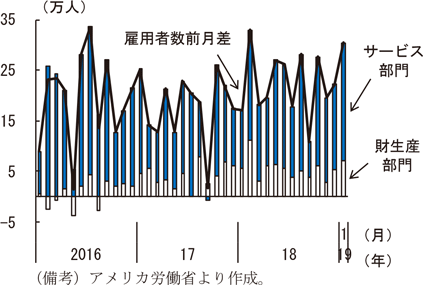
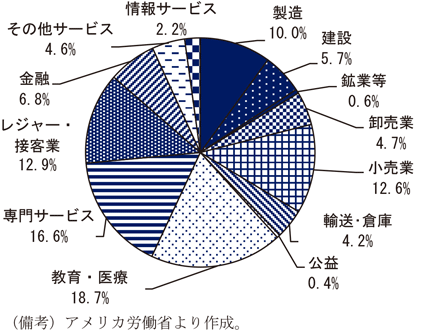
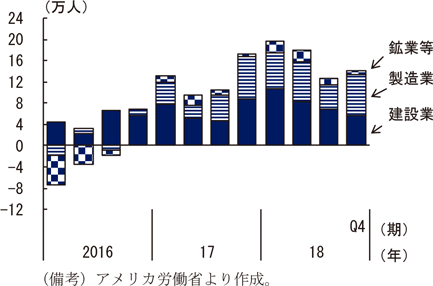
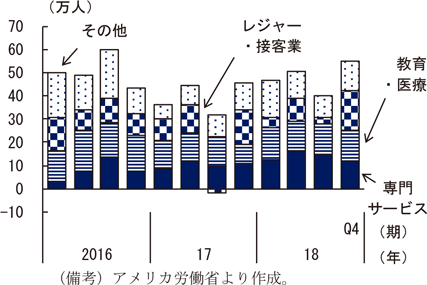
失業率(U39)は、09年10月の10.0%を最近のピークに徐々に低下し、18年9月及び11月には3.7%と1969年12月の3.5%以来の低水準を記録するなど、FOMC参加者が予測する長期失業率の4.4%(中央値)を下回る水準で推移している。また、広義の失業率(U610)をみると、18年8月が7.4%と01年4月以来の水準まで低下するなど、18年4月以降は世界金融危機前の最低水準(06年12月の7.9%)を下回る傾向にあった(第2-2-26図)。
時間当たり賃金の伸びは、世界金融危機後の最低水準である12年10月の前年比1.5%から18年終わりには同3%強まで高まった(第2-2-27図)。企業の雇用マインド11が高水準で推移している(第2-2-28図)ほか、アメリカ地区連銀経済報告(ベージュブック)においても需給のひっ迫により人員確保が困難となっていることが指摘されていることから12、今後は賃金の伸びが更に高まっていくことが期待される。
一方、時間当たり賃金の伸びは高まっているものの、過去の景気回復局面でみられた4%程度までは到達していない。賃金・俸給に福利厚生費を加えた雇用コスト指数を確認しても、近年は上昇傾向にあるが、過去の上昇率と比較すると高い伸びとはいえない(第2-2-29図)。賃金の伸びの鍵となる時間当たり労働生産性上昇率をみると、18年入り後も世界金融危機前の景気回復局面ほどの高まりを見せていない(第2-2-30図)。アメリカでは、こうした労働生産性の伸び悩みのほか、労働組合組織率や団体交渉適用率の低下がもたらす労働者の賃金交渉力の低下13が、過去と比較して賃金の伸びが高まりにくい要因となっている可能性がある。
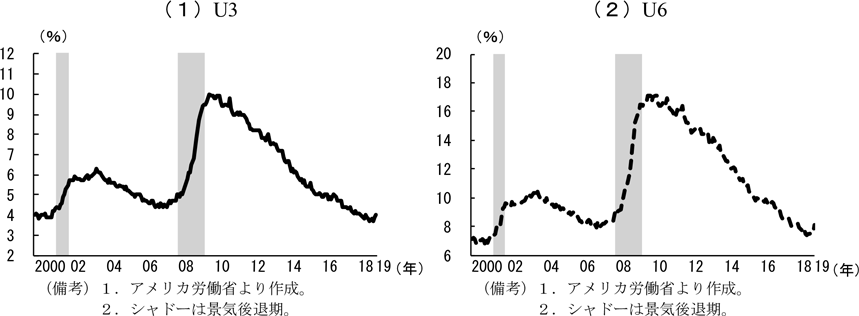
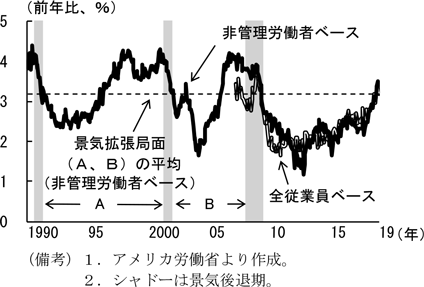
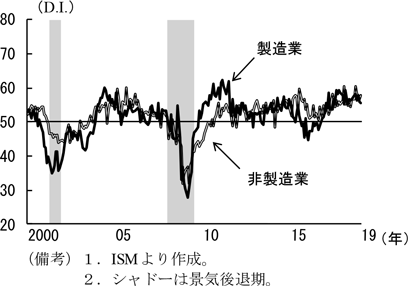
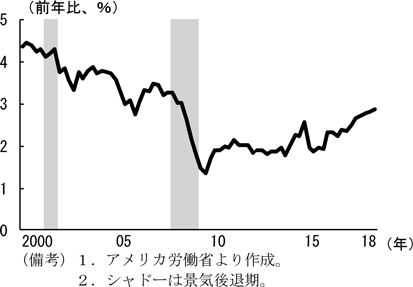
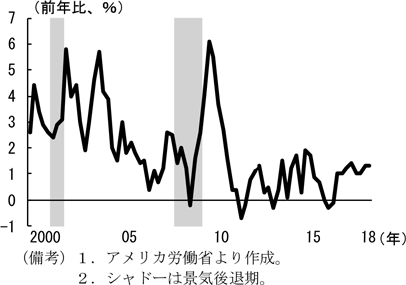
(3)企業部門の動き(生産・設備投資・輸出)
(鉱工業生産は緩やかに増加)
18年の鉱工業生産は17年に引き続き、鉱業関連の安定した生産に支えられ、緩やかな増加基調が続いている。製造業については過去最高である07年12月の水準にはまだ戻っていないものの、総合は過去最高であった14年11月の水準を18年4月に超え、その後も安定して増加を続けている(第2-2-31図)。
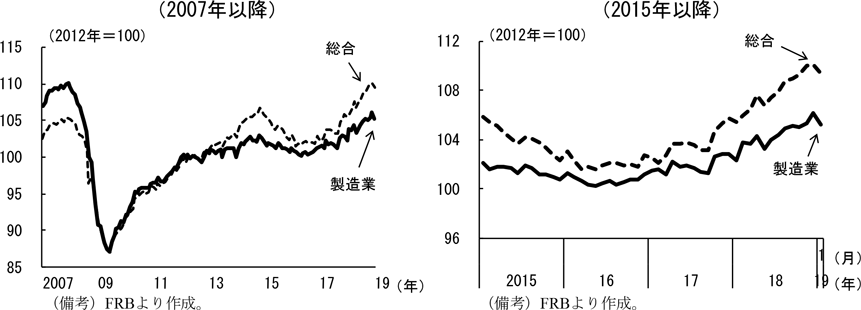
総合の押上げ要因である鉱業生産の内訳をみると、原油価格の上昇を受けたシェールオイルやシェールガスの増産が確認でき、シェールオイル及びシェールガスがそれぞれ原油生産量及び天然ガス生産量に占める割合は年々増加している(第2-2-32図、第2-2-33図、第2-2-34図)。ただし、18年後半には原油価格の下落もみられたことから、今後も安定して鉱業生産の増加が続くかどうかについては注意が必要である。
設備稼働率は、生産の増加に伴い、17年以降、緩やかな上昇傾向が続いている(第2-2-35図)。ただし、総合・製造業共に世界金融危機前の水準までにはいまだ戻っていない。
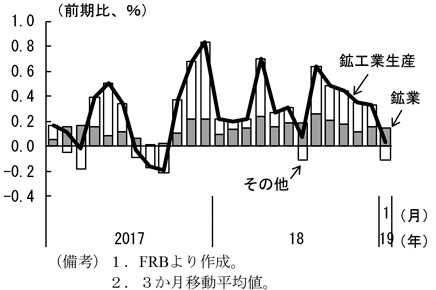
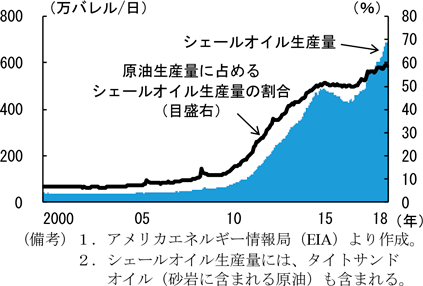
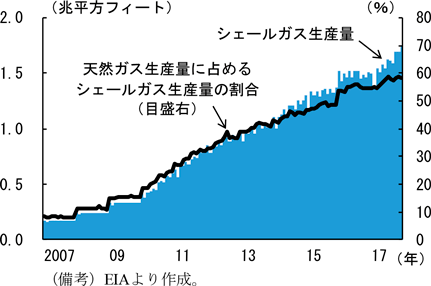
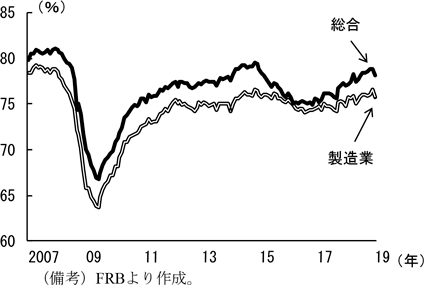
(設備投資は緩やかに増加)
民間設備投資は、前年比でみれば18年を通じて6~7%台と緩やかに増加している。前期比でみると、18年前半は非常に高い伸びであったが、7~9月期に4四半期ぶりに構築物投資がマイナス寄与となり、機械・機器投資の増加寄与もわずかになるなど、後半は伸びが鈍化している(第2-2-36図)。
民間設備投資の先行きをみるため、機械・機器投資の先行指標であるコア資本財受注(民間航空機を除いた非国防資本財)をみると、18年後半に前月比でマイナスに転じ、弱めの動きがみられる(第2-2-37図)。鉱業関連の設備投資も、18年4~6月期まで民間設備投資全体の増加に寄与していたが、7~9月期には7四半期ぶりにマイナス寄与へ転じた(第2-2-38図)。油井採掘リグ稼働数は18年5月以降横ばいで推移しているが、鉱業関連の設備投資の採算性を判断するのに利用される原油価格(WTI)は、18年12月に約50ドルまで低下している(第2-2-39図)。また、地区連邦準備銀行による製造業の6か月後の投資動向に関する調査をみると、「増加」と回答する企業の割合が引き続き「減少」と回答する企業を上回っているものの、18年の終わりにその幅は縮小傾向となっている(第2-2-40図)。
民間設備投資と相関の高い企業収益の動向をみると、18年1月より実施された連邦法人税率の引下げ等を背景に高い伸びとなっている(第2-2-41図)。
上記を総合すると、民間設備投資は当面は減速しつつも緩やかな増加基調を維持していくと見込まれる。ただし、米中貿易摩擦による不確実性が民間設備投資の見直しや延期をもたらす可能性、上昇傾向となっている金利、増加基調にある企業部門の債務(第2-2-42図)もあり、今後の民間設備投資が増加基調を維持できるかについては注視する必要がある。
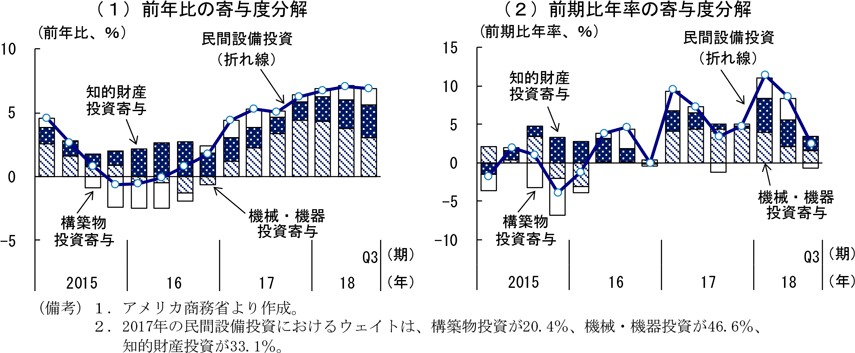
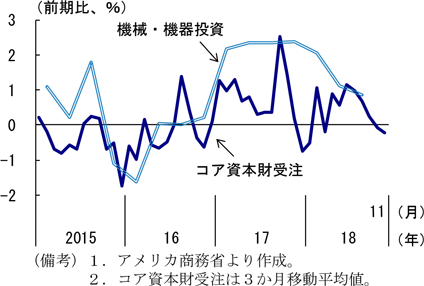
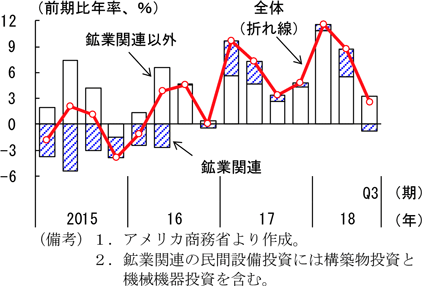
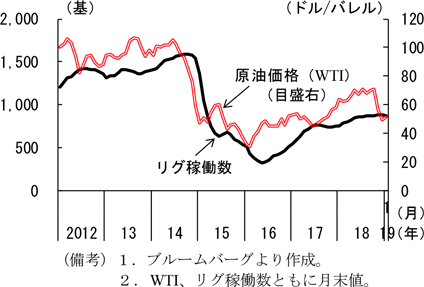
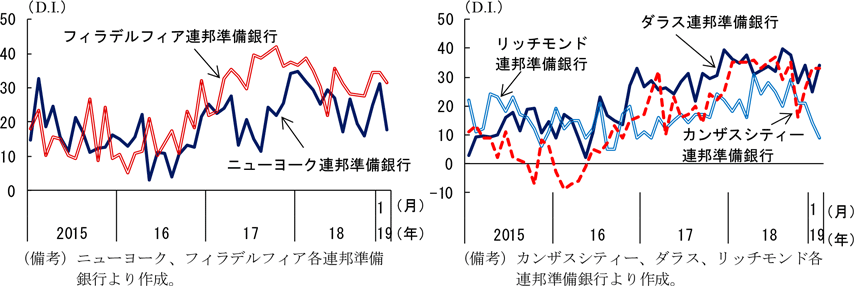
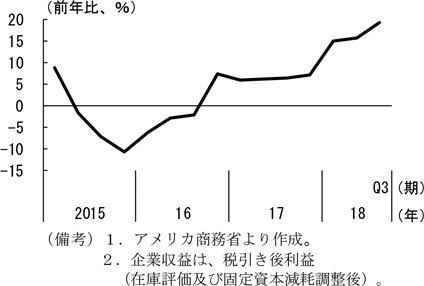
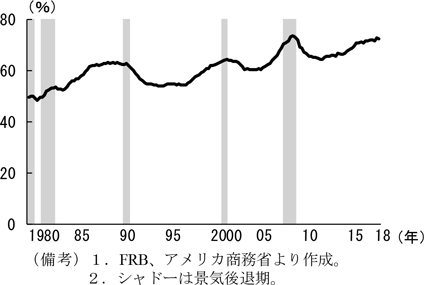
(企業マインドはこのところ低下)
企業による景況感をISM製造業景況指数14でみると、18年は8月の総合指数が61.3と04年5月の61.4以来の高水準を記録し、生産や新規受注も60付近で推移するなど、中立水準である50を大幅に上回って推移していた(第2-2-43図)。また、ISM非製造業景況指数も、事業活動や新規受注が好調であり、総合指数が18年半ばに60を連続して超えるなど、高水準を維持していた(第2-2-44図)。
一方、18年12月以降は、米中間の貿易摩擦や政府機関の一部閉鎖等を背景に企業の景況感は製造業・非製造業ともに50台半ばまで低下しており、こうした傾向が続いた場合、今後の民間設備投資の抑制要因となる可能性がある。
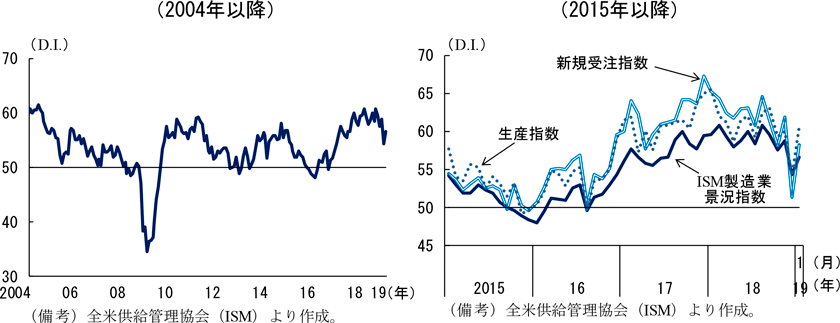
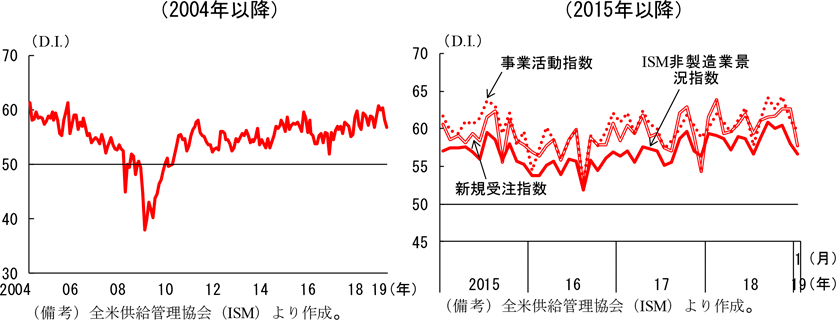
(財輸出は弱い動き)
先進国と新興国が共に回復する世界経済の同時回復により、17年末以降のアメリカの財輸出は緩やかに増加していたが、18年5月頃から続くドル高傾向を背景に、弱い動きとなっている(第2-2-45図、第2-2-46図)。
財輸出の動向を国別にみると、主要な輸出先国・地域の全てに対して伸びが鈍化傾向にあり、特に中国向けの輸出が減少を続けている(第2-2-47図)。中国向け輸出を財別にみると、中国がアメリカへの対抗措置として追加関税を賦課した大豆や自動車が大幅にマイナスに寄与するなど、18年後半の輸出動向には米中間の通商問題の影響が出始めており15、今後も楽観できない状況が続くと見込まれる。
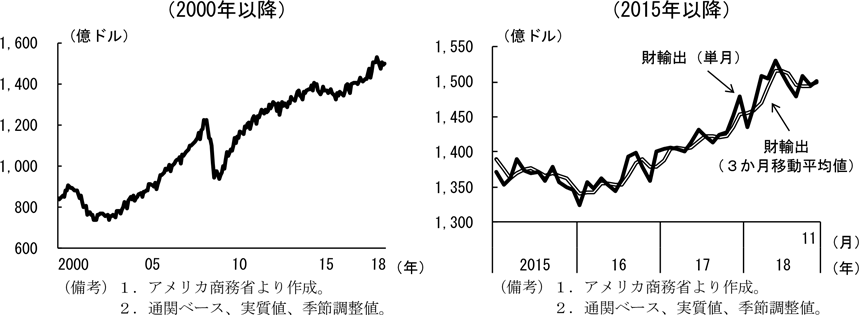
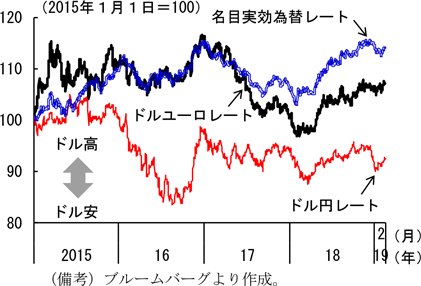
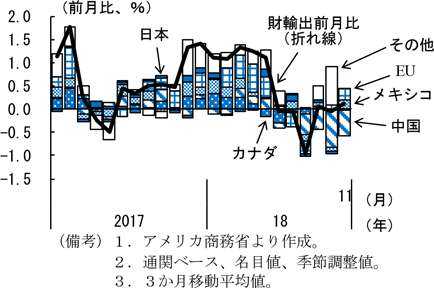
2.財政・金融政策の動向
(1)財政政策の動向
18年以降のアメリカの財政政策は、税制改革による減税や歳出上限の引上げといった政策により、拡張的なものとなっている。一方、潜在成長率を超える経済成長率を実現しているにもかかわらず、拡張的な財政スタンスを採ることは、財政赤字の拡大から将来の財政の持続可能性への懸念を引き起こし、長期金利の上昇をもたらす可能性もある。以下では、18年度(17年10月から18年9月まで16)の財政の状況及び19年度予算の動向について概観する。
18年度の連邦政府の財政収支は7,790億ドルの赤字となった。17年度から赤字幅が1,132億ドル拡大し、赤字幅は12年以来、6年ぶりの水準となった。財政赤字をGDP比でみても、18年度は3.9%と17年度の3.5%から悪化している(第2-2-48図)。
18年度の連邦政府の財政収支を歳入と歳出の両面からみると、歳入が3兆3,287億ドルと17年度の3兆3,149億ドルからわずかな増加にとどまる一方、歳出が4兆1,077億ドルと17年度の3兆9,807億ドルから増加している(第2-2-49表、第2-2-50図)。
歳入面では、18年1月から実施されている連邦法人税率の引下げ等により、18年度の法人税収が2,047億ドルと17年度の2,970億ドルから大幅に減少している(第2-2-51図)。一方、18年度の個人所得税収は18年1月から実施されている個人所得税の減税にもかかわらず、良好な雇用・所得環境を反映して1兆6,835億ドルと17年度の1兆5,871億ドルから増加している(第2-2-52図)。なお、18年度の関税収入をみると、18年3月から段階的に実施されている鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置や中国からの輸入品に対する追加関税措置を背景に413億ドルと17年度の346億ドルから2割程度増加している(第2-2-53図、コラム1-2を参照)。
歳出面では、国防費が18年度は6,647億ドルと17年度の6,313億ドルから増加した。また、18年度は人口高齢化を背景に社会保障費等の支出が引き続き増加傾向となっている。17年度と比較して最も増加幅が大きかったものは利払費であり、長期金利の上昇を背景として18年度は3,247億ドルと17年度の2,627億ドルから620億ドル増加した。CBOの見通し17では、将来へ向けて利払費が増加していくことが見込まれており、財政の持続可能性への懸念が更なる金利上昇を引き起こし、それが利払費の増加をもたらすという悪循環を生む可能性もある(第2-2-54図)。
18年10月から始まる19年度の予算18は、トランプ大統領がメキシコとの国境の壁建設費用を盛り込むことを主張していたことを背景に、共和党と民主党との間で予算案の合意に至らなかったことから、18年12月7日、12月21日をそれぞれ期限とするつなぎ予算によって手当てされた。その後も引き続き、トランプ大統領が国境の壁建設費用を含まない予算案には署名しない姿勢を示したことで12月21日までに上下両院で新たな予算案を可決できず、18年12月22日から19年1月25日までの35日間19、政府機関が一部閉鎖することとなった20。
18年12月22日から19年1月25日までの政府機関の一部閉鎖により、税関・国境警備局等の42万人以上の職員が給与未払いの状態で勤務、商務省等の38万人以上の職員が一時解雇されたほか、貿易統計等の経済統計の公表が延期された。CBOの見通し21によれば、35日間の政府機関の一部閉鎖により、18年10~12月期及び19年1~3月期の実質経済成長率は押し下げられ、19年4~6月期の実質経済成長率が歳出の反動増により一時的に押し上げられるものの、19年通年の実質GDPは0.02%押し下げられるとしている22(第2-2-55図)。
19年1月25日に2月15日までのつなぎ予算が成立した後、2月15日にトランプ大統領は国境の壁建設費用の一部を含む19年度予算案に署名し、再度の政府機関の一部閉鎖は回避されることとなった。一方、トランプ大統領は同日に非常事態宣言を行うことなどにより、国境の壁建設のための追加費用を捻出することを表明したことから、政府と議会の間の緊張感が高まっている。
また、アメリカでは2018年超党派予算法により債務上限23の適用の一時停止が定められており、その期限が19年3月1日に設定されている。実際の債務残高がこの法定上限を超えた場合、国債の新規発行を行うことができず、予算執行に支障が生じることとなる。債務上限の問題は国債の格付にも影響を与え得ることから、期限が迫るにつれ、その動向も注目されることとなる。
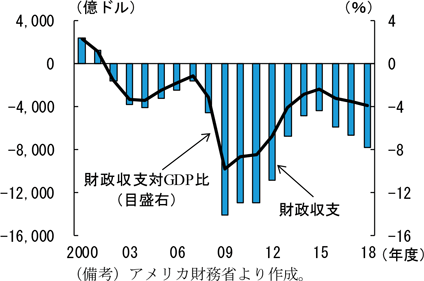
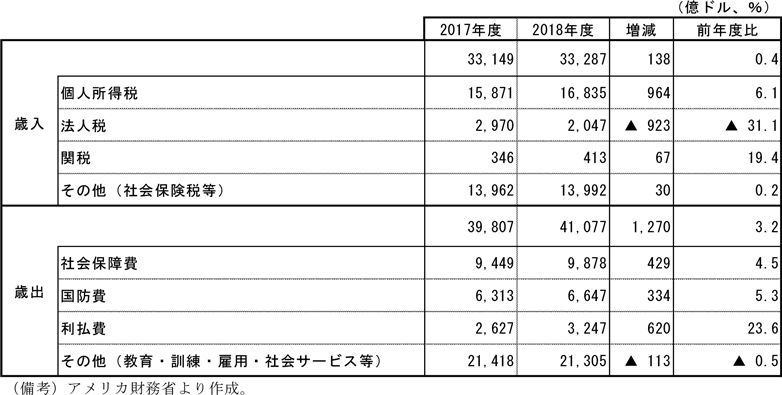
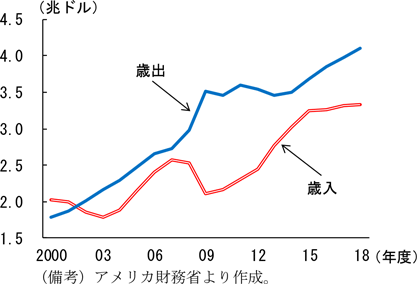
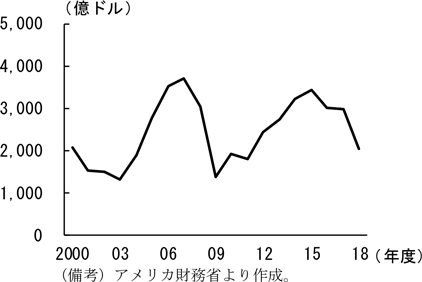
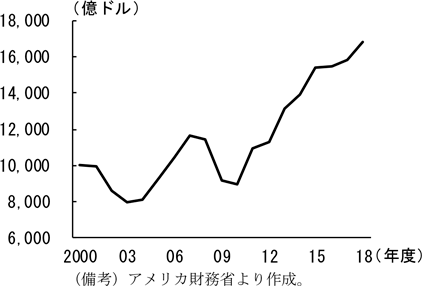
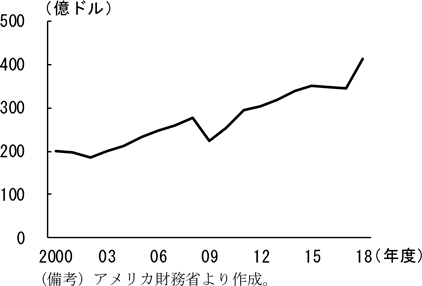
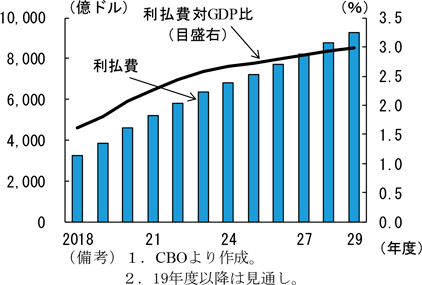
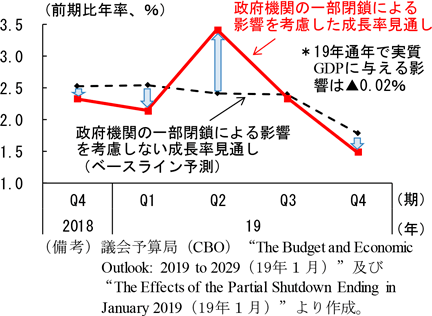
(2)金融政策の動向
アメリカ経済は着実に回復を続けており、労働市場においては、雇用者数の増加が続き、失業率は低下傾向となっている。また、物価情勢については、PCE総合及びPCEコアデフレーターがともに18年3月以降、前年比2%付近で安定している(第2-2-56図)。こうした中、FRBは、雇用の最大化と物価の安定化の「デュアル・マンデート」の達成状況に照らし、緩やかなペースでの政策金利の引上げとバランスシート正常化に向けた保有資産の縮小を行っている。
FOMCによる経済状況の判断を18年12月会合時点のFOMC参加者の見通しの中央値で確認すると、18年及び19年の実質経済成長率は、拡張的な財政政策の効果を踏まえ、それぞれ3.0%及び2.3%と長期の見通しの1.9%を超える高めの伸びが見込まれている。また、失業率は19年に長期の見通しの4.4%を大幅に下回る3.5%まで低下することが見込まれている。PCE総合及びPCEコアデフレーターは、共に18年から21年まで1.9%から2.1%で推移し、PCE総合は長期の見通しでみても2.0%と安定して推移することが見込まれている(第2-2-57表)。
FRBは15年12月以来、政策金利であるFFレート(フェデラル・ファンド・レート)の誘導目標範囲を引き上げているが、こうした良好な経済状況の見通しを踏まえ、18年においても3月、6月、9月及び12月にそれぞれ0.25%ポイントずつ引き上げ、現在では2.25%~2.50%としている(第2-2-58図)。
今後のFFレートの引上げについて、FOMC参加者によるFFレートの見通しの中央値をみると、19年末の中央値が2.875%、20年及び21年末の中央値が3.125%とされていることから、毎回の利上げ幅を0.25%と仮定すると、毎年の利上げ回数はそれぞれ、19年に2回、20年に1回、21年は0回となり、20年に最後の利上げが行われることが示唆される。仮に上記の見通しどおりに利上げが行われると、FOMC参加者によるFFレートの長期の見通しの中央値は2.75%となっており、19年にはFFレートがこの水準を超えることになる。FFレートの長期の見通しが景気を過熱も冷やしもしない中立的な金利水準であるとすると、FRBがこの水準を超えてFFレートの誘導目標範囲を設定するかどうかが、今後の注目点となる。
バランスシート正常化に向けたFRBの保有資産の縮小については、17年9月の会合において、再投資政策の見直しを17年10月から開始することが決定24されて以降、漸進的な縮小が続けられている25。再投資政策見直し前の17年9月末時点で約4.5兆ドルとなっていた資産規模は、19年1月末時点で約4.1兆ドルとなっており、満期を迎えた保有債券の再投資額を徐々に削減する形で極めて緩やかなペースで資産規模の縮小が進められている26(第2-2-59図)。
19年の金融政策のスタンスについては、19年1月のFOMC会合において「世界経済と金融の動向、落ち着いた物価上昇圧力(muted inflation pressures)を踏まえ、委員会は将来の政策金利の調整に忍耐強くなる(be patient)」との文言が声明に追加され、FRBは更なる利上げに慎重な姿勢をみせた。なお、1月のFOMC会合では、別途バランスシート正常化に関し、見直しを行うとした声明も併せて公表された。バランスシート正常化に関する声明においては、「委員会は引き続き、金融政策のスタンスを調整する第一の手段は、FFレートの誘導目標範囲を調整することと認識している」とした上で、「委員会は経済・金融の動向を踏まえて、バランスシート正常化のための詳細を調整する準備をしている」と言及した27。
FRBによるFFレートの引上げは、ペースが急激な場合には景気後退のリスクに、逆に緩やか過ぎる場合には物価と資産価格の行き過ぎた上昇のリスクとなる。FFレートの誘導目標範囲が長期の水準として見込まれている2.75%に近づく中、今後の政策金利の引上げペースの動向が注目される28。
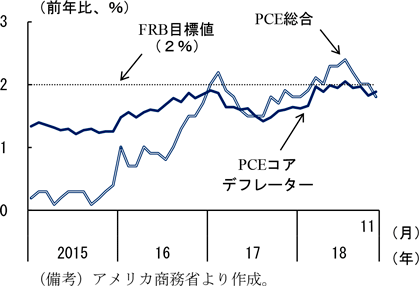
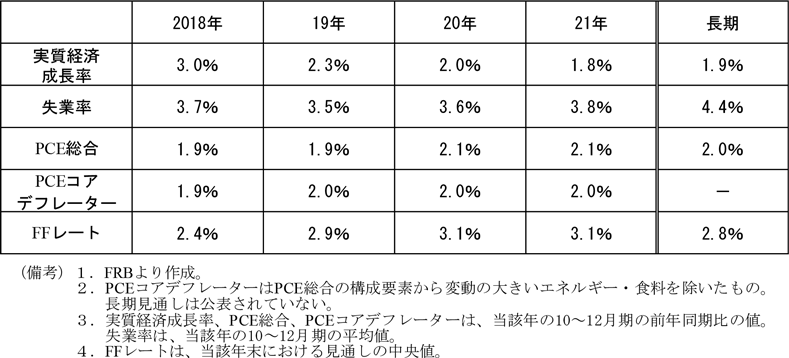
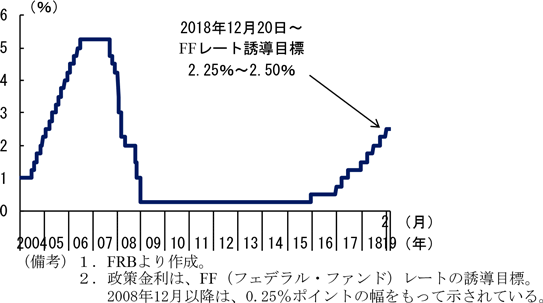
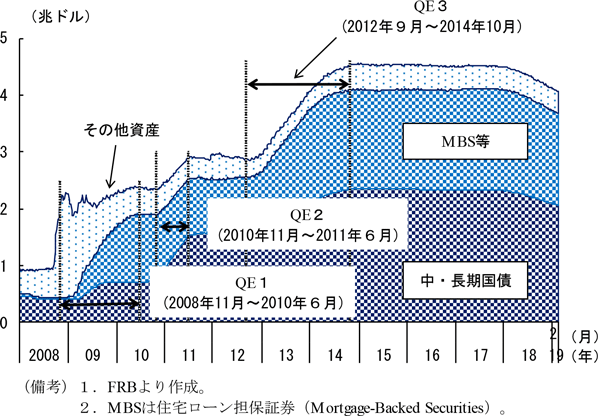
3.通商政策の動向
アメリカ政府は、(1)安全保障の維持、(2)経済の強化、(3)より良い貿易協定の交渉、(4)国内の貿易関連法の積極的な執行、(5)多国間による貿易体制の改革、の5つを貿易政策の優先事項と位置付け、他国に対して新たな政策の実行及び交渉を開始している。18年3月23日には安全保障上の脅威を理由に鉄鋼及びアルミニウムへの追加関税措置を実施、5月23日には自動車輸入がアメリカ国内の安全保障に与える影響について調査を開始、7月以降は段階的に中国からの輸入品に対する追加関税措置を実施している。また、94年にアメリカ、メキシコ及びカナダ間で締結された自由貿易協定であるNAFTA(北米自由貿易協定)についても再交渉を進め、18年9月30日に3か国間で新たな協定に合意し、名称をUSMCA(United States-Mexico-Canada Agreement)とした。以下では、18年以降のアメリカの貿易政策について整理し、その影響等を概観する29。
(鉄鋼・アルミニウムへの追加関税)
アメリカ政府は、18年3月23日、1962年通商拡大法第232条30に基づき、「安全保障上の脅威」を理由として、カナダ、メキシコ、EU、韓国、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジルの7か国・地域を除く国に対し、鉄鋼の輸入に25%、アルミニウムの輸入に10%の追加関税措置の適用を開始した31。18年6月1日からは、韓国、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジルは期日までにアメリカとの間で代替的手段につき合意がなされたことを理由に引き続き適用除外国となったが、カナダ、メキシコ、EUはそのような合意がなされなかったとして本措置の適用が開始された。
追加関税を課せられた鉄鋼及びアルミニウムの対象項目の輸入額は、アメリカの1年間の全輸入額に占める割合が2%と小さいが、これらの主な輸入先はカナダやメキシコなどアメリカと経済的に結びつきの強い国となっている(第2-2-60表、第2-2-61図)。
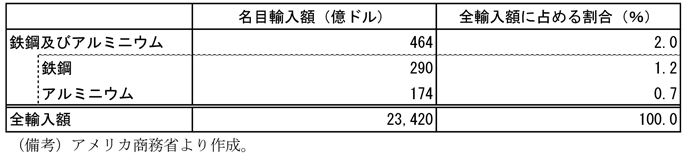
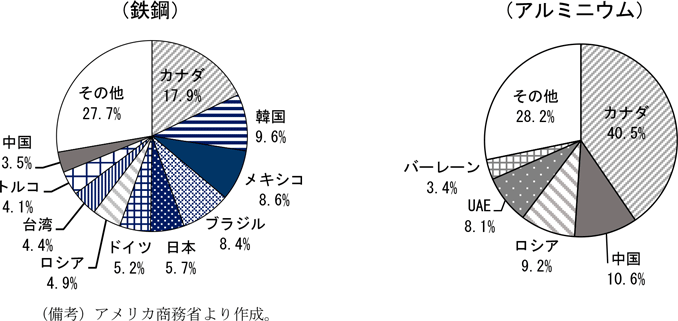
鉄鋼及びアルミニウムの輸入額の推移を確認すると、全体としては追加関税の適用が開始された18年3月以降も大きな動きはないが、追加関税の対象となった鉄鋼及びアルミニウムに限定して輸入額を確認すると、カナダ、メキシコ、EUへの適用が開始された18年6月に一時的に比較的大きな前年比マイナスとなり、その後も前年比で0%程度と追加関税の適用前と比較して伸びが低下している(第2-2-62図、第2-2-63図、第2-2-64図)。
なお、鉄鋼及びアルミニウムの生産に目を転じると、アメリカにおける鉄鋼及びアルミニウムの生産が、18年以降、緩やかに増加しており、追加関税の適用が国内生産の増加に寄与した可能性を指摘できる(第2-2-65図)。
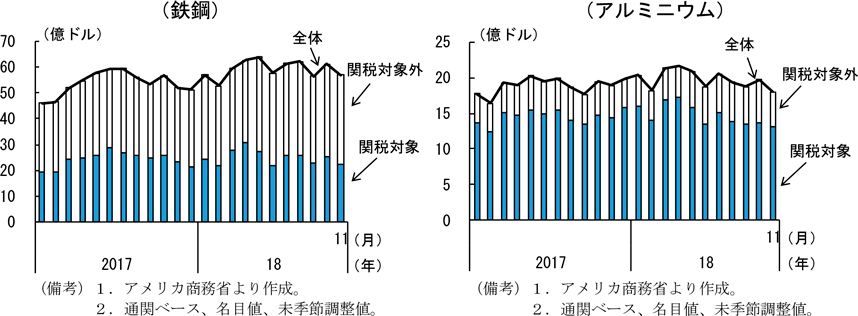
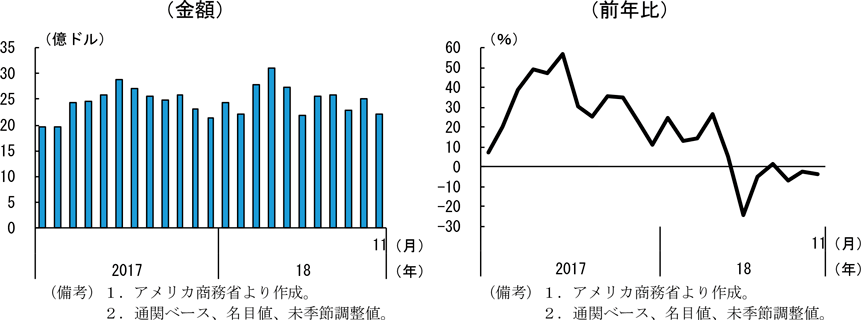
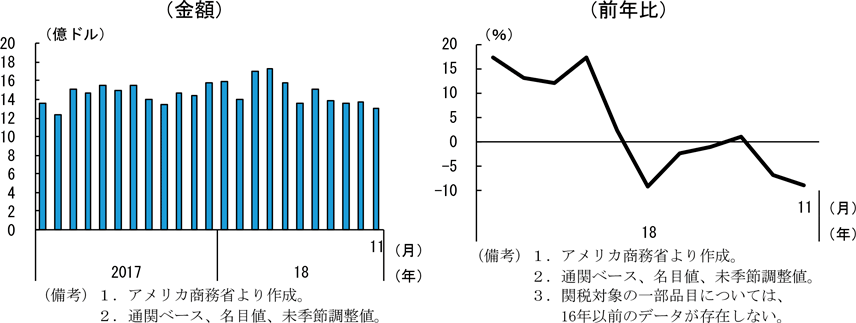
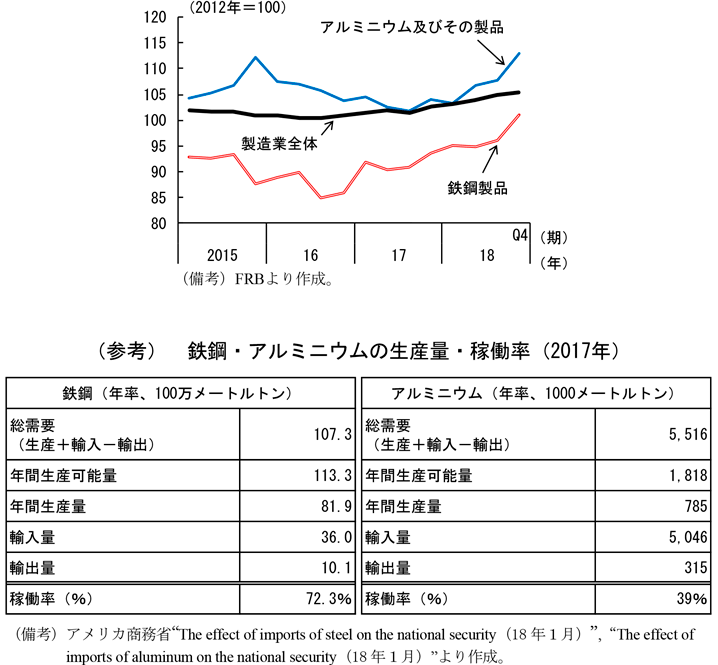
以下では追加関税が物価に与える影響を確認する。まず、輸入物価32に対しては、18年以降のドル高傾向の影響もあり、鉄鋼及びアルミニウムともに顕著な上昇はみられない(第2-2-66図、前掲第2-2-46図)。
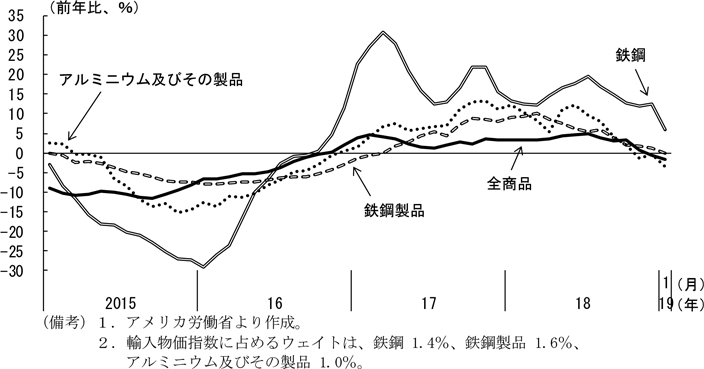
次に、生産者物価を確認すると、アルミニウムにおいては顕著な上昇がみられなかったが、鉄鋼においては、中間需要、商品別、産業別でみた場合に追加関税の影響による上昇が確認できる(第2-2-67図、第2-2-68図、第2-2-69図)。
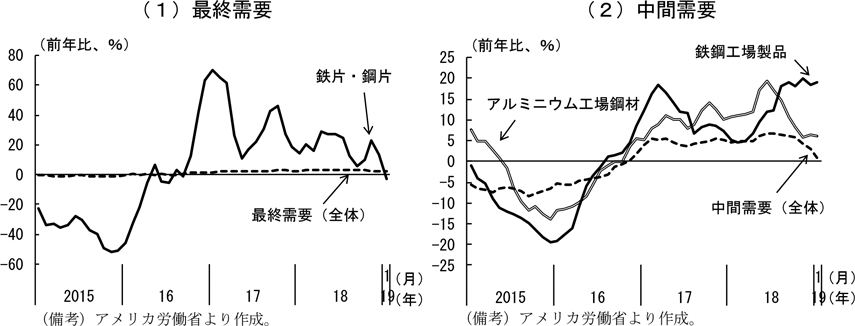
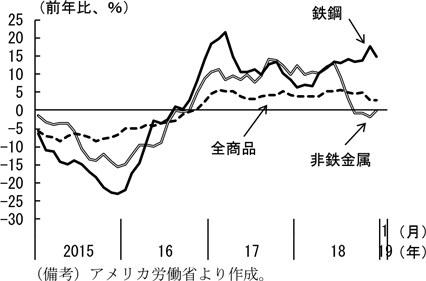
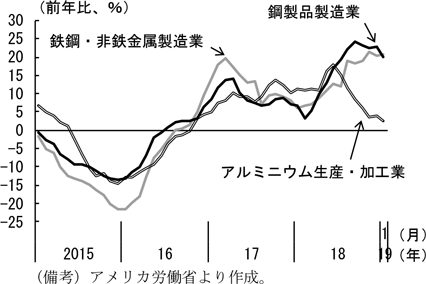
鉄鋼における生産者物価の上昇は、市場価格、とりわけ国内価格の上昇に伴って生じている可能性がある。鉄鋼の国内価格は、世界への輸出価格に比べて高くなっているが、追加関税賦課以降、その差が開いており、また、前年比をみると、国内価格が世界への輸出価格と比較して伸びが高い(第2-2-70図)。世界鉄鋼協会33によれば、世界の鉄鋼需要の見通しは、17年前年比+5.0%、18年同+3.9%、19年同+1.4%と伸びが緩やかになっていくことが見込まれており、需要面から価格上昇圧力が高いことは考えられない。それにもかかわらず、国内価格が高まっている背景には追加関税賦課分の国内価格への転嫁が一部で進むとともに、便乗値上げといったその他の要因も加わっている可能性が示唆される。18年4月及び5月に公表されたベージュブックにおいても、追加関税賦課による鉄鋼価格の上昇が指摘されている34。
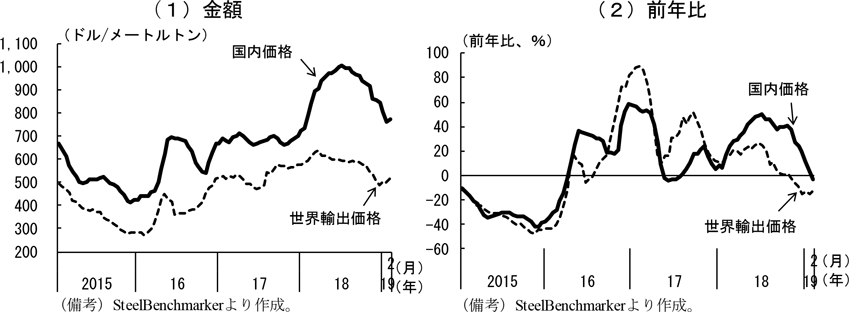
一方、アルミニウムの国際的な取引市場価格は、18年7月以降、弱含みとなっており、これが鉄鋼と異なり、アルミニウムの生産者物価が追加関税措置の開始をもっても大きく上昇しない要因の一つとなっていると考えられる(第2-2-71図)。
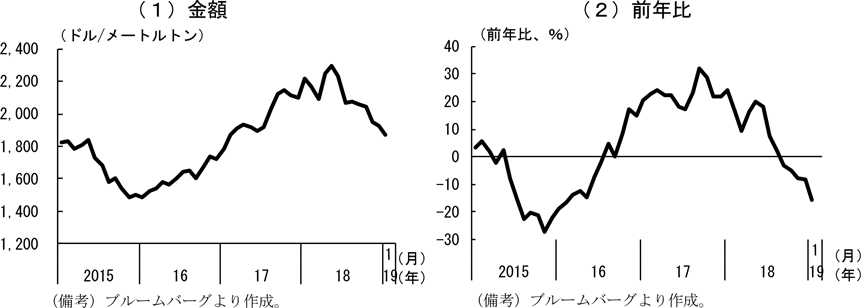
(自動車に対する追加関税)
トランプ大統領は、18年5月23日、「自動車及び同部品のような中心的な産業は、アメリカの国力にとって重要である」とし、鉄鋼及びアルミニウムと同様に、安全保障を理由にした貿易制裁を認める規定を有する通商拡大法第232条に基づき、輸入自動車(トラックや部品を含む)がアメリカの安全保障に与える影響を商務省に調査するよう命じた。商務省のロス長官は、「何十年にもわたって、海外からの輸入によりアメリカ国内の自動車産業が蝕まれていることを示す証拠がある」、「商務省は、輸入自動車がアメリカの国内経済を弱体化させ35、安全保障を害している可能性があるかどうかについて、徹底的に、公正な、透明性のある調査を行う」とし、同日に調査を開始した(第2-2-72表)。
アメリカの自動車及び同部品の輸入を国・地域別にみると、メキシコ、カナダ、EUが上位の3か国となっており(第2-2-73(1)図)、これらの国・地域では自動車及び同部品の関税をめぐって交渉がなされている。18年7月25日には、トランプ大統領とユンケル欧州委員会委員長の間で会談が開催され、通商交渉が行われている間は、追加関税の引上げはなされないことが合意された。また、18年9月30日には、メキシコ及びカナダとの間でのNAFTA再交渉の結果、新たな協定(USMCA36)が合意され、追加関税については、両国は当面適用除外となった37。
アメリカの自動車及び同部品の輸出を国・地域別にみると、輸入と同様にメキシコ、カナダ、EUが上位の3か国となっているが、中国が全体の約10%を占め、EUとの差もわずかとなっている(第2-2-73(2)図)。中国政府はアメリカ政府による追加関税措置への対抗措置として、自動車に追加関税を課していたが、アメリカ政府は中国に対し、「中国はアメリカの自動車輸入に対して40%という、他国に賦課している15%の2倍以上、アメリカが中国からの自動車輸入に賦課している27.5%の約1.5倍の税率を課している」と批判し、「自動車への関税が同等となるよう、採り得るあらゆる手段を検討する」としていた。こうした中、18年12月1日の米中首脳会談後の12月14日、中国はアメリカから輸入する自動車及び同部品への追加関税を19年1~3月の間停止することを発表38するなど、両国間の交渉には進展もみられている。
通商拡大法の規定により、商務省は、調査開始から270日以内に調査結果を大統領へ報告することとなっていることから、報告書の提出期限は19年2月17日とされていた。商務省は、2月17日に自動車及び同部品の輸入が国家安全保障に与える影響についての調査結果をトランプ大統領に提出したと公表したが、その内容については公表されていない。通商拡大法の規定では、大統領は調査結果を受領後、90日以内に内容を確認の上、勧告されている措置について対応を決定することとされており、その後15日以内に決定した措置を実施することとなっている。自動車及び同部品への追加関税をめぐり、トランプ大統領が今後、どのような判断を下すのかに注目が集まっている。
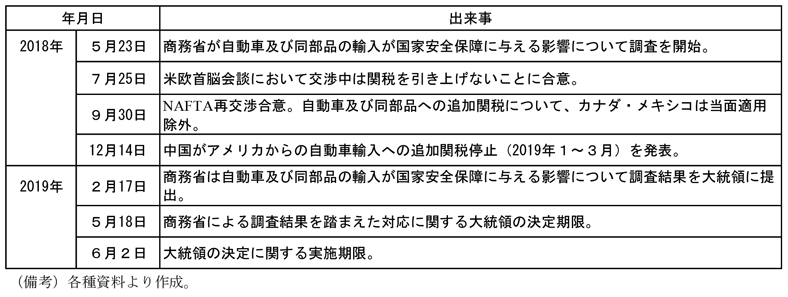
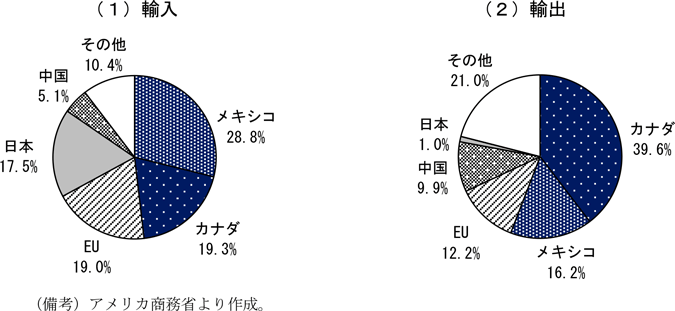
(NAFTAの再交渉)
アメリカ政府は、「貿易赤字を減少させ、製造業、農業、サービス業においてカナダ及びメキシコの市場アクセスを改善させることによって、全てのアメリカ人にとって公平となる貿易協定とする」ことを目的に、17年5月、94年から発効している北米自由貿易協定(NAFTA:North American Free Trade Agreement)の再交渉の開始を表明した。その後、度重なる交渉の後、18年8月27日にアメリカ-メキシコ間でNAFTA再交渉の大筋合意がなされ、9月30日にアメリカ-カナダ間でもNAFTA再交渉の合意がなされた。これらをもって、アメリカ-メキシコ-カナダの3か国間で新たな通商協定が成立し、名称はNAFTAからUSMCA(United States-Mexico-Canada Agreement)に変更された39。18年11月30日にはアメリカのトランプ大統領、メキシコのペニャニエト大統領、カナダのトルドー首相による署名式が行われた。
USMCAの主な概要は以下のとおりである。まず、自動車については、乗用車の関税がゼロとなる条件を定める原産地規則について、(1)域内での乗用車部品の調達比率を現行の62.5%から75%へ引上げ(「2025年1月」若しくは「協定発効後5年」のどちらか遅い方より適用)、(2)40%の乗用車部品は時給16ドル以上の労働者によって生産すること(「2023年1月」若しくは「協定発効後3年」のどちらか遅い方より適用)を合意した。また、カナダ、メキシコからアメリカへの乗用車輸入にそれぞれ年260万台の数量制限を設定40し、自動車部品輸入でもカナダに年324億ドル、メキシコに年1,080億ドルの輸入枠を設定した。加盟国間の紛争処理については、海外企業が政府に異議を申し立てることのできるISDS(Investor State Dispute Settlement)の枠組みをカナダとの間では廃止、メキシコとの間ではエネルギーといった一部分野でのみ存続することとした。このほか、不公正に競争上の優位を得るための為替操作を行わないことを確認し、各国に各月の為替介入の状況等の報告を義務付け、違反が疑われる場合には各国が紛争解決のための小委員会(パネル)に審理を要請することを可能とした。協定の見直し及び期間延長については、原則6年ごとに再評価し、各国が更新意思を示さない限り協定発効後16年後に失効するサンセット条項が追加された。
アメリカ、カナダ、メキシコの輸出入がGDPに占める割合をNAFTA発効前から17年までの推移でみると、アメリカ及びカナダはわずかな上昇にとどまっているものの、メキシコは輸出入共に93年は15%前後だったものが17年には40%程度まで上昇している(第2-2-74図)。
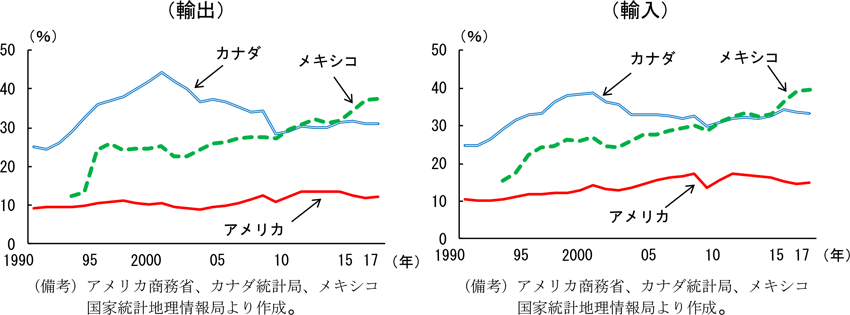
アメリカ、メキシコ、カナダの3か国はアメリカを中心とした経済圏となっており、メキシコとカナダの間の結びつきは弱い。アメリカ、カナダ、メキシコの輸出入について、それぞれ他の2国が占める割合をみると、輸出面では、アメリカの輸出に占めるカナダ及びメキシコ向けの割合は、合計しても40%に満たないが、カナダ及びメキシコの輸出のうち、アメリカ向けはそれぞれ76%、80%と大半を占めている。同様に輸入面をみても、アメリカの輸入のうち、カナダ及びメキシコが占める割合は合計しても約25%と低いが、カナダ及びメキシコの輸入のうち、アメリカが占める割合はそれぞれ50%前後となっている。これに対し、カナダ及びメキシコの輸出入において、互いの国が占める割合はいずれも低く、これら2国の間の直接的な結びつきは弱いことがわかる(第2-2-75図)。
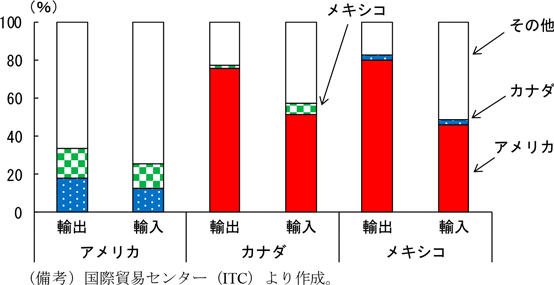
USMCAは、今後、各国議会での承認手続きに移る予定である。NAFTAについては、92年8月に基本合意、同年12月に正式署名がなされた後、1年の期間を経て94年1月の発効へ至った。USMCAについては、一部の規定41で施行日が「2020年1月」若しくは「協定発効日」のどちらか遅い方とされていることから、3国の間では2020年1月の協定発効が目指されているとする見方もある。なお、アメリカでは、18年11月の中間選挙により、上院と下院で多数を占める政党が異なる「ねじれ議会」となったことから、USMCAが議会で承認されるか否か不透明な状況となっている42。
こうした状況の下、トランプ大統領はNAFTAの早期脱退を示唆43するなどし、議会に対してUSMCAの早期承認を強く促している。
4.アメリカ経済の見通しと主なリスク要因
(1)アメリカ経済の見通し
アメリカ経済は、18年1月から実施されている税制改革や歳出上限の引上げによる拡張的な財政政策を背景として、堅調な雇用・所得環境に支えられた個人消費の増加等から、当面は着実に回復が続くことが見込まれる。各種機関による経済見通しにおいても、今後も回復が続くことが見込まれている(第2-2-76表)。
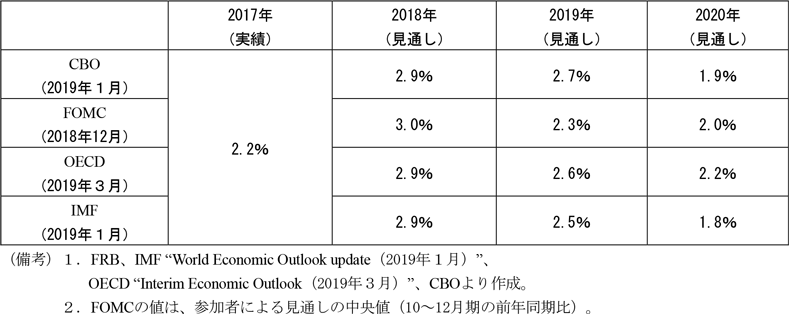
このようにアメリカ経済は回復が続くと見込まれているが、20年度が始まる19年10月以降は、税制改革による減税及び歳出上限の引上げによる拡張的な財政政策の効果が低下することなどから、経済成長率が潜在成長率並みに回帰していくと見込まれる。
税制改革の減税幅は、18年度から27年度までの10年間で19年度が最大となるが、その後は減少し、27年度には増税となる(第2-2-77(1)図)。税制改革が財政に与える影響の動きをより詳細に確認するため、以下では税制改革を個人税制改革と法人税制改革に分けてみていきたい。
まず、個人税制改革による影響は、個人所得税の最高税率等の引下げが大きな減税幅をもたらすものの、これは25年12月31日までの時限となっている。また、オバマケア未加入者への罰金廃止(オバマケアの実質廃止に伴う歳出減が財政支出を減らす効果)なども影響し、税制改革による影響は26年度に大幅に低下し、27年度は一転して増税となる(第2-2-77(2)図)。
法人税制改革による影響は、恒久的措置となっている連邦法人税率の引下げが27年度まで大きな減税幅をもたらすものの、特別減価償却に関する制度変更等が影響し、減税幅は逓減していく見込みである(第2-2-77(3)図)。
また、歳出上限について、2018年超党派予算法においては、19年度の引上げまでしか決まっていないことから、現行法の下では20年度以降の歳出上限は当初の歳出上限まで引き下げられることとなる。(第2-2-78図)
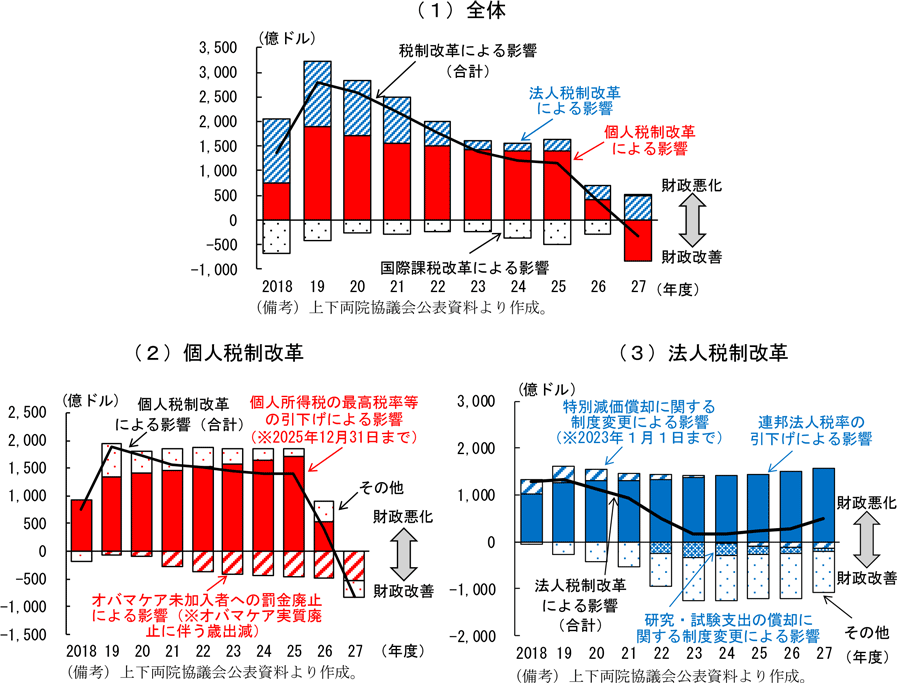
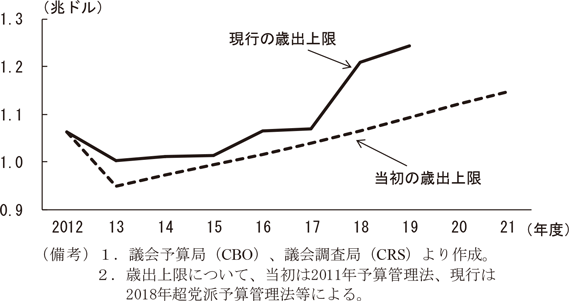
財政支出の増加、またそれに伴う消費や設備投資の増加は、経済を下支えする一方で、貯蓄・投資バランスの不均衡につながる側面もある。貯蓄・投資バランスの観点からは、民間経済における純貯蓄と財政収支の和が経常収支となるが(第2-2-79(1)図)、アメリカでは国内の投資が常に貯蓄を上回って推移しており(第2-2-79(2)図)、経常収支が恒常的に赤字となっている。アメリカの経常収支赤字は、グローバル・インバランスをもたらし、世界経済の不安定要因ともなり得るため、アメリカの財政収支や消費及び投資の動向には注意が必要である。
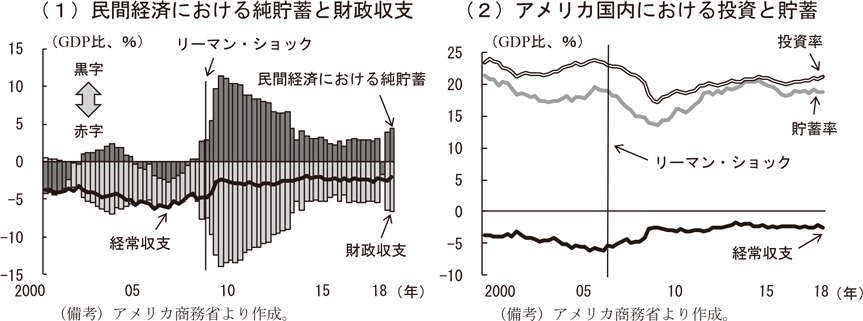
(2)アメリカ経済の主なリスク要因
アメリカの経済政策不確実性指数(Economic Policy Uncertainty Index)の動向を確認すると、総合指数は、トランプ大統領の就任が決まった16年11月に大きく上昇し、その後は振れを伴いつつも低下傾向を示してきたが、依然として過去の景気拡張局面に比べ高い水準となっている(第2-2-80(1)図)。特に18年12月及び19年1月に総合指数が急上昇しているが、これは国境の壁予算をめぐり政府機関が一部閉鎖したことに伴い財政政策及び安全保障の指数が上昇したことや金融政策の指数が上昇したこと44などが影響していると考えられる(第2-2-80(2)図、第2-2-80(3)図、第2-2-80(4)図)。
(トランプ政権による通商政策の動向)
トランプ政権が進める通商政策が、どのように展開していくかについて不確実性がある。世界的なサプライチェーンの構築等、企業活動のグローバル化が進む中で、貿易制限的な通商政策が推し進められた場合には、相手国による報復措置も加わり、世界的な貿易・投資の縮小をもたらす可能性がある。
(財政政策の動向)
アメリカでは、財政政策に関する不確実性も存在する。アメリカ政府の歳出上限は、先述のとおり、19年度予算の引上げは決定されているが、20年度以降についてはその扱いが決まっておらず、現行法の下では20年度以降の歳出上限は当初の歳出上限まで引き下げられることとなる(前掲第2-2-78図)。19年度予算は大幅な引上げとなったことから、20年度予算で歳出上限が全く引き上げられない場合には、アメリカ政府の歳出が急速に抑えられる、いわゆる「財政の崖」が発生する可能性があり、アメリカ経済の押下げ要因となる。これが消費者や企業マインドの低下等に波及した場合は、アメリカ経済の更なる押下げ要因となる可能性もある。
(金融政策の動向)
FRBは漸進的なバランスシート縮小を進めつつ、緩やかに政策金利の引上げを行っているが、FRBによる利上げペースが急激な場合には景気後退のリスクが、逆に緩やかすぎる場合には物価と資産価格の行き過ぎた上昇のリスクが存在する。また、上述のとおり、減税や歳出拡大といった拡張的な財政政策が講じられていることも金利上昇圧力となっており、市場においても、金利上昇がアメリカ経済のリスク要因として、これまで以上に強く意識されている点にも留意が必要である。