第2章 主要地域の経済動向(第1節)
第1節 世界経済
1.世界経済の現状と見通し
(より緩やかとなった回復)
2018年の世界経済は、17年に引き続き緩やかに回復した。ただし18年は、17年にみられたような世界各国・地域における同時進行の景気回復とは異なり、各国・地域間で回復の勢いに差がみられた。18年後半から19年初めには中国やドイツ等、アジアやヨーロッパの中で弱い動きがみられるが、全体としては引き続き緩やかに回復している。国際通貨基金(IMF)によると、世界全体の実質経済成長率は、17年は3.8%、18年は3.7%であったとされる(第2-1-1図)。アメリカでは18年に成長率が加速する一方、その他の先進国では成長のスピードは緩やかになっている。四半期ごとの成長率(前年比)の動きをみても、16年と比較すれば高い水準にあるものの、17年と比べるとそのペースが緩やかになっていることが確認できる(第2-1-2図)。
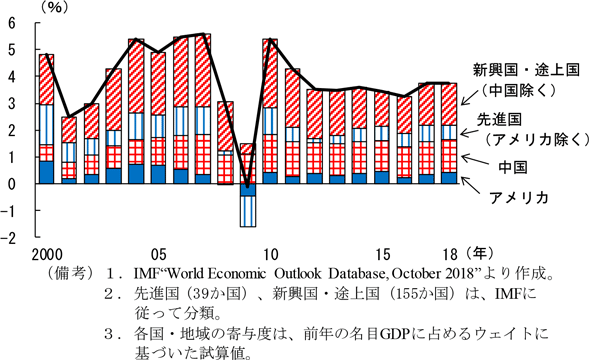
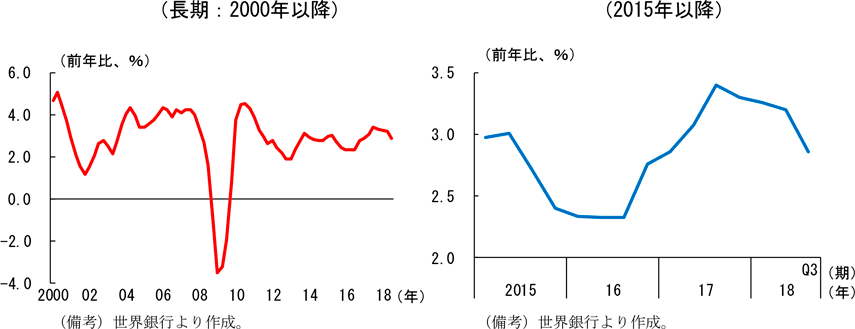
(政策の不確実性の高まり)
17年の世界経済が同時進行で堅調な回復を見せた背景には、世界貿易が拡大し、それを受けて生産も拡大したことが挙げられる1。第2-1-2図でみた18年に入ってからの世界経済の動きを更に詳しくみるために、月次の世界鉱工業生産の伸び(前年比)をみると、18年初めには既にピークアウトしており、18年11月には長期平均を下回っている(第2-1-3図)。
18年は、米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題等、主要国の経済政策の不確実性が世界経済に大きな影響を与えた年であった。経済政策不確実性指数(Global Economic Policy Uncertainty Index)2の動きをみると、英国でEU離脱を問う国民投票が行われた16年6月、アメリカで大統領選挙が行われた16年11月に大幅に上昇し、18年初めまでは低下傾向にあったが、米中貿易摩擦の高まり等から18年を通じて上昇基調となり、2018年12月には同指数が開始された1997年1月以降過去最大となった。鉱工業生産の伸びと比較すると、全体としては、世界経済が下降局面にある時期に、不確実性指数が高まりをみせる傾向にあることが確認できる。16年は世界経済が回復局面にある中で、不確実性指数が高まったこと、また、18年は世界経済の回復がピークアウトする中で、不確実性指数が高まりを見せたが、その高まりは、過去の世界経済の下降局面と比較すると、極めて大幅なものであったことがわかる。
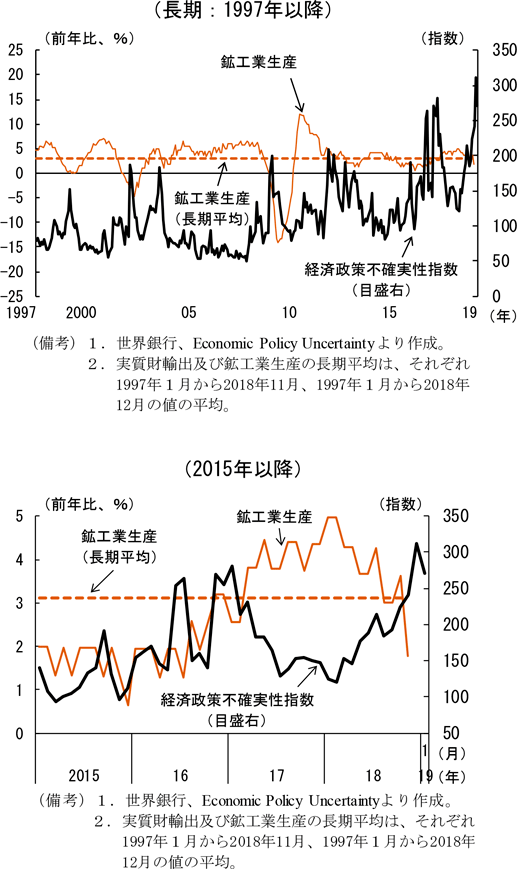
こうした経済政策不確実性の大幅な高まりは、世界的に企業マインドを押し下げる要因となった。世界各国の企業(製造業とサービス業)の景況感(購買担当者指数:PMI)と新規受注指数をみると3、いずれも16年を底として上昇した後、18年2月をピークに急速に低下している(第2-1-4図、第2-1-5図)。
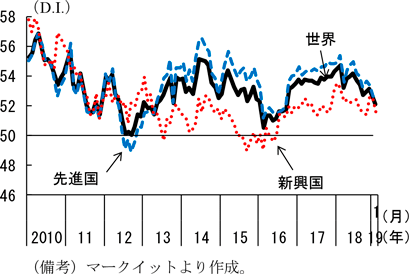
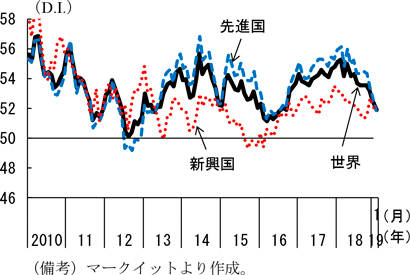
(民間債務の動向)
世界金融危機後、長期にわたる金融緩和政策を受けて、民間債務(家計部門・企業部門)が積み上がり、高水準となっている。仮に民間債務が過剰に積み上がった場合には、金融安定性へのリスク、ひいては経済成長へのリスクとなるおそれがある4。
主要国・地域5の家計部門の債務残高対GDP比をみると、アメリカとユーロ圏では世界金融危機後、ほぼ一貫して低下傾向にあり、18年もその傾向が続いている。カナダでは、世界金融危機後も住宅価格が上昇を続けていることを背景に、家計部門の債務も上昇を続けてきたが、17年に入り住宅価格の低下がみられ始めたことから、17年10~12月期以降はやや低下している。一方で、中国は対GDP比の水準は先進国よりも低いものの、データが入手可能な06年以降、ほぼ一貫して上昇し続けており、その傾向は17年、18年も続いている。結果として、06年には40%以上あったユーロ圏と中国の差は、18年1~3月期には約7%にまで縮まっている。家計部門の債務は金融市場が発展し、個人が金融市場にアクセスしやすい先進国の方が高い傾向があるが6、中国も先進国の水準に近付いていると言える(第2-1-6図)。
一方、企業部門の債務は、先進国では世界金融危機後は緩やかに上昇又はおおむね横ばいで推移しているのに対し、中国では世界金融危機後に大幅に上昇し、極めて高い水準となっている。中国政府の金融リスク防止のための取組により、企業部門の債務は16年4~6月期をピークに低下していたが、18年1~3月期には上昇し高止まっている(第2-1-6図)7。
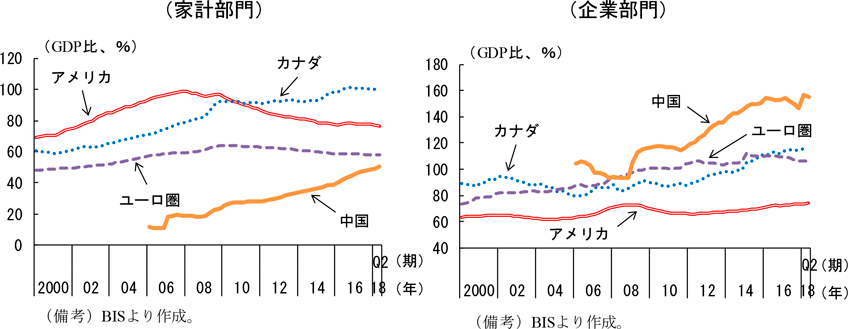
次に、国際決済銀行(BIS)が金融危機に対する早期警戒指標8として位置付けている指標のうち、債務返済比率(DSR: Debt Service Ratio)9と債務(総与信)対GDP比ギャップ(Credit-to-GDP Gap)10を確認する。
DSRについて、データが入手可能な99年以降の長期平均からのかい離をみると、アメリカやドイツでは長期平均を下回る一方、中国やカナダでは長期平均を大きく上回っている。また、カナダでは16年10~12月期以降低下傾向にあるが、中国では16年、17年はおおむね横ばいで推移していたものの、18年1~3月期に上昇に転じた(第2-1-7図)。
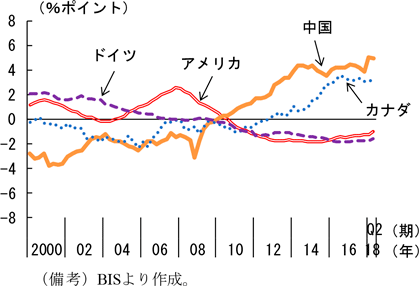
債務対GDP比ギャップについて、BISでは「9%ポイント」を、3年(12四半期)以内に金融危機が起こる可能性が高い債務対GDP比ギャップの閾値としており11、当該閾値との関係をみると、アメリカとユーロ圏では9%ポイントを大きく下回っている。カナダでは、15年以降9%ポイントを超える状況が続いていたが、17年より低下し、18年1~3月期に7.9%ポイントとなり、閾値を下回った。中国では、12年4~6月期以降9%ポイントを超えて急速に上昇し、16年1~3月期には22.1%ポイントに達した。その後は低下し続け、17年10~12月期には閾値を下回ったものの、DSRと同じく18年1~3月期には上昇に転じ、その後も引き続き高水準にある(第2-1-8図)。
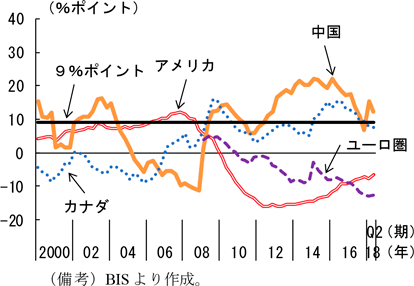
(世界経済の見通し)
18年夏までに公表された国際機関による見通しでは、18年の世界全体の経済成長率は17年から加速し、その勢いを19年も維持すると見込んでいた。しかし、これまでみてきたように、世界経済の拡大のペースは18年後半以降緩やかになっている。そのため、IMFやOECDの経済見通しでは、18年秋までの見通しから下方に改訂されている12。公表時点の違いを反映して、OECD の経済見通し(19年3月公表)の方が、IMFの見通し(19年1月公表)よりも大幅に下方改訂されているが、いずれも、19年の世界全体の経済成長率は18年よりも低下し、20年は19年とほぼ同じ水準で推移する姿を見込んでいる(第2-1-9表)。
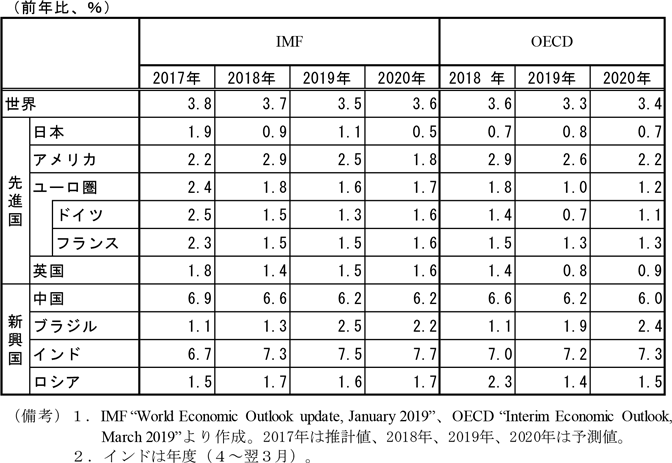
2.世界経済の主なリスク要因
世界経済は、今後も全体としては緩やかな回復が続くと見込まれるが、留意すべきリスク要因が存在する。
(1)通商問題の動向
18年には、第1章で取り上げた米中間の貿易摩擦を始めとして、アメリカと多くの国・地域との間で貿易制限措置がとられた。米中間の貿易摩擦については、18年7月6日にアメリカが中国からの輸入品340億ドル相当に対する追加関税措置を開始して以降、米中間で貿易制限措置の応酬が続いており、企業マインドのみならず、米中間の実際の輸出入にもその影響が表れ始めている。18年3月に開始されたアメリカによる鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置に関しても、複数のアメリカの貿易相手国がそれに対する対抗措置を採る状況が続いている。加えてアメリカ政府は19年2月に、自動車輸入がアメリカ国内の安全保障に与える影響について、安全保障を理由とした貿易制裁を認める規定を有する通商拡大法第232条に基づく調査をとりまとめたところである。また、米EU間でも通商交渉が進められており、交渉期間中は自動車を含め新たな関税を発動しないとされているものの、19年に入り、アメリカ・トランプ大統領が、合意に達しない場合には自動車への追加関税を実施する可能性を示唆するなど、米EU間の緊張も高まっている。
こうした通商問題の影響としては、貿易量の減少のみではなく、企業マインドの悪化やそれに伴う投資の抑制が懸念される。また、企業がグローバル・バリュー・チェーン(GVC)を構築する現在の世界経済にあっては、二国間の通商問題であっても、その影響が他国に波及、増幅されて世界経済全体に影響を与える可能性がある。
(2)中国経済の先行き
中国は世界第2位の経済規模を有しており、その減速は貿易等を通じて世界経済全体に相応の影響を与える可能性がある。中国経済は緩やかに減速しているが、今後、前述の通商問題の動向や過剰債務問題への対応等によっては、景気が下振れするリスクもある。過剰債務問題については、中国政府による民間部門のデレバレッジの取組が進められているが、18年にはその取組が当初想定されていた以上に景気を下押しした可能性もある。中国政府は企業の資金調達環境の緩和のための対応を進めるなど、景気安定に配慮する姿勢を強めているが、他方で、引き続き企業部門のデレバレッジを重要課題と位置付けている。過剰債務問題については、削減に向けた取組が進むことが期待されるが、景気との関係もあり、実施のペースやタイミングについて難しい舵取りが求められている。
(3)アメリカの財政金融政策動向
アメリカでは、15年12月以来、連邦準備制度理事会(FRB)が政策金利の引上げを進めてきた。18年は、金利上昇圧力が市場でも強く意識されるようになった年でもあった13。こうした中、19年1月の連邦公開市場委員会(FOMC)の声明では、将来の政策金利の調整に忍耐強くなる旨に言及し、バランスシートの正常化についても見直しを行うとした声明が公表された。
また、アメリカでの利上げが新興国からの資本流出や通貨下落のきっかけとなる可能性もある。18年にはアメリカの利上げを背景として、アルゼンチンやトルコ等新興国の中でも経済のファンダメンタルズがぜい弱な国で資本流出や通貨下落がみられた14。19年の利上げペースは18年より緩やかになると見込まれるが、今後の金融政策運営がアメリカ内外の金融資本市場に与える影響には注視が必要である。
さらに、アメリカでは、財政政策に関する不確実性も存在する。アメリカ政府の歳出上限は、19年度予算では引上げが決定しているが、20年度以降については引上げが決まっていない。このため、20年度予算で歳出上限が引き上げられない場合には、アメリカ政府の歳出が急速に抑えられる、いわゆる「財政の崖」が発生する可能性がある。
アメリカの金融政策や財政政策の動向は、アメリカにとどまらず、世界経済全体に影響を与える可能性があり、留意する必要がある。
(4)英国のEU離脱を始めとするヨーロッパにおける政策に関する不確実性
英国のEU離脱期日が19年3月29日に迫る中、英国とEUが合意した離脱協定や将来関係に関する政治宣言について英国議会下院の承認を得られない状況が続いている。仮に議会の承認を離脱期日までに得られなければ、「合意なし」での離脱に陥る可能性がある。英国は金融サービスをはじめ、EU内外の国にとってヨーロッパにおける拠点的な役割を担っている面もあり、将来の英国とEUの経済関係に関する不透明感は、ヨーロッパのみならず世界的な企業及び消費者マインドの悪化を通じ、設備投資を始め、経済活動の抑制等を招くおそれがある。
ユーロ圏では、財政政策の動向にも留意が必要である。イタリアでは、18年6月に発足したEUに懐疑的な政党による連立政権の下で拡張的な予算案が策定されたことから、財政リスクプレミアムが上昇し、資金調達環境が悪化、18年の7~9月期及び10~12月期の経済成長率がマイナスに転じた。また、フランスでは、18年11月以降、燃料税増税への抗議をきっかけに低・中所得者層を中心とした大規模な反政権デモが継続的に実施され、サービス業を中心に、景気を下押ししている。また、増税の撤回や最低賃金の引上げ等の拡張的な財政政策対応が採られたことから、19年度の財政収支赤字の対GDP比は、安定成長協定の基準である3%を超える見込みとなっている。こうしたユーロ圏における財政の先行きへの懸念は、ユーロの信認低下等、金融資本市場に波及するおそれもある。
(5)金融資本市場の変動等
これまで述べた様々なリスクが顕在化し、金融資本市場が短期間に大きく変動した場合、その影響は世界各国の実体経済に波及する可能性がある。18年には、米中間の通商問題、アメリカの財政赤字拡大への懸念や長期金利の上昇等からアメリカで株価が急落し、それが他の主要国の株式市場へと波及する局面が複数回あった15。17年には主要国の株価はほぼ一貫して上昇していたことと比較すると、18年は世界経済のリスクを市場が強く意識した一年であったといえる。19年も引き続き金融資本市場の動向を注視していく必要がある。
また、18年は、OPEC加盟国・非加盟国による協調減産、イランに対する経済制裁や世界経済の減速懸念等の要因により、原油価格の変動が大きい一年であった16。原油価格の大幅な上昇・下落は、世界各国の経済に影響を与える可能性があり、留意が必要である。
コラム2-1:2018年の原油市場
(1)原油価格の動向
18年の原油価格は10月初めまでは上昇基調にあったものの、その後大きく下落し、ここ数年の中では値動きの大きい展開となった(図1)。
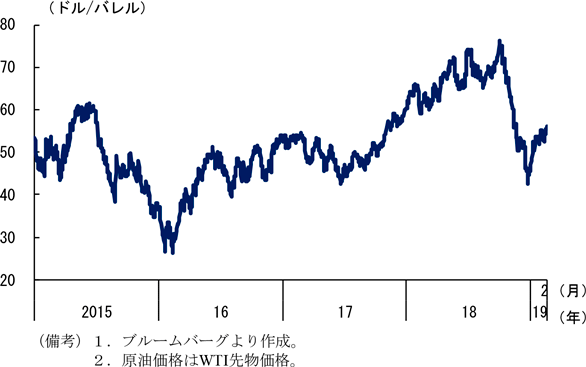
2月のアメリカ雇用統計に端を発した世界的な株安(注1)や、米中間の貿易制限措置の応酬に対する懸念による投資家心理の冷え込みから一時的に下落した局面もあったが、OPEC加盟国及び協調減産に参加する非加盟国(OPECプラス)(注2)の協調減産による供給減少や、アメリカの対イラン経済制裁(注3)による供給懸念から、18年の前半は総じて上昇傾向にあった(図2)。
6月のOPEC総会では、実質的に増産することが決定された(本コラム後述)ものの、その効果は限定的であるとの見方から上昇が続いた。その後、米中間の通商問題への懸念から下落したが、アメリカの経済制裁の影響でイランの原油生産量が減少したことや供給減少懸念から上昇に転じ、10月3日には76.41ドル/バレルに達した。
10月中旬以降、原油価格は急落し、12月中旬には50ドルを下回った。急落の要因としては、11月5日にイラン産原油に関するアメリカの制裁が発動されたものの、8か国・地域に対してイラン産原油輸入停止の適用を180日間除外することが発表されたことから、イラン産原油の供給の減少が早急には進まないとの観測が広がったことが挙げられる(注4)。また、アメリカ、ロシア、サウジアラビアの原油生産量が増加傾向にあったことや(図3)、いずれ世界経済が減速して需要の伸びが鈍るのではないかといった観測も価格を押し下げる要因として働いた。その後の原油価格は、12月6日のOPEC総会及び7日のOPECプラス閣僚会合で協調減産の延長が決定されたこと(本コラム後述)を受け、一時上昇する局面もあったが、アメリカでの株価の大幅下落や世界経済の減速懸念などを背景に下落が続いた。
19年に入ってからは、米中貿易協議の進展に対する期待や、OPECプラスの協調減産で需給が引き締まるとの観測が高まり、原油価格は上昇に転じている。
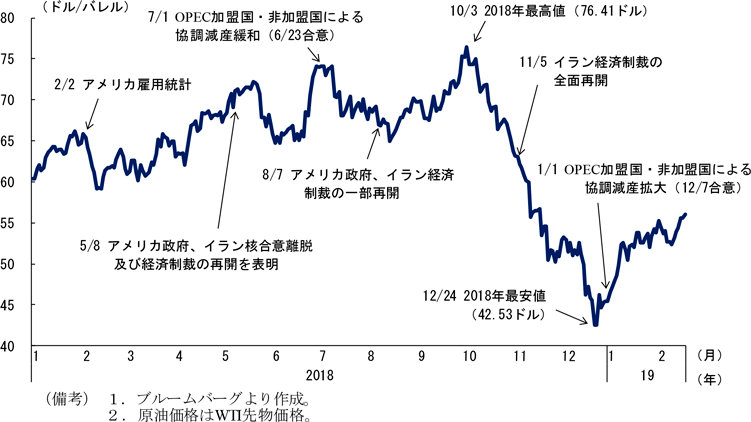
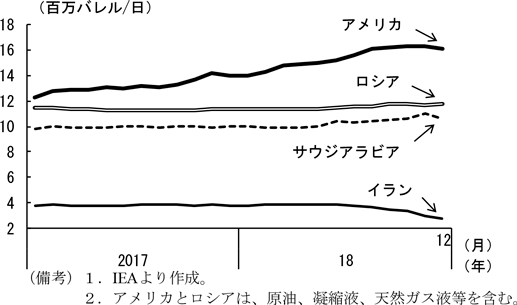
(2)OPECプラスによる協調減産
OPECプラスは、16年12月に日量180万バレル程度の協調減産を実施することで合意し、17年1月1日より協調減産を実施している。減産目標である日量180万バレル程度のうち、OPEC加盟国は16年10月時点の産油量から120万バレルの減産、ロシア等非加盟国全体は日量55.8万バレルの減産を目標とした。協調減産の期限は当初17年6月末までであったが、その後、減産目標を変えない形で延長され、17年11月30日には18年末まで1年間の延長が決定された(注5)。
協調減産は順調に進み、17年8月以降、OPECプラス全体の減産目標の遵守率(注6)は100%を連続して超える状況が続いた。遵守率は18年前半まで上昇し続け、3月以降150%近辺にまで達した。こうした状況や18年前半の原油価格の上昇を受け、18年6月22日のOPEC総会及び翌日のOPECプラス閣僚会合では、OPECプラスで5月に147%に達していた協調減産の遵守率を100%まで低下させる協調減産の緩和(実質的な増産)で合意した。この合意を受け、OPEC加盟国、ロシア共に生産量が増加しており、18年11月にはOPECプラスの減産目標遵守率は100%を切る水準まで低下している(図4)。
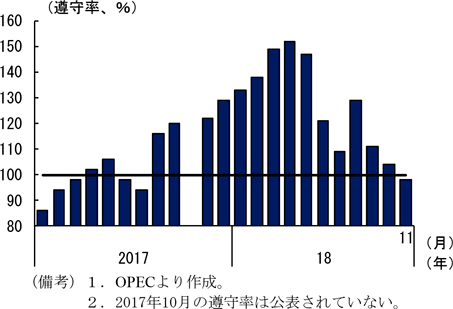
(3)協調減産の延長をめぐる動き
18年10月中旬以降、原油価格が大幅に下落する中、12月6日にOPEC総会が、翌7日にOPECプラス閣僚会合が開催され、18年12月末までとされていた協調減産の延長について議論された。その結果、19年1月より6か月間、18年10月の産油量からOPEC加盟国で日量80万バレル、ロシア等の協調減産に参加する非加盟国で日量40万バレルの日量計120万バレルの減産を行うことで合意した。また、19年4月にOPECプラス閣僚会合を開催し、協調減産の見直しを議論することとなった(注7)。
OPECプラス全体での日量120万バレルの減産合意については、原油価格を下支えする効果が期待されるものの、今回の合意では国別の減産割合が明示されていないため、協調減産の遵守に関して不確実性がある。また、最大の原油輸入国である中国をはじめ、世界経済に対する景気減速懸念が、先行きの需給バランスの緩和観測につながる可能性もある。
なお、OPECプラスによる協調減産をめぐっては、アメリカのトランプ大統領が原油相場の上昇は望ましくないとして、OPECと主要産油国をけん制する発言をしていた。今回の決定はこうしたけん制には応えない姿勢を示したものであるが、OPECプラスとアメリカとの関係にも引き続き注視が必要である。
(4)原油需給・原油価格の見通し
今後の見通しについて、米エネルギー情報局(EIA)は、18年後半には18年10月以降にみられた原油価格の大幅な下落や協調減産により、需給バランスは19年におおむね均衡するものの、供給量が消費量を上回る状況が続くとみている(図5)。
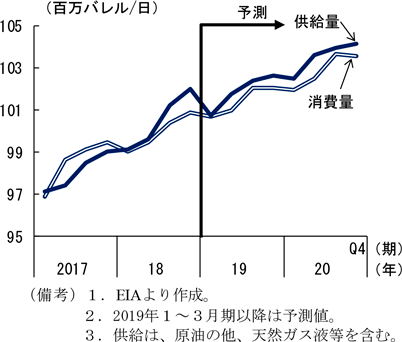
また、EIAの原油価格(WTIスポット価格)の見通しでは、19年は緩やかに価格が上昇し、20年には58.0ドル/バレルで安定することが見込まれているが、18年の平均64.94ドル/バレルには達しないとされている(図6)。このように、19年には大幅な原油価格上昇は見込まれないところ、19年4月に予定されているOPECプラス閣僚会合、またこれを受けた協調減産の動向が注目される。
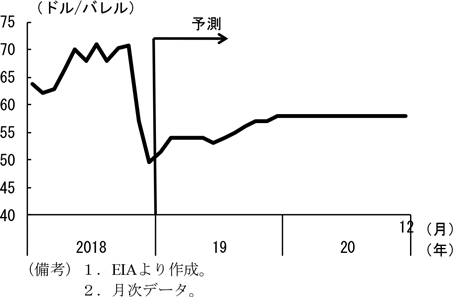
(注1)内閣府(2018)を参照。
(注2)19年1月現在、OPEC14か国、非OPEC10か国の合計24か国。19年1月にカタールがOPECを脱退した。
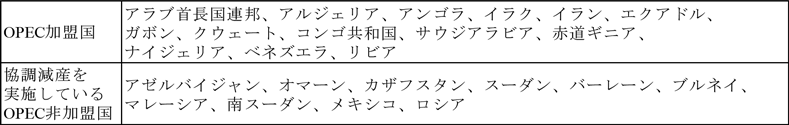
(注3)18年5月8日にトランプ大統領がイラン核合意からの離脱を表明し、核合意以前に行っていたイランに対する経済制裁を復活する意向を表明した。経済制裁のうち、8月7日には、イラン政府によるドルの取得等に対する制裁を再発動、11月5日には、イラン企業との石油関連の取引やイラン中央銀行・イランの金融機関との取引に対する制裁等を再発動した。制裁の対象には、イランと取引を行う第三国の企業や個人も含まれる。
(注4)イラン企業との石油関連の取引に関する制裁については、8か国・地域(日本、イタリア、インド、韓国、ギリシャ、台湾、中国、トルコ)を最長180日間の適用除外とした。
(注5)その他、それまで対象外であったナイジェリアとリビアに対しても両国合計で日量280万バレルの上限が設定された。
(注6)減産目標遵守率=(各月の減産量)/(合意された減産量=約180万バレル/日)
(注7)その他報道によると、イラン、リビア、ベネズエラは実質的な減産の除外が認められた。また、カタールの19年1月のOPEC脱退についても確認された。

