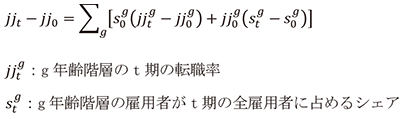第1章 欧米主要国における賃金の伸び悩み(第2節)
第2節 欧米主要国における賃金伸び悩みの要因
欧米主要国・地域における賃金伸び悩みの要因と考えられる主な事項について、その状況を検証していく。近年、先進国共通で失業率が低下しているにもかかわらず、賃金の伸びが高まらない要因に関しては、活発な議論が行われており、様々な要因が指摘されているが、一つの決定的な要因によるものではなく、複数の要因が関与していると考えられる。ここでは、賃金伸び悩みの要因と考えられる事項のうち、(1)労働需給の緩み(スラック)の存在、(2)労働生産性の上昇率の鈍化、(3)労働者の賃金交渉力の低下、(4)予想インフレ率の低下、(5)労働者のモビリティの低下、(6)人工知能(AI)等の技術革新の影響について、アメリカ、ユーロ圏、ドイツ、フランス及び英国の動向を確認していく9。
1.労働需給の緩みの存在
労働市場の情勢を把握する際に参照される代表的な指標は失業率であるが、失業率は前節で確認した通り、欧米主要国・地域で低下傾向を示しており、歴史的にみてもおおむね低い水準にあるといえる。このことは一般に、労働需給がタイト化していることを示し、賃金の伸びの高まりにつながると考えられているが、前節で確認した通り、欧米主要国・地域の賃金上昇率は低迷している。
このため、賃金の伸び悩みを検証する上で、失業率の低下は必ずしも労働需給のタイト化を示しておらず、失業率からでは把握できない労働需給の緩み10の存在が指摘されている。失業率からは把握できない労働需給の緩みが存在する場合、その者が求職活動を行えば、労働供給が増加することとなり、賃金上昇率を抑えると考えられる。そのため、ここではまず欧米主要国・地域の労働参加率をみた後、労働需給の緩みにつながる未活用労働力の大きさを示す各種指標を確認し、欧米主要国・地域の労働需給の緩みの状況を検証する。
(労働参加率の動向)
労働需給の緩みの存在を示す指標として、特にアメリカにおいて労働参加率の低下が挙げられている。労働参加率は、生産年齢人口に占める労働力人口(就業者数と失業者数の合計)の割合であり、その低下は非労働力人口の割合の上昇を意味している。労働参加率低下(非労働力率上昇)の要因としては、高齢化といった人口構成要因のほかに、求職活動を一定期間以上行っていない11ために労働市場から退出したとみなされる者の増加も含まれるため、そうした者が潜在的に労働需給の緩みとなっている可能性がある。景気回復が進むにつれて一度非労働力化した者が求職活動を再開し、労働市場に再び参入すれば、労働需給の緩みが顕在化することになる。
欧米主要国・地域におけるいわゆるプライムエイジ(25~54歳)全体の労働参加率をみると、ユーロ圏全体、ドイツ、フランス及び英国は、女性の労働参加率上昇もあり、2000年以降緩やかな上昇傾向にあるのに対し、アメリカについては、16年にはわずかに上昇したものの、長期的にみれば明らかな低下傾向をたどっている(第1-2-1図)。男女別にみても、アメリカのみヨーロッパ主要国・地域と異なる傾向がみられる。プライムエイジの男性の労働参加率は、ヨーロッパ主要国・地域では、ほぼ横ばいかわずかな低下にとどまっている一方、アメリカでは2000年代半ばから急激に低下している。プライムエイジの女性の労働参加率については、ヨーロッパでは2000年代はほぼ一貫して上昇傾向にあるが、アメリカのみ2000年代前半にほぼ横ばいで推移した後、2000年代後半以降低下している。このため、ヨーロッパでは、2000年代に男性の労働参加率にわずかながら低下傾向がみられたものの、女性の労働参加率が上昇したため、プライムエイジ全体では2000年以降やや上昇している(第1-2-2図)。
これを踏まえると、2000年代半ば以降の労働参加率の低下は、アメリカで顕著であるものの、ヨーロッパでは確認できず、欧米主要国・地域に共通した現象とは言えない。アメリカ大統領経済諮問委員会(Council of Economic Advisors)(2016)は、アメリカにおけるプライムエイジの男性の労働参加率が低下している理由として、低スキル・中スキルの労働需要の減少を挙げており、その背景には技術進歩やグローバル化があり得るとしている。他方で、そのような要因は先進国共通であることから、アメリカ特有の要因として、求職活動の補助や職業訓練といった積極的労働市場政策が他のOECD加盟国と比較して充実していないことや、刑務所に収監される人数が急増している12ことを挙げている。また、男性より低下の幅が小さいものの、女性でも労働参加率が低下していることについては、アメリカでは仕事と育児・介護の両立支援に資する労働市場政策の拡充が他のOECD加盟国と比較して実施されなかった影響の可能性が指摘されている13。さらに、90年代以降、育児や介護といった家庭の事情以外を理由として過去1年間に求職活動を行わなかったプライムエイジの割合は、男女共に上昇しており、特に2000年代に入って以降上昇している。育児や介護といった家庭の事情を除けば、男女共に病気や障害があることが求職活動を行わない理由として最も多い。このため、健康面での問題が、アメリカのプライムエイジにとって男女共に労働参加の障壁となっているとも指摘されている14。
アメリカにおける労働参加率の低下の背景にあるこのような特有の構造的問題により非労働力化した者には、景気回復に伴い労働力化するという性質ではない者が少なからず存在すると考えられる。ただし、就業を希望しつつも育児や介護を理由として非労働力化している者の中には、仕事と育児・介護の両立支援に資する労働市場政策がとられれば、直ちに労働力化する者がいる可能性がある。
以上の構造的問題を踏まえると、アメリカにおけるプライムエイジの労働参加率の低下は、中長期的にみれば労働需給の緩みとなっている可能性はあるが、短期的にみて賃金の伸びに影響する労働需給の緩みとなっているとは限らず、景気回復に伴い労働力化する労働需給の緩みが、ヨーロッパと比較してアメリカにおいて大きいことを示しているとは必ずしもいえない。
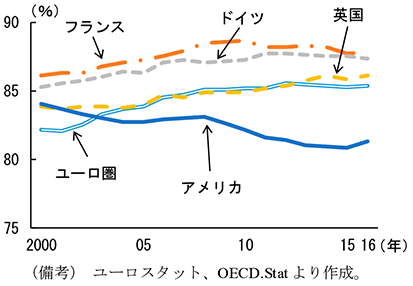
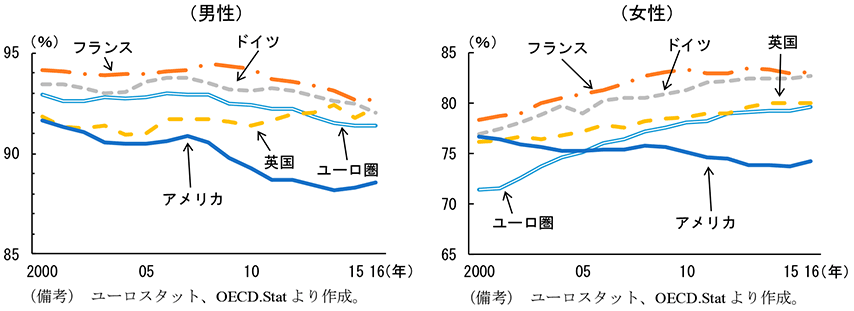
(未活用労働の指標)
先に欧米主要国・地域の失業率の推移をみたが、各国の就業、失業分野の統計のほとんどは、ILO(国際労働機関)が定める国際基準に基づいている。ILOでは失業率を補う「未活用労働」の考え方が重要であるとの観点から、国際基準改定に向けた議論が進められ、13年に採択された「仕事または労働、就業、労働力の未活用に関する決議」(Resolution Concerning Statistics of Work, Employment and Labour Underutilization)において、「未活用労働」に関する新たな指標が設けられた。従来は人口を就業者、失業者及び非労働力人口の3つに分類していたが、13年の決議により、これらに加え「未活用労働」の定義が明確化され、「未活用労働」は、労働時間に関連した未活用労働力、失業者及び潜在労働力を合わせた概念とされた(第1-2-3表)。このうち労働需給の緩みに関連するのは、「労働時間に関連した未活用労働力」及び「潜在労働力」である。
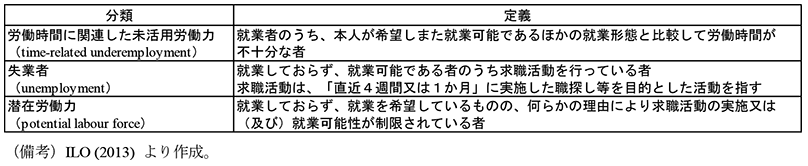
本ILO決議には、第1-2-4表に掲げた未活用労働に関する指標が示されており、このうちいくつかを公表すべきとしている。なお、未活用労働の総合指標(LU4)は、「広義の失業率」と呼ばれることもある。
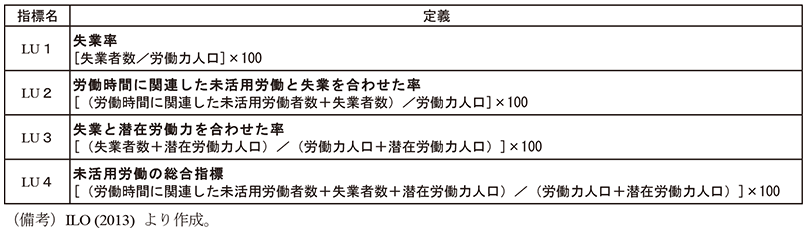
(未活用労働力と労働需給の緩み)
失業者、潜在労働力及び労働時間に関連した未活用労働力は、可能であれば就業または労働時間を増やしたいと考えている者であり、労働市場の需給との関係ではいずれも労働供給を増やす要因であり、「労働需給の緩み」の構成要素である(第1-2-5図)。前述のLU4(広義の失業率)は、その時点での各国・地域における労働需給の緩みのレベルを示したものであるといえる。
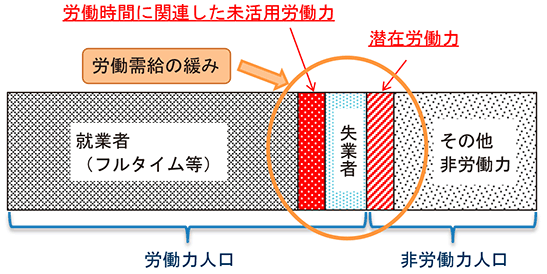
(欧米主要国における未活用労働の指標)
欧米主要国・地域においては、上記のILO決議を踏まえ、未活用労働の分類の詳細が決定されており、それに基づき未活用労働に関する指標が公表されている。第1-2-6表及び第1-2-7表に、以下で取り上げるアメリカ及びEUにおける未活用労働の分類及び指標をあらかじめ示しておく。
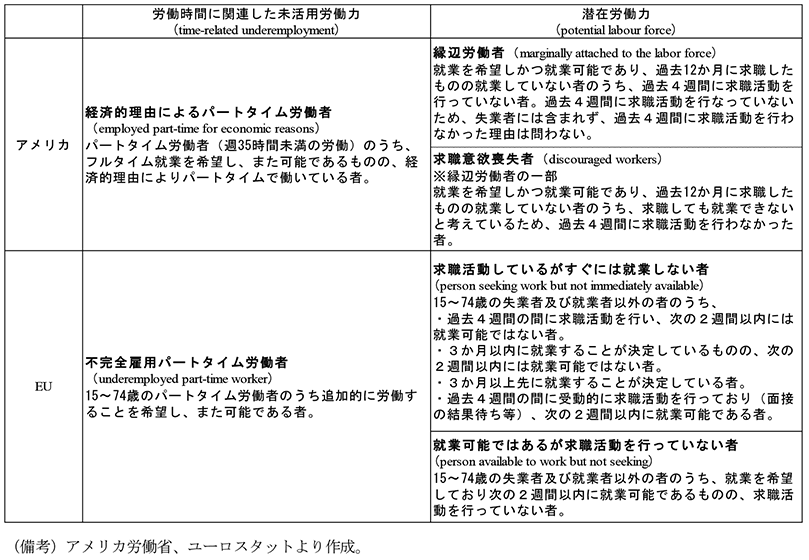
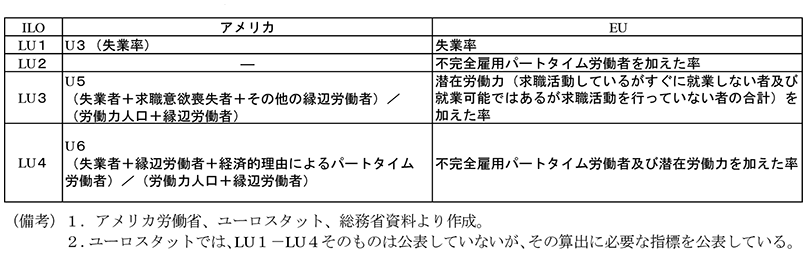
(欧米主要国における広義の失業率)
通常の失業率(LU1)は、未活用労働のうち失業者のみを測定する指標であるため、労働需給の緩みを正確に測定できていないとの指摘がある。就業可能ではあるものの求職活動を一定期間以上行っていない者は、景気回復等により仕事が見つけやすい状況になれば、たとえ低賃金であっても就業すると考えられる。また、より長時間働くことを希望しながらパートタイム労働にとどまっている者は、パートタイム労働からフルタイム労働に移行できれば、賃金の上昇が緩やかであってもそれを許容する傾向にあると考えられる。これらは、賃金上昇圧力を抑制する原因となり得ることから、労働時間に関連した未活用労働力及び潜在労働力を加えた広義の失業率の動向を確認する必要がある。
まず、アメリカの広義の失業率(U6)をみると、08年9月のリーマン・ショックに端を発する世界金融危機の発生後、広義の失業率は09年末から10年初めにかけて17%台まで急激に上昇した(第1-2-8図)。しかし、その後、長期にわたる景気回復が続く中で、広義の失業率も着実に低下し、17年に入り世界金融危機発生直前の水準に近付きつつある。しかし、過去最長であった91年3月から01年3月の景気回復期終盤の2000年には世界金融危機発生直前よりも広義の失業率はさらに低く、アメリカの景気回復が続けば、今後、広義の失業率は、更に低下する可能性もあると考えられる。
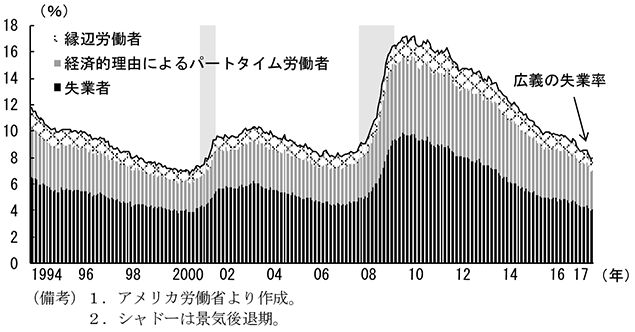
次に、ユーロ圏全体、ドイツ、フランス及び英国について、データが入手可能な08年以降の広義の失業率の動向をみていく(第1-2-9図)。ユーロ圏全体では、08年の世界金融危機、10年のギリシャ問題を契機とする欧州政府債務危機により、広義の失業率は上昇を続け、13年及び14年には20%を超えて推移した。15年以降は低下しているものの、依然としてリーマン・ショック直前の水準には戻っていない。
ユーロ圏主要国を見るとユーロ圏全体とは異なる動きもみられる。ドイツでは、世界金融危機や欧州政府債務危機に関わらず、08年以降ほぼ一貫して広義の失業率は低下を続けており、水準もユーロ圏全体と比較して低く、潜在労働力の比率も他のユーロ圏の国と比較して低い。ドイツにおいてこのような傾向がみられる背景には、世界金融危機後輸出主導で景気が回復した後、欧州政府債務危機の際も経済成長率が底堅く推移したほか、2000年代前半に実施された「シュレーダー改革」の一環として、労働市場改革(いわゆる「ハルツ改革」)が進められた影響があるものと考えられる。ハルツ改革では、失業に対する補償から就労促進へと労働政策の方針転換が図られ、ミニ・ジョブ制度の拡充、派遣労働の規制緩和等により労働市場の柔軟化・多様化が進められた15。その結果、失業率は2000年代半ば以降低下しており、これに合わせて広義の失業率も低下している。
フランスについては、広義の失業率のデータが入手可能な14年以降をみると、17年以降やや低下しているものの、ユーロ圏全体とほぼ同じ水準で高止まりしている。
英国では、ユーロ圏全体よりもやや早く、13年後半以降低下しており、16年後半に入りリーマン・ショック前とほぼ同水準にまで低下している。
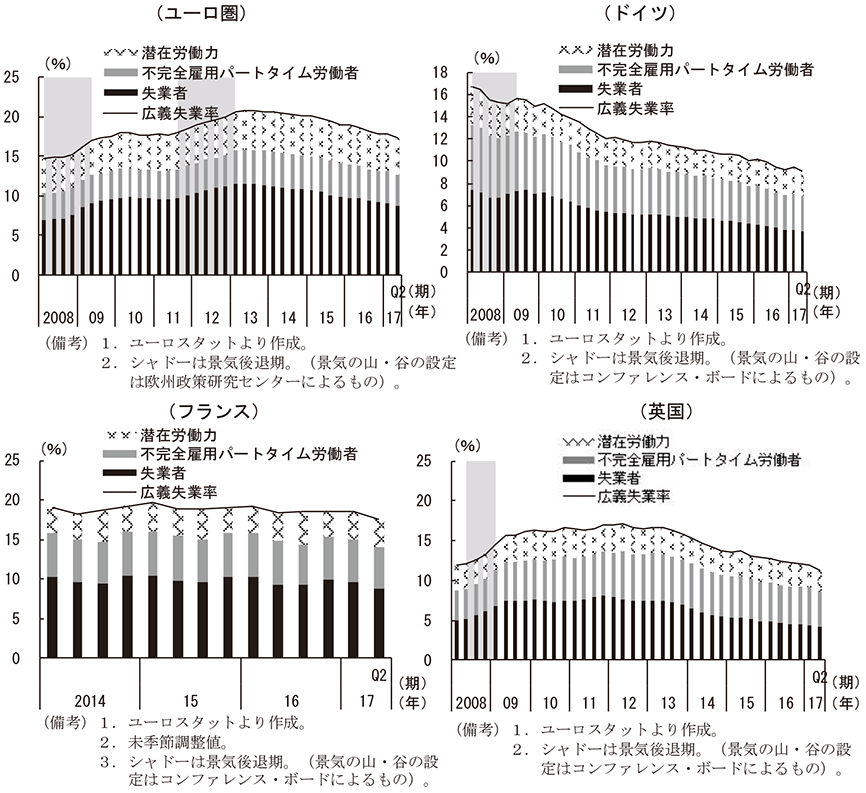
(アメリカにおける経済的理由によるパートタイム労働者)
アメリカの広義の失業率全体の動きを確認したが、以下では広義の失業率に含まれる未活用労働力の中でも、「労働時間に関連した未活用労働力」に着目していく。未活用労働力は失業者には当たらないことから、増加すれば失業率の押下げ要因となり、労働市場の需給の引き締まりを過大に見せることになり得る。アメリカでは、広義の失業率(U6)に含まれる「経済的理由によるパートタイム労働者」(前掲第1-2-6表)がこの「労働時間に関連した未活用労働力」に当たる。
以下では「経済的理由によるパートタイム労働者」をその主な構成要素である「業務量の削減/企業の経営状況」(Slack Work or Business Conditions)と「パートタイムの仕事のみ見つかった」(Could Only Find Part-Time Work)に分けてみていきたい(第1-2-10図)。前者が個々の企業の事業上の都合によるパートタイム労働であるのに対し、後者はフルタイムの仕事の不足に起因するパートタイム労働を意味する。世界金融危機発生直後に、「業務量の削減/企業の経済状況」を理由としたパートタイム労働者が急増したことにより、「経済的理由によるパートタイム労働者」が大きく押し上げられている。09年半ばにアメリカの景気回復が始まると、「業務量の削減/企業の経済状況」を理由としたパートタイム労働者が着実に低下した一方、「パートタイムの仕事のみ見つかった」者の割合は緩やかな増加を続け、14年にようやく低下に転じている。結果として、現在の「経済的理由によるパートタイム労働者」の構成は、09年後半の景気回復初期と比較して、企業都合ではなく、パートタイムの仕事しか見つからなかったことを理由としている者の割合が高くなっている。このようにフルタイムの仕事を見つけられないことを理由とするパートタイム労働者は、景気回復局面に入った後もすぐには減少しておらず、労働需給の緩みとして比較的長期にわたり一定程度残存し続ける様子がうかがえる。
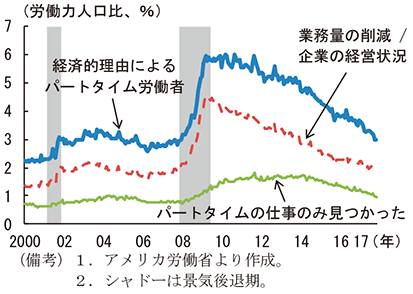
(欧米主要国における非自発的パートタイム労働)
ここまでアメリカを例に「労働時間に関連した未活用労働力」の中でも、フルタイムでの就業を希望しているものの、パートタイムの仕事のみ見つかったことを理由とするパートタイム労働者(非自発的パートタイム労働者)が、景気回復の過程で比較的長期にわたり労働需給の緩みとして残存することをみた。そこで、非自発的パートタイム労働者16に着目して、欧米主要国・地域の状況を比較する。非自発的パートタイム労働者は、パートタイム労働に従事せざるを得ない状況にあることから、低い賃金上昇率を許容しやすい可能性や、非自発的パートタイム労働者がフルタイムでの就業先を探す過程で、既存のフルタイム労働者との競争が生じ、そのことがフルタイム労働者の賃金上昇の抑制要因となるといった可能性が指摘されている17。IMF(2017)では、総雇用者数に占める非自発的パートタイム労働者の割合が1%ポイント上昇した場合、名目賃金上昇率は0.3%ポイント低下するとの試算が示されている。
第1-2-11図は、欧米主要国・地域のプライムエイジについて、非自発的パートタイム労働者が労働力人口に占める比率を男女別にみたものである。これをみると、2000年以降、いずれの国・地域でも男性に比べ女性の比率が高くなっており、また、男女ともにドイツを除きパートタイム労働者の割合は上昇傾向にある。
ドイツを除く国・地域では、世界金融危機以降、非自発的パートタイム労働者の割合は大きく上昇している。フランスを除きここ数年は低下に転じているが、低下のスピードが緩やかであるため、男女ともに依然としてリーマン・ショック前より高い水準にとどまっている。ドイツの非自発的パートタイム労働者の動向が他国と異なる要因としては、前述した2000年代前半の「ハルツ改革」の影響が考えられる。ハルツ改革の結果、労働市場の柔軟化・多様化が進み、2000年代を通じてパートタイム労働者比率は緩やかに上昇したものの、このうち非自発的パートタイム労働者の割合は他の主要国と比較して低位で安定的に推移している18。
また、世界金融危機発生後のプライムエイジの失業率と非自発的パートタイム労働者比率のピークを比較すると、アメリカ、ユーロ圏全体、英国いずれにおいても、失業率の方がおおむね1年から3年程度早くピークを迎えている(第1-2-12図、第1-2-13表)。景気回復の初期段階では、求職活動を続けていたものの就業できずにいた者や、非労働力化していた者が、フルタイムでの就業を希望するにもかかわらず、まずはパートタイムで就業するために、失業率の低下と非自発的パートタイム労働者比率の増加が同時にもたらされ、その後、景気回復が進展するにつれ、そのような労働者がフルタイムに移行することで、非自発的パートタイム労働者比率が低下すると考えられる。このことは、景気回復初期の失業率の低下が労働需給の緩みの縮小を過大に表している可能性を意味し、失業率の低下開始後も非自発的パートタイム労働者の増加という形でしばらくの間労働需給の緩みが残存することを示唆している。
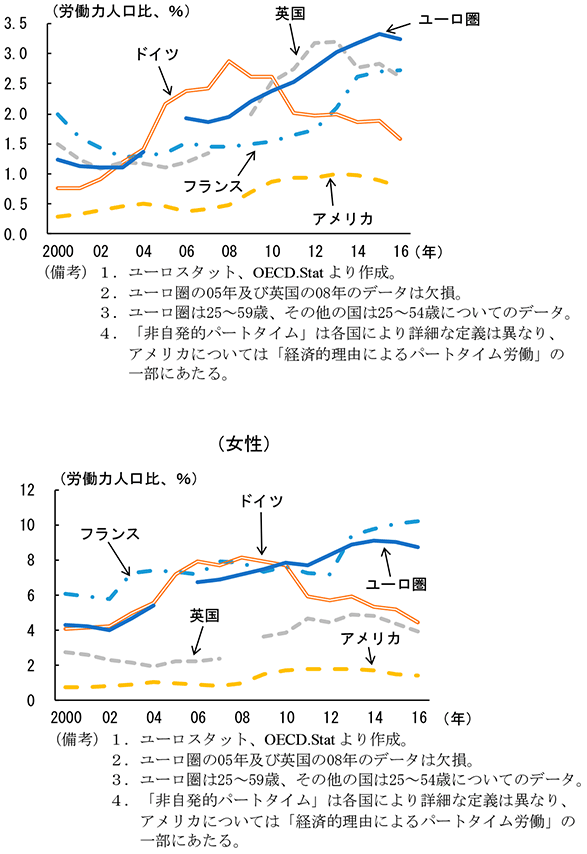
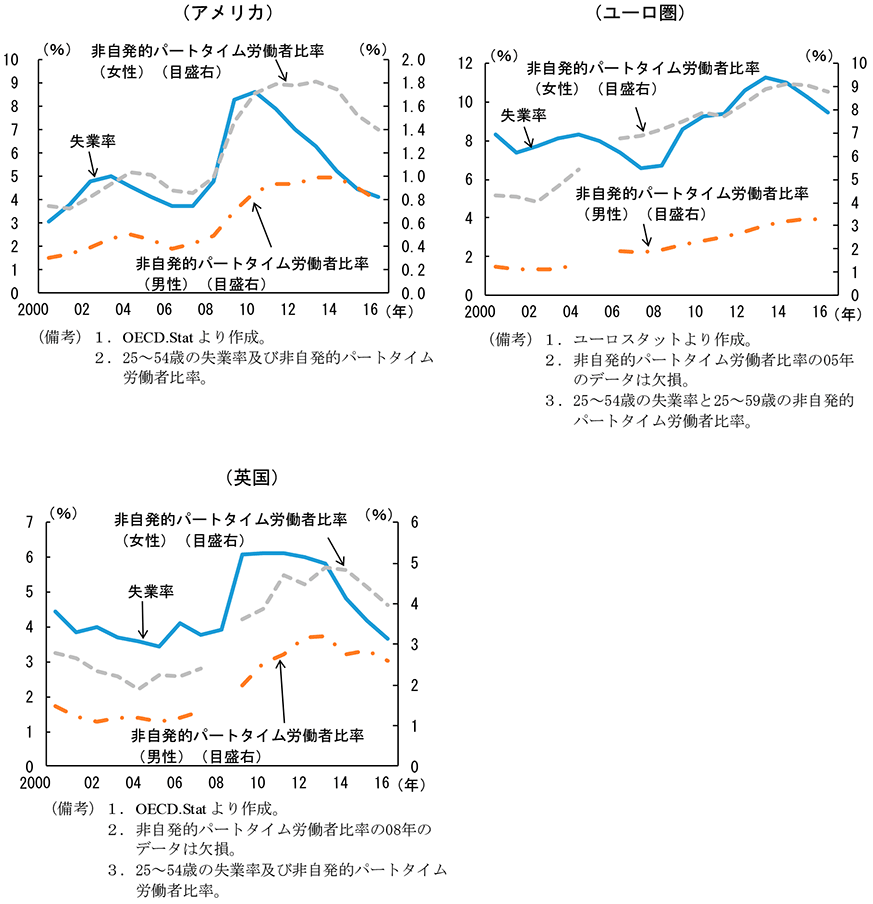
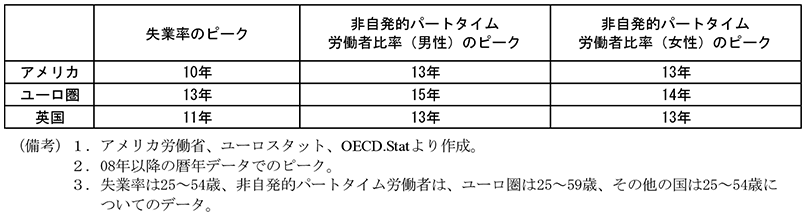
(労働需給の緩み:欧米主要国により差異が存在)
ここまで複数の指標から確認してきた欧米主要国・地域における労働需給の緩みの状況をまとめてみよう。失業率が低下しながらも賃金が伸び悩む状況は欧米主要国・地域で共通しているが、労働需給の緩みの状況には差異が存在する。
アメリカでは、過去三番目の長さに達するとみられる景気回復を背景に、失業率のみならず、広義の失業率や非自発的パートタイム労働者比率も低下し、リーマン・ショック前とほぼ同水準に達している。このため、残存する労働需給の緩みは小さいと考えられる。
ユーロ圏全体では、広義の失業率は近年低下傾向にはあるものの、依然として高い水準にあり、また、非自発的パートタイム労働者比率は、男性は15年、女性は14年をピークにようやく低下し始めた状況であることから、労働需給の緩みが一定程度残存し、その大きさはアメリカや英国よりも大きいとみられる。
ユーロ圏の中でもドイツは、広義の失業率や非自発的パートタイム労働者比率が、リーマン・ショックや欧州政府債務危機の影響を受けずに着実に低下しており、労働需給の緩みの縮小が確実に進み、残る需給の緩みは限られているとみられる。
フランスは、失業率の水準が過去と比較して依然高く、広義の失業率、非自発的パートタイム労働者比率ともに低下傾向を示すに至っていないことから、労働需給の緩みは大きく、ユーロ圏全体以上に存在するものとみられる。
英国では、広義の失業率の着実な低下がみられ、リーマン・ショック前の水準におおむね到達しており、また非自発的パートタイム労働者比率の低下もユーロ圏全体と比較して数年早く始まっていることから、労働需給の緩みも着実に縮小し、残る需給の緩みは小さいと考えられる。
2.労働生産性上昇率の鈍化
賃金の伸びには労働生産性の上昇が鍵とされる。労働生産性は、労働1単位当たりの付加価値を示しており、この上昇は、企業に対して賃金引上げの余地を与える。第1-2- 14図は、アメリカを例に1948年から2016年の長期にわたる労働生産性上昇率と賃金上昇率の関係をプロットしたものであり、これをみても両者の間に正の相関があることを確認できる。ここでは、欧米主要国・地域の労働生産性上昇率について、その動向を確認する。
まず、第1-2-15図は、71年以降の労働生産性上昇率の推移を示しているが、長期的にみて、これらの国・地域のいずれにおいても労働生産性上昇率が低下している。労働生産性上昇率は、TFP(Total Factor Productivity)19上昇率と資本装備率の伸び率の寄与との和20となることから、労働生産性上昇率の低下は、これらのいずれか、もしくは双方の低下が起きていることとなる。中島他(2016)は、95年から04年までと05年から14年までの先進国における労働生産性の伸びをTFPの要因と資本装備率の要因に分解し、その双方が鈍化していることを指摘している。また、OECD(2017a)は、特に金融危機後にOECD諸国で広くみられる労働生産性の低下について、投資全体の低迷に加え、ICT投資及び非ICT投資の双方において労働生産性への寄与が低下しており、資本装備率の伸びの低下が原因であると指摘している。
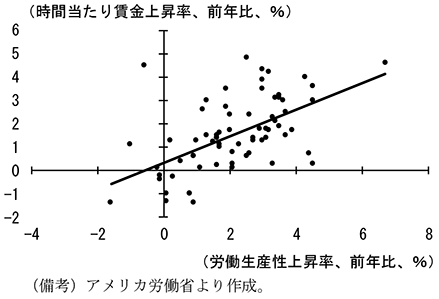
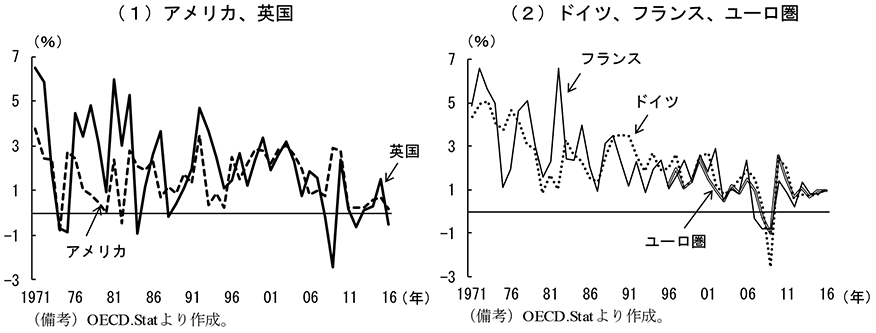
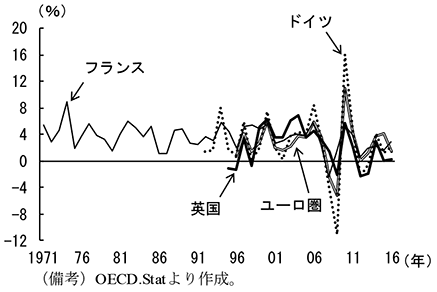
賃金の伸びと労働生産性の関係を把握するため、生産1単位当たりの賃金コストを表す単位労働コスト(ULC:Unit Labor Cost)を賃金要因と労働生産性要因に分解することもよくなされる(第1-2-17図)。第1-2-17図をみると、大きな傾向としては、各国・地域の労働生産性の低下に伴い、賃金の上昇も低下傾向にある。アメリカ、英国、フランス及びユーロ圏全体は、生産性要因の寄与が縮小していく中で、賃金要因も2000年代前半と比較して近年小幅の寄与にとどまっている。一方、ドイツでは、近年においても賃金要因による押上げが、2000年代前半の水準と変わらない点は注目に値する。この傾向は、業種を製造業に限定しても同様であり、英国、フランス及びユーロ圏全体は生産性要因と賃金要因の寄与がともに縮小していく中で、ドイツは賃金要因による押上げが2000年代前半から変わっていない(第1-2-18図)。
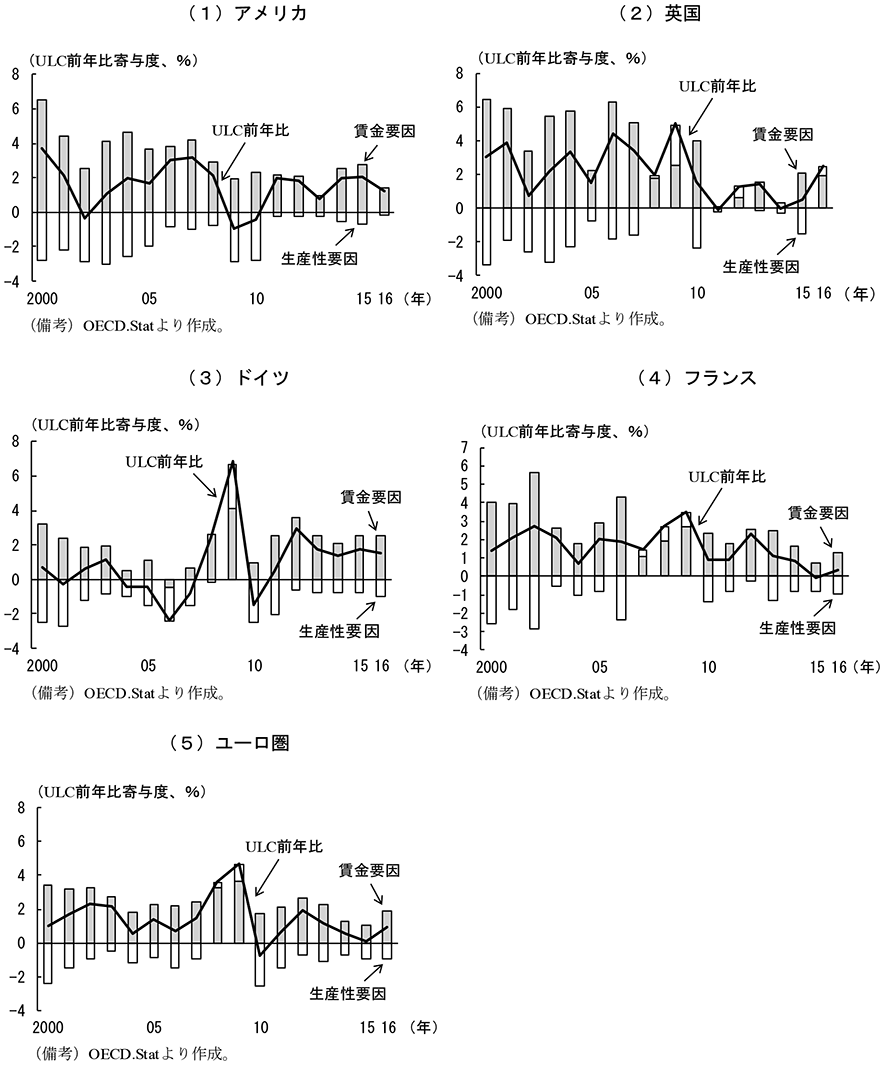
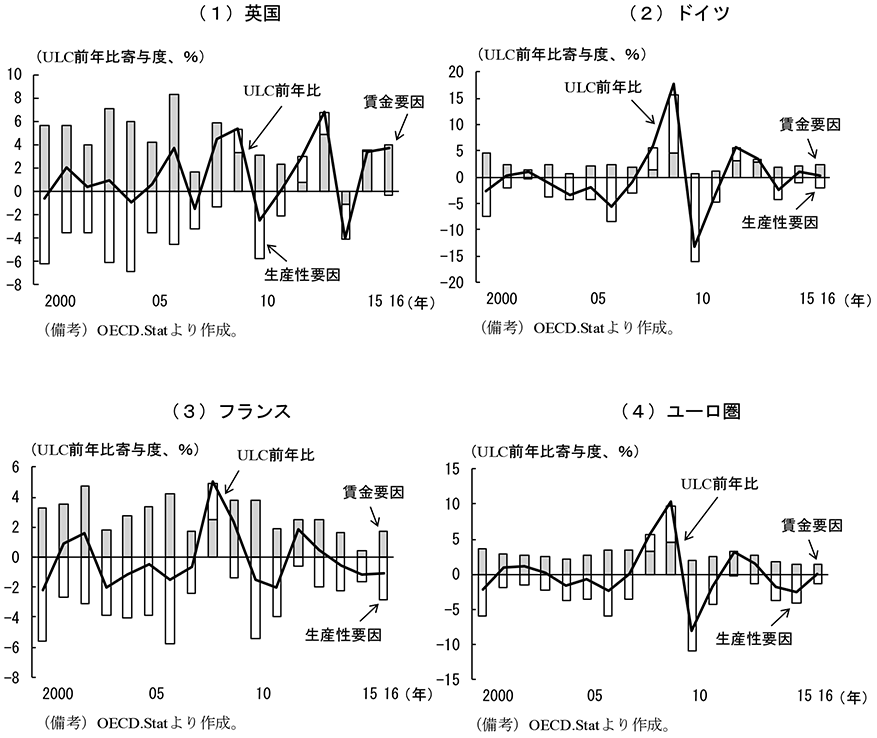
3.労働者の賃金交渉力の低下
労働市場における制度・政策は、賃金の動向に大きな影響を与える。ここでは、賃金交渉力に影響を与えうる要因として、欧米主要国における団体交渉とアメリカの非競争契約の動向について検証する。
(労働組合と団体交渉)
労働組合は、団体交渉により賃金等の労働条件を交渉する主体であり、賃金決定に大きな影響を与えている。労働組合の組織率の低下は、労働者の賃金交渉力を弱める可能性があり、賃金上昇の抑制要因となり得る。欧米の労働組合の参加率をみると、85年以降、多くの国で一貫して低下傾向を示している(第1-2-19図)。OECD(2017b)は、その要因として、労働組合組織率が高いとされる公的部門の縮小や、全組合員の25%21を占める製造業の縮小、より柔軟な雇用契約の増加といった点を挙げている。
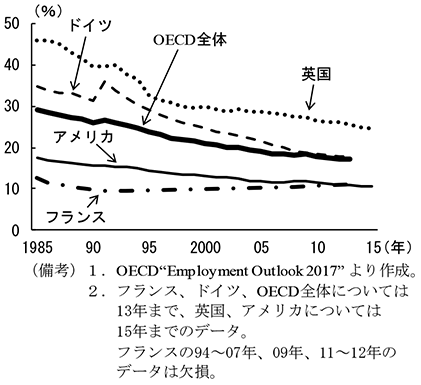
しかし、労働組合組織率が、そのまま団体交渉の結果を受け締結される労働協約の適用範囲を示しているとは限らない。労働組合組織率が低い場合でも、団体交渉の適用率が高ければ、団体交渉を通じた賃金上昇は、広範囲の労働者に適用されることとなる。団体交渉の適用範囲が広いほど、実質賃金が経済成長により有意に相関するとの分析もある22。また、ヨーロッパについては、企業内で労働協約が適用される労働者の割合が高いほど、賃金低下の可能性が低く、賃金上昇の可能性が高いとの指摘もある23。そこで、団体交渉適用率をみると、OECD全体では長期的に低下傾向にあるが、適用率が高水準にある国と低下傾向にある国に二極化している(第1-2-20図)。
この二極化は、団体交渉が主として行われるレベル(産業・企業)の違いが影響しているものと考えられる。企業レベルの交渉よりも、産業レベルの交渉の方が、より広範な労働者に交渉結果が適用されることになる。団体交渉適用率の高いドイツやフランスを含む大陸ヨーロッパでは、産業レベルでの団体交渉が主流であるのに対し、適用率の低いアメリカや英国では、企業レベルでの団体交渉が主流となっている(第1-1-21表)24。
また、団体交渉適用率は、労働政策の変更によっても大きな影響を受ける。フランスでは82年の労働法改革(オルー改革)により、産業レベル及び企業レベルそれぞれについて、一定の事項の団体交渉を法律で義務付けた。これを受け、80年代に団体交渉適用率が大幅に上昇し、近年は90%を超える水準に達している。他方、英国では、80年代に保守党政権による労働組合への規制強化や公共部門の民営化が進められたことを受け、産業レベルでの団体交渉が減少し、団体交渉適用率も大幅に低下した。ドイツでは、90年の東西ドイツ統一以降、製造業からサービス業への産業構造の変化により、労働組合組織率が低下したことが団体交渉適用率の低下に影響したといわれている。
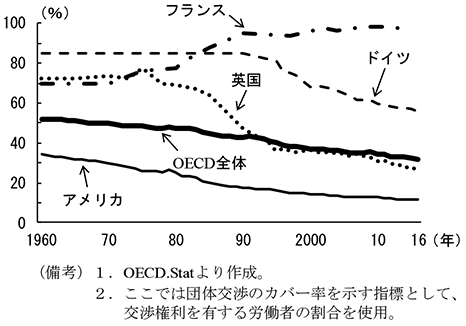
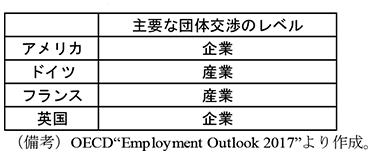
アメリカ及び英国では、労働組合組織率や団体交渉適用率が示すように労働者の賃金交渉力が低下していると考えられる一方、フランスとドイツでは依然として団体交渉や労働協約が賃金決定に重要な役割を果たしているとみられる。
(賃金低下に影響を与えうる雇用契約:アメリカの非競争契約)
雇用契約の中には、労働者の賃金交渉力の低下をもたらす可能性があるものも存在する。そうしたものの一つとして、アメリカにおける非競争契約(non-compete agreement)が挙げられる25。非競争契約とは、雇主と労働者との間の雇用契約で、当該労働者が競争相手である他企業に転職することを離職後一定期間禁止するものである。非競争契約がもたらす主な社会的・経済的利益としては、企業秘密が保護されることによりイノベーションが促進されることや、労働者の転職可能性の低下に伴い労働者に対するトレーニング実施のインセンティブが高まることが挙げられる。他方、社会的・経済的不利益としては、労働者の賃金交渉力低下による賃金の低下、雇用流動性の低下による労働市場の効率性の毀損といった点が挙げられる。
非競争契約と賃金との関係を具体的にみると、非競争契約は、労働者が現在雇用されている企業にとって競争相手となる企業からの転職オファーの受諾を妨げる契約であるため、雇用されている企業との賃金交渉を困難にするほか、当該企業外でのキャリア形成を妨げることを通じて賃金の伸び率と初期の賃金の低下に寄与すると指摘されている。例えば、アメリカ財務省の分析によれば、非競争契約の適用が標準偏差一単位増加した場合、賃金が1.4%低下するとの結果が得られている。
非競争契約はアメリカで広く活用されており、14年時点で、労働者の18.1%が非競争契約の下で働いており、38.1%はこれまでのいずれかの時点で非競争契約を結んだ経験がある26。なお、企業秘密の保護が非競争契約の理由であるとすれば、契約の対象は高学歴・高収入の労働者に偏ると考えられ、実際に非競争契約を締結した経験がある労働者の割合は、四年制大学卒の学位以上を持つ労働者で45.4%、年収100,000ドル以上の労働者で56.1%と半数近く又はそれ以上に上り、14年現在、非競争契約を締結している割合も、前者が26.6%、後者が36.5%となっている。他方、低学歴・低収入の労働者についても、四年制大学卒の学位を持たない労働者の34.7%、年収40,000ドル以下の労働者の33.3%が非競争契約を締結した経験を有し、14年現在も前者の14.3%、後者の13.5%が非競争契約を締結している(第1-2-22図)。
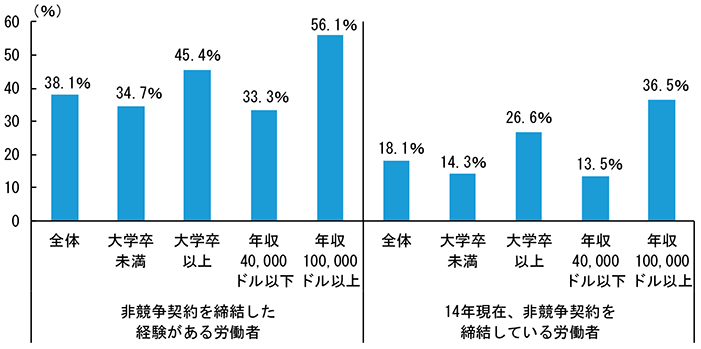
4.予想インフレ率の低下
賃金の伸びをみる上では、予想インフレ率の動向を把握することも重要である。労働者は、インフレによる購買力の低下を避けるべく、賃金交渉を行うことから、予想インフレ率の上昇は、賃金の上昇につながる。
予想インフレ率については、主に市場ベースと調査ベースの大きく分けて2つの情報源がある。市場ベースの予想インフレ率は、インフレ連動債やインフレスワップ金利の動向から市場参加者の予想インフレ率を計算するものであり、調査ベースの予想インフレ率は、消費者、企業又はエコノミストに直接、予想インフレ率を聴取したものである。以下では、アメリカ、ユーロ圏及び英国について予想インフレ率がどのように推移しているかをみていく。
(アメリカの予想インフレ率)
アメリカの市場ベースの予想インフレ率をブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)27でみると、14年ごろから低下し始め、16年ごろに上昇に転じたが、17年後半においても、2%を下回り低水準となっている(第1-2-23図)。
次に、調査ベースの予想インフレ率をミシガン大学の消費者を対象とした調査により確認する。ミシガン大学の調査では、1年先と5年先の予想インフレ率は、ともに10年代半ばから低下傾向を示しており、17年後半においても3%を下回り過去と比べて低い水準にとどまっている(第1-2-24図)。
このように、アメリカの予想インフレ率は、市場ベースでみても調査ベースでみても、長期的に低下傾向を示しており、直近でも低い水準にとどまっている。
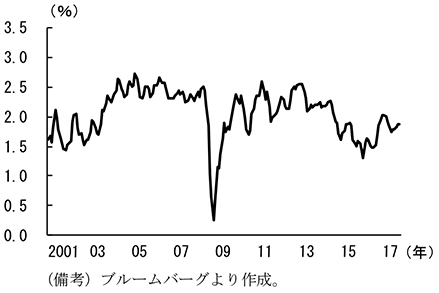
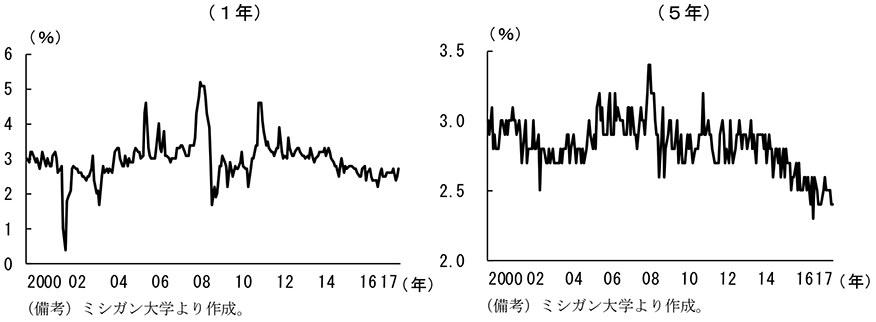
(ユーロ圏の予想インフレ率)
次に、ユーロ圏の予想インフレ率を確認していく。市場ベースの予想インフレ率のうち、ECB(欧州中央銀行)が注目しているとされる指標として、インフレスワップ・フォワードレート(5年先5年物)28がある。これは、5年後から5年先のインフレ率についての市場関係者の予想を示すものである。インフレスワップ・フォワードレートは、14年半ばまではおおむね2%を超える水準であったが、その後は低下傾向を示し、17年には2%を切る水準で推移している(第1-2-25図)。
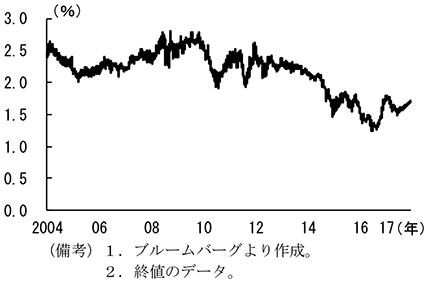
ECBが重要視する調査ベースの予想インフレ率として、ECB 経済予測専門家調査(Survey of Professional Forecasters (SPF))がある。SPFは、EU圏内の金融及び非金融機関に所属するエコノミストが予測するインフレ率を調査したものである。1年先の予想インフレ率は、世界金融危機時に1%近辺まで大きく下落し、その後上昇したが、13年以降再び下落した。15年入り後は再び上昇傾向にあるものの、17年時点で1.5%程度にとどまっている。5年先の予想インフレ率については、1.8~2.0%の間の比較的安定した動きとなっている(第1-2-26図)。
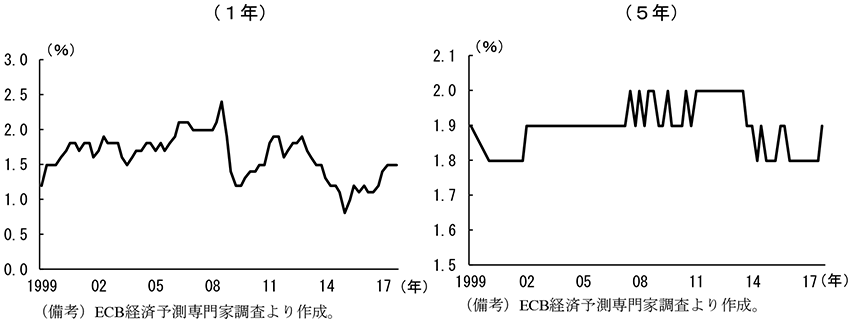
また、欧州委員会は、消費者に対し、過去12か月と比較した、今後12か月の消費者物価の見通しを調査している。これをみると、2000年代はじめまでは、「過去12か月と同程度に上昇する」と答えた者の割合が「横ばいとなる」と答えた者の割合を大きく上回っていたが、2000年代半ば以降は「横ばいとなる」の割合が高くなる局面がみられるようになり、ここ数年は、「横ばいとなる」の割合が大きく上昇し、「過去12か月と同程度に上昇する」と同程度の割合となっている(第1-2-27図)。
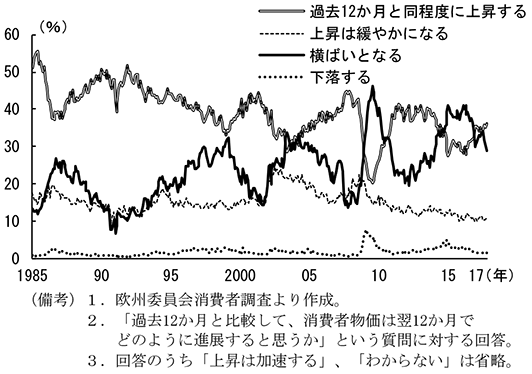
このようにユーロ圏においても、市場ベース、調査ベースともに長期的にみて予想インフレ率が低下傾向にあるといえる。
(英国の予想インフレ率)
英国の市場ベースの予想インフレ率をブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)でみると、14年ごろから低下し始めたが、16年ごろに上昇に転じ、17年はおおむね3%前後で横ばいとなっている(第1-2-28図)。また、インフレスワップ・フォワードレート(5年先5年物)は、13年の3.5%を超える水準から16年後半の2%台へと低下傾向を示していたが、17年はおおむね3.5%前後で推移している(第1-2-29図)。
英国の調査ベースの予想インフレ率をイングランド銀行(BOE)のインフレ態度調査(Inflation Attitudes Survey)により確認する。インフレ態度調査は、消費者に対して、小売店が1年先と5年先にどの程度価格を上げると予想しているかを調査したものである。1年先の予想インフレ率は、2000年以降おおむね2~4%の間で推移しており、11年には4%を超えていたが、その後2%を切る水準にまで低下した。16年ごろからは再び上昇し、3%程度となっている。5年先の予想インフレ率については、09年以降おおむね3%を超える推移となっている。13年ごろから低下傾向を示し3%を下回ったものの、15年ごろに上昇に転じ3%を上回っている(第1-2-30図)。
このように、英国では、一時的に予想インフレ率が低下する局面もみられるが、長期的な低下傾向は認められない。

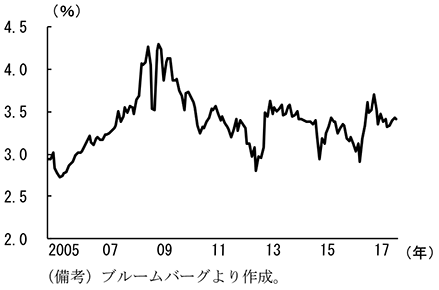
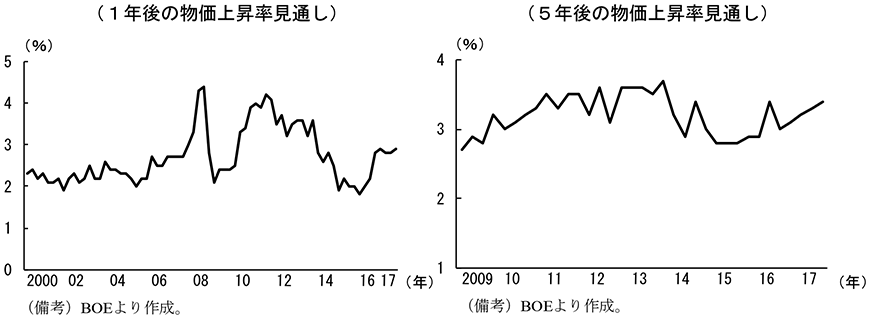
5.労働者のモビリティの低下
労働者のモビリティ(流動性)の低下が、賃金上昇を抑制しているのではないかとの議論がある。これは、転職が労働市場のマッチングの改善や、低生産性企業から高生産性企業への労働の再配分を通じて、労働者の賃金の上昇につながるとされているためである29。また、転職率の上昇は、雇主が労働者の転職を防ぐために賃金引上げ圧力にさらされやすくなることも意味する30。
(アメリカにおける労働者のモビリティの状況)
Hyatt and McEntarfer (2012)によれば、98年から10年にかけての転職による賃金の上昇率(中央値)は、特に30歳以下の若年層で高く、41~55歳では2~5%の上昇にすぎないのに対し、21~30歳では12~16%に上るとのことである。このため、特に若年層の転職率が低い場合には、賃金上昇率を抑制する可能性がある。
まず、2000年以降のアメリカの年齢階層別の転職率の状況について確認する(第1-2- 31図)。転職率は若年層(14~24歳)が最も高くなっているが、いずれの年齢層においても世界金融危機を契機に大きく落ち込んでいる。しかしその後は、景気回復とともに徐々に転職率も上昇し、16年には全ての年齢階層において、ほぼ世界金融危機前の水準に戻っている。
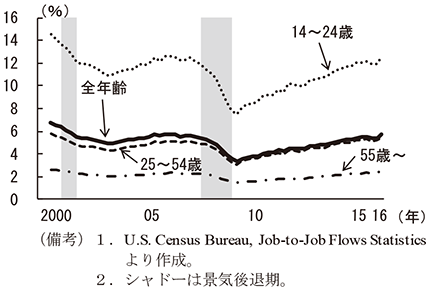
次に、ベビーブーマーの退職や少子化・高学歴化といった人口構成の変化の影響をみるため、前回の景気の山である07年10~12月期以降の転職率の変化を(1)各年齢階層の全雇用者数に占めるシェアの変化(人口構成要因)と(2)各年齢階層の中での転職率の変化(転職率要因)に分解してみる31。これをみると、転職率の低下は、おおむね25~54歳と14~24歳の「転職率要因」がマイナスに寄与したことによる。14~24歳と25~54歳の「人口構成要因」はマイナスに寄与しているものの、その影響は大きくないことから、ベビーブーマーの退職や少子化・高学歴化の影響は限定的と考えられる(第1-2-32図)。
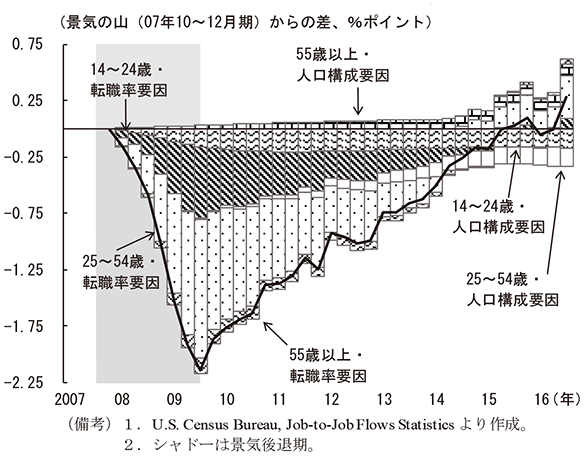
以上を踏まえるとアメリカでは、労働者のモビリティの低下は、世界金融危機以降しばらくの間は、賃金上昇率の押し下げに寄与した可能性があるが、15年以降大きな要因にはなっていないと考えられる。
(英国における労働者のモビリティの状況)
英国における転職率の状況を確認する。英国における転職率もアメリカと同様、世界金融危機を契機に大きく落ち込んだ。その後の景気回復局面では、転職率は上昇し、16年以降は金融危機直前とほぼ同水準に達している(第1-2-33図)。このため、英国でもアメリカと同様、労働者のモビリティの低下が近年の賃金上昇率の低下の要因とはなっていないといえる。
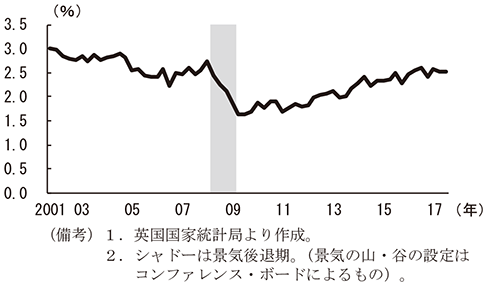
6.技術革新による影響
近年、財、サービス、情報等のインターネットを介しての流通が加速する中、新しい技術革新が進展している。最近では例えば、モノのインターネット化(IoT:Internet of Things)、ビッグデータ、人工知能(AI:Artificial Intelligence)、ロボットの導入が注目されている。
AI等の最新の技術革新が短期的に雇用や賃金にもたらす影響に関しては様々な議論がある。労働市場への影響に関連して、短期的に雇用が喪失される可能性も指摘されている。ただし、中心的に雇用が失われる層がどこなのかについては、様々な見解が存在する。アメリカ大統領府(Executive Office of the President)(2016)は、低賃金・低学歴の職種の方が、高賃金・高学歴の職種と比較して、AI等による自動化の影響を大きく受けると指摘している。OECD(2016)は、デジタル技術の進展は、業務がルーチン化された職種を代替する一方、業務がルーチン化されていない職種に関しては、デジタル技術が職務の推進を助けると指摘している。さらに、業務がルーチン化されていない職種には、管理職等の高賃金層や手作業を要する低賃金層の両方が含まれ、業務がルーチン化された職種には、予約管理等の主に中賃金層が含まれるとしている。このことは技術革新が、高賃金層と低賃金層への二極化をもたらす可能性を示唆している。また、自動化に関しては、「業務の自動化=雇用の喪失」では必ずしもない点に注意が必要である。Arntz et al. (2016)は、OECD加盟国のうち21か国について分析を行い、自動化により完全に代替される職はわずか9%であるとの結論を得ている。この理由については、技術革新が実際に活用されるまでには時間を要し、また多くの労働者は求職活動のサポートや職業訓練を受けることで、技術革新が創出した分野を含む新たな業務を担うことができるためとしている。
また、デジタル技術の進展は、特定の職種の賃金上昇につながることも考えられる。例えば、情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)専門家といった高度な技術を要する労働者の賃金は上昇する可能性がある。これは、デジタル技術の進展に伴い、ICT専門家に対する需要が供給を上回る状況となり、雇主が必要な技術者を見つけることが困難になるためである32。
他方で、技術革新が労働者の賃金交渉力の低下につながるとの議論もある。BIS(2017)は、ロボット等による自動化が、製造業に従事する労働者のみならず、ソフトウェアの開発や情報技術の進展による知識の自動化を通じて、サービス業の労働者の賃金交渉力の低下にも寄与すると指摘している。また、OECD(2016)は、シェアリング・エコノミーといった技術革新がもたらした新たな業態が、賃金交渉を阻害しているとしている。シェアリング・エコノミーにおいて、プラットフォーム上で財やサービスを提供している者は、当該プラットフォームの運営者(雇主)との間で、一時雇用契約や独立した契約を結んでいる場合が多く、組織化されていない。このため、団体交渉を行うことができず、正規雇用者と比較して低い賃金で働く状況に陥る傾向があると指摘している。
このように、IoT、ビッグデータ、AI、ロボットといった技術革新が雇用や賃金に与える影響については、低・中賃金の雇用の喪失、賃金の二極化、ICT専門家など一部職種での賃金上昇、団体交渉を通じた賃金交渉力の低下等様々な点が指摘されており、現段階では、賃金上昇率への影響について一概に結論づけることができない。
長期的には、過去の技術革新と同様、こうした新しい技術革新は、適切な職業訓練や教育、労働移動の促進を伴えば、雇用の創出や賃金の上昇につながると考えられる。過去の技術革新については、短期的には雇用の喪失をもたらしたものの、長期的には生産性の向上や報酬がより高い雇用の創出につながり、労働市場に対しプラスの効果が大きいとの見方が多い。最近の技術革新の中でもICTの導入に関してOECD(2017d, 2017e)は、技術革新により失業が増加したことはなく、またICTへの投資は長期的な労働需要に影響を与えていないとしている。
最新の技術革新は、短期的には雇用の喪失、賃金の二極化等、労働市場にマイナス面をもたらしうるが、長期的に雇用の創出や賃金の上昇につながるために労働市場政策や教育政策が重要である。例えば、新技術により職を失う労働者への職探し(active job search)の支援や適切な所得補助、新技術に対応するための職場での訓練や生涯学習のための効率的なシステムの構築、人々が必要な時にアクセス可能な再訓練の整備といった政策が有用と考えられる33。
7.賃金伸び悩みの要因:欧米主要国共通の要因と違い
本節では、欧米主要国・地域における賃金の伸び悩みの要因とされている事項について検証してきた。各要因について各国・地域の状況を検証した結果は、第1-2-34表のとおりである。近年の欧米主要国・地域の賃金上昇率の伸び悩みは、複合的な要因によるものであり、各要因の影響の大きさについては、各国・地域により差異があると考えられる。
各国・地域に共通の要因としては、労働生産性上昇率の鈍化が挙げられる。また、英国を除く国・地域で予想インフレ率が低下している点もほぼ共通していると言えるだろう。
他方、労働需給の緩みと労働者の賃金交渉力の低下については、国・地域によりまちまちである。労働需給の緩みについては、アメリカ、ドイツ及び英国で相当程度縮小してきているとみられる一方で、ユーロ圏全体とフランスでは、依然需給の緩みが存在すると考えられる。労働者の賃金交渉力については、アメリカと英国ではかなりの程度低下してきている一方で、フランスでは依然高い交渉力を、ドイツでも相当程度の交渉力を有すると考えられる。
国・地域ごとに要因を整理すると、アメリカでは、労働生産性上昇率の低下及び予想インフレ率の低下のほか、労働者の賃金交渉力の低下や非競争契約のような制度の存在が、賃金上昇の妨げになっている可能性がある。なお、アメリカでは労働需給の緩みは小さいと考えられる一方、積極的労働市場政策や仕事と育児・介護の両立支援策の不足、プライムエイジの者が抱える健康問題といった構造的問題から、労働参加率がヨーロッパと異なり男女共に低下傾向にあるという課題も存在する。
英国は、予想インフレ率が上昇し、労働需給の緩みは縮小しているものの、労働生産性上昇率及び労働者の賃金交渉力は低下しており、こうしたことが賃金伸び悩みの一因となっている可能性が考えられる。
失業率が依然高水準にあるユーロ圏全体とフランスでは、労働生産性上昇率の低下や予想インフレ率の低下とともに、労働需給の緩みの存在が賃金伸び悩みに影響していると考えられる。
ドイツでは、労働需給の緩みは確実に縮小しており、労働者の賃金交渉力もアメリカや英国と比べると高いことから、労働生産性の伸びの低下が、賃金伸び悩みの一因と考えられる。
また、AIやビッグデータ等の新しい技術革新の賃金への影響について、欧米主要国・地域間での差異の有無は明らかではないが、そうした技術は短期的には、低・中賃金の雇用の喪失、賃金の二極化等を通じて賃金に影響を与えうる。しかし長期的には、適切な職業訓練や教育、労働移動の促進を伴えば、技術革新による生産性の向上が賃金上昇につながると考えられる。
以上より、先進国においては、賃金上昇のためにも労働生産性向上に向けた取組が共通して重要であると言える。それに加え、各国・地域の実情に応じた適切なマクロ経済政策に加え、労働市場政策も必要である。労働需給の緩みが賃金伸び悩みに影響していると考えられるユーロ圏全体やフランスでは、就業を希望する潜在労働力が就業し、非自発的パートタイム労働者がフルタイム労働に移行することを助ける求職活動支援や、職業訓練といった積極的労働政策が重要である。労働需給の緩みが小さいものの労働参加率が低下しているアメリカでは、潜在労働力以外の非労働力となっている者もヨーロッパと比較して多いと考えられ、そうした者を労働力化するための社会政策が必要と考えられる。
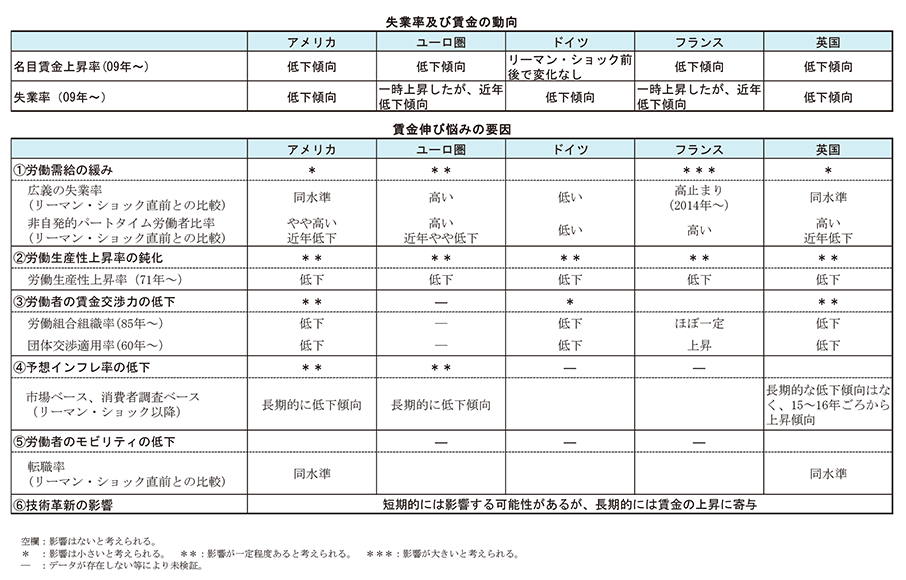
Y=A(KS)α(LH)(1-α)
となる。両辺を総労働投入量LHで除し、対数をとると、
ln(Y/LH)=lnA+αln(KS/LH)
となる。すなわち、労働生産性の伸び率は、TFP上昇率と資本装備率の伸び率の寄与の和となる。