第1章 第2節
回復の続くアメリカ経済
1.回復の続くアメリカ経済
アメリカ経済は、雇用環境の改善が個人消費の増加に結び付く好循環が形成されており、景気は回復している。2014年1~3月期には大雪・寒波の影響等もあって実質経済成長率は前期比年率▲2.1%と大きく落ち込んだものの、4~6月期は同4.6%、7~9月期には同3.9%と回復が続いている(第1-2-1図)。需要項目別にみると、個人消費や設備投資が堅調に推移している一方、住宅投資の回復は遅れている。
また、アメリカは他の先進国と比較して、おおむね高い成長率を維持しており、世界経済をけん引する役割が期待されている。
金融政策では、景気回復に伴って金融政策の正常化に向けて舵が切られ、連邦準備制度(Fed)は13年12月に資産購入プログラムの縮小を決定した。以降、資産購入額は連邦公開市場委員会(FOMC)が開催されるたびに100億ドルずつ減額され、14年10月に資産購入プログラムの終了が決定された。今後は政策金利の引上げを模索する段階に入っている。
本節では、アメリカ経済について、景気回復のメカニズムを明らかにするとともに、世界金融危機を経たアメリカ経済の構造がどのように変化してきているのかを概観する。
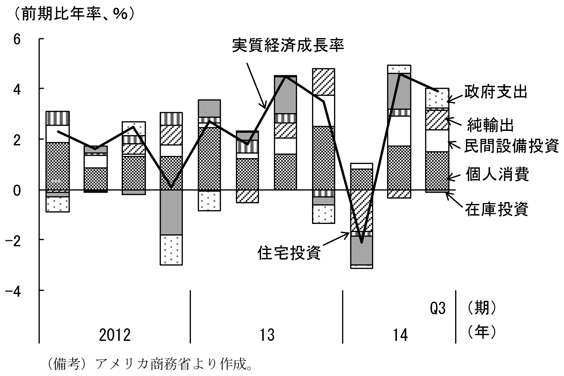
アメリカ経済は、09年6月を景気の谷として、すでに5年以上回復局面にある。
景気回復の初期には大規模な景気刺激策や新興国の需要拡大による新興国向けの輸出が景気を下支えしていた。また、家計のバランスシート調整が続く一方で、各種の政策効果が個人消費を下支えしていた。一方、雇用者数は、技能のミスマッチに加えて地域のミスマッチがあり、10年半ば過ぎまでは増減を繰り返していた。住宅価格の低下によって、住宅の売却で損失を被る世帯が多く、職の豊富な地域への移住が困難であった。これらのミスマッチに改善の兆しがみられるようになってきたため、雇用者数は10年末ごろから増加傾向が明確になった。
過去の回復局面と比較すると、実質GDPは過去よりも弱いテンポの回復となっている(第1-1-2図(1))。一方、雇用者数は、景気が谷となってから1年弱は減少が続きジョブレス・リカバリーの様相を呈していたものの、その後は前回の回復局面(01年11月~)を上回るテンポで回復している(第1-2-2図(2))。企業収益や株価については、総じて過去と同程度のテンポの回復となっている(第1-2-3図)。
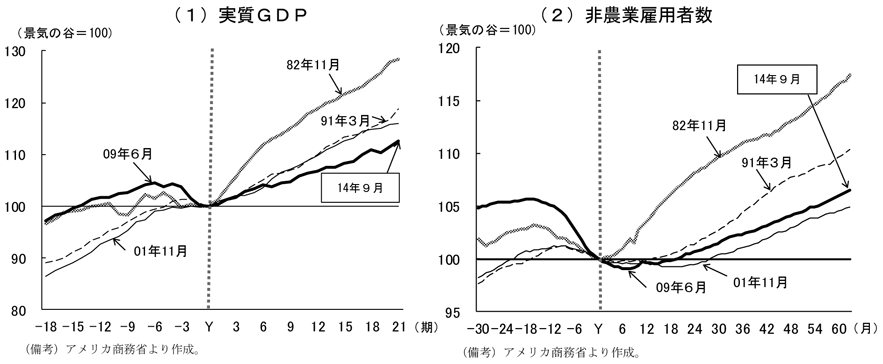
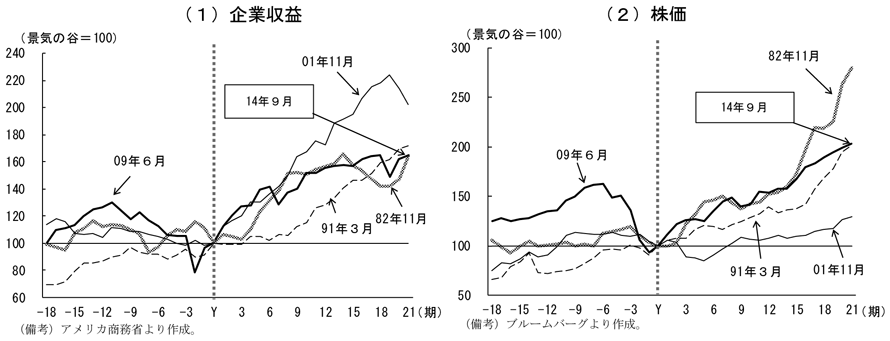
(1)スラックが減少しつつある雇用情勢
(i)改善を示す指標の多くなってきている雇用情勢
14年11月現在、アメリカ経済の回復を支えているのは、雇用情勢の改善である。
イエレン連邦準備制度委員会(FRB)議長が政策判断の際に重視するとみなしている9つの雇用関連指標(いわゆる「イエレン・ダッシュボード」)をみると、14年7~9月期は同年1~3月期と比べて、労働参加率以外の指標は改善している(第1-2-4表)。
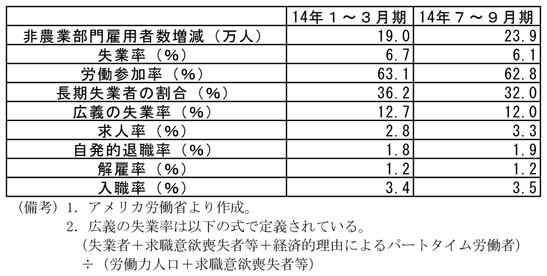
こうした広範な雇用関連指標が改善していることなどから、14年10月のFOMCにおいて労働市場の判断が「労働資源の未活用が著しい」から「労働資源の未活用が徐々に減少しつつある」に上方修正された。
雇用者数は14年5月に世界金融危機前のピークの水準まで回復し、その後も増加を続けている。14年7~11月には月平均で25.6万人増加しており、12年の18.6万人、13年の19.4万人、14年1~6月の22.8万人を上回るペースとなっており、雇用情勢の改善テンポが加速している(第1-2-5図)。
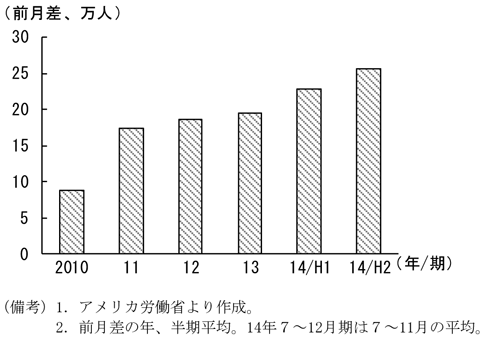
また、失業率は14年11月に5.8%(世界金融危機前の08年6月の水準)まで低下した。失業率を短期失業率と長期失業率(失業期間27週以上の失業者)に分けると、14年以降、短期失業率は緩やかに低下しており、長期失業率も低下している(第1-2-6図)。
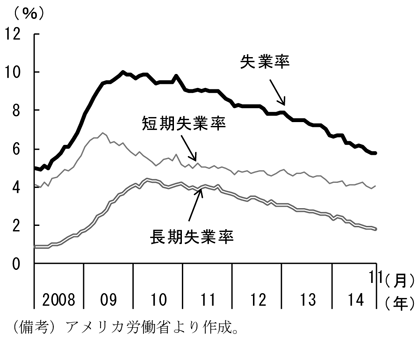
こうした雇用情勢の改善は、積極的労働政策(職業紹介や職業訓練等によって、失業者を労働市場に復帰させる政策)よりも労働市場の効率性に関係があるとみられる。アメリカの労働市場の効率性はほかの先進国と比較して高いと考えられる(第1-2-7表)。世界金融危機後の失業率の変化幅と労働市場の効率性をみると、労働市場の効率性が高い国は労働市場のダイナミズムが高く、失業率の改善幅が大きくなるという緩やかな関係がみられる(第1-2-8図)。一方、積極的労働政策のための財政支出(GDP比)をみると、アメリカはほかの先進国と比較して小さくなっている(第1-2-9図)。
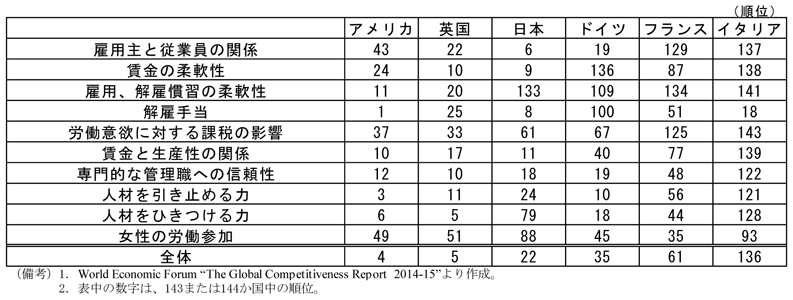
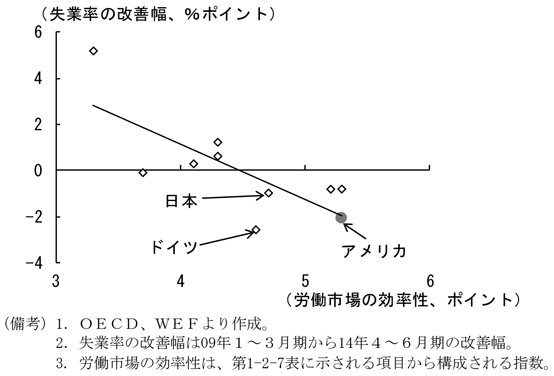
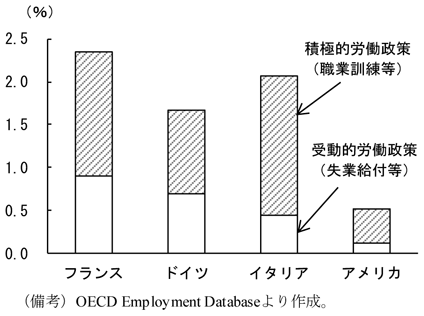
これまでは雇用者数等の雇用の「量」をみてきたが、次に雇用の「質」について検証する。まず、賃金の動きを分析する前提として労働分配率(名目GDPに占める名目雇用者報酬の割合)みると、世界金融危機後にやや低下した後、おおむね横ばいとなっている(第1-2-10図)。
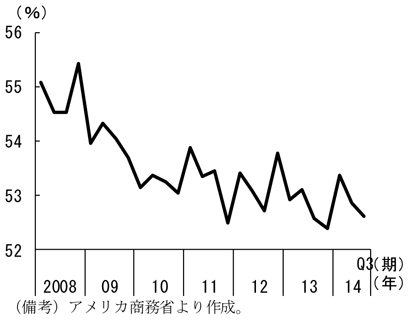
過去の景気回復局面では、短期失業率が4%程度まで低下すると賃金上昇圧力が強まる傾向がみられた1。14年4月以降、短期失業率はおおむね4%程度で推移しているものの、14年11月現在、時間当たり賃金の上昇率は前年比2%程度で推移しており、世界金融危機前と比較すると低い伸びにとどまっている(第1-2-11図)。
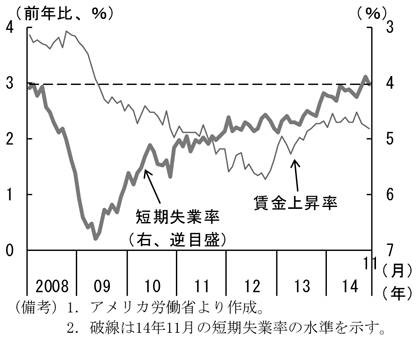
賃金の伸び悩みは第1節で分析したとおり、産業構造の変化やパートタイム労働者比率が影響していると考えられる。パートタイムを活用するインセンティブとして、フルタイムとパートタイムの便益費用(福利厚生や医療保険等)の差が指摘されている。フルタイムとパートタイム労働者の便益費用の比率をみると、11年以降拡大傾向にある(第1-2-12図)。
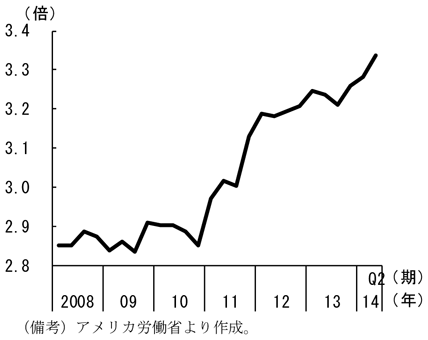
加えて、アメリカ特有の事情として、医療保険改革法の間接的な影響も指摘されている。同法は、国民の医療保険への加入を促進させることを目的としている。その一環として、週30時間以上勤務する労働者を50人以上雇用する企業に対して、労働者に医療保険を供与する義務を課している(この部分の完全施行は16年)。ニューヨーク連銀の調査(14年8月)によると、多くの企業が同法によって医療保険コストが増加すると回答している(製造業の81.4%、サービス業の73.0%が、15年の医療保険コストが少し/多く増加する見込みと回答)。またコスト増への対応として、2割程度の企業が(1)パートタイム労働者比率を高める、(2)労働者1人当たりの賃金及び便益費用を減少させるとしている2。
一方、同法には、企業保険でカバーされず保険会社の提供する医療保険に加入する低中所得者層に対して、所得水準に応じて補助金を支給する制度もある。これが、労働者がパートタイム労働を選択するインセンティブになるという分析もある3。
なお、議会予算局は、今のところ同法がパートタイム労働者比率を上昇させているという明確な根拠はないとしている4。
しかしながら、同法の影響もあってフルタイムとパートタイム労働者の便益費用の差は今後も拡大すると見込まれるため、この点がパートタイム労働者比率に与える影響を引き続き注視する必要がある。
現在の景気回復局面において、雇用吸収力が高い業種をみると、専門サービスや教育・医療、レジャー・接客業等がシェアを伸ばす一方、建設、製造業等はシェアが低下している(第1-2-13図)。
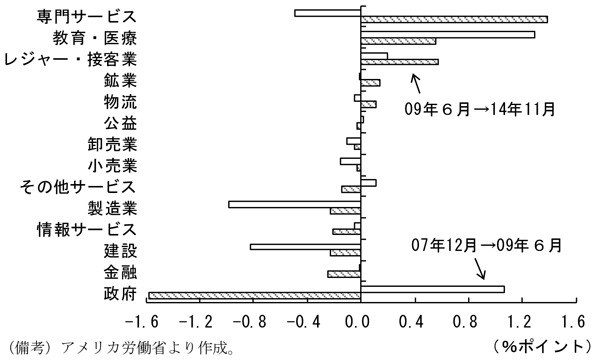
一方、フルタイム労働を希望しながらパートタイムを選択せざるを得ない労働者(経済的理由によるパートタイム労働者)の割合は、07年から13年にかけて全業種で上昇している(第1-2-14表)。雇用吸収力の比較的高いレジャー・接客業では経済的理由によるパートタイム労働者の割合が特に上昇しており、雇用の量の回復が質の改善を伴っていないことがうかがわれる。また、専門サービスのうち雇用者数のシェア増加に寄与しているのは人材派遣業であり、レジャー・接客業と同様に経済的理由によるパートタイム労働者の割合が上昇していると推察される。
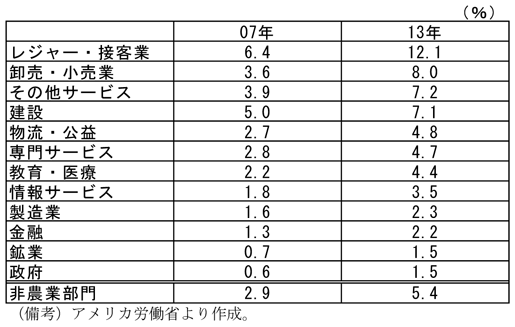
14年に入って経済的理由によるパートタイム労働者は依然として高い水準にあるものの、緩やかに減少している(第1-2-15図)。
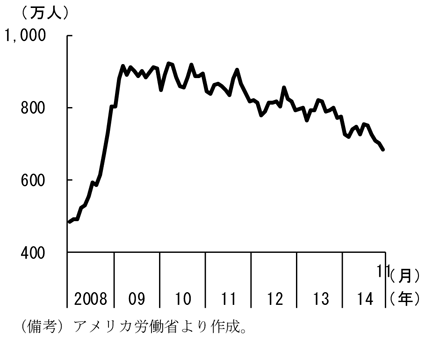
また、経済的理由によるパートタイム労働者は、パートタイム労働に従事している理由として「事業環境の悪さを挙げた者」と「パートタイム労働しか見つけることができなかった者」に大別することができる。「事業環境の悪さを挙げた者」は減少しているが、「パートタイム労働しか見つけることができなかった者」はおおむね横ばいで推移しており、前回の景気回復局面と比較しても高水準にある(第1-2-16図)。
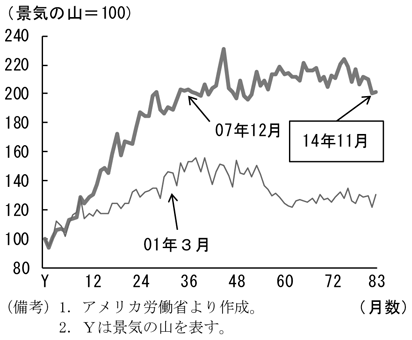
(ii)開業の雇用吸収力は低下
雇用情勢は上記でみたとおりスラックが減少しつつあり、改善が続いている一方で、中には今後の懸念要因となり得る動きも散見される。以下では、特に開業による雇用の創出と労働参加の状況について取り上げる。
企業の新陳代謝の高さはアメリカのダイナミズムを支える一因と考えられる。開業数の動向をみると、世界金融危機後に減少したものの、その後は01~07年の平均を上回る水準まで回復している(第1-2-17図)。
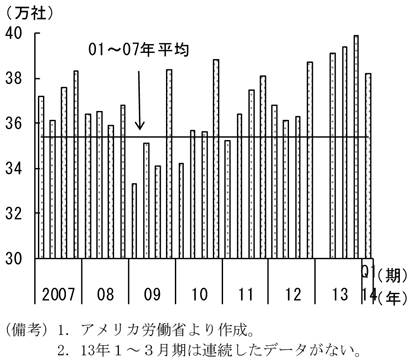
一方、開業による雇用創出効果をみると、1件当たりの雇用者数が減少していることから、開業による雇用者数は01~07年の平均以下の水準となっている。開業数の増加が雇用者数の増加をもたらすというメカニズムは弱くなっていると考えられる(第1-2-18図)
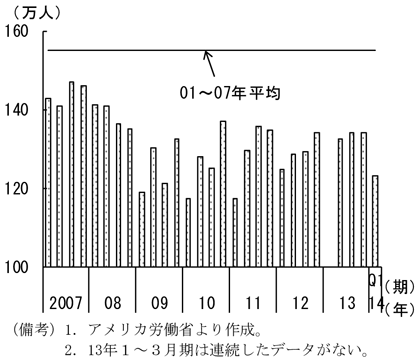
また、開業時の年齢をみると、若年層が若干減少している一方、高齢層が増加している(第1-2-19図)。若年層の起業マインドが低下すれば、柔軟な発想や最新の技術を活用した新しい製品・サービスが開発されにくくなるとも考えられ、産業の新陳代謝が停滞する可能性もあるため、今後の動向に注視が必要である。
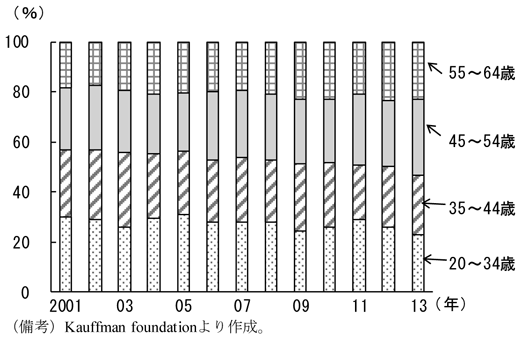
(iii)低下傾向にある労働参加率
労働参加率は高齢化の進展に伴って緩やかな低下傾向にあるものの、13年10月以降はおおむね横ばいで推移している(第1-2-20図)。議会予算局によると、07年から13年にかけての労働参加率の低下は、就職をあきらめた人や雇用のミスマッチによる循環要因と高齢化の進展による構造要因の両方に起因するとされている。雇用情勢の改善に伴い、就職をあきらめた者が労働市場に再参入する動きがみられる一方で、55~64歳の労働参加率は13年1月をピークに緩やかながら低下している。この年齢層は、世界金融危機による資産価値の減少や年金受給年齢の段階的引上げ等を背景にやむを得ず働いていたものの、住宅価格や株価の上昇による資産価値の回復もあって退職を選択するようになってきている可能性がある。
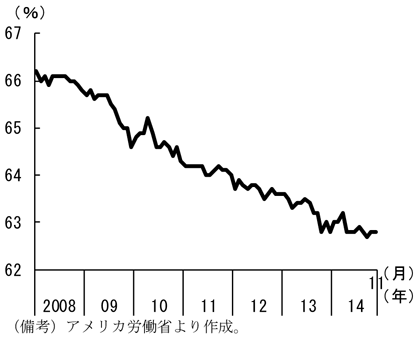
一方、65歳以上の労働参加率は、水準は低いものの緩やかに上昇している(第1-2-21図)。高齢化が進む中で労働参加率の低下は避けられないとみられるものの、高齢者の労働参加率が上昇していけば、労働参加率の低下を緩和することが期待される。
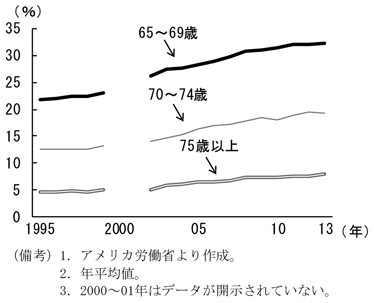
今後アメリカの高齢化が進む中で、高齢者の労働参加率は平均を下回っていることから、労働参加率は緩やかに低下すると予想されている(第1-2-22図)。労働参加率の低下は、労働供給の減少を通じて潜在成長力を低下させる懸念があるため、その動向に注視する必要がある。
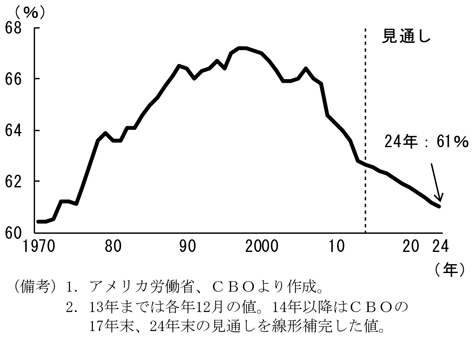
(2)家計部門の回復
(i)堅調な個人消費
(ア)可処分所得の増加
雇用情勢の改善は可処分所得の増加をもたらしている。雇用者報酬は13年にやや伸び悩んだものの5、14年に入って寄与が拡大している。世界金融危機後にマイナス寄与の続いた資産収入も11年以降はプラスに寄与することが多くなっている(第1-2-23図)。
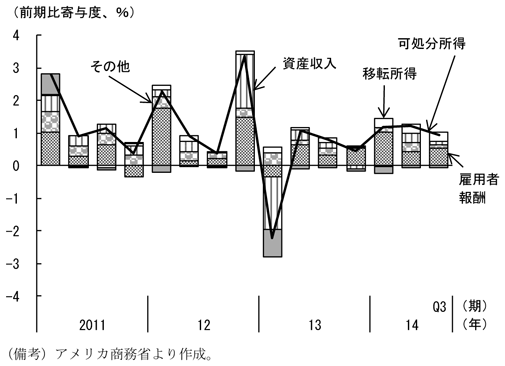
資産収入を配当と利子に分けてみると、企業業績の回復に伴い配当収入は増加している。また、金利は低水準にあるものの、利子収入も緩やかに増加している(第1-2-24図)。
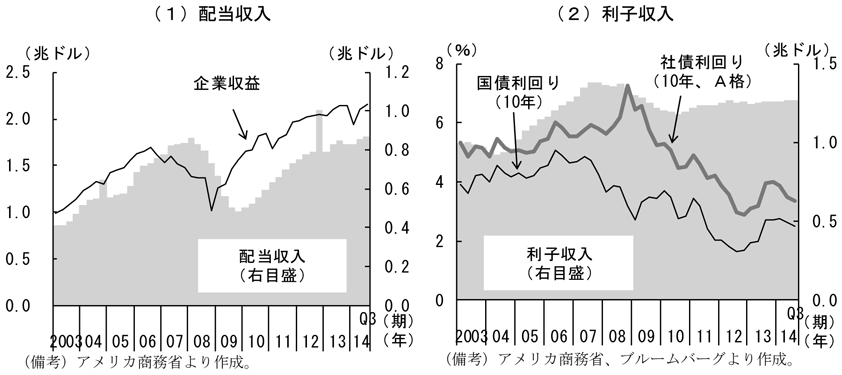
ただし、資産収入の増加を享受しているのは高所得者層に集中している。所得階層別(世帯数を所得順に20%ずつ分けたもの)にみると、所得第1分位の資産収入と第5分位の資産収入の比は13年には約40倍になっており、07年の約36倍から拡大している(第1-2-25図)。
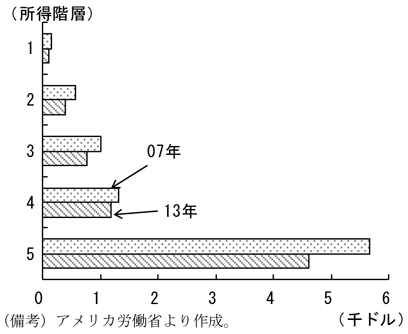
(イ)耐久財を中心に増加する個人消費
所得環境の改善に伴って、個人消費は10年1~3月期以降増加を続けている。耐久財の寄与度は13年には3割程度であったが、14年4~6月期以降、特に自動車がけん引して耐久財の寄与度が高まっている。ただし、同年1~3月期に寒波・大雪の影響もあって落ち込んだ自動車購入が4~6月期に行われた影響も一部にあるとも考えられる(第1-2-26図)。
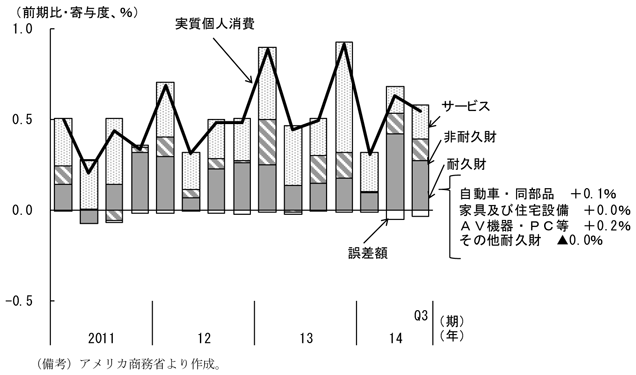
アメリカの個人消費に占める自動車・同部品の割合は3.5%程度であるものの、自動車販売は景気に敏感に動くことから注目されている。新車販売台数は、14年7~9月期の平均で年率1,672万台と、世界金融危機前の過去の10年間(99~08年)の平均(1,644万台)を上回って推移している。アメリカの車の平均使用年数は14年1月時点で11.4年となっており6、買替え需要が見込まれることから、自動車市場は当面堅調に推移すると予想される。
アメリカ人の消費行動に着目すると、借金をして消費するという消費行動が復活しつつあるとも考えられる。特に、オートローンの残高は、10年7~9月期を底に、14年4~6月期までに約3割増加しており、1兆ドルが目前となっている(第1-2-27図)。
さらに、オートローンのうち、サブプライムローンとディープ・サブプライムローン7の占める割合は、12年以降はおおむね横ばいで推移しているものの、ディープ・サブプライムローンの割合が若干の上昇傾向にある(第1-2-28図)。自動車は個人消費のけん引役になっているが、信用力の低い消費者への販売を拡大させて自動車市場を活性化させるのは持続可能とはいえない。また、サブプライムローンを担保とする債券のデフォルトが発生すれば、金融市場が動揺する可能性も否定できない。
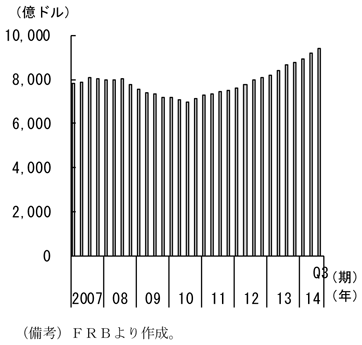
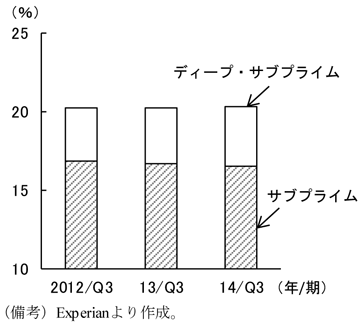
一方、ホームエクイティローン(持ち家の含み益を担保に借り入れ枠を設定する個人向け融資)の残高は低下傾向にあり、今のところ消費を押し上げる力は鈍い。もっとも、住宅価格の回復から含み損を抱える消費者は減少してきており、バランスシートの悪化を通じた消費押し下げ懸念は小さいと考えられる(第1-2-29図)。
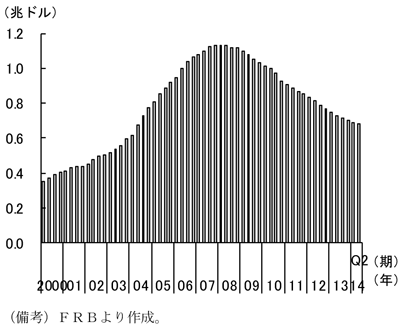
借金をしながら消費をするという、アメリカ人の消費行動は復活しつつあるものの、消費者ローンの伸びは緩やかであり、消費を大きく押し上げる力にはなっていないと考えられる。また、前節で分析したとおり賃金の伸びは緩やかにとどまっており、消費の増加を全て説明できるわけではない。そこで、10年から13年にかけての個人消費の増加を所得階層別にみると、第5分位(課税前所得が年間95,336ドル以上、13年)の寄与度が4割強を占め、最も高くなっている(第1-2-30図)。高所得層は資産収入の増加を享受しており、この層の消費が活発になっていることが消費全体を押し上げている一因と考えられる。また、前回の回復局面と比較すると、第3分位の消費寄与が低下しており、中間層の消費が伸び悩んでいることがうかがえる。これが後述する回復の実感にも影響しているとみられる。
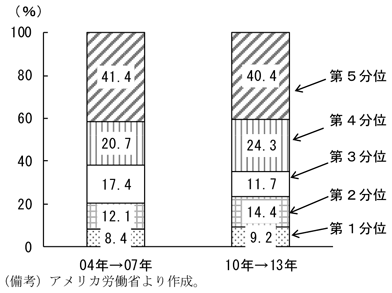
(ウ)回復の実感
アメリカ経済が回復し、個人消費が全体としては増加傾向にある中で、人々に経済の回復が実感されているかは消費者マインドの観点から注目される。世論調査によると、14年4月及び8月の両時点において「回復はしているがさほど強くはない」と感じている人が過半を占めている(第1-2-31図)。
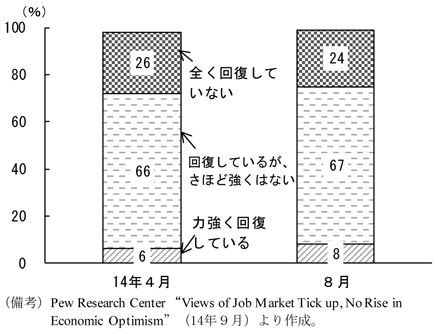
以下では、回復の実感を具体的なデータで確認する。まず、所得階層別の平均所得について世界金融危機前後を比較すると、すべての階層で増加しているものの、所得が高くなるほど、所得の伸び率も高いという傾向がみられる(第1-2-32図)。
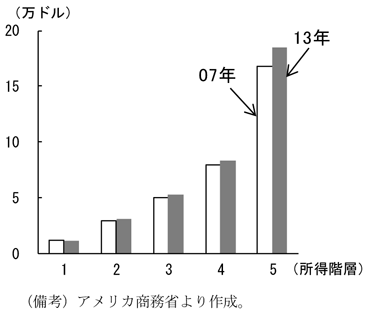
次に消費者マインドをみると、所得の実額と同様に、年収5万ドル以上の階層で顕著にマインドが改善しているが、所得階層が下がるほど改善が緩やかになっている(第1-2-33図)。
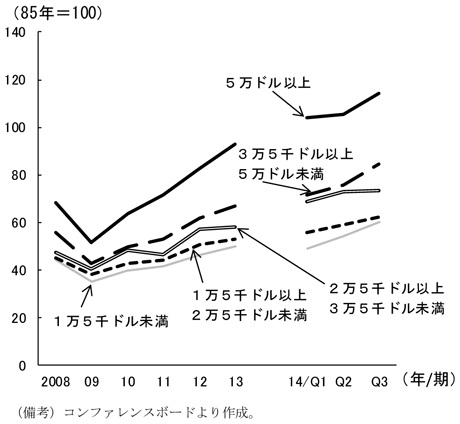
貧困率8は、世界金融危機後のピークよりはやや低下しているものの、歴史的には引き続き高い水準にある(第1-2-34図)。また、最低賃金9
以下で働く労働者の割合10
は世界金融危機の影響により急上昇したが、10年をピークに低下している。ただし、依然として世界金融危機前の水準を上回っている(第1-2-35図)。
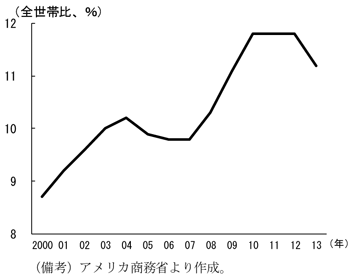
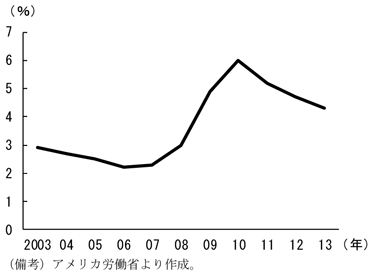
以上のように、景気回復の効果はまず高所得層に現れており、所得水準が低くなるにつれて回復の実感が伝わりにくく、消費者マインドの改善が遅れる要因となっている。ジニ係数の上昇(後掲第1-2-95図)が示すように、所得格差は拡大している。格差の拡大は消費全体の底上げにつながらず、ひいては経済成長を阻害する要因になることが懸念される。
(ii)回復の鈍い住宅市場
住宅投資のGDPに占める割合は3%程度と高くないものの、住宅市場が活発になれば家具や家電といった耐久消費財等への需要の波及効果が期待されることから注目されている。
住宅市場は、05年前後からみられた住宅バブルの崩壊以降、回復途上にある。在庫調整が進展し、雇用環境が改善傾向にあるものの、開発規制による土地の供給制約や住宅ローンの貸出態度の厳格化といった制約要因が残っており、住宅市場の回復テンポは緩やかなものにとどまっている。
住宅着工件数をやや長期的にみると、05年の206.8万件をピークに減少に転じ、景気の谷(09年6月)を含む09年には55.4万件まで落ち込んだ。その後、在庫調整を進めるために住宅着工は世帯形成件数(年間100万件以上の純増)を下回るペースで推移した。賃貸需要の増加からまずは集合住宅の着工が回復し、12年に入って一戸建て住宅も持ち直しの動きがみられるようになった。建設労働者不足や資材価格の上昇といった供給面の制約要因はみられたものの、13年9月に金融緩和縮小が見送られたことで金利が低下し、年末にかけて駆け込み需要が発生した。14年に入ってからは雇用情勢の回復や低金利を背景に、14年9月時点の年平均の住宅着工件数は97.8万件と13年(92.3万件)を上回るペースとなっている(第1-2-36図)。
今回の回復局面では、集合住宅が増加傾向にあることが特徴的である。集合住宅の着工件数が全体に占める割合は、2000年代前半には20%前後であったが徐々に上昇し、13年7月以降は30%超で推移している。
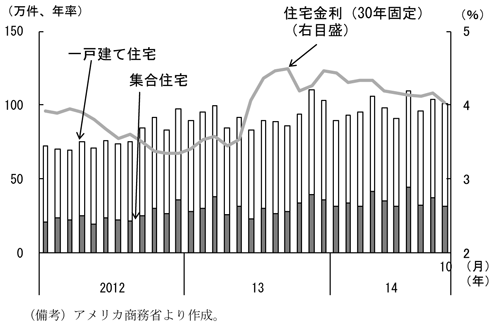
この背景には、サブプライムローン問題以降、集合住宅への需要が高まっていることが挙げられる。自宅を失う代わりにローン返済義務を放棄した消費者は、新たに住宅を購入する資金に乏しく、賃貸の集合住宅に入居していると考えられる11。このため、自宅保有率の低下に伴って、集合住宅の需要が増加していることから、集合住宅の空室率が顕著に低下している(第1-2-37図)。
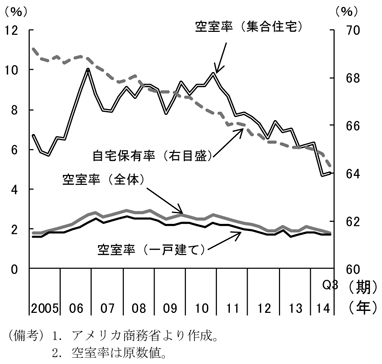
賃貸需要の高まりは、初回住宅購入者の割合が減少していることも要因として挙げられる。全米不動産業者協会(NAR)によると、14年6月までの1年間の販売における初回住宅購入者の割合は33%と、87年以来の低水準であり、調査開始の81年から14年までの平均の40%程度を下回っている。初回購入者は年齢の中央値が31歳と、2回目以降の購入者(年齢の中央値は53歳)と比較して若い世代である。若年層はより良い雇用機会があれば、遠隔地であっても転居できるように自宅購入を避ける傾向にあること、また、クレジットスコアが低いために金融機関の貸出態度が厳格化する中で住宅ローンを組みにくくなっていること等から、賃貸住宅を選択する傾向にあるとされる12。
こうした状況から、今後の住宅着工も、賃貸向けの集合住宅を中心に回復すると見込まれる。
住宅市場の需要面を確認すると、新築住宅販売、中古住宅販売ともに14年に入って緩やかに持ち直している。金融機関の貸出態度が厳格化する一方で、雇用・所得環境の改善や住宅ローン金利の低下が寄与していると考えられる。また、在庫不足が解消しつつあることも要因として挙げられる。
ただし、新築住宅販売を価格帯別にみると、15万ドル未満の低価格帯の割合が低下傾向にある。低所得者層は住宅ローンを取得することが難しくなっており、購入を見送っているためと考えられる(第1-2-38図)。景気回復の低所得者層への波及が遅れる中、低所得者層の住宅需要が回復するには更に時間がかかるとみられる。
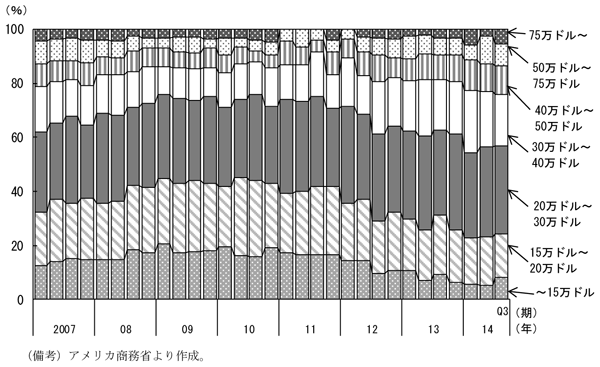
住宅価格は、銀行に差し押さえられていた物件の投資目的による購入が活発だったことや在庫不足もあって、13年から14年半ばにかけては住宅取得能力の改善を上回るペースで上昇していた(第1-2-39図)。これに伴い、今まで資産価値がローン残高を下回っていたため売り控えられてきた物件が、資産価値が上昇したことから市場に出回るようになってきている。このため在庫不足が解消しつつあり、14年夏頃から住宅価格は前月比で低下に転じている。住宅価格の先安観から、投資目的による購入が手控えられている可能性があり、現金一括購入(投資家や外国人、二回目以降の住宅購入者が使うとされる支払い方法)の住宅販売に占める割合は低下して、14年8月には23%と、09年12月(22%)以来の低水準になった。
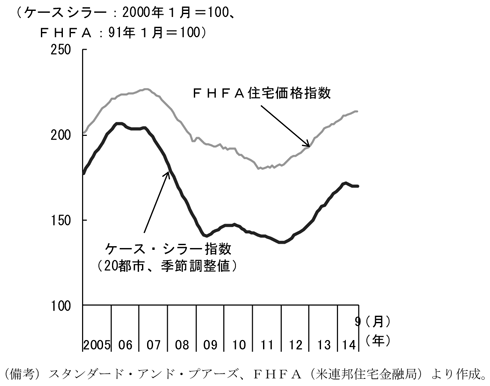
住宅価格に値ごろ感が出てきたことから、今後は潜在需要が顕在化することが期待される。一方、住宅価格の低下は逆資産効果を通じて個人消費に影響をもたらすことも考えられるため、引き続き注視が必要である。
なお、11年頃までは、住宅市場の低迷により保有する家を手放さず、雇用機会に恵まれた地域への転居が出来ない結果、失業状態が続く可能性が指摘されていた13。国内転居率は低下傾向にあるものの、住宅市場の調整が進んだこともあって、下げ止まりの兆しがみられる(第1-2-40図)。持ち家が原因となって転居ができない状況は解消されてきており、人の移動が活発化する素地が整いつつあると考えられる。
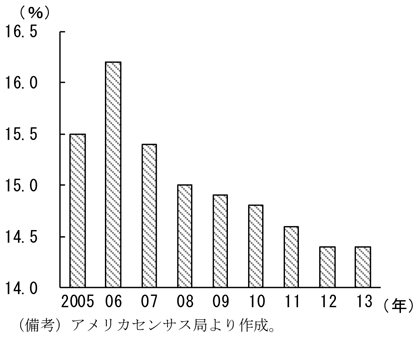
(3)今後の見通し
アメリカでは、雇用情勢の改善が続く中、景気回復が続くと見込まれる。今後、長期失業率の更なる低下やパートタイム雇用からフルタイム雇用への転換が進み、雇用情勢のひっ迫に伴って賃金の上昇ペースが速まれば、消費が一層活発になることも期待される。
設備投資については、機械設備投資14の先行指標となるコア資本財受注が、14年に入ってから緩やかに増加しており、金利の先高感はあるものの今後も緩やかな増加傾向が続くことが期待される(第1-2-41図)。
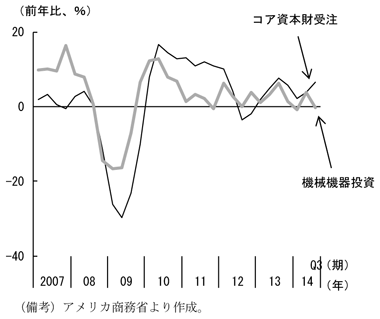
なお、輸出は、14年9月頃からドル高傾向が強まっていることや、原油価格が下落していることから、14年夏ごろまでの緩やかな増加ペースを維持するのは難しくなってきていると考えられる。
以下では、今後進められる予定の金融政策正常化をめぐる動き及び財政の見通しについて分析する。
(i)金融緩和の終了
Fedは14年9月のFOMCにおいて金融政策の正常化に向けた計画を公表した。これによると、資産購入プログラム終了後、まずは政策金利を引き上げ、その後、長期国債等の償還分の再投資を停止し、段階的にFedのバランスシートを縮小させる、としている。
10月のFOMCにおいて、資産購入プログラムの終了が決定された。また、同プログラム終了後も「相当な期間(considerable time)」、現在の政策金利(0~0.25%)を維持することは適切との表現を維持し、利上げ時期は経済状況次第で早くも遅くもなり得ることが改めて強調された。また、同年12月には金融政策の正常化の開始に向けて「辛抱強くなれる」として、フォーワードガイダンスを微修正した。
Fedは雇用の最大化と物価の安定という二大責務を負っており、このうち雇用動向に着目すれば、前述のとおり改善が続いており、金融政策を正常化する時期が近いことを示唆している。一方、物価動向に着目すると、インフレ目標の2%を下回る水準でおおむね横ばいとなっており、緩和的な金融政策が維持されることを示唆している(第1-2-42図)。
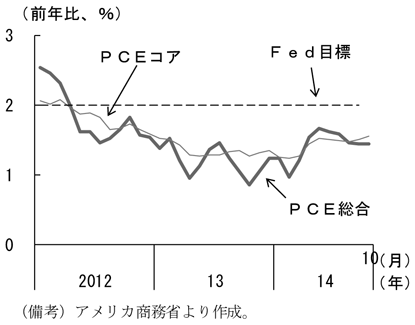
両分野の経済指標が金融政策の方向性に対して相反する形で進んでいるため、FOMC参加者の発言内容等に注目が集まっている。なお、13年5月にはバーナンキFRB議長が金融緩和の縮小を示唆する発言を契機に新興国通貨等の下落がみられ、同年9月に市場の予想に反して金融緩和の縮小が見送られた時には、年末にかけて住宅の駆け込み需要が発生した。今後金利を引き上げる過程において、無用の混乱を引き起こさないようにフォーワードガイダンスの活用等により市場との対話を深めることが期待される。
(ii)財政の見通し
財政面をみると、景気回復に伴う税収増等(前年比9%増)に加えて歳出増の伸びが抑えられた(同1%増)ことから、13年会計年度(13年10月~14年9月)の財政収支は大幅に改善した(第1-2-43図)。今後は、アメリカ経済の回復が続く中で財政収支も改善方向で推移すると考えられる。なお、11月に行われた中間選挙で共和党が両院を制したことから、政治の不透明感は増している。15年3月には現行の債務上限の適用期限となるため、新たな債務上限の扱いが焦点となる(コラム1)。
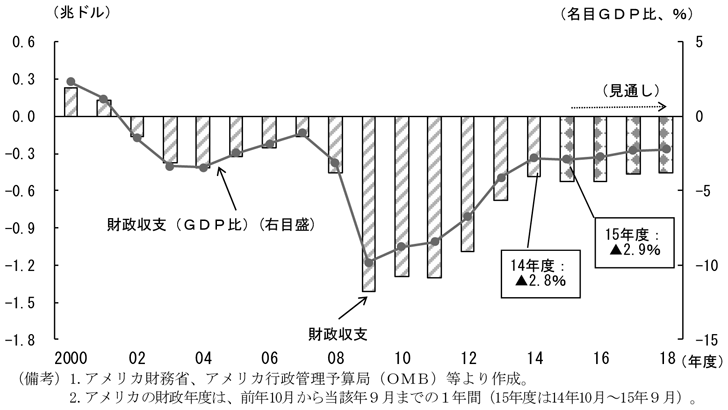
コラム1:中間選挙結果と財政をめぐる動き
アメリカの中間選挙は2014年11月4日に実施され、上院は約1/3、下院は全議席が改選された。選挙前には上院は民主党が、下院は共和党が多数派を占め、いわゆる「ねじれ状態」になっていた。選挙の結果、上下両院ともに共和党が過半数を占めるようになったことから、民主党であるオバマ政権の議会運営はさらに困難になると予想されている。
今後の財政面の課題としては、現行の連邦債務上限の適用期限が15年3月15日に切れるため、新たに債務上限の引上げを決定する必要性がある。前回の債務上限の引上げをめぐっては、オバマ大統領・議会民主党と議会共和党の調整がつかず、連邦政府機関が13年10月に2週間以上閉鎖される事態となった。
共和党の重鎮(注)は政府機関のシャットダウンや連邦債務のデフォルトは引き起こさないと明言しており、前回のような事態に陥る可能性は低いとみられている。
(注)ロイター(14年11月5日)による(http://www.reuters.com/article/2014/11/05/us-usa-elections-mcconnell-idUSKBN0IP2J620141105 )

