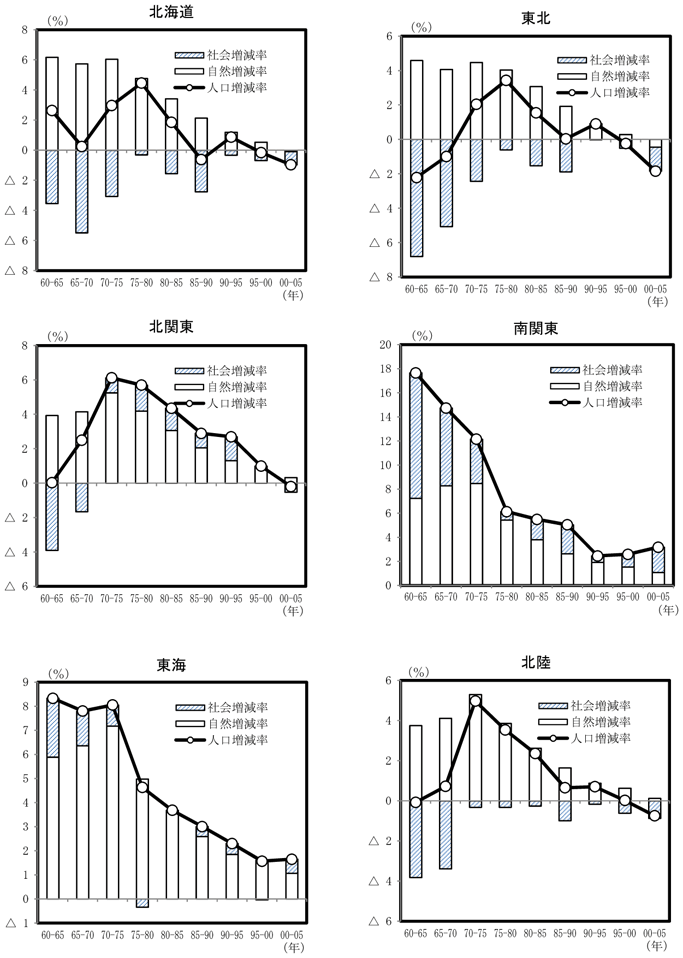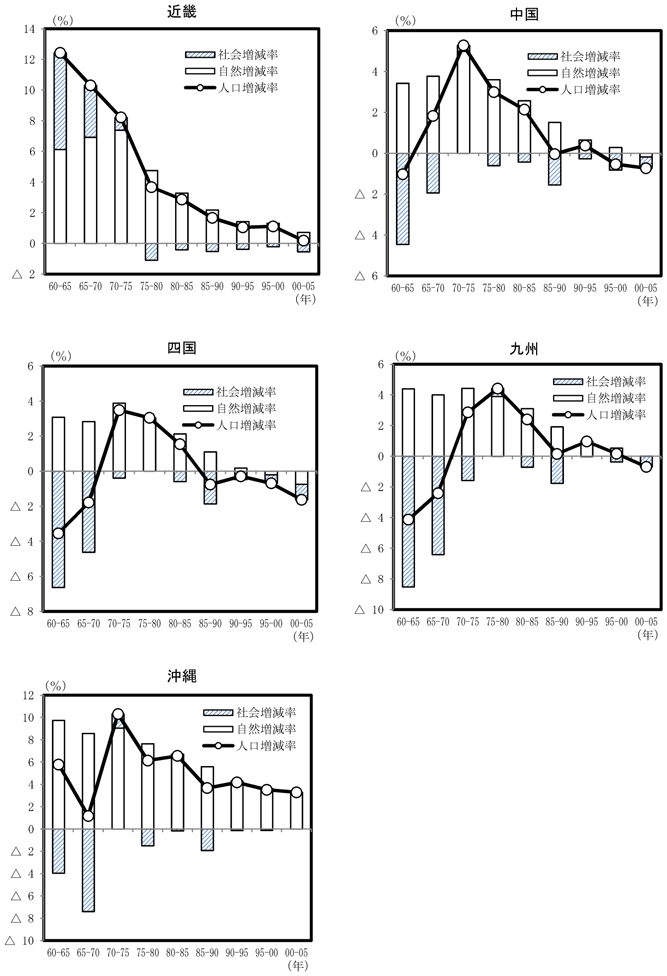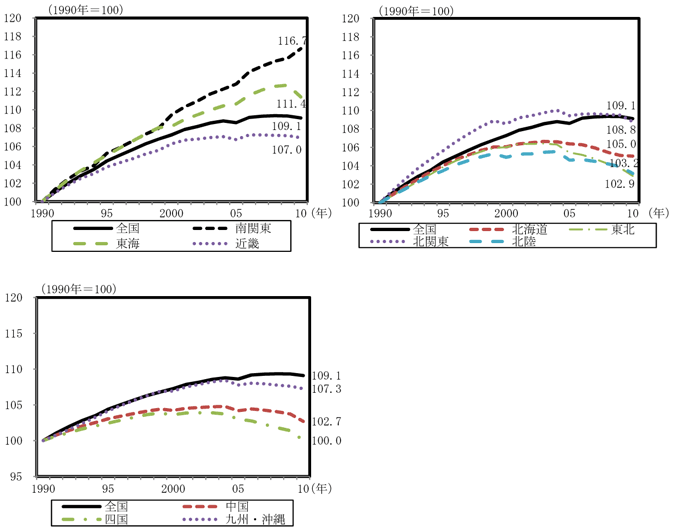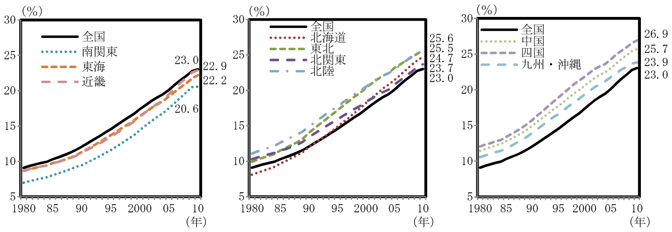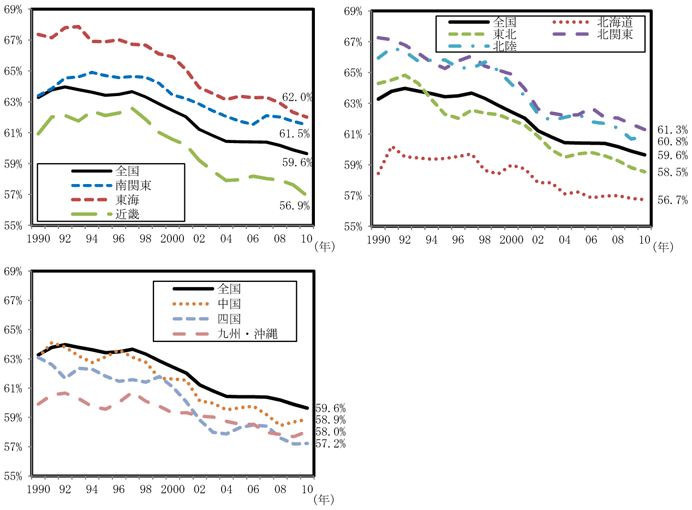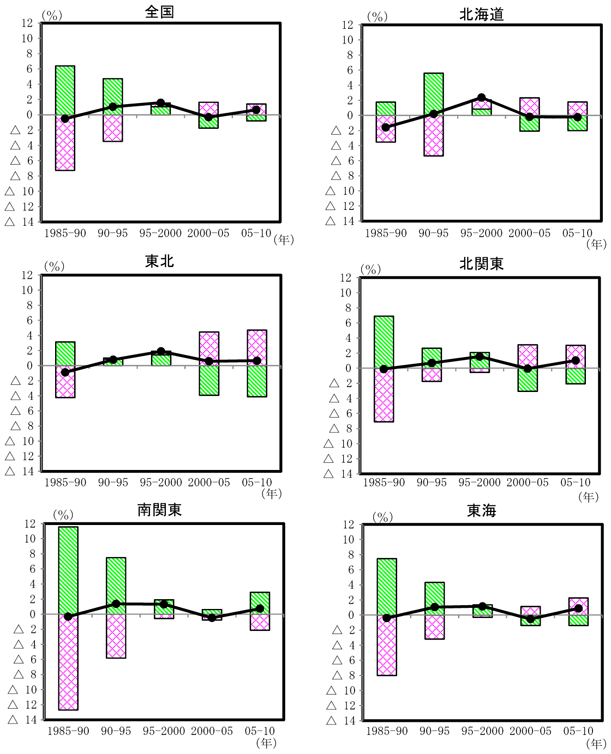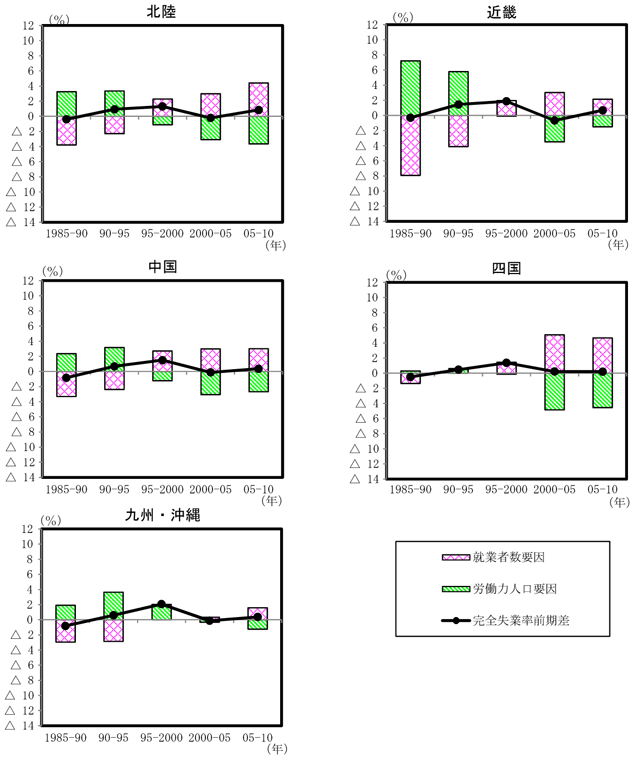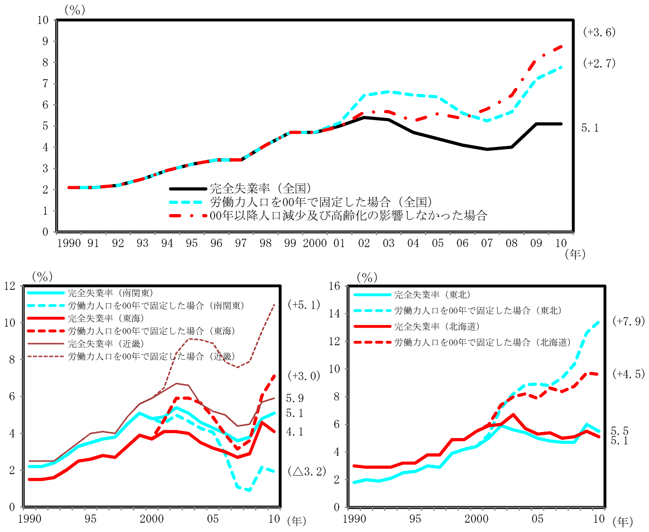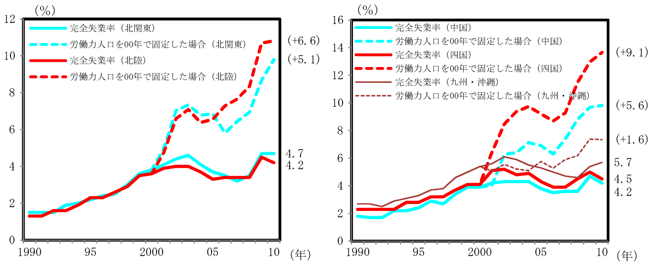2.労働市場と人口変化
(人口の変化が労働市場に与える影響)
人口や人口構成の変化は、様々な経路を通じて労働力人口の増減に影響を与える。労働力人口は、15歳以上人口と、そのうちどれだけの人が労働市場に参加しているかの度合いを示す労働力率の積で表されることを念頭に、この点を検討してみる。
第1に、地域の人口の変化は、自然増減及び社会増減を通じて、15歳以上人口を増減させる61。例えば、他地域へ雇用口を求めて若年層が流出し、人口の社会減となった場合、その地域の15歳以上人口はその分減少する。第2に、人口構成の変化は、労働力率に影響を与えることにより、労働力人口を左右する。具体的には、高齢化が進行して人口に占める高齢者比率が上昇すると、高齢者は引退して労働市場から退出している割合が高いため、全体の労働力率が低下し、労働力人口は減少する。
地方部の地域において90年代以降みられた労働力人口の減少も、これらの要因が働いていたことが考えられる。以下ではこの点について詳しくみてみよう。
(地方部における人口の流出)
戦後、特に高度成長期以降に、地方部から都市部へ人口が若年層を中心に大量に流出した62。第3-1-4図は、60年代以降の各地域の人口の増減率を自然増減と社会増減に分解したものだが、これをみると、南関東、東海及び70年代以降の北関東地域を除いては、各地域とも概ね人口の流出超過すなわち社会減が観察されている。都市部の近畿地域でも、70年代後半以降は人口の流出超過となっている。特に70年代前半までは大幅な流出超過となっている地域が多く、それ以降は人口流出圧力が緩和したものの、依然として流出傾向にあり、90年代以降でもその傾向は継続している。
人口の自然増について長期的推移を地域別にみても、70年代前半までは高い増加率であったが、その後逓減し続けており、地方部では社会減と合わせると、90年代後半から人口の伸びがマイナスになっている地域が多い。こうした人口の流れは、15歳以上人口の減少に直結することとなる。各地域の15歳以上人口の推移をみても、地方部では2000年代前半ないし半ばには減少に転じており、近年特に都市部よりも減少傾向が強まっている(第3-1-5図)。
(地方部における高齢化の進行)
加えて、人口の高齢化が特に地方部で進行している。これを老年人口比率(人口全体に占める65歳以上人口の比率)の推移でみると、第3-1-6図にあるように、各地域ともほぼ並行して急速に上昇しており、特に四国、中国、東北地域で高い比率となっている。
こうした高齢化の進行は、地域全体の労働力率を押し下げることとなる。年齢層別の労働力率は、第3-1-7図が示すように、女性で近年全体的に上昇傾向にあるものの、年齢層が上がるにつれて低くなっており、50歳代後半から顕著に低下し、65歳以上の高齢層では大きく低下する。
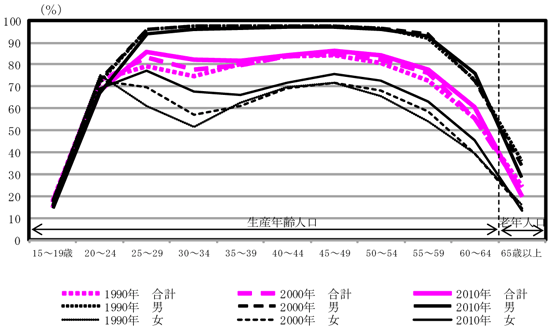
このため、高齢化が進行した地域では高齢者が多数労働市場から退出する結果、労働力率が大きく低下することになる(第3-1-8図)。
労働力率は、高齢化といった人口要因以外にも、景気変動や賃金水準、教育水準、年金等社会保障制度の充実度等様々な要因から影響を受ける。この点について、労働力率の変化のうちどの程度が高齢化に影響されているのかを、寄与度分解して定量的に検証してみよう。
労働力人口を生産年齢人口(15~64歳)と老年人口(65歳以上)について分けて考えると、15歳以上人口全体の労働力率の変化の要因は、①生産年齢人口の労働力率変化の要因、②老年人口の労働力率変化の要因、それに③老年人口指数63の変化の要因(高齢化要因)に分解できる。この寄与度分解を行った結果が、第3-1-9図のグラフである。
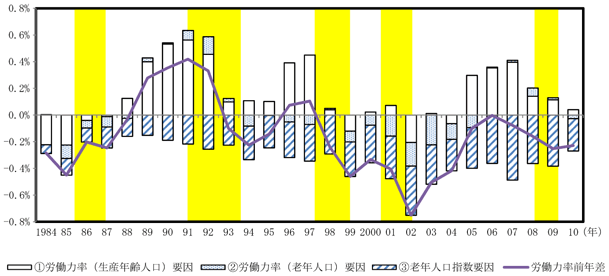
- 総務省「国勢調査」、「労働力調査」より作成。
- 労働力率の寄与度分解式は以下の通り
 (
( :全体の労働力率、
:全体の労働力率、 :生産年齢人口の労働力率、
:生産年齢人口の労働力率、 :老年人口の労働力率、
:老年人口の労働力率、 :15歳以上人口に対する老年人口の割合)ただし、
:15歳以上人口に対する老年人口の割合)ただし、
- シャドー部は景気後退期。
①の生産年齢人口については、景気上昇・後退局面に合わせて労働力率が上下しており、景気上昇で労働需要が高まる時期に労働市場に参入し、景気後退期に労働市場から退出する就労行動が強く見て取れる64,65。②の老年人口の労働力率変化についても、寄与は小さいものの、生産年齢人口と同様に景気局面に即した動きが観察される。他方、③の老年人口指数の上昇については、一貫して労働力率を引き下げる方向に働いており、しかもその影響度は年々強まっている。つまり、高齢化の進行が労働力率を傾向的に押し下げ続けており、しかも、その労働市場への影響力は増している。
(「失業率」の意味)
前述の失業率の考え方からすると、その地域の経済が拡大して労働需要に波及し就業者数が増加すること(労働需要側要因)によっても低下するが、人口の減少や高齢化に伴い労働力人口が減少すること(労働供給側要因)によっても低下する。失業率の低下は、前者の場合は、まさに地域経済が成長している証左であり望ましいが、後者の場合は、単に地域経済が縮小していることを意味するのかもしれない。
つまり、各地域経済の“実力”を雇用情勢から評価する場合に、その地域で行われる財・サービスの生産活動の派生需要としての雇用需要がどれくらい拡大しているかが重要であり、単に人口の流出や労働市場からの退出が増えて労働市場が収縮することで失業率が低下しても、雇用情勢が改善したとは判断できない。また、失業率が低位で安定していても、それが失業率の分子要因である就業者数が大幅に減少する一方で、同時に分母要因である労働力人口がまた大きく減少していることによって維持されているのであれば、この地域の労働市場は縮小過程を辿り続けていることを意味しており、地域経済にとってはむしろ深刻な状況であると言える66。
そうした観点から、各地域の失業率の動きについて分析してみよう。分析に当たっては、以下のような段階を踏んでアプローチする。すなわち、第1段階として、失業率の変化を、その分子要因である就業者数と分母要因である労働力人口を分解して、それらの寄与度をみる。次に第2段階として、分母要因である労働力人口をさらに15歳以上人口の変化と労働力率の変化に分解して、それぞれの失業率の変化への寄与度を分析する。そして第3段階として、人口減少及び高齢化(人口構成の変化)の影響を抽出するために、労働力率の変化をさらに、生産年齢人口及び老年人口の労働力率、老年人口指数の3つに分解して、それぞれの失業率の変化への寄与度を計算する。
(労働力人口と失業率の関係)
既に述べたように、各地域の労働市場において、労働需要側要因である就業者数の動向は、その地域の財・サービスの生産活動の規模に依存して、また、労働供給側要因である労働力人口は、15歳以上人口の多寡と労働力率の高低に依存してそれぞれ独立に変動し、その差が失業者数となり、また比率として失業率が求められる。では、仮に各地域で労働供給側要因である労働力人口の減少がなかった場合、失業率の水準はどの程度となるのであろうか。これをみるために、労働供給側要因を固定して、生産活動の派生需要としての労働需要がどれくらい不足しているかという動きのみに注目した場合に、失業率がどの程度変化するかを試算する。
第3-1-10図は、90年代以降5年毎に失業率の変化を、労働力人口要因と就業者数要因に分解したものである67。ここからいくつかの特徴が明らかになる。第1に、全国的な労働力人口の減少局面への転換を背景に、2000年以降南関東を除く全地域で労働力人口の減少が失業率を引き下げる方向に寄与したことがうかがわれる。特に東北、北陸、中国及び四国地域では、その幅が3%以上と寄与が大きい。第2に、分子の就業者数要因は地域により違いがあるものの、90年代後半から失業率を押し上げる方向に働いている。つまり、主に地方部では、90年代後半から分子要因である就業者数が減少して失業率が上昇していくが、その動きを分母要因である労働力人口の減少が抑えている構図になっているのである。
このように、2000年以降の各地域の失業率は、労働力人口の減少によって比較的低位に抑えられていたとも言える。南関東を除く全地域で労働力人口が本格的に減り始めたのは2000年頃であるが、もし仮にこの時期の労働力人口が2000年時点の水準で維持されていた場合、失業率は現実の失業率よりどの程度高まっていたのだろうか。この場合の失業率の動きを示したのが、第3-1-11図である。
失業率は各地域とも概ね2007年まで低下した後、上昇傾向に転じた。その中で、労働力人口の減少幅が徐々に拡大していることから、それが失業率を押し下げていた寄与はここ数年で大きくなり、全国ベースでは2010年で2.7%ポイントに達する。すなわち、労働力人口の減少がなければ、3%ポイント程度高かった計算になる。特に地方部ではその差が5%を超えるケースもあり、特に四国地域は2010年の失業率が全国を下回る4.5%であるが、労働力人口の減少がなければそれより9%ポイント程度高かったという結果になっている。また、都市部でも近畿地域では、通常の失業率も高水準にあるが、労働力人口が一定であればさらに5%ポイント程度跳ね上がることとなる。
この状況を後ろ向きに解釈すれば、経済活動が停滞して雇用創出力が弱まり、雇用需要が傾向的に減退していることが暗示され、労働力人口の減少がその事実が顕在化するのを抑制していることとなる。しかし、前向きに解釈すれば、労働力人口の減少を前にして、産業構造の変化や各産業での労働節約型投資等の対応により労働生産性を高めることで、雇用需要を抑制しているとも考えられる。この点については、次節で改めて検討する。
他方、労働力人口を固定した場合の南関東地域の失業率の低下幅が示すことは、仮に人口流入による労働力人口の増加がなければ失業率が著しく低下して労働需給が逼迫していたことが想定されるということである。今後本格的な人口減少社会になった場合に、労働力供給の減少が顕著になると、雇用需要を充足できなくなり、労働力不足になる可能性を示唆している。
(人口減少及び労働力率変化の失業率への影響)
労働力人口の減少が失業率の上昇を抑える方向に働いていたことが見て取れたが、先述したように、労働力人口の減少は、人口の大幅な流出による社会減や高齢化による人口構成の変化によってもたらされる。地域の人口減少や労働力率の低下は、それぞれ失業率の変化にどのように寄与しているのだろうか。
先ほどの第3-1-10図では、失業率の変化を労働力人口の変化(労働供給側要因)と就業者数の変化(労働需要側要因)に要因分解したが、ここで全国及び各地域について年次データで、さらに労働力人口の変化の部分も15歳以上人口の変化と労働力率の変化に寄与度分解して図示したのが、第3-1-12図である。
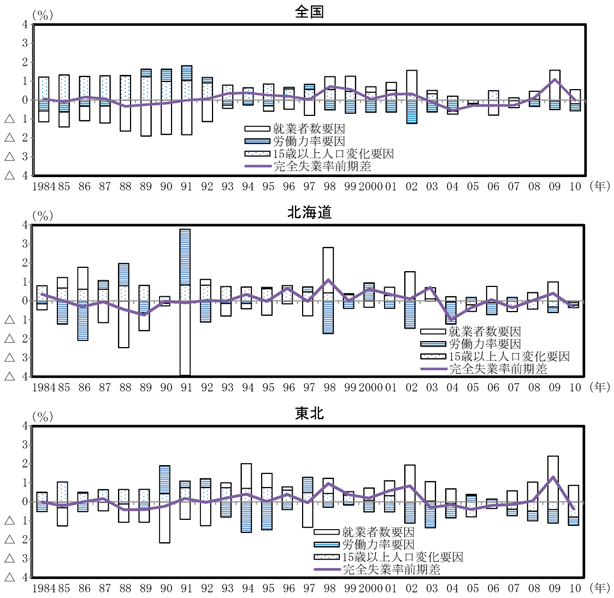
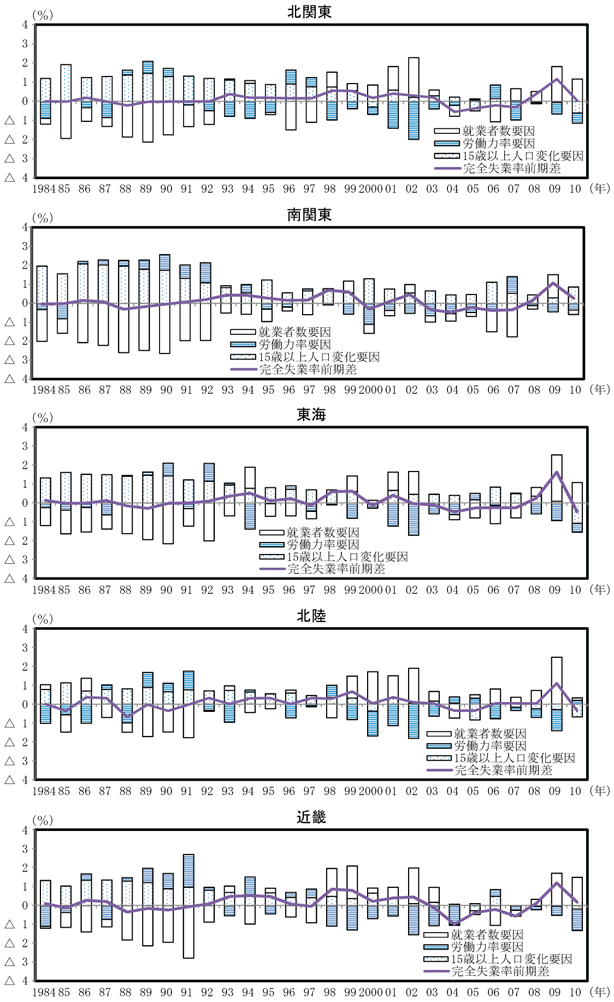
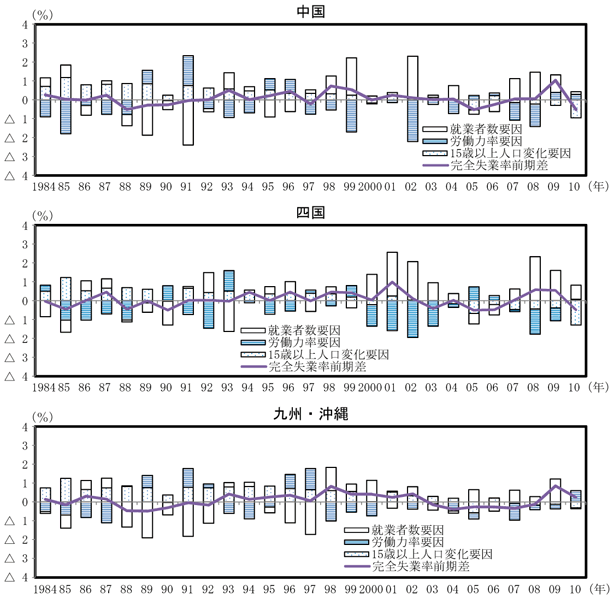
- 総務省「国勢調査」、「労働力調査」より作成。
- 地域区分はC。
- 完全失業率=1-(就業者数/労働力率×15歳以上人口)より、
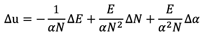 (
( :就業者数、
:就業者数、 :労働力率、
:労働力率、 :15歳以上人口)
:15歳以上人口)
これを見ると、まず分子要因である就業者数要因は、明らかに景気局面に即して変動しており、景気上昇期には就業者数が増加することで下方にグラフが伸び、後退期には逆に上方に立っている。一方で、15歳以上人口は前掲第3-1-3図でみたとおり、2000年代後半まで緩やかにスピードを減じながらも増加していたことから、2008年までは失業率に対して上向きに寄与していたが、2009年以降は失業率を引き下げる方向に転換している。また、労働力率も、先にみたとおり、98年以降2005~07年までの期間横ばいとなったことを除いて一貫して低下したことから、この98年以降は失業率を押し下げる方向に働いている。
また、景気下降局面において就業者数要因が失業率を大きく押し上げた際には、先述したように、労働力率要因が逆に大きく引き下げる傾向があり、景気後退で就業者数が減少すると、その分失業者数が増加するのではなく労働市場から退出することで労働供給(労働力人口)も減少していることが推察される。景気上昇局面では、逆の現象が見て取れる。
この失業率変化の要因分解を地域別に見てみよう。まず15歳以上人口要因は、各地域とも失業率への寄与を傾向的に減じている。地域差があり、地方部においては2000年代前半ないし半ばにはマイナス寄与に転じているが、2010年には南関東以外の全地域でマイナス傾向が明らかになっている。また、労働力率要因の寄与度も地方部で大きいことが分かる。
(人口減少及び高齢化の失業率への影響)
では、人口減少及び高齢化(人口構成の変化)は、結局のところどれくらい失業率を変化させたのか。先述したとおり、そうした人口要因は、15歳以上人口とともに、労働力率を通じて失業率に影響する。そこで、前掲第3-1-9図での労働力率に係る分析のように、15歳以上人口を生産年齢人口と老年人口に係る部分に分け、後者のウェイトである老年人口指数の変化すなわち高齢化の進行が労働力人口を通じて失業率に影響した部分を、人口構成要因を通じた寄与分として抽出し、15歳以上人口の変化による寄与分と合わせて、人口及び人口構成の変化による失業率の変化への寄与度として試算する。その結果が、第3-1-13図である。
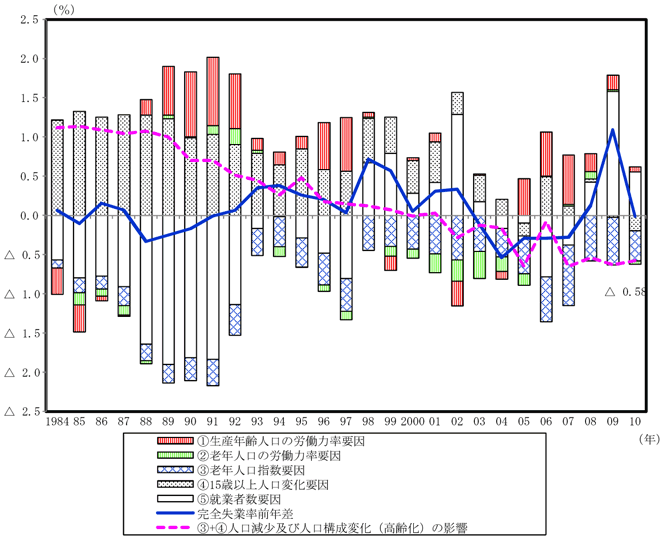
- 総務省「国勢調査」、「人口推計」、「労働力調査」より作成。
- 要因分解式は以下の通り。
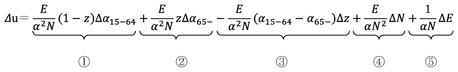 (
( :15歳以上人口、
:15歳以上人口、 :就業者数、
:就業者数、 :全体の労働力率、
:全体の労働力率、 :生産年齢人口の労働力率、
:生産年齢人口の労働力率、 :老年人口の労働力率、
:老年人口の労働力率、 :15歳以上人口に対する老年人口の割合)ただし、
:15歳以上人口に対する老年人口の割合)ただし、
まず15歳以上人口は、先ほども見たように、かつてはその高い伸びを背景に労働力人口を増加させ、失業率を押し上げる方向に働いていており、90年では押上げ幅は1%程度にもなったが、伸びのスピードが顕著に漸減してきたことから失業率押上げ効果は年を追って低下し、足元ではマイナス寄与に転じ始めている(グラフ中④)。今後さらに15歳以上人口が減少すれば、失業率を押し下げる効果が大きくなっていくことが予想される。他方、人口構成の変化(高齢化)は、老年人口指数の上昇を通じて労働力率及び労働力人口を引き下げることで、失業率を一貫して引き下げており、その引下げ幅も徐々に拡大している(グラフ中③)。
この結果、景気変動で変化する就業者数及び労働力率の短期的な影響を除けば、図中の点線の折れ線グラフで示されるように、人口減少及び人口構成の変化は、2000年頃を境に失業率に対してプラスの寄与からマイナスの寄与に転じており、その加速は構造的に失業率をさらに引き下げていくこととなる。特に地方部では、人口の減少や高齢化の進行が都市部より顕著であることに鑑みれば、この傾向はさらに強いものとなることが想定される。
この人口減少及び人口構成変化分のみ(グラフ中③+④)を取り出して、仮にこれらの変化がなかった場合の失業率を、先ほどの労働力人口の減少がなかった場合の失業率の計算と同様に全国について試算すると、その失業率は、前掲第3-1-11図の全国の破線部のように推移し、2010年では4%ポイント弱押し上げられていたこととなる。
こうしたことから、長期的に労働需要が減退して就業者数が減少する傾向にあるとすれば、我が国の労働市場は、人口増加の減速や高齢化といった人口要因により労働力人口が減少することで、失業率水準の悪化が覆い隠されている状況にあるということになる68。
本節では、各地域の労働需給についてみてきたが、ここの試算が含意することを改めて確認すると、各地域の失業率や有効求人倍率等雇用指標に表れる数値は、必ずしも各地域の労働市場の様子を反映しているとは限らず、各地域の雇用面での“実力”を表してはいない。むしろ、特に地方部において、2000年代に入って労働需要である就業者数が減少傾向にある中で、人口減少局面への転換や高齢化といった人口要因により労働力人口も縮小していく状況となっており、地域の中長期的経済発展を考える上で、労働市場を注視していく必要がある。次節では、就業者数、すなわち労働需要を左右する生産について議論を進める。
(人口増減)=(自然増減)+(社会増減)=(出生数-死亡数)+(流入数-流出数)