第2章 第3節 アメリカ経済における生産性の向上
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |
第3節 アメリカ経済における生産性の向上
1990年代後半におけるアメリカ経済の良好なパフォーマンスの要因は、前節で示したように適切な政策運営や柔軟な経済構造といったことに求めることができるが、それ以外にも、過去数十年と比べ、ここ数年の労働生産性上昇率が高まっていることも要因として挙げられる[注1]。
労働生産性の推移をみると、70年代初頭以降、それ以前に比べて伸びが鈍化している。しかし、96年以降については、60年代までと比べると低い伸びが続いていることには変わりはないものの、伸びが相当程度高まっている。しかし、この観察される労働生産性上昇率の高まりが、本当の意味での高まりを示しているかどうかについては、検討を加える必要がある。なぜならば、統計の改訂や景気変動によって、みかけ上高まっているだけという可能性があるからである。
以下では、a)労働生産性は90年代後半に本当に向上したのか、b)仮にそれが事実であれば、どのような産業で向上したのか、c)また、労働生産性向上の要因は何か、特に、情報化の進展が生産性を高めている可能性はあるのかという点について検討する。
労働生産性について検討することは、今のアメリカにおいて次のような意味において重要である。
- a)労働生産性上昇率の高まりが、潜在的な成長力を高め、インフレなき高成長をもたらしている可能性がある[注2]。
- b)労働生産性上昇率が高まっていれば、期待収益率も大きくなるため、最近の株高を支持する一つの要素にもなる。
- c)労働生産性は中長期的な生活水準を規定する要因であり、今後ともこの高い上昇率が続くとなると、70年代以降鈍化した労働生産性の上昇率が再び高まることで、今後のアメリカ人の生活水準(一人当たり実質GDP)に大きな影響を与える可能性がある。
- d)情報通信革命にもかかわらず、生産性が向上せず「生産性パラドックス」と呼ばれていたが、ついに情報通信革命の影響が生産性に影響を及ぼし始めた可能性がある。
1 労働生産性の推移
ここ数年、経済成長率が高まる中で、労働生産性の急速な上昇が観察されるようになった。労働生産性の伸びは、短期的な景気変動の影響を受けるため、わずか数年間の労働生産性の高い伸びをもって真の労働生産性の伸びが高まっているとするのは早計である。しかし、ここ数年では、以下にみるように、景気変動要因などを取り除いても生産性の伸びが高まっていることから、真の労働生産性上昇率が高まっているものと考えられる。
(96年以降における労働生産性の高い伸び)
まず、労働生産性上昇率の推移をみてみよう。民間総合及び民間非農業部門における労働生産性の伸びは、60年代は年率3%程度で推移していたが、73年以降大幅に鈍化し、1%台前半となった。これは石油ショックによる原油価格上昇などにより世界的に成長率が鈍化したためである。また、それ以外にも、以前に比べ緩やかな資本ストックの蓄積、環境規制強化によるコストの上昇[注3]、労働参加率の上昇による未熟練な労働者の増加なども、労働生産性上昇率が鈍化する要因となった。しかし、労働生産性上昇率は、96年以降、高まる傾向にある(第2-3-1表)。
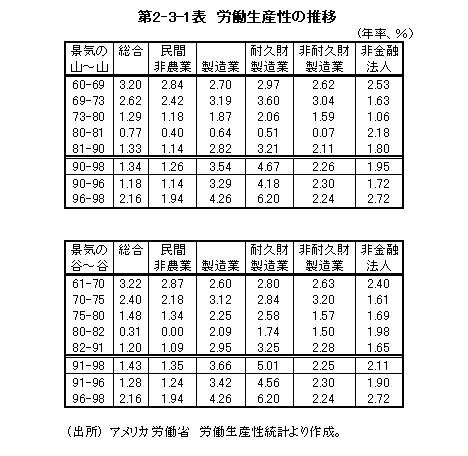
労働生産性上昇率は、景気拡大期の終盤においては鈍化するのが通常のパターンである。これは、労働需給がタイトなため、職務経験の少ない労働力を雇う機会が増えることや、経営者の楽観的な雇用計画により単位労働投入量あたりの生産額の伸びが鈍化することなどによる。91年から始まった今次景気拡大局面においても、労働生産性の伸びは初期に大きく上昇した後、景気の過熱感が指摘された95年にかけて一旦鈍化することで通常のパターンを踏襲したが、その後再び伸びが高まり、96年から平均年率2.0%以上の上昇をみせ始めた(第2-3-2図、第2-3-3図)。
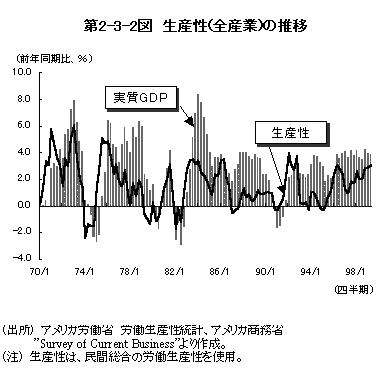
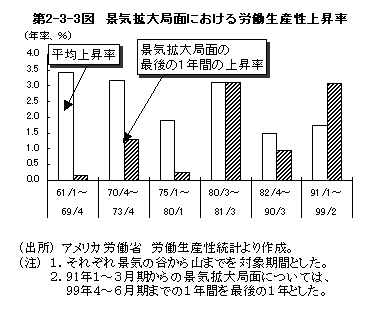
このように、長期にわたる景気拡大の後半で労働生産性が高い伸びを示すことは、珍しい現象であるが、90年代半ば以降、労働生産性上昇率のトレンドに変化が生じたと考えるべきなのであろうか。このことを調べるためには、まず、a)統計の改訂によるみかけ上の上昇率の向上、及びb)景気変動などによる短期的な変動による向上を取り除く必要がある。
(物価統計の改訂によるみかけ上の伸び)
90年代は、デフレータの大幅な下方修正を伴う(実質GDPの上方修正を伴う)GDP統計の改訂が何度か実施されている。このため90年代の実質GDP及び労働生産性の伸びは、それ以前に比べてみかけ上高くなっている。
一般的に物価統計には上方バイアスが存在する。例えば、96年末に提出されたボスキン・レポートでは消費者物価指数は年率1.1%ポイント過大評価されていると指摘した。消費者物価指数は毎年少しずつ改訂が行われているが、GDP統計の改訂においてもデフレータの下方修正が行われており、90年代には特に大きな改訂が行われた[注4]。
99年の大統領経済報告によって、90年代におけるGDPデフレータ改訂の影響を把握してみよう。大きなものは二回あるが、1回目(93~94年)は、医療費デフレータの改訂であり、これによってGDPデフレータが年0.06%ポイント下方修正された。2回目(98年)は、一部消費項目に消費者物価指数の幾何平均指数を導入するという改訂であり、95年まで遡って実施され、GDPデフレータは年0.15%ポイント下方修正された。その他の小さな改訂も考慮すると、96年以降はそれ以前(73~95年まで)に比べて0.21%ポイントだけGDPデフレータが下方修正されており、その結果、労働生産性上昇率も同じだけ押し上げられている(第2-3-4表)[注5]。なお、95年末に固定ウエイトによる物価統計の上方バイアスを軽減するために、連鎖価格デフレータが採用された。これについては遡及改訂が行われており、全期間の計数が改訂されたので、最近の労働生産性上昇率をみかけ上押し上げてはいない。
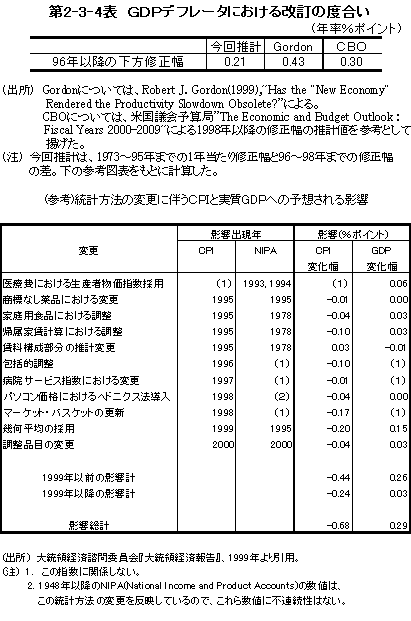
(景気変動と労働生産性)
労働生産性は、短期的にみると、景気変動の影響を大きく受ける。景気回復の初期には、生産の急増に労働投入が追いつかないため、みかけ上労働生産性上昇率が高まったかのようにみえる。また、景気拡大の終盤には、労働力確保のため労働稼働率が高まる一方、生産はあまり伸びず、労働生産性上昇率はみかけ上鈍化する。[注6] Gordon(1999)によると、民間非農業部門の労働生産性上昇率は、96年以降、需要が急増したことなどに伴い、みかけ上年0.30%ポイント高い伸びとなっている。さらに統計改訂の影響(0.21%)も考慮すると、実際の上昇率は年約1.43%程度であったと考えられる(第2-3-5表)。この伸び率は、それまでの伸び率(1.12%)よりも高いことから、真の労働生産性は、96年以降、高まっていると考えられる。
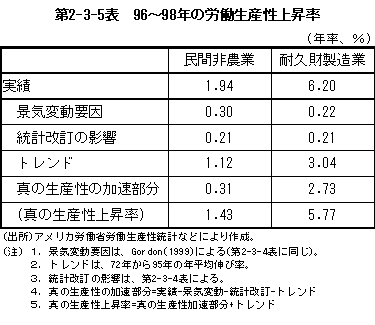
2 産業別生産性の推移
さて、このような90年代後半における労働生産性上昇率の高まりは、どのような産業で生じているのだろうか。産業別の動向をみると、90年代に入り、製造業において高い労働生産性の伸びが続いている。さらに、製造業の中では、特に電気機械などのハイテク産業で生産性の伸びが高く、90年代後半には、更に伸びを高めており、これらの業種における90年代に入ってからの労働生産性の高い伸びが、最近の経済全体における労働生産性の加速をもたらした。
その他の産業をみると、90年代に入り労働生産性が向上している分野もあるものの、非製造業全体では、サービス業におけるマイナスの伸びに相殺され、労働生産性の上昇はみられない。しかし、サービス業などにおいて労働生産性の伸びがマイナスとなっているのは、後述するように統計上の問題によるところも大きいと考えられるため、実際には真の労働生産性はみかけほど悪くない可能性があるといえよう。
(製造業における労働生産性の高い伸び)
米国労働省が四半期ベースで公表している労働生産性統計においては、民間部門、民間非農業、製造業、耐久財製造業、非耐久財製造業、非金融法人の労働生産性の動向を知ることができる[注7]。これによると製造業における労働生産性上昇率は90年代に入ってから高まり、ここ数年は伸びが更に高まっている(前掲第2-3-1表)。また、製造業の中では、耐久財製造業の伸びが著しく高まっており、非耐久財製造業においては、労働生産性の伸びはほとんど変化していない。製造業全体における労働生産性の伸びは、耐久財製造業によってもたらされていることが分かる。
直近のデータはないが、アメリカ労働省の公表している製造業生産性統計によって製造業の細かい内訳についてみると、90年代においては、耐久財製造業のうち、電気機械や産業機械が高い伸びを示していることが分かる(第2-3-6表b))。他の業種における伸びはそれほど高くないことから、90年代後半の耐久財製造業の労働生産性の伸びは、これらの部門を中心にもたらされていると考えられる。
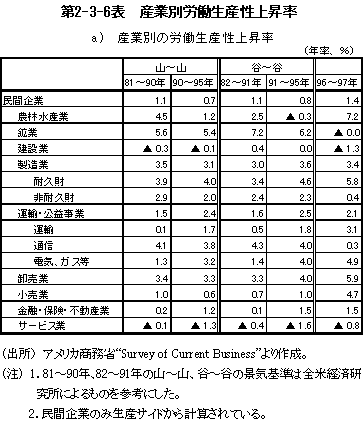
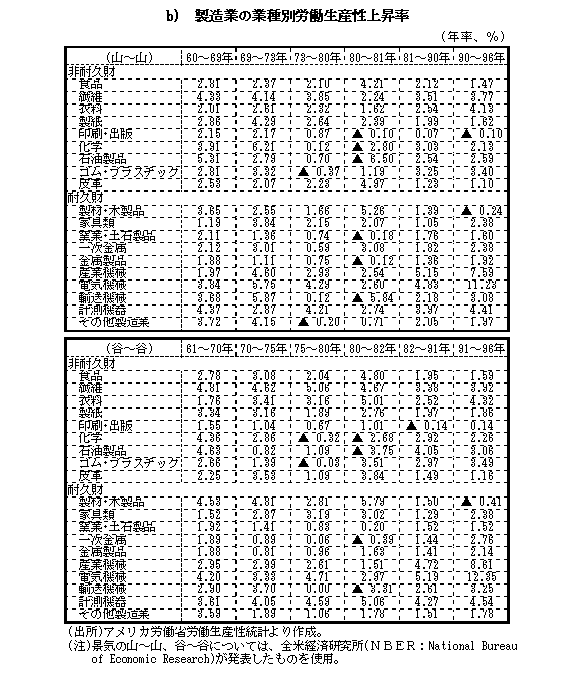
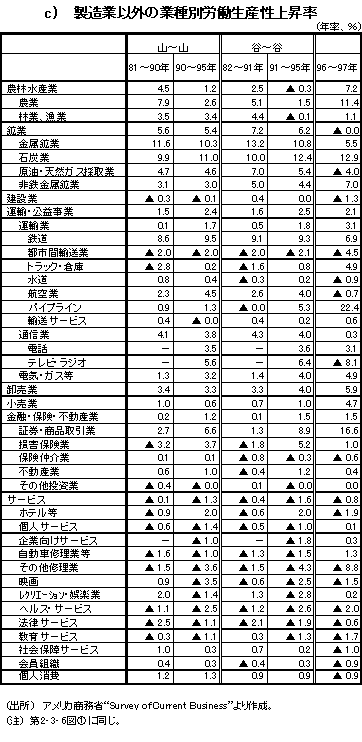
製造業の多要素生産性の推移をみると、73年以降一時伸びが鈍化したものの、79年以降回復し、90年以降は、73年までの伸びを上回っている(第2-3-7表)。また、業種別にみると、労働生産性と同様に機械関連で多要素生産性が高まっている。多要素生産性の伸びは、製造業全体では、労働生産性の伸びよりも相当程度低く、主に資本装備率の上昇が労働生産性の高い伸びに寄与したことを示唆している。多要素生産性の伸びの方が高いのは、電気機械や産業機械などであり、これらの業種では、技術革新やダウンサイジングなどの経営効率化の成果も労働生産性の高い伸びに寄与していると考えられる。
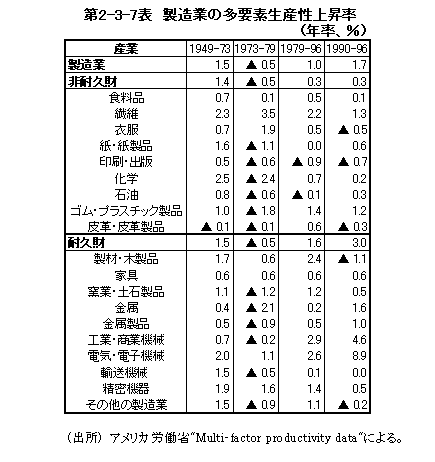
(非製造業全体の生産性の伸びは横ばい)
では、90年代において、非製造業の労働生産性はどのように推移しているのであろうか。労働省の労働生産性統計に基づいて生産性の変化をみると、非製造業全体では、ほぼ横ばいで推移している(第2-3-8表)。産業別GDP統計[注8]によって、業種別の動向をみると、運輸・公益、卸売、小売、金融・保険・不動産業においては、労働生産性上昇率が高まっており、通信業では高い伸びが続いている(第2-3-6表a)、c))[注9]。また90年代後半についてみると、卸売、小売業などで伸びが高まっている。しかし、サービス業では伸びはマイナスとなっており、90年代に入り、マイナス幅が拡大している。サービス業の内訳をみると、ホテル業を除くほぼ全てでマイナスとなっており、マイナス幅が拡大しているところも多い。このため、非製造業全体でみるとサービス業とそれ以外が打ち消し合い、横ばいとなっていると考えられる[注10]。
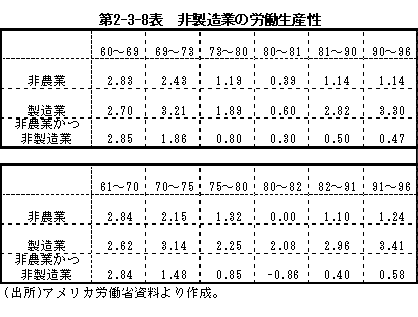
(サービス業の生産性上昇率は本当にマイナスか?)
労働生産性の伸びがマイナスとなっているサービス業においても、コンサルティングやソフトウェア産業など、高い収益を誇り、高賃金を支払っている業種もみられる。したがって、労働生産性の高い伸びが観測されないようないくつかの業種においても、実際には労働生産性の伸びが高い可能性は否定できない。つまり、サービス業の労働生産性は過小評価されている可能性がある。
サービス業におけるGDPの過小評価は主に次のような理由で生じている。
- a)新製品バイアス:移り変わりの激しい、新しいサービスの出現といった経済変化が十分とらえられていない。
- b)品質向上バイアス:現在のGDP統計では、向上しているサービスの質を把握するのが困難である。サービスの質が向上し、顧客の満足度が高まったとしても、数字でとらえることができない。
- c)生産量の計測の困難性:医療、教育、音楽など多くのサービス業では何を「生産」とするか、その定義付けが困難である。したがって、生産の計測にも困難が伴い、一部のサービス業では、生産量が投入量をもとに算出されている。労働生産性を算出するためには、生産と投入はそれぞれ独立に推計されていなければならず、この点でもサービス業の労働生産性は正確に評価されているとはいえない。
これらのバイアスはその他の非製造業についても当てはまるため、非製造業のそれぞれの産業についても、労働生産性が過小評価されている可能性がある。
さらに、非製造業における労働生産性がみかけほど低くないことについて、実質賃金の点からも検討してみよう。産業別の労働生産性上昇率の違いは、マークアップ率や価格競争、労働市場などの条件が同等であれば、実質賃金の違いとなって表れる。そこで、実質賃金について産業別の推移をみると、金融などでは高い伸びを示しており、サービス業でも他産業と比べ遜色ないなど、サービス業において労働生産性がGDP統計で計測されるよりも高い可能性がある(第2-3-9図)。
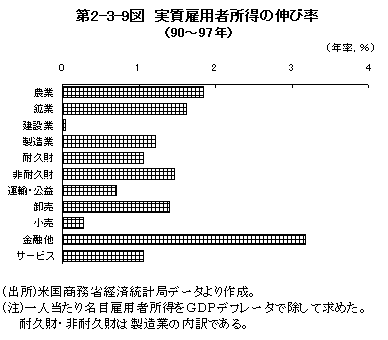
3 生産性向上の要因
これまでみてきたように、電気機械を中心とした耐久財製造業や卸売、小売業などにおいて、90年代後半に労働生産性上昇率が高まっているが、これはどのような要因によってもたらされたのであろうか。現時点では、データの制約もあり、不確定な部分も多いが、90年代における投資ブームなどによって資本ストックの質が向上していると考えられることや、情報通信革命によるプラスの効果、経営革新などが挙げられる。旺盛な投資の大部分が情報化投資によるものであることや労働生産性の伸びが高くなっている産業では情報関連ストック比率が高まっていることから、一部の産業において現れた情報通信革命の成果がマクロでみたここ数年の労働生産性の上昇に反映されていると考えてよいであろう。その他にも、規制緩和やグローバリゼーションなどの影響も考えられるが、90年代についてみると、規制緩和の行われた電力などでは生産性の伸びが高まっているが、シェアがごく小さいことから、その効果は、マクロの労働生産性に影響を及ぼすほどのものではなかったと考えられる。
(資本ストックの質の向上)
資本ストックの質が向上すれば、基本的には、実質資本ストック額の増加を通じて、労働生産性が向上する(資本に体化されない場合は、全要素生産性を通じて向上に寄与)。近年の設備投資ブームや80年代からの旺盛な情報化投資の進展は、資本ストックのビンテージ(平均年齢)を低下させ、情報化装備率の上昇や技術革新の取り込みを通じ、資本ストックの生産能力を高めていると考えられる。
資本ストックの質の向上を計測するのは、いくつかの方法が考えられる。最初に、資本のビンテージの推移をみてみよう。ビンテージが低いほど、新規投資が活発に行われ、新しい技術を取り込んだ生産性の高い資本ストックが蓄積されていることを示している。産業別の資本ストックのビンテージをみると、卸売業や運輸、耐久財製造業などの労働生産性の伸びが90年代に入り高まっている分野では、90年代以降にビンテージが大きく低下している。これは、当該産業において、新規投資が活発に行われたため、老朽設備の更新が進み、資本の生産能力向上を通じて、労働生産性の伸びが高まったことを意味している。他方、建設業などのようにビンテージは低下しているものの、生産性の向上がみられない産業もある。建設業においては、労働集約的な側面があり、資本装備率の向上が直ちに労働生産性の向上にはつながらないためと考えられる(第2-3-10図)。
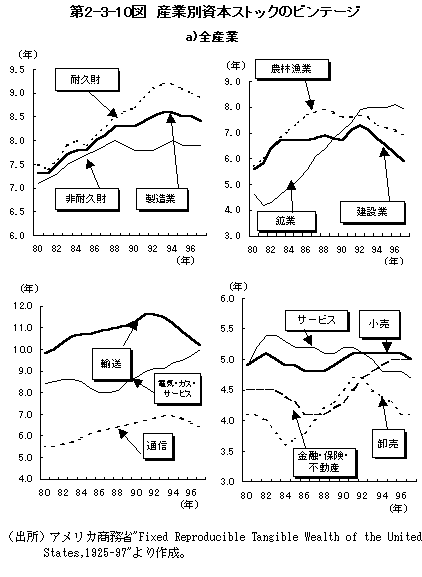
次に、製造業の設備稼働率データの分母である稼働能力指数の推移をみると、耐久財製造業を中心に、ここ数年資本ストックの実質額の増え方に比べて稼動能力の増え方が特異的に高くなっていることが観察される(第2-3-11図)。したがって、資本ストックの質が向上していると考えられることから、製造業の労働生産性が大幅に向上していても不思議はない。そこで、一人当たりの稼働能力の伸び率と労働生産性の関係をみると、一人当たりの稼働能力の伸び率が高い機械類などといった産業において、労働生産性も高くなっており、資本ストックの質の向上が労働生産性向上に寄与していることがわかる(第2-3-12図)。単純に資本装備率と労働生産性の伸びを比較すると、相関関係が弱いことから、この背景には、近年の情報化投資を始めとした新規投資による資本ストックの質の向上が、実質ベースの資本ストック額によって正確に把握されていないということがあるものと考えられる。そこで、情報関連ストック比率(情報関連資本ストック/資本ストック総額)を用い、製造業における情報関連ストック比率と稼働能力の関係を調べてみた。その結果、耐久財製造業では、情報関連ストック比率の上昇している業種ほど稼働能力の伸びが高く、情報関連ストック比率の高まりが稼働能力の向上に結びついたとみることもできる(第2-3-13図)。したがって、耐久財製造業においては、近年の旺盛な情報化投資が資本ストックの質の向上を通じて労働生産性上昇率の高まりに一役買った可能性があるといえよう。
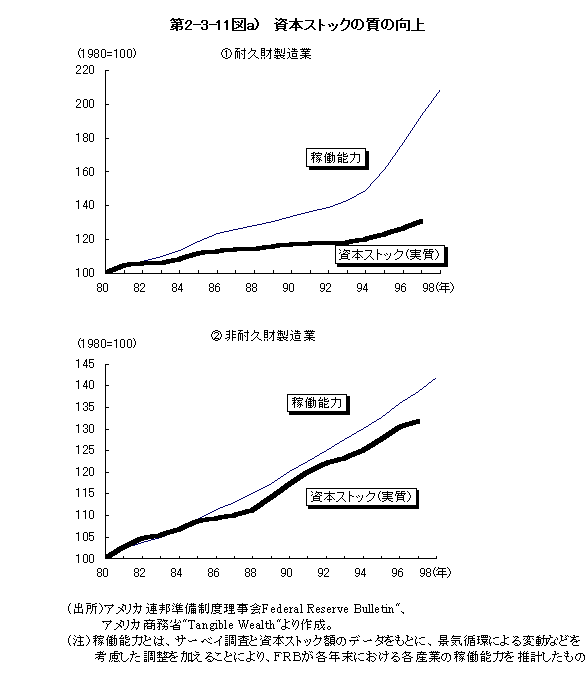
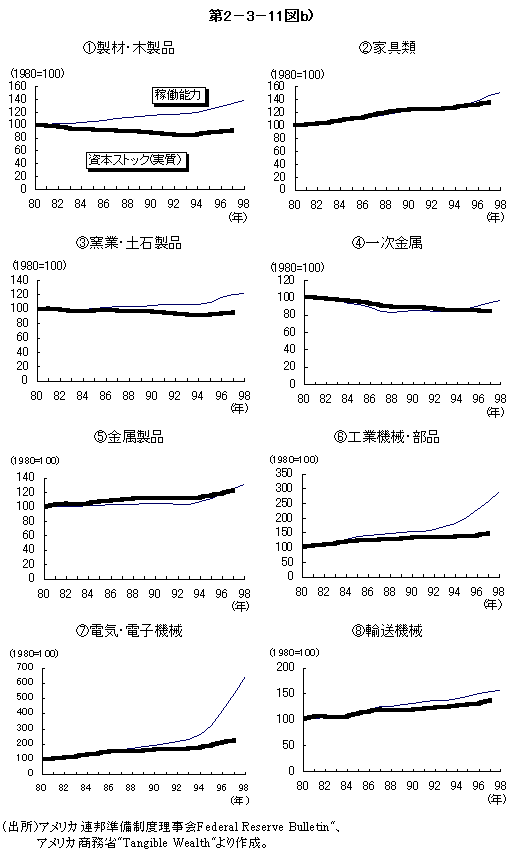
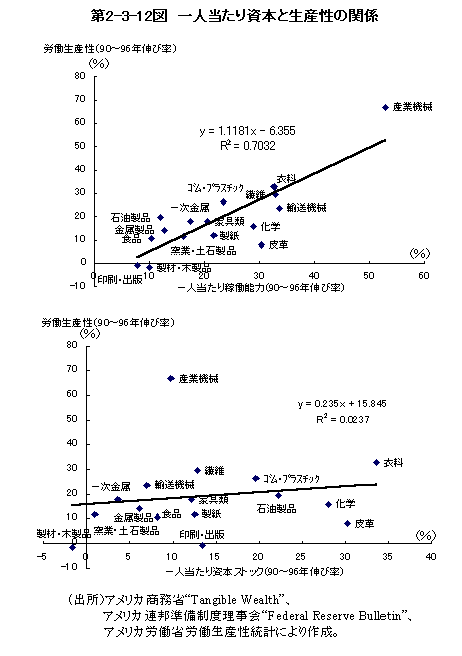
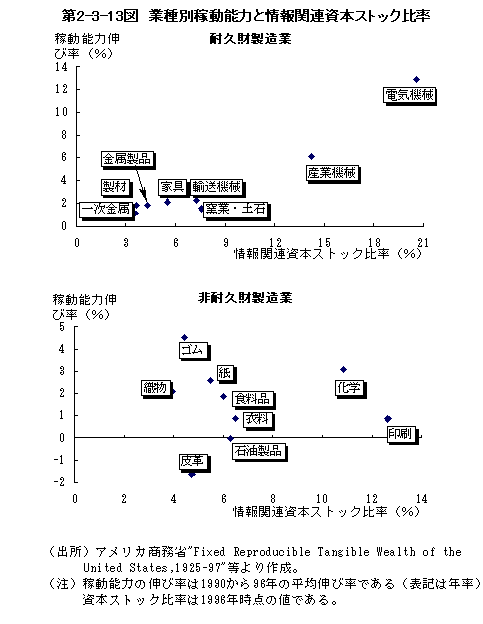
(情報通信革命の進展)
情報通信革命にもかかわらず、従来は生産性の向上がみられず、生産性パラドックスと呼ばれていた。情報化が進んでいるのにもかかわらず、経済全体では労働生産性の明確な向上がみられない原因の一つに情報関連ストック比率(情報関連資本ストック/資本ストック総額)が10数%と低いことが挙げられている。しかし、いくつかのミクロ的観点からみると、情報化と労働生産性には相関関係が観察される。
情報関連ストックの全ストックに占める割合の推移をみると、90年代半ば以降、生産性の向上している卸売業や金融、耐久財製造業(特に、電気機械や産業機械)において比率が高まっていることが分かる(第2-3-14図)。近年生産性を高めている小売業においては、レベルは低いものの、情報関連ストック比率の上昇速度は速い。また、労働生産性の伸びていない建設業などでは比率は小さく、高まっていない。このように、これらの業種では、情報関連ストック比率と労働生産性上昇率の推移には正の相関関係がみられる。他方、サービス業においては、生産性と情報化の関係が明確ではなく、情報関連ストック比率は高まっているが労働生産性の伸びはマイナスとなっている。ただし、サービス業においては、生産性が正確に捕捉できていない可能性もあり、情報化と生産性の関係がみえにくくなっているとみることもできよう。
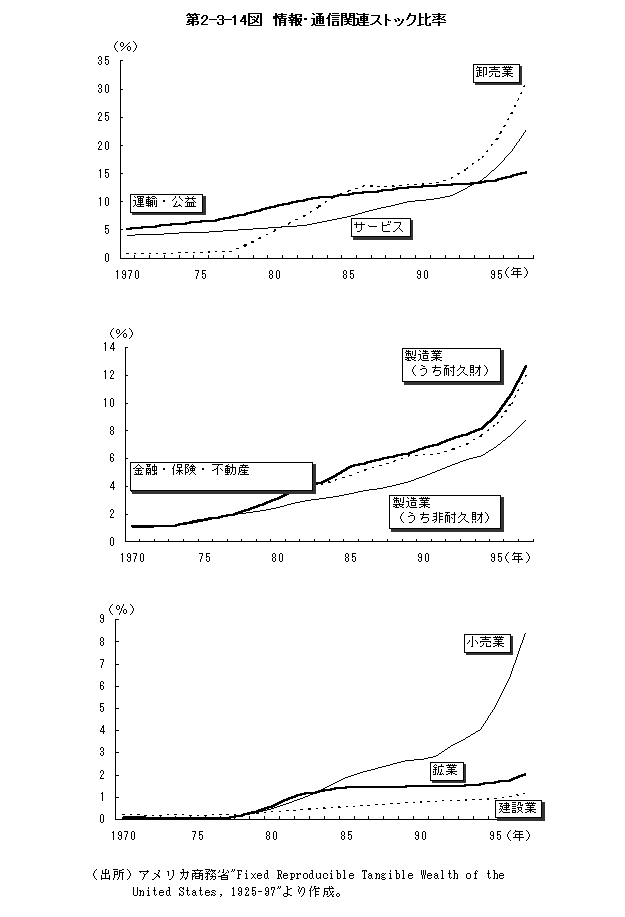
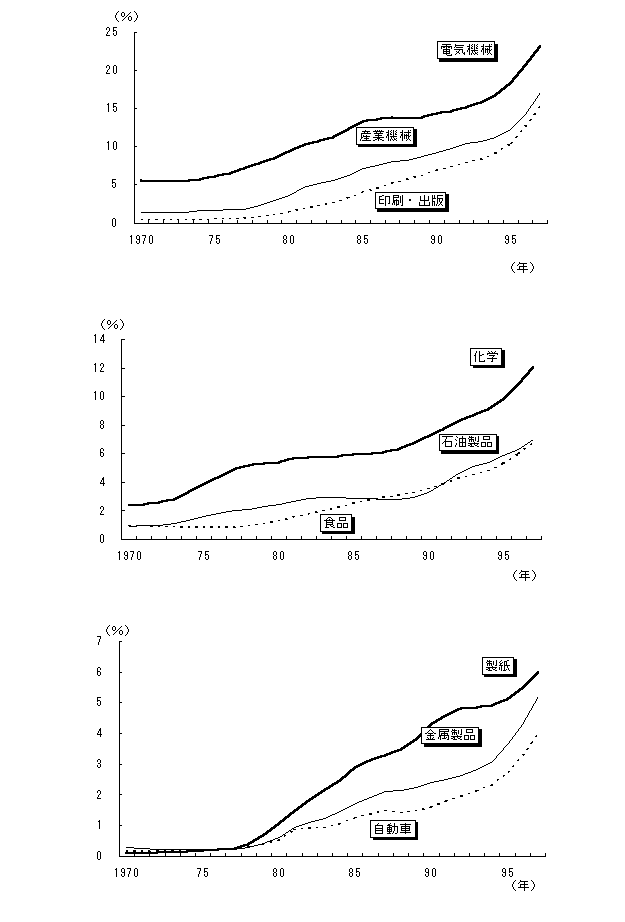
そこで、サービス業を除いた80年代と90年代の産業別労働生産性上昇率と産業別情報関連ストック比率の推移との関係をみると、明らかな正の相関関係があり、情報関連ストック比率が高いほど生産性上昇率の伸びが高く、情報関連ストック比率が上昇しているほど生産性上昇率も高まっていることが分かる(第2-3-15図)。耐久財製造業のみについてみると、情報関連ストック比率と労働生産性上昇率との関連はより明確であり、情報関連ストック比率の水準が高く上昇テンポも速い電気機械や産業機械において労働生産性上昇率が高く、上昇率自体も高まっていることが分かる(前項でみたように稼働能力の向上が関係している)。ただし、非耐久財製造業については明らかな関係は見られない。いずれにせよ、総じてみれば、情報関連ストック比率の高まりが、労働生産性上昇率を押し上げているとみることができよう。
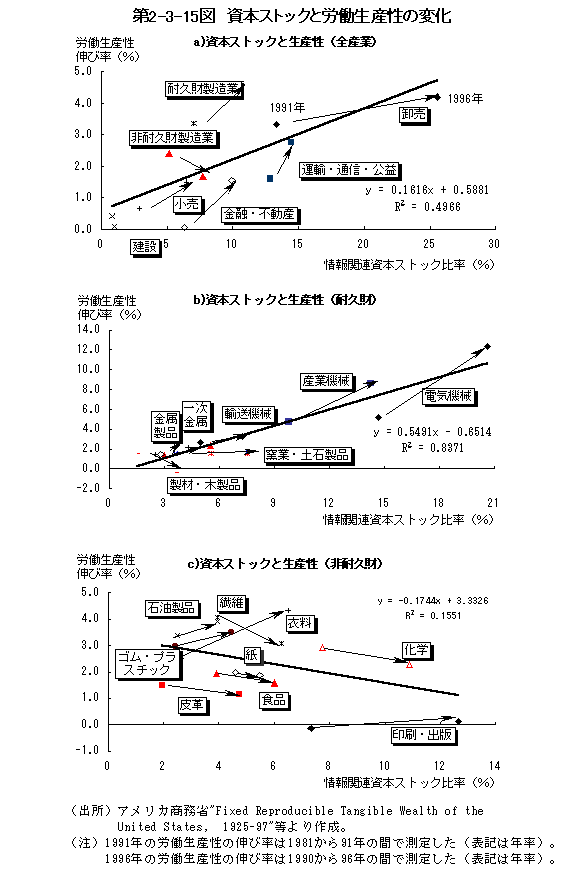
次に、情報関連ストック装備率と労働生産性の関係を分析してみると、情報関連ストックが1%増えたときの労働生産性の伸びは、非情報関連ストックが1%増えたときのそれよりも小さく、経済全体でみると必ずしも情報化投資の比率を高めることで生産性がより向上するという関係はみられない。これは、経済全体の5分の1を占めるサービス業において情報関連ストックの伸びと労働生産性の伸びとの関係が明確でないため、情報化によるプラスの効果が薄まって見えることや、近年における情報化投資の伸びが非常に高いといった理由であると考えられる(第2-3-16表)。しかし、情報関連ストック装備率の伸びに対する労働生産性の伸びへの波及効果は、80年代以降は、それまでに比べて高まっている。なお、製造業においても同様の分析を行ったが、有意な結果を得ることができなかった。
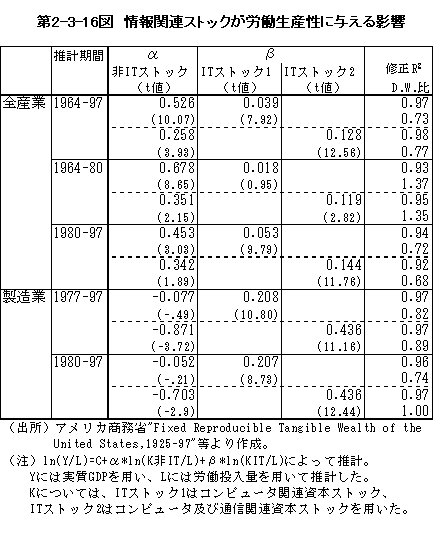
(経営手法の革新による効率化)
リストラによる労働コストなど各種コストの削減、部品調達の合理化・外部化、不採算部門の切り離しなどにより、企業の経営資源をより効率的な分野に投入できたことも労働生産性の上昇に寄与していると考えられる。具体的には、個々の企業において、いわゆるダウンサイジングと呼ばれる企業規模の縮小や企業組織のフラット化などがみられている。また、90年代に入ってから不採算部門の切り捨てや戦略部門の強化による企業収益の向上などを意図したM&Aが活発化している。こうした経営手法は一般化されてきており、人材の流動性の高まりとも相まって、産業全体の経営効率の向上につながっている。
4 生産性向上の持続可能性
90年代のアメリカは、情報化投資を中心とする資本ストックの充実によって、機械などの耐久財製造業を始めとする産業において労働生産性を高め、90年代の後半に経済全体の生産性を向上させた。
では、これまでみてきたような一部の製造業における労働生産性の高い伸びは、今後も続くのだろうか。さらに、現在労働生産性の向上がみられない他の産業においても、今後労働生産性の高い伸びがみられるようになるのだろうか。これらの点については、不確定な要素が大きく、一概には断定できないが、楽観的に考えることは難しいであろう。他方、情報化投資は、コンピュータなどの技術革新スピードが速く、景気変動の影響を受けにくいため、今後も旺盛な投資が続き、既に労働生産性の向上がみられる分野では引き続き生産性の上昇が続くとともに、情報関連ストックの積み上がり度合いが低い小売業などにおいても、情報関連ストック比率が高まることで、生産性の伸びも高まっていく可能性もある。しかし、次のようなことから、今後は労働生産性の高い伸びが持続しない可能性がある。
- a)現在の投資ブームは景気減速とともに後退すると見込まれるため、労働生産性の加速がみられる産業において、旺盛な情報化投資などによる資本ストックの質の向上が今後も続くかどうか不明瞭である。また仮に設備投資の高い伸びが続いたとしても、一般的には限界的な生産額の増加は鈍化していくと考えられる。
- b)情報化投資の効果が特定の産業でみられるとしても、他の業種においても同等の効果が発揮されるかどうかは不確定である。なぜならば、産業によっては情報化投資によって代替可能でない労働や資本ストックを必要としている場合があるからである(例えば建設業)。
- c)サービス業における労働生産性の向上が適切に計測できないため、これらの産業における今後の労働生産性の推移を見通すことが困難である。
したがって、情報化と労働生産性の関係に関するより精緻なデータ収集・分析やサービス業などにおける付加価値生産額の適切な把握などに努め、今後を見極めるために十分な材料を用意することが重要である。
- 注1 80年代末にも労働生産性が70年代に比べて向上する局面があり、現在と同じような議論がなされたことがある。(88年大統領経済報告参照)
- 注2 ただし、長期的には、労働生産性の伸びの高まりは、実質賃金の伸びに反映されるため、インフレに対して中立的である。
- 注3 例えば、規制をクリアするために生産性向上に結びつかない設備投資を行うことなどが挙げられる。
- 注4 消費者物価指数は、98年に、幾何平均指数やパソコン価格におけるヘドニック法の導入などという大幅な改訂を行っている。
- 注5 ただし、このデフレータの改訂状況は、産業ごとに一律ではない。例えば、98年改訂時における労働生産性の修正状況をみると、民間企業部門全体では、上方修正されたが、製造業は下方修正されている。
- 注6 設備稼働率に着目すると、景気拡大局面では稼働率が上昇するため、労働生産性の伸びが高くなり、景気後退局面では稼働率が低下するため、労働生産性の伸びが低めに出る傾向がある。これを現在の局面に当てはめると、資本ストックの積み上がりによって稼働率が低下しているため、真の労働生産性はみかけよりも高いと考えることができる。
- 注7 労働省の統計においては、非営利団体や個人企業は含まれていない。
- 注8 所得サイドから計算されており、非営利団体などを含んだベースである。このため、労働省統計との単純な比較はできない。
- 注9 業種別の労働生産性は、産業別実質GDP/就業者数によって求めている。
- 注10 例えば、79年以来、非製造業は企業部門の多要素生産性の上昇率にほとんど寄与しておらず、寄与度は79~90年では0、90~96年でも同様に0という指摘もある(Gullickson&Harper "Possible measurement bias in aggregate productivity growth" Monthly Labor Review, 1999.2.)。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 アメリカ経済の長期拡大の要因と課題 | 第3章 物価安定下の世界経済 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | 通貨・金融システム | 特徴 | 要因 | 生産性 | 課題 | 現状 | 要因 | 特徴 | 金融政策 |

