第1章 日本経済の現状とデフレ脱却に向けた動き(第1節)
第1節 日本経済の現状
本節では、最近の景気動向を概観し、堅調な雇用・所得環境の改善と消費との関係、企業収益が高い水準にある中での設備投資の動向といった支出面の動向について検証する。
1 景気の現況と今次景気回復期の特徴
(緩やかな回復基調が続くが、海外経済等に不確実性)
2016年のGDPの動向については、1-3月期から7-9月期まで3期連続で名目及び実質ともに成長率がプラスとなるなど堅調な動きとなっている。需要項目でみると、低金利の下で住宅投資が持ち直し、公共投資も底堅く推移するなど、財政金融政策による政策的な下支え効果も出てきた。一方で、設備投資は2012年以降おおむねプラスで推移してきたものの、2016年に入ってからは、年初から為替レートが円高方向へ動いたことなどを背景に、企業マインドの一部に慎重さがみられ、持ち直しの動きに足踏みがみられる。(第1-1-1図(1))
個人消費については、基調としては底堅く推移したものの、一時的な下押し要因の影響がみられた。具体的には、2016年4月に発生した熊本地震の影響、7月の軽自動車の燃費計測不正問題等による自動車販売への影響、夏場の台風上陸回数が例年よりも多かった影響等により、個人消費の伸び率が低めに抑えられたとみられる。ただし、こうした中でも、2016年1-3月期から7-9月期まで実質の家計消費支出は3期連続プラスとなるなど、雇用・所得環境が引き続き改善する中で、2016年秋以降は一時的な要因の影響が薄れ、持ち直しの動きもみられる。
外需については、四半期の動きをならしてみれば輸出入とも実質でほぼ横ばい圏内の動きとなっており、GDPへの寄与も限定的であったが、2016年央以降はアジア向け電子部品・デバイス等を中心に輸出がやや持ち直している。他方、年初にみられた円高方向の動きや原油価格の低下などもあり、同年前半には輸入金額が輸出金額と比べて相対的に大きく低下し、交易条件の面から名目GDPを押し上げた。年後半には、円高方向の動きや原油安の動きも一服し、交易利得の寄与は縮小している。
生産面については、2016年夏以降の自動車の国内販売の回復を受けて自動車生産が持ち直すとともに、アジアを中心にしたスマートフォン関連の需要増加を反映して、電子部品・デバイスや半導体製造装置などの生産も持ち直している。雇用については、人手不足感が強まる中で、2016年11月時点で、有効求人倍率は1.41倍まで上昇し、失業率も3.1%に低下するなど、いずれも1990年代以来の水準まで回復している。
今後の経済動向に関するリスクとしては、海外経済の不確実性や金融資本市場の動向に留意する必要がある。2015年末のアメリカの政策金利引上げの影響もあって、金融資本市場に大きな変動がみられ、原油価格も更に低下する中で、2016年前半には、中国を始めとする新興国経済や資源国経済が減速したことから、それによる我が国経済への影響が懸念された。ただし、2016年後半の動きをみると、中国では政策的な下支えもあって景気は持ち直しており、資源国経済は、原油生産量に関する一定の合意がなされる中で原油価格も上昇に転じ安定化に向けた動きがみられる環境にあるなど、弱さが和らいでいる。他方、各国の政策動向に関する不確実性は引き続き注視する必要がある。2016年6月には、英国のEU離脱に関する国民投票において離脱賛成派が多数となったことなどから、今後、EU離脱に向けて英国がどのように進むのかについて不確実性が高まっており、それが英国及び欧州経済に与える影響について留意する必要がある。また、11月にはアメリカで次期大統領が選出されたが、今後、新政権がどのような経済政策を打ち出していくのか等、注視していく必要がある。加えて、中国についても、過剰設備や、不良債権問題などにどのように対処していくのか留意する必要がある。
(今次景気回復局面の特徴)
第1-1-1図(2)は、2012年10-12月期を起点として、実質GDPの各項目の推移を示し、それ以前の3回の景気回復と比べたものである。これによれば、2012年11月以降の今次景気回復局面は、過去の景気回復局面と比べて次のような特徴を持っている。
第一に、内需のうち消費や投資の伸びが弱いことである。個人消費は消費税率引上げに伴う駆け込み需要もあってプラスとなっていたが、その後、反動減によりマイナスとなり、2016年7-9月期の時点までの期間を通じて2012年10-12月期の水準をわずかに上回る程度となっている。また、設備投資は2012年10-12月期からすぐに増加したが、2016年に入ってからは横ばいとなっている。他方で、住宅投資については、消費税率引上げ後に一度は減少したものの、その後低金利もあって2016年になってからプラスとなっている。
第二に、外需については、景気回復の起点からの実質GDPに対する累積寄与でみても1%程度と限定的なものとなっている(第1-1-1図(1))。それ以前の景気回復期の外需の推移と比べても弱い動きにとどまっている。これは、輸出及び輸入とも、2015年前半から横ばい圏内となっていることによるものである。ただし、2016年後半にはアジア向け輸出が好調なことから、輸出全体で増勢がみられる。
第三に、デフレーターの動きをみると、過去3回の景気回復期と比べて大きく環境が異なっており、景気回復期が始まってからプラスの方向に推移した。2016年に入ってからは、原油安や円高方向への為替レートの変動等の影響もあり、横ばいとなっている。
以下では、第1節第2項及び第3項において消費や住宅といった家計部門について、第4項及び第5項において輸出入の動向と企業部門についての分析を行う。物価については、第2節において、最近の賃金引上げに関する政策との関係も踏まえ、分析する。第3節では、長期的な視点に立って、人口減少・少子高齢化の影響も踏まえた労働市場の変化について考察する。
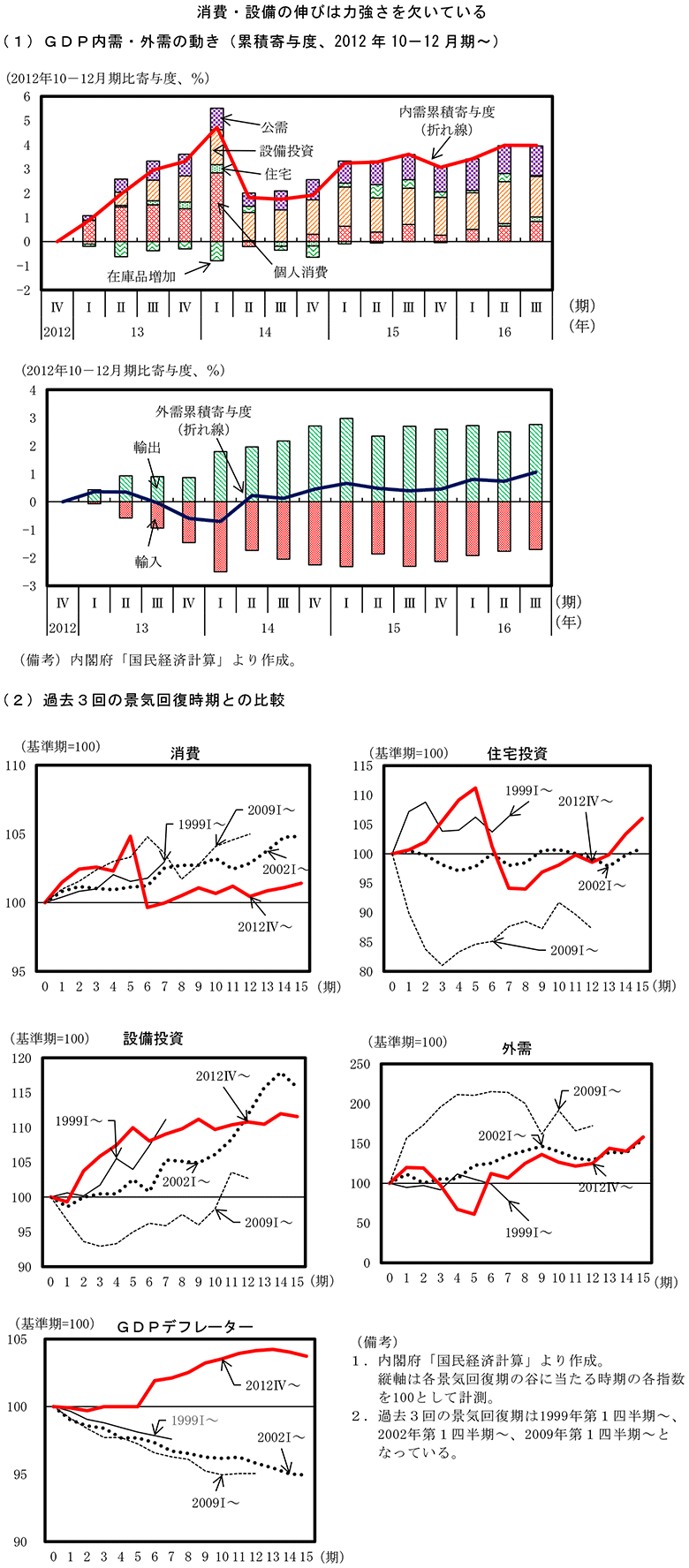
2 雇用情勢と家計の所得・消費動向
(引き続き改善がみられる雇用情勢)
雇用情勢は引き続き改善している。2016年11月時点で、有効求人倍率は1.41倍と1991年8月以来の高水準、失業率は3.1%と1995年以来の低水準で推移している(第1-1-2図(1))。労働市場の詳細な分析は第3節で行っているが、こうした雇用情勢の改善は、単に人口減少による人手不足が反映されているだけではない。労働供給面では、労働参加率の高まりによって労働力人口が増加する中で就業者数も伸びており、労働需要面では、非製造業において新たな雇用が創出されているとともに、製造業においてはリーマンショック後の景気低迷以降みられた雇用喪失からの持ち直しなどもみられる。就業者数は2016年度の上半期で前年同時期と比べて1.6%程度の高い伸びとなっている。ただし、就業者に占めるパートタイム労働者比率の一貫した上昇や、正社員等でも比較的勤務時間が短い労働者の労働参加が進んだこと等から、一人当たりの平均労働時間は低下しており、マンアワーでみた総労働供給(就業者数に一人当たり労働時間を乗じたもの)は、就業者数の増加にもかかわらず、緩やかな伸びにとどまっている。
一人当たりの現金給与総額は、パートタイム労働者比率の上昇が下押しに影響しているものの、2016年の上半期で前年同期比0.5%程度の伸びとなっている。就業者数の増加も考慮した総雇用者所得については、2016年1~9月期までの間、前年の同時期と比べて2.1%と緩やかに上昇しており、実質でみても2.5%程度の伸びとなっている(第1-1-2図(2))。
この所得の伸びは、給与の高い層の割合等が極端に増えたことによるものではない。比較的高い給与所得者層の推移をみると(第1-1-2図(3))、1,000万円から2,000万円の給与所得者の割合は1990年代に5%程度まで上昇したが、2008年ごろに減少し、その後3%台で推移している。2,000万円以上の給与所得者の割合は過去から長期間にわたって増加傾向にあるが、2014年時点で0.5%にも満たない。一方で、比較的低い所得者の所得は若干の増加がみられる。例えば家計調査(2人以上の世帯のうち勤労者世帯)について、その年収の少ない順に5つのグループに分け、グループごとの平均所得を比較すると、最も年収の低いグループとなる第1分位の所得は、2012年以降若干の増加傾向にある。これは、最低賃金引上げの影響等もあると考えられる(1章2節2参照)。
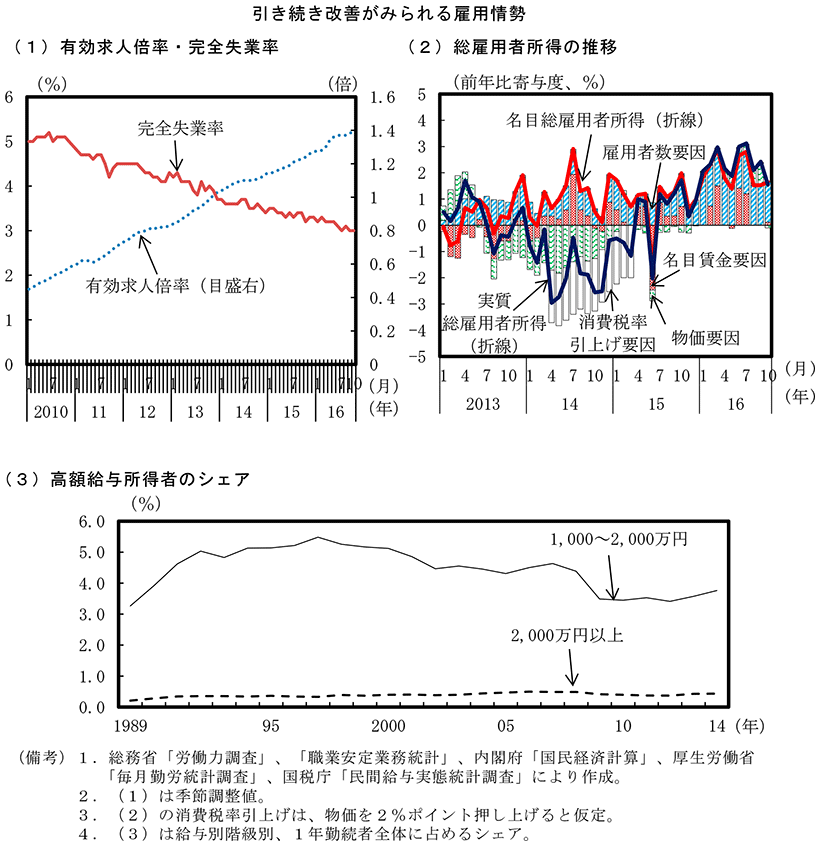
(家計の可処分所得の動向と消費との関係)
こうした賃金の伸びと比べて、消費は底堅いとはいえ、その伸びは力強さを欠いている。このことについては、前述のような一時的な消費下押し要因のほか、政策面の影響や、家計の消費に対する慎重な態度などが影響している。具体的には、エコカー補助金や家電エコポイント制度の利用による購入や消費税率引上げ前の駆け込み等、耐久財等を始めとする需要の先食いや一部家計における消費を手控える動き等である1。
個人消費と所得の関係について、雇用者報酬及び金融資産等を説明変数に用いて推計を行うと、2011年度から2013年度にかけて所得等から推計される伸びを上回って消費が増加した後、2014年度以降は消費が推計値の伸びを下回って推移した。ただし、2016年になってその差が縮小している(第1-1-3図)。消費が所得等からみた推計値の伸びと比べて下方にかい離していた要因としては、耐久財を中心にした需要の前倒しからの反動減によるところが大きいと考えられ、最近では、そうした影響を相殺する消費の持ち直しによって所得に見合った伸びに戻りつつあると考えられる。以下では、賃金・俸給だけでなく、財産所得、税や社会保障の負担、社会保障給付等も含めた可処分所得を念頭において、所得と消費との関係について考察する。
マクロでみた家計の所得動向について、名目実績値について国民経済計算の所得支出勘定の推移をみると(第1-1-4図(1))、長期的には、1990年代から2010年にかけて、一次所得及び可処分所得は緩やかに減少し、その後、増加傾向にある。この動きについて、所得面の各項目をみてみると、賃金・俸給は、1990年代半ば以降おおむね低下を続けたが、2013年以降は増加に転じている。財産所得は、低金利等の影響もあって利子受取が減る一方、配当がすう勢的に増え、全体としては2000年代半ば以降で長く横ばいの動きとなっている。分配面においては、年金の受取等、現金による社会給付の受取が増している影響がある。1990年代から2000年代前半にかけてその伸びは10年間平均で5%程度の増加がみられるが、2010年~15年は5年間平均で0.5%程度の推移となっている。他方、税・社会保障の負担についてみると、社会保険の負担(雇用主・雇用者双方の負担)は、賃金等の伸びに加え、保険料率の上昇等に伴い長期的に増加する傾向にあるが、所得税についてはおおむね、賃金等の所得の増減に伴う動きとなっている。
このように、プラスとマイナスに作用する要因がある中で、2013年~15年までの3年間で賃金・俸給は年平均1.2%増加したのに対し、可処分所得は0.6%程度の増加にとどまっている。可処分所得に対する家計最終消費支出の割合(いわゆる平均消費性向)は、2013年~14年の初めにかけて消費税率引上げ前の駆け込み需要があったことなどから可処分所得の伸びを家計の最終消費支出の伸びが上回って1%ポイント程度上昇し、2013年でほぼ100%となったが、その後2014年~15年には1%ポイントずつ低下している。2016年の消費支出の動きについては、7~9月までの伸びでみておおむね横ばいとなっているが、第1-1-3図にあるように2016年後半に差し掛かって消費の伸びがみられており、年を通じると微増の動きとなると見込まれる。
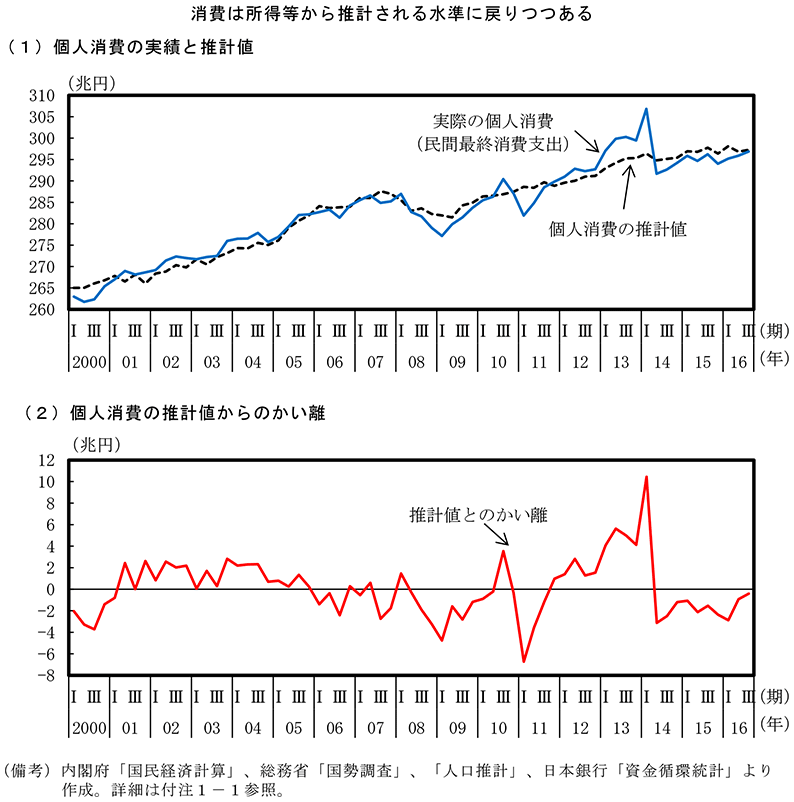
第1-1-4図(2)は、2013年以降について可処分所得を算出する各項目のその前年からの変化をみたものである。2016年の値については7-9月期までのデータを用いて試算したものである2。その傾向をみると、2014年~16年にかけて賃金・俸給の伸びが継続している。特に、2015年以降については所得税や社会負担の伸びはあるものの、賃金・俸給等の所得の伸びが進み、社会給付も一定程度増えていくことで、可処分所得の伸びも高まっている。
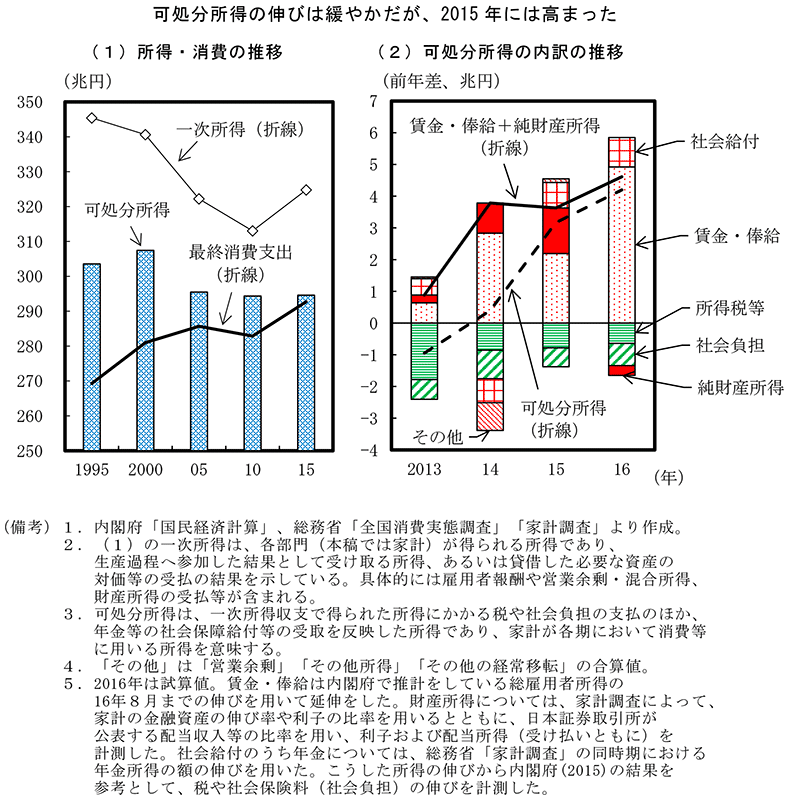
以上は、マクロでみた結果だが、全ての世帯がこうした支払や受取について同様の影響を受けるわけではなく、世帯によって様々となる。特に賃金との関係に注目し、家計調査の2人以上の世帯のうち勤労者世帯の平均消費性向の動きをみると(第1-1-5図(1))、世帯の属性によって、その水準や動きは異なっている。世帯主年齢別にみると、59歳以下の世帯については75%以下で推移し、この数年は平均消費性向が低下している。この層の消費も増加してはいるが可処分所得の伸びほどではなかったと考えられる。一方で、60歳以上の世帯については、2000年代になって消費性向が上昇しており、それまで80%台で推移していたが、2015年時点では90%を超える水準で推移している。第1-1-5図(2)は世帯の年間収入について、5つのグループに分け、平均消費性向をみたものである。収入の最も低い階層を第1分位としており、所得が低い階層の方がおおむね消費性向は高い傾向がある。特に、最も年収の低い第1分位階級では2015年に消費性向が下落している。これには一時的な所得の増加があったにもかかわらず、消費が増加しなかったこと等が影響している。当期の所得増と同等に消費が必ずしも増加するわけではなく、消費にはある程度の習慣性があることから、一時的な所得の増加は平均消費性向の減少に寄与する。収入等の継続的な増加によって消費行動に変更があれば、平均消費性向もまた上昇する等の動きが想定される。ただし、第1分位や第2分位においては、年金受給世帯も多く含まれ、年齢属性等の影響も色濃く反映されることに留意は必要であり、所得の増加についても勤労所得や年金所得等の所得の源泉については、同じ分位の中でも世帯間の差があると考えられる。
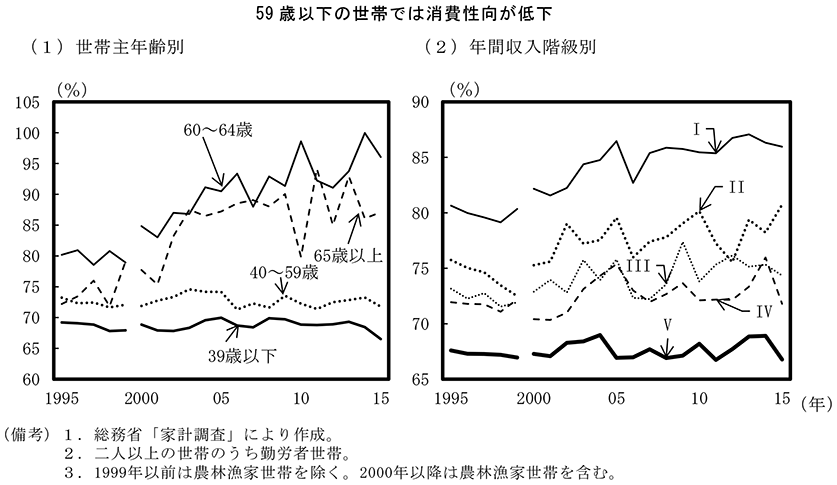
コラム1 余暇時間とサービス消費について
余暇と消費支出の関係については、一般的には、余暇が減少した場合には消費が増加することで個人の効用を一定に保つような代替関係があると考えられる。ただし、旅行を始めとするサービス消費のように、一定以上の時間がないと物理的に消費ができないものについては、労働時間の増加で余暇時間が圧縮されると、その消費が制約される可能性もある。
2000年以降の労働時間の推移をみると、相対的に労働時間の短いパート労働者比率の高まりにより総労働時間は減少傾向にあるものの、一般労働者の労働時間は高止まりしていることが分かる(コラム1-1図)。ここで、年齢階級別の生活時間を比較すると、40~50代の働き盛り世代は他の世代に比べて消費支出が多いにもかかわらず、仕事等の第2次活動に時間を圧迫され、趣味・娯楽に使う時間が少ない傾向にあり、特に男性では、買い物にかける時間も少なくなっている(コラム1-2図)。また、労働時間と個人消費との関係を照らし合わせると、一般労働者の労働時間が大きく減少した2000年代前半ではサービス等の消費が伸びたが、2009年以降では、労働時間が高止まりしており、サービス消費の伸びの低下が同時にみられている(コラム1-3図)。
家計は余暇と消費の代替関係を考慮して、最適となる余暇時間(労働時間)を選択すると考えられる。しかし、自らの都合で就労時間を自由に決定できる就業者は多くないため、家計は最適な時間配分を行うことができていない可能性がある。このことは、働き盛り世代が柔軟な労働時間の選択を可能にすることにより、サービスを中心として、これら世代の余暇消費が促進される可能性を示唆している。
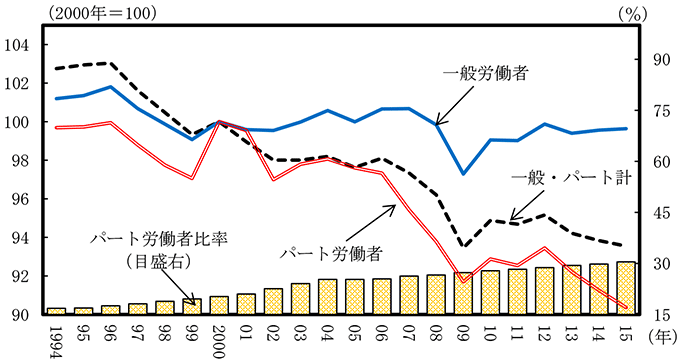
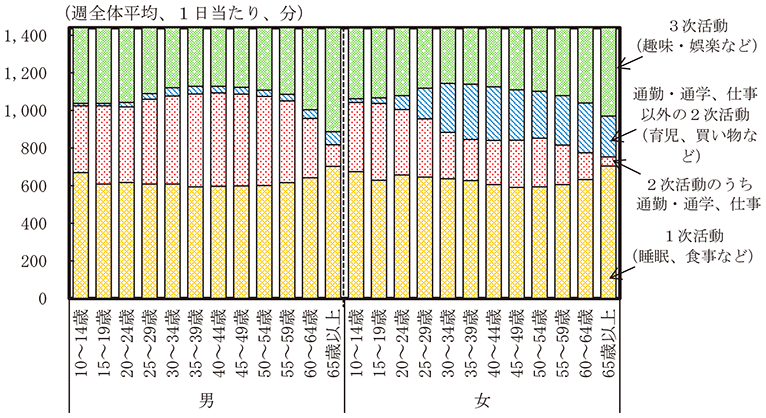
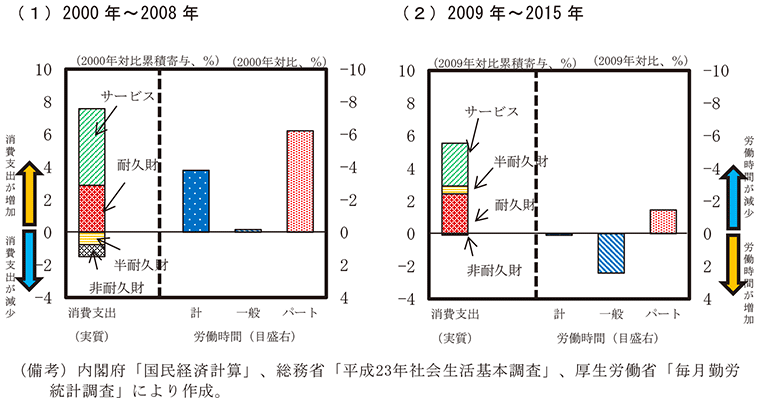
(少子高齢化が個人消費に与える影響)
中長期的にみると、少子高齢化の進展による人口構造の変化が個人消費にも影響を与えている。我が国の世帯の年齢分布をみると、世帯主が60歳以上である世帯は、2000年には3割程度であったが、2015年には4割を超えている。他方で、同期間に40歳未満の世帯の割合は3割であったものが2割まで減少している(第1-1-6図(1))。
高齢化による消費の変化を分析するため、年齢階級ごとの消費支出の変化をみると、世帯当たりの消費支出の総額は年齢が上がるとともに増加し、50歳代をピークに減少していく。これは、50歳代が最も世帯人員が多くなることも影響している。支出の内訳をみると(第1-1-6図(3))、シェアの大きい食料や交通・通信、教養娯楽への支出額は、世帯人員数におおむね比例すると考えられ、支出総額と同様に40~50歳代をピークとする山形となっている。教育は、シェアとしては1割に満たない支出となっているが、子どもが大学等に通う時期に大きく増加し家計の支出を押し上げる。また、保険・医療への支出は健康問題が出てきやすい高齢期に増加するが、住居費は持ち家率が高くなる50歳代以降で小さくなる。
また、消費行動は、年齢別の世帯類型だけでなく、生まれ年によっても違った特徴があると考えられる。生まれ年別に年齢別の消費支出額(消費プロファイル)をみると、1970年代以降生まれの世代では消費水準がそれ以前の世代と比べて低い傾向にある(第1-1-6図(2))。その背景として、少子化や核家族化といった社会構造の変化により平均世帯人数が減少傾向にあること等が考えられる。また、若い世代ほどパートやアルバイト等正規の職員・従業員以外の雇用形態で働く者の割合が高まっており、雇用の不安定さや収入が家族形成を難しくする要因となっている可能性が指摘されている。最新の国勢調査(2015年)では、40代前半男性のうち単身世帯が16%(2000年調査では11%)、非世帯主が24%(2000年調査では21%)となっており、単身世帯化や独立せずに世帯主とならない「非世帯主化」が進んでいる可能性がある3。
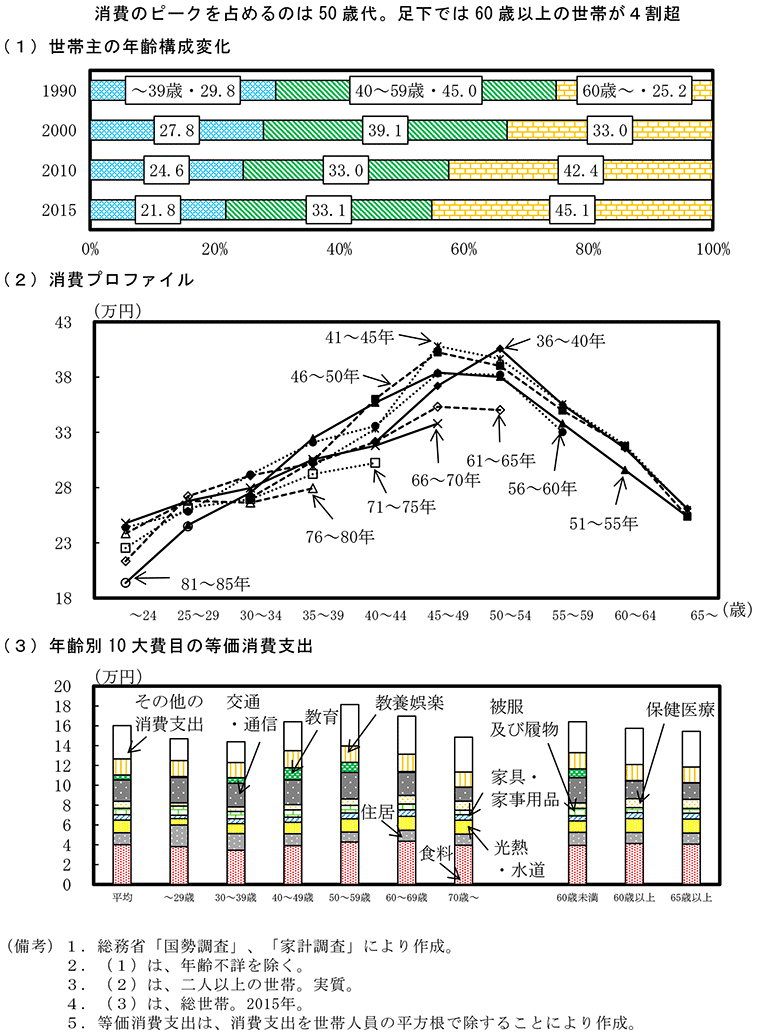
人口構造の変化がマクロでみた個人消費に与える影響をみるために、家計調査を用いて、一人当たり消費支出の動向と世帯数の動向に分けてみると、2002年以降は世帯数の増加が一貫して個人消費に対してプラスに寄与している一方で、1世帯当たりの消費支出は世帯当たり人員の減少もあってマイナスに寄与している。また、60歳未満の世帯の消費支出は60歳以上の消費支出よりも大きいため、60歳以上世帯の構成割合が高まると、マクロの消費支出が下押しされる。こうした世帯の高齢化の影響は、2002年時点と比べて、2015年の段階でマクロの消費支出を3%ポイント程度押し下げている(第1-1-7図(1))。
以上の分析は、純粋に年齢の違いによる消費行動の差だけでなく、既に述べた生まれた年代に特有の消費行動(世代効果)やその時々の景気状況等の影響(時代効果)も含んでいる。これらの影響を推計によって取り除き、年齢の違いによる消費行動の差のマクロの消費への影響だけを試算したところ、2000年から2015年にかけて1世帯当たりの消費が低下する結果を得た(第1-1-7図(2))。これは、人口構成上大きな割合を占める第一次ベビーブーム世代、いわゆる「団塊の世代」(1947年~49年生まれ)が高齢化によって徐々に消費額の低い年齢層に移行したことによるものと考えられる。今後については、第二次ベビーブーム世代、いわゆる団塊ジュニア世代が親世代と同様の消費パターンを描くことを仮定すれば、50歳代に入って消費支出を増加させると考えられることから、2025年にかけて消費を押し上げる方向に働くことが見込まれる。ただし、その人口構成の変化のインパクトは全体の消費額に比べて小さく、限定的なものといえる。
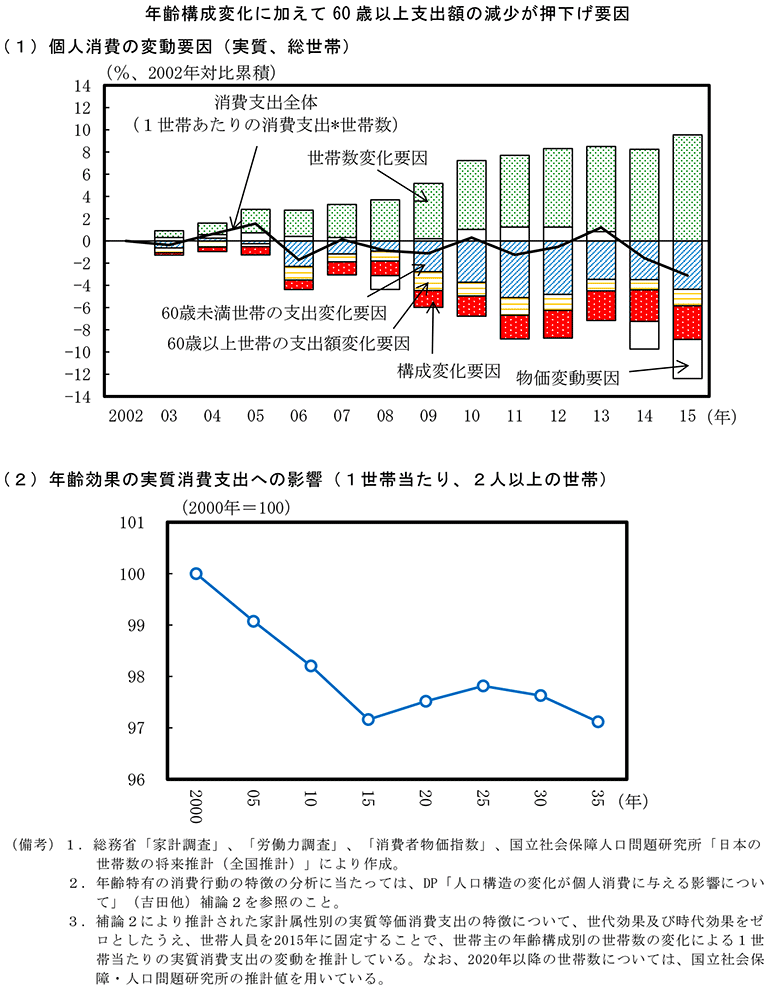
3 住宅投資・公共投資
(住宅投資は貸家が伸びている)
新設住宅着工戸数は、総数でみると、2016年に入って持ち直しに転じ、2016年央以降は、消費税率引上げ前の駆込み需要があったとみられる2013年下半期に並ぶ年率100万戸前後の水準で推移している。利用関係別にみると、持家や分譲は2016年後半に入って横ばい圏内の動きとなっているが、貸家は2016年に入って以降、増加ペースが更に加速しており、この貸家の増勢が着工戸数の増加の主な要因となっている。
貸家が増加する背景としては、家主側からみて金利の低下によって採算性が改善していることを反映していると考えられる(第1-1-8図(1))。貸家建設向けの貸出金利の動向をみると、2016年に入ってから、長期金利の一段の低下を受けて大きく低下している。また、貸家建設によって節税効果が得られることも背景の一つにあるとの指摘もある。ここでは、貸家建設に係る採算性について、金利だけでなく建設費用や家賃の動向等も含めて包括的にみてみよう。東京近隣県は2015年半ば頃から空室率が拡大するとともに家賃収入が伸び悩んでいるものの(第1-1-8図(2))、家賃収入を年間の返済額で除した採算性指数で賃貸住宅を経営する家主(以下「貸家オーナー」という。)の収益性は、建築コストが緩やかに減少していることや低金利を背景に2016年に入ってから大きく上昇している。そのため、貸家オーナーとなるインセンティブが高まり、貸家の建設需要が強まっていると考えられる。また、建設に伴う資材調達状況が緩和し、建設業者においても、持ち家などの伸びが一服する中で、持ち家の建設に従事する人員の不足感も解消されていることから、貸家の建設供給に人的物的リソースをシフトしている可能性が考えられる。
貸家全体の需給状況を確認するために、人口動態や貸家ストックの滅失について一定の前提を置いて推計した貸家の潜在需要の増加と実際の貸家の着工戸数を比較すると、少子高齢化の進行等に伴い、若年を中心にした賃貸居住の対象となり得る世帯数の伸びが低下すると見込まれることにより、2016年では貸家着工戸数の実績値が潜在需要を超過する可能性が示唆される(第1-1-8図(3))。貸家のオーナー側の需要が更に伸びて住宅の供給超過となる場合には、家賃の下落やこれに伴う貸家オーナーの採算性の悪化などが懸念されることから、今後の動向については、注視していく必要がある。
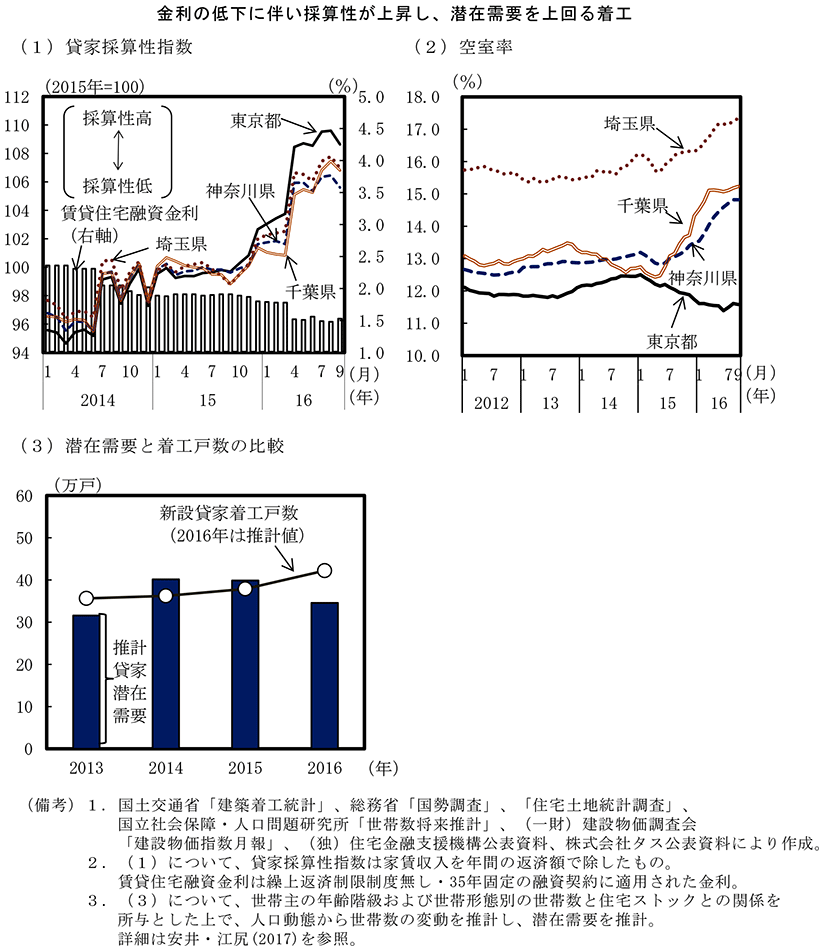
(公共投資は底堅い動き)
2016年度の公共投資は、2015年度補正予算の執行や2016年度当初予算の早期執行もあり、底堅い動きとなっている(第1-1-9図(1))。特に、2016年度の予算については、上半期(4~9月)のうちに8割程度が契約済みになることを目標として早期執行が行われたこともあり、この上半期の請負金額は堅調な伸びとなった。請負金額を発注者別にみると、予算の早期執行目標の対象となる国や独立行政法人等で前年度を上回ったほか、地方においては、全国防災事業4の終了等により投資的経費の計画予算が前年度を下回る中にあっても、都道府県でも昨年度の水準を超えて堅調に推移した(第1-1-9図(2))。
今後は、「未来への投資を実現する経済対策」及びそれを具体化する2016年度第2次補正予算が執行されることやオリンピック関連投資が本格化することで、請負金額も増加するとともに、工事の進捗を示す出来高も押し上げられると見込まれる。
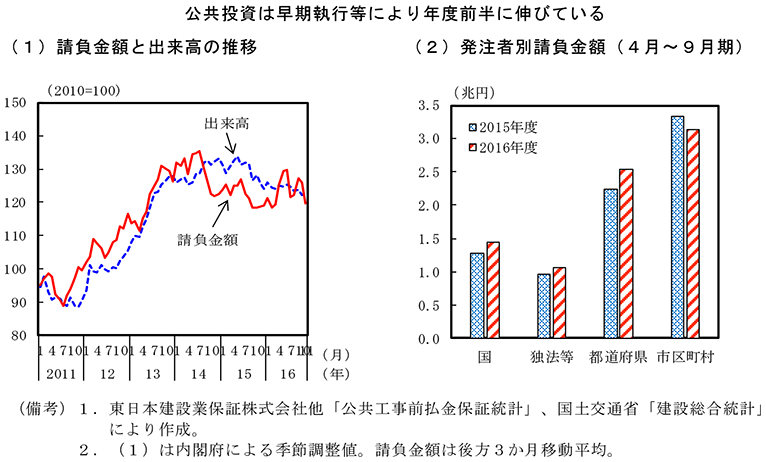
4 企業部門の動き
(世界経済の動向と日本の輸出及び生産)
国際通貨基金の世界経済見通しによると、世界の実質GDP成長率は、2016年に3.1%程度と2015年の3.2%成長から引き続き弱い伸びにとどまると見込まれている(第1-1-10図(1))。こうした中で、世界全体の貿易量は2000年代までと比べると、世界金融危機以降は伸びが大きく低下している(第1-1-10図(2))。その背景として、これまで高い成長が続いた新興国や資源国における経済成長の鈍化の影響に加え、2000年代に進んでいた自由貿易圏の拡大やグローバル・バリュー・チェーンの構築が一服したことや、世界的な設備投資の低迷によって資本財等を中心とする貿易が低迷していること等が挙げられる。中間財の輸出入額を世界全体でみても、2000年代に大きく伸びたが、その後横ばいの動きとなっている。この中間財輸出入のシェアを高めているのは中国などのアジア諸国となっており、日本の中間財輸出入のシェアはやや低下している(第1-1-10図(3))。
そのほか、我が国の主な財別の輸出動向をみると、自動車輸出は、2016年前半に弱い動きとなっていたものの、後半には、アメリカ・欧州向けの輸出が堅調であることや、資源国向けの輸出の落ち込みが一服したことから、持ち直しがみられた(第1-1-11図(1))。また、2016年後半に入ってからは、電子部品・デバイス等の輸出が大きく増加した。年初は前年の世界におけるスマートフォン販売の伸び悩み等の影響を受けて下がっていったが、年後半からは、中国等アジア諸国における高品質のスマートフォン需要の高まり等を背景として、液晶ディスプレイや半導体等電子部品の輸出が堅調となっている(第1-1-11図(2))。
生産の動向については、アジア向けのスマートフォン関連の好調な輸出動向等を反映して、電子部品・デバイスや半導体製造装置の生産を中心に2016年央から持ち直しているほか、自動車の生産についても、熊本地震や軽自動車燃費不正等による生産停止からの挽回生産に加えて、秋以降の新車効果もあり、年央から持ち直している。
なお、インバウンド消費5については、訪日客数が増えているものの、その消費内容に変化が生じている(第1-1-12図)。インバウンド消費の動向をみると、為替レートが円高方向に動いたこともあって2015年末に伸びがやや減速したが、2016年に入ってからは緩やかに持ち直している。その内訳をみると、買い物の金額がやや低下する一方で、訪日客数の増加に伴って宿泊や飲食・娯楽が着実に増加している。また、買い物の内容についても変化がみられ、カメラやその他の家電製品から、化粧品やその他の消耗品といった内容にシフトしているという特徴がみられる。訪日観光客だけではなく、こうした商品に対する海外での人気は高く、化粧品等が分類として含まれる化学製品の輸出も堅調となっているが、訪日客一人当たりの消費額増加の伸び率は以前と比較すると緩やかなものとなっている。
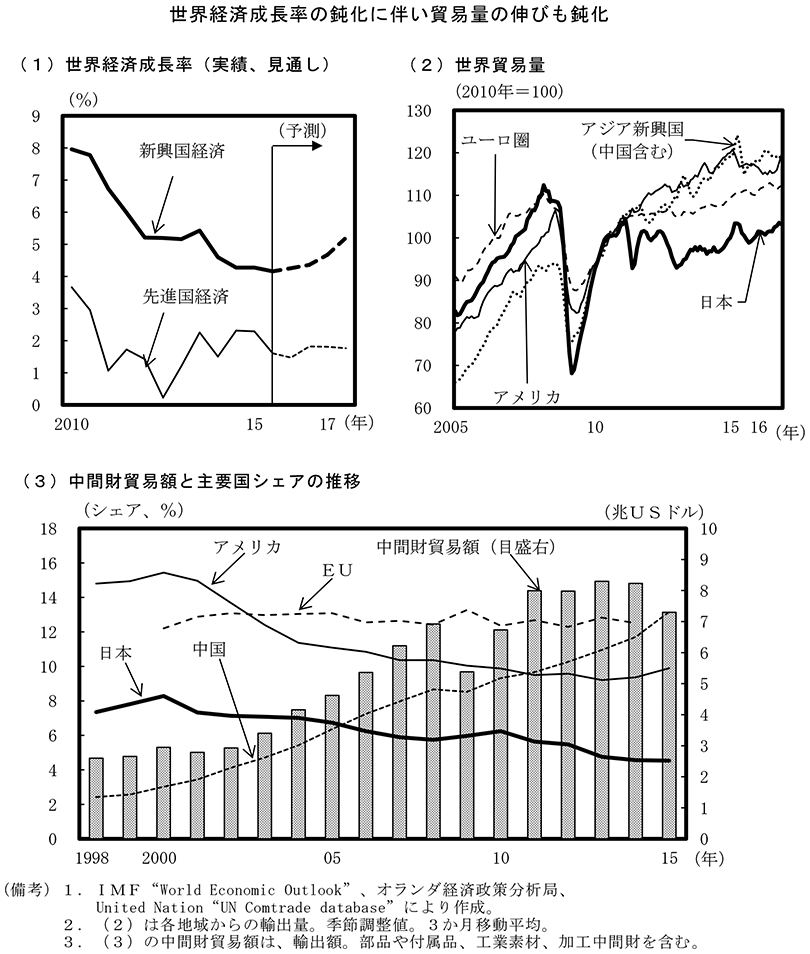
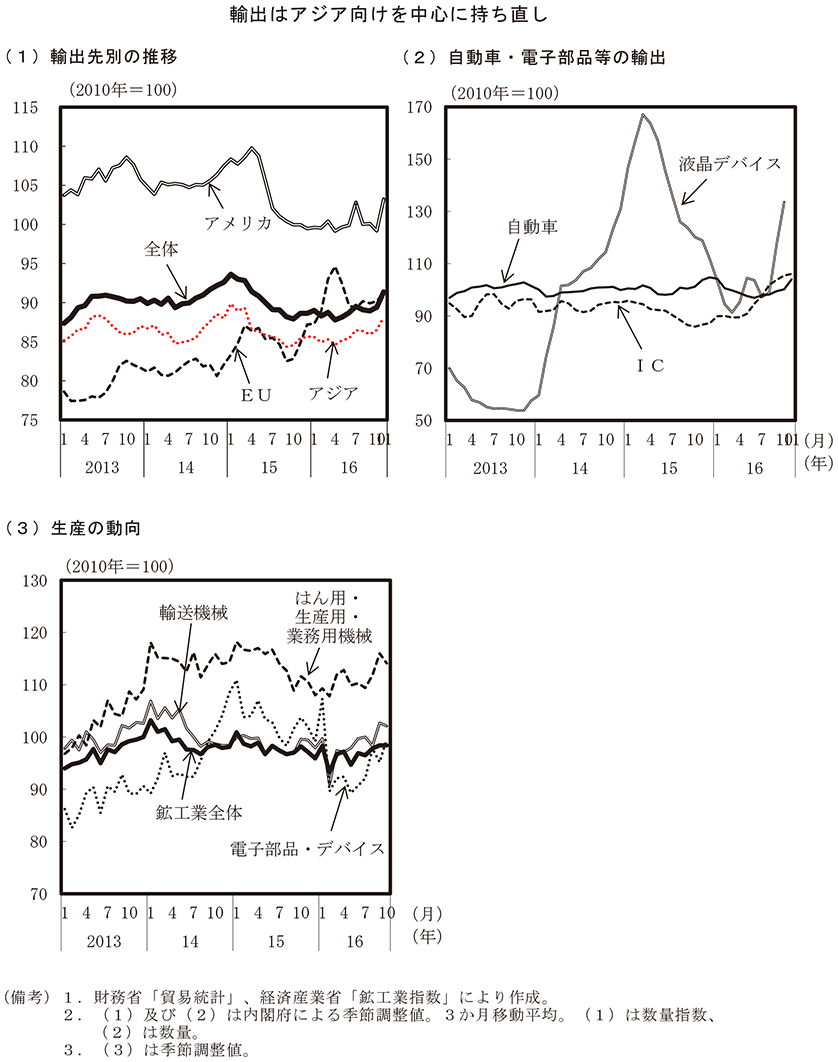
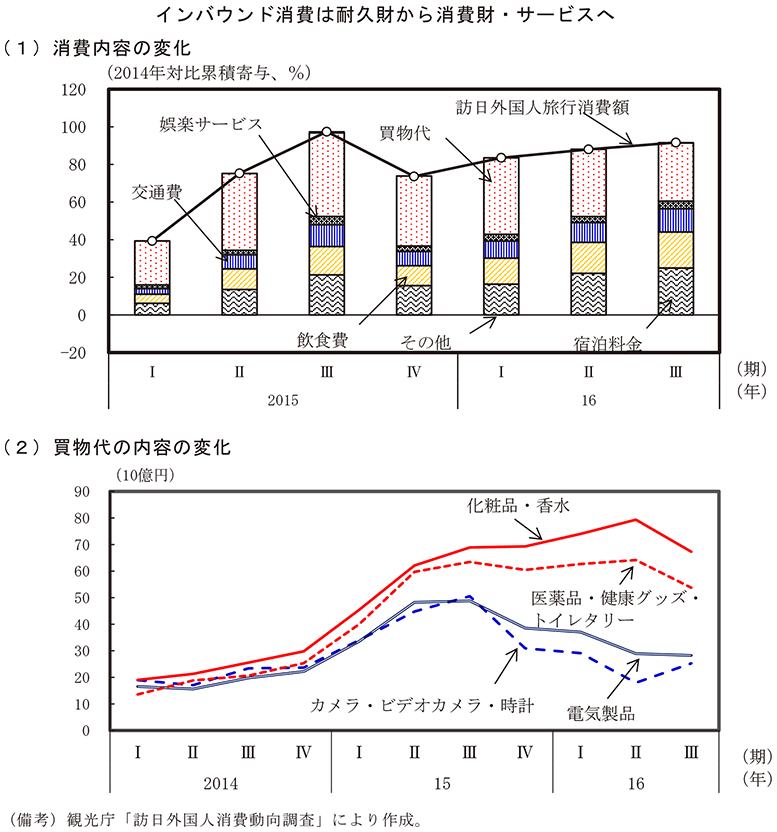
(企業収益の動向)
企業収益は、2015年に過去最高益を記録した後、2016年に入ってからは、引き続き高い水準にはあるものの、改善に足踏みがみられている。こうした背景としては、2015年後半から円高方向の動きがみられ、2016年に入ってもその動きが続いたことから、輸出産業を中心に、経常利益6のうち、為替差益等による収益が減少したことがある。これは、円高方向への動きによって、円建てでの輸出入価格が低下したことによるものと考えられ、さらに資源価格の低迷も、海外で資源関連の投資を行っている企業の収益押下げ要因となった。ただし、2016年後半には、資源価格にも底打ちがみられ、また、11月以降は為替レートも円安方向に推移していることから、こうした資源価格や為替レートの動向が収益に与える影響は縮小するとみられる。なお、企業は、2010年代に入ってから人件費を中心とする固定費を低下させ、損益分岐点売上高の水準が低下してきており、2012年以降の円安方向で為替レートが推移した時期にあっても、そうした合理化を続けてきた。このため、2015年~16年の円高方向への動きによって生じる売上高の減少の影響があっても、営業利益を大きく損なうことのない財務構造となっていたといえる(第1-1-13図(1))。
企業の資産・負債の動向をみると、資金調達面においては、負債残高がほぼ横ばいで推移する中で、利益剰余金(内部留保)が大きく増加し、2016年7-9月期の段階で378兆円に達している。資産面においては、構築物や機械といった面での設備投資が抑制的であることなども影響して有形固定資産が減少傾向にある一方で、M&Aの増加等を反映して長期保有株式が増加しているほか、現金・預金も引き続き増加している(第1-1-13図(2))。
以上を踏まえると、企業は、世界経済や為替の変動等がある中でも、収益を上げられるような体制を作っているとみられる。また、海外でM&Aの活用を積極的に行っている一方で、国内の有形固定資産への投資や人件費を中心とするコストについては、引き続き抑制している側面もみえる。
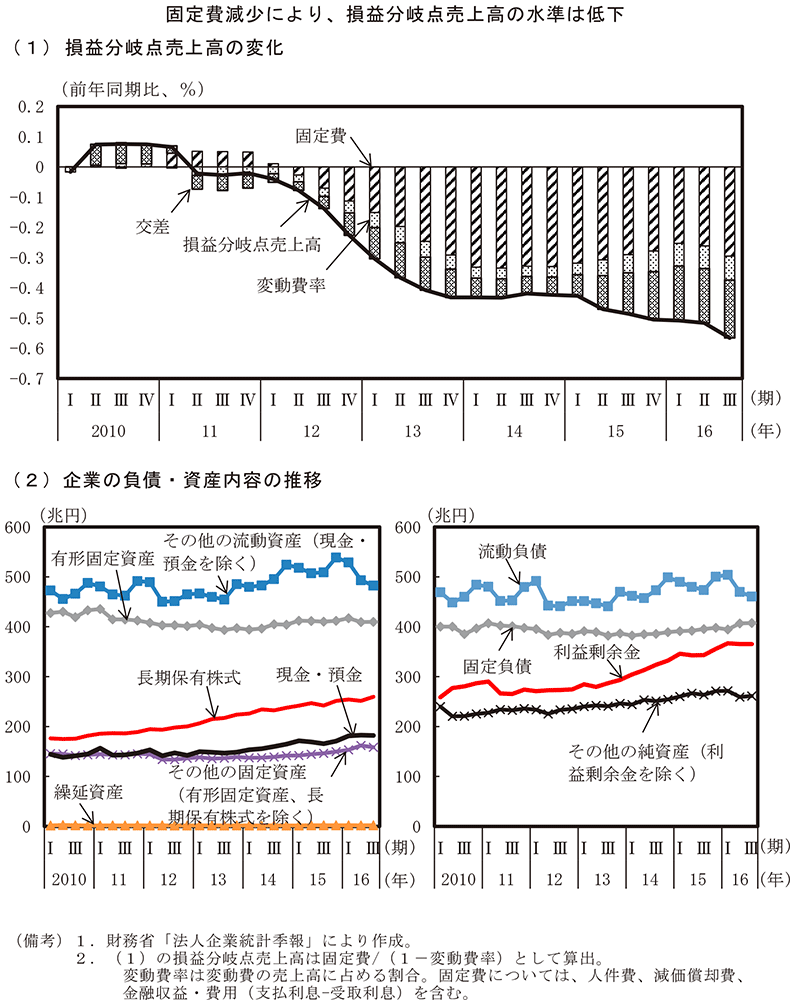
5 設備投資の動向
設備投資は持ち直しているものの、2016年1-3月、4-6月、7-9月と前期比でみて一進一退で推移するなど、足踏みしている。短期的な要因としては、2016年初からの為替レートの円高方向への動きを反映した企業マインドの慎重化の影響があると考えられるが、中長期的な要因についてみると、企業が設備以外の投資活動を多様化させていることや、内外の需要が弱いこと等があると考えられる。
(投資の多様化)
設備投資の伸びは緩やかであるが、引き続きM&A等の広い意味での投資が活発になっている傾向がある7。企業の資産の保有状況をみると、M&Aの広がりを反映し、1年以内に売却予定のない長期保有株式の残高が増えている。
特に、海外を含めたM&A等により、海外子会社の保有する証券から得られる利益は営業利益に上乗せされる形で営業外収益を高めている。既にみたように、海外からの収益については、円安方向の動きがみられる際には経常利益を押し上げ、2015年末からの円高方向への動きがみられる際には利益を縮小させる圧力となっている。
有形固定資産への投資である設備投資の勢いは緩やかとなっている。民間企業の資本係数は1990年代から2009年にかけて大きく上昇したが、それ以降横ばいの傾向となっており、資本ストックの伸びは低いものにとどまっている(第1-1-14図(1))。第1-1-14図(2)は、設備投資・資本ストック比率(I/K比率)を横軸に、設備投資前年比を縦軸として、両者の関係を示す資本ストック循環図である。設備投資の前年比が上昇すると上方に移動し、設備投資が減耗等を上回る程度に続けば、徐々にI/K比率も増加し右下方向に移動していくことになる。2016年に入ってからは、設備投資前年比上昇率はほぼゼロであるが、設備投資の水準としては資本減耗を若干上回っていることから、資本ストックは0.5%をやや下回る伸びとなっている。資本係数が過去のトレンドで推移すると仮定して、資本ストックの伸びに見合う経済成長率を推定すると、0.5%弱程度となっており、企業はこの程度の経済成長率を前提として投資をしていると推測される。ただし、こうした投資行動の前提となっている予想成長率は、実際の経済成長率と比較しても低く、現状の設備投資が実際の成長率に対して十分な水準という状況とはなっていないと考えられる。
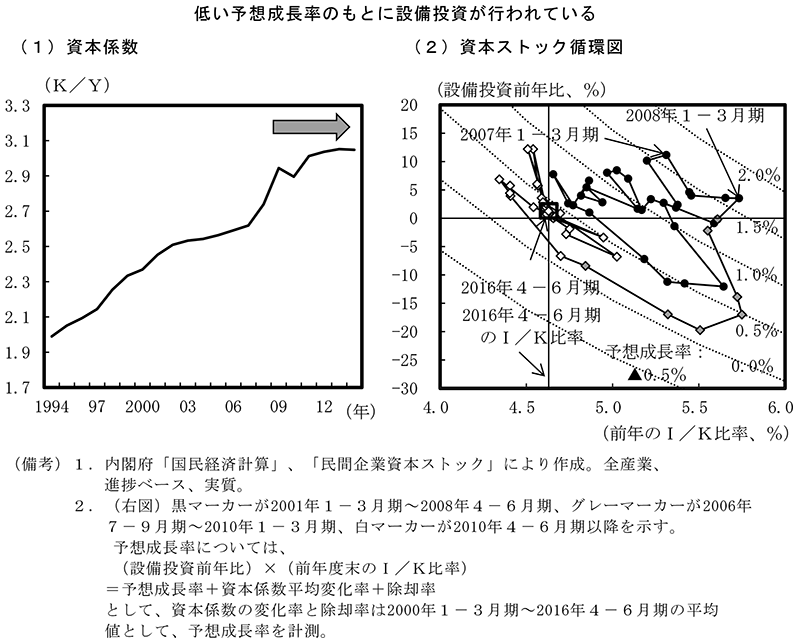
(設備投資の内容の変化)
設備投資がどのような分野で拡張、抑制されたりしているかを詳しくみるために、設備投資の構成について、機械、構築物、ソフトウェアに分けて考えてみよう。世界金融危機前の時期と後の時期に分けて、産業別に設備投資の各構成要素の状況をみると、製造業では、2000年代の世界金融危機前においては、機械、構築物、ソフトウェアともに増加していたが、危機後においては、いずれの投資構成要素も減少に転じている。他方、非製造業については、世界金融危機後においても、不動産業や卸小売業を中心に構築物投資が増加しているほか、金融業で機械、構築物に加え、特にソフトウェアに増加がみられるなど、設備投資は全般に非製造業がけん引している(第1-1-15図(1))。
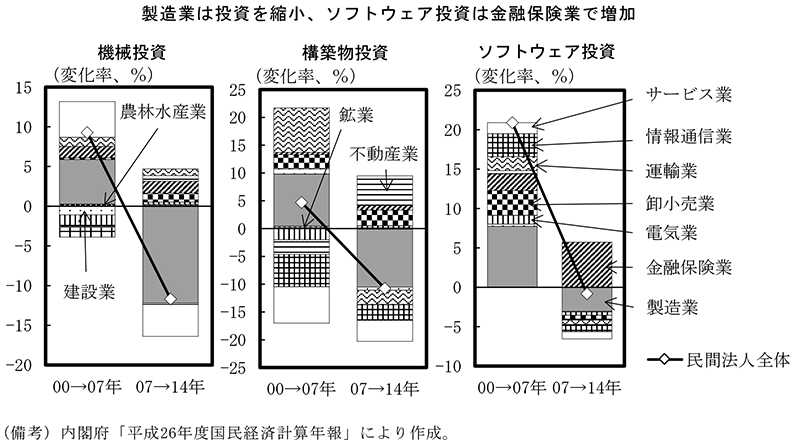
以上のような製造業における設備投資の抑制はどのような要因で起こっているのであろうか。製造業における機械設備投資、構造物投資について、売上高、借入金利水準の動向、従業者一人当たりの資本装備率、設備過剰感、海外への投資比率といった設備投資とかかわりの深い変数との関係を分析した(第1-1-16図)。推計結果によると、機械投資については、売上高や、設備過剰感が押下げ方向の大きな要因となってきたと考えられるが、近年は、これらの影響が少なくなってきたとみられる。構築物投資については、海外移転が進んでいることが抑制の一因となっている可能性が高いが、これも2015年には一服している様子がみられる。したがって、世界金融危機後に製造業の設備投資の押下げに働いてきた要因については解消されつつあると考えられる。また、建物等の構造物の投資を行うと、同時にそこに設置される機械設備の拡充が行われ、また、機械設備の拡充に伴ってソフトウェアの投資も必要となるという補完関係があるため、連動して投資が加速する場合も考えられる。
なお、機械設備については、上記からは、企業の売上等の業況に左右される度合いが大きい様子がみられるが、自動車など幾つかの産業では、売上げや収益がやや弱かった2016年前半でも、新製品の開発など前向きな投資を行うことを見込んでいた。このように、イノベーションによって予想成長率の高まりが見込めるような産業では、計画時点で想定される業況にかかわらず前向きな投資が行われることが期待される。
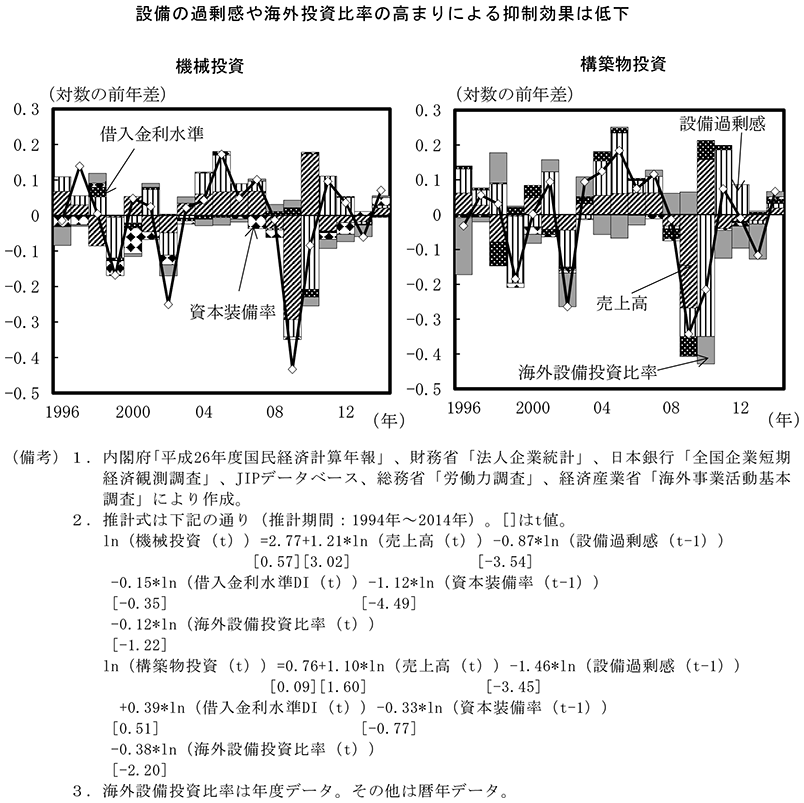
さらに、ソフトウェア投資については、リーマンショック後の時期においても、構造物や機械設備と比べてその抑制幅は小さい。特に金融業に関しては投資を拡大させている。元来金融機関にとっては、情報技術は重要な経営資源として位置付けられており、セキュリティを確保する必要からも、預金や融資等の業務処理などを担う勘定系システムのほか、顧客情報管理システム(CRM)や融資・審査支援などの情報系システムへの投資を拡大させてきた経緯がある8。最近では、マイナンバー制度等新しい社会制度への対応や、それに伴う投資が必要となっていると考えられる。今後は、フィンテック等の新しいサービスへの対応に合わせた投資も期待される9。第2章で詳細に論じるように、今後、第4次産業革命と呼ばれる技術革新の波に対して、企業が積極的に対応していくことで、設備投資が中長期的に増加していくような状況も期待される。さらに、以上で論じた機械投資、構築物投資、ソフトウェア投資に加えて、平成27年度国民経済計算年次推計から、研究開発(R&D)投資が設備投資として計上されることとなった10。これらR&Dも含めた投資の有効な増加が、我が国の競争力強化につながることが期待される。

